Contents
Global Warming: A Case Study in Groupthink: How science can shed new light on the most important “non-debate” of our time (GWPF Report Book 28)
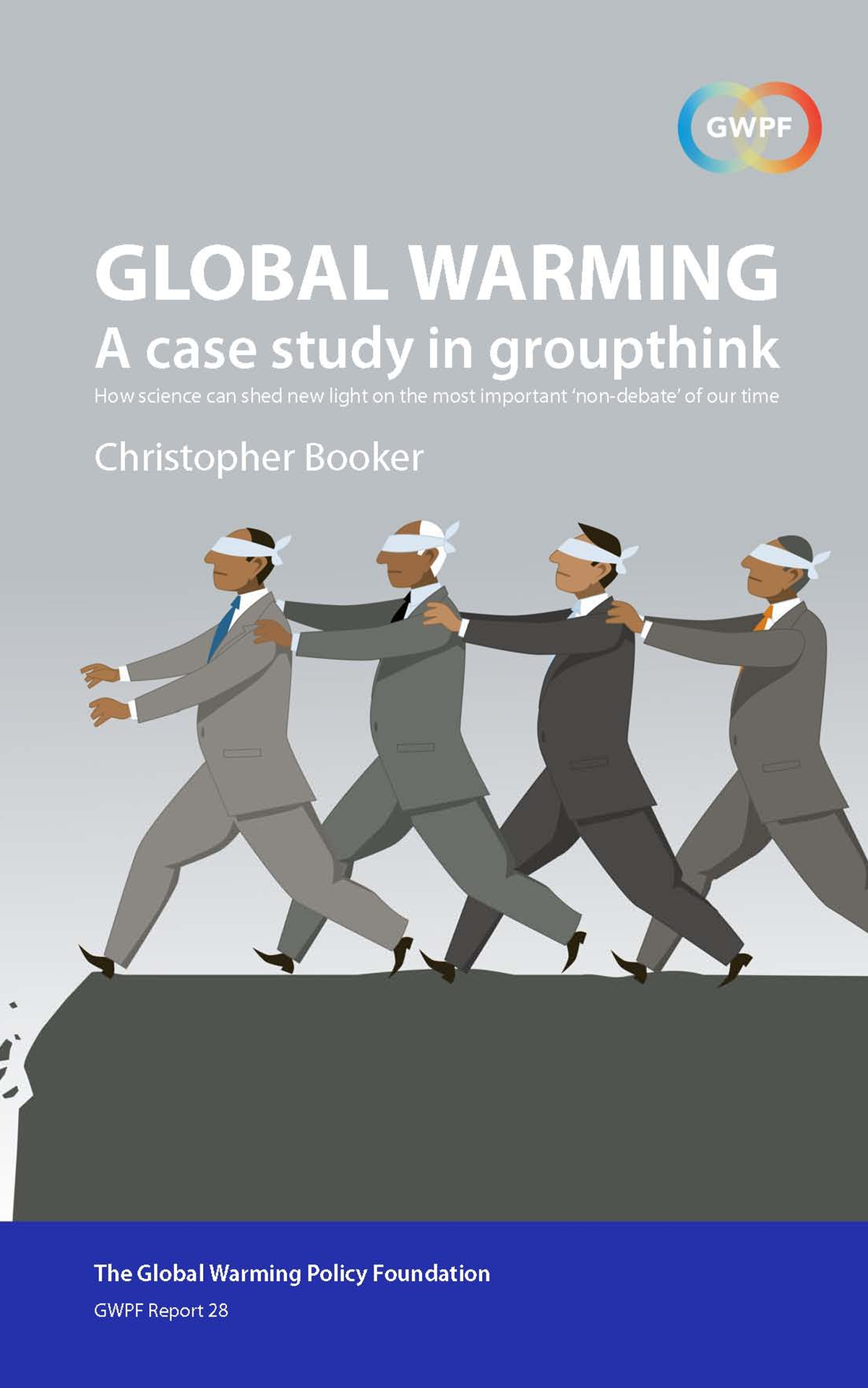
クリストファー・ブッカー
発行:地球温暖化政策財団
目次
- 序文
- 著者について
- 著者の個人的なメモ
- 要旨
- 1 はじめに
- 2 ジャニスのグループシンク理論
- 3 グループ・シンクの3つのルール
- 4 セカンドハンドシンキングの威力
- 5 地球温暖化とグループ・シンクの原型
- 6 「その時が来た」という考え
- 7 IPCCは自らのルールを破った:「コンセンサス」は最初の大きなスキャンダルを乗り切った
- 8 「コンセンサス」は証拠をごまかす
- 9 グループシンクが外の世界と出会うとき
- 10 「コンセンサス」とメディア
- 11 ヒステリーが最高潮に達する
- 12 物語が変わり始める:反対意見の声
- 13 グループ・シンクと希望的観測
- 14 「コンセンサス」はどこから「事実」を得たのか?
- 15 グループ・シンクは自分たちを守る
- 16 危機の余波、2010年~2014年
- 17 パリへの序曲:理論に合うように事実を「調整」する(再び)
- 18 2015年パリ:集団思考の最後の「勝利
- 19 真の地球温暖化災害:集団思考はいかにして政治的対応を形成したか
- 20 イギリスの特異なケース
- 21 トランプ大統領、ついに集団思考のハッタリに対抗する
- 22 結論 集団思考が現実に遭遇するとどうなるのか?
- 23 個人的なエピローグ:より広い視点から
- ノート
序文
リチャード・リンゼン教授
気候破局論という奇妙な問題は、十分に長い間存在してきたため、その歴史を詳細にたどることができるようになった。実際、最近のいくつかの優れた書籍では、この問題を環境、経済、政治のさまざまな動向の中に位置づけることで、この問題を扱っている。ダーウォールの『Green Tyranny: Exposing the Totalitarian Roots of the Climate Industrial Complex』やルーインの『Searching for the Catastrophe Signal: この関連では、ダーウォールの『Green Tyranny: Exposing Totalitarian Roots of the Climate Industrial Complex』とルーインの『Search for the Catastrophe Signal: The Origins of The Intergovernmental Panel on Climate Change』が特筆に値する。ブッカーの比較的短いモノグラフは、かなり異なるが非常に重要な問いを投げかけている。すなわち、ありえないこと、内部矛盾、矛盾するデータ、明らかな腐敗、おかしな政策的意味合いにもかかわらず、そうでない知的な人たちはどうしてこのようなばかげたことを信じるようになるのだろうか、ということである。ブッカーは、われわれが何らかの役割を果たすことを期待している理性的な能力を圧倒する「集団思考」の力を説得力を持って示している。集団思考という現象は、なぜ普通の社会人がこの欠陥に陥りにくいのかを説明するのに役立つ。結局のところ、信者が属したいと思う集団は、教育を受けたエリートの集団なのである。このことは、ドナルド・トランプの当選に大きな役割を果たしたと思われるが、それは、非エリート(ヒラリー・クリントンのいうところの「デプラブル」)が「ベター」のバカさ加減を認識したことに対するフラストレーションに大きく依存した。
ブッカーが英国の状況を強調するのは、この問題への対応の不合理さがこれほどまでに明白な場所はないという点で参考になるが、問題は先進国全体に存在する。ヒステリーから多大な利益を得ている数多くの個人やグループ(学者を含む。米国では、警告を支持することを前提とした資金提供が約15〜20倍に増加した)の存在によって、どこでも状況は強化されているが、なぜ他の多くの人々が、そうすることの明らかな不利益にもかかわらず従ってきたのかは、Bookerが提供する注目に値するものである。
リンゼン教授は、2013年に退職するまで、マサチューセッツ工科大学のアルフレッド・P・スローン教授(気象学)を務めていた。GWPFのアカデミック・アドバイザリー・カウンシルのメンバーでもある。
著者について
クリストファー・ブッカーは、過去11年にわたり、サンデー・テレグラフ紙などで気候変動やエネルギー問題について執筆している。2010年に出版した地球温暖化の科学と政治の歴史書「The Real Global Warming Disaster: Is the obsession with climate change turning into one of the most costly scientific blunders in history? は、ブックセラー誌でアル・ゴア、ジェームズ・ラブロックと並び、過去10年間にイギリスで最も売れた環境に関する本のベスト3としてランク付けされた。
1937年生まれ。ケンブリッジ大学で歴史を学び、1961年から1963年にかけて『プライベート・アイ』の創刊編集長を務めた。その他の著書に、The Neophiliacs: a study of the revolution in English life in the Fifies and Sixties (1969), The Seven Basic Plots: Why we tell stories, a psychological analysis of storytelling (2004), The Great Deception, a history of the European Union (co-writing with Dr Richard North), Scared to Death.などがある。Why scares are costing us the earth (2007)などがある。1979年にはBBCのテレビドキュメンタリー番組「City of Towers」を制作し、戦後のイギリスの都市再開発にル・コルビュジエが与えた決定的な影響を追跡し、高い評価を得ている。
著者の私的メモ
10年以上にわたって地球温暖化問題について幅広く執筆してきた私が、2014年までこの論文のきっかけとなった本と出会わなかったことを自責の念に駆られている。アーヴィング・ジャニスの「集団思考」についての代表的な分析にようやく出会ったとき、私や他の多くの人々が長い間追いかけてきた物語について、それがどれほど多くのことを説明するのに役立っているかに気づいた。
特に 2009年に『The Real Global Warming Disaster』という人為的な気候変動に対する警告の歴史をまとめた本を出版したときに、このことを知っていれば、まったく異なる本になっていたかもしれない。
ここでは、より簡単に、この物語を再び取り上げ、最新の情報を提供するとともに、ジャニスの理論が、科学と政治の歴史における最も顕著で不可解なエピソードの一つに対するわれわれの理解に、全く新しい次元を加えるものであることを紹介する。
群衆の心理についてある種の洞察を得ることによってのみ、群衆が押しつけられた意見以外の意見を持つことがいかに無力であるかを理解することができる。
ギュスターヴ・ル・ボン「群衆」
ある現象学の中にいる限り、人は驚かないし、それが何なのか疑問に思うこともない。そのような哲学的な疑念は、ゲームの外にいる者にしか生じない。
C.G.ユング『心理学と国家問題』
要旨
地球が「人為的な気候変動」という未曾有の脅威に直面しているという考え方は、科学と政治の歴史において最も異例な出来事の一つであったと言える。そのため、科学者や政治家は、現代産業文明の機能を維持するために必要なエネルギーを調達する方法を完全に変革し、その文明の基盤となっている化石燃料を段階的に廃止する以外にないのではないかと考えるに至った。
しかし、この30年間、専門家たちは、このような事態にますます困惑することになった。特に、次のような疑問が持たれている。
- 人間の二酸化炭素排出が世界を危険なほど温暖化させているという信念が、世界の気候科学者の「コンセンサス」によって共有されていると宣言されるようになるまでのスピードが速かったこと。
- その信念を支持するために引用された証拠の性質と信頼性。
- 「コンセンサス」の根拠となったコンピューターモデルの予測通りに地球の気温が上昇しなかったこと。
しかし、「コンセンサス」の支持者たちが、多くの著名な科学者やその他の専門家を含む、これらすべてに疑問を呈する人々に対して、独特の敵意と拒絶反応を示していることも事実であった。
この論文の目的は、1970年代にエール大学の心理学教授の科学的洞察を用いて、地球温暖化に関する警報の全容を驚くべき新しい光で示すことである。故アーヴィング・ジャニス教授は、人々が「グループシンク」と呼ばれる、3つの特徴的なルールを持つ集団心理の行動パターンに巻き込まれるとどうなるかを分析した。
- ある集団は、証拠を適切に評価することなく、ある特定の見解や信念を共有するようになる。
- そのため、彼らは自分たちの信念が、正しい考えを持つすべての意見の「総意」によって共有されていると主張するようになる。
- 彼らの信念は結局主観的なものでしかなく、不安定な基盤の上に成り立っているため、彼らはその信念に疑問を呈する人に対して不合理で見下した敵意を示すことでしか、その信念を守ることができない。
本稿ではまず、1980年代後半、二酸化炭素濃度の上昇が地球温暖化の危険性をもたらすという信念が初めて世界に知られたとき、この3つの症状が最初からいかに強く現れていたかを示すことから始める。
1990年の国連気候変動に関する政府間パネル (IPCC)の第一次報告書と1992年のリオ「地球サミット」の前後には、地球温暖化が国際的な科学的・政治的「コンセンサス」として採用され、グループシンクの法則がいかに有効であったかが示されている。
集団思考の存在は1997年の京都会議で確認され、世界の気温上昇を遅らせるための実際的な措置が初めて合意された。この措置とは、欧米の豊かな先進国が二酸化炭素の排出量を減らす一方で、中国やインドなどのまだ「発展途上」の国々は、経済が欧米に追いつくまで排出量を増やし続けることを認めるというものであった。結局、この論文で紹介するように、欧米とそれ以外の国々との間のこの対立が、この物語の核心であることが判明することになる。
「コンセンサス」が依拠したコンピューターモデルが予測したように、二酸化炭素の濃度と地球の気温が共に上昇し続けたため、「コンセンサス」理論は数年間、もっともらしく思われ続けてきた。1998年には、太平洋で異常に強いエルニーニョ現象が発生し、気温は記録的な高さになった。
しかし、その後「ホッケースティック」論争が起こり、IPCCが強く支持する「コンセンサス」の支持者が、自分たちの主張をより説得力のあるものにするために、重要な科学的証拠を操作しなければならなかったという非難を浴びることになった。この疑惑に対する彼らの対応は、ジャニスの第三のルール、すなわち「コンセンサス」に異議を唱えるいかなる試みも無視し、拒絶し、抑圧しなければならないことをさらに証明するものであった。
2004年から2007年にかけて、アル・ゴアのドキュメンタリー映画『不都合な真実』や2007年のIPCC第4次評価報告書に代表されるように、地球温暖化が地球にもたらす脅威に関する主張は、これまで以上に誇張され極端になり、「コンセンサス」は依然としてすべてを支配しているように思われた。
しかし、この頃、「コンセンサス」のケースに、より深刻な亀裂が入り始めていた。1998年のエルニーニョの年以来、地球の気温がコンピューターモデルの予測通りに上昇しないことが続いていたのだ。「コンセンサス」の支持者が、グループシンクの外にいる世界的に著名な科学者に初めて直面したとき、いかに非合理的な反応をしたかを示す例もある。
さらに重要なのは、インターネットを通じて、「コンセンサス」が依拠するあらゆる科学的主張に異議を唱える資格を持つ技術専門家が率いる、新しい「カウンターコンセンサス」が出現したことであった。ジャニスの第三の法則に従って、「コンセンサス」の支持者は、自分たちに反対する勇気のある人を「気候変動否定論者」、「反科学者」として中傷するようになった。
2009年から2010年にかけて、「コンセンサス」はこれまでで最も大きな3つの打撃を受けた。
- IPCC設立の中心である少数の科学者グループ間のクライメイトゲートメールの公開。
- コペンハーゲンにおいて、新しい国際気候変動条約に合意するために長い間計画されていたことが、やはり基本的には発展途上国と欧米の間の分裂が原因で破綻したこと。
- 2007年のIPCC報告書で最も多く引用され警鐘を鳴らした主張が、科学的根拠は全くなく、気候活動家によって出されたプレスリリースや虚偽の報告書に基づいた主張であることを明らかにした一連のスキャンダル。
クライメートゲート電子メールとIPCCのスキャンダルの両方について、「気候変動体制」は、その支持者によって演出された一連の「独立した」調査によって、その線を維持するためにできる限りのことをした。しかし、ダメージは大きかった。2010年から2014年にかけて、BBCや英国気象庁などの「コンセンサス」支持者が警戒を続けようと努力したにもかかわらず、コペンハーゲン前の数年間に最高潮に達したヒステリーを維持することはもはや不可能であることが明らかになった。
しかしその後、本稿が示すように、2015年にパリで再び大規模な国際気候変動会議が開かれることになり、「コンセンサス」の最後の一投が行われた。その前兆として、2015/2016年に再び記録的なエルニーニョ現象が発生し、「一時停止」が終わったと主張されるほど地球の気温が上昇した。しかし、世界中の専門家による分析では、主要な地表温度記録の数値に大規模な「調整」が加えられていることが判明し、地球の温度トレンドが、元の記録データで正当化されるよりもはるかに上昇している印象を与えていることがわかった。
そして、地球温暖化が叫ばれて以来、最も重要な出来事が起こった。パリ会議の前に各国が提出した「INDC (Intended Nationally Determined Contributions)」と呼ばれる、将来のエネルギー政策についての文書である。技術的な詳細に埋もれているが、西側諸国がいかに「炭素」排出量の削減を計画していても、中国とインドを中心とするその他の国は、20-30年までに化石燃料による発電所を建設し、世界の排出量をほぼ50%増加させる計画であることは明らかである。中国は排出量を2倍に、インドは3倍にするつもりだった。
言い換えれば、世界の他の国々は、世界経済の全面的な「脱炭素化」に合意するというパリの公約に沿うつもりはなかったということである。しかし、驚くべきことに、先進国は集団思考に陥り、欧米のメディアは何が起きているのか認識できなかった。
その一人がトランプ大統領である。トランプ大統領は、まだ集団思考に囚われているすべての人々の怒りを買い、パリ協定から米国を離脱させる理由として、世界の二酸化炭素排出量削減の拒否を挙げた(ただし、今でも欧米の報道関係者はトランプ大統領の決断について取り上げていない)。
結論に至る前に、本論文では、地球温暖化に対する警鐘がもたらす巨大な政治的影響の一部を簡単に要約する。すなわち、化石燃料から「低炭素」エネルギー源に転換するために、主に西洋でとられている措置のコストと無益性についてである。
続いて、3つの見出しで結論が述べられる。第一章は、30年前から欧米で行われている地球温暖化に関する公的な議論のほとんどを支配してきたグループシンクの本質を要約したものである。第2章では、欧米がこの知的拘束具から逃れることを困難にしている要因について考察している。
しかし、最後の章では、トランプ大統領のパリ否決を頂点とする過去2年間の出来事が、実は全体の核心であったことを浮き彫りにする。経済成長の著しい中国やインドに代表される世界の他の国々は、西側諸国が何を信じ、何をし続けようと、それとは関係なく前進していることを明らかにした。これは、2017年7月、トランプが、世界がこれまで知っていた中で最も有害な集団思考の例の1つであるハッタリをついにかけたときに認識したことである。今後、この物語は二度と同じになることはない。
1. はじめに
地球温暖化に関する議論は30年前から行われているので、全く新しい科学的な視点が有益にもたらされるとは考えにくいかもしれない。しかし、この論文の目的は、イェール大学の著名な元心理学教授の洞察力を用いて、この論争の本質を驚くべき新しい光で示し、観察者が長い間不可解に思っていたことの多くを理解する手助けをすることである。
人間の活動が地球を危険なほど温暖化させているのではないかという考え方がもたらした結果は、どう考えても歴史上最も異常なエピソードの一つである。人間が排出した二酸化炭素やその他の温室効果ガスが、地球上の生物の将来に前例のない脅威を与えているという説を確かめるために、数え切れないほどの何十億ドルもの資金が投入されたのだ。この考えは、世界の政治家の多くに説得力があり、この脅威を回避するためのあらゆる方策に、さらに何兆ドルも費やす覚悟があることがわかった。
その中心的な目的は、彼らの言葉を借りれば、世界経済の「脱炭素化」である。200年にわたる人類の物質的進歩の基盤となってきた化石燃料を段階的に削減し、代わりに「自然エネルギー」や原子力などの「カーボンフリー」エネルギー源に依存することを求めている。そうすれば、人類が排出する二酸化炭素を減らすことができ、地球の気候に大きな影響を与えることができる、と彼らは信じている。
地球を救うには、現代の産業文明を支えてきたエネルギー源を排除し、人類の営みを根本から見直すしかない、という考え方が広く受け入れられている。
しかし、このような議論が展開されるようになった背景には、長い間、非常に大きな謎があった。1980年代後半、このような考え方が世界的なアジェンダのトップに躍り出た瞬間から、その考え方がすべてを担っているかのように思われたかもしれない。しかし、当初から多くの信頼できる科学者たちは、この見解に説得力や根拠があるとは到底思えなかった。しかし、科学的見解の「コンセンサス」として即座に宣言されたその勢いは非常に強く、それに対する疑問は一掃された。
何年もの間、他の専門家が現れ、「コンセンサス」そのものだけでなく、それを推進するために使われている方法、特に、人為的な温暖化を主張する際に中心となっていたコンピューターモデルによるグラフや予測に疑問を投げかけた。同様に、脅威とされる現象に対抗するために政治家が採用している方法、例えば「ゼロカーボン」エネルギー源に巨額の補助金をつぎ込むことなども疑問視されていた。
しかし、「コンセンサス」に疑問を投げかけるこれらの試みがいかに権威あるものであったとしても、答える価値はほとんどないとして自動的に退けられた。言い換えれば、気候変動をめぐる「議論」とされるものの最も明白な特徴は、それが実際にはまったく議論になっていなかったということである。
なぜなら、世界の主要な科学研究機関や多くのメディアを含む「コンセンサス」の支持者たちは、それ以上の議論が必要であることを受け入れることができなかったからだ。この話が始まって間もなく、私たちは「科学は解明された」と繰り返し言われるようになった。
しかし、多くのオブザーバーにとって、これは非常に奇妙なことであった。両者の間に対話が存在しないだけでなく、「コンセンサス」の支持者が、自分たちと同じ見解を持たない者に対して示した独特の敵意であったのだ。どう考えても、この時代の最も重要な問題の一つであるにもかかわらず、このような事態は予想されなかった。では、何がそれを説明するのだろうか。この「非論争」の異常に一方的な性質を説明するのに役立つような、人間心理の手がかりがあったのだろうか。
1970年代にエール大学で心理学を教えていたアーヴィン・ジャニスは、この見慣れた物語をまったく新しい視点で見ることを可能にする、決定的な欠落した視点を私たちに与えてくれた人物なのである。
2. ジャニスのグループ・シンク理論
私は、「グループ・シンク」という言葉を、結束力の強い内集団に深く関与しているときに人々が陥る思考様式を指す手軽な言葉として使っている。それは、メンバーの全員一致を求める気持ちが、代替的な行動方針を現実的に評価する動機に打ち勝つときである。集団思考は、ジョージ・オーウェルが『1984年』で提示したニュースピーク用語、すなわち「二重思考」や「犯罪思考」といった用語と同じ系統の言葉である。グループシンクをこれらのオーウェル的な言葉と一緒に並べることで、私はグループシンクがオーウェル的な意味合いを持つことに気づいた。グループシンクは、精神的な効率、現実のテスト、道徳的な判断の劣化を意味する。
アーヴィン・ジャニス『グループ・シンクの犠牲者たち』1972年
ジャニスの科学へのユニークな貢献は、彼が「グループ・シンク」と呼ぶ現象に人間が巻き込まれたときに何が起こるかを、規律正しく分析したことにある。もちろん、この言葉は、今ではあちこちで気軽に使われている言葉であり、自分の意見と異なる集団が共有する考え方を否定するためのものである。この言葉は、1952年にウィリアム・ホワイト・Jr.が作ったとされているが、ジャニス自身が作った言葉ではない。しかし、ジャニスは、ジョージ・オーウェルの『Nineteen Eighty-Four』の中の「ダブルシンク」を意識的に引用し、新たにこの言葉を作り出した。そして、彼の貢献が非常に価値あるものであったのは、1972年に出版した『Victims of Groupthink』(後の改訂版では『Groupthink』と短縮されている)1において、集団思考が一貫して機能するルールには科学的構造があることを示したことである。
実際、彼の著書があまり知られていない唯一の理由は、彼自身が、彼の洞察が当初の研究対象だけでなく、より一般的に関連していることに気づいていなかったように思われるからだ。彼の著書の副題は「外交政策の決定と失敗に関する心理学的研究」であり、彼がその論文を説明するために用いた例は、1940年代から1960年代にかけてのアメリカの外交政策における悪名高い失敗ばかりであった。1941年の日本軍の真珠湾攻撃に関する情報機関の警告に耳を貸さなかったこと、1950年にマッカーサー将軍が北朝鮮への進出を運命的に決定したこと、1961年にケネディ大統領がCIAによる悲惨なキューバのピッグス湾侵攻を支持したこと、1965年にジョンソンがベトナム戦争をエスカレートさせる決定をしたことなどであった。さらに、ニクソン大統領のウォーターゲート事件への関与も追加された。
しかし、ジャニスが入念に調査した各事例を通してより一般的に示したのは、このような人間の集団心理が、ある明確に識別可能なルールに従ってどのように機能しているかということであった。ジャニスは「集団思考の症状」のリストを何度も提示し、彼の長大な研究にはそのほかの属性についての分析も多く含まれている。しかし、私たちの今回の目的には、彼の研究から、絶対的に基本的で私たちのテーマに関連するグループシンクの3つの特徴を引き出すことができる。ここで注意深く「から引き出す」という表現を使ったのは、ジャニス自身、これらがグループシンクの3つの基本ルールであるとはどこにも明言していないからだ。しかし、これらは本書全体を通して彼の分析に暗黙的に含まれており、グループシンクがどのように機能するかについての彼の理論の核心を形成している。
3. グループ・シンクの3つのルール
ルール1は、ある集団が、何らかの形で現実にきちんと基づいていない共通の見解や信念を共有するようになることである。彼らは、自分たちの意見が正しいことを確認するあらゆる種類の証拠があると信じているかもしれないが、彼らの信念は、最終的には疑いを超えてそれを確認する方法でテストすることはできない。したがって、本質的には、それは共有された信念にすぎない。
ルール2は、彼らの共有する見解が外部からの証明に服することができないからこそ、彼らはそれを「コンセンサス」(ジャニス自身が強調した言葉)に昇華させることによって、その権威を強化する必要性を感じるということである。コンセンサス」を支持する人々にとって、その共通の信念は知的にも道徳的にも自明であり、良識ある人々はみなそれに同意するに違いないと思われる。彼らが許せないのは、自分たちのグループの中にも外にも、誰かがそれに疑問を持ったり挑戦したりすることだ。いったん確立された信念体系の本質は、何としてでも守らなければならないのだ。
ルール3は、ある意味で最も明白なことだが、全員が「コンセンサス」を支持しなければならないという主張の帰結である。それを共有できない人の意見は、まったく受け入れられなくなる。彼らとの対話の可能性はない。それ以上の議論からは排除されなければならない。せいぜい疎外され無視されるだけかもしれないが、最悪の場合、公然と攻撃され、信用を失墜させなければならない。異論は許されない。
ジャニスは、これらのルールがいかに一貫して、致命的に機能しているかを、それぞれの例で示した。集団思考にとらわれた人々は、自分たちの「コンセンサス」である見解に疑問を呈する証拠を提出する者を厳格に排除した。彼らは自分たちの主張が正しいと確信しているので、それに賛同できない人は積極的に議論から締め出された。そして、いずれの場合も、自分たちの二次元的な「コンセンサス」が現実の適切な評価に基づいていないことを示唆するいかなる証拠も考慮することを拒否したため、結局は大惨事につながった。
情報の警告に耳を傾けることを集団で拒否したために、日本軍は平然と真珠湾攻撃を行うことができた。マッカーサーは北朝鮮に進攻するという傲慢な決断を下し、中国を戦争に巻き込み、致命的な結果を招いたことは予想できた。ケネディとその親密なアドバイザーたちの小さな輪が、CIAのキューバ侵攻計画を無謀にも受け入れたことは、恥ずべき大失敗につながることは必定であった。ベトナムへの米軍の大規模な増強は、米国を10年にわたるフラストレーションと増大する悪夢に引き込む結果となり、1975年の屈辱的な撤退でようやく幕を閉じた。
1940年代後半のマーシャル・プランと、1962年に新たな世界大戦の脅威となったキューバ・ミサイル危機の終結である。1940年代後半のマーシャル・プランと、1962年に新たな世界大戦の脅威となったキューバ・ミサイル危機の終結である。この違いは、これらの構想が集団思考とは正反対の方法で推進されたことにある。どのケースでも、責任者は意図的に幅広い専門家の意見を聞き、すべての関連する証拠をテーブルに乗せることを確実にするためだった。彼らは、提案されたものがもたらすあらゆる可能性を追求しようとした。そして、どのケースでも、その政策は見事に成功した。
この3つの要素が、グループシンクの運営を定義する典型的なルールを構成していることを認識すれば、それが時代を超えて、異なる装いをしながら、いかに一般的に適用されてきたかが分かる。
明白な例として、ほとんどの組織化された宗教の形がある。宗教は定義上、「信念体系」であり、いったん確立されると、それを共有しない人に対して非常に不寛容になる傾向がある。したがって、こうした部外者は「異端者」「異教徒」「不信心者」として断罪される。正しい考えを持つ正統派を守るために、彼らは社会から疎外され、主流派から排除され、迫害され、死刑にさえされなければならない。
もう一つの明白な例は、共産主義やナチズムのような全体主義的政治イデオロギーで、同様に「破壊者」や「反体制派」、「党の方針」(ソ連では「正しい考え」と呼ばれた)に従わない者に対して冷酷な不寛容を示した。この場合も、そのような人たちは既存の社会から排除され、投獄されるか、物理的に「排除」されなければならなかった。
太陽が地球の周りを回っているという教会の「コンセンサス」に疑問を呈したガリレオに与えられた処置から、1950年代初頭にアメリカでマッカーシーと上院非米活動委員会が「共産主義者」、つまり裏切り者として悪者にできる人物に対して巻き起こしたヒステリーまで、このパターンは歴史を通して大小無数の例を容易に特定することができる。
集団思考の完璧なフィクションは、ハンス・クリスチャン・アンデルセンの「皇帝の新しい服」という物語である。皇帝がまばゆいばかりの新しい服を着て通りをパレードすると、臣下は皆、この上なくハンサムだと賞賛する。しかし少年は、皇帝は服を着ておらず、全裸であることを指摘する。もちろん、「コンセンサス」の中にいる人々は、真実を指摘した少年を悪しざまに非難する。
エピローグでは、現代社会で見慣れた集団思考の事例を簡単に紹介することにしよう。しかし、地球温暖化をめぐる「非議論」にジャニスの3つのルールを適用する前に、彼が分析した特定の例とは関係ないために触れなかった、集団思考の作用のもう一つの非常に重要な側面も付け加えておかなければならないだろう。
4. 二番煎じが持つ力
肯定、反復、伝染によって伝播する思想には、「威信」として知られる不思議な力を時間的に獲得する状況によって、大きな力が与えられる。世界の支配者であったものは、それが思想であろうと人間であろうと、大方、われわれが威信と呼ぶこの抗しがたい力によって、その権威を行使してきた。
ギュスターヴ・ル・ボン『群衆』より
ジャニスは、集団思考が米国の最高レベルの政策を担当する小集団にどのような影響を与えるかにのみ関心を寄せていた。しかし、人為的な地球温暖化に対する信念について考えるとき、私たちはもちろん、学者、政治家、メディア、教師、企業経営者、さらには世論一般など、数え切れないほどの人々がこの信念を共有していたことに注目することになる。
しかし、これらの人々は、人為的な地球温暖化が現実のものであり、危険であるという信念に、他人からそう言われたからこそ流されたに過ぎない。しかし、このような人たちは、人から聞いたことや読んだこと、あるいはテレビで見たことを、何の疑問も持たずに真実として受け入れていた。つまり、なぜそう思うのか、その理由がわからない。このような複雑で専門的なテーマを、根本的に勉強する必要はないと考えていたのだ。彼らはただ、どこからか伝わってきたことをそのまま口にしただけである。それはたいてい、見慣れた議論や信条という形で、承認されたマントラのように、延々と繰り返される。
例えば、地球は太陽から9,300万キロ離れているとか、東京は日本の首都であるとか、私たちは皆、自分が信じていることや知っていると思っていることの大部分を、最初に学んだ情報源の信頼性を確認することなく受け入れている。例えば、地球が太陽から9,300万マイル離れているとか、東京が日本の首都であるとか、そういうことは、みんながそう思っているからそうなのだと信じて、必要ならば、確かな証拠によって確認できると思い込んでいるのだ。
しかし、人為的な地球温暖化を信じるようになったとき、別の要因が作用した。この要因は、集団思考の事例を見るときに常に関連してくるものである。それは、「集団思考」と呼ばれるものである。これは、全く新しい考え方であるため、それを提唱する人たちにどれだけ権威があるかということにかかっており、このことが、この物語の重要な部分を占めることになる。
ジャニスがグループ・シンクの理論を発表するずっと以前から、フランスの作家ギュスターヴ・ル・ボンは、同様のアイデアを科学的ではない形で探求していた。彼は1895年に『群衆』という本を出版している。ルボンは、1895年に『群衆』という本を出版した。ルボンの最も鋭い観察は、大勢の人々の意見を変えるのに、「威信」、つまり、率先して意見を述べる人に払われる特別な敬意が重要な役割を果たすということであった。
このことは、人為的な地球温暖化に対する信念が、あれほどまでに広く受け入れられるようになった経緯からも明らかである。その最たるものが、国連の「気候変動に関する政府間パネル (IPCC)」と呼ばれる組織に与えられた独特の威信である。IPCCの威光は、世界の「一流の気候科学者」の意見を代表し、地球の気候の状態に関する究極の客観的権威として世界に示されたことにある。他の科学者、政治家、ジャーナリスト、その他誰でも、地球温暖化について主張したいことがあれば、IPCCをその権威として引き合いに出せばよい。IPCCが発表したことは福音として扱われる。そして、そのような人々でさえも、IPCCを引用するという事実によって、IPCCの権威を少しばかり借りている。
しかし、そもそもIPCCはなぜそのような比類なき権威を与えられたのだろうか。このことは、地球温暖化信仰の高まりとそれに続くすべてのものが、ジャニスの3つの基本ルールによっていかに密接に形成されたかを見るとき、非常に関連性が高くなる。
5. 地球温暖化と集団思考の原型
まず、人為的な地球温暖化に対する信念がどのように生まれたかを再検討することから始める。
ルール1:信念体系の構築
この信念の最も顕著な特徴の一つは、それが劇的に突然に世に送り出されたことである。1970年代後半、スウェーデンのバート・ボリン教授を中心とする国際的な気象学者の小さなグループが、地球の気温が30年間緩やかに低下していた後、再び上昇していることを観測したとき、この物語は無名のまま始まった。実は、ボリンは1950年代後半から、温室効果ガスである二酸化炭素の増加によって地球が温暖化するのは必然であると確信していたが、当時はまだそのような説は全くなかった。1970年代初頭には、地球の気温が30年間も下がり続け、多くの科学者が新たな氷河期の到来を予言していたため、ボーリンは奇異な存在に過ぎないと考えられていた2。
しかし、1970年代後半になると、彼は二酸化炭素のレベルが上昇しているだけでなく、気温も再び上昇していることに気づいた。しかし、1970年代後半になると、二酸化炭素の増加だけでなく、気温も再び上昇していることに気づき、この2つの現象は直接つながっており、前者が後者を引き起こしているのだと確信するようになった。そして、人類の未来に起こりうる結果を、彼ははっきりと憂慮すべきものと結論づけた3。
1979年、ボリンは世界気象機関 (WMO)の主催でジュネーブで開かれた初の「世界気候会議」で自分の主張を展開した。聴衆は納得し、ボリンの理論を最優先議題としてさらに会議を開催することが合意された。
1985年、オーストリアのフィラッハで開かれた会議では、ボリンは「人為的な気候変動」の問題は非常に深刻であり、世界最高レベルの緊急行動をとる必要があると主張し、長いペーパーを準備していた。この会議では、ボリンの発言はすべて支持された。特に力強く感じたのは、福音主義キリスト教徒で、オックスフォード大学の大気物理学教授を経て、1983年から英国気象庁のトップを務めるジョン・ホートン博士であった。彼は、1983年から英国気象庁の長官を務めていた。彼は、ボリンの最も影響力のある科学的な味方となった。
しかし、もし、より影響力のある政治的な同盟者を獲得していなかったら、彼らはまだこの大義を達成できなかったかもしれない。ストロングは、10代の頃から、国連を世界政府にすることが人類の未来につながると確信していた。ストロングは、10代の頃から、国連を世界政府にすることが人類の未来につながると確信していた。また、彼は、政治的なネットワーク作りが非常に巧みであった。1972年、国連総長との人脈を買われ、ストックホルムで開催される「環境に関する世界会議」の運営を任され、その最初の責任者として、新しい国連機関「国連環境計画 (UNEP)」の立ち上げを依頼された。
実は、ストロングは環境についてほとんど何も知らなかった。しかし、国連の威信を利用して左翼的な政策を推進するためには、環境が重要であると考えるようになった。地球の天然資源は全人類の共有財産であり、その開発によって不釣り合いなほどの利益を得てきた豊かな西側諸国が、他の国々の貧しい人々の経済に追いつくための資金を提供しなければならない、と主張した。
1985年、UNEPはWMOと共同でヴィラッハ気候会議を主催した。この会議の議長は、ストロングと同じ志を持つUNEPの後継者、ムスタファ・トルバ博士が務めた。1987年、二人はブルントラント委員会のメンバーとして、自分たちのアジェンダをさらに推し進めることができた。この委員会は、その後何十年もの間、政治家や官僚の専門用語として「持続可能」という言葉を使うことになった。ブルントラント委員会は、ヴィラッハの提言を引用しながら、「人為的な気候変動」の危険性を特に強調し、地球の気温が上昇すれば、農業に深刻な影響を与え、「海面上昇、沿岸都市の洪水、国家経済の混乱」を引き起こすと警告した。そのため、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出を抑制するための世界的な大規模な取り組みが必要だと訴えた。
同年、ストロングは母国カナダで開催された会議において、舞台裏で重要な役割を果たし、「環境保護」のための最初の国際条約であるモントリオール議定書を作成し、オゾン層を破壊すると考えられていた化学物質フロンの使用を段階的に廃止することに成功した。この過程で、ストロングは、地球温暖化という、自分の長年の政治的アジェンダを推進するための、より強力なテーマを見出した。そして、1988年というブレイクスルー年に、突然、すべてが一つになるように思えた。
彼はNASAのゴダード宇宙研究所 (GISS)の所長として、世界の4つの公式気温記録のうちの1つを管理していた。この公聴会は、ティム・ワース上院議員が議長を務め、アル・ゴア上院議員も委員として参加するもので、米国のマスコミはこぞって出席するよう説明されていた。記者たちは、かなりセンセーショナルな話を聞くことができると約束されていた。ハンセン氏の「世界はハルマゲドンに向かっている」という荒唐無稽な予測は、『タイム』や『ニューズウィーク』誌の表紙を飾り、アメリカ国内はもとより、世界各国で大々的に報道された。ワースとハンセンは、地球温暖化の脅威をメディアのトップアジェンダに押し上げるという、まさに一石を投じた。
しかし、この年の11月、ジュネーブでWMOとUNEPが共同で設立したIPCCの設立総会が開催された。IPCCは世界の科学者による公平な組織として世界にアピールされるはずだったが、設立に関わった人々はそのような意図は全くなかった。その責任は、初代議長に任命されたボーリンと、IPCCが最初の報告書を作成する際に、気候変動の科学に関する重要なセクションを担当する「ワーキンググループI」の議長に選ばれたホートンの2人が最も大きい。二人とも「人為的な気候変動」の信念に完全に傾倒していただけでなく、各国政府を代表してそれぞれが提出した声明文からわかるように、34カ国を代表するIPCCの最初の会合でテーブルについたほとんどすべての劣等生も同様だった4。わずか2年以内に、IPCCはその最初の「評価報告書」を発表すると提案され、その中では二酸化炭素レベルの上昇がどの程度世界を温暖化するかを判断するためにプログラミングしたコンピューターモデルが重要視される予定であった5。
1990年にこの第1次評価報告書が発表されると、その「政策決定者向け要約」の中で、IPCCは「最近の世界の温暖化の半分以上は、風力発電の増加だけによるものだと確信している」「そのためには、人間活動による排出を直ちに60%以上削減する必要がある」と主張して、世界の話題をかっさらった。
「現在のモデルに基づくと」、抜本的な対策を講じない限り、21世紀を通じて地球の気温は10年ごとに最大0.5度ずつ上昇し、「過去1万年間に見られた」上昇よりもはるかに大きくなると、このサマリーは予測する。過去100年の間に気温は0.6度上昇したが、現在モデルでは10年ごとに同じように上昇する可能性があると予測している。しかし、この「政策決定者向け要約」はホートン自身が起草したものである。しかし、「政策決定者向け要約」はホートン自身が作成したものであり、要約と称している何百ものページを見てみると、かなり違った様相を呈していることがわかる。要約を担当した科学者の中には、矛盾がないとは言えないまでも、より慎重な結論を出している者もいたのだ。例えば、ある文章では次のように書かれている。
温室効果ガスの顕著な増加を伴わない、より大規模な地球温暖化は、最終氷期以降に少なくとも一度、ほぼ確実に起こっている。…..そして、過去の温暖化の理由がわかっていないため、最近の小規模な温暖化の特定の割合を、温室効果ガスの増加に帰することはできない
しかし、ホートンが意図したように、この報告書の実際の結果を憂慮するような表現で、世界中のメディアと政治家の注目を集めた。そして、これこそが、2年後にリオデジャネイロで開催される前代未聞のスペクタクルショーの準備を進めていた、彼らの盟友ストロングの狙いであった。
1992年、リオで開催された「地球サミット」は、これまでで最大規模の会議であった。この会議には、キューバのフィデル・カストロから、どちらかといえば消極的なアメリカ大統領ジョージ・ブッシュ・シニアまで、108人の世界の指導者と、2万人の公式代表団が出席した。さらにリオには、2万人の気候変動活動家とグリーン・ロビー団体のメンバーも参加し、その費用はすべてストロング自身が手配し、国連と政府の資金から支払われた。彼はこの特別な集会の細部にわたって指揮をとり、世界的な「気候政策」への前進を導く「気候変動枠組み条約 (UNFCCC)」の設立を確実なものにした。
1997年、UNFCCCは京都で再び大規模な会議を開き、世界の国々が二酸化炭素の排出を大幅に削減することに同意する条約に署名する予定であった。もっと正確に言えば、ストロングの真の長期計画に従って、この条約は欧米の「先進国」が二酸化炭素の排出量を削減することを約束し(問題の主要な責任は彼らにあると考えられているからだ)、一方で中国やインドなど他の国々のまだ発展途上の国々に巨額の資金を提供し、彼らの経済が欧米に追いつくように支援するものであった。
1980年代半ばに、地球温暖化が深刻な脅威であることを政治家に認めさせる方法を議論していたほんの一握りの気象学者にとって、これは驚くべきクーデターであった。わずか4年の間に、彼らは地球温暖化を世界の政治課題のトップにまで押し上げた。1988年、英国のマーガレット・サッチャー首相は、国連大使のクリスピン・ティッケル氏によって、地球温暖化問題に取り組むよう説得され、最初のリーダーとして迎えられた。サッチャー首相は、国連大使のクリスピン・ティッケル氏によって、この問題に関心を持つようになった。そして、IPCCの設立を計画していたジョン・ホートンを熱烈に支持し、英国気象庁に気候変動ハドレーセンター(後に気候予測研究ハドレーセンターとなる)を設立するための資金を提供した。このセンターは、イースト・アングリア大学の気候研究ユニット (CRU)と共に、世界4大気温記録となったうちの1つを担当することになる(6)。
アメリカでは、この大義に完全にコミットした最も著名な政治家は、テネシー州のアル・ゴア上院議員であった。1988年にこの上院委員会のメンバーであった彼は、ビル・クリントンの下でアメリカの副大統領になるところであった。
1991年10月、ブリュッセルにおいて、欧州共同体(後に欧州連合となる)は、IPCC報告書が「温室効果による影響とリスクについて科学者の間で初めてコンセンサスが得られた」ことを高く評価している。これは、「二酸化炭素の排出を制限するための共同体戦略」という長い文書で示され、ヨーロッパ全体の再生可能エネルギーへの転換を提案するものであった。
全体として、「気候変動との戦い」の必要性は、まさにその時期が来たということであった。しかし、ジャニスの3段階分析の第1段階に照らしてみると、当時でさえ、「真の信者」たちの理論の科学的基盤は、彼らがふりかざすほどには決して安全ではなかったことに気づかなければならない。彼らが正しいとする唯一の「証拠」は、二酸化炭素の増加が地球の気温と気候を変化させる最も重要な要因であると想定して特別にプログラムされた、コンピュータモデルの予測にあった。政治的には、彼らは確かに驚くべき進歩を遂げた。しかし、ホートンが「政策決定者向け要約」を「セクシーに」する必要があったことからも分かるように、自分たちの主張が完璧であると思わせるためには、まだかなりの努力が必要であった。そして、彼らの主張を支持する人々は、「人為的気候変動」の事例が世界の科学者の「コンセンサス」によって受け入れられていると、可能な限り主張することによって、ジャニスの規則の第二段階に進まなければならないことが、すでに非常に明白になっていた。
ルール2:「コンセンサス」の錯覚を起こす
地球温暖化の危機を否定している科学者は、ごく一部である。議論の時間は終わった。科学は解決したのだ。
アル・ゴア、1992年
リチャード・リンゼン博士は、マサチューセッツ工科大学のアルフレッド・P・スローン気象学教授であり、アメリカで最も尊敬されている大気物理学者の一人である。そのテーマは、1980年代後半に、地球温暖化が科学的意見の圧倒的な「コンセンサス」によって支持されているという印象を与えるために、異常な圧力が蓄積されたというものであった。レスター・レーヴは、1988年に上院の委員会に呼ばれ、ジェームス・ハンセンが劇的なスピーチをした他の証人の一人であった。
レスター・レーヴは、ハンセンとは異なり、地球温暖化仮説はまだ「論争中」であり、決してすべての科学者が同意しているわけではなく、気候変動の原因については科学的にまだ非常に不確かであると上院議員に語っていた。これに対してゴア上院議員は、そんなことを言う人は自分の言っていることがわからないはずだと激しい苛立ちを示し、これ以上レーヴ教授の証拠を聞いても意味がない、と言い放った7。
レーヴは、委員会からあまりにあっさりと退けられたことに驚き、アメリカで最も著名な気候学者の一人であるリンゼンに、自分の考えは間違っていたのか、と尋ねる手紙を出した。リンゼンは、地球温暖化のケースは「議論の余地がある」だけでなく、彼の見解では「ありえない」ものであることを確認した8。
2年後、IPCCが最初の報告書を作成したとき、リンゼンは、科学者としてその報告書に深い不安を覚えた。また、ホートンの「政策決定者向け要約」が、報告書の一部に示された「不確実性」をほとんど無視し、「相当な温暖化の予測を確固たる根拠に基づく科学として提示」しようとしたことに衝撃を受けた9 実際、これはホートン自身が認めていることであった。
…主執筆者たちは、彼らのコメントを取り入れるためにあらゆる試みをしたが、場合によっては、より大きなコンセンサスと調和させることができない少数派の意見を形成することもあった10。
しかし、報告書に対するリンゼンの最大の反論は、彼自身が比類のない専門性を持っている科学分野に基づくものであった。彼は、IPCCが予測した将来の気温と気候変動が、すべてコンピューターモデルに基づいていることを指摘した。そして、特に印象的だったのは、これらのモデルのプログラミングがあまりにも単純すぎるということであった。将来の気温を左右する主な「強制力」として二酸化炭素やその他の温室効果ガスに極端な位置を与え、気候に及ぼすその他の自然の影響を考慮していないため、彼らの発見は明らかに誤解を招くものであった。
特に、最も重要な温室効果ガスである水蒸気がモデル全体の90%以上を占めていることを見落としているか、重大な誤判断をしている、とリンゼンは指摘する。また、海洋の温暖化によって湿度が高くなり、雲量が増加することも考慮していない。これらの効果は、いずれも地球温暖化の影響を軽減するものである。彼は、これらの効果を正しくモデル化すれば、二酸化炭素濃度の上昇による「温室効果」が誇張されたものであることがわかると主張した。さらに、このことは、同じコンピューターモデルを過去にさかのぼって実行し、もしそれが正しければ、20世紀を通じて気温がどのように推移したかを示すことによって証明することができる。このような単純化しすぎたプログラムは、20世紀の気温に実際に起こった変動を説明することができないことが、明らかになった。二酸化炭素の排出量が比較的少なかった1920年代と1930年代には、気温は急激に上昇した。しかし、1940年から1970年代にかけて、二酸化炭素の排出量がさらに急増した年には、気温が下がり、気候学者の間で「小冷却」と呼ばれるようになった。実際、リンゼンによれば、モデルの仮定は、20世紀の温暖化を実際の記録の4倍も予測させるものであった(しかも、そのほとんどは大気中の二酸化炭素が現在のレベルに達する前に起こっていた)。これでは、将来の気温上昇を予測する彼らの能力を信用することはできないだろう。リンゼンが単刀直入に言ったように、モデルには「不穏な恣意的」でない結果を出すための物理学も数値精度もない。
しかし、リンゼンがIPCCによる将来の温暖化に関する説明を「ありえない」ものであり、著しく誇張していると考える理由はこれで確認できたが、「コンセンサス」とされるものの本質に関する彼の長文の論文は、実際には非常に広範囲に及んでいる。特に、彼は、「コンセンサス」という概念が公的な議論を支配するためにどれほど利用されてきたか、また、それに疑問を呈する勇気のある者が疎外されるようにどれほど異常な圧力がかけられてきたかに焦点を当てた。
まず、他の有力な利益団体が、いかに早くこの運動に参加したかが注目される。例えば、グリーンピース、フレンズ・オブ・ザ・アース、WWFといった環境保護団体が、地球温暖化問題に熱心に取り組んでいることを紹介した。これらの圧力団体は、もともと1960年代の「環境の目覚め」から生まれたもので、今では「非政府組織」 (NGO)として非常に大きな地位と影響力を持つに至っている。
これらすべての運動団体の当初の主要な目標は、核兵器と原子力発電所がもたらす「脅威」から世界を救うことであった11。しかし、冷戦が終結すると、驚くべき一致をもって、すべての団体が突然、地球に対する新しい脅威に関心の焦点を移したのだ。リンゼンはこう言っている。
これらのロビー団体は、数百万ドルの予算と約5万人の従業員を抱えている。彼らの支援は、多くの政治家たちに高く評価されている。どんな大きなグループでもそうだが、自己増殖が重要な関心事となる。「地球温暖化」は、彼らの資金調達活動における主要な叫び声の一つとなっている。同時に、メディアはこれらの団体の発表を客観的な真実として疑うことなく受け入れている。
1989年3月、主要なNGOは、地球温暖化に関するキャンペーンを調整するために、「Climate Action Network」という傘下組織を結成した。この影の組織は、1992年にストロングがリオのサミットに参加した2万人の活動家の勧誘に利用されることになった。
同じ頃、「憂慮する科学者同盟」は、もともと核問題で結成された団体であったが、地球温暖化を人類最大の危機として認識するよう求める嘆願書を作成した。ノーベル賞受賞者や全米科学アカデミーの会員を含む700人の署名者が集まり、大変な盛り上がりを見せた。しかし、リンゼンによれば、そのうち気候科学者の資格を持つ者は「3,4人程度」しかいなかった。
1990年の全米アカデミーの会合で、会長はこの請願について特に言及し、「自分たちが特別な知識を持っていない問題に信憑性を与える」ことのないよう、わざわざ警告を発した12。
ハリウッド俳優のロバート・レッドフォード、バーブラ・ストライサンド、メリル・ストリープが、レッドフォードの言葉を借りれば、温暖化の脅威を「研究」するだけでなく、「行動」するよう人々に呼びかけた(リンゼンが皮肉ったように、俳優が提案したことは無理もないことだった)。
しかし、気候変動の研究にどれだけの資金が投入されるようになったかも、今や明らかである。1989年、ジョージ・ブッシュ・シニア大統領のホワイトハウス上級顧問は、当初この問題に懐疑的だったが、今や政治的圧力は非常に大きく、1989年に気候変動研究のための連邦予算の大幅な増額を許可している。次の4年間で、この予算は、わずか1億3400万ドルから28億ドルに増加することになった13。
しかし、リンゼンが指摘するように、地球温暖化に対して両義的であるとみなされるような提案が受け入れられる可能性は極めて低いことが、すぐに明らかとなった。1989年の冬、MITの同僚であるレジナルド・ニューウェル教授のデータ分析が、前世紀に温暖化があったことを示すことができなかったため、全米科学財団から資金援助を打ち切られたことを彼は回想している(ある審査員は、彼の結果は「人類にとって危険」であると示唆した)14。
これは、「コンセンサス」に対する批判者を議論から締め出す圧力がいかに冷酷なものになっているかを示すものであった。リンゼン自身が、地球温暖化論に対する批評を米国科学振興協会の機関誌『サイエンス』に投稿したところ、彼の論文は読者にとって「興味のない」ものとして拒絶された。しかし、驚いたことに、『サイエンス』誌は未発表の論文にもかかわらず、彼の論文を攻撃してきたのだ。
その中には、1970年代には世界が新しい氷河期に向かっているかもしれないという信念を支持していた科学者で、現在は温暖化の主要な擁護者の一人であるスティーブン・シュナイダーによるリンゼンへの攻撃も含まれていた。
しかし、この論文に寄せられた読者からの手紙は、人為的な温暖化に対して懐疑的なものがほとんどであった。アメリカ気象学会とアメリカ物理学連合に所属する気候科学者を対象にしたギャラップ社の世論調査では、49%もの人が人為的温暖化を否定している。人為的な温暖化があると考える人はわずか18%で、33%は「わからない」と答えた。
リンゼンは、IPCC報告書に参加した科学者の多くが、次のようなことを述べている。
現在のシナリオを支持する結果を強調し、他の結果を抑制するように圧力をかけられたことを証言している。この圧力はしばしば効果的であり、参加者を調査したところ、最終報告書に対してかなりの異論があることが判明した15。
「なぜ、温暖化問題で科学的な一致を求めるのか」と、Lindzen は問いかけた。結局のところ、彼は次のように観察している。
科学における全会一致は、はるかに複雑な問題においては事実上存在しない。『地球温暖化』のような不確かな問題で全会一致というのは、驚きと疑念を抱かざるを得ないだろう。さらに、なぜ科学者は専門分野に関係なく意見を求められるのだろうか。生物学者や医師が、高エネルギー物理学の理論を支持するよう求められることはまずない。どうやら、「地球温暖化」に関しては、科学者であれば誰でも賛成してくれるようだ。
「コンセンサス」の支持者たちは、自分たちの正統性にあえて疑問を呈する人々に対して明らかに焦りを感じ始めていた。このことは、ジャニスの集団思考の3つのルールの最終段階、すなわち、「コンセンサス」に異を唱える者に対し、冷酷なまでに擁護しなければならない、ということにつながる。これは、「コンセンサス」の支持者にとって必要なことである。プロパガンダの観点からだけでなく、批判者がいても安全に無視できることをより広い聴衆に示すため、また心理学的な観点から、「コンセンサス」が疑いなく正しいという彼ら自身の信念を強化するためである。
ルール3:「非信仰者」を蚊帳の外に置く
論文で述べたように、リンゼンの懐疑的な見解が知られるようになると、彼は毒牙にかけられ、例えば、上院の民主党多数党指導者ジョージ・ミッチェルが1991年に出版した『炎上する世界:絶滅の危機にある地球を救う』などの本にまで登場するようになった。実際、このような扱いを受けているのはリンゼン一人ではない。例えば、アル・ゴアは、ニューヨーク・タイムズ紙の記事の中で、皮肉にも、自分と同じ考えを持つ人々を、当時の不寛容なコンセンサスに対して勇敢に真実を主張したガリレオになぞらえて、嘲笑の対象にしている。
しかし、「コンセンサス」の支持者がいかに批判を抑圧することに悪質になっているかは、「コンセンサス」に与しないことを公にした他の二人の著名な科学者の運命が物語っている。1992年の夏、アル・ゴアは、今やアメリカにおける地球温暖化問題の代表的な政治家であり、民主党の副大統領候補に立候補していた。選挙運動の一環として、彼は『アース・イン・ザ・バランス』という本を出版し、地球温暖化 は「私たちがこれまでに直面した最悪の脅威」であると主張した16。
ゴアは、ハーバード大学時代の1960年代半ばに、この脅威を最初に警告してくれた人物、著名な海洋学者ロジャー・ルベールに対して熱い賛辞を送った。1950年代、カリフォルニア大学サンディエゴ校の学科長だったルヴェルは、ハワイのマウナロア火山の頂上に、大気中の二酸化炭素濃度を測定する観測所を設置することに尽力していた。その結果、二酸化炭素の濃度が着実に上昇していることが分かり、地球温暖化に対する警鐘を鳴らすきっかけとなった。
ルヴェルは、温室効果ガスと気温の関係を認識していたものの、ゴア自身が主張する温暖化対策よりもはるかに慎重な見方を長年していたことを、ゴアは1992年の著書執筆当時は知らなかったようである。1988年7月、ハンセンがワースの上院委員会で証言して話題になった後、ルヴェルはある国会議員に手紙を出した。
この問題に詳しいほとんどの科学者は、今年の気候が「温室効果」の結果であることにまだ賭けようとしない。存知のように、気候は年によって大きく変動し、その原因もよく分かっていない。私個人の考えとしては、温室効果が人類にとって良い意味でも悪い意味でも重要であると確信するには、あと10年か20年待つべきだと思っている17。
その4日後、ルヴェルはヴィルトに宛てて、次のような注意を促している。
4 日後、ルヴェルはヴィルトに次のような注意を促している。「温暖化の速度と量が明らかになるまで、過剰な警戒心を抱かせないよう注意する必要がある」。この夏の猛暑と干ばつが、地球規模の気候変動の結果なのか、それとも単に気候変動の不確実性を示す一例なのかは、まだ明らかではない。私自身の感覚では、確信に満ちた予測を立てるには、あと10 年は待った方がよいと思っている18。
1990年、アメリカ科学振興協会の会議で、ルヴェルは旧友のフレッド・シンガー博士に声をかけられた。彼は当時バージニア大学の環境科学教授だったが、1960年代にはNASAと協力してアメリカの国立衛星気象局を設計し、初代局長として設立に携わった人物だった。二人は、地球温暖化に関する非公式の論文を一緒に書こうという話になり、シンガーは、発行部数の少ない雑誌『コスモス』に投稿するための下書きをすることになった。シンガーとルヴェルは校正について話し合い、いくつかの修正に合意し、その論文は1991年4月に出版された。その論文のタイトルは「温室効果ガスをどうするか:跳ぶ前に見てほしい」であった。彼らの主な主張は、ルベールが以前、議員に宛てた手紙の中で表明した意見と同じで、次のようなものだった。
「温室効果ガスの影響を遅らせるために、思い切った、急な、特に一方的な手段をとれば、雇用と繁栄を犠牲にし、効果もないのに世界の貧困の人的コストを増大させることになる。今、厳しい経済規制を行えば、特に発展途上国にとっては経済的に壊滅的な打撃を与えるだろう。…..」。
彼らはこう結論づけた。
温室効果ガスの科学的根拠は不確かであり、現時点で思い切った行動をとることはできない。
この論文はほとんど注目を集めず、その3カ月後、最後までプロとして活躍したルヴェルは82歳で亡くなった。しかし、その年の暮れ、シンガーが地球温暖化に関する本への寄稿を依頼され、彼らの論文を再掲載することを提案した。
翌1992年夏、アル・ゴアが副大統領候補として奮闘していたとき、『ニュー・リパブリック』紙は、彼の新著の中で言及されているルヴェルと、シンガーとの共著の中で述べられている見解との対比を取り上げた19。ゴア氏の対応は、論文中のルヴェルの見解が「文脈から完全に切り離されている」と抗議するだけでなく、側近の一人であるハーバード大学のジャスティン・ランカスター博士を使って、論文からルヴェルの名前を削除するようにシンガー氏に依頼することであった。しかし、これはすでに出版されていたため、現実的ではなかった。
しかし、ランカスターは、ルヴェルは論文の共同執筆者ではなく、「彼の反対を押し切って」名前が載せられただけだと主張し、シンガーが精神能力の衰えた病身の老人に圧力をかけたに違いないとまで言って、その努力を続けた。
ゴアが米国副大統領に就任した後、ランカスターが再び告発すると、シンガーは1993年4月、名誉毀損で彼を訴えた。そして、これがきっかけで驚くべき事実が判明した。ランカスターは、シンガーがルヴェルの能力の衰えを利用した極めて不適切な行為であると指摘した。
しかし、ランカスターは、ルヴェルは実際「最後まで精神的に鋭かった」ことを認める用意があるようだ。また、ランカスターは、出版前にルベールからこの記事を見せられ、「真実でないことは何もないようだ」と言われたことも認めている20。
1994年2月、ABCニュースの司会者テッド・コッペルは、ナイトラインの番組で、ゴア副大統領から直々に電話を受け、彼が「反環境保護運動」と呼ぶものの背後にある政治的、経済的悪しき勢力を暴くように勧められたことを明らかにした。特にゴアは、シンガーをはじめ、地球温暖化に懐疑的な意見を述べる科学者が、石炭産業などの化石燃料の利権から金を受け取っている事実を暴露するよう求めていた。
このような告発は、すでに議論の常套句となりつつあった。しかし、コッペルがゴアのはったりに対抗して、副大統領からの電話を放送で報告したとき、一流のニュース番組を使って敵の信用を落とそうとしたこの試みは、政治的混乱を引き起こし、その後まもなく、ランカスターはシンガーに全面的に撤回と謝罪をして決着した22。
この残念なエピソードは、集団思考にとらわれた人々が、自分たちに賛同しない人にどのような反応を示すかを、さらに生々しく示している。ジャニスが示したように、彼らが認めようとする唯一の証拠は、自分たちの考え方を裏付けるものであるため、異論を唱える者は、無礼な動機からそうしているだけだと信用を落とし、ステレオタイプ化し、戯画化しなければならないのだ。
反対者が提起している点を取り上げようとするのではなく、彼らの人格に対する悪口攻撃で対抗するのが常套手段である。そのような人たちに耳を傾けてはいけない理由を説明するために、何か暗い理由を見つけなければならない。例えば、彼らはお金をもらっているから「コンセンサス」に疑問を投げかけているだけだと示唆するようなものである。
しかし、このようなプロパガンダ戦術は、幻想の「コンセンサス」が道徳的優位を保持し続ける限り、有効であるに過ぎない。
6. その時が来たアイデア
私たちを団結させる新しい敵を探しているうちに、私たちは、公害、地球温暖化の脅威、水不足、飢饉などが当てはまるという考えに行き着いた。これらの危険はすべて人間の介入によって引き起こされている。..ならば本当の敵は人類そのものである。
ローマクラブの報告書「第一次地球革命」(199123年
これまでのところ、この信念体系の起源が、集団思考の仕組みの完璧なケーススタディとなることを、この典型的なパターンの三つの段階すべてが、地球温暖化の物語のまさに始まりからいかに早く出現したかを実証することによって、詳しく見てきた。この後、ジャニスのルールがいかに一貫して地球温暖化問題を形成し続けたか、より顕著な例を挙げながら、より要約した形でこの物語を追っていくことにしよう。しかし、その前に、1980年代後半に地球温暖化の「物語」が「来るべき時期の考え」として広く急速に定着した2つの深い心理的理由を簡単に考えてみる必要がある。
第一の理由は、1950年代後半から1960年代にかけて起こった、「環境保護主義」や「環境運動」として知られるようになった集団意識の深い変化である。これは、歴史上初めて、科学が人類に地球上のすべての生命を破壊する力を与えたという認識であった。この思想の最高の表現が、核戦争の可能性が投げかける恐怖の影であることは明らかである。冷戦によって、世界は2つの大きな陣営に分断された。それぞれが水素爆弾を搭載したミサイルで武装し、即座に壊滅的な破壊をもたらすだけでなく、地球の大部分を住めなくしてしまうほど放射能を拡散させることができる。
しかし、この認識は、有毒化学物質、近代農業の方法、破壊不可能なプラスチック廃棄物による海の汚染、人口過剰の圧力、人間の活動によって多くの種が絶滅の危機にさらされているという証拠など、人類がすでに自然や自然環境に与えている被害についての新しい認識とも重なっていた。
1958年には核軍縮キャンペーンが、1961年にはWWFが設立され、1962年にはレイチェル・カーソンが農薬による野生生物への脅威を訴えて大ベストセラーとなった「沈黙の春」が生まれた。1960年代の終わりには、グリーンピースとフレンズ・オブ・ザ・アースという、最も影響力のある2つの環境保護団体が設立され、当初は核の脅威に焦点を当てた活動を行っていた。
1968年にアポロ11号が撮影した柔らかな青い地球の写真「Earthrise」ほど、当時の新しいムードを捉えたイメージはない。「私たちが手に入れた唯一の惑星」として、地球が人類の破壊的な力に対していかに脆弱になったかを示していると、広く解釈されている。
1972年、モーリス・ストロングが国連のために企画し、彼自身の政治的意図に従って形成された、最初の「世界環境会議」が開催された。同年、ローマクラブが発表した『成長の限界』 (The Limits to Growth)は、世界で3,700万部も売れ、コンピュータモデルを用いて、人口増加がやがて食糧生産と天然資源を追い越し、文明の存続を脅かすようになることを示した。
人類が地球の未来にもたらす他のあらゆる脅威とは別に、(もちろん核によるホロコーストは別として)最悪の事態は、人間が排出する温室効果ガスによる地球温暖化の暴走によって、地球上のすべての生命が滅亡する可能性があるというものであった。
だからこそ、冷戦が終結し、ソビエト共産主義帝国が突然崩壊し、一夜にして核戦争の恐怖がなくなると、核兵器と原子力に反対することで設立された環境保護団体が、人為的な地球温暖化の脅威に立ち向かうことを新しい大義として、スムーズに変身することができた。WWFも、絶滅の危機に瀕した生物種の保護という本来の目的に、地球温暖化対策が新たに加わったという理由で、これに参加した。
この新しい大義の成功の鍵は、まさにそれが道徳的感覚に訴えかけるものであったということだ。この運動に巻き込まれた人々は、前例のない大災害から「地球を救おう」とする「善人」を支持しているのだと確信した。しかし、彼らはこうして、人間の集団心理の非常に古く、原型的なパターンに当てはめることになった。聖書のノアの物語以来、歴史(あるいは神話)は、人類が世界の終わりを脅かす巨大な災害に直面していると信じられているエピソードで満ちていた。このような千年王国説に共通するのは、それが道徳的に間違った方向に進んでしまった人類の邪悪さへの罰であるという確信であった。このシナリオの強力な魅力は、化石燃料に依存する道を歩んで人類を破滅に導いた「悪者」と、それがいかに危険な誤りであったかにようやく気づいた「善人」とに世界を分けることであった。この新しい聖なる大義に参加することは、地球上のすべての生命に死をもたらす道を盲目的に歩み続けるのではなく、「生命」の側に立つことを選択することである-ただし、人類が時間内に目を覚まし、それだけで救いをもたらすことができる非常に思い切った行動をとるよう説得できない限りは。
集団思考のいかなる形態も、自分たちが道徳的に優位な立場にあるという確信に依存しているとすれば、地球温暖化をめぐる「コンセンサス」は、それ自身初の真の道徳的挑戦に直面しようとしていた。そのとき初めて、最も権威ある機関であるIPCCの内部で、深刻なスキャンダルが明るみに出た。
22. 結論 集団思考が現実と出会うとき、何が起こるか?
大きな信念が絶望的な状況に陥る正確な瞬間は簡単にわかる。あらゆる一般的な信念は虚構に過ぎず、それを検証しないという条件下でのみ生き残ることができる。
ギュスターヴ・ル・ボン「群衆」
本稿の結論は、3つの部分に分かれている。第一は、地球温暖化騒動を引き起こした集団思考の致命的な欠陥は何であったのかについて、全般的な回顧を行う。第二は、集団思考があまりにも強力に定着してしまったために、その支配力をどうすれば断ち切ることができるかを想像するのが難しいかもしれない、より明白な理由のいくつかを要約したものである。しかし、3つ目は、実際にそれがすでに起こっていることを示唆している。最近の出来事から、人為的な地球温暖化が地球の将来に未曾有の脅威をもたらすという世界的な政治的「コンセンサス」が、真のコンセンサスでは全くなかったことが確認された。そして、このことがついに全体のストーリーを変え始めた。
グループシンクの致命的な欠点
「Nullius in verba」王立協会のモットー
20世紀後半から21世紀初頭にかけての人為的な温暖化に対するパニックは、科学や政治の歴史上最も奇妙なエピソードの一つとして、後世に語り継がれるかもしれない。しかし、そのような現実逃避がなぜ起こったのかを理解するためには、人間の集団心理、特に集団思考の性質を定義するルールについて言及しなければならないだろう。もちろん、このような集団思考の勝利は、偉大な宗教の歴史や、マルクス主義に基づく信念体系が20世紀の大半を通じて世界の広大な地域を支配したように、世界では以前にも見られたことである。
地球温暖化のイデオロギーは、決定的な点で、これらの例と多くの共通点がある。これらの例と同様に、地球温暖化も、空想的な考えに取り付かれたごく少数の人々から生まれた。また、仮説的な未来に対する予測、つまり予言に基づいており、その正否を決定的に証明することができないのも、これらの例と同様である。それゆえ、彼らと同じように、この信念体系はすべての良識ある人々の「総意」によって信奉されなければならないと主張し、社会的、政治的、心理的なあらゆる圧力を用いて、この信念体系への適合を強制することが重要になった。そして、彼らと同じように、この信念体系の一部とならない人物は「異端者」「破壊者」「否定者」として非難され、その反対意見は多かれ少なかれ冷酷に弾圧されなければならないという反応を必然的に形成した。
しかしこの最新の例が他のものと異なっていたのは、それが近代世界において科学に与えられている比類なき権威に基づいていたことだ95。そしてここに、やがてその致命的な弱点が証明されることになる。他の信念体系とは異なり、この信念体系は最終的に、経験的に検証可能な事実に対してテストされる可能性があるのだ。それは、極めて重要なコンピューターモデルによる予測に依存しており、年月が経つにつれて、実際に起きていることの客観的証拠と比較できるようになった。
最初の10年間ほどは、存知のように、大気中の二酸化炭素が増加した結果、世界が温暖化したという説はまだもっともらしく思えた。しかし、1998年以降、予測と現実の証拠が次第に乖離し始めた。そして、グループシンクの中の人々の反応は、適切な科学の原則が指示するように、理論自体に何らかの欠陥があるのではないかと問うことではなかった。
「コンセンサス」の中にいた何人かの科学者は、実際に、なぜ予言が証拠によって確認されなくなったかを説明できるような理論の修正を考え出そうとした。2007年頃、地球の気温が驚くほど低下したため、彼らは初めて、世界の主要な海流の変化などの「自然要因」が、IPCCのコンピューターモデルが許容していた以上に、気候形成に影響を与えていないのではないか、と考え始めた96。しかし、彼らもまた、これらの自然要因が「根本的な温暖化傾向を覆い隠している」だけで、やがてそれが再び現れると示唆することで、このことを説明しようとした。あるいは、人為的な温暖化によって生じた熱は、「海に隠れて」見えなくなっただけだとも言った。
この主張は、2013年のIPCC第5次評価報告書でも支持され、一時停止の間に世界に流入した余分な熱の「93%」が海洋に吸収され、地表の気温を上昇させたのはわずか1%だったと認めている97。他の科学者は、モデルが間違っていたという証拠が増えていることを単に無視するか、もっと悪いことには、理論が予測したように世界はまだ本当に温暖化していると示すために地表温度の記録の大規模な「修正」のように証拠を操作し始めたのだ。実際、「コンセンサス」に属する人々が、自分たちの主張を支持するために科学的データを操作しようと繰り返し試みたことほど、この理論に根本的な疑問があることを明確に疑わせるものはないだろう。その最たるものが、「中世温暖期の存在を消し去り、世界は歴史上最も暑い時代になった」と主張する、あの拷問のような努力であることは言うまでもない。
しかし、このような事態を招いた背景には、科学界だけでなく、政治家やメディアなど多くの人々が、人為的温暖化説を疑問視することなく受け入れる用意があったことも大きく関係している。
本稿の冒頭で、「二番煎じの力」という見出しのセクションで、「コンセンサス」に従う大多数の人々が、それを真剣に研究したり証拠を自分で調べたりしたことがなかったからそうなっただけだということが明らかであることを見てきた。彼らは、単に他人から言われたことを自分の意見としていたのだ。その意味で、「コンセンサス」の受け入れは、伝染病のようなものであった。なぜ、そう思うのか」と問い詰めると、「実は、何も知らないのだ」ということがよくある。彼らの頭の中は、マントラや誤った情報 (例えば、北極の氷の消失がホッキョクグマの生存を脅かしているというような)で一杯で、それらはしばしば明らかに真実とは正反対のものだった。
しかも、これは多くの一般市民だけに当てはまることではない。環境ジャーナリストや政治家、そして多くの科学者たちなど、お金をもらっている人たちや、よりよく知る資格を持った人たちにも同じことが言えるのだ。私の隣人は、有名大学の化学の教授であったが、地球温暖化について語るとき、「科学者」としての権威を誇示するのが好きだった。しかし、彼は、気候変動による海面上昇で、サマセットの丘の上にある私たちの村もいずれ水没すると、厳粛に語るのだった。
このように確信に満ちた無知が、「真の信者」の顕著な特徴の一つを明らかにしている。「コンセンサス」の外にいる人々は、彼らと真剣に対話することが不可能なのである。集団思考に取り付かれた人々は、自分たちが知っていると思っていることを「知っている」と思い込んでいた。同じ信念を持つ人たちとのみそのことについて話すことに慣れていた。自分たちの確信に反すると思われる証拠には、まともに目を向けることができないのだ。
自分たちの意見に反対する人たちに対する唯一の反応は、まず、そんな愚かな人がいるとは信じられないということであり、次に、「否定者」たちに対する唯一の適切な対処方法と考えられている軽蔑的な罵倒に訴えることであった。
もちろん、実際には、リチャード・リンゼンやポール・ライターのような懐疑論者たち自身が、正しい科学を守ろうとしていた。また、最終的には、例えばプリンストン大学のベテラン物理学者であるフリーマン・ダイソンとウィル・ハッパーのような世界の科学界で著名な人物も含まれるようになった。「コンセンサス」の支持者たちこそ、正しい科学の原則を悲劇的に裏切っていることが、彼らにはわかった。
しかし、これは「コンセンサス」のヒエラルキーの頂点に立つ大物たちにも同じことが言える。これまで見てきたように、クライメイトゲートの電子メールに関わった上級科学者たち、あるいは「主任科学者」のデイヴィッド・キング卿や王立協会会長のメイ卿、ポール・ナース卿といった権威ある人物が示したのもまさに同じ態度だった。世界で最も古く、最も尊敬されている科学者団体のモットーが、1660年代以来「nullius in verba」、一般に「誰の言葉も借りない」と訳されてきたことは、(少なくとも王立協会の多くの反対派会員によって)なんと皮肉なことだろう、と観察された。ロバート・フック、ロバート・ボイル、アイザック・ニュートンの時代から、この権威ある学会の数え切れないほどの優れたメンバーが知っていたように、科学的手法においてこれ以上に基本的な原則はない。新しい科学的命題は、それが証拠によって適切にサポートされていることを証明できない限り、「他人の言葉」だけで真実として受け入れられてはならないのだ。仮説を検証するためには、すべての証拠に目を通し、その理論を無効にするようなものがあれば、それも十分に考慮しなければならない。
このように、「二酸化炭素=地球温暖化」説は、すべてをひっくり返してしまった。欧米の科学者たちは、この説の単純さに流されて、三次元的な科学的検証をすることがなかった。そして、その通りにコンピュータ・モデルを作り上げた。そして、その理論に何らかの欠陥があることを示唆する議論に対しては、無視するか、嘲笑することだけが必要な反応だと考えていた。
理論が予測どおりにはならないことを示す証拠が増え始めても、その反応は、理論の端々を修正する方法を見つけて、まだ理論が維持できるようにするか、単に理論をまだもっともらしく見せるための新しい「事実」を作り上げるかのどちらかであった。このように、最初から、仮説の検証や真の科学的議論を行うことなく、「他人の言葉を信じる」ことを基本としていた。そのため、自分たちの説を支持するような証拠を集めようとしても、そうでない事実がどんどん入り込んでくる。
だから、いつの日か後世の人々がこの物語を振り返って、「一体どうしてこんなことが起こったのだろう」と不信と驚きを抱くことになる。
結論の2番目に進む前に、アイザック・ニュートンの言葉を引用するのは不適切ではないだろう。
私は、海辺で遊ぶ少年のように、時々、普通より滑らかな小石やきれいな貝殻を見つけては気を紛らわせていたようだが、目の前には真実の大海が広がっていたのだ。
そして、トーマス・クーンの代表的な著書『科学的革命の構造』(1962)と地球温暖化に関する「コンセンサス」の関連性について一言付け加えよう。クーンの論文は、科学の歴史は支配的な「パラダイム」の普及によって特徴付けられるというものである。パラダイムは、科学のある領域における全体的なコンセンサスを提供し、大多数の科学者は、その特定のパラダイムが一般に受け入れられ続ける限り、思考と研究を続ける。クーンが取り上げた最も有名な例は、1500年以上にわたって支配してきたアリストテレス/プトレマイオスの地動説である。このパラダイムは、コペルニクスが1543年に亡くなる直前に発表した、太陽を太陽系の中心に置くという新しい宇宙論モデルによって、ようやく道を開き始めた。しかし、それでもコペルニクスのモデルが完全に受け入れられるまでには長い時間がかかった。古い地動説のパラダイムが依然として強力に残っていたからである(ガリレオが約1世紀後にそのことを発見した)。
クーンが言及していない、より迅速なパラダイムシフトのもう一つの身近な例は、ルイ・パスツールが、病気の主な原因の一つは「汚れた空気」中での「自然発生」(いわゆる「瘴気」説)という支配的な正統派に挑戦した後のものであった。パスツールは、病気の本当の原因は、空気中に存在するバクテリアとウイルスという微生物であることを明らかにした。しかし、パスツールでさえも、当初は既存のパラダイムに縛られた人たちから激しい反発を受けた。なぜなら、彼らの思考、キャリア、評判はすべてこのパラダイムに依存していたからだ。というのも、このパラダイムに思考、キャリア、評判のすべてが依存していたからだ。彼らは、慣れ親しんだバブルの外側で考えることができなかった。
温室効果ガスと気温という単純な方程式を中心に、現代の支配的なパラダイムとして確立された地球温暖化に関するコンセンサスについても、今日、同じような問題に直面している。
クーンは、あるパラダイムが最終的に取って代わられるまでに、しばしば厄介な「異常」が明らかになり、その中で、確立されたコンセンサスに対する信念を捨てずに説明しようとすることを示した。もちろん、「二酸化炭素の増加=気温の上昇」という正統派の学説がそうであったように。観測された証拠を予測するコンピューターモデルの失敗から、気候に影響を与えるあらゆる自然要因まで、あらゆる種類の異常が生じたが、パラダイムがあまりにも粗雑で適切に考慮されていない。
クーンが述べたように、本当の意味でのパラダイムシフトは、すべての証拠を説明できる新しい理論が出現したときにのみ起こるのである。そして、単純すぎる地球温暖化理論の問題は、それがすべての証拠を説明するには全く不十分であることを示唆する十分な異常が発生しているにもかかわらず、それに代わる十分包括的な新理論がまだ現れていないことである。
その理由は、悔しいほど単純である。私たちは、気候を実際に形作っているものが、どのような理論的枠組みでも対応しきれないほど複雑であることを、十分に理解した。私たちはジグソーパズルの新しいピースをたくさん持っているが、それらが表す全体像はまだ見えていない。
実際、エルニーニョ-南方振動のような自然現象が、これまでのパラダイムが認めていたよりもはるかに大きな影響を地球の気温の変動に与えていることは、認識され始めている。太陽放射と気候の相互作用については、1801年にウィリアム・ハーシェルがその関係を初めて観測して以来、ずっと知られてきたし、過去30年の間にこのテーマについて多くの重要な新しい研究がなされてきた。しかし、地球が最後の氷河期を脱した後の地球の気温の変動については、まだ誰も包括的な説明を始めていない(それ以前の地質時代から続く、より劇的な変動についてもわかっていることは言うまでもない)。
中世の温暖期をもたらした気温の上昇はなぜ起きたのか?また、何世紀にもわたる小氷河期をもたらした気温の低下は何だったのか?そして、過去30年間の緩やかな温度上昇を連続体の一部とみなすことができる現代の温暖化の2世紀を特徴づける温度上昇への回帰は、何を説明するのだろうか?
実は、これらの自然現象について、私たちは適切な説明を持っていない。世界の気候の形成に間違いなく関与しているさまざまな要因について知れば知るほど、既知と未知の両方の「未知」がまだたくさんあることを受け入れなければならない。
しかし、ニュートンとは異なり、多くの科学者は、自分たちがどれほど多くのことを知らないかということを認めるわけにはいかない。簡単に説明できそうなバブルの中にとどまり、自分たちのパラダイムの中で夢想されている以上のことが「天と地にはある」かもしれないと示唆する人を無視するか嘲笑する方がずっと安全である。
では、世界はどうなっているのだろう。いつ、どのようにして現実が明らかになるのだろうか?
もし、気温に取るに足らない上昇があるとすれば、それは人為的な要因ではなく、地球そのものと太陽活動に関連した自然な要因によるものである。二酸化炭素のレベルと気温の変化の間に正の相関関係があることを確認する証拠はない。全体主義的イデオロギーに基づいた最大の国際的冒険…偽情報と偽造された事実を用いて自分たちを守ろうとするものを見るとき、これを「戦争」以外に表現する言葉を考えるのは困難である。
アレクサンドル・イラリオノフ、モスクワ 200498
この物語をよく知る観察者たちが長い間抱いてきた疑問は、「いつ、どのようにして、ついに現実が押し寄せ始めるのか」ということである。このような妄想の霧をようやく払拭し始める可能性のある要因は何なのだろうか。
もちろん、現実の問題は、とりわけ欧米では、集団思考のパラダイムがあまりにも蔓延しており、2017年になっても、その支配を最終的に打ち破れるとは到底思えないことである。そして、その最大の障害は、このドラマのさまざまなプレーヤーが、学問的にも、経済的にも、イデオロギー的にも、どれほど集団思考に依存してしまっているかということだ。まず第1に、ほぼすべての主要な科学機関、科学雑誌、大学を含む、西洋の科学界のほぼ全体に対して行使されるようになった呪縛がある。多くのキャリアと評判が「コンセンサス」と完全に一体化しているため、多くの関係者が考えを改めることなど、ほとんど想像もつかない。彼らは、「気候産業」として知られるようになったものの一部であり、特に、公式見解を疑うことなく遵守することに研究資金を依存する学者の軍団はその典型である。
気候産業のもう一つの重要な部分は、WWFやFriends of the Earthのような「環境」ロビー団体であり、彼ら自身が国際的な気候変動対策の確立において重要な役割を担ってきた。これらの団体の多くが政府から巨額の資金援助を受けていることは、現在でも一般には理解されていない。この団体は、公然とキャンペーンを行うだけでなく、政府に対する圧力団体として、「クリーンでグリーンな」エネルギーを推進し、「汚い」化石燃料を排除するためにこれまで以上に思い切った措置を取るよう求めているのだ。
既得権益という点では、このような「グリーン」エネルギー計画そのものに与えられる巨額の補助金に比べれば、取るに足らない。世界中にある何十万もの風力タービンや何百万ものソーラーパネル、石炭から「バイオマス」燃焼へと転換した発電所、食用からエネルギー作物に転換した数百万の農地、「環境にやさしい」バイオ燃料のために伐採した広大な熱帯雨林、後者は生態系にとって計り知れない災害と言える。
「脱炭素化」を急ぐあまり、他の多くの金融利権が後戻りの邪魔をしているが、もう一つ、単に儲かるからというだけでなく、あまりにも露骨な皮肉であるため、言及しなければならないことがある。リオサミット当時、モーリス・ストロングが中心となって考案された「炭素取引」と呼ばれるシステムほど、未来の世代が異様と感じる気候変動産業はないだろう99。すでに指摘されているように、これは中世後期の「免罪符」販売と同じで、教皇庁は金銭と引き換えに、だまされやすい人々の罪の許しを得た。このような妄信的な行為がまかり通るとは、現代では信じがたい。しかし、私たち自身のバージョンは、UNFCCCの後援の下、二酸化炭素を排出し続ける権利を企業やその他の組織に売ることで何十億もの利益を得ることができるシステムであり、その見返りに「カーボンクレジット」や「カーボンオフセット」を購入すれば、これまでと同じように「罪」を犯し続けることができるのだ。
無数の受益者を抱える気候変動産業は、ある調査によると、今や世界で年間1兆5000億ドルもの価値を持つまでに膨れ上がっている。これは、ほんの一握りの国を除くすべての国の年間GDPよりも大きい100。そして、これには、「コンセンサス」の物語に流されて、無意識のうちにそれに従ってしまった他の無数の個人や組織のすべてが含まれていない101。これは、英国で最も成功し、尊敬されている慈善団体の一つ、ナショナル・トラストの事務局長が、2015年に「気候変動」がトラストが直面していた「最大の挑戦」だと発表した方法に見られるように、組織が気候問題と金銭的またはその他の面で全く関係がない場合でもよく起こることである。環境省が気候変動法を起草していた当時、環境省のトップ公務員だったデイム・ヘレン・ゴーシュは、地球温暖化による海面上昇によって、トラストが所有する多くの海岸線が「海に落ちる」ことによって浸食されていると説明した。
不思議なことに、国の歴史的遺産を守ることを最大の関心事としていた彼女は、歴史をほとんど知らないようで、海面上昇と土地の陥没でイギリスが島国になって以来、6000年もの間、イギリスの東海岸が後退し「海に落ちる」ことが続いていることに気づいていなかった。これによって、人為的な地球温暖化という信念の勢いを逆転させようとする合理的な試みに対して強力な重石として立ちはだかるようになった他の利益団体の軍隊にトラストが加わり、その恐るべき政治的結果がすべてもたらされることになった。
しかし、この信念とそれに対する政治的対応の両方を動かしている集団思考は、本質的に常に西側世界の国々に集中しており、彼らはそもそも地球規模のパニックを引き起こしただけでなく、それ以来ずっとその主要な推進者であり続けている。実際、この事実こそが、今、この物語の核心であることが判明している。
欧米対その他、ただし米国抜きで
われわれは、パリ協定からの離脱という米国の決定に留意する。..他のG20メンバーの首脳は、パリ協定が不可逆的であると述べている。われわれは、先進国が、途上国を支援するための資金を含む実施手段を提供するというUNFCCCの約束を果たすことの重要性を改めて確認する。..われわれは、パリ協定への強いコミットメントを再確認し、その完全実施に向けて迅速に行動する。
2017年7月8日、ハンブルクでのG20会合後に発表されたコミュニケ
この強大なドラマがどのように展開し続けるかという点で、その最も大きな特徴は、「先進国」とそれ以外の国々との間の長年慣れ親しんだ溝であり、そこでは西洋の集団思考の力が現実には常に非常に小さな影響力を行使してきた。地球温暖化をめぐる騒動の最大の皮肉は、1992年にモーリス・ストロングがリオサミットを開催した際に、地球温暖化に対する世界の対応の中心に据えた基本原則が、最終的にどれほど損なわれているかということである。すなわち、排出量の大幅な削減を率先して行うことが期待される西側諸国の附属書I諸国と、経済が西側諸国のそれに追いつくまで排出量の削減を免除されるその他の地域の「発展途上国」とに世界を分割することであった。
京都とコペンハーゲンで、意味のある世界的な「気候変動条約」の合意を二度も妨げたのは、この取引のあからさまに一方的な性質であった。西側諸国が排出量を削減するために、これまで以上にコストがかかり、経済的に損害を与える試みに着手する一方で、「途上国」の経済は成長を続け、中国とインドが世界第1位と第3位の二酸化炭素排出国となるまでになった。
そして2015年、パリがやってきた。欧米の希望的観測に現実が立ちはだかったのは、途上国が今後15年間のエネルギー政策の方向性を示すINDCを発表したときだった。
欧米諸国が求めるものにどう応えていくのか、次々と説明された。中国は20-30年までに二酸化炭素の排出量を100%増加させる計画であった。インドでは200%。世界の排出量上位20カ国に含まれる他の「発展途上国」のほとんどすべてが、ロシアと日本とともに、同様に大幅な増加を予測していた。つまり、アメリカ(まだオバマの時代)とEUは20-30年までに年間の二酸化炭素排出量を17億トン削減することを提案している一方で、インドは49億トン、中国は109億トン排出量を増加させる計画だという全体像が浮かび上がってきた。確かに、これはすごいことだ。
INDCは、わずか15年以内に世界の総排出量が2013年時点の50%近く増加することを示した102。これは、少なくとも二つの意味で、歴史的に重要な瞬間と見なされるはずだ。102 これは、少なくとも二つの意味で歴史的に重要な出来事と見なされるべきである。第一の点は、明らかに、西側諸国の見せかけの意図を示し、その宣言がパリの意図のすべてを完全に嘲笑するものだったということである。しかし、この論文の主題である第二のポイントは、それと同じくらい重要である。それは、欧米の政治家やマスコミが、この出来事をまったく認識せず、報道しなかったことである。欧米での報道だけでパリを知った人は、非欧米諸国がこのような提案をしていたとは思いもよらなかっただろう。INDCを読んだことのあるジャーナリストは、いたとしてもほとんどいなかった。国際的な気候変動対策機関が、真の意味で重要なことは何も達成されなかったと見せかけ、プロパガンダとして流したものでしかないのだ。
だからこそ、1年以上経ってから、トランプ大統領が「グリーン気候基金を含む『パリ協定』から米国を離脱させる」と発表したときには、大きな衝撃を受けた。彼は、西側諸国のリーダーとして初めて、INDCの実際の内容について沈黙を破り、「協定」が全くの見せかけに過ぎなかったことを示した(彼は演説の中で明確に言及した)。
西側諸国の最も重要な政治家が、ついに、過去30年間に苦労して作り上げてきた政治的幻想の全構造に疑問を呈した。トランプ大統領をどう思おうが、彼が決断した理由をどう考えようが、彼の演説はついに、これまで起こったことのないほど、その無茶苦茶な構造を崩し始めた。
しかし、それができたのは、すべての「発展途上」国が、欧米諸国の思惑をそのまま示したからにほかならない。自然エネルギー」の必要性を訴える皮肉な広報活動もあったが、彼らは欧米の集団思考が自分たちに何をさせたいか、何を言わせたいかには無関心であった。
2017年7月にトランプが出席した最初のG20会議の後に出されたコミュニケの見せかけとは裏腹に、地政学的なバランス全体が決定的に変化していた。二酸化炭素の削減を約束した国は、EUに属する国だけとなり、カナダとオーストラリアも加わって、世界の総排出量のわずか11.3パーセントを担っているに過ぎなくなった。G20に含まれる他の附属書1国は、日本とロシアだけであり、世界の二酸化炭素排出量の8パーセントを占めている。そして彼らは、2017年7月のG20のハンブルグ会議後にコミュニケに合意した他のすべての国々と同様に、石炭火力発電所をさらに建設し、それによって排出量を増やすことを約束していた。
その完全に不誠実な文書によって、地球温暖化をめぐる政治的集団思考のまやかしが、かつてないほど不気味に露呈された103。
しかし、究極の皮肉は、パリで起こったこと、つまり、気候体制が条約を手に入れたかどうかにかかわらず、地球の気候の将来には何の影響も及ぼさないということであった。海流のサイクルの変化や太陽の活動といった自然要因の複雑な相互作用によって、これまでと同じように気候は変化し続ける。
パリの決定的な教訓は、集団思考がついに、そして不可逆的にその力を失い始めた瞬間であったということだ。集団思考は、今後何年にもわたって西側世界を支配し続けるかもしれない。しかし、東洋のダイナミックで急成長する経済圏に代表される他の地域は、ほとんど関心を示さないことがますます明らかになるだろう。実際、これは最近起きている顕著な地政学的変化のもう一つの反映に過ぎない。政治的、経済的、文化的に、西洋は数世紀にわたって享受してきた世界における卓越した地位とそれに伴う権威を次々と失い始めている。中国やインドをはじめとする他の国々が、欧米に取って代わり、追い越そうと動き出している。中国はここ数十年で世界第2位の経済規模に成長し、インドも急速に追い上げており、ある指標ではすでに第4位となっている。今世紀半ばには、この人口の多い2つの国が2大経済大国になるだけでなく、インドが中国を追い抜くかもしれないとの予測もある。
このように、近年、西欧、とりわけヨーロッパの政治力と影響力が相対的に低下していることを示す兆候が多く見られる。この点で、パリで拘束力のある気候変動条約を得ようとした西側の試みが拒否され、その後、パリが達成したとされるわずかな成果からもトランプが撤退したことは、気候変動の大脅威がついにその力を失い始めた瞬間としてだけでなく、振り返られるかもしれない。それは、私たちが今ようやくその本質を認識し始め、その全貌をまだ予見できない、より広い歴史的プロセスにおける重要なランドマークの1つと見なされるかもしれない。間違いなく、私たちは今、物語の中でまったく新しい章に入りつつあり、ヨーロッパとイギリスが非常に居心地悪く孤立しているように見えるものである。遅かれ早かれ、このような新しい現実が外から押し寄せてきて、これまで長い間暮らしてきた科学的、政治的な見せかけのバブルを維持することが非常に難しくなるだろう。
だからこそ、この30年間、現実から逃避してきたものの本質を認識することが、これまで以上に重要になってきている。それは、集団思考が人々を幻想の世界へと連れ去る驚異的な力の最高の例であり、定義上、それは必ず最終的に幻滅に終わるものである。
しかし、人為的な気候変動への信奉は、今日の世界における集団思考の力を示す無数の例の一つに過ぎず、すべてがアーヴィング・ジャニスが指摘した規則に従って同様に行動している。だからこそ、私は個人的なエピローグとして、彼の分析が、私たちが今生きている奇妙な時代について不可解に思っていることの多くについて、より明確な理解を与えてくれる他の例について簡単に触れて終わりたい。
23. 個人的なエピローグ:より広い視野で
人間は、よく言われているように、群れで考え、群れで気が狂う。
チャールズ・マッケイ著「異常な大衆の妄想と群衆の狂気」
私が地球温暖化防止活動推進財団からこの論文の執筆を依頼されたことを嬉しく思った理由は2つある。一つは、このページで実証されたように、ジャニスの集団思考に関する分析が、人類史上最も奇妙なエピソードの一つの本性を新たな光で見るのに役立つからであった。しかし、もうひとつは、彼の論文が人間の集団心理を理解する上で、これまで一般に認識されてきたよりも非常に大きな関連性を持っていることを示す機会を提供したことである。
その理由の一つは、自説を説明するために、20世紀半ばのアメリカ政治史の中で、研究の焦点となったいくつかのエピソードだけを引き合いに出したからだ。彼はそれぞれのケースで、権力の中心にいる小さなグループが、特定の政策に執着するあまり、自分たちの合意内容に疑念を抱かせるような証拠には耳を貸そうとしなかったことを示した。どのケースでも、起こりうるすべての結果を考慮することを怠り、大惨事を招いた。
確かに、最近の歴史では、ジャニスのケーススタディーに加えられるような事例が数多くある。例えば 2003年にジョージ・W・ブッシュとトニー・ブレアが行ったイラク侵攻は、無謀なまでに強迫観念的であった。サダム・フセインを打倒することに集中するあまり、目的が達成された後に何が起こるかをまともに考えず、その結果、イラクは何年にもわたる流血の宗派間の混乱に陥ることになったのだ。
しかし、私が最初にジャニスの論文に出会ったときに特に驚いたのは、彼が特定の限定された例から実証できた以上に(あるいは、おそらく彼自身が気づいている以上に)、人間の集団行動を理解する上でこの論文がどれほど広く関係しているかということだ。地球温暖化の話を新しい視点で見るのに役立つのは確かだが、ジャニスのグループ・シンクの基本法則をいったん理解すれば、歴史上にも、そして私たちを取り巻くますます不可解になる今日の世界にも、より一般的な事例があちこちに見られるようになる。集団思考のほとんどのケースは少数の人々からしか生まれないが、その信念が、何らかの理由でその信念に魅力を感じ、名声の力と二次的思考の伝染力によってそれを共有するように引き込まれた、より多くの人々によって共有されるようになると、同じ規則が適用され続けることが分かる。
集団思考の泡の中にいる人たちは、泡の外を考えることができず、自分の信念を補強する証拠だけを探すので、それに疑問を持つ人たちとまともに対話することは不可能である。そのため、自分たちのバブルの中で安心して、自分たちに反対する無知な部外者に対して道徳的優越感を味わうことができる。
歴史上、宗教の狂信的な曲解ほど極端な例はほとんどなかった。だからこそ、イスラム原理主義に影響を受けたISISやアルカイダのようなテロ運動ほど、集団思考によってメンバーが集団精神異常者になっている例はない。
同様に、このような一般的な図式は、分割された政治の世界が大小さまざまな種類の集団思考の餌食になることを避けられず、どのグループも政治スペクトルの「極左」または「極右」に向かうほど、それがより顕著になることを考慮しなければならない。
このことは、全体主義政権が独自の集団思考を国民全体に押し付けようとする国ほど顕著に表れる。1640年以降のイギリス、1789年以降のフランス、1917年のロシアなど、こうした政権が最初に権力を握るきっかけとなった大革命ほど、歴史が私たちに示すドラマチックな例はない。いずれも、一見抑圧的な支配体制の力を抑えようとしたことが発端となっているが、結局は、それに取って代わるよりもはるかに悪い新たな支配体制が誕生している。
民主主義国家においてさえ、集団思考の極端でないバージョンがあらゆる方法で機能しているのを見ることができる。政治においては、トランプ大統領を当選させた異常に対立的なアメリカ大統領選挙や、英国のブレグジット国民投票における二つの対立するキャンペーンのように、現実とほとんどあるいはまったく関係のない荒っぽい主張を互いに競い合う集団思考の二つの対立形式をよく目にすることができる。
実際、さまざまな形の集団思考は現代においていたるところに見られるようになり、私はジャニスの著書に初めて触れたとき、職業人生の大半を通じて知らず知らずのうちにその例について書いていたことに気づいた。最も奇妙で顕著な例は、ここ数十年、「政治的に正しい」とされる様々なイデオロギー的立場に従わなければならないという強い社会的圧力が高まっていることである。これは現代の「新清教徒主義」となっており、17世紀の初代清教徒たちの不寛容さから連想される独善的な確信がすべて表示されている。ポリティカル・コレクトネスから連想される道徳的憤慨は、ほとんどの場合、抑圧、偏見、差別によって、他のグループを「被害者」に仕立て上げたと見なされる人々に向けられている-「性差別」「人種差別」「同性愛嫌悪」その他何でもそうだ。
同じ基本的な物語が、より狂信的な「動物の権利」運動家たちの意見を刺激している。また、人為的な気候変動が、政治的に正当な理由の羅列に加えられるようになった背景には、地球そのものを「被害者」として捉え、「ビッグオイル」「ビッグカーボン」など、地球を破滅的な温暖化で脅かすあらゆる悪意ある勢力の害から救わなければならない、という考え方がある。
1969年に私が最初に書いた本は、『ネオフィリアックス:50年代と60年代の英国生活における革命の研究』であった。この本は、1956年以降の10年間に起こった社会的、道徳的、文化的変化の爆発的な広がりによって、イギリスがほとんど認識できないほど別の国に変貌してしまったことを分析したものであった。今になってようやく、私が書いていたことの多くが、同じ集団思考のルールによって形成されていたことに気づいた。ポップカルチャー」や「寛容な社会」の台頭から、ハロルド・ウィルソンの「ニューブリテン」まで、その多くは本質的にさまざまな形の集団的仮構に基づいていた。その結果、変化への猛進が始まったときに想像していたものとはまったく異なることが判明するのだ。
1979年、私はBBCのために2時間のドキュメンタリー番組「City of Towers」を制作した。この番組は、1960年代に建築家やプランナー、政治家がイギリスの都市にもたらした混乱が、1920年代に建築家ル・コルビュジエが描いた「残忍主義」の都市ヴィジョンからいかに直接的に引き起こされていたかを追跡するものだった。ここでもまた、思い込みに基づく集団思考が、いかに悲惨で予期せぬ結果をもたらすかを示す、完璧なケーススタディとなった。
1980年代後半から1990年代にかけて、イギリス人の生活に大きなダメージを与えたBSEなどの食の恐怖から、現代で最も野心的な政治プロジェクトである欧州連合の背後にある集団心理まで、ジャニスの論文が明らかに新しい光を当てることができるテーマについて私は後に本を書いた。
そして、ここ数十年、集団思考がBBCの文化をいかに変容させたかを描かなければ、最近の集団思考の力を語ることはできないだろう。地球温暖化に関する執拗な宣伝は、BBCの報道が、その時々の論争的な問題のほとんどについて、同様に一方的な「党是」によって規定され歪められるようになったことの、より顕著な症状のひとつに過ぎない。
しかし、人々がいかにして集団思考に陥ってしまうか、これらの大きく異なる例には三つの共通点がある。一つは、彼らの信念は常に最終的には世界の誤ったイメージに基づいていたことが判明することで、何らかの形で、世界は実際とは異なるものであるという仮定のもとに形成されている。二つ目は、自分たちの信念を共有しない人たちに対して、非合理的なまでに不寛容であることだ。第三は、彼らの集団思考は、最終的には必ず、彼らが見落とした現実と何らかの形で不愉快に衝突して終わるということである。
南海バブルはすべて暴落に終わる。どんなグループシンクも、いずれはその日が来る。それは、人間が自分の頭で考えることを放棄し、群集心理に流されたときに起こることである。
