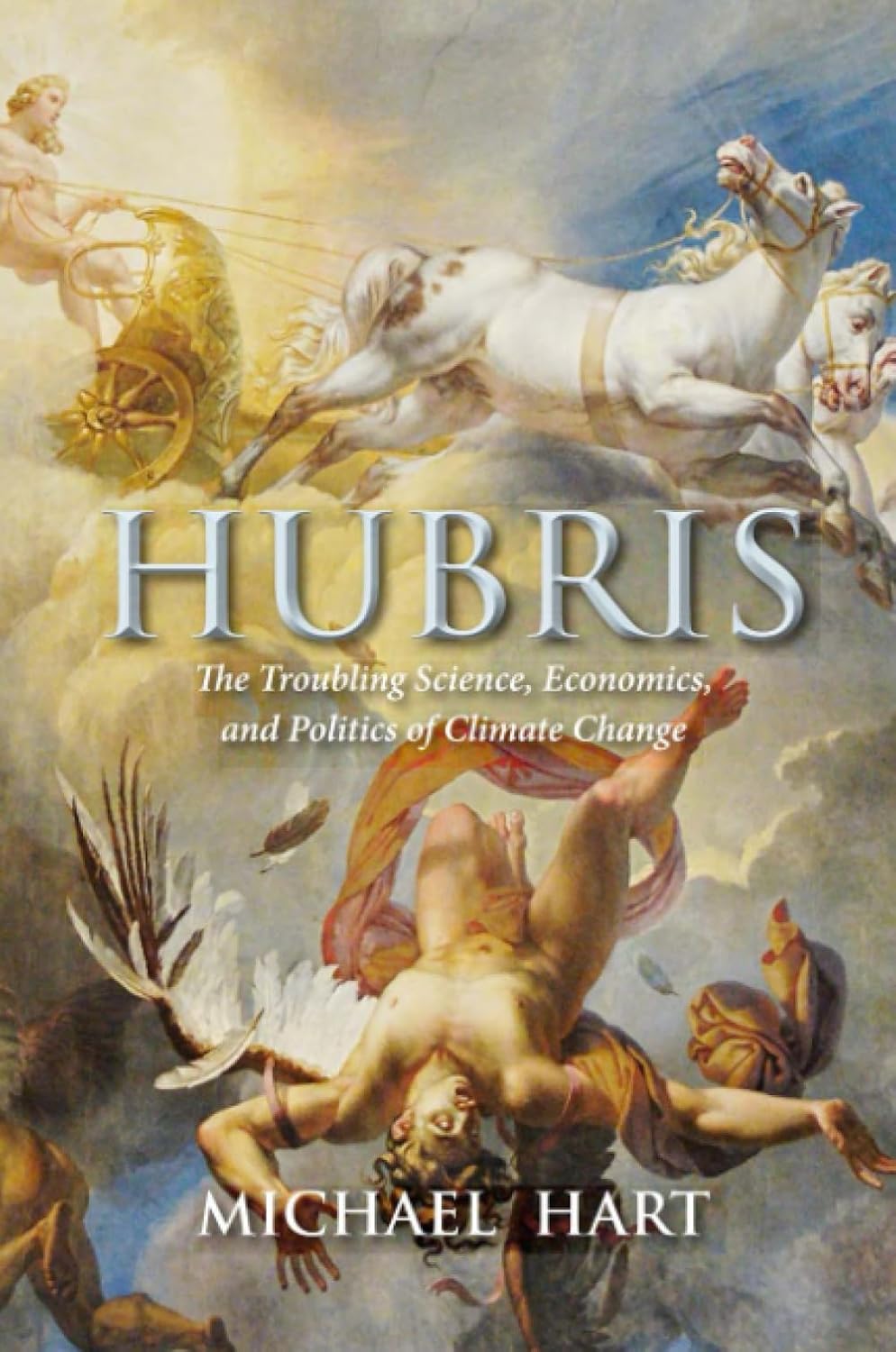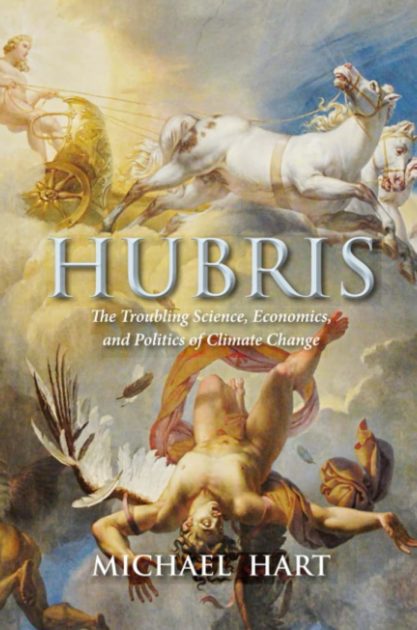
英語:『Hubris:The Troubling Science, Economics, and Politics of Climate Change』Michael Hart 2015
日本語タイトル:『傲慢:気候変動をめぐる厄介な科学、経済学、そして政治』マイケル・ハート 2015
目次
- 序文 / Preface
- 第1章 問題の提示 / The Problem Stated
- 第2章 科学と公共政策 / Science and Public Policy
- 第3章 科学とその病弊 / Science and Its Pathologies
- 第4章 人為的気候変動の科学 / The Science of Anthropogenic Climate Change
- 第5章 IPCCの科学と政治 / The Science and Politics of the IPCC
- 第6章 二次的証拠と影響 / Secondary Evidence and Impacts
- 第7章 科学は確定していない / The Science is Not Settled
- 第8章 緩和戦略の限界 / The Limits of Mitigation Strategies
- 第9章 気候変動政策の経済学 / The Economics of Climate Change Policy
- 第10章 バプテスト、密輸業者、そして機会主義者 / Baptists, Bootleggers, and Opportunists
- 第11章 地球的意識の構築 / Building Global Consciousness
- 第12章 国益 vs. 地球的規範 / National Interests vs. Global Norms
- 第13章 修辞学 vs. 現実 / Rhetoric vs. Reality
- 第14章 美徳を装う不道徳 / Immorality Pretending to Virtue
本書の概要
短い解説:
本書は、気候変動をめぐる議論が科学的不確実性にもかかわらずどのようにして政治的・社会的な「危機」として構築されたかを批判的に分析し、主流派の主張に疑問を呈する読者を対象としている。
著者について:
著者マイケル・ハートは、カナダの元外交官であり、国際貿易政策の専門家。長年の政府勤務の経験から、国際交渉、政策形成、そして科学が政治化されるプロセスについて深い洞察を持つ。本書では、その経験を活かし、気候変動レジームの形成過程を冷徹に分析する。
テーマ解説
- 主要テーマ:科学的主張の政治化:気候科学が不確実性を内包するにもかかわらず、特定の政治的アジェンダを推進するために確定的な「脅威」として提示されるプロセスを描く。
- 新規性:「バプテストと密輸業者」の枠組み:宗教的・理念的な環境活動家(バプテスト)と経済的利益を求める企業や政治家(密輸業者)が連携し、気候変動政策を推進する構図を提示する。
- 興味深い知見:科学の「病理」:資金、キャリア、イデオロギーが科学者の客観性を歪め、データの捏造や誇張といった「高貴な目的のための汚職」を引き起こす実態を描く。
キーワード解説
- 科学的不確実性:気候システムの複雑さゆえに、将来予測や温暖化の影響評価には本質的に誤差と不確実性が伴うという前提。
- IPCC(気候変動に関する政府間パネル):国連の下で気候変動に関する科学的知見をとりまとめる組織。著者は、そのプロセスが政治化され、政策立案者向けに「警報」を強調するよう歪められていると批判する。
- 予防原則:科学的に完全な確証がなくとも、深刻な被害のリスクがある場合には対策を取るべきとする考え方。著者は、これがコストベネフィット分析を無視し、非効率な政策を正当化するために使われていると論じる。
- 高貴な目的のための汚職:より大きな善(地球温暖化の防止)のために、科学者がデータを操作したり、リスクを誇張したりする行為を許容する風潮を指す。
- バプテストと密輸業者:道徳的規制を求める理想主義者(バプテスト)と、その規制から経済的利益を得る者(密輸業者)が暗黙の連携を組み、規制を強化する政治力学。
3分要約
本書『傲慢』は、現代社会において最も議論を呼ぶテーマである気候変動に対し、根本的な疑問を投げかける。著者マイケル・ハートは、元外交官としての豊富な経験を活かし、気候変動をめぐる「危機」がどのようにして科学、経済、政治の複雑な相互作用の中で構築され、増幅されてきたかを徹底的に解剖する。本書の核心は、「人為的気候変動の科学は確定しており、早急な対策が必要である」という主流派の主張に対し、それは科学的な不確実性を無視し、政治的・イデオロギー的なアジェンダを推進するための「傲慢」であると断じることにある。
ハートはまず、現代科学、特に政策に関わる科学が抱える病理を指摘する。ピアレビュー制度の形骸化、研究資金獲得のための競争、そして何よりも「より良い世界」を目指すイデオロギーが、科学者の客観性を損ね、「高貴な目的のための汚職」、すなわちデータの捏造やリスクの誇張を生み出していると論じる。この文脈で、IPCCのような組織は、科学的不確実性を「後ろ暗い不確実性」として扱い、コンセンサスを作り上げることで、その政治的影響力を強めてきたと批判する。
次に、気候変動科学そのものの核心に迫る。地球温暖化の基本メカニズムを認めつつも、現在の気候モデルの限界、過去の気温復元(特にIPCC報告書で有名になった「ホッケースティック曲線」)の問題点、そして実際の観測データとモデル予測の乖離を詳細に検証する。ハートは、極地の氷床融解、海面上昇、ハリケーンの増加など、しばしば温暖化の「決定的証拠」とされる二次的な影響についても、データの選択的解釈や誇張が行われていると指摘する。そして、多くの気象学者、物理学者、統計学者など、気候科学の主流派に異議を唱える専門家が存在する事実を挙げ、「科学者の97%が同意」という言説は誤解を招くと主張する。
さらに、政策論に移り、CO2排出削減(緩和策)の非現実性と経済的非効率性を暴く。現代文明は化石燃料に依存して構築されており、経済成長とエネルギー消費のリンクを断ち切ることは極めて困難である。風力や太陽光といった「グリーン」エネルギーは、その不安定性と低いエネルギー密度ゆえに、化石燃料に代替できないと論じる。炭素税や排出権取引といった経済的手段も、経済成長を阻害するだけで、地球規模のCO2濃度に与える影響は微々たるものであると批判する。対照的に、温暖化には適応策(堤防建設、作物種の変更など)の方が遙かに費用対効果が高いと主張する。
後半では、政治とイデオロギーの側面を深く掘り下げる。ハートは、環境活動家(バプテスト)と、規制から利益を得る企業や政治家(密輸業者)の「不聖なる同盟」が気候変動政策を推進していると分析する。ここには、資本主義批判や「成長の限界」といった、環境問題に仮託されたより深遠な政治的・イデオロギー的アジェンダが存在する。国連は、この「危機」を利用して地球規模のガバナンスを強化しようとしていると見る。主要国の国益と地球的規範の衝突(京都議定書の失敗、コペンハーゲン合意の頓挫)を詳細に追い、国際的な気候変動レジームの脆弱性を明らかにする。
最終章でハートは、気候変動政策の動きを「美徳を装う不道徳」と総括する。貧困層へのエネルギーコスト負担、発展途上国の発展権の阻害といった現実の悪影響を無視し、不確かな未来のリスクに対処すると称する政策こそが、真の不道徳であると断じる。本書は、気候変動を「科学的コンセンサス」として受け入れる前に、その背後にある科学の不確実性、政策の非効率性、そして政治の力学を冷静に考察する必要性を強く訴える一冊である。
各章の要約
第1章 問題の提示
本書は、気候変動をめぐる議論が、確固たる科学的事実というよりも、不安、政治的野心、経済的利益が複雑に絡み合った「問題」として構築されてきたという認識から出発する。ハートは、公衆衛生や環境リスクをめぐる過去の警告(例:脂質恐怖症と心血管疾患)が、後に誇張や誤りであったことが判明した事例を挙げ、科学的主張がしばしば不確実性を伴い、政治やメディアによって増幅される危険性を示唆する。本章では、国連が主導する気候変動対策が、科学的根拠よりも特定の政治的・イデオロギー的アジェンダ(「地球的意識」の構築)に沿って進められているという本書全体のテーマを提示する。
第2章 科学と公共政策
公共政策の形成において科学は重要な役割を果たすが、その関係は複雑である。ハートは、理想的な科学的方法(仮説、検証、反証)と、現代の科学研究が抱える現実(再現性の危機、研究費獲得のための圧力)との乖離を指摘する。特に、不確実性が大きく価値観が対立する問題においては、従来の科学とは異なる「ポストノーマルサイエンス」と呼ばれる手法が用いられる。これは科学者が不確実性を隠蔽し、政治的結論を先取りする危険性を内包している。科学が政策の「隠れ蓑」として使われる危険性を、本書はここで警告する。
第3章 科学とその病弊
この章では、科学コミュニティ内部の病理がより詳細に分析される。ピアレビューは新規性や既存パラダイムに挑戦する研究を排除する「護符」と化し、研究資金は既存の権威に集中する。さらに深刻なのは、科学者が自身の信じる「大義(noble cause)」のためにデータを歪めたり、都合の悪い事実を無視する「高貴な目的のための汚職」である。ハートは、特に環境疫学分野で見られる「ジャンクサイエンス」の横行を批判し、こうした科学の病理が、不確かなリスクを確定的な危機として喧伝する土壌を作り出したと論じる。
第4章 人為的気候変動の科学
気候変動科学の基礎を解説しつつ、その不確実性を浮き彫りにする章。温室効果の基本メカニズムを認めつつも、地球全体の「平均気温」を定義し測定することの難しさ(特に都市化によるヒートアイランド現象)、気候システムを構成する複雑なフィードバック(雲、水蒸気、海洋循環など)の理解不足を指摘する。現在の気候モデルはこれらの複雑さを完全には再現できず、その予測には大きな幅がある。また、過去の気温データの「改ざん(gerrymandering)」や影響の誇張が行われていると批判する。
第5章 IPCCの科学と政治
IPCCの設立から現在までの歴史を追い、その役割が「科学の評価」から「政策の推進」へと変質した過程を描く。特に、第3次評価報告書で用いられた「ホッケースティック曲線」は、中世の温暖期を抹消し、20世紀の温暖化を異常に見せるグラフィカルな操作であったと批判する。IPCCの報告書は、政策要約(SPM)の作成過程で政治的な文言修正が行われ、科学的主張が増幅される。ハートは、IPCCが科学的不確実性を「後ろ暗い不確実性」として扱い、政策立案者により強い「警報」を届けるようになったと結論づける。
第6章 二次的証拠と影響
北極海の氷融解、海面上昇、極端な気象現象の増加、サンゴ礁の白化など、温暖化の影響とされる「二次的証拠」を検証する。ハートは、これらの現象の多くがデータの選択的な読み方や期間の設定によって誇張されていると主張する。例えば、ホッキョクグマの個体数は減少しておらず、南極の氷床面積は増加傾向にある地域もある。ハリケーンの発生頻度に明確な増加傾向は見られず、熱波の増加も地域的・一時的な現象に過ぎない。これらの「影響」は、不確かな科学に基づき、恐怖を煽るために利用されていると論じる。
第7章 科学は確定していない
「気候科学における97%のコンセンサス」という言説は虚構であると断じる章。ハートは、実際には多くの気象学者、物理学者、地質学者、統計学者が主流派の主張、特に気候モデルの感度や人為的影響の大きさに対して異議を唱えていると指摘する。彼らは、太陽活動の変動や自然の気候変動サイクルの重要性を指摘し、現在の温暖化も自然現象の範囲内で説明可能であると論じる。「コンセンサス」は科学的真実を決める方法ではなく、政治的・社会的に反対意見を封殺するために使われるレトリックに過ぎないと主張する。
第8章 緩和戦略の限界
CO2排出削減(緩和策)の具体的な方法を検証し、その非現実性を明らかにする。現代文明の繁栄は化石燃料の豊富で安価なエネルギーに支えられており、それを代替できるだけの「グリーン」エネルギーは存在しない。風力や太陽光は不安定でエネルギー密度が低く、バックアップ電源が必要。バイオ燃料は食料生産と競合する。原子力には安全性とコストの問題がある。炭素税や排出権取引も、経済を縮小させずに排出を大幅に削減することは不可能である。真の選択肢は、経済成長を犠牲にするか、気候変動に「適応」するかであると論じる。
第9章 気候変動政策の経済学
気候変動政策の経済分析を行う。まず、温暖化そのものには、寒さによる死者の減少や農作物の生育期間延長といったプラスの効果もあることを指摘する。その上で、主流派が依拠する「予防原則」は、極端なリスクばかりを強調し、対策コストの大きさを無視していると批判する。英国のスターン報告やオーストラリアのガーノー報告などの代表的経済分析を俎上に載せ、それらが割引率の操作や最悪シナリオの偏重によって、対策の費用対効果を過大評価していると論じる。効率的な資源配分の観点からは、緩和よりも適応の方が遙かに優れた選択肢であると結論づける。
第10章 バプテスト、密輸業者、そして機会主義者
気候変動政策を推進する政治的・社会的連合を分析する。「バプテスト」(理念的な環境活動家や科学者)は、地球を救うという道徳的使命から規制強化を求める。一方「密輸業者」(グリーンエネルギー産業、特定の金融業者、規制を自らのビジネスに利用できる企業)は、その規制から経済的利益を得る。この二つのグループの「不聖なる同盟」が、強力な政治ロビー活動を展開している。さらに、メディアは危機を煽ることで視聴者を獲得し、政治家は有権者の不安に訴えることで支持を集める。こうした利害の一致が、非効率な政策を推進する原動力となっている。
第11章 地球的意識の構築
気候変動問題が、いかにして「地球規模の意識」を構築するための手段として利用されてきたかを論じる。国連は、科学者の「危機」認識を捉え、これを自らの政治的アジェンダ(富の再分配、国家主権の制限、地球的ガバナンスの強化)を推進するための格好の「危機」として利用した。教育、メディア、国際的な会議を通じて、気候変動は単なる環境問題を超え、人類共通の道徳的課題として「フレーミング」されていく。このプロセスは、特定の価値観や世界観を地球規模で普及させようとする試みであるとハートは見る。
第12章 国益 vs. 地球的規範
主要国(米国、英国、欧州、ロシア、日本、カナダ、オーストラリア、途上国)の気候変動政策への対応を、国益の観点から比較分析する。どの国も、美辞麗句の裏では、自国の経済的利益とエネルギー安全保障を最優先している。京都議定書の交渉過程は、この現実を如実に示している。欧州連合は国際的なリーダーシップを求めて議定書を推進したが、米国は経済的負担を理由に批准を拒否。途上国(中国、インド)は経済成長を優先し、排出削減義務を拒否し続けた。国際的な合意は、地球的規範よりも国益の壁によって阻まれてきた。
第13章 修辞学 vs. 現実
国際的な気候変動外交の現実を、京都議定書からコペンハーゲン合意を経て、その後の展開まで追う。京都議定書は、その非現実的な枠組みと主要排出国の参加不足により、排出削減に実質的な効果をもたらさなかった。コペンハーゲンでの華々しい期待は、主要国首脳による「政治的な取引」によって裏切られ、法的拘束力のある合意は成立しなかった。この間、世界のCO2排出量は増加し続け、特に中国の排出量は急増した。同時に、一般市民の気候変動問題への関心は、科学的な論争や政策の失敗が明らかになるにつれて低下していった。
第14章 美徳を装う不道徳
結論として、ハートは気候変動をめぐる一連の動きを「美徳を装う不道徳」と総括する。不確かな科学に基づき、非効率で高コストな政策を推進することは、特に貧困層や発展途上国の人々から、より安価なエネルギーへのアクセスを奪い、経済発展の機会を損なうという点で、真に道徳的な態度ではない。気候変動対策を声高に叫ぶ知識人や活動家たちの「傲慢(Hubris)」こそが、現実の人間の福利を損なっていると断じる。本書は、懐疑主義の重要性を再確認し、科学的・経済的な理性に基づいた冷静な議論への回帰を訴えて結ばれる。
パスワード記載ページ(note.com)はこちら
注:noteのメンバーのみ閲覧できます。