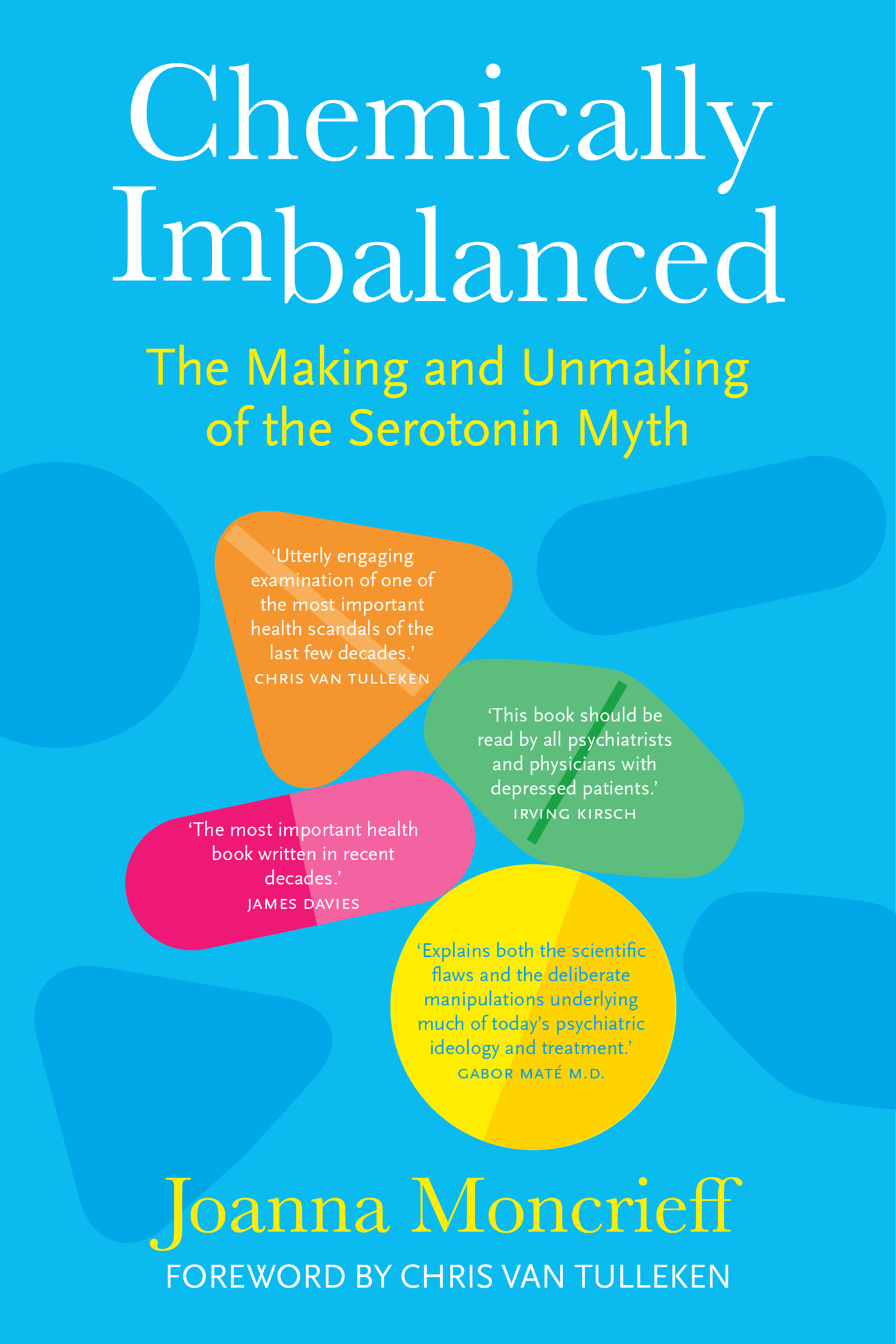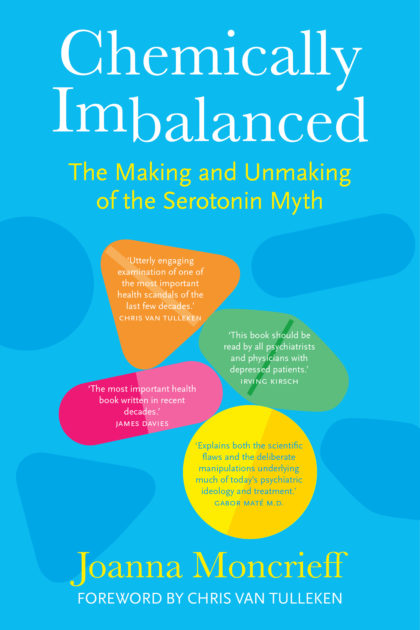
『The Chemical Imbalance Myth:How Antidepressant Advertising has Changed our Lives and What to Do about It』Chemical Imbalance:Antidepressants and the Medicalisation of Modern Life
ジョアナ・モンクリーフ 2025年
目次
- 第一部 問題提起 / The Issues
- 第1章 化学物質不均衡理論が私たちの人生を変えた / How the Chemical Imbalance Theory Changed Our Lives
- 第2章 抗うつ剤を正当化するもの:化学物質不均衡理論の目的 / Justifying Antidepressants:The Purpose of the Chemical Imbalance Theory
- 第3章 では、うつ病とは何か? / So, What is Depression?
- 第4章 抗うつ剤とは何か? / What are Antidepressants?
- 第二部 歴史 / The History
- 第5章 化学物質不均衡理論の起源と抗うつ剤の初期の歴史 / The Origins of the Chemical Imbalance Theory and the Early History of Antidepressants
- 第6章 セロトニンの登場 / Serotonin Arrives on the Scene
- 第7章 「うつ病の時代」 / The ‘Age of Depression’
- 第三部 科学 / The Science
- 第8章 うつ病のセロトニン説のエビデンスのレビュー / Reviewing the Evidence on the Serotonin Theory of Depression
- 第9章 抗うつ剤研究が本当に示すこと / What Antidepressant Research Really Shows
- 第10章 藁から金を紡ぐ:いかにして私たちは抗うつ剤が効果的だと信じるようになったか / Spinning Straw into Gold:How We Came to Believe that Antidepressants are Effective
- 第11章 抗うつ剤がいかに感情と性に影響するか / How Antidepressants Affect Feelings and Sex
- 第12章 抗うつ剤の依存と離脱症状 / Dependence and Withdrawal Effects of Antidepressants
- 第四部 反応 / Reactions
- 第13章 ゴールポストを動かすこと / Moving the Goalposts
- 第14章 防波堤を固める:公衆の反応 / Battening Down the Hatches:Public Reactions
- 第15章 専門家集団の反撃 / The Profession Strikes Back
- 第五部 未来 / The Future
- 第16章 代替アプローチ:良いもの、悪いもの、そして懸念すべきもの / Alternative Approaches:The Good, the Bad and the Worrying
- 第17章 インフォームド・コンセント / Informed Consent
- エピローグ:/ Epilogue
本書の概要
短い解説:
本書は、広く信じられてきた「うつ病は脳内化学物質(特にセロトニン)の不均衡によって引き起こされる」という理論(化学物質不均衡理論)が科学的証拠によって支持されていないことを明らかにする。この神話がいかに製薬産業と精神医学界によって作り上げられ、維持されてきたかを歴史的・科学的に検証し、抗うつ剤の真の作用、その限定的な効果、そして深刻な副作用について警鐘を鳴らす。一般読者や薬物治療を受ける(または検討している)人々が、情報に基づいた判断をするための知識を提供することを目的としている。
著者について:
著者ジョアナ・モンクリーフは、英国の上級精神科医であり、研究者・学者としても活動する。英国国民医療サービスで20年以上の臨床経験を持ち、精神医学の批判的立場を取る「批判的精神医学ネットワーク」の設立者でもある。抗うつ剤を含む精神科薬物の作用を「疾患中心モデル」ではなく「薬物中心モデル」で理解することを提唱し、科学的証拠と哲学的な洞察に基づいて、精神科治療の在り方を問い直す著作を多数発表している。
テーマ解説
- 主要テーマ:うつ病の医学化と抗うつ剤の神話 [化学物質不均衡理論という未証明の仮説が、いかにして商業的・専門家的利益のために事実として普及し、現代社会に深く根付いたかを検証する。]
- 新規性:薬物中心モデルによる抗うつ剤理解 [抗うつ剤は「疾患を修正する」のではなく、「脳の正常な状態を変化させる(感情の麻痺など)」という、より直観的で科学的にも支持される理解の枠組みを提示する。]
- 興味深い知見:拡大されたプラセボ効果 [抗うつ剤の臨床試験で見られるわずかな効果の多くは、副作用などから被験者が偽薬か実薬かを推測できる「二重盲検法の破綻」による「拡大されたプラセボ効果」で説明可能である。]
キーワード解説
- 化学物質不均衡理論:うつ病が脳内の特定の神経伝達物質(特にセロトニン)の不足や不均衡によって引き起こされるという仮説。科学的には一貫した証拠がない。
- 疾患中心モデル:精神科薬物が、精神疾患を引き起こすと想定される根本的な生物学的異常(例:化学物質不均衡)を標的として修正することで効果を発揮するという見方。
- 薬物中心モデル:精神科薬物が、脳の正常な化学状態を変化させることで特徴的な精神状態(感情の麻痺、鎮静など)を生み出し、それが元の苦痛に重なることで「効果」として現れるという見方。
- 拡大されたプラセボ効果:臨床試験において、被験者や研究者が副作用などから実薬か偽薬かを推測できる場合、その期待や信念が結果に大きく影響し、薬理学的効果以上の改善が観察される現象。
- 抗うつ剤離脱症候群:抗うつ剤を中止または減量した際に生じる一連の身体的・精神的症状。軽度から重度まで幅広く、長期的に持続する場合もある。
- 抗うつ剤後持続性性機能障害 (PSSD):抗うつ剤(特にSSRI)の服用後、薬の中止後も持続する性欲減退、性感麻痺、オーガズム障害などの性機能障害。
3分要約
本書は、うつ病が「脳内の化学物質(セロトニン)の不均衡」によって引き起こされるという、過去数十年間にわたって広く普及し信じられてきた理論が、実は確固たる科学的証拠によって支持されていないことを明らかにする。著者らが2022年に発表したシステマティック・レビューは、セロトニンとうつ病の因果関係を示す決定的な証拠が存在しないことを示した。この発見は、抗うつ剤の使用を正当化する中核的な物語を揺るがすものであった。
なぜこの神話はこれほどまでに広まったのか。その歴史を振り返ると、1950~60年代の精神医学界が、自らを「本格的な医学」として確立したいという欲求から、抗うつ剤という「魔法の弾丸」を過剰に歓迎したことが始まりである。そして1990年代、プロザックなどの新世代抗うつ剤(SSRI)の登場とともに、製薬産業は大規模なマーケティングキャンペーンを展開した。その中核メッセージが「うつ病は化学物質不均衡という病気であり、薬で修正できる」というものだった。製薬会社は直接広告や情報提供を通じて、また精神医学界の専門家組織(英国王立精神医学会など)は「うつ病撲滅キャンペーン」などの啓発活動を通じて、このメッセージを公衆に浸透させていった。
その結果、人々は自らの悲しみや苦悩を、人生に対する意味のある反応として理解する代わりに、脳の機能障害の症状として捉えるよう教育され、抗うつ剤の処方を受けることが当然のこととなっていった。抗うつ剤の処方数は過去30年間で劇的に増加し、今や成人の相当部分が服用するに至っている。
しかし、抗うつ剤は本当に効果的なのだろうか。著者は、無作為化比較試験のメタ分析を詳細に検証する。それによれば、抗うつ剤と偽薬の間の症状スコアの差は統計学的には有意だが、臨床的に意味のある差とは言いがたいほど小さい(ハミルトンうつ病評価尺度で約2点)。さらに、多くの試験では被験者が実薬を推測できてしまうため、この小さな差の多くは「拡大されたプラセボ効果」、つまり薬への期待によって説明できる可能性が高い。長期服用を正当化する「再発予防試験」も、実は離脱症状を「再発」と誤認している可能性が指摘されている。つまり、抗うつ剤の有益性は極めて疑わしいのである。
一方で、抗うつ剤のリスクは過小評価されてきた。一般的な副作用に加え、近年、深刻で長期にわたる離脱症状と、中止後も持続する性機能障害(PSSD)が大きな問題として浮上している。これらの「レガシー効果」は、抗うつ剤が脳の正常な機能を変化させ、時に回復に長い時間を要する、あるいは永続的なダメージを与えうることを示唆している。
にもかかわらず、この神話は強固に維持されている。著者のセロトニン説に関する論文発表後、精神医学界の主流派は、同説が既に否定されたものであると主張したり、セロトニンの関与はより複雑だと言い換えたり、他の生物学的理論(神経新生説、炎症説など)を持ち出したりと、ゴールポストを動かすことで、生物学的モデルと抗うつ剤の正当性を守ろうとした。メディアにもその姿勢が見られ、批判的な報道は限定的であった。
本書は最終的に、うつ病を「人生の課題に対する意味のある感情的反応」として再構築することを提案する。回復とは、個人が自分の人生や価値観を見直し、変化を起こすプロセスである。支援は、薬物投与ではなく、社会的つながり、心理療法、生活環境の改善、そして人間的な理解と共感を通じて行われるべきである。読者には、抗うつ剤を含むあらゆる治療について、商業的・専門家的バイアスから解放された科学的証拠に基づき、十分な情報を得た上で判断する権利と必要性があることが強調される。現在、ケタミンやサイケデリックなど新たな「魔法の弾丸」が登場しているが、同じ過ちを繰り返さないためには、この神話の解体が不可欠なのである。
各章の要約
第一部 問題提起
第1章 化学物質不均衡理論が私たちの人生を変えた
現代社会では、うつ病や不安などの「精神的健康問題」が普遍化し、その治療として薬物療法が主流となっている。特にうつ病においては、セロトニンの不足といった「化学物質不均衡」が原因であるという考えが文化に深く浸透しており、抗うつ剤の使用が当然視されるようになった。著者自身の1980年代の抑うつ体験では、薬への懸念が強かったが、1990年代以降の製薬会社の広告キャンペーンにより、人々の認識は大きく変化した。共著者マーク・ホロウィッツの例は、抗うつ剤が長期にわたる有害な副作用(離脱症状、持続的性機能障害)を引き起こし、人生を大きく損なう可能性を示している。本書の目的は、抗うつ剤に関する誤解を解き、科学的証拠に基づく真実を提示することで、人々が情報に基づいた選択を行えるようにすることである。
第2章 抗うつ剤を正当化するもの:化学物質不均衡理論の目的
抗うつ剤の処方は過去30年以上にわたり劇的に増加している。この広範な使用を正当化する中核的物語が「化学物質不均衡理論」である。製薬会社は広告で、精神医学界は啓発活動で、この理論を事実として公衆に伝えてきた。しかし、この理論は科学的に証明されていない。著者らのセロトニン説に関する論文発表後、精神医学界の主流派はこの事実を軽視・否定しようとし、抗うつ剤が「効く」ことだけが重要だと主張した。抗うつ剤には出血リスク、骨粗鬆症、若年層における自殺リスク増加などの身体的副作用に加え、重度かつ長期にわたる離脱症状や持続的性機能障害(PSSD)といった深刻な問題があるが、これらは過小評価されてきた。本書は、抗うつ剤が脳の正常な状態を変化させる薬物であることを明らかにし、そのリスクを十分に理解した上での使用を促す。
第3章 では、うつ病とは何か?
「うつ病は脳の生物学的疾患である」という主張には二つの形態があるが、いずれも科学的証拠に乏しい。感情や気分は、個人の歴史、性格、価値観を持った人間全体の属性であり、単なる脳の状態ではない。医学的診断名(「大うつ病」など)は、症状にラベルを貼るだけであって、関節リウマチのような根本的な生物学的プロセスを特定するものではない。一方で、うつ病はストレスの多い生活事件や社会的逆境と強く関連しており、それは人生への意味のある反応として理解できる。重度のうつ病(メランコリー)でさえ、通常は人生の過程や状況に対する極端な反応である。うつ病を生物学的状態と考えることは、個人の無力感を助長し、回復への期待や自己変革の努力を弱める可能性がある。
第4章 抗うつ剤とは何か?
抗うつ剤の作用について、従来の「疾患中心モデル」(薬が根本的な生物学的異常を修正する)と、著者が提唱する「薬物中心モデル」を対比する。薬物中心モデルでは、抗うつ剤はアルコールやレクリエーショナルドラッグと同様に、脳の正常な化学状態を変化させることで、特徴的な精神的・身体的変化(感情の麻痺、眠気、性機能障害など)を生み出す。これらの変化は、元の抑うつ感情に重なることで、一時的な緩和をもたらす可能性がある。この見方は、抗うつ剤が多様な化学物質から成り立つことや、多くの異なる物質が抗うつ剤と同程度の効果を示すこととも整合する。薬物中心モデルは、薬の脳への干渉に伴う必然的リスクを強調し、その使用が本当に有益かどうかの慎重な評価を促す。
第二部 歴史
第5章 化学物質不均衡理論の起源と抗うつ剤の初期の歴史
1950年代以前、精神に作用する薬は、その一般的な精神変容作用(薬物中心モデル)に基づいて理解されていた。最初期の「抗うつ剤」とされるイプロニアジドやイミプラミンも当初はそのように記述されていた。しかし、精神医学界が医学としての地位を確立したいという欲求から、これらの薬は次第にうつ病という「疾患」を標的とする特異的な「抗うつ剤」として再定義されていった。ノルアドレナリンを介した化学物質不均衡理論が1960年代にジョゼフ・シルトクラウトによって提唱された。ジュリアス・アクセルロッドによるノルアドレナリンの「再取り込み」発見は、イミプラミンの作用機序と結び付けられたが、この解釈には矛盾があった。理論構築においては、都合の良い証拠が強調され、都合の悪い事実は無視される傾向があった。疾患中心モデルは科学的証拠よりも、専門家集団の願望によって採用されたのである。
第6章 セロトニンが現場に到着する
セロトニンがうつ病と結び付けられるようになったのは、1960年代のアレク・コッペンらの研究がきっかけであった。彼は、うつ病は生化学的異常であり、治療はその異常を正常化することだと主張し、薬物中心モデルを完全に退けた。スウェーデンの薬理学者アービッド・カールソンは、セロトニン系に選択的に作用する薬の開発を提唱し、最初のSSRIであるジメリジン(商品名ゼルミッド)の開発につながった。一方、米国イーライリリー社の研究者らは、フルオキセチン(プロザック)を合成した。この時期までに、うつ病の生物学的原因と抗うつ剤の疾患中心的作用機序というパラダイムは固まっていたが、その科学的基盤は脆弱であった。カールソン自身、後年に自身の単純化した仮説を否定している。
第7章 「うつ病の時代」
1980年代、依存性が問題視されたベンゾジアゼピン系薬剤(バリウムなど)に代わる新たな市場が必要となった。1987年に発売されたプロザックは、「うつ病の時代」の幕開けを告げる大ヒット商品となった。その成功は、セロトニンを「幸福の化学物質」として称えるマーケティングと、「うつ病は一般的で治療可能な医学的疾患である」というメッセージによるものが大きかった。製薬産業は、疾患啓発キャンペーンを通じてこのメッセージを拡散し、英国王立精神医学会などの専門家組織も「うつ病撲滅キャンペーン」でこれに協力した(製薬企業からの資金提供は公表されなかった)。これらのキャンペーンは、うつ病を人生への反応と考える従来の見方を変えさせ、抗うつ剤は非依存性で安全だと人々を説得した。その結果、抗うつ剤の処方数は急増し、うつ病は世界的主要疾患とされるに至った。これは、苦悩を薬で解決する文化的要請と、製薬産業のマーケティングが結びついた現象であった。
第三部 科学
第8章 うつ病のセロトニン説のエビデンスのレビュー
著者らが2022年に発表したシステマティック・レビュー(アンブレラレビュー)は、セロトニンとうつ病の因果関係を支持する一貫した証拠がないことを示した。脳脊髄液中のセロトニン代謝産物の濃度、トリプトファン枯渇実験(脳内セロトニンを一時的に低下させる)、セロトニン受容体やトランスポーターの研究のいずれにおいても、明確な関連性は見られなかった。大規模な遺伝子研究も、セロトニントランスポーター遺伝子の変異と、うつ病やストレス経験との相互作用を否定する結果であった。むしろ一部の研究は、長期の抗うつ剤服用がセロトニンレベルを低下させる可能性すら示唆していた。何十年にもわたる研究にもかかわらず、うつ病の原因としてのセロトニン説は科学的に支持されていない。
第9章 抗うつ剤研究が本当に示すこと
抗うつ剤の無作為化比較試験のメタ分析によれば、抗うつ剤は偽薬よりも統計的に有意だが極めて小さい改善を示すにすぎない(ハミルトンうつ病評価尺度で約2点差)。この差は臨床的に意味のある差とは言えず、さらに、被験者が副作用などから実薬を推測できる「拡大されたプラセボ効果」によって説明できる可能性が高い。実際、被験者の推測を統計的に考慮した分析では薬理学的効果は消失するという研究もある。SSRIとは逆にセロトニン再取り込みを促進するチアネプチンなど、多様な作用機序の物質が抗うつ剤として有効とされることも、疾患中心モデルでは説明が難しい。抗うつ効果のスクリーニングに使われる動物モデルも信頼性が低い。重度のうつ病に対する効果も立証されておらず、自殺を防ぐという証拠もない。長期服用を正当化する「再発予防試験」は、離脱症状を「再発」と誤認している可能性が高い。
第10章 藁から金を紡ぐ:いかにして私たちは抗うつ剤が効果的だと信じるようになったか
抗うつ剤の有効性に関する誤った信念は、いくつかのメカニズムによって維持されてきた。ネガティブな試験結果の非公表(出版バイアス)、データの操作(グラクソ・スミスクラインの「スタディ329」)、データの不適切なカテゴリー化による効果の誇張(オックスフォード大学の2018年メタ分析)などである。大規模実践研究(STAR-D研究)を精査すると、最先端の薬物治療を受けても1年後の回復率は低く、抗うつ剤を服用しない場合よりも長期的な転帰が悪い可能性を示すデータさえある。それでも多くの人が抗うつ剤の有効性を感じるのは、強力なプラセボ効果と、自然経過による回復を薬の効果と誤認するためである。しかし、プラセボ効果に依存する治療は、薬理学的副作用のリスクを伴い、時に回復への自信を損なう可能性がある。
第11章 抗うつ剤がいかに感情と性に影響するか
抗うつ剤、特にSSRIは、感情の鈍麻(ブランティング)と性機能障害を引き起こすことが一般的である。感情鈍麻は、ポジティブ・ネガティブ双方の感情の強度を減衰させ、無感動や無関心をもたらす。これは、うつ病の症状ではなく薬理学的効果である。また、抗うつ剤は性欲減退、性感鈍麻、オーガズム障害などを引き起こす。最も深刻なのは、これらの性機能障害が薬物中止後も持続する「抗うつ剤後持続性性機能障害(PSSD)」であり、欧州医薬品庁はその存在を認めている。一方、若年者では抗うつ剤が躁状態、自殺念慮、攻撃性を引き起こすリスクがある。これらの影響は、抗うつ剤が脳の正常な機能を広範囲に変化させることを示しており、軽視できない。
第12章 抗うつ剤の依存と離脱症状
抗うつ剤は、離脱症状を引き起こすという意味で依存性がある。離脱症状は多くの中止者に起こり、一部では重度かつ数ヶ月から数年にもわたって持続する(長期離脱症状)。オンラインサポートグループには何万人もの苦悩する人々が集まっており、キャリアの喪失や人間関係の崩壊など深刻な影響が報告されている。ベンゾジアゼピンの場合と同様、このような長期症状は、薬物が中枢神経系に「ゆっくりと可逆的あるいは時には構造的な神経損傷」を与えた可能性を示唆する。しかし、精神医学界の主流派は長年この問題を軽視・否定してきた。抗うつ剤のリスクとベネフィットを比較衡量するためには、これらの「レガシー効果」を含む全ての影響を理解することが不可欠である。
第四部 反応
第13章 ゴールポストを動かすこと
著者らのセロトニン説論文発表後、精神医学界の主流派は、そのインパクトを中和しようとするさまざまな議論を展開した。それは「フロイトのやかん」のように矛盾に満ちていた。すなわち、1) 誰もそんな説は信じていない(しかし公的機関は今も関連を主張)、2) セロトニンは関与しているがより複雑だ(具体的証拠は示さない)、3) 新しい研究が証拠を示している(しかしその研究も決定的ではない)、そして最終的に「抗うつ剤は効くから問題ない」と繰り返すのである。また、セロトニン説に代わるものとして、神経新生説、炎症説、グルタミン酸説など、他の生物学的理論が次々と持ち出されたが、いずれも決定的な証拠に欠けている。これは、うつ病の生物学的モデルと抗うつ剤の正当性を守るための「ゴールポスト移動」戦略である。
第14章 防波堤を固める:公衆の反応
論文発表直後は多くのメディアが取り上げ、公衆の関心は高かった。多くの人が、長年誤った情報を与えられてきたことに衝撃と怒りを感じた。しかし、メディアの反応は次第に二極化した。右派メディアは製薬産業批判として好意的に取り上げた一方、リベラル系メディアは懐疑的・批判的となり、著者が極右論者と結びつけられたりするケースもあった。番組や記事では「抗うつ剤は効く」というフレーズが繰り返し強調され、真剣な議論は避けられる傾向にあった。抗うつ剤を服用するメディア関係者も多く、自身のアイデンティティや選択を脅かされることに不安を感じた人もいた。公衆の科学的議論は、商業的・専門家的利害と、多くの人々の個人的な心理的投資によって、複雑に形作られている。
第15章 専門家集団の反撃
精神医学界の指導層は、自らの専門的アイデンティティと地位が抗うつ剤と生物学的モデルに結びついているため、著者らの研究を強く敵対視した。ポーランドでは、同様の内容を紹介したジャーナリストが精神科医団体から訴えられ、社会的に抹殺されかける事件が起きた。英国では、著者らの論文に対して、製薬企業との利害関係が多数記載された36名の生物学的精神科医による組織的な批判キャンペーンが展開され、論文の撤回を求める動きさえあった。彼らの批判は方法論的瑣末事にこだわるもので、結論自体は否定できず、科学的議論というよりは専門家集団の権威と物語を守るための政治的活動であった。精神医学は、薬物という「医学的治療」によりアサイラムのイメージから脱却し、医学としての地位を確立してきた。抗うつ剤の神話の崩壊は、その土台を揺るがすものなのである。
第五部 未来
第16章 代替アプローチ:良いもの、悪いもの、そして懸念すべきもの
セロトニン説に代わる新たな「魔法の弾丸」として、ケタミン(エスケタミン)やサイケデリック(シロシビン)が注目されている。しかし、そのエビデンスもまた、短期試験、プラセボ効果の混入、副作用(解離、依存、膀胱障害など)の軽視など、多くの問題を抱えている。特に商業化が進むにつれ、療法要素が削られ、長期・反復使用へと向かう傾向が懸念される。さらに、鎮咳薬成分を含むアベリティや、ベンゾジアゼピン様作用のあるズラノロンなど、新たな抗うつ剤の開発も続いている。一方で、うつ病を「人生への意味のある反応」と再定義する真の代替アプローチが必要である。回復とは、個人が自分の状況や価値観を見直し、変化を起こす成長のプロセスである。支援は、社会的処方箋、心理療法、運動、コミュニティの再構築(例:リコネクト・クラブ)、そして何よりも人間的な理解と共感を通じて行われるべきである。医学化は社会問題を個人の病理にすり替え、保守的な体制を温存する。
第17章 インフォームド・コンセント
化学物質不均衡の神話は、商業的・専門家的利益のために作り上げられ、維持されてきた。抗うつ剤は、その設計意図(うつ病の原因を修正する)を果たしておらず、臨床的に意味のある効果もなく、感情を鈍麻させ、深刻で長期に及ぶ有害作用のリスクがある。それにもかかわらず、精神医学界とメディアの一部は、この事実から公衆の目をそらそうと組織的に努力した。これは、人々が自己決定を行うための基本的権利である「インフォームド・コンセント」を侵害するものである。現在、新たな物質が次々と市場に出ようとしているが、同じ過ちを繰り返さないためには、この神話を解体し、うつ病とその「治療」に関する真実を人々が知ることが不可欠である。最終的に、苦悩に対する解決策は、私たちの脳の化学物質ではなく、私たち自身の人生と、私たちが共に築く社会の中にある。
エピローグ
化学物質不均衡の神話は、無数の個人の人生を形作り、多くの人に薬物誘発性の障害をもたらし、人生の困難を脳のせいにする文化を作り出した。うつ病は、人生の問題の医学化のテンプレートとなっている。うつ病や不安が「現実」ではなく、助けが必要ではないと言っているわけではない。しかし、医学化は誤った希望を与え、潜在的に有害な薬物の過剰処分をもたらす。うつ病を意味のある人間的反応と理解することは、より実り多く持続可能な解決策へと導く。私たちの感情は、選択を行う能力を持つ複雑な生物としての性質を反映している。私たちは状況を変え、自分自身を変えることができる。それが個人で、家族や専門家の助けを借りて、あるいは社会を変える集団的行動を通じて行われるにせよ、うつ病のような精神的健康問題の解決策は、最終的には私たちの脳の化学物質ではなく、私たち自身の人生と私たちが共に築く社会の中にあるのである。
会員限定記事
新サービスのお知らせ 2025年9月1日よりブログの閲覧方法について
当ブログでは、さまざまなトピックに関する記事を公開しています。2025年より、一部の詳細な考察・分析記事は有料コンテンツとして提供していますが、記事の要約と核心部分はほぼ無料で公開しており、無料でも十分に役立つ情報を得ていただけます。 さらに深く掘り下げて知りたい方や、詳細な分析に興味のある方は、有料コンテンツをご購読いただくことで、より専門的で深い内容をお読みいただけます。パスワード保護有料記事の閲覧方法
パスワード保護された記事は以下の手順でご利用できます:- Noteのサポーター会員もしくはコアサポーター会員に加入します。
- Noteの「続きを読む」パスワード記事にて、「当月のパスワード」を事前にお知らせします。
- 会員限定記事において、投稿月に対応する共通パスワードを入力すると、その月に投稿したすべての会員記事をお読みいただけます。
サポーター会員の募集
- サポーター会員の案内についての案内や料金プランについては、こちらまで。
- 登録手続きについては、Noteの公式サイト(オルタナ図書館)をご確認ください。
会員の方は以下にアクセスしてください。(note.com)
パスワードお知らせページ