Contents
- 目次
- 序文
- 序文
- 1.1 はじめに
- 1.2 進化医学のためのコア・プリンシプル
- 1.3 具体的なコア・プリンシプル
- 1.3.1 すべての形質には近接的説明と進化的説明の両方が必要である。
- 1.3.4 選択は様々な時間枠で可塑性を媒介する機構を形成する
- 1.3.5 自然淘汰は主に遺伝子のレベルで働く
- 1.3.6 個体繁殖成功率を低下させる形質も血縁淘汰で説明できる
- 1.3.7 細胞複製の制御はメタゾアンの生命維持に不可欠
- 1.3.8 ゲノム内コンフリクトは健康に影響を与えうる
- 1.3.9 体細胞選択により、個体の生涯で細胞の遺伝子型は変化する
- 1.3.10 自然淘汰による生活史形質の形成
- 1.3.11 欠損効果を持つ遺伝子は、それを補う効果があれば選択されうる
- 1.3.12 崖っぷちのフィットネスランドスケープがいくつかの遺伝病の存続を説明する可能性
- 1.3.13 倫理への配慮は重要である
- 1.3.14 人種は生物学的カテゴリーではない
- 1.3.15 ヒトのサブグループ間の遺伝的差異が健康に影響する
- 1.3.16 あるものが、あるべきものであると仮定するのは間違いである
- 1.3.17 人間にとって自然淘汰は終わらない
- 1.3.18 関係をたどるための遺伝学的手法と系統を追跡する遺伝学的手法は、進化医学において多くの応用がある
- 1.3.19 進化仮説の組み立てと検証のための方法は、依然として開発中である
- 1.3.20 有機的な複雑性は、機械における複雑性とは種類が異なる
- 1.4 結論
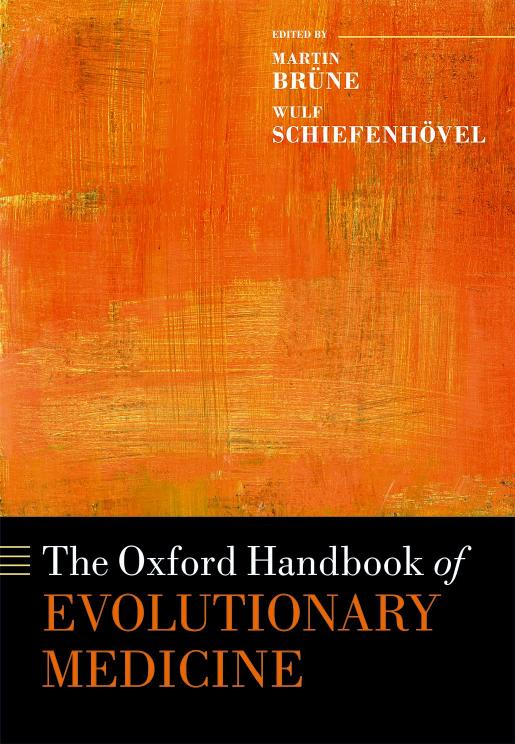
目次
- 表紙
- オックスフォード進化医学ハンドブック
- 著作権について
- 前書き
- 目次
- 寄稿者リスト
- 第I部:一般原則
- 第1章:進化医学のための基本原則
- 1.1 はじめに
- 1.2 進化医学の基本原則
- 1.2.1 コア・プリンシプルとは何か?
- 1.3 具体的なコア・プリンシプル
- 1.3.1 すべての形質には近接的な説明と進化的な説明の両方が必要である。
- 1.3.2 形質に関する完全な説明には、ティンバーゲンの4つの質問に対する回答が必要である
- 1.3.3 病気にかかりやすい体質には、いくつかの進化的説明の可能性がある。
- 1.3.3.1 自然淘汰の限界は、病気の脆弱性を説明するのに役立ちうる
- 1.3.3.1.1 選択は突然変異を最小化するが、排除することはできない
- 1.3.3.1.2 経路依存性は多くの最適でない形質の原因である
- 1.3.3.2 変化する環境と身体のミスマッチは多くの病気の原因である
- 1.3.3.3 宿主の脆弱性は病原体との共進化で説明できる
- 1.3.3.3.1 共進化は病原性のパターンを説明する
- 1.3.3.3.2 抗生物質耐性は自然淘汰の産物である
- 1.3.3.3.3 微生物(マイクロバイオーム)は有用であり、その乱れが病気を引き起こす
- 1.3.3.3.4 共進化は、危険な防御を形成する武器競争を引き起こす
- 1.3.3.4 トレードオフが身体のあらゆる側面を特徴づける
- 1.3.3.5 自然淘汰は健康を犠牲にして対立遺伝子の伝達を最大化する
- 1.3.3.5.1 性的淘汰は健康を犠牲にして繁殖を増加させる
- 1.3.3.5.2 伝達を偏らせる対立遺伝子は、ある種の疾病の原因である可能性がある
- 1.3.3.6 防衛は脅威と被害から身を守るが、相当なコストがかかる
- 1.3.3.6.1 防衛が回避的であるのには十分な理由がある
- 1.3.3.6.2 ネガティブな感情は有用な防御反応である
- 1.3.3.6.3 煙探知機の原理は防衛反応の不必要な表出を説明する
- 1.3.3.1 自然淘汰の限界は、病気の脆弱性を説明するのに役立ちうる
- 1.3.4 選択は様々な時間枠で可塑性を媒介する機構を形成する
- 1.3.4.1 健康と病気の発生起源(DOHaD)は病気に対する脆弱性の重要な原因である
- 1.3.4.2 選択は速い生命史と遅い生命史を形成し、健康への影響を与えた
- 1.3.5 自然淘汰は主に遺伝子のレベルで働く
- 1.3.5.1 集団選択は制約された状況下でのみ有効な説明となる
- 1.3.5.2 多世代間の視点が重要
- 1.3.6 個体繁殖成功率を低下させる形質については血縁淘汰で説明可能である
- 1.3.6.1 自然淘汰は閉経後も作用し続ける
- 1.3.6.2 離乳の競合は避けられない
- 1.3.6.3 母系ゲノムと父系ゲノムの競合は病気の原因になりうる
- 1.3.7 細胞複製の制御は後生動物の生命維持に不可欠である
- 1.3.8 ゲノム内コンフリクトは健康に影響を及ぼす可能性がある
- 1.3.9 個体選択により、一生の間に細胞の遺伝子型は変化する
- 1.3.10 自然淘汰は生活史的形質を形成する
- 1.3.11 消滅的な影響を及ぼす遺伝子は、それを補う利益があれば選択されることがある
- 1.3.12 崖っぷちのフィットネスランドスケープは、いくつかの遺伝性疾患の持続性を説明することができる
- 1.3.13 倫理に注意を払うことは重要である
- 1.3.14 人種は生物学的カテゴリーではない
- 1.3.15 ヒトのサブグループ間の遺伝的差異が健康に影響を与える
- 1.3.16 あるものが、あるべきものであるとするのは間違いである。
- 1.3.17 人間にとって自然淘汰は終わっていない
- 1.3.18 遺伝学的手法による関係や系統の追跡は、進化医学に多くの応用がある
- 1.3.18.1 ヒトの祖先をたどることは医学的意義がある
- 1.3.18.2 病原体の起源と拡散を追跡できる系統発生学的手法
- 1.3.19 進化仮説の構築と検証のための方法は、現在も開発中である。
- 1.3.20 有機体の複雑さは、機械の複雑さとは種類が異なる
- 1.4 おわりに
- 謝辞
- 参考文献
- 第2章 細胞内情報伝達システム
- 2.1 コミュニケーションの進化
- 2.2 多細胞化の進化
- 2.3 ゲノム進化-細胞間情報伝達の前提条件
- 2.3.1 遺伝子の獲得
- 2.3.1.1 遺伝子の複製
- 2.3.1.2 遺伝子の移動
- 2.3.2 遺伝子の消失
- 2.3.1 遺伝子の獲得
- 2.4 細胞間情報伝達のモジュール
- 2.4.1 シグナル分子
- 2.4.1.1 短距離または長距離のコミュニケーション
- 2.4.1.2 細胞表面あるいは内部での標的細胞への刺激
- 2.4.2 受容体およびトランスデューサー
- 2.4.2.1 Gタンパク質共役型受容体によるシグナル伝達
- 2.4.2.2 受容体チロシンキナーゼ
- 2.4.2.3 リガンドゲートイオンチャネル
- 2.4.2.4 核内ホルモン受容体
- 2.4.3 セカンドメッセンジャーとエフェクター
- 2.4.3.1 普遍的なシグナル伝達分子であるカルシウムイオン
- 2.4.3.2 環状ヌクレオチド-シンプルであることの成功
- 2.4.1 シグナル分子
- 2.5 細胞通信にノイズは重要か?
- 2.6 保存されたシグナル伝達系がもたらす医学的帰結
- 参考文献
- 第3章:遺伝学とエピジェネティクス
- 3.1 はじめに
- 3.1.1 遺伝的原因と環境的原因
- 3.1.2 必須因子と増悪因子
- 3.1.3 究極的な原因と近接した原因
- 3.1.4 疾患の原因の三段論法
- 3.1.5 エピジェネティクス
- 3.2 必須原因としての対立遺伝子
- 3.2.1 代償的な利益をもたらす遺伝性疾患
- 3.2.2 補償的利益を伴わない遺伝性疾患
- 3.2.3 統合的アプローチの適用。嚢胞性線維症(Cystic Fibrosis
- 3.3 増悪させる原因としての対立遺伝子
- 3.3.1 イプシロン4遺伝子、アテローム性動脈硬化症、アルツハイマー病
- 3.3.2 動脈硬化の初期病態
- 3.3.3 コレステロールとアテローム性動脈硬化症
- 3.3.4 脂肪酸、炎症、およびイプシロン4受容体
- 3.3.5 感染症、イプシロン4,およびコレステロール
- 3.3.6 アルツハイマー病とε-4,そして感染症
- 3.3.7 ニンニクとイプシロン4の病気
- 3.3.8 喫煙とイプシロン4,そして感染症
- 3.3.9 イプシロン4の進化的な減少
- 3.4 疾患に対する複数の遺伝子の寄与
- 3.5 「複雑な遺伝性疾患」における遺伝的因果関係を評価する。統合失調症
- 3.5.1 複雑な遺伝病としての統合失調症
- 3.5.2家族性関連と感染症
- 3.5.3.生まれた季節
- 3.5.4地理的な関連性
- 3.5.5 病原体候補としてのトキソプラズマ・ゴンディ(Toxoplasma gondii
- 3.6 健康および疾患におけるエピジェネティクス(Epigenetics in Health and Disease
- 3.6.1 DNAのメチル化
- 3.6.1.1 ゲノムインポーチンティング
- 3.6.2 ヒストン修飾
- 3.6.2.1 ヒストンのアセチル化
- 3.6.2.2 ヒストンのメチル化
- 3.6.3 非コードRNA: エピジェネティクスにおける特異性のメカニズム 3.
- 3.6.4 胎児から成体へのヘモグロビンのスイッチ。エピジェネティックモデル
- 3.6.5 エピジェネティクスと環境
- 3.6.6 宿主・病原体間の相互作用とエピジェネティクス
- 3.6.7 エピジェネティクスと脳。3.6.7 エピジェネティクスと脳:アルツハイマー病、神経精神疾患、神経変性疾患
- 3.6.1 DNAのメチル化
- 3.7 統合的アプローチの意味するもの
- 3.7.1 疾患の分類への影響
- 3.7.2 治療法の選択への影響
- 3.7.3 恩恵の代償の意味するところ
- 3.7.4 医療倫理への影響
- 謝辞
- 参考文献
- 第4章 成長と発達
- 4.1 はじめに
- 4.2 発達の進化
- 4.3 比較からみた現代人の成長
- 4.3.1 成長段階(子宮内成長を含む) 4.3.2 受精と出生前段階
- 4.3.2 受精と出生前段階
- 4.3.3 出産、新生児、乳児期
- 4.3.4 幼年期
- 4.3.5 青年期
- 4.3.6 青年期(Adolescence
- 4.3.7 なぜ人間の幼年期と青年期は進化したのか?
- 4.3.8 成人期
- 4.3.9 後期高齢者(Late Life Stage
- 4.4 比較からみた成長の生理的調節機構
- 4.4.1エピジェネティクス
- 4.4.2 ホルモン、栄養、感染症、そして成長
- 4.5 DOHaDと環境変化における人間の成長・発達
- 4.6 成長研究と進化医学の生きた実験場としてのグアテマラとメキシコのマヤ
- 4.7 地域社会への影響
- 4.8 結論と今後の方向性
- 参考文献
- 第5章 老衰と加齢
- 5.1 老化の定義と測定法
- 5.2 加齢の進化的理論
- 5.2.1 加齢の適応理論
- 5.2.2 非適応的加齢論
- 5.3 加齢進化論の仮定と予測
- 5.3.1 年齢に応じた突然変異の影響
- 5.3.2遺伝的変異
- 5.3.3トレードオフ
- 5.3.4外来種の死亡率
- 5.4 加齢の近接メカニズム
- 5.4.1 環境による加齢の調節
- 5.4.2 加齢の遺伝学
- 5.4.3老化のエピジェネティクス
- 5.4.4 加齢の進化論的再検討
- 5.4.5 加齢のメカニズム-保存的か収斂的か?
- 5.5 加齢に関連する病態
- 5.5.1 がん
- 5.5.2 心血管系疾患
- 5.5.3 神経変性疾患
- 5.6 おわりに
- 参考文献
- 第6章 栄養、エネルギー消費、身体活動、および体組成
- 6.1 はじめに
- 6.1.1 Tinbergenの分析レベルの統合
- 6.2 栄養
- 6.2.1旧石器時代の食事。旧石器時代の食事:どのように特徴づけることができるか?
- 6.2.2 脂肪と飽和脂肪酸
- 6.2.3 食餌性コレステロール
- 6.2.4 タンパク質
- 6.2.5炭水化物
- 6.2.6食物繊維
- 6.2.7ナトリウムとナトリウム: ナトリウムとカリウムの比率
- 6.2.8 電解質および酸塩基平衡
- 6.2.9 実験的な臨床研究
- 6.3 エネルギー消費と身体活動
- 6.3.1 ミスマッチと生活史理論
- 6.3.2 エネルギー消費量と身体活動量の測定
- 6.3.3生態学的・経済的背景による身体活動の比較
- 6.3.4 他の霊長類・哺乳類との比較アプローチ
- 6.3.4.1 霊長類における総合的なエネルギー消費量
- 6.3.4.2ヒトの形態的、生理的、代謝的適応
- 6.3.4.3 持久力活動とエネルギー貯蔵に関するヒトの適応
- 6.3.5 ライフヒストリーのトレードオフと生涯を通じた身体活動
- 6.3.5.1胎児期および初期生命期の発達
- 6.3.5.2幼少期と思春期の発達
- 6.3.5.3生殖期の成人期
- 6.3.5.4生殖後期の成人期
- 6.4 身体組成
- 6.4.1 循環インスリンに対する脂肪細胞-筋細胞間の競争
- 6.4.2 高インシュリン血症と真性インスリン抵抗性
- 6.4.3 脂肪組織分布の影響
- 6.5 疑問と課題
- 6.5.1 主張:狩猟採集民は基本的に肉食動物である。
- 主張:飽和脂肪は健康的であり、祖先のものである。
- 主張:高炭水化物、低脂肪食は最も健康的である。
- 主張:塩分制限は必要ではなく、おそらく祖先伝来のものでもない
- 6.5.5主張:動脈硬化は常に一般的であり、人間の条件の一部である。
- 6.5.6主張。最近の肥満の増加には、身体活動よりも食事摂取がはるかに重要である。
- 6.5.7 主張:過去1万年の遺伝的進化はミスマッチモデルを否定する
- 6.6 結論
- 参考文献
- 第II部:特定のシステム
- 第7章 筋骨格系
- 7.1 はじめに
- 7.2 筋骨格系の進化、機能、および機構
- 7.2.1 ヒト科動物の二足歩行に関する化石の記録
- 7.3 筋骨格系の古病理学と古整理学。先端巨大症を例として
- 7.4 進化の制約の表出としての臨床的疾患
- 7.4.1 背中の問題
- 7.4.1.1 ヒト科動物の化石記録における背部障害
- 7.4.2 変形性関節症(Osteoarthritis
- 7.4.2.1 膝関節
- 7.4.2.2 過去の人類における変形性膝関節症
- 7.4.2.3 股関節
- 7.4.2.4 過去の人類における変形性股関節症(Hip Osteoarthritis
- 7.4.2.5 肩関節
- 7.4.3 骨粗しょう症
- 7.4.4 遺伝的素因の一例としての第三大臼歯の圧入または欠落
- 7.4.5 遺伝子と環境の複合障害の例としての二分脊椎
- 7.4.6 環境要因による疾患の例としての手根管症候群
- 7.4.7 扁平足と偏平足
- 7.4.8 おわりに
- 7.5 筋骨格系疾患の予防と治療への影響
- 参考文献
- 第8章:皮膚と器官
- 8.1 皮膚。体内最大の臓器
- 8.2 皮膚。基本構造の紹介
- 8.3 皮膚 継続的な発展
- 8.3.1 皮膚の発生学
- 8.3.2 カセオパチーノ
- 8.3.3 出生後期
- 8.3.4 思春期と性差
- 8.4 皮膚の構造
- 8.4.1 表皮
- 8.4.2 真皮
- 8.4.3 皮下組織(Hypodermis
- 8.4.4 ケラチノサイトの内側と外側
- 8.4.5 構造と経表皮水分損失
- 8.5 皮膚遺伝子の制御
- 8.5.1 表皮分化複合体
- 8.5.2 Ectodysplasinシグナル伝達機構
- 8.5.3.角化
- 8.5.4ケラチン
- 8.5.5 動物皮膚モデル
- 8.6 皮膚の特殊性
- 8.6.1 皮膚腺
- 8.6.2 乳房
- 8.6.3毛髪
- 8.6.4爪
- 8.6.5 指紋
- 8.6.6 感覚受容器と皮膚器官
- 8.6.7 角膜
- 8.7 進化した肌の色の機能
- 8.7.1 紫外線曝露の地理的・季節的な変化
- 8.7.2 紫外線のダメージから肌を守るために
- 8.7.3 紫外線曝露に対する日焼け反応
- 8.8 ホルモン産生における皮膚の機能
- 8.8.1 ビタミンD
- 8.8.2 メラトニン
- 8.9 ヒトの無毛化
- 8.10 社会変化と衣服
- 8.11 環境と遺伝子が皮膚に与える影響
- 8.11.1 現代病、HIV/AIDS、そして皮膚
- 8.11.1.1 単純ヘルペスウイルス
- 8.11.1.2 カポジ肉腫
- 8.11.1.3 伝染性軟属腫(Molluscum Contagiosum
- 8.11.1.4 カンジダ真菌
- 8.11.1.5 光線性皮膚炎および結節性痒疹
- 8.11.2 現在よく知られている皮膚の感染症
- 8.11.3 皮膚癌
- 8.11.4 進化する抗生物質と殺菌剤耐性
- 8.11.5 蚊とマラリア
- 8.11.6 外部寄生虫
- 8.12 皮膚の老化
- 8.13 皮膚の未来
- 8.13.1 皮膚の幹細胞
- 8.13.2 加齢する皮膚
- 8.13.3 21世紀の皮膚の未来予想図
- 参考文献
- 第9章 造血系
- 9.1 造血の進化生物学
- 9.1.1 動物の複雑化・大型化により循環系が必要とされた
- 9.1.2 凝固と組織修復
- 9.1.3 宿主の防御
- 9.1.4 環境圧力と疾病が造血機能を制御するヒト遺伝子に与える影響
- 9.2 造血器官の発生
- 9.2.1 造血幹細胞とは何か(そして造血幹細胞でないもの
- 9.2.2 造血器形成の波形
- 9.2.3 胎児および成体の造血における放浪の旅
- 9.2.4 造血器官の階層性と運命の制御
- 9.2.5 血液産生を生理的な必要性に適応させること
- 9.3 加齢に伴う造血系の変化
- 9.3.1 加齢とは何か?
- 9.3.2 進化と加齢の理論
- 9.3.3 加齢した血液システムの特徴
- 9.3.4 造血幹細胞の加齢のメカニズムと影響
- 9.4 造血器悪性腫瘍
- 9.4.1 なぜがんはほとんどが老齢期の病気なのか?
- 9.4.2 進化した腫瘍抑制戦略
- 9.4.3 ほとんどの造血器悪性腫瘍が晩年に発生することの進化的および近似的な説明
- 9.4.4 小児白血病の進化的説明
- 9.4.5 進化論の腫瘍クリニックへの導入
- 参考文献
- 第10章 免疫系
- 10.1 はじめに
- 10.2 免疫系の進化
- 10.2.1胸腺の検閲の役割
- 10.2.1.1胸腺の進化的発達
- 10.2.1.2胸腺皮質
- 10.2.1.3胸腺髄質
- 10.2.2 現代人とネアンデルタール人・デニソワ人の遺伝子の交換
- 10.3 微生物叢の進化
- 10.3.1 自然免疫と適応免疫による微生物叢の制御
- 10.3.2 食事と微生物叢の進化、そして免疫系
- 10.3.2.1.料理
- 10.3.2.2.発酵食品
- 10.4 免疫系が依存する生物について
- 10.4.1 ‘古い感染症’
- 10.4.1.1 ヘルミンス菌
- 10.4.1.2 ヘリコバクター・ピロリ菌
- 10.4.1.3 ピロリ菌と蠕虫の間の相互作用
- 10.4.1.4 出生時に蠕虫は必要か?
- 10.4.1.5結核
- 10.4.1.6マラリア
- 10.4.2 自然環境からの生物
- 10.4.2.1自然環境と免疫系
- 10.4.2.1.1 自然環境、気道、および喘息
- 10.4.2.1.2 遺伝子水平伝播
- 10.4.2.1.3都市環境
- 10.4.2.1.4芽胞
- 10.4.3 微生物相
- 10.4.3.1出生前の微生物叢と免疫系
- 10.4.3.2 マイクロビオタによる免疫調節のメカニズム
- 10.4.3.3 エンドトキシン(LPS)耐性と免疫調節機構
- 10.4.3.4 現代食と微生物叢、そして免疫系
- 10.4.3.4.1食物繊維とSCFA
- 10.4.3.4.2.ポリフェノール
- 10.4.3.4.3油脂および精製糖
- 10.4.3.5 微生物叢を悪化させるその他の行動上の変化
- 10.4.3.5.1帝王切開
- 10.4.3.5.2母乳育児
- 10.4.3.5.3.抗生物質
- 10.4.3.5.4 抗生物質、肥満、および2型糖尿病
- 10.5 ディスバイオーシスと関連するその他の炎症性疾患
- 10.5.1 癌
- 10.5.2 精神疾患
- 10.5.2.1うつ病
- 10.5.2.2 自閉症と統合失調症
- 10.5.2.3 微生物代謝産物と精神疾患
- 10.6 環境と進化を調和させるこれからの試み
- 10.6.1 古くからの感染症
- 10.6.2マイクロビオタ
- 10.6.3自然環境
- 参考文献
- 第11章 循環器系
- 11.1 はじめに
- 11.2 心血管系の進化的起源
- 11.2.1伝導系の進化
- 11.2.2最初の心臓の出現
- 11.2.3 魚類と二室性の心臓
- 11.2.4 両生類と爬虫類の心臓
- 11.2.5 鳥類の心臓と哺乳類の心臓
- 11.3 心血管系の病態生理
- 11.3.1 動脈硬化
- 11.3.2 心不全
- 11.3.2.1 たこつぼ心筋症(ストレス性心筋症)
- 11.3.3 大動脈弁狭窄症
- 11.3.4 心房細動
- 11.4 予防医学と進化論的アプローチ
- 11.5 おわりに
- 参考文献
- 第12章 呼吸器系
- 12.1 はじめに
- 12.2 酸素の物理化学的性質に関連したガス交換の進化的課題
- 12.3 呼吸器系の進化的な個体群像
- 12.3.1 ヒトの呼吸器系の個体発生について
- 12.4 機能とメカニズム
- 12.4.1 解剖学と組織学
- 12.5 呼吸器系の系統樹(Phylogeny of the Respiratory System
- 12.6 ヒト呼吸器の進化、適応、および進化上の課題
- 12.7 呼吸器系の疾患
- 12.7.1 生活習慣と呼吸器系疾患
- 12.7.1.1 肥満と呼吸器疾患
- 12.7.1.2 新しい環境にさらされることによる呼吸器疾患
- 12.7.2 医療の進歩と呼吸器疾患
- 12.7.2.1 早産と呼吸器疾患
- 12.7.2.2 遺伝性呼吸器疾患
- 12.8 おわりに
- 謝辞
- 参考文献
- 第13章 消化器系
- 13.1 消化器系の機能、生理、および構造
- 13.1.1 消化管のデザイン
- 13.1.2 共通のビルディングブロック
- 13.1.3 疾患脆弱性に関連する消化管設計の特徴
- 13.2 消化管の進化を探る
- 13.3 消化の制御システム、神経系、腸内分泌系とその進化
- 13.3.1 腸管神経系の進化
- 13.3.2 腸管ホルモンシグナルの進化
- 13.4 消化戦略の比較
- 13.5 人類による食物調理の歴史とその進化的影響
- 13.5.1 ヒトの食事における加工食品。旧石器時代から現代まで
- 13.6 ヒトの進化における消化プロセスの食事に関連した分岐の証拠
- 13.6.1 成体ラクターゼの持続性と乳牛の家畜化
- 13.6.2 アミラーゼのコピー数と食餌性デンプンの関係
- 13.6.3 セリアック病(Coeliac Disease
- 13.6.4エタノール代謝。進化と母集団の違い
- 13.6.5 脂肪酸脱飽和酵素遺伝子群の進化
- 13.6.6肝酵素
- 13.6.7 消化管の大きさと脳の大きさ
- 13.6.8膵臓
- 13.6.9 咀嚼筋と歯並び
- 13.7 ヒトの進化速度。13.7 ヒトの進化速度:消化器系の分岐に必要な時間はあったか?
- 13.7.1 短期間での適応
- 13.7.2 腸内細菌群
- 13.7.3 食事が誘発する世代を超えた変化
- 13.7.4 最近の食生活の変化が健康に与える影響
- 13.8 消化器疾患および関連疾患の予防
- 13.9 おわりに
- 謝辞
- 参考文献
- 第14章:排泄系
- 14.1 はじめに
- 14.2 機能と機構
- 14.2.1 二足歩行の霊長類における腎臓のクリアランスの概念
- 14.2.2 ネフロン。ネフロンの数と構造的な組織
- 14.2.3 糸球体における血液の濾過
- 14.2.4 濾過圧と糸球体濾過量の自動調節
- 14.2.5 ナトリウムバランスによる細胞外容積の制御
- 14.2.6 水分バランスは細胞内体積を制御する
- 14.2.7 亜硝酸性廃棄物の腎臓からの排出
- 14.2.8 腎臓のネフロンがpHを一定に保つ仕組み
- 14.2.9 腎臓における骨形成性ミネラルの排出と腎臓結石の形成
- 14.3 排泄系の進化的個体発生
- 14.3.1 哺乳類における腎臓の発生
- 14.3.1.1 前立母体
- 14.3.1.2 中隔系腎臓
- 14.3.1.3 後腎 (確定腎)
- 14.3.2 哺乳類の腎臓の生後の発達
- 14.3.2.1新生児の腎臓
- 14.3.2.2:成長期の腎臓
- 14.3.2.3 加齢の腎臓
- 14.4 排泄器官の系統図
- 14.4.1 水の中の生命。前骨格から中骨格へ
- 14.4.2 水中から陸上へ。水中から陸上へ:メタネフロスの出現と亜硝酸性廃棄物の排泄という大きな問題
- 14.4.2.1 両生類の腎臓とメタモルフォーゼ
- 14.4.2.2 昆虫。新たな解決策を見出す
- 14.4.2.3 爬虫類。後頭葉の出現
- 14.4.3 鳥類の腎臓。ヘンレ輪の外観
- 14.4.3.1 水の再吸収の問題
- 14.4.4 進化に伴う腎臓と体積・血圧のコントロール
- 14.4.4.1 水生動物における体積の調節
- 14.4.4.2 レニン-アンジオテンシン系
- 14.5 適応と広範な進化的課題
- 14.5.1 未熟児・低出生体重児のミスマッチ
- 14.5.2 肥満と糖尿病によるミスマッチ
- 14.5.3 腎臓の加齢。進化上の必要性を超えて
- 14.5.4 選択圧力の副次的損害としての腎臓病
- 14.5.4.1 APOL1 変異株、トリパノソーマ感染、CKD のトレードオフ関係
- 14.5.4.2 ウロモデュリンと尿路感染症のトレードオフ
- 14.5.4.3 尿酸値と血圧コントロールのトレードオフ関係
- 14.5.4.4 再生とのトレードオフ。ネフロンがたくさんある方がよいか、それとも新しいネフロンを作る方がよいか?
- 14.5.4.4.1 魚類と両生類
- 14.5.4.4.2昆虫
- 14.5.4.4.3爬虫綱
- 14.5.4.4.4 鳥類
- 14.5.4.4.5 哺乳類
- 14.6 疾患の予防と治療への影響
- 14.6.1 十分な量の普通の水を飲むこと。
- 14.6.2 水を飲む量については自分の喉の渇きを信じましょう。
- 14.6.3 カリウムが豊富でナトリウムや果糖の少ない食事に気をつける
- 14.6.4 低出生体重児と早産児の長期的なフォローアップ
- 14.6.5 生涯に渡ってネフロン数を最大化し、保護すること
- 14.6.6 ネフロン数のマーカーを同定する研究の支持
- 14.6.7 文化的進化が人工腎臓を進化させた
- 14.6.8 ネフロン移植は最良の腎臓代替療法である
- 参考文献
- 第15章 内分泌学
- 15.1 はじめに
- 15.2 ヒト生殖の進化的個体発生学
- 15.2.1 進化論的内分泌学
- 15.3 内分泌系の機能と機構
- 15.3.1 生殖内分泌学
- 15.3.2 生殖器官の組織学的側面
- 15.3.3生殖器の成熟-思春期
- 15.3.4女性生殖器の成熟
- 15.3.5.男性生殖器の成熟
- 15.3.6卵巣機能と受胎能力
- 15.3.7 生体計測と女性生殖内分泌学
- 15.3.8妊娠
- 15.3.9授乳
- 15.3.10.胎児死亡
- 15.3.11.精巣機能
- 15.3.12女性生殖器の老衰
- 15.3.13 男性の生殖機能の衰え
- 15.3.14 代謝内分泌学
- 15.3.14.1 副腎ホルモン
- 15.3.14.2 インスリン
- 15.3.14.3 甲状腺ホルモン
- 15.3.14.4 レプチン
- 15.3.14.5 アディポネクチン
- 15.3.14.6 グレリン
- 15.4 生殖器系の系統樹
- 15.4.1 比較内分泌学の機能的意義
- 15.4.2雄の生殖生態
- 15.4.3 ヒト科動物の祖先
- 15.5 適応と広範な進化的課題
- 15.6 疾患の予防と治療への帰結
- 15.6.1 リプロダクティブヘルスの進化的内分泌学
- 15.6.2 乳がん
- 15.6.3 卵巣癌と子宮癌
- 15.6.4 前立腺がん
- 15.6.5 多嚢胞性卵巣症候群
- 15.6.6 エストロゲン補充/サプリメント
- 15.6.7 男性ホルモンの補充/補強
- 15.6.8 生殖努力と加齢
- 15.7 結論
- 参考文献
- 第16章 性、生殖、そして出産
- 16.1 はじめに
- 16.2 セクシュアリティ
- 16.2.1 霊長類のセクシュアリティ
- 16.2.2 ヒトのセクシュアリティ
- 16.2.3 精液の競争
- 16.2.4オーガズム
- 16.2.5 ロマンティックな愛
- 16.2.6 セクシュアリティと現代
- 16.2.7 ホモセクシュアリティ
- 16.3 妊娠と出産
- 16.3.1妊娠
- 16.3.2 陣痛
- 16.3.2.1オキシトシン
- 16.3.2.2 陣痛の段階と位相 16.3.2.3 陣痛の段階と位相
- 16.3.2.3 陣痛時の姿勢
- 16.3.3 分娩 – 出生
- 16.3.4 分娩時の姿勢
- 16.3.5 手術による分娩
- 16.4 産褥期(さんじょくき
- 16.4.1 産後出血
- 16.4.2 へその緒の切断
- 16.4.3 新生児高ビリルビナ血症
- 16.4.4 新生児
- 16.4.5 産後すぐの母子相互作用
- 16.4.6 出産時の母子相互作用
- 16.4.7 産後うつと’ベビーブルース’
- 16.4.8 授乳・母乳育児・乳幼児期初期
- 16.5 おわりに
- 参考文献
- 第17章 脳・脊髄・感覚器系
- 17.1 はじめに
- 17.2 ヒトの中枢神経系におけるマクロ解剖学的特徴
- 17.2.1 脊髄の解剖学的特徴
- 17.2.2 脳の解剖学的下位区分
- 17.2.3 等尺性成長
- 17.2.4 異時性(Heterochrony
- 17.2.5 側位
- 17.2.6.性差
- 17.2.7血液とエネルギー供給
- 17.2.8 排水と老廃物の排出
- 17.3 ヒトの脳の微小解剖学的特徴
- 17.3.1 比較的な細胞構造
- 17.3.2.シナプス伝達
- 17.3.3神経伝達物質
- 17.3.3.1 アセチルコリン
- 17.3.3.2 カテコールアミン
- 17.3.3.3 セロトニン
- 17.3.3.4 グルタミン酸と GABA
- 17.3.3.5 ニューロペプタイド
- 17.3.3.6 エンドカンナビノイド
- 17.3.4 ミクログリアと自然発症の脳内免疫
- 17.3.5 神経細胞の特殊化?
- 17.4 感覚系の進化
- 17.4.1 総論
- 17.4.2インターオセプション
- 17.4.3 外部感覚(Exteroception
- 17.4.3.1視覚
- 17.4.3.2.聴覚
- 17.4.3.3 前庭系
- 17.4.3.4 嗅覚
- 17.4.3.5 味覚系
- 17.5 中枢神経系における遺伝子発現
- 17.6 健康と病気における中枢神経系の役割の統合的な見方
- 17.6.1 社会脳と高価な組織
- 17.6.2 ストレス制御と脳
- 17.6.3 CNSと他の臓器とのクロストーク
- 17.6.4 CNS 疾患の予防
- 謝辞
- 参考文献
- 第III部:将来の方向性
- 第18章 医療の未来
- 18.1 はじめに
- 18.2 歴史的考察
- 18.2.1 歴史的発見の現代的実践的意味合い
- 18.3 予防
- 18.4 診断と治療
- 18.5 世界の医療問題
- 18.6 予測不可能な問題
- 18.7 おわりに
- 謝辞
- 参考文献
- 用語集
- 著者名索引
- 主題索引
オックスフォード・ハンドブック・オブ
序文
チャールズ・ロバート・ダーウィンが、ついにブレイクスルー適応と自然淘汰の理論『種の起源』を発表したとき、彼は明らかに疑問と疑念に悩まされた。それは、「自然淘汰による種の起源、あるいは生命のための闘いにおける有利な人種の保存」というフルタイトルにも表れている。このように、ダーウィンが述べたメカニズム、すなわち現在我々が進化と呼ぶものの明確な部分は、最も適応した個体が生き残り繁殖し、他の個体が淘汰されるという淘汰のプロセスを指している。ダーウィンは、実は「進化」という言葉を嫌っており、また、ハーバート・スペンサーの造語である「適者生存」にも不満であった。メンデルの遺伝学的研究は、まだ知的な休眠状態にあり、実際、数十年間は休眠状態にあったのである。しかし、ダーウィンは、トーマス・マルサスが提唱した人口増加論に大きな影響を受けていた。幾何学的に増加した人口は、算術的にしか増加しない資源の崖を突き崩する。
別の言い方をすれば、進化論が始まった当初から、医学の領域との関連は明らかでしたが、長い間無視され、注目されたとしても、しばしば誤解されていた。その結果、社会ダーウィニズムという危険な盲点が生まれ、さらにひどい社会政策につながった。ダーウィンの卓越した業績に対する残虐な曲解によってもたらされた途方もない、計り知れない苦痛を要約し、ましてや分析することは、現在の範囲と目的を超えているが、それ以外のことは、すべてよく記録されている。
ここで重要なことは、これらのどれもがダーウィンによって承認されたものではない、ということだ。では、現代の医学や健康科学において、進化論は何のために「良い」と言えるのだろうか。進化論は、通常、ゆっくりとした漸進的なプロセスとして解釈されるが、医学は、健康状態を迅速に診断し治療するという、異なるモードとテンポを持っている。しかし、医学が治療の進歩や、少なくとも緩和、より大きな発見的理解のために活用することができる進化的なものがあるかもしれない?はい、ある。
ひとつは、私たちを取り巻く微生物の世界が急速に進化していることだ。大腸菌は20分ごとに分裂することができる。私たちの皮膚や腸には、私たち自身のゲノムを持つ細胞の数に近い数の「エイリアン」が生息している。ほとんどの微生物相は、私たちの生命維持や健康に役立つ常在菌であるが、中にはそうでないものもある。
実際、細菌の繁殖の速さは、それと同じくらい急速な進化を促し、その結果、新たに病原性の形質が生じることもある。このように、ある種の細菌は、私たちの身体と「彼ら」との相互作用、および生理学的・病理学的相互作用のメカニズムについて深い知識がなければ理解できない特殊な条件下で、深刻な医療問題を引き起こす。
第二に、進化は遅いという考え方は、少なくとも種のボープランに関しては、もちろん一抹の真実もある。例えば、何百万年もの間、私たちの祖先や私たち自身の種のすべてのメンバーは、二本足で歩いてきた。言葉によるコミュニケーションは少なくとも50万年前から存在し、我々の先祖は約3万年前に動物を飼い始め、選択によって私たち(あるいは少なくとも我々の一部)は乳児期以降もミルクを消化する手段を与えられてきたのだ。しかし、私たちの身体は、他の点では生きた化石である。
例えば、私たちの脊椎は二足歩行には向いていないし、ましてやデスクワークやテレビを見るような現代的な座り姿勢には向いていない。また、脳もそうである。コンピュータゲームなどのハイテク機器に長時間さらされることがもたらす影響については、医学的な問題として認識され始めたばかりである。同様に、摂取したカロリーの過剰摂取は、代謝に大きな打撃を与える可能性がある。つまり、私たちの生物学的遺産は、現代人の生活様式と、ある程度ミスマッチしているのである。
第三に、人間は進化を続けている。その理由と方法は、最近になってようやく解明され始めた。人間が適応しうる環境の変化には、新旧の病原体への曝露、社会的偶発性、現代医学の影響などがあり、これらは自然淘汰の「緩和」であるとする説もある。
これらのことは、現在よりももっとよく理解される必要がある。したがって、医学教育カリキュラムは、系統的な視点に立脚していない科学でしばしば荒れた生地に、進化科学の酵母を入れる必要がある。実際、仮想のすべての臓器系は、私たちの体と私たちの環境-妊娠、発達、社会、文化、微生物、栄養、その他-の間の進行中の 「軍拡競争」に関与している。
『オックスフォード進化医学ハンドブック』は、医学文献の中で「区切り進化」、すなわち形態と機能における異常で急速な進歩の素晴らしい例である。本書は、進化に関する知識を健康科学の学生や専門家になじみのある形式に包括的に統合するという巨大な課題に取り組んだ最初の教科書として、従来の医学生理学や病態生理学のテキストと同様に、器官系ごとに配列されている。
また、非常に多くの相互参照により、各章が互いにリンクされ、有機体がいかに部分の総和を超えた存在であるかが強調されている。また、本書に不可欠な進化論的背景知識についても、わかりやすく解説されている。さらに、本書は各分野の専門家によってよく編集されており、健康と病気に関する進化論的な洞察をまとめた最先端の一冊となっている。
この成功の多くは、編者のマーティン・ブリューネ教授とヴルフ・シーフェンヘーベル教授が、この巨大な仕事に圧倒的な専門知識をもたらしたことに起因するものである。ブリューネ教授は、1988年にミュンスターのヴェストファーレン・ヴィルヘルムス大学で医学部を卒業後、1995年に神経学、精神医学の研修を受け、さらにオーストラリア国立大学およびシドニー大学の精神センターで客員研究員として研究した。進化神経精神医学への深い関心は、この分野そのものが出現しつつあった頃にも出芽ていたため、これらの時系列は重要である。
現在、ドイツ・ルール大学ボーフム校LWL大学病院精神科教授で、250以上の論文や本の章を執筆しており、その中には、珍しい深い単行本のTextbook of Evolutionary Psychiatry and Psychosomatic Medicineが含まれている。The Origins of Psychopathology』(第2版、オックスフォード大学出版 2016)。一方、シーフェンヘーベル教授は、マックス・プランク鳥類学研究所の人体倫理学グループ長を務めている。ミュンヘン大学とエアランゲン=ニュルンベルク大学で医学を学び、ミュンヘンでは長年、医療心理学と民族医学の教授を務めている。
1965年以来、ニューギニア本土と島嶼で、民族医学、進化医学、社会人類学、人間倫理学、言語学、集団遺伝学のフィールドワークを行い、特に、当時(1974)パプア州の新石器時代の高地パプア族エイポ族で顕著であった。また、ミュンヘン大学人間科学センターの創設メンバーであり、同大学の元医療心理学教授であるなど、数十年にわたる数多くの貢献がある。また、数十年にわたり、インスブルック大学およびフローニンゲン王立大学行動生物学研究所の客員教授として、人間生態学の研究を続けている。
ブリューネ教授とシーフェンヘーベル教授は、このテーマに関する膨大な博識と専門知識だけでなく、権威があり、内容やスタイルが調和している優れた執筆陣を集めている。本書は、医学、人類学、生物学、心理学を学ぶ学生だけでなく、学者や臨床医にも強くお薦めしたい一冊だ。生徒、教師、専門家、患者、あるいは関心のある一般人など、あなたがどのような立場で医学を学んでいるかにかかわらず、The Oxford Textbook of Evolutionary Medicineは、医学がより適応できる新しい「生態系」として、あなたが驚くほど詳細に探求できる素晴らしい本だ。
ダニエル・R・ウィルソン(MD、PhD
米国ウエスタン大学学長
序文
私たちが進化医学の本を編集しようと考えたのは、数年前にさかのぼる。私たち二人は、進化論は医学的状態の理解、診断、治療に大いに貢献するものだと考えていたが、一方で、進化論は医学部のカリキュラムはおろか、教科書でもほとんど扱われていなかったか、ほとんど顧みられていない状態であった。
しかし、ウェンダ・トレバサンの『人間の誕生』(1987)のように、医学の特殊な分野での教科書はいくつかあった。また、私たちの一人(WS)がドイツ語で出版した「出産行動と生殖戦略」(原題:Geburtsverhalten und Reproduktive Strategien, 1988)のように、特殊な医学分野の教科書もいくつかあった。
これらの本と、『なぜ病気になるのか』という独創的な古典的な本があるにもかかわらず、である。The New Science of Darwinian Medicine by Randolph Nesse and George C. Williams (1994) は、一部の学界では好評を博したが、その主要な教訓はベンチとベッドサイドの両方で聞かれることはなかった。
しかし、健康や病気を理解する上で、身体は機械のようなものではなく、進化の過程で生まれた複雑な環境への適応の集合体であること、そして、人間の表現型には現在も淘汰が働いていることを認めることは、非常に重要なことだ。
これらのメッセージの妥当性は、自然が生存と生殖に関わる、時には正反対の生物学的要求の間で妥協とトレードオフをデザインしてきたという事実にある。古代の適応の多くが、現代の環境ではほとんどその生物学的目的を果たしていないという観察とともに、これらの洞察は、「弱点」や「設計ミス」がないように選択されたはずの生物学的適応の長い歴史にもかかわらず、身体の機能がなぜうまくいかないのかという問題に取り組む知的努力を前進させた。
実際、人間の身体は、他の生物と同様、ウイルス、細菌、真菌、蠕虫などの他の生物と共進化した「生態系」であり、ほとんどの場合、宿主と共生者の両方に利益をもたらすが、時には人間の生物に不利益をもたらすこともあるということが分かってきている。
環境の変化は、しばしば文化的進化と結びついて、人間の生活環境に新たな試練をもたらした。その多くは、あまりにも急速に生じたため、生物学的適応が追いつかず、進化医学的に「ミスマッチ」と呼ばれている。
例えば、農業の変遷は、新しい食糧獲得方法を生み出しただけでなく、心身の健康に関わる新しい問題を生み出した。その中には、(祖先の条件として)一般によく知られている乳糖不耐症や、家畜が人間と近接して暮らすようになったことで種の境界を越えた新しい感染性物質などがある。
同じように、進化的に古くから存在するマラリア原虫のような病原菌は、アノフェレスの進化によって、動物ではなく人間の血液を好んで吸う株が出現したため、牧畜業者にとってより問題となった。同じような現象は、東アジアでの鳥インフルエンザや豚インフルエンザの流行、エボラ出血熱の流行など、最近でも起きている。
このように、最近の歴史では、新しい感染症や新しい癌などの病状が現れているが、これらは進化論的な観点を採用することによってのみ十分に理解することができる。このような視点は、医学の授業や臨床の場においても必要であると、私たちは強く信じている。抗生物質耐性を獲得した細菌にどう対処したらよいかを探るのは、単なる学問的な試みではない。これはほとんどすべての集中治療室における臨床的な現実であり、耐性菌によって生じる生命を脅かす状態に対処するための新しいアプローチを見つける必要があるのである。実用的な問題のリストは容易に拡大することができるが、ここはそのための適切な場所ではない。読者は、この巻の各章を参照されたい。
興味深いことに、進化論と医学の結びつきは新しいものではない。ダーウィンは生涯を通じて、クローン病、乳糖不耐症、メラス症候群(ミトコンドリア遺伝子の欠陥による脳筋症、乳酸アシドーシス、脳梗塞)などの、衰弱しがちな臨床症状に悩まされたことが知られている。あるいは、ビーグル号で世界一周をした際に、南米を馬に乗って長距離移動した際にかかったかもしれない、シャーガス病(Trypanosoma cruziによる)である可能性もある。チャールズ・ダーウィンの父ロバート・ダーウィンは、イギリスのシュルーズベリーで定評のある医学者であり、二人の息子に自分も医者になることを望んだ。
しかし、次男チャールズはその職業が血生臭いことに愕然とし、エディンバラ大学で医学者の道を止めた。いとこのエマ・ウェッジウッドとの結婚は、ダーウィンに大きな不安を与えた。近親相姦の縁にあるこの結婚は、子孫に病気をもたらすのではないかと、特に彼自身が植物の近親交配の影響について実験をしていたこともあり、非常に心配した。
嘔吐や鼓腸は病気の兆候の一つであり、生涯の負担となるため、自宅のダウンハウスの書斎の一角はトイレとして仕切られていた)その苦しみを考えると、ダーウィンが発見した進化の原理を、一つの例外を除いて医学分野に拡張しなかったのは興味深いことだ。
その例外とは、1872年に出版された『人間と動物の感情表現』という本で、心理学や精神医学に重要な貢献をしたことだ。この本で彼は、哺乳類と人間が共通の子孫によってつながっており、それによって非言語による感情の知覚やコミュニケーションにさまざまな類似性があることを説得的に示したのである。この本で彼は、ダーウィンが書いているように、非患者よりも極端でコントロールの効かない方法で表情を見せる精神科患者の写真を使った。
ダーウィンの思想が、自然淘汰の考え方を大規模な社会問題に適用できると考えた研究者や政策立案者によって取り上げられたことは、私たちもよく知っている。「社会ダーウィニズム」は、強制不妊手術を含むマイノリティに対する最も恐ろしい医療過誤への道を開き、より広いスケールではホロコーストの基礎となったのである。ダーウィンは、人間として、科学者として、社会ダーウィニズムとは正反対のことを主張した。
ダーウィンのブレイクスルー業績以降、ワトソンとクリックによるDNAの二重らせん構造、ハミルトンの血縁淘汰の法則、スターンズの生命誌理論など、多くの新しい科学的発見があり、進化生物学の分野では大きな進展があった。さらに、ノーベル生理学・医学賞を受賞したニコラス・ティンバーゲンは、あらゆる解剖学的特徴や生物学的プロセスを十分に理解するためには、どのような問題(すなわち原因、個体発生、進化、生存価値)に取り組む必要があるかを正確に説明している。
これらの概念は、現在、進化医学に関するいくつかの優れた教科書に反映されている。その一例として、Diseases and Human Evolution by Ethne Barnes (2005), Evolution in Health and Disease edited by Stephen C. Stearns and Jacob C. Koel a, Evolutionary Medicine and Health edited by Wenda Trevathan, E.O. Smith, and James J. McKenna (2008), Evolutionary Medicine and Health (2008), Evolutionary Medicine and Health edited by Wenda Trevathan, E.O. Smith, and James J. McKenna (2008), Peter Gluckman, Al an Beedle, and Mark Hanson (2009), Robert Perlman (2013), Alexandra Alvergne, Crispin Jenkinson, and Charlotte Faurie (2016), Evolutionary Medicine (Stephen C. Stearns and Ruslan Medzhitov (2016), これらはすべて医学、生物、心理、人類、関連科学の学生向けに非常に有用かつ学術的に書かれているものである。では、なぜ別のものを編集するのか?
本書で採られているアプローチは、既存の教科書の構成方法とは異なる点がある。医学生や臨床医、そして他の生命科学の学生や研究者にとって、医学生理学や病態生理学の教科書の系統的な論理に従って進化医学を扱えば、特に役に立つと考える。つまり、教科書を有機システムに従って分類すれば、異なる有機システムが互いにどう作用しているかという考えを含め、進化的概念の人間医学全体に対する関連性を容易に把握することができるだろう。このような構成により、進化医学が教室やカリキュラムに浸透していくことが期待される。
このような経緯から、『オックスフォード進化医学ハンドブック』は大きく2つのパートに分かれている。第I部では、進化科学の一般原理と医学的問題の理解との関連性を扱っている。この原則は、ノーベル賞受賞者であるニコラス・ティンバーゲンが、同じ民族学者であるコンラート・ローレンツの60歳の誕生日に際して発表した論文(1963)で初めて提唱されたものである。
第2章は、Diana Le DucとTorsten Schönebergが執筆した、細胞シグナル伝達システムに関するものである。
第3章では、遺伝学とエピジェネティクスの進化的原理について、Paul Ewald と Hol y Swain Ewald が概説し、一般的な疾患との関連で遺伝子と環境の相互作用を例示している。
第4章「成長と発達」では、Robin BernsteinとBarry Boginが、進化的な観点から人間の個体発生と成長パターンを解説している。
第5章「老化」では、身体機能の低下を特徴とするライフステージについて、Xiaqing ZhaoとDaniel Promislowが執筆している。
そして、Ann Caldwel, Stanley Boyd Eaton, Melvin Konnerによる第6章 Nutrition, Energy Expenditure, Physical Activity, and Body CompositionでパートIは完結する。
第二部では、「Specific Systems」と題して、臨床の理論と実践に焦点を当て、古典的な人体生理学と病態生理学の教科書とは対照的に、進化の枠組みにおける疾患病理の概念に特に重点を置いている。
Martin Häusler, Nicole Bender, Lafi Aldakak, Francesco Galassi, Patrick Eppenberger, Maciej Henneberg, and Frank Rühliによる第7章では、筋骨格系が扱われている。
第8章では、Mark Hillが皮膚と器官について、その発生学的な発達と皮膚疾患の理解との関連性を含めて説明している。第9章では、Eric PietrasとJames DeGregoriが、血液システムの進化と、白血病などの病気に対する血液システムの脆弱性について述べている。
第10章では、グラハム・ルックが、免疫系という複雑な問題を取り上げ、発育初期に細菌にさらされることが免疫機能の成熟にどのように影響するか、また、なぜ現代の環境では機能障害が過去に比べはるかに頻繁に発生するのかについて説明している。
第11章では、Kevin Shah, Kalyanam Shivkumar, Mehdi Nojoumi, Barbara Natterson-Horowitzが、循環器系に影響を及ぼす現代社会で最も頻繁に見られる疾患を取り上げている。
第12章では、Olga CarvalhoとJohn Mainaが、呼吸器系の進化と、哺乳類の呼吸器官の特異的適応に関連して肺疾患がどのように発生するかについて述べている。
第13章では、John Furness, Eve Boyle, Josiane Fakhry, Joanna Gajewski, Linda Fothergillが、腸内細菌が他の器官系と相互作用する多様かつ最近研究されたばかりの方法など、人間の消化器官の進化を描いている。
第14章では、パオラ・ロマニャーニとハンス・ヨアヒム・アンダースが、腎臓全体ではなく個々のネフロンに注目した進化的な視点が、排泄系の疾患の理解に新たな道を開くことを教えてくれている。
第15章では、リチャード・ブリビエスカスが、内分泌学、特に性ホルモンに関する男性と女性の身体の違いについて新しい洞察を示し、これが内分泌系疾患の理解にどのように役立つかを教えてくれる。
第16章 性、生殖、出産(Wulf Schiefenhövel and Wenda Trevathan)は、人間の性行動、分娩、母子の相互作用について、これらの生活領域がどのように、そしてなぜ強い進化の力によって形作られ、生物学的原理と文化的伝統に支配されているか、進化的洞察が現代の産科・小児科にどのように貢献できるかを掘り下げて説明している。
第17章では、脳、脊髄、感覚器について、なぜこのような複雑な器官が進化したのか、他の器官系とどのように相互作用するのか、「ストレス」環境からの挑戦にどのように対処するのか、時には神経精神疾患を生じさせるような最適とは言えない方法で対処するのか、マーティン・ブリューネが解説している。
第18章「医学の未来」は、それ自体で成り立っている。ここでは、進化医学が人間の医学的状態の予防、診断、治療にどのように貢献できるかを探る。また、100年後の医学の姿を想像し、推測することも試みている。
このハンドブックの著者として、国際的に高く評価されている学者や臨床医を獲得できたことを誇りに思う。彼らの献身的な努力と献身、そしてサポートがなければ、本書の実現は不可能だっただろう。複数の著者で構成されるハンドブックには多くの利点があるが、同時にいくつかの不利な点もある。
異なる分野の専門家が参加することは、進化医学に関する最新かつ最良の見解を盛り込む努力に関して、非常に貴重である。しかし、科学とは実証的な証拠に基づいて概念や考えを発展させていくものであり、論争や議論が命である。であるから、読者の皆さんには、本書の最初のページから最後のページまで読んでいただくことをお勧めする。そのために、可能な限り各章をリンクさせ、相互参照することに重点を置いている。
このハンドブックで読者が期待してはいけないことの一つは、網羅的な図版や図表の掲載だ。なぜなら、解剖学的断面を巧みに描いた偉大な解剖学者の仕事を真似ることは目的ではないし、現代の画像技術に基づく解剖学の教科書に載っているような解剖学の詳細を掲載することも本書の目的ではないからである。
最後に、本書の刊行にあたり、多大な支援をいただいた方々や機関に感謝いたする。ティッセン財団からは 2016年10月にデルメンホルストのHanse-Wissenschaftskolleg(HWK)高等研究所で開催された進化医学に関する会議を開催するための多額の助成金をいただいた。
これにより、寄稿者の大半は私たちの招待に応じ、学術会議ではなかなか見られない、敬愛と激励と学識の雰囲気の中で、素晴らしい研究成果を発表し、議論することができたのである。2017年10月にHWKでのフェローシップに追加y招待してくださったDorothe Poggel博士とReto Weiler教授には特に感謝し、編集に関連する問題について議論し作業する機会を与えていただきた。
また、The Oxford Handbook of Evolutionary Medicineの出版にあたり、オックスフォード大学出版局のコミッショニング・エディターのマーティン・バウム、コミッショニング・エディター上級補佐のシャーロット・ホロウェイ、プロジェクトマネージャーのクマル・アンバズハガン、コピーエディターのジュリー・マスクの素晴らしい支援に感謝する。
*マーティン・ブリューネ、ヴルフ・シーフェンヘーベル
要旨
20世紀後半、進化と医学に対する新たな関心は、突然変異の必然性に加え、病気に対して脆弱な身体の側面について、いくつかの種類の進化的説明が可能であるとの認識から生まれた。関連する仮説の検討により、進化医学は急速に発展し、人口統計学、系統学、集団遺伝学の手法を統合するまでに至った。病気を理解するための進化的アプローチは、身体を設計された機械とみなすことから、身体の有機的な複雑さを設計された機械とは根本的に異なるものとして完全に生物学的にみなすことへと、生物学における大きな転換期の一部である。
キーワード
進化医学、ダーウィン医学、近縁、自然選択、脆弱性、有機的複雑性、メカニズム、系統樹、集団遺伝学
1.1 はじめに
進化生物学と医学の接点に対する新しい関心が急速に高まっているが、これは20世紀後半に発展した3つの考え方によって拍車がかかったものである。第一は、すべての形質にはメカニズムの説明に加え、進化的な説明が必要であるという認識である。この考えはエルンスト・マイヤー (Mayr 1982)によって推進されたが、現在ではティンバーゲンの4つの質問 (Tinbergen 1963; Bateson and Laland 2013; Nesse 2013; Medicus 2015)として広く認識されているものにおいて、その完全な表現が与えられている。第二の展開は、自然淘汰は主に集団や種に利益をもたらすように形質を形成するのではなく、どのような方法であれ、他の対立遺伝子よりも早く次世代に伝達される対立遺伝子の頻度を高めるという認識である (Williams 1966; Dawkins 1976)。3つ目の展開は、2つ目と関連して、個体の健康や繁殖の成功に害を与える対立遺伝子は、それでも親族に十分な利点を与えれば選択されうるという認識だった (Hamilton 1964; Crespi et al.2014 )。これら3つの考え方が交わることで、病気に対して脆弱な身体の側面には、広く認識されている突然変異の必然性に加えて、進化的な説明があることが示唆された (Williams and Nesse 1991; Nesse and Williams 1994; Stearns 1999)。
最適でない形質に対する説明を求めることは、決して新しいことではない。ウィリアム・ペイリーの1802年の著書「自然神学:あるいは神の存在と属性に関する証拠、自然の外観から集めて」 (Paley 1802)でも、このことが大きな焦点となった。ペイリーは、身体の最適でない「仕組み」を、神が科学者に感銘を与え、占有させるために提示したパズルであると説明した。この本に触発されたチャールズ・ダーウィンは、自然淘汰の発見により、なぜ身体がそのような形をしているのかを科学的に説明した (Darwin 1859; Ayala 2007)。20世紀半ばの「近代合成」によって自然淘汰が遺伝学と統合されると、最適とは言えない形質が突然変異や遺伝的浮動に起因することが常態化するようになった。「自然淘汰はこれ以上うまくいかない」というのが最も一般的な説明で、病気に対する脆弱性について他の可能性があるという話は、しばしば憶測として退けられた。
20世紀後半に起こった新しい展開は、自然淘汰が適応と同様に不適応を説明するのに役立つという認識であった。自然淘汰の限界に加えて、病気に対して脆弱な体質を説明するいくつかの可能性が認識されるようになった。それらは、形質が進化した環境と生物が現在さらされている環境との不一致、他の生物との共進化、トレードオフ、自然選択の限界からだけでなく健康を犠牲にした生殖成功、大きなコストを伴う防御などである (Crespi 2000; Nesse 2005a)。
体の場合と同様に、進化医学の分野にも、その長所と密接に関連する脆弱性がある。一見すると有害な形質が持続するというパラドックスを解決することは、本質的に魅力的である。この魅力は、自然淘汰によって形成されなかったものに対して進化的説明を見出そうとする熱心な試みにつながった。病気そのものに対して進化的説明を提供しようとする誤った試みは、今でもあまりにも一般的である。しかし、この分野全体としては、この問題に比較的うまく対処してきた。しかし、劇的な推測にさらされたことで、近接メカニズムにのみ焦点を当てる一部の科学者、特に進化的仮説を検証する方法に慣れていない科学者は、一般的に懐疑的になってしまった。病気に関する進化的な仮説を立て、検証する最善の方法を見つけるという課題は、乱暴な憶測を助長することなく、こうした疑問への関心を高めるという課題とともに、今も続いている (Nesse 2011a)。
目の盲点など、進化の初期に確立された発達経路のために、身体には最適とはいえない形質があるように、進化医学の分野も、その起源によって最適とはいえない形で制約を受けている。それは、ダーウィンの2つの発見のうちの1つ、すなわち、形質がなぜそのようになるのかを説明するプロセスとしての自然淘汰だけを強調するものである。ダーウィンはまた、すべての生命が共通の系統的起源に由来する単一性を示すことも示した。この2つ目の発見は軽視され、系統発生学的手法、そしてより一般的な集団遺伝学的手法は、いまだ完全に統合されていない。
1.2 進化医学のためのコア・プリンシプル
1.2.1 コア・プリンシプルとは何か
進化医学のコア・プリンシプルを説明するには、進化医学の分野だけでなく、一般的なコア・プリンシプルを定義することから始めなければならない。教育研究者は、永続的で思考を組織化する大きなアイデアに焦点を当てる方法として、分野の中核的原則を策定することを奨励してきた。Niemi and Phelan (2008) は、コア・コンセプトを「中心的な概念や原理、あるいは 「ビッグ・アイデア」を中心に組織化されたもの」と定義している。これらの概念の性質は領域によって異なるが、一般的には、知識の広い領域を整理し、領域内の推論を行うために使用できる抽象的な原理であり、また、幅広い問題を解決するための戦略を決定するものである」と述べている。
進化医学とは、進化生物学の原理を用いて、病気の理解、予防、治療をより良く行う分野であり、病気の研究を用いて基礎的な進化生物学を発展させる分野である。進化医学には、進化生物学の基礎科学と医学および公衆衛生の専門職が交差するすべての仕事が含まれる。進化医学」という言葉は、それが特殊な医療行為であるかのような誤解を与えている。これは、この分野の初期の歴史がもたらした不幸な結果であり、容易に訂正することはできない。
「ダーウィン医学」はより正確な同義語であるが、同じ欠点がある。「ダーウィン」は多くの一般市民にとって否定的な意味を持つので、現在ではあまり使われていない。進化と医学」は、進化医学を定義する分野間の重複を説明するのに便利な言葉だが、これには公衆衛生、看護、心理療法、獣医学が含まれていない。「進化と医療専門職」は正確だが、普及しそうにない。「進化医学」というキーワードは、その限界にもかかわらず、今後も使われる可能性が高い。
いくつかの教科書や多くの総説が、進化医学の原理を説明している (Nesse and Williams 1994; Stearns 1999; Trevathan et al. 2007; Nesse and Stearns 2008; Stearns and Koel a 2008; Gluckman et al. 2009a; Nesse et al. 2010; Stearns 2012; Perlman 2013; Stearns and Medzhitov 2016).これらを一つのリストに統合することは、手強い課題である。この課題を解決するために、最近の研究では、デルファイ法を用いて、37人の進化医学の専門家の提言を、この分野の14の中核的原則に整理した (Grunspan et al.2018)。この研究では、次のような問いを投げかけた。進化医学のコア・プリンシプルは何か?4波にわたる投票と修正の後、14の原則が80%以上の回答者から支持された。また、調査回答者は、さらに14の中核的原則の可能性を提案したが、合意には至らず、そのうちのいくつかは重複、上位、または下位のカテゴリーに分類された。
本章では、デルファイ調査によって策定された原則に大きく依存する。この研究の過程で、進化医学の中核となる原則を整理する作業は、特別な課題をもたらすことが明らかとなった。あるものは他のものと入れ子になっており、あるものは重なり合い、またあるものは他のいくつかのカテゴリーに当てはまる。この章では、核となる原則を拡大し、可能な限り、それらが互いに、進化生物学と、進化医学とどのように関連しているかを示しながら、検討する。また、進化医学に特化した原則ではなく、進化医学に特に有用な進化生物学の原則を検討する。その結果、Box 1.1に示すような基本原則のリストができあがった。そのほとんどは進化生物学からそのまま出てきたものであるが、正常な機能ではなく病態を理解するために用いると、新たな視点が加わるものが多くある。いくつかは、進化医学と特に密接に関連する、より専門的な原則で、病気をよりよく理解するための努力から生まれたものもある。コア・プリンシプルのカテゴリー間の境界はあいまいなので、それぞれを明確に分類しようとする代わりに、この章では、適宜、関連する問題を書き留めておくことにする。
Box 1.1 進化医学に有用な基本原則
** デルファイ調査による最終的なコア・プリンシプルの一つを示す。
* デルファイ調査の回答者が提案した原則のうち、80%の合意に至らなかったものを示す。
- 1. **すべての形質には近接的説明と進化的説明の両方が必要である。
- 2. どのような形質であっても、その完全な説明には、ティンバーゲンの質問の4つ全てに対する回答が必要である。
- 3. 病気に対して脆弱な体質には、いくつかの進化的説明が可能である。
- 3.1. **自然淘汰の限界は、病気に対する脆弱性を説明するのに役立つ。
- 3.3.1. 淘汰は突然変異を最小限にとどめるが、完全に防ぐことはできない
- 3.3.2. 経路依存性は多くの最適でない形質の原因である
- 3.2. 3.2. **身体と環境の変化とのミスマッチが、多くの病気の原因である。
- 3.3. 病原体との共進化は、宿主の脆弱性のいくつかの種類を説明する3.3.1. **共進化は病原性のパターンを説明する
- 3.3.2. 抗生物質耐性は自然淘汰の産物である
- 3.3.3. *マイクロバイオームは有用であり、その乱れが病気を引き起こす
- 3.3.4. **共進化は、危険な防御を形成する軍拡競争を引き起こす
- 3.4. **トレードオフは身体のあらゆる側面を特徴づけており、身体を病気にかかりやすくしている多くの特徴を説明する。
- 3.5. **自然淘汰は健康を犠牲にして対立遺伝子の伝達を最大化する
- 3.5.1. **性淘汰は健康を犠牲にして生殖を増加させる3.5.2. 伝染に偏りのある対立遺伝子は、ある種の疾病の原因となっている可能性がある
- 3.6. **防衛は脅威や損害に直面したとき、かなりのコストで保護することができる
- 3.6.1. 防衛が忌避されるのにはそれなりの理由がある
- 3.6.2. 否定的な感情は有用な防衛反応である
- 3.6.3. 3.6.3. *煙探知機の原理は、防衛反応の不必要な発現を説明する。
- 1.3 具体的な基本原則 7
- 4. **様々な時間枠で可塑性を媒介する機構を形成する4.1. 4.1. *健康と疾病の発生起源 (Developmental Origins of Health and Disease: DOHaD)は、疾病脆弱性の重要な原因である
- 4.2. **選択によって速い生活史と遅い生活史が形成され、健康に影響を及ぼしている5. **自然淘汰は主に遺伝子のレベルで働く
- 5.1. 集団選択が有効な説明となるのは、制約された状況下においてのみである5.2. 多世代の視点が重要である
- 6. *繁殖成功率を低下させるいくつかの形質については、血縁淘汰で説明することができる。
- 6.1. 自然淘汰は閉経後も作用し続ける
- 6.2. 乳離れの衝突は避けられない
- 6.3. 母方ゲノムと父方ゲノムのコンフリクトは病気の原因になりうる
- 7. 細胞複製の制御は後生動物の生命維持に欠かせない
- 8. *8. ゲノム内コンフリクトは健康に影響を及ぼす可能性がある
- 9. *体細胞選択により、一生の間に細胞の遺伝子型が変化する。
- 10. 自然淘汰は生活史形質を形成する
- 11. 害を及ぼす遺伝子は、それを補う利益があれば選択され得る
- 12. 崖っぷちのフィットネスランドスケープは、いくつかの遺伝病の存続を説明することができる。
- 13. *倫理的な配慮が重要
- 14. 人種は生物学的カテゴリーではない
- 15. ヒトのサブグループ間の遺伝子の違いは健康に影響する
- 16. あるものがあるべきものであると考えるのは間違いである。
- 17. 人間にとって自然淘汰は終わっていない
- 18. **関係や系統をたどる遺伝学的手法は、進化医学に多くの応用がある
- 18.1. ヒトの祖先をたどることは医学的に意義がある
- 18.2. 系統発生学的手法により、病原体の起源と拡散を追跡できる19. 進化的仮説の構築と検証のための方法は、現在も開発中である。
- 20. 有機体の複雑さは、機械の複雑さとは種類が異なる
1.3 具体的なコア・プリンシプル
ボックス1.1には、進化、健康、および疾病に関連する20の基本原則と追加の下位原則が示されている。それぞれについて、以下に簡単な説明を加え、その関連性と一般的な誤解についての考察を加える。
1.3.1 すべての形質には近接的説明と進化的説明の両方が必要である。
この原則は次第に認識されつつあるが、未だに広く誤解されている。近位的説明とは、形質とその働きを説明するものである。進化的説明とは、形質がどのようにしてそのようになったかを説明するものである。多くの科学者がこの区別を理解するためには、簡単な会話で十分であることはほとんどない。私の経験では、学生がこの区別を理解するには、数時間かけて多くの事例を議論する必要がある。
この区別は、エルンスト・マイヤーが、いくつかの論文(1961年、1974)と、その大著 『The Growth of Biological Thought』(1982)の中で述べているもので、生物学を、メカニズムを説明する事業とそのメカニズムの進化という2つの事業が交錯するものとして描いてい ます。彼はこれらの説明を「近接」と「究極」と呼んだが、「究極」という言葉が哲学的・宗教的伝統と結びついていることから、ほとんどの著者はこれらを単に「進化的説明」と呼ぶようになった。場合によっては、これらを異なる「説明のレベル」 (Reeve and Sherman 1993)と呼ぶこともあるが、これは、互いに入れ子になっている組織のレベルを指す通常のレベルとの混同を招く恐れがある。この区別の有用性を疑問視する声もあり、多くの進化プロセスには相互因果関係があり、近接メカニズム自体が将来の選択力に影響を与えることを指摘している(性的選択形質とその形質に対する嗜好がその例) (Laland et al.2011)。両方が必要なのである。
健康科学分野の臨床医や科学者の多くは、近接的説明と進化的説明の両方が必要であることを知らないままである。この区別に気づいている人は、両者は相乗的な補完的説明であるにもかかわらず、時として両者を代替案とみなしてしまう。
さらに、進化的仮説の検証方法は、近接メカニズムの仮説の検証方法と大きく異なるため、さらなる困難が待ち受けている (Nesse 2011a)。
つまり、医学において近接的な説明のみに頼るのではなく、進化的な仮説も提起して検証する必要性が日常的に認識されるようになるまでの移行は、まだ進行中なのである。進化医学は、この移行を促進するのに役立っている。
1.3.2 あらゆる形質の完全な説明には、ティンバーゲンの4つの質問すべてに対する回答が必要である。
ティンバーゲンの「4つの質問」に焦点を広げると、いくつかの難問を克服することができる。ニコ・ティンバーゲン(1963)は、友人であり同僚であったコンラート・ローレン ツを称える記事の中で、あらゆる行動を完全に説明するためにすべて取り組むべき 4 つの異なる質問を提案した。これらは、動物行動学の分野の基礎として広く受け入れられるようになり、精神医学を含む進化医学 (Nesse 2013)にも多くのインスピレーションを与えている (Brüne 2014b)。私は数カ月かけてその全容を理解しようと試んだが、最終的に、2つは近接メカニズムに関するもので、2つは進化に関するものであることを把握することができた。
さらに、近接的な質問には、現在のメカニズムの説明と、DNAコードから成体までの個体においてメカニズムがどのように発展するかについての説明という2つの種類がある。また、進化に関する問題には、ある形質の適応的意義の記述と、その形質の系統の記述の2種類がある。メカニズムや適応的意義に関する問題は、ある生物の時間的断面の記述によって答えられる。発生と系統に関する質問には、歴史的な一連の出来事を考察することが必要である。これらの区別により、4つの質問は表11に示すように整理される (Nesse 2013)。
1.3.3 病気にかかりやすい体質には、いくつかの進化的説明が考えられる
突然変異、遺伝的ドリフト、自然淘汰の一般的な限界は、長い間、最適ではないと思われる身体の側面に対する一般的な説明として受け入れられていた。これは、あたかも生物が設計され、完成されたものであるかのように、また、最適な生物を作り出す正常な設計図が存在するかのように、生物を暗黙のうちに創造論的に捉えていたことを反映している。より進化的な見方をすれば、対立遺伝子は遺伝子の伝達を最大化するようなソーマを形成し、変異はゲノムと表現型に内在していることが認識される。
進化医学において新しいことの多くは、遺伝的に「正常な」個体がそれにもかかわらず病気にかかりやすい理由について、他の5種類の説明を考慮することから生まれている (Williams and Nesse 1991; Nesse and Williams 1994; Nesse 2005a; Gluckman et al.2009a; Stearns and Medzhitov 2016)。よく挙げられるのは、環境とのミスマッチ、病原体との共進化、完璧さを制限するトレードオフ、健康を犠牲にした繁殖成功、病気と思われる防御などである。病気に対する脆弱性を説明するために考えられるこのようなリストは有用であることが証明されているが、決して唯一の選択肢ではない。特に「健康と疾病の発達的起源 (DOHaD)」を研究する人々 (Kuzawa et al. )これは有用である。しかし、発生に由来する疾患の中には、主に制約によるもの、主にトレードオフによるもの、そして多くは環境とのミスマッチによるものがあるため、より具体的なカテゴリーにすることで原因要因により近い注意を喚起することができる。
このリストは、より少ないまたはより多くのカテゴリーに分類または拡張することができる。ミスマッチと共進化の両方は、自然淘汰が遅すぎて種を急速に変化する環境に適応させることができないため、病気の脆弱性をもたらす。物理法則による制限、完全に正確なコードを維持することの不可能性、経路依存性、つまり根本的に新しい設計から始めることの不可能性などである。トレードオフは、すべての形質の最適性を制限する。防御反応は病気に対する脆弱性の理由にはならないが、コストがかかり、しばしば問題を引き起こす。特に、痛みや発熱などの反応は、通常の誤情報を多く発生させ、治療の依頼につながるため、病気のように思われることがある。最後に、概念的に最も重要な原則は、選択は、健康、長寿、幸福のために生物を形作るのではなく、遺伝子の最大限の伝達のためにのみ生物を形作るということである。
このような説明は、しばしば二つ以上関連する。例えば、動脈硬化に対する脆弱性は、現代環境とのミスマッチ、動脈の内膜にある炎症細胞の恩恵、病原体との共進化によって説明される (Nesse and Weder 2007)。
ある種の説明を強調して他の説明を犠牲にしたり、2つの異なる種類の説明を代替案として扱ったりする傾向があるため、多くの混乱が生じている。
これらのカテゴリのほとんどは、機械にも身体にも等しく適用される。設計図やDNAコードの誤りを完全に防ぐことはできないし、すべての形質と機械や身体にはトレードオフが避けられない。しかし、いくつかの要素は、身体に特徴的である。特に、機械は技術者がゼロから設計し直すことができるが、自然淘汰はいじくることに限界があり、例えば反回喉頭神経が脳幹から胸郭に下り、食道の後ろから再び上昇するような極端な摺り合わせの設計になってしまう。
もう一つの大きな違いは、機械やその部品が特定の機能を果たすように設計されているのに対し、身体は健康や長寿を犠牲にしてでも遺伝子を最大限に伝えるように形作られ、その部品は重複した機能を持っていることである。そのため、身体は機械とは大きく異なる。また、冗長性についても重要な違いがある。機械には、主システムが機能しなくなったときに作動するバックアップシステムがある。身体にも同様の冗長システムがあるが、複数のシステムが緊密に統合されているため、1つの部品が故障しても機能にはほとんど影響がない場合が多い。
1.3.3.1 病気の脆弱性を説明するのに役立つ自然淘汰の限界
進化医学にとって特に重要なのは、情報コードの保存能力の限界と、経路依存性という2つの主要な制約である。しかし、身体は機械とは異なり、機械の設計図のような決定的な完璧なプランが存在しない。
正常なゲノムは一つではないし、ゲノムは本質的な種類ではない。むしろ、ゲノムは多様な対立遺伝子の集合体であり、将来の世代における代表性を争っている。その他にも、より一般的な制約が、あらゆる身体や機械に適用される。空間と時間には限りがある。エネルギーは保存される。エントロピーは、長い目で見れば、不屈のものである。
1.3.3.1.1 選択は突然変異を最小化するが、消滅させることはできない
突然変異は完全に防いだり修復したりすることはできず、また突然変異を除去するのに時間がかかるため、病気は避けられない。しかし、通常、遺伝子の変異は、ある個体が病気になる理由の説明として提案されるのであって、ある種のすべてのメンバーが、例えば、気管が食物通路と交差しているような形質を持っていて、全員がある病気にかかりやすくなっている理由の説明にはならない。
一般に普及しているモデルでは、それぞれの形質には頑健性と効率的な機能をもたらす最適なものがあり、突然変異によってその分布が常に広がり、安定化選択によって分布が狭められると仮定している。この原則は正しいし、適切であるが、ある種のすべての個体が病気にかかりやすい形質を共有している理由を説明するのには、あまり役に立たない。
自然選択は、ゲノムの完全性を維持するためのコストと物理的制約を考えると、高等生物の突然変異率を可能な限り小さくする。この原則について言及する必要があるのは、自然淘汰は種の進化に役立つように突然変異率を高く維持するという考え方が根強いからだ。この間違いは、淘汰は個人の対立遺伝子を犠牲にして、種に利益をもたらす形質を形成するという誤解から生じている。突然変異率を高める対立遺伝子は、その対立遺伝子を持つ子孫に欠陥が生じる傾向があるため淘汰され、突然変異率が高くなると、その後の世代ごとにコードの劣化が進むことになる。淘汰は、突然変異率を、そのコストがDNA複製・修復機構のコストと等しくなるレベルまで、あるいは、化学的要因や環境放射線による不可避な損傷などの物理的制約によって忠実度が制限されるレベルまで下げるメカニズムを形作る (Sung et al.2016 )。一般原則の例外となりうるのは、ある種の強いストレスに反応して突然変異率が上昇するバクテリアのfacultativeメカニズムに見られる (Rosenberg et al.2012)。このような場合、子孫の数が膨大になるため、一時的に突然変異率を高める対立遺伝子が有利に働く可能性があり、成功するかどうかは、チケットの番号が違えば当選確率が上がるという勝者総取りのくじ引きに依存する。
1.3.3.1.2 経路依存性は多くの最適でない形質の原因である
身体は機械よりも経路依存性の制約を受けやすい。自然淘汰では、大きな変化は致命的であったり、物理的に不可能である可能性が高いため、小さな変化しか起こせない。
しかし、自動車でも、ガソリンタンクの位置を変えるような大きな変更はコストがかかるので、技術者は軽々しく手を出さない。車体の場合は、そのような根本的な再設計はほとんど不可能である。自然淘汰は「いじる」ことで成立する。その結果、気管が食物通路と共有するスペースに開いたり、精管や反回喉頭神経が長い風を通すなど、最適でない形質が生まれる。このような形質は、ウィリアム・ペイリーに、このような最適でない形質を神の設計と調和させようとする、並外れた創造的な議論の飛行を促した(ペイリー1802)。
1.3.3.2 多くの病気は、身体と環境の変化とのミスマッチから生まれる
現在の環境に適応していない身体がもたらす病気への脆弱性は、進化医学の主要なテーマである (Eaton et al.1988、Gluckman and Hanson 2006)。時には、それが進化医学の唯一の焦点であるかのような間違った見方もされてきた。
この原則は、祖先の環境では人々がより健康であったことを意味すると考える人々に、時として誤解を生じさせることがある。彼らは現代病に悩まされることはなかったが、それにもかかわらず、膨大な疾病の負担を強いられていた。しかし、現代社会の慢性疾患の多くは、祖先にはなかった現代社会の側面にさらされることによって生じていることも事実である。現在、園芸家では動脈硬化性疾患がはるかに少ないことを確認する証拠が得られつつある (Kaplan et al.2017)。長寿も飛躍的に伸びたが、これは老化が遅くなったことや、成人期の死亡率が劇的に低下したことが主な理由ではなく、大きな違いは子供の死亡率が低下したことである。昔は乳幼児死亡率が高かったので、平均寿命は30歳だったかもしれないが、30歳まで生き延びた人の多くは、さらに何十年も生きていた (Hill and Hurtado 1996)。
ミスマッチによる疾病の正確な負担は定かではないが、大きいことは確かである。
心血管疾患と乳がんの割合は、採食する祖先の時代と比較して、現在は少なくとも1桁高い (Kaplan et al.2017)。肥満と糖尿病が蔓延している (Flegal et al.2012)。アレルギーは、さらなる研究が急務である理由から、過去50年間に指数関数的に増加している (Armelagos and Barnes 1999; Brüne and Hochberg 2013)。グルテン過敏症に関連する疾患は、私たちがまだ農業と穀物ベースの食事に適応していることを示唆している (Lindeberg 2009; Brüne and Hochberg 2013)。薬物乱用は、純粋な薬物や斬新な投与手段が容易に入手できるようになるまで、珍しいことではなかった (Nesse and Berridge 1997)。摂食障害は、ここ数十年で劇的に増加した (Rosenvinge and Pettersen 2015)。電子機器への偏愛に関連する障害が急増している。避妊をすることで生殖を制限する嗜好は遺伝するが (Mealy and Segal 1993)、変化は緩やかである。十分な時間があれば、淘汰は心身をよりよく適応させることができると思われるが、環境の変化が速すぎる。(詳細については、第6章 栄養、エネルギー消費、身体活動、身体組成を参照)。
自己免疫疾患は、特に劇的な例であり、課題でもある。クローン病、1型糖尿病、多発性硬化症、その他の自己免疫疾患は、過去数十年の間に急速に増加した(Bach 2002)。この急激な変化の原因はまだ不明だが、マイクロバイオームを破壊する抗生物質が疑わしいとされている (Blaser 2014)。(さらなる考察は、第10章「免疫系」を参照)。
ミスマッチは、環境の変化だけでなく、移動によっても生じる。このことは、北部に住む肌の黒い人がくる病にかかりやすいこと (Jablonski 2004)や、赤道に近い場所に住む肌の白い人が皮膚がんにかかりやすいこと (Greaves 2014)などの現象を説明している。選択によって、集団が病原体にさらされる状況に応じて、HLA対立遺伝子やその他の遺伝子の違いが形成される (Karlsson et al.2014)。マラリア寄生虫が血セルに入るために使うタンパク質の損失は、マラリアと一緒に進化してきた一部のヒト亜集団でよく見られ (Miller et al. 1975; Lentsch 2002)、現在より約4万年前の起源以来、0.043という強い選択係数によって、一部の地域でこの損失の固定化に近い状態になった (Karlsson et al. 2014; McManus et al. 2017)。マラリア環境と非マラリア環境間の移動により、このような遺伝子型が適応的または不適応的になる可能性がある。
1.3.3.3 病原体との共進化は、様々な種類の宿主の脆弱性を説明する
宿主と病原体の共進化から生じる特別な力学の認識は、進化医学における初期の大きな進歩の一つであった (May and Anderson 1983; Ewald 1994; Ebert and Hamilton 1996)。最も単純な形では、宿主の一生の間に病原体が何万世代も繰り返される可能性があるため、共進化は脆弱性をもたらすのである。このような観点から見ると、寿命の長い大型の多細胞生物が存在することは驚くべきことである。
免疫細胞の中には、抗原を認識する細胞を、変化の速い病原体の挑戦に適応させるために、免疫細胞間の体細胞選択を行っているものもある。
1.3.3.3.1 共進化は病原性のパターンを説明する
ほんの数十年前までは、「病原体は宿主を殺したくない」という一般論が広く受け入れられていた。自然淘汰が種に利益をもたらすのは、個体に利益をもたらす程度までだという認識が、微生物学を一変させ、自然淘汰が病原性を形成する方法についての進化モデルがますます洗練されてきた (Read 1994; Ewald 1995; Frank 1996; Schmid-Hempel and Frank 2007)。感染様式が大きな影響を及ぼすことは、早くから認識されていた。直接感染しかできない病原体は、宿主の生存を確保し、すぐに死滅しないようにすることで優位に立つことができる。注射針、医師の手、蚊、不純水などによって感染する病原体は、宿主の寿命をあまり気にせず、大量に複製することによって有利になる傾向がある (Frank 1992; Levin and Bull 1994; Read 1994; Ewald 1995; Levin 1996)。
微生物間の協力に関する研究は、基礎的な進化生物学を応用することで、臨床に関連した研究がいかに進むかを示す良い例である (Velicer 2003; West, Griffin and Gardner 2007; Schmid-Hempel 2011; Foster and Bell 2012)。バイオフィルムは、臨床的に困難な問題であると同時に、個々の細胞の繁殖成功に害を及ぼす形質が、近傍の細胞に利益をもたらすことで存続することができるという進化的説明にとって大きな課題を提供し続けている (Queller 1994; Hansen et al.2007; Oliveria et al.2015).基本的な原理は変わらない:対立遺伝子は、その対立遺伝子を持つ者が他の者よりも平均的に多くの生存親族を持つ場合にのみ頻度が増加する (West et al.2007)。この分野では、集団選択モデルと血縁選択モデルがともに有用であることが証明されている (Queller 1994; Redfield 2002; Kreft 2004; Dugatkin et al.2005; Crespi et al.2014).
1.3.3.3.2 抗生物質耐性は自然淘汰の産物である
抗生物質耐性は、進化の医学への最も実用的な応用であるとよく言われている。20世紀半ば、自然淘汰の力に対する認識が欠けていたために、抗生物質が感染症の撲滅につながるという悲劇的なまでに楽観的な予想がなされた (Neu 1992; Salmond and Welch 2008)。病原体は、自分たちを狙うあらゆる分子に対して耐性を進化させることが可能であることが判明した。抗生物質そのものが、他の生物と効果的に競争するために何十億年もかけて形成された細菌や菌類の産物であることを考えれば、これはそれほど驚くべきことではないだろう (D’Costa et al.)なぜなら、ある生物が耐性を獲得するたびに、研究者はその耐性を回避するための新しい薬剤を見つけようとし、生物はすぐに適応してしまうからだ。
こうした洞察にもかかわらず、抗生物質耐性に対する完全に洗練された進化的アプローチはまだ発展途上であり、多くの医学論文では「進化」という言葉は避けられている (Antonovics et al.2007)。感染症に対抗する新しい戦略を見出すには、より洗練された進化モデルに頼る必要がある (Pepper 2008; Vale et al. 2016; Huijben and Paaijmans 2017)。抗生物質を10日間フルコースで続けることが賢明かどうかといった基本的な問題でさえ、依然として論争が続いているが (Read et al. 2011; Day and Read 2016; Bouglé et al. BMJは最近、「The antibiotic course has had its day」と題する記事を掲載した (Llewelyn et al.2017)。それは、抗生物質のフルコースを取ることは多くの場合不要であり、耐性を防ぐことはできないと主張したが、進化、自然選択、または抗生物質耐性を研究する進化生物学者の仕事には言及しなかった。
1.3.3.3.3 マイクロバイオームは有用であり、その乱れが病気を引き起こす
ほんの数年前までは、ほとんどの医師が、細菌は悪いもので、避けるか殺すのが最善だと考えている傾向があった。1980年代、私は、難治性の下痢を訴える多くの患者の相談に乗り、何度も抗生物質を投与され、便に病原体が見当たらないことから、心因性の疾患であると言われた。振り返ってみると、こうした患者の多くは、正常なマイクロバイオームが課す制約から解放され、クロストリジウム・ディフィシルやその他の過剰増殖菌に感染していた。今なら、彼らはマイクロバイオーム移植で効果的に治療できるだろう (Agrawal et al.2016)。その誤差の大きさは理解しがたい。
「旧友」仮説の研究により、私たちは多くの微生物に依存しており、それらを乱すと病気になることが明らかになった (Rook et al.2017)。マイクロバイオームを崩壊させる抗生物質の役割は明らかになりつつある (Blaser 2014)。最近の手法では、グローバルシークエンスを使ってマイクロバイオームを測定することで、私たちのマイクロバイオームで相互作用する無数の微生物が明らかになり、そのうちのいくつかは病気、特に肥満に影響を与えることが分かっている (Turnbaugh et al.2006)。
また、食生活の変化によってわずか数日で引き起こされる変化 (Davidら、2014)や、季節による食生活の変化がハッザ族のマイクロバイオームにどのように影響するか (Smitsら、2017)も明らかにされている。
これとは逆のスキーマとして、私たちは多くのよく協調する生物からなるホロビオントであるという考え方もある (Bordenstein and Theis 2015)。個人をマイクロバイオーム抜きで考えるのは間違いであるとさえ言う人もいるだろう。確かに、微生物との共存は私たちの自然な状態であり、その乱れは多くの病気、おそらく現在流行している自己免疫疾患のほとんどを引き起こしている。しかし、微生物たちは必然的に、自分たちを保存し、広めるのに最適な表現型に進化していく。その結果、多くの協力が生まれるが、同時に多くの競争も起こる。(1.3.3.3.4 共進化は、危険な防御を形成する武器競争を引き起こす。
宿主の新しい防御を形成する淘汰は、防御を回避する方法について病原体に新たな淘汰圧を与え、それが防御を改善する新たな淘汰を引き起こす。その結果、宿主と病原体は共に、「不思議の国のアリス」の赤い女王のように、相手の変化についていくために「全力疾走」する (Ridley 1994; Morran et al.2011)。
これは、性の維持、およびその非常に大きなコストに関する説明であると思われる (Ridley 1994; Auld et al.) 人間の病気に対する影響は相当なものである。
保護された形にはそれなりの危険性がある。したがって、感染症による疾患が減少する一方で、免疫系による疾患がより多くなっていることは驚くべきことではない (Bach 2002)。病原体からの淘汰圧は、防御能力を、確実に得られる限界利益が時折生じる限界費用よりも小さくなるところまで押し上げるので、淘汰はしばしば宿主に害を与える防御を形成することができる。このことは、炎症を抑える薬を使うかどうかの判断に実際的な影響を与える。インフルエンザでは、致命的な結果は、ウイルスの直接的作用、炎症反応、またはその組み合わせのいずれかによってもたらされる。インフルエンザ患者にステロイドを投与した複数の試験で、一貫した結果が得られていない(Salomon et al. 2007)。進化論的な観点から、どの患者が炎症反応の抑制により恩恵を受け、どの患者が害を受けるかを予測することは可能であると考えられる。
1.3.3.4 トレードオフは身体のあらゆる側面を特徴づける
ある形質を改善すると、他の形質や同じ形質の他の適応的側面が損なわれるため、完璧な形質というものは存在しない。例えば、胃酸の濃度が高ければ、感染症に対する防御力が高まるが、その代償として潰瘍のリスクが高まる。より広範な抗原に対する免疫モニタリングは、感染に対する防御力を高めるが、自己免疫反応のリスクを高める(Bergstrom and Antia 2006)。悪性腫瘍の可能性がある細胞のアポトーシスが起こりやすいと、がんから身を守ることができるが、その代償として組織修復能力が低下する(Abegglen et al. 2015)。体重を高く維持することは、食料不足の時期に身を守ることになるが、その代償として運動速度が低下し、体を維持するために多くのカロリーを必要とする。
トレードオフは生活史理論の中心であり、特に早期繁殖と長寿のメリットとコスト、体節維持と競争力のオスとメスの相対的なメリットとコストなどが挙げられる (Stearns 1989; Hill 1993; Brüne 2014a)。防御の制御を理解するには、そのコストと利益、そして反応が少ない、あるいは反応しないという選択肢を理解することが必要である。生命のあらゆる側面でトレードオフが中心的な役割を果たすことは、進化医学の最も重要な原則である。臨床医や研究者は、形質が完全か欠陥かということではなく、自然淘汰がどのようにトレードオフを形成し、結果として病気に対する脆弱性を含むフィットネスを最大化するかを考えるよう奨励されている。
1.3.3.5 自然淘汰は健康を犠牲にしてアルエレ伝搬を最大化する
これは最も深く、最も驚くべき原理であり、進化医学に最も特有なものであるかもしれない。自然淘汰は、繁殖の成功率を高める範囲でのみ、健康と長寿を形成する。健康を害したり寿命を縮めたりする対立遺伝子が選択されるのは、それが包括的なフィットネスを向上させる場合である。その例としては、ここで検討した性選択と、後述する加齢、速い生命史と遅い生命史、ゲノム内競争がある。
1.3.3.5.1 性的選択は健康を犠牲にして繁殖を増加させる
寿命の性差は、交配相手を獲得するための競争力のコストを示している。交尾の競争力がオスに大きな報酬を与える種では、リスクを負うことや組織の損傷を修復する能力が限られているにもかかわらず、競争力に高い投資をするようにオスが選択される(Trivers 1972; Liker and Székely 2005)。メスも一般的には同じトレードオフの関係にあるが、組織修復への投資から相対的に多くの利益を得ている。その結果、先進国におけるヒトの男性の性成熟時の死亡率は、女性の死亡率の約3倍にもなる (Kruger and Nesse 2006)。この過剰な死亡率の一部は、リスクテイクや行動によるものであるが、男性は感染症、癌、代謝性疾患などのリスクも高い (Kruger and Nesse 2004)。
医学的な関連性のある性差は、性選択によって説明できる。例えば、男性に対して女性の不安障害のリスクが2倍増加することは、世界中でかなり一貫している (Ruscio et al.2017)。このことから、多くの人が「なぜ女性には不安が多いのか」と問いかけている。進化的な情報に基づく見解では、代わりに、女性の不安調節機構は個々の女性に利益をもたらすために最適に近い閾値に設定され、一方、男性の不安閾値が高いと、害の割合の増加を犠牲にして競争力を高めるという可能性を考える (Stein and Nesse 2015)。体力に対する対立遺伝子の影響における性差は、血色素症によって示されている:結果として生じる肝臓の損傷は、月経によって定期的に血液が失われるため、女性ではそれほど深刻ではない (Moirand 1997)。
1.3.3.5.2 伝達を偏らせる対立遺伝子は、ある種の疾病の原因である可能性がある。
対立遺伝子は、個体の犠牲の上に自身の複製を進めることができる。このような現象は、1.3.8節でさらに説明するように、「遺伝子の議会」の利益を促進する自然選択によって形成されたメカニズムによって、通常うまく制御されている。
1.3.3.6 防衛は脅威や損害に直面したときに保護を提供するが、かなりのコストがかかる
人々が医療機関に持ち込む問題の多くは、病気の直接的な産物ではなく、自然淘汰によって形成された防御機能であり、それが役立つ状況をモニタリングするメカニズムが備わっている (Nesse and Williams 1994)。防御機能は、感染症に直面したときに特に顕著に現れる (Ewald 1980)。鼻汁、咳、嘔吐、下痢によって病原体を排出することは、強力な防御となる。炎症は、特定の感染症に対する段階的な特異的反応を提供する。すでに述べたように、病原体との共進化は、防御が非常に高いコストとリスクを伴うにもかかわらず、維持されている理由を説明するものである。
淘汰は、他の多くのリスクから防御するシステムを形成してきた(Harvell 1990)。防御の中には固定化されているものもある。例えば、皮膚の色素沈着は、ビタミンD欠乏症やくる病に対する脆弱性を高めるというトレードオフのもと、皮膚障害や皮膚がんから身を守る (Jablonski and Chaplin 2010; Greaves 2014; Jablonski and Chaplin 2017)(第8章参照)。
その他の防御は、必要な時に発現する反応である。熱や組織損傷からの反射的な撤退は有用である。まばたきは目の異物から、くしゃみは鼻腔の異物から、かゆみは皮膚の寄生虫から身を守る。震えは低体温症から、発汗は高体温症から身を守る。これらのシステムは、その反応が必要とされる状況をモニタリングするシステムと関連しているため、通常「facultative response」と呼ばれる。より正確には、利点がコストより大きい場合であり、このようなシステムで誤情報が普通で一般的である理由を説明している。
1.3.3.6.1 防衛が回避的であるのには理由がある
ほとんどの防衛反応の活性化は、主観的な苦痛や他の回避的な体験と関連しており、それ自体が障害であるかのように思われる。その回避性は逃避や回避の動機となる。回避反応が有用であることを認識することは、臨床医学における進化論的アプローチの大きな貢献となる。このことは、そのような反応を阻止するために薬物を使用することが適切な場合とそうでない場合について、臨床上の意思決定の指針となり得る。
1.3.3.6.2 ネガティブな感情は有用な防衛反応である
特定のものに特定の機能を持たせようとする認知的傾向は、感情研究の歴史に表れている。例えば、恐怖は逃避を促し、怒りは攻撃から身を守る機能を果たすと言われている。しかし、より進化的なアプローチでは、感情には複数の機能があり、異なる感情はその機能によってではなく、それらが有用である状況によって区別されることが認識されている (Plutchik 1980; Wierzbicka 1986; Nesse 1990; Nesse and El Sworth 2009)。このアプローチは、基本的な感情がいくつあるかという解決不可能な議論を超越し、感情反応は事前の反応から発展するため、それらは別個ではなく、重複していると予想されることを認識するものである。また、感情状態がほとんどすべて快楽や苦痛の主観的体験と結びついている理由も説明できる。機会や脅威を伴わない状況では、どのような反応も形作られることはない。
不安障害やうつ病がもたらす疾病の負担は非常に大きい (Kessler et al.2009)。
これらの疾患に対するアプローチは、脆弱性の違いを説明する事象やメカニズムにのみ注目したものがほとんどである。しかし、進化医学では、感情の表出がどのように制御されているのか、また、ネガティブな感情が過剰に表出されたり、必要でない場面で表出されたりすることが多いのはなぜか、といった分析を奨励している (Nesse 2011b)。この知識は、そのような感情の起源を探る臨床評価や、その感情を遮断するための薬物をいつ使用しても安全であるかという臨床判断に役立つものである。
1.3.3.6.3 煙探知機の原理は防衛反応の不要な発現を説明する
多くの防衛反応は、必要なときに防衛反応を起こさなかった場合の莫大なコストに比べれば、比較的安価なものである。例えば、嘔吐には数百カロリーしかかからない。しかし、毒素や病原体が腸内にある場合、嘔吐の失敗は致命的となり得る。これは、大学生が酒を1本全部飲んでも吐かなかったり、嘔吐を抑制する薬剤を含むピルを過剰摂取した患者が死亡したりすることで、定期的に見られる悲劇的な現象である。
「煙探知機の原理」は、特に情緒障害に関係する。例えば、パニック発作のコストはわずか100カロリーかもしれないが、捕食者に直面してパニック反応がない場合は、死、約10万カロリーになるかもしれない。この状況に標準的な信号検出分析を適用すると、逃げるのが最適となる前に、どの程度の強さの信号が必要かを計算することができる。コストの比率は1000:1である。つまり、ライオンの存在の可能性が1000分の1より大きいことを示すのに十分な大きさのノイズがあれば、1000回中999回は不要であることが判明しても、逃げることが最適なのである。このようなシステムでは誤情報はつきものであり、予想されることである。
煙探知機からの誤情報は、実際の火災から完全に身を守るために必要かつ正常であると認識されているため、「煙探知機の原理」という呼称が適切である (Nesse 2001, 2005b)。この考え方は新しいものではない。17世紀、ブレーズ・パスカルは、神の存在がありそうもないものであっても、可能性があるのであれば、永遠の天罰が無限に続く苦痛である一方で、コストが低いため、信じることにまだ価値があると主張した (Hacking 1972)。煙探知機の原理は進化心理学者によって「エラー管理理論」として認知領域に適応され、明らかに誤った決定や信念の適応的意義を分析するようになった (Haselton and Buss 2000)。より大きな枠組みは信号検出理論で、グリーンとスエッツ(1966)によって最初に記述され、現在では心理学者が実験を分析するために、またエンジニアが回路や機械を設計するために使用されている。進化医学や公衆衛生におけるその応用範囲は、まだ十分に検討されていない。
1.3.4 選択は様々な時間枠で可塑性を媒介する機構を形成する
防御は、自然選択によって形成された多くの可塑的反応のうちのいくつかに過ぎない (West-Eberhard 2003)。進化的アプローチでは、固定された反応や「遺伝的決定論」が強調されるという誤解がいまだに広まっている。機械と身体の主な違いの一つは、身体には内外の状態をモニタリングし、さまざまな状況に対処するために生理と行動を調整する無数のシステムがあることだからだ。その範囲は、瞬きの瞬時反応、数秒の心血管系反応、数分の代謝調整、数日の皮膚の日焼け、数年の生活史特性、さらには世代を超えた脂肪蓄積レベルやストレス反応の調整など、多岐にわたる。
1.3.4.1 健康および疾病の発達的起源 (DOHaD)は疾病脆弱性の重要な原因である
David Barkerらは、低出生体重児がその後の肥満や動脈硬化などの炎症性疾患に対する脆弱性を予測することを発見した (Barkerら、1993)。彼らはこの考えを「倹約的表現型仮説」 (Hales and Barker 2001)と呼び、James Neel(1962)が提唱した「倹約的遺伝子型」仮説と関連づけた。Peter Gluckmanらは、この考え方を拡張し、倹約的表現型は、母親が胎児に伝える将来の環境に関する手がかりに基づいて生涯の代謝を調整する「予測的適応反応」であるかもしれないという提案をした (Gluckman et al.2005)。この考えは、DOHaD (Developmental Origins of Health and Disease)という活気ある研究分野に発展し、発展途上国の経済的移行により肥満や炎症性疾患の疫病が増え続ける中で特に重要視されている (Hanson 2015)。特定のエピジェネティックなメカニズムがその効果を媒介し (Gluckman et al. 2009b)、いくつかのエピジェネティックマークは世代を超えて伝達され、肥満の非ゲノム家族性伝達を説明する (Gluckman et al.2007)。この現象が適応なのかエピフェノメノンなのかは、まだ議論の余地がある (Wells 2012)。特に興味深いテストでは、子宮内でカロリー剥奪を受けたヒヒは、成体になってからその後の飢饉を乗り切る能力が劣ることが判明した (Tung et al.)
1.3.4.2 選択が形成した速い生命史と遅い生命史と健康への影響
DOHaDは、初期環境に対する代謝反応の可塑性を強調している。これに関連して、初期の経験が生活史の特徴、特にいわゆる速い生活史戦略と遅い生活史戦略にどのように影響するかを研究する原則がある (Dobson and Oli 2007)。生命が短い可能性が高い過酷な環境では、組織の修復と維持に投資する方が、健康上のコストはかかるものの、早期に頻繁に子孫を残すことに投資するよりも見返りが少ない傾向がある。いくつかの証拠によると、おそらくコルチゾールレベルで示されるストレスレベルを生命の初期にモニタリングし、それに応じて行動と代謝システムを調整して、一般的な環境に対処するメカニズムがあることが示唆されている (Del Giudice et al.2011)。速い生活史モードに設定されたシステムでは、感染症や老化に対する防御が低下し、リスクを取って早期に繁殖する傾向が強くなる。これは、精神障害 (Del Giudice 2014)やその他の障害をより一般的に理解するための包括的な枠組みとして提案されている。これは、コルチゾール曝露によって開始される特定のエピジェネティックなメカニズムが、母親から胎児へ、そして世代間でストレス感受性を伝えることができるという証拠によって裏付けられている (Meaney 2010)。
エピジェネティック効果の役割は、重要な医学的応用を伴う、急速に発展している分野である(Feinberg 2007; Esteller 2008; Keverne 2014)。子宮内のストレスへの曝露は、子孫だけでなく孫のストレス反応性を高める可能性がある (Skinner 2014)。同様に、出生前に飢餓にさらされると、体格や糖尿病や統合失調症のリスクに影響する (Lumey et al.) ラットの海馬では、舐めたり毛づくろいする行為に早期にさらされると、コルチゾール受容体のメチル化が変化するが (Weaverら 2004)、メチオニンの投与により回復する (Weaverら 2005)。この効果は、幼少期に虐待にさらされたヒトにも確認されており (McGowan et al. 2009)、神経機構を介した複数の病原作用が記録されている (Nemeroff 2016)。(さらなる考察は、第17章「脳・脊髄・感覚系」を参照)。
学習は進化的説明の代替案として驚くほど頻繁に引き合いに出されるが、それは個体を特定の環境に適応させる可塑性メカニズムの一つに過ぎない。自然対育成という対立軸で議論を展開する傾向は、何十年も前から批判されてきたが、根強く残っている (Weatherall 1995; Ridley 2003)。個人や集団間の差異を説明する遺伝的・環境的変異の役割が政治的な意味を持つ可能性を強調する傾向があるため、状況は複雑になっている (Gould 1981)。
このことは、遺伝子が環境と相互作用してすべての形質を形成していることを強調するあらゆる努力にもかかわらず、こうした議論が持続することを示唆する生来の認知的偏向に拍車をかけている。
学習と同様に、人間の文化に関する能力も、家畜化に似たプロセスで自然選択によって形成された (Nesse 2010; Wilkins et al.2014; Henrich 2015)。模倣、モラルへの敏感さ、道徳的感情、適合性、その他の心理的特性は、安定した文化を持つ複雑な社会集団の中で生きるのに適している。自然淘汰は文化を可能にする心を形成し、文化は多くの効果を持つ淘汰力を生み出す (Richerson and Boyd 2005)。例えば、大人になってから乳糖を消化できる能力は、酪農文化圏の個体に大きな利益を与え、その結果、酪農をより有益なものにする (Tishkoff et al.) 乳糖耐性対立遺伝子の広がりは、突然変異や淘汰だけでなく、移住も反映している。牧畜集団の急成長は、移住に拍車をかけたのかもしれない (Itan et al.2009)。
1.3.5 自然淘汰は主に遺伝子のレベルで働く
淘汰は主に集団や種に利益をもたらすような形質を形成するものではないという認識は、行動を理解するだけでなく、身体や病気を理解する上でもブレイクスルーものだった。ジョージ・C・ウィリアムズは、1966年に『適応と自然淘汰』を出版し、このことに広く注目するようになった。この洞察は、ほぼ同時期にウィリアム・ハミルトンが発見した血縁淘汰と見事に相乗効果を発揮し、個体の繁殖成功を低下させる対立遺伝子でも、同じ対立遺伝子を持つ親族に十分な利益を与えれば、淘汰される可能性があるというものだった (Hamilton 1964a, b)。これらの考え方は、1982年にドーキンスの『利己的な遺伝子』が出版されたことで、より広く知られるようになった。その結果、さらなる論争と推敲が休むことなく続いている (West et al. 2007; Queller and Strassmann 2009; Leigh 2010; Nowak et al. 2017)。ここで論争を解決しようとしても無駄であり、進化医学の発展に不可欠であった関連する中核的な原理と、これらの原理に対する混乱から生じる誤解を説明することが不可欠である。
1.3.5.1 集団選択は制約された状況下でのみ有効な説明となる
集団内の他の個体よりも繁殖成功率が低い対立遺伝子であっても、集団に十分な利益をもたらすのであれば、それが存続し、あるいはより一般的になることさえある。集団の他のメンバーが血統的に対立遺伝子を共有している場合、その過程は血縁淘汰によってよく説明される。血縁淘汰と集団淘汰のモデルは、同じプロセスを異なる方法で見ることができるという点で一般的な合意が得られているが (Lehmann et al.2007; Frank 2012)、どちらの枠組みが日常的に優れているかについては多くの意見がある (West et al.2008; Wilson 2008)。最近では血縁淘汰の有用性さえも問われている (Nowak et al.) すべての論争にもかかわらず、核となる原理は依然として重要である:その保有者が平均よりも少ない子孫を残す対立遺伝子は、その対立遺伝子が血縁者に利益をもたらすか、またはその個体へのコストが制約された特性のセットを持つ集団の成長率に実質的に影響を与える効果と比較して小さな場合、時間とともに集団で少なくなる傾向にある;後者の条件はまれである。
集団選択の模範となったのは、Wynne-Edwardsが報告した、不十分な食料供給を経験した動物の集団が、集団の存続を確実にするために繁殖を減らす傾向があるという証拠である (Wynne-Edwards 1962)。この研究はウィリアムズ(1966)による批判を促し、集団の利益のために繁殖を抑えた個体は次世代に伝える対立遺伝子が少なくなり、その形質は淘汰されるだろうと指摘した。このため、このような「利他主義」の傾向と関連する対立遺伝子の頻度の持続や増加を説明するために、集団への利益がどのような状況で十分であるかについて永続的な議論が行われてきた (Wilson and Sober 1994、Foster et al.)
論争の一部は、本来の概念とは全く異なる現象に「集団選択」という言葉を使ったことから生じている (West et al.2007)。特に、特定の形質を持つ個体の選択的会合の効果は集団選択と呼ばれ、その結果多くの混乱が生じている。利他主義者が他の利他主義者と結びつくことで、相互に利益を得て、選択力が生じるようなプロセスであれば、どのようなものでもよい。そのメカニズムは、子孫を近接させる粘性のような単純なものから、人間が共同事業で誰と組むかの選択をするような複雑なものまである。Stuart Westらは、このようなモデルを集団選択と呼ぶことについて簡潔に述べている。「別の方法としては、できるだけ簡単に、利他的遺伝子の非ランダムな品揃えのモデルであると述べることだ」 (Westら 2007、p. 11)。
1.3.5.2 多世代にわたる視点が重要である
個体の繁殖成功に害を及ぼす形質でも、将来のある時期に集団を完全な集団崩壊から守ることができれば、存続する可能性がある。このことは、無性生殖と比較してかなりのコストがかかるにもかかわらず、性差が維持されていることの説明となる可能性がある (Stearns 1987; Hamilton et al.) 無性生殖能力を獲得したトカゲの集団は、有性生殖を維持する他の集団の2倍の速度で成長するが、その結果、遺伝的多様性が欠如し、感染のリスクが高まる (Moritz et al.1991)。これが集団選択なのか、それともクレード選択なのかは議論の分かれるところである(Williams 1996)。
性比の研究はもうひとつの有用な視点を提供してくれる。多くの種で性比が1対1に近いことは、集団選択の一貫した強い影響に対する証拠となる。性比は自然淘汰の対象であり、雌雄同数の集団に比べ、雌(メス)中心の集団は2倍近い速度で拡大する。もし、集団選択が広く、強力であれば、雌に偏った性比が一般的になるはずだ。性比が等しいのは、フィッシャーが観察したように、どのような性であれ、親は子孫を残すことで適応度において有利になり、その子孫は平均的に多くの子孫を残すことになるからである(フィッシャー1930)。この原理は、どのパブに行くかでよく理解できる。異性の比率が高い場所を選べば、繁殖の成功、あるいは少なくとも交尾の成功は最大になる。性比が等しいということは、負の周波数依存淘汰によって安定化した形質の典型的な例である (Parker and Smith 1990)。
異常な性比は、雄と雌の生産に等しい努力をすることで適応度が最大になるというハミルトンの認識 (Hamilton 1967)と、その後の特定のケースに関する広範な研究 (Trivers and Wil ard 1973)に基づいて、より深い洞察を与えてくれる。このようなケースを集団選択、血縁選択、社会選択、多階層選択のどれと見るのが最適なのか、あるいはすべての枠組みが寄与しうるのか、論争が続いている (Kramer and Meunier 2016)。
人工繁殖は、集団淘汰の説得力のある実証を提供している。例えば、典型的な小型ケージの中で複数のニワトリが攻撃的につつき合うと、卵の生産量が減少する。
つつきが少なく、卵の数が多いケージからニワトリを繁殖させると、数世代でさらにつつきが減り、卵の生産量が増えるように選択される(Ortman and Craig 1968)。この集団選択の好例は、個体の繁殖成功を最大化する行動を選択するというニワトリの自然状態に、繁殖がいかに逆らうことができるかを示している。
野生の無関係な個体の間で集団選択が行われた事例を記録する試みは、今も続けられている。例えば、社会性クモにおける事例は有望と思われたが (Pruitt and Goodnight 2014)、すぐに深刻な批判を受けた (Grinsted et al.2015)。これらの論争は魅力的であり、医学にも関連するが、集団選択に基づく説明には問題があり、注意深く、代替的な説明を十分に検討した上でのみ呼び出すべきであるという核心的な原則から目をそらすべきではない。
1.3.6 個体繁殖成功率を低下させる形質も血縁淘汰で説明できる
すでに述べたように、ミツバチの利他的行動の謎は、ウィリアム・ハミルトンが血縁関係によって同一の遺伝子を持つこと、つまり、個体の適応度を下げる対立遺伝子であっても、血縁者の適応度を十分に高めれば選択される可能性があることを認識するに至った (Hamilton 1964a, b)。この発見は、動物の行動研究に革命をもたらし (Alcock 2001)、人間を含む生物は親族を他よりも助けることを示す何百もの研究に拍車をかけた (West et al.2002; Lehmann and Keller 2006)。それは、「ハミルトン医学」 (Crespi et al. 2014)の重要なレビューで概説されているように、医学にとって多くの重要な意味を持っている。
1.3.6.1 閉経後も自然淘汰は作用しつづける
多くの医学研究者や臨床医は、閉経後は淘汰が何も影響を与えることはないと考えている。この誤解は、閉経そのものが説明が必要な形質であることを認識していないことと、血縁淘汰の役割を認識していないことという2つの誤りを反映している。
閉経は哺乳類に普遍的な形質ではない。閉経が観察されるのはごく一部の種であり、そのほとんどは社会的関係が体力に強く影響する種である (Peccei 2001)。閉経を説明する試みは、ウィリアムズ(1957)が、ある年齢を超えて繁殖を続けると既存の子孫の成功が危うくなるため、個人の繁殖を止め、代わりに既存の子孫や他の血縁者に投資することで適応度を最大化できるのではないか、と提案したことから始まっている。この考えは、祖母が孫に与える恩恵を反映し、「祖母仮説」と呼ばれている (Hawkes et al.1998)。祖父母のいる子どもの生存率が高いという研究はこの考えを支持しているが (Hawkes 2003)、その恩恵が直接的な繁殖成功の損失を補うほど大きいかどうかはまだ不明である (Hill and Hurtado 1991; Rogers 1993; Austad 1994; Shanley and Kirkwood 2001; Kachel et al.2011)。別の説明では、閉経は、おそらく他の霊長類に比べてヒトの寿命が急速に伸びた結果、卵母細胞間の競争により、その一部しか放出されないというエピフェノメノンとして捉えられている (Reiber 2010)。(さらなる議論については、第15章と第16章を参照)。
1.3.6.2 離乳の競合は必然である
母親は子供とは r = 0.5の関係だが、自分とは r = 1.0の関係にある。生まれたばかりの乳児は完全に母親の世話に依存しているので、母親の繁殖的成功を最大化するには、乳児の最初の数ヶ月のニーズをすべて満たす必要がある。しかし、授乳をやめて再び妊娠することで、将来の世代でより大きな遺伝的代表性を得ることができる時期が来る。しかし、その時点でも授乳を続けることによって赤ちゃんの体力は最大化される。その結果生じる離乳の競合は哺乳類に普遍的なものである。少し大きくなると、幼児は母親からミルクをもらうのをあきらめ、幼児と共通の対立遺伝子を持つ弟妹を作ることができるようになり、幼児の遺伝的利益は最大となる。この単純な原理は、ロバート・トリバースが親子間の対立を説明するために提案したより一般的な理論の一側面である (Trivers 1974)。このほか、病気に対する脆弱性を高める父性ゲノムと母性ゲノムの競合については、以下で取り上げる。
1.3.6.3 母性ゲノムと父性ゲノムの競合は病気を引き起こす可能性がある
雌が異なる生殖エピソードのために異なる雄と交尾する可能性がある種では、父性ゲノムの利益は雌からこの子孫への追加投資を誘発することによってもたらされ、母性ゲノムの利益は体細胞の維持と将来の生殖のための資源を蓄えることによってもたらされる。David Haigは、このようなメカニズムが妊娠中の病気の重要な要因である可能性を示唆し、ゲノムインプリンティングのパターンがその予測に合致していると述べている (Haig 1993)。卵はインスリン様成長因子2遺伝子 (IGF2)の発現を低下させるエピジェネティックマークを持ち、母体ゲノムの利益のために、胎児の成長をいくらか低下させる。精子にはIGF2rというIGF2と拮抗する効果を持つ遺伝子の発現を低下させるインプリンティング・マークがある。インプリンティングが正常に機能すれば、両者の効果は釣り合うが、一方が欠落すると、子孫は平均より大きくなったり小さくなったりする (Haig 2004)。
ヒトの病気におけるこれらの競合システムの役割は、染色体15q11-q13上の遺伝子の発現不全によって引き起こされるプラダー・ウィリー症候群によって明らかにされている。予測されるように、プラダー・ウィリー症候群の乳児は、弱い早期哺乳や、父性ゲノムに対して母性ゲノムを利するような他の行動を特徴とする行動表現型を持つ (Haig and Wharton 2003)。ウィリアムズ症候群は、関連した解釈をしている (Crespi and Procyshyn 2017)。
ベックウィズ・ウィーデマン症候群とシルバー・ラッセル症候群も、性的に拮抗する刷り込みエラーに起因すると思われる (Eggermann et al.2008)。このような刷り込みに関するシステムの臨床的意味は、刷り込みマークを沈着させる発生段階を迂回する体外受精 (IVF)法にとって特に重要である。体外受精で生まれた赤ちゃんは、ベックウィズウィーデマン症候群になる確率が他の赤ちゃんより14倍も高い (Halliday et al.2004)。妊娠中に投与される高用量の葉酸など、DNAのメチル化に影響を与える薬剤の影響については、細心の注意を払う必要がある (Smith et al.2008)。(Bernard Crespiらは、関連する考えを統合失調症と自閉症に関する仮説に発展させた (Crespi et al.2007; Crespi and Badcock 2008; Crespi 2010)。彼らは、自閉症は父性ゲノムからの過剰な影響による男性過多脳 (Baron-Cohen 2002)と関連し、統合失調症は母性ゲノムの過剰な影響によるものと考えている (Dinsdale et al.2016)。これは、障害に影響を与える遺伝子のメチル化のパターンと一致するようだ。また、自閉症を発症するようになった子どもは、統合失調症と比較して出生時体重が少し高くなることも予測されており、この予測はデンマーク人70万人のデータベースを用いた研究でも確認されている (Byars et al.2014)。これは、決してその理論を決定的に裏付けるものではないが、進化的な視点がいかに新しい道を切り開くかを示す調査結果である。
1.3.7 細胞複製の制御はメタゾアンの生命維持に不可欠
細胞複製の制御という課題は、多細胞生物の起源を数十億年先送りにした (Valentine 1978; Queller and Strassmann 2013)。しかし、このようなシステムの限界は、癌が常に問題であることを意味する (Frank 2007)。細胞は当初、自己防衛と環境制御のために集合した。このような集団に属するすべての細胞は遺伝的に同一ではないため、他の細胞よりも速く複製するような対立遺伝子が選択され、たとえそれが大きな集団に害を与えるとしても、そのような集団は存在しない。この対立は通常、人間の「協力」と「離反」という言葉を使って表現される。協力を強制する方法が進化するまでには、数十億年かかった。
解決策の鍵は、個体内のすべてのセルを発生初期に遺伝的に同一にすることである。また、体内のほとんどの細胞(体細胞系列)は新しい個体を作ることができないため、個体の福祉に貢献することによってのみ、自らの遺伝的利益を増進できるようにすることであった。そのために、生殖細胞系列という特別な細胞を隔離し、慎重に管理された環境下で生殖にのみ専念させる必要があった。
1.3.8 ゲノム内コンフリクトは健康に影響を与えうる
ゲノムレベルでの対立 (Austin et al.2009)は、進化医学の研究において大きな焦点となっている。もし、同一でない細胞集団から生殖が開始された場合、古くからの対立が再び起こり、個体にとって大きなリスクとなる。将来の生殖細胞になる可能性が高い対立遺伝子を持つ細胞が、たとえ個体に害を与えても選択されることになる。その解決策が減数分裂である。ゲノムを一本鎖のDNAにスリム化するプロセスにより、次のソーマのすべての細胞が遺伝的に同一であることが保証される (Hurst and Nurse 1991)。同一の細胞は、その個体の包括的な適応度にとって良いことをすることによってのみ、遺伝的利益を向上させることができる。
しかし、これでも十分に保護されているとは言えない。ある対立遺伝子は、同じ対立遺伝子を持たない隣接する細胞の発達を阻害することで、将来の世代でより一般的になる可能性がある。このような減数分裂に基づくシステムには、通常、毒素と解毒剤が別々の場所に必要である (Sandler and Novitski 1957; Lyttle 1993)。減数分裂の際の交差によって、このような対立遺伝子のペアが分離され、ゲノム内の衝突からシステムを保護することが示唆されている (Haig and Grafen 1991; Hurst 1998)が、遺伝的エラーが生じるリスクもある。
ミトコンドリアゲノムの複数コピーの遺伝は特殊なケースである。
ミトコンドリアの遺伝は母親からのみであり、卵子では数個のコピーしか伝達されない。それらは個体内で増殖し、妊娠中期には300億個に達する (Haig 2016)。その過程で、個体の福祉への貢献度が低くても、複製を早める対立遺伝子を持つミトコンドリアがより一般的になっていく。世代を超えて、生殖細胞への優先的なアクセスをもたらす対立遺伝子を持つものが、より一般的になる。
このような非効率性を制御するために、さまざまなメカニズムが進化してきた。受胎時のボトルネックは、卵子間の変異を増加させ、より協力的なミトコンドリアを選択できるようにする。細胞複製時にミトコンドリアが融合することで、可溶性生成物を共有し、「競争の場を均等にする」ことができる。
「競技場を平準化」し、将来の分裂で個体に利益をもたらすミトコンドリアを選択できるようにする (Haig 2016)。競合する選択力がどのようにミトコンドリアを形成するか、そしてミトコンドリアゲノムに利益をもたらすミトコンドリア形質がどのように疾患の脆弱性を高めるかについての研究は、進化医学に重要な機会を提供する (Wal ace 2005; Ma and O’Farrell 2016)。
1.3.9 体細胞選択により、個体の生涯で細胞の遺伝子型は変化する
体細胞選択は、悪性腫瘍の中で、異なる遺伝子型を持つ細胞同士が競争することで劇的に示される。体細胞選択の役割が認識されたことで、抗生物質耐性の研究で開発された分析手法が、がん化学療法に応用されつつある。また、悪性腫瘍を取り巻く組織や、微小環境の変動がどのように腫瘍の成長を早めたり遅らせたりするかを調査するために、生態学的手法を導入することも奨励されている (DeGregori 2017)。これらの新しい視点は共に、化学療法をより効果的にする方法を示唆しており、しばしば「適応的化学療法」 (Gillies et al.2012、Enriquez-Navas et al.2016)において投与量を減らすことによって、化学療法をより効果的にする。(さらなる考察は、第9章 血液形成系を参照)。
体細胞選択は、通常の適応免疫においても、エピトープを認識するリンパ球がより速く分裂し、より広く普及し、記憶を発達させて、その後起こりうる再感染のエピソードに備えるときに起こる。このようなシステムでは、多くの抗原を認識する細胞集団を持つことの利点と、自己免疫疾患のリスクとの間で、トレードオフのバランスがとられている (Schmid-Hempel 2011)。
1.3.10 自然淘汰による生活史形質の形成
子孫の数、子孫のサイズ、生殖のタイミング、成熟年齢、老化の速度などの形質は、包括的なフィットネスを最大化するための選択によって形成される(Stearns 1989; Chisholm 1993; Hill and Kaplan 1999)。すべてにおいてトレードオフの関係にある。子孫の数が多ければ、必然的に子孫の数は少なくなる。生殖を早く始めると、必然的に子孫は小さくなり、質も低下する。出産間隔が短いと母親の健康が損なわれ、既存の子孫に投資する能力が損なわれる。オスとメスで異なる子孫への投資パターンは、生活史理論を使って分析することができる (Hinde 2009)。淘汰は、平均包括適応度を最大化するように、これらの生活史形質を形成する (Kaplan et al.2000)。
生活史理論 (LHT)は種間の違いを説明するために開発されたが、個体間の生活史形質の違いを考慮するために適応された。妊娠期間や生殖開始年齢のようないくつかの違いは、選択によって作用する遺伝的形質であり、その種におけるその形質の平均や分布を形成している。他のすべての形質と同様に、生活史形質も現代の状況には適合しないことがある。
例えば、初潮を迎えるメカニズムは、現代の環境と相互作用して、私たちの祖先よりも4年以上早くサイクリングを開始し、生殖能力ほど速く身体と脳が発達していない非常に若い母親を何百万人も生み出している (Al sworth et al.2005)。詳しくは第4章を参照。
最近では、環境の影響によって引き起こされる生活史形質の変動に注目が集まっている。特に、早期にストレスにさらされると、リスクテイキングと繁殖能力の低下を特徴とする「速い生活史戦略」が誘発される
Kaplan et al. 2000; Dobson and Oli 2007; Austad and Finch 2016; Shalev and Belsky 2016; Wel s et al. 2017)である。このようなメカニズムは、逆境や差別を受ける人々の健康リスクの増加を説明するのに役立つと提案されている (Promislow and Harvey 1990; Bielby et al.2007; Dobson and Oli 2007)。また、精神障害を理解するための組織原理を提供するとも言われている (Del Giudice and Ellis 2016)。
これらの変異が淘汰によって形成された先天的な適応なのか、それとも他のプロセスのエピフェノムエナなのかは、提案されているメカニズムごとに取り組むべき重要な問題である。一つの寿命内での影響と世代を超えた影響についての提案には、別々のアプローチが必要になりそうである。
1.3.11 欠損効果を持つ遺伝子は、それを補う効果があれば選択されうる
拮抗的多面性とは、ある状況や時期には有益な効果があり、他の時期には有害な効果がある遺伝子のことである。これは特に老化の進化を理解する上で重要であり (Williams 1957; Hamilton 1966; Kirkwood and Austad 2000)、現在では複数の研究が、早い生殖と早い老化の間のトレードオフを実証している (Kirkwood and Rose 1991)。野生個体群における老化のフィットネスへの強い影響は、突然変異の蓄積では説明がつかないことを示す証拠となっている (Nesse 1988; Nussey et al.)
他の時期におけるトレードオフも関連する可能性がある。例えば、受精や子宮着床の可能性を高める対立遺伝子は、後にかなりのフィットネスコストを課すとしても、強く選択されるであろう。性的に拮抗する選択は、特別な種類の拮抗的多面性と見なすことができる (Rice 1992)。例えば、鉄の吸収を高める対立遺伝子は、男性ではヘモクロマトーシスを引き起こす傾向があるが、女性では月経周期に伴って血液が失われるため、ほとんど問題はない (Adams et al.1997)。(さらなる議論は、第5章老化を参照)。
Dobzhansky (1963)が説明したBalancing selectionは、頻度や状況に依存した選択により、ある遺伝子座で対立遺伝子が維持される過程を示している。
鎌状赤血球のヘモグロビン対立遺伝子と通常のヘモグロビン対立遺伝子がバランスよく維持されているのは、その典型的な例である (Allison 1954; LivingS-1 1960)。通常のヘモグロビンを持つホモ接合体はマラリアに弱く、鎌状赤血球ヘモグロビンを持つホモ接合体は重度の鎌状赤血球症にかかり、生殖成功率が大幅に減少する。
ヘテロ接合体の個体はマラリアによる死亡からある程度保護されるが、鎌状赤血球症の重い症状は出ない。そのため、マラリアが流行している地域では、ヘテロ接合体の方が体力があり、鎌状赤血球対立遺伝子の頻度が高くなり、ホモ接合体が一般的になってしまうのである。マラリアがない環境では、鎌状赤血球の対立遺伝子は淘汰される。鎌状赤血球症は、進化医学の模範として取り上げられることがある。しかし、進化の時間スケールで見ると、鎌状赤血球の対立遺伝子は比較的新しく、バランス選択で説明できる病気の例は少なく、ほとんどがマラリアから身を守る赤血球の変異に関連したものである。考えられる説明は、ヘテロ接合体の優位性のコストが、代替的な解決策に強い選択を課していることである。(病気の脆弱性は、著者が実際には単一の対立遺伝子による拮抗的な多面的効果、あるいは形質レベルでのトレードオフの効果を意味しているのに、均衡淘汰のせいだとされることがある。しかし、バランス淘汰が病気の脆弱性を説明するのに有効である場合もある。ゲノムワイドなスキャンにより、均衡選択が起こっていると思われる遺伝子座が発見され (Asthana et al. 2005)、新しい手法により均衡選択を示唆する部位がさらに特定されており (Charlesworth 2006; de Filippo et al.2016、Gloss and Whiteman 2016)、この分野は調査のチャンスである。
バランシング選択は、自閉症、てんかん、統合失調症への脆弱性を高める小さな効果を持つ対立遺伝子のスコアなど、病気を引き起こす組み合わせの希少対立遺伝子の存続を説明するためにしばしば誤って唱えられる。一般に、このような対立遺伝子が、その頻度や異なる状況での効果に依存した選択的優位性によって、ある中間的な頻度で維持されているという証拠はほとんどない。しかし、これは依然として可能である。突然変異と選択のバランスは、エピスタシスや拮抗的な多面性から生じる複雑さとともに、より妥当な説明となることが多い (Keller and Miller 2006)。
1.3.12 崖っぷちのフィットネスランドスケープがいくつかの遺伝病の存続を説明する可能性
ヒトゲノムの解読により、自閉症、統合失調症、てんかんのような遺伝性の高い疾患の原因となる対立遺伝子がすぐに見つかるという希望がもたらされた。しかし、ゲノムワイド関連研究により、これらの疾患のほとんどに対する脆弱性のごく一部以上を占める共通対立遺伝子はないことが判明した (Woo et al.2017)。ある形質の値に対する適応度が、適応度の崖の近くで急激に上昇し、それを超えると壊滅的な失敗をする可能性がある場合、一つの可能な説明が生じる。例えば、速さを求めて馬を選抜すると、折れやすい細長い脚の骨が形成される。平均的な個体にとってスピードを最大化する(そして繁殖の可能性を最大化する)骨の形態は、少数の個体にとっては破滅的な失敗となる。これは、個体の健康を犠牲にして対立遺伝子の適合度を最大化する淘汰の劇的な例である。統合失調症への脆弱性を高める対立遺伝子の存続を説明するのに役立つかもしれないし (Nesse 2004)、胎児の頭の大きさと骨盤の開きのトレードオフに応用されている (Mitteroecker et al.2016)。(さらなる考察は、第16章 性的・生殖・出産を参照)。
崖っぷちの適応度関数が一般的であれば、大きな影響を及ぼす共通対立遺伝子が見つからない他の高遺伝性障害の存続を説明するのに役立つかもしれない。形質を崖っぷちに追い込むことの利点と、少数の個体にとって破滅的な失敗のコストが組み合わさって、安定化選択が生じ、最大適合度点周辺の変異の範囲が狭められるはずだ。この安定化に小さな効果を持つ多くの対立遺伝子の効果が含まれるなら、その結果は「欠落した遺伝率」と呼ばれているものを説明するのに役立つだろう。このモデルは、親族がその病気に罹患している場合に大きな利点がないこと、また、その原因となる対立遺伝子が異常でない可能性があることと矛盾しないことに注意されたい。また、対立遺伝子は必ずしも突然変異ではなく、また必ずしも異常でもないことに注意してほしい。複数の対立遺伝子が一緒になって形質を安定した表現型に形成し、平均適応度を最大化するが、一部の個人にとっては破滅的な病気や怪我が不可避になる (Nesse, in preparation)。
1.3.13 倫理への配慮は重要である
医学における進化的アプローチの歴史を振り返ると、人種と遺伝学に対する誤解が、深刻な過ちと、より周辺的には優生学とホロコーストという道徳的破滅と結びついた「医療ダーウィニズム」へとつながっていったことがわかる (Zampieri 2009)。現代の進化医学は、個人の健康を向上させるために進化的原理を用いた、根本的に異なる事業であり、これまでのところ、大きな倫理的妥協は避けられている。しかし、ゲノムデータの増大により、ヒトのサブグループ間の違いがさらに明らかになり、また、ゲノム編集技術が広く使用されるようになったことから、引き続き注意が必要である。しかし、病気に関する進化論的な考え方が、人間のサブグループや個人を軽蔑するために使われないように、警戒が必要である。
1.3.14 人種は生物学的カテゴリーではない
異なる地理的起源を持つ人々を、定義可能な特徴を持つ異なる外接集団の一員と見なす傾向は根強い。20世紀初頭の人類学的研究は、人種を生物学的に分離された集団として本質化し、この傾向を強めた (Smedley and Smedley 2005)。異なる人種を指定する言葉が使われることで、人間のサブグループを変異株と見なす誤った考え方がさらに定着してしまうのである。ヒトの亜集団間の遺伝的差異を証明する新たな調査は、亜集団が互いを根本的に異なると見なすときに栄える反感とともに、こうした誤った分類を再び呼び起こす危険性がある(グレーブス2001)。ヒトの現実は、他の霊長類の亜集団と比較して、亜集団間の遺伝的差異が比較的小さく、肌の色は決して地理的起源の異なる個体を識別するための信頼できる形質ではないということである。さらに、最近のデータによると、皮膚の色素のバリエーションをコードする遺伝子は、ほとんどがアフリカから人類が移住した時期よりはるかに古く、この常在バリエーションに対する選択により、人種カテゴリーを超えた汎用の肌色のバリエーションが生まれた (Crawford et al.2017 )。
1.3.15 ヒトのサブグループ間の遺伝的差異が健康に影響する
地理的に異なる祖先を持つヒトの間の遺伝的差異は比較的小さいにもかかわらず、遺伝マーカーによって個人の出身大陸を確実に特定することができ (Elhaik et al. 2014)、主成分分析によってヒトのゲノムグループが異なる大陸に対応するものに分かれていることが確認されている (Jorde and Wooding 2004)。
遺伝子の違いによって、英国の多くの人々の出身年齢を正確に特定することも可能だ(レスリーら2015)。しかし、これらの差は、近縁の霊長類のグループ間の差よりもかなり小さい (Long and Kittles 2009)。人種という考え方の社会的性質は、病気に対する脆弱性に影響するヒトのサブグループ間の遺伝的差異を考慮することを妨げてはならない。
地理的に異なる場所に祖先を持つ人間には、健康に影響を与える遺伝的差異がある。明らかな例は、ビタミンDを合成する能力の低下と、北部の気候におけるくる病の関連リスクと引き換えに、皮膚がんや葉酸の破壊から保護する皮膚色素のバリエーションである (Greaves 2014; Jablonski and Chaplin 2017)。ビタミンD欠乏症の有病率が高いにもかかわらず、アフリカ系の人々の骨密度が比較的高いことから、ビタミンD結合を増加させる対立遺伝子の選択が発見された調査が行われている (Powe et al.2013)。
他にも、寒冷地出身者の手足が短いなど、肉眼で観察できる違いがあり、熱を奪われることが重要な選択的要因であった。しかし、突然変異、移動、遺伝的ドリフトも、亜集団間の遺伝的差異を説明する有力な材料である。特に重要なのは、アフリカからの移住の過程で、人類の遺伝的変異の約半分が失われたことである。この世界的なボトルネックは、適応的な意義を持たない遺伝的差異をもたらす追加のボトルネックによって増強された。
病原体への曝露に関連した遺伝的差異も重要である。住血吸虫症が選択力となっている地域では、住血吸虫症に対する抗体を作る傾向があり、それはゴキブリ抗原への曝露に反応して喘息を引き起こす防御免疫反応の傾向とも関連している (Barnes et al.1999)。すでに述べたように、ヘモグロビンSは、マラリア感染のストレスにさらされた赤血球を、脾臓でのクリアランスの増加に関連した形状に変化させる。これは、マラリア感染に対する防御にはならないが、感染した赤血球のクリアランスを促進することにより、死亡率を低下させる (Luzzatto 2012)。マラリアが流行している地域の人々の大半は、正常なDARCタンパク質を欠いている (Lentsch 2002; McManus et al.2017)。新しい安価な配列決定法により、他の病原体への曝露によって選択されたと思われる遺伝的変異の調査が加速している (Penman and Gupta 2017)。(さらなる議論は、第9章 血液形成系を参照) アルコールデヒドロゲナーゼとアルデヒドデヒドロゲナーゼの活性低下は、東アジア系の人々に特に多く、紅潮などの症状を引き起こす (Lin and Cheng 2002)。これらの対立遺伝子が特定の地域に多いのは、蒸留酒に長く触れる文化の中でアルコール依存症を防ぐという利点があるためと考えられ、これらの対立遺伝子を持つ人は他の人より飲酒量が少ない傾向があるようだ。また、この遺伝子がアジア人で最も長いハプロタイプの中央に位置していることは、アルコール依存症に対する保護をもたらす選択を裏付ける証拠になるようだ。しかし、新しい遺伝学的証拠は、アルコール脱水素酵素の違いは、アルコールへの曝露以外の形質に対するこれらの変異の多くの影響から生じることを示唆している (Polimanti and Gelernter 2018)。
1.3.16 あるものが、あるべきものであると仮定するのは間違いである
ある形質が「自然」であることを学ぶと、多くの人は問題の形質が良いものであるか、少なくとも受け入れられるものであると信じるようになる (Elqayam and Evans 2011)。この傾向は、形質を形成した適応的機能についての議論によって増幅される。最も顕著な例は、交配パターンに関するものである。オスはメスに比べて、交尾を重ねることでより大きな適応度を得ることができる。この洞察は多くの人にとって、交配関係におけるオスの不貞を正当化するのに役立っているようである。自然に見える形質から道徳的判断を差し控える一般的な傾向は、長い間哲学者によって指摘され、批判されてきた。しかし、そのような勧告は広い世界ではほとんど影響を与えないので、進化論の考えが医学でより広く適用される際には警戒が必要である。この「ある対べき」の対立はしばしば「自然主義的対立」と表現されるが、この用語は哲学界ではやや異なる意味を持っている (Greene 2003; Curry 2006)。
1.3.17 人間にとって自然淘汰は終わらない
公衆衛生の進歩により、小児期に死亡する可能性は低くなり、現在生まれてくる子供のほとんどは生殖能力のある大人に成長する。このため、自然淘汰はもはや人類の進化に影響を及ぼしていないと結論づける人もいた (Rose 2001)。この間違いは、単純な誤解から生じている。自然淘汰は死亡率の違いを必要としない。必要なのは、生き残る子孫の数に影響を与える遺伝子の違いだけであり、その違いは持続する。しかし、小児期の死亡率、そしてより一般的な死亡率の劇的な低下は、現代の集団に作用する選択の力を大きく弱めていることは確かで、ゲノムへの影響について懸念を抱く人もいる (Kondrashov 2017)。
1.3.18 関係をたどるための遺伝学的手法と系統を追跡する遺伝学的手法は、進化医学において多くの応用がある
冒頭で述べたように、進化医学の原点は、病気の脆弱性を説明しようとしたことで、系統や集団遺伝学の手法が相対的に軽視されるようになった。この分野での私自身の限界から、この章では、このような手法を用いた広範な研究が存在すること (Kumar et al. )分類学的関係の特定、分岐時間の推定、形質が時間の経過とともに獲得または喪失される理由の理解に有用である。このような研究を進化医学の他の側面と統合する努力を続けることは、すべての関係者に利益をもたらす。
1.3.18.1 ヒトの祖先をたどることは医学的意義がある
ほんの数十年前までは、ネアンデルタール人のDNA配列の解読や、ましてや現代人の特定の遺伝子座の特定が可能になるとは誰も想像しなかった (Green et al.2010)。デニソワ人の別系統が同定されたことは、さらに予期せぬ驚きであった。ホモ・サピエンスとデニソワ人との交配で最近組み込まれた遺伝子の医学的意義を考える人もいるが (Tishkoff and Verrelli 2003; Simonti et al.2016)、今のところ精査を促すものがほとんどである。ヒトとチンパンジーのゲノムの比較から、さらなる洞察が得られている (Olson and Varki 2003)。
X染色体やY染色体の変異パターンを調べる専門的な技術は、農耕によって食糧貯蔵と社会階層が可能になった後に社会組織が劇的に変化したという人類学の理論を強力にサポートすることが判明した。最近の分析では、少数の男性が平均的なヒトゲノムに不釣り合いに貢献するという生殖の偏りが、ちょうど農業が急速に普及した時期に劇的に増加したことが判明した (Webster and Wilson Sayres 2016)。
1.3.18.2 系統遺伝学的手法で病原体の起源と拡散を追跡することができる
数十年前、配列を用いて特定の食品媒介性病原体の拡散をその発生源まで追跡することは大きな成果であった。現在では、新しい手法によって、しばしば緊急の公衆衛生上の意味を持つ知見が明らかになりつつある (Zhao et al.2014)。SARSウイルスに関する研究では、その発生源がコウモリであることがすぐに判明した (Li et al.) エボラ出血熱に関する新しい研究では、その広がりだけでなく、いつ、何回、ヒトに渡ったのかも記録されている (Gire et al.2014)。ヒトにおけるHIVの起源に関する推測は、系統学的手法のおかげで、以前疑われていたよりもはるかに長くヒトに循環していたウイルスから広がったことが確認された (Heenyら 2006;Wertheim and Worobey 2009)。
ヒト集団内での病原体の広がりは、遺伝学的手法で追跡することができる。結核は、アザラシを介したヨーロッパ人の新世界への侵入に先行し、その後、ヒトに適応した系統の侵入があった (Bos et al.) 病原体の系統を追跡する方法は、急速に発展し続けている (Hartfield et al.2014)。
1.3.19 進化仮説の組み立てと検証のための方法は、依然として開発中である
すでに指摘したように、多くの科学者やほとんどの臨床医は、近接的説明と進化的説明の違いを十分に理解していない。理解できていても、進化的仮説を構築し、検証するための幅広い手法や、両方を体系的に検討することの利点を知らないことが多い (Hinde and Milligan 2011)。その結果、誤解と懐疑が広がっている。病気や病気に関連する特定の対立遺伝子に適応的な機能を提案するなど、初歩的な間違いが多いことから、多くの懐疑論が正当化されている。このような仮説の検証の難しさや、初歩的な間違いの多さに注意を払うとともに、忍耐が必要である (Mace et al.2003; Ellison and Jasienska 2007; Nesse 2011a)。
進化医学の中核となる概念は数多くあり、中には微妙なものもある。本書のように多くの例を挙げながら、一冊の本を作ることが必要である。
人間の認知によくあるいくつかの不具合は、これをより難しくしている (Kahneman 2011; Nisbett 2015)。単因性説明の欲求は強く、動脈硬化のような病態が、ミスマッチ、トレードオフ、制約、防御を含む説明を必要とすることを多くの人が理解することは困難である。人間の傾向として、特定のものに特定の機能を持たせようとする傾向があるため、「これは○○の遺伝子だ」「△△は△△だ」と説明することがほとんど意味をなさないことを人々に理解させるのは難しい。
「の遺伝子である」「この感情の機能はXである」と言うことは、ほとんど意味をなさないことを人々に理解させるのは困難である。こうした困難は、進化医学に限ったことではないが、研究対象のシステムが有機的に複雑であるため、特に顕著である。
1.3.20 有機的な複雑性は、機械における複雑性とは種類が異なる
私たちは、身体を設計された機構として見ることから、有機的な複雑さを特徴とする自然淘汰の産物として見ることへと移行している最中である (Nesse et al.2012; Hauser et al.2017 )。生物学や医学の多くは、身体を暗黙のうちに創造論的にとらえ、特定の機能を持つモジュールがきれいに分離され、他のモジュールと単純な方法で接続されているかのように考えている。生化学的な経路を描いた図は、理想化されたシステムを示す傾向があり、分子同士や受容体との無数の厄介な相互作用が無視されている。私たちは内分泌系を、あたかも1つの標的に対して単純な分子が作用しているかのように教えている。神経科学者たちは、根底にある有機的な複雑さとは裏腹に、機能を持った遺伝子座や神経回路を説明する。
単純化することを求めるのは理解できることだ。科学の力と美しさの多くは単純化する能力に由来しており、私たちは原理や発見を人間の脳が理解できる方法で他の人々に説明しなければならない。しかし、遺伝子、分子、ホルモン、臓器は、機械の構成要素とは全く異なる形で相互作用している。1つまたはいくつかのバックアップ機構ではなく、部品が欠けていても安定性を維持できるような、絡み合った機能を有している (Nijhout 2002; Hammerstein et al.)
何か特定の目的を果たすために設計されたのではなく、繁殖を最大化するために、時には健康を犠牲にして形成された。このような、有機的に複雑な身体という進化論的な見方は、徐々に広まっていくことだろう。しかし、進化論的なレンズを通して身体や病気を見るようになれば、病気はますます意味を持つようになり、私たちは病気を予防したり治療したりする能力を高めていくことだろう。
1.4 結論
進化と医学への新たな関心は、自然淘汰がなぜ身体に病気になりやすい形質を多く残したのか、という新たな問いかけによって始まったものである。その結果生まれた新しい分野は、こうした原点に縛られたまま、急速に拡大しているため、核となる原則のリストを完全なものにすることはできない。読者は自分なりの原則を追加すべきだし、教師は授業の内容をここに挙げた原則に限定すべきではない。
謝辞
Anne Stone, Benjamin Trumble, Daniel Grunspan, Jon Laman, Martin Brüneから、本章の改善に役立つコメントと示唆を得たことに感謝する。
