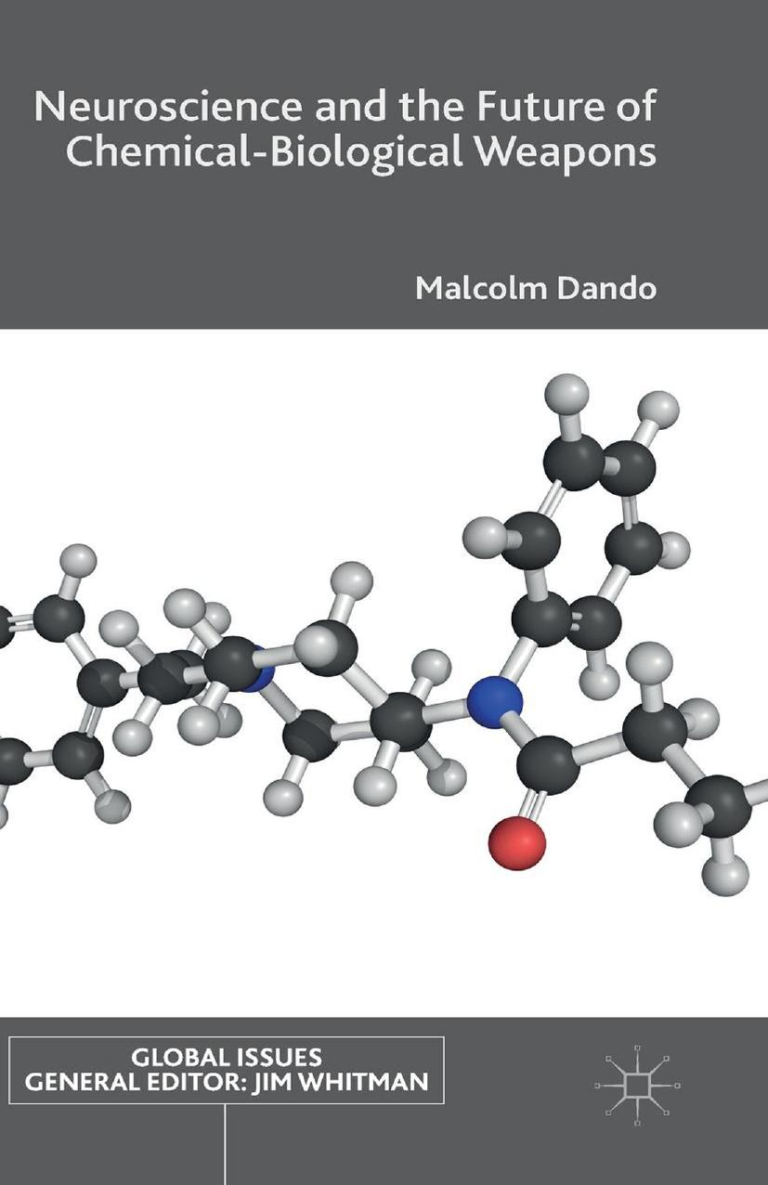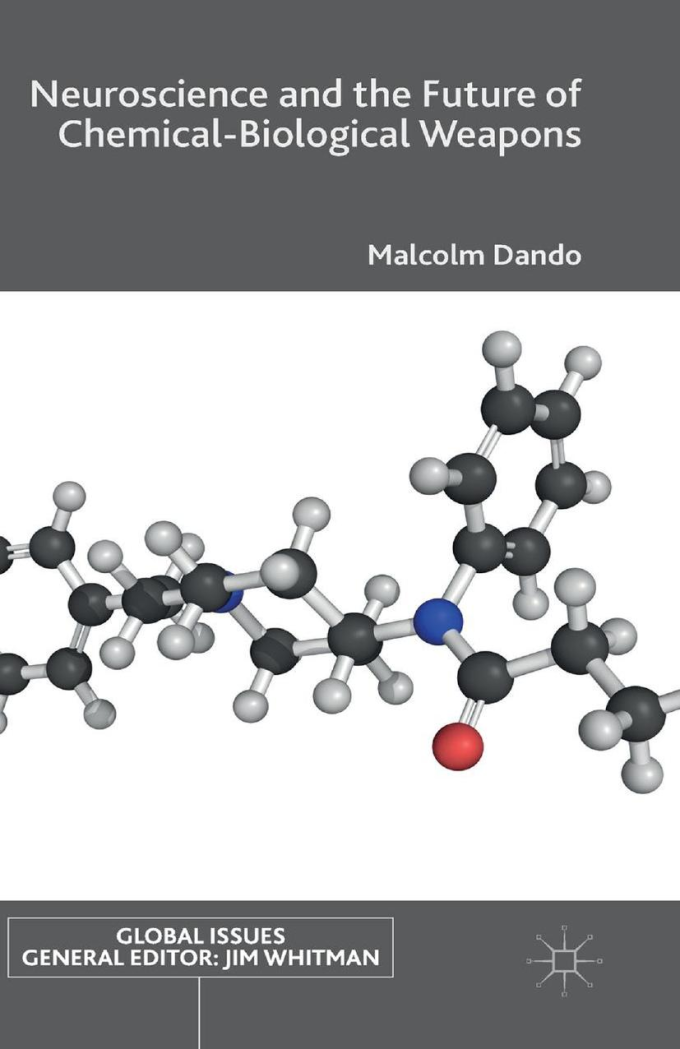
英語タイトル:Neuroscience and the Future of Chemical-Biological Weapons/ Malcolm Dando 2015
日本語タイトル:『神経科学と化学・生物兵器の未来』/ マルコム・ダンド 2015年
目次
- 第一部 過去:神経科学とCBW / Part I The Past:Neuroscience and CBW
- 第1章 神経科学と化学・生物兵器 / Chapter 1:Neuroscience and CBW
- 第2章 脳の構造と機能 / Chapter 2:The Structure and Function of the Brain
- 第3章 CBW不拡散体制 / Chapter 3:The CBW Non-Proliferation Regime
- 第4章 デュアルユースの課題 / Chapter 4:The Dual-Use Challenge
- 第二部 現在:現代の神経科学 / Part II The Present:Modern Civil Neuroscience
- 第5章 現代の民間神経科学 / Chapter 5:Modern Civil Neuroscience
- 第6章 新型神経兵器 / Chapter 6:Novel Neuroweapons
- 第7章 神経科学の進展がもたらすもの / Chapter 7:Implications of Advances in Neuroscience
- 第8章 無力化剤の探索 / Chapter 8:The Search for Incapacitants
- 第9章 バイオレギュレーターと毒素 / Chapter 9:Bioregulators and Toxins
- 第三部 未来:化学・生物兵器不拡散体制の今後 / Part III The Future
- 第10章 科学技術の変化に直面するBTWCとCWC / Chapter 10:The BTWC and CWC Facing Scientific Change
- 第11章 我々はどこに向かっているのか? / Chapter 11:Where Are We Going?
- 第12章 デュアルユース神経科学のガバナンス / Chapter 12:The Governance of Dual-Use Neuroscience
本書の概要
短い解説
本書は、神経科学の急速な進歩が、化学・生物兵器(CBW)の開発に悪用される可能性に焦点を当て、その歴史的経緯、現在の脅威、未来の展望を分析する。対象読者は、神経科学者、安全保障政策関係者、国際関係研究者であり、科学と安全保障の接点における「デュアルユース(軍民両用)」の課題を理解することを目的としている。
著者について
著者マルコム・ダンドは、英国ブラッドフォード大学の国際安全保障学教授であり、35年以上にわたり化学・生物兵器の軍縮・不拡散問題を研究してきた。特に、生物・毒素兵器禁止条約(BTWC)と化学兵器禁止条約(CWC)の強化に焦点を当て、生命科学者の教育と意識向上の重要性を主張している。
テーマ解説
- 主要テーマ:神経科学の進歩が、新型の「無力化化学剤」や「神経兵器」の開発につながる危険性。
- 新規性:神経回路や神経調節メカニズムの解明が、行動の精密な操作を可能にし、それが兵器に転用される可能性を指摘。
- 興味深い知見:寄生虫による宿主行動操作の研究(神経寄生学)が、将来的な人間の神経操作技術のモデルとなりうる。
キーワード解説(抜粋)
- デュアルユース:平和目的で開発された科学技術が、兵器など有害目的に転用されること。
- 無力化化学剤:致死ではなく、一時的に行動能力を奪うことを目的とした化学物質(例:オピオイド系鎮静剤)。
- バイオレギュレーター:体内で生理機能を調節する物質(例:オキシトシン)。大量投与で行動操作に悪用される可能性。
- 神経寄生学:寄生虫が宿主の神経系を操作して行動を変えるメカニズムを研究する学問。将来の神経兵器のモデルとなる。
3分要約
本書は、神経科学の進歩が、化学・生物兵器の新たな世代を生み出す危険性を警告する。歴史的に、アセチルコリンの発見から神経ガスの開発、精神薬の研究から無力化剤BZの兵器化など、民間研究が軍事転用されてきた経緯を第1部で詳述する。
第2部では、現代神経科学の最先端、特に米国「BRAINイニシアチブ」やEU「ヒューマンブレインプロジェクト」が目指す「神経回路の機制的理解」が、行動操作技術の飛躍的進歩をもたらす可能性を示す。同時に、軍や治安機関による「無力化化学剤」への関心や、オキシトシンなどバイオレギュレーターを利用した「影響操作」研究の進展が、国際的な不拡散体制を脅かしている現状を分析する。
第3部では、BTWCとCWCが科学技術の急速な変化に対応できていない現実を指摘し、条約の強化と科学者コミュニティの意識向上が急務であると主張する。特に、神経科学者を含む生命科学者に対する「デュアルユース教育」の徹底と、国際的なガバナンス枠組みの構築を提言する。
著者は、神経科学の悪用が「紛争の性質を根本的に変える」可能性を危惧しつつも、その未来は決定されていないと説く。科学者自身が社会的責任を自覚し、研究の悪用を防ぐための積極的関与こそが、悲劇を回避する鍵であると結論づける。
各章の要約
第一部 過去:神経科学とCBW
第1章 神経科学と化学・生物兵器
20世紀において、神経科学を含む生命科学の進歩は、化学・生物兵器の発展に大きく寄与した。神経伝達物質アセチルコリンの発見は、神経ガスの開発につながり、向精神薬の研究は無力化剤BZの兵器化をもたらした。毒素においても、ボツリヌス毒素やSEBなど神経系を標的とするものが研究・開発された。この歴史は、平和目的の民間研究が常に軍事転用のリスクをはらんでいる「デュアルユース」の典型である。
第2章 脳の構造と機能
脳と神経系の基本的な仕組みを解説する。中枢神経系と末梢神経系、神経伝達の化学的・電気的メカニズム、そして特定の行動を制御する「神経回路」の概念を説明する。特に、覚醒と注意を司る「青斑核ノルアドレナリン系」や、睡眠覚醒を調節する「オレキシン系」など、行動操作の潜在的標的となる神経回路について詳述し、現代神経科学が目指す「神経回路の機制的理解」の意味を明らかにする。
第3章 CBW不拡散体制
化学・生物兵器の使用と開発を禁止する国際条約、1925年ジュネーブ議定書、生物・毒素兵器禁止条約(BTWC)、化学兵器禁止条約(CWC)の成立過程と概要を説明する。BTWCとCWCに共通する「一般目的規定」は、物質の性質ではなく「目的」によって平和利用か敵対的利用かを区別する重要な原則である。しかし、条約には検証体制の不備や執行機関の脆弱性などの課題が残る。
第4章 デュアルユースの課題
「デュアルユースのジレンマ」とは、研究の成果が善意で利用される一方で、悪意ある者によって兵器開発など有害目的に転用される可能性を指す。2000年代のマウスポックスウイルス実験やH5N1鳥インフルエンザの「機能獲得実験」を例に、この問題が微生物学だけでなく神経科学にも広く関連することを示す。科学者コミュニティがこのリスクを認識し、研究の計画段階から社会的責任を考慮することが必要である。
第二部 現在:現代の神経科学
第5章 現代の民間神経科学
米国とEUが巨額を投じている大規模脳研究プロジェクト(米国「BRAINイニシアチブ」、EU「ヒューマンブレインプロジェクト」)の目的と内容を分析する。これらのプロジェクトは、脳の神経回路の活動をマッピングし、その機能を機制的に理解することを目指している。この理解は、精神疾患の治療に役立つ一方で、神経回路を操作する新技術の開発につながり、悪用の危険性をはらむ。著者はこう述べる。「BRAINイニシアチブの中間報告書には、その成果が敵対的に悪用される可能性についての言及は一切見当たらなかった。」
第6章 新型神経兵器
神経科学の進歩がもたらす新たな安全保障上の脅威について、米国を中心とした近年の公式・学術報告書をレビューする。特に、軍や治安機関による「無力化化学剤」への関心が高まっている。オピオイド(フェンタニル類)、ベンゾジアゼピン系、α2アドレナリン受容体作動薬などが候補として研究され、2002年モスクワ劇場占拠事件では実際にオピオイド系薬剤が使用された(多数の死者を出した)。「性能低下市場」が形成され、対策と新兵器開発のいたちごっこが起きる危険性が指摘されている。
第7章 神経科学の進展がもたらすもの
神経科学の将来の可能性を探るために、自然界にすでに存在する「宿主の神経系を操作する寄生虫」の研究(神経寄生学)を考察する。例えば、トキソプラズマは齧歯類の脳に寄生し、猫の尿への恐怖を消失させ捕食されやすくする。このような複雑な行動操作が、神経伝達物質(ドーパミン)のレベルを変えるなど、分子レベルで実現されている。このことは、将来的に人間の特定の行動や情動を化学的・生物学的に操作する技術が成立しうることを示唆している。
第8章 無力化剤の探索
現在、兵器として関心が持たれる「無力化化学剤」の種類とその作用機序を詳述する。代表的なものとして、鎮静作用を持つオピオイド系、ベンゾジアゼピン系、α2アドレナリン受容体作動薬(デクスメデトミジン)、そして睡眠覚醒を制御するオレキシン(ヒポクレチン)神経ペプチド系がある。オレキシン受容体拮抗薬は不眠症治療薬として開発中だが、急速な睡眠誘導剤として悪用される可能性がある。鼻腔内投与やナノ粒子を用いた標的送達技術の進歩が、こうした薬剤の兵器としての実用性を高めている。
第9章 バイオレギュレーターと毒素
「毒素」と「バイオレギュレーター」の中間的な性質を持つ「ミッドスペクトル剤」に焦点を当てる。サブスタンスPは気管支収縮を引き起こし、オキシトシンは信頼や社会的行動に影響を与える。米国国防高等研究計画局(DARPA)は、物語が行動に与える影響(ナラティブ・ネットワーク)とオキシトシンなどの神経化学物質との関係を研究するプロジェクトを資金援助している。このような、行動や認知に影響を与える物質の研究は、国家の安全保障・情報機関の関心を集めており、BTWCおよびCWCの規制対象としての検討が急務である。
第三部 未来
第10章 科学技術の変化に直面するBTWCとCWC
BTWCとCWCは、科学技術の進歩をレビューする仕組み(5年ごとの検討会議、科学諮問委員会など)を持っているが、その対応は十分ではない。BTWCの「年次会合プロセス」は議題が多すぎて実質的な進展が難しく、CWCも「その他の化学物質生産施設」の検証範囲や「法執行目的」の解釈をめぐる問題で膠着状態にある。神経科学の進歩のような新たな課題に対して、条約を適応させていく政治的意志と実効性のある対話の場が不足している。
第11章 我々はどこに向かっているのか?
OPCW科学諮問委員会の報告書は、現時点では生物学的プロセスを用いた毒素やペプチドの大量生産・悪用の脅威は低いと評価しているが、「現在のところ」という留保をつけている。一方で、脳深部刺激療法などの神経調節技術は、精神疾患治療としてDARPAの資金援助を受けて急速に発展している。著者はこう述べる。「脳科学研究の相当部分が軍事的な目的に直接的・間接的に費やされているという事実は、その潜在的な軍事転用の可能性について、常に念頭に置いておくべきである。」
第12章 デュアルユース神経科学のガバナンス
神経科学の悪用を防ぐための将来のガバナンスを論じる。鍵となるのは、科学者コミュニティ自身の意識改革と教育である。米国では、政府資金を受ける研究機関に対し、「懸念のあるデュアルユース研究」の監視体制と研究者教育を義務付ける政策が始まっている。国際的には、BTWCとCWCの強化が不可欠だが、2016年のBTWC第8回検討会議に向けて、より効率的で実践的な「年次会合プロセス」への改革が求められている。未来は決まっておらず、科学者が積極的に社会的責任を果たし、研究の悪用を防ぐための国際的な枠組み作りに参加することが、最悪のシナリオを回避する唯一の道であると結論づける。
続きのパスワード記載ページ(note.com)はこちら
注:noteの有料会員のみ閲覧できます。
メンバー特別記事
脳を操る兵器:神経科学者が知らない軍事転用の現実 AI考察
by Claude 4.5
民生技術が兵器になる歴史的必然性
この書籍が提示する最も本質的な問いは、神経科学の進歩が「必然的に」兵器開発に転用されるのか、それとも私たちはその運命を回避できるのか、という点にある。著者マルコム・ダンドーは、過去100年の歴史を振り返り、化学・生物学の進歩が一貫して兵器開発に応用されてきた事実を示す。
アセチルコリンという神経伝達物質の発見は、本来は脳の働きを理解するための純粋な科学的探求だった。しかし、この発見はすぐに農薬開発に応用され、そしてその知識は神経ガス兵器の開発へと転用された。サリン、ソマン、VXといった致死的な神経剤は、すべて民間の農薬研究から派生したものだ。
興味深いのは、BZ(3-キヌクリジニルベンジレート)のような無力化剤の開発経緯である。これは元々、胃腸疾患の治療薬として研究されていた。しかし、試験中に被験者が混乱や幻覚を経験したという報告を受けて、すぐに米軍に引き渡され、無力化剤として兵器化された。
この「民生から軍事へ」という流れは、まるで重力のように避けられないものなのだろうか。歴史を見る限り、そう思えてしまう。しかし、ダンドーは明確に述べる──これは「必然」ではなく、私たちの「選択」だと。
2002年モスクワ劇場事件が明かした現実
理論的な懸念ではなく、現実の事件として、2002年のモスクワ劇場人質事件は極めて重要な意味を持つ。ロシア特殊部隊は、チェチェン武装勢力が占拠した劇場に「フェンタニル誘導体」のエアロゾルを投入した。
この作戦の詳細を見ると、無力化化学剤の現実的な問題点が浮き彫りになる。英国ポートンダウンの研究所による分析では、使用されたのは「カルフェンタニル」と「レミフェンタニル」の混合物だった。カルフェンタニルはフェンタニルの100倍、モルヒネの10,000倍の効力を持つ。通常は大型野生動物を無力化するためにのみ使用される。
結果は悲惨だった。800人の人質のうち127人(16%)が死亡し、650人以上が入院を要した。ロシアの保健大臣は「このガスそれ自体は致死的とは言えない」と述べたが、現実は異なる。なぜか。
問題は、個人差にある。年齢、健康状態、体重によって、同じ濃度のエアロゾルでも効果は大きく異なる。さらに、オピオイドは鎮静作用と同時に呼吸抑制を引き起こす。両者は同じμ-オピオイド受容体を介して作用するため、分離できない。つまり、眠らせるには十分だが殺さない「安全な濃度」など、実戦では存在しないのだ。
しかし、この事件後も無力化剤の研究は続いている。それどころか、研究者たちは「呼吸抑制を起こさずに鎮静効果だけを得る方法」を探している。セロトニンアゴニストやアンパカインなどの新しい薬剤が研究されており、これらは呼吸中枢を刺激してオピオイドの呼吸抑制効果を打ち消す可能性がある。
もしこれが成功したら何が起こるか。より「安全な」無力化剤が開発され、その使用のハードルが下がる。そして化学兵器禁止条約(CWC)の解釈をめぐる議論が再燃する。
オレキシンの発見が開いた新しい扉
1998年、二つの独立した研究グループが「オレキシン」という神経ペプチドとその受容体を発見した。これは睡眠・覚醒サイクルの制御に中心的な役割を果たしていることが、驚くべき速さで明らかになった。
ナルコレプシー(過眠症)は、オレキシン産生ニューロンの喪失によって引き起こされる。患者は日中に突然眠りに落ち、カタプレキシー(突然の筋緊張喪失)、入眠時幻覚、睡眠麻痺などを経験する。
この発見は、製薬企業に不眠症治療の新しい道を開いた。オレキシン受容体拮抗薬の開発競争が始まった。特に興味深いのは、OX2R受容体が睡眠・覚醒サイクルに主に関与していることが判明し、より特異的な薬剤の開発が可能になったことだ。
JNJ1037049という化学物質は、OX2R受容体を特異的に標的とし、「堅牢な催眠効果」を示した。これは医療にとっては素晴らしい進歩だ。しかし、同時に何を意味するか。
オレキシンニューロンは、青斑核(LC)のノルアドレナリン産生ニューロンなど、脳内の複数のモノアミン系を直接標的としている。光遺伝学を用いた最新の研究では、オレキシンニューロンを刺激すると10〜30秒で睡眠から覚醒への移行が起こるが、LC ニューロンを刺激すると5秒未満で移行することが示された。
つまり、オレキシン系は、脳の覚醒状態を統合的に制御する「マスタースイッチ」のような役割を果たしている。そして、このスイッチを薬理学的に操作する技術が急速に発展している。
さらに懸念すべきは、オレキシンの鼻腔内投与の成功例が複数報告されていることだ。血液脳関門を迂回して、嗅神経を通じて直接脳に薬剤を届ける技術だ。これは大きな分子や荷電分子でも機能する。
寄生虫が教える行動操作の青写真
最も不気味な章の一つは、寄生虫が宿主の行動を操作するメカニズムについての考察だ。これは、将来的に人間の行動を操作する可能性を示唆する、自然界の「概念実証」とも言える。
宝石バチ(Ampulex compressa)とゴキブリの関係は特に詳細に研究されている。このハチは、ゴキブリに二度刺す。一度目の刺しで前脚を一時的に麻痺させ、二度目の刺しで脳の特定の神経節に毒を注入する。
二度目の刺しの効果は驚くべきものだ。ゴキブリは約30分間グルーミング行動を示した後、長期的な「低運動状態」に入る。歩行開始の閾値が8倍以上に上昇する。つまり、歩行のための神経回路自体は無傷だが、その回路を起動する「やる気」が失われるのだ。
研究により、この毒は「ドーパミン」と「オクトパミン」(昆虫における ノルアドレナリンの類似物)などのモノアミン系に作用することが示唆されている。哺乳類においても、これらのモノアミン系は動機付け、覚醒、運動に深く関与している。
さらに興味深いのは、トキソプラズマ(Toxoplasma gondii)と齧歯類の関係だ。この寄生虫に感染したラットは、猫の尿の臭いに対する恐怖を失い、むしろ魅力を感じるようになる。これは寄生虫が最終宿主である猫に戻るための巧妙な戦略だ。
感染したラットの脳では、ドーパミンレベルの上昇が確認されている。トキソプラズマは、ドーパミン合成の律速酵素であるチロシン水酸化酵素に類似したタンパク質を産生する。つまり、寄生虫が直接的に宿主の神経化学を改変しているのだ。
人間にとっての含意は何か。世界人口の約3分の1がトキソプラズマに感染していると推定される。感染者は反応時間の遅延(交通事故リスクの上昇と相関)を示し、統合失調症などの精神疾患との関連も示唆されている。
これらの発見が示すのは、特定の神経回路を標的とした化学的介入により、複雑な行動パターンを操作できる可能性だ。進化は何億年もかけてこれらのメカニズムを洗練させてきた。人間の技術が同じ目標に向かえば、はるかに短い時間で同様の、あるいはより洗練された操作手段を開発できるかもしれない。
オキシトシン研究とDARPAの関心
オキシトシンは「愛情ホルモン」や「信頼ホルモン」として知られているが、その機能は遥かに複雑だ。オキシトシンとバソプレシンは、わずか2つのアミノ酸の違いしかない9個のペプチドから成る分子だが、哺乳類の社会的行動に中心的な役割を果たす。
2013年、米国防高等研究計画局(DARPA)は、「オキシトシン:測定感度と特異性の改善」という公募を出した。その中で、DARPAは率直に述べている:
「オキシトシンは国家安全保障に関連する行動にも影響を与える。オキシトシンは、二人の個人が互いを信頼するかどうか、ストレスへの反応の仕方、さらには創傷治癒にまで影響を及ぼす可能性がある。」
そして、この公募は「Narrative Networks(物語ネットワーク)」プログラムとの関連を明示している。このプログラムの目的は何か。DARPAの説明によれば:
「物語は人間の思考と行動に強力な影響を及ぼす。物語は記憶を統合し、感情を形成し、判断におけるヒューリスティックスとバイアスを誘発し、内集団・外集団の区別に影響を与え、個人のアイデンティティの基本的内容にさえ影響を与える可能性がある。」
つまり、DARPAは「物語が人々の行動をどのように変えるか」を理解し、その神経生物学的基盤を解明しようとしている。そして、オキシトシンなどの神経化学物質がこのプロセスでどのような役割を果たすかを知りたがっている。
技術領域2(神経生物学)の主要目標は:
- 物語が特定の神経伝達物質やホルモンの産生を調整するかどうかを判定する
- 物語の影響下で、オキシトシンやセロトニンなどの行動的に重要な神経伝達物質の産生と取り込みがどのように影響を受けるかを判定する
- 物語の影響によって調整される新規の神経伝達物質や他の生物学的に活性な分子を特定する
これは「敵対的物語に対抗する」という防御的目的で説明されているが、同じ知識は攻撃的にも使用できる。ある集団の行動を特定の方向に操作したい場合、適切な「物語」と適切な「神経化学的プライミング」を組み合わせれば、より効果的かもしれない。
ナノテクノロジーがもたらす配送革命
無力化剤の開発における最大の障壁の一つは、血液脳関門(BBB)だった。多くの神経活性化合物は脳に到達できない。しかし、二つの技術的進歩がこの障壁を克服しつつある。
第一に、鼻腔内投与経路の開発だ。オキシトシン、オレキシンなど、通常は血液脳関門を通過できない大きな分子でも、嗅神経を通じて直接脳に到達できることが示されている。
第二に、ナノテクノロジーだ。CWCの科学諮問委員会の一時作業部会は、2014年の報告書で次のように述べている:
「ナノキャリアベースの送達システムは、従来のものに比べていくつかの利点を提供する:溶解性の問題の克服、外部環境からの薬剤の保護、放出プロフィールの制御。」
さらに:
「ナノキャリアベースの送達システムは、作用部位でのより正確で制御された標的化を可能にし、非標的組織の曝露時間を減少させる。」
つまり、ナノ粒子は:
- 薬剤を安定化させ、エアロゾル中での分解を防ぐ
- 血液脳関門を通過させる
- 脳内の特定の細胞タイプを標的とする
- 制御された放出プロフィールを提供する
これらの技術は、もちろん医療目的で開発されている。脳腫瘍の治療、神経変性疾患の治療などだ。しかし、同じ技術が兵器開発にも応用できる。
特に懸念されるのは、抗体や他の標的化分子をナノ粒子の表面に付着させることで、特定の細胞タイプを標的にできることだ。米国BRAIN Initiativeの中間報告書は、「特定の細胞タイプに遺伝子、タンパク質、化学物質を標的化する方法の完全な説明は非常に望ましい」と述べている。
条約体制の構造的欠陥
生物兵器禁止条約(BTWC)と化学兵器禁止条約(CWC)は、理論的には神経科学の悪用を防ぐはずだ。両条約とも「一般目的基準」を持ち、すべての生物剤・毒素(BTWC)、すべての化学物質(CWC)を非平和的目的での使用を禁止している。
しかし、実際には両条約とも科学技術の急速な進歩に対応できていない。
BTWCの問題点:
- 検証システムの欠如:1990年代に検証議定書の交渉が行われたが、2001年に崩壊した
- 常設機関の脆弱性:2006年まで常設機関すら存在せず、現在でもスタッフは10人未満
- 科学技術レビューの不十分さ:5年ごとのレビュー会議で科学技術の変化を検討することになっているが、実質的な議論や決定はほとんど行われていない
- 教育・啓発の欠如:生命科学者の大多数がBTWCの存在すら知らない
CWCの問題点:
- 第II条9項(d)の曖昧さ:「国内暴動鎮圧を含む法執行目的」という例外規定の解釈をめぐる論争。これが無力化剤開発の「抜け穴」になる可能性
- OCPF(その他の化学生産施設)の検証不足:生物学的プロセスによる化学物質生産施設を検証システムに含めるかどうかで20年以上議論が続いている
- 締約国の消極的姿勢:多くの締約国が、無力化剤の研究開発を明確に禁止することに消極的
2012〜2014年のBTWC会合を見ると、この機能不全が明確だ。2011年の第7回運用検討会議で、科学技術レビューのための「常設議題項目」が設置された。しかし、その議題は以下のように広範すぎた:
- 条約に反する用途の可能性を持つ新しい科学技術の発展
- 高速シーケンシング、DNA合成、バイオインフォマティクス、システム生物学などの実現技術の進歩
- 責任ある行動を奨励するための自主的行動規範
- 生命科学とバイオテクノロジーのリスクと利益に関する教育と啓発
- その他の関連する科学技術の発展
これらすべてを、年に1週間の専門家会合と1週間の締約国会合で議論することになっている。結果は予想通りだった。南アフリカは2012年の会合後に、科学技術に関する実質的な議論がほとんど行われなかったと指摘した。
科学者コミュニティの無関心
最も憂慮すべき事実の一つは、神経科学者自身がこの問題をほとんど認識していないことだ。
米国BRAIN Initiativeの中間報告(2013年)と最終報告(2014年)は、神経回路の理解と操作に年間4〜5億ドルの投資を提案している。報告書は明確に述べている:
「最も重要な成果は、BRAIN Initiativeの下で開発された新技術と概念的構造の相乗的応用から生まれる、精神機能の包括的なメカニズム的理解である。」
つまり、脳を「機械的に理解し、操作する」ことが目標だ。しかし、報告書のどこにも、デュアルユース(二重用途)の問題や、化学・生物兵器への悪用の可能性についての言及はない。
EU Human Brain Projectにも同様の問題がある。倫理的考察のセクションはあるが、BTWCやCWCへの言及はない。唯一、ニューロモルフィック・ニューロロボティクス技術の軍事利用(ドローンなど)については触れているが、化学・生物兵器については沈黙している。
2004年のFink委員会報告(米国科学アカデミー)は、デュアルユース問題への対処の第一の推奨事項として、「科学者コミュニティへの教育」を挙げた。しかし、10年後の2014年、状況はほとんど変わっていない。
教育の欠如は偶然ではない。ブライアン・ラッパートと著者が16カ国で生命科学者に聞き取り調査を行ったところ、BTWCやCWCの存在を知っている科学者はほとんどいなかった。大学のカリキュラムにバイオセキュリティやデュアルユースの問題が含まれることはまれだった。
誤認の危険性:軍拡競争の引き金
デュアルユース研究のもう一つの危険は、善意の研究が他国に誤解され、軍拡競争を引き起こす可能性だ。
2008年の米国科学アカデミー報告書「Emerging Cognitive Neuroscience and Related Technologies」は、「劣化市場」(degradation market)の概念を提示した:
- ステージ1:ある国が認知兵器を開発するかもしれないという恐れが、対抗措置の開発を正当化する
- ステージ2:対抗措置をテストするために、実際の認知兵器を開発する必要がある
- ステージ3:効果的な劣化製品が開発されると、この市場の拡大は自己実現的になる
- ステージ4:拷問の概念もこの市場の製品によって変容する可能性がある
この悪循環は、透明性の欠如と不信によって加速される。例えば:
- ロシアは2002年のモスクワ劇場事件でフェンタニル誘導体を使用した実績がある
- 中国企業はBBQ-901という麻酔銃システムを広告している(40メートルの射程)
- インドでは2010年に防衛科学者が無力化剤の開発で賞を受賞した
- イランでは、革命防衛隊が管理する大学でメデトミジンのエアロゾル化研究が行われた
- 欧州のある国では、軍と関連したプログラムで無力化剤の集中的な研究が行われた
これらの研究が、実際には防御目的や獣医学目的であったとしても、他国からは攻撃的プログラムと誤解される可能性がある。そして誤解が対抗措置を生み、対抗措置がさらなる研究を生む。
第一次世界大戦前、英国とその同盟国はドイツに効果的な生物兵器プログラムがあると信じ、報復能力を開発した。実際にはドイツに大規模な生物兵器プログラムはなかった。しかし、ドイツは新しい神経剤(サリン、ソマンなど)を開発しており、連合国はそれを全く知らなかった。
日本の文脈で考える
日本にとって、この問題は特に重要な意味を持つ。
1995年のオウム真理教によるサリン攻撃は、非国家主体による化学兵器使用の現実を世界に示した。この事件は、CWCの交渉を加速させる一因となった。日本は化学兵器テロリズムの実体験を持つ数少ない国の一つだ。
同時に、日本は神経科学研究の最前線にいる。理化学研究所などの機関は、世界トップレベルの脳研究を行っている。光遺伝学、オプトジェネティクス、脳イメージングなど、最新の技術を駆使している。
しかし、日本の神経科学者は、自分たちの研究のデュアルユース性をどの程度認識しているだろうか。大学のカリキュラムにバイオセキュリティは含まれているだろうか。おそらく、他の国々と同様、ほとんど含まれていない。
日本の研究倫理教育は、主に研究不正(捏造、改ざん、盗用)と人間を対象とする研究の倫理に焦点を当てている。バイオセキュリティやデュアルユースは、せいぜい付け足し程度だ。
また、日本の安全保障政策の変化も考慮する必要がある。集団的自衛権の解釈変更、防衛費の増加傾向。これらが、防衛研究への圧力を高める可能性がある。
日本学術会議は、2017年に「軍事的安全保障研究に関する声明」を発表し、軍事研究への慎重な姿勢を示した。しかし、神経科学のデュアルユース問題は、必ずしも「軍事研究」という明確なラベルを持たない。DARPA資金であっても、「PTSD治療」や「ナルコレプシー治療」という医療目的を掲げることができる。
制御可能性への疑問
技術決定論に陥るべきではない。しかし、楽観論も危険だ。
CWCの科学諮問委員会の一時作業部会は、2014年の報告書で比較的楽観的な評価を示した:
「毒素:現在のところ、この技術の悪用の脅威は低いと考えられる」 「バイオレギュレーター:ペプチドの無力化剤としての潜在性は、一部の論者によって過大評価されている可能性がある。この技術の悪用の脅威は現在のところ低いと考えられる」
しかし、これらの結論には「現在のところ」という重要な修飾語がついている。そして、報告書自体が、ナノテクノロジーによる送達システムの進歩、ペプチドの代謝安定性の向上、血液脳関門透過技術の発展など、状況を変える可能性のある技術的進歩を詳述している。
歴史が示すのは、「技術的に不可能」と思われていたことが、驚くべき速さで「可能」になることだ。1990年代には、毒素の大量化学合成は非現実的と考えられていた。しかし、ペプチド合成技術の進歩により、多くの毒素が今や化学的に合成可能だ。
遺伝子編集技術CRISPRの登場は、わずか10年で生物学研究を一変させた。誰が2005年に、2015年には学部生でも遺伝子編集ができるようになると予測しただろうか。
神経科学も同様だ。オレキシンの発見(1998年)から、特異的受容体拮抗薬の開発(2000年代後半)、臨床試験(2010年代)まで、わずか15年だ。
統治の空白
最も深刻な問題は、科学技術の進歩の速度と、国際統治メカニズムの進化速度との間の致命的な不均衡だ。
BTWCの科学技術レビューは、5年ごとのレビュー会議が主な手段だ。しかし、神経科学は5年で革命的に変化する。オプトジェネティクス、CLARITY、拡大顕微鏡、ミニスコープ、高密度電極アレイ──これらすべてが過去10年間に登場した。
CWCには科学諮問委員会があり、より機動的だ。しかし、諮問するだけで、決定権はない。締約国会議は政治的考慮に支配され、科学的緊急性に応答する能力は限られている。
2014年10月、米国政府は機能獲得(gain-of-function)研究への新規資金提供を一時停止した。これは、CDC、FDA、NIHでの相次ぐバイオセーフティ違反を受けてのことだ。しかし、これは米国内の措置だ。他国は追随しなかった。
国際的な合意形成は、さらに困難だ。2013〜2014年のBTWC会合では、科学技術レビューの体系的な改善についての提案が多数出されたが、実現しなかった。各国の優先順位が異なり、検証をめぐる古い対立が影を落とし、科学的議論は政治的思惑に埋もれた。
希望の萌芽?
完全に悲観的である必要はない。いくつかの前向きな動きもある。
米国は2014年に、デュアルユース研究への制度的監視を義務付ける政策を発表した。研究機関は、指定された15の病原体・毒素を扱う研究について、政府資金の有無にかかわらず、監視することが求められる。教育・訓練も義務化された。
ドイツ倫理評議会は2014年に包括的な報告書を発表し、第一の推奨事項として「生命科学コミュニティにおける責任の文化の促進」を挙げた。
科学者主導の取り組みもある。Curtis Bellらは、神経科学者のための「誓約」(pledge)の創設を提案した。これは医師のヒポクラテスの誓いに類似したものだ。
しかし、これらは断片的で、自主的で、国際的調整を欠いている。必要なのは、以下のような包括的アプローチだ:
- 教育の制度化:すべての神経科学(および関連分野)の学生に、バイオセキュリティとデュアルユースについての必修教育を
- 研究監視の国際化:米国型のDURC監視を、他の主要研究国も採用する
- 科学者の組織的関与:神経科学会などの専門組織が、積極的にこの問題に取り組む
- 条約メカニズムの強化:BTWCに常設の科学技術パネルを設置する。CWCの科学諮問委員会に、より大きな権限と資源を
- 透明性の向上:軍事関連の神経科学研究について、より大きな透明性を(機密を損なわない範囲で)
- 倫理審査の拡大:研究倫理委員会が、デュアルユースの側面も審査する
しかし、これらすべてに共通する前提条件がある。それは、科学者と政策立案者が、この問題の緊急性を認識することだ。
時間との競争
ダンドーが引用するマシュー・メセルソンの言葉は、核心を突いている:
「バイオテクノロジーは、大量破壊能力を多数の手に委ねる可能性を持つ。我々が何者であり、我々自身をどう見るかの深部に到達する可能性を持つ。」
神経科学は、この予言の最も深刻な実現形態かもしれない。なぜなら、それは文字通り「我々が何者であるか」──我々の思考、感情、意思決定、社会的行動──を操作する技術だからだ。
楽観的シナリオでは、今後20〜30年で、統合失調症、うつ病、PTSD、アルツハイマー病などの治療法が大きく進歩する。脳損傷からの回復が改善する。Brain-computer interfaceが障害者の生活を変える。
悲観的シナリオでは、同じ技術が、ますます混沌とした国際環境の中で、「wars amongst the people」(人々の間の戦争)において、無力化兵器、行動操作兵器として展開される。テロリストがこれらの技術にアクセスする。独裁政権が反体制派の鎮圧に使用する。
どちらのシナリオが実現するかは、まだ決まっていない。しかし、時間は限られている。技術は「法律、倫理、統治構造が追いつくのを待ってはくれない」。
そして、日本の神経科学者にも、この問題への真剣な関与が求められている。オウム真理教のサリン事件を経験した国として、化学・生物兵器の恐怖を知る国として、日本は国際的な議論でユニークな視点を提供できる立場にある。
しかし、そのためには、まず国内で議論を始める必要がある。大学で、学会で、政策フォーラムで。沈黙は選択肢ではない。なぜなら、沈黙は、デフォルトで悲観的シナリオへの道を開くことになるからだ。