Medical Apartheid: The Dark History of Medical Experimentation on Black Americans from Colonial Times to the Present
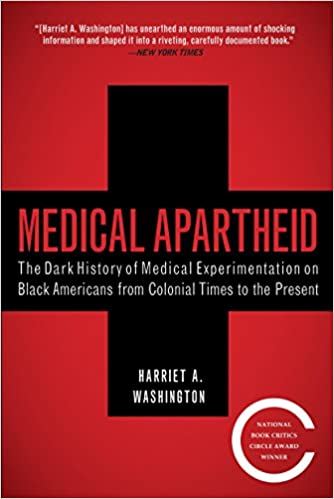
英語タイトル:『Medical Apartheid:The Dark History of Medical Experimentation on Black Americans from Colonial Times to the Present』Harriet A. Washington 2006
日本語タイトル:『メディカル・アパルトヘイト:植民地時代から現代までの黒人アメリカ人に対する医学実験の暗黒史』ハリエット・A・ワシントン 2006年
目次
- 第一部 憂慮すべき伝統 / A Troubling Tradition
- 第1章 南部の苦痛:プランテーションにおける医療的搾取 / Southern Discomfort:Medical Exploitation on the Plantation
- 第2章 利益をもたらす驚異:奴隷と解放奴隷を使った南北戦争前の医学実験 / Profitable Wonders:Antebellum Medical Experimentation with Slaves and Freedmen
- 第3章 サーカス・アフリカヌス:黒人身体の大衆的展示 / Circus Africanus:The Popular Display of Black Bodies
- 第4章 外科劇場:南北戦争前の診療所における黒人身体 / The Surgical Theater:Black Bodies in the Antebellum Clinic
- 第5章 安らかならぬ死体:解剖学的解剖と展示 / The Restless Dead:Anatomical Dissection and Display
- 第6章 診断:自由:南北戦争、解放、世紀末の医学研究 / Diagnosis:Freedom:The Civil War, Emancipation, and Fin de Siècle Medical Research
- 第7章 「悪名高い梅毒漬けの人種」:タスキギーで本当は何が起きたのか? / “A Notoriously Syphilis-Soaked Race”:What Really Happened at Tuskegee?
- 第二部 お決まりの被験者 / The Usual Subjects
- 第8章 黒いコウノトリ:アフリカ系アメリカ人の生殖をめぐる優生学的管理 / The Black Stork:The Eugenic Control of African American Reproduction
- 第9章 核の冬:アフリカ系アメリカ人に対する放射線実験 / Nuclear Winter:Radiation Experiments on African Americans
- 第10章 檻の中の被験者:黒人受刑者を対象とした研究 / Caged Subjects:Research on Black Prisoners
- 第11章 子供たちの十字軍:若いアフリカ系アメリカ人を標的にした研究 / The Children’s Crusade:Research Targets Young African Americans
- 第三部 人種、技術、医学 / Race, Technology, and Medicine
- 第12章 遺伝的破滅:分子的偏見の台頭 / Genetic Perdition:The Rise of Molecular Bias
- 第13章 感染と不平等:犯罪としての病 / Infection and Inequity:Illness as Crime
- 第14章 機械の時代:外科技術へのアフリカ系アメリカ人の犠牲 / The Machine Age:African American Martyrs to Surgical Technology
- 第15章 異常な戦争:黒人を標的とするアメリカの生物テロリズム / Aberrant Wars:American Bioterrorism Targets Blacks
- エピローグ:今日の黒人を対象とした医学研究 / Epilogue:Medical Research with Blacks Today
本書の概要
短い解説:
本書は、植民地時代から現代に至るまで、アフリカ系アメリカ人を対象に行われてきた組織的かつ倫理的に問題のある医学実験と医療行為の歴史を、膨大な一次資料に基づいて体系的に暴露した記録である。医療従事者、歴史学者、社会正義に関心を持つ一般読者に向けて、アメリカ医学の光と影、特に「影」の部分を浮き彫りにすることを目的としている。
著者について:
著者ハリエット・A・ワシントンは、医療倫理と科学史を専門とするジャーナリスト・研究者であり、アフリカ系アメリカ人の医療における不正義の問題に長年取り組んできた。本書では、従来の医学史の叙述からは抜け落ちてきた「人種」という要素に焦点を当て、医療が時に「管理」や「抑圧」の装置として機能してきたことを、冷静かつ詳細な筆致で検証する。その視点は、被害者の声と加害者の記録を往還し、構造的な暴力の実態を明らかにする。
テーマ解説:
- 主要テーマ:医療における人種的隔離と支配の歴史:奴隷制時代の身体の商品化から現代のバイオテクノロジーに至るまで、医学が「科学的」権威を借りて黒人身体を支配・利用してきた連続性を描く。
- 新規性:通史的な視座と「メディカル・アパルトヘイト」概念の提示:個別のスキャンダル(タスキギー研究など)を超え、400年にわたる歴史的連続性を実証し、それを「メディカル・アパルトヘイト」という概念で総称する。
- 興味深い知見:同意の虚構と構造的脆弱性の利用:法的・社会的に脆弱な立場に置かれた黒人コミュニティ(奴隷、囚人、貧困層、子どもなど)が、一貫して「都合の良い被験者」とされ、インフォームド・コンセントの原則が空洞化されてきた過程を暴く。
キーワード解説:
- メディカル・アパルトヘイト:人種に基づく医療資源や倫理的保護の体系的かつ意図的な隔離と差別。単なる偏見ではなく、制度的に組み込まれた構造的問題を指す。
- 身体の所有権と自律性の剥奪:奴隷制下では法的に、その後は社会的・経済的圧力によって、黒人が自己の身体に関する決定権を奪われ、医学的対象とされた歴史。
- 科学的人種主義:医学や科学の装いを借りて、黒人を生物学的・道徳的に劣った存在として定義・固定化し、その支配や実験を正当化してきたイデオロギー。
3分要約
本書『メディカル・アパルトヘイト』は、アメリカ医学の輝かしい進歩の陰で、アフリカ系アメリカ人が体系的に実験対象とされ、その身体と生命が搾取されてきた長く暗い歴史を、植民地時代から21世紀初頭まで通覧するものである。
著者は、この歴史を単なる過去の過ちの寄せ集めではなく、「メディカル・アパルトヘイト」という概念で捉える。これは、医療の場において人種に基づく隔離と差別が制度的に実施され、黒人の身体が同意なく、あるいは欺瞞的に、医学的探求や技術開発のための資源とみなされてきた状態を指す。
第一部では、奴隷制時代に起源を辿る。プランテーションでは奴隷の身体は経済的資産として管理され、医師はその価値を維持・向上させる「修理人」として機能した。奴隷所有者と医師は協力して、手術法の開発や治療法の実験を奴隷に対して行い、彼らには身体的苦痛に対する補償も自律性も与えられなかった。さらには、見世物や医学展示会での生身の展示、そして死後は解剖学教室への屍体の供給源として、黒人身体は商品化の対象となった。南北戦争と解放は法的地位を変えたが、医学的対象としての扱いを終わらせはしなかった。
第二部は、20世紀における「お決まりの被験者」としての黒人に焦点を当てる。優生学政策の下で黒人女性の不妊化手術が推進され、冷戦期には囚人や患者を対象とした危険な放射線実験が実施された。刑務所は安価で管理しやすい被験者を供給する場となり、子どもたちさえも、精神病院や施設で治験や実験の対象とされた。悪名高いタスキギー梅毒研究は、このような構造のほんの一例に過ぎず、公的医療機関が貧しい黒人男性を治療しないまま観察し続けたという事件であった。
第三部では、現代のより洗練された形態の「メディカル・アパルトヘイト」を分析する。遺伝子研究の進展は、黒人を特定の疾患に「遺伝的に predisposed(なりやすい)」とする新たな生物学的決定論の台頭を招きかねない。感染症対策はしばしば犯罪対策と結びつき、黒人コミュニティが監視と隔離の対象とされる。先端医療技術(心臓手術、臓器移植など)の開発過程でも、黒人は不適切な臨床試験の犠牲者となった。さらに、アメリカ政府が国内の黒人コミュニティを標的に生物剤の試験を行ったという、国家的規模の生物テロの歴史すら存在する。
エピローグでは、この歴史が単なる過去のものではなく、医療格差や臨床試験における倫理的問題、そして黒人コミュニティの医療不信として現在も続いていることを指摘する。真の変化のためには、この暗い歴史を直視し、医療倫理の原則が人種に関わりなく全ての人に平等に適用される制度的保障が不可欠であると結論づける。本書は、医学の進歩が誰の犠牲の上に成り立ってきたのかを問い直す、重くしかし不可欠な記録なのである。
各章の要約
第一部 憂慮すべき伝統
第1章 南部の苦痛:プランテーションにおける医療的搾取
奴隷制時代、黒人奴隷の身体は労働力であると同時に、所有者の経済的資産であった。医師はこの資産の「管理」と「修復」を請け負い、奴隷の健康維持は道徳的配慮ではなく経済的関心に基づいていた。病気や怪我は財産価値の減損を意味したため、医師はしばしば奴隷所有者と緊密に連携し、治療法や手術法の実験を奴隷に対して実施した。これらの医療行為には、奴隷自身の同意はほとんど考慮されず、彼らの苦痛は記録されることも補償されることも稀だった。ここに、黒人身体を自律的な個人としてではなく、医学的介入の対象とみなす伝統の起源が見出される。
第2章 利益をもたらす驚異:奴隷と解放奴隷を使った南北戦争前の医学実験
19世紀、アメリカ南部の医師たちは医学的地位の向上と経済的成功を求めて競い合い、奴隷を理想的な「臨床材料」として利用した。麻酔が発明される以前や普及初期において、多くの外科的処置や手術の開発・練習は黒人奴隷の身体で行われた。著名な医師J・マリオン・シムズも、何人もの黒人女性奴隷を被験者として、麻酔なしで繰り返し手術を行い、産科瘻管修復術を「完成」させた。奴隷は移動できず、また所有者の許可さえ得れば抵抗できない存在だった。解放後も、貧しく脆弱な立場の黒人は同様に実験対象とされた。この時代、医学的進歩と黒人身体の搾取は不可分に結びついていた。
第3章 サーカス・アフリカヌス:黒人身体の大衆的展示
医学的搾取と並行して、黒人身体は見世物として大衆の好奇心と人種的偏見の的となった。サーカスや見世物小屋では、「原始的な」あるいは「奇形的な」黒人として特徴づけられた人々が展示され、白人の優位性を「科学的」に立証する視覚的材料とされた。特に「ホッテントットのヴィーナス」として知られるサルティ―・バートマンの例は、彼女の身体的特徴が生きたまま、そして死後も解剖学的標本として展示され続けたことを示す。このような展示は、黒人を非人間的で観察・分析の対象とする見方を強化し、医学的実験への心理的土壌を形成した。
第4章 外科劇場:南北戦争前の診療所における黒人身体
医学教育の現場である診療所や病院も、黒人身体を利用する場となった。貧しい白人患者とは異なり、黒人患者(特に奴隷)はしばしば医学教育用の「教材」として提供された。学生たちは彼らに対して繰り返し検査や処置の練習を行った。この慣行は、黒人が苦痛を感じる能力が低い、あるいは医学の進歩への貢献を当然負うべき存在であるという人種的偏見によって支えられていた。診療所は、医学的権威が黒人の自律性を無視し、その身体を公共の学習資源とみなす空間であった。
第5章 安らかならぬ死体:解剖学的解剖と展示
死後も、黒人身体は医学的探求の対象であり続けた。19世紀、解剖学教育の需要が高まる中、合法的な屍体供給源は限られていた。その結果、「レシング(屍体盗掘)」が横行し、その主要な標的は黒人の墓地、特に貧困層や囚人のものだった。奴隷の屍体は所有者から売買されることもあった。法律も、死刑囚の屍体の解剖を認めるなど、黒人に偏って適用される傾向にあった。解剖台の上でさえ、黒人は自らの意志とは無関係に「医学に奉仕」することを強いられたのである。
第6章 診断:自由:南北戦争、解放、世紀末の医学研究
南北戦争と奴隷制の廃止は、黒人の法的地位を変化させたが、医学的実験対象としての地位を一掃することはなかった。むしろ、解放された何十万人もの黒人は、極度の貧困と医療へのアクセスの欠如に直面し、新たな脆弱な集団を形成した。軍医や研究者は、黒人兵士や解放奴隷を対象に、天然痘や壊疽などの疾病研究を行った。また、解放によって黒人の「身体的・道徳的退化」を憂慮する疑似科学的言説が広まり、それが医学的監視や介入を正当化する根拠とされた。自由は、新たな形態の医学的対象化から逃れることを意味しなかった。
第7章 「悪名高い梅毒漬けの人種」:タスキギーで本当は何が起きたのか?
1932年に始まったタスキギー梅毒研究は、米国公衆衛生局がアラバマ州の貧しい黒人男性600人(うち400人は梅毒感染者)を対象に実施した非倫理的研究である。その目的は、治療なしで梅毒の経過を観察することにあった。被験者には研究の真の目的は告げられず、単に「悪い血」の治療を受けると説明された。ペニシリンが梅毒の有効な治療法として確立された後も、被験者への治療は意図的に阻止され、研究は1972年に内部告発されるまで40年間続いた。本章では、この事件を単独の悪例ではなく、黒人を「疫学的リスク・グループ」と見なす人種的偏見、貧困と教育機会の欠如による脆弱性、そして公的機関の加担という構造の中で理解する。著者はこう述べる。「タスキギーの物語は、医学的人種差別について我々が知っていることの象徴であると同時に、知らないことの象徴でもある。」
第二部 お決まりの被験者
第8章 黒いコウノトリ:アフリカ系アメリカ人の生殖をめぐる優生学的管理
20世紀初頭に隆盛した優生学運動は、黒人の生殖に直接的な介入を行った。「社会的に不適格」とみなされた者、特に黒人女性に対する強制的な不妊化手術が、多くの州で合法化され、実施された。同意の形骸化、知的能力に関する誤った診断、社会的偏見に基づいて手術が行われ、黒人コミュニティの人口増加を抑制しようとする意図が働いていた。この政策は公民権運動期以降も続き、医療福祉を受ける条件として不妊化を迫られるケースもあった。国家が黒人女性の生殖能力を管理・剥奪するというこの歴史は、奴隷制時代の繁殖管理の現代的な継続であった。
第9章 核の冬:アフリカ系アメリカ人に対する放射線実験
冷戦期、アメリカ政府と科学界は放射線の人体への影響について強い関心を持ち、多数の人体実験を実施した。その被験者には、意識のない患者、囚人、兵士など、社会的に脆弱な立場の黒人が数多く含まれていた。例えば、妊婦への放射性鉄投与実験、囚人への睾丸への放射線照射実験、黒人新生児への放射線を活用した血液検査などである。これらの実験は、適切なインフォームド・コンセントなく行われ、被験者に長期的な健康リスクをもたらした。国家の安全保障と科学の進歩という名目の下、黒人身体が再び「消耗可能な資源」とみなされた事例である。
第10章 檻の中の被験者:研究対象としての黒人受刑者
20世紀中頃まで、アメリカの刑務所は製薬会社や政府機関にとって理想的な臨床試験の場となった。囚人たちは、経済的報酬や特権(仮釈放の可能性ではない)と引き換えに、マラリア、性病、新薬の治験、皮膚移植実験など、様々な危険な研究に参加させられた。黒人受刑者はこの被験者集団の中で過剰に代表されていた。刑務所という閉鎖的環境は被験者の管理を容易にし、「自発的同意」の概念は甚だ疑わしいものだった。1970年代後半に規制が強化されるまで、囚人体験は医学研究の重要な一部を成していた。
第11章 子供たちの十字軍:若いアフリカ系アメリカ人を標的にした研究
子どもたち、特に施設に収容された黒人や貧困家庭の子どもたちも、医学実験の対象から逃れることはできなかった。ニューヨークのウィローブルック州立学校では、知的障害児(多くは黒人や移民の子)に意図的にA型肝炎ウイルスを経口投与する研究が行われた。ボルチモアのジョンズ・ホプキンス大学とケネディ・クリーガー研究所では、貧しい黒人家庭の子どもたちを対象に、鉛含有塗料の曝露影響を調べる研究が行われ、一部の家庭には鉛汚染除去を行わずに観察が続けられた。親の貧困、教育的機会の欠如、情報の非対称性が、子どもの「同意」を形骸化させた。
第三部 人種、技術、医学
第12章 遺伝的破滅:分子的偏見の台頭
現代の遺伝子医学は、病気の理解に革命をもたらしたが、同時に新たな危険をはらむ。特定の人種集団と疾病を結びつける遺伝子研究は、黒人をある病気に「本質的」にかかりやすい存在として再定義し、生物学的決定論を復活させる可能性がある。この「分子的偏見」は、社会的・経済的・環境的要因を無視し、健康格差を個人の遺伝的宿命に帰着させかねない。さらに、黒人コミュニティの遺伝情報が同意なく収集・利用される懸念も生じている。遺伝子は、かつての頭蓋骨計測と同じく、人種的不平等を正当化する新たな「科学的」根拠として機能するリスクを孕んでいる。
第13章 感染と不平等:犯罪としての病
エイズや結核などの感染症の流行は、黒人コミュニティに偏って大きな打撃を与えてきた。しかし公衆衛生上の対応は、しばしば医療支援というよりも刑事司法システムによる監視と処罰の色彩を強く帯びた。例えば、HIV陽性であることを理由に起訴されること、結核治療を強制収容で確保しようとする試みなどである。このアプローチは、感染者を「加害者」または「公衆衛生上の脅威」として烙印を押し、黒人コミュニティを犯罪者扱いする従来の傾向と結びつく。病への対策が、人種的偏見に基づく社会管理の手段へと転化する危険性を示している。
第14章 機械の時代:外科技術へのアフリカ系アメリカ人の犠牲
心臓外科、臓器移植、人工臓器など、20世紀後半の高度な医療技術の開発と洗練化の過程でも、黒人は不当なリスクを負わされた。初期の心臓カテーテル検査やバイパス手術、人工心臓の植込みなどの臨床試験において、黒人患者は適切な説明なく、あるいは他の選択肢を与えられずに、リスクの高い処置の「最初の被験者」とされる事例が多発した。これらの技術が確立され安全になると、今度は経済的・地理的障壁によって黒人がその恩恵にアクセスできなくなるという逆説も生じた。技術革新の犠牲と恩恵の両面で、人種的不平等が現れている。
第15章 異常な戦争:黒人を標的とするアメリカの生物テロリズム
最も衝撃的な暴露の一つは、アメリカ政府自体が国内の黒人コミュニティに対して生物・化学物質を用いた実験を行ったという事実である。1950年代から60年代にかけて、国防総省やCIAは、生物戦争の可能性を探るため、あるいは都市環境での拡散をシミュレートするため、黒人居住区の上空から無害とされた(しかし後に有害性が疑われる)細菌や化学物質を散布する「野外試験」を実施した。セントルイスやタスキーギーなどがその標的となった。これは、国家が自国民の一部を、その同意なく、潜在的に危険な実験の標的と見なしたことを意味する。著者はこう記す。「…黒人身体は、文字通り、国の防衛のための実験場となった。」
エピローグ:今日の黒人を対象とした医学研究
暗い歴史を直視した上で、現在の状況を評価する。規制の強化(ベルモント報告書、共通規則など)と倫理審査委員会(IRB)の設置により、かつてのような露悪的な実験は減少した。しかし、医療へのアクセス格差、臨床試験への参加における人種的不均衡(過少代表または過剰代表)、そして黒人コミュニティに深く根付いた医療不信は、未解決の重大な課題として残っている。この不信は、過去の被害の記憶に起因する「非合理的」なものではなく、制度的な裏切りへの正当な反応である。真の変革のためには、透明性の確保、コミュニティ参加型研究の推進、医療倫理教育への歴史的視点の組み込み、そして何よりも、黒人の身体的自律性と尊厳をあらゆる医療の場で最優先するという根本的なパラダイム転換が必要である。過去の「メディカル・アパルトヘイト」は、未来の医療倫理を構築する上で避けては通れない教訓なのである。
パスワード記載ページ(note.com)はこちら
注:noteのメンバーのみ閲覧できます。
メンバー特別記事
医療の闇に光を当てる:米国医学における黒人身体の「管理」史 AI考察
by DeepSeek
「善意」の仮面と構造的暴力の連続性
この『メディカル・アパルトヘイト』という本を読み終えて、まず感じるのは、非常に重いけれども避けては通れない歴史的事実の積み重ねだ。著者のハリエット・ワシントンが提示する400年にわたる証拠の連鎖は、単に「過去の過ち」という言葉で片付けられるものではない。むしろ、科学と医学という「客観性」と「進歩」を標榜する領域において、人種に基づく体系的な差別と搾取が、いかに制度的に組み込まれ、継承されてきたかを赤裸々に示している。
ここでまず考えなければならないのは、この歴史をどう理解するかという枠組みだ。主流の医学史は、しばしば画期的な発見や技術革新の物語として語られる。ペニシリン、ワクチン、外科手術の進歩…。しかしワシントンは、その輝かしい物語の裏側に、誰かの犠牲と苦痛があったことを忘れさせない。特に黒人という「他者」の身体が、医学的進歩の「燃料」として消費されてきた構図は、科学の「中立性」という神話を根本から揺るがす。
私自身、パンデミック政策を巡る議論の中で、公衆衛生や医学的権威への信頼が大きく揺らいだ経験がある。政府や専門家が「科学に基づく」と主張する政策が、実は政治的・経済的要因と切り離せないことを目の当たりにした。この本が描く歴史は、その不信感をさらに深めるものだ。なぜなら、ここで問題にされているのは単なる「過ち」や「無知」ではなく、明確な「構造」と、場合によっては「意図」だからだ。
「治療」という名の搾取:奴隷制下の医療経済
第一部の核心は、奴隷制が単なる労働搾取のシステムではなく、黒人身体の包括的な「管理」システムであったことを医学の面から実証した点にある。ワシントンが示すように、プランテーションにおける医師の役割は、奴隷の「健康維持」というよりも、所有者の「資産価値維持」だった。ここで重要なのは、この関係性が「悪意」だけでは説明できないことだ。むしろ、当時の経済的合理性と医学的実践が、自然に、そして必然的に結びついていた構造が見える。
例えば、麻酔なしで奴隷女性に繰り返し手術を行ったJ・マリオン・シムズの事例を考えてみよう。後世、彼は「産科外科の父」として称えられる一方で、その研究方法は非倫理的と批判される。しかしワシントンの叙述は、それを単なる個人の倫理的問題に還元しない。シムズが利用したのは、奴隷制という制度的現実だった。奴隷は移動できず、同意を求められることもない「理想的な」臨床材料だった。医師の探求心と野心が、制度的弱者を標的にするシステムと完璧に適合したのだ。
これは現代の臨床試験の構造と無関係だろうか? 考えてみてほしい。今日、製薬会社の臨床試験が、しばしば医療アクセスの乏しい発展途上国や、国内の貧困層を対象に行われることが問題視される。経済的インセンティブ(報酬)と、医療への切実なニーズが結びつき、「自発的同意」の質が問われる構造は、奴隷制下の医療実験と根本的に異なるだろうか? 制度の形態は変わっても、社会的・経済的弱者が医学的進歩の「フロンティア」として利用される構図には、不気味な連続性を感じる。
さらに興味深いのは、死後も続く搾取、つまり解剖用屍体の供給源としての黒人墓地の役割だ。ここでは、法律そのものが人種的に偏って適用された。死刑囚の屍体提供を義務付ける法律は、事実上黒人に偏って適用され、「レシング」(屍体盗掘)の主要な標的も黒人墓地だった。科学教育という「公共善」の名の下に、特定の集団の尊厳と身体的自律性が体系的に踏みにじられる。このパターンは、後の優生学政策や放射線実験においても繰り返される。
タスキギーを超えて:「公衆衛生」という権力装置
第二部で扱われる20世紀の事例、特にタスキギー梅毒研究は、この歴史の中で最もよく知られた事件だ。しかしワシントンが強調するのは、タスキギーを特別な「悪の例外」として切り離して考えることの危険性だ。彼女はこれを、より広範な「メディカル・アパルトヘイト」のほんの一例に過ぎないと位置づける。
ここで注目すべきは、加害者が「悪の科学者」の個人ではなく、米国公衆衛生局という国家的機関だった点だ。国家が、自国民の一部を「観察対象」とし、知らせずに治療を保留する。その目的は、「未治療の梅毒の自然経過を観察する」という「科学的知見」の獲得である。これは単なる倫理的失敗ではない。これは、国家権力が特定の人種集団を「管理」すべき対象、さらには「実験」の対象と見なす「統治理性」の露呈だ。
「タスキギーの物語は、医学的人種差別について我々が知っていることの象徴であると同時に、知らないことの象徴でもある。」
この引用は深い。タスキギーが「象徴」であるのは、その非倫理性が明白だからだ。しかし「知らないことの象徴」であるのは、それが氷山の一角に過ぎず、同じ論理に基づく無数の実験や政策が、記録にも残らず、告発されることもなく行われてきたからではないか。ワシントンが挙げる放射線実験、囚人実験、子どもを対象とした研究は、すべて同じ構造を共有している。つまり、「社会的に脆弱で、声が届きにくく、同意を取りやすい(あるいは無視しやすい)集団」が、リスクの高い医学的探求の「最初の被験者」としてシステム的に選ばれるという構造だ。
この選定プロセスには、しばしば「科学的」な正当化が伴う。「黒人は梅毒にかかりやすい」「貧困層の子どもは環境汚染の影響を調べるのに適している」「囚人は管理された環境で長期観察できる」。これらの言説は、一見すると「客観的」な観察に基づいている。しかし、その「客観性」は、歴史的に構築された社会的条件(貧困、隔離、差別的医療アクセス)を無視し、それを生物学的・本質的な「特性」として固定化する働きを持つ。ここに、「科学的人種主義」の現代的な変奏を見る。
現代における「アパルトヘイト」の変容:遺伝子、監視、生物テロ
第三部は最も衝撃的だ。なぜなら、ここで扱われるのは「過去の歴史」ではなく、現代に続く、あるいは新たに現れた形態の「メディカル・アパルトヘイト」だからだ。
第12章の「遺伝的破滅」は、現代の遺伝子研究がもたらす新たなリスクを指摘する。特定の疾患と人種集団を結びつける遺伝子研究は、一見すると「精密医療」への貢献のように見える。しかし、歴史的文脈を無視すれば、それは黒人をある病気に「本質的」にかかりやすい存在として再定義し、健康格差を個人の「遺伝的宿命」に帰着させかねない。社会的不平等が生み出した健康被害を、生物学的決定論で説明しようとする誘惑は強い。かつての頭蓋骨計測や知能検査が「科学的」権威を借りて人種的階層を正当化したように、遺伝子データも同じ役割を担う可能性がある。問題はデータそのものではなく、その解釈と利用が、構造的差別を強化する文脈で行われる危険性だ。
第13章「感染と不平等」は、パンデミック下で私たちが経験したことと重なる。エイズや結核への対応が、医療支援ではなく刑事司法による「監視と処罰」の様相を帯びる傾向は、COVID-19における移動制限や監視技術の適用と無関係だろうか? 感染者を「公衆衛生上の脅威」として烙印を押し、その自由と権利を制限する論理は、人種的マイノリティや社会的弱者に偏って適用される傾向がある。公衆衛生が、時に「管理」と「統制」の手段となりうることを、この歴史は警告している。
だが、最も言葉を失うのは第15章「異常な戦争」だ。アメリカ政府が、国内の黒人居住区に対して生物・化学物質を用いた野外試験を実施したという事実は、国家権力の本質について深く考えさせる。
「…黒人身体は、文字通り、国の防衛のための実験場となった。」
この一節が意味するものは大きい。国家が「国防」や「国家安全保障」を名目に、自国民の一部を、その同意なく、潜在的に危険な実験の標的とする。これはもはや「構造的差別」の域を超え、計画的で意図的な「国家犯罪」の匂いがする。セントルイスやタスキーギーで空中散布が行われたという事実は、陰謀論ではなく、文書化された歴史的事実としてワシントンは提示する。ここで問われるのは、「なぜ黒人地区が選ばれたのか?」という意図だ。人口密度? 風向き? それとも、声が上がりにくく、抗議が組織化されにくいコミュニティが「都合が良かった」からか? 後者であれば、これはまさに「メディカル・アパルトヘイト」の極致であり、国家による生物学的テロリズムと言えるのではないか。
この事例は、陰謀論と構造的分析の狭間で思考を揺さぶる。完全な「陰謀」(少数の人間が密室里で計画)として片付けるのは単純化しすぎかもしれない。しかし、無意識の「構造的バイアス」だけで説明するには、あまりに計画的な行為だ。おそらく現実はその中間、つまり「このコミュニティは実験の影響に対して脆弱で、政治的リスクが低い」という冷徹な「リスク計算」が、人種的偏見と制度的権力の文脈で行われた結果なのだろう。それは「悪意」というより、「非人間化」された行政的・軍事的判断の帰結だ。そして、その「非人間化」こそが、最も危険な状態なのである。
権威、科学、そして「進歩」の代償
この本を読みながら、何度も考えたのは「科学の権威性」と「進歩の物語」についてだ。私たちは通常、医学的進歩は人類全体の利益であり、その過程での犠牲は残念だがやむを得ない「コスト」と考えがちだ。しかしワシントンは、その「コスト」が特定の人種集団に偏って押し付けられ、その負担が不可視化されてきた歴史を暴く。
ここで想起されるのは、医学研究における「倫理規範」の発展史そのものだ。ニュルンベルク綱領(1947年)もヘルシンキ宣言(1964年)も、ナチスの人体実験やタスキギー研究のような明らかな倫理的惨事への反応として生まれた。つまり、倫理規範は、しばしば「後付け」の歯止めなのである。そして、その規範ができる前、あるいは抜け穴を探る中で、どれだけの「実験」が行われたのか。ワシントンが掘り起こす歴史の多くは、公式の倫理規範が確立される「前」、あるいはその「隙間」で起きている。
もう一つの重要な視点は、「同意」の概念の空洞化だ。奴隷には法的同意能力がなかった。囚人には「報酬」という形の経済的強制が働いた。貧しい親には「無料の医療」という誘惑があった。いずれの場合も、「自由で、十分な情報に基づいた同意」という理念は、社会的・経済的権力の格差の前で無力だった。現代の臨床試験でさえ、経済的報酬や治療へのアクセスを求める被験者の「同意」が、本当に自由な意志に基づいているかは疑問が残る。この問題は、医学研究が市場原理と結びつく限り、根本的には解決できないかもしれない。
日本の文脈に当てはめて考える
最後に、日本の文脈でこの問題を考えてみたい。日本にはアメリカのような人種的マイノリティに対する大規模な医学実験の歴史はないかもしれない。しかし、「構造的弱者」を対象とした医学的搾取や倫理的問題が全くなかったと言えるだろうか?
戦時中の731部隊による人体実験は、国家的規模で組織された医学的犯罪であり、その対象は主に中国人や朝鮮人などの「敵性」民族だった。この歴史は、国家が「軍事研究」や「国の利益」を名目に、特定の集団を非人間化し、実験対象とする論理が日本にも存在したことを示す。戦後処理と真相解明が不十分なまま現在に至っている点も、タスキギー研究が長く隠蔽されていた歴史と重なる。
また、薬害エイズ事件を思い起こす。非加熱血液製剤の投与により多くの血友病患者がHIVに感染したこの事件では、製薬会社と行政の責任が問われた。被害者の多くは社会的に脆弱な立場にあった血友病患者であり、有効な治療法(加熱製剤)の導入が遅れた背景には、経済的利害と官僚の保身があったと指摘されている。ここでも、「医療的決定」が患者の利益ではなく、企業と行政の都合に左右される構図が見える。
在日コリアンやアイヌ民族といったマイノリティ、あるいはハンセン病患者などに対する歴史的差別と医療の関わりは、もっと掘り下げて検証する必要があるだろう。日本の医学史も、決して「清い」ものではあり得ない。むしろ、「単一民族」神話の下で、内部の多様性とそれに伴う格差や差別が見えにくくなっている可能性すらある。
結論:不信から再構築へ
『メディカル・アパルトヘイト』が最終的に読者に促すのは、単なる怒りや絶望ではない。むしろ、「認識」と「警戒」、そして「再構築」への呼びかけだ。ワシントンはエピローグで、現在の医療制度や研究倫理の改善を認めつつも、根本的な課題が残っていると指摘する。黒人コミュニティの医療不信は、「非合理的な偏見」ではなく、歴史的経験に基づく「合理的な懐疑」である。
この本を読んだ後では、政府や医学的権威が「科学的証拠に基づく」と主張する政策や研究を、無条件に受け入れることはできなくなる。常に「その証拠は誰によって、どのような目的で、誰を対象に作られたのか?」「利益とリスクは誰にどのように分配されるのか?」「本当に同意は自由で十分な情報に基づいているのか?」と問いかける必要がある。
しかし、懐疑が全てを否定するニヒリズムに陥ってはならない。ワシントンが示す道は、過去の過ちを直視し、透明性を高め、コミュニティをエンパワーメントし、真の意味での「インフォームド・コンセント」と「利益の公正な配分」を制度的に保障する医療システムを再構築することだ。
科学と医学は、人類に計り知れない恩恵をもたらした。しかし、その光は非常に長く、暗い影を伴っていた。その影の中に、無数の黒人たちの苦痛と犠牲が沈んでいた。私たちは、光だけを見て影を無視することをやめ、影の存在を認め、なぜ影が生まれたのかを理解しなければならない。そうして初めて、光と影の両方を含んだ、より公正で倫理的な医学の未来を構想することができるのだ。
この本は、そのための最初の、そして不可欠な一歩なのである。
