コンテンツ
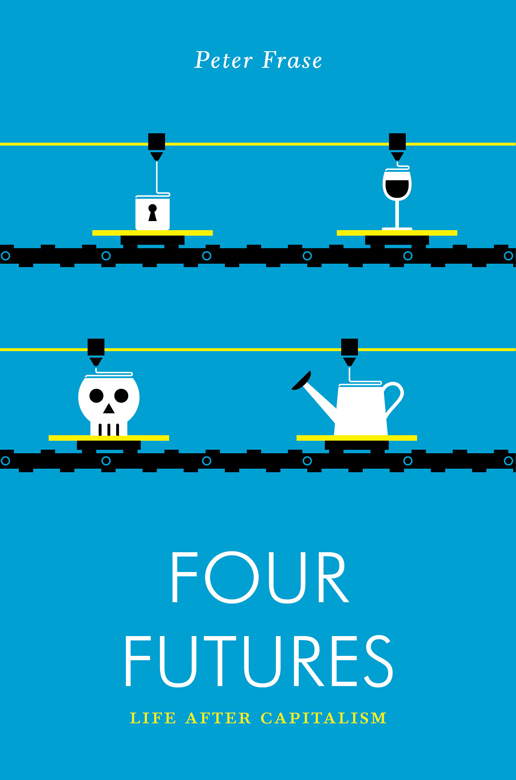
目次
- はじめに 黙示録とユートピアとしてのテクノロジーとエコロジー
- 1.共産主義平等と豊かさ
- 2.賃借主義階層と豊かさ
- 3.社会主義平等と欠乏
- 4.絶滅主義:階層と希少性
- 注釈
- 結論移行と展望
はじめに 黙示録とユートピアとしてのテクノロジーとエコロジー
21世紀の地球には、生態系の破滅とオートメーションという2つの亡霊がつきまとっている。
2013年、アメリカ政府の観測所は、地球の大気中の二酸化炭素濃度が観測史上初めて400ppmに達したことを記録した1。気候変動に関する政府間パネルは、海氷の減少、海洋の酸性化、干ばつや異常気象の頻度の増加を予測している2。
同時に、高い失業率と賃金の低迷という状況下での技術革新のニュースは、自動化が仕事の未来に及ぼす影響についての不安な警告を生み出している。2014年初頭、マサチューセッツ工科大学のエリック・ブリンヨルフソン教授とアンドリュー・マカフィー教授は、『The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies(第二の機械時代:輝かしいテクノロジーの時代における仕事、進歩、繁栄)』を出版した3。彼らは、農業や製造業といった伝統的な領域だけでなく、医療や法律から輸送に至るまで、幅広い分野でコンピューターやロボット技術が人間の労働に取って代わる未来を調査した。オックスフォード大学の研究部門は、今日のアメリカにおける仕事の半分近くがコンピューター化の影響を受けやすいと推定する報告書を発表し、広く知られるところとなった4。
この2つの不安は、多くの点で正反対である。気候変動への不安は、少なすぎることへの不安である。天然資源が不足し、農地や居住可能な環境が失われ、最終的には人間の生命を維持できる地球が滅亡することを予期しているのだ。オートメーションへの恐怖は、裏を返せば、多すぎることへの恐怖でもある。完全にロボット化された経済が、人間の労働力をほとんど使わずに多くのものを生産し、もはや労働者を必要としなくなるのだ。私たちは本当に、欠乏の危機と豊かさの危機に同時に直面しているのだろうか?
本書の主張は、私たちは実際にそのような矛盾した二重の危機に直面しているということである。そして、この2つの力学の相互作用こそが、私たちの歴史的瞬間を非常に不安定で不確実なものにしており、将来性と危険性の両方に満ちたものにしているのである。この後の章では、これら2つの原動力の相互作用の可能性のいくつかを概説しようと思う。
しかしその前に、自動化と気候変動をめぐる現在の議論の輪郭を整理しておく必要がある。
ロボットの台頭
「リベラル派の評論家ケヴィン・ドラムによるこの記事は、近年、経済のあらゆる分野で自動化とコンピューター化が急速に広がっていることを伝える報道を象徴している。これらの記事は、この新しいガジェットの可能性に対する驚きと恐怖の間を行き来する傾向がある。ドラムのような話では、オートメーションの急速な進歩は、より質の高い生活と、すべての人にとってより多くの余暇を持つ世界の可能性を告げるものである」
これは決して新しい緊張関係ではない。19世紀に生まれた「ジョン・ヘンリーと蒸気ハンマー」という民話は、鋼鉄で動くドリルと競争しようとした鉄道労働者が勝利し、その努力の末に死んでしまうという話である。しかし、テクノロジーとそれが労働に及ぼす影響に関する懸念を際立たせる要因がいくつか重なっている。景気後退後の労働市場の低迷が続き、雇用喪失に対する一般的な不安が背景にある。自動化とコンピューター化は、長い間無縁と思われていた専門職やクリエイティブな業界にまでおよび始めており、これらの問題を取材するジャーナリストたちの雇用を脅かしている。変化のスピードは、少なくとも多くの人々にとっては、かつてないほど速くなっているように見える。
「第二の機械時代」とは、ブリンジョルフソンとマカフィーが提唱する概念である。ブリンジョルフソンとマカフィーは同名の著書の中で、第一の機械時代(産業革命)が人間の筋肉を機械の力に置き換えたように、コンピュータ化によって「頭脳を使って環境を理解し形成する能力」が大幅に拡大され、あるいは置き換わりつつあると論じている6。彼らの見解の中心は、世界の多くがデジタル情報に加工され、書籍や音楽から道路網に至るまで、あらゆるものが瞬時にコピーされ、ほぼ無料で世界中に送信可能な形で利用できるようになったことだ。
この種のデータが可能にするアプリケーションは、特に物理世界のロボット工学やセンシングの進歩と組み合わせることで、非常に多様なものとなる。オックスフォード大学の研究者であるカール・ベネディクト・フレイとマイケル・A・オズボーンは、米国労働省が作成したさまざまな職業の詳細な分析を用いた広く引用された研究の中で、現在の技術開発のおかげで、現在の米国雇用の47%がコンピューター化の影響を受けやすいと推測している7。これらの図は、主観的な分類判断と複雑な定量的手法の両方の結果であるため、正確な数字を過信するのは間違いである。とはいえ、近い将来、自動化が急速に進む可能性が非常に高いことは明らかだろう。
ブリンジョルフソンとマカフィーはおそらく、急速な自動化の予言者として最もよく知られているが、彼らの仕事は爆発的に拡大しつつあるジャンルに当てはまる。例えば、ソフトウェア起業家のマーティン・フォードは、2015年に発表した『Rise of the Robots(ロボットの台頭)』で似たような領域を探求している8。彼は同じ文献の多くに依拠し、自動化のペースについて同じ結論の多くに達している。彼の結論は、本書で後述する、保証された普遍的ベーシックインカムが重要な位置を占めている。対照的に、ライバルとなる文献の多くは、教育についてのお決まりの文句を述べているに過ぎない。
多くの人々が、急速で社会的な混乱をもたらすオートメーションについて書いているからといって、それが差し迫った現実だというわけではない。前述したように、省力化技術に対する不安は、資本主義の全歴史を通じて実は不変のものである。しかし、人間の労働力の必要性を劇的に減らす可能性がある(必ずしも現実ではないが)という兆候は数多く見られる。いくつかの例を挙げれば、人間の労働力が削減され、あるいは完全に排除されつつある多様な分野があることがわかるだろう。
2011年、IBMはスーパーコンピューター「ワトソン」を開発し、ゲーム番組「ジェパディ」で人間との対戦に勝利して話題となった。この偉業はやや軽薄な宣伝行為ではあったが、ワトソンが他の、より価値のある仕事にも適していることを示した。この技術はすでに、膨大な量の医学文献を処理して患者をよりよく診断するために医師を支援するためにテストされている。しかし、「ワトソン・エンゲージメント・アドバイザー」としてもリリースされており、カスタマーサービスやテクニカル・サポート用途を想定している。ユーザーからの自由形式の自然言語による問い合わせに対応することで、このソフトウェアは、現在このような業務を行っているコールセンターの労働者(多くはインドのような場所にいる)に取って代わる可能性がある。従来は大勢の若手弁護士が行っていた、非常に時間のかかる法律文書のレビューも、このテクノロジーの有望な応用分野である。
もうひとつの急速な進歩の分野は、ロボット工学、つまり機械と物理的世界との相互作用である。20世紀には、自動車の組立ラインを動かすような大規模な産業用ロボットの開発で大きな進歩があった。しかし、人間が得意とする分野、つまり細かな運動技能や複雑な物理的地形のナビゲーションに挑戦し始めたのはごく最近のことだ。米国防総省は現在、制服を中国から調達するのを避けるため、コンピューター制御のミシンを開発している9。現在では、センサー技術と包括的な地図データベースの組み合わせにより、グーグルの自動運転車などのプロジェクトで実現されつつある。一方、Locus Roboticsという会社は、巨大な倉庫で注文を処理するロボットを発表し、アマゾンや他の企業で、しばしば残酷な環境で労働に従事している労働者に取って代わる可能性がある10。
かつては人間の労働力が最も大きな割合を占めていたが、現在では雇用のごく一部を占めるにすぎない農業でも、自動化が進んでいる。カリフォルニア州では、メキシコの経済状況の変化と国境取り締まりによって労働力が不足している。このことは、これまで人間の手による正確さが必要とされてきた、果物の収穫のような繊細な作業でさえもこなすことができる、新しい機械への投資に農家を駆り立てている。低賃金の出稼ぎ農民が大量にいる場合、10万ドルの果物収穫機は無駄な浪費に見える。しかし、労働者が不足し、より良い賃金を要求できるようになると、労働者を機械に置き換えるインセンティブが強まる。
オートメーション化の傾向は、資本主義の歴史全体を通して見られる。近年は、ソビエト連邦崩壊後にグローバル資本主義が安価な労働力を大量に投入し、中国が資本主義に転じたため、この傾向は弱まり、やや目立たなくなっていた。しかし今や、中国企業でさえ労働力不足に直面し、自動化やロボット化の新たな方法に目を向けている。
さらに数え切れないほどの例を挙げることができる。医師に代わるロボット麻酔医。マクドナルドの店員に代わるハンバーガー製造機。一日で家一軒を完成させる大型3Dプリンター。毎週、奇妙な新しいことが起こる。
オートメーションは、これさえも超えて、女性の労働の最も古く、最も基本的な形態へと移行する可能性がある。1970年代、急進的なフェミニストの理論家シュラミス・ファイアストンは、生殖関係における支配的な立場から女性を解放する方法として、人工子宮で赤ちゃんを育てることを呼びかけた12。日本の科学者たちは、人工子宮からヤギを出産させ、ヒト胚を最長10日間育てることに成功した。この技術をヒトの赤ちゃんに応用するためのさらなる研究は、現在では科学と同様に法律によって制限されている。日本では、ヒト胚を14日間以上人工的に育てることを禁止している13。しかし、義務から解放されることを望む女性も多いはずだ。
本書の大半は、オートメーション楽観主義者の前提を当然視している。ケビン・ドラムが『マザー・ジョーンズ』で述べたように、わずか数十年のうちに、「ロボットは人間ができることをすべてこなし、それを1日24時間、淡々とこなし」、「普通の消費財の欠乏は過去のものとなる」というスタートレックのような世界に住むことができるのだ。 「14 このような主張は誇張表現である可能性が高いが、本書の目的からすればそれは構わない。私のアプローチは、基本原則を説明するために単純化した理想型をスケッチし、意図的に誇張しているのだ。私のアプローチは、基本原理を説明するために単純化された理想的なタイプを意図的に誇張して描いているのだ。絶対にすべてがロボットによって行われるようになることが重要なのではなく、現在人間が行っている労働の大部分が自動化される過程にあるということだけが重要なのだ。
しかし、自動化がどの程度のスピードで進むのか、どのようなプロセスが自動化の影響を受けやすいのかについては、依然として多くの議論がある。そこで、その過程で起こりうる社会的影響を掘り下げる前に、私たちが生きている「第二の機械時代」と呼ばれる最近の急速な進展の一端をスケッチしておこう。これは、大規模な産業オートメーションによる「第一の機械時代」の続編であり、あるいは単にその延長線上にあるという見方もある。
機械惑星への恐怖
広範囲に及ぶ自動化の予測や恐怖に対する反対意見は、大きく3つに分類される。新技術に関する報道は大げさで誇張されすぎており、ほとんどの分野で本当に人間の労働に取って代わることができるようになるにはまだまだ時間がかかると主張する者もいる。また、主流派経済学の伝統的な議論に従って、過去の急速な生産性上昇のエピソードは、単に新しい種類の仕事と新しい雇用をもたらしただけで、大規模な失業につながったわけではなく、今回も同じだと主張する者もいる。最後に、左派の一部には、未来的な自動化シナリオに執拗に注目することは、政府投資や景気刺激策、職場における賃金や労働条件の改善など、より差し迫った政治的課題から目をそらすことになると考える者もいる。
労働の終焉に関する報道: 大きく誇張されていないか?
テクノロジーが誇張された重要性を与えられていると考える人々は、通常、生産性の伸びに関する公表された統計を指摘する。ロボットや機械が大量に導入されれば、労働生産性を測定する統計、つまり労働者1人当たりが生み出すことのできる生産量の急激な増加として現れるはずである。しかし実際には、近年の生産性の伸び率は比較的低い。米国労働統計局によれば 2007年から2014年までの年間変化率はわずか1.4%だった。これは1970年代以降のどの時期よりも低いペースであり、戦後の好況期の半分である。
このことから、ロボット工学や計算機における大躍進の逸話は誤解を招くものであり、実際に経済的な成果に結びついていないという意見もある。経済学者のタイラー・コーウェンやロバート・ゴードンは、この見解に最も近い15。左派の『Left Business Observer』のダグ・ヘンウッドも、左派から同様の主張をしている16。
コーウェンやゴードンのような保守的な経済学者にとって、問題は主に技術的なものである。コーウェンやゴードンのような保守的な経済学者にとって、問題は主に技術的なものだ。新しい技術は、少なくとも経済的な観点からは、電気や内燃機関のようなブレイクスルー技術と比べて、それほど素晴らしいものではない。コーウェン氏の言葉を借りれば、私たちは「低くぶら下がる果実」を摘んでしまったのである。
ヘンウッドや経済政策研究センターのディーン・ベイカーのような左派の批評家は、われわれの問題を技術ではなく政策に求めている。彼らに言わせれば 2008年の不況後の弱い景気回復をオートメーションのせいにするのは、政府の政策が財政刺激策や雇用創出に十分に力を注いでこなかったため、経済が完全雇用に到達できなかったという本当の問題から目をそらすことになる。この観点からすれば、ロボットに対する懸念は(生産性の伸びが低いため)反実仮想的であり、政治的に反動的である。
しかし、ブリンジョルフソンやマカフィーをはじめとする他の人々は、たとえ根本的な大躍進が目前に迫っていないとしても、すでに目にした大躍進を洗練させ、再結合させることで得られるものは多いと主張する。これは歴史的によく見られるパターンである。例えば、大恐慌時代に発見された多くの新しい技術は、戦後の好景気まで経済的に十分に活用されなかった。さらに、国内総生産に数字として反映されない変化であっても、私たちの社会的豊かさに貢献することはある。例えば、インターネット上で自由かつ迅速に入手できる膨大な量の情報は、本書の執筆効率を大いに高めてくれた。
自動化論に批判的な左派の人々には、より複雑な答えを提示することができる。というのも、最近の生産性のトレンドは、経済の短期的均衡と長期的潜在力との間の奇妙な緊張の反映とも読めるからである。
21世紀の最初の2回の不況は、賃金の低迷と高い失業率を特徴とする弱い回復につながった。このような状況では、失業者や低賃金労働者が大量に存在することが、雇用主にとって自動化を阻害する要因となる。結局のところ、労働者の方が安いのに、なぜ労働者をロボットに置き換えるのだろうか?しかし、この原則の帰結として、賃金が上昇し労働市場が逼迫し始めれば、雇用主は追加的な労働コストを支払うよりも、現在開発中の新技術に目を向け始めるだろう。以下のセクションで論じるように、逼迫した労働市場に対する真の阻害要因は、現在のところ、技術的なものではなく政治的なものである。
自動化の永遠回帰
主流派の経済学者たちは、オートメーションが労働にもたらす危険性について、何世代にもわたって同じ議論をしてきた。一部の仕事が自動化されれば、労働力は他の、新しい、そしておそらくより優れた仕事のために解放される、と彼らは主張する。彼らは、かつては労働力の大半を占めていた農業が、現在ではアメリカのような国で2%程度しか占めていないことを指摘する。農業雇用の減少によって労働者は解放され、工場で働くようになり、20世紀半ばの巨大な工業製造業経済を築き上げた。その後、製造業の自動化とオフショアリングが進み、サービス業が活況を呈した。
では、なぜ今日と違うのだろうか?もしロボットがあなたの仕事を奪えば、別の仕事が必ずやってくる。この立場の支持者は、ジェレミー・リフキンの『仕事の終わり』やスタンレー・アロノヴィッツとビル・デファジオの『雇用なき未来』といった作品を生み出した1990年代のような、自動化に対する不安の過去の波を指摘することができる17。早くも1948年には、数学者でサイバネティシストのノーバート・ワイナーが、その著書『サイバネティクス』の中で、「第二のサイバネティック産業革命」において、「平凡な業績かそれ以下の平均的な人間には、誰かが金を出して買う価値のある売り物が何もない」社会に近づいていると警告している18。確かに多くの仕事がオートメーション化によって失われ、失業率は景気循環とともに上下してきたが、これらの著者の多くが予期していたような、極度の大量失業という社会的危機は到来していない。
もちろん、このような議論は学問的な高みからしかできないことであり、最終的に新しい仕事を見つけられるかどうかにかかわらず、職を奪われた実際の労働者に生じる痛みや混乱を無視したものである。そして主流派の中にも、もしかしたら今回は本当に違うのではないかと疑っている者がいる。ノーベル賞受賞者でニューヨーク・タイムズ紙のコラムニストであるポール・クルーグマンは、こうした疑念を口にする最も著名な人物であろう19。しかし、従来の分析のより深い問題は、実際には社会的・政治的選択であるにもかかわらず、そのプロセスを科学的必然として提起していることである。
今日、ほとんどの労働争議は、賃金・手当の引き上げや労働条件の改善に焦点が当てられている。しかし、1930年代の世界恐慌が起こるまで、社会主義運動や労働運動は、労働時間の漸進的な短縮を求めて闘い、それを勝ち取った。19世紀には、10時間労働運動は8時間労働運動に道を譲った。1930年代にも、アメリカ労働総同盟は週労働時間を30時間に短縮する法律を支持した。しかし、第二次世界大戦後、さまざまな理由から、労働時間の短縮は労働組合の課題から徐々に消えていった。週40時間(またはそれ以上)労働は当然のこととされ、問題は単にそれをどれだけ補償するかということになった。
これには経済学者ジョン・メイナード・ケインズも驚いたことだろう。彼は1930年代に、現代人は週15時間しか働かないだろうと推測していた。これは、現在でも広く標準とされている週40時間労働の3分の1以下しか働いていないことを意味する。しかし、ケインズの時代から生産性は3倍以上になったのだから、その成長を大衆の自由な時間という形で取り込むことは可能だったはずだ。それが実現しなかったのは、技術的に不可能だからではなく、20世紀の政治的選択と社会的闘争の結果のためである。
スマートフォン、薄型テレビ、インターネットなど、ケインズが想像もしなかったような現代社会のあらゆる装備が可能になったからだ。というのも、多くの人が労働時間の短縮を考えるとき、スマートフォンやテレビのような、先進資本主義社会で享受しているものを手放さなければならないと考えるからだ。
労働時間の短縮の程度にもよるが、それはある程度正しいかもしれない。しかし、労働時間を短縮することは、生活費を削減することにもつながる。なぜなら、そうしなければ誰かにお金を払ってやってもらわなければならないことをする時間を確保し、働くためだけに支払わなければならない通勤費などのコストを削減することができるからだ。そしてそれ以上に、現在の社会は、人間の繁栄には何の役にも立たず、誰かの収益を豊かにするためだけに存在する仕事であふれている。例えば、学生ローンの徴収(教育が無料であれば存在しない)や、危険で不安定な投機を助長する多くの大手銀行の役職などである。
いずれにせよ、労働削減を社会的な優先課題とするならば、生産性の向上に合わせて労働時間を徐々に減らしていくことで、同じ生活水準を享受しながら徐々に労働時間を減らしていくことができる。そして、より多くのものを蓄積するために、より多く働き続けることを好む人もいるかもしれないが、おそらく他の多くの人はそうではないだろう。純粋なポスト・ワーク・ユートピアには到達できなくても、それに近づくことはできる。労働時間を週40時間から30時間に減らせば、その方向に進むだろう。ユニバーサル・ベーシック・インカムのようなものもそうだろう。労働や、従来の福祉制度に付随するその他のしがらみに関係なく、すべての国民に最低限の支払いを保証するものだ。
気晴らしの技術としてのテクノフィリア
長期的に見れば、オートメーションがもたらす政治的な疑問や可能性が現実的なものであると仮定しても、短期的にはもっと重大な課題に直面しているということは十分に主張できる。前述したように、経済を動かすのに実際に必要な労働者数を示す生産性の伸びは、実際、近年かなり低迷している。さらに、近年の景気後退後に雇用が伸びなかったのは、ロボットのせいではなく、政府の政策の失敗のせいだと考えるのが妥当だろう。
というのも、短期的には、雇用の不足は自動化のせいではなく、経済学者の専門用語で総需要と呼ばれるものの不足のせいだと考えられるからだ。言い換えれば、雇用主が労働者を増やさないのは、彼らの製品を買う人が足りないからであり、人々が製品を買わないのは、お金が足りないからである。
伝統的なケインズ派の経済理論によれば、この状況の解決策は、政府が金融政策(金利の引き下げ)、財政政策(インフラ整備などによる雇用創出への政府投資)、規制(最低賃金の引き上げなど)を組み合わせて需要を増やすことである。大不況後、政府は金利を引き下げたが、雇用創出への十分な投資と組み合わせては行わなかったため、生産高、つまり財やサービスの生産量は緩やかに再び伸び始めたが、雇用は不況前の水準に戻らなかったという「雇用なき回復」につながった。
私は、伝統的なケインズ的救済策が重要で必要であることに異論はない。また、政治的中心地や右派が、失業者の短期的問題から注意をそらすために、ロボットの未来の亡霊を利用し、あたかも大量の失業や不完全雇用が不可避であるかのように見せかけることがある、という懸念も共有している。
しかし私は、より高度に自動化された未来が私たち全員にとって何を意味するかについて語る価値はあると思う。その理由のひとつは、懐疑論者とは反対に、生産性統計に反映されるような形でまだ経済に浸透していないとしても、さらなる省力化技術の可能性は急速に開発されていると思うからだ。また、緊縮経済と不十分な政府刺激策という短期的な障害を乗り越えたとしても、産業革命以来私たちが直面してきた政治的な問題に直面することになるからだ。新しい生産技術は、すべての人の自由な時間を増やすことにつながるのか、それとも、生産性の向上が一部の人だけに利益をもたらし、残りの人はこれまで以上に長く働くというサイクルに閉じ込められたままなのか。
気候危機の恐怖
ここまでは、冒頭に挙げた課題のうち、労働者を置き去りにするテクノロジーがもたらす脅威についてだけ述べてきた。しかし、2つ目の課題である生態系の危機は、資本主義と人類の将来にとって、少なくとも同じくらい重要である。気候変動に関する科学的コンセンサスは明らかだ。人類が排出する炭素が大気を温暖化し、気温の上昇、異常気象、水やその他の必須資源の不足を引き起こしている。見解の相違は主に、その影響がどの程度深刻なのか、人類文明にとってどの程度の破壊的影響があるのか、そしてその破壊的影響にどのように(あるいはどのように)適応できるのか、という点にある。
人為的な気候変動の存在を完全に否定する人々もいるからだ。このような人々は確かに存在し、非常に懐の深い企業利益に支えられており、主要政党の中にも著名な支持者がいる。しかし、こうした人々を真剣な科学的議論の支持者とみなすのは間違いである。否定派の理論を推進する作家や科学者のごく一派は、真理を追求するという主張において誠実であるかどうかは別として、彼らの資金提供者は、彼らの行動が別のアジェンダを推進する皮肉屋と見なさなければならない。
後の章で述べるように、気候変動をめぐる重要な問題は、気候変動が起きているかどうかではなく、誰が気候変動を生き延びるかである。最悪のシナリオであっても、科学者たちは地球がまったく住めなくなるとは主張していない。実際に起こっていることだが、生息地の劣化に伴い、空間と資源をめぐる争いが激化するだろう。このような状況の中で、そして特に上述の技術的トレンドと相まって、一部のエリートが地球を汚染し続け、自分たちの快適さを守りつつ、世界人口の大半を不幸に追いやることが可能になるかもしれない。企業の巨頭を否定主義の方向へと駆り立てるのは、気候科学に真剣に取り組むことではなく、このアジェンダなのだ。
しかし、すべての資本家が否定論に傾倒しているわけではない。気候変動の大きさを認めながらも、解決策をもたらす自由市場の働きを信頼できると主張する者もいる。しかし、これは全く馬鹿げているわけではないが、非常に誤解を招きやすい。啓蒙的なエコ資本主義者たちは、実際には愚鈍な否定論者とさほど変わらないことが判明したからだ。
起業家たちは、政府の介入なしに化石燃料依存から脱却するための新たなグリーンテクノロジーを見つけるだろうと私たちは確信している。しかし、多くの場合、こうした技術革新には、富裕層しかアクセスできないハイテク・グリーン・ソリューションが関わっている。同時に、炭素への課税のように、表向きは「市場」による解決策であっても、真にグローバルな解決策は拒否される。エコ資本主義者たちを興奮させる構想は、その代わりに「地球工学」の空想的なプロジェクトであり、気候を操作しようとするものである。コーク兄弟やその否定論者たちと同様、エコ資本主義者たちは、たとえ環境保護主義者の皮を被ったとしても、エリートの特権とライフスタイルを守ることを第一に考えている。これらについては第4章で触れる。
次に、本書の具体的な目的に話を移そう。
司令塔としての政治
読者は、なぜオートメーションとポストワークの未来について別の本を書く必要があるのかと尋ねるかもしれない。ブリンヨルフソンとマカフィーはその一例に過ぎない。その他にも、フォードの『Rise of the Robots(ロボットの台頭)』や、アトランティックのデレク・トンプソン、スレートのファルハド・マンジュ、マザー・ジョーンズのケヴィン・ドラムの記事などがある20。それぞれが、テクノロジーが急速に仕事を時代遅れにしつつあると主張しているが、テクノロジーが不平等を拡大するのではなく、繁栄を共有することにつながることを確認するという問題への答えに空回りしている。せいぜい、ブリンジョルフソンやマカフィーのように、リベラル派のお決まりの文句に引き戻されるのが関の山だ。起業家精神と教育があれば、たとえ現在の仕事がすべて自動化されたとしても、われわれ全員が繁栄することができるというのだ。
これらの説明の中で欠けているもの、私がこの議論に入れたいものは、政治、特に階級闘争である。ルーズベルト研究所のマイク・コンザールが指摘しているように、ポストワークの未来予測は、「繁栄が再分配をもたらし、余暇と公共財をもたらす」という「過去のケインジアン・フォーディズムの前方投影」である、ぼんやりとした技術主義的ユートピア主義に向かいがちである21。従って、移行は場所によっては困難かもしれないが、最終的には技術開発の加速に満足し、あらゆる可能な世界の中ですべてが最善になると安心すべきなのだ。
このような見方は、資本主義階級と財産関係という、現在私たちが生きている社会の中心的な特徴を無視している。自動化によって誰が得をし、誰が損をするかは、結局のところ、ロボットそのものではなく、誰がロボットを所有するかということの結果なのだ。したがって、両者を媒介する第三の危機、すなわち資本主義経済の危機を理解することなしに、生態系の危機とオートメーションの発展を理解することは不可能である。気候変動もオートメーションも、それ自体を問題(あるいは解決策)として理解することはできないからだ。むしろ危険なのは、利益と成長を最大化することに専心し、資金と権力がごく一部のエリートの手に握られている経済において、それらがどのように顕在化しているかということである。
世界における富と所得の不平等の拡大は、活動家、政治家、識者からますます注目されるようになっている。「ウォール街を占拠せよ」は、「われわれは99%だ」というスローガンで衝撃を与え、ここ数十年の経済成長による利益のほとんどすべてが、人口の1%以下にもたらされているという事実に注目を集めた。経済学者のトマ・ピケティは、富の歴史とますます不平等になっていく世界についての大著『21世紀の資本』で、まさかのベストセラーを記録した22。
これまで述べてきた2つの危機も、基本的には不平等に関するものである。希少性と豊かさの分配について、誰が生態系へのダメージのコストを負担し、誰が高度に生産的で自動化された経済の恩恵を享受するかについてである。人類が地球の気候に与える影響に対処する方法はあるし、オートメーション化によって、多くの人々が困窮し絶望するのではなく、すべての人々に物質的な繁栄をもたらすようにする方法もある。しかし、そうした可能性のある未来には、20世紀後半までに世界的に支配的となった経済システムとはまったく異なる種類の経済システムが必要となる。
4つの未来
映画学者トム・アンダーセンは、映画におけるロサンゼルスの表現について3時間にわたって考察した『Los Angeles Plays Itself』の中で、「ドキュメンタリーのドラマ性を評価することができるのであれば、フィクション映画のドキュメンタリーの啓示を評価することもできるだろう」と述べている23。
本書は通常のノンフィクションではないが、フィクションでもない。むしろ、社会科学の道具と推理小説の道具を組み合わせて使い、未来の政治的対立がどのような可能性の中で展開されるかを探ろうとする試みである。これは一種の「社会科学フィクション」である。
社会科学とSFを区別する一つの方法は、前者が現存する世界を描写するものであるのに対し、後者はあるかもしれない世界を推測するものだということだ。しかし実際には、どちらも想像力と経験的調査の混合物であり、異なる方法で組み合わされている。どちらも経験的な事実や生きた経験を、抽象的で直接には知覚できない構造的な力によって形作られたものとして理解しようとしている。
ある種の推理小説は、社会構造や政治経済の特殊性に他のものよりも敏感である。『スター・ウォーズ』では、銀河の政治経済の詳細にはあまり関心がない。ジョージ・ルーカスが『スター・ウォーズ』の前日譚を映画化した際に行ったように、作者がそれを具体化しようとしても、ストーリーを台無しにするだけだ。一方、スタートレックのような世界では、このような細部は実際に重要である。『スター・ウォーズ』と『スター・トレック』は、表面的には似たような宇宙旅行や冒険物語のように見えるかもしれないが、根本的に異なるタイプのフィクションである。前者は登場人物と神話的な物語のためだけに存在し、後者は豊かで論理的に構成された社会世界に登場人物を根付かせようとする。
これは、SFファンの間で慣例的に行われている「ハード」SFと「ソフト」SFの区別に関連しているが、それを超越している。前者は現在の科学に根ざしているため、より説得力があるとされる。しかしこの区別は、このジャンルの伝統的なファン層の偏見と、自然科学に対するフェティシズムを反映している。より重要なのは、先ほど述べたように、世界構築に真剣に取り組んでいる物語と、そうでない物語の違いである。ソフト・サイエンス・フィクションと呼ばれるものは、スター・ウォーズ風の冒険物語に過ぎないこともあるが、社会科学をより豊かに利用していることもある。一方、「ハード」とされるものの多くは、物理学の詳細な釈明と、社会関係や人間行動についてのナイーブな、あるいはまったくありきたりの理解とを対にしている。ケン・マクラウドの小説『フォール・レボリューション』は、政治的動乱と宇宙植民地化の物語であるが、マルクス主義政治経済学の理解と、1970年代のスコットランド社会主義運動における彼の個人的背景に根ざしている。宇宙旅行や火星のテラフォーミングの物理学に対する特別な洞察というよりも、そのような基盤が小説に「硬さ」を与えているのだ。
社会分析や批評の道具としての推理小説は、メアリー・シェリーの『フランケンシュタイン』でなくとも、少なくともH・G・ウェルズの『タイムマシン』まで遡るが、この分野は近年特に豊かさを増している。大衆文化においては、『ハンガー・ゲーム』や『ダイバージェント』のようなディストピアのヤングアダルト小説が大成功を収めている。しかし、そのような物語は、我々がすでに生きている階級社会のかなり透明な寓話である一方で、境界線をさらに押し広げ、現在のトレンドの長期的な影響について推測している他の人々を見つけるのは難しくない。現実と可能性の接点は、ウィリアム・ギブスンの21世紀初頭の連作小説(『パターン認識』、『スプーク・カントリー』、『ゼロ・ヒストリー』)や、コーリー・ドクトロウの『ホームランド』(および近刊の『ウォーカウェイ』)のように、現在のほんの数歩先に物語を置く作家たちの近未来小説に最も強く現れている。情報技術、オートメーション、監視、生態系破壊の重要性は、本書を通して繰り返し語られるテーマである。
さまざまな想像の世界が持つ政治的意味合いもまた、前面に押し出され始めている。チャールズ・ストロスは社会派SF作家であると同時に、より社会科学的なブロガーでもある。彼は特に、人気のある「スチームパンク」サブジャンルを批判している。彼は、スチームパンクが、ゼッペリンや蒸気で動くガジェットでいっぱいの、ある種理想化された19世紀を提示しているが、その時代の重要な社会関係、つまり労働者階級のディケンズ的な悲惨さや植民地主義の恐ろしさには目をつぶっていると指摘している。しかし、ストロスや、ケン・マクラウドやチャイナ・ミエヴィルのような他の作家たちは、未来や過去、そして代替世界に関するフィクションを用いて、階級や社会的対立の全体像を描き出している。
私に言わせれば、フィクションの未来は、未来を直接予測しようとする「フューチャリズム」の作品よりも好ましく、その本質的な不確実性と偶発性をあいまいにし、それによって読者を茫洋とさせる。本書で論じる分野では、レイ・カーツワイルのような人物が典型的なフューチャリストである。彼は2049年までにコンピュータが人間のような知能を獲得し、世界を変えるようなあらゆる結果をもたらすと自信満々に予言している24。SFは未来論にとって、陰謀論にとっての社会理論と同じようなものである。別の言い方をすれば、一般から一般へ(未来論)、あるいは特定から特定へ(陰謀論)を試みるよりも、特定から一般へ(社会理論)、あるいは特定から一般へ(SF)を導き出す説明を読む方が、常に興味深いのである。
20世紀初頭の偉大な社会主義理論家であり組織者であったローザ・ルクセンブルクは、「ブルジョア社会は、社会主義への移行か野蛮への後退かの岐路に立っている」というスローガンを広めた25。本書では、2つの社会主義と2つの野蛮主義という、2つではなく4つの可能な結末を提案する。社会学者マックス・ウェーバーが「理想型」と呼んだもので、社会がどのように組織されうるかを単純化した純粋なモデルである。もちろん、現実の社会は常にもっと複雑であるが、理想型のポイントは、他の問題はさておき、特定の問題に焦点を当てることである。
その目的は、私たちの現在を理解し、その先にある可能性のある未来を定型化した形で描くことである。基本的な前提は、経済のあらゆる領域で自動化が進む傾向が続くということである。さらに、20世紀にほとんどの経済学者が仮定したような、機械化によって一部の仕事がなくなっても、その損失を補うだけの十分な数の新しい仕事が市場から自動的に生み出されるというような仮定はしない。
つまり、機械化によって一部の仕事がなくなっても、市場はそれを補って余りある新しい仕事を自動的に生み出すというものだ。理想的なタイプで仕事をするという精神に則り、私は可能な限り強い仮定を立てることにする。実際、映画『マトリックス』のように機械が人間を支配するのではなく、機械が人間に奉仕する世界を想像しているのであれば、これは論理的には不可能である。私たちは、機械を管理・維持するために、少なくとも少しは仕事をしなければならないだろう。
しかし、産業革命以来、左派を悩ませてきた議論、つまり生産手段を支配する資本家ボスがいないポスト資本主義社会では、どのように労働と生産を管理するかという議論に巻き込まれないようにするために、私は人間の労働をすべて排除すると仮定している。これは重要な(そして現在進行中の)議論であるが、それを脇に置くことができれば、私の問題意識はより明確になるだろう。したがって、私の方程式における不変のものは、技術革新が完全な自動化に向かう傾向にあるということである。
自動化が定数であるならば、生態系の危機と階級権力は変数である。エコロジーの問題は、多かれ少なかれ、気候変動と資源枯渇の影響が最終的にどの程度になるかということだ。最良のシナリオでは、再生可能エネルギーへのシフトが気候変動を改善し、逆転させる新しい方法と組み合わされ、実際、すべての人に高水準の生活を提供するために、すべてのロボット技術を使用することが可能になる。言い換えれば、そのスペクトラムは欠乏から豊かさへと変化する。
階級権力の問題は、今日の世界における富、所得、政治権力の巨大な不平等に最終的にどう取り組むかということに帰着する。富裕層が権力を維持できる限り、私たちは彼らが自動生産の恩恵を享受する一方で、それ以外の人々は生態系破壊の代償を払う世界に住むことになる。私たちがより平等な世界に向かうことができる限り、未来は犠牲の分かち合いと繁栄の分かち合いの組み合わせによって特徴づけられるだろう。
つまり、このモデルでは、ヒエラルキーか平等のどちらかと並んで、欠乏か豊かさのどちらかの世界に行き着く可能性があると仮定している。その結果、4つの組み合わせが可能になり、2×2のグリッドとして設定することができる。
| 豊かさ | 希少性 | |
| 平等 | 共産主義 | 社会主義 |
| ヒエラルキー | レンタリズム | 絶滅主義 |
このような演習は前例がないわけではない。似たような類型論は、ロバート・コスタンザが1999年に『Futurist』に寄稿した記事にもある26: 「スタートレック」、「大きな政府」、「エコトピア」、「マッドマックス」である。しかしコスタンザにとって、2つの軸は「世界観と政策」と 「世界の現実」である。例えば、「大きな政府」のシナリオでは、「技術懐疑論者」が無限の資源という現実を否定するため、安全基準によって進歩が抑制される。
この議論に対する私の貢献は、資本主義と政治の重要性を強調することである。生態学的限界の可能性と階級社会の政治的制約の両方が、この見解では「物質的」制約である。そして、両者の相互作用こそが、私たちの進むべき道を決定するのである。
したがって、資本主義が階級権力のシステムとして存在し、支配エリートがいかなる可能性のある未来にも自らを維持しようとすることは、本書の中心的な構成テーマであり、高度に自動化されたポスト工業経済の軌跡を理解しようとする他のほとんどすべての試みには欠けているテーマであると私は考える。技術開発は社会変革の背景を与えるが、それが直接的に決定することはない。変化は常に、組織化された大衆間の権力闘争によって媒介される。問題は、誰が勝ち、誰が負けるかであり、コスタンザのような技術主義的な著者が言うように、世界の客観的性質について誰が「正しい」見解を持っているかということではない。
だから私にとって、複数の未来をスケッチすることは、政治的なものや偶発的なもののための場所を残す試みなのだ。私の意図は、外から現れる技術的・生態学的要因の魔法のような働きによって、ひとつの未来が自動的に現れると主張することではない。むしろ、私たちが行き着く先は政治的闘争の結果であると主張することである。SFと政治の交錯は、昨今、リバタリアン右派とその決定論的なテクノ・ユートピア幻想と結びつけられることが多いが、私は、想像力豊かな思索を政治経済と混ぜ合わせるという左派の長い伝統を取り戻したいと考えている。
この分析全体の出発点は、資本主義が終焉を迎えるということであり、ルクセンブルクが言ったように、それは「社会主義への移行か、野蛮への退行か」のどちらかである27。したがって、この思考実験は、復活した左翼が成功すれば到達できるかもしれない社会主義と、失敗すれば追いやられるかもしれない野蛮について、意味を理解しようとする試みである。
これは、資本主義に確固とした終末期日を設定する世俗的終末論に関与することを意味するものではない。「資本主義」や「社会主義」といった社会システムのレッテルは抽象的なものであり、一方が他方に変わるという決定的な瞬間はない。私の考えは、社会学者ヴォルフガング・シュトレックに近い:
資本主義の終わりについて私が抱くイメージは、すでに終わりつつあると信じているが、それは、それ自身の理由と、実行可能な代替案の不在にかかわらず、慢性的に荒廃している社会システムのイメージである。資本主義がいつ、どのように消滅し、何がそれを引き継ぐのかは正確にはわからないが、重要なのは、経済成長、社会的平等、金融安定の3つの下降傾向を逆転させ、それらの相互強化に終止符を打つと期待できるような力が手元にないということである28。
以下の4つの章は、それぞれ共産主義、賃借主義、社会主義、絶滅主義という4つの未来のうちの1つを取り上げている。もっともらしい未来を描くだけでなく、4つの章はそれぞれ、われわれが今生きている世界に関連し、その特定の未来において特別に重要な意味を持つであろう重要なテーマを強調している。
共産主義の章では、生活が賃金労働を中心としない場合の意味の構築の仕方や、資本主義という支配的な物語によって構成されなくなった世界ではどのような階層や対立が生じるかについて触れている。レントイズムの描写は、主に知的所有権についての考察であり、私有財産の形態が、我々の文化や経済を導く非物質的なパターンや概念により多く適用されたときに何が起こるかを描いている。社会主義の物語は、気候危機とそれに適応する必要性についての物語であると同時に、自然界と市場に関するいくつかの古い左派のしきたりが、資本主義を超えた生態学的に安定した世界を構築しようとする試みに、自然界のフェティシズム化も市場の憎悪も必ずしも十分でなく、関連性すらないことを見抜く妨げになっていることについての物語でもある。最後に、絶滅主義の物語は、世界の軍事化の物語である。この現象は、中東における終わりのない戦争から、アメリカの都市の路上で警察に射殺される黒人のティーンエイジャーまで、すべてを包含している。
私たちはすでに、20世紀に私たちが理解したような産業資本主義から急速に離れつつあり、その方向に戻る可能性はほとんどない。私たちは不確実な未来へと向かっているのだ。私は、その未来について幅広い文脈を提供したいと願っているが、確実だという感覚を作りたいわけではない。私は、SF作家であると同時に「未来学者」というレッテルを貼られているデヴィッド・ブリンが、「可能性よりも可能性を探ることに興味がある。」
見込みよりも可能性を評価することの重要性は、われわれの集団行動を中心に据えることである。同じエッセイの中で、ブリンはジョージ・オーウェルの『1984年』を「自己予防的予言」として引用しているが、これは同書が描いたシナリオが実現するのを防ぐのに役立った。対テロ戦争と元NSA(国家安全保障局)分析官エドワード・スノーデンのNSA監視に関する情報公開を受け、その特定の予言がどれほど自己予防的であったかを疑問視することはできるが、一般的な指摘は正しい。
本書が、記述された抑圧的な未来を自己予防し、その平等主義的な代替案を自己実現させることに少しでも貢献するのであれば、本書はその目的を果たしたことになる。
4 絶滅主義:ヒエラルキー
そして希少性
ニール・ブロムカンプ監督の2013年の映画『エリジウム』は、2154年のディストピア的な地球を描いている。1パーセントの少数エリートが、エリジウムと呼ばれる宇宙ステーションに逃げ込んだ。そこでは、奇跡的な「メドベイ」テクノロジーを利用できるため、彼らは快適で悠々自適な生活を楽しんでいる。一方、地球に戻った残りの人類は、ロボット警察によって統治され、混雑した汚染された惑星で暮らしている。筋書きの中心は、放射能に汚染された地球に住む人々のひとり、マックス(マット・デイモン)が、エリジウムの聖域に侵入し、その驚異的な医療技術にアクセスしようとすることだ。
エリジウムの政治経済を映画から抽出するのはやや難しいが、示唆に富むテーマがいくつか浮かび上がってくる。最も重要なのは、エリジウムの富裕層が経済的に地球に依存しているようには見えないことだ。映画の冒頭でマックスが働き、エリジウムのエリートの一人が経営する工場が登場する。しかし、その工場の目的は、単に兵器やロボットの生産であり、その目的は地球の人口をコントロールすることにあるようだ。ほとんどの場合、地球の住民はプロレタリアートというより、強制収容所の収容者のように見える。したがって、エリジウムの政治経済は、例えば『ハンガー・ゲーム』のような、首都パネムの高級なライフスタイルが、貧困層が必要不可欠な日用品を生産する周辺の「地区」によって支えられているのとは異なる。
『エリジウム』の結末は、富裕層のライフスタイルが一般化され、すべての人に贅沢と不老不死がもたらされることを示唆している。しかし、これは決して一義的なものではない。前章で私は、もしこのようなポスト欠乏社会が階級階層の中で生まれるとしたら、それは知的財産を中心としたレンティア経済の形をとる可能性が高いと示唆した。つまり、欠乏はすべての人にとって完全に克服することはできないが、一部のエリートにとっては克服することができるという世界である。
少数者のための共産主義
皮肉なことに、エリジウムのバブルの中で享受される生活は、数章前に描いた共産主義のシナリオとあまり変わらないように見える。もちろん、違いは少数者のための共産主義であるということだ。そして実際、現代の経済にはすでにこのような傾向が見られる。チャールズ・ストロスが指摘しているように、大金持ちはほとんどの商品が実質的に無料の世界に住んでいる。つまり、彼らの富は、食費、住居費、旅行費、その他の快適さに比べて非常に大きいため、何かのコストを考える必要がほとんどないのだ。欲しいものは何でも手に入る。
大金持ちにとって、世界のシステムはすでに先に述べた共産主義に似ている。もちろん、彼らのポスト欠乏状態は、機械だけでなく、世界の労働者階級の労働力によって実現されているという違いはある。しかし、将来の発展に対する楽観的な見方(私が共産主義と表現した未来)は、最終的には、ある意味で私たち全員が1%の人間であるという状態になるというものだ。ウィリアム・ギブスンの有名な言葉にあるように、「未来はすでにここにある。」
しかし、もし資源やエネルギーがあまりにも不足しすぎて、富裕層が現在享受しているような物質的な生活水準をすべての人が享受できないとしたらどうだろう。生産に大衆プロレタリアートの労働力をもはや必要としないが、すべての人に恣意的に高い消費水準を提供することができない未来がやってくるとしたらどうだろう。もし私たちが平等主義社会としてそのような世界に到達すれば、私たちのシステムは前節で述べた社会主義的な共有保全体制に似てくるだろう。しかし、その代わりに、特権階級のエリートと社会的弱者との二極化した社会のままであれば、最も妥当な軌道はもっと暗いものにつながる。富裕層は、レプリケーターやロボットがあらゆる必要を満たしてくれるという知識に安心して座っている。残りの私たちはどうなるのだろうか?
ヒエラルキーと乏しい資源の世界において、生産の自動化がもたらす大きな危険は、支配者であるエリートの立場からすれば、多くの人々を不要な存在にしてしまうことだ。資本主義と対照的に、資本と労働の対立は、利害の衝突と相互依存の関係の両方によって特徴づけられていた。
実際、過去の多くの社会主義運動に希望と自信を与えたのは、この相互依存関係だった。ボスは我々を嫌っているかもしれないが、彼らは我々を必要としている。労働者・社会主義者の古いスタンダードである『連帯は永遠に』では、労働者の勝利は避けられないとされている。ロボットの台頭により、第二の路線は成り立たなくなった。
貧困に喘ぎ、経済的に余剰な有象無象の存在は、支配階級に大きな危険をもたらし、支配階級は当然、差し迫った収奪を恐れる。この脅威に直面した場合、少なくとも資源の制約がそれほど大きくないのであれば、富裕層が社会福祉プログラムの形で富を分配することで、ある程度の資源の再分配を行い、大衆を買収することができる。しかし、富裕層の生活に再び欠乏をもたらす可能性があることに加え、この解決策は、大衆の側からの要求がますます高まり、収奪の恐怖が再び高まることになりかねない。
これは本質的に、大恐慌と第二次世界大戦の後、福祉国家の最盛期に起こったことである。しばらくの間、強力な社会的給付と強力な労働組合は、高収益と急成長と重なり、労働と資本は不安な平和を享受した。しかし、まさにその繁栄が、労働者が労働条件についてより多くの権力を要求するようになるという状況を招き、その結果、ボスは利益と職場支配の両方が自分たちの手から滑り落ちることを恐れ始めた。資本主義社会では、これは避けることのできない緊張関係である。ボスは労働者を必要としているが、同時に労働者の潜在的な力を恐れているのだ。
では、大衆が危険ではあるが、もはや労働者階級ではなく、したがって支配者にとって何の価値もない場合はどうなるのだろうか?やがて誰かが、彼らを排除した方がいいという考えに至るだろう。
絶滅の最終手段
1980年、マルクス主義の歴史家E・P・トンプソンは、「文明の最終段階である絶滅主義についてのノート」と呼ばれる、冷戦と常に存在する核兵器による消滅の脅威を振り返るエッセイを書いた。軍拡競争と軍備増強を、ソ連の計画経済であれ、アメリカの資本主義市場であれ、争っている側のより大きな政治経済を守るための単なる道具として理解するのは不十分だと彼は考えた。豊かな資本主義諸国では、軍産複合体が経済に占める割合がますます大きくなっており、ソビエトも同様に軍備増強にますます夢中になっていた。
トンプソンは、この社会形成を理解するために新しいカテゴリーが必要だと提案した。彼は『哲学の貧困』からマルクスの有名な一節を引用している: 「つまり、ある社会の中心的な経済関係が変化すると、その社会におけるすべての社会関係もそれに伴って変化する傾向があるということだ。トンプソンは、軍産主義の論理に立ち向かいながら、「人間を絶滅させる手段を粉砕するために、今まさに働いている悪魔のような工場から、われわれは何を与えられているのか」と問いかける。彼の答えは、必要なカテゴリーは「絶滅主義」であるというものだった。この用語は、「経済、政治、イデオロギーの中で、程度の差こそあれ、社会を、その結果が多数の絶滅でなければならない方向へと突き動かす、社会のこれらの特徴」をカバーしている4。
トンプソンが論じた具体的な構図はほとんど消滅した。軍国主義的な新保守主義者などが、ロシアや中国との大国間対立を懐古的に再現しようと精一杯努力しても、トンプソンの頭にのしかかった核の恐怖の影とは比べものにならない。そこで私は、トンプソンの言葉を再利用して、別の秩序、つまり私が想定する4つの社会の最後の秩序を説明することにした。しかし、私が説明するのは、それにもかかわらず、「その結果が多数の絶滅でなければならない方向に……突き進む」もう一つの種類の社会である。
トンプソンがエッセイを書いた当時と同じように、軍事予算がアメリカ経済に占める割合はほとんど変わらない。しかし、いわゆる「対テロ戦争」の時代を特徴づける紛争は非対称的なものであり、技術的に進歩した軍隊が弱小国家や無国籍の反乱軍と戦うものである。このような舞台で学んだ教訓は自国に持ち帰られ、国内警察活動の軍事化にもつながっている。
支配階級がもはや労働者階級の労働力の搾取に依存しない世界は、貧しい人々が単に危険で不便なだけの世界である。彼らを取り締まったり抑圧したりすることは、結局のところ、正当化できないほど面倒なことに思える。「大群衆の絶滅」への突き進みはここに端を発している。その究極の終着点は、文字通り貧民の絶滅であり、そうすることで、最終的に庶民は一掃され、富裕層はエリジウムで平穏無事に暮らすことができるのだ。
ノーベル経済学賞を受賞したワシリー・レオンティーフは、1983年の論文で、本書を通して考察されている大量失業の問題を予見していた。控えめな表現ではあるが、「少々ショッキングだが、本質的には適切な例え」として、彼は労働者を馬に例えている。
コンピュータ化され、自動化され、ロボット化された新しい機器の漸進的な導入が、労働の役割を減少させると予想される過程は、トラクターやその他の機械の導入が、農業における馬やその他の輓用動物をまず減少させ、次いで完全に駆逐した過程に似ていると言えるかもしれない5。
その結果、ほとんどの人が「人間から見れば、休んでいる馬をすべて飼うことは……ほとんど意味がない」という結論に達した。その結果、アメリカの馬の頭数は1900年の2150万頭から1960年には300万頭にまで減少した6。レオンティーフは続けて、人間は馬ではないのだから、社会のすべての構成員を支える方法は必ず見つかるはずだと、世紀半ばの技術者らしい朗らかな自信に満ちた言葉を述べている。ゴルツをはじめとする賃金労働の批判者たちと同じように、彼は「遅かれ早かれ……『雇用』の需要は、第一義的には『生活』、つまり所得の需要であることを認めざるを得なくなるだろう」と主張する7。しかし、今日の支配階級の侮蔑的で残酷な態度を考えれば、それを当然のことと考えることは決してできない。
幸いなことに、富裕層でさえ、最初の手段としてこの最終的解決策に手を伸ばすことを困難にする道徳規範を身につけている。彼らの最初の手段は、『エリジウム』の登場人物のように、貧しい人々から身を隠すことだ。しかし、私たちの周りでは、「過剰」な人口をただ集めて管理することから、彼らを永久に排除するための正当化へと、徐々に流れが変わっているのを見ることができる。
飛び地社会と社会統制
社会学者のブライアン・ターナーは、われわれは「飛び地社会」に生きていると主張している8。グローバリゼーションのもとで移動性が高まっているという神話にもかかわらず、われわれは実際には、「政府やその他の機関が空間を規制し、必要な場合には、囲い込み、官僚的障壁、法的排除、登録」といった手段によって、人、モノ、サービスの流れを固定化しようとする」秩序に生きている9。
もちろん、動きが制限されるのは大衆の動きであり、エリートは国際的で移動可能なままである。ターナーが挙げる例の中には、フリークエント・フライヤー・ラウンジや公立病院の個室など、比較的些細なものもある。金持ちのためのゲーテッドコミュニティ(あるいはもっと極端な例ではプライベートアイランド)や、貧乏人のためのゲットー(警察が貧乏人を「間違った」地域から締め出す責任を負っている)のような、より深刻なものもある。生物学的隔離や入国制限は、飛び地の概念を国民国家のレベルまで引き上げている。連邦刑務所であれ、グアンタナモ湾の収容所であれ、いずれの場合も、刑務所は従わない人々のための究極のディストピア的飛び地として立ちはだかる。ゲーテッド・コミュニティ、プライベート・アイランド、ゲットー、刑務所、テロ被害妄想、生物学的隔離、これらは逆グローバル収容所に等しく、富裕層は不幸の海に散らばる富の小島で暮らしている。
クリスチャン・パレンティは『カオスの熱帯』の中で、気候変動が生態系の変化、経済的不平等、国家破綻の「破滅的収束」と呼ぶものをもたらす中で、この秩序が世界の危機的地域でどのように生み出されているかを示している10。植民地主義と新自由主義の後、豊かな国々は貧しい国々のエリートたちとともに、傷ついた生態系から失われつつある恵みをめぐってさまざまな部族や政治的派閥が争い、無秩序な暴力への崩壊を促進してきた。この暗澹たる現実に直面した富裕層の多くは(世界的に見れば、富裕国の労働者の多くも含まれる)、無人偵察機や民間の軍事請負業者によって守られる要塞に閉じこもることを諦めた。賃借主義社会の特徴であるガードマン労働は、より悪質な形で再び登場し、幸運な少数の労働者が富裕層のために執行官や保護者として雇用されている。
しかし、飛び地の建設は貧しい地域に限ったことではない。世界各地で、富裕層は他の人々から逃れたいという願望を示している。2013年の『フォーブス』誌の記事によると、富裕層の間では、ますます精巧なホームセキュリティがマニアックになっている11。あるセキュリティ会社の幹部は、ロサンゼルスの自宅のセキュリティは「ホワイトハウス並み」だと自慢している。また、赤外線センサーや顔認識技術、有害な煙や唐辛子スプレーを噴射する防御システムを売り込む会社もある。これらはすべて、金持ちとはいえ、ほとんど匿名であり、自称攻撃者の目立つ標的とはなりにくい人々のためのものだ。被害妄想的に見えるかもしれないが、経済エリートの多くは、自分たちを社会の他の部分と戦争状態にある少数派とみなしているようだ。
シリコンバレーはそうした感情の温床であり、富裕層は「分離独立」について公然と語っている。サンフランシスコの遺伝子関連企業の共同設立者であるバラジ・スリニヴァーサンは、新興企業家の聴衆を前に、「テクノロジーによって運営される、アメリカ国外でのオプトイン社会を構築する必要がある」と語った。しかしこれは、余剰人口とみなされる人々から富裕層を締め出そうとする衝動を示している。
他の傾向は、オプトイン社会への移行ほど劇的なものではないが、それでも憂慮すべきものである。アメリカ全土で、裕福な地域の住民が、隣人の脅威から身を守るために民間の警備員を雇い始めている。オークランドでは、近隣住民の小グループが結束して警備員を雇い、ある地域ではクラウドファンディングで9万ドルもの資金を集めている13。
そして、大衆から身を隠すために都市全体を建設しようとする人々がすでにいる。ナイジェリアのラゴス沖では、レバノン人の開発者グループが25万人を収容する私設都市「エコ・アトランティック」を建設中だ。この都市は「持続可能な都市であり、クリーンでエネルギー効率に優れ、二酸化炭素の排出を最小限に抑える」14。また、エリートたちが、1日1ドル以下で暮らし、インフォーマル経済であえぐ近隣の何百万人ものナイジェリア人から逃れられる場所にもなる予定だ。2014年、マンハッタンの500万ドル以上の不動産売買の半数以上が、外国人か、ペーパーカンパニー(そのほとんどがアメリカ人以外と思われる)の背後にいる匿名バイヤーによるものだった15。こうした購入は、資金洗浄と詮索好きな政府からの隠蔽という2つの目的を果たすだけでなく、自国が不穏な状況に陥った場合の避難場所にもなる。
パラノイアと無味乾燥な消費の交差点に、「富裕層向け究極の生命保険ソリューション」をウェブサイトに掲げるビボスがある。同社はドイツの山に80戸の耐放射線メガバンカーを建設中だ。これは普通の防空壕ではなく、革とステンレスの装飾が施された高級アパートだ。創業者のロバート・ヴィチーノは『ヴァイス』のウェブサイトで、この複合施設を「地下ヨット」に匹敵すると表現している。わずか250万ユーロからで、あなたもスタイリッシュに黙示録を待つことができる。そしてヴィボスは、『フォーブス』誌が「億万長者のバンカー」産業と呼ぶものの一例にすぎない16。
飛び地からジェノサイドへ
2014年、富裕層への批判を1938年のナチス・ドイツにおけるユダヤ人襲撃事件「水晶の夜」になぞらえたベンチャーキャピタリストのトム・パーキンス17や、2015年のフィナンシャル・タイムズ紙の会議で、貧困層の反乱の予感に「夜も眠れない」と語ったカルティエの宝飾品担当重役ヨハン・ルパート18のような、常識外れの億万長者を、今日、私たちは笑いものにしている。超格差社会と大量失業の世界では、しばらくの間、大衆を買収し、その後、武力で抑圧しようとすることもできる。しかし、没落した大群が存在する限り、いつか彼らを抑えることが不可能になる危険性がある。大量労働が不要になったとき、最終的な解決策が潜んでいる。それは、富裕層による貧困層に対する大量虐殺戦争である。オートメーションの恐怖が再び立ち上がるが、その方法はまったく異なる。レントリズムのもとでは、オートメーションはますます多くの労働者を不要にし、不完全雇用と需要低迷に向かうシステムの傾向を強めるだけだった。駆逐社会は、抑圧と駆逐のプロセスを自動化・機械化し、支配者とその手下が自分たちの行動の結果から距離を置くことを可能にする。
しかし、抑圧から完全な絶滅へという最終的な動きは、本当にあり得るのだろうか?このような滑落は、イスラエルのパレスチナ占領のように、階級的対立が国家的対立と重なるところから始まる。かつてイスラエルは、安価なパレスチナ人労働力に大きく依存していた。しかし、政治経済学者のアダム・ハニエが実証しているように、1990年代後半以降、こうした労働者はアジアや東欧からの移民労働者によって居場所を奪われている19。こうしてパレスチナ人を労働者として不要にしたイスラエルは、シオニズムの入植者植民地プロジェクトの狂信的な側面を自由に行使できるようになった。2014年のガザ地区への攻撃では、病院、学校、発電所を空爆し、男性も女性も子供も無差別に殺し、住宅ストックの大部分を壊滅させたにもかかわらず、政府はほとんど笑えないような場当たり的な「自衛」を主張した。イスラエル議会の議員からは、大虐殺を公然と呼びかける声が上がった。その一人、アイェレト・シェイクは、「パレスチナ人全体が敵である」と宣言した。これを根拠に、彼女は「高齢者や女性、都市や村落、財産やインフラを含む」ガザ全体の破壊を正当化した20。
アメリカ人は、政治クラスがイスラエルのガザ戦争をほぼ一様に支持しているにもかかわらず、このような蛮行には無関心だと思うかもしれない。しかし、ノーベル平和賞を受賞したバラク・オバマ大統領はすでに、正当な手続きを踏まずにアメリカ市民を殺害する権利を主張している。彼の政府は、必ずしも身元を知らなくても標的を特定できるアルゴリズムの手法さえ使っている。
2012年、『ワシントン・ポスト』紙は「処分マトリックス」と呼ばれるものについての記事を掲載した21。これはオバマ政権の「次世代標的リスト」であり、テロリスト容疑者として匿名の無人機による暗殺の対象としてマークされたすべての外国人を追跡するために使われる、運命のスプレッドシートのようなものだ。この記事には、政府関係者の冷ややかなコメントが満載だった。そのうちの一人は、殺人ドローンは「芝刈り機のようなもの」で、テロリストを何人殺しても「草はまた生えてくる」と述べている。無期限殺害のプロセスを合理化するために、そのプロセスは部分的に自動化されている。『ポスト』紙は、いわゆる「『シグネチャー・ストライク』のためのアルゴリズム開発について報じている。『シグネチャー・ストライク』は、CIAと(統合特殊作戦司令部が)活動のパターンに基づいて標的を攻撃することを可能にするもので、殺されることになる人物の身元がはっきりしない場合であっても……」22。
このような行動は、かなりの数のアメリカ人に支持されている。悲しいことに、このように外国人あるいはそれ以外とみなされる人々の死に対する無関心は、長い間、米国の温暖化に対する反応を特徴づけてきた。しかし、この排外主義的な考え方は、国内でも反響を呼んでいる。アメリカでは、手に負えない余剰人口の排除を容認しようとする姿勢は、人種差別と密接に絡み合っている。このことは、現在200万人を収監している刑務所システムに見ることができる。そして、最高裁判事アンソニー・ケネディが、カリフォルニア州の刑務所の過密状態に関する意見の中で、「人間の尊厳という概念と相容れない」、「文明社会にはふさわしくない」と呼んだような状況で、しばしばそれが行われている23。
アメリカの刑務所制度は長い間、刑務所に収容される失業者を管理する一方で、刑務所の外に残る失業者を買収する手段であった。ルース・ウィルソン・ギルモアは、カリフォルニア州の刑務所システムを分析する中で、収容の大規模な拡大を「黄金の収容所」の建設と表現している24。社会サービスや仕事に恵まれない都会の若者たちは、警察の冷酷な標的にされ、強権的な薬物法とカリフォルニア州の「スリーストライク」条項の下で長期収容される。その結果、刑務所の建設が爆発的に増え、不況にあえぐ州の農村部に雇用がもたらされる。農作業が自動化されたり、超低賃金の出稼ぎ労働者にシフトしたり、非工業化によって製造業の仕事が失われたりする中で、刑務所の仕事はこれらの地域に残された最後の高賃金労働のひとつとなっている。
刑務所の量刑をアルゴリズムに委ねることで、管理者がこうした悲惨な倉庫の建設に積極的に関与していることを否定することができる。現在、アメリカの少なくとも20の州が、いわゆる「証拠に基づく量刑」を採用している。その名前は無害に聞こえる。誰が証拠の使用に反対できるだろうか?バージニア大学の法学教授であり、この方法の提唱者であるリチャード・レディングは、「透明性」と「完全な合理性」を欠く量刑手法を用いることは「非倫理的でさえある」とまで主張している25。しかし、レディング自身の説明によれば、証拠に基づく量刑に含まれる要素には、その人が犯した犯罪だけでなく、将来犯す可能性のある犯罪、すなわち「再犯の可能性を高める」「危険因子」と「犯罪発生的ニーズ」も含まれる。この時点で、こうした「将来の犯罪リスク」のモデルは、フィリップ・K・ディックの小説(後にトム・クルーズの映画)『マイノリティ・リポート』のディストピアに違和感を覚え始める。
今日、右派の一部でさえ、予算上の理由だけで、大量収容に疑問を呈している。しかし、囚人や刑務所ブームから利益を得ている労働者に実際に手当を支給する努力をしない限り、これらの余剰人口はどうなるのだろうか?刑務所に入ることができた者は、時に幸運な者である。すぐに暴力に訴える文化に染まっている警察は、軽微な犯罪やまったく犯罪のない容疑者を日常的に傷つけ、殺している。警察の残忍さは今に始まったことではないが、2つのことが変わった。警察がより軍事化し、より重武装になったことと、インターネットとビデオ録画機器の普及によって、警察の行動の記録化が容易になったことだ。
ラドリー・バルコは、警察の軍国主義化を「戦士警官」の出現と表現している26。SWATチーム(重武装した準軍事ユニット)は、もともとは高度な脅威への対応として推進されたが、今では日常的に配備されている。SWATによる急襲は、1970年代には全米で年間数百件だったが、今では毎日100~150件も行われている。多くの場合、こうした家宅捜索はマリファナ所持や賭博などの軽微な犯罪に対応している。また、免許証の検査などの「行政捜査」という名目で、令状なしに行われることもある。インターネット上では、こうした家宅捜索の様子を撮影したビデオをいくつか見ることができるが、数オンスのマリファナをめぐって重装備の大隊が誰かの家を襲撃するというシュールな恐怖が伝わってくる。
その結果、容疑者やその家族、あるいはSWATチームが間違った家に侵入してしまうというよくあるシナリオでは、容疑者ではない人々が次々と死傷することになる。2003年、57歳の公務員アルバータ・スプルイルが、ニューヨーク市警が匿名の情報だけに基づいて麻薬の売人のアパートと思われる場所に「閃光手榴弾」を投げ込んだ後、心臓発作で死亡した事件のような急襲を、彼は挙げている。
たとえ正しい住所を知っていたとしても、軍国主義化された警察の対応は、最初に警察を呼んだ人々でさえ意図しなかった混乱と破壊を引き起こす可能性がある。2015年のドキュメンタリー映画『ピース・オフィサー』は、元ユタ州保安官のダブ・ローレンスの物語である。彼の義理の息子が、ガールフレンドからの家庭内暴力の通報に端を発したにらみ合いの最中にSWATチームの警官に射殺され、警察批判者となったのだ27。
街頭レベルでも、特に黒人や褐色人種にとって、警察による暴力の脅威は絶えない。2014年7月、ニューヨーク市在住のエリック・ガーナーは、未課税の粗末なタバコを販売した容疑により、警官に首を絞められて死亡した。彼の死が騒動を引き起こしたのは、この事件が携帯電話のカメラに映っていたからでもあるが、あまりにも日常的なことに注目が集まったからでもある。その直後、マイク・ブラウンがミズーリ州ファーガソンの路上で射殺され、全国的な運動にさらに拍車がかかった。事件の正確な詳細については議論があるが、ブラウンが非武装であったこと、彼を撃った警官が通りを歩いていたという重大な犯罪をめぐって対立を始めたことは、誰もが認めるところである。これらの事件は、全米各地で起こった多くの類似事件と呼応し、長年にわたって絶え間なく続く暴力の鼓動となっている。例えば、オークランドではオスカー・グラントが警察によって処刑された。BARTの列車内で喧嘩があったとの通報で交通巡査に拘束された後、傍観者が携帯電話で撮影したビデオには、巡査がグラントに向かって人種差別的な言葉を叫び、彼が拘束されてホームにうつ伏せになった状態で射殺する様子が映っていた。これは、オークランドを占拠せよの重要な先駆けとなる抗議運動を引き起こした。
最近の警察の軍事化は、国家が黒人の自由と反戦運動を抑圧しようとした1960年代の社会的動乱にルーツがある。そして、警察が占領軍のようなものへと変貌を遂げることは、アメリカ帝国主義や海外での戦争主義の歴史と切り離すことができない。歴史家のジュリ ー・コーラー=ハウスマンは、「都市のジャングル」のイメー ジが、「都市の警察が貧しい地域社会で戦争のような包囲戦を繰り広げているという考えを、広く社会的に受け入れる」ことにつながったと、こうした闘争とベトナムそのものとの交差を述べている28。「テロとの戦い」の時代には、イメージだけでなく武器も戦場から家庭に流入し、軍事化のプロセスは加速している。
拡散的な文化的変化というよりも、軍国主義化された警察活動は、連邦政府が反テロリズムを口実に、地方警察を兵士に近づけるための意識的な国家戦略として理解されるべきである。警察官の多くは退役軍人で、イラクやアフガニスタンなどでの経験によって民間人の死に対して硬化している。アメリカ政府は、地域指向型警察サービス(COPS)プログラムを通じて、退役軍人を雇用する機関に優先的に助成金を支給することで、兵士から法執行機関への移行を奨励している。一方、彼らが使用するテクノロジー、つまり現在では小さな町でさえも通りを彩る巨大な装甲戦闘車両は、軍用品を再利用したものである。米国土安全保障省は、大小の警察署がこのような装備を購入できる「対テロ」補助金を交付している。また、イラクやアフガニスタンでの軍撤退によって余剰となった軍用品を配布する国防総省の1033プログラムに参加すれば、他の機関も同様の装備を無料で手に入れることができる29。
その結果、フロリダ州ハイ・スプリングス(人口5,350人)にMRAP(Mine Resistant Ambush Protected)車両が納入されるような不条理が起きている30。この重装甲の戦車のような車両は、もともとはイラクやアフガニスタンの反乱軍の爆発物から兵士を守るために使われたもので、フロリダ州中部では一般的に珍しいと考えられている。ハイ・スプリングスの警察署長が、MRAPを受け取ってから1年間は使用しておらず、他の機関に譲渡することを望んでいると報告したのは、当然といえば当然かもしれない。しかし、ファーガソンの映像に見られるように、他の警察署は戦車や防護服を喜んで配備している。ポール・バーホーベン監督の映画『ロボコップ』(1987)を思い起こさせるこの映像は、当時、軍国主義化された近未来のデトロイトを描いた、ばかばかしいほど大げさなディストピア映画だった。
戦士の警官は、単に電車に乗る人やタバコを売り歩く人、違法ギャンブラーや時折マリファナを吸う人にとって危険なだけではない。彼らの運命は、アメリカや世界中で見られるように、政治的動員の運命と結びついている。エジプトや中国のような権威主義的と一般にみなされている国家だけでなく、あらゆる場所で大規模な抗議活動はすでに暴力的に抑圧されている。市民的自由団体の国際ネットワークが2013年に発表した報告書には、カナダからエジプト、ケニア、南アフリカ、米国に至るまで、「社会的・政治的見解を表明しようとするおおむね平和的な集会に対して、致死的・殺傷的な武力が広く用いられている」と記されている。一方、元国家安全保障局(NSA)の内部告発者エドワード・スノーデンらによって明らかにされた監視国家の技術は、反対意見を抑圧し、活動家の活動を監視するための国家の手段がいかに強力であるかを示している。
この文脈では、非人道的な刑務所、暴力的な警察の取り締まり、時折行われる略式処刑から、より組織的な排除の形態への移行が容易に想像できる。アルゴリズムによるターゲティングは、無人の戦闘用ドローンのパワーの増大と相まって、暴力を動員する人々とターゲットとの距離を縮めることで、大量殺戮の道徳的不快感を和らげることを約束する。オペレーターは遠隔地のサイロに安全に座り、遠く離れた場所で死のロボットを操縦することができる。これはオーソン・スコット・カードの『エンダーのゲーム』の世界に近づいている。その物語では、ある子供がエイリアンの種族との戦争の訓練に採用される。最終訓練の一環として、彼は母星全体を破壊するシミュレーションに参加する。もちろんシミュレーションではない。若きエンダーは実際に大量殺戮を行い、戦争を終わらせたのだ。私たちの世界では、このような文字通りの欺瞞は起こらないかもしれないが、政治的・経済的エリートたちが、自分たちが偉大な人道主義者であると確信しながら、悲惨さと死のレベルをますます高めていくことを正当化しようとしていることは、すでに目に見えている。
結論
変遷と展望
私は社会発展の正確な道筋を予測することを目的としていない。そのような予測にはひどい実績があるだけでなく、必然的なオーラを醸し出し、私たちにじっと座って受動的に運命を受け入れるよう促す。未来が1つだけでなく4つあるのは、自動的に起こることは何もないからだ。進むべき道を決めるのは、私たち自身なのだ。
気候正義の活動家たちは、たとえそう言わないとしても、現在、気候変動に対する駆逐的な解決策ではなく、社会主義的な解決策を求めて闘っている。また、種子から音楽まで、あらゆるものの厳格な知的所有権に反対し、知識へのアクセスを求めて戦う人々は、賃借主義のディストピアを食い止め、共産主義の夢を守り続けようと奮闘している。これらの運動を詳細に取り上げようとすれば、それだけでかなりの分量が必要になる。だから、無理な要約を試みるよりも、4つの未来を単なる理想や自己完結的なユートピアとしてではなく、ダイナミックで進行中の政治的プロジェクトの対象として考えたときに生じる複雑さについて、いくつか考えて終わりにしよう。
左翼的で平等主義的な傾向のある人なら、賃借主義と絶滅主義は悪の側面の代表であり、社会主義と共産主義は善の希望の代表だと言うのは簡単だ。それらの理想社会を目的地として、あるいは旗印に掲げるスローガンとしてしか考えていないのであれば、それで十分かもしれない。しかし、これらのモデル社会はいずれも、現在の社会関係を一夜にして完全に変革するような、実行可能なものを表すものではない。実際、おそらくどれも純粋な形ではまったく不可能である。歴史はそのためにはあまりにも厄介であり、現実の社会はどんな理論的モデルのパラメーターも超えている。
ということは、最終目的地の正確な性質よりも、ユートピアやディストピアに至る道に特に関心を持つべきだということだ。特に、ユートピアに至る道自体がユートピアであるとは限らないからだ。
第1章で、私はユートピアの目的地へ至る、特に空想的でユートピア的な道筋を提案した。それは、ユニバーサル・ベーシック・インカムが完全な共産主義への移行を促進する「共産主義への資本主義的道筋」である。しかし、その移行には、現在政治と経済を支配している超リッチなエリートを退けなければならない。ベーシックインカム制度に関する限られた歴史的経験から、富裕層は自分たちの富と権力が枯渇するのを黙って見ているはずがない。
例えば 2008年と2009年にナミビアのオトジベロ・オミタラで実施されたパイロット・プロジェクトを考えてみよう。2年間、村の全員が毎月100ナミビア・ドル(約13米ドル)の支払いを受けた。学校の出席率は上昇し、子どもの栄養失調は激減し、犯罪も減少した。しかし、地元のエリートを構成する白人農民にとっては、そんなことはどうでもよかった。彼らはあらゆる証拠に反して、ベーシックインカムが犯罪やアルコール中毒を引き起こしたと主張した。ベーシック・インカム・プロジェクトの実施に協力した経済学者で神学者のディルク・ハールマンは、「貧困層が何らかの影響力を獲得し、人口の20%を占める白人の富裕層からその権力を奪うことを恐れていた」と推測している1。また、おそらくより直接的な懸念は、月100ドルでは労働者が1時間2ドルの最低賃金を受け入れなくなることだろう。
豊かで平等な世界への移行は、波乱と対立に満ちたものになりそうだ。富裕層が自発的に特権を手放そうとしないのであれば、力ずくで収奪しなければならない。フリードリヒ・ニーチェが有名な格言で言ったように、「怪物と戦うときは、自分自身が怪物にならないように気をつけよ・・・深淵を長く見つめるとき、深淵もまた自分を見つめるからである」2。あるいは、共産主義の詩人ベルトルト・ブレヒトが『後世へ』で書いたように、残忍な体制に対する革命は、それに参加した人々自身を残忍にする可能性がある。
不正義に対する怒りさえも
声を荒げる。残念なことに、私たちは
優しさの礎を築きたいと願った者は
自分自身が親切になることはできなかった3。
「革命は晩餐会ではない」4 つまり、最も成功し正当化された革命でさえ、敗者や犠牲者がいるのだ。
批評理論家のハーバート・マルクーゼは、1962年に経済学者のポール・バランに宛てた手紙の中で、「歴史の犠牲者については誰も気に留めたことがない」と述べている5。この発言は、ソビエト共産主義の犠牲者については熱心に道徳的に説明するが、資本主義の甚大な人的被害については沈黙するリベラリストの偽善に向けられたものである。これは辛辣な、おそらく残酷な判断であり、マルクーゼ自身もそれを超える必要性を示唆している。しかし、社会の4つの未来がきちんとした道徳的な箱に収まらないことを理解することで、私がここで取り組んだ運動に対する重要な視点を提供してくれる。
それは1つの危険性であり、私たちが踏破しなければならない道のりの難しさを過小評価したり、終着点の美しさが途中の無制限の残虐性を許すことになる。しかし、もうひとつの可能性は、旅の終わりに、その旅がいかに困難なものであったか、そして誰を置き去りにしてきたかを忘れてしまうことだ。ヴァルター・ベンヤミンは、そのエッセイ『歴史の概念について』の中で、歴史的記述は必然的に勝者に共感しがちである。「しかし、現在支配している人々は、過去に勝利したすべての人々の後継者である。しかし、明確な支配者がいない社会であっても、歴史は生存者に共感する傾向があるとも言える。そのことを踏まえて、最初の共産主義の未来の住民をもう一度見てみよう。おそらく彼らは、共産主義に至る資本主義的な道の終点にいるのではなく、絶滅主義の恐怖を通り抜ける、もっと長く暗い旅の終点にいるのだ。
絶滅主義の中心的な問題点を思い出してほしい。豊かさと労働からの解放は少数派には可能だが、物質的な限界によって、同じ生き方をすべての人に広げることは不可能なのだ。同時に、オートメーション化によって大量の労働者が不要になった。その結果、監視、抑圧、投獄の社会が生まれ、常に大量殺戮の社会へと傾きかけている。
しかし、その奈落の底を見つめたとしよう。「余分な」死体が処分され、金持ちがロボットと塀に囲まれた屋敷だけになったとき、何が残るのだろうか?戦闘用ドローンや死刑執行ロボットは退役させられ、監視装置は徐々に解体され、残された人々は残虐で非人間的な戦争道徳を乗り越え、平等で豊かな生活、つまり共産主義へと進化していくかもしれない。
在米ヨーロッパ人の子孫である私には、それがどのようなものなのか見当がつく。結局のところ、私は大量虐殺の受益者なのだ。
私の社会は、北米大陸の原住民の組織的な絶滅の上に築かれた。今日、初期のアメリカ人の生き残りの子孫は、十分に貧しく、数が少なく、地理的に孤立しているため、ほとんどのアメリカ人は彼らの生活を無視することができる。時折、生存者たちが私たちの注意を引こうとすることがある。しかし、たいていの場合、先祖の残虐さを嘆くことはあっても、豊かな生活や土地を手放そうとは考えない。マルクーゼが言ったように、歴史の犠牲者など誰も気にも留めないのだ。
もう少しズームアウトしてみると、私たちは必ずしも4つの未来から1つを選ぶわけではないということだ。
我々は、絶滅主義がどのように共産主義になるかを見てきた。共産主義は、人為的な欠乏を再び導入し、新たな賃借エリートを生み出す方法を誰かが見つけることができれば、常に反革命の対象となる。社会主義は、物質的な苦難を共有するレベルが高ければ高いほど、ある集団が自らを特権的なエリートとして設定し、制度を絶滅主義的なものに変えようとする原動力が高まるため、この圧力にさらに厳しくさらされる。
しかし、蓄積された知識から切り離され、新たな暗黒時代に突入するほどの完全な文明崩壊がない限り、我々が知っているような産業資本主義に戻る道はなかなか見えない。これが本書のもうひとつの重要なポイントである。過去に戻ることはできないし、今あるものにしがみつくことさえできない。そして実際、ウィリアム・ギブスンの言葉を借りれば、4つの未来はすべて「偏在」したまま、すでにここにあるのだ。私たちが望む未来のために闘う集団的な力を構築するのは、私たち次第なのだ。
