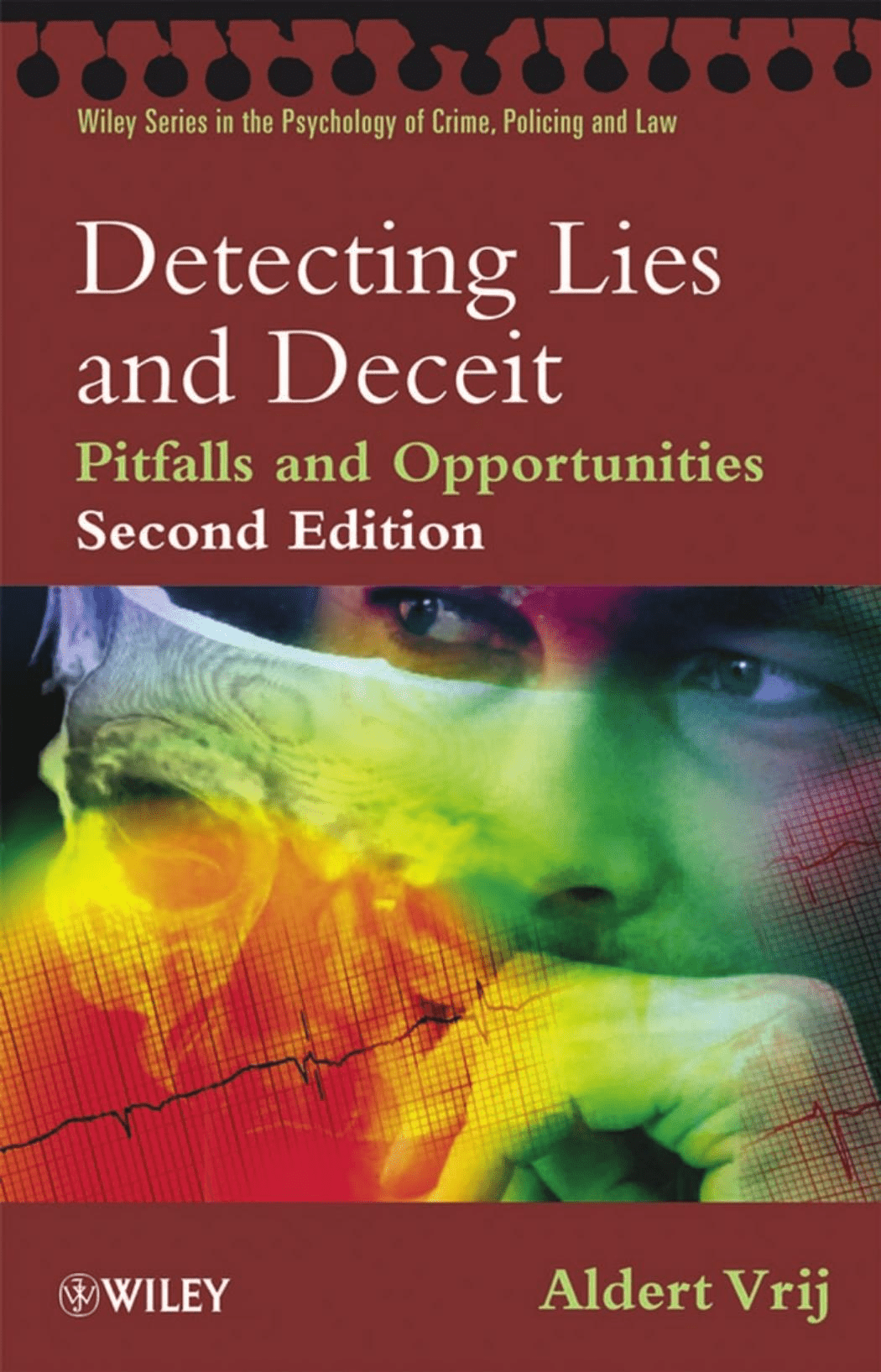
Detecting Lies and Deceit Pitfalls and Opportunities Aldert Vrij
目次
- 著者について
- シリーズ序文
- 序文
- 謝辞
- 1 はじめに
- 2 嘘をつく: 利己的な行為と社会の潤滑油
- 3 非言語的行動と欺瞞
- 4 欺くための個々の言語的手がかり
- 5 欺くための非言語的および言語的手がかりに関する信念
- 6 特殊な道具を使わない嘘の発見
- 7 行動分析面接
- 8 ステートメントの妥当性評価
- 9 リアリティ・モニタリング
- 10 科学的内容分析
- 11 生理的嘘発見懸念アプローチ
- 12 生理的嘘発見指向性反射アプローチ
- 13 生理学的嘘発見:機能的磁気共鳴画像法(fMRI)
- 14 落とし穴 人はなぜ嘘をつかなかったのか
- 15 機会 人はどのようにして嘘発見能力を向上させることができるのか?
- エピローグ
- 参考文献
- 索引
著者について
ポーツマス大学(英国)心理学科応用社会心理学教授。これまでに300本以上の論文や本の章を発表しており、主なテーマは欺瞞や嘘発見における非言語的・言語的手がかりである。また、容疑者との面接の実施に関する警察への助言、法廷での専門家証人としての活動、世界中の実務家や研究者を対象とした嘘発見に関する招待講演やワークショップも行っている。現在、英国心理学会発行の法心理学雑誌『Legal and Criminological Psychology』の編集長を務めている。
シリーズ序文
犯罪・警察・法の心理学に関するワイリーシリーズは、現代研究の重要な分野のレビューを出版している。本シリーズの目的は、研究成果をわかりやすく読みやすい形で紹介するだけでなく、政策と実践の双方に対する示唆を引き出すことにある。そうすることで、このシリーズが心理学者だけでなく、犯罪の摘発や予防、取り締まり、司法過程に携わるすべての人々に役立つことを期待している。
本書は、嘘やごまかしを見抜くこと、つまり真実を見抜くことに焦点を当てている。冒頭の章では、欺瞞を見抜くことに関して広く信じられている神話と、人が欺瞞か真実かを判断しようとするときに犯す(結果として生じる)誤りについて重要な扱いがなされている。次の章では、多くの人が(善意であるにせよ)しばしば嘘をつくことを指摘している。したがって、ほとんどの人はうまく嘘をつく方法を学ぶことができる。第3章と第4章では、(a) 言語的および言語的な行動/合図が欺瞞/真実性に関係する可能性があること、(b) 究によって実際に欺瞞に関係することが判明した合図について、さまざまな心理学理論が提示されている。第5章では、どの合図が嘘を示していると考えるかについての人々の信念と、前の2章で紹介された研究が誤った信念であることを明らかにした多くの信念の起源についての研究が増えていることをレビューする。続く包括的な章では、関連する専門家を含め、人が真実/嘘を見抜く能力がどの程度あるのかについて述べている。
第7章から第10章では、人の行動や話し方から欺瞞/真実を判断しようとするために開発された、様々な手順/技術を検証する。世界中で広く販売されているものも含め、これらの手法の多くは、公表された研究によって有効であることが判明していない。実際、これらに依存すると、無実の人が迫害され、罪を犯した人が野放しのままさらなる悪事を働くことになりかねない。
第11章から第13章は、身体/脳の活動から欺瞞を検出する試みに焦点を当てている。ここでもまた、利用可能な研究は、そのような手順の多くが、偶然から遠くないか、偶然に近いレベルの性能を達成していることを確認している。また、これらの章と第14章では、なぜ嘘つきの発見が難しいのかを説明しようとしている。
重要な終章では、多くの嘘発見本が主張するような不勉強な方法ではなく、豊富な心理学理論と研究に基づいた綿密な方法で、人々が嘘発見能力を向上させる方法に焦点を当てている。
この広く深い第2版(1100近い文献を引用)では、アルダート・ヴリイ教授は 2000年の初版(世界的に衝撃を与えた)よりもさらに質の高い本を作ることに成功している。本書は最高レベルの学術書の一例である。本書は、嘘をつくことと真実を語ることを見分けることが通常なぜこれほど困難なのかを人々に気づかせてくれるだろう–正直なところ、そうなるだろう!
レイ・ブル、グレハム・デイヴィーズ 2007年8月
序文
2000年に『Detecting Lies and Deceit(嘘と欺瞞を見抜く)』を出版したとき、少なくとも10年間は第2版を出版するつもりはなかった。しかし、重要な出来事が私の考えを変えた。 2000年以降、世界はテロ攻撃や安全保障上の脅威を何度も経験し、米国は「テロとの戦い」を開始した。このような背景から、嘘を見破りたいという願望はかつてないほど緊急のものとなり、各国政府は自国民を攻撃から守るため、嘘発見ツールを設計するよう学者に求めている。
科学者たちはこれに応えて研究を進め、現在では毎年150以上の欺瞞と嘘発見に関する論文が査読付き学術誌に発表されている。何人かの学者は、精度の高い嘘発見ツールを開発したと主張し、政府に彼らのツールを使うよう勧めている。彼らは何を提案しているのだろうか?中身なのか、スピンなのか、あるいはその両方の混合物なのだろうか?私の考えでは、実質とスピンはしばしば絡み合っている。また、この2つを区別する唯一の方法は、嘘と嘘発見に関する事実の包括的な概要を提供することだと思う。事実に基づいた説明によって、読者はこれらの主張がどれほど正確かについて、情報に基づいた意見を持つことができる。
本書は、現在までに発表された欺瞞研究の包括的なレビューを提供する。旧版とはいくつかの点で異なっている。第一に、旧版の文章が更新され、何百もの新しい研究が追加されている。 第二に、行動分析面接、科学的内容分析(SCAN)、音声ストレス分析、サーマルイメージング、P300脳波研究、機能的磁気共鳴画像法(fMRI)研究など 2000年版では取り上げられなかった嘘発見法についての記述も含まれている。第三に、欺瞞研究の世界では非常に多くのことが変化しているため、新たな発展を加えようとするよりも、私の本をほとんど書き直す方が本質的に簡単であった。したがって、私は古い文章の大半を書き直し、再構成した。例えば、本書では、専門家がしばしば欺瞞を見抜けないのはなぜか、よりよい嘘発見者になるためにはどうすればよいか、に関する概説の章を設けている。このような章は2000年版にはなかった。
その結果 2000年版よりも構成が良く、より包括的な欺瞞に関する本ができたと私は信じている。また、本書には2000年版よりもかなり多くの文章が含まれているため、おそらく読者は、この本を最初から最後まで読むよりも、個々の章に入り込むことを好むだろう。それを容易にするために、各章がそれぞれ独立して読めるようにした。
第6章 特別な道具を使わずに嘘を見抜く
この章は、人の嘘を見抜く能力を検証する8つの章のうちの最初の章である。第7章から第13章では、プロの嘘発見者や学者が使用する特殊なツールの精度について論じる。本章では、そのような専門的な道具を使わずに、相手の非言語的・言語的行動に注意を払った場合に、人々が嘘を見抜く能力を検証する。
嘘を見抜く能力とは、真実と嘘を見分ける能力のことである。優れた嘘発見器は、誰かが嘘をついているときだけでなく、誰かが本当のことを言っているときも判断できる。ある人が10個の発言の真偽を判断しなければならないとする。もし彼が10個の発言すべてを欺瞞的だと判断したなら、彼は5個の嘘すべてを正しく識別することになるが、これで彼は優れた嘘発見器になるのだろうか?私の定義によれば、彼は5つの真実の発言すべてについて誤った判断を下しているからだ。しかし、もし彼が5つの嘘と5つの真実を正しく見分けたとしたら、私は彼の技能に感心するだろう。
この章では、素人が(i) 対面の人、(ii)自分の友人やパートナー、(iii)子供の真実と嘘を見抜く能力がどの程度あるかについて論じる。その結果、素人の能力は、偶然に期待される能力、つまりコインをひっくり返して期待される能力よりも、ほんのわずかしか優れていないことがわかるだろう。素人は、誰かが本当のことを言っているかどうかをある程度見分けることはできるが、嘘つきの判別は苦手である。このことは、他人、友人、パートナー、子供の評価においても同様である。この章で明らかになるのは、彼らもまた、見知らぬ人がついた真実と嘘を見分ける際に、偶然に予想されるよりもわずかに良い結果を出すに過ぎないということである。彼らは、誰かが嘘をついていると判断することでは素人よりいくらか優れているが、真実を語る人を正しく識別することは犠牲になっている。おそらく、プロの嘘発見者と素人の間で最も顕著な違いは、プロは以下の通り: (i) 人よりも疑い深い(相手を嘘つきと呼ぶ傾向が強い)、(ii)真実と嘘を見分ける能力に自信がある。
人々の真実と嘘を見分ける能力に関するこのような悲観的な見方にもかかわらず、研究によってこの能力には個人差があることが明らかになっている。これらの違いを説明しうる要因として、嘘発見者のジェンダー、性格、動機について述べる。
さらに、観察者が行う真実性判断(つまり、誰かが真実を言っていると信じるか、嘘をついていると信じるか)に影響するいくつかの要因についても述べる。白人以外の人は、白人以外の人が自然に見せる行動により、白人観察者に疑わしい印象を与えることが多い。さらに、特定の性格的特徴を持つ人は、その特徴を持たない人よりも信じられる傾向がある。ここでも、これらの人々が示す自然な行動がこの効果を引き起こしている。私はまた、次のことも実証している: (i) の人を受動的に観察するのではなく、実際にインタビューすること、(ii)その人にさらに質問すること(「プロービング」)は、真実性の判断に影響を与える。インタビュアーは受動的な観察者よりも信頼性が高く、プロービングは誰かを信じる傾向をさらに高める。
本章ではまず、非言語的コミュニケーションと言語的コミュニケーションが真実性評価に与える相対的影響について議論する。つまり、人々が欺瞞を見抜こうとする場合、その判断に最も影響を与えるのは何かということである。この問いに一般論で答えることはできないことを実証する。
信頼性評価における非言語的行動と言語的行動の相対的重要性
いくつかの情報源(警察マニュアル、研究結果、現実の観察)は、非言語的行動が信憑性判断において重要な役割を果たすことを示している。警察マニュアルは通常、言葉によるごまかしの手がかりよりも非言語的な手がかりに多くのページを割いている。実際、基準ベースの内容分析(第8章)やリアリティ・モニタリング(第9章)のような言語的真実性判断ツールは、嘘つきと真実を語る人をある程度識別することが示されているが、そのようなマニュアルでは言及されていない。非言語的な手がかりの重要性は、警察マニュアルではさらに強調されており、「人と人との間で伝達されるメッセージの70%もが非言語的なレベルで発生する」(Inbau, Reid, Buckley, & Jayne, 2001, p.143)といった記述がある。
研究結果については、われわれの嘘発見実験では、99人の英国警察官に、容疑者に対する警察の取り調べの断片をビデオに録画した54本を見せた。各断片の後に真偽判定を行い、その判断の根拠となった手がかりを報告するよう求めた(Mann, Vrij, & Bull, 2004)。警察官が報告した手がかりの大部分(78%)は非言語的なものであった。また、観察者は、ある人の非言語的行動がその人の発話内容と食い違っていることに気づいたとき、通常、非言語的チャンネルに頼る。したがって、選考面接で控えめな態度の応募者が仕事に熱心だと主張した場合、人々はその応募者が主張するほど熱心ではないと考える傾向がある(DePaulo, Rosenthal, Eisenstat, Rogers, & Finkelstein, 1978; Hale & Stiff, 1990; Heinrich & Borkenau, 1998; Hoffner, Cantor, & Thorson, 1989; Zuckerman, Driver, & Koestner, 1982; Zuckerman, Speigel, DePaulo, Rosenthal, 1982)。
いくつかの現実の観察は、誰かが嘘をついているかどうかを判断する際の非言語的行動の重要性をさらに実証している。Kaufmann, Drevland, Wessel, Overskeid, and Magnussen (2003, p. 22)は、彼らの母国であるノルウェーでは、利用可能な証拠と矛盾する場合でも、司法判断が非言語的コミュニケーションに基づくことがあることに注目した。彼らは、有罪の状況証拠は強かったが、被告(ファイナンシャル・アドバイザー)が無罪になった裁判について述べている。フロリダでは、トム・ソーヤーが性的暴行と殺人で告発された。捜査当局は彼を16時間にわたって尋問し、脅しをかけ、おそらく虚偽の自白を引き出した。彼が第一容疑者となったのは、犯罪への関与を否定した最初の取調べで、恥ずかしそうにし、顔を紅潮させていたからである(Meissner & Kassin, 2002)。(トム・ソーヤー事件については、Ofshe, 1989とBox 11.2を参照のこと)。アメリカの別の事件では、14歳のマイケル・クロウが長時間の取調べを受け、妹を刺殺したことを自白した。少年に対する起訴は後に取り下げられた。彼が第一容疑者となったのは、妹の死に対して不適切なほど感情を抑えて反応したと刑事たちが考えたからである(Kassin, 2005)。
なぜ嘘発見器は非言語的行動にこれほど注意を払うのだろうか?第一に、彼らはそれを解釈する能力に自信があるのだろう。行動を観察するだけで、人は性格的特徴(外向性や社交性など)、男らしさ、女らしさ、性的指向など、他人に関するあらゆることを合理的な精度で判断することができる。また、行動から地位、優位性、恋愛関係などの情報を見分けることも可能である(Ambady, Bernieri, & Richeson, 2000; Ambady & Rosenthal, 1992; DePaulo, 1992; DePaulo & Friedman, 1998)。つまり、人は非言語的行動から推論することに慣れているのである。
第二に、おそらく観察者が非言語的行動に注意を払うのは、人は発話よりも非言語的行動を意識することが少なく、その結果、非言語的チャネルを通じて隠そうとする情報が「漏れる」と想定しているからである(DePaulo et al., 1978; Hale & Stiff, 1990; Kalbfleisch, 1992; Maxwell, Cook, & Burr, 1985; Stiff, Hale, Garlick, & Rogan, 1990; Vrij, Dragt, & Koppelaar, 1992)。実際、ある状況下では、個人は言語的コミュニケーションよりも非言語的行動のある側面をコントロールする能力が低い(DePaulo, 1992; DePaulo & Kirkendol, 1989; Ekman, 1993; Ekman & Friesen, 1969, 1974)。空港で税関職員がヘロイン密輸犯に、スーツケースの中に違法なものはないかと尋ねたとしよう。密輸業者が「隠し事は何もない」と言うのは簡単だが、普通に振る舞い、行動によって疑いを持たれないようにするのは、おそらくもっと難しい。また、試験中に床に落ちていた自分の講義ノートが自分のものでないことを試験監督に伝えることも、学生にとっては難しいことではないだろうが、冷静でいることはもっと難しいだろう。嘘つきがこのような状況で自分の行動をコントロールするのが難しい理由は、すでに第3章で述べた。とりわけ、信憑性のある行動を示す一方で、緊張の兆候を抑える必要がある。
しかし、主に非言語的な行動に注意を払うことは、嘘発見器が常に行うことではない。調査によると、人は真実性を判断する際、非言語的行動に注意を払うこともあれば、発話内容に注意を払うこともあり、この2つのチャネルの相対的重要性は多くの要因に左右される。例えば、観察者が会話のトピックについて何を知っているかにもよる(Stiff, Miller, Sleight, Mongeau, Garlick, & Rogan, 1989)。観察者に知識がある場合、観察者は通常、発話に集中し、自分が知っていることと対象者が話すことを比較する。第4章では、ジェフリー・アーチャーが首相との電話疑惑についてついた嘘が、この方法でバレた例を紹介した。また、観察者が利用できる発話内容の量にもよる。上記のヘロイン密輸業者や学生の例のように、数語や数センテンスしか発言しない場合もある。そのような場合、観察者はその人の行動を調べる以外にほとんど選択肢がない。他の状況では、観察者はより多くの発話内容を利用することができる。例えば、観察者は複数の発言にアクセスすることができる。同一人物から疑惑の出来事に関する複数の供述を得ている場合もあれば、異なる人物から疑惑の出来事に関する供述を得ている場合もある。このような場合、嘘発見器は発話内容に注目し、異なる供述間の一貫性をチェックする傾向がある(Granhag & Stro¨mwall, 1999, 2000a,b, 2001a,b; Stro¨mwall & Granhag, 2005, 2007; Stro¨mwall, Granhag, & Jonsson, 2003)。
真実性判断における非言語的手がかりと言語的手がかりの相対的影響に影響を与えるもう1つの要因は、これらの手がかりの明確性である。例えば、人は話の信憑性が低いと感じたり(Kraut, 1980)、ある発言が話の語り手の自己利益に反しているように見えたりする場合(Noller, 1985)、言語的なチャンネルを頼りにする。対照的に、誰かが凝視するような奇妙と思われる行動を示すと、彼らの真実性判断はその奇妙な行動に影響される可能性が高い(Bond, Omar, Pitre, Lashley, Skaggs, & Kirk, 1992)。
さらに、人が何に注意を払うかは、その人の真実性についての期待に影響されるかもしれない。警察官は容疑者が有罪であると容易に思い込む(Evans, 1994; Kassin, 2005; Moston, Stephenson, & Williamson, 1992; Stephenson & Moston, 1994)。イギリスにおける警察の取調べの分析によれば、73%のケースで、警察の取調官は取調べの前に容疑者が有罪であると「確信していた」(Moston et al. 嘘が予想される場合、警察官は容疑者の平然とした否認を聞くことにあまり興味を示さず、ごまかしを見抜くために体のサインを見ることを好むかもしれない(Millar & Millar, 1998)。
最後に1、言語的チャネルと非言語的チャネルは、人によって評価が異なる可能性がある(Friedman, 1978)。Noller(1985)は、女性は男性よりも発話内容に反応しにくく、非言語的な手がかりに頼ることが多いと報告している。一般的に、女性は男性よりも非言語的行動に関する知識が豊富で、その解釈にも長けている(Hall, 1984)。この能力の高さが、非言語的手がかりへの注意を導いているのかもしれない。これと同様に、嘘発見器も、言葉や非言語的な手がかりに関する知識が、注意を向ける焦点に影響を与える可能性がある。自分は言葉による欺瞞の手がかりに詳しいと思う人は、相手の言うことに注意深く耳を傾けるかもしれないし、自分は非言語による欺瞞の手がかりに詳しいと思う人は、相手の行動を注意深く吟味するかもしれない。
前述したように、警察のマニュアルでは、言葉による手がかりよりも、欺くための非言語的な手がかりを重視している。このことは、警察官が、話の内容を聞いた方が適切な状況であっても、欺瞞の非言語的手がかりにより注意を払う傾向があることを意味しているのかもしれない。捜査を開始するとき、警察官は犯罪に関する情報をほとんど持っていないことがあり(Horvath & Meesig, 1996)、そのため容疑者が誰であるかについてまだ明確な考えを持っていない。そのため、犯罪が起こった地域に住む人々や、犯罪を犯した可能性があると思われる人物を何人も聴取することになる。これらの人物の非言語的なプレゼンテーション・スタイルによって、その人物が有力な容疑者とみなされ、2回目の面接に招かれるかどうかが決まる可能性が高い(Greuel, 1992; Kraut & Poe, 1980; Rozelle & Baxter, 1975; Vrij, Foppes, Volger, & Winkel, 1992; Walkley, 1985; Waltman, 1983)。これは、先に述べたトム・ソーヤーとマイケル・クロウのケースで起こったことである。私は、このアプローチには限界があると考えている。第4章で述べたように、否定的な感情などの精神状態も発話によって漏れる可能性があり、その場でもっともらしい答えを出すことは時に困難である。また、発話をコントロールすることも困難であり、非言語的な行動に主に注意を払うという嘘発見器の戦略は、このような状況では制約が多すぎるかもしれない。また、本章で明らかになったように、人は誰かを見ているよりも、むしろ聞いている方が、真実と嘘を見分けるのに長けていることが多い。
まとめると、観察者が言語的チャネルと非言語的チャネルのどちらに注意を払うかは、観察者が会話のトピックについて何を知っているか、観察者が利用できる発話内容の量、言語的・非言語的手がかりの区別、相手が嘘をついているかどうかについての観察者の期待、欺瞞の言語的・非言語的手がかりについての観察者の知識によって決まる。
素人の嘘を見抜く能力
見知らぬ人の嘘を見抜く素人の能力は、ここ数十年の間に広く研究されてきた。典型的な嘘発見研究では、観察者(通常は大学生)に、真実を言っているか嘘をついているかのどちらかである、見知らぬ人の短いビデオの断片が与えられる。観察者は、それぞれの断片の後に、その人物(しばしば送り手と呼ばれる)が本当のことを言っているのか、嘘をついているのかを示すよう求められる。このような研究では、送信者が真実を話したか嘘をついたかを推測するだけで、真実の50%(真実の正確率)と嘘の50%(嘘の正確率)を正しく分類することになり、合計の正確率は50%となる。本章の冒頭で紹介した不審な観察者が、実際には5つの発言が欺瞞的で5つの発言が真実であったにもかかわらず、10個の発言すべてを欺瞞的と判断した場合、嘘の正確率は100%、真実の正確率は0%、合計の正確率は50%となる。後者のスコアは、彼のパフォーマンスが偶然のレベル(50%)と同じであったことを示す。
嘘発見研究では、観察者は発信者とその発言に関する背景情報を一切与えられていないため、利用可能な情報源は発信者が示す非言語的行動と言語的行動のみである。実生活と比べると、これは嘘を発見する方法としてはやや特殊である。Park, Levine, McCornack, Morrisson, & Ferrara (2002)の研究では、大学生に、人生で他人が嘘をついたことを発見した事例を思い出し、どのように嘘を発見したかを報告するよう求めた。ウソをついた人の非言語的行動や発話内容だけを頼りに、ウソをついた瞬間に発見されたウソは2%以下であった。より一般的なのは、第三者からの情報(38%)、物的証拠(23%)、自白(14%)によって嘘を発見することであった。嘘の80%以上は、嘘を言ってから1時間以上経ってから発見され、40%は1週間以上経ってから発見された。
多くの嘘発見研究では、観察者が判断しなければならない断片は、第3章と第4章で論じた研究から得られたものである。これらの研究の多くでは、送信者は実験のために真実を話すか、嘘をついた。嘘つきは一般的に認知的負荷を経験し、真実を言う人と嘘をつく人の利害は軽微なものから中程度のものまで様々であった。
Kraut (1980)は、嘘発見に関する研究のレビューを発表した。これらの研究のほとんどの合計的中率は45%から60%であり、平均的中率は57%であった。1980年にKrautの総説が発表されて以来、多くの研究が発表されている。付録6.1は、1980年以降に英語で発表された、素人が知らない人から聞いた真実と嘘を識別する能力に関する、私が知る79の研究を示している。最も低い正答率は31%(Brandt, Miller, & Hocking, 1982)であり、これは異常値と思われる。2番目に低い合計正確率は38%で、これはBrandt, Miller, and Hocking (1982)による別の研究で得られたものである。これまで報告された中で最も高い合計正確率は68%であった(Wan Cheng & Broadhurst, 2005)。残りの合計的中率は42%から65%であった。付録6.1ではさらに、大半の研究(79件中62件)で50%から60%の精度が報告されていることが示されている。これら79の研究の平均的な正確率は54.27%であり、これはKraut (1980)が発見した57%の正確率よりやや低い。54.27%という精度は、50%の確率レベルをわずかに上回る程度である。
付録6.1は、34の研究において、真実の正確さ(真実を正しく分類)と嘘の正確さ(嘘を正しく分類)を区別していることを示している。通常、真実の正確さの方が嘘の正確さよりも高い: 34件の研究のうち25件では、真実の正確さの方が嘘の正確さよりも高かった。真実の正確さの範囲は49%から81%であった。65%以上の真実正確率は一般的で、34研究中16研究で達成されている。平均的な真実の正確さは63.41%であり、これは偶然に予想されるよりも高い。対照的に、報告された最も高い嘘の正確さは70%であったが、27%という低い嘘の正確さも得られている。50%を下回る嘘の正確さは一般的で、34の研究のうち18で達成されている。嘘の正確さの平均は48.15%で、これは偶然に予想される正確さを下回っている。
真実バイアス
真実精度の高さは、少なくとも部分的には真実バイアスの結果である。真実バイアスとは、観察者がメッセージを欺瞞的なものではなく真実であると判断する傾向のことである(Ko¨hnken, 1989; Levine, Park, & McCornack, 1999; Zuckerman, DePaulo, & Rosenthal, 1981)。BondとDePaulo(2006)は、嘘発見研究のメタ分析で、真実と嘘に同数さらされているにもかかわらず、観察者はメッセージの56%を正直と判断し、44%しか欺瞞的と判断しないことを発見した。つまり、観察者は鵜呑みにする傾向があるのだ。真実バイアスには少なくとも8つの説明がある(DePaulo, Wetzel, Weylin Sternglanz, & Walker Wilson, 2003; Gilbert, 1991; Vrij, 2004b; Vrij & Mann, 2003a)。第一に、日常生活では、人は欺瞞的な発言よりも真実的な発言に直面することが多く(第2章)、誰かが真実を述べていると仮定する傾向が強い(いわゆる可用性ヒュー リスティック、O’Sullivan, Ekman, & Co.
(1959)は、人生は劇場のようなものであり、人はしばしば役者のように振る舞い、ショーを演じるものだと主張した。日常生活で他人に見せる「自分」は、本当の自分ではなく、編集されたバージョンである。このような劇場では、私たちは他人が自分の見せ方を尊重してくれることを期待するが、同時に、他人が自分に見せる見せ方も受け入れる。後者は真実偏重をもたらす。
第三に、社会的な会話ルールは、人々が疑念を抱くことを抑制する(Toris & DePaulo, 1984)。会話の相手が、話していることすべてに疑問を投げかけると、人はすぐに苛立ちを覚えるだろう。「信じられない」、「そんなはずはない」、「証明してくれない?」などと言って、あなたの話を遮ってばかりいる人を想像してみてほしい。会話は長続きしないだろう。つまり、社会的な会話のルールは信憑性に左右されるのだ。
第四に、人々は欺瞞が実際に起こっているかどうか確信が持てないかもしれない。この不確実性を考えると、最も安全で礼儀正しい戦略は、あからさまに表現されたことを信じることかもしれない(DePaulo, Jordan, Irvine, & Laser, 1982)。
これに関連するのが、真実バイアスの5つ目の説明であるフィードラーとワルカの反証可能性ヒューリスティック(1993)である。フィーダーとワルカは、リアリティ・チェックによって容易に反証可能な発言は、反証が容易でないメッセージよりも信憑性が低く見えると主張した。しかし、人は自分の感情、嗜好、態度、意見など、容易に反証できない話題についてしばしば嘘をつく(第2章)。そのような場合、観察者はメッセージを鵜呑みにする傾向がある。
第6に、ギルバート(1991)は、スピノザ的な知識表現モデルに基づき、最初はすべてが真実であると考えられ、不信には余分な努力が必要であると主張した。言い換えれば、真実バイアスは社会的相互作用における初期設定である。
これに関連して、Elaad(2003)は、Tversky and Kahneman(1974)のアンカリング・ヒューリスティックに基づいて、真実バイアスが存在する7つ目の理由を提示した。これは、人が初期値(アンカー)から不十分な調整をすることで、最終的な判断がその値に偏ることを指す。したがって、観察者が誰かが真実を言っていると考えることに夢中になっている場合、対照的な証拠が出てきたときに不十分な調整を行うことになる。
最後に、Grice (1989)は、社会的相互作用において、人々が使う言語は一連の原則に従うことが期待されると主張した(McCornack, 1992も参照)。例えば、量の原則は、情報は啓発的であるべきであることを指示し、関係の原則は、情報は関連性のあるものであるべきであることを強調する。しかし、人はしばしばこのような規則に反し、あいまいな話し方をする。会話の相手はそれに慣れており、それを許容しているため、このようなことが起きても不審に思わないことが多い。その結果、たとえ嘘つきの話し方が言語原則に反していても、観察者は簡単には疑わない。
真実バイアスは頻繁に発見されるが、それは絶対的なものではなく、疑い深さを高めることによって排除することができる(DePaulo, Lindsay, Malone, Muhlenbruck, Charlton, & Cooper, 2003)。例えば、商品を販売する販売員の発言を観察者が判断する研究では、観察者は嘘バイアスを示した(DePaulo & DePaulo, 1989)し、他の研究では、参加者が送信者に「完全に真実でなかったかもしれない」と告げられると、嘘判断の数が増加した(McCornack & Levine, 1990a,b; Millar & Millar, 1997b)。最後に、後述するように、取り調べる容疑者が有罪であると決めつけることが多い警察官も、真実バイアスを示さない。
AI 解説
真実バイアスの8つの説明をまとめると以下のようになる。
- 可用性ヒューリスティック:日常生活では真実の発言に遭遇する頻度が高いため、人は誰かが真実を述べていると仮定する傾向が強い。
- 人生は劇場のよう:日常生活で他人に見せる「自分」は編集されたバージョンであり、私たちは他人が自分の見せ方を尊重し、同時に他人が自分に見せる見せ方も受け入れる。
- 社会的な会話ルール:会話の中で相手の発言すべてに疑問を呈することは社会的に許容されないため、信じる方向に傾く。
- 欺瞞の不確実性:欺瞞が実際に起こっているか確信が持てない場合、最も安全で礼儀正しい戦略は、あからさまに表現されたことを信じること。
- 反証可能性ヒューリスティック:感情、嗜好、態度、意見など、容易に反証できない話題についての嘘は、観察者がメッセージを鵜呑みにする傾向がある。
- スピノザ的な知識表現モデル:最初はすべてが真実であると考えられ、不信には余分な努力が必要であるため、真実バイアスは社会的相互作用における初期設定。
- アンカリング・ヒューリスティック:観察者が誰かが真実を言っていると考えることに夢中になっている場合、対照的な証拠が出てきたときに不十分な調整しかしない。
- 言語原則:会話の相手は、人がしばしば言語原則に反しあいまいな話し方をすることに慣れており、許容しているため、嘘つきの話し方が言語原則に反していても、観察者は簡単には疑わない。
真実バイアスは絶対的なものではなく、疑い深さを高めることによって排除できるが、日常生活における社会的相互作用では、これらの理由から真実バイアスが生じやすい傾向にあるといえる。
欺瞞媒体
ウソ発見器は、さまざまな方法で発信者を判断することができる。たとえば、対面での会話では発信者の声も目も聞こえるが、電話では発信者の声しか聞こえない。Bond and DePaulo (2006)は、この欺瞞媒体の研究を再検討し、媒体が嘘を発見する能力に影響を与えることを発見した。送り手の声しか聞こえない嘘発見者は、送り手を見ることも聞くこともできる観察者と同じようにうまくいったが、送り手を見ることしかできない観察者は、送り手の声しか聞こえない観察者(d .37)または送り手を見ることも聞くこともできる観察者(d .44)よりもうまくいかなかった5。言い換えれば、観察者は送り手の声が聞こえないと嘘発見がうまくいかないのである。これには少なくとも2つの説明がある。第一に、第3章と第4章では、視覚的な手がかりよりも、声や言葉によるごまかしの手がかりの方が多いことが明らかになったが、送り手の声が聞こえない観察者は、こうしたより診断しやすい声や言葉による手がかりを利用することができない。第2に、人は嘘つきが目をそらしたり、動作を大きくしたりすると強く信じているが(第5章)、これらは欺瞞の診断手がかりにはならない(第3章)。観察者が送り手しか見ることができない場合、真偽を判断する際に誤った固定観念に頼る傾向があり(Bond & DePaulo, 2006)、誤った判断が起こりやすい。また、このようなステレオタイプな見方は、真実を語る人がどのように振る舞うかではなく、嘘つきがどのように振る舞うかについてのものである。したがって、送り手が見えるだけの観察者は、送り手が見え、かつ聞こえる、あるいは送り手が聞こえるだけの観察者よりも、誰かを嘘つきと決めつける可能性が高い(Bond & DePaulo, 2006; Mann, Vrij, Fisher, & Robinson, 2007; Vrij, in press)。
動機/利害
第3章ですでに述べたように、嘘つきは欺瞞を成功させようとする動機が皆等しいわけではない。信用されないことによる否定的な結果や、信用されることによる肯定的な結果が大きいハイ・ステークスの状況では、人はロー・ステークスの状況よりも信用できるように見せたいという動機が強くなる可能性がある。嘘がばれないようにする動機が高いほど、その行動から嘘がばれる可能性が高くなる。この効果を説明すると、やる気のある嘘つきの方が、やる気のない嘘つきよりも、ごまかしに対する行動的反応を引き起こす可能性のある3つのプロセス(感情、認知的努力、行動制御の試み)がより深くなるということになる(第3章)。
もし嘘つきが、低い嘘よりも高い嘘の方が、欺くための手がかりをより多く示すのであれば、高い嘘の方が発見しやすいはずである。実際、利害を操作した一連の実験では(利害が本当に高かったことはないが)、観察者は、利害の低い設定よりも、利害の高い設定の方が、真実と嘘を区別するのに優れていた6。 BondとDePaulo(2006)のレビューでも、嘘は、非意欲的な送り手よりも意欲的な送り手によって語られた方が、真実から幾分識別しやすいことが明らかにされている(d = 0.17)。
準備
人は前もって嘘を準備する機会がある場合もあれば、自発的に嘘をつかなければならない場合もある。計画的な嘘は、自発的な嘘よりもいくらか言いやすく、そのため認知的負荷の兆候も少ないことを、第3章ですでに見た。したがって、Bond and DePaulo (2006)のメタ分析によると、観察者は、自発的なメッセージを判断する方が、計画的なメッセージを判断するよりも、真実と嘘を区別する能力がわずかに優れている(d = 0.14)。
送信者への親近感
人の行動や話し方には個人差があることは第3章で述べた。なぜなら、観察者は見知らぬ人が普段どのように振る舞い、話すかを知らないからである。おそらく、観察者が判断の対象となる見知らぬ人の真実の行動や話し方を知るようになり、真実であることが分かっているメッセージと判断の対象となるメッセージとの間の行動や話し方の変化を探すことができるようになれば、嘘の検出は容易になるであろう。これについては、いくつかの研究がある。それらの研究では、観察者はやはり知らない発信者の発言の真偽を判断しなければならなかったが、今回は嘘発見課題の前に、これらの発信者の「真実のベースラインメッセージ」を見せられた(観察者はベースラインメッセージが真実であることを知らされていた)。これらの研究によると、真実のベースライン・インタビューに接した観察者は、そのようなベースライン・インタビューに接しなかった観察者よりも、その後の嘘発見課題でよい結果を示した(Brandt, Miller, & Hocking, 1980a, b, 1982; Feeley, deTurck, & Young, 1995)。言い換えれば、送り手の真実の行動に慣れ親しむことで、真実と嘘の識別が容易になるということである。
他の研究者は、真実か欺瞞かのベースラインメッセージを観察者に見せたが、これらのベースラインメッセージの真実か嘘かの状態については観察者に知らせなかった。その結果、ベースラインメッセージを観察することは、それが真実である場合にのみ、観察者に利益をもたらすことがわかった(Garrido & Masip, 2001; O’Sullivan, Ekman, & Friesen (1988). O’Sullivan、Ekman、Friesen (1988)は、観察者は観察した行動が正直であると仮定する傾向があるため(可用性ヒューリスティック)、最初に見た行動(つまりベースライン行動)は不正であるよりも正直であると仮定する可能性が高いと主張した。最初の行動が正直であれば、その後に続く異なる行動を不誠実と識別することが容易になる。しかし、最初の行動が実際には欺瞞的であるにもかかわらず、正直であると誤ってラベル付けされた場合、その後の行動を評価する際にエラーが発生する可能性がある。
まとめ
素人は、見知らぬ人から言われた真実と嘘を区別しようとするとき、偶然よりもわずかに良い結果を出すだけである。また、見知らぬ人を信じる傾向(真実バイアス)があるが、観察者が疑心暗鬼になると真実バイアスは消失する。嘘発見精度はいくつかの要因に影響される。観察者は、次のような場合、真実と嘘を見分けるのに優れている: (iii)送信者のメッセージは計画的ではなく自発的であり、(iv)送信者の真実のベースライン行動を熟知している。
もし、送り手の自然な真実の反応に慣れ親しんでいることが、真実や嘘を見抜くことを容易にするのであれば、人は見知らぬ人よりも、友人や恋愛相手の真実や嘘を見抜くことに長けていると予想される。これと同じように、Boon and McLeod (2001)は、人は自分のパートナーの嘘を見抜くのがかなり上手だと考えていると報告している7。いくつかの実験では、観察者はよく知っている人のビデオ断片を見せられ、見知らぬ人を対象とした研究と同様に、非言語的行動と発話内容だけが唯一の情報源となった。表61は、私が知る限り、英語で発表された研究の結果をまとめたものである。これらの研究は、友人や家族、恋人から聞かされた真実と嘘の識別が、見知らぬ人から聞かされた真実と嘘の識別よりも容易であるという考えを支持していない。Miller、Mongeau、Sleight(1986)はBauchnerが行った研究を報告しているが、それによると、友人同士は74%の精度でお互いの嘘を見抜くことができたという。私の知る限り、赤の他人を対象とした研究でこれほど高い精度が得られたことはない。しかし、この発見は再現されていない。他の研究では、49%から59%の精度が得られている。このような正確率は、観察者が見知らぬ人の真実と嘘を見抜こうとしたときに見られた正確率と同様である。実際、見知らぬ人の真実と嘘を見抜く能力と、友人やパートナーの真実と嘘を見抜く能力を直接比較した研究では、いずれも正確率に差は見られなかった(Anderson, DePaulo, & Ansfield, 2002; Buller, Strzyzewski, & Comstock, 1991; Fleming, Darley, Hilton, & Kojetin, 1990; Millar & Millar, 1995)。Comadena(1982)は、友人や親しい人を判断する際に、真実と嘘を識別する能力を調べたが、この2つのグループにも違いは見られなかった。他の研究では、関係の親密さと正確さとの関連が検討された。そのいずれでも、親密さと正確さとの関連は認められなかった(Levine & McCornack, 1992; McCornack & Parks, 1986; Stiff, Kim, & Ramesh, 1992)。
Anderson, Ansfield, and DePaulo (1999)は、関係の親密さと欺瞞の発見精度との間に関連性が存在しないと思われる理由をいくつか挙げている。彼らは、親密な関係のパートナーが互いの欺瞞を検出しようとするとき、互いに関する多くの情報を思い浮かべることを示唆した。この情報は圧倒される可能性があり、ウソ発見器は、ごまかしの本物の手がかりを注意深く探すのではなく、ヒューリスティックに(つまり単純な判断操作を使って)情報を処理することでこれに対処するのかもしれない。もう一つの説明は、親しい間柄での相互作用において、嘘発見器は社会的認知(例えば、欺瞞の可能性のある手がかりを解読すること)と社会的行動(例えば、それらの相互作用において支持的に見えること)を同時に行わなければならないということである(Patterson, 1995, 2006)。これは嘘発見器にとっては集中しすぎることであり、その結果、欺瞞への貴重な手がかりが気づかれないままになってしまう可能性がある。さらなる説明として、人間関係が発展するにつれて、人は互いを欺くために独自のコミュニケーションを作り出すことに熟練するようになる。つまり、嘘つきはパートナーとの交流を通じて、パートナーに見破られにくい嘘をつくことを学んできたのだ。
さらに、恋愛関係でつく嘘のかなりの数は、相手を守るため、あるいは相手の気分を良くするためにつく他者志向の嘘である(第2章)。このような嘘をつくとき、人は一般的に悪い気はしないので、嘘をつくときにごまかしの手がかりを示さないかもしれない。また、他者志向の嘘には恋愛相手が聞きたい情報が含まれているため、相手はそのような嘘を見抜こうという意欲を持たないかもしれない。最後に、人は人間関係に感情的に投資する傾向があり、ある情報は人間関係を脅かす可能性がある。そのような場合、人は嘘を見破りたくないので、嘘を見破らないかもしれない(第1章では、嘘を見破ろうとしない動機的理由をダチョウ効果と名付けた)。
後者の2つの動機による説明は、ほとんどの恋愛関係に真実バイアス(truth-bias)が存在する可能性を示唆している。実際、人間関係がより親密になるにつれて、パートナーは相手を真実であると判断する傾向が強くなり、いわゆる関係的真実バイアス・ヒューリスティック(Relational truthbias heuristic)と呼ばれるようになると論じられている(Stiff et al. McCornackとParks (1986)とLevineとMcCornack (1992)は、これを説明するモデルを開発し、検証した。彼らの主張の核心は、親密さと真実バイアスは互いに直接結びついているわけではなく、両者は信頼と結びついているということである。二人の関係が深まると同時に、二人は互いの嘘を見抜く自信が高まる(「私はあの人のことをよく知っているから、あの人が嘘をついているかどうか見抜ける」)。そして自信の高さは、相手が自分に嘘をつく勇気はないだろう(「あの人は気をつけたほうがいい、私はあの人のつく嘘はすべて見抜くことができる」)と考えるようになる。その結果、相手が嘘をついているかどうかを見抜こうとする労力がどんどん減っていくことになる(「どうせあの人は私に嘘をつかないから、そんなに心配する必要はない」)(Stiff et al., f92)。
Cole, Leets, and Bradac (2002)は、関係的真実バイアスが観察者の愛着スタイルに依存するかどうかを調べた。愛着スタイルは、人々が恋愛関係をどのように認識しているかを教えてくれる(第2章)。セキュア8の人は、自分自身と他者に対して肯定的な見方を持っている。彼らは親密さを心地よく感じ、人間関係においてそれを重視する。先入観の強い人は、恋愛相手を理想化する一方で、自分自身を否定的に見る傾向がある。簡単に恋に落ちるが、相手の長期的なコミットメントや関心の度合いを疑う。恋愛関係における親密さに憧れるが、パートナーが自分の関係上の欲求を満たしてくれるかどうか不安である。恐怖心の強い人は、自分自身や他人を否定的に見る傾向がある。他人を信頼することが難しく、親密さを避ける傾向があり、人間関係において親密になることを嫌う。最後に、否定的な人は、自分自身については肯定的な見方をしているが、他者については否定的な見方をしている。彼らは親密さの重要性を否定し、自律性を達成しようと努力する傾向がある。まとめると、安全な人も夢中な人も、恋愛相手からの親密さを望み、他者に対して肯定的な見方をしている。これとは対照的に、恐れを抱く人や消極的な人は親密さを避け、他者に対して否定的な見方をする傾向がある。コールらは、関係的真実バイアスは、他者を肯定的に見る観察者(安全な観察者と夢中な観察者)に特に存在することを発見した。
友人や恋愛相手の嘘を見抜く能力が低く、そのような友人や相手を信じる傾向があることは、テロとの戦いにおいて憂慮すべき事態をもたらす。イギリスでは 2005年7月7日にロンドンで爆弾テロが発生し、さらなる破壊を生み出そうとして失敗した後、人々は友人や家族を含め、自分たちのコミュニティで警戒するよう求められている。このセクションで示された調査結果は、人々が親しい友人や家族の中に潜在的なテロリストがいることを見分けるのに適しているかどうかを疑問視している。
まとめ
素人は、友人やパートナーと同じように、見知らぬ人の真実や嘘を見抜くことができる。これにはいくつかの説明がある。人間関係が深まるにつれて、人は互いを欺くためのユニークなコミュニケーションを巧みに操るようになる。また、パートナーとの関係が親密になるにつれ、パートナーは相手の嘘を見抜くことができるという確信を持つようになり、その結果、最終的には相手が自分に嘘をつかないと信じるようになる(関係的真実バイアス・ヒューリスティック)。このように相手を信じようとする傾向は、愛着スタイルが恐怖型や棄却型の人よりも、安心型や先入観型の人の方が強い。
素人が子どもの嘘を見抜く能力
幼い子供と大人が同じ出来事について嘘をついた場合、どちらの嘘を見抜くのが最も簡単だろうか?おそらくほとんどの人は、幼児の嘘を見破る方が簡単だと答えるだろう。実際、幼い子どもはまだ、(i) っともらしい嘘をでっち上げる認知能力を持っていない、(ii)信用できる印象を与えることが重要であることに気づいていない、(iii)正直な態度を示すのに必要な筋力コントロールを持っていない(第3章)。しかし、第3章は、子どもの嘘を見抜くことは、口で言うほど簡単ではないことも示唆している。例えば、子どもはまだ、信じてもらえなかった場合の否定的な結果に気づいておらず、そのため嘘をつくときにあまり恐怖を感じない可能性がある。また、年齢が上がるにつれて、人は自発的な感情的表情を見せるようになる。また、体験した出来事を思い出してもらうとき、幼児は通常、大人よりも短い発話をする。なぜなら、嘘をつく人が話す時間が短ければ短いほど、嘘をつくための非言語的手がかりを示す機会が減り、そのような手がかりを示す可能性が低くなるからである(DePaulo, Lindsay et al.) 言葉が欺瞞の言語的手がかりを伝えるからである(Vrij, Mann, Kristen, & Fisher, 2007)。
大人が子どもの言う真実と嘘を区別する能力を調べる研究がいくつか行われている。これらの実験では、見知らぬ人の欺瞞を検出する研究と同じパラダイムが用いられている。つまり、大人の観察者は知らない子どもの発言の真偽を評価するのであり、頼りになる情報は子どもの行動と発言だけである。表62は、私が知る限り、英語で発表された研究のうち、観察者が強制選択テストに直面し、それぞれの子どもについて、嘘をついていると思うか、嘘をついていないと思うかを示さなければならなかったものを示している9。
これらの研究の合計的中率は49%から66%であった。ほとんどの研究で、真実は嘘よりも発見しやすかった。表62の正確率は印象的なものではなく、大人が子どもの真実や嘘を見抜くのは難しいという印象を与える。特にJackson and Granhag (1997)の研究では、嘘の正確率が25%と低かった。これは実験デザインに原因があるかもしれない。本当のことを言う人は、野生で暮らすチンパンジーの群れについての映画を見て、見たことを思い出すよう求められた。嘘つきは、その映画を見たふりをし、ストーリーをでっち上げるよう求められた。ほとんどの子どもたちが真実であると判定されたので、嘘つきの子どもたちは非常にうまくいったようだ。可能性として考えられるのは、ほとんどの子どもたちが、野生のチンパンジーについての映画を見たことがあるか、動物園でチンパンジーを見たことがあるため、詳細で説得力のある話を作り上げることができたということである。
いくつかの研究で、観察者は年齢の異なる子どもたちの真実と嘘を見抜こうとしており、年齢が上がるにつれて子どもたちの嘘を見抜くのが難しくなるかどうかを検証する機会を得ている(DePaulo, 1991)。その結果、ジェンダー差はあるものの、この仮説はおおむね支持された(Feldman, 1979; Feldman, Jenkins, & Popoola, 1979; Feldman, Tomasian, & Coats, 1999; Feldman & White, 1980; Morency & Krauss, 1982; Westcott, Davies, & Clifford, 1991)。FeldmanとWhite (1980)は、5-12歳児を対象とした研究で、女児では、男児ではなく、年齢が高くなるにつれて、顔が欺瞞について明らかにすることが少なくなり、高年齢の女児が最高の嘘つきになることを発見した。女児は一般に、男児よりも表情豊かであることで報われるため、非言語的な感情表現を練習する機会が多いのかもしれない。ShennumとBugental(1982)は、6歳から12歳を調査し、年齢が上がるにつれて、否定的な感情を中和する(嫌いなものに対して中立のふりをする)能力において、男児が女児よりも優れていることを発見した。男の子は否定的な感情を見せないように教えられているため、否定的な感情を中和する訓練が特によくできているのかもしれない。
これらの結果は、子どもの方が大人よりも嘘を見破るのが簡単であることを示唆しているかもしれないが、そうではないようだ。2つの研究で、幼児(5歳から7歳)と成人の真実と嘘を見分けるよう大人に要求した。その結果、2つの年齢層で精度に差は見られなかった(Edelstein, Luten, Ekman, & Goodman, 2006; Vrij,Akehurst, Brown, & Mann, 2006)。さらに、表62(子どもの欺瞞検出能力)に示された正確率は、付録6.1(成人の欺瞞検出能力)に示された正確率と同程度である。これらの結果は、子どもの真実と嘘を見抜くことは、大人の真実と嘘を見抜くことと同じくらい難しいことを示唆している。
子どものいない観察者よりも、子どものいる観察者の方が、子どもの真実や嘘を見抜く能力が高いかどうかを調べた研究者もいる。その結果はまちまちである。Chahal and Cassidy (1995)は、子どもの真実と嘘の検出において、親がそうでない人よりも優れていることを発見したが、他のいくつかの研究では違いは見られなかった(Ball & O’Callaghan, 2001; Talwar & Lee, 2002; Vrij, Akehurst, Brown, & Mann, 2006)。しかし、これらの研究では、親は自分の子どもではなく、子ども全般の真実と嘘を見抜くよう求められた。MorencyとKrauss (1982)は、親は他の大人よりも自分の子どもの欺瞞を見抜くのに長けていることを発見した。
子どもの発話を聞いたり、発話記録を読んだりするよりも、子どもの顔や体の動きを観察する方が、真実と嘘を識別するのが難しいかどうかを調べた研究がいくつかある(Ball & O’Callaghan, 2001; Chahal & Cassidy, 1995; Feldman & White, 1980; Shennum & Bugental, 1982; Talwar & Lee, 2002)。ChahalとCassidyは、観察者が子どもの顔と体のどちらを見ることができても、嘘発見能力に差がないことを発見した。他の研究では、成人の場合と同様の傾向が見られた。観察者は、子どもの行動を観察するよりも、子どもの声や話し方を聞いたり、話し方の記録を読んだりした方が、子どもの真実や嘘をより正確に見抜くことができた。
年齢が上がるにつれて、子どもたちが嘘を見抜く能力が向上するかどうかを調べた研究もある。そのようなケースもあるかもしれない。デ・パウロ、ジョーダンら(1982)は、子どもは年齢とともに、より多くの文化的、社会的、対人的知識を得ることを示唆している。このことは、他人が説明するある種の影響、出来事、経験が、説明されたとおりに起こるとは考えにくいことに気づくのに役立つかもしれない。この人生経験論は、性的虐待を受けた子どもが、虐待を受けていない子どもよりも嘘発見器に優れている理由を説明できるかもしれない(Bugental, Shennum, Frank, & Ekman, 2001)。また、役割分担の技能が嘘を見抜く能力に関係するというのも合理的である(Feldman, White, & Lobato, 1982; Saarni & von Salisch, 1993)。発信者がどのような状況で発言したかを理解することは、観察者が相手の行動反応がその状況から見て適切かどうかを解釈するのに役立つはずである。
研究が限られているため明確な答えを出すことはできないが、この問題に取り組んでいるすべての研究が、子どもの真実と嘘を見抜く能力は年齢とともに高まることを発見している(DePaulo, Jordan et al., 1982; Feldman et al.) この問題を徹底的に研究したDePaulo, Jordanら(1982)は、年齢の上昇と欺瞞発見能力の向上との間にほぼ完全な直線関係を見出した。Feldmanら(1982)は、嘘発見課題に先立って子どもの「他人の立場に立つ」能力を調査し、この能力と真実と嘘を発見する能力との間に正の相関関係があることを発見した。
まとめ
素人は子どもがついた真実や嘘を見抜くことはできない。親であることは子どもの嘘発見を促進しないが、親は自分の子どもの欺瞞を発見することにおいて、他の大人よりも優れているかもしれない(ただし、これは1つの研究でのみ検証されている)。子どもの真実や嘘は、子どもの行動を観察するよりも、観察者が子どもの言うことに耳を傾けたほうが発見しやすく、子どもの嘘を発見する能力は、年齢が上がるにつれて向上する。
プロの嘘発見者の成人における欺瞞発見能力大学生(嘘発見研究において一般的に観察者である)は、習慣的に欺瞞を発見することはないと主張することができる。おそらく、警察官や税関職員といったプロの嘘発見者の方が、素人よりも優れているのではないだろうか?それは、人々にインタビューし、うそつきを捕まえた経験が、彼らのごまかしを見抜くスキルに良い影響を与えているのかもしれない。職業人自身も一般人も、プロの嘘発見者は一般人よりも真実と嘘を見分ける能力に優れていると考えている(Garrido, Masip, & Herrero, 2004)。
プロの嘘発見者は、数多くの研究にオブザーバーとして参加している。素人の場合と同様、彼らは知らない人の断片を見、その断片の中で発信者が示した非言語的・言語的行動だけが唯一の情報であった。表63は、私が知る限り、英語で発表された研究を示している。正確さの他に、参加者の職業的背景も示している。このグループのほとんどが警察官であることがわかる。表の上部は、専門家が大人の送り主を判断した研究であり、表の下部は、専門家が子どもの欺瞞を見抜く能力を扱ったものである。3つの成人の研究では、「専門家」は囚人であった。まずこれらの結果について述べる。
囚人
Bondらの囚人研究はいずれもアメリカの刑務所で行われ、Hartwigらの研究はスウェーデンの刑務所で行われた。3つの研究の結果は似ていた。囚人は真実を見抜くよりも嘘を見抜く方がはるかに優れていた。嘘の的中率は67%から89%であったのに対し、真実の的中率は35%から51%であった。3つの研究すべてにおいて、一般人(大学生)も観察者として参加しており(付録6.1参照)、囚人と一般人の嘘発見能力を直接比較することが可能である。受刑者は、3つの研究すべてにおいて、総合的な精度の点で一般人を上回った。囚人が真実と嘘を見分ける能力が高いことは、嘘つきがどのように振舞うかについて囚人が素人よりも詳しいことを考えれば、おそらく驚くべきことではないだろう(第5章)。
一般人が2つの研究で真実バイアスを示し、3つ目の研究ではバイアスを示さなかったのとは対照的に、受刑者は3つの研究すべてで嘘バイアスを示し、ほとんどの断片を不正と判断した。囚人における嘘バイアスは、おそらく驚くべきことではない。犯罪者の世界では、人を欺くことはおそらくより一般的であり、犯罪者が犯罪者仲間を信用することは、結果として彼らに欺かれることになりかねないからである。このような人脈がビジネス上の人脈であれば、利用されることになるかもしれないし、そのような状況下で疑いの心を持つことは最善の戦略である。
プロの嘘発見器合計的中率
表63に示した残りの24の研究(28サンプル)では、プロの嘘発見者(主に警察官)が参加している。彼らの総合的正確率は40%から73%の範囲であり、平均総合的正確率は55.91%であった10。8つの研究において、警察官と一般人の嘘発見能力が比較された(DePaulo & Pfeifer, 1986; Ekman & O’Sullivan, 1991; Garrido & Masip, 2001; Garrido et al., 2004; Kassin, Meissner, & Norwick, 2005; Masip, Garrido, & Herrero, 2003b; Meissner & Kassin, 2002; Vrij & Graham, 1997)。これら8件の研究のうち7件では、警察官と一般人との間の総合的な正確率に差は認められず、1件の研究では一般人が警察捜査官を上回っていた(Kassin et al.) 言い換えれば、真実を語る人とうそをつく人の識別において、警察官が一般人より優れていることを示した研究はひとつもない。
エクマンと彼の同僚は、2つの研究において、プロの嘘発見者のいくつかのグループの嘘発見能力をテストした。その結果、あるグループは他のグループよりも嘘発見能力に優れていると結論づけた。1991年の研究では、シークレット・サービスのメンバーは素人よりも優れていたが、彼らの64%の正確さはまだ中程度であった。1999年、彼らは嘘発見能力に優れたグループをさらにいくつか特定し、特にCIAのメンバーは合計73%の正確率を得た11。第一に、シークレット・サービスのエージェントの多くは、政府の要人を潜在的な攻撃から守る保護業務を行ってきた。この仕事には群衆をスキャンすることも含まれ、スキャン作業では非言語的な手がかりに頼らざるを得ない。おそらく、非言語的な手がかりに頼った経験が、欺瞞タスクで欺瞞を示す非言語的な手がかりを見抜くことに長けているのだろう。第二に、シークレット・サービスの職員は、自分たちが扱うほとんどの人は本当のことを言っていると信じている。例えば、警察官は容疑者が嘘をついていると信じていることが多いのとは対照的である。そのため、シークレットサービスは嘘をつく基本的な割合が低く、欺瞞の非言語的・言語的兆候により重点を置いている可能性がある。多くの人が嘘をついていると思い込んでいる警察官にとって、ごまかしを見抜くことは実りある選択肢ではないかもしれない。彼らは、容疑者の主張を裏付ける、あるいは信用を失墜させる証拠を探すことに、より依存するかもしれない12。
真実と嘘の正確率と嘘バイアス
真実と嘘を見抜く能力を別々に検証して初めて、プロの嘘発見者と一般人の違いが浮かび上がってくる。一般人は嘘よりも真実を見抜くのが得意であるが、プロの嘘発見者にはこの傾向は見られない。彼らの真実の的中率は20%から73%、嘘の的中率は31%から80%であった。9つのサンプルでは、彼らは嘘よりも真実を発見する方が得意であり、他の10サンプルでは、彼らは真実よりも嘘を発見する方が得意であった。プロの嘘発見者の平均的な真実発見率は56.35%、平均的な嘘発見率は56.11%であった13。一般人と比較すると、プロは嘘を発見する能力がやや高く、真実を発見する能力がやや低いようである。これは少なくとも部分的には、プロの嘘発見者が真実バイアスを示さないためである。実際、多くの研究で、警察官は嘘バイアスを示しており、接した断片の大半を欺瞞と判断している14。さらに、プロの嘘発見者と一般人の両方が参加したすべての研究において、プロの嘘発見者は一般人よりも断片を欺瞞と判断する傾向が強かった(Garrido et al, 2004; Kassin et al.) 最後に、警察官の警察での勤務年数が長ければ長いほど、嘘バイアスは顕著になる(Masip, Alonso et al., 2005; Meissner & Kassin, 2002)15。おそらく、警察内での社会化が警察官の疑念を増大させ、その結果、より多くの嘘判断をするようになるのだろう(Masip, Alonso et al., 2005)16。
信頼性
多くの嘘発見研究では、正確性に加えて、観察者が下した真実性判断に対する自信を測定している。このような研究では、通常、確信度と正確さの間には関係は認められない(メタ分析については、DePaulo, Charlton, Cooper, Lindsay, & Muhlenbruck, 1997を参照)。つまり、自信は正確さを予測しないのである。プロの嘘発見者と一般人の信頼度と正確度を比較した研究では、興味深い傾向が示されている:プロの嘘発見者は、一般人よりも真実性判断に自信を持っているが、正確性は高くない(DePaulo & Pfeifer, 1986; Garrido et al.) AllwoodとGranhag (1999)は、自信を持つ傾向は警察官や嘘発見器に特有のものではなく、様々な仕事を遂行する多くの専門家グループに共通するものであると指摘している。
しかし、自分の嘘発見能力に対する高い自信は、その自信が不当なものである場合には有害となりうる(Kalbfleisch, 1992)。高い自信は、限られた情報に基づいて迅速な決定を下すことにつながることが多い(Levine & McCornack, 1992; Lord, Ross, & Lepper, 1979)。次のような状況を想像してみよう。ある人が車で休暇に出かけようとするが、その人が出発しようとする時は天気が特に悪い。このような状況では、不安なドライバーはおそらく経験豊富なドライバーよりも道路上の状況についてより多くの情報を収集し、したがって運転するかどうかについてより熟考された決定を下すだろう。例えば、不安なドライバーは天気予報に耳を傾け、状況がどのように進展するかを調べるだろう。経験豊富なドライバーは、「天気はそれほど長くは続かないだろう」とか「ここの天気は悪いことで有名だが、休暇の目的地に近づけばよくなるだろう」といった不十分なヒューリスティックに頼るだろう。これと同様に、嘘発見スキルに対する高い自信は、真実を語る人と嘘をつく人を識別する際にヒューリスティクスを使うことにもつながるかもしれない。欺瞞の発見におけるヒューリスティックの使用は、誤りを犯しやすい。第3章で述べたように、欺瞞と非言語的行動の関係は、単純な判断ルールでアプローチするには複雑すぎる。
高い信頼性は他の理由でも有害である。捜査官が相手の態度を判断することでウソを見抜こうと躍起になり、物的証拠を探すことが犠牲になってしまう可能性がある(Colwell, Miller, Lyons, & Miller, 2006)。また、高い自信は嘘発見についてさらに学ぶ意欲を減退させる可能性が高い。なぜなら、捜査官は自分自身がすでにこのテーマについて知識があると考えるかもしれないからである。プロの嘘発見者がこのタスクにおいて典型的な中程度のパフォーマンスを示すことを考えると、嘘発見についてもっと学びたいという意欲が低下することは望ましくない。さらに、本章の「考察」で詳しく述べるが、刑事が容疑者が嘘をついていると確信している場合、刑事は自白を得るために説得的な尋問技術を容疑者に課すことがある。容疑者が無実であれば、これは虚偽の自白につながるかもしれない。最後に、高い自信は、法廷で情報が提示されるときに結果をもたらすかもしれない。陪審員は、証人がどれほど自信を持っているかによって、特に影響を受けることが研究で示されている(Cutler, Penrod, & Dexter, 1990; Cutler, Penrod, & Stuve, 1988; Lindsay, 1994)。このことは、陪審員は、容疑者の態度から容疑者が嘘をついていることがわかったと自信をもって表明した警察官を、そのような自信を表明していない警察官よりも信じる可能性が高いことを示唆している。
賭け金
すでに述べたように、嘘発見研究では、観察者は通常、実験のために嘘をついたり真実を話したりする送り手にさらされる。このような研究では、例えば、警察官のごまかしを見抜く能力を正確に測定することはできないと主張することができる。なぜなら、このような研究における送り手の賭け金は、警察での取り調べにおける容疑者の賭け金よりもはるかに低いからである。実験室で高い賭け金を導入することの問題点(第3章)を考えると、警察官の真の欺瞞発見能力を調査する唯一の有効な方法は、現実の犯罪捜査の場で語られる真実と嘘を発見する際のスキルを調べることである、と主張することができる。われわれは、一連の嘘発見実験でまさにこれを行った。表63中の「*」印のついた研究はすべて、警察官に現実の危険な状況下で語られた真実と嘘を見分けるよう求めたものである。いくつかの研究では、警察官は、殺人、放火、レイプなどの犯罪で告発された容疑者に対する警察の取調べの断片をビデオテープで見せられた(Mann & Vrij, 2006; Mann, Vrij, & Bull, 2004, 2006; Mann et al.) この断片は、第3章で詳述したMann, Vrij, and Bull (2002)による実際の警察と被疑者の面接の分析から得られたものである。これらの研究は、警察官が重大な真実や嘘を見抜く能力がそれなりに高いことを示唆する、比較的高い総合的正確率(65%から72%の範囲)を示している。しかし、この結論を導き出す際には注意が必要である。別の研究(Vrij & Mann, 2001b)では、行方不明の親族を探す手助けを一般大衆に求めたり、親族を殺した犯人についての情報を求めたりする人々の記者会見をビデオに録画したものを警察官に見せた。これらの記者会見では全員が嘘をつき、その後全員が行方不明者を殺害した罪で有罪になった。この研究では、警察官は偶然のレベル(正確率51%)の成績を収めた。最後に、第3章で詳述した、有罪判決を受けた殺人犯(Vrij & Mann, 2001a)のインタビューの断片を警察官に見せた。警察官は比較的多くの真実を正しく分類したが(70%)、嘘発見能力は中程度であった(57%)18。このように、全体的な調査結果は、警察官は重大な状況下でも、真実/嘘発見において頻繁に誤りを犯すことを示唆している。
プロの嘘発見者の子どもの欺瞞発見能力
表64は、私が知る限り、英語で発表された研究のうち、プロの嘘発見者の子どもの真実と嘘を発見する能力が検証されたものを示している。子どもを対象とした研究は8件(9サンプル)しかないが19、その結果は成人を対象としたものと類似している。つまり、正確さの範囲は43%から67%であり、これは成人の研究で達成された正確さの範囲に匹敵する。さらに、専門家と一般人の間で比較が行われた研究(Hershkowitz, Fisher, Lamb, & Horowitz, 2007; およびWestcott, Davies, & Clifford, 1991を除くすべての研究)では、専門家は一般人と同じ嘘発見能力を達成した。最後に、素人より正確でないにもかかわらず、専門家は素人より自分の判断に自信があった(Leach, Talwar, Lee, Bala, & Lindsay, 2004)。
まとめ
プロのライ・キャッチャーは、コインをひっくり返して予想されるよりもいくらか高い精度で真実と嘘を見抜くことができる。おそらく諜報員を除けば、プロがこのタスクで素人を上回ることはないだろう。素人に比べ、プロの嘘発見者は、誰かを不正直と判断する傾向が強く、自分が下す真実性の判断により自信を持っている。
真実と嘘を識別する能力における個人差
多くの嘘発見研究では、50%から60%の精度を示しているが、研究内でも観察者間に個人差がある。例えば、警察官が殺人犯、強姦犯、放火犯のビデオテープに録画された警察官と被疑者の面接を評価した我々の嘘発見実験(Mann et al., 2004)では、大きな個人差が認められ、個々の警察官の正確率は、低い30%から非常に高い90%(3人の警察官が達成、Mann 2001)まで様々であった。嘘発見研究におけるこのような個人差は、どのように説明できるのだろうか?まず、精度が高いか低いかは、運の良し悪しによるところもあるだろう。われわれの実験では、30%の精度を得た警官が2回目の研究でより高い精度を得る可能性もあるし、90%の精度を得た3人の警官が追跡研究でより低い精度を得る可能性もある。実際、嘘発見器を1回の嘘発見テストではなく、4回の嘘発見テストに曝した研究では、どの警察官も一貫して非常に低い、あるいは非常に高い正確率を得なかった(Vrij, Mann, Robbins, & Robinson, 2006)。にもかかわらず、4回のテストの後でも、一部の警察官は他の警察官より優れており(正確率は62%から82%)、安定した個人差が存在する可能性を示している20。また、あるテストで嘘を見抜く能力は、別のテストで嘘を見抜く能力とある程度正の関係があることを発見した警察官もおり(Edelstein et al.
ある人が他の人より嘘発見能力が優れている理由を解明しようとする研究が行われてきた。個人差を説明できない2つの要因についてはすでに述べた。嘘発見能力は、嘘発見者の職業(おそらく諜報員を除く)とは無関係であり、嘘を発見する能力に対する自信とも無関係である。嘘発見と無関係な他の特徴は、プロの嘘発見者としての勤続年数(レビューはAamodt & Custer, 2006を参照)、嘘発見者の年齢である(Aamodt & Custer, 2006; Vrij & Mann, 2005)。本節では、その他の可能性のある関係を検討する。まず、ウソ発見者のジェンダーと真実とウソを識別する能力との関係について述べ、続いて、ウソ発見技能とウソ発見者の性格との関係、ウソ発見者がごまかしを発見する際に用いる手がかり、ウソ発見者が発信者のコミュニケーション・スタイルに精通していること、ウソ発見者の動機について述べる。
嘘発見スキルのジェンダー差
女性は他人の非言語的行動の解釈において男性より優れている。つまり、女性は男性よりも、他人が意図的に自分に伝えているメッセージを理解することに長けている(Hall, 1979, 1984; Rosenthal & DePaulo, 1979)。女性は男性よりも非言語的な手がかりの観察と解釈に時間がかかり、意思決定プロセスでより多くの手がかりを使う(Hurd & Noller, 1988)。表情を読み取ることでは男性よりも女性の方が有利であり、隠すことのない人の表情をより正確に読み取ることができる(DePaulo, Epstein, & Wyer, 1993)。Hall (1979)は、このような所見に対して、宿泊施設の説明を行った。彼女は11カ国で非言語的メッセージの理解における女性の優劣を比較した。彼女は、女性が最も抑圧されていると思われる国々、例えば高等教育を受ける女性の割合が少ない国々において、女性が最も優れていることを発見した。多くの社会における女性の性的役割は、男性以上に他者に合わせなければならないことを意味している。相手の非言語的な行動を解釈できることは、そのための貴重なスキルかもしれない。
女性は非言語的メッセージを読み取る能力では男性より優れているが、見知らぬ人の真実や嘘を見抜く能力では男性に及ばない(DePaulo, Wetzel et al., 2003; DePaulo, Epstein, & Wyer, 1993; Hurd & Noller, 1988; Manstead, Wagner, & MacDonald, 1986; Porter, Woodworth, McCabe, & Peace, 2007)。しかし、女性は男性よりも疑い深くなく、自分が真実を言われていると信じる傾向が強い(DePaulo, Epstein, & Wyer, 1993)。言い換えれば、女性は嘘発見タスクにおいて、非言語的行動を読み取ることにおいて男性に対する優位性を失い、見知らぬ人を評価する際に真実バイアスを示すようである。次の説明は合理的に聞こえる。女性は男性よりも、相手が伝えたい情報を読み取ることに長けている。しかし欺瞞の最中、嘘つきは自分の本心や考えを隠そうとする。嘘を見破るとき、観察者は人が何を伝えたいかを調べるのではなく、何を隠そうとしているかを見るべきである。おそらく、女性が見知らぬ人の嘘を見抜こうとするとき、その人が伝えようとしていることに影響されすぎて、嘘の見抜き方に誤りが生じ、真実バイアスがかかってしまうのだろう。
しかし、女性は、ロマンチックなパートナーや友人など、知っている人の真実や嘘を見抜こうとするとき、非言語的行動を読み取ることにおいて、男性に対する優位性を失うようには見えない。McCornackとParks (1990)は、恋愛相手の嘘を見抜くことにおいて、女性は男性より優れていることを発見した。別の研究では、女性は、男性ではなく、恋愛相手が残念な知らせを受けたかどうかを見分けることができたが、男女ともに、見知らぬ人が残念な知らせを受けたかどうかを見分けることはできなかった(DePaulo, Wetzel et al., 2003)。最後に、女性の友人同士は、友だちになって最初の1カ月間よりも、6カ月間の方が、互いの嘘を見抜く精度が高くなったが、男性の友人同士は、6カ月間、互いの嘘に対する洞察力は変わらなかった(Anderson et al., 1999)。まとめると、女性は男性よりも嘘発見能力が高いが、それは嘘を見抜こうとする相手を知っている場合に限られるということである。おそらく女性は、友人やパートナーの自然で正直な振る舞いや話し方を男性よりもよく知っているため、ウソを見抜こうとするときに、この正直な基本的態度と調査対象の態度とを比較することで、有利になるのだろう。あるいは、男性も女性も友人やパートナーの正直な態度に同じように気づいているが、女性はこの正直な態度と友人やパートナーの嘘との微妙な違いに気づき、男性は気づかないのかもしれない。
観察者の性格と嘘発見能力
観察者の性格が真実と嘘を見抜く能力に影響を与えるかどうか、何人かの研究者が検証している。DePaulo and Tang (1994)は、おそらくこれを調査した最初の研究者である。彼らは性格特性である社交不安を調べた。社交不安の高い人は、自尊心が低く、社交の際に緊張し、自分はうまく伝わらないと考える。デパウロとタンは、いくつかの理由から、社会不安の高い観察者は、社会不安の低い観察者よりも真実と嘘を見抜くのがうまくいかないだろうと主張した。緊張は、比較的少数の手がかりに注意を集中させることにつながる。つまり、社会不安のある観察者は、限られた手がかりに集中しすぎて、ごまかしの重要な手がかりに気づかない可能性がある。また、社会不安のある人は、無能感や地位を失うことへの懸念など、課題とは関係のない考えに気を取られやすい。そのような注意散漫は、またしてもごまかしの重要な手がかりを見逃すことにつながりかねない。
さらに、嘘を見抜こうとすることと、タスクに無関係な心配事が組み合わさることで、観察者のワーキングメモリに大きな負荷がかかる。タスクの要求が高くなりすぎると、嘘発見タスクに関連する情報を処理する能力が損なわれる可能性がある。最後に、社会不安のある観察者が情報を適切に処理し、重要な手がかりを見つけたとしても、それを誤って解釈することがある。社会不安のある人は、社会的相互作用に対して防衛的なアプローチをとることが多い。他人に悪い印象を与える可能性を心配するあまり、それを防ごうと安全な交流をしてしまうのである。安全なアプローチの一つは、送り手が読まれることを望む方法で合図を読むことである。DePauloとTangの研究では、社会不安の高い観察者は、社会不安の低い観察者よりも、確かに真実と嘘を見分けるのが苦手であることが示されたが、他の研究では、社会不安の高い観察者と低い観察者の間に差は見られなかった(Vrij & Baxter, 1999; Vrij, Harden, Terry, Edward, & Bull, 2001)。他の研究者は、自己認識とごまかしを見抜く能力との関係を調べた。自己認識とは、自己に注意を向けている状態と定義できる。自己認識の高い人は、私的自己意識と呼ばれることもあるが、「自分についてよく考えている」、「自分の内面にある感情に概して気を配っている」、「自分の動機を常に吟味している」といった発言に同意する傾向がある。自己認識は自分の心を洞察するものであるから、他人の心の中で何が起こっているかを洞察することもできる。この読心能力は、嘘の発見を容易にするかもしれない。実際、自己認識/私的自己意識と、真実と嘘を見分ける能力との間には、正の関係が見出されている(Johnson, Barnacz, Constantino, Triano, Shackelford, & Keenan, 2004; Malcolm & Keenan, 2003)。
私的自意識は内向性と関連している。内向的な人は一般的に、考えや概念の内的世界を志向する。思考や考察がもっぱら自己を対象とする私的自己意識とは異なり、内向的な人の内的世界は自己以外の問題にも及ぶ。内向的な人が自分自身を振り返ることは、自己認識のスコアが高い人にとって有益であったのと同じように、嘘を見抜くのに有益なのかもしれない。内向性と真実と嘘を見分ける能力との間に関係は見られなかったが(Vrij & Baxter, 1999; Vrij, Harden et al., 2001)、O’Sullivan(2005)は、彼女が例外的に優れた嘘発見能力を持っていると主張する人々(魔法使い、脚注12参照)のほとんどが内向的であるようだと報告している。自己認識能力が高く、内向的な人は他人の心を読むのが得意かもしれないし、優れた俳優は他人の行動を読むのが得意かもしれない。嘘つきは、見せたくない緊張や認知的負荷の合図を抑え、信用できると思われる行動を見せるために演技を始めることがあることは、前の章ですでに述べた。おそらく演技のうまい人は、誰かが「自然な」行動(例えば、真実を話すこと)を見せているのか、それとも誰かが「演技」(例えば、嘘をつくこと)をしているのかに気づく能力に優れているのだろう。ある研究では、演技の上手な人の方が下手な人よりも真実と嘘を見分ける能力に優れていることがわかったが、2番目の研究ではこの結果を再現することはできなかった(Vrij, Harden et al.) まとめると、所見はまちまちで結論は出ていないが、自己認識が高く、内向的で、演技が上手な人は比較的嘘発見能力が高く、社会的不安の強い人は比較的嘘発見能力が低いという十分な証拠がある。
別の問題は、嘘発見者の性格が嘘発見技術に対する自信に関係しているかどうかである。社交不安の高い人、内向的な人、内気な人は、社交不安の低い人、外向的な人、内気でない人に比べて、社会的相互作用に自信がない。社会的相互作用に対する自信のなさが、社会的相互作用を判断する自信のなさにつながるというのは理にかなっている。研究はこの仮説を支持している(Vrij & Baxter, 1999; Vrij, Harden et al.) 嘘発見課題の難しさを考えると、自信を持ちすぎないことが嘘発見において有益であろうことはすでに説明した。
観察者が用いる手がかりと嘘発見スキルの関係
欺瞞の診断手がかりに詳しいと、真実や嘘を見抜く能力が高くなるというのは、もっともらしく聞こえる。James Forrestらは、まさにこのことを発見した(Forrest, Feldman, & Tyler, 2004)。彼らはまず、参加者に18項目の「欺瞞の手がかりに関する信念」質問票に記入してもらい、その後、嘘発見実験に参加してもらった。参加者は、欺瞞の手がかりに関する信念の質問に正確に答えれば答えるほど、嘘発見課題の成績が良くなった。
他のほとんどの研究では、観察者が使う手がかりと嘘発見能力との関係は別の方法で調べられている。ほとんどの研究では、観察者は嘘発見課題の前に、欺瞞を発見しようとするときにどの手がかりに注意を払うかを尋ねられるか、あるいは、それぞれの真実性判断の後に、どの手がかりに基づいて判断したかを尋ねられる。殺人犯、強姦犯、放火犯に対する警察の取調べの断片をビデオに録画したものを警察官に見せたわれわれの研究では、警察官が報告した手がかりと、真実と嘘の検出の正確さとの間にいくつかの関係が生じた(Mann et al.) 第一に、優れた嘘発見者は、下手な嘘発見者よりも言語的な手がかり(あいまいな返事、話の矛盾など)に言及する頻度が高かった。第二に、視覚的手がかり(視線嫌悪、姿勢、動作など)を多く口にするほど、その精度は低くなった。特に、「嘘つきは目をそらす」「そわそわする」と述べた警察官のスコアが最も悪かった。言い換えれば、容疑者の言葉に注意深く耳を傾ける人の方が、容疑者の非言語的行動に集中する人よりも、嘘発見器として優れていたのである。
他の研究でも、送り手の話を聞いている人は嘘発見能力が高く、送り手を見ている人は嘘発見能力が低いことが明らかになっている。Andersonら(1999)とFeeley and Young(2000)は、参加者が口にする声の手がかり(話し間違い、話しの詰め、間、声)が多いほど、精度が高くなることを発見した。第3章で述べた有罪判決を受けた殺人犯がついた真実と嘘を検出しようとした研究では、欺瞞の手がかりとして視線嫌悪とそわそわを挙げた参加者が最も低い精度を達成したことがわかった(Vrij & Mann, 2001a)。また、Porter, Woodworth, McCabe, & Peace (2007)は、被験者が報告した視覚的手がかりが多いほど、真実と嘘を見分ける能力が低下することを発見した21。
しかし、エクマンとその同僚は、視覚的手がかりに注意を払うことが、ごまかしを見抜くのに有用であることを実証した。FrankとEkman (1997)は、優秀な嘘発見者は、下手な嘘発見者よりも短い感情表情を見抜くのが得意であると報告している。EkmanとO’Sullivan(1991)は、発声/言語的手がかりと視覚的手がかりの両方を挙げた参加者は、発声/言語的手がかりまたは視覚的手がかりだけを挙げた参加者よりも高い正確率を得ることを発見した。
まとめると、事実上すべての研究で、嘘を見抜くためには、発言に注意深く耳を傾けることが必要であり、単に行動に注意を払うだけでは嘘の発見が妨げられることが示された。これらの知見は、発信者を見ることしかできない観察者は、聞くことしかできない観察者、あるいは発信者を見ることも聞くこともできる観察者よりも成績が悪いという、上で報告された知見と一致している。これとは対照的に、警察マニュアルはしばしば欺瞞の視覚的手がかりに焦点を当てている(第5章)。例えば、Inbauら(2001)は、嘘つきは視線回避、不自然な姿勢変化、自己適応、話すときに口や目に手を当てるなど、さまざまな視覚的手がかりを示すことを示唆している。私たちは、嘘発見研究(Mann, Vrij, & Bull, 2004)において、これらの「インバウ・キュー」を使うことの有効性を測定した。警察官が口にしたインバウ・キューの数を数え、これを嘘発見課題の成績と関連づけた。その結果、警察官が言及したインバウ・キューの数が多ければ多いほど、真実と嘘を見分ける能力が低くなることがわかった。さらに、Kassin and Fong (1999)の実験では、インバウらがマニュアルで述べている視覚的手がかりを何人かの観察者に教えた。その後の嘘発見テストの成績は、訓練を受けていない参加者の成績よりも悪かった。つまり、Inbauら(2001)のマニュアルで議論されている欺瞞の視覚的手がかりに関する情報を支持することは逆効果であり、嘘発見器をより悪いものにしてしまうのである。他の警察マニュアルでも、Inbauら(第5章)が報告したものと同様の視覚的手がかりが報告されており、それらのマニュアルでも同様であると考えられる。それらのマニュアルで報告されている視覚的手がかりに関する情報を支持すると、嘘発見が不得意になる可能性が高い。
嘘つきのコミュニケーション・スタイルに慣れ親しむ
ウソをつく人のコミュニケーション・スタイルに慣れていると、ウソ発見がうまくなる。たとえば、人は魅力的な人と話すとき、魅力的でない人と話すときよりもオープンなコミュニケーション・スタイルをとる。つまり、魅力的な人とそうでない人は、異なるコミュニケーション・スタイルに慣れているのである(DePaulo, 1994)。DePaulo, Tang, and Stone (1987)は、このことが真実と嘘を見抜く能力に影響を与えるかどうかを調べた。発信者は、魅力的な会話相手と魅力的でない会話相手に真実と嘘を言うよう求められた。これらの発言はビデオテープに録画され、魅力的な観察者と魅力的でない観察者に提示された。ビデオテープには、送信者のみが映し出され、嘘を言われた魅力的な人と魅力的でない人は映し出されなかった。その結果、魅力的な観察者は、魅力的な人についた真実や嘘を見抜くのに長けているのに対し、魅力的でない観察者は、魅力的でない人についた真実や嘘を見抜くのに長けていることが明らかになった。したがって、魅力的な人も魅力的でない人も、自分が慣れ親しんでいるコミュニケーション・スタイルで話しかけられたときには、嘘を見抜くのに長けているのである。
同じようなパターンが、同じ国の出身者や、異なる国に住む人々から語られた真実や嘘を検出しようとした場合にも現れる。観察者は、外国人の発信者よりも自国の発信者の方が、真実や嘘を見抜く能力が高い。例えば、ある研究では、観察者は音声なしで表示されるビデオの断片を見た。アメリカ人の観察者は、同じアメリカ人の送り手によってなされた真実や嘘を偶然のレベル以上に見抜くことができたが、ヨルダン人の送り手に対してはそれができなかった。ヨルダン人観察者は逆のパターンを示した。彼らは、ヨルダン人の送り手の真実と嘘を偶然のレベル以上に見抜くことができたが、アメリカ人の送り手の真実と嘘は見抜くことができなかった(Bond, Omar, Mahmoud, & Bonser, 1990)。
その後の研究で、BondとAtoum (2000)は、観察者が発言内容も聞き取れる場合に、真実と嘘を識別する能力を調べた。彼らはインド人もサンプルに加えた(Bond & Rao, 2004も参照)。このとき、アメリカ人、ヨルダン人、インド人は、外国人が話した真実と嘘を偶然のレベル以上に見分けることができたが、それは外国人の話を聞いたり見たりすることができた場合に限られた。これらの外国人の行動を観察したり、彼らのスピーチを聞いたりするだけでは、偶然のレベルのパフォーマンスしか得られなかった。つまり、外国人の嘘を見抜くには、視覚と聴覚の両方が必要だったのである。観察者は外国人が何を話しているのか理解できない–彼らは外国語を話せないのだ–ので、音の条件では、発声の合図は示されたが、言葉の合図は示されなかった。したがって、これらの声の合図を聞くことは、嘘を発見するために必要な条件であった。
やる気のある嘘発見器
人は嘘を見破るのに、いつも同じようにやる気があるわけではない。ある母親は、自分の息子が「食事がおいしかった」と言ったときに、その話が本当かどうかを確かめようとはあまり思わないかもしれないが、自分の財布からお金を出したことを否定したときには、真実を知りたいと思うかもしれない。動機づけは、真実発見と嘘発見とで異なる影響を与える可能性がある。直感的に言えば、動機づけはパフォーマンスを向上させ、動機づけの高い嘘発見器は、動機づけの低い嘘発見器よりも真実と嘘を見分ける能力が高いと予想される。動機づけはおそらく、嘘発見器をより注意深くさせ、その結果、そうでなければ発見できないかもしれない偽りの手がかりを発見しやすくする。しかし、動機づけが高まると嘘発見能力が低下する可能性もある。心理学的研究では、一般に、動機づけが高いと、課題が比較的簡単な場合にはパフォーマンスが向上するが、課題が比較的難しい場合にはパフォーマンスが低下することが実証されている(Kim & Baron, 1988; Pelham & Neter, 1995; Zajonc, 1980)。
この現象を説明するために、Zajonc (1980)は、動機づけが覚醒を生み出し、覚醒が個人の「支配的反応」を行う傾向を高めると提唱した。課題が簡単であったり、よく学習されたものであったりすると、支配的反応は正しいことが多いが、課題が複雑であったりすると、支配的反応は正しくないことが多い。嘘発見は複雑な情報処理と解釈を必要とする難しい課題であるため、ザジョンクの仮定が正しければ、動機づけは嘘発見のパフォーマンスを向上させるどころか、むしろ損なわせるはずである。研究はZajoncの仮定を支持し、動機づけが真実と嘘を見抜く能力を低下させることを実証している(Forrest & Feldman, 2000; Porter et al.) おそらく動機づけがあると、観察者は偽りの診断指標になると信じている手がかり(優勢な反応など)に頼るようになり、人の好きな手がかりは診断指標にならないことが多いので(第5章)、嘘を見抜く能力が損なわれる可能性が高い。もしこの推論が正しければ、動機づけが高まれば、優秀な嘘発見器の性能が向上するはずである。なぜなら、動機づけがあれば、嘘を見抜く手がかりに集中できるからである。この点については、これまで誰も検証していない。
O’Sullivanは、動機づけと優れた嘘発見器であることの間には正の関係があると主張している(O’Sullivan, 2005; O’Sullivan & Ekman, 2004)。しかし、彼女は動機づけについて、これまで議論されてきたのとは異なる方法で言及している。上述した研究では、観察者は特定の嘘発見課題で良い結果を出すために動機づけられたが、実生活では、つまり実験の文脈の外では、これらの観察者は必ずしも動機づけられた嘘発見者ではなかったかもしれない。O’Sullivanは、実生活でウソつきを捕まえようとする意欲のある人々のことを指している。彼女は、優秀な嘘発見者は他人を理解する能力を向上させたいと考えており、自分のパフォーマンスについてのフィードバックを求めていると主張する。後者について、彼女は、嘘発見タスクで間違った判断をしたときに苦悩した数人の嘘発見の魔術師について述べている。彼らは何度もそのことを口にし、数日後もそのことを思い出し、自分が何を間違えたのかを理解しようとする(O’Sullivan, 2005)。言い換えれば、オサリバンは、欺瞞についてより深く知ろうとする意欲のある人々のことを指している。上述したように、欺瞞について知識があることは嘘の発見を容易にする可能性が高いからである。
まとめ
真実と嘘を見抜く能力にはいくつかの要因が影響する。友人や恋愛相手のごまかしを見抜こうとするとき、女性は男性よりもこの作業が得意であるが、見知らぬ人を判断するときには男性に勝ることはない。さらに、自己認識の高い人、内向的な人、演技のうまい人は比較的嘘発見がうまいが、社交不安の強い人は比較的嘘発見が下手である。優れた嘘発見者は、下手な嘘発見者よりも、ごまかしの診断的手がかりに詳しい。良い嘘発見者はさらに、送り手の言うことを注意深く聞いたり、送り手の話し方と行動の両方に注意を払うが、悪い嘘発見者は送り手の行動だけに注意を払う。嘘発見器が送り手のコミュニケーション・スタイルに精通している場合は、そうでない場合よりも嘘発見がいくらか容易である。真実と嘘を識別する意欲があると、偽りの手がかりに疎い嘘発見器の成績は低下する。しかし、動機づけの結果、ごまかしの手がかりについて知識が深まるのであれば、動機づけはおそらくウソ発見能力を向上させる。
真実性判断に影響を与える要因
前のセクションでは、真実/嘘発見における嘘発見者の精度に影響する要因について論じた。このセクションでは、正確さではなく、観察者の真実性判断に影響を与える要因について論じる。真実性判断とは、観察者がある発言を真実と判断するか欺瞞と判断するかということである。真実性判断に影響を与える要因の1つ、「疑わしいと思うことで、嘘の判断が多くなる」ことについてはすでに述べた。このセクションでは、発信者の性格、発信者の民族的背景、観察者が能動的なインタビュアーか受動的なインタビュアーか、そして質問(「プロービング」)である。
送り手の性格
第5章では、人々は嘘つきがどのように振舞うかについてステレオタイプ的な見解を持っていることを述べた。こうした見方の結果として、嘘をついているか真実を話しているかにかかわらず、観察者に疑わしい印象を与える人がいる一方で、観察者に正直な印象を与える人もいる。嘘つきがどのように振舞うかというステレオタイプに自然に正直に振舞う人は、嘘をついているという印象を与え(不誠実な態度バイアス)、正直者がどのように振舞うかというステレオタイプに自然に正直に振舞う人は、本当のことを言っているという印象を与える(正直な態度バイアス)22。
不誠実な態度バイアスと正直な態度バイアスは性格的特徴に関連している。人前での自意識が強い人は、本当のことを言っているか嘘をついているかにかかわらず、他者に対してあまり信用できない印象を与える傾向がある。このような人は、他人から詮索されることを過度に気にし、不安になる。その不安が行動に表れ、不誠実に見えるのだ。内向的で社交的な人は、他人に不誠実な印象を与える。内向的な人の社会的不器用さや、社会的不安のある人が自然に放つ緊張、神経質、恐怖といった印象は(Schlenker & Leary, 1982)、観察者に欺瞞の指標として解釈される。
対照的に、表現豊かな人は、主張の真偽にかかわらず、信頼性を醸し出す。表現力または「自発的発信」(DePaulo & Friedman, 1998)は、「他者に自分の感情を意図的に伝えようとしていないときに、その非言語的表現行動から人の感情を読み取ることができる容易さ」(DePaulo & Friedman, 1998, p.13)と定義することができる。表現力はカリスマ性と関連している(Friedman, Riggio, & Casella, 1988)。表現力豊かな人の第一印象は一般的に肯定的で、一般的に好かれ、魅力的と評価されることが多い(DePaulo & Friedman, 1998; Gallaher, 1992)。彼らの自発性は疑惑を和らげる傾向があり、そのため嘘から逃げやすくなる(Riggio, 1986)。最後に、社会的に機転が利き、有能な人は誠実な印象を与える。そのような人は、社交的な交流において快適でリラックスしており、自分を効果的に見せる訓練を積んでいる。
興味深いことに、こうした態度は嘘をつく人の気質を正確に反映しているわけではない(第2章も参照)。例えば、内向的な人は頻繁に嘘をつかず(Kashy & DePaulo, 1996)、犯罪を犯す回数も外向的な人よりも少ない(Eysenck, 1984)。さらに、社会的不安の強い人は、挑発されるとすぐに嘘をつき続ける傾向が少ない(Vrij & Holland, 1998)23,24。
発信者の民族的起源
非言語的行動は文化的に媒介されている(第3章)。例えば、視線嫌悪がある。アフリカ系アメリカ人は白人アメリカ人よりも視線嫌悪を示し(LaFrance & Mayo, 1976)、オランダに住むトルコやモロッコ出身者は生粋のオランダ人よりも視線嫌悪を示す(van Rossum, 1998; Vrij, Dragt, & Koppelaar, 1992)。このように、会話相手の目を見ることは典型的な白人的行動であり、非白人にはしばしば見られないようである。文化の違いがこの効果をもたらしている。会話相手の目を見ることは、西洋文化では礼儀正しいとされているが、他のいくつかの文化では無作法とされている(Vrij & Winkel, 1991; Vrij, Winkel, & Koppelaar, 1991; Winkel & Vrij, 1990)。
非言語的行動には、さらに文化的な違いが見られる。オランダでは、生粋のオランダ系白人およびスリナム系黒人(オランダの旧植民地スリナム出身で、現在はオランダ在住)が、警察の模擬面接で嘘をついたり真実を話したりする際の非言語的行動パターンを調べた(Vrij & Winkel, 1991)。オランダ人またはスリナム人の面接官が面接を行ったが、このことは調査結果に影響を与えなかった。25しかし、オランダ人白人とスリナム人の参加者の間には、真実を話すか嘘をつくかにかかわらず、行動に大きな違いが見られた。スリナム人は、嘘をついているかどうかに関係なく、より多くの発話障害を起こし、より多くの視線嫌悪を示し、より頻繁に微笑み、より多くの自己適応者とイラストレーターを作った。
このことは、観察者は異文化間の相互作用に注意する必要があり、異なる民族出身の送り手が示す非言語的行動を、その文化の知識をもって解釈すべきであることを意味する(Ruby & Brigham, 1997; Vrij, 1991)。われわれは、これが常に起こるとは限らないという証拠を得た。オランダ人とスリナム人の送り手(プロの俳優)が参加した、警察の模擬面接のビデオテープを用意した。それぞれのインタビューには異なるバージョンが用意された。送り手は、あるバージョンの事情聴取では典型的な「オランダ系白人」の行動を示し(例えば、視線回避を限定的に示す)、別のバージョンの事情聴取では典型的な「スリナム人」の非言語的行動を示した(例えば、視線回避をより多く示す)。他のビデオテープでは、送り手が行った自己適応と発話妨害の数を操作した。白人のオランダ人警察官は、それぞれのインタビューの1つのバージョンを見て、行為者がどの程度不審な印象を与えたかを示すよう求められた。警察官はスリナム人の発信者とオランダの白人発信者を同じように怪しいと感じた。しかし、送り手の非言語的行動は警察官の印象に影響を与えた。送信者が典型的なスリナム人の振る舞いを見せたときは、典型的なオランダ系白人の振る舞いを見せたときよりも、一貫して不審な印象を与えた(Vrij & Winkel, 1992b, 1994)。例えば、自己適応者を使った実験では、典型的なスリナム人の非言語的行動を示した場合、72%の警察官が送り主を疑わしいと感じたのに対し、典型的なオランダ系白人の非言語的行動を示した場合は、41%しか疑わしいと感じなかった。
これらの結果は、嘘つきがどのように行動するかについての人々の信念を考慮に入れれば容易に説明できる。第5章で明らかになったように、スリナム人に典型的な行動パターンである視線回避、自己適応、発話障害は、すべて欺瞞の指標として認識される。つまり、ある民族に典型的な非言語的行動パターンが、白人観察者には欺瞞の兆候として容易に解釈されてしまうのである。
能動的面接者と受動的観察者
これまで紹介した嘘発見研究では、観察者は送信者に実際にインタビューすることはなく、ビデオテープで観察するだけであった。もし観察者が送信者と面接すれば、精度は向上するのだろうか?警察官、検察官、裁判官はそう考えている(Stro¨mwall & Granhag, 2003b)。おそらく彼らは、事情聴取をすることで、観察者がウソつきの裏をかくような質問をする機会が得られると考えているのだろう。それゆえ、面接そのものが嘘発見には役立たないということは、専門家にとっては意外なことなのだろう。いくつかの実験によれば、実際の面接者(一般人やプロの嘘発見者)の正確率は、受動的観察者の正確率よりも決して高くないが、低いこともある(Buller, Strzyzewski, & Hunsaker, 1991; Burgoon, Buller, & Floyd, 2001; Durban, Ramirez, & Burgoon, 2003; Feeley & DeTurck, 1997; Granhag & Stro¨mwall, 2001b, c; Hartwig, Granhag, Stro¨mwall, & Vrij, 2004; Kalbfleisch, 1994; Stiff, Kim, & Ramesh, 1992)。 26
インタビュアーとオブザーバーの間には、彼らが行う真実性判断のタイプに違いが現れる。面接者(一般人とプロの嘘発見者の両方)は、観察者よりも送信者を信じる傾向がある(Bond & DePaulo, 2006; Hartwig, Granhag, Stro¨mwall, & Vrij, 2004)。おそらく送り手は、面接中の面接官の反応に反応し、面接官に信頼されるような言語的メッセージや非言語的なプレゼンテーションスタイルを作り上げることに成功しているのだろう。送り手はビデオに録画された面接を見る観察者とは対話しないので、観察者の反応に影響を与えることはできない。この結果、正確率が低くなり、真実バイアスがかかることになるが、嘘つきが常にそうしようとして説得力のある印象を与えることに成功するとは限らないため、この説明は完全に納得できるものではない(第3章)。あるいは、送信者は説得力のある印象を与えようとはせず、単にインタビュアーに好かれようとしているのかもしれない。人は一般的に好かれたいという願望を持っており、それを達成する一つの方法は、他人に親切にすることである(Baumeister, 1982; Monahan, 1995)。おそらく面接官は、観察者よりも発信者をより肯定的に評価する傾向があり、その結果、面接官は自分が気に入った人を正直な人だと認識するのかもしれない。
プロービング
送り手の発言に対して、インタビュアーがさらに説明を求めることがある。質問(プローブ)には、中立的な言い回し(「私はこれが理解できません、説明していただけませんか」)、肯定的な言い回し(「私はあなたを信じていますが、これが理解できません。「どうしてそんなことが可能なのでしょうか」)、否定的な言い回し(「私はあなたを信じません、私を騙そうとしているのですか」)がある。直感的には、さらに質問することで、真実や嘘の発見が容易になると考えるかもしれない。嘘つきは、より多くの情報を話し続けなければならなくなる。明らかに、嘘つきがより多く話し、より多くの情報を与えれば与えるほど、彼らが間違いを犯し、言語的な合図(自分自身と矛盾したり、観察者が間違っていると知っていることを言ったりすることによって)、あるいは非言語的な合図によって、自分の嘘をばらしてしまう可能性が高くなる。しかし、いくつかの研究では、プロービングは正確さを増すのではなく、相手を真実であると判断する傾向があることが示されている(Bond, Malloy, Thompson, Arias, & Nunn, 2004; Buller, Comstock, Aune, & Strzyzewski, 1989; Buller, Strzyzewski, & Comstock, 1991; Levine & McCornack, 2001; Stiff & Miller, 1986)。これはプロービング・ヒューリスティック(Levine, Park, & McCornack, 1999)と呼ばれる。プロービングの種類(否定的、中立的、肯定的)は関係なく、どのタイプのプロービングも同じ効果をもたらし、嘘つきに利益をもたらす。
しかし、LevineとMcCornack (2001)は、プロービング効果には限界があることを発見した。プロービングは、観察者が単に各送信者の真実性を判断するよう求められた場合には、真実性バイアスをもたらしたが、嘘発見課題の前に、観察者が欺瞞の診断的手がかりと非診断的手がかりについて知らされており、真実性判断を行う際には診断的手がかりのみに集中するよう指示された場合には、効果がなかった。LevineとMcCornackは、何も指示を受けないと発見的処理になり、指示を与えると能動的情報処理になると主張した。どうやら、観察者が能動的な情報処理に関与している場合には、プロービング効果は起こらないようである。このことは、Granhag and Stro¨mwall (2001b, c)が、同じ容疑者との3回の面接を観察者に見せた実験で、プロービング効果が認められなかった理由を説明できるかもしれない。これらの研究では、観察者が供述間の矛盾を検出しようとしていたため、能動的な情報処理が行われていた。
まとめ
観察者が行う真実性判断には、いくつかの要因が影響する。一部の人(人前での自意識が高い人、内向的な人、社会的不安の強い人)は、彼らが自然に見せる行動により、真実を言っているか嘘をついているかにかかわらず、観察者に不誠実な印象を与える。また、非白人の送り手もこれと同じ理由で、白人の観察者に不誠実な印象を与える。対照的に、表情豊かで社交的な人は、自然に見せる振る舞いのせいで、観察者に正直な印象を与える。観察者ではなく、積極的なインタビュアーであることは、送り主を信じる傾向をもたらし、送り主を探ることも同様である。
エピローグ
本書の冒頭で、安全保障上の脅威やテロ攻撃の増加により、うそつきを捕まえることの重要性が増していることを述べた。また、研究者たちがあらゆる種類の嘘発見技術を試すことで、この需要に応えてきたことも報告した。私は、これらの技術を注意深く検証する必要があると述べた。これらの技術がどのように機能するのか、そして実際に機能するのかどうかを調べる必要がある。なぜなら、誤りを犯しやすいツールを導入しても、嘘つきの逮捕という解決に近づくことはないからだ。本書の中で私は、何人かの研究者が、真実と嘘を非常に高い精度で識別する技術を開発したと主張していることを報告した。彼らに忠告したいのは、地に足をしっかりとつけておくことだ。私に言わせれば、どんなツールも無謬ではないし、現在までに開発されたツールにもかなりの問題や限界がある。なぜ私がこのようなやや悲観的な結論に至ったのか、本書を読んで納得していただけたなら幸いである。これは、真実と嘘を見分けることが不可能だという意味ではない。それどころか、嘘つきを突き止める方法や機会は数多くある。本書がそのためのヒントになれば幸いである。
