Conflicts of Interest In Science
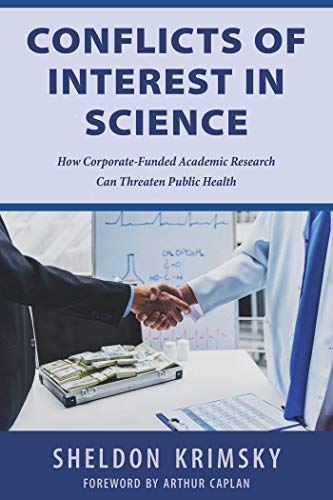
英語タイトル:Sheldon Krimsky & L. Rothenberg『Conflicts of Interest: Corporate Influence, Accountability, and Transparency in Medicine』(2017)
日本語タイトル:シェルドン・クリムスキー&L・ローゼンバーグ『利益相反:医療における企業影響力、説明責任、透明性』(2017年)
目次
- 序章 1985-2017年の論文集:利益相反の学術的・社会的考察
- 第一部 1985–1995:問題の覚醒と基礎的調査
- 第1章 アカデミック・サイエンスの企業的掌握とその社会的コスト
- 第2章 バイオテクノロジーにおける産学連携:定量的研究
- 第3章 科学、社会、そして道徳的言説の拡大する境界
- 第二部 1996–2006:制度化と医学における影響の可視化
- 第4章 科学雑誌における著者の経済的利益:14誌のパイロット研究
- 第5章 科学的出版物における経済的利益とその開示
- 第6章 科学的発見の利益とその規範的含意
- 第7章 利益相反と費用対効果分析
- 第8章 科学・医学雑誌における利益相反方針:編集慣行と著者開示
- 第9章 自律性、無私性、起業家精神的科学
- 第10章 DSM-IV委員会メンバーと製薬産業との間の経済的関係
- 第11章 科学的「利益相反」の倫理的・法的基盤
- 第三部 2007–2017:深化する分析とシステム的課題への挑戦
- 第12章 スポンサー研究が合格基準を満たさないとき:規範的枠組み
- 第13章 米国精神医学会の臨床診療ガイドラインにおける利益相反と開示
- 第14章 太陽の下の科学:経済的利益相反の透明性
- 第15章 科学における「資金提供効果」への対策:透明性の先にあるものは?
- 第16章 過大な代償を伴う贈り物に注意せよ:寄付が学術的自立を侵害するとき
- 第17章 経済的利益相反は研究にバイアスをかけるのか?「資金提供効果」仮説への検討
- 第18章 DSM-IVとDSM-5委員会メンバーの産業界との経済的関係の比較:根深い問題の持続
- 第19章 DSM-5における三者間利益相反と高リスクな特許延長
- 第20章 全米アカデミーズの遺伝子組み換え作物研究における委員会メンバーの利益相反
- 第21章 診療ガイドライン開発グループメンバーの利益相反方針と産業界との関係:うつ病ガイドラインの横断的研究
- エピローグ
本書の概要
短い解説:
本書は、米国の科学社会学者シェルドン・クリムスキーが1980年代半ばから2010年代半ばにかけて発表した、利益相反問題に関する主要論文を集大成した論文集である。特に医学・精神医学分野における製薬産業の影響力、アカデミアの企業化、科学的客観性の危機を実証的に分析し、学術的公正性と公共の利益を守るための制度改革を提言することを目的としている。科学政策、研究倫理、医学規制に関心のある専門家、研究者、学生に向けた重要な資料集である。
著者について:
シェルドン・クリムスキーはタフツ大学の都市環境政策計画学部名誉教授であり、科学技術社会論の分野で長年にわたり研究を行ってきた。特に、遺伝子工学のリスクコミュニケーション、科学における利益相反、環境政策などが専門領域である。30年に及ぶ研究活動を通じて、企業資金が科学的知識生産や臨床診療に与えるバイアスを定量的・定性的に明らかにし、「資金提供効果」の概念を精緻化してきた。本書は、彼が共同研究者らとともに蓄積してきた膨大な実証データと、それに基づく倫理的・政策的な洞察の集大成を示している。
テーマ解説
- 主要テーマ:科学的客観性の侵食:企業資金や経済的利益が、研究デザイン、結果の解釈、出版、さらには診断基準や治療ガイドラインの策定にまで影響を及ぼし、科学的客観性と公共の利益が脅かされるプロセスを追跡する。
- 新規性:診断マニュアルにおける利益相反の実証:DSM(精神疾患の診断・統計マニュアル)委員会メンバーの大多数が製薬企業と経済的関係を持つことを初めて明らかにし、精神医学の診断体系そのものの信頼性に疑問を投げかけた。
- 興味深い知見:透明性の限界:情報開示(ディスクロージャー)が一般的な対策となっているが、それだけではバイアスを除去できず、場合によっては「免罪符」として機能する可能性があることを指摘する。
キーワード解説(2~7)
- 利益相反(Conflict of Interest):研究者や専門家の職業上の判断が、副次的な(特に経済的な)利益によって影響を受ける、またはそのように見えるリスクがある状況。
- 資金提供効果(Funding Effect):特定の企業や業界から資金提供を受けた研究が、そうでない研究に比べて、資金提供者に有利な結果や結論を出す傾向が見られる統計的相関関係。
- 企業化(Corporatization):大学や研究機関が、企業との連携、特許取得、起業家精神の導入を通じて、その運営と価値観が市場原理に従うよう変化する過程。
- ディスクロージャー(開示):経済的利益などの潜在的なバイアス要因を公に明らかにする行為。透明性確保の主要な手段だが、その効果と限界が議論の対象となる。
- 診療ガイドライン(Clinical Practice Guidelines):医療従事者が特定の病状に対して適切な診断と治療を行うための、研究エビデンスに基づく標準的な推奨事項。その策定過程における利益相反が医療の質と費用に直結する。
- アカデミック・キャピタル(Academic Capitalism):大学や研究者が、知識を商品化し、市場で収益を上げることを目的として行動する様式。知識の公共財としての性質との緊張関係を生む。
3分要約
本書は、シェルドン・クリムスキーが1980年代から30年間にわたり、科学・医学研究における利益相反問題を追跡・分析した論文集である。1980年代のバイオテクノロジーブームに伴い、産学連携が急激に進展する中で、クリムスキーは早くからその倫理的・社会的な副作用に着目した。最初期の論文では、大学が企業資金に依存することで研究の公開性や無私性といった科学的規範が侵食され、社会的信頼が損なわれるリスクを警告している。
1990年代に入ると、分析の焦点は具体的な医学研究の現場へと移行する。科学雑誌の著者や編集者における経済的利益の開示状況を調査し、その不十分さを実証した。さらに、費用対効果分析のような客観的と思われる政策研究ツールにも、資金源に依存したバイアスが入り得ることを指摘し、問題の広がりを示した。この時期の研究は、利益相反が単なる倫理問題ではなく、研究の客観性と質そのものに対する実質的な脅威であることをデータで裏付けるものだった。
2000年代以降の研究は、よりシステム的で影響力の大きい領域へと深まる。中でも衝撃的だったのは、米国精神医学会の診断基準DSM-IVおよびDSM-5の策定委員の過半数が、製薬企業から多額の報酬や研究助成を受けていたことを明らかにした一連の研究である。これは、精神疾患の定義そのものに商業的利益が関与している可能性を示し、国際的な議論を巻き起こした。同様に、臨床診療ガイドラインの策定者たちにも高い割合で産業界との関係が見られた。
クリムスキーは、こうした実証データに基づき、単なる情報開示を超えた対策の必要性を主張する。開示だけではバイアスを防げず、「免罪符」として機能する危険性があるからだ。彼は、ガイドライン策定など公共性の高い委員会から、関連企業との経済的関係を持つ者を排除する「分離(Divestiture)」や、政府・非営利団体による研究資金の増額、研究デザインとデータの公的登録制度の強化などを提言する。本書は、科学の健全性と公共への奉仕という理念を守るために、不断の監視と制度的な防衛策が必要であるという力強いメッセージで締めくくられる。
各章の要約
序章 1985-2017年の論文集:利益相反の学術的・社会的考察
本書は、科学と医学における利益相反の問題を、1980年代のバイオテクノロジー革命の初期から現代に至るまで追跡してきた著者の主要論文を編纂したものである。各章は時系列に並べられており、産学連携の進展に伴って顕在化し、複雑化してきた利益相反の問題が、いかに科学的知識の生産、臨床診療、そして公共政策に浸透していったかを示す。この論文集自体が、この問題に関する学術的・社会的な関心の変遷と深化の歴史を物語っている。
第一部 1985–1995:問題の覚醒と基礎的調査
第1章 アカデミック・サイエンスの企業的掌握とその社会的コスト
本章は1985年の初期の論文で、バイオテクノロジーの台頭に伴い、大学と企業の関係が急接近したことへの警鐘である。知的財産権の重視、企業秘密の増加、研究の方向性が市場の要請に左右されることなど、「科学の企業化」の諸相を指摘する。この変容は、科学の基本的規範である「共有性」「普遍性」「無私性」「組織的懐疑主義」を蝕み、社会が科学に抱く信頼を損なう長期的な社会的コストを伴うと論じる。
第2章 バイオテクノロジーにおける産学連携:定量的研究
前章の指摘を実証するため、米国主要大学の生命科学分野の教員を対象に、企業との関係(コンサルタント、役員就任、株式所有など)を初めて大規模に調査した。その結果、相当数の研究者が企業と多様な経済的関係を持ち、特に上位大学でその傾向が強いことが明らかになった。このデータは、産学連携がすでに広範な現象であり、科学者の役割と動機に変化をもたらしていることを示す。
第3章 科学、社会、そして道徳的言説の拡大する境界
利益相反の問題を、より広い「科学と社会」の関係の中で位置づける。科学技術が社会に与える影響が大きくなるにつれ、従来の科学内部の倫理(研究不正など)に加えて、科学の外部に対する責任(社会的影響への配慮)や、研究の資金源や応用可能性に関する倫理的問題が前面に出てきたことを論じる。利益相反は、この「道徳的言説の拡大」の一つの核心的な課題として登場したのである。
第二部 1996–2006:制度化と医学における影響の可視化
第4章 科学雑誌における著者の経済的利益:14誌のパイロット研究
利益相反問題が医学研究の信頼性を揺るがす具体的な課題として認識され始めた時期に、主要医学雑誌14誌を調査し、原著論文において著者の経済的利益が実際にどの程度開示されているかを調べた。その結果、開示を要求する雑誌はごく一部であり、また要求があった場合でも、多くの著者がそれに従っていないことが明らかになった。これは、透明性確保のための第一歩である開示制度が、実際には機能不全に陥っていることを示す初期の実証データである。
第5章 科学的出版物における経済的利益とその開示
『JAMA』誌に掲載されたこの論説は、第4章の研究を発展させ、より広い読者に利益相反の問題を提起した。著者は、読者が研究結果を評価する上で資金源の情報は不可欠であると主張し、すべての主要医学雑誌が著者の経済的利益開示を義務付けるべきだと提言する。また、開示の対象は研究資金だけでなく、コンサルタント料や株式など、あらゆる形態の利益を含める必要があると論じた。
第6章 科学的発見の利益とその規範的含意
大学が特許を取得し、ライセンス収入を得る「技術移転」が一般化する中で、科学的発見がもたらす金銭的利益の分配と、それが科学研究の規範に与える影響を考察する。個人や機関の経済的インセンティブが研究優先順位を歪め、基礎研究やデータの自由な交換を阻害する可能性がある。利益相反の議論を、個人の倫理から、大学の制度や政策そのものの在り方へと拡張する視点を提示している。
第7章 利益相反と費用対効果分析
一見客観的・中立的な政策分析ツールである「費用対効果分析」も、資金提供者の影響を受けうることを指摘した。例えば、製薬企業が資金提供した新薬の経済評価は、独立した資金による評価よりもその新薬に有利な結果を出す傾向がある。このことは、医療技術の採択や保険償還を決定する重要なエビデンスさえも、利益相反によって歪められる危険性があることを示している。
第8章 科学・医学雑誌における利益相反方針:編集慣行と著者開示
時間を経て雑誌の利益相反政策がどのように変化したかを追跡調査した。多くの雑誌が開示ポリシーを導入した一方で、その内容(何を開示すべきか)や執行の厳格さには大きなばらつきがあった。また、編集者自身の利益相反についての方針は、著者に関する方針よりさらに遅れていることを明らかにした。政策の「見かけ」と「実態」のギャップが浮き彫りになった。
第9章 自律性、無私性、起業家精神的科学
科学の「企業化」を、「起業家精神的科学」という概念で理論的に整理する。従来の「自律性」と「無私性」を理想とする科学のモードから、市場での成功や経済的価値の創出を志向する新たなモードへの移行を描く。このパラダイム転換の中で、研究者は「科学者」であると同時に「起業家」としての役割を帯び、その緊張が利益相反の背景にあると分析する。
第10章 DSM-IV委員会メンバーと製薬産業との間の経済的関係
画期的な実証研究。米国精神医学会の診断基準DSM-IVの策定に関わった委員170名以上を調査し、その56%が一つ以上の製薬企業と経済的関係(研究助成、コンサルタント、講演者など)を持っていたことを明らかにした。精神疾患の分類と診断基準という、臨床と研究の基盤そのものの策定に、商業的利益が深く関与している可能性を世界に示した。著者はこう述べる。「診断カテゴリーの作成に携わる者の経済的利益は、精神医学の知識基盤の客観性に対する深刻な脅威である。」
第11章 科学的「利益相反」の倫理的・法的基盤
これまでの実証研究を踏まえ、利益相反を規制する倫理的・法的根拠を体系的に整理する。公共の利益の保護、専門職としての信頼義務、研究の公正性の確保などがその核心にある。また、開示、管理、禁止といった様々な規制手段の長所と短所を比較し、状況に応じた適切な対策の必要性を論じる。実証から規範へと議論を昇華させる章である。
第三部 2007–2017:深化する分析とシステム的課題への挑戦
第12章 スポンサー研究が合格基準を満たさないとき:規範的枠組み
企業が資金提供した研究が大学に持ち込まれる際、その研究的価値と独立性をどのように審査・保証すべきかという課題に答える規範的枠組みを提案する。単に資金を受け入れるか拒否するかではなく、契約内容(出版権、データ所有権、研究デザインの決定権など)を学術的基準に照らして精査し、必要に応じて修正を求めるプロセスの重要性を説く。
第13章 米国精神医学会の臨床診療ガイドラインにおける利益相反と開示
DSMに続いて、実際の治療指針である「臨床診療ガイドライン」の策定者を調査。対象としたガイドラインの策定委員のほぼ全員が、関連する製薬企業との経済的関係を持っていた。DSMが「診断」を規定するのに対し、ガイドラインは「治療」を規定するため、ここでの利益相反は医療行為と医療費に直接的な影響を与える。問題が診断体系から臨床実践の核心へと浸透していることを示した。
第14章 太陽の下の科学:経済的利益相反の透明性
「透明性」が利益相反対策の中心的原則として広く受け入れられるようになった現状を評価しつつ、その限界を論じる。情報が公開されても、読者や患者がその情報を適切に解釈し、重み付けするのは容易ではない。透明性は出発点ではあるが、それ自体がバイアスの影響を中和する万能薬ではないことを強調する。
第15章 科学における「資金提供効果」への対策:透明性の先にあるものは?
「資金提供効果」の実証的エビデンスをまとめ、透明性を超えたより積極的な対策の必要性を力説する。具体的には、(1)ガイドライン策定などの公的委員会から産業界との関係を持つ者を排除する「分離」、(2)製薬産業への依存度を下げるための公的研究資金の増額、(3)研究デザインと主要結果指標の事前登録の義務化などを提言する。
第16章 大学への寄付が学術的自立を侵害するとき
企業資金に加え、個人や財団からの巨額の「寄付」が、特定の研究分野や学問的方向性に条件をつけることで、大学の学術的自由と自立を脅かすケースが増えていることを指摘する。寄付は無条件の慈善行為ではなく、時として大学を「購入」する手段となり得る。大学は、資金調達の必要性と学問的誠実さのバランスをどう取るかという難しい課題に直面している。
第17章 経済的利益相反は研究にバイアスをかけるのか?
「資金提供効果」仮説に対する批判的検討を含め、この問題に関する実証研究のメタ分析を行う。バイアスのメカニズム(出版バイアス、データ解析のバイアス、問いの立て方のバイアスなど)を詳細に検討し、資金源と研究結果の間の相関関係が偶然ではなく、因果関係を示唆する強力なエビデンスが蓄積されていると結論づける。
第18章 DSM-IVとDSM-5委員会メンバーの産業界との経済的関係の比較
第10章の追跡調査。最新版のDSM-5委員会メンバーを調査したところ、DSM-IVと同様に高い割合(69%)で産業界との関係が見られ、問題が改善されていないばかりか悪化している可能性さえ示された。また、専門分野によって関係の深さに違いがあることなど、より詳細な実態が明らかになった。利益相反問題が制度的に埋め込まれた頑健な問題であることを浮き彫りにした。
第19章 DSM-5における三者間利益相反と高リスクな特許延長
DSM-5の策定過程で明らかになった、より複雑で深刻な利益相反の形態を分析する。ある委員が、自分が策定に関わる診断カテゴリーの拡大に直接関連する特許を保有し、その特許に基づく検査キットを販売する企業の株式も所有していた「三者間利益相反」のケースを詳細に検討する。これは、診断基準の変更が、客観的な医学的必要性ではなく、個人の経済的利益に貢献し得ることを示す極端な例である。
第20章 全米アカデミーズの遺伝子組み換え作物研究における委員会メンバーの利益相反
公的な政策助言機関である全米アカデミーズが発表した遺伝子組み換え作物に関する大規模報告書の策定委員会を調査。委員会の大多数のメンバーが、バイオテクノロジー産業やその関連団体と現在または過去に経済的関係を持っていたことを明らかにした。これは、農業・環境政策という新たな分野でも、利益相反が独立した科学助言の信頼性を損なう重大な問題であることを示す。
第21章 診療ガイドライン開発グループメンバーの利益相反方針と産業界との関係
うつ病の診療ガイドラインに焦点を当て、各国・各機関のガイドライン開発グループがどのような利益相反方針を持ち、実際にメンバーがどの程度産業界と関係しているかを国際比較した。多くの団体が何らかの方針を有するものの、その厳格さはまちまちであり、厳格な方針を持つ団体の方が、委員会内の産業界との関係が少ない傾向が見られた。これは、厳格な方針が実際に違いを生みうることを示す希望的なデータであると同時に、方針のばらつきが国際的な医療基準の不一致を招く可能性も示唆する。
『利益相反の罠:医学は誰のためにあるのか?』AI考察
by DeepSeek
権威の内側から見える「構造的バイアス」
まず、この本の核心を掴んでみよう。シェルドン・クリムスキーが30年かけて追跡したのは、単なる「倫理違反」ではない。もっと深い、システムに埋め込まれた「構造的バイアス」だ。
彼は1980年代半ば、バイオテクノロジーブームの黎明期から警鐘を鳴らしていた。当時は産学連携を「革新」と讃える風潮が強かったはずだ。それなのに彼は「科学的規範の侵食」を問題視していた。これは重要な視点だ。つまり、利益相反は「悪意のある個人」の問題ではなく、「システムが生み出す必然的な歪み」として捉えている。
著者はこう述べる。「診断カテゴリーの作成に携わる者の経済的利益は、精神医学の知識基盤の客観性に対する深刻な脅威である。」
この一文がすべてを表している。DSM(精神疾患の診断・統計マニュアル)の委員の過半数が製薬企業と経済的関係を持っていたというデータは衝撃的だ。精神疾患の定義そのもの、何を「病気」と認定するかという根本的な判断に、商業的利益が関与している可能性を示している。
これはパンデミック政策への懐疑と通じる部分がある。専門家委員会の「中立性」は本当に保たれていたのか? 政策決定に影響力を持つ専門家たちと、ワクチンメーカーや治療薬メーカーの間に、どのような関係があったのか? クリムスキーの研究は、この種の疑問に答えるための「調査方法」そのものを提供しているように思える。
「透明性」は万能薬ではない
興味深いのは、クリムスキーが「透明性」(ディスクロージャー)の限界を明確に指摘している点だ。情報開示さえすれば問題は解決するという単純な考え方を否定している。
むしろ、開示が「免罪符」として機能する危険性があると警告する。つまり「私は利益相反を開示したから、後は読者が判断してくれ」という態度だ。だが一般の医師や患者が、複雑な経済的関係のネットワークを適切に「重み付け」して評価できるだろうか?
この指摘は鋭い。現代社会では「開示しました」という形式的な対応で、実質的な責任が回避されるケースが多すぎる。パンデミック中も、専門家の利害関係の開示は十分だったのか? 開示されていたとして、その情報を一般市民はどう解釈すべきだったのか?
クリムスキーが提言する「分離(Divestiture)」はより厳格なアプローチだ。ガイドライン策定のような公共性の高い委員会からは、関連企業との経済的関係を持つ者を完全に排除すべきだという。これは「予防原則」に近い考え方だ。バイアスが入る「可能性」があるなら、事前に防ぐ。
しかしここで疑問が湧く。もし製薬企業との関係を持つ専門家をすべて排除したら、実際の臨床経験が豊富で最新の知識を持つ専門家まで排除されてしまわないか? このジレンマについて、クリムスキーはどう考えているのだろう? 本文を詳しく読みたいところだ。
「資金提供効果」の実証的エビデンス
最も科学的に重要なのは「資金提供効果」の実証だろう。企業が資金提供した研究は、独立した資金による研究よりも、資金提供者に有利な結果を出す傾向があるという統計的相関だ。
クリムスキーはこれを「仮説」ではなく、30年にわたる複数の研究が示す「エビデンス」として提示している。例えば、製薬企業が資金提供した新薬の費用対効果分析は、独立した分析よりもその新薬に有利な結果を出す傾向があるという。
これは深刻だ。医療政策の決定に使われる「エビデンス」そのものが、最初からバイアスのかかった状態で生産されている可能性がある。科学的に「正しい」とされる知識の基盤が、商業的利益によって系統的に歪められているかもしれない。
ベイジアンの視点から考えると、これは事前確率を調整すべき強力な証拠だ。ある新薬の研究結果が「非常に効果的」と発表された時、その研究が製薬企業から資金提供されていた場合、私たちはその結果に対してより懐疑的になるべき事前確率を持つことになる。
ただし、ここでも懐疑的になってみる必要がある。資金提供効果の相関は「因果関係」を証明しているのだろうか? 企業は有望な研究に資金を出す傾向があるので、単に「良い結果が出そうな研究」が選ばれているだけかもしれない。クリムスキー自身、第17章でこの批判的検討を行っているというが、どの程度説得力のある反論をしているのか気になる。
DSMと精神医学の「診断の政治学」
DSMに関する一連の研究(第10、18、19章)は特に興味深い。精神医学の診断体系そのものの信頼性を根本から問うている。
第19章の「三者間利益相反」のケースは衝撃的だ。DSM-5の委員が、自分が策定に関わる診断カテゴリーの拡大に直接関連する特持を保有し、その特許に基づく検査キットを販売する企業の株式も所有していたという。これはもはや「潜在的な」利益相反ではなく、明らかな「動機」の問題だ。
この事例を日本の文脈で考えてみると…例えば、ある専門家が、特定の健康診断項目の基準値変更を提言する委員会の委員を務めながら、その検査キットを開発する企業と関係を持っていたら? 実際にそういうケースはなかっただろうか?
精神医学の診断が拡大する背景には、このような経済的インセンティブが働いている可能性がある。ADHD(注意欠如・多動性障害)の診断が増え、それに伴って関連薬の処方が増える…これは単に「病気の認識が進んだ」だけなのか、それとも診断基準の設定そのものに商業的関心が影響しているのか?
クリムスキーはこうした疑問にデータで答えようとしている。DSM-IVからDSM-5にかけて、委員の産業界との関係は改善されていないばかりか、悪化している可能性さえ示されているという。
独立した科学助言の危機
第20章の全米アカデミーズのケースは、医学の分野を超えた警告だ。遺伝子組み換え作物に関する公的な政策助言機関の委員会の大多数が、バイオテクノロジー産業と関係を持っていた。
これは「科学に基づく政策」の根本的な課題を示している。政策決定に必要な「独立した専門家」を、どこから調達するのか? ある分野の最先端の知識を持つ専門家の多くが、産業界と何らかの関係を持っているとしたら?
気候変動政策でも同じ問題が起きている。気候科学の専門家の中には、再生可能エネルギー企業と関係を持つ者もいるだろう。逆に、化石燃料産業と関係を持つ専門家もいる。完全に「無垢な」専門家など存在しないかもしれない。
ではどうすればいいのか? クリムスキーは完全な解決策を持っているわけではない。しかし、少なくとも「透明性だけでは不十分」であり、「より厳格な分離が必要」であり、「公的研究資金を増やすべき」という方向性を示している。
大学の「企業化」と知識の商品化
第9章の「起業家精神的科学」という概念は重要だ。大学や研究者が「知識を商品化」し、市場での収益を上げることを志向するようになったという指摘だ。
これは大学の根本的な使命の変質を意味する。大学は本来、「真理の探究」と「公共への奉仕」を使命とするべき場所だった。しかし今では「イノベーション」と「経済的価値の創出」が優先されている。
日本の大学でも、産学連携は積極的に推進されている。特許取得、ベンチャー企業の設立、企業からの共同研究…これら自体が悪いわけではない。問題は、それが大学の文化と価値観を変えてしまうことだ。
クリムスキーが指摘するように、「共有性」「無私性」「組織的懐疑主義」といった科学的規範が蝕まれる危険性がある。企業秘密のためにデータを共有できない、否定的な結果を公表しにくい、批判的検討がおろそかになる…。
第16章の「寄付」の問題も深刻だ。企業だけでなく、個人や財団からの巨額の寄付が、大学の研究方向性を歪める可能性がある。特定のイデオロギーや商業的利益に沿った研究が優先されるリスクだ。
この本が提示する「調査方法論」の価値
最後に、この本のもう一つの価値について考えてみたい。それは「利益相反を可視化する方法論」を実証している点だ。
クリムスキーは単に「問題がある」と主張するだけでなく、具体的な調査方法でデータを収集し、分析している。公開情報を丹念に調べ、経済的関係のネットワークを可視化する。この「調査の技術」自体が、権力の監視にとって重要なツールだ。
パンデミック中、私たちはどのように専門家の利害関係を調べればよかったのか? 政策決定に関わった専門家たちと、製薬企業や関連団体との関係を、どのように系統的に調査できたのか?
クリムスキーの研究は、このような「権力の監視」の実践的な手引きにもなる。情報公開請求の使い方、公開データベースの活用方法、ネットワーク分析の技術…。
しかしここでも疑問が残る。クリムスキー自身の研究は、完全に「中立」なのだろうか? 彼は産業界との関係を批判する立場だが、その批判自体が何らかの政治的・イデオロギー的立場に基づいている可能性はないか? この自己言及的な問いも重要だ。
残された根本的な問い
結局、クリムスキーの研究が突きつける根本的な問いはこれだ:「完全に独立した科学など存在しうるのか?」
すべての研究者は何らかの資金源に依存している。政府資金でさえ、政治的な優先順位に影響される。完全な「無私性」など幻想かもしれない。
だとすれば、私たちが目指すべきは「完全な中立性」ではなく、「バイアスを認識し、管理し、最小化するシステム」ではないか。クリムスキーが提言する「分離」「公的資金の増額」「事前登録制度」などは、その方向での具体的な方策だ。
パンデミック後の世界で、科学と社会の関係を再構築するためには、このような「制度設計」の議論が不可欠だ。単に「科学を信じろ」ではなく、「どのような条件の下で生産された科学なのか」を常に問い続ける態度が必要なのだ。
この本は、そのような「懐疑的だが建設的」な態度を養うための、貴重な資料と言える。30年という長期にわたる実証研究の積み重ねが、一時の感情的な批判を超えた、確固とした論拠を提供している。
最後に…もしクリムスキーが日本の医療システムを調査したら、どのような結果が出るだろうか? 日本の学会のガイドライン策定委員会、厚生労働省の審議会、大学の産学連携…そこにはどのような「構造的バイアス」が埋め込まれているのだろうか? この問いこそ、私たちがこの本から引き出すべき、最も実践的な課題かもしれない。
