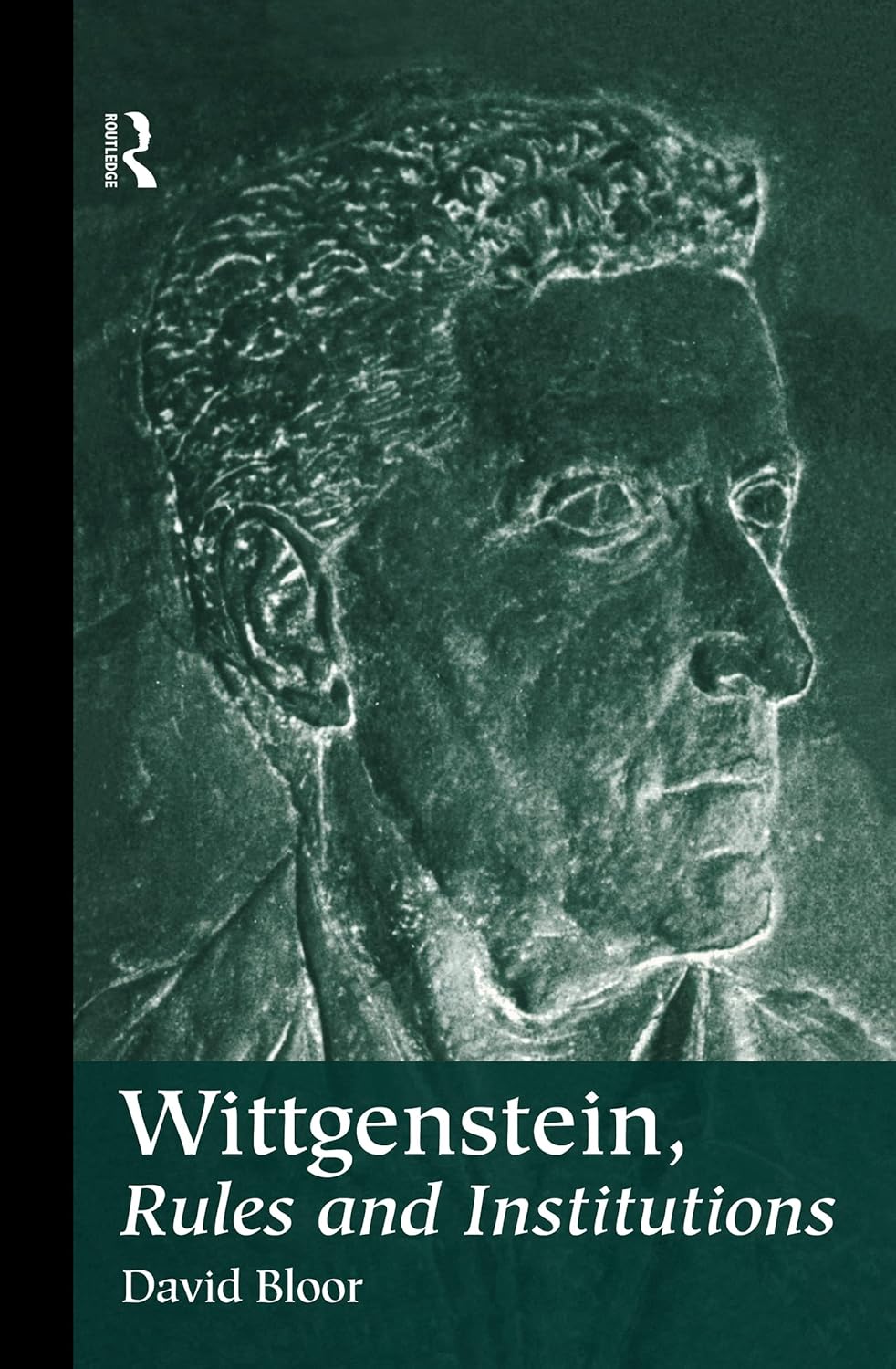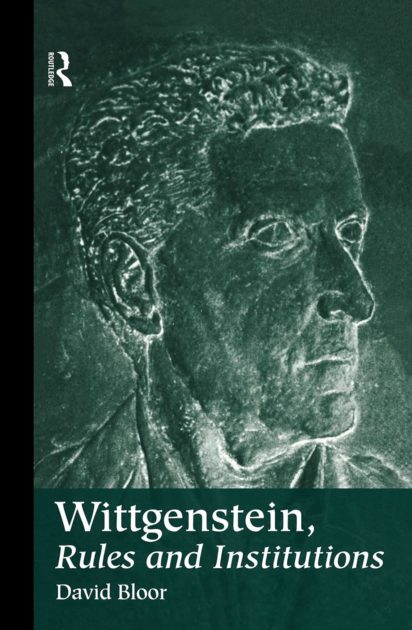
『WITTGENSTEIN, RULES AND INSTITUTIONS:Wittgenstein on Rules and Institutions』David Bloor 1997
日本語タイトル:『ウィトゲンシュタイン、ルールと制度:ルールと制度についてのウィトゲンシュタイン』デイヴィッド・ブロア 1997
目次
- 謝辞:/ Acknowledgements
- 略語表:/ Abbreviations
- 第1章 序論 / Introduction
- 第2章 意味有限主義 / Meaning Finitism
- 第3章 制度としてのルール / Rules as Institutions
- 第4章 良心的であること / Conscientiousness
- 第5章 ルール懐疑論 / Rule Scepticism
- 第6章 フォン・ミーゼスとの類推 / The Analogy with Von Mises
- 第7章 個人主義 / Individualism
- 第8章 孤立と革新 / Isolation and Innovation
- 第9章 ルールと自然状態 / Rules and the State of Nature
- 第10章 結論 / Conclusion
- 注:/ Notes
- 参考文献:/ Bibliography
本書の概要
短い解説
本書は、ウィトゲンシュタインの後期哲学、特にルールに従うことの概念を、個人主義的解釈に対抗する集団主義的・社会学的観点から読み解き、擁護することを目的とする。
著者について
著者デイヴィッド・ブロアは、エディンバラ大学名誉教授であり、科学知識社会学(SSK)の「ストロング・プログラム」で知られる社会学者・科学哲学者。本書では、その社会学的視点からウィトゲンシュタイン解釈に挑む。
テーマ解説
- 主要テーマ:ルールに従うことの本質 [ルールに従うという現象を、個人の心的能力ではなく、社会的な制度への参与として説明する試み。]
- 新規性:ウィトゲンシュタインの集団主義的読解 [主流であった個人主義的解釈に対し、彼のテクストを社会制度論の観点から体系的に読み直す。]
- 興味深い知見:制度の自己言及性 [貨幣や所有権と同様、ルールもまた、それを「ルールと呼ぶ」という集団的実践によって初めて存在するという分析。]
キーワード解説
- 意味有限主義:ルールの意味は、その適用のつど、その都度、創造されていくという立場。
- 制度の自己言及モデル:あるものが「制度」であるのは、人々がそれを制度として言及し、扱うという、自己完結的な実践によって成り立つというモデル。
- 規範性:ルールが「正しい/間違っている」という判断を生み出す性質。本書ではこれを社会的合意に求める。
- 個人主義 vs 集団主義:ルールの根拠を個人の心に求める立場と、社会集団に求める立場の対立。
- クリプキの懐疑的パラドックス:過去の使用だけでは、現在のルール適用を決定できないという、意味の事実を問う問題提起。
- 良心的条件:ルールに従うためには、自分が従っているという意識(意図)が必要であるという条件。
- 人工的徳:ヒュームの用語。約束のように、自然的な感情ではなく、人為的な慣習によって生み出される規範。
3分要約
本書は、ウィトゲンシュタインの後期哲学、特に『哲学探究』や『数学の基礎』における「ルールに従うこと」の分析を、集団主義的かつ社会学的な観点から体系的に解釈することを目指す。著者のデイヴィッド・ブロアは、序論で、ルールに付随する「無限性」と「規範性(〜ねばならない)」という二つの謎を提示し、これを伝統的な「意味決定論」がどのように説明してきたかを概観する。意味決定論は、ルールの意味そのものが将来の適用をあらかじめ決定しているとする考え方であり、これが個人主義的なルール解釈の基盤となっている。ブロアは、ウィトゲンシュタインがこの見解を明確に拒否したと主張する。
第2章では、その代わりとなる「意味有限主義」が提示される。ルールの学習は有限の事例によって行われ、学習者はそこから次のステップへと「飛躍」しなければならない。この飛躍は、論理や解釈によって強制されるのではなく、生物学的・本能的な反応の傾向に依存する。しかし、この本能だけでは「正しさ」の基準は生まれない。正しさは、多数の個人の反応が一致するという「暗黙の合意」、すなわち社会集団による是認によって初めて成立する。これがルールの規範性の源泉である。
第3章では、この集団的側面をより精緻化し、「制度」の自己言及的なモデルを導入する。貨幣や所有権と同様に、ルールもまた、人々がそれを「ルール」として言及し、それに従って行動するという、集団的で自己完結的な実践によって存在する。ルールの正しさとは、結局のところ、集団が正しいと「呼ぶ」ところのものに他ならず、それ以上の根拠は存在しない。第4章では、この制度論と、ルールに従う際に必要な個人の意識(良心的条件)との関係が考察される。ルールに従うとは、単に外的に一致するだけでなく、自らがルールに従っているという意識を伴う必要がある。この一見循環する条件は、社会化のプロセスを通じて、意識と実践が同時に形成されることで解決される。
第5章からは、現代の論争との対話が始まる。まず、クリプキの『ウィトゲンシュタインの規則と私的言語』における「懐疑的パラドックス」が検討される。ブロアは、クリプキの定式化には曖昧さがあり、個人主義的事実の不在を証明したに過ぎない「強い懐疑説」と、社会的事実という回答を許容する「弱い懐疑説」が混在していると指摘する。第6章では、クリプキが脚注で示したフォン・ミーゼスの社会主義計算論争との類似性を手がかりに、市場価格という「制度的事実」が、個人の主観を超えた客観的拘束力を持つように、ルールの意味も社会的事実として理解できると論じる。
第7章と第8章では、マッギンに代表される個人主義的解釈が批判的に検討される。マッギンは、ウィトゲンシュタインを、ルールの根拠を個人の「自然的傾向」に求める自然主義者として読む。しかしブロアは、この解釈は社会化された「第二の天性」を見落としており、結局は非社会的な主観主義に陥ると反論する。また、ロビンソン・クルーソーのような孤立した個人でもルールに従えるという個人主義の主張は、「物理的孤立」と「社会的孤立」を混同していると指摘する。たとえ孤島にいても、クルーソーの思考や行動は社会との関係性(記憶や期待)によって規定されており、これは「社会的」な活動である。さらに、科学的発見のような「革新」も、個人の着想(開始局面)と共同体による承認(結実局面)という二つの社会的局面からなるプロセスであり、個人の孤立した行為だけで完結するものではないと論じる。
第9章では、この現代の論争を、ヒュームとリードによる18世紀の約束の義務をめぐる論争と重ね合わせる。ヒュームは、約束の義務が個人の心の能力(意志や理性)からは説明できず、社会的慣習に基づく「人工的徳」であると論じた。これに対しリードは、義務は個人の道徳感覚(理性)によって直接把握される「自然的」なものであると主張した。ブロアは、この対立を、ウィトゲンシュタイン解釈における集団主義(ヒューム的)と個人主義(リード的)の対立に正確に対応するものと見なす。さらに、ウィトゲンシュタインがシュリックとの対話で示した「善とは神が命じるものである」という「神学的自然主義(唯名論)」の立場は、ヒュームの社会慣習論と同様、それ以上遡ることのできない究極の根拠として集団的実践(あるいは神の意志)を置くものであり、リードのような「神学的合理主義」とは完全に相反することを示す。
最終章の結論では、議論が総括され、ルールとは社会的制度であり、その事実は集団への帰属の事実であると断言される。この結論は、知識社会学にとって根本的な意義を持つ。すなわち、マンハイムが社会学の限界とした「概念の内的論理」による展開も、実は社会的プロセスであり、知識社会学の分析対象となり得ることが示されたのである。ブロアは、ウィトゲンシュタインを理解することは、彼を乗り越え、より豊かな社会理論を構築することだと結ぶ。
各章の要約
第1章 序論
ルールに従うこと、例えば「2, 4, 6, 8…」という数列を生成する単純な行為には、その無限の適用可能性と、「〜ねばならない」という規範性という二つの謎が潜んでいる。伝統的な「意味決定論」は、これらの謎を、ルールの意味そのものが将来の適用を決定しているという考え方で説明する。この立場は個人主義の基盤であり、個人の心による「意味の把捉」がルールの正しさの源泉だと見なす。しかしウィトゲンシュタインはこの見解を拒否し、「ルールは制度・慣習である」という集団主義的な立場を打ち出したと著者は主張する。本書の目的は、この集団主義的解釈を擁護し、クリプキやマッギンらの現代の論争を踏まえつつ、ウィトゲンシュタインの議論を体系的に再構築することである。
第2章 意味有限主義
ウィトゲンシュタインは、ルールの理解を教授・学習のプロセスに着目して分析する。ルールの教授は常に有限の事例によって行われ、学習者はそこから次の未知のケースへと「飛躍」しなければならない。この飛躍は、解釈によって媒介されるのではなく(解釈には更なる解釈が必要となるため)、生物学的・本能的な反応の傾向に依存する。しかし、個々人の本能的反応だけでは、何が「正しい」のかという規範性を生み出せない。正しさは、多数の個人の反応が一致するという「暗黙の合意」、すなわち社会集団による是認によって初めて成立する。これがルールの規範性の源泉であり、ルールの意味は事前に決定されているのではなく、適用の都度、創造されていく(意味有限主義)。
第3章 制度としてのルール
ウィトゲンシュタインは「ルールは制度である」と述べるが、制度とは何かを定義していない。この欠落を補うため、著者はアンスコムとバーンズの「自己言及的モデル」を導入する。貨幣や所有権と同様、あるものが「制度」であるのは、人々がそれを制度として「呼び」(言及し)、それに基づいて行動するという、集団的で自己完結的な実践によって成り立つ。ルールも同様に、人々がそれを「ルール」として言及し、それに照らして行為を是認したり批判したりする実践そのものの中にのみ存在する。ルールの正しさとは、集団が正しいと「呼ぶ」ところのものに他ならず、それ以上の根拠は存在しない。これがルールの規範性を支える客観性の正体である。
第4章 良心的であること
ルールに従うこと(例:命令に従う)と、単に外見的に一致すること(例:たまたま命令と同じ行動をとること)は区別されねばならない。この区別は、ルールに従うためには、自分が従っているという意識(意図)が必要であるという「良心的条件」を導く。この条件は、一見すると「ルールに従うこと」を説明する際に循環を引き起こすように思える。しかし、この循環は、社会化のプロセスを通じて、意識と実践が同時に形成されることで解消される。また、ウィトゲンシュタインが「盲目的にルールに従う」と言うとき、それは無意識ではなく、訓練によって獲得された習慣的な反応(「第二の天性」)を意味する。さらに、私的言語論は、内的な感覚だけではルールは成立せず、「自分は従っていると思う」ことと「実際に従っている」ことの区別を可能にする独立した基準(=社会)の必要性を論証するものである。
第5章 ルール懐疑論
クリプキは、ウィトゲンシュタインの議論を「懐疑的パラドックス」として再構成する。過去の使用だけでは、「足す」という概念が将来の「68+57」に対して125を要求するのか、5を要求する「クワス」なのかを決定できない。このパラドックスは、個人の内的状態や過去の実践、傾向性のいずれも、意味の「事実」を構成できないことを示す。クリプキは、これに対するウィトゲンシュタインの解決を「懐疑的解決」と呼び、意味についての言明は事実を述べるのではなく、コミュニティにおける特定の主張条件(assertability conditions)を持つと解釈する。しかし著者は、クリプキの定式化には曖昧さがあると指摘する。それは、個人主義的事実の不在を証明しただけであり、社会的事実という「直截的解決」の可能性を不当に排除している。
第6章 フォン・ミーゼスとの類推
クリプキが脚注で示唆した、フォン・ミーゼスの社会主義経済計算論争との類似性は、この「直截的解決」を支持する。フォン・ミーゼスは、合理的な経済計算には市場によって形成される「価格」という客観的データが必要であり、中央計画当局のような孤立した主体にはそれが得られないと論じた。この「価格」は、個人の主観を超えた社会的事実であり、それ自体が市場参加者の相互行為によって自己言及的に生成される。同様に、「意味」も個人の心的状態ではなく、言語共同体の相互行為によって生成される社会的事実であると理解できる。この類推は、クリプキの懐疑的パラドックスに対する「直截的解決」の道筋を示すものである。
第7章 個人主義
マッギンは、クリプキの解釈を批判し、ウィトゲンシュタインは個人主義者であったと主張する。彼は、意味は「既約な事実」であり、個人の「能力」や「自然的傾向」に基づくと論じ、規範性はこの自然に根ざすとする。また、集団主義はルールの適用に際して「社会に相談する」という解釈の無限後退に陥ると批判する。著者はこれに反論する。マッギンは、社会的に訓練された「第二の天性」による自動的な反応を見落としており、彼の「自然」は非社会的な主観主義に陥る。また、ウィトゲンシュタインが「将来の使用は現在の意味によって決定される」と述べているというマッギンの解釈は、テクストの誤読であり、彼こそがウィトゲンシュタインが否定した意味決定論を彼に帰していることになる。
第8章 孤立と革新
個人主義の強力な論拠は、ロビンソン・クルーソーのような物理的に孤立した個人でもルールに従えるという直感である。著者は、これに対し、「物理的孤立」と「社会的孤立」を区別する。クルーソーの行動は、社会で獲得した知識や将来の社会との関わり(例:お金を取っておく)によって動機づけられており、それは本質的に社会的である。また、新しいルールを「発明」する革新性についても、個人の着想(開始局面)と共同体による承認(結実局面)というプロセスを経るものであり、個人の孤立した行為だけで完結するものではない。科学史の事例(酸素の発見など)は、発見が共同体の承認によって初めて「発見」として成立することを示している。個人主義者の直感は、この複雑な社会的プロセスを単一の「点」として捉え誤ることに起因する。
第9章 ルールと自然状態
現代の論争は、ヒュームとリードによる18世紀の約束の義務をめぐる論争の焼き直しである。ヒュームは、約束の義務は個人の意志や理性からは説明できず、相互利益に基づく社会的慣習(人工的徳)に由来すると論じた。これに対しリードは、義務は個人の道徳感覚(理性)によって直接把握される自然なものであり、社会的慣習を前提しないと主張した。この対立は、ウィトゲンシュタイン解釈における集団主義(ヒューム的)と個人主義(リード的)の対立に正確に対応する。さらに、ウィトゲンシュタインが「善とは神が命じるものである」という神学的唯名論に共感を示したことは、リードのような神学的合理主義(神でさえも予存する善に従う)を退け、それ以上遡れない究極の根拠として集団的意志(または神の意志)を置くヒューム的立場を裏付けるものである。
第10章 結論
ルールとは社会的制度であり、ルールに従うことの事実は、個人の心的状態ではなく、その社会集団への帰属の事実である。これは、クリプキの懐疑に対して、個人主義的事実の不在を認めつつ(懐疑的側面)、社会的事実という明確な回答を提供する(直截的側面)ものである。この結論は、知識社会学にとって決定的な意義を持つ。マンハイムが社会学の限界とした「概念の内的論理」による展開も、実は社会的プロセスであり、分析対象となり得ることが示されたからである。神経科学などの個人主義的・自然主義的説明は、コンピュータの比喩にせよ、結局は「制度」としての規範性を説明できない。ウィトゲンシュタインを真に理解することは、彼の洞察を乗り越え、より豊かな社会理論を構築することにある。
ルールは誰が決めるのか:ウィトゲンシュタインが暴く「正しさ」の社会的起源
by Claude Sonnet 4.6
数列「2、4、6、8……」の次は本当に自明か?
まず引っかかったのはここだ。「2ずつ加えるルール」に従うとき、1000の次に1002と書くのは「当然」だと思っていた。でもブルーア(David Bloor)はそこで立ち止まって問う——その「当然」はどこから来るのか?
ウィトゲンシュタインが発見したのは、このゾッとする事実だ:いかなる有限個の例示も、ルールの「正しい」継続を論理的に決定できない。1000の次に1002と書くのが「正しい」のは、数学的必然性があるからではなく、われわれがそのように訓練され、そのように反応することを互いに承認しているからだ。
これは一見トリビアルに見えるが、掘り下げると恐ろしい含意を持つ。
「意味決定論」という幻想
ブルーアが「意味決定論(meaning determinism)」と呼ぶ立場がある。ルールの意味を一度「把握」すれば、その意味が将来の正しい適用をすべて事前に決定するという考え方だ。フレーゲはこれを信じていた——数列「+2」の移行は「すでにそこにある」と。
でも待て。「把握する」とは何をすることか?頭の中に何らかの対象が生じることか?それもまた解釈を必要とし、その解釈もまた解釈を必要とし……無限後退が始まる。
ウィトゲンシュタインの答えは「意味有限論(meaning finitism)」だ——意味はケースからケースへと移行する中で、その都度「創られる」。あらかじめ確定された意味などない。過去の事例が「正しい継続」を決定するのではなく、次のステップでわれわれが何をするかが、ケースバイケースで「意味」を構成していく。
ルールは「制度」である
ここが核心だと思う。ブルーアはウィトゲンシュタインの「ルールは習慣であり制度である」という主張を徹底的に擁護する。
制度とはどういうものか?コインを例にとると、コインはその物理的特性(金属の形状)によってコインなのではない。人々が「これをコインと呼ぶ」という集合的な実践によってコインになる。この「呼ぶ」は単なる言語行為ではなく、それに伴う行動パターン全体を指す。そして「コインと呼ぶこと」の正しさは、他の人々が「コインと呼ぶ」という実践によって構成される——これが「自己参照的」システムだ。
結婚も、財産権も、数学のルールも、同じ構造を持つ。われわれは「1000の次は1002だ」と言う。なぜなら他の全員もそう言うからだ。そして他の全員がそう言うことが、「1002が正しい」という事実を構成する。
これはトートロジーではなく、制度の論理だ。
パンデミック対応を思い出す
ここで自分の経験と接続してしまう。「科学的コンセンサス」とは何だったのか。
専門家たちは「エビデンスに基づく」と言った。でもブルーアが明らかにするのは、「何がエビデンスとして認められるか」自体が制度的決定だという事実だ。RCT(ランダム化比較試験)を「証拠の階層」の頂点に置くEBMの枠組みも、一つの「ルールとしての制度」だ——その枠組みを採用することで、それ以外の証拠(医師の臨床経験、症例報告、メカニズムに基づく推論)が「エビデンスではない」と排除される。
ブルーアが分析するカリプキー(Saul Kripke)の「懐疑論的挑戦」はここで効いてくる:ある数学的関数の「正しい」適用を決定する「事実」は、個人の心の中には存在しない。では医学的「エビデンス」の「正しい」解釈を決定する「事実」はどこにあるのか?
答えは:それを承認する共同体の実践の中にある。
マクギンの個人主義的反論の失敗
コリン・マクギン(Colin McGinn)はウィトゲンシュタインを「個人主義者」として読む。ルール遵守は本質的に社会的ではなく、個人の自然な傾向性に基づくという立場だ。
ブルーアはこれを二重に批判する。
第一に、マクギンは「解釈によって媒介されない」ことと「社会化されていない」ことを混同している。訓練によって「自然になった」反応は、社会的でありながら同時に自動的・反射的でありうる。「第二の自然」の概念だ。
第二に、個人の自然な傾向性は「規範性」を生み出せない。私がある数列の次を「当然こう続く」と感じても、それだけでは正しい/間違いの区別が成立しない。ウィトゲンシュタインの言葉で言えば「何でも自分に正しいと思えることが正しい——これは正しさについて何も語っていない」。
個人主義的な立場の真の問題は、「規範性の出所」が説明できないことだ。マクギンは「能力(capacity)」や「原始的自然傾向」に訴えるが、それは「意味は意味だ」という循環論法と変わらない——ラッセルの言葉を借りれば「正直な労働より窃盗の利点」だ。
ヒュームとリードの再演
ブルーアが引き込む歴史的比較が面白い。18世紀のヒュームとリードの論争は、現代のクリプキーとマクギンの論争の先行形態だ。
ヒュームは問う:なぜ借りたものを返さなければならないのか?「義務があるから」という答えは循環する。彼の答えは:約束の拘束力は社会的慣行から生まれる。最初は利己的な計算(返すことが得だから)に基づく協調パターンが積み重なり、やがてその上に「道徳的義務感」という現象が乗っかる。
リードはこれに反論する:道徳的義務は直接知覚される——ユークリッド幾何学の公理のように自明だ。「常識哲学」の立場から、ヒュームの懐疑論を「社会の基盤を危うくする危険な思弁」として退けた。
この構図、どこかで見たような気がする。パンデミック対応で「科学的コンセンサスを疑うな」と言われたとき、それはリード的な立場だった——「専門家の判断は直接知覚される真実であり、それを疑うのは無責任だ」。
「正しさ」はいつも権力と一緒にある
ブルーアが示すのは、数学的真理でさえ「正しい」という規範性は、個人の心の中や抽象的な数学的プラトニズムの世界にあるのではなく、「それを正しいと承認し合う集合的実践」の中にあるということだ。
これは相対主義ではない——数学のルールに反する答えは本当に「間違い」だ。しかしその「間違い」を構成するのは、社会的制度としての数学的実践であり、その実践を維持・再生産する訓練・制裁・承認のメカニズムだ。
だとすれば「科学的コンセンサス」の「正しさ」もまた、制度としての科学——学術誌、査読システム、研究資金配分、専門家コミュニティの承認——によって構成される。その制度が腐敗している、あるいは特定の利害関係に汚染されているとしたら?
ブルーアは「制度は自己参照的・自己創造的」と言う。制度は自分自身を参照することで存在する。それはつまり、制度を支える実践から切り離されたとき、制度の「正しさ」は蒸発する可能性があるということだ。
最も深い問い:われわれは何に縛られているのか
個人は社会に縛られている——個人の傾向性が規範を作るのではなく、規範が集合的実践から生まれる。でも「社会全体」は何に縛られているのか?
ブルーアはここで正直だ:「社会全体に対する外部の標準は存在しない」。社会の外に出てそれを評価するための中立な立場はない。これはウィトゲンシュタインの「神のコマンド論」的な立場——「善いものは神が命じたから善い」という論理と同型だ。
これは虚無主義ではない。でも根底的な偶発性(contingency)を認めることだ。われわれが「当然2002の次は2004だ」と感じるのは、ある訓練を受け、ある集合的実践の中に生きているからだ。別の訓練を受け、別の実践の中に生きていたなら、別の「当然」があったかもしれない。
そしてここが怖い:われわれの「常識」も「科学的知識」も、ある特定の社会的制度の産物であり、その制度の内部で訓練された者にとってだけ「自明」なのかもしれない。パンデミック対応で問いを発したとき感じた「異端者扱い」——「明らかに間違っている人間」として排除されること——は、制度の自己参照的な規範維持メカニズムそのものだった可能性がある。
「2000の次は2008だ」と書いたウィトゲンシュタインの生徒のように。
この本を読み終えて残るのは、一つの問いだ:われわれが「自明」だと思っているものの、どれくらいが社会的訓練の産物で、どれくらいが本当に「抵抗しがたい実在」なのか。そしてその二つを区別する方法が、そもそもあるのかどうか。