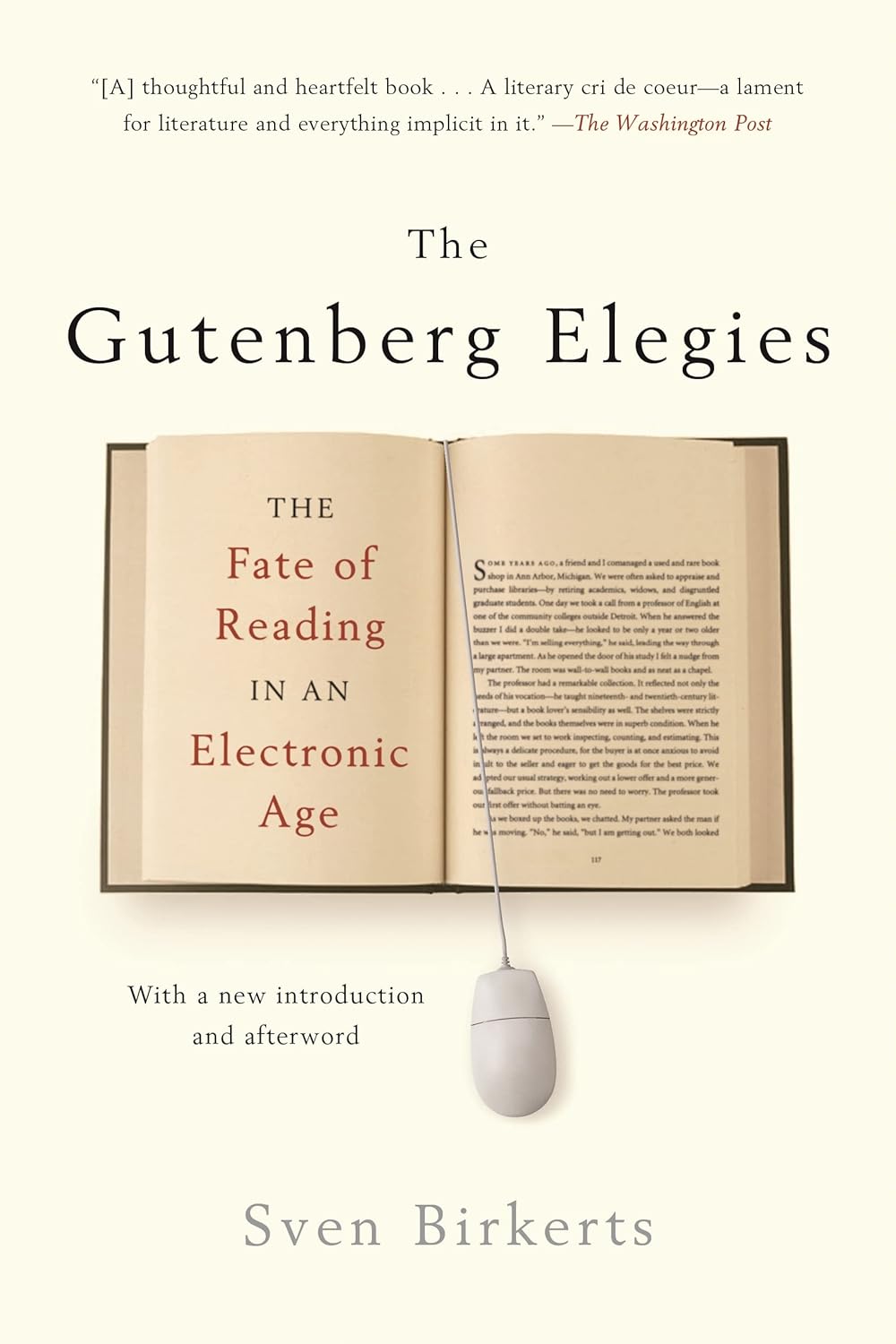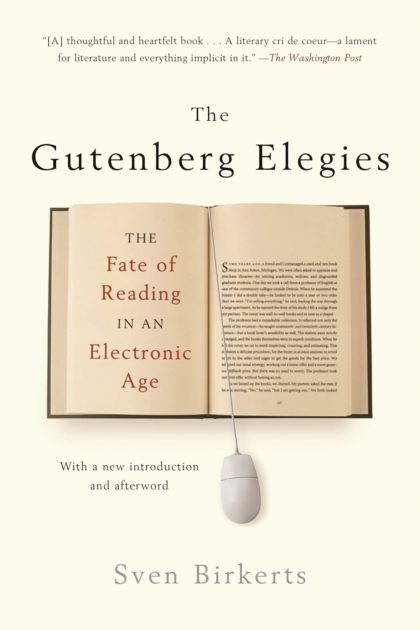
英語タイトル:The Gutenberg Elegies:The Fate of Reading in an Electronic Age
著者名:Sven Birkerts
日本語タイトル:『グーテンベルクのエレジー:電子時代における読書の運命』
著者名:スヴェン・バーカーツ
出版年:1994年 (2006年版の追記と後書きを含む)
目次
- 前書き:読書戦争 / Introduction:The Reading Wars
- 第一部 読書する自己 / The Reading Self
- 第1章 エムヴーヴーパー / MahVuhHuhPuh
- 第2章 紙の追跡:自伝的断片 / The Paper Chase:An Autobiographical Fragment
- 第3章 飛び去ったフクロウ / The Owl Has Flown
- 第4章 庭園の女 / The Woman in the Garden
- 第5章 自己をめくる:読書の私密性 / Paging the Self:Privacies of Reading
- 第6章 読書の影の生活 / The Shadow Life of Reading
- 第7章 列車の窓から / From the Window of a Train
- 第二部 電子の千年期 / The Electronic Millennium
- 第8章 電子の千年期へ / Into the Electronic Millennium
- 第9章 解き放たれたペルセウス / Perseus Unbound
- 第10章 耳をすませて / Close Listening
- 第11章 ハイパーテキスト:マウスと人間 / Hypertext:Of Mouse and Man
- 第三部 臨界質量:三つの黙想 / Critical Mass:Three Meditations
- 第12章 西洋の亀裂 / The Western Gulf
- 第13章 文学の死 / The Death of Literature
- 第14章 狭まる岩棚 / The Narrowing Ledge
- エピローグ:ファウスト的契約 / Coda:The Faustian Pact
- 2006年版への追記:/ Afterword to the 2006 Edition
本書の概要
短い解説:
本書は、活字・書物中心の文化から急速に電子通信中心の文化へと移行する歴史的転換期に、文学的な読書と「読書する自己」の内面的体験がどのような変容と危機に直面しているかを考察する。主に1990年代半ばに書かれ、2006年に補筆されたこれらのエッセイは、テクノロジーの浸透が深い読書、省察、主観性にもたらす影響に警鐘を鳴らし、読書の文化的・精神的意義を擁護する。
著者について:
スヴェン・バーカーツは、批評家・エッセイストであり、自らを「矯正されざる読者」と称する。両親はラトビアからの移民であり、自身は英語を第二言語として学んだ複数の言語的アイデンティティを持つ。書店員、書評家、教師としての経験を背景に、自らの読書遍歴と内省を織り交ぜながら、テクノロジーによる変容を個人的かつ文化的なレベルで深く考察する。
テーマ解説
- 主要テーマ:活字文化から電子文化への移行とその人間性への影響。
- 新規性:単なるメディア論ではなく、「読書する自己」の内面的経験(深い時間、持続、主観性)の喪失を中心に据えた文化的批判。
- 興味深い知見:電子技術による「深い時間」の破壊が、知恵や存在の意味の感覚を蝕んでいるという主張。
キーワード解説
- 深い読書 (Deep Reading):持続的な注意と内省を伴い、意味を内面化する深く集中的な読書体験。
- 深い時間 (Deep Time):物事の意味が共鳴し、持続性を持つ時間体験。電子的な「瞬間性」と対立する。
- 主観性 (Subjectivity):個人の内面的な意味形成の領域。電子ネットワークによる過剰な接続性と媒介は、この主観性を希薄化させる。
3分要約
本書は、1990年代に急速に進行した「活字から電子へ」の歴史的パラダイムシフトを、読書という行為と「読書する自己」の内面性を通して考察する一連のエッセイ集である。著者のスヴェン・バーカーツは、自身の読書遍歴や書店員・教師としての体験を縦糸に、活字文化が育んだ「深い読書」「深い時間」「持続的な内省」の体験が、電子メディアによる情報の瞬時の流れ、断片化された注意力、絶え間ない接続性によって侵食されていると警鐘を鳴らす。
第一部では、読書の個人的・内面的価値を描く。読書は単なる情報摂取ではなく、自己形成に寄与する「深い時間」の体験であり、他者の世界への没入を通じて自己の境界を拡張する行為である。著者はヴァージニア・ウルフの思考法に触発され、自身の読書体験を振り返りながら、読書が育む持続的で深い意味の感覚を浮き彫りにする。
しかし第二部では、こうした読書体験を支えてきた文化的・技術的条件が、電子千年期の到来によって根底から揺さぶられていることが論じられる。コンピュータ、ハイパーテキスト、オーディオブック、インタラクティブ・ビデオなどの新技術は、読書のリニアな論理性や持続的注意を損ない、情報の「横方向」への拡散と「瞬間性」を優先させる。著者は大学教育におけるマルチメディア教材の導入や、読者の著者に対する「共犯者」化といった現象を例に、変化の実態とその危険性を指摘する。
第三部では、この文化的転換をより大きな思想的文脈で捉え直す。リオネル・トリリングの『リベラルな想像力』とアルヴィン・カーナンの『文学の死』を対照的に論じ、文学と知的批評がかつて持っていた社会的権威と連続性の感覚が失われつつある状況を分析する。最終章では、著者の個人的な苦闘が語られる。電子技術の魅力と効率性を認めつつも、それがもたらす「軽さ」と主観性の喪失を深く恐れ、ファウスト的な取引への抵抗を試みる。
2006年版の追記では、著者は自身がかつて「拒絶せよ」と宣言した技術に部分的に順応せざるを得なかった現実を認める。しかし、その適応は「緊張した抱擁」であり、テクノロジーの使用とその文化的コストに対する批評的意識を維持するための闘いであると述べる。ネットワーク化された「代理現実」が「一次的な現実」を覆い隠す中で、書物と深い読書は、失われつつある集中力、内面性、存在の重みを取り戻すための最後の砦としての意義を強めていると主張する。本書は、単なるノスタルジーではなく、変化する時代において「人間らしい生」を構成するものは何かを問い直す、持続的な文化的考察の記録である。
各章の要約
前書き:読書戦争
著者は、過去数十年で文化が根本的な変貌を遂げつつあるという前提を提示する。印刷ページの安定したヒエラルキーは、電子回路を通る衝動の奔流によって取って代わられようとしている。この変化は文学実践、特に読書のあり方に衝撃を与えている。本書は二段構えで、まず読書の主観的エコロジーを描き、次にその均衡を脅かす力を論じる。著者は、言語が真の進化的奇跡であると信じる「矯正されざる読者」として、文学体験がもたらす深遠さと、束縛された書物が書かれた言葉の理想的な媒体であるという信念を告白する。しかし、その価値観を共有しない人々との対話を念頭に、議論は時に自伝的・主観的になることも厭わない。
第一部 読書する自己
第1章 エムヴーヴーパー
ヴァージニア・ウルフの間接的で主観的な思考法に触発され、著者は「読書と意味の場所」についての思索を始める。大学でヘンリー・ジェイムズを教えた経験は、学生たちが複雑な構文や内面的な間接性、道徳的区別を扱う文学にほとんど接点を持てないという「歴史的連続性の断絶」を示していた。これは単なる教育問題ではなく、電子文化で育った世代の体験が、印刷物に刻まれた集合的主観的歴史(種としての思索の蓄積)を異質なものにしていることの表れだ。著者は、ハーディの『日陰者ジュード』などを通じて過去の世界の「感じ」を想像し、かつての「垂直的」(深い)意識が、現在の「水平的」(広いが浅い)意識に取って代わられつつあると考える。この変化は、読書を通じて育まれる持続性や意味の感覚を脅かす。著者は5歳の娘の落書き(「MahVuhHuhPuh」)に、言葉と意味への原初的な関心の萌芽を見出す。
第2章 紙の追跡:自伝的断片
著者の読書と書くことへの愛着の形成を辿る自伝的エッセイ。ラトビア系移民の家庭で育ち、英語を「彼らの言語」と感じながらも、書物を秘密の逃避場所として愛した少年時代。10代ではジャック・ケルアックやヘンリー・ミラーなどに熱中し、作家となるロマンティックな幻想を抱く。大学を出た後、書店員として働き、稀覯書店の共同経営者となるが、書物への情熱が創作への情熱を圧倒する危うさも感じる。ヨーロッパ旅行、メイン州での隠遁生活、失恋を経て、遂には小説ではなくロバート・ムジールについての評論を書くことで、批評家・エッセイストとしての自らの「声」を見いだすまでの遍歴が語られる。
第3章 飛び去ったフクロウ
読書の歴史的変遷を概観し、「垂直的」読書(少数の書物を深く繰り返し読む)から「水平的」読書(大量の情報を一度だけ流し読みする)への移行を指摘する。情報の氾濫は文脈感覚を弱め、長期記憶を衰退させ、深い時間での「共鳴」を不可能にする。この共鳴の喪失は、部分の総和としての全体を理解するという「知恵」の理想そのものの衰退を意味する。著者は、知恵が育まれるためには垂直的意識、すなわち深い時間が必要であり、それは書物や芸術作品、あるいは沈黙の場(セラピストのオフィス)でのみ持続可能だと論じる。
第4章 庭園の女
「庭園で本から目を上げて物思いにふける女性」という絵画的イメージを手がかりに、読書行為の形而上学を探る。読書とは、物理的現実から別の現実(作者が創造した現実)への移行であり、自己の再定位を伴う変化である。書物の言葉は読者によって内面で活性化され、作者の意図されたコヒーレンス(統一性)の感覚に浸る。この感覚は、私たちの日々の体験には稀な、意味と目的に向かう生の感覚を一時的に与えてくれる。読書は、人生が単なる瞬間の連続ではなく「運命」であるという危険で exhilaration な考えを生かし続ける行為なのである。
第5章 自己をめくる:読書の私密性
読書が、特に子供と思春期において、どのように感受性(センスビリティ)の形成に役割を果たすかを考察する。子供の読書は空想への自由な没入だが、思春期では書物が自己変容のテストの場となる。小説の登場人物への同一化や、その物語が暗示する「連結された運命」の感覚は、若者が自分自身の生に意味と方向性を見いだす手助けをする。読むことは、慣習的な自己の境界から自由になることであり、その体験は後に自己理解の要素として組み込まれる。読書は、日々の雑事からは得難い、生を統一された全体として構想する感覚を育む。
第6章 読書の影の生活
読書体験は、ページを離れた後も「影の生命」として続くことを論じる。読んでいる最中ですら、読者は読み終えた内容を文脈として記憶し、その上に新たな理解を積み重ねている。読書記憶は、実際の経験の記憶と似ているが、自分自身の想像力によって創造されたものを対象とする点で独特である。深く没入した読書は、読者の気分や知覚を変え、現実世界の見え方に色を付ける。例えばナイポールの小説を読んだ後では、人種的緊張に関する新聞記事がより強く目に留まるようになる。著者は、自らの読書歴を振り返り、読書が単に情報を加えるだけでなく、世界を見るための「レンズ」や内なる「文脈」を提供してきたことを確認する。
第7章 列車の窓から
ボストンからニューヨークへの列車の旅で、「読者と書き手」というフレーズがリズミカルに頭を駆け巡った経験から、読むことと書くことの根本的な親和性について思索する。書き手は内的な言語記憶を「読む」ことで表現を発見し、読者は作者の言葉を自分の経験で満たすことで、つまり内的に「書き写す」ことで意味を創造する。この両活動は、意識の流れの表裏をなしており、自己を読み、書き記すという営みの一部である。著者はこう述べる。「読者はみな書き手であり、書き手はみな読者である。」
第二部 電子の千年期
第8章 電子の千年期へ
かつて文学教授が蔵書を全て売り払いコンピュータに転向したエピソードを起点に、印刷言葉から電子通信への全文化的な移行が進行中であると論じる。テレビやコンピュータネットワークが織りなす「電子の網」は、自然世界との直接的な関係や歴史的展望を覆い隠し、永続的な「現在」の意識を生み出している。この変化は、言語の浸食、歴史的展望の平坦化、私的自体の衰退といった「病的症状」として現れる。著者は、接続性と効率性の代償として、深い主観性や内面性が失われる危険を指摘し、言語を「魂のオゾン層」と称してその希薄化を危惧する。
第9章 解き放たれたペルセウス
教育現場へのインタラクティブ・ビデオやマルチメディア教材の導入を批判的に検討する。特に古典学のデータベース「ペルセウス」を例に、技術が情報へのアクセスを拡大する一方で、習得の「過程」や「文脈」、時間と格闘するという知的努力を損なう可能性を論じる。知識の「横方向」の拡大は「深さ」の犠牲の上に成り立ち、データの氾濫は物語的で意味のある理解を困難にする。著者は、最終的には情報の検索技術に長けた「技術者」が、記憶し理解する「知者」に取って代わる未来を憂う。
第10章 耳をすませて
オーディオブックを体験した著者の考察。通勤中のドライバー向けに急成長するこの産業は、時間に追われる現代の生活様式に適応したものだ。聴くことの受動性や速度の固定化は、「深い読書」に特有の、立ち止まり、内省し、自己と結びつける自由を奪う。複雑な文学作品は聴覚による消化が難しく、読み手の声は読者の内的声を押しのける一種の「声の専制」となりうる。しかし一方で、朗読は文学の「音」を思い出させ、よく書かれた散文のリズムやアイロニーを浮き彫りにする利点もある。著者は、ソローを聴きながら車を運転した体験で、語られた言葉の直截的な力に一時的な高揚を覚えたことを認める。
第11章 ハイパーテキスト:マウスと人間
ハイパーテキスト小説『Victory Garden』を体験し、その非線形的で読者が経路を選択する形式が、伝統的な読書の前提を根本から書き換えようとしていると論じる。スクリーン上の言葉はページ上の言葉とは異なる「存在」を持ち、流動的で暫定的なものとして感知される。ハイパーテキストは、固定された作者の権威を「読者=書き手」の協働へと置き換え、作品の統一性や必然性という概念を脅かす。著者は、このような開かれたテキストの魅力を認めつつも、それが提供する「自由」が、作者の規律ある想像力に身を委ねるという読書の本質的喜びを損なうのではないかと危惧する。書物は、外部の騒乱から隔てられた「可搬式の囲い」であり、その価値は改めて確認されるべきだと主張する。
第三部 臨界質量:三つの黙想
第12章 西洋の亀裂
リオネル・トリリングの『リベラルな想像力』(1950年)を手がかりに、文学と知的生活が文化的中心にあった時代の感覚を振り返る。トリリングは、文学が感情と思想、政治と想像力を結びつけると信じていた。著者は、トリリングの時代と現在との間の「亀裂」を測り、メディアの変容、特にマーシャル・マクルーハンの予言した電子メディアの台頭が、人間主義の連続性の信念を瓦解させたと論じる。文学批評の衰退は、社会が文学と思想の提供する「答え」を見出せなくなったことの表れである。
第13章 文学の死
アルヴィン・カーナンの『文学の死』を引き合いに、トリリングの時代以降、文学の制度的権威が完全に失墜した状況を分析する。大学では構造主義や脱構築が作者の権威やテキストの優位性を否定し、印刷文化はテレビやコンピュータの「スクリーン文化」に駆逐されつつある。文学の読者層は高齢化し、出版は採算性に支配される。著者はこの診断をほぼ共有するが、完全な絶望には与さない。人間には「意味」への配線がなされており、電子文化による極度の「外方向」への偏重が、いずれ「意味の危機」として反動を引き起こす可能性を指摘する。その時、人々は宗教、セラピー、そして再び芸術(文学)のもとに回帰するかもしれない。
第14章 狭まる岩棚
ヘルマン・ウォークの小説『ヤングブラッド・ホーク』(作家志望の青年が成功する物語)が描いた、作家の英雄的個人主義がもはや成り立たない文化的状況を論じる。出版の商業化、電子メディアの侵食、大学における「作者の死」論は、作家の社会的地位を低下させた。さらに根本的に、電子ネットワークへの適応は「接続性」を理想とし、孤立した主観的個人という古い理想を陳腐化させつつある。現代小説は、この過度に媒介され、断片化された現実を描くことに苦闘している。著者は、文学が生き残るためには、この前例のない集合的変化に挑み、「群衆」に属するという見込みに対し「ならず者としての自己」の場所を探求するという、危険な課題に取り組まねばならないと示唆する。
エピローグ:ファウスト的契約
雑誌『Wired』が描くデジタル未来礼賛のヴィジョンと対峙し、技術と魂の対立というテーマを深める。著者は電子技術の進展が「一次的な現実」との間に「媒介の網」を作り出し、人間の「オーラ」(存在の独自性)や「深い時間」を侵食していると論じる。私たちは便利さと引き換えに、適応を重ね、集合的な電子部族の生活へと順応しつつある。これは主観的個人主義の終焉を意味するかもしれない。著者はウォーカー・パーシーの「生物の喪失」論やヴァルター・ベンヤミンの「オーラ」論を援用し、最終的に「接続性」が存在の重力と神秘性を消し去るのではないかと恐れる。そして、内なる声に従い「それを拒絶せよ」と宣言する。
2006年版への追記
初版から10年以上を経て、著者は自身がかつて拒絶を宣言した技術に部分的に順応せざるを得なかった現実を認める。生活と仕事の現実がそれを要求したからだ。しかし、その適応は「緊張した抱擁」であり、内心では依然として古きものへの忠誠を抱いている。この10年間で進行した変化──インターネットと携帯機器の爆発的普及による「信号の網」の深化──は、前景と背景の区別を消し去り、想像力と情感そのものを衰弱させている可能性すらある。著者は、9.11のような巨大な現実のショックでさえ、メディア・ストリームに吸収され神話化されてしまう状況を憂う。それでも、書物と深い読書は、失われつつある集中力と内面性を取り戻すための対抗技術としての意義を強めていると信じる。結論は、個々人が新たな誘惑にどう向き合い、どれだけを拒絶するかを決めるという、個人の選択に委ねられている。