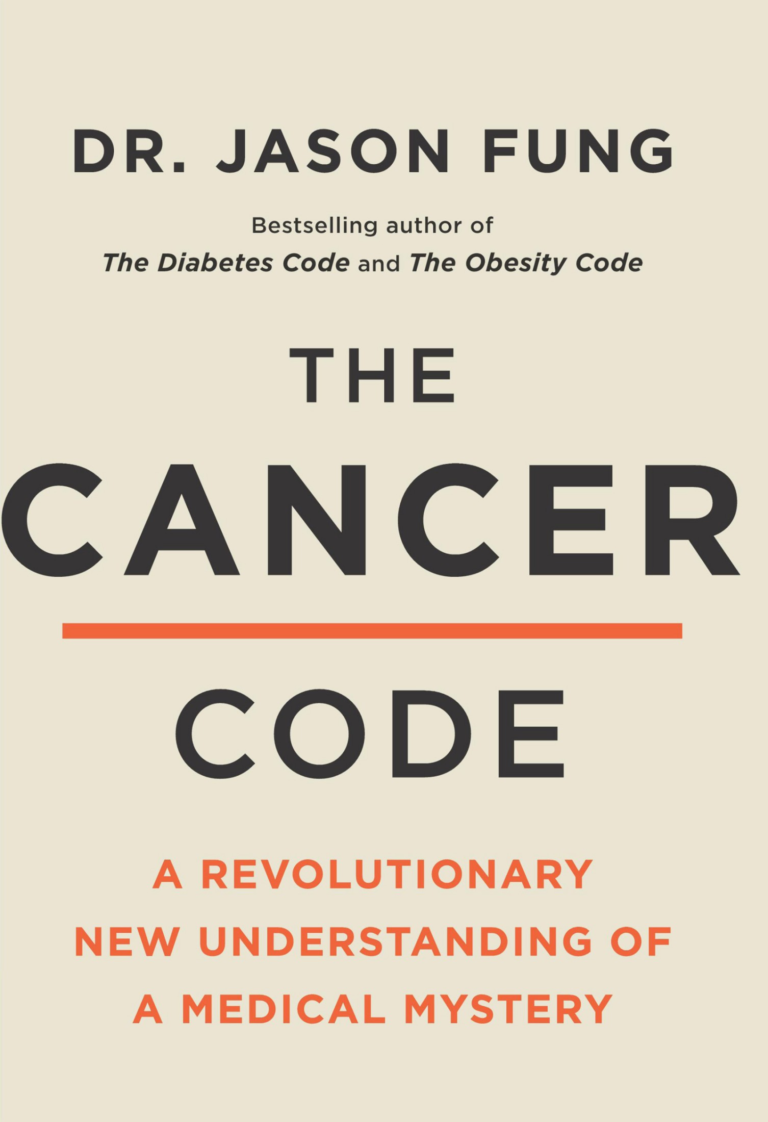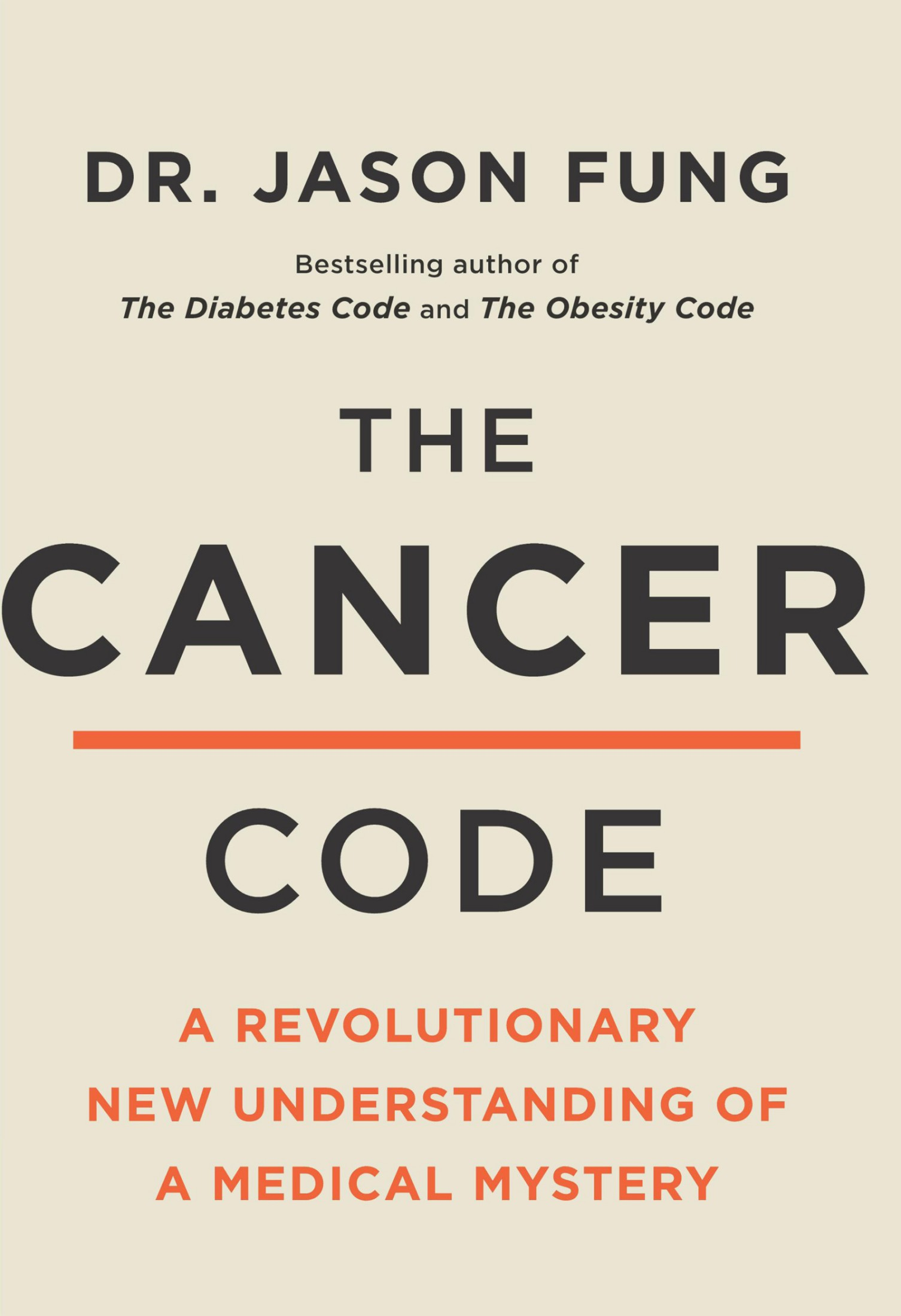
英語タイトル:『The Cancer Code:A Revolutionary New Understanding of a Medical Mystery』Jason Fung 2020
日本語タイトル:『がんの暗号:医学最大の謎に対する革命的な新たな理解』ジェイソン・ファング 2020
目次
- 第一部 過剰な成長としてのがん / CANCER AS EXCESSIVE GROWTH
- 第1章 塹壕戦 / Trench Warfare
- 第2章 がんの歴史 / The History of Cancer
- 第3章 がんとは何か? / What Is Cancer?
- 第4章 発がん物質 / Carcinogens
- 第5章 がんはウイルス性となる / Cancer Goes Viral
- 第二部 遺伝子疾患としてのがん / CANCER AS A GENETIC DISEASE
- 第6章 体細胞突然変異説 / The Somatic Mutation Theory
- 第7章 がんのプロクルステスのベッド / Cancer’s Procrustean Bed
- 第8章 分母の問題 / The Denominator Problem
- 第9章 偽りの夜明け / A False Dawn
- 第三部 形質転換 / TRANSFORMATION
- 第10章 種と土壌 / The Seed and the Soil
- 第11章 生命の起源とがんの起源 / The Origins of Life and the Origins of Cancer
- 第12章 腫瘍進化 / Tumoral Evolution
- 第13章 がん化 / Cancerous Transformation
- 第四部 進行 / PROGRESSION
- 第14章 栄養とがん / Nutrition and Cancer
- 第15章 高インスリン血症 / Hyperinsulinemia
- 第16章 成長因子 / Growth Factors
- 第17章 栄養センサー / Nutrient Sensors
- 第五部 転移 / METASTASIS
- 第18章 ワールブルク効果の復活 / The Warburg Revival
- 第19章 浸潤と転移 / Invasion and Metastasis
- 第20章 がんの奇妙な物語 / The Strange Story of Cancer
- 第六部 治療への示唆 / TREATMENT IMPLICATIONS
- 第21章 がん予防とスクリーニング / Cancer Prevention and Screening
- 第22章 食事の決定因子 / Dietary Determinants of Cancer
- 第23章 免疫療法 / Immunotherapy
- エピローグ:/ Epilogue
本書の概要
短い解説:
本書は、一般読者を対象に、がん研究の歴史を辿りながら、「がんとは何か」という根本的な謎に対する理解のパラダイム(枠組み)がどのように変遷してきたかを解説する。特に、近年登場した進化生物学・生態学的視点からの「がんパラダイム3.0」を中心に、がんの起源と振る舞いを「単細胞生物への先祖返り」と捉える革新的な理論を提示し、予防・治療への新たな示唆を考察する。
著者について:
著者ジェイソン・ファングは、カナダ在住の腎臓専門医。肥満や2型糖尿病の治療・研究で知られ、断続的断食(インターミッテント・ファスティング)の提唱者としても著名である。医師としての臨床経験と、既存の医学常識を批判的に見つめる視点を持ち、本書では栄養・代謝の観点からがんを包括的に捉える独自のアプローチを展開する。
テーマ解説
- 主要テーマ:がん理解のパラダイムシフト。がんを「過剰成長の病気」「遺伝子突然変異の病気」と捉える従来の限界を指摘し、進化・生態学的視点による新たな枠組みを提唱する。
- 新規性:「がんパラダイム3.0」の提唱。がんを、多細胞生物内の細胞が「単細胞生物の生存プログラム」を再活性化した先祖返り(アタビズム)の結果として位置づける。
- 興味深い知見:高インスリン血症(肥満、2型糖尿病)とがんの強力な関連性。インスリンが単なる代謝ホルモンではなく、主要な成長因子としてがんの「土壌」を肥沃化することを強調する。
キーワード解説
- がんパラダイム1.0:がんを「過剰成長の病気」と定義。これに基づく治療は、切除、放射線、化学療法といった「細胞大量破壊兵器」となる。
- がんパラダイム2.0:がんを「蓄積された遺伝子突然変異による病気」と定義。ヒトゲノム計画や標的治療薬の開発を促したが、がんの複雑さを説明しきれず限界に直面する。
- がんパラダイム3.0:がんを「進化・生態学的現象」と定義。慢性的な亜致死的損傷への適応としての「形質転換」、栄養センサーによる「進行」、自然選択による「転移」の3段階からなる。
- アタビズム:進化の過程で失われた祖先の形質が再び現れる現象。がんは多細胞生物の細胞が、その進化的起源である単細胞生物の生存プログラム(成長、不死性、移動、ワールブルク効果)を再活性化した状態であるとする。
- 種と土壌:がん細胞そのもの(種)だけでなく、それを取り巻く環境、特に高インスリン血症や慢性炎症といった「土壌」が、がんの発生・進行に決定的な役割を果たすという比喩。
3分要約
本書は、がんに対する人類の理解が「過剰成長の病気(パラダイム1.0)」から「遺伝子突然変異の病気(パラダイム2.0)」へと移行しながらも、いずれも根本的な「なぜ」に答えられず、治療の進歩が停滞した歴史を描く。
パラダイム2.0は、イマチニブやトラスツズマブといった画期的な標的薬を生み出したが、多くのがんが数百もの異なる変異を持ち、転移や薬剤耐性を容易に発展させるという複雑さの前に限界に達した。著者は、がん研究が「木を見て森を見ず」の状態、すなわち膨大な遺伝子変異のカタログ化に没頭し、大局的な理解を欠いていたと批判する。
ここから著者が提唱するのが「がんパラダイム3.0」、すなわち進化生物学と生態学の視点に立った理解である。この枠組みでは、がんの起源を生命の多細胞化の歴史に遡る。すべての多細胞生物の細胞には、その祖先である単細胞生物の生存プログラム(種)が埋め込まれている。慢性的な亜致死的損傷(喫煙、炎症など)に直面した細胞が、多細胞社会の協調ルールを捨て、この太古の生存プログラムを再活性化するのが「がん化」である。
そして、この「種」が成長するかどうかは「土壌」、つまり体内環境に大きく依存する。特に、インスリン、mTOR、AMPKといった「栄養センサー」は同時に「成長因子」でもあり、肥満や2型糖尿病による高インスリン血症は、がん細胞に豊富な栄養と成長シグナルを提供し、がんを育む最良の土壌となる。
転移は、がんの驚異的な適応能力を示すプロセスである。それはがんの晩期現象ではなく、ごく早期から循環腫瘍細胞として血液中に放出される。血流という過酷な環境が自然選択圧として働き、より生存力の高い、攻撃的ながん細胞のクローンが選択され(腫瘍自己播種)、最終的に遠隔臓器にコロニーを形成する能力を獲得する。がんは静的ではなく、宿主と環境に対して絶えず進化する動的な「侵入種」なのである。
この新たな理解は、治療と予防への重要な示唆をもたらす。スクリーニングの成否は、がんが秩序だった線形進化をとるか、分岐進化をとるかによって異なる。食事の役割は、高インスリン血症を避け、がんの「土壌」を貧しくすることにある。そして最も有望な治療の新領域は、がんの「最大の強み」を攻撃するのではなく、その「最大の弱点」、すなわち免疫システムによる認識と攻撃を強化する「免疫療法」であり、放射線療法との相乗効果(アブスコパル効果)や、がんを根絶ではなく「管理」する適応療法といった新戦略が登場している。
各章の要約
第一部 過剰な成長としてのがん
第1章 塹壕戦
医学界は、肥満、2型糖尿病、がんといった公衆衛生上の大問題に対し、現状の治療法や理解の限界を認めることをためらい、進歩を妨げてきた。1971年に始まった「がんに対する戦争」は、莫大な資金と研究にもかかわらず、長らく成果が上がらなかった。がん死亡数は増加し、新薬の多くは生存期間をほとんど延ばさない「腫瘍縮小効果」のみで承認されていた。しかし、1990年代以降、喫煙率の減少と新たながん理解のパラダイムの登場により、死亡率は低下に転じ始めた。著者は、がんを理解するための旅を始める。
第2章 がんの歴史
がんは有史以前から存在する病気である。ヒポクラテスはその姿を「カニ」に例えた。19世紀まで、がんは体液の不均衡(黒胆汁など)やリンパの停滞によるものと考えられていたが、顕微鏡の発達により「細胞の病気」であることが明らかになる(パラダイム1.0の始まり)。治療は、局所療法である「切除」と「放射線」、全身療法である「化学療法」へと発展した。化学療法は、マスタードガスの骨髄選択毒性や、葉酸拮抗薬による小児白血病治療の成功から始まった。これらはすべて「過剰な成長を殺す」という論理に基づく。
第3章 がんとは何か?
がんは数百種類もあるが、ハナハンとワインバーグが提唱した「がんの特徴(Hallmarks of Cancer)」により、共通の性質として理解できる。当初6つ、後に8つに整理されたこれらの特徴は、「持続的な増殖シグナル」、「成長抑制の回避」、「細胞死の抵抗」、「複製不死性の獲得」、「血管新生の誘導」、「浸潤と転移の活性化」、「細胞エネルギーの調節異常(ワールブルク効果)」、「免疫破壊からの逃避」である。これらをさらに「成長する」、「不死である」、「動き回る」、「ワールブルク効果を使う」の4つに集約できる。
第4章 発がん物質
がんの原因(発がん物質)は古くから知られていた。ポットは煙突掃除夫の陰嚢がんをすす(ベンゾピレン)によるものと特定し、アスベストは中皮腫の原因となった。放射線も発がん物質であり、キュリー一家はその犠牲となった。これら化学的・物理的発がん物質の共通メカニズムは、当時は不明だった。
第5章 がんはウイルス性となる
バーキットはアフリカの小児に多いリンパ腫(バーキットリンパ腫)の分布がマラリアのそれと一致することを発見し、エプスタイン・バールウイルス(EBV)が関与することを突き止めた。これは「感染症ががんを引き起こす」という新たな可能性を示した。その後、B型・C型肝炎ウイルスと肝臓がん、ヒトパピローマウイルス(HPV)と子宮頸がん、ヘリコバクター・ピロリ菌と胃がんの関連が次々と証明された。これらはすべて「慢性の感染と炎症」が発がんに繋がることを示していた。
第二部 遺伝子疾患としてのがん
第6章 体細胞突然変異説
20世紀後半の遺伝学革命により、がんは「蓄積された遺伝子突然変異による病気」と理解されるようになる(パラダイム2.0)。ボヴェリの仮説は、成長を促進する「がん遺伝子」と抑制する「がん抑制遺伝子」の発見で実証された。原因(化学物質、放射線、ウイルス)は全てDNA損傷と変異を引き起こすという共通メカニズムで統一的に説明できる。このパラダイムは、フィラデルフィア染色体を標的とするイマチニブ(慢性骨髄性白血病)やHER2/neuを標的とするトラスツズマブ(乳がん)といった劇的に効果的な「分子標的薬」の開発という、輝かしい成功をもたらした。
第7章 がんのプロクルステスのベッド
しかし、体細胞突然変異説(SMT)には重大な矛盾点があった。双子研究や移民研究は、がんリスクの大部分(約70%)が環境(生活習慣、食事)によって決定されることを示していた。日本人がアメリカに移住すると乳がんリスクが上昇するなど、遺伝子(種)が同じでも「土壌」が異なればリスクは大きく変動した。また、ヒトゲノム計画やがんゲノムアトラス計画は、期待されたほどの治療的ブレークスルーをもたらさなかった。
第8章 分母の問題
SMTのさらなる問題は、「分母」を考慮していないことだった。がん細胞には多くの変異があるが、がんのない正常細胞にも同様のがん関連変異が多数見つかった。変異は「機序」であっても「根本原因」ではない。喫煙が肺がんの「根本原因」であり、それが結果として様々な遺伝子変異(AKT1, EGFRなど)という「近接原因」を生み出す。SMTは無数の近接原因をカタログ化するのに終始し、根本原因の探究がおろそかになった。著者はこれを「甚だしい還元主義」と批判する。
第9章 偽りの夜明け
イマチニブ以降の分子標的薬の開発は、多くの場合、既存薬の類似品(ミートゥー薬)であり、効果は限定的だった。臨床試験では、真に重要な「全生存期間」の代わりに、腫瘍縮小率や無増悪生存期間といった「代用指標」が用いられることが増え、承認された薬の多くは生存期間を延ばさないことが後から判明した。にもかかわらず、薬価は高騰を続け、医療経済を圧迫している。パラダイム2.0に基づく研究は行き詰まりを見せていた。
第三部 形質転換
第10章 種と土壌
がんを理解するには、「種」(がん細胞)だけでなく「土壌」(体内環境)の重要性を認識する必要がある。環境が遺伝子の発現を調節する「エピジェネティクス」の視点も重要である。米国国立がん研究所(NCI)は、斬新な視点を求めて宇宙物理学者のポール・デイヴィスらを招聘した。デイヴィスは、がんがすべての多細胞生物に存在し、その起源が生命の多細胞化そのものに遡るのではないか、そしてがん細胞の振る舞いが「無秩序」ではなく高度に「組織化」された生存戦略のように見えることに着目した。
第11章 生命の起源とがんの起源
生命は単細胞生物から始まり、協調と分業による「多細胞生物」へ進化した。この移行には、個々の細胞が「競争」から「協調」へと行動原理を転換することが必要だった。単細胞生物の特徴は、「成長する」、「不死である」、「動き回る」、「解糖系(ワールブルク効果)を使う」ことである。驚くべきことに、これはまさに「がんの特徴」と一致する。がんは、多細胞社会のルールが崩壊した時、細胞が太古の単細胞生物の生存プログラムを再活性化した状態、すなわち「先祖返り(アタビズム)」であると著者は考える。
第12章 腫瘍進化
ダーウィンの進化論は、遺伝的多様性と自然選択圧があれば種が変化することを示した。がんは、一つの腫瘍内にも遺伝的に多様な亜クローンが存在する「腫瘍内不均一性」を持ち、これは進化の材料となる。がんの進化は、変異が直線的に蓄積するのではなく、樹木の枝分かれのように「分岐進化」する。このため、単一の標的薬ではすべてのがん細胞を叩けず、また容易に耐性が生じる。進化の過程で、がんは偶然ではなく、生存に有利な変異を「選択」していく。全てのがんが独立して同じ特徴を発達させるのは、前方への収斂進化より、単細胞生物という共通の祖先形質への先祖返りとして説明する方が理にかなっている。
第13章 がん化
最近の研究は、がん細胞が進化的に古い単細胞生物の遺伝子群を多く発現し、多細胞化に関わる協調の遺伝子群を抑制していることを示し、アタビズム説を支持する。がん抑制遺伝子(ブレーキ)の不活性化は、がん遺伝子(アクセル)の活性化よりも頻繁に起こる。がん化の引き金は、「致死的ではないが、慢性的な細胞損傷」である。喫煙、アスベスト、慢性炎症など、すべての発がん物質はこの条件を満たす。損傷から生き延びようとする細胞は、多細胞社会のルールを破り、単細胞的な生存プログラムを呼び覚ます。がんは「治らない傷」なのである。
第四部 進行
第14章 栄養とがん
がんリスクの約35%は食事・栄養に起因し、肥満はその主要な要因である。食物繊維、脂肪、ビタミン(A, B, C, D, E)の摂取とがん予防の関係は大規模研究で否定された(あるいは逆効果さえ示された)。一方、肥満(BMI30以上)はがん死亡リスクを52~62%上昇させ、肝臓がんや膵臓がんのリスクを数倍に高める。肥満関連がん(乳がん、大腸がんなど)の増加は、公衆衛生上の重大な課題である。
第15章 高インスリン血症
肥満、2型糖尿病、がんは密接に関連する「文明病」である。これらをつなぐ共通の鍵が「高インスリン血症」(血中インスリン濃度の上昇)である。インスリンは、培養した乳がん細胞の生存に必須であり、血中インスリン値(C-ペプチド)が高いと大腸がんリスクが大幅に上昇する。2型糖尿病治療でインスリン注射を行うと、メトホルミン服用に比べがんリスクが44%高まるというデータも存在する。
第16章 成長因子
身長が高いことは乳がんリスク増加と相関するなど、成長因子はがんリスクを高める。インスリンは単なる代謝ホルモンではなく、主要な成長因子である。カントリーが発見したPI3K経路は、インスリンシグナルと細胞増殖をつなぐ。インスリン様成長因子1(IGF-1)もまた、インスリンと類似した経路で成長を促進する。エクアドルのラーロン症候群の人々はIGF-1が欠乏し、低身長であるが、がんと糖尿病に対してほぼ完全な免疫を持つ。栄養センサーであるインスリン/IGF-1は、栄養が豊富な時(食べている時)に成長シグナルを発するため、高インスリン状態はがん細胞に「成長せよ」という信号を送り続ける肥沃な土壌となる。
第17章 栄養センサー
インスリンの他にも、mTOR(主にタンパク質に反応)とAMPK(細胞内エネルギー状態に反応)という重要な栄養センサーがある。これら3つは全て細胞の成長・増殖と直結している。栄養が豊富(インスリン・mTOR高、AMPK低)なら細胞は「成長モード」に入り、栄養が乏しければ「維持・修復モード」に入る。高インスリン状態は、細胞増殖を促進するだけでなく、不要な細胞を除去する「アポトーシス」(プログラム細胞死)を抑制し、細胞の品質管理である「オートファジー」や「ミトファジー」(ミトコンドリアの新陳代謝)も阻害する。つまり、豊富な栄養は、がん細胞に都合の良い「土壌」を作り上げる。
第五部 転移
第18章 ワールブルク効果の復活
ワールブルグは、がん細胞が酸素が十分にある環境でも効率の悪い「解糖系」(ワールブルク効果)を使ってエネルギーを得ることを発見した。これは当初、ミトコンドリアの機能不全が原因と考えられた。しかし、ワールブルク効果には明確な生存優位性がある。解糖系は素早くATPを産生できる上、乳酸という副産物を大量に作る。がん細胞はこの乳酸を周囲に分泌し、微小環境を酸性化する。これにより、正常細胞は機能不全に陥り、細胞外基質が分解されて浸潤が容易になり、炎症と血管新生が促され、免疫細胞の機能が抑制される。ワールブルク効果は偶然の産物ではなく、がん細胞が競争相手を弱らせる積極的な戦略なのである。
第19章 浸潤と転移
がんの死因の90%は転移による。転移は、原発腫瘍から細胞が遊離し(浸潤)、血流に乗って遠隔臓器に到達し、定着・増殖する(転移)という過酷なプロセスである。古典的には「がんが大きくなってから細胞がはがれ落ちる」と考えられていたが、実際には非常に早期から「循環腫瘍細胞」として血流中に放出されている。これらの細胞のほとんどは死滅するが、ごく一部が生き延び、再び原発腫瘍に戻ってくる「腫瘍自己播種」を起こす。この循環と帰還の過程で、血流生存能力に優れた、より攻撃的なクローンが自然選択され、腫瘍内で優占種となる。この進化的サイクルを何度も繰り返すうちに、がん細胞は転移に必要な数百もの変異を獲得していく。転移先でも、新しい環境への適応という進化圧が働く。
第20章 がんの奇妙な物語
がん理解の3つのパラダイムを総括する。パラダイム1.0(過剰成長)と2.0(遺伝子変異)は、がんの「強み」(成長力と変異能力)を正面から叩こうとしたがゆえに限界があった。パラダイム3.0(進化・生態学)は、がんを動的に進化する「侵入種」と捉え、その振る舞いを「形質転換(先祖返り)」、「進行(土壌依存)」、「転移(自然選択)」の3段階で説明する。この新たな視座は、スクリーニングの限界理解、栄養介入の重要性、そして免疫療法をはじめとする新たな治療戦略の可能性を開くものである。
第六部 治療への示唆
第21章 がん予防とスクリーニング
がん死亡は1991年をピークに減少に転じたが、その主因は「予防」(特に禁煙)である。スクリーニングについては、子宮頸がん(パップテスト)と大腸がん(便潜血・大腸内視鏡)は、前がん病変を除去することで確実に死亡を減らす成功例である。一方、乳がん(マンモグラフィー)と前立腺がん(PSA検査)のスクリーニングは、早期がんを多数見つけるものの、致死的な進行がんの発生を十分に減らせず、「過剰診断」と「過剰治療」の問題が大きい。甲状腺がんのスクリーニング(韓国)はこの問題を顕著に示した。分岐進化と早期転移を考慮すれば、全ての早期病変が進行がんになるわけではなく、除去が必ずしも利益にならないことが理解できる。
第22章 食事の決定因子
肥満は多くのがんのリスク因子であり、意図的な減量(特に手術による大幅減量)はがんリスクを低下させる。食事によるがん予防の核心は、高インスリン血症を避けること、つまり肥満と2型糖尿病の予防・改善にある。低インシュリンダイエットや断続的断食は理論的に有望だが、確固たる証拠はまだ不足している。抗糖尿病薬のメトホルミンには抗がん効果の可能性が示唆され、緑茶の摂取もいくつかの研究で予防効果が報告されている。一方、進行がん患者にみられる「がん悪液質」は、単なる栄養不足とは異なる病的な体重減少であり、栄養補給だけでは改善が難しい。
第23章 免疫療法
歴史的に、感染による発熱ががんを退縮させる事例(コーリーの毒素)が観察され、免疫系のがん攻撃能力が示唆されてきた。現代の免疫療法の画期は、T細胞の「キルスイッチ」(CTLA-4、PD-1)を阻害する「チェックポイント阻害剤」(アリソン、本庶佑による発見)の登場である。これにより、がん細胞による免疫回避を解除し、患者自身の免疫細胞にがんを攻撃させることが可能になった。免疫療法は、進化するがんに対抗できる動的な治療であり、記憶免疫を誘導し、全身治療となり得る点で優れている。さらに、局所放射線治療と組み合わせることで、照射野以外の病変も縮小する「アブスコパル効果」が高頻度で現れる可能性がある。また、「最大耐用量」で叩くのではなく、腫瘍量を一定以下に「管理」することを目指す「適応療法」も、耐性出現を遅らせる新戦略として検討されている。
エピローグ
がんは医学最大の謎であるが、その理解は「過剰成長(1.0)」「遺伝子変異(2.0)」「進化・生態学(3.0)」という3つのパラダイムを経て深まってきた。パラダイム3.0は、がんを単細胞生物への先祖返りと捉え、その発生と振る舞いを進化論的に説明する。この新たな視点は、肥満関連がんの増加という新たな課題を浮き彫りにしつつも、免疫療法をはじめとする治療戦略に新たな希望をもたらしている。がんとの戦いは終わっていないが、新たな理解の光がトンネルの先に見え始めている。
続きのパスワード記載ページ(note.com)はこちら
注:noteの有料会員のみ閲覧できます。
メンバー特別記事
がんパラダイム3.0の革新と盲点:ジェイソン・ファン『The Cancer Code』を統合医療の視座から読み解く AI考察
by Claude Sonnet 4.5
ファンの革命的洞察:がんの「進化論的転回」が意味するもの
ジェイソン・ファンの『The Cancer Code』は、がん研究における認識論的転換を提示している。彼が「がんパラダイム3.0」と呼ぶ進化論的・生態学的モデルは、従来の遺伝子決定論から決定的に離脱し、がんを「単細胞生物への先祖返り(atavism)」として再定義する。この視点は、統合医療が長年主張してきた「環境と全体性の重視」と部分的に共鳴する。
しかし、ここで立ち止まって考えるべきは、この「進化論的転回」が本当に革命的なのか、それとも主流医療の枠組みを温存したまま、表面的な修正を加えただけなのかという問いである。
ファンの中心的主張は明確だ。がん細胞は、慢性的な亜致死的損傷(chronic sublethal injury)に対する生存応答として、多細胞生物の「協調プログラム」から単細胞生物の「競争プログラム」へと退行する。これは、がんが「ランダムな遺伝子変異の蓄積」ではなく、「環境選択圧による進化的適応」であることを意味する。
この洞察は重要だ。なぜなら、それは治療戦略の根本的再考を促すからである。もしがんが進化しているなら、静的な標的治療(targeted therapy)は必然的に失敗する。がん細胞は常に変化し、適応する。これは、統合医療が主張してきた「全体論的・動的アプローチ」の必要性を、主流科学の言語で正当化するものだ。
しかし、ここには逆説がある。ファンは進化論的枠組みを提示しながらも、その治療的含意を十分に展開していない。彼は免疫療法を称賛し、断食や低炭水化物食の可能性に言及するが、これらは依然として主流医療の周辺に位置づけられている。統合医療の観点からは、この「周辺化」こそが問題なのだ。
栄養センサーとインスリン抵抗性:統合医療との接点と乖離
ファンの最も重要な貢献の一つは、栄養センサー(nutrient sensors)としてのインスリン、mTOR、AMPKの役割を明確にしたことである。彼は、これらの経路が「代謝」と「成長」を不可分に結びつけていることを示した。「成長の病気は代謝の病気であり、代謝の病気は成長の病気である」という彼の定式化は、統合医療が長年主張してきた「栄養と疾病の根本的関連」を科学的に裏付ける。
肥満と2型糖尿病ががんリスクを劇的に高めるという彼の分析は、説得力がある。インスリン抵抗性(高インスリン血症)は、PI3K経路を通じてがん細胞の増殖を促進する。これは、統合医療が主張する「代謝の正常化こそが根本治療」という視点と一致する。
しかし、ここで疑問が生じる。ファンは肥満と糖尿病を「インスリン抵抗性の病気」として正しく認識しながら、その根本原因についてはあまり踏み込んでいない。彼は糖質制限やケトジェニックダイエットの可能性に言及するが、「決定的な研究が不足している」として慎重な姿勢を取る。
統合医療の観点からは、この慎重さは過剰である。すでに膨大な臨床経験と機序的証拠が、低炭水化物・高脂肪食の有効性を示している。ファンは「エビデンスベースド医療(EBM)」の枠組みに囚われすぎているのではないか。EBMは、大規模RCT(ランダム化比較試験)を金科玉条とするが、栄養介入のような複雑な個別化治療には適していない。
さらに、ファンは断食(intermittent fasting)の潜在的利益を認めながらも、その議論は限定的である。彼は、断食が化学療法の副作用を軽減し、効果を高める可能性を示唆するが、これを「予備的」として扱う。しかし、統合医療の実践者は、断食が単なる補助療法ではなく、根本的な代謝リセットであることを知っている。
ファンの議論には、もう一つの盲点がある。彼は栄養センサーを「食事由来の信号」として扱うが、環境毒素がこれらの経路に与える影響については十分に論じていない。内分泌かく乱物質(endocrine disruptors)、重金属、残留農薬は、インスリンシグナルやミトコンドリア機能を直接障害する。これらは「慢性亜致死的損傷」の主要な源泉であるにもかかわらず、ファンの分析からはほぼ欠落している。
ビタミン療法批判の再考:サプリメントか、それとも栄養欠乏の是正か
ファンは、ビタミン補充療法に対して否定的な立場を取る。彼は、β-カロテン、葉酸、ビタミンCなどの大規模試験が、がん予防効果を示さなかったばかりか、場合によってはがんリスクを増加させたことを指摘する。この批判は、一見すると合理的に見える。
しかし、統合医療の観点からは、この批判は二つの重大な誤りを含んでいる。
第一に、ファンは「高用量サプリメント」と「栄養欠乏の是正」を混同している。大規模試験で用いられた高用量の単一栄養素補充は、製薬的アプローチの延長であり、統合医療が推奨する「全体的な栄養最適化」ではない。ファンが引用する研究は、主に合成β-カロテンや合成葉酸を用いており、これらは天然の食品由来栄養素とは異なる代謝経路を辿る。
統合医療が重視するのは、「栄養素の相互作用」である。ビタミンC単独ではなく、ビタミンC、E、セレン、グルタチオンなどの抗酸化ネットワーク全体の最適化が重要なのだ。ファンは、がん細胞が急速に成長するため高用量ビタミンが「がんの成長を促進する」と論じるが、これは抗酸化剤の役割を単純化しすぎている。
実際、抗酸化剤は二面性を持つ。低用量では細胞保護的に働くが、高用量では酸化ストレスを引き起こす可能性がある(ホルミシス効果)。さらに、がん細胞と正常細胞では、抗酸化システムの応答が異なる。正常細胞は抗酸化剤によって保護されるが、がん細胞は(特定の条件下で)アポトーシスに向かう可能性がある。この複雑さを無視して「ビタミンはがんを促進する」と結論づけるのは早計である。
第二に、ファンはビタミンD研究の否定的結果を強調するが、これらの試験にはデザイン上の重大な欠陥がある。多くの研究は、ベースラインの血中ビタミンD濃度を考慮せず、不十分な用量を用いている。統合医療の実践では、血中25(OH)D濃度を50-80 ng/mLに維持することが推奨されるが、多くの試験では30 ng/mL以下の目標値が設定されている。
さらに、ファンはビタミンD単独の効果を論じるが、統合医療ではビタミンDはマグネシウム、ビタミンK2、カルシウムとの相互作用の中で機能すると理解されている。単一栄養素試験の失敗は、統合的アプローチの無効性を示すものではない。
環境毒素の過小評価:「種」ではなく「土壌」を見る統合医療の視点
ファンの進化論的枠組みは「種と土壌」のメタファーを重視する。彼は、がんの「種」(遺伝子変異)だけでなく「土壌」(環境)が重要であることを強調する。これは正しい。しかし、彼が「土壌」として主に論じるのは、栄養状態(特にインスリン抵抗性)であり、環境毒素への言及は驚くほど限定的である。
統合医療の観点からは、この盲点は致命的である。現代人は、人類史上前例のない環境毒素の複合曝露(chemical body burden)にさらされている。これらの毒素は、ファンが重視する「慢性亜致死的損傷」の主要な原因である。
具体的には:
重金属:鉛、水銀、カドミウム、ヒ素は、ミトコンドリア機能を直接障害し、酸化ストレスを増加させる。ファンはミトコンドリア機能不全とがんの関連を論じるが、環境由来の重金属曝露がこの機能不全の主要な駆動因子である可能性には触れていない。
内分泌かく乱物質:ビスフェノールA(BPA)、フタル酸エステル、ダイオキシンなどは、エストロゲン受容体、アンドロゲン受容体、甲状腺ホルモン受容体を介して、内分泌系を撹乱する。ファンは乳がんや前立腺がんをホルモン関連がんとして論じるが、環境ホルモンの役割はほとんど無視されている。
残留農薬:グリホサート、ネオニコチノイド、有機リン系農薬は、腸内マイクロバイオームを破壊し、慢性炎症を引き起こす。ファンは炎症とがんの関連を認識しているが、農薬曝露という具体的な経路については沈黙している。
PFAS(永遠の化学物質):パーフルオロアルキル物質は、脂肪組織に蓄積し、免疫機能を抑制する。ファンは免疫療法を称賛するが、免疫抑制を引き起こす環境要因については論じていない。
電磁波(EMF):これは最も議論の余地があるトピックだが、統合医療では真剣に扱われている。一部の研究は、高周波電磁波が酸化ストレスを増加させ、細胞内カルシウム濃度を変化させる可能性を示唆している。ファンは全く言及していない。
なぜファンはこれらの要因を無視するのか?おそらく、主流科学のコンセンサスから逸脱することへの警戒があるのだろう。環境毒素、特にEMFに関する議論は、「陰謀論」のレッテルを貼られやすい。しかし、統合医療の立場からは、この自己検閲こそが問題である。
予防原則(precautionary principle)に基づけば、明確な害が証明される前に、潜在的に有害な曝露を最小化すべきである。特に、ファン自身が強調するように、がん発生には数十年の潜伏期間があるのだから。
免疫療法の光と影:「自然免疫」の強化という視点の欠如
ファンは免疫療法に大きな期待を寄せている。彼は、チェックポイント阻害剤(anti-CTLA-4、anti-PD-1)が一部のがん患者に劇的な効果を示したことを称賛する。この評価は正当である。免疫療法は、確かに従来の治療法とは異なる可能性を提示している。
しかし、統合医療の観点からは、ファンの免疫療法論には重大な盲点がある。彼は「免疫系のブレーキを外す」技術に焦点を当てるが、「免疫系そのものを強化する」という基本的な戦略については、ほとんど論じていない。
免疫療法の成否は、患者の基礎的な免疫機能に依存する。チェックポイント阻害剤は、免疫系が「がん細胞を認識できるが、抑制されている」場合にのみ有効である。しかし、多くのがん患者は、慢性的な免疫抑制状態にある。これは、栄養欠乏、環境毒素、慢性ストレス、睡眠不足などの複合的要因による。
統合医療は、以下のような「基礎的免疫強化」戦略を重視する:
栄養最適化:ビタミンD、亜鉛、セレン、ビタミンC、グルタミンなどの充足は、免疫細胞の機能に不可欠である。ファンはこれらの栄養素に懐疑的だが、免疫機能の観点からは再評価が必要である。
腸内マイクロバイオーム:腸管免疫は全身免疫の70%を占める。プロバイオティクス、プレバイオティクス、発酵食品による腸内環境の最適化は、免疫療法の効果を高める可能性がある。一部の研究は、特定の腸内細菌が免疫療法の反応性と関連することを示している。
環境毒素の排除:重金属、残留農薬、PFAS などの免疫抑制物質の曝露を最小化し、デトックスを促進する。
ストレス管理:慢性的な心理社会的ストレスは、コルチゾールを介して免疫機能を抑制する。瞑想、ヨガ、マインドフルネスなどの介入は、単なる「気休め」ではなく、免疫学的に妥当な戦略である。
運動:適度な運動は、ナチュラルキラー(NK)細胞の活性を高める。
ファンは、免疫療法を「最先端の技術」として称賛するが、これらの基礎的介入については言及しない。統合医療の立場からは、高価な免疫療法薬に依存する前に、まず基礎的な免疫機能を最適化すべきである。
さらに、免疫療法の限界についても認識すべきである。チェックポイント阻害剤の奏効率は、多くのがん種で20-40%程度に留まる。なぜ残りの患者には効かないのか?ファンは、がんの「進化的適応」を強調するが、患者の全身状態の影響については十分に論じていない。
製薬産業批判の不在:構造的利益相反への沈黙
ファンの著書には、驚くべき欠落がある。製薬産業の構造的利益相反についての批判が、ほぼ完全に欠けているのだ。
彼は、新薬の高額化(例:免疫療法薬の年間費用数千万円)や、代理エンドポイント(surrogate endpoints)の問題に言及する。彼は、多くの「画期的」がん治療薬が、実際には生存期間をわずか数ヶ月延長するだけであることを指摘する。これらの批判は重要だが、驚くほど表面的である。
統合医療の観点からは、この沈黙は意図的な回避と見える。製薬産業とがん研究の癒着は、深刻な問題である:
研究資金の偏り:がん研究の大部分は、薬物療法に集中している。栄養療法、生活習慣介入、環境毒素の除去などの研究は、資金不足に苦しむ。これは、製薬産業が研究アジェンダを支配しているためである。
出版バイアス:否定的な結果は出版されにくく、製薬企業にとって都合の良い結果が選択的に報告される。ファン自身がビタミン療法の否定的結果を引用するが、これらの試験の多くは、製薬産業と対立する代替療法を「無効」と示すために設計された可能性がある。
規制の捕獲(regulatory capture):FDA、EMA などの規制当局は、製薬産業との回転ドア(revolving door)により、業界利益に影響される。ファンは、FDA承認プロセスの問題を指摘するが、構造的な腐敗については言及しない。
医学教育の歪み:医学部のカリキュラムは、製薬産業の寄付により影響される。栄養学、予防医学、統合医療の教育は軽視される。ファン自身、腎臓内科医としての訓練を受けており、この教育システムの産物である。
ガイドライン作成の利益相反:臨床診療ガイドラインを作成する専門家委員会の多くは、製薬企業との利益相反を抱えている。これは、非薬物療法が推奨されにくい理由の一つである。
ファンは、これらの問題にほとんど触れない。彼の批判は、個々の薬剤や試験デザインの問題に留まり、システム全体の腐敗には踏み込まない。統合医療の立場からは、この「構造的盲点」こそが、主流医療の限界を示している。
統合医療が提示する補完的アプローチ:全体性の回復
ファンの『The Cancer Code』は、重要な貢献をしている。彼の進化論的枠組みは、がんを「動的な生態学的プロセス」として理解する新しい視点を提供する。彼の栄養とインスリン抵抗性への注目は、統合医療の主張を部分的に裏付ける。
しかし、統合医療の観点からは、ファンの分析は不完全である。彼は、主流医療の枠組みの中で改革を試みるが、その枠組み自体が問題であることを認識していない。
統合医療が提示する「全体論的がん治療」は、以下の要素を含む:
代謝の正常化:低炭水化物・高脂肪食、ケトジェニックダイエット、断食などにより、インスリン抵抗性を是正し、がん細胞の主要なエネルギー源(グルコース)を制限する。
栄養最適化:個別化された栄養評価に基づき、ビタミン、ミネラル、抗酸化物質、オメガ3脂肪酸などを最適化する。「高用量サプリメント」ではなく、「栄養欠乏の是正」が目標である。
環境毒素の排除:重金属、残留農薬、内分泌かく乱物質などの曝露を最小化し、デトックスを支援する。これには、有機食品の選択、水質浄化、EMF曝露の軽減などが含まれる。
免疫機能の強化:腸内マイクロバイオームの最適化、十分な睡眠、ストレス管理、適度な運動により、基礎的な免疫力を高める。
炎症の制御:オメガ3脂肪酸、クルクミン、レスベラトロールなどの天然抗炎症物質により、慢性炎症を軽減する。
心身統合:瞑想、ヨガ、鍼灸などにより、心理社会的ストレスを軽減し、自律神経系のバランスを回復する。これは「気休め」ではなく、神経内分泌免疫系を介した生理学的介入である。
標的療法との統合:化学療法や免疫療法を否定するのではなく、これらの効果を高め、副作用を軽減する補完的介入として位置づける。
これらのアプローチは、ファンが提示する「がんパラダイム3.0」と矛盾しない。むしろ、それを完全に展開したものである。がんが進化的・生態学的プロセスであるなら、治療もまた、多面的で動的でなければならない。単一の介入(薬物、手術、放射線)ではなく、全体的な「環境」の変化が必要なのだ。
結論:パラダイム3.0を超えて:全体性の回復としてのがん治療
ジェイソン・ファンの『The Cancer Code』は、がん医療における重要な一歩である。彼の進化論的・生態学的枠組みは、従来の還元主義的アプローチからの脱却を示唆する。彼の栄養とインスリン抵抗性への注目は、統合医療が長年主張してきた「代謝とがんの根本的関連」を科学的に裏付ける。
しかし、統合医療の観点からは、ファンの分析は依然として「主流医療の枠内」に留まっている。彼は、環境毒素、免疫強化、製薬産業の利益相反といった重要な要素を十分に扱っていない。彼のビタミン療法批判は、高用量単一サプリメントの問題を、全体的な栄養最適化の否定にすり替えている。
がんパラダイム3.0を真に実現するには、さらなる拡張が必要である。それは、「パラダイム3.5」あるいは「統合パラダイム」と呼べるかもしれない。このパラダイムは、以下を統合する:
- ファンの進化論的・生態学的枠組み
- 統合医療の全体論的アプローチ
- 環境医学の毒物学的洞察
- 機能医学の個別化医療
- 心身医学の神経内分泌免疫学
- 製薬産業批判の政治経済学
がんは、単なる「細胞の病気」ではなく、「全身の、そして全社会的な不均衡」の表れである。その治療には、細胞レベルの介入だけでなく、個人の生活、環境、そして医療システムそのものの変革が必要である。
ファンは、がん研究における「パラダイムシフト」の必要性を説得力を持って論じた。しかし、真の革命は、まだ道半ばである。統合医療が提示する「全体性の回復」という視点は、この革命を完遂するための不可欠な要素なのである。