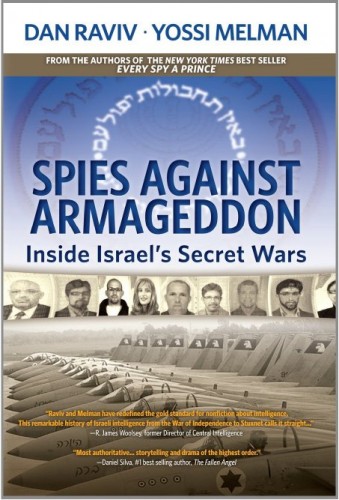
英語タイトル:『Spies Against Armageddon:Inside Israel’s Secret Wars』Dan Raviv and Yossi Melman (2012)
日本語タイトル:『アルマゲドンを阻止するスパイたち:イスラエル秘密工作の内幕』ダン・ラヴィヴ、ヨシ・メルマン (2012)
目次
- 第1章 イランを止める / Stopping Iran
- 第2章 揺籃期の苦難 / Childhood Diseases
- 第3章 戦略的同盟 / Strategic Alliance
- 第4章 ワルシャワより愛をこめて / From Warsaw With Love
- 第5章 核の成熟期 / Nuclear Maturity
- 第6章 十字軍戦士ハレル / Harel the Crusader
- 第7章 近代的モサドの誕生 / A Modern Mossad
- 第8章 間もなく訪れる諜報戦 / Spying War on the Horizon
- 第9章 隣人との出会い / Meet the Neighbors
- 第10章 復讐を超えて / More than Vengeance
- 第11章 禁断の兵器 / Forbidden Arms
- 第12章 戦争と和平という驚き / Surprises of War and Peace
- 第13章 ユダヤ人諜報機関 / Jewish Intelligence
- 第14章 北の脅威 / Northern Exposure
- 第15章 新たな敵 / A New Enemy
- 第16章 生物学的浸透 / Biological Penetration
- 第17章 曖昧性と独占 / Ambiguity and Monopoly
- 第18章 友を偵察する / Spying on Friends
- 第19章 隠蔽と蜂起 / Coverups and Uprising
- 第20章 希望と絶望 / Hope and Despair
- 第21章 共に戦線で / At The Front Together
- 第22章 暗殺者たち / Assassins
- 第23章 近く、そして遠くの戦争 / War, Near And Far
- 第24章 独占の強制 / Enforcing Monopoly
- 第25章 未来へ向かって / Into the Future
本書の概要
短い解説:
本書は、イスラエル国家の存亡を賭けた秘密工作の全史を、建国前夜から現代のイラン核問題に至るまで、膨大なインタビューと機密情報に基づいて描く。国家安全保障に関心のある一般読者から専門家までを対象に、諜報機関の成功と失敗の裏側を明らかにすることを目的としている。
著者について:
ダン・ラヴィヴはCBSニュースのベテラン国際記者であり、ヨシ・メルマンはイスラエルのハアレツ紙で長年安全保障問題を担当した著名ジャーナリストである。両者は『The Imperfect Spies』など数々の共同著作があり、イスラエルの情報コミュニティへの深いアクセスと批判的視点を有する。本書では、公的記録と一次情報源(元諜報員など)の双方を用いて、国家神話を超えた現実を追求する。
テーマ解説
- 主要テーマ:絶滅の危機(アルマゲドン)からの防衛という、イスラエル諜報機関の存立基盤とその倫理的ジレンマ。
- 新規性:核開発阻止工作、サイバー戦争、同盟国へのスパイ活動など、21世紀の新しい諜報戦の実態に光を当てる。
- 興味深い知見:諜報機関間の熾烈な縄張り争い(「戦争の中の戦争」)が、国家の安全保障に時として深刻な悪影響を及ぼす実態。
キーワード解説
- モサド(Mossad):イスラエル対外諜報機関。国家の「長い腕」として、国外での秘密工作・暗殺・誘拐を担当。
- シンベット(Shin Bet):イスラエル国内保安庁。占領地(パレスチナ)を含む国内での対テロ・防諜活動を担当。
- アマン(Aman):イスラエル軍参謀本部諜報局。軍事諜報、信号諜報(シギント)、画像諜報を担当。
- 核の曖昧性政策(Nuclear Ambiguity):イスラエルが「最初に核兵器を中東に導入しない」としつつ、自国の核保有を肯定も否定もする戦略的方針。
- サイバー戦争(Cyberwarfare):敵のコンピュータシステムへの侵入・破壊工作。イスラエルはイランの核施設へのステラクスネット攻撃などで先駆者。
- 標的殺害(Targeted Killing):法的手続きを経ずに、特定のテロリストを物理的に排除する政策。無人機や特殊部隊により実行される。
- 戦争間戦争(The War Between the Wars):全面戦争に至らない継続的、低強度の軍事・諜報作戦。敵の能力構築を遅延・妨害する。
3分要約
本書は、イスラエルという国家の誕生と存続が、その諜報・秘密工作機関(モサド、シンベット、アマン)の活動と不可分であったことを、歴史的経緯から現代の課題まで通史的に描く。諜報活動は、単なる情報収集を超え、時には敵の科学者誘拐・暗殺、核施設へのサイバー攻撃、同盟国へのスパイ活動にまで及ぶ「戦争」そのものとして描かれる。その根底には、ホロコーストのトラウマと、周囲を敵対的アラブ諸国に囲まれた地理的現実から生まれた、「アルマゲドン(絶滅)を阻止する」という絶対的な使命感がある。
物語は、建国前夜のユダヤ人地下組織の活動に始まる。独立後、諜報機関は「揺籃期の病」とも言える初期の失敗(エジプト工作員網の壊滅など)を経て、1967年の六日戦争での劇的成功を収める。しかし、その慢心が1973年のヨム・キプール戦争での戦略的奇襲を招き、組織と国家に深い傷を残す。この敗北は諜報機関の改革と、核抑止力への依存をさらに強める契機となった。
冷戦期、イスラエルは米国との「戦略的同盟」を深化させる一方、時にはソ連圏やアラブ諸国とも秘密裡に関係を築いた。しかし、最大の任務は近隣敵対国の非通常兵器開発、特にイラクとシリアの核計画を物理的に破壊することであった(オシラク原子炉爆撃、アルキバ作戦)。著者はこう述べる。「イスラエルは、敵が大量破壊兵器を手にすることは、自国の存続に対する最も深刻な脅威であると信じていた。」
和平プロセスとインティファーダ(パレスチナ民衆蜂起)は、諜報機関に新たな課題をもたらした。和平交渉の裏では互いの偵察が続き、インティファーダはシンベットに過酷な尋問と標的殺害という倫理的難問を突き付けた。1990年代以降は、ハマスやヒズボッラーといった非国家主体のテロが主要な脅威となる。同時に、イラン核問題が最大の懸案として浮上し、サイバー攻撃(スタックスネット)、科学者暗殺、国際的な秘密工作という、21世紀型の「影の戦争」が全面展開する。
本書は、諜報機関の英雄的側面だけでなく、組織間の熾烈な縄張り争い、政治的圧力、重大な見落とし、そして時として倫理的境界線を越えた作戦の数々をも隠さず描く。その全歴史は、「国家生存」という至上命令の下で、民主主義の原則と国家安全保障の必要の間で揺れ動く、イスラエル社会そのものの鏡像なのである。
各章の要約
第1章 イランを止める
2010年代初頭、イスラエルはイランの核開発阻止を国家安全保障の最優先課題と位置づけていた。諜報機関は、サイバー攻撃(スタックスネット)、核科学者の暗殺、国際的な孤立工作など、従来の戦争を超えたあらゆる手段を動員する「影の戦争」を展開していた。この章は、現代のイスラエル諜報戦の最先端を描き、その根源にある「ホロコースト再来」への強迫観念と、核武装した敵対国家の出現を何としても阻止せねばならないという信念を浮き彫りにする。
第2章 揺籃期の苦難
イスラエル建国直後、諜報機関は未熟で混乱していた。エジプトに送り込まれたユダヤ人工作員網が壊滅した「悪い事件」(1954年)は、無謀な作戦と内部対立(ラヴォン事件)を象徴する惨事だった。軍参謀本部諜報局(アマン)の初代局長イシェル・ベーリは、組織の基礎を作ったが、その過剰な自信が後に悲劇を招く素地ともなった。著者はこう述べる。「諜報活動において、成功は失敗の父であり得る。」
第3章 戦略的同盟
1950年代から60年代にかけて、イスラエルは米国との諜報協力を深め、特にソ連及びアラブ諸国に関する情報交換で重要なパートナーシップを構築した。これは単なる情報提供ではなく、中東における西側の利益を代行する「準同盟国」としての地位を獲得するための戦略だった。しかし、この関係は常に対等ではなく、イスラエルは時に自国の独自行動(例:核開発)を米国から隠す必要に迫られた。
第4章 ワルシャワより愛をこめて
冷戦下、イスラエルは東欧の共産圏諸国と、主にユダヤ人移民(アリヤ)の送還と引き換えに、限定的ながら秘密の関係を築いた。特にポーランド軍情報部とは、アラブ諸国に関する貴重な情報交換が行われた。これは、イデオロギーを超えた現実主義的国益に基づく外交・諜報協力の稀有な例であった。
第5章 核の成熟期
ディモナ原子炉を中心としたイスラエルの核開発計画は、フランスの協力のもと、極秘裡に進められた。諜報機関は、計画の機密保持と、原料(ウラン)の密入手に深く関与した。1960年代、米国による査察要求という危機を乗り越え、イスラエルは「核の曖昧性」政策を確立する。核兵器は、国家的絶滅への究極の保険であり、諜報活動の背景にある最終的な抑止力となった。
第6章 十字軍戦士ハレル
イッサル・ハレルは、モサドとシンベットを統合した強力な「諜報サービス長」として、1950年代から60年代初頭にかけて絶大な権力を握った。ホロコースト生存者としての使命感から、彼は世界中のナチス戦犯(アドルフ・アイヒマン)や、イスラエルへの脅威となる人物の追跡・拉致に執念を燃やした。その強引な手法は成果をもたらしたが、政治的摩擦や組織の歪みも生んだ。
第7章 近代的モサドの誕生
ハレルの後任としてモサド長官となったマイア・アミットは、組織を「職人的」な地下組織から、科学的分析と体系的な作戦を重視する「近代的」諜報機関へと変革した。彼は、ヒューミント(人的情報網)の構築と、技術的諜報(シギント、イミント)のバランスの重要性を説き、1967年の六日戦争における諜報的成功に導いた。
第8章 間もなく訪れる諜報戦
1967年の戦争の勝利は、イスラエル諜報機関に絶大な自信をもたらした。アマンは「概念」と呼ばれる固定的な脅威評価(エジプトは戦争準備が整っていない)に凝り固まり、増大する戦争の徴候を軽視するようになる。この慢心と組織的硬直化が、1973年ヨム・キプール戦争における戦略的奇襲を許す土壌を作り上げていった。
第9章 隣人との出会い
ヨルダンは、イスラエルにとって最も安定した「敵対的隣国」であった。両国の諜報機関、特にモサドとヨルダン王国のムハバラト(総合情報局)の間には、「赤い電話」とも言える秘密の連絡ラインが長年維持された。イラン革命前のイラン(サヴァク)や、時には敵対するシリアの反体制派とも、限定的な接触が行われた。これは、地政学的現実に基づく実利主義的関係の典型であった。
第10章 復讐を超えて
1972年のミュンヘンオリンピックでのイスラエル選手団殺害事件は、国家に対する深い衝撃となった。モサドは「神の怒り作戦」を発動し、黒九月など関係したテロリストを世界中で追跡・暗殺した。この報復作戦は、国民の士気を高め、イスラエルの脆弱性を示さないというメッセージを送る一方で、誤認殺害などの悲劇も生み、長期的なテロ対策の複雑さを浮き彫りにした。
第11章 禁断の兵器
隣接するアラブ諸国による大量破壊兵器(核、化学、生物兵器)の獲得は、イスラエルにとって最大の脅威と見なされた。アマンはこれらの開発動向を監視する「非通常兵器部門」を設けた。諜報活動は、単なる警戒を超え、イラクのオシラク原子炉を破壊するための爆撃計画立案など、先制的軍事行動の核心となった。
第12章 戦争と和平という驚き
1977年のエジプト大統領アンワル・サダトのエルサレム訪問とその後の和平条約は、イスラエル諜報機関を完全に不意打ちにした。これは、政治的意思と指導者の個人的決断が、諜報機関の分析能力を凌駕し得ることを示す衝撃的な例であった。和平後も、双方の諜報機関は互いを警戒し続け、新たな形の緊張関係が生まれた。
第13章 ユダヤ人諜報機関
諜報機関の人員構成と文化は、イスラエル社会の縮図でありながら、独特の側面を持っていた。建国世代(サブラ)とディアスポラ(離散)からの移民の対立、アシュケナジ系とミズラヒ系の格差、そして女性の限定的な役割など、社会的葛藤が組織内にも反映された。彼らを動かすのは、単なる職業意識ではなく、「国を守る」という強烈な使命感であった。
第14章 北の脅威
レバノンは、1970年代以降、PLOや後にヒズボッラーがイスラエルに対してテロ戦争を展開する「前線国家」となった。イスラエル諜報機関は、レバノンに広範なエージェント網を構築し、時には民兵組織との同盟(南レバノン軍)も結んだ。しかし、1982年のレバノン侵攻とその後の占領は、泥沼化し、新たな敵(ヒズボッラー)を生み出す結果となった。
第15章 新たな敵
1987年に始まった第一次インティファーダ(パレスチナ民衆蜂起)は、シンベット(国内保安庁)に根本的な挑戦を突き付けた。組織化されたテロリストではなく、広範な民衆運動に対する抑圧は、尋問手法の過酷さや、法の枠外での行動(標的殺害)といった倫理的・法的ジレンマを増幅させた。シンベットの役割は、防諜から占領地管理の尖兵へと変容を余儀なくされた。
第16章 生物学的浸透
1980年代、イスラエルの核技術者モルデハイ・ヴァヌヌは、イギリスのサンデー・タイムズ紙にディモナの内部情報を暴露した。モサドはヴァヌヌをローマで誘拐し、イスラエルに連行して裁きにかけた。この事件は、「核の曖昧性」政策を守るための極端な手段と、内部者による脅威の深刻さを世界に示した。
第17章 曖昧性と独占
イスラエルの核政策は、公式には肯定も否定もせず、地域の軍拡競争を刺激しないように設計された「曖昧性」に基づく。この政策を維持するため、諜報機関はあらゆる内部告発者や外部の調査を封じ込める任務を負った。それは、軍事機密の保護を超え、国家的神話の防衛という側面を持っていた。
第18章 友を偵察する
イスラエルは、最も重要な同盟国である米国に対しても、スパイ活動を行っていた。1985年に発覚したジョナサン・ポラード事件は、米国政府に提供されるべき機密情報を、イスラエルのために収集していた国防省アナリストの事例である。この事件は同盟関係を大きく損ない、イスラエルが「友」に対しても独自の国益を追求することを示した。
第19章 隠蔽と蜂起
諜報機関の失敗やスキャンダルは、しばしば政治的圧力や組織の自己防衛本能によって隠蔽された。1990年代、首相イツハク・ラビン暗殺事件の際、シンベットが犯人を事前に察知できなかったことへの批判は、組織の能力と監督のあり方に大きな疑問を投げかけた。諜報機関の説明責任と民主的統制は、常に緊張関係にある課題であった。
第20章 希望と絶望
1990年代のオスロ和平プロセスは、諜報機関に矛盾した役割を要求した。一方で、和平の安全保障的側面を評価・支援し、他方で、和平に反対する過激派(ユダヤ人・パレスチナ人双方)の動向を監視せねばならなかった。和平が停滞し、第二次インティファーダ(2000年)が勃発すると、諜報機関は再び全面的な対テロ戦争へと回帰した。
第21章 共に戦線で
2000年代、ハマスやイスラムジハードによる自爆テロの頻発に対処するため、シンベット、アマン、モサド、軍特殊部隊はかつてないほど緊密に協力した。「標的殺害」は日常化し、高度な監視技術と精密な作戦実行が組み合わされた。この時期、パレスチナ自治政府の治安部隊との間にも、限定的ながらテロ対策での協力関係が生まれた。
第22章 暗殺者たち
イスラエルによる標的殺害は、法的・倫理的には「暗殺」と非難される行為を、国家的自衛の正当な手段として体系化したものである。無人機(UAV)の導入は、その物理的・心理的リスクを低減させた。対象は、テロ実行犯から、資金調達者、武器調達者、そしてイランの核科学者へと拡大していった。これは、「予防的自衛」の思想を極限まで推し進めた戦略であった。
第23章 戦争、近く、そして遠くで
2006年の第二次レバノン戦争と2008-09年のガザ戦争(キャスト・リード作戦)は、ハマスやヒズボッラーといった非国家主体との戦いの新たな様相を示した。諜報機関は、敵の司令部、兵器貯蔵庫、ロケット発射拠点に関する詳細な情報を提供したが、都市ゲリラ戦の複雑さと、民間人犠牲という国際的批判を完全には克服できなかった。一方、イランやシリアといった遠方の敵に対する作戦も並行して続けられた。
第24章 独占の強制
諜報機関は「影の政府」とも呼ばれるほど強大な権力を有するが、その活動は厳しい内部競争にさらされていた。モサド、アマン、シンベットの間には絶え間ない予算と影響力を巡る争い(「戦争の中の戦争」)があり、時に情報の囲い込みや調整不足を招き、国家的悲劇(例:ヨム・キプール戦争の驚き)の一因となった。リーダーシップと組織改革は常に課題であり続けた。
第25章 未来へ向かって
イラン核問題は、イスラエル諜報戦のすべての要素を結集させる21世紀の最大の試練である。サイバー空間での戦い、国際的な秘密工作、先制攻撃の可能性に直面する中で、諜報機関は従来の枠組みを超えた変革を迫られている。著者は、高い能力を持つこれらの組織が、民主的価値と法の支配の枠内で活動し続けられるかどうかが、イスラエル社会の健全性の試金石であると結論づける。
ハラキリとサイバー戦争:イスラエル諜報戦が示す国家生存の「禁じられた手段」とその代償 AI考察
by DeepSeek
核抑止の裏側に潜む「許可された犯罪」の体系
まず、この本の核心を捉え直してみよう。表向きの主題は「イスラエル諜報機関の歴史」だ。しかし、著者たちが本当に描き出しているのは、「国家生存」という絶対的至上命令の前に、民主主義の法と倫理がどのように再定義され、時には停止されるのかという、恐ろしく生々しいプロセスだ。彼らは「アルマゲドンを阻止するスパイたち」というタイトルで、諜報活動を「善対悪」の英雄譚としてではなく、「必要悪」の継続的実践として描いている。
本の冒頭から現代のイラン核問題に焦点を当てる構成自体が、読者にメッセージを送っている。つまり、過去の歴史は全て、「今ここにある危機」を理解するための前史なのだ。そしてその危機とは、核武装した敵対国家の出現という「第二のホロコースト」の可能性である。ここに、イスラエル国家安全保障思想の根源がある。ホロコーストは単なる歴史上の悲劇ではない。それは、ユダヤ民族が絶滅の淵に立たされたという「生存のトラウマ」として、すべての政策と行動の深層を規定する「神話的核」だ。
この本を読みながら、私は著者たちが提示する「証拠」の扱い方に注意を払わざるを得ない。彼らは元諜報員へのインタビュー、機密文書の断片、公開記録を巧みに組み合わせている。しかし、ここで問わなければならない。この「証拠」は誰によって、何の目的で「許可」された情報なのか? イスラエルという国家、そしてその諜報機関は、自らのイメージ管理に非常に長けている。特にモサドは、意図的に「伝説」を創り出すことで抑止力の一端を担ってきた。本書で描かれる成功談の数々――アイヒマン拉致、エンテベ空港救出作戦、オシラク原子炉破壊――は、部分的には真実だろうが、同時に「許された物語」として流布されている側面があるのではないか?
逆に、著者たちが強調する「失敗」や「醜聞」――ヨム・キプール戦争の驚き、ポラード事件、ヴァヌヌ誘拐、誤認殺害――は、それらが「公に知られても構わない」あるいは「知られた方が都合がいい」類の失敗なのかもしれない。真に都合の悪い失敗、例えば、同盟国へのスパイ活動がもっと大規模に発覚した事件、あるいは国内の反体制派に対する違法な監視の全貌は、この本には出てこない。情報統制のプロである組織について書かれた本そのものが、一種の「管理された開示」の産物である可能性を、頭の片隅に置いておく必要がある。
「核の曖昧性」は欺瞞か、それとも高度な戦略か
この本が最も興味深い点の一つは、「核の曖昧性」政策の実態に迫ろうとしていることだ。イスラエルは「最初に中東に核兵器を導入する国にはならない」と宣言する一方、自国の核保有を肯定も否定もせず、国際的な査察も拒否する。これは、核拡散防止条約(NPT)体制に対する明白な挑戦であり、国際法のグレーゾーン、あるいは逸脱ですらある。
著者たちは、この政策が単なる「ごまかし」ではなく、緻密に計算された「戦略的曖昧性」であることを示す。その目的は二つある。第一に、近隣アラブ諸国を刺激して核開発競争を誘発するのを防ぐ。第二に、核の使用に関して敵に不確実性を与え、抑止力を最大化する。つまり、「彼らは核を持っているかもしれない。だから攻撃すれば壊滅的な報復を受けるかもしれない」という恐怖を利用するのだ。
しかし、ここで思考を深めてみよう。この政策は本当に成功していると言えるのか? イランやかつてのイラク、シリアが核開発に狂奔した理由の一つは、まさにイスラエルの「曖昧な」核能力への恐怖ではなかったか? 「曖昧性」が逆に、敵対国の「ならず者国家化」と核武装への欲望を駆り立てている可能性はないか? 本書は、イスラエルが敵の核施設を先制攻撃する一連の作戦を「自衛」として描くが、その「自衛」を必要とした根本原因の一端は、イスラエル自身の核政策にあるのではないか、という循環論法に陥る危険性を内包している。
さらに倫理的な問題がある。「曖昧性」を維持するためには、内部告発者モルデハイ・ヴァヌヌのような人物を、外国で誘拐し、秘密裡に裁くという「超法規的措置」が必要となる。著者はヴァヌヌ事件を「核の曖昧性」政策を守るための必然的行動として描くが、これは民主主義国家における「表現の自由」や「内部告発者保護」の原則に対する重大な侵害だ。国家機密の名の下に、個人の権利が完全に無視される構図がここにある。これは、「国家生存」がすべての価値を凌駕する「例外状態」が、イスラエルにおいては恒常化していることを示す一例ではないか。
「標的殺害」:戦争の個人化と倫理の消失
本書が詳細に描く「標的殺害」は、現代戦争の最も問題的な側面を象徴している。これは、戦場の兵士対兵士という従来の戦闘ではなく、国家の情報機関が、特定の個人を「テロリスト」と認定し、法的手続きを経ずに物理的に抹殺する行為だ。無人機(UAV)による攻撃は、これを地理的・心理的距離を置いて実行可能にし、「殺害のボタン」を押す行為を事務作業に近づけた。
著者たちの記述は、この作戦が「効果的」であることを強調する側面がある。ハマスの技術者や爆弾製造者を除去することで、テロ攻撃の頻度を減らせた、と。しかし、ここで立ち止まって考えなければならない。「効果的」であることと「正当」であることは全く別次元の問題だ。効果性は功利主義的な計算(殺害によるテロ防止効果)で測れるが、正当性は法の支配、無罪推定の原則、正当な裁判を受ける権利といった、民主主義の根幹をなす原理に基づく。
本書は、シンベットや軍が「標的殺害」の対象者リストを精査し、法務官の承認を得る「プロセス」が存在すると述べる。しかし、それは国家内部の「行政手続き」に過ぎず、司法による独立した審査ではない。対象者が本当に罪を犯したのか、逮捕や裁判による解決の可能性はなかったのか、という根本的な問いが置き去りにされる。さらに、「近接者」(付近にいた一般人)の殺害は「残念ながら避けられない犠牲」として処理される。この論理は、国家が生命の価値に序列をつけ、一部の生命を「許容可能な損害」として切り捨てることを正当化する。それは、戦争における「区別の原則」(戦闘員と非戦闘員の区別)の深刻な毀損だ。
そして最も危険なのは、この「標的殺害」の対象が、「テロリスト」から「核科学者」へと拡張されていることだ。イランの科学者に対する暗殺(本書でも言及されている)は、新しいパラダイムを示唆する。それはもはや「差し迫った攻撃」を阻止するための緊急措置ではなく、敵対国の長期的な技術的能力そのものを、非戦時において破壊する「予防的戦争」の一形態だ。この論理を突き詰めれば、敵国のあらゆる科学者、技術者、さらには教育者までもが、「潜在的な脅威」として標的になりうる。戦争と平和の境界が完全に曖昧になる世界である。
諜報機関の「戦争の中の戦争」:組織的利益と国家の危険
本書が明らかにする重要なテーマは、モサド、アマン、シンベットという主要3機関の間の熾烈な縄張り争いだ。著者たちはこれを「戦争の中の戦争」と表現する。これは単なる官僚的ないざこざではない。各機関は、予算、人的資源、そして「陛下」(首相)へのアクセスという「権力」を巡って競合する独立した「帝国」として描かれている。
この内部競争が、国家の安全保障に深刻な悪影響を及ぼす実例が、1973年のヨム・キプール戦争における「驚き」だ。アマンは、エジプトとシリアが大規模攻撃を準備しているというシギント(信号情報)や人的情報(ヒューミント)の報告を、「概念」(固定的な脅威評価)に合わないとして軽視・排除した。なぜなら、その「概念」こそがアマンの組織的権威の基盤だったからだ。情報を独占し、「我々だけが全体像を知っている」という地位を維持することが、組織の利益となった。その結果、国家は壊滅的な奇襲攻撃を受けた。
この構造は、あらゆる大規模組織に通底する病理だ。しかし、諜報機関という、その本質が「秘密」と「独占」にある組織では、この病理が特に深刻な形で現れる。情報は権力であり、それを他機関と共有することは、自らの重要性を毀損することになる。本書は、この問題を認識しつつも、有効な解決策を示せていない。改革は試みられるが、根本的な組織の「帝国」化を止めることはできないようだ。
ここで、より深い疑問が浮かぶ。これは単なる「組織の非合理性」なのだろうか? それとも、権力者(首相や国防相)にとって、諜報機関が一枚岩ではなく、互いに競争し、互いを監視し合う状態の方が「統治」しやすいという側面があるのではないか? 分裂した諜報機関は、政治指導者に対して単一の「専門家の答え」を提示できず、指導者は複数の選択肢から「政治的に都合の良い」情報を選び取ることができる。諜報機関間の争いは、政治指導者による「分断統治」を可能にする機能すら果たしている可能性がある。この視点は、本書ではほとんど探求されていない。
同盟国へのスパイ活動:国際関係の本質を映す鏡
ジョナサン・ポラード事件は、イスラエルが最も重要な同盟国である米国に対して組織的なスパイ活動を行っていたことを暴露した。本書はこの事件を「愚かな過ち」として描き、その後、米国へのスパイ活動は抑制されたとほのめかす。しかし、これはあまりに楽観的すぎる見方ではないか?
国家間の関係において、「スパイ活動」は「友好」や「同盟」と矛盾しない。むしろ、すべての国家は、たとえ親密な同盟国に対しても、何らかの形で情報を収集しようとする。それが国家の本質だ。問題は、その「程度」と「方法」、そして発覚した時の「処理」である。ポラード事件が特別なのは、イスラエルが米国政府の内部に「エージェント」を抱え込み、機密文書を大量に盗み出していたことだ。これは、「情報共有」の枠を超えた、明らかな「敵対的行為」に近い。
著者たちの記述から感じられるのは、イスラエル諜報コミュニティの一部にあった(あるいは今もある)一種の「傲慢」だ。つまり、「我々の生存は絶対的であり、そのためには同盟国の法律なども超越しうる」という考え方だ。ポラードの雇い主であった「ラカム」(科学関係諜報局)は、イスラエル国防省の一部門だった。つまり、これは国家による組織的犯行だった。事件後、イスラエル政府はポラードを「単独犯のローンウルフ」として切り捨てようとしたが、米側の調査は組織的関与を疑わせる証拠をつかんでいた。
この事件は、イスラエルにとっての「同盟」の本質を問いかける。それは価値観を共有する対等なパートナーシップなのか? それとも、自国の生存を確保するための「手段」の一つに過ぎず、必要とあらばその「手段」自体をも欺くことが許されるのか? ポラード事件の後、イスラエルは米国からの巨額の軍事援助と技術協力をこれまで通り受け続けている。この事実は、国際政治における「非難」と「実利」の奇妙な分離を示している。道義的非難はあっても、戦略的必要性がそれを上回る時、「同盟」は存続する。ここに、国際関係のシニカルな現実がある。
サイバー戦争とステラクスネット:無血戦争の幻想と現実
本書は、イスラエル(およびおそらく米国)によるイラン核施設へのコンピュータウイルス「スタックスネット」攻撃について言及する。これは、物理的破壊を伴わずに敵のインフラを麻痺させる「サイバー戦争」の先駆けとされる。メディアなどでは、これを「クリーンでスマートな戦争」として賞賛する向きもある。
しかし、ここにも大きな落とし穴がある。第一に、「スタックスネット」はイランの核施設を標的としたが、その過程で世界中の無関係なコンピュータシステムにも感染し、甚大な経済的損害を与えた。サイバー兵器は、生物兵器や化学兵器のように、その影響を特定の標的に限定することが極めて難しい。つまり、無差別兵器化する危険性を本質的に孕んでいる。
第二に、物理的破壊を伴わないからといって「無血」とは限らない。仮に、サイバー攻撃によって国の電力網が大規模に停止し、病院の生命維持装置が止まったり、交通システムが麻痺して事故が多発したりすれば、間接的に多くの死者が出る可能性がある。にもかかわらず、攻撃者の責任は極めて問いにくい。攻撃経路の隠蔽が容易だからだ。
第三に、最も深刻なのは、サイバー攻撃の「参入障壁」の低さだ。核兵器開発には国家レベルの莫大な資源が必要だが、高度なサイバー攻撃能力は、比較的小規模な組織(テロリスト集団や犯罪組織)でも獲得可能だ。イスラエルや米国がこの分野で先端を行くからといって、独占状態が続く保証はない。むしろ、彼らが開発した兵器や技術が流出し、やがて自分たちに向けられる可能性が高い。サイバー空間は、本質的に「非対称戦争」に最も適した領域なのだ。
本書は、スタックスネットを「成功例」として提示するが、それは短期的な視点に過ぎない。長期的には、サイバー軍拡競争を激化させ、世界をより不安定で予測不能な場所にしている可能性が高い。国家は、目に見えない攻撃に常にさらされる恐怖に苛まれ、先制攻撃の誘因が高まる。ここでも、「国家生存」のための短期的技術的「解決策」が、長期的にはより深い安全保障のジレンマを生み出している構図が見える。
「アルマゲドン・ナラティブ」の危うさ:自己充足的なパラノイア
最後に、この本全体を貫く「アルマゲドンを阻止する」という物語(ナラティブ)そのものについて考えてみたい。このナラティブは、イスラエルの諜報活動と安全保障政策を、道徳的に無謬で、歴史的に必然的なものとして見せる強力な装置だ。それは次のような論理だ。
- 我々は絶滅の危機(アルマゲドン)に常に直面している。
-
この危機は、敵対的な外部勢力(アラブ諸国、イラン、テロ組織)によってもたらされる。
-
したがって、我々の生存を守るためには、あらゆる手段が正当化される。
-
諜報機関は、その「あらゆる手段」を実行する「守護者」である。
このナラティブは、内部に対しては社会の結束を強め、外部に対しては行動を正当化する。しかし、これは極めて危険な思考様式でもある。なぜなら、それは本質的に「反証不可能」だからだ。脅威が顕在化しなかった場合は「我々の努力が成功したから」と解釈され、脅威が顕在化した場合は「我々の努力が不十分だった、もっと強硬な手段が必要だ」と解釈される。いずれにせよ、ナラティブ自体は強化される。
このパラノイア的な世界観は、和平の可能性を常に懐疑的に見るように仕向ける。敵の穏健派は「欺瞞」であり、譲歩は「弱さの現れ」と解釈される。本書が描く、和平プロセスにおける諜報機関の「二重の役割」(和平を支えつつ、和平の破綻に備える)は、まさにこの矛盾を示している。諜報機関の存在意義そのものが「脅威の管理」にある以上、脅威が消え去る真の和平は、彼らの組織的存立基盤を危うくする。この構造的利害関係は、和平プロセスにどのような微妙な影響を与えているのか? 本書はこの問いに深く立ち入らない。
さらに言えば、「アルマゲドン・ナラティブ」は、イスラエル国内の民主主義と人権を浸食する正当化理由として機能してきた。アラブ系イスラエル人に対する差別的な法律、ヨルダン川西岸における入植地拡大とパレスチナ人への抑圧、そして先に述べた「標的殺害」や「超法規的措置」——これらすべてが「生存のため」という大義の下で行われてきた。諜報機関の活動は、このナラティブの最も先鋭的で不可視的な実行部隊なのである。
日本の文脈で考える:平和憲法と「積極的平和主義」の狭間で
このイスラエルの事例を、日本の安全保障環境に当てはめて考えてみると、極めて示唆的で、そして不気味な光景が見えてくる。
日本は、イスラエルとは正反対に、「戦争放棄」をうたった憲法9条の下で、「専守防衛」と「非核三原則」を国是としてきた。日本の防衛力は、長らく「矛」よりも「盾」の要素が強く、諜報機関(内閣情報調査室、公安調査庁、外務省国際情報統括官組織など)の規模と権限も、イスラエルのそれとは比較にならないほど小さい。
しかし、近年の「積極的平和主義」への転換、防衛費の増大、サイバー防衛部隊や宇宙部隊の創設、そして「対敵基地攻撃能力」の保有論議は、日本の安全保障のあり方を根本から変えつつある。その背景にあるのは、北朝鮮の核・ミサイル開発、中国の軍拡と海洋進出、そして「台湾有事」という、日本版の「生存の危機」ナラティブである。
ここで問われるのは、日本はイスラエルの道を、どこまで、どのように踏襲しうるのか、また踏襲すべきなのか、という点だ。
- 日本は、「専守防衛」の枠組みを維持しつつ、イスラエルのような先制的・予防的攻撃(敵のミサイル発射拠点攻撃など)を正当化する「解釈」を広げようとしている。これは「法の支配」の拡張的解釈であり、イスラエルの「核の曖昧性」や「標的殺害」の論理と通底するものがある。
- サイバー空間や宇宙空間における「影の戦争」は、日本も否応なく巻き込まれている。防衛省のサイバー部隊は「防御」が主任務だが、その境界は曖昧だ。防御のための「探査」活動が、他国からは「攻撃的準備行為」と見なされる可能性は大いにある。
- 最も重要なのは、民主的統制の在り方だ:イスラエルの事例が示すのは、強大な諜報機関と秘密工作の体系は、いったん構築されると、議会や司法による実効的な監視が極めて難しくなるということだ。「国家機密」の壁が、あらゆる審査を阻む。日本で「特定秘密保護法」が成立したのは、まさにこの流れの中にある。機密の範囲が広がり、内部告発が抑圧されれば、市民は政府の行為を監視する目を失う。
日本社会は、イスラエル社会のような「生存のトラウマ」を(沖縄戦や原爆を除けば)国家的規模では共有していない。また、自衛隊や警察への社会的信頼は比較的高い。しかし、安全保障環境の「厳しさ」が強調され、危機感が煽られる中で、「平時の倫理」が「非常時の論理」に置き換えられていくプロセスは、どの社会にも起こりうる。イスラエルの歴史は、その危険な坂道を、国家が組織的に、そして多くの場合「成功裡に」滑り降りてきた過程の記録なのである。
この本は、最終的には読者に一つの根源的な問いを投げかけているように思える。それは、「国家が生存するために、その国家が守ると標榜する価値(法の支配、人権、民主主義)を踏みにじる行為が、どこまで許されるのか?」という問いだ。イスラエルは、このジレンマと70年以上にわたって直面し、多くの場合、「生存」を選択してきた。その代償として何を失ったのか、あるいは失いつつあるのか。本書は、その答えを直接示すことはない。しかし、暗殺、誘拐、欺瞞、内部抗争の詳細な描写が積み重なるほどに、その代償の重さが、沈黙のうちに読者に迫ってくる。それは、国家の魂の侵食であり、平和な日常という幻想が、永遠に失われたという事実かもしれない。
