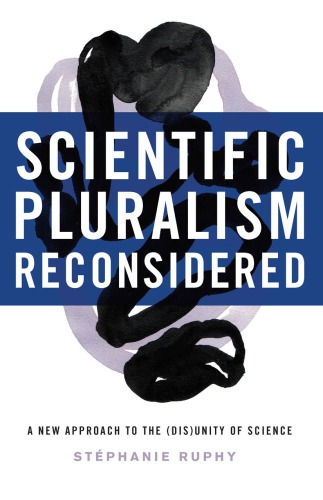
Scientific Pluralism Reconsidered: A New Approach to the (Dis)unity of Science
ステファニー・リュフィ
ピッツバーグ大学出版局
フランチェスカのために
目次
- 謝辞
- 序論
- 1. 言語,方法,対象
- ウィーン・サークルの言語的統一性
- カーナップにおける科学の対象領域の統一性の問題
- 伝統的な方法論の統一性
- ハッキングの科学的推論のスタイル
- 存在論的充実と「葉身的多元主義」
- 2. このような場合、「汝は汝なり。
- この論文では、「intelligence 」と「intelligence 」の関係について、「intelligence 」と「intelligence 」の関係、「intelligence 」と「intelligence 」の関係、「intelligence 」と「intelligence 」の関係について、それぞれ説明する。
- アプローチ
- 非還元的な神学間関係と自然の単一性 71 中間結語
- 3.表象
- 一元論対多元論論争における現在の画一化された線引き
- 実世界の物理システムのシミュレーション永久に相容れない多元性のケース
- 分類学的多元主義
- 結論
- ノート
- 参考文献
- 索引
謝辞
数年前、コロンビア大学で大学院生として彼の指導を受けていたとき、私の哲学的志向に決定的な役割を果たしたフィリップ・キッチャーに特別な謝意を表したい。彼の指導と著作は私に大きな影響を与え、また彼との会話から多大な恩恵を受けた。私はフィリップに莫大な知的負債を負っている。
この原稿の最終版を読み、多くの貴重な示唆を与えてくれたDavid Ludwigに心から感謝したい。ピッツバーグ大学出版局の匿名レフェリーからのコメントも原稿を改善するのに貢献した。特に、私のアクワイアリング・エディターであるアビー・コリアーには大変お世話になり、チャールズ・ウルフには私の英語を滑らかにするために多大な貢献をしていただきました。
また、初期のフランス語原稿を丁寧に読んでくださったマックス・キスラー、ジャン・ガヨン、ピエール・リヴェ、サンドラ・ロージェ、フランソワ・クレマンツに感謝する。
本書のアイデアや議論の一部は、別の場所に掲載されている。第1章の第4節と第5節は、私の「ハッキングの科学的推論の複数スタイルから『葉っぱ付き複数主義』へ」を引用している。2011年にPhilosophy of Scienceに掲載された「From Hacking’s Plurality of Styles of Scientific Reasoning to ‘Foliated Pluralism’: A Philosophically Robust Form of Ontologico-Methodological Pluralism」である。第2章の第1節から第4節は、拙著「世界は本当にまばゆいのか?A Response to Cartwright’s Charge against ‘Cross-Wise’ Reduction,「 that appeared in Philosophy of Science in 2003, 」Why Metaphysical Abstinence Should Prevail in the Debate on Reductionism,” that appeared in International Studies in the Philosophy of Science in 2005, 「Ontology Relativized,」 that appeared in Synthese in 2006.この3つの論文から、第2章は、”If the World Really Dappled? 第3章の第2節は、私の「Limits to Modeling: 第3章の第2節は、Simulation and Gamingに掲載された私の「Limits to Modeling: Balancing Ambition and Outcomes in Astrophysics and Cosmology」(宇宙物理学と宇宙論における野心と成果のバランス)を引用している。「An Interdisciplinary Journal」に掲載されたものである。また、第3章では、「恒星系は自然系か?A Challenging Newcomer in the Monism/Pluralism and Realism/Antirealism debates,” (2010年Philosophy of Scienceに掲載された論文)。
はじめに
科学哲学は、その専門化された存在のかなりの部分において、科学の統一という(雑多な)旗を振っていたが、今日、哲学の潮流が明らかに科学の複数性を支持する方向に変わったことを否定する人はほとんどいないだろう。ウィーン・サークルの科学統一プログラムは、言語学的なプログラムとしては死んでいる(そして、すぐに復活することは期待できない)。少なくとも、「科学的方法」(一般的な方法論はもちろん、正当化の論理という意味でも)の哲学的探求はまだ死んでおらず、むしろ病的で、良かれ悪しかれ、関連する分界問題は最近あまりトピック性を保っていない。長年の探求であり、科学的進歩の特徴であった理論的統一は、もはやすべての学問分野にわたって、特に還元的な形では望ましいとは見なされなくなった。もう一つの歴史的に重要な現象連結の方法であるアナロジーの確立は、もはや哲学的な注目を集めることはない。1906年に書かれたピエール・デュエムのこの科学的実践の分析が、このテーマに関する参考文献として残っている。物事を分類する基本的で正しいシステムは一つであるとする分類学上の統一論は、科学者の実践とはやや無関係のように思われる。自然を動物に見立て、その関節を切り分けるというプラトン的な比喩は、科学的分類の実際の目的を理解する上であまり役に立たない古い哲学的な比喩に過ぎないと思われるかもしれない。当然のことながら、現代の科学哲学において、こうした統一的な実践に関連する形而上学的信念を(少なくとも公然と)支持する哲学者の数は、かなり限られている。例えば、イアン・ハッキング(1996, 47)が「世界に関する真理には独特の基本構造があり、中心的な真理は周辺的な真理を暗示する」と表現した構造に関する形而上学的テーゼは、還元主義に関する現在の哲学論争ではほとんど発言されていない。
科学的統一性という考え方は、その方法論的側面において、哲学者や実験史家の研究に再浮上したことは認められるが、認識できないほどではないにしても、かなり萎んだ形で再浮上している。道具、器具、知識の断片が科学を支えているのであって、理論的統一や推論の共通規範に向けた何らかの主張される傾向ではない。言い換えれば、「科学の無数の枝があらゆる方向に飛び去るのを止めたのは、高度な理論ではなく、広く共有された実験手法と道具の一群の普及である」(Hacking 1992d, 48)のである。この「実験主義者」のテーゼは、統一性に関して非常に控えめな見解を示している。すべての理論的知識の壮大な統合も、宇宙の秩序ある構造に関する大胆な主張も、世界を知るための唯一最善の方法の存在に対する信念もなく、ただ、科学者が実際に何を実践して共有しているかを洞察しているのだ。
実際の科学的実践に注目することは、科学の単一性というテーゼに反対する人たちが異議を唱えるような方法論的推奨事項ではないことは確かである。それどころか、科学の単一性に反対する最初の体系的な哲学的発言の一つであるパトリック・サッペスの1978年の論文「科学の複数性」が、まさにそうした実践的な方向転換を哲学者たちに促したことは、記憶に新しいところである。「統一性の叫びの後に還元主義への万歳三唱をするのではなく、異なる科学が言語、主題、方法においてどのように異なるのか、また、どのように類似しているのか、忍耐強く検証してみるべきだ」(1978年、9)。しかし、世界と科学の両方について、大胆かつ一般的な主張が、多元主義者の側にも見られるようになったのは、皮肉としか言いようがない。なぜなら、本書で詳しく述べるように、多元主義者の主張は、今日の科学に見られるX(言語、対象、方法論、理論、モデル、分類スキームなど)の多重性を単に認め、記述することをはるかに超えているからだ。
形而上学的な野心に溢れ、「秩序ある」世界という考えを無効化しようとするものであるため、一見すると印象的な論文もあるが、これは私たちの知識に固有の基本構造の存在を意味する。ナンシー・カートライトの著書『The Dappled World』(1999)では、この形而上学的関心が、さまざまな形態の還元主義に対する攻撃の形をとっている。この還元主義は、世界の「斑点」の性質、つまり、ある特徴は正確に秩序づけられているが、別の特徴は手に負えない、ということの肯定と関連している。ジョン・デュプレは、著書『The Disorder of Things』(1993)の題名から直ちに自身の形而上学的野心を表明し、還元主義と自然種の存在の両方を否定することによって、無秩序な世界の擁護を根拠づけている。ヘレン・ロンギノ(2002, 2013)のような有力な多元主義者は、世界の複雑性に関する考察を援用し、ある現象について互換性のない複数の表現が存在することの認識論的許容性を唱え、これらの部分表現の統合は期待できないとしている。形而上学的な考察は、フィリップ・キッチャー(1983)やジェリー・フォドー(1974)のような有力な反帰納主義の議論にも見られるもので、その結果、ある理論や学問が他のものに還元できないことが科学の永久的な特徴として考えられている。
また、多元的なテーゼの中には、その一般的な方法論的な規定的な野心によって、印象的なものもある。たとえば、Hasok Chang(2012)の提唱する複数の実践と知識のシステムの育成は、一般的に有効であることを意図している。つまり、学問の適切なダイナミズム、成熟度、目標に関して、ある分野のいかなる特定の特徴からも独立して、それぞれの分野で有効であるということである。世界の構造に関する私たちの信念は、それを研究するために私たちが採用する方法論と密接に関係している」(Cartwright 1999, 12)という信念に後押しされ、デュプレやカートライトの多元主義的見解は、明確な方法論的意味も持っている。問題解決のために科学者が還元的アプローチを志向することは、特定の問題に対する局所還元主義の成功可能性をあまり検討せずに、世界はまばらであるという理由で否定されているのだ。
このような科学的多元主義(scientific pluralism)は過度に野心的なのだろうか。この問いに答えることは、本書を通じて繰り返し行われる関心事だが、決して本書の唯一の目的ではない。科学的多元主義の旗印の下にある様々な立場や問題を考えると、第一の目標は、科学の単一性あるいは複数性の議論について、その方法論、認識論、形而上学の次元に焦点を当てた新しい構造化を提供することである1。このような議論の雑多な性質をさらに説明するために、主要な問題のいくつかを次のような問いとして捉え直すことができる。異なる方法でしか知ることのできない、異なる種類のものがあるのだろうか。あるいは、ルドルフ・カルナップの言葉を借りれば、「すべての状態は一種類であり、同じ方法によって知られる」([1934] 1995, 32)のだろうか。私たちの最良の理論が還元的なタイプのユニークな構造を形成していると期待すべきか、あるいはそうではなく、断片が自律的に残っている一種の「パッチワーク」であると期待すべきなのか。ある現象に対する複数の相容れない表現が存在することは、認識論的に満足できる場合があるのか、それとも、科学はそれが提供する表現の収束を目指すべきなのだろうか。科学が発見しようとすべき正しい分類方法は一つしかないのか、それとも複数の分類体系が存在する現状が続くのか。これらの疑問は、それぞれ異なるタイプの議論や視点に関連しており、今日の科学について一元論者や多元論者を名乗ることはあまり意味をなさない。
私は、この本の3つの章に対応するように、論証の3つの主要な領域を区別することを提案する。第一は、科学における言語、対象、方法の単一性あるいは複数性を扱う分野、第二は、私たちの理論的知識の構造、特に異なる言説の領域あるいは科学分野に属する理論間の還元関係の可能性について、第三は、表現上の複数性、すなわち与えられた現象について複数の科学的説明が同時に存在することを意味する分野である。これらの各領域の核となる議論は、ほぼ自律的に発展してきた。とはいえ、いくつかのトピックの間にはつながりがあるので、議論を進める中で明らかにしていきたいと思う。また、これら3つの論題は、現在の哲学的状況において同じような位置を占めているわけではないことも強調しておく。一見したところ、最初の分野は歴史的な関心が強いようだが、2番目と3番目はより継続的な議論を提起している。言語の複数性の問題と、それに関連して科学の対象領域の存在論的方法論的統一性(あるいはその欠如)の問題は、ウィーン・サークルのプログラムの中核を成していた。この科学の単一性というテーゼの最初の形が歴史的に(少なくとも分析哲学の伝統の中で)いかに重要であったとしても、それはもはや現在の哲学的な議論を形成するものではない。他の2つの多元的議論領域で問われている一元論的立場は、ウィーン・サークルが擁護してきたものではない。例えば、理論間還元論は、私たちの理論的知識の構造を扱う第二の領域の中核をなすものだが、科学の統一プログラムの中心的な信条ではなかったし、「科学の究極の目的は、あらゆる与えられた現象について、その本質を完全に記述すること」(Kellert, Longino, and Waters 2006, xi)という考えも、後に見るように、表現的多元主義の支持者の現在のお気に入りの標的になっていた。
では、なぜ現在の科学的多元主義の形態について書かれた本で、ウィーン・サークルに立ち戻ったのだろうか。私の目的は、科学哲学の歴史において、この時代に焦点を当てたすでに非常に豊かな研究成果に貢献することではない。もっと控えめに言えば、科学統一計画の核となる主要な動機と考え方を思い起こし、グループのメンバーが共有したのは、共通の教義というよりも、科学のさまざまな部門間の協力を促進するという共通の関心事であり、この関心事は、その時事性が失われるにはほど遠いことを強調したいだけなのである。しかし、それよりも重要なことは、ウィーン環、特にカルナップにとって中心的な問題であった、異なる方法でしか知り得ない異なる種類のものが存在するかどうかという問いは、哲学的に非常に興味深い問題であり続けていることである。確かに、今日、この問題が興味深いのは、ウィーン環の時代とは別の理由からであり、私がこの問題に答えるために用いる概念的な道具もまた異なっている。しかし、本書の第1章で示すように、存在論的方法論的多元主義の形態を哲学的に分析することで、私が本質的と考える現代の科学的実践のある特徴を把握することが可能になるが、これは他の二つの論証の領域に関連する科学的多元主義の形態では見落とされてしまうものである。
より正確には、本書の第1章で、私はまず、ウィーン環の「科学の言語的統一」プログラムの中で定式化された、科学の合理的再構成の複数性についてのカルナップの弁護を論じることから始める。そして、第1章で展開された様々な考察をつなぐ共通のテーマである、「異なる方法でしか知り得ない異なる種類のものが存在するか」という問いに対するカルナップの否定的回答の根拠を説明する。そこで、ハッキングの科学的推論のスタイルという概念が、存在論的側面(スタイルは対象を創造する)と正当化論的側面(スタイルは独自の妥当性基準を開発する)の両方を含むことから、この経験科学の領域の統一、あるいは不統一という問題を再検討することが有効であろう。私は、科学における推論の複数のスタイルの存在がもたらす存在論的・方法論的帰結を調査する。その結果、科学的推論のスタイルによって、科学が研究する対象が「存在論的に豊かになる」という概念を提案し、「葉身的多元主義」という概念を構築することになる。つまり、異なる方法論によって研究される異なる種類のものが科学に存在することを平凡に認めるだけでは済まされない多元主義である。さらに、異なるスタイルの推論を同時に使用することによって生じる、新しい知識を得るための学際的かつ累積的な進め方など、現代の科学的実践の本質的な特徴を、葉理的多元主義がどのように捉えることが可能だろうかを説明する。したがって、第1章で提案する存在論的方法論的多元主義の風景は、特定の方法を特定のタイプの対象に関連付ける従来の「パッチワーク」のような不統一の形態とは大きく異なるものである。
本書の第2章では、第1章で論じた存在論的方法論的統一とは全く異なる、科学の統一を考える方法に焦点を当て、しばしば科学の異なる枝や科学分野に対応する、異なる記述レベルで発展した様々な理論の間に成立しうる関係の問題を取り上げる。このことは、科学の単一性あるいは複数性に関する議論において、かなり伝統的な側面、すなわち、理論間還元性の問題を議論することにつながるだろう。理論間還元性とは、ある理論や言説の領域が他の理論に吸収されたり、包含されたりする可能性を意味する。2 理論間リンクの性質をどのように考えるかによって、還元論に関心を持つ理由は異なる。理論間関係の「局所的」な検証は、主に記述的な野心を反映したものであり、その要点は、関係する学問の歴史におけるある時期に、ある理論が他の理論に還元可能かどうか、また還元という概念についてどのような正確な意味を持つかを見出すことである。この最初のタイプの分析では、還元性の問題は科学に「内面的」なものであり、得られる結論は、与えられた認識論的文脈と採用された特定の還元概念に依存したままである。ある学問分野や下位の学問分野(例えば、分子生物学)を他の学問分野(例えば、マクロ生物学)より優遇することは、還元論的な科学観では認識論的に正当化されるが、反還元論ではそうではない。還元主義の議論に参加するもう一つの理由は、それが形而上学的な意味を持っているからだ。還元主義であろうとなかろうと、私たちの最も優れた理論的知識の構造は、世界に存在するもの(対象や性質)とその名目的秩序や無秩序の程度について何らかの光を当ててくれるはずだからだ。
私が還元論に関心を持ったのは、カートライト、フォドー、キッチャー、デュプレといった、規範的方法論と形而上学的な重要性を併せ持つ有力な反還元論者の論文を読んでいて不満に思ったからであった。記述的アプローチとは異なり、これらの著者は、ある理論や学問の他への還元可能性の問題を、科学内部の問題として定式化せず、その答えは関係する学問の歴史的発展の過程で変化しうるものであるとする。それどころか、これらの反帰還主義的議論は、その結論が認識論的コンテクストの進化とは無関係に有効であり続けることを目指す限り、部分的に科学の外部に、「ぶら下がっている」ように見えるのだ。キッチャー(1984)によれば、例えばマクロ生物学は分子生物学と不可分であるとされるが、この主張は関係する学問の発展に指標されるものではない。また、物理学に対する特殊科学の不可逆性については、Fodor (1974)も同様である。したがって、このような「はみ出し者」の立場の根源と説得力を問うことが必要だと思った。この懸念から、私は、影響力のあるこれらの反帰納主義的議論において、様々な(多かれ少なかれ暗黙のうちに)形而上学的考察が果たす役割を調査することにした。私の結論は、彼らが主張する反帰納主義的な科学観は、実際にはいくつかの形而上学的な主張を受け入れることを前提にしており、そのことが、これらの反帰納主義的立場に付随する方法論の規定の信頼性を著しく弱めている、というものである。私は逆に、還元主義的アプローチの有用性(またはその欠如)は、科学に内在する経験的な問題であると主張する。形而上学的な前提に基づく哲学的な立場は、還元主義的であろうとなかろうと、どのアプローチが好まれるかを外から決めつけることはできない。このように、還元論に関する私の研究は、反還元論的主張の有効性を、与えられた認識論的文脈に制限することによって、制限を設けていると読み取ることができる。
形而上学的な意味合いについては、還元主義的なプログラムの失敗から、多元主義陣営では世界のイメージがよく導かれることを見ていた(例えば、カートライトのダップルド・ワールドやデュプレの存在論的に無秩序な世界など)。世界の秩序性(あるいは無秩序性)に関する主張は、与えられた理論的枠組みに依存するばかりでなく、より根本的には、その枠組みの中で探求者が発する問いかけに依存するのだ。したがって、形而上学に自然主義的な考え方を採用するならば、秩序や無秩序という観点から見た世界のイメージは、採用した理論的枠組みに依存するだけでなく、その枠組みの中で表現される認識論的、偶発的な関心によっても変化しうるということになる。この二重の相対性というテーゼは、その後、科学が描く存在論の風景が理想化され、二重に多元的であることを主張する、特定の多元主義テーゼの弁護につながる。そして、非還元的な理論間関係(アナロジーと合成的統一)にも議論を広げ、その形而上学的な意味合いも検討する。
反帰還主義は、世界の複数の理論的表象の存在を擁護することと密接に関係しており、表象多元主義の一形態として読むことができる。しかし、科学における表象の概念には、法則や理論だけでなく、モデル、コンピュータ・シミュレーション、説明メカニズム、分類体系なども含まれるため、他の形態の表象多元主義も検討する価値がある。第3章では、このような科学的表象の他の形態に焦点を当て、同じ現象や世界の一部について複数の表象(モデル、シミュレーションなど)が共存する、科学では非常によく見られるケースを検討する。このような表象の複数性は、例えば、ある分野の中で、同じ現象やプロセスについて、その性質に関する異なる信念を反映して異なるモデルが競合する場合(例えば、惑星科学では、月の形成を説明するために、巨大衝突モデル、共形モデル、捕獲モデルが共存する)、あるいはモデラーの認識的関心に応じて異なるモデル化作業が共存する場合に見られる(それぞれの部分モデルは研究対象の現象の特定の側面を説明しようとするものである)。また、同じ現象に対して異なる理論的アプローチが存在することを反映することもある(例えば、行動原因メカニズムの研究では、遺伝的、神経生物学的、社会・環境的、発達システム的アプローチが共存する[Longino 2006, 2013] )。また、科学者が物事を区別し、グループ化する方法に関しても、表現上の複数性はむしろ一般的である。たとえば、生物の分類について考えてみよう。よく指摘されるように、集団生態学者は生物学者と同じようには分類しないし、生物学における分類の複数性は言うまでもなく、採用する理論的視点に依存するものである。
このような科学的表象の複数性という状況を踏まえて、この複数性の原因をどのように分析し、概念化するかによって、多くの異なる、そして多かれ少なかれ寛容な哲学的態度が発展してきたのである。このような哲学的態度の根底には、どのような種類の認識論的、方法論的、形而上学的コミットメントがあるのかを明らかにする。その範囲は、統合された説明に対する(実在論的)期待(例えば、キッチャーの謙遜な実在論形式)から不可積な表現に対する認識論的許容(例えば、ロンジーノの不可積多元主義)に至るまでである。この分析によって、科学的表現に関する一元論対多元論の現在の議論の主要な定義づけを、時には批判的に説明することができるだろう。特に、ある現象について互換性のない複数の表象が共存する状況が避けられないと主張する、世界の複雑性を考慮した複数派の立場の妥当性に影響する両義性を強調したい。
第3章では、表象の多元性をめぐる議論への積極的な貢献を二つ挙げる。第一に、現実の物理システムの複合コンピュータ・シミュレーションを含む、ある種の非互換な表現的複数性の状況について、新しい分析を提案することである。宇宙物理学と宇宙論の二つのケーススタディから、このような状況の持続は、世界の「複雑さ」ではなく、関係する表象が時間とともに構築される方法に起因することを明らかにする。また、この種のシミュレーションの具体的な特徴である経路依存性と可塑性についての考察は、実際に提供される知識のタイプの再考を促すだろう。私の主な主張は、(経験的に成功した)複合コンピュータシミュレーションは、実際に何が起こっているのかについての信頼できる洞察ではなく、与えられた現象についてのもっともらしい現実的な物語や絵を提供するということである。私の第二の貢献は、先に述べた別の種類の表現上の複数性、すなわち科学的分類法に関するものである。科学的分類や自然の種類に関する膨大な文献を調べていて、私は、領域が著しく分かれていることに驚かされた。自然の摂理を主張する人々は、物理科学における分類の安定性と単一性を強調する(メンデレーエフの周期表がその好例)。一方、物事を分類する正しい方法が越えがたいほど複数あるという主張者は、しばしば生物科学における現在の分類の複数性を引き合いに出して論証する。この議論に対する私の貢献は、まず、これまであまり哲学的な注目を集めなかった分類学的領域である星の分類方法についての分析から始まる。一見したところ、天体物理学における分類法は、現在確立されているこの領域分割にうまく当てはまらないように思われる。なぜなら、この物理科学の一分野における分類システムは、複数主義に非常に適しているように見えるからだ。結局のところ、恒星のケースは、一元論対多元論の議論において、どちらかの陣営に有利に働くようなケーススタディではない。私が恒星の種類と分類に関して弁護する多元的立場は、ある種の分類(例えば、化学元素の分類)の安定性と単一性をどう解釈すべきかについても新しい光を投げかけている。より一般的には、科学的な分類法が自然の秩序を把握したり、明らかにしたりできるという考え方に異議を唱える。物理学と化学の分類の安定性が持つ形而上学的な重要性を制限することは、自然界の種類という概念に対する現実主義的な捉え方を否定することと密接に関係している。さらに、一元論対多元論の論争における現在の主要な立場に対するステラケースによって提起された疑問は、自然界の種類に関する哲学的教義の目的そのものを再考することを促す。形而上学的な傾向を満足させるような単一の概念を精緻化するのではなく、認識論的な探求は、科学のある分野で最も認識論的に実りある性質やクラスのタイプを特定し、その理由を理解することを目指すべきである、と私は内的かつ局所的な転向を提唱している。
最後に、短い結論として、科学の単一性あるいは複数性の議論の特定の側面に関して、私が擁護する様々な立場の共通点を強調する。たとえ、この議論の雑多な性格から、科学的多元主義の新しい一般版を期待すべきではないとしても。
