コンテンツ
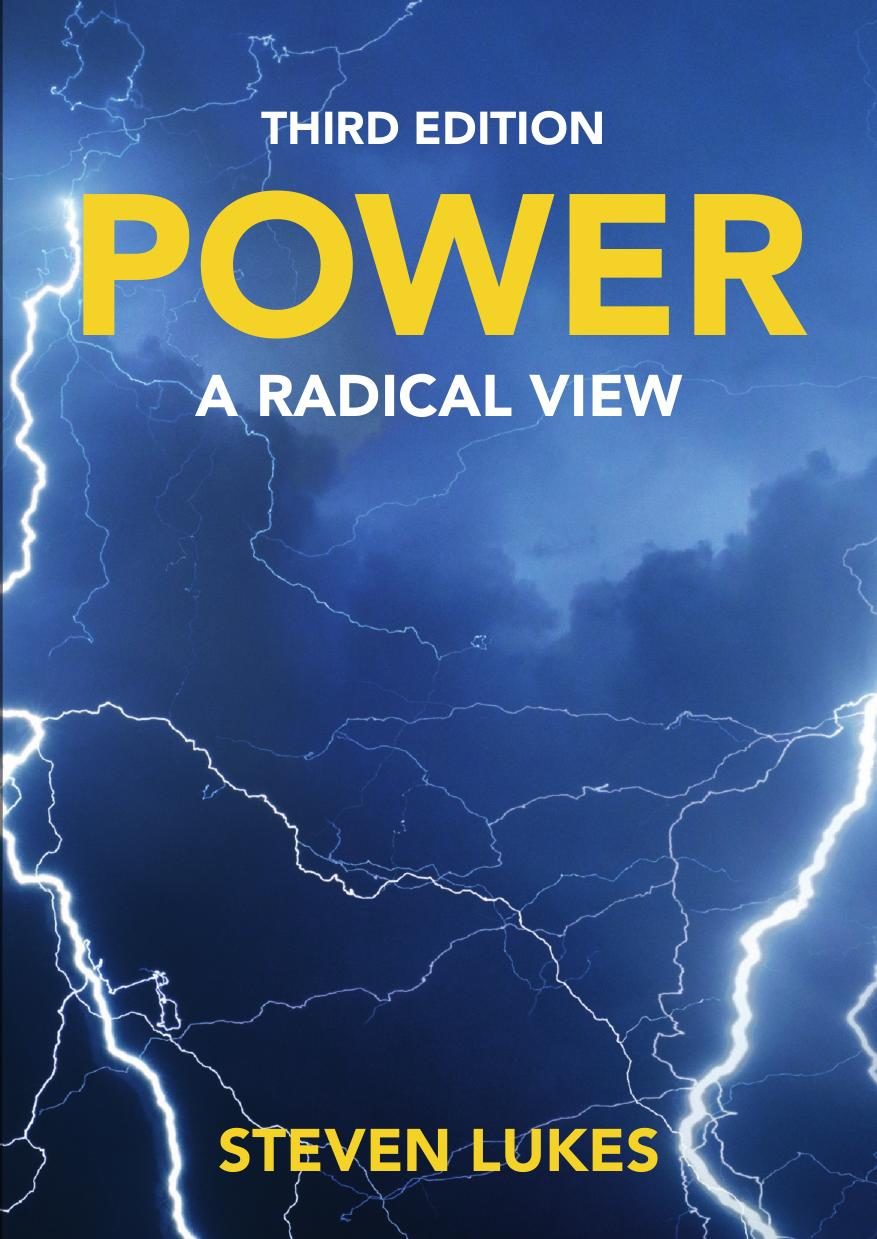
Power: A Radical View 3rd Edition
Power: A Radical View, Third Edition / パワー:ラディカルな視点 第三版 Steven Lukes 2021
目次
- 第三版への序文 / Introduction to the Third Edition
- 第二版への序文 / Introduction to the Second Edition
- 第1章 パワー:ラディカルな視点 / Power: A Radical View
- 第2章 パワー、自由、理性 / Power, Freedom and Reason
- 第3章 三次元的パワー / Three-Dimensional Power
- 第4章 支配と同意 / Domination and Consent
- 第5章 第三の次元の探求 / Exploring the Third Dimension
- 注 / Notes
- 参考文献と参照文献 / Bibliography and References
- 索引 / Index
本書の概要
短い解説:
本書は、社会的権力の本質をめぐる学術的議論に決定的な貢献をした古典的著作の第三版である。権力概念を「三次元的」に分析する著者の視点を深化・発展させ、現代社会における支配と自発的同意のメカニズムを探求する。社会科学の研究者、学生、そして権力関係の動態に関心を持つ一般読者を対象とする。
著者について:
スティーブン・ルークスは、政治社会学、社会理論、政治哲学の分野で国際的に著名な研究者である。オックスフォード大学およびニューヨーク大学で教鞭を執り、権力、合理性、個人主義、道徳的相対主義などをテーマに多数の著作を発表している。本書では、1974年の初版以来続く「権力論争」における自身の立場を、批判に応答しつつ、現代的な事例と理論的展開を通じて精緻化している。
主要キーワードと解説
- 主要テーマ:権力の三次元的理解 [観察可能な意思決定における勝利(一次元)、議題設定の操作(二次元)に加え、人々の信念や欲望を形成することで自発的同意を確保する隠れた権力(三次元)を分析する]
- 新規性:支配の議論との対話 [近年の政治理論における「支配(domination)」概念をめぐる議論(新共和主義など)を参照し、権力論を深化させている]
- 興味深い知見:自発的服従のメカニズム [デジタル監視資本主義や環境的不公正などの現代的事例を用いて、権力が人々の認識能力そのものを弱体化させるプロセスを分析する]
3分要約
本書『パワー:ラディカルな視点』は、スティーブン・ルークスが1974年に発表し、社会科学における権力論争に大きな影響を与えた著作の第三版である。権力を「AがBの利益に反するようにBに影響を及ぼすとき、AはBに対して権力を行使する」と定義した初版の核心的テーゼを発展させつつ維持している。本書の目的は、権力概念を「三次元的」に理解するその「ラディカルな視点」を、過去半世紀近くにわたる批判や新たな理論的展開を踏まえて、精緻化し、擁護し、現代の文脈に適用することにある。
権力分析の「一次元的」視点は、ロバート・ダールら pluralists(多元主義者)に代表され、観察可能な意思決定の場面での紛争と勝利に焦点を当てる。「二次元的」視点は、ピーター・バックラックとモートン・バラッツが提唱し、権力が「非決定」を通じて政治的議題そのものを操作し、特定の問題が公的議論の場に上がること自体を防ぐ作用を明らかにした。ルークスはこれらを認めつつも、さらに「三次元的」権力の存在を主張する。それは、最も効果的で、しばしば見えにくい権力の形態であり、人々の主体的な同意を、彼らの信念や欲望、知覚、さらには自己認識そのものを形成することによって確保する。この権力は、人々が自らの従属状態に不満を感じることさえ妨げ、それを「自然な」もの、「当然の」もの、あるいは「望ましい」ものと見なすように仕向ける。
第三版では、この「三次元的権力」の概念をめぐる論争が詳細に追跡され、その概念的精緻化が図られている。特に、ミシェル・フーコーの権力論(権力の生産性、「主体化」)やピエール・ブルデューの「象徴的暴力」と「ハビトゥス」の概念との対話を通じて、権力が主体を「構成する」という主張の限界と有効性が検討される。また、権力の「第四の次元」を主張する議論にも言及しつつ、三次元の枠組みの有効性を再確認する。
さらに、ジェームズ・スコットのような研究者が主張する、被支配者の絶え間ない(しかししばしば隠れた)抵抗という見方に対して、真の同意や「適応的選好」(ジョン・エルスター)の形成が支配において果たす役割を擁護する。現代社会における具体例として、デジタル監視資本主義による行動修正(シュシャナ・ズボフの分析)、アルゼンチンのスラム「ビジャ・フラマブル」における環境的不公正と「有害な不確実性」(ハビエル・アウジェロの研究)、そしてジョン・ガベンタらが開発した「パワー・キューブ」分析フレームワークを用いた社会変革の実践的研究などが取り上げられ、三次元的権力の多様なメカニズムと、それに対する抵抗・変革の可能性が示される。
本書は、権力概念が「本質的に争いのある概念」であることを認めつつも、その三次元的理解が、不平等、支配、イデオロギー的操作の隠れた力学を批判的に分析するための最も深く包括的な視点を提供すると結論づける。それは、人々が「自らの本性と判断が命じるように生きる」自由を阻害する、見えざる拘束のメカニズムを可視化するための理論的・実践的な道具なのである。
各章の要約
第三版への序文
本書が初版から約50年を経て刊行されるにあたり、権力概念をめぐる論争が未だに続いていることが確認される。権力は、所得や富のような客観的に測定可能な概念とは異なり、その定義と実証的研究方法について根本的な合意が存在しない。これは、権力の概念化の仕方が、社会世界の見方や道徳的・政治的態度を反映し、同時に形成するからである。第三版では、特に「支配(domination)」としての権力と、その同意を確保する「三次元的権力」の概念を、現代の議論や事例を通じてさらに深く探求する。
第二版への序文
初版『パワー:ラディカルな視点』(PRV)が書かれた1970年代初頭の政治的・知的文脈(C. ライト・ミルズやフロイド・ハンターの「エリート論」に対するロバート・ダールら「多元主義者」の批判とその後の「権力論争」)が説明される。PRVは、権力を意思決定における勝利(一次元)や議題設定(二次元)だけでなく、人々の欲望や信念を形成することで自発的同意を確保する隠れた力(三次元)として捉える視点を提唱した。この第三の次元の核心は、チャールズ・ティリーの言う「なぜ従属者は従うのか?」という問い、特に「神秘化、抑圧、あるいは代替的なイデオロギー的枠組みの単なる不在の結果として、従属者は自分自身の真の利益に気づかないままなのである」という説明に関わる。この序文は、第一版のテキストをそのまま再録し、それを補完する新たな二章(第2章、第3章)を追加する本書の構成を説明する。
第1章 パワー:ラディカルな視点
権力の三つの概念的「見方」が提示される。(1) 一次元的見方(多元主義的):観察可能な意思決定における行動と勝利に焦点。(2) 二次元的見方(バックラッハとバラッツ):「非決定」と議題設定の操作に焦点。(3) 三次元的見方(ルークス):潜在的紛争と「真の利益」の概念を導入し、権力が最も効果的に働くのは、観察可能な紛争さえも防止され、人々が自らの従属を自発的に受け入れるように社会化・イデオロギー的に形成される場合であると主張する。権力の概念は「本質的に争いのある」価値依存的であり、その行使の特定には反実仮想的な主張とメカニズムの同定が必要であることが論じられる。マシュー・クレンソンの大気汚染研究などの実証研究が、この分析の有効性を示す例として引用される。
第2章 パワー、自由、理性
権力概念をめぐる絶え間ない不一致を認めつつ、なぜこの概念が必要か(実践的、道徳的、評価的文脈において)、そしてその包括的な概念地図が提示される。権力は、行為者(個人または集団)が有意な結果をもたらす能力(「~する力」)として広く定義され、その一部として、他者に対する非対称的な「~に対する力」、特に「支配」が位置づけられる。ミシェル・フォーコーの権力論(権力の生産性、主体化、権力と知識の結びつき)が詳細に検討される。フォーコーの修辞的過激さ(権力からの解放は不可能など)は批判されつつも、その研究が権力の微視的メカニズムを探求する豊かな実証的研究を刺激した功績が評価される。権力の分析は、スピノザの言葉を借りれば、人々が「自らの本性と判断が命じるように生きる」自由をいかにして制限するかを問うものでなければならない。
第3章 三次元的パワー
PRVで提示された権力の定義と主張が再検討され、その欠点(例えば、権力を「行使」に結びつけすぎている点)が認められつつも、支配への自発的同意を確保する「三次元的権力」の核心的テーゼが擁護される。この擁護は、ジェームズ・スコット(被支配者は常に抵抗している)やジョン・エルスター(「適応的選好」は権力によって生み出されえない)からの二種類の強力な批判への応答として行われる。ジョン・スチュアート・ミルによるヴィクトリア朝女性の従属の分析や、ピエール・ブルデューの「ハビトゥス」と「象徴的暴力」の概念は、権力が人々の信念と欲望を形成するメカニズムを理解するための重要な資源として論じられる。最後に、「真の利益」や「虚偽意識」といった問題含みの概念を、尊大さや独断論なしに、どのようにして批判的社会分析において不可欠なものとして保持しうるかが考察される。
第4章 支配と同意
近年の政治理論における「支配(domination)」をめぐる活発な議論(特に「新共和主義」における自由を「支配からの自由」と定義する議論)が検討される。この議論は、支配を、他者の恣意的な意志への依存関係(例えば、主人と奴隷の関係)として特徴づける。ルークスはこの洞察を認めつつも、この定義が、意図的でないものや、行為者間の直接的な関係を超えて作用する構造的・間接的な支配の形態を捉えきれていないと論じる。本書で提唱されるより広い支配の概念は、人々の同意が、選択肢の操作、誤解導き、あるいは不正の歴史によって、自由に与えられたものとは見なせない状況において機能する。この同意は、非強制的でありうるが、それは権力の三次元的な働き——人々の信念と選好への影響——を通じて確保されたものなのである。
第5章 第三の次元の探求
権力の「第四の次元」(主体性の社会的構成に焦点を当てる)を主張する議論に応答しつつ、三次元的枠組みの有効性を維持する。その後、現代における三次元的権力の働きを例示する四つのケーススタディが提示される。(1) ヴァーツラフ・ハヴェルの「無力な者たちの力」:社会主義チェコスロバキアにおける、イデオロギーへの不信と戦略的服従の世界。ここでの権力は、同意を生み出すよりも、見せかけの儀礼的遵守を強制する。(2) シュシャナ・ズボフの「監視資本主義」:データ収集とアルゴリズムによる行動修正と予測を通じて、人々の振る舞いに影響を与え、しばしばその認識能力を迂回させる「器械主義的権力」。(3) ハビエル・アウジェロによるアルゼンチンのスラム「ビジャ・フラマブル」の研究:企業、政府、医師、弁護士など多様な行為者による「有害な不確実性」の生産が、住民の混乱と無力化をもたらし、汚染への抗議を妨げる。(4) ジョン・ガベンタの「パワー・キューブ」:権力の三つの形態(可視的、不可視的、不可視的)、三つの空間(閉鎖的、招待的、主張的)、三つのレベル(地域、国家、地球)を組み合わせた分析フレームワーク。これは、世界中の社会変革の実践と研究において、支配の力学とエンパワーメントの戦略を理解する「使用可能な理論」として機能している。これらの事例は、三次元的権力が、同意を形成し、時には人々の合理的判断能力そのものを損なう、多様で複雑な方法で作用していることを示す。
続きのパスワード記載ページ(note.com)はこちら
注:noteの有料会員のみ閲覧できます。
メンバー特別記事
権力の三次元:見えない支配を可視化する AI考察
by Claude 4.5
権力概念の測定不可能性という根本問題
ルークスが序論で設定する問題は、一見技術的に見えて実は深く存在論的な性質を持つ。所得や富は貨幣という便利な尺度で測定可能だ。しかし権力には、そのような客観的な測定単位が存在しない。これは単なる方法論上の困難ではない。
考えてみると、所得や富の測定可能性は、それらが物質的な交換価値として社会的に構成されているという事実に由来する。貨幣制度という共有された記号体系があって初めて、数値化が可能になる。では権力はどうか。
権力には共有された尺度が存在しない。それはおそらく、権力が単一の次元で測定できる現象ではないからだ。ルークスの議論の核心は、まさにこの点にある。彼は権力を「三次元」で捉えようとする。
第一の次元は顕在的な意思決定における権力だ。これはロバート・ダール(Robert Dahl)らの多元主義的な権力観が捉えようとしたもので、投票や公開討論における勝敗として観察可能な権力行使である。
第二の次元は、バクラックとバラッツ(Bachrach and Baratz)が指摘した非決定の力だ。特定の問題が議題に上がること自体を阻止する権力。これは表面には現れない。会議で何が議論されなかったか、どの選択肢が最初から排除されていたかという不在の次元だ。
三次元目の権力:欲望の形成という最も深い支配
そしてルークスが提示する第三の次元。これが最も論争的で、最も深い洞察を含む。それは人々の欲望や認識そのものを形成する権力だ。
ここで立ち止まって考える必要がある。もし権力が、人々が何を望むか、何を問題と認識するか、何を自然で変更不可能と見なすかを形成できるとしたら、どうなるか。そのとき権力は完全に不可視化される。支配される者自身が、自分の真の利益に反する状況を望むようになる。あるいは、そもそも自分が支配されているという事実を認識できなくなる。
これは虚偽意識の問題と密接に関連する。マルクス主義の伝統では、労働者階級が資本主義体制を内面化し、自らの搾取を自然な秩序として受け入れる状態を虚偽意識と呼んだ。ルークスの三次元的権力概念は、この洞察を一般化し、あらゆる支配関係に適用可能にしたとも言える。
しかし、ここには深刻な認識論的問題が潜んでいる。もし人々の欲望や認識が権力によって形成されているなら、誰が「真の利益」を判定できるのか。外部の観察者が「あなたは本当は別のことを望むべきだ」と言う権利はどこから来るのか。これは家父長主義の危険性を孕む。
ルークスはこの問題を認識している。だが彼は、この困難を理由に三次元的権力概念を放棄すべきではないと主張する。なぜなら、この概念なしでは現代社会における最も深刻な形態の支配を捉えることができないからだ。
構造と主体性の緊張:権力は誰のものか
ルークスの議論を読み進めると、もう一つの根本的な緊張が浮かび上がってくる。それは構造的権力と行為者的権力の関係だ。
第一次元の権力は明確に行為者に帰属する。AがBに何かをさせる。ここでは主体が明確だ。しかし第二次元、特に第三次元になると、権力の所在が曖昧になってくる。欲望を形成する権力は、特定の個人や集団が意図的に行使するものなのか、それとも社会構造や文化、言説の効果として生じるのか。
フーコー(Michel Foucault)はこの問題に対して、権力を関係として、ネットワークとして捉えることで応答した。権力は誰かが所有するものではなく、社会関係全体に遍在する。規律や規範化のメカニズムを通じて、権力は主体そのものを産出する。
ここでフーコーとルークスの違いが鮮明になる。ルークスは依然として、権力を「AがBに対して持つ能力」という枠組みで考えようとする。一方フーコーは、この枠組み自体が権力の作用を捉え損ねると主張する。権力は遍在的で生産的なものであり、単なる抑圧や支配ではない。
しかし、フーコー的な権力観には別の問題がある。もし権力があらゆる場所に遍在し、主体を産出するなら、どこから抵抗が生まれるのか。批判的な視点を取る主体はどこに立脚するのか。権力に完全に構成された主体は、権力を批判できるのか。
グラムシのヘゲモニー:同意の組織化という権力
ルークスはアントニオ・グラムシ(Antonio Gramsci)のヘゲモニー概念に注目する。グラムシは、支配階級が単に暴力や強制によって支配するのではなく、被支配階級の「同意」を獲得することで支配を維持すると論じた。
ヘゲモニーとは、特定の世界観や価値体系を社会全体の「常識」として確立することだ。資本主義社会において、自由市場経済が唯一の合理的システムとして受け入れられる。競争が自然で望ましいものとされる。個人の成功は自己責任とされる。これらは自明の真理ではなく、歴史的に構築されたヘゲモニーの産物だ。
グラムシの洞察は、ルークスの三次元的権力概念に理論的基盤を提供する。支配は物理的強制だけでなく、むしろ主に文化的・イデオロギー的な領域で作動する。学校、メディア、宗教、家族といった「市民社会」の諸制度を通じて、支配的な価値観が再生産される。
ここで興味深いのは、ヘゲモニーが決して完全ではないという点だ。グラムシは「陣地戦」という概念で、支配的イデオロギーに対する長期的な対抗文化の構築を説いた。もしヘゲモニーが完璧なら、抵抗は不可能になる。しかし現実には、支配的価値観に対する疑念や亀裂が常に存在する。
ブルデューの象徴的暴力:身体化された支配
ピエール・ブルデュー(Pierre Bourdieu)は、さらに精緻な分析を提供する。彼の象徴的暴力概念は、支配が単なる意識のレベルではなく、身体そのものに刻み込まれることを示す。
ブルデューの「ハビトゥス」概念は重要だ。これは、社会的に形成された知覚、思考、行為の持続的な性向だ。階級社会で育った人間は、特定の身振り、話し方、好みを無意識のうちに身につける。これらは単なる表層的な習慣ではなく、その人の存在様式を規定する。
例えば、労働者階級出身の学生が大学に入学したとき、中産階級の文化的規範に違和感を覚える。その違和感は頭で理解できるものではなく、身体的な居心地の悪さとして経験される。これは意識的な洗脳ではない。社会構造が身体化されているのだ。
ブルデューの分析が示すのは、支配が前言語的・前反省的なレベルで作動するという事実だ。人々は自分が支配されていることを認識する前に、すでにその支配を身体的に受け入れている。この洞察は、ルークスの三次元的権力をさらに深化させる。
しかし、ブルデューの理論には批判もある。ハビトゥスがあまりに決定論的に描かれているのではないか。人々は自分の社会的条件づけを反省し、乗り越える可能性を持つのではないか。
真の利益と適応的選好:判断の基準をどこに置くか
三次元的権力概念の最大の難問に戻ろう。人々の欲望が権力によって形成されているなら、「真の利益」をどう判定するか。
ルークスは、人々が「自律的」に判断できる状況を想定する。もし人々が完全な情報を持ち、強制されることなく、熟慮の末に選択したなら、その選択は真の利益を反映すると考えられる。しかし、このような理想的状況は現実には存在しない。
ハーバーマス(Jürgen Habermas)の「理想的発話状況」は、似た発想だ。権力関係のない対話の場で、合理的な討議を通じて到達される合意が、真の共通利益を表すという考え方だ。しかし批判者は問う。そのような場は可能なのか。すでに権力関係に浸透された主体が、権力から完全に自由な対話をできるのか。
適応的選好形成という概念がある。これはジョン・エルスター(Jon Elster)らが発展させた考えで、人々は達成不可能な目標を望むのをやめ、実現可能な範囲で満足するよう自分の選好を調整するというものだ。「酸っぱい葡萄」の寓話のように。
この概念は、三次元的権力を理解する鍵になる。女性が伝統的な性役割を「自発的に」受け入れる場合、それは本当に自由な選択なのか、それとも家父長制社会で生き延びるための適応なのか。この区別は容易ではない。
ただし、ここで注意すべきは、外部の知識人が安易に「彼らは虚偽意識に囚われている」と断じる傲慢さだ。被支配者の主体性を尊重しながら、同時に構造的抑圧を分析する、この微妙なバランスが必要だ。
ハヴェルの「無力な者の力」:抵抗の可能性
ヴァーツラフ・ハヴェル(Václav Havel)の有名なエッセイ「無力な者の力」は、全体主義体制下での三次元的権力の作動を描き出す。共産主義チェコスロバキアでは、人々は体制のイデオロギーを内面化することを強制された。しかし同時に、誰もがそのイデオロギーの欺瞞を知っていた。
ハヴェルが描く八百屋の例は印象的だ。店の窓に「世界の労働者よ、団結せよ!」というスローガンを掲げる。八百屋はそれを信じていない。しかし掲げる。なぜか。掲げないことのコストが高いからだ。そして他の誰もが同じことをしているからだ。
これは「真実の中で生きる」ことの困難さを示す。しかしハヴェルは、まさにこの欺瞞的な体制において、真実を語ることが最も根本的な抵抗行為になると主張する。嘘の体系は、一人でも真実を語る者がいれば、その脆弱性を露呈する。
ハヴェルの洞察は重要だ。三次元的権力がどれほど深く浸透しても、それは決して完璧ではない。人々は自分が演じている役割と、自分の内面的な真実との間の亀裂を感じる。その亀裂こそが、抵抗の可能性を開く。
現代の権力:アルゴリズムと監視資本主義
ルークスの理論を現代に適用すると、新たな権力形態が見えてくる。デジタル技術とアルゴリズムは、三次元的権力の新しい形を生み出している。
ショシャナ・ズボフ(Shoshana Zuboff)の「監視資本主義」概念は示唆的だ。グーグルやフェイスブックのようなプラットフォームは、利用者の行動データを収集し、その行動を予測し、さらには形成する。推薦アルゴリズムは、人々が何を見て、何を読み、何を買うかに影響を与える。
これは前例のない規模の三次元的権力だ。人々は自分が操作されていることを認識しない。むしろ、アルゴリズムが提示する選択肢を自分の自由意志による選択と信じる。
さらに問題なのは、このシステムが個別化されている点だ。かつての大衆操作は、マスメディアを通じた画一的なメッセージ伝達だった。しかし現代のアルゴリズムは、各個人に最適化されたメッセージを送る。抵抗するためには、まず自分が操作されていることに気づく必要があるが、その気づき自体が困難になっている。
中国の社会信用システムは、この傾向の極端な例だ。人々の行動がすべて監視され、点数化される。「良い市民」には特典が与えられ、「悪い市民」には制裁が加えられる。これは単なる監視ではない。人々の行動様式、価値観、欲望そのものを形成するシステムだ。
新自由主義の主体化:企業家的自己という規範
フーコーが晩年に分析した「統治性」概念も、現代の三次元的権力を理解する鍵だ。新自由主義は、単なる経済政策ではない。それは特定の主体性の形式を産出する。
新自由主義的主体は、自分自身を「人的資本」として管理する。自己投資し、自己ブランディングし、常にスキルアップを目指す。失業や貧困は「自己責任」とされる。この論理の下では、構造的な不平等は個人の努力不足に還元される。
ここで作動しているのは、明示的な強制ではなく、規範の内面化だ。人々は強制されて企業家的自己になるのではなく、それが「正常で望ましい」主体のあり方として提示される。そしてその規範に適合できない者は、自分を責める。
バーンアウト、うつ病、不安障害の蔓延は、この新自由主義的主体化の病理的帰結かもしれない。人々は常に自己最適化を強いられ、休息することさえも「生産的」でなければならない。
対抗権力の構築:集合的な認識と組織化
では、三次元的権力に対してどのような抵抗が可能なのか。ルークスやグラムシの議論から導かれるのは、対抗文化と対抗ヘゲモニーの構築の必要性だ。
まず必要なのは集合的な意識覚醒だ。個々人が孤立して自分の状況を「個人的な問題」と認識している限り、抵抗は生まれない。フェミニズムのスローガン「個人的なことは政治的なこと」は、この洞察を表現している。女性たちが自分の経験を共有し、それが個人の失敗ではなく構造的な性差別の結果だと認識したとき、運動が始まった。
次に必要なのは代替的な制度と実践の創造だ。既存の権力構造に対抗するだけでは不十分で、別の生き方、別の組織形態を実験する必要がある。協同組合、コミュニティ通貨、参加型民主主義の実践など。
ジョン・ホロウェイ(John Holloway)の「権力を取らずに世界を変える」という提起は示唆的だ。国家権力の奪取を目指す従来の革命戦略は、結局新しい支配構造を生み出すだけだった。むしろ、既存の権力構造の外側に、別の社会関係を構築することが重要だという主張だ。
しかし、この戦略にも限界がある。資本主義と国家の権力は、あらゆる領域に浸透している。完全に「外側」に立つことは可能なのか。小さな対抗的空間は、容易に包摂され、商品化されてしまうのではないか。
認識論的謙虚さと政治的実践の緊張
最後に、ルークスの議論が投げかける根本的な問いに向き合う必要がある。私たちは他者の「真の利益」を知ることができるのか。
正直に言えば、完全な確信を持って答えることはできない。しかし、それは相対主義に陥る理由にはならない。ある種の暫定的な判断は可能であり、必要だ。
例えば、明らかな身体的危害は誰の利益にもならないと言える。飢餓、拷問、奴隷制は、「文化的相対主義」で正当化できない。ここには最低限の普遍的基準がある。
また、選択の条件を問うことはできる。ある選択が、暴力や脅迫の下でなされたなら、それは自由な選択ではない。情報が組織的に隠蔽されている状況での選択は、真の選択ではない。選択肢自体が不当に制限されているなら、その「選択」は自律的ではない。
さらに、被支配者自身の声に耳を傾けることは可能だし、必要だ。抑圧された集団が自ら組織し、自らの状況を分析し、要求を掲げるとき、その声には特権的な地位がある。外部の知識人の分析よりも。
日本社会における三次元的権力
ルークスの理論を日本の文脈で考えると、独特の権力作動が見えてくる。日本社会では、明示的な命令や強制よりも、「空気を読む」という形での権力行使が顕著だ。
この「空気」は、まさに三次元的権力の典型だ。明確な規則として存在しないが、強力な規範として作動する。「場の雰囲気」を壊さないように、「和」を乱さないように、人々は自己検閲する。そして、この同調圧力に従うことを「成熟した大人」の態度として内面化する。
企業社会における「社畜」化も、三次元的権力の産物だろう。長時間労働や理不尽な命令への服従が、「会社への忠誠」として美徳化される。過労死すら、個人の「頑張りすぎ」として処理され、構造的問題として認識されにくい。
福島原発事故後の状況も示唆的だ。放射能への懸念を口にすることが「風評被害を広げる」として非難される。「絆」や「復興」という言葉が、批判的思考を封じる装置として機能した。これは、善意や連帯という肯定的な価値を通じた権力行使だ。
しかし同時に、日本社会にも抵抗の系譜がある。学生運動、反原発運動、反基地闘争。そして日常レベルでの小さな不服従。完全な同調圧力の社会など存在しない。
権力は遍在する。しかし抵抗もまた遍在する。ルークスの理論が教えるのは、権力を可視化し、その作動メカニズムを理解することの重要性だ。それは抵抗の第一歩である。完全な解放が不可能だとしても、より自律的な、より公正な社会への漸進的な変革は可能なはずだ。そう信じることもまた、権力への抵抗の一形態なのかもしれない。
