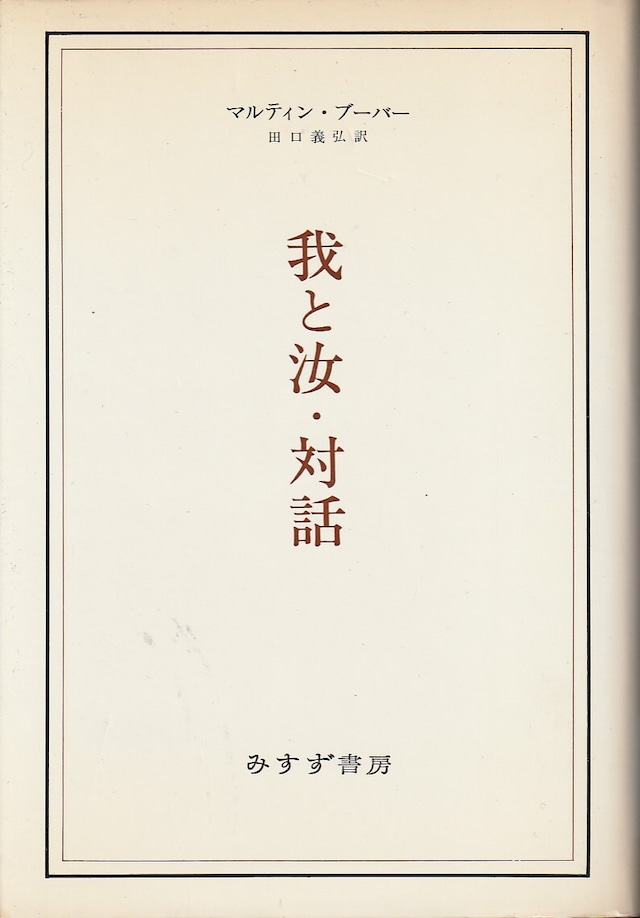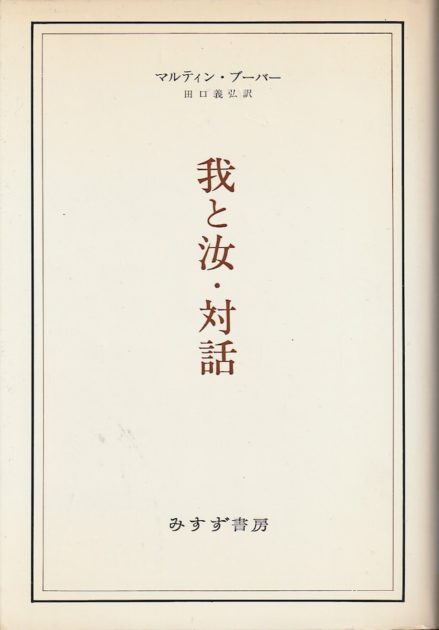
『I AND THOU』Martin Buber 1923
目次
- 第一の部 / First Part
- 第二の部 / Second Part
- 第三の部 / Third Part
- 放棄された計画 / A Plan Martin Buber Abandoned
- あとがき / Afterword
本書の概要:
短い解説:
本書は、人間の存在の根本的な二つの態度、「私-汝」と「私-それ」の関係性を探求し、真の対話と出会いを通じてのみ、自己、世界、そして神とのかかわりが可能になることを示す。宗教的、哲学的関心を持つ読者に向けて書かれた。
著者について:
マルティン・ブーバー(1878-1965)は、オーストリア生まれのユダヤ系哲学者・宗教思想家である。ハシディズムの思想の紹介や、ザイオニズム運動への参加でも知られる。その思想の核心は「対話的哲学」にあり、本書はその代表作である。彼は第一次世界大戦後の人間疎外の時代において、真の共同体と個人の再生を「対話」に求めた。
主要キーワードと解説
- 主要テーマ:関係性の哲学 [人間存在の根源は単独の「私」ではなく、「私」と「汝」の出会いにあるとする]
- 新規性:二つの基本語 [「私-汝」と「私-それ」という二つの根源的な言葉(態度)によって世界は二重に構成されると説く]
- 興味深い知見:永遠の汝 [すべての個別的な「汝」との出会いの彼方に、絶対的な「永遠の汝」としての神を見出す]
3分要約
本書『私と汝』は、人間の世界に対する二つの根本的な態度を「私-汝」と「私-それ」という二つの「基本語」として提示する。この二つの言葉は単なる言葉ではなく、人間が世界とかかわる根本的な姿勢、存在の様式そのものを表している。
「私-それ」の関係は、世界を経験し、利用する対象として扱う態度である。ここでは、世界は時空間の中に秩序立てられ、因果関係によって説明可能な「それ」の集合体となる。「私」もまた、この関係においては、対象を経験し使用する主体としての「自我」に過ぎない。この態度は人間生活に不可欠ではあるが、それだけでは世界は意味を失い、人間は疎外されてしまう。
これに対して「私-汝」の関係は、全体存在をもって他者と向き合い、直接的な出会いと応答を行う態度である。この関係においては、「汝」は決して対象ではなく、一切の媒介物を排した直接性において「私」の前に現れる。例えば、一本の樹を単に観察の対象(それ)として見るのではなく、その全体存在をもって我々と関わる生きた存在(汝)として出会うことがありうる。この出会いにおいてのみ、世界は意味と現実性を与えられる。
この「私-汝」の関係は三つの領域に現れる。第一は自然との関わりであり、ここでは関係は言語の閾に留まる。第二は人間同士の関わりであり、ここでは関係は言語において完全に実現される。第三は精神的な存在との関わりであり、ここでは関係は言語を欠くが、それを創造する。
しかし、すべての「汝」は、その関係の出来事が過ぎ去れば、必然的に「それ」へと変化せざるを得ない。これが人間の悲劇的な運命である。唯一、この運命から免れうるのが、「永遠の汝」としての神との関係である。神との「私-汝」の関係は、他のすべての「私-汝」の関係を包括し、それらをその中で止揚する。すべての個別的な「汝」は、「永遠の汝」への窓なのである。
第二の部では、歴史の中で「それ」の世界が肥大化し、人間の関係性をつくる力が衰えていく様が描かれる。制度と感情が分離した現代社会は、真の共同性を失っている。このような「病んだ時代」において必要なのは、「回帰」、すなわち関係性の中心へと立ち返ることである。自由と運命は、この回帰の決断において初めて約束され合うのである。
第三の部では、「永遠の汝」としての神との関係が論じられる。ブーバーは、神を論証の対象としてではなく、出会いと対話の相手として捉える。神への関係は、世界からの逃避ではなく、世界をその本来の根拠において見つめ直すことによって可能となる。すべての真の生は出会いであり、すべての出会いは神への呼びかけを含んでいる。この関係においてのみ、人間はその存在の全体性と意味を見出すのである。
各章の要約
第一の部
人間の世界は、その二重の態度に応じて二重である。人間の態度は、彼が口にすることのできる二つの基本語、「私-汝」と「私-それ」に応じて二重である。「私-それ」の関係は、世界を経験し使用する態度であり、世界は時空間の中で秩序立てられた対象の世界となる。これに対して「私-汝」の関係は、一切の媒介物を排した直接的な出会いであり、ここでは「汝」はもはや対象ではなく、関係そのものが重要となる。この関係は自然、人間、精神的存在という三つの領域に現れる。例えば、樹を「汝」として出会うとき、それはもはや観察の対象ではなく、我々と相互に働きかける生きた存在となる。しかし、すべての「汝」は、関係の出来事が過ぎ去れば、必然的に「それ」へと変容する。この悲哀の中にあって、すべての個別的な「汝」との出会いは、「永遠の汝」への窓なのである。
第二の部
人類の歴史と個人の歴史は、「それ」の世界の増大という点で一致する。この「それ」の世界の進歩は、人間の関係性をつくる力の減退を伴う。精神とは、人間が「汝」に応答するときに現れるものであり、それは「私」と「汝」の「間」に成立する。しかし、この応答は「汝」を「それ」へと縛り付けてしまう。現代社会では、制度と感情が分離し、真の共同性と人格的生き方が失われている。経済や国家といった「それ」の世界の機構が人間を支配し、因果性と運命のドグマが人間の自由を圧迫する「病んだ時代」において、必要なのは「回帰」である。回帰とは、関係性の中心へと立ち返り、埋もれた関係性の力をよみがえらせることであり、この決断においてのみ、自由と運命は意味を見いだす。自己を「自我」として閉じこもるのではなく、「人格」として他者と世界に関わるとき、人間は真の現実性を得るのである。
第三の部
すべての「私-汝」の関係の延長線上に、「永遠の汝」が存在する。あらゆる個別的な「汝」はその一端であり、あらゆる「汝」を通して我々は「永遠の汝」へと呼びかける。神を「それ」として語ることはできない。神は常に「汝」としてのみ語りかけられる対象である。神との純粋な関係に入るために必要なのは、感覚世界を捨て去ることではなく、現在を全面的に受け入れることである。この関係は、他のすべての「私-汝」の関係を包括し、世界をその本来の根拠に置き直す。神は「全くの他者」であると同時に「全くの現前」なのである。神との関係は、世界からの逃避をもたらすのではなく、世界のうちで意味を実証する使命(ミッション)として現れる。これは「回心」や「没我」ではなく、「回帰」の道なのである。歴史を通じて、神の言葉は、生き生きとした関係として現れ、やがて形式化され、時に死んだものとなるが、新たな回帰によって再び甦る。この神の側から見た出来事を、ブーバーは「贖罪」と呼ぶ。
我と汝:相互性の哲学における存在の深層考察
by Claude 4.5
ブーバーの革命的視点:関係性こそが実在である
マルティン・ブーバーの『我と汝』は、一見すると神秘主義的な宗教書のように見える。しかし本書の核心は、極めて具体的で現実的な主張にある。それは「関係性が存在に先行する」という洞察だ。
ブーバーは冒頭で「根源語は単独の語ではなく、語の対である」と宣言する。我々は「我―汝」か「我―それ」のいずれかの根源語を語る。この二つの態度によって、世界は二重に現れる。ここで重要なのは、「我」が先にあって「汝」や「それ」と関係するのではないという点だ。根源語を語ることが存在様式を確立するのである。
これは西洋哲学の伝統に対する根本的な挑戦である。デカルトの「我思う、ゆえに我あり」は、孤立した自我の確実性から出発する。しかしブーバーにとって、孤立した「我」など存在しない。「我―汝」の我と「我―それ」の我は異なる。「我」は常にすでに関係の中にある。
「我―汝」と「我―それ」:経験を超えた関係性
「我―それ」の世界は経験と使用の世界である。我々は物事を知覚し、感じ、想像し、欲する。この活動は目的指向的な動詞の領域に属する。ブーバーはこの領域を否定しない。むしろ人間の生は「我―それ」なしには成り立たないと認める。
しかし「我―汝」の関係は根本的に異なる。「汝と語る者は、何かを対象として持たない」。汝には境界がない。「我―汝」を語る者は、何も持たないが、関係の中に立つ。
ブーバーは三つの領域を区別する。第一に自然との生活、第二に人間との生活、第三に精神的存在との生活。これらすべての領域において、我々は「永遠の汝」の列車を見つめる。あらゆる個別の「汝」を通じて、我々は永遠の汝に語りかける。
木を見つめる例は印象的だ。私は木を絵として受け入れることができる。運動として感じることができる。種に割り当て、法則の表現として認識することができる。これらすべてにおいて、木は「それ」であり、対象である。
しかし「もし意志と恩寵が結びつくならば」、私が木を観想する時、私は関係の中に引き込まれ、木は「それ」であることをやめる。排他性の力が私を捉える。木のすべて―その形態、力学、色彩、化学、要素との対話、星々との対話―が全体として含まれる。木は私に対して身体的に対峙し、私が木と関わらなければならないように、木も私と関わらなければならない。
「関係は相互性である」とブーバーは断言する。これは形而上学的主張ではなく、生きられた現実の記述である。
芸術と創造:形態との出会い
ブーバーの芸術論は彼の関係哲学の中核的応用例である。芸術の永遠の起源は、「人間が彼を通じて作品になろうとする形態に対峙すること」にある。
重要なのは、これが魂の虚構ではないという点だ。魂に現れ、魂の創造力を要求する何かが存在する。必要なのは「人間が全存在をもって行う行為」である。彼が全存在をもって形態に根源語を語るとき、創造力が解放され、作品が生まれる。
この行為には犠牲と危険が伴う。犠牲とは、無限の可能性を形態の祭壇に捧げることである。危険とは、根源語は全存在をもってのみ語られ得るということだ。自分を部分的に留保することはできない。
創造は発見である。形成は見出しである。私が実現する時、私は覆いを取る。私は形態を「それ」の世界へと導く。創造された作品は物の中の一つの物となり、質の集合として経験され記述され得る。しかし受容的な観照者は、時折身体的に対峙されるかもしれない。
現在という時間:汝の存在論
「本質的なものは現在において生きられ、対象は過去において生きられる」。この命題はブーバーの時間論の核心である。
充実した現在は、現前性、出会い、関係が存在する限りにおいてのみ存在する。「汝」が現前するようになることによってのみ、現在は生じる。
「我―それ」の基本語の「我」、つまり「汝」に身体的に対峙されておらず、多数の「内容」に囲まれている「我」は、過去しか持たず、現在を持たない。人間が経験し使用する物事で済ませる限り、彼は過去に生き、彼の瞬間は現前を持たない。彼は対象しか持たない。そして対象は「かつてあったもの」から成る。
しかし「汝」の世界は時間と空間において結合していない。個別の「汝」は関係の出来事が終わると「それ」にならざるを得ない。個別の「それ」は関係の出来事に入ることによって「汝」になり得る。
これは「我―それ」の世界の二つの特権である。しかしこれらの特権は、人々に「我―それ」の世界を、人が生きなければならず、また快適に生きることもできる世界として考えさせる。この堅固で健全な年代記において、「我―汝」の瞬間は奇妙な叙情的・劇的エピソードとして現れる。
ブーバーは率直に問う。「純粋な現在において生きることはできない。それは我々を消費してしまうだろう」。しかし「純粋な過去においては生きることができる。実際、そこでのみ生活を整えることができる」。
それでも真理の深刻さにおいて聞くべきである。「それなしには人間は生きられない。しかしそれだけで生きる者は人間ではない」。
関係の衰退と精神の本質
ブーバーによれば、個人の歴史も人類の歴史も「我―それ」の世界の漸進的増大を意味する。各文化の「我―それ」の世界は前任者のそれよりも包括的である。経験し使用する能力の向上は、一般的に人間の関係する力の減少を伴う。
「人間の精神の現れとしての精神は、人間の汝に対する応答である」。言語の精神は真の出来事の屈折にすぎない。「真理において言語は人間の中にあるのではなく、人間が言語の中に立ち、そこから語るのである」。すべての精神についても同様である。「精神は我の中にあるのではなく、我と汝の間にある」。
精神は人が汝に応答できる時に生きる。彼は全存在をもってこの関係に入る時にそれができる。人間が精神において生きることができるのは、ひとえに彼の関係する力によってである。
しかし関係的出来事の運命が最も強力に立ち上がるのもここである。応答が強力であればあるほど、それは汝を強力に縛り付け、呪文によって対象へと変える。対象となったものはその意味と運命を授けられている―常に再び変化して戻る運命、現在へと戻る運命を。
だが「我―それ」の世界と和解した人間は、物事を解放する代わりに縛り付けたままにする。彼は物事に注意を払う代わりに観察し、受け取る代わりに利用する。
共同体と制度:分離の病理
ブーバーは人間の共同生活を二つの明確に定義された地区に分割されたと診断する。制度と感情である。「制度は『外にある』もので、そこで様々な目的のために時間を過ごし、働き、交渉し、影響を及ぼし、組織し、管理し、説教する場所である。感情は『内にある』もので、そこで人は生き、制度から回復する場所である」。
しかしこの分離は虚偽である。「制度は公共生活をもたらさない。感情は個人生活をもたらさない」。真の共同体は、すべての成員が単一の生きた中心に対して生きた相互関係に立ち、互いに対して生きた相互関係に立つことによってのみ生じる。
真の公共生活と真の個人生活は結合の二つの形態である。それらが生じ持続するためには、変化する内容としての感情と、恒常的形式としての制度が必要である。しかしこれら両者の組み合わせさえも、第三の要素によってのみ創造される人間の生を創造しない。その第三の要素とは、「汝」の中心的現前、あるいはより真実に語れば、現在において受け取られる中心的「汝」である。
国家が経済を規制するか、経済が国家を指揮するかは、両者が変わらない限り重要ではない。決定的なのは、精神―「汝」を語り応答する精神―が生き実在し続けるかどうか、共同的人間生活に残るものが国家と経済に従属し続けるか独立して活動的になるか、個人的人間生活に残るものが再び共同生活に組み込まれるかである。
自由と運命:決定の形而上学
「我―それ」の世界において因果性は無制限の支配力を持つ。しかし「我―それ」の世界に閉じ込められておらず、「我―汝」の世界へと繰り返し出て行くことができる人間は、因果性の支配を抑圧的だとは感じない。ここで「我」と「汝」は因果性に巻き込まれることのない自由な相互性において互いに対峙する。
「決定を下す者は自由である。なぜなら彼は顔の前に立ったからである」。私の意志能力のすべての燃える物質が手に負えずに湧き上がり、私に可能なすべてのものが原初的に回転し、もつれ合い分離不可能に見える時、可能性の誘惑的な視線があらゆる角から燃え上がる時、宇宙は誘惑として、そして私は瞬時に生まれ、両手を火の中に、深く、私を意図する者が隠されている場所に、私の行為を掴む。今だ!そして直ちに深淵の脅威は抑えられる。
ここでは意志が実在する。しかしこの自由は孤立した自我の恣意性ではない。自由と運命は互いに約束されている。運命は自由を実現する者にのみ出会われる。
病んだ時代においては、「我―それ」の世界が「我―汝」の世界からの生きた流れによって灌漑され肥沃にされなくなり、分離され停滞して、巨大な沼の幻影となり人間を圧倒する。因果性が抑圧的で破壊的な運命へと成長する。
神:永遠の汝
「拡張された関係の線は、永遠の汝において交差する」。個々の汝はそれへの一瞥である。個々の汝を通じて、根源語は永遠の汝に語りかける。
人々は多くの名前で永遠の汝に語りかけてきた。彼らが命名したものについて歌った時、彼らはまだ「汝」を意味していた。最初の神話は賛美の賛歌だった。その後、名前は「それ」の言語に入った。人々はますます永遠の汝を「それ」として考え、それについて語ることを強いられたと感じた。
神という言葉の使用を否定する者もいる。なぜならそれがあまりにも誤用されてきたからである。確かにそれはすべての人間の言葉の中で最も重荷を負わされた言葉である。まさにそれゆえに、それは最も不滅で避けがたい言葉である。
神の本性と業についてのすべての誤った語り(そのような語りはすべて常に誤っていたし、これからもそうであろう)は、すべての人が神に語りかける時に本当に彼を意味していたという一つの真理と比較して、どれほどの重みがあるだろうか。「神」という言葉を発し、本当に「汝」を意味する者は、彼の妄想が何であれ、他のすべてのものによって制限され得ない、彼の生の真の「汝」に語りかけており、他のすべての関係を含む関係において彼に立っている。
啓示と人間の応答
ここと今において現前する永遠の啓示が何であるかについて、ブーバーは驚くべき主張をする。「それは人間が至高の出会いの瞬間から出現し、入った時と同じではなくなることである」。
出会いの瞬間は、受容的な魂の中で湧き起こり至福に丸くなる「生きられた経験」ではない。何かが人間に起こる。時にはそれは息吹を感じるようであり、時には格闘のようである。どうであれ、何かが起こる。
純粋な関係の本質的行為から出てくる人間は、彼の存在に何か「より多くのもの」を持っている。彼が以前に知らなかった新しい何かがそこに成長した。聖書の言葉で言えば、「神を待つ者は交換に力を受け取る」。
人間は受け取る。そして彼が受け取るものは「内容」ではなく現前であり、力としての現前である。この現前と力は三つの要素を含む。第一に、実際の相互性の全豊穣、関与されること、結合されること。第二に、意味の言い表せない確認。それは保証されている。何も、何も、今後無意味であり得ない。人生の意味についての問いは消滅した。そして第三に、この意味は「別の生」の意味ではなく、この我々の生の意味であり、「彼岸」のそれではなく、この我々の世界のそれであり、それはこの生とこの世界において我々によって示されることを望んでいる。
意味それ自体は普遍的に妥当で一般的に受け入れ可能な知識の断片として伝達されたり表現されたりすることはできない。行為においてそれを試すことも、妥当な当為として手渡すことはできない。我々が受け取る意味は、各人の存在の独自性と彼の生の独自性においてのみ、行為において試すことができる。
現代への問い:テクノロジーと監視の時代に
ブーバーのテキストは1923年に書かれたが、その診断は現代により鋭く当てはまる可能性がある。彼は「我―それ」の世界の増殖を警告した。今日、我々はアルゴリズムとデータによって中介された世界に生きている。ソーシャルメディアは「つながり」を約束するが、しばしば人々を「それ」に還元する―プロフィール、データポイント、ターゲット可能な人口統計に。
ブーバーは「病んだ時代」において、「我―それ」の世界が「巨大な沼の幻影」になると書いた。これは、監視資本主義の時代、すべてが測定され最適化され収益化される時代の予言的記述ではないか。
彼の解決策は単純だが深遠である。帰還である。「我―汝」の関係への帰還、他者の現前への帰還、聖なるものへの帰還。「何も人間を運命づけることはできない。ただ運命への信念が、なぜならこれが帰還の運動を妨げるからである」。
これは後戻りへの呼びかけではない。ブーバーは技術や科学を拒絶しない。彼はそれらを「我―汝」の精神によって浸透させることを求める。「この世界から離れて」神を見出すのではなく、世界を神の中で見ることによって。
批判的考察と限界
ブーバーの思想は強力だが、いくつかの問題も抱えている。
第一に、彼の言語は意図的に曖昧である。彼自身が認めるように、「霊感の呪縛の下で書いたものを変更してはならない。たとえ正確さのためであっても」。この神秘化は深遠さの印象を与えるが、批判的検討を困難にする。
第二に、彼の木や猫との「我―汝」関係の例は、多くの読者には非合理的に見えるかもしれない。動物や自然との相互性という彼の主張は、人間中心主義を避けようとする現代の試みと共鳴するが、これらの例における「相互性」の正確な性質は不明確なままである。
第三に、ブーバーの政治的含意は曖昧である。彼は共同体を主張するが、具体的な社会的・経済的構造については限定的な指針しか提供していない。
第四に、彼の神論は一神教の枠組みに深く埋め込まれている。無神論者や非有神論的伝統からの人々にとって、「永遠の汝」は疎外的に見えるかもしれない。
しかし、これらの限界にもかかわらず、ブーバーの中心的洞察―関係性が存在に先行すること、真の出会いは相互的であること、人生は「我―それ」と「我―汝」の間の交替であること―は耐久性のある力を持つ。
現代において、我々がますます画面を通じて、アルゴリズムを通じて、データを通じて中介される時、ブーバーの呼びかけはより緊急である。直接性へ、現前へ、相互性へ―一言で言えば、人間性そのものへ。