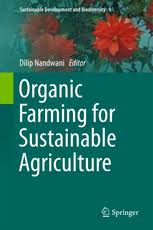Contents
Human health implications of organic food and organic agriculture: a comprehensive review
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5658984/
要旨
このレビューでは、有機食品が人間の健康に与える影響に関する既存の証拠を要約している。人間の健康に重要なパラメータに関して、有機食品と従来の食品生産を比較し、EUの条件に重点を置いて有機的な管理慣行の潜在的な影響を論じている。
有機食品の消費は、アレルギー性疾患のリスクと太りすぎや肥満のリスクを減らすことができるが、有機食品の消費者が全体的に健康的なライフスタイルを持っている傾向があるので、証拠は、おそらく残留交絡に起因する決定的なものではない。しかし、動物実験では、有機または従来の生産から同一に構成された飼料は、成長と開発に異なる方法で影響を与えることを示唆している。
有機農業では、農薬の使用は制限されており、従来の果物や野菜の残留物は、人間の農薬曝露の主なソースを構成している。疫学研究では、現在の暴露レベルでの子どもの認知発達に対する特定の農薬の悪影響が報告されているが、これらのデータはこれまでのところ、個々の農薬の正式なリスク評価には適用されていない。
有機農作物と慣行農作物の間の組成の違いは限られており、例えば有機果物や野菜のフェノール化合物の含有量がやや高く、有機穀物作物のカドミウムの含有量も低い可能性がある。有機乳製品、そしておそらくまた肉は、従来の製品に比べてオメガ3脂肪酸の含有量が高い。しかし、これらの違いは、限界の栄養学的意義の可能性がある。
より大きな懸念は、社会における抗生物質耐性のキードライバーとして、従来の動物生産における抗生物質の普及した使用であり、抗生物質の使用は、有機生産ではあまり集中的である。
全体的に、このレビューでは、有機食品生産に関連するいくつかの文書化された可能性の高い人間の健康上の利点を強調しており、そのような生産方法の適用は、例えば、統合的な害虫管理で、従来の農業の中で有益である可能性が高い。
キーワード
農作物、抗生物質耐性、食品安全性、栄養素、有機食品、残留農薬
背景
持続可能な食糧システムを開発するという長期的な目標は、いくつかの政府間組織によって高い優先度を持つと考えられている[1-3]。異なる農業管理システムは、人間の健康だけでなく、動物の健康、食糧安全保障、環境の持続可能性にも影響を及ぼす可能性があるため、食糧システムの持続可能性に影響を及ぼす可能性がある。本論文では、農業システム(慣行栽培と有機栽培)と人間の健康との関連性について、利用可能なエビデンスをレビューする。
食品生産方法を分類するのは必ずしも容易ではない。この複雑さは、従来型と有機農業システムの数や形態の多様性だけでなく、これらのシステムの重複に起因するものである。この論文では、欧州連合(EU)における集約的農業の支配的なタイプとして「在来型農業」という用語を使用し、一般的に合成農薬や鉱物性肥料を大量に投入し、動物生産における従来生産された濃縮飼料の割合が高い。逆に「有機農業」とは、EUの規制または有機生産の類似基準に準拠したもので、農地や緑肥などの有機肥料の使用、生態系サービスへの優勢な依存、害虫の予防と防除のための非化学的措置、家畜が露地や粗飼料を利用できることなどで構成されている。
2015年には、世界179カ国で5,090万ヘクタール以上が有機栽培されており、その中には転換中の地域も含まれている[4]。有機栽培の管理下にある面積(完全転換および転換中の面積)は、有機生産のための拘束力のある基準が開発された欧州連合(EU)では、この数十年の間に増加している[5, 6]。現在のEUを形成する28カ国では、総農地面積に占める有機栽培地の割合は、過去30年間で着実に増加している。1985年、1995年 2005,2015年には、農地の0.1%,0.6%、3.6%、6.2%がそれぞれ有機栽培であり 2015年には1,120万haに相当する[7-9]。7つのEU加盟国では、農地の少なくとも10%が有機栽培である[7]。2003年には、EU内の125,000の農場が有機農業に積極的に取り組んでいたが、その数は2013年には185,000に増加した[10]。2006年から 2015年の間に、EUのオーガニック小売市場は107%成長し、271億ユーロに達した[7]。
本レビューでは、有機食品と有機食品生産が人の健康に及ぼす影響に関する科学を詳しく解説し、以下のような
- 1. 疫学的研究や臨床試験で直接そのような効果に対処する研究。
- 2. 従来の飼料や食品と比較して有機物の生物学的効果を評価する動物試験および試験管内試験試験の研究。
生産のより狭い側面に焦点を当て、次に、生産システムの影響を議論する
- 3. 植物保護、農薬曝露、農薬の人体への影響
- 4. 植物の栄養、作物の組成と人間の健康のための関連性。
- 5. 動物の給餌レジメン、動物性食品の組成への影響、および人間の健康との関連性。
- 6. 動物の健康と幸福、動物生産における抗生物質の使用、抗生物質耐性の発達におけるその役割、そして公衆衛生に対する抗生物質耐性の結果。
議論の中では、生産システムから食品システムと持続可能な食生活へと視点を広げ、農業生産システムと個々の食の選択の相互作用に取り組む。公衆衛生上のこれらの側面の結果は、簡単に議論されている。
限られた証拠ベース、最小限の重要性、生産システムと健康の間のもっともらしいリンクの欠如、または欧州連合における関連性の欠如のために、我々は以下の点には触れていないか、または簡単にしか触れていない。
- 生産システムに明確な原因がない病気の発生(植物生産と家畜の屠殺・加工の衛生規制は、有機農業と慣行農業ではほとんど同じ)や、飼料市場への汚染飼料の不正な導入など、食品安全上の特異な事象。
- 歴史的な出来事と歴史的な被ばく源、例えば、現在では禁止されている牛の肉や骨粉を牛に与える習慣によって引き起こされたBSE危機や、現在では世界的にすべての農業分野で禁止されているDDTの歴史的な使用による継続的な影響などの歴史的な出来事と被ばく源
- 食品添加物
- 食品添加物などの食品加工の側面
- 収穫後の貯蔵と加工の結果としてのマイコトキシンの存在は、主に貯蔵中の水分と温度に支配される。
- 成長ホルモン剤の動物生産への使用
さらに、生物多様性や温室効果ガスの排出など、環境の持続可能性の側面は、農業生産システムによっても影響を受ける可能性があり[11, 12]、また、食料安全保障を通じた人間の健康に影響を与える可能性がある[13, 14]。これらの間接的なつながりは本レビューの範囲外であるが、議論の中で簡単に触れておく。また、これらの問題は農薬の影響に関する疫学的証拠の一部として考慮されているが、本稿の焦点は公衆衛生であり、農業従事者や地域住民の職業的健康ではない。農業基準は国や地域によって異なるが、適切な場合にはグローバルな視点を維持し、それ以外の場合には欧州の視点を重視している。
本レビューのための文献検索は、まずPubMedとWeb of Scienceのデータベースを用いて、最も関連性の高いキーワードとともに「有機食品」または「有機農業」を適用しなが et al 2016年末まで実施した(システマティックサーチでは特定できなかったが、関連性がある場合には、より最近の文献も含めた)。可能な場合には、既存のシステマティックレビューおよびメタアナリシスを利用した。科学的文献が不足している場合には、当局や政府間組織などの灰色の文献を含めた。我々はまた、配置されたソースで引用された参照を考慮した。
有機食品の消費と健康の間の協会。人間の研究からの知見
一般的に食品頻度調査から得られた回答から定義される有機食品消費に関して、個人のライフスタイル、動機、食事パターンを特徴づけることを目的とした文献が増えてきている[15-23]。しかし、人間の健康における有機食品消費の役割に関する現在の研究は、他の栄養疫学のトピックに比べて少ない。特に、有機食品消費と健康との間の潜在的なリンクを特定することを目的とした長期介入研究は、主にコストが高いために不足している。プロスペクティブコホート研究は、コンプライアンスの評価が困難であるが、そのような関係を調べるための実行可能な方法を構成している。暴露のバイオマーカーがないことを考慮すると、暴露、すなわち有機食品消費の評価は、必然的に測定誤差が生じやすい自己報告データに基づくことになる。
最近のレビューでは、有機食品の消費と健康との関連を扱った臨床研究から得られた知見 [24-26] をまとめたものもある。これらの研究は乏しく、一般的に非常に小さな母集団と短い期間に基づいているため、統計的な力と長期的な効果を特定する可能性が制限されている。Smith-Spanglerら[25]は、従来の食品を消費する対照群と比較して、有機食品を消費する参加者の間で健康に関連するバイオマーカーや栄養状態に臨床的に有意な差が全体的に見られなかったという臨床研究からの証拠をまとめている。栄養摂取量の研究のうち、33人の男性を対象としたOrgTraceクロスオーバー介入研究では、対照的なフィールド試験で食事の植物ベースの割合が生産されたが、12日間の介入では、亜鉛と銅の全体的な摂取量またはバイオアベイラビリティ、またはカロテノイドの血漿状態に対する生産システムの影響は明らかにされなかった[27, 28]。
観察研究では、特定の課題として、有機食品を定期的に購入する消費者は、より多くの野菜、果物、全粒粉製品を選び、肉類を減らす傾向があり、全体的に健康的な食事パターンを持つ傾向があるという事実がある[18, 29]。これらの食生活の特徴はそれぞれ、特定の慢性疾患による死亡率や発症リスクの低下と関連している[30-36]。有機食品を定期的に購入する消費者はまた、より身体的に活動的であり、喫煙する可能性も低い [18, 19, 37]。興味のある結果に応じて、有機食品と従来型食品の消費量と健康状態の関連性は、したがって、食事の質や生活様式因子の違いを慎重に調整する必要があり、残留交絡因子の存在を考慮する必要がある。子供の場合、いくつかの研究では、有機食品を好むライフスタイルを持つ家庭では、アレルギーおよび/またはアトピー性疾患の有病率が低いことが報告されている[38-44]。しかし、これらの研究のほとんどでは、有機食品の消費はより広範なライフスタイルの一部であり、他のライフスタイルの要因と関連している。したがって、オランダのコアラ出生コホートでは、2700人の母子を対象とした [39] 、妊娠中および乳児期に有機乳製品を独占的に摂取することは、2歳時の湿疹リスクの36%低下と関連していた。このコホートでは、有機食品の嗜好性は母乳中の反芻動物性脂肪酸の含有量の高さと関連しており[40]、これは2歳までの親からの湿疹のオッズ比の低下と関連していた[45]。
28,000人の母親とその子孫のMOBA出産コホート研究では、妊娠中に有機野菜の頻繁な消費を報告している女性は、子癇前症[29](OR = 0.79,95%CI 0.62から0.99)のリスクの低下を示した。全体的な有機食品消費量、または他の5つの食品群と子癇前症との間には有意な関連は観察されなかった。
有機食品の消費レベルに応じた経時的な体重変化を調査した最初の前向き研究では、NutriNet-Santé研究の参加者62,000人が含まれていた。BMIの経時的増加は、オーガニック食品の消費量が多い人の方が消費量が少ない人に比べて低かった(ベースラインBMIの%としての平均差=-0.16,95%信頼区間(CI)。−0.32; −0.01). 肥満のリスクの31%(95%CI:18%、42%)の減少は、低消費者と比較して有機食品の高消費者の間で観察された。2つの別々の戦略が交絡因子を適切に調整するために選択された [46]。この論文は、このようにして、同じ研究[18]からの以前の横断的分析を確認した。
慢性疾患に関しては、研究の数は限られている。Nutrinet-Santéの研究では、オーガニック食品の消費者(時折、定期的に)は、非消費者と比較して、高血圧、2型糖尿病、高コレステロール血症(男女とも)および心血管疾患(男性)の発生率が低かったが、がんの既往歴を申告する頻度が高かった[47]。横断的研究に特有の逆因果関係を除外することはできない;例えば、がんの診断自体が食生活の積極的な変化につながる可能性がある [48]。
成人を対象に実施された1件のプロスペクティブコホート研究のみが、がん発生率に対する有機食品消費の効果に対処した。英国の中年女性623,080人のうち、9.3年の追跡期間中に有機食品消費とがんリスクとの関連が推定された。がんの全リスクは有機食品の消費とは関連していなかったが、有機食品を全く消費しない人と比較して、通常または常に有機食品を消費している参加者では、非ホジキンリンパ腫のリスクの有意な低下が観察された(RR = 0.79,95%CI:0.65;0.96)[37]。
結論として、有機食品の消費と健康との間のリンクは、疫学研究ではまだ十分に文書化されていない。したがって、プロスペクティブデザイン、長期継続期間、および高い統計力を可能にする十分なサンプルサイズを特徴とする、十分に計画された研究が必要である。これらの研究には、特に食事消費量や摂取源(すなわち従来型か有機か)に関する暴露評価のための詳細かつ正確なデータが含まれていなければならない。
試験管外および動物実験
試験管内試験
後述するように、有機栽培と慣行栽培の作物を比較する際に単一の植物成分に焦点を当てることは、食品中の化合物が個別に存在して作用するのではなく、自然の文脈の中で作用するという事実を無視している [49]。したがって、細胞株などの生物学的系における食品全体の影響を試験管内試験で研究することで、食品の化学分析からは予測できない影響を指摘することができる可能性があるが、ヒトのほとんどの細胞は食品や食品抽出物と直接接触していないという限界がある。
2つの研究では、有機栽培と従来の作物栽培ががん細胞株に及ぼす影響を調査しているが、いずれも十分に文書化された農法で生産された作物を使用し、複数の農業的および生物学的複製を用いている。最初の研究では、有機栽培されたイチゴからの抽出物は、従来栽培されたイチゴと比較して、1つの結腸癌細胞株と1つの乳癌細胞株に対してより強い抗増殖活性を示した[50]。2つ目の研究[51]では、有機自然発酵ビーツジュースの抽出物は、従来の抽出物と比較して、胃癌細胞株において初期のアポトーシスのレベルが低く、後期のアポトーシスと壊死のレベルが高かった。このように、両研究ともに、試験管内試験 での有機栽培と慣行栽培の作物抽出物の生物学的活性には顕著な違いがあることが示されており、さらなる研究が必要とされている。しかし、これらの研究のいずれも、癌細胞に対する選択的な抗増殖効果と一般的な細胞毒性を区別することはできなかった。したがって、有機食品抽出物と従来の食品抽出物のどちらが、もしあるとすれば、人間の健康の観点から望ましい生物学的活性を持っていたのかを決定することはできない。
健康効果の動物実験
ヒトで長期的な食事介入研究を行うことの難しさを考慮すると、動物実験は、生体内での食品の長期的な健康効果を研究するためのいくつかの可能性を提供している。しかし、動物研究から得られた結果をヒトに外挿することは一筋縄ではいかない。この分野の研究はほぼ100年前に始まった。多数の研究のレビュー[52]では、動物の健康に対する有機飼料のプラスの効果が可能であると結論づけているが、これらの知見を確認するためにはさらなる研究が必要である。ここでは、主な健康面に焦点を当てる。
最もよく設計された動物実験の 1 つでは、従来の飼料を与えられた 2 代目のニワトリの成長速度が速かった。しかし、免疫チャレンジの後、有機飼料を与えられたニワトリはより早く回復した [53]。この挑戦に対する抵抗力は、より良い健康の証として解釈されている [54, 55]。
慎重に実施された作物生産実験とラット給餌試験では、生産システムは血漿中のIgG濃度には明らかな効果を示したが、栄養状態や免疫状態の他のマーカーには影響を与えなかった[56]。有機栽培と慣行栽培の要因設計(受精×植物保護)で栽培した飼料を用いた二世代ラットの研究では、生産システムが子孫のいくつかの生理学的、内分泌学的、免疫学的パラメータに影響を与えていることが明らかになった [57]。特定された影響のほとんどは施肥レジメンに関連していた。これらの研究では、いずれの飼料生産システムも動物の健康をよりサポートすることは見出されていない。
他にもいくつかの研究(主にラットを対象とした)では、飼料生産システムが免疫系パラメータに 対して何らかの影響を及ぼすことが報告されている [57-60]。しかし、これらの知見とヒトの健康との直接的な関連性は不明である。
試験管内試験 および動物実験を総合すると、作物生産システムが細胞の生命、免疫系、および全体的な成長と発達の特定の側面に影響を与えることが実証されている。しかし、これらの知見と人間の健康との直接的な関連性は不明である。一方で、これらの研究は、人間の健康に従来の食品と有機食品の潜在的な効果に信憑性を提供する可能性がある。しかし、動物実験で観察された結果のほとんどは、これまでのところヒトでは検討されていない。
農薬
有機農業と慣行農業における植物保護
従来の農業における植物保護は,合成農薬の使用に大きく依存している。逆に、有機農業は一般的に、作物の輪作、間作、耐性品種、天敵を用いた生物学的防除、衛生慣行、その他の手段など、植物保護のための予防と生物学的手段に依存している[61-64]。しかし、特定の農薬は有機農業での使用が承認されている。EU では、殺虫剤(この文脈では、より具体的には化学的な植物保護製品;人の健康との関連性が低いため、ミクロおよびマクロ生物学的薬剤はこの議論から除外されている)は、動物実験での一連の毒性試験を含む広範な評価の後に承認されている[65]。食品中の許容残留濃度は、同じ文書と、農薬の承認された用途に応じた予想濃度から計算される。現在、EUでは385物質が農薬として認可されている(表1)。これらのうち26物質は、同じ法的枠組みに従って評価され、有機農業での使用も承認されている[6, 66]。
表1 EUで承認されている活性物質とEFSAのリスク評価に基づく重要な毒性特性
| EU農業で承認された | EUの有機農業でも承認されています | |
|---|---|---|
| EU承認の有効成分の総数(+基本物質b) | 385(+15) | 26(+10) |
| これらの: | ||
| 確認された毒性c | 340 | 10 |
| d として分類 | ||
| 急性毒性クラス1+ 2 + 3 + 4、合計e | 5 + 17 + 26 + 76、99 | 0 + 0 + 2 + 2、3 f |
| 発がん性カテゴリー2g | 27 | 0 |
| 生殖細胞変異原性カテゴリー2時間 | 2 | 0 |
| 生殖毒性カテゴリー1B + 2 i | 5 + 21 | 0 |
| 代替候補j | ||
| 低ADI / ARfD / AOEL | 19 | 0 |
| 2つのPBT基準がkを満たしました | 54 | 1リットル |
| 生殖毒性1B I | 5 | 0 |
| 内分泌かく乱物質 | 5 | 0 |
- a[6]の慣例に従い、銅化合物、フェロモン、脂肪酸C7~C20(有機農業用に認可されたカリウム塩のみ)パラフィン油を1群1物質としてカウントしている。[6]とは異なり、植物油は毒性が異なるため4物質としてカウントしている。微生物(生物学的植物保護製品)は含まない。
- b塩基性物質とは、植物保護に有用であるが、主に他の用途を持つリスクの低い化合物のことである。塩基性物質は、EUの活性物質とは異なる承認手続きを経ている。
- c特定された慢性毒性(ADI-許容一日摂取量の割り当て)および/または急性毒性(ARfD-急性基準用量の割り当て)および/または特定された許容作業者曝露レベル(AOEL)。
- d規制1272/2008による。ヒトへの健康影響に関連し、「代替候補」の基準のうち少なくとも 1 つに関連する分類のみが表に含まれている(例:皮膚感作性は含まれていない)。これらの分類は、その使用や暴露パターンにかかわらず、化合物の本質的な有害性に関連する。化合物を含まない分類は、この表には含まれていない(例えば、発がん性クラス 1 A + B)。
- eクラス1とは、最高の急性毒性を指す。物質によっては、異なるエンドポイントに対して複数の分類があるため、化合物の合計数が
- fピレスリンは、菊芋からの抽出物で、急性毒性のクラス4に分類されている。さらに、2つの急性毒性のある合成ピレスロイドは、有機農業の特定の捕虫器での使用が承認されている:ラムダ-シハロトリン(クラス3 + 4)とデルタメトリン(クラス3)である。
- カテゴリー2:「ヒトに対する発がん性が疑われる物質」。(カテゴリー1A/B:ヒトに対して発がん性を有する可能性があることが知られている/推定されている物質) このクラスの物質はない)
- hカテゴリー2:「ヒトの生殖細胞に遺伝性突然変異を誘発する可能性があり、ヒトに懸念を与える物質」(カテゴリー1A/B:「ヒトの生殖細胞に遺伝性突然変異を誘発することが知られている/誘発すると考えられる物質」)。(カテゴリー1A/B:「ヒトの生殖細胞に遺伝性突然変異を誘発する可能性があることが知られている/誘発すると考えられる物質」。本分類に該当する物質はない。)
- i1B:「推定ヒト生殖毒性物質」、2:「推定ヒト生殖毒性物質」。(1A:「既知のヒト生殖毒性物質」、このクラスの物質はない)
- 有害性の低い物質・製品が入手可能になった場合に代替すべき承認物質を指す。この表では、「発がん性1A/1B」(化合物なし)「重大な影響の性質」(化合物なし、基準が定義されていない)「非活性異性体」(2つの化合物、有機農業で認可されていない)の基準を省略している。
- kPBT基準:[65]に規定されている基準に従った難分解性、生物蓄積性および毒性
- l銅。淡水/河口底質への蓄積(P)と藻類およびミジンコへの毒性(T)に基づくPBTの分類
有機農業のために承認された農薬のほとんどは、それらが識別された毒性(例えば、スペアミント油、石英砂)に関連付けられていないため、消費者にとって比較的低い毒性学的懸念であるか、それらが通常の食事の一部であるか、または人間の栄養素(例えば、鉄、重炭酸カリウム、菜種油)を構成するため、またはそれらが捕虫器のみで使用することが承認されているため、食物連鎖に入る危険性が無視できる程度である(例えば、合成ピレスロイド系農薬)。 鉄分、炭酸水素カリウム、菜種油など)または、それらは捕虫器での使用のみが承認されており、食物連鎖に入る危険性が無視できる程度のものであるため(合成ピレスロイドのラムダ-シアロトリン、デルタメトリン、フェロモンなど)消費者への使用は認められていない。2つの顕著な例外は、ピレスリンと銅である。ピレスリンは菊芋から抽出した植物エキスで、合成ピレスロイド系殺虫剤と同じ作用機序を持つが、安定性は劣る。銅は、植物、動物、人間にとって必須の栄養素であるが、高濃度に摂取すると毒性があり、水生生物への毒性により生態毒性が懸念されている。
有機農業で、そして有機農業のために開発された植物保護の実践は、農業システム全体に利益をもたらす可能性がある[67-70]。これは、予防や生物学的薬剤を含む非化学的な植物保護対策に重点を置いている EU における農薬の持続可能な使用への移行に特に価値がある [63, 64]。さらに、真菌病予防のための穀物種子の蒸気処理(http://thermoseed.se/)は、化学的な種子処理の代替手段として有機農業のニーズに牽引されて開発されてきた [71, 72]。これらの方法は現在、特に統合病害虫管理(IPM)のために、慣行農業向けにも販売されている [73]。
農薬の使用-消費者と生産者の暴露
有機食品生産の主な利点の一つは、合成農薬の使用が制限されていることである[5,6]。また、農場労働者の農薬への職業的曝露や農村部の住民の漂流曝露も減少する。過去3年間の平均では、EFSAは、有機食品サンプルの全サンプルの43.7%と13.8%において、最大残留基準値(MRL)を下回る残留農薬を報告している。MRLは、残留物の毒性学的関連性ではなく、農薬の承認された使用を反映している。有機製品には個別のMRLはない。全サンプルの2.8%と有機サンプルの0.9%の合計がMRLを超えたが、これは残留レベルが高いためか、または残留レベルは低いが特定の作物への特定の農薬の未承認使用によるものである可能性がある [74-76]。より毒性学的に関連性が高いのは、リスク評価、すなわち毒性学的基準値との関連で予想される曝露である。平均して 1.5%のサンプルが、検討した食事シナリオのいずれかについて急性基準線量(ARfD)を超えると計算され、有機リン酸クロルピリホスが約半数を占め、アゾール系殺菌剤(イマザリル、プロクロラズ、チアベンダゾール)が約 15%を占めた。有機試料のうちARfDを超えたもの(0%)はなかった [74]。2 種類以上の農薬の残留物が約 25%のサンプルから検出されたが、累積リスクの計算は報告書には含まれていなかった [74-76]。
有機製品と従来製品を比較した唯一の累積慢性リスク評価は、スウェーデンで実施されたものである。ハザード指数(HI)法[77]を用いて、1日500gの果物、野菜、ベリー類を平均的な割合で摂取した成人は、輸入された慣行品、国内の慣行品、有機品を想定した場合、それぞれHIが0.15,0.021,0.0003という計算値を示した[78]。これは、有機食品をベースにした食事の場合、毒性で加重した場合の暴露量が少なくとも70倍低いことを示している。有機農業での使用が承認されていない農薬が有機製品を汚染する経路はいくつかあり、近隣の畑からの散布剤の漂流や揮発、不正使用、従来の製品が入っていた容器や貯蔵庫での輸送中や保管中の汚染、意図的または過失による表示の誤りなどがある。しかし、全体的に見ると、有機製品の認証及び管理のための現在のシステムは、上記の慢性及び急性リスクで示されるように、農薬汚染のレベルが低いことを保証しているが、まだ改善することは可能である[79]。
一般住民のいくつかの農薬への曝露は、米国で日常的に行われているように、血液や尿サンプルを分析することで測定することができる[80]が、欧州ではまだ行われていない。しかし、フランス [81-83]、ドイツ [84]、オランダ [85]、スペイン [86]、ベルギー [87]、ポーランド [88]、デンマーク [89] からのいくつかの散在したヨーロッパの研究では、EU 市民が有機リン酸塩およびピレスロイド系殺虫剤に一般的に曝露されていることが示されている。一般的な観察では、子どもの殺虫剤代謝物の尿中濃度が成人に比べて高いことが示されているが、これは子どもの体重に対する食物摂取量の増加を反映している可能性が高く、また曝露しやすい行動が多いことを反映している可能性が高い。ヨーロッパで行われた研究のほとんどで、有機リン酸塩(ジアルキルリン酸塩、DAPs)およびピレスロイド(3-フェノキシ安息香酸、3-PBA)の一般的な代謝物の尿中濃度は、米国で行われた研究と同程度かそれ以上であった。尿中の代謝物濃度は、食品中にあらかじめ形成された代謝物を摂取することにより、親化合物への曝露量を過大評価する可能性があるが、以下に述べるように、尿中の代謝物濃度と神経行動障害との関連性が報告されている研究がいくつかある。また、代謝物は親化合物よりも毒性が低いとは限らない[90]。
一般集団の場合、食品中の残留農薬は、一般集団の主な曝露源を構成している。これは、有機食品への消費を 1 週間制限した後、農薬の尿中排泄が著しく減少した介入研究で示されている [91-93]。農薬の尿中濃度と、食品摂取量、さまざまな食品の頻度、有機食品の選択に関するアンケート情報との関連を調査した研究でも、同様の結論が得られている。このように、果物や野菜の多量摂取は農薬排泄と正の相関があり[94]、有機農産物の頻繁な消費は尿中の農薬濃度の低下と関連している[95]。
農薬曝露と健康影響
現在 EU で実施されている農薬の規制リスク評価は包括的であり、多くの毒性学的影響が動物実験やその他の実験研究で取り上げられている。それにもかかわらず、このリスク評価は、特に発がん性影響 [96] や内分泌かく乱作用 [97,98]、神経毒性 [99] と同様に、混合暴露への対応が不十分であるという懸念がある。さらに、試験プロトコルが独立した科学[100]に遅れをとっているという懸念があり、独立した科学からの研究は十分に考慮されていない[101]とデータギャップがあまりにも容易に受け入れられている[102]。これらの懸念は、主に慢性曝露の影響と急性曝露の慢性影響に関連しており、急性影響よりも発見が一般的に困難である。ほとんどの研究は農薬代謝物の尿中排泄に頼っており、一般的な仮定として、被験者は代謝物ではなく親化学物質に曝露されたということが挙げられる。
果物や野菜を多く摂取することによる全体的な健康上の利点は十分に文書化されている [31, 35]。しかし、最近、精液の質への影響 [103] が示されたように、これらの利点は残留農薬の悪影響によって損なわれる可能性がある。利益が汚染物質によって相殺されると、逆交絡の状況が発生し、調整が非常に困難になる可能性がある[104]。食餌性残留農薬が消費者の健康に及ぼす潜在的な負の影響は、もちろん、青果物の消費量を減らすための論拠として用いられるべきではない。どちらも、栄養素の内容が農薬への暴露を正当化するために使用されるべきではない。従来の作物の生産に関連する暴露(すなわち散布からの職業的またはドリフト暴露)は、パーキンソン病[105-107]、2型糖尿病[108,109]と非ホジキンリンパ腫[110]と小児白血病またはリンパ腫を含む癌の特定のタイプを含むいくつかの疾患のリスクの増加に関連している、例えば妊娠中に職業的暴露[105,111]または妊娠中に農薬の家庭内使用[105,112]または小児期[113]の後に。これらの知見がまた食品中の残留農薬からの暴露にどの程度まで関連しているかは不明である。しかし、胎児期および幼児期は、神経毒性物質および内分泌かく乱物質への暴露のための特に脆弱な期間である。女性が妊娠していることを知る前の妊娠最初の数週間の間に短時間の職業暴露であっても、温室労働者の子供に関するデンマークの研究では、子供の成長、脳機能、および性的発達に対する長期にわたる悪影響に関連している[114-118]。
食餌性農薬への曝露に関連した消費者の潜在的な健康リスクを評価するためには、敏感な健康アウトカムと曝露対策との関連性についての疫学的研究に頼る必要がある。このような研究は、困難な曝露評価と必要な長期追跡調査の両方によって複雑になる。これまでのところ主な焦点は、妊娠中の有機リン酸系殺虫剤への母親の暴露レベルに関連して、子供の認知障害にあった。実験動物モデルで多くの殺虫剤の神経毒性が知られていること [99] と、早期発育期のヒトの脳の実質的な脆弱性 [119] を考えると、この研究は非常に適切である。
ヒトを対象とした研究のほとんどは米国で実施されており、出生前の有機リン酸塩曝露に関連した小児の脳機能の評価に焦点を当てている。カリフォルニア州の農場労働者を対象とした縦断的出生コホート研究(CHAMACOSコホート)では、妊娠中の有機リン酸代謝物の母体尿中濃度は、新生児の異常な反射神経 [120]、2歳時の不利な精神発達 [121]、3歳半と5歳時の注意力の問題 [122]、および7歳時の知的発達の低下 [123] と関連していた。これに関連して、ニューヨークの出生コホート研究では、妊娠中の有機リン酸塩の母親の尿中濃度に関連して、12歳24ヵ月および6~9歳での認知発達障害が報告されている[124]。ニューヨーク市内の別の出生コホートでは、臍帯血中の有機リン酸クロルピリホスの濃度は、生後7年間の子どもの精神運動および精神発達の遅れと関連していた [125] 、7歳時のワーキングメモリおよびフルスケールIQの低下と関連していた [126] 、学齢期の子どもの脳における皮質厚の減少などの構造変化 [127] 、および11歳時の腕の軽度から中等度の振戦と関連していた [128]。これらおよび同様の研究に基づき、クロルピリホスは最近、ヒトの発達神経毒性物質として分類されている[129]。ヒトにおける有機リン酸塩系殺虫剤の神経発達への影響に関する最近のレビューでは、妊娠中の曝露(一般集団で一般的に見られるレベル)は、子どもの神経発達に悪影響を及ぼす可能性が高いと結論づけられている [130-132]。この結論と一致して、内分泌かく乱を引き起こすと考えられている有機リン酸塩系殺虫剤は、そのような化合物へのヒト曝露によるEU域内の年間健康コストの最大の原因となっており、これらのコストは、以下で議論されるように、主に神経発達毒性によるものである。
ヒトの脳の成長と機能発達は小児期にも継続しているため、出生後の期間も神経毒性暴露に対して脆弱であると想定されている[119]。したがって、CHAMACOSコホートの5歳児は、有機リン酸代謝物の尿中濃度が高い場合、注意欠陥多動性障害(ADHD)の発症リスクスコアが高かった [122]。NHANESのデータベースからの横断的データに基づいて、8~15歳の小児の有機リン酸代謝物の尿中濃度が10倍に上昇すると、ADHDを発症するリスクが55%増加することが示された [133]。また、NHANESのデータに基づいて、尿中のピレスロイドの検出可能な濃度を持つ子供は、検出限界以下の子供と比較してADHDを持つ可能性が2倍になる[134]。さらに、子供のピレスロイド代謝物の尿中濃度と親が報告した子供の学習障害、ADHDまたは他の行動問題との関連性は、最近、米国とカナダの研究で報告されている[135, 136]。
これまでのところ、一般集団の小児における農薬の尿中濃度と神経発達との関連を扱ったEUのプロスペクティブ研究は数件しか発表されていない。3件の研究はフランスのPELAGIEコホートに基づいており、それぞれ有機リン酸塩とピレスロイドについての結果が報告されている [81, 82, 137]。6歳児の認知機能に対する悪影響は、妊娠中の有機リン酸塩の母親の尿中濃度には関係なかったが、ピレスロイド代謝物の濃度は、6歳児の内臓障害と関連していた。また、子供自身のピレスロイド代謝物の尿中濃度は、言語・記憶機能の低下、外向的な困難、異常な社会行動と関連していた。このヨーロッパでの唯一の研究は、一般集団に見られるレベルの有機リン酸塩系殺虫剤への妊娠中の曝露が胎児の脳の発達に害を及ぼす可能性があるという米国の出生コホート研究の結果を裏付けるものではなかったが、PELAGIEコホートで測定された曝露レベルは、有機リン酸塩とピレスロイドの両方について、他のヨーロッパの研究や米国やカナダの研究で測定された曝露レベルよりもかなり低かった。例えば、PELAGIE コホートにおける妊婦の有機リン酸塩代謝物の尿中濃度中央値は、他の研究で測定された妊婦の尿中濃度よりも 2~6 倍低く [85, 122, 138]、一般的なピレスロイド代謝物である 3-PBA の濃度は、他の研究では 80~90%であったのに対し、30%の女性の尿サンプルでしか検出されなかった [88, 139]。したがって、フランスの研究と温室労働者の子供を対象とした前述のデンマークの研究を補足するために、EU市民のより代表的な曝露レベルを含む追加の研究が望まれる。
ヨーロッパ諸国で検出された曝露レベルは、一般的には米国の研究で検出された濃度と同程度、またはわずかに高いが、ヨーロッパの人々における神経発達への悪影響のリスクについては、さらに特徴を明らかにする必要がある。曝露に寄与する有機リン酸塩系殺虫剤は、経口摂取量や呼吸器摂取量に関しても、米国とEUでは異なる可能性がある。欧州食品安全庁(EFSA)によると、すべての有機リン酸系殺虫剤の中で、クロルピリホスが最も多くの場合、毒性学的基準値(ARfD)を超えている[74]。最近の報告書では、学齢期の子供のIQレベルへの悪影響に関する米国のデータを利用して、EUにおける有機リン酸塩曝露のおおよそのコストを計算している。これらの農薬によって失われたIQポイントの総数は年間1,300万点と推定され、その価値は約1,250億ユーロ[140]、すなわちEUの国内総生産の約1%に相当する。この計算にはいくつかの不確実性があるが、農薬の1つのグループにのみ焦点を当てているため、過小評価されている可能性が高い。
残念ながら、農薬曝露と人への健康影響を関連付ける疫学的証拠は、規制機関が実施するリスク評価に考慮するのに十分な信頼性があるとは考えられていない。例えば、クロルピリホスに関する疫学研究から得られた結論は、出生前のクロルピリホス曝露と有害な神経発達転帰との関連性はありそうだが、他の神経毒性物質を除外することはできず、動物実験では1000倍以上の曝露でのみ有害な影響が示されているというものである[141]。最近、いくつかの作物におけるクロルピリホスの残留上限値が引き下げられたが [142, 143]、これは動物実験のみに基づくものであった [144] が、姉妹化合物であるクロルピリホスメチルの残留上限値は変更されていない。この事例は、幅広い種類の農薬から一般の人々を保護するための現在のアプローチの大きな限界を浮き彫りにしている。
植物性食品の生産システムと組成
有機農業における施肥は、農地の糞尿、堆肥、緑肥などの有機肥料に基づいているが、一部の無機鉱物肥料は補助として使用されている。窒素(N)の投入量は年間 170 kg/ha * に制限されている [5, 145]。従来型農業では、一部の国では農地の糞尿も一般的であるが、施肥は鉱物肥料が主である。窒素投入に一般的な制限はない。一般的に、作物の収量は、有機系では植物の N 利用可能性によって制限されるが、慣行系では制限されない [146] [147] リン(P)の投入量は、有機系では平均的に同等かやや低い [147]。
特定の栄養素の欠乏がない場合には、単一の栄養素に焦点を当てても、食品や食事が人間の健康に与える影響を評価する上では限られた価値しかないかもしれない[49];上述したように、実際の健康への影響の研究は、単一の栄養素の研究よりも一般的に有益である。
作物全体の構成
メタボロミクス [148-152]、プロテオミクス [153, 154]、トランスクリプトミクス [155, 156] の研究は、対照的な圃場試験での研究で、生産システムが作物の生育に全体的に影響を及ぼすという証拠を提供しているが、これらの研究が人間の健康に直接関連しているわけではない。さらに、有機栽培システムでは一般的に作物の収量が低い [146] ことから、植物の発達に対する管理戦略の影響があることが示唆されている。
対象範囲、包含基準、統計的手法が異なるいくつかのシステマティックレビューとメタアナリシス [25, 157-159]では、作物、品種、土壌、気候、生産年などにまたがる全体的な傾向を求めて、慣行生産と有機生産に関連して植物の化学組成のいくつかの側面を報告している数百件のオリジナル研究を要約している。これらの系統的なレビューの全体的な結論は一見矛盾しているように見えるが、詳細な調査結果のほとんどでは一致している。
窒素とリン
既存のシステマティックレビューでは、従来の作物と比較して有機栽培の方が全窒素(7% [157]、10% [159])が低く、リン(標準化平均差(SMD)0.82 [25]、8% [157])が高いことが一貫して明らかになっている。これらの知見は、人間の健康への直接的な関連性を欠いている。しかし、上記で議論した施肥戦略の違い、および植物の発育における N、P [160-162]、および N:P 比 [163]の基本的な重要性を考慮すると、この結果は、作物の組成に対する生産システムの他の観察された効果に、いくつかの信憑性を与える可能性がある。
ビタミン
システマティックレビューでは、作物中の多量栄養素、ビタミン、ミネラルの濃度は、生産システムによって全く影響を受けないか、あるいはわずかにしか影響を受けないということが一般的に合意されている。例えば、アスコルビン酸(ビタミンC)は、この文脈で最も注目されている。メタアナリシスでは、ビタミンC含有量に対する有機生産システムの効果の大きさは小さいとしか報告されていない[25, 158, 159]。
ポリフェノール
(ポリ)フェノール化合物は、ヒトにとって必須の栄養素ではないが、心血管疾患、神経変性、および癌を含むいくつかの非伝染性疾患の予防に役割を果たす可能性がある[164]。詳細なメカニズムは複雑であり、完全には解明されていない[164]。いくつかの環境および農学的慣行は、光、温度、植物栄養素の利用可能性、および水管理を含む作物のフェノール組成に影響を与える[165]。窒素の利用可能性が高い条件下では、多くの植物組織はフェノール化合物の含有量の減少を示すが、逆の関係の例もある[165]。
メタアナリシスでは、総フェノール含有量に対する生産システムの中程度の効果の大きさ、例えば14~26%の増加が報告されている[25, 158, 159]。いくつかのより狭いフェノール化合物のグループについては、有機作物と慣行作物の間のより大きな相対濃度差(パーセント単位)が報告されている[159]。しかし、このような知見は、典型的には小規模で少数の研究からの非加重平均であり、したがって信頼性が低い。
発表されたメタアナリシスをまとめると、有機食品中のフェノール化合物の含有量がやや高いことが示されているが、利用可能な証拠は、人間の健康に関して従来の植物製品と比較して有機物のポジティブな効果についての結論を導くのに十分な根拠とはならない。
カドミウムおよびその他の有害金属
カドミウム(Cd)は腎臓に毒性があり、骨を脱灰し、発がん性がある[166]。カドミウムは土壌中に自然に存在するが、P 肥料や大気中の沈着物によっても土壌に添加される。土壌構造や土壌化学、腐植含量、pHなどのいくつかの要因が、植物のカドミウムの利用可能性に影響を与える [167]。カドミウム含有肥料を施用すると、作物中のカドミウム濃度が上昇する [167, 168]。土壌の有機物量が少ないと、一般的に作物へのカドミウムの利用可能性が高まる [169]。
鉱物肥料中のカドミウムの供給源は、原料のリン酸塩岩である。鉱物肥料中の欧州平均カドミウム含有量は、68 mg Cd/kg P [170] または 83 mg Cd/kg P [171]と報告されている。農場糞尿中のカドミウム含有量は様々であるが、多くの場合は低いようである。ドイツのあるコレクションに含まれる様々な種類の動物糞尿の平均は 14~37 mg Cd/kg P [172] であった。
Smith-Spanglerら[25]はメタ分析で有機作物と慣行作物のカドミウム含有量に有意な差は見られなかった(SMD = -0.14,95% CI -0.74 -0.46)が、Barańskiら[159]は別のメタ分析で有機作物と比較して慣行作物のカドミウム濃度が48%高くなった(SMD = -1.45,95% CI -2.52 -0.39)と報告しているが、主に同じ元の研究を基にした別のメタ分析では含まれる基準は異なるものの、有機作物と比較して有意に高いカドミウム濃度が報告されている。この不一致を理解するために、これらのメタアナリシスの著者に連絡を取った。いくつかの矛盾点が対処され、原著者[173]によって提供されたBarańskiメタアナリシスの更新版では、有機作物と比較して慣行作物のカドミウム含有量が有意に30%(SMD = -0.56,95%CI -1.08~-0.04)上昇していることが示されている;サブグループ分析では、この差は穀類作物に限定されている。Smith-Spanglerの分析では、最新のメタ分析は利用できなかった[25]。明らかに、有機作物のカドミウム含有量が低い傾向にある2つの大規模でよく計画された研究は、包含基準を満たしているように見えるが、考慮されていない[174, 175]。また、鉱物肥料が土壌や作物へのカドミウムの重要な供給源であるという先行知識を考えると、多重試験の補正が課されているが、これは過度に保守的であるかもしれない。これらの点がSmith-Spanglerのメタアナリシスの結果にどのような影響を与えるかは不明である。
肥料からのカドミウムの流入が作物のカドミウム含有量に及ぼす短期的および長期的な影響はあるが [167] 、有機作物と慣行作物のカドミウム含有量を比較した長期的な研究は存在しない。このような直接的な証拠がない場合、2 つの長期実験では、100 年以上栽培した後、有機的に施肥された穀類作物と比較して、 鉱石施肥された作物の方が時間の経過とともにカドミウム濃度に高い傾きがあることが示されている [176, 177]。
したがって、有機農作物のカドミウム含有量が低いのは、有機農業で使用される肥料中のカドミウム含有量が低いためであり、有機農地では土壌の有機物が多いためである可能性がある。一般住民のカドミウムへの曝露量は、許容摂取量に近く、場合によってはそれを上回っているため、カドミウムへの曝露量は低減されるべきである。非喫煙者にとっては、穀類と野菜が最も重要な寄与者であり、食品が曝露の主な原因である[168]。
鉛、水銀、ヒ素を含む他の有害金属については、有機作物と慣行作物の濃度の差は報告されていない[25, 159]。ウラン(U)は、懸念される汚染物質として、鉱質の P 肥料にも存在するが [178] [179] 、有機肥料にはあまり存在しない[179]。ウランは鉱物肥料を施した土壌に蓄積するようであり[180]、農業活動は地表水や地下水のウラン含有量を増加させる可能性がある[181, 182]。しかし、有機製品と慣行製品のウラン含有量を比較した証拠は見出されていない。
真菌類の毒素
作物中の真菌毒素については、あるメタ分析では、特定のフザリウム種が産生するデオキシニバレノール(DON)の有機物への汚染が従来の穀類作物に比べて低かったことが報告されている[25]。完全には理解されていないが、殺菌剤の散布は穀類の葉の真菌群集を変化させ、病気を抑制する種を弱体化させる可能性がある [183, 184]。また、穀類以外の作物を含む輪作はフザリウムの蔓延を減少させる可能性があり[185]、Nの利用可能性は穀類のDON含有量と正の相関がある[186]。これらの要因は、有機穀物で観察された低いDON汚染に信憑性を与えている。EUでは、幼児、乳児、子供のDONへの平均慢性曝露量は、穀物と穀物ベースの製品が総曝露量の主な要因となっており、1日当たりの許容摂取量(TDI)を超えている。TDIは、マウスで観察された体重増加の減少に基づいている[187]。生産システムは、穀物生産において重要な別の真菌毒素であるオクラトキシンA(OTA)の濃度には観察されない影響を与えない[25]。
動物性食品
規制により、有機生産の草食動物は、乾物ベースで飼料摂取量の少なくとも 60%を粗飼料として受け取ることになっている。牧草の季節的な利用可能性に応じて、粗飼料は新鮮なもの、乾燥したもの、またはサイレージにすることができる。また、有機生産の雑食動物は毎日の飼料の一部として粗飼料を受け取り、家禽は牧草を利用できる [6]。これに対応する規制は、ほとんどの場合、従来の畜産では見られない。結果として、有機畜産における給餌戦略には、従来のシステムに比べて粗飼料の割合が高く、例えば乳牛の場合 [188, 189] である。
脂肪酸
有機食品と従来の動物性食品の組成の違いに関する既存の研究の多くの焦点は、人間の健康にとって重要であるため、オメガ3脂肪酸に大きな関心があり、脂肪酸組成にある。また、いくつかの研究では、ミネラルやビタミンの含有量も取り上げられている。
飼料のFA組成は、牛乳、卵または肉の脂肪酸組成を強く決定するものである[190,191]。草とレッドクローバー、典型的な粗飼料は、総FAの30%と50%の間のオメガ3 FAを含むが、濃縮飼料は、穀物、大豆、トウモロコシ、およびパームカーネルケーキは、すべての総FAの10%以下のオメガ3 FAを含む[190]。人間と同様に、家畜は、エロンゲナーゼおよびデサチュラーゼ酵素の助けを借りて、長鎖オメガ3脂肪酸に飼料中のα-リノレン酸のごく一部を回す。
牛乳については、最近のメタ分析では、従来の牛乳と比較して有機乳の方がオメガ3系脂肪酸の含有量(総脂肪酸の割合として)が約50%高いことが結論的に報告されており[192]、これまでのレビュー[25, 189]を概ね確認している。また、反芻動物のFA(牛のルーメンで産生される天然のトランスFAのグループ)の含有量は、オーガニック牛乳の方が高い。飽和脂肪酸、一価不飽和脂肪酸、およびオメガ6 PUFAの含有量は、有機乳と従来の乳で類似していた[192]。
これらの所見にはかなりの統計的不均一性が報告されている。上記に記載された個々の差異は、含まれている11から 19の研究からの結果に基づいている。観察された違いは、給餌レジメンの違いに直接リンクしているため、もっともらしいものである。また、他にもいくつかの要因が乳中の脂肪酸組成に影響を与えることにも留意すべきである [193]。具体的には、季節(屋内 vs 屋外)は摂食体制に影響を与え [188]、その結果、牛乳中のオメガ3含量に影響を与える。しかし、オメガ3脂肪酸の含有量は、屋外と屋内の両方の季節の間、有機乳の方が高い[189]。
卵については、飼料の FA 組成 [190]、その結果として有機系などの牧草 [194, 195]へのアクセスが、卵の脂肪酸組成の強い決定要因であることがよく述べられている。しかし、有機系と慣行系の卵のFA組成を比較した研究は数件しかなく[196]、系統的なレビューは利用できない。有機卵のより高いオメガ3含有量はもっともらしいが、文書化されていない。
67のオリジナル研究の合計は、有機および従来の飼育からの肉(主に牛肉、鶏肉、ラム肉、豚肉)の組成の側面を報告し、最近メタアナリシス[197]でまとめられた。それぞれ23件と21件の研究に基づいて、総PUFAとオメガ3 PUFAの含有量は、従来の肉に比べてオーガニックの方が有意に高いことが判明した(それぞれ23%と47%)。ヨーロッパの平均的な消費量で加重し、一定の消費量を維持しながら、従来の食肉の代わりにオーガニックを選択すると、肉からのPUFAとオメガ3 FAの摂取量がそれぞれ17%と22%増加した[198]。これらの知見は、特にオメガ3 PUFAの場合には、オーガニックと従来の生産における給餌レジメンの既知の違いを考慮すると、もっともらしいものである。しかし、各解析に利用可能な研究が少なく、多くの解析は不確実性が高く、統計的な力が弱いままであった。さらに、脂肪酸代謝は反芻動物と単胃動物では異なる[190]。また、慣行飼育動物と有機飼育動物の間の摂食レジメンの実際の違いは、種によって、また国によっても異なる可能性がある。研究間および種間のばらつきが大きく、したがって、これらの結果の全体的な信頼性は、上記のミルクと比較して低い。このメタアナリシスは、したがって、有機食肉中のオメガ3含有量のもっともらしい増加を示しているが、この効果を確認するためには、よりよく計画された研究が必要である[197]。
乳製品は、ヨーロッパのほとんどの人口における総PUFA摂取量の4~5%を占めているが、肉および肉製品はさらに7~23%を寄与している[199]。オメガ3系PUFA摂取量に対する乳脂肪の寄与度(α-リノレン酸の摂取量として近似)は5~16%と推定されており[200, 201]、肉類は12~17%と推定されている[201, 202]。消費量を一定に維持しつつ、有機物を従来の乳製品に交換した場合のオメガ3 PUFA摂取量への影響については、厳密に検討されていない。ここに提示された摂取量と組成のデータから、それは有機製品を選択すると、2.5-8%(乳製品)とあまり特定の2.5-4%(肉)によって平均的な食事オメガ3 PUFAの摂取量を増加させると推定することができる。FAOの食糧供給データに基づいて最近の予備的な見積もりは、同様の数字[198]をもたらした。特定の人口集団や脂肪酸については、これらの数値が高くなる可能性があり、一部のサブ集団ではオメガ3 PUFAの摂取量が推奨値よりも低いため、オメガ3 PUFAの消費量の増加が一般的に望ましいとされている[203]。しかしながら、全体的には、オメガ-3 PUFA摂取量に対する動物生産システムの影響は軽微であり、特定の健康上の利点を導き出すことはできない。さらに、他の食餌性オメガ3 PUFAソース、具体的には特定の植物油や魚は、追加の利点を運ぶ利用可能である[204-206]。反芻動物のトランス脂肪酸(産業用トランス脂肪酸とは対照的に)の特定の健康上の利点の存在は、いくつかの研究[207]によって示されているが、強く支持されていない[208]。反芻動物トランス脂肪酸の実際の消費量を考慮すると、これは公衆衛生上の関連性を欠いている可能性が高い[208]。
微量元素とビタミン
最近のメタ分析では、従来の牛乳のヨウ素(74%)とセレン(21%)の有意に高い含有量と、それぞれ6,4,8および9の研究に基づいて、有機牛乳の鉄(20%)とトコフェロール(13%)の[192]を指摘している。妊娠中および乳児期のヨウ素欠乏は、子孫の脳の発達障害をもたらすが、過剰なヨウ素摂取は同様の効果と関連しており、最適なヨウ素摂取量の窓は比較的狭い[209]。全体的に、ヨーロッパでのヨウ素摂取量は低く、軽度の欠乏症が蔓延している[210]。欠乏を是正する好ましい方法は、塩のヨウ素化 [210, 211] であり、塩はほぼ全世界で消費されており、季節変動がほとんどないため [212]。
ヨウ素は承認された飼料添加物としてリストアップされており、補給量の上限はすべての乳生産に おいて同じであるため、飼料ヨードの補給は規制によって生産システムとは関連していない。乳牛への最適な補給は、ヒトのヨウ素摂取に関する他の国家戦略との関連で見るべきである。これはまた、乳製品の摂取量が少ない、または全く摂取していないヒトの小集団も考慮に入れるべきである。
トコフェロール、セレン、鉄については、一般的に高い含有量が望まれ、セレンの場合は牛乳が重要な供給源となる。しかし、有機牛乳と従来の牛乳の濃度差は控えめであり、いくつかの研究のみに基づいている。
抗生物質耐性菌
動物生産における抗生物質の過剰な予防的使用は、耐性菌による人間の健康問題を増加させる重要な要因である。抗生物質の使用は有機栽培では強く制限されており、その代わりに、動物の健康を促進するために、良好な動物福祉と十分なスペースを提供することを目的としている。
抗生物質は今日の集中的な動物生産の不可欠な部分を構成しており、農場動物は細菌の耐性遺伝子の重要な貯蔵庫として機能する可能性がある[213, 214]。抗生物質のかなりの割合(50~80%)が世界的に家畜生産に使用されていると報告されている[215]。2014年の「バイオマス1kgあたり」ベースでは、調査対象のEU/EEA28カ国では、家畜が消費する抗菌薬の量はヒトに使用する抗菌薬の量をわずかに上回っており、量や物質の種類に関しては国によってかなりの差がある[216]。
ここ数十年の間に、家畜への抗生物質の使用が、人間の医療における抗生物質治療の効率を損なうことに寄与するのではないかという懸念が高まっている[217]。抗生物質耐性菌の膨大な細菌叢と耐性遺伝子の伝搬経路に関する詳細な情報がないにもかかわらず、抗生物質の効率性の低下と公衆衛生およびより一般的な環境への影響に関連した新たな課題を軽減するための行動が世界的に必要とされている[218, 219]。
抗生物質の使用は動物生産の経済的成果を高めるかもしれないが[220, 221]、多剤耐性遺伝子の拡散は動物生産部門だけの問題ではない。マイナスの影響は、畜産とは直接関係のない社会の部分にも影響を与えている。つまり、副作用のコストは、主に農業部門が負担しているのではなく、社会全体が負担していることになる。しかし、農場動物におけるすべての抗生物質治療が公衆衛生への危険性を表しているという一般化はできない[222, 223]。
集中的な畜産における抗生物質の使用は、農場動物の収容および飼育条件と密接に関連している。例えば、EU の動物福祉基準を上回る従来型の豚の生産とスウェーデンの農家の態度などである[224, 225]。従来型の生産は一般的に、スペースや飼料などの投入資源が制限された高生産レベルを目指しており、このような条件は、例えば豚の生産において、個々の動物が状況に対処できず、ストレスを引き起こす可能性がある[226, 227]。これは、より高い飼養密度、制限されたスペース、不毛の環境が病気の発症リスクを高める要因であることを意味し、したがって、このような条件下の動物は抗生物質による治療を必要とする可能性が高くなることを意味する。
有機栽培では、動物の飼育密度を下げることを目的としており、一般的には、動物がより広々とした豊かな環境を手に入れることができ、屋外での飼育が可能で、グループのサイズが制限されているなどの前提条件が整っていることを意味している[70]。これにより、動物はより自然な行動をとることができ、健康を維持する機会が増えるため、最終的には予防的な投薬の必要性が減ることになる。しかし、実際には、有機家畜の健康状態は複雑であり、病気の予防は個々の農場に適応させる必要がある[228]。デンマークにおける有機生産の結果に関する報告書では、有機生産の要件を満たすことが、動物の福祉と健康に関連していくつかのプラスの結果をもたらすことが示されている[70]。
EU の規制によると、有機生産における動物の日常的な予防的投薬は認められていない。しかし、苦痛を避けるために病気はすぐに治療しなければならず、抗生物質の治療的使用は認められているが、従来の生産よりも長い離脱期間が必要です[5]。さらに、12ヶ月間に3回以上、あるいは生産ライフサイクルが1年未満の場合は1回以上の治療を受けた動物からの製品は、有機物として販売することはできない[6]。つまり、治療的には、従来の農業で使用されていた抗生物質と同じものが、有機農業では使用されていても、条件が異なる場合があるということである。例えば、主に予防としてサブ治療に使用される抗生物質は、有機栽培では決して考慮されない。
有機規制は畜産における抗生物質の使用量を少なくすることを目標としているが、ヨーロッパの有機栽培における抗生物質の実際の使用量は、従来の畜産と比較して包括的に文書化されているわけではない。散在した研究によると、抗生物質の使用量は一般的に有機系と比較して慣行系の方が実質的に多く、特に豚については(約5~15倍)多いことが示されている[229, 230]。デンマーク [231] とオランダ [232] の研究では、乳牛の抗生薬物使用量は、有機酪農場と比較して慣行酪農場の方が 50%と 300%高かったが、スウェーデンの研究では、例えば乳房炎 [233] などの疾患治療戦略には有機酪農場と慣行酪農場の間で差がないことが明らかになっている。文書化されているのはごくわずかであるが(例:[234, 235])EU の有機ブロイラー生産では抗生物質の使用はほとんどない。これは、予防的な使用を禁止し、屠殺前に長い休薬期間を規定している規制 [6, 236] の結果であり、ブロイラーの群れでは単一の動物を治療することは不可能である。従来のブロイラー生産では、抗生物質の使用が一般的である(例えば、[237-239])。
最近、遺伝子配列決定により、ヒトと農場動物のリザーバー間の耐性遺伝子の伝播経路が複雑であるように思われることが明らかにされた[213,222,240]。それにもかかわらず、最近のEFSAの報告書では、「ヒトと動物の両方で、調査した組み合わせのほとんどで、抗菌薬の消費とそれに対応する細菌の耐性との間に正の関連が観察された」[241]ことが判明しており、これはその後強化されている[216]。接触または食物を介した動物とヒトとの間の直接感染に加えて、耐性菌株および耐性遺伝子が環境中に拡散する可能性もある[242]。
これまでに、有機畜産における抗生物質の必要性と使用量を減らすことで、抗生物質耐性化のリスクが減少するとの説があり[243]、これは有機豚の耐性大腸菌に関しても、従来の豚と比較して実証されている[244]。また、養鶏場が従来型から有機生産基準に変更された場合、抗生物質の予防的使用を中止することで、抗生物質耐性サルモネラ菌の有病率が減少することも示されている[245]。
耐性菌は、農場からフォークまでの生産チェーン内で移動する可能性がある[246]。豚肉や鶏肉では、有機畜産物の方が耐性菌を保有する可能性が低いことがわかっている[25]。
豚の生産では、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)に特に注意が払われており、例えばオランダとドイツの研究では、MRSAは、試験した全豚の30%と55%で分離されている[247, 248]。さらに、健康なフランスの養豚農家は対照者よりもMRSAを保有している可能性が高く[249]、養豚場で発見されたものと同様の株のMRSAを保有していることが明らかになっている[250]。しかし、豚生産におけるMRSAの有病率は慣行農場と有機農場で異なる可能性があり、400頭のドイツの肥育豚群を対象としたメタ研究では、慣行農場(n = 373)と比較して有機農場(n = 23)ではMRSA有病率のオッズ比(OR)は0.15(95%CI 0.04,0.55)であった[248]。潜在的な危険因子を多変量に調整すると、この関連性は有意ではなくなり、それが他の因子によって運ばれたことを示唆している、そのような非スラット床、抗生物質の使用なし、および分娩から仕上げまでの牛群の種類など、有機生産で規制されているか、または有機生産に関連する因子を含む。さらに、国によって抗生物質の使用にかなりの差があるとしても、フランス、イタリア、デンマーク、スウェーデンでは、有機豚では従来の豚に比べて抗生物質耐性が少ないことがわかっている[251, 252]。
従来の農場では、有機基準に合わせて農場を転換する場合を除き、有機生産から管理や飼育に関する知識を採用することは稀であるが、抗生物質の使用を減らすために、従来の農場に知識を移転することで動物の健康と福祉を改善するという選択肢もあるかもしれない[253]。
有機生産においては,市場に出回っている有機製品の原産地を保証するために,表示にはすべての段階で完全なトレーサビリティが必要である [5]。フードチェーン全体の透明性に関する有機規制の一般原則を適用することで、抗菌薬耐性の伝播という新たな問題を緩和することができる。しかし、家畜部門全体の有機生産への移行は、それだけでは、抗生物質耐性問題の解決策の一部にすぎない。
議論
有機食品の生産に基づいて食事に関連付けられている人間の健康への影響の評価は、証拠の2つのセットに依存しなければならない。証拠の最初のセットは、有機V.従来の製品の選択肢に関して実質的に異なる食生活習慣を持つ集団を比較する疫学的研究である。これらの研究は、ある程度動物モデルと試験管内試験モデルを使用して実験的研究によって補完されている。データの2番目のセットは、そのような食品の化学分析や栄養素や汚染物質の内容、または抗生物質の使用と耐性パターンなどの間接的な証拠に依存している農業生産方法の連続で。どちらの結果にも長所と短所がある。
人間の健康に対する有機食品の影響を直接調査した数少ないヒトの研究は、これまでのところ、有機食品の消費者における小児アレルギー、成人の過体重/肥満[18,46]および非ホジキンリンパ腫(ただし、全癌ではない)[37]のリスクが低いことの指標を含む、いくつかの観察結果を得ている。プロスペクティブ研究の希少性や欠如、およびメカニズム論的証拠の欠如により、有機食品がこれらの観察において因果関係のある役割を果たしているかどうかを決定することは、現在のところ不可能である。しかし、有機食品を好む消費者は、果物、野菜、全粒粉、豆類の消費量が多く、肉類の消費量が少ないなど、全体的に健康的な食事パターンを持っていることも観察されている[18,29,37]。このことは、残留交絡因子または測定されていない交絡因子のために、有機食品の嗜好の潜在的な効果を他の関連する生活様式因子の潜在的な効果から分離する際に、方法論的な困難さをもたらす。これらの食事パターンは、他の文脈では糖尿病や心血管疾患[30-36]を含むいくつかの慢性疾患のリスクの低下に関連付けられている。したがって、定期的に有機食品を食べる消費者は、食事のパターンの結果として、従来生産された食品を消費する人々と比較して、これらの疾患のリスクが低下していることが期待されている。このような食生活パターンは、平均的な食生活よりも環境的に持続可能であるようにも見える[254]。
食品分析は、有機食品には何らかの健康上の利点があるかもしれないという考えを支持する傾向がある。有機食品の消費者は、農薬への食餌曝露が比較的少ない。EUでは、化学農薬は市場投入前に包括的なリスク評価を受けているが、このリスク評価には重要なギャップがある。いくつかのケースでは、具体的には妊娠中の有機リン酸系殺虫剤曝露の影響として小児期の認知発達のために、疫学研究では、副作用[140,255]の証拠を提供している。有機農業は、食品中の残留農薬の低減を可能にし、非化学的な植物保護のための大規模な実験室を提供することで、従来型農業の統合的な害虫管理への移行に役立つ可能性がある。
このレビューでは、従来型の食品生産からの農薬曝露が主な健康問題を構成していることを強調している。最近になって生物医学的研究の中で探求されるようになった重要な問題は、早生期の曝露、特に脳の発達に害を及ぼす可能性のある出生前の曝露が大きな懸念事項であることである。ほとんどの殺虫剤は昆虫の神経系に毒性があるように設計されているが、多くの高等種は同様の神経化学的プロセスに依存しているため、すべての種がこれらの物質に対して脆弱である可能性がある[129]。殺虫剤以外にも、多くの除草剤や殺菌剤についても、神経系に悪影響を及ぼす可能性があることが実験的研究で示唆されている[99]。しかし、神経毒性(特に発達神経毒性)の試験が登録プロセスの一部として一貫して要求されていないため、体系的な試験は実施されておらず、許容曝露量はそのような影響から保護されていない可能性がある。少なくとも100種類の農薬が成人に神経学的に有害な影響を引き起こすことが知られており[129]、したがって、これらの物質はすべて、発達中の脳にもダメージを与える可能性があると疑われなければならない。これらの有害な結果の予防の必要性は、最近のコスト計算[140]や、農薬への暴露がパーキンソン病、糖尿病、特定の種類の癌などの重要な疾患につながる可能性があるという追加のリスクによって示されている。
子どもと大人の転帰と用量依存性はまだ不完全なままであるが、さらなる限界は、異なる集団における曝露評価が不足していること、また食生活との関連性である。人の健康に関する農薬使用によるコストと社会への関連コストは、最近検討されたように、隠れた外部コストのために大幅に過小評価されている可能性が高い[256]。また、農薬の規制上の承認プロセスのギャップは、重要な影響が無視され、検出されずに残ることにつながる可能性がある。
栄養素に関しては、有機乳製品、そしておそらく肉類も、従来の製品と比較してオメガ3脂肪酸の含有量が約50%高い。しかし、これらの製品は平均的な食生活におけるオメガ3脂肪酸のごくわずかな供給源に過ぎないため、この効果の栄養的意義はおそらく低いと考えられる(これは証明されていないが)。現在の知見によれば、作物の栄養成分は生産システムの影響をほとんど受けていない。ビタミンとミネラルは、どちらの生産システムの作物でも同じような濃度で含まれている。一つの例外は、有機栽培の作物に見られるフェノール化合物の含有量の増加であるが、この問題に取り組んだ多くの研究にもかかわらず、これはまだ不確実性の対象となっている。したがって、一般的には有機製品に有利であるが、有機食品と従来の食品の間に確立された栄養の違いは小さく、人間の健康のための強力な結論は、現在のところ、これらの違いから引き出すことはできない。有機作物は、従来の作物に比べて少ないカドミウムが含まれているという指標がある。これは、主にミネラル肥料が土壌中のカドミウムの重要な供給源であることから、もっともらしいことである。しかし、この関係を確実に確立したり、反証したりするために必要な長期的な農場ペアリング研究や圃場試験は、特に不足している。食品中のカドミウムの健康への関連性が高いことから、この研究の欠如は重要な知識のギャップを構成している。
細菌における抗生物質耐性の発生に関しては、有機畜産は、集中的な生産によってもたらされるリスクを制限し、抗生物質耐性の蔓延を減少させる方法を提供する可能性がある。有機農場の動物は、従来の農場の動物に比べて、集中生産に関連した特定の病気を発症する可能性が低い。その結果、臨床疾患の治療に必要な抗生物質の使用量が少なくなり、予防的に使用することも強く制限されている有機経営のもとでは、抗生物質の使用量も少なくなる。これにより、細菌の抗生物質耐性化のリスクが減少する。さらに、有機生産における透明性は、食品生産における抗菌薬耐性の伝播をめぐる問題に対処するための知識や方法を得るのに役立つかもしれない。
ポスト抗生物質時代に突入するリスクを減らすためには、動物生産における抗生物質の使用を強力に減少させるか、完全に停止させることが不可欠であるように思われる。有機ブロイラー生産のように、抗生物質を使用しない、または使用量の少ない飼育システムの開発と拡大は、将来の持続可能な食糧システムへの有機農業の重要な貢献となるかもしれない。
このレビューで検討された研究のほとんどは、農産物生産が製品組成や健康に及ぼす影響を調査したものである。食品加工の潜在的な影響については、あまり注目されていない。加工は食品の組成及び食品成分のバイオアベイラビリティに影響を与える可能性がある。食品添加物が従来の製品に比べて有機製品には制限されていることは規制されており [5]、認識されている [257]。また、食品加工の程度が人の健康に関連している可能性があることも認識されている [258, 259]。有機食品加工では、加工は「慎重に、好ましくは生物学的、機械的、物理的な方法を用いて」行われるべきである[5]が、具体的な制限やガイドラインはない。化学添加物を除いて、特定の食品加工方法(野菜の発酵、野菜の低温殺菌など)が有機と従来の製品や消費パターンでより一般的であるかどうか、あるいはそのような違いが人の健康に関連しているかどうかは不明である。
ノルウェー[260]とデンマーク[70]の最近の2つの報告書の範囲は、本研究と一部重複している。大まかに言えば、これらの報告書で紹介されているレビュー結果と結論は、本稿の内容に沿ったものである。いくつかのトピックについては、重要な新しい証拠が近年発表されている。その結果、いくつかのケースでは、より強力な結論を今日に至るまで導き出すことができる。さらに、今回のレビューでは、レビューされたエビデンスベースの中に農薬の影響に関する疫学研究が含まれている。
全体として、利用可能な証拠は、有機食品に関連付けられているいくつかの明確な、いくつかの潜在的な利点を示唆した。一般的に利点は、厳密に現在の法律で定義されているように必ずしも有機食品の生産を必要としない。農薬や抗生物質の使用方法の変更など、特定の生産方法は、従来の生産でも実施することができ、例えば、農薬の持続可能な使用に向けた開発を支援することができる [261]。それによって、有機農業の実践と開発は、有機部門の外でも実質的な公衆衛生上の利益を持つことができる。
食事の選択と関連する食品生産方法もまた、環境の持続可能性に重要な影響を与える[254]。有機食品を好む消費者の消費パターン[16, 18, 19, 37, 47]は、持続可能な食生活とよく一致しているように思われる[2]。これらの消費パターンはまた、地中海式ダイエット[262-265]や新北欧式ダイエット[266-269]との類似性も示しており、土地使用、エネルギー、水の消費、温室効果ガス排出量に関しては、同時に行われている平均的なダイエットと比較して、より低い食生活のフットプリントを示している。有機食品システムが持続可能な食品システムの例として機能し得る程度を評価するためには、さらなる評価が必要である[270]。
将来的に健康的で環境的に持続可能な食品システムを開発するためには、生産と消費を統合的に考慮する必要がある[2, 271]。環境持続可能性に対する様々な食品システムの全体的な影響の評価が非常に望まれるが[270]、本レビューでは、持続可能性の重要な側面である有機生産方法と有機食品に対する消費者の嗜好に関する人間の健康問題を評価することを試みた。
結論
示唆的な証拠は、有機食品の消費は、アレルギー疾患のリスクと太りすぎや肥満のリスクを低減する可能性があることを示しているが、有機食品の消費者は、全体的に健康的なライフスタイルを持っている傾向があるので、残留交絡が可能性がある。動物実験は、成長と開発は、有機または従来の生産から同一に構成された飼料を比較する場合、飼料の種類によって影響を受けることを示唆している。有機農業では、農薬の使用は制限されており、従来の果物や野菜の残留物は、人間の暴露の主なソースを構成している。疫学研究では、現在の暴露レベルでの子供の認知発達に対する特定の農薬の悪影響が報告されているが、これらのデータは、これまでのところ、個々の農薬の正式なリスク評価には適用されていない。栄養成分の組成は有機作物と慣行作物の間ではわずかな違いしかなく、有機果物と野菜のフェノール化合物の含有量はわずかに高い。有機穀物作物のカドミウム含有量も低いと思われる。この違いは、限界的な栄養上の重要性の可能性が高いが、有機乳製品、およびおそらくまた、肉は、従来の製品に比べてオメガ3脂肪酸の高い含有量を持っている。より大きな懸念は、社会における抗生物質耐性のキードライバーとして、従来の動物生産における抗生物質の普及した使用であり、抗生物質の使用は、有機生産ではあまり集中的である。このように、有機食品生産は、人間の健康のためのいくつかの文書化された潜在的な利点を持っており、従来の農業でも、例えば、統合的な害虫管理で、これらの生産方法を広く適用することは、したがって、最も可能性の高い人間の健康に利益をもたらすだろう。