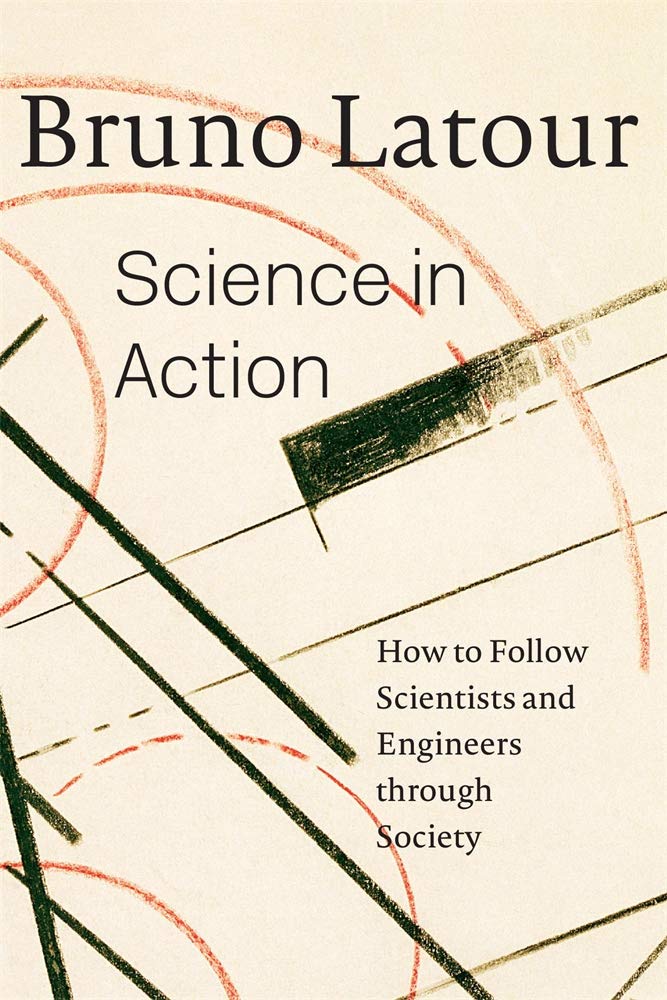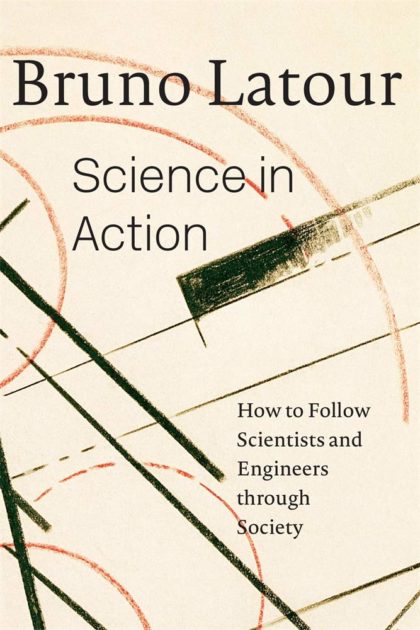
英語タイトル:『Science in Action:How to follow scientists and engineers through society』Bruno Latour 1987
日本語タイトル:『科学が作られている最中:社会の中の科学者と技術者をどう追うか』ブルーノ・ラトゥール 1987
目次
- 謝辞:/ Acknowledgements
- 序論 パンドラの箱を開ける / Introduction Opening Pandora’s Black Box
- 第一部 より弱いレトリックからより強いレトリックへ / FROM WEAKER TO STRONGER RHETORIC
- 第1章 文献 / Literature
- 第2章 実験室 / Laboratories
- 第二部 弱い地点から要塞へ / FROM WEAK POINTS TO STRONGHOLDS
- 第3章 機械 / Machines
- 第4章 部外者を内部へ / Insiders Out
- 第三部 短いネットワークからより長いネットワークへ / FROM SHORT TO LONGER NETWORKS
- 第5章 理性の審判 / Tribunals of Reason
- 第6章 計算の中心 / Centres of calculation
- 付録1 方法の規則:/ Rules of Method
- 付録2 原理:/ Principles
- 注:/ Notes
- 参考文献:/ References
- 索引:/ Index
本書の概要:
短い解説:
本書は、科学技術の「完成品」ではなく、「作られつつある最中」のプロセスを観察する方法を読者に提示することを目的とする。科学社会学、人類学に関心のある読者に向けて書かれている。
著者について:
著者ブルーノ・ラトゥールは、フランスの科学社会学者、人類学者。パリ国立高等鉱業学校で教鞭をとり、科学技術社会論(STS)のアクターネットワーク理論で知られる。本書は、実験室でのフィールドワークに基づき、科学知識の構築プロセスを描き出す。
テーマ解説
- 主要テーマ:科学知識の構築プロセス。科学的事実は、自然に発見されるのではなく、人間やモノのネットワークの中で「作られる」という視点を提示する。
- 新規性:アクターネットワーク理論の基盤。人間以外のモノ(実験装置など)も「アクター」として社会のネットワークに組み込み、分析する方法論を提示する。
- 興味深い知見:科学論における「黒い箱」。科学の成果は、内部が議論されなくなった時点で「黒い箱」となり、自明のものとして扱われるというメタファーを示す。
キーワード解説
- 黒い箱:科学や技術の成果が完成し、内部の複雑な議論やプロセスが見えなくなった状態。
- アクターネットワーク:人間と非人間(モノ、概念など)が対等に結びつき、作用し合うネットワーク。
- 翻訳:異なるアクターの利害を一致させ、ネットワークに引き込むプロセス。
- 循環論法:科学的事実を証明するために、その事実によって作られた装置を使うという論理の循環。
- 強固な発言:多くの支持者や装置に裏付けられ、反論が困難になった科学的言説。
3分要約
本書『科学が作られている最中』は、科学技術の成果を所与のものとして受け入れるのではなく、それが「作られる」プロセスを追跡するための方法論を提示する。著者ラトゥールは、科学的事実や技術的な人工物は、完成した瞬間に内部の複雑な交渉や闘争が「黒い箱」に隠されてしまうと指摘する。そこで読者に対し、科学者が論文を書き、実験室で争う「科学が作られている最中」の現場に立ち会うことを勧める。
第一部では、科学者がどのようにして自らの主張を強固なものにしていくかを分析する。第1章では、科学論文が単なる知識の報告ではなく、反論を想定した修辞的な武器であることを示す。論文中の引用や図表は、読者を味方につけ、敵対者を黙らせるための資源として機能する。第2章では、実験室に焦点を当てる。科学者の主張は、実験室という特殊な空間で作られた人工的な現象によって裏付けられる。しかし、その現象の存在を証明するためには、当の主張が正しいことを前提とする装置が必要になるという循環が生じる。
第二部では、科学者のネットワークがどのように拡大し、強固になるかを考察する。第3章では、科学者や技術者が自らのプロジェクトに他者を引き込むために、彼らの「関心」を「翻訳」する必要があると論じる。例えば、ある研究に資金を提供してもらうには、資金提供者の目的と研究の目的を一致させるよう、うまく言いくるめる必要がある。第4章では、こうして集めた同盟者の数と資源が、科学的主張の強さを左右すると述べる。多くの研究室や産業界を味方につけた主張は、反論が困難になる。
第三部では、ネットワークが社会全体に広がる様子を描く。第5章では、合理性や科学的方法といった概念自体が、特定のネットワーク内部でのみ有効な「審判」の産物であると論じる。ある集団にとっての「事実」は、別の集団にとっては単なる「意見」に過ぎない。第6章では、コロニーや探検隊から集めた標本やデータを集積する「計算の中心」としての研究所や博物館の役割を分析する。これらの中心は、遠く離れた場所から収集した情報を組み合わせ、新たな事実を生み出す力を獲得する。結論としてラトゥールは、科学の力は、より多くの味方(人間と非人間)を動員し、より長いネットワークを構築した者に帰属すると主張する。
各章の要約
序論 パンドラの箱を開ける
本書の目的は、完成した科学技術の「黒い箱」を開け、それが作られる現場を観察することだと宣言する。科学的事実や技術的物体は、それが当たり前になった瞬間に、その形成プロセスが不可視化される。読者は、科学者が議論し、実験し、同盟者を募る「作られている最中」の科学に立ち会わなければならない。著者はこう述べる。「科学の『中身』に入り込む前に、我々は科学の『外部』から出発しなければならないのである。」
第1章 文献
科学論文は、客観的な真理を伝える媒体ではなく、論争に勝利するための戦略的なテキストである。著者は、論文がどのように引用を用いて味方を増やし、反論の可能性を潰していくかを分析する。論争が激化すると、論文はより専門的で技術的になり、読者を限定することで議論の質をコントロールしようとする。最終的に、多くの数字や図表を動員した論文は、反論するためには同様の装置が必要となる「強固な発言」へと変貌する。
第2章 実験室
科学者の主張は、実験室という人為的な環境で生み出された「現象」によって支えられている。しかし、ここには循環論法が潜む。ある現象を記録する装置は、その現象の存在を前提として作られているからだ。論争の相手は、この「事実」を覆すために、独自の「対抗実験室」を構築し、異なる装置と手法で同じ現象をテストしようとする。科学者が「自然」に訴えるとき、それはすでに実験室という人工物を通してしか姿を現さない。
第3章 機械
事実や機械を構築しようとする者は、まず他者の「関心」を自らのプロジェクトへと「翻訳」しなければならない。これは、純粋に科学的な問題を、他者の目的や利益に結びつける作業である。例えば、新しいエンジンを開発するには、軍には「より速い戦車」、企業には「より安いコスト」として提示する。関心を獲得した後も、同盟者が逸脱しないよう、様々な装置や規則で彼らを「繋ぎ止めて」おく必要がある。この翻訳と繋ぎ止めのプロセスが、科学技術の普及を説明する翻訳モデルの中核である。
第4章 部外者を内部へ
科学者の強さは、どれだけ多くの人間や資源を自らの研究室に引き込み、味方につけられるかにかかっている。この章では、外部のアクターを内部に取り込むための具体的な戦略を検討する。資金提供者、産業界、政府、他の研究者。これら多様なアクターそれぞれに対して、異なる関心に合わせた「翻訳」を提示し、彼らをプロジェクトの一部とする。集めた同盟者の数と、彼らから調達できる資源(データ、装置、資金)が、科学的主張の信頼性を最終的に決定づける。
第5章 理性の審判
「理性」や「科学的方法」と呼ばれるものは、超越的な審判ではなく、特定のネットワーク内部での合意の結果である。異なる集団は、それぞれ異なる「合理性」の基準を持っている。ある集団にとっての強固な事実も、別の集団にとっては理解不能な言説に過ぎない。科学的な論争が決着する時、それはより説得力のある論理の勝利ではなく、より多くの強力な同盟者を動員したネットワークの勝利なのである。
第6章 計算の中心
本章は、遠く離れた場所にあるものを操作する「作用の及ぶ距離」の概念を中心に展開する。探検隊が持ち帰った標本や、測量隊が記録した地図は、研究所や博物館といった「計算の中心」に集積される。これらの中心では、多様な情報が組み合わされ、比較され、視覚化されることで、新しい知識が生み出される。地図を持った探検家は、現地を知らなくともその土地について語ることができるように、「計算の中心」にいる科学者は、集められたデータを操作することで、世界を支配する力を手に入れる。
科学の黒い箱を開ける:作られつつある事実の民族誌 AI考察
by Claude 4.5
完成品ではなく、製造過程を見よ
この本の核心は、タイトルに凝縮されている。「Science in Action」—動いている最中の科学。ラトゥールは読者にこう促す。完成した事実や機械を前にして頭を下げるのではなく、それらが「作られている最中」の現場に立ち会え、と。
私はまず、この視点の転換自体が持つ意味を考えたい。通常、私たちは科学の成果を「発見」として受け取る。ニュートンが万有引力を「発見」したように。しかしラトゥールは言う、それは後から作られた物語だと。実際の科学者は実験室で迷い、争い、同盟者を募り、修辞を駆使して自分の主張を「事実」に仕立て上げる。
この見方は、科学に対する私たちの直感を根底から揺さぶる。もし事実が「作られる」ものなら、客観性はどうなるのか? しかし彼は、科学を否定しているのではない。その生成プロセスを、ありのまま記述しようとしているのだ。
引用が武器になるとき
第1章 でラトゥールは、科学論文を「修辞的な武器」として分析する。これは興味深い視点だ。
論文の引用を思い浮かべてほしい。あれは単なる参考文献リストではない。味方の数を誇示し、敵の論点を先回りして潰すための戦略的資源なのだ。「既に多くの研究者がこの結論を支持している」—この一文に込められた力は大きい。反論しようとする者には、これら先行研究すべてと戦う覚悟が求められる。
論争が激化すると、論文はより専門的で技術的になる。これは一種の「入場制限」だと気づく。理解するには同じ装置や訓練が必要になり、結果的に議論できる者が限定される。最後には数字と図表の洪水。これらに反論するには、同様の装置を揃え、同じ実験を再現するしかない—つまり、相手も「強固な発言」で対抗するしかなくなる。
実験室という舞台装置
第2章でラトゥールは、実験室に踏み込む。ここで彼が指摘する「循環論法」は、科学哲学上の重要な問題をはらんでいる。
ある科学者が「X線が結晶構造を回折する」と主張する。その証拠として、X線回折装置の記録を示す。しかし、その装置自体が「X線が回折する」という前提で設計されている。つまり、証明したい事実を、その事実によって作られた装置で証明している。
これは堂々巡りではないか? ラトゥールはそう問いかける。論争が起これば、相手は別の装置で「対抗実験室」を構築する。そして決着がつく時、それは「自然の声」が聞こえたからではない。より多くの同盟者(人間と装置)を動員した側の「事実」が、黒い箱に納められるのである。
ここで私は、日本の研究現場を想像する。理化学研究所の大型施設で、膨大なデータを生産する科学者たち。彼らの「事実」は、まさにこの装置と人間のネットワークから生まれている。ラトゥールの記述は、どこか民族誌的なリアリティを持つ。
関心を翻訳する
第3章の「翻訳」概念は、アクターネットワーク理論の中核だ。科学者や技術者は、自分のプロジェクトに他者を引き込むため、彼らの「関心」を自らの言葉で「翻訳」し直す。
新しい電池技術の研究者を想像する。彼は自動車メーカーには「低コスト」と語り、環境団体には「持続可能」と語り、軍には「高出力」と語る。同じ技術でも、相手の関心に合わせて姿を変える。そして一度引き込んだ同盟者は、特許や規格や装置で「繋ぎ止める」。逸脱させない仕組みが必要なのだ。
この翻訳モデルは、従来の「優れた技術は自然に普及する」という拡散モデルとは対照的だ。ラトゥールは、普及には絶え間ない政治的・社会的な労力が伴うと主張する。これは技術経営の現場でも実感できる視点だろう。
誰が味方かが真実を決める
第4章から第6章で、ネットワークは拡大する。外部のアクター(資金提供者、政府、産業界)を内部に取り込み、同盟者の数を増やす。多くの研究室や産業界が支持する主張は、反論が極めて困難になる。
第5章の「理性の審判」は挑発的だ。合理性や科学的方法は、超越的な基準ではなく、特定のネットワーク内部の合意だという。ある集団にとっての事実は、別の集団には理解不能な言説に過ぎない。論争の決着は、より強力な論理の勝利ではなく、より多くの強力な同盟者を動員したネットワークの勝利なのである。
最終章「計算の中心」は、地理的なメタファーが鮮やかだ。探検隊が持ち帰った標本、測量隊の地図は、パリやロンドンの研究所に集積される。ここでデータは比較・加工され、新たな知識となる。地図を持つ者は、現地に行かずともその土地を語れる。同様に、「計算の中心」にいる科学者は、集められたデータを操作することで、世界を支配する力を手に入れる。
科学の外部から内部へ
序論でラトゥールは言う。「科学の『中身』に入り込む前に、我々は科学の『外部』から出発しなければならないのである」。
これは逆説的だ。内部を知りたければ、まず外部から攻めよ、と。完成した科学を「ブラックボックス」として扱い、その中身を問題にしない。代わりに、それを取り巻く人や装置や論文のネットワークを追跡する。そうすることで、中身が「作られる」プロセスが浮かび上がる。
私はこの方法論に一貫性を感じる。科学的事実を説明のために使うのではなく、説明の対象にする。これが科学社会学の基本姿勢だろう。
残る問い
しかし、いくつかの疑問も湧く。
第一に、ラトゥールの記述は科学者の実際の行動をどこまで正確に描いているのか。彼自身の方法論は、どの程度の「ネットワーク」に支えられているのか。本書の主張が広く受け入れられたのは、説得力のためか、それとも十分な同盟者を集めたためか。これは自己言及的で難しい問いだ。
第二に、この視点は科学の「真理」を相対化しすぎないか。たしかに事実の構築プロセスは社会的だが、それでも最終的に「自然」は沈黙していないのではないか。薬の効能や橋の強度は、ネットワークがいかに強固でも、物理的現実に制約される。ラトゥールは非人間もアクターに含めるが、その「声」がネットワークにどう影響するかは、さらに分析が必要だろう。
第三に、この方法論は日本の科学技術政策にどう応用できるか。例えば、日本の研究開発プロジェクトを「アクターネットワーク」として分析すれば、成功と失敗の要因が新たに見えるかもしれない。しかし、それには詳細なフィールドワークと、関係者への深い聞き取りが必須だ。
本書の価値は、科学を「崇拝の対象」から「分析の対象」へと引き戻した点にある。科学技術が社会の隅々に浸透した現代、その生成プロセスを問い直す作業は、ますます重要性を増している。ラトゥールは私たちに、ブラックボックスを開ける勇気と、その方法を同時に与えてくれるのだ。