コンテンツ
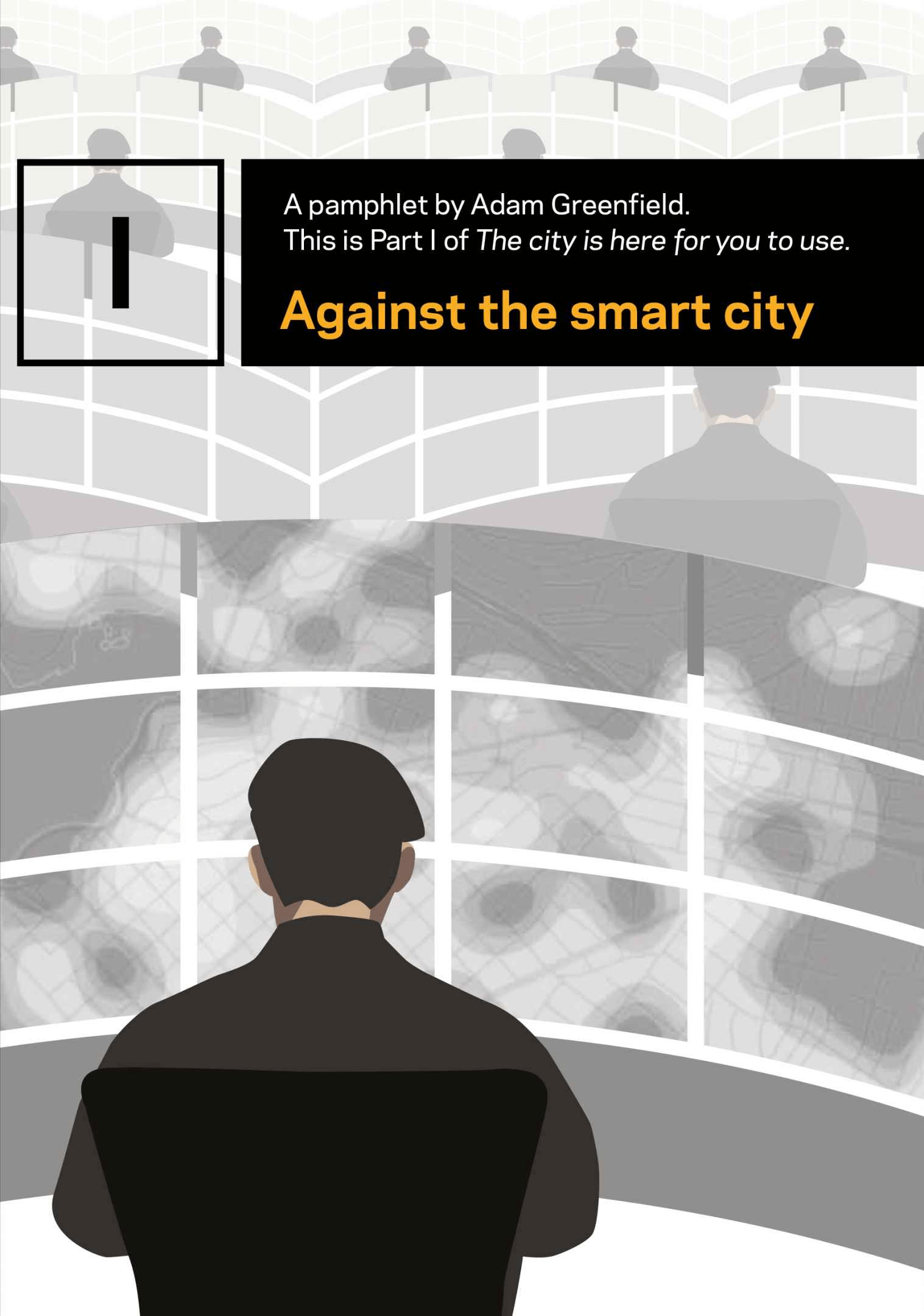
Against the smart city (The city is here for you to use)
Adam Greenfield
目次
- タイトルページ
- 献辞
- エピグラフ
- 「スマート・シティに抗して」への前評判
- 0. スマートシティとは何か?
- 1. スマートシティは一般的な空間に構築される。
- 2. スマート・シティは一般的な時間の中で展開する。
- 3. スマート・シティは、テクノロジーそのものを
- 4. スマート・シティは客観性を装う。
- 5. スマートシティは独自のプラットフォーム上に構築されている。
- 6. スマートシティはオーバースペックである。
- 7. スマート・シティは、信用されないことを前提としている。
- 8. スマートシティは不適切なシステムを前提としている
- 9. スマート・シティのシステムは、そのようなシステムのために導入されている。
- 10. スマート・シティは、それを前提にしている。
- 11. スマート・シティは一連の可能性を提示する
- 12. おそらく最も非難されるべきなのは、スマートシティだ。
- 13. スマート・シティは、トーン、テナー、フォームにおいて複製される
- 14. スマート・シティに技術的な可能性を与えているのと同じである。
- 謝辞
- 参考文献
- アダム・グリーンフィールドについて
- This is Do 1302.
- ノート
2013年10月13日
いつも私のナターシャであるNのために、彼女のレミーから。
「アルファヴィルではなく、ゼロヴィルだ」
AI解説
本書は、近年注目を集めている「スマートシティ」構想に対する批判的な考察を行い、その問題点を浮き彫りにしながら、都市とテクノロジーの関係性についての新たな視座を提示している。
著者は、スマートシティの代表的な事例を詳細に分析し、そこに見られる共通の特徴を指摘する。すなわち、都市を抽象的な空間とみなし、文脈から切り離された形で技術を導入しようとする姿勢、効率性と最適化を至上の価値とする技術主義的な志向、都市の複雑性と多様性への理解の欠如、公共性よりも民間企業の利益を優先する新自由主義的なイデオロギーとの親和性などである。
こうしたスマートシティの言説は、都市の有機的で創発的な側面を無視し、トップダウンの管理と制御を正当化する権威主義的な統治と結びつく危険性を孕んでいる。さらに、20世紀のモダニズム都市計画の轍を踏襲し、非人間的で画一的な都市空間を生み出しかねない。
著者は、スマートシティの技術的基盤そのものを否定するのではなく、むしろその可能性を、より民主的で持続可能な都市の実現のために活用すべきだと主張する。そのためには、技術の導入をめぐる意思決定プロセスにおける透明性と市民参加の拡大、データの民主化とオープン化、都市に内在する多様な価値観の尊重、コミュニティの主体性の重視など、抜本的な方向転換が不可欠である。
本書は、都市とテクノロジーの関係性をめぐる批判的な議論に新たな視点を提供すると同時に、スマートシティという言葉に還元されがちな技術と都市の未来の可能性を、より豊かなものへと開いていく試みとして高く評価できる。技術万能主義に陥ることなく、都市に生きる人々の多様な営みを支え、エンパワーメントにつなげていくようなオルタナティブなビジョンの必要性を説得的に論じた本書は、都市計画や情報学、社会学など様々な分野に示唆を与える重要な一冊と言えるだろう。
各章のAI要約
0. スマートシティとは何か?
現在、世界人口の多くが都市部に集中し、これらの都市は広大な影響圏を持つ。都市生活者の環境認識や利用方法は大きく変化しつつある。この変化は、強力なアイデアと技術の複合体に関係しており、日常環境に大きな影響を及ぼし始めている。スマートシティのビジョンはこの出会いを意味づける物語だが、可能性のほんの一端しか描いていない。本書では、スマートシティ言説で何が語られ、誰によって語られているかを探り、懸念すべき点を浮き彫りにし、より実りある可能性を指し示す。
1. スマートシティは一般的な空間に建設される。
代表的な3つのスマートシティは、「グリーンフィールド」と呼ばれる未開発の土地に一から建設された。デベロッパーは、白紙の状態から都市を作ることで、制約のない自由を得ている。これは最適な管理・サービス提供の実験に理想的な舞台となる。情報技術業界は伝統的に製品・サービスの利用環境を「純粋な背景」と見なす傾向があるが、スマートシティ提案者も都市を事業の抽象的な地形と捉えている。しかし、物理的・人間的地形の特性を無視することは問題を招く。スマートシティのビジョンには、場所の特性から生まれる都市の知性への理解が欠けている。
2. スマートシティは一般的な時間の中で展開する
スマートシティの提唱者は、都市の物理的実在性は強調するが、肝心の「スマート」な性質については、時間に対して早合点な言葉遣いをする。スマートシティは常に「近未来」に位置づけられ、現在と未来が混在する奇妙な時制で語られる。具体的な成果よりも可能性が強調され、完全な実現を遠い未来に設定することで現時点での説明責任が回避される。物語では、テクノロジーだけが進歩し、生活様式は変化しないという非現実的な想定がなされている。過去の「明日の都市」の教訓から、スマートシティも実現しない可能性が高いが、想定外の形で出現するかもしれない。
3. スマートシティは、テクノロジーそのものを一般的なものとして位置づける
スマートシティの描写では、中核となるはずの情報技術製品やサービスが、一般的で特質のないものとして扱われる。具体的な技術仕様や調達・設置の詳細は明示されず、曖昧なままだ。しかし、情報技術のコンポーネントはモジュール化されているが、それらから構成されるシステムは個別のもので、簡単に互換性を持たせられるものではない。個々の技術選択がユーザー体験や長期的利用に大きな影響を与える点が看過されている。また、スマートシティの技術は地域の慣習、法律、ビジネスモデルなどの文脈と不可分であり、それらを切り離して分析・移植することは難しい。一般的な未来の風景に一般的な技術を導入することを提案することで、提唱者は実際の導入で生じる複雑な問題から目をそらしている。
4. スマートシティは、原理的にさえ達成不可能な客観性、統一性、完全な知識を装っている
スマートシティの価値提案には、世界は完全に知りうるものであり、その内容は列挙可能で、技術システムで符号化できるという論理実証主義的前提が根底にある。しかし、システムを観察することはそれに介入することであり、センサーは世界の一部の性質しか捉えられない。データ収集には様々な歪みが入り込む余地がある。人間の行動の意味が一義的で機械に理解できるという前提も非現実的だ。「データはデータ」というスマートシティ推進者の主張は、データ収集の政治性を覆い隠している。また、都市には多様な価値観が存在し、単一のパレート最適解は存在しない。都市管理のアルゴリズムを作ること自体が政治的行為だが、設計者の説明責任への言及はない。NYランド研究所の失敗は、モデルの欠陥と政治的歪曲がもたらす悲惨な結果を示している。都市の複雑性を考えれば、自律システムによる完璧な制御は不可能であり、都市を一元的な目標の存在とみなすのは誤りである。
5. スマートシティは独自のプラットフォーム上に構築されている
情報技術システムは、独占的な知的財産として公開されるか、オープンソースのライセンス条件で公開される。この選択はシステムの利用や発展に大きな影響を与える。オープンなシステムや標準は普及しやすく、セキュリティ面でも優れ、低コストで、参入障壁が低い。自由なライセンスは共有と協力の価値観に基づいている。しかし、スマートシティ情報基盤のオープン性や、データの自由な再利用などの仕様の詳細はベンダーの資料からは不明確だ。リビングプラネットは「完全にオープン」と「独占的な所有と収益化」という矛盾した主張をしている。シスコやシーメンス、IBMはオープン技術の部分的採用とプロプライエタリなシステム統合で利益を上げる戦略をとる。スマートシティの情報システムには、コミュニティや個人に対する十分な説明責任が求められる。しかし、スマートシティ構想では、市民が自ら生成したデータへのアクセスが、有料サービスを通してのみ可能になるといった制限が示唆されている。
6. スマートシティはオーバースペックである。
スマートシティでは、あらゆる面にセンサーやアクチュエーターを組み込むことが提案されているが、継続的なアクセスの必要性が考慮されていない。情報システムの部品は物理的構造よりも速いペースで進化するが、陳腐化や故障のリスクが考慮されていない。すでに普及しているスマートフォンなどのモバイル技術の可能性も活用されていない。過剰な仕様は設計者の思い上がりと将来の用途変更への硬直性をもたらす。都市機能を固定的なゾーンに分離するモダニズム都市計画の手法が踏襲されており、新しいニーズや創発的秩序に対応できない。多様な用途の混在と人々の自由な活動の追求こそが都市の本質だが、スマートシティ計画はこれを無視している。オーバースペックは技術的・社会的変化への適応力を損なう。進化する状況に対応する柔軟性が組み込まれていないのだ。
7. スマートシティは、シームレスという信用できない概念を前提にしている。
「シームレス」という言葉は、技術的に媒介された体験の途切れのなさを意味し、情報技術の介入で都市生活の不便や疑念、遅延が除去されることを約束するものとして語られる。しかしシームレスなシステムは内部動作の不透明性ゆえに、故障時のトラブルシューティングを難しくする。一度に完全に故障するリスクもある。都市生活の興味深く価値ある多くのことは、異なる状態間の継ぎ目やインターフェイスで生じるのに、シームレス化はこうした機会を奪う。日常のささいな摩擦の中にも、個人や地域社会に有意義な働きをするものがある。シームレス化は、消費者体験に適した価値観の都市への無批判な持ち込みを意味する。公共サービスと民間サービスのシームレスな統合は両者の区別を曖昧にし、民主的説明責任を損なう。都市の問題点の理解も妨げられる。スマートシティのビジョンには、都市の主体性や市民性を驚くほど受動的に捉える価値観が組み込まれている。
8. スマートシティは不適切な最適化モデルを前提としている。
スマートシティ言説で頻繁に使われる「最適化」という言葉は、経営管理の文化に根付いた考え方の不適切な応用例である。抽象的な「最適化」は意味をなさず、何を犠牲にするかが明示されない限り評価できない。都市を最適化可能な機械とみなすのは見当違いで、資源配分の優先順位づけは民主的プロセスでのみ正当化される。効率至上主義は都市生活の単純な楽しみを見落とす。非効率性にはゆとりと冗長性という価値があり、問題解決の多様性、スキル習得、不測の事態への緩衝材となる。ストライキや抗議行動など、効率を妨げる活動も重要なフィードバック機能を果たす。スマートシティ言説は、都市の複雑性を無視し、政治が技術システムのように管理できると想定している。効率が都市プロセスの唯一の判断基準だと本気で信じているのか、誰の利益のための最適化なのかを問う必要がある。
9. スマートシティのシステムは、管理者だけの利益のために導入されている
スマートシティ言説では、住民は重要なステークホルダーとして扱われず、焦点は公共セクターや私有地の開発者・所有者に当てられる。関連する白書は制度的投資のケースを作ることに偏り、市民はデータ提供者や消費者としてしか登場しない。巨額の投資は、市民のためというより、都市管理者に市民の行動を調整するツールを与えることを目的としている。IBMのインテリジェント・オペレーション・センターは、セクターと機関の意思決定を重視し、市民の直接参加は想定していない。スマートシティにおける市民の役割はデータ生成だけで、コミュニティ改善のための能動的行動は期待されていない。収集データの分析結果を市民と直接共有する規定はなく、情報アクセスの制限は管理者の特権を守るためと解釈できる。スマートシティ技術は管理者の特権強化のために構想されており、市民は受動的な制御対象とみなされている。
10. スマートシティは、新自由主義的な政治経済が前提となっている(実際、新自由主義的な政治経済以外を想像するのは難しい)
正統的なスマートシティは、民営化、規制緩和、自由貿易、小さな政府を主張する新自由主義の論理を前提としている。この思想は表立っても語られ、マスダールシティ代表の発言などに端的に表れている。スマートシティでは、都市機能だけでなく都市全体の所有・運営の民営化が当然視されており、強固な自治コミュニティや公共圏の形成が難しい。スマートシティは通常の法律から除外された経済特区に立地することが多く、外資誘致のために優遇措置や規制緩和が導入される。地元の利益より国際的資本の流れが優先される。法人税・所得税の減免、賃料補助など新自由主義的政策がインセンティブとして提供される。都市財政難を所与とする言説が大手ベンダーに無批判に再生産されている。情報技術と新自由主義の間に本質的な結びつきはないが、スマートシティのビジョンそのものが市場原理重視のアクターによって生み出されたため、両者は分かちがたく結びついている。スマートシティの住環境は特権階級の飛び地「邪悪な楽園」に類似しており、壁の外の貧困層を過酷な環境に追いやることに依存している。新自由主義とハイテク都市の親和性が問われるべきだ。
11. スマートシティは、権威主義の行使と不穏に一致する一連の可能性を提示している
スマートシティは公共圏の概念が弱い政治的環境に立地することが多い。松島の民主的権利の保護は不透明で、マスダールシティは権威主義的なアブダビの法理に基づく。建設労働者への虐待や学者・活動家への弾圧も横行している。PlanITバレーでは政治のあり方への言及がない。スマートシティの監視・予測技術は市民的権利の土壌が弱い場合、抑圧に利用される危険性がある。リオでは貧困層の強制立ち退きの口実にIBMのシステムが使われた疑惑がある。観光業者や不動産業者の利益のために貧困層が犠牲になっている。スマートシティ言説には都市管理への執着が市民の行動管理への欲望に変質している面がある。シンガポールの厳格な規制がモデルとされがちだ。シスコの推奨する「緩やかな」行動変容アプローチも、外発的動機づけによる行動操作を肯定する点で問題がある。ベンダーが権威主義国家に親和性を示すのは、意思決定の迅速さへの憧れと、大企業との取引を好む構造的傾向が背景にある。しかし、権威主義的効率性は常に暴力に支えられている。スマートシティ技術のベンダーがそれを容認することは、この取り組み全体に暗い影を落とす。
12. おそらく最も非難されるべきなのは、スマートシティは都市とはほとんど関係がないということだ
スマートシティのスタンスやコミットメントの多くは、都市とはほとんど関係がない。新松島の開発者は世界の偉大な都市の表面的な要素の寄せ集めで都市の本質を再現できると誤解している。提案されるスマートシティは規模の点で「都市」と呼ぶには小さすぎる。単一の市場セグメントのみで構成され、都市を特徴づける多様性を欠く。用いられる情報技術は都市に特化したものではない。ユビキタスなデータ収集は都市機能に不可欠なインフォーマルセクターを抑圧しかねない。スマートシティの核心にあるのは、予測不可能なものへの不快感と、リスクを排除してコントロールを確立する欲望だ。自治体ガバナンスの目的は株主価値の最大化以上のものではないと想定されている。「居住者支援と利便性システム」というフレーズに象徴されるように、提唱者の都市概念は侮蔑的なほど貧弱だ。スマートシティに商業的関心を持つ人々は、舞台である都市について十分理解していない。
13. スマートシティは、20世紀のハイ・モダニズムの都市計画手法から連想される失策のすべてとは言わないまでも、その基調、調子、形式、実質のほとんどを再現している
スマートシティ構想の原則の多くは、1880年から1960年の高度モダニズム都市計画の理念と共通する。唯一の違いは新自由主義との親和性だ。効率性重視、行政志向、完璧な都市形態への信念など、スマートシティ言説はル・コルビュジエの都市理論(輝く都市)と驚くほど共鳴する。ル・コルビュジエが主導したCIAMはハイモダニズムを主流化したが、シャンディガールやブラジリアの実際の都市環境は平等主義的価値観を反映していなかった。1960年代までに、ル・コルビュジエ流の都市計画が生活の質を支えられないことが明らかになり、プルイット・イゴーの取り壊しが象徴的な出来事となった。設計の過剰な仕様はメンテナンスを困難にした。ジェーン・ジェイコブズらによる批判で1960年代末にはハイモダニズムの欠陥が広く認識された。スマートシティ構想にはこの過ちが再現されており、都市への本質的な敵意も共通している。ハイモダニズムの失敗から得られた教訓が無視され、同じ過ちが繰り返されようとしている現状への著者の失望が語られる。
14. スマートシティを生み出す技術的な可能性と同じものを、より手応えのある目的に向けることができる
スマートシティを生む技術は、提唱者の想定とは異なる有益な目的に用いることができる。データ収集・分析インフラを市民が活用して問題提起や議論を行うことが可能だが、機関の抵抗も予想される。市民が生成したデータへの自由なアクセスを確保し、地域のニーズに応えるために活用すべきだ。各都市の市民をグローバルな流動空間のノードとして力づけ、都市間の相互依存を認識して全体の回復力を高める必要がある。技術的介入によって都市的な知性や主体性の出現を支援することに焦点を当てるべきだ。スマートシティ言説は、都市的知性を高める方法への問いを無視している。
–
実在する場所とニーズに根ざし、開放性と説明可能性を備え、単なる効率ではなく価値のバランスを追求し、変化に適応できるデザインが求められる。技術的洗練性と同時に、長年にわたって機会と再発明の原動力として機能してきた都市の価値観とプロセスを尊重することが肝要だ。
スマートシティは、都市が複雑すぎて一般市民には管理できず、統治は市民に任せられないという仮説を内包している。これに代わる根本的に異なる都市像、すなわち情報技術を市民のエンパワーメントのために活用する都市を、私たちは想像し、実現していかなければならない。
『スマートシティに反対する』への前評判
アダム・グリーンフィールドは、21世紀の「都市再生」のために、20世紀のジェーン・ジェイコブスが行ったことを行っている。
– イアン・ボゴスト、アイヴァン・アレン大学メディア研究特別講座、ジョージア工科大学インタラクティブ・コンピューティング教授。
スマートシティの制約された現実と、その自由奔放な物語を批判的に探究する。このテーマに関するアダム・グリーンフィールドの膨大な知識は、「スマートシティのイデオロギーが最も純粋な表現を見出す」極限の瞬間を突き止めることを可能にしている。素晴らしい分析であり、鋭い釈義であり、そして素晴らしい文章である。
– サスキア・サッセン、コロンビア大学、『グローバル・シティ』の著者。
テクノロジーの最も優れた、最も広範に力を与える都市への応用がまだ展開されていないと考える人々にとって、本書はあなたのためのものだ。本書は、支配的なスマートシティの物語に「反対」しているというよりも、グリーンフィールドがスマートシティを解体した後に残る部品や断片から、我々がまだ組み立てるかもしれないものを考えるための基礎となるものだ。
– ジョン・トルバ、シカゴ市最高技術責任者
アダムはスマートシティのマーケティング・ゲームをばっさり切り捨てる。彼は、偉大なアーバニストがそうであったように、都市とは人であり、その人らしさ、主体性、独立性、そして知性によって都市をボトムアップで形成する人であることを思い出させてくれる。
– ベンジャミン・デ・ラ・ペーニャ、ロックフェラー財団
スマートシティを論破する。アダム・グリーンフィールドは、ウィットと明晰さをもってこの言葉を論破し、スマートシティはスマートでもシティでもないことを暴く。洞察に富み、タイムリーで爽快な読書は、明日の都市を再考させるだろう。
– J・ミージン・ユン、マサチューセッツ工科大学、建築家・デザイナー。
世界中の「スマートシティ」提唱者は、この短い本を読むべきだ。市議会で引用される前に、今すぐ読もう。
– ブルース・スターリング(『シェイピング・シングス』著者
0. スマートシティとは何か?
AI解説
- スマートシティの定義:ネットワーク化された情報技術を都市環境に組み込むことで都市の管理を最適化しようとする取り組み。センサーから大量のデータを収集・分析し、都市プロセスの可視化と制御を目指す。
- スマートシティの2つのアプローチ:1つは松島やマスダールシティのように情報技術を最初から組み込んで一から設計された都市、もう1つは既存都市にセンサーなどの技術を後付けで導入する取り組み。
- スマートシティ技術の主要プレイヤー:IBM、シスコシステムズ、シーメンス、リビングプラネットなどの大手IT・電機メーカーがソリューションを提供。都市計画の専門家ではなく企業主導でコンセプトが形成されている点が特徴。
- 各社のスマートシティビジョン:IBMは意思決定の最適化、シーメンスは自律的なITシステムによるサービス提供、シスコは共通ネットワーク上の公共・民間サービス統合、リビングプラネットは建物単位の管理最適化などをうたう。
- スマートシティ言説の問題点:コンセプトの具体性に乏しく、プロモーション資料からは都市や機能に関する企業のモデルや哲学が読み取りにくい。言説の背後にある前提を慎重に吟味する必要がある。
- ネットワーク技術の都市への浸透:スマートシティの取り組みを通じて、ITが都市空間を大きく変容させつつある。その影響を理解するには、スマートシティの言説を鵜呑みにせず批判的に分析することが重要。
この問題の輪郭をどのように測定し定義するかにもよるが、現在30億人から40億人の人々が、私たちが都市と考える密集した居住地で暮らしている。これは、これまで以上に高い割合を占めているだけでなく、地球上の人口が大幅に増加しているため、絶対数でいえば、人類史上かつてないほど多くの都市居住者を地球が支えていることになる。
もちろん、これらの都市は以前の都市とは形式的に異なっている。より広い地形に広がり、より大きな容積を占め、さらに遠く離れた後背地をその影響圏に引き込んでいる。私たちは、これらの都市が、それ以前のどの都市よりも、後背地と互いに密に絡み合い、移動と交流の惑星的な網の目のようにつながっていることも知っている。しかし、これらは都市構造や形態の進化的発展であり、程度の差として理解するのが最も適切である。日常的な経験の原動力としてどのような影響を及ぼすにせよ、私たち都市生活者が集団として周囲の環境を理解し、アプローチし、利用する方法において、現在起きている一連の変化に比べれば、相対的に取るに足らないものに過ぎない。
このような体験的変化はごく最近起こったものであり、まだ十分に理解されていない。しかし、目の前にある証拠を信用するならば、それは変革的であり、完全なものに近い。それは、過去10年ほどの間に都市環境に導入された強力なアイデアと技術的能力の複合体と関係している。私たちがもはや「テクノロジー」と考えることを忘れてしまいそうなパーソナル・ネットワーク・デバイスと常時接続のワイヤレス接続、私たちがますます都市の布地に織り込まれているのを見かけるようになったコネクテッド・センサー、アクチュエーター、ディスプレイ・システム、さらには、これらすべてが生み出す膨大な量のデータから感覚を引き出す強力な分析技術などである。この拡張された技術的アーマチュアとの出会いは、多くの場合、何世紀にもわたって都市生活が築き上げてきた基本的な条件を変え始めている。21世紀も後半に差し掛かろうかというこの早い時期からでさえ、このネットワーク化の結果が都市経済に波及し、地域政治を再編成し、日常環境の物質的構成を押し下げ、私たち自身の精神の構造と内容に影響を及ぼすことを、私たちはすでに感じ取っている。
このように複雑で広範囲に影響を及ぼすような状況に直面した場合、出会いを構造化し、意味づけるために物語を活用することは有益である(必要でさえあるかもしれない)。結局のところ、新しいアイデアを統合し、私たちの生活に溶け込ませるのに、自分自身に語りかけるストーリーの中に織り込んでいくことほど強力な方法はないのだ。しかし今のところ、私たちは都市環境におけるネットワーク化された情報科学の展開について、ある特定の物語を提示されているに過ぎない。それは広く文化の中で優勢ではあるが、可能なことのほんの一端を描いているに過ぎない。それが「スマート・シティ」のビジョンである。
私たちの瞬間が生み出すかもしれないあらゆる可能性、そして私たちが都市でネットワーク化された情報技術を利用することを選択するかもしれないあらゆる方法の中で、現在私たちに明示され、進められているスマート・シティの物語は、最も興味深くなく、最も問題のあるものである。この小冊子は、このような枠組みで何が、そして誰によって語られているのかを探るものである。このパンフレットの目的は、スマートシティプログラムの懸念すべき具体的な側面を浮き彫りにし、都市がどのように意味や価値を生み出すかについて私たちが知っていることの多くになぜ反しているのかを明らかにし、最後に、より実りある可能性を指し示すことである。
§
わかりやすくするために、スマートシティというテーマが浮上するたびに混同されがちな、補完的ではあるが別個の、異なる2つの思考と発展の流れを分けて考える必要がある。もともとこの言葉は、過去10年間に開始された少数の個別開発プロジェクト、つまり韓国の新松島、アラブ首長国連邦のマスダール・シティ、ポルトガルのプランITバレーと呼ばれる奇妙な集落のような、何も描かれていない取り組みだけを指していた。これらは、日常生活を構成する物体、表面、空間、相互作用に情報処理機能を組み込んで、一から設計された都市規模の環境である。それらは、地球の都市がネットワーク化されたインフォマティクスによって決定的に植民地化された後、未定義だがそう遠くない未来のある時点で、私たちが住むかもしれない都市環境の先駆者であり模範として、私たちの前に掲げられている。
この文献で最も頻繁に引用されている実際の場所は、53.4km2の新松島市で、より正式には松島国際ビジネス地区(SIBD)として知られている。ニューヨークを拠点とするゲイル・インターナショナルが韓国のポスコ・エンジニアリング・アンド・コンストラクションと共同で開発し、コーン・ペダーセン・フォックスがマスタープランを担当した松島は、黄海から回復した土地に50万人規模の新都市を建設する。その価格は200億ドル1,350億ドル2、さらには400億ドル3など様々だ。
新松島での生活は、まるで高級自動車のように、BMWのよく知られたキャッチフレーズ(「究極のライフスタイルと仕事体験4」)に近い言葉で売り出されている。この「究極のライフスタイル」は、バイオメトリック入退室管理から全自動宅配便まで、さまざまな進化を遂げてきた。現在の主契約者であるシスコシステムズが作成したプロモーションビデオでは、壁一面のユビキタスなビデオ会議スクリーン、「インテリジェントな道路料金設定」、視聴者の人口構成の変化にリアルタイムで適応する広告表示などが宣伝されている。まるで『マイノリティ・リポート』をディストピアのビジョンではなく、ショッピングカタログやパンチリストとして捉え、その結果を沖合に横たわる数千エーカーの干潟に設置したかのようだ。
松島のすぐ近くには、ロンドンを拠点とするフォスター+パートナーズがマスタープランと建築設計を手がけた、220億ドル5,000万ドルのアブダビのマスダール・シティがある。わずか6平方キロメートルのマスダール・シティは、政府が所有する持続可能なエネルギー関連企業の名前を冠しており、首長国の他の地域から通勤する最大5万人の労働者によって毎日増員される約4万人の定住者を収容する予定だ。マスダールは、直線的な公園を挟んで低層ビルが密集している。内部は、ネットワーク化された入退室管理やエネルギー管理など、期待されるあらゆる設備6を備えているが、マスダールでは建物と建物の間のスペースに重点が置かれているようだ。この都市の推進者たちは、この都市を技術的に実現された、果てしなく荒れ果てたエンプティ・クオーターのオアシスとして描いている。高度に反応するインフラが日射量と湿度を調整し、容赦ない砂漠の空気そのものから快適さを引き出し、空港型の全電気式個人用高速輸送ネットワークが従来の自動車の必要性をなくす場所である。
ポルトガルのパレデス郊外にある100億ユーロ(約7,000億円)の町は、スイスに本社を置くLiving PlanIT社が、マイクロソフト、シスコシステムズのスマート+コネクテッド・シティ部門、英国のエンジニアリング・コンサルタント会社Buro Happoldの協力を得て開発中のものだ。リビング・プラニットが「ボストンのダウンタウンとほぼ同じ大きさ」8と表現している6.7km2のPlanIT Valleyは、マスダール・シティよりもわずかに大きい。しかし、最終的な目標人口22万5,000人9は、マスダール・シティの数倍であり、はるかに大きな松島(ソンド)の予想人口のおよそ半分である。(実際、彼らの言葉を鵜呑みにするならば、ポルトガルの田舎の緑豊かな丘陵地帯に建設されるのは、ムンバイ、コルカタ、カラチ、ラゴス10よりもはるかに高密度のコミュニティである)
松島やマスダールと比べても、プランITバレーの日常生活におけるネットワーク化された情報学の役割は、積極的に構想されている。少なくとも理論上は、都市内のあらゆる接続された空間、乗り物、デバイス、衣服の相互作用を管理する、統一された都市オペレーティングシステムに他ならない11)。エネルギー利用、モビリティ、アクセス制御、仕事、レジャー、エンタテインメントのすべてが同じデジタル・フレームワークによって媒介されるため、プランITバレーは現在、計算機によって管理される都市環境のコンセプトにおけるネプラスウルトラの立場にある。
§
これが、典型的なスマートシティである。過去半世紀にわたり、スマートシティに関する息の長い論評は枚挙にいとまがない。この分野の研究者は、熱心なデザインブログから『エコノミスト』誌のような権威ある雑誌に至るまで、講演に次ぐ講演、記事に次ぐ記事で、これらの名前を何度も何度も取り上げている。それらは完成度の差こそあれ(特にプランITバレーは、主張と約束が永遠に先延ばしにされているに過ぎない)、21世紀の都市を支えるシステムのプロトタイプであり、ポールスターであり、さまざまな意味で参考となる実装として、私たちに提供されている12。
しかし、「スマートシティ」という言葉が指し示すものは他にもある。それは、ネットワーク化された情報技術を既存の都市の場所に後付けしようという、より広範ではるかに重大な動きである。マスダールや松島のような場所を建設する努力とは異なるが、後者の文化的・知的生産には、同じ技術、手法、慣行の多くが関わっている。もう一度言うが、都市のプロセスに関する有用な総合的認識は、建築環境全体に散在するセンシング・デバイスから得られるという考え方がある。ゴミ箱にセンサーを、街灯にカメラを、地下鉄にRFIDリーダーを、舗道にロードセルを取り付けるという提案もまた見られるが、この場合、関係するデバイスは、都市の構造そのものに最初から設計されたものではなく、ボルトオンであることが多い(あるいは、データ収集の使命は、すでに設置されたハードウェアの再利用である)。そしてまたもや、データの収集と分析が、誰かの考える自治体のスチュワードシップの中心に据えられていることに気づく。
どちらかといえば、数年の経験の恩恵を受けて、このスマートシティの考え方は、現在私たちの多くが携帯しているネットワーク接続された携帯電話やタブレットを採用することで、さらに私たちの生活にフィーラーを押し込むことができる。これらはインターフェースの対象であると同時に、私たちの居場所、活動、意図に関する最も詳細なデータの情報源として扱われる。しかし、これは単なる推敲に過ぎない。包括的な目標は変わらない。都市に接続されたすべてのデバイスが発する音を集中的に収集し、その結果得られる膨大な量のデータに高度な分析技術を適用することだ。
このような計算による精査の最終的な目的は、都市の管理を任されている人々に、都市のあらゆる展開プロセスを可視化すること、以前は不透明だったことや不確定だったことを、単に知ることができるだけでなく、行動できるようにすること、そして最終的には、偉大な都市を構成する物質、エネルギー、情報の流れすべてを「最適化」できるようにすることだと言われている。このアプローチの典型は、IBMがリオデジャネイロ市のために建設したインテリジェント・オペレーション・センターである。1400万ドルをかけて建設されたこの施設は、気象観測所、交通カメラ、警察のパトロール、下水道に設置されたセンサー、ソーシャルメディアへの投稿などのデータを統合し、作戦会議室風の全体像を把握することができる。このセンターの主な革新性は、計算機による認識と対応の全装置を一つの部屋に集め、管理者がリアルタイムで(理想的には先行して)市のダイナミックなパフォーマンスを微調整できるようにしたことだ。しかし、それ以外の点では、今この瞬間に存在する自治体行政の最先端技術を完全に代表するものである。
このような介入は、ほとんどの場合、段階的な強化の問題である。既存の調達ルートを通じて入手した既製品を、従来の契約を通じてサービスし、すでに存在する空間的・制度的取り決めに付加する。デジタル・センシングとアクチュエーションの技術を取り入れるために一から建設された場所ほど、その野心の範囲は広くない。過去数年間で、地球上の何百もの自治体が何らかの公式なスマートシティ計画13やイニシアチブを採用し、その数は月を追うごとに増えている。このような取り組みによって影響を受ける人口は、すでに数千万人規模に達している。今後10年間で、ネットワーク化された情報技術を都市の管理に統合する取り組みに、数千億ドル、予算総額の少なくない部分、そしておそらく最も重要なこととして、膨大な人的関心とエネルギーが費やされるだろう。そして、この活動は事実上すべて、スマートシティという旗印の下で行われることになる。
松島(ソンド)やマスダール、プランITバレーに住む人はほとんどいないだろうから、仮にこれらの場所が完全に整備されたとしても、一見したところ、この活動を意味するのはほとんど後者だけであるように見えるだろう。そして、IBMのインテリジェント・オペレーション・センターのように、既存の都市に導入されることを想定した介入策を検討することで、私たち自身の生活や選択に関わるスマート・シティの最も顕著な属性、特徴、特質の少なくともいくつかを容易に特定することができるのは事実である。しかし、この小冊子では、スマート・シティのイデオロギーが最も純粋に表現されている場所に、分析の焦点を絞ることにした。このような想定された都市が大きな成果を上げるかどうかは別として、そのような都市のために意図されたものは、必然的に他の地形や他の文脈で同じテクノロジーを応用する際に漏れ出し、色濃く反映されることになる。実際、この領域で現在最先端の実践と考えられていることを学び、このような物事の枠組みで縛られている前提、信念、コミットメント、評価について知り、おそらく私たちが暮らす都市に将来何が待ち構えているのかを知りたければ、古典的で、自己完結的で、希釈されていない形で、この命題を注意深く問うことから始めるより良い場所はないだろう。
§
問題のスマートシティがマスダールであろうとミネアポリス14であろうと、同じテクノロジーが関係しているのと同じように、どちらのバージョンの物語にも、関係するシステムのメーカー、ベンダー、インテグレーターとして、同じ機関のほとんどが登場する。
この仕事に携わっている最も著名な関係者は、ニューヨーク州アーモンクのIBM社、サンノゼのシスコシステムズ社、ミュンヘンを拠点とするシーメンス社などである。これらのグローバル企業は「システム」または「ソリューション・インテグレーター」として機能し、ハードウェアとソフトウェアをシーメンスの「シティ・コックピット」15、IBMの「インテリジェント・オペレーション・センター」ソフトウェア・スイート16、またはシスコが「スマート+コネクテッド・コミュニティ」17のラベルの下で販売しているさまざまな「インテリジェント・デジタル・インフラ」プロジェクトといった、より高度なビジネス提案に統合している。(このグループに、はるかに小規模なLiving PlanIT18を含めたのは、彼らのUrban Operating System19が上記の製品とほぼ同等であることと、彼らがスマートシティのコンセプトを最も精力的に提唱し、たゆまぬ自己宣伝を行っているからである)。
その下には、サムスン、インテル、フィリップス、日立製作所などが参加する第2層の活動がある。比較的少数の例外を除いて、少なくとも今日に至るまで、これらの関係者は、この領域における自分たちの仕事を文脈づけるために、大々的に想像力豊かなヴィジョンを提示しない傾向がある。確かに、より深く投資している同業者たちが制作する大掛かりなコンセプト・ビデオや精巧なインタラクティブ・インスタレーションほど劇的なものはない。しかし、彼らもまた、スマート・アーバニティという既成の言説の中に自分たちが提供するものを位置づけることを選択し、訴求のフレーミングに同じような表現を用いたり、製品やサービスの表向きの利点を説明するために同じ言葉を使ったりしている。
明確な知的先例があることは確かだが20、完全な現代的形態のスマートシティという概念は、都市計画の理論や実践への貢献が認められたいかなる団体やグループ、個人というよりも、むしろこれらの企業の中で生まれたように思われる。つまり、ここに列挙した企業は、驚くほど大きな度合いで、スマートシティの基礎となる技術システムと、それらを概念的に結びつけるレトリックの両方を生み出している21。産業界で一般的な基準からすれば、これは特に驚くべき状況ではないかもしれないが、都市の設計や設備に関するアイデアの萌芽に大規模な商業主体が深く関与していることは、アーバニズムの歴史においてやや異例なことである。まるで、ル・コルビュジエやジェーン・ジェイコブズではなく、ユナイテッド・ステーツ・スチール、ゼネラル・モーターズ、オーチス・エレベーター・カンパニー、ベル電話22が、20世紀の都市思想の基礎となる著作を共同執筆したかのようだ。
このようなレトリックの数々を、それに接する様々な意思決定者、一般市民、その他の人々が少しでも真剣に受け止め、乏しい予算や注目すべきリソースの配分に何らかの形で反映させるのであれば(そして、現在の兆候からすると、そうであり、そうなっているのであれば)、それが何を言っているのかを見極めることは、極めて重要になる。これらの企業は、スマートシティをどのように定義しているのだろうか。そして、自分たちが提供していると信じている価値提案とは、いったいどのようなものなのだろうか。
- この領域に関わるすべての企業の中で、IBMはスマートシティのビジョンを一般大衆に伝えることに最も率直であった(そして、自らの資本を投資することに最も意欲的であった)。2009年半ばから、IBMのシステムが「交通量を20%削減する」、「犯罪を未然に防ぐ」、「よりスマートな地球のために公共の安全を向上させる」などと主張する、一連のジャジーな広告23ポスターが世界中の目立つ場所に掲示された。
これらの広告に興味をそそられた人は、IBM Smarter Citiesのウェブサイトをフォローアップして、さらに詳しい情報を得ることを勧められた。そこでは、IBMが提供するテクノロジーを地域ごとに展開するものだと定義する概要ページがあり、「セクターや機関間の取り組みをその都度同期・分析し、意思決定者が問題を予測するのに役立つ統合情報を提供する。
- シーメンスはこれまで、発電所、街灯、地下鉄車両、廃水処理施設など、潜在的な顧客数が比較的少ない、重厚長大な自治体規模のインフラ・システムの製造と導入に取り組んできた。しかし、IBMの定義の実利主義に比べると、彼らの定義には高い志が感じられる。主要なテクノロジー・インテグレーターの中で、スマートシティに対する野望が最も遠大に表現されている。「今から数十年後、都市には自律的でインテリジェントに機能するITシステムが無数に存在し、利用者の習慣やエネルギー消費を完璧に把握し、最適なサービスを提供するようになるだろう25」と彼らは主張している。(もちろん、そのようなシステムの大部分はミュンヘンで考案され、構築されるということだ)。
- 世界のインターネットトラフィックの大部分26を経由するルーターのメーカーであるシスコシステムズは、スマートシティの惑星が意味する世界的なビットの流れの大規模な激化から、明らかに大きな利益を得る立場にある。彼らの立場からすれば、関連する規模での経験が乏しいにもかかわらず、このコンセプトを組織的に擁護する背景には、それなりに説得力のある論理がある。シスコのSmart+Connected Communities事業部門は、スマートシティを「個人、政府、 企業に共通のネットワークインフラを通じて提供される、公共と民間のサービスがシームレスに統合されたもの」と定義している27。
シスコの定義は、明確にオープンで共有されたインフラを想像させる、私が出会った唯一の定義である。さらに、この定義では、関連するほとんどのアクターが、私が正しいと考える優先順位で説明されている。たしかに、商業的でも政府的でもない集団的な表現形態については一切触れていない。さらに気になるのは、公共と民間のサービス提供の間の重大な意味のある区別を消し去っていることだ。しかし、シスコが表現している地形は、他のどのインテグレーターが喚起している地形よりも、私がよく知っている声の多い異質な都市に似ている。
- 少なくとも、シスコの物事の枠組みは、私が検討したベンチャー企業の中で最も小さく、最も若い企業が生み出すものよりも、具体的な都市生活についてより魅力的なビジョンを暗示している: ニューハンプシャー州を拠点とするLiving PlanITは、「不動産とテクノロジー分野のミッシングリンク28」を構築するために意識的に設立された。(ニューハンプシャー州を拠点とするLiving PlanITは、「不動産とテクノロジー部門のミッシング・リンク28」を構築するために意識的に設立された) Living PlanITによるスマートシティの説明では、「建物の状態、使用状況、運用の全体像」が「継続的に維持され、エネルギー、資源、環境、居住者支援・利便システムの絶え間ない最適化が可能になる」場所とされている29。
この文言は、建物レベルのシステムに比較的タイトに焦点を当てている点で興味深い。ここでの主な革新は、各建物を、管理されたフローの都市全体のメッシュワークと結合させることにあるようだ。この比較的保守的なビジョンと、PlanIT Valleyのショーケースに刻まれた野心との間のギャップを埋めることはおろか、Living PlanITがどのようにしてこれを大規模に達成するつもりなのか、まだわからない。
§
新松島が誕生してから12年ほどが経過したが、新松島が象徴する具体的なビジョンは、技術化された都市を論じる上で避けて通ることはできない。実行における躓き、淀み、不足は十分に文書化されているにもかかわらず、スマートシティの美辞麗句はなぜか印象的な信頼性を保っている。今さらながら、この話題は一般紙でもうらやましいほど注目され、世界各地の市議会や都市主義者団体の議題で大きく取り上げられている。また、マイクロソフトに勝るとも劣らない参入企業を誘うに十分な、説得力のあるビジネスケースを提示しているらしい(レドモンドの巨大企業は2013年7月、この分野のベンチャー企業であるシティネクストの立ち上げを大々的に発表した30)。
しかし、このような動きがあるにもかかわらず、その核となる思想は具体性に乏しいままだ。スマートシティが何をもたらすのか、抽象的な関心事として、あるいは自分たちのコミュニティに影響を与えるような具体的な内容として、深く理解しようとする人たちは、自己中心的なプレスリリースや媚びたブログ記事、そしてこのテーマに必ずつきまとうような軽薄なルポルタージュだけを武器に、貴重な情報をほとんど得ることができない。
そこで私は2011年秋から、スマートシティ推進派が潜在的な顧客や一般市民、その他の利害関係者に向けて自分たちの主張を展開する際に使用した資料を、入手可能な限り精読した。この資料には、広告、ウェブサイト、プロモーション・ビデオ、展示会ブースのコピー、主に機関投資家パートナー向けのPDFや印刷パンフレット、デベロッパーの資料、展示会や同様のイベントを訪れた際に、静的な魅力に引き寄せられるかのように手に取る安価なマーケティング資料などが含まれる。
私は、関係企業の幹部によるインタビューやその他のパブリックコメントを調べ、スマートシティのビジネスケースを分析するコンサルタントが発行した報告書を咀嚼し、業界コンソーシアムが公布した技術標準案を解析した。インタラクティブなディスプレイをタップし、電話会議に潜み、営業担当者にメールを送り、スペックシートを取り寄せた。私の目的は、現在広く出回っているものよりも洗練されたスマートシティについての説明を展開することだった。さまざまな提案を切り離し、その開発の根底にある原理や哲学をより深く理解し、都市とその機能に関するどのようなモデルがそれらに刻まれているかを解明することだった。
最終的に、私はこの試みに着手した企業が21世紀の都市をどのようなものだと考えているのか、どのような側面が重要だと考えているのか、そしておそらくもっと微妙なことだが、そもそも彼らは都市を「それ」として、多様性よりもむしろ単一性として考える傾向があるのだということを、大まかに理解することができた。この不思議な事業について私が感じたことを、ここで皆さんと分かち合いたいと思う。
この後、私が説明することすべてにおいて、杓子定規であるとか、故意に難解であるとか、異論があるかもしれない。結局のところ、単なる宣伝材料に過ぎないものを、このような綿密な分析にかける意味はほとんどない、あるいは、企業がこのような資料を世に発表するときに、彼らが言っていることをそのまま意味していると仮定するのは、どうにもフェアではないと感じるかもしれない。確かにあなたは、私がこれらの発言を傾向的で、敵対的な読み方をしていると思うかもしれない。しかし、私たちは自分たちの仕事を説明し、議論するために選んだ言葉に対して責任を持つ必要があると私は信じている。この要請は、他の誰にとってもそうであるように、都市技術を開発する人々にも当てはまる。もし場所が、地理学者イー・フー・トゥアンの美しい定義である「配慮の場」31と本当の意味で一致するのであれば、場所を構築するために私たちが使う言葉が重要なのは間違いない。したがって、建築家やスマートシティの支持者の言葉を鵜呑みにしない理由はない。
私たちがそれを気にかけるかどうかは別として、現在のところ、私たちの都市はネットワーク化された認識と反応の技術によって、ますます包括的に投資され続けることになりそうだ。地理学者のロブ・キッチン(Rob Kitchin)とマーティン・ドッジ(Martin Dodge)が「コード/空間」32と呼ぶように、都市環境が変容していくのを、私たちはますます目の当たりにすることになるだろう。そして、この変容がスマートシティのレトリックによって少しでも彩られるのであれば、私たちはスマートシティが意味するすべてをより深く理解する必要がある。
スマートシティとはどのような場所なのだろうか?
1. スマートシティは一般的な空間に建設される。
AI 解説
- グリーンフィールド開発:代表的なスマートシティは、都市計画家が「グリーンフィールド」と呼ぶ、これまで何もなかった場所に一から建設された。
- 「何でもありの空間」としてのスマートシティ:開発者は、歴史に影響されず、既存の制約や権利関係のない白紙の状態の土地で、やりたい放題の自由を得ている。これは最適な管理やサービスの提供、民営化モデルの実験に理想的な舞台となる。
- 抽象的な地形としての都市環境:情報技術業界は伝統的に、製品やサービスが使われる環境を「純粋な背景」として扱う傾向があった。スマートシティの提案者も、都市を事業運営のための抽象的な地形と見なしている。
- 場所の特性を無視することの問題点:ある技術を場所を問わず同じように適用することは、時間と資源の浪費につながる。物理的・人間的な地形の特性を考慮することが不可欠。
- 「何でもありの空間」の感受性の欠如:スマートシティのビジョンには、都市が住民のために価値を生む方法への理解が欠けている。かつてはそれが許容されたが、今日、物理空間とデジタル空間の融合が進む中では許されない。
- 都市の知性は場所の特性から:都市の知性は、その土地で進化してきた生活様式や文化の中に存在する。それが根付くには長い時間がかかる。歴史のない土地に一朝一夕で生まれるものではない。
代表的な3つのスマートシティは、いずれも都市計画家が「グリーンフィールド」と呼ぶ、それまで何もなかった、あるいは誰もいなかった場所に、ゼロから建設された。
「我々は、都市主義がどのように行われているかを考えると、周囲に先行開発のない白紙の状態から何かを創造する機会を得たのだ」と、33リビング・プランITのスティーブ・ルイスCEOは説明する: 松島は東シナ海を埋め立てた「不毛の干潟34」に、マスダール・シティは砂漠の低木地帯に、そしてPlanITバレーはポルトガルのパレデス郊外の未開発地に建設された。
ルイスが言うチャンスとは、非常に特殊なものだ。開発者たちは、何もないところから都市を建設し、現実的に可能な限りデカルト平面に近い場所に建設することで、哲学者ジル・ドゥルーズが「何でもありの空間」35と形容した、無条件、ゼロ度、相互接続の無限の可能性を提供する限界的な環境を大地から作り出す。無条件のゼロ度であり、無限の相互接続の可能性を提供する。あらゆる空間は、歴史に影響されず、歴史に刻印されていない。既存の傾向も方向性もない。形式的にも法的にも、白紙の状態なのだ。デベロッパーの視点に立てば、スケジュールを早めること、既存の建築物に制約されることなくグリッドや区画、フロアプレートを考案できること、土地に存在する権利やリース、クレームなどの形態がまったくないことなど、非常に望ましい資質がいくつもある。あらゆる空間に建物を建てることは、デベロッパーにやりたい放題の自由を与える。
ドゥルーズが定義するように、どんな空間であれ、それ自体の品質が重要なのではなく、それが促進する、あるいは存在させるつながりだけが重要なのだ。スマートシティという特殊なケースにおいて、重要なつながりは物理的なものではなく、アイデア、技術システム、実践の間に作られるものである。あらゆる空間に摩擦がないため、市民行動の最適な管理、サービスとしてのガバナンスの策定、そして究極的には、完全に民営化された都市のビジネスモデルの開発における実験の理想的な舞台となる。
何でもありの論理は、既存の場所に建設されるスマートシティプロジェクトにさえも感染する傾向がある。後述するように、マスダール・シティやプランITバレーのような場所は、スマート・シティの実践を行うための実験室として明確に位置づけられている。シスコは明らかに、松島(ソンド)のアパートを彩る一連のテクノロジーを、あらゆる場所の住居に適用するつもりだ。リオデジャネイロ、バルセロナ、ムンバイ、シンガポールのように、歴史も風合いも性格も異なる場所に、まったく同じ技術システムを導入しようという提案(尊敬する関係者37が発案したもので、かなり本格的なものらしい)が存在することからも、関係企業が実際には都市環境を主に事業運営のための抽象的な地形として考えていることが推測できる。
どんなに好ましくないと思われようとも、都市という場所の複雑さに対するこの意志的な盲目的さは、過去半世紀にわたって情報技術に蔓延してきた傾向と見事に一致している。さまざまな理由から、情報システムの設計者は歴史的に、製品やサービスが使用される環境を抽象化した「純粋な背景38」として扱ってきた。当初は、情報技術のすべてのユーザーが開発者でもあり、これらのユーザーと開発者が働く環境(軍、企業、学術機関のコンピュータ施設)は、関連するすべての次元において互いに十分に類似していたため、これらについてこれ以上詳しく説明する必要がなかったからである。その後、スケーラビリティの論理と、「一度作れば何度でもデプロイする39」という命令が支配するようになった。これらは本質的に経済効率からの議論であり、その影響下では、使用環境に関する特に広範な考察は、不要な摩擦の原因以外の何ものでもないと解釈されることはほとんどなかった。この時代を通じて、支配的な言説は概して、技術的人工物そのものを自律的で自己完結的なものとして位置づけ、環境は意味のある行動が展開されるための単なる背景として位置づけてきた。
しかし、マルコム・マッカローやポール・ドゥーリッシュ40のような洞察に満ちた技術観察者が指摘するように、これはそうではないし、決してそうありえない。したがって、ある技術をそのまま移植しようとする試みは、時間、労力、エネルギー、資源の完全な浪費とまではいかなくても、せいぜい「損な」ものになるに違いない。
ある地形における情報技術の展開を考えるとき、その地形の性質が重要になる。インタラクション・デザイナーのマット・ジョーンズは、CM撮影のためにパリからロンドンに飛んだパルクールの達人、トレースールのチームの素敵な逸話を紹介している。彼らは2日間の準備期間中、縁石と歩道、歩道と街灯、バスシェルターと建物の壁の間に足を挟み、ただ通りを歩き回った。彼らは文字通り、その土地のゲージを測り、その木目に体を慣らすのだ。アスリートたちが望む街の利用方法にとって、これらの量のわずかな違いは、成功した作戦と鎖骨の骨折、あるいはそれ以上の違いを意味する。技術的介入の成否は、このようなマージンに敏感に左右される41。
このような介入を計画する際に、物理的な地形の局所的な細部を考慮しなければならないとすれば、最近流行の用語では、人間の地形と位置づけられているものを考慮することが絶対的に重要である。テクノロジーによって生活の質を向上させる42」ことを提案する政党が、その土地に住む人々の具体的な行動様式や日々の独特のリズム、日常生活の用事を済ませるために使用する特定のスペースや種類の空間について、何らかの印象を抱くことに関心を持つだろうと想像できるかもしれない。しかし、このような特殊性こそ、「何でもありの空間」として構想された都市では、ほとんど、あるいはまったく表現の余地がない。その結果、私たちが松島やマスダール・シティ、プランITバレーで目にするスマート・シティには、何かが欠けているように見える。単にこれらの場所が文字通り非歴史的であるというだけではない。開発者たちが、都市が実際にそこに住む人々のために価値を生み出す方法について、まったく理解していないように見えるのだ。
物理的な世界とバーチャルな世界が別個の独立した存在領域であると広く信じられていた時代には、このような感受性の欠如は何のコメントもなく過ぎ去っていたかもしれない。歴史も、その歴史が生み出した都市の質感も、邪魔なもの、摩擦の元、捨てても大丈夫なものと考えられていた。レム・コールハースのような人物は、「ジェネリック・シティ」43を「都市生活の大部分がサイバースペースに移行した後に残されたもの」として称賛し、「歴史の存在は(都市の)パフォーマンスの足を引っ張るだけだ」とまで主張した。このような風潮のもとでは–コールハースが知的な隠れ蓑を提供できたことは言うまでもない–、どんな空間であれ都市をデザインすることは擁護可能であり、合理的な提案にさえ思えたかもしれない。プラニット・バレーのような注意深く殺菌された無機質な非場所は、たとえ短期間であっても、住んだり働いたりするのに望ましい場所だと感じられたかもしれない。
しかし 2000年にクリントン政権が非軍事事業者にクリーンなGPS信号を提供することを決定してから44,2008年頃にフェイスブックが単一アイデンティティのクリアリングハウスとして台頭するまでの間に、バーチャルはかなり決定的に物理的なものに折り返された。その過程で、かつて「サイバースペースに入り込んだ」ものの多くが、本当に入り込んでいたとしても、すぐに戻ってきた。自己を非物質化し、永続的な「肉体のない歓喜45」の状態にするどころか、生体認証技術は今やますます自己を肉体の中に、そして肉体に固定するようになっている。そして世界は、ブロックごとに、建物ごとに、1と0に変換され、グーグルのストリートビューカーによって超高解像度でマッピングされ、Foursquareではジオコーディングされた個別の場所に区画されている。ネットワーク化された時代に私たちが直面する都市デザインの課題は、これまでと同様、現実の空間における現実の身体の移動に関連したものである。そう考えると、コールハースのジェネリック・シティや、スマート・シティに見られるような都市概念に見られるような、歴史に対するさりげない侮蔑は、特に口先だけで、思春期的で、不満足なものに感じられる。
建設しようとしているものが「スマート」都市であるなら、なおさら軽率に感じられる。そもそも都市に知性があると言えるのであれば、その知性は特異なものであり、特定の場所で進化してきた独自の生活様式や文化、実用的な地域適応の中に存在するものであるに違いない。このような状況が生まれるには時間がかかるし、それが定着するにはさらに時間がかかる。少なくとも数年、もっと長いと数十年はかかるだろう。このように妊娠期間が長いため、インテリジェンスやそれに類するものが、マスダールや松島、プラニット・バレーといった人を寄せ付けない土地に根付く可能性は極めて低くなる。
14. スマートシティを生み出す技術的な可能性と同じものを、より手応えのある目的に向けることができる
AI 解説
- 技術的可能性の再解釈の必要性:スマートシティを生み出す技術は、提唱者が想定するものとは異なる、より有益な目的に向けることができる。
- 疑問を投げかけるためのインフラ:データ収集・分析インフラを、市民が自ら利用して問題提起や議論を行うために活用することができる。しかし、それには機関からの抵抗も予想される。
- オープンなデータアクセスの重要性:市民が生成したデータへの自由でオープンなアクセスを確保することで、そのデータを地域のニーズに応えるために活用できる。
- グローバルにつながるローカルなアクター:各都市の市民がグローバルな流動空間の中で力を持つノードとして活躍できるようにすべき。都市間の相互依存を認識することで全体の回復力が高まる。
- 技術の都市化:技術的介入によって、都市特有の知性や主体性、主観性の出現を支援することに焦点を当てるべき。
- スマートシティ言説の問題点:スマートシティの推進者が作成した資料は、都市的な知性をどう高めるかという重要な問いを無視している。
- スマートシティ言説を覆すデザイン:実在する場所とニーズに根ざし、技術の特殊性を考慮し、開放性と説明可能性を備え、単なる効率ではなく価値のバランスを追求し、変化に適応できるデザインが必要。
- 都市の価値観とプロセスの尊重:技術的洗練性を追求しつつ、都市が長年にわたって機会と再発明の原動力として機能してきた価値観とプロセスを理解し、それに根ざすことが重要。
- スマートシティの示唆する仮説:スマートシティは、都市が複雑すぎて一般市民には管理できないという仮説と、統治は難しすぎて市民には任せられないという仮説を内包している。
- 言葉を超えた根本的な発想の転換:スマートシティに代わる言葉だけでなく、ネットワーク化された都市についての根本的に異なる考え方が必要。情報技術を市民のエンパワーメントのために活用する都市を目指すべき。
私がこのパンフレットで明らかにしようとしたのは、スマートシティの概念を支える思想的・理論的なコミットメントである。もし何らかの意味で、そのような場所を実現することに専心する運動が存在するとすれば、ここで検討した記述は、その指導哲学の初歩を構成するものである。控えめに言っても、多様性を生み出すゆりかごとしての都市という考え方を大切にする人々や、市民やコミュニティが自らの存在条件を決定する能力を増幅させるべきものとしてテクノロジーを考える人々を安心させるような信念の体系ではない。
しかし、このような哲学は重要なのだろうか?それがどんなにグロテスクなものであっても、実際の世界にまったく影響を与えず、地球上のどこであろうと、たった一人の都市生活者の経験さえも形作ることができるのだろうか?
これらは妥当な疑問である。現在の視点から見れば、マスダール・シティ、新松島、プランITバレーが、どう考えても失敗作であることは明らかだ。確かに2012年末には、これらのプロジェクトに関する誇大宣伝は聞かれなくなっていた。これらのベンチャーが最終的に商業用不動産開発の真っ当な提案として、狭い範囲で成功することになったとしても、あまりにも長い間、世間の目にさらされ、開発者の約束を大差で果たせなかったため、日常生活の高度な技術に関する主張を、誰もが特別に真剣に受け止めることはなかった。
さらに関連性があるのは、これらの計画がさまざまな形で枯れ、頓挫したのと同じ頃、スマートシティプロジェクト全体を最も鮮明に浮き彫りにするような、別の何かが世界で胎動していたことだ。2007年6月29日、アップルがiPhoneを発表し、スマートフォンの時代が本格的に始まった。その後、スマートフォンが大量普及のカーブを上るにつれて、世界中の都市空間がネットワーク化された情報技術によって植民地化された。
スマートフォンのユビキタス化182は、どのような歴史的基準から見ても例外的な速さであったが、松島や同業他社の開発ペースの遅れに比べると、特に劇的であった。これらの計画が停滞していたとしても、パーソナル・ネットワーク・デバイスは繁栄し、それ以前にはなかったような技術として人類の集落に広がっていった。この10年の終わりまでに、スマートフォンは、モバイルデータゾンデ、インターフェース・オブジェクト、アイデンティティの代理人として(そしてまれに、この3つすべてを同時に)、日常的な都市での相互作用の驚異的な配列に介入するようになった。モバイル・アプリケーションとモバイル・サービスのエコシステムは、完全に成熟しているとは言えないまでも、かなり発達している。それは、地球上のほぼすべての都市で、日常的な体験の範囲をますます広げ、媒介し、情報を与え、条件を整えている。しかし、スマートシティのオーソドックスな概念は、その住民がスマートフォンを装備しているかもしれないという見通しについて、事実上何も語っていない。スマートシティは、私たちの世界に関するこの顕著でかなり重要な事実を、最も表面的なレベルでさえ取り入れるのに苦労しているのだ。松島のような場所で今もなお提案されているビジョンは、その本質において、21世紀初頭、つまり社会技術的に大きく異なる時代に始まった時から変わっていない183。
では、なぜ私はスマートシティにこれほど多くの時間とエネルギーを費やしてきたのだろうか。
私たちが松島のような場所で実践しているスマートシティは、すでに死滅しているかもしれない。しかし、IBMやシスコ、シーメンスといった企業が、より現実的な他の都市のために情報化システムを提案する際に想定していることの多くは、すでに検討されることなく過ぎ去ってしまっている。そして現在、少なくとも私には、これらの企業やその直接の競争相手が、市民の情報インフラ提供に何らかの形で深く関与していない世界を想像することは難しい。都市が給与計算をし、サービスを管理し、車両を追跡し、収入を徴収する限り、これらの企業はどこかに入り込み、したがって、現代の都市環境における情報技術の適切な場所を構成するものについての彼らの考えもそうであろう。
したがって、松島のような場所の計画は重要である。このような場所で最初に開発された技術、方法、枠組みは、後にマイクロソフトのような後発企業が公共部門の顧客に提示する構想に反映される。これは特に、この言説の核心にある唯一の重要な考え方に当てはまる。シビック・ガバナンスとは、都市が存在し、行うこと全てに及んでいるアーマチュアを中央集権的な計算機で管理することだと考えられている。より野心的なもの、より野心的でないもの、さまざまなバージョンが登場するものの、この考え方は決して疑問視されることはなく、触れるものすべてをその性格で染め上げてしまう。これに異議を唱え、代案となるモデルをうまく具体化しない限り、このクラスのベンダーが都市情報の提供に携わる限り、今後何年にもわたって、自治体サービスがどのように提供され、有権者間の緊張関係が裁かれ、公共空間の経験が形成されていくことになるだろう。そして、このビジョンの明確化が、コンテンツから切り離され、歴史から切り離され、政治から切り離され、究極的には都市性から完全に切り離された場所においてのみ、古典的な形で可能であったとするならば、私たちが暮らす都市に、多かれ少なかれそのままの形で移植することを提案する人がいるたびに、私たちはかなり鋭い疑問を投げかける必要があると思う。
§
それでも、なぜ私がマーケティングや宣伝コピーの分析にこれほど焦点を絞ったのか、という疑問が生じるかもしれない。私がここで光にかざした修辞的な作品はすべて、単なる誇張表現として許されるべきであると主張するのは簡単である。もっと言えば、そのような発言を誠実に読むという普通の礼儀を尽くすべきなのに、綿密な分析にかけるのは、何か見苦しい。先に述べたように、このような反応は、この資料を紹介する際に私が慣れ親しんできた反応である(決して、私が名前を挙げた企業に勤める人々だけが示す反応ではない)。しかし、このような言葉を真に受けることを拒否することは、今日、知識が再生産される方法と、それが世界で働くプロセスについて、ある種のナイーブさに屈することを意味する。
企業の新しいスマートシティ・イニシアチブの立ち上げ時には、それを宣伝し、企業の包括的なブランド提案と整合させるコンテンツがマーケティング部門によって作成され、1分もかからずにグーグルにインデックスされるグローバル・ウェブサイトに公開される。このイニシアチブは、ほぼ即座に地球上の数千人のテクノロジー・ブロガーの目に留まり、様々な発信元で記事を書いている。これらのブロガーは同時に、1日に何度も投稿しなければならないという強い契約上のプレッシャーにさらされており、テクノロジーに熱狂的であり、概して懐疑的なルポルタージュの技術を学んでいないため、提供された主張を額面通りに受け取る傾向がある。(これは、『ガーディアン』紙や『ニューヨーク・タイムズ』紙に寄稿するブロガーにも言えることだ)
あっという間に、オリジナルのプレスリリースの要点がブロガーの好きな言い回しで言い換えられ、新しい記事にまとめられる。これらの投稿へのリンクは、自動化されたツイッター・アカウントによって瞬時に生成され、ツイッター自身と、ツイッターのAPIを通じてリンクされた他のソーシャル・メディア・チャンネルの両方で無限に複製される。これらは、未来に生きるという見通しに同じように興奮している世界中のはるかに多くの人々からの反応の波を刺激し、せいぜい数時間のうちに、豊かなオンライン論評のロームが築かれる。これらの論評のうち、主張されていることを深く評価したり、同じ機関が過去に主張したことと比較したりするものはほとんどないが、その話題の多さには目を見張るものがある。そして、グーグル自体の仕組みも少なからず影響しているが、この分散された談話は、そこに何かがあるという印象を即座に与える。数時間の間に、深い関心を持つ当事者から発信されたフレーミングや視点は、単に合意された知識の織物の疑う余地のない一部となったのだ。
このようなマーケティング・キャンペーンの主な想定読者である自治体の内部で、受け手側はどうなるのだろうか。時間に追われ、洞察力に飢えている下級官僚たちは、ざっとキーワードを検索して、この藪のような会話に行き当たる。彼らは、最初のそれなりに信頼できそうな検索結果から数行をコピーし、そのままパワーポイントのスライドに貼り付ける。そして、そのスライドは階層が上がるにつれて提出されることになる。その言葉は組織全体に広まり、しかも、誰かが有名ブランドの経営コンサルタントのウェブサイトで見つけた、そのテーマに関する急いでダウンロードしたホワイトペーパーにある言葉と一致してしまう。賢明なスタッフほど、この用語を自信を持って使い、この用語で話し、この用語で考えるようになる。つまり、提案されていることを正確に理解できるほどテクノロジーに精通し、なぜそれが問題なのかを説得力を持って説明できるほど自分たちの街の仕組みに精通し、そうすることで安心できるほど自分たちの立場を保証し、喜んでリスクを背負うほどこの問題に情熱を持っている。(IBMを買ってクビになった人はいない、ということわざがあるように、IBMのウェブサイトからそのまま印刷されたものに反論するのは、不安定な立場に立たされることになりかねない。) 最終的に、市の資源をどのように配分すべきかについて提案を迫られたとき、委員会メンバーにとって最も簡単なことは、流れに身を任せることである。
もちろん、このようなことは、自治体機関が直面する可能性のあるあらゆる問題で起こる。しかし、消費者レベルの製品やサービスでさえも、異常なほどの謎めいた雰囲気に包まれていることを考えると、情報技術に関する問題は特にそうであるように思われる。決断を迫られ、自信に満ちた見解が展開され、それに異議を唱えるために必要な善意を持った当事者が名乗りを上げない場合、自然な、そして人間的な行動は、従うことである。そうして、コード・ライブラリがGithubやSourceForgeのようなオープンソースのリポジトリからダウンロードされるのと同じように、このアイデアの集合体が再生産されるのである。そして、そのたびに、非常に特殊な評価と優先順位が一緒に再生産される。かつては、マーケティング部門がそのユーフォニー、ビジネスモデルへの貢献、特定のブランド価値との整合性のために作った言葉の羅列にすぎなかったものが、都市の公式プログラムに、あるいは公式プログラムとして刻まれるようになる。
これが、スマートシティと呼ばれるものの望ましさをめぐって、時期尚早で先制的なコンセンサスが形成された経緯である。強調しておきたいのは、このような考えを広める役割を担っている人物たちは、概して善意であるということだ(ただし、彼らの中には確信犯的な新自由主義イデオローグや、少なくとも1人か2人の自信家もいることは確かだ)。都市生活の状況を改善したいという真摯な願いの大部分は、時には耐え難いほどで、概して悪い人たちではない。しかし、彼らの考えは悪いものであり、さらに重要なことは、少なくとも私は悪い価値観に基づいていることだ。
ここまでくれば、「スマートシティ」は、もっと大きな可能性の空間の中での特定の修辞的な動きであることに同意できるだろう。正確には、都市構造の機器化と自治体プロセスの数値化、特に管理の容易さと効率化に関する言説にほぼ限定される。このような心理的テンプレートが適用される場所ならどこでも、現代都市の規模と複雑性が中央集権的な計算機による監視を絶対的に要求しているとか、そのような場所の管理は、主要業績評価指標のバランスを公称しきい値の間で保つという単純な問題であるとか、自治体ガバナンスの最優先方向は、世界的に移動可能な資本と才能のプールをめぐる競争でなければならないとか、そういうことを示唆することは、まったく目立たないことになる。その自覚の有無にかかわらず、このような提案をする人は、都市の生きた経験よりも、最も薄っぺらい抽象論を持ち上げているだけでなく、ネットワーク技術に閉じ込められた、はるかに興味深い可能性に背を向けている。
結局のところ、ウェブサイトやインタビュー、エキスポ・スタンドで語られる一時的な表現に、かなりの注意を向ける価値があると私が考える理由はここにある。端的に言えば、このレトリックは世界で機能している。それは議題を設定し、「先進的」であることの意味についての認識に影響を与え、規範を再調整し、資源の配分を導く。ネットワーク上で際限なく増殖するこのレトリックは、社会技術的な可能性の空間全体を、誰も戦う時間もエネルギーもない、ひとつの悪しきアイデアの無風なヘゲモニーで埋め尽くしている。今こそ、この知的生産に異議を唱え、代替概念を開発し、前進させ、議論する時なのだ。
§
非常に幸運なことに、スマートシティを支持する人々がどんなに熱心に、人間の居住の進化における自然な、あるいは中立的な段階であるかのように表現しようとも、スマートシティは利用可能な可能性の束の中から選ばれた1つに過ぎない。私たちが利用できるものは他にもある。中央集権的な計算機管理を支えているのと同じ技術の集合体は、まったく異なる方法で使用することができ、もっと実りある目的に向けることができる。
何もなければ、そのアンサンブルは不毛な「解決策」を提供するのではなく、疑問を投げかけるために使われるかもしれない。インテリジェント・オペレーション・センターに供給されるデータ収集、視覚化、分析の同じインフラを、市民が自分たちで利用し、啓発するために活用し、自治体資源の分配における公平性の問題を提起し、権力とアクセスに関する他の問題を切り開くことができることを考えてみよう。この目的は、協調的かつ継続的な闘いなしには達成できず、そうでなければ妨げられることのない権威がこのような形で挑戦の的にされることになるあらゆる機関によって、必ずや抵抗されるだろう。実際、そのような機関が、何が危機に瀕しているかを完全に理解していることはすでに明らかである。例えば、ある技術に精通した市民が最近、アサートン(カリフォルニア州)警察独自のデータ公開を利用して、同警察が運転手に対して違法な人種プロファイリング184を行っている可能性が高いと判断した後、同警察はそのデータセットへの一般公開を取りやめた185。このようなことをする公的機関はこれが最後ではないだろうし、またそれを試みることもないだろう。しかし、ユビキタスなデータ収集やその他の計算監視の技術を受け入れるのであれば、そのようなツールは議論を妨げるのではなく、議論を引き起こすために使用されるべきであるという理解のもと、関与する市民の完全な自由裁量に置かれるという条件のもとでそうしなければならない。技術的な用語で言えば、この目的には、スマートシティの主役である企業によって予見される独占的な取り決めを、市民が生成したデータのための自由でオープンなライセンスに置き換えることが必要である。
ロックフェラー財団のベンジャミン・デ・ラ・ペーニャが「自己触媒的都市186」と考えているように、このデータへのオープンなアクセスを確保することで、データはその場所のニーズに応えるために解放される。何億もの人類がこのようにして環境から生計を立て、 「都市開発のデフォルト・モード187」とまで言われているにもかかわらず、このような日常的な生存の実践は、スマートシティの文献ではほとんど認識されていない。このような自己組織化のプロセスを弱体化させるのではなく、むしろ支援するような技術的枠組みを考案すべきなのは、ほとんど言うまでもないことである(しかし、どうやらそうらしい)。
このような設計アプローチによって、ネットワーク化された市民一人ひとりが、単にローカルなアクターとしてではなく、グローバルな流動空間の中で完全に力を与えられたノードとして活躍できるようになる。そうすることで、各都市を他の都市と競争する境界のある孤立した存在として扱うという、スマートシティに関する文献でしばしば見られる頑固な主張を、最終的に超越することができる。実際のところ、私たちの都市はすでに互いに密に、密接にリンクしており、市民によってアトムやビットの絶え間ない相互強化の往来で結ばれている。それぞれの都市を地球上の他の都市との相互依存の網の目のように考え、それぞれの隣人や近隣に、同じような状況にある他の人々の洞察力を革新し、共有し、学ぶためのツールを与えることで、私たちは全体の回復力を向上させることができる。
そしてこれは、名目だけでなく、影響や展望においても都市的な地球への重要な一歩となるだろう。社会学者のサスキア・サッセンは「urbanizing technology(都市化する技術)」と語っているが、これは、地球上のどこで、どのような歴史の時代に遭遇しようとも、都市生活がそれを受け入れる人々に確実に生み出すと思われる特質を意識的にデザインする実践を意味すると私は理解している。それならば、都市の知性を高めることに専念するよりも、むしろその前提を逆転させ、技術的な介入によって、都市特有の知性や主体性、主観性の出現をどのようにサポートできるかを問うべきなのかもしれない:
- データ収集、分析、可視化ツールの可能性をどのように活用すれば、コミュニティが直面する課題、リスク、機会に対する感覚を向上させ、自律的な自治を目指すコミュニティを支援できるだろうか。
- スマートシティのパラダイムから著しく欠落している特権、特に連帯、相互性、集団行動に関する特権を促進するために、ネットワーク化されたテクノロジーをどのように活用できるだろうか。
- 個人のモビリティ、市民参加、(個人的・集団的)自己決定のプロセスを強化することを意図したものに限定されないが、提案されているすべての技術的介入に、都市に対する権利という強固な概念をどのように組み込むことができるだろうか。
- そして、私たちが大都会での生活から連想する、開放的で、寛容で、気が強く、意見しやすい性格、とりわけ、カニネス(canniness)、ヌー(nous)、サヴォアフェール(savoir faire)などと様々に形容される性質を、都市の日常におけるテクノロジーについて、どのような代替概念で支えることができるだろうか。
スマート・シティの推進者、メーカー、ベンダー、インテグレーターが作成した資料は、こうした疑問について語り始めたわけではないし、そのような素振りを見せたこともない。しかし、これらの疑問こそが重要であり、私たちが提示された提案や目の前の機会を合理的に評価するためには、最も緊急に答えなければならない疑問なのだ。
§
ネットワーク化された都市や市民のためのデザインの実践にどの程度かかわっている私たちにとって、こうした機会を最大限に活用することは、スマートシティのあらゆる質や特性を覆すことを意味する。私たちは、抽象的で特徴のない地形のためではなく、実際の場所や人々のためにデザインすることを学ばなければならない。漠然とした未来のためではなく、今ここにあるニーズのためにデザインする。特定の技術システムの特殊性と特殊な限界をしっかりと念頭に置いて設計すること。何をするにしても、必然的に部分的で、偏りがあり、重みがあることを受け入れること。これらの偏りのバランスをとる優れた方法として、私たちの計画に開放性を設計すること。浅はかな最適ではなく、競合する特権の実りあるバランスを追求すること。可能な限り、私たちがデザインしたものが、それが生活に入り込む人々に対して自らを説明できるように、ものごとの継ぎ目を消すことなくデザインすること。管理職のエリートだけでなく、すべての人がシステムにアクセスできるようにすること。物事が変化していくという確信に対して、織り目にゆるみを残すこと。単に意識するだけでなく、都市生活を深く深く愛してデザインすること。少なくとも、新しい失敗をする勇気を持つこと。
これらのことに成功すれば、21世紀の都市における生活条件が、技術的な能力や、技術的な製品やサービスを提供する業者の知覚的なニーズのみによって決定されることがないようにすることができる。私たちの仕事は技術的に洗練されたものであるべきだし、創発的なやり方や作り方によってもたらされるあらゆる利点を活用することができる。しかし、それと同じように、都市が7千年以上もの間、機会の重要な原動力として、個人の再発明のためのプラットフォームとして、また表現的な創造物として機能してきた価値観やプロセスに対する理解にも、深く根ざさなければならない。どこにでもある都市は、常にすでにスマートであり、その知性は人々の中に宿っているとすれば、デザイナーとしての私たちの仕事は、その知性を活かす最善の方法を見つけることである。
§
あらゆるテクノロジーやテクノロジーの集合体は、人間の行動に関する仮説を内包している。偶然にも、スマートシティが抱く特別な仮説は2つある。その第一の仮説は、現代の都市環境は非常に複雑で厄介な要求が多いため、それを理解することはおろか、賢明に管理することも、助けを借りない普通の人間の集団には望めないというものだ。この命題は、ある場所の現場の事実を反映しているかどうかはわからないが、少なくともそのぜひを論じることはできる。それは、現代都市が必要とする統治技術は、それ自体があまりにも難しく、困難なものであるため、その場所に住む人々が自分たちの問題を管理する力を託すことはできないということだ。この点で、スマートシティは、都市居住の全歴史を通じて何らかの形で表現されてきた思想の流れの、最新の現れに過ぎない。効率性、敏捷性、持続可能性という魅惑的な言葉でその場は飾られてはいるが、その流れをそのまま呼び出した方がいいかもしれない。この衝動は、どのような言語や技術で表現されようとも、人間の心の中に永遠に湧き上がるものだ。それは局所的・一時的に抑圧されたり、変質させられたりすることはあっても、別の時・別の場所で、別の装いで再び湧き上がるに違いない。スマートシティは、現代において私たちがそれに直面する局面である。
技術学者のファビアン・ジラルダンは、スマートシティという概念に最も重きを置いている機関は、少なくとも文字通りのレベルでは、批評に応えてレトリックを調整する素晴らしい能力を発揮してきたと指摘する188。誰かが、都市環境は常にある種の知性を呼び起こすことができ、「スマート」そのものは新しいものでも、必ずしも技術的に確立された性質でもないと観察すると、会議やプログラムはスマートシティを呼び起こす。他の誰かが、そもそも無生物に知性を持たせるのは間違っているのではないかという反省を述べると、各企業はよりスマートな市民のために努力をし直す。このような考えを包括する言葉は、ウイルスの表面を覆うタンパク質の包みに例えることができる。つまり、定量化と強迫的な測定が他のあらゆる指よりも優先され、私たちに立ちはだかる問題に対処するための他のあらゆる方法を排除した科学主義、そして常に支配の亡霊がつきまとうのだ。
言語が重要でないわけではない。どちらかといえば、言語が最も重要であり、私たちが想像する未来を形作るために使用する言葉には細心の注意を払わなければならないと私は信じている。分散化、分散型、コミュニティ指向のスマートシティなど存在しないと私が主張するのはそのためだ。乾いた水や雪のように真っ白な日焼けはありえない。中央集権、テクノクラシー、上からの権力の主張がこの言葉を意味するのであれば、ありえない。そうではない。もし私たちが別の目的に関心を持つのであれば、私たちが共に築こうとしているものが何なのかを説明するために、別の言葉を使わなければならない。
しかし、新しい言葉だけでは十分ではない。私たちは、ネットワーク化された都市について、根本的に異なる考えを持つ必要がある。
私がここで示したかったのは、スマートシティには事実上あらゆるレベルで深い概念的な問題があるということ、これらの問題は、そのような都市が、どのような形であれ、またどのような場所でインスタンス化されようとも、すべての市民の要求に有意義に応える可能性を阻む最大の障害であるということ、そして、そのような都市の日常生活は、必然的に一連の破棄、断絶、エリジョン、裏切りの上に成り立っていなければならないということである。そして、そのような都市の日常生活は、必然的に一連の破棄、断絶、排除、裏切りの上に成り立つものでなければならない。しかし、私たちは、もうひとつの都市が可能であるという考えを決して見失ってはならない。それは、ネットワーク化された情報技術を、その都市に住み、その都市に生命を与え、その都市をその都市たらしめている人々の永続的なエンパワーメントのために活用する都市である。
そのような場所を建設することは、プランITバレーやマスダール、新松島市のような場所で提示された、都市の未来についての浅薄なビジョンを見過ごすことを意味する。それは、IBMやシスコ、シーメンスといった企業との生産的な協力の仕方を学ぶということであり、同時に、彼らが慣れ親しんできた、あるいは慣れ親しんできた以上に鋭い質問を投げかけるということでもある。そのためには、自分自身のコンフォートゾーンの枠を超え、自分自身に必要なことを教え、他の人々が同じレベルの熟練度に到達するのを助ける必要がある。そして何よりも、ネットワーク化された都市を支えるシステムが、権力、特権、正義を根底に据えて設計されていることを要求することになる。しかし、私たちはそれを手に入れることができる。どんな都市であれ、その能力が実際に存在する人々を一度も見失わなければ、私たちはそこで生き、繁栄することができる。
謝辞
コルビュジエの都市論を読み解く上で、ジェームス・C・スコットの『国家のように見る』という貴重な著作に負うところが大きい。
忍耐強く編集に携わってくれたスーザン・ワイル・シュワルツとエレン・ハドソン、洞察に満ちた貴重なコメントを寄せてくれたマシュー・シャルマーズ、ファビアン・ジラルダン、ヌリ・キム、ニニ・スニ、そして特にフレッド・シャーメン、バルセロナで現実を見続けてくれたジェイク・バートン、ローラ・フォルラーノ、アンソニー・タウンゼント、サラ・ウィリアムズのニューヨーク勢、そして常に親交を深めてくれたアニー・クォン、パメラ・プチャルスキー、アドリアナ・ヤングに感謝する(そしてカヴァも)。Timo Arnall、Engin Ayaz、Martin Brynskov、Stephen Graham、Usman Haque、Chris Heathcote、Stephan Hügel、Laura Kurgan、Greg Lindsay、Benjamin de la Peña、Saskia Sassen、Gavin Starks、Tom Taylor、John Tolva、Rena Tom、Meejin Yoonは皆、私に重要な洞察を与えてくれた。
Urbanscaleの同僚であり同志であるJ.D. Hollis、Jeff Kirsch、Leah Meisterlin、Mayo Nissenには、善戦し、スマートシティの代替案を開発し、「ネットワーク化された都市と市民のためのデザイン」が意味するものを想像する手助けをしてくれたことに感謝する。
都市と都市生活に関する継続的で集団的な会話が育まれていることは、ニューヨークをアーバニストとしてこれほど豊かでやりがいのある場所にしている少なからぬ要因である。ニューヨーク建築連盟ではロザリー・ジェネブロ、アン・リーゼルバッハ、ヴァリック・シュート、カシム・シェパードに、公共空間デザイン・トラストではミーガン・カニングに、フォード財団ではジェニー・トゥーミーに、ニューミュージアムではリチャード・フラッド、コリンヌ・エルニ、カレン・ウォンに感謝している。ロンドンでは、LSE Citiesのリッキー・バーデットとリチャード・セネットにお世話になった。
このパンフレットは、Oren Ambarchi、Antony and the Johnsons、Barn Owl、Current 93、Earth、Horseback、Zoe Keating、Krallice、Labradford、Okkyung Lee、Liturgy、Locrian、Machinefabriekを聴きながら書いた、 Mogwai、Queen Elephantine、Rachel’s、Sleep、SUNN O)))、Swans、Teeth of the Sea、Mika Vainio、White Hills、Wolves in the Throne Room、Year of No Light、Black Sabbathの最初の4枚のアルバム。
アダム・グリーンフィールドはPeet’sのフレンチローストコーヒーを愛飲し、支持している。
参考文献
すべてのURLの最終取得日は2013年9月15日である。
原著参照
アダム・グリーンフィールドについて
アダム・グリーンフィールドは、ニューヨークを拠点とする都市システムデザイン事務所Urbanscaleの創設者兼マネージング・ディレクターであり、『Everyware』の著者でもある: 著書に『Everyware: The dawning age of ubiquitous computing』(2006)、『Urban computing and its discontents』(2007年、マーク・シェパードとの共著)がある。
2008年から2010年にかけては、ノキアのサービスおよびユーザー・インターフェース・デザインのデザイン・ディレクション責任者を務めた。それ以前の10年間は、インターネット・コンサルタント会社レイザーフィッシュの東京オフィスでリード・インフォメーション・アーキテクトを務めた。
妻でアーティストのヌリ・キムとともに、共同制作のためのプラットフォームであるDo projectsの共同設立者でもある。2010年以来、Do projectsは世界中の都市で「ウォークワークショップ」を開催し、デジタルネットワークが路上から情報を収集する(そしてそれを路上に還元する)方法を調査することに特化した一連のウォーキングツアーを行っている。
彼はアメリカ、イギリス、フランス、フィンランド、韓国、日本に住み、仕事をしている。
アダムの作品はspeedBIRD.wordpress.comとurbanscale.orgで見ることができる。
Do 1302. スマートシティに抗う。Kindle版。
2013年10月13日版1.2。
人事
このプロジェクトの実現のため、Doはアダム・グリーンフィールド、エレン・ハドソン、ヌッリ・キム、エイミー・クォン、スーザン・ワイル・シュワルツ、トゥオモ・ヴァーナネンで構成された。カバーイラストはヌッリ・キムが担当した。
バージョンノート
本書は2013年10月13日発行の第1.2版で、lacunabooks.comから入手可能なラクナブックスのデジタル版である。『「スマートシティに抗して』は、Literature & Latte社のオーサリング環境Scrivenerを使用し、アップル社のマッキントッシュ・コンピューターで制作された。
ライセンス
本作品は、クリエイティブ・コモンズ表示-非営利-継承ライセンス、バージョン3.0に基づき提供される:
- あなたは、この作品をアダム・グリーンフィールドに帰属させなければならない(ただし、アダム・グリーンフィールドがあなたまたはあなたの作品の利用を支持していることを示唆するような方法であってはならない)。
- この作品を商業目的で使用してはならない。
- 本作品を改変、変形、構築する場合、あなたは、本作品と同一または実質的に類似した条件を指定するライセンスのもとでのみ、結果として生じる作品を頒布することができる。
- 本作品の画像などを再利用する場合は、Do projectsに電子メールで通知するようお願いする。

