Contents
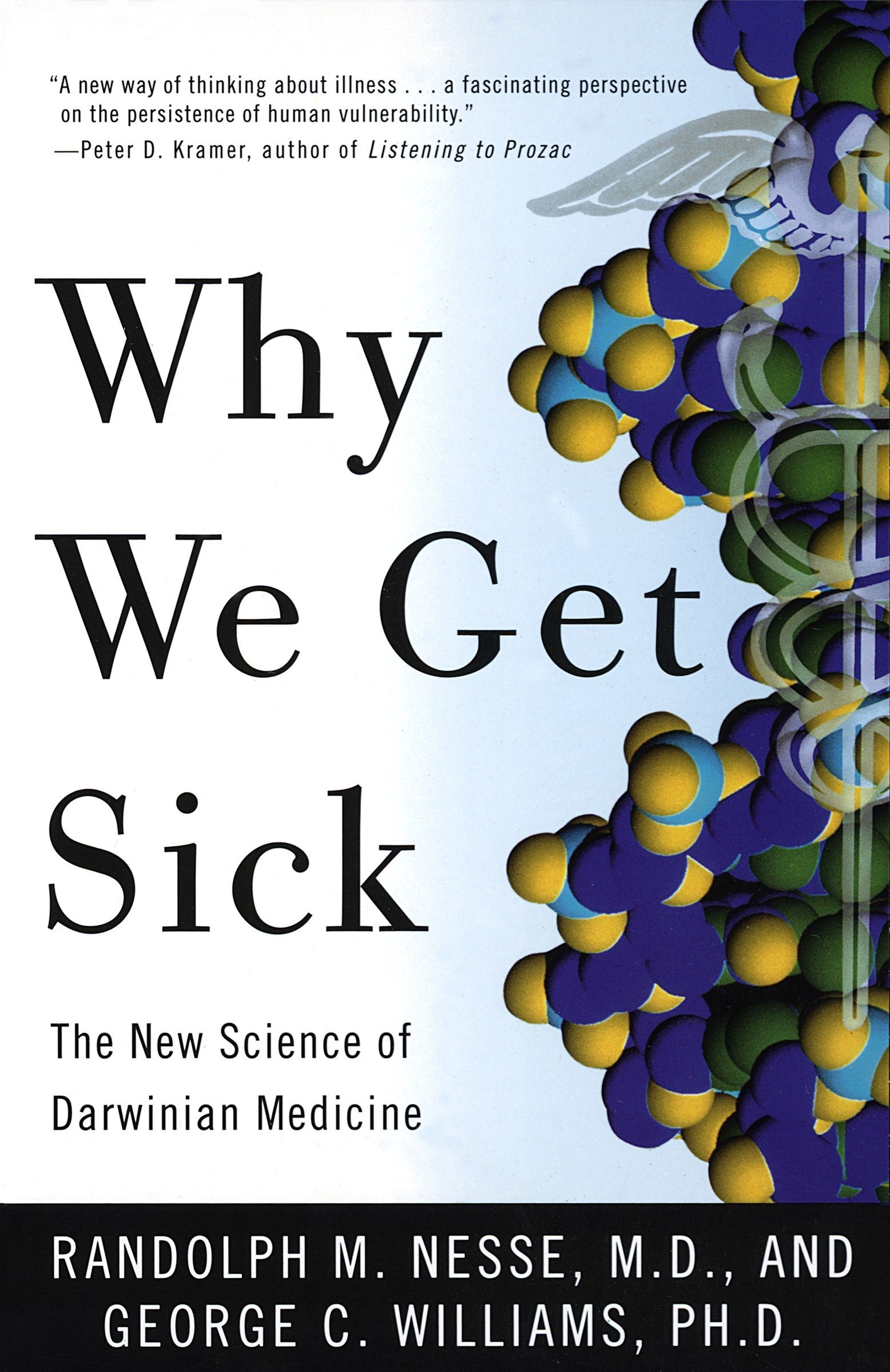
絶賛の声
ランドルフ ML ネッセとジョージ C. ウィリアムズによる
「これは、過去50年間の生物医学の問題について書かれた最も重要な本である。世界有数の進化生物学者(ウィリアムズ)と思慮深い医師(ネッセ)が手を組めば、私たちの体がなぜ怪我や病気に対してそのように反応するのか、手に汗握る探究ができる。」
マイケル・S・ガザニガ博士、神経科学センター所長。
カリフォルニア大学デービス校
ダーウィン医学は、生物学における他のすべてのものと同様に、人間の病気や身体的弱点にも進化的説明があり、これらの洞察がより良い治療を促すことができると考えている。 なぜ病気になるのか』では、ダーウィン医学の二人の支持者が、この冒険的な新しい学問の野心的な到達点を示している」。
-ニューヨーク・タイムズ・マガジン
「この素晴らしい本はその一つであり、私たちの生き方、死に方を変える力をもっている。この素晴らしい本がその一つであり、医師の教育方法、診療方法、さらには熱や咳のある子供を見守る親のあり方にまで革命を起こす可能性がある。」
ロバート・オーンスタイン教授(『意識の心理学』著者)
「ある種の赤身肉を食べると心臓発作を防げるということを受け入れるだろうか?病気のときにアスピリンを飲むと、事態を悪化させる可能性があるということを受け入れるだろうか?乳児の突然死を防ぐために、母親は乳児のすぐそばで寝るべきだということだか?先史時代の祖先がどのように生きてきたかを聞いた後では、そうかもしれない。小さいが、「ダーウィン医学」思想家の一団によれば、そうなのだ。彼らは、あまりにも長い間、医師は進化の過程でわれわれを形成してきた力を無視してきたと主張している・・・このような考えは・・・議論を呼ぶが、そこがポイントである。
-ウォール・ストリート・ジャーナル
「なぜ病気になるのか』は、この10年間で最も重要な本の一つとして認識されることは確実であり、しかも、美しく書かれている。
-ロジャー・ルイン
「人間進化論 第3版」の著者
「なぜ人は病気になるのか」は、医学に対する挑発的な挑戦と、進化論がいかに人間に適用されるかについての思慮深い議論の両方を提供する。
-ビジネスウィーク
ランドルフ・M・ネッセ医学博士
ジョージ・C・ウィリアムズ博士
人はなぜ病気になるのか
ミシガン大学医学部精神医学科教授、教育・学術担当副教授、開業医。
ジョージ・C・ウィリアムズ博士は、ストーニーブルック州立大学の生態学と進化学の名誉教授であり、「生物学の季刊誌」の編集者である。
1996年1月、ヴィンテージブック初版
謝辞
私たちの研究は、医学と進化のある側面について私たち以上に知っている多くの同僚や友人からのコメントによって、非常に大きな恩恵を受けている。私たちは常に彼らの助言を受け入れるだけの分別があったわけではないので、私たちの間違いを責めることはない。この原稿にコメントやその他の示唆を与えてくれた人たちの中には、次のような人たちがいる。James Abelson, M.D., Ph.D., Laura Betzig, Ph.D., Helena Cronin, Ph.D., Lyubica Dabich, M.D., Wayne Davis, Ph.D., William Ensminger, M.D., Paul Ewald, Ph.D.,, ジョセフ・ファントーネ(医学博士)、ロザリンド・ファントーネ(看護師)、ロバート・フェケティ(医学博士)、リンダ・ガーフィールド(医学博士)、ロバート・グリーン(医学博士)、ダニエル・ハーディー(医学博士)、サラ・ハーディ(博士)、マット・クルーガー(医学博士)。参考文献を探すのに協力いただいたDoris Williams, Jeanette Underhill, M.D., Joann Tobinに特に感謝する。Randolph Nesseは、ミシガン大学のサバティカル制度とJohn Greden, M.D., George Curtis, M.D. の支援により、Brant Wenegrat, M.D., Anne O’Reilly のいるスタンフォード大学で原稿を執筆することができた。バーバラ・ポルシン(Barbara Polcyn)の忠実で効果的な秘書としてのサポートはすばらしいものであった。エージェントのジョン・ブロックマンには、一般読者向けの本で本格的な新しい科学を紹介できると確信させ、交渉や出版の詳細を効果的に処理してくれたこと、そしてバーバラ・ウィリアムズには、ジョン・ブロックマンを真剣に受け止めるよう説得してくれたことに感謝している。この本のスタイルと構成は、マーガレット・ネッセとタイムズブックスの編集者エリザベス・ラポポートによる詳細な編集のおかげで、かなり改善された。
私たちの最大の恩人は、この本を書く理由があることを気づかせてくれた人たちである。彼らはパイオニアであり、先見の明があり、そのアイデアや研究は、現在隆盛を極めるダーウィン医学の分野の中核を成している。ポール・エワルドやマージー・プロフェットのように、本書で何度も登場する人物もいる。他の人たちは、もっと簡単に言及したり、巻末の注にその出版物を列挙しているだけである。今後数年の間に、これらの人々が、彼らにふさわしい評価を受けるようになると確信している。
目次
- 表紙
- タイトルページ
- 著作権について
- 謝辞
- 序文
- 1. 病気の謎
- 2. 自然淘汰による進化
- 3. 感染症の徴候と症状
- 4. 終わりのない軍拡競争
- 5. 傷害
- 6. 毒素:新しいもの、古いもの、そしてどこにでもあるもの
- 7. 遺伝子と病気。欠陥、癖、妥協点
- 8. 若返りの泉としての加齢
- 9. 進化史の遺産
- 10. 文明の病
- 11. アレルギー
- 12. 癌(がん
- 13. 性・生殖
- 14. 精神疾患は病気か?
- 15. 医学の進化
- ノート
はじめに
私たちは1985年、後に「人間行動と進化学会」となるグループの会合で初めて出会い、共通の関心を持つに至った。私たちのうちの一人(ネッセ)は、ミシガン大学医学部精神科の医師であった。精神医学の理論的基盤の欠如に対する不満と、進化論が動物行動学にもたらした驚異的な進歩に魅了され、ミシガン大学の「進化と人間行動プログラム」に参加することになった。その学際的なグループの同僚たちは、加齢の進化的起源に対する彼の長期にわたる関心を聞き、ジョージ・ウィリアムズという生物学者による1957年の論文を薦めた。その論文は驚くべきものだった。老化には進化論的な説明がつくのだ。不安障害や精神分裂病ではだめなのだろうか?その後、ウィリアムズをはじめとする進化論者や、医学部の研修医や教員と何年も話し合ったおかげで、患者の障害に対する進化論的な見方が、着実に自然で有用なものになってきていることがわかった。
もう一人の著者(ウィリアムズ)は、海洋生態学的研究と進化に関する理論的研究との間でキャリアを積んできた。彼が進化論の考え方を医学的に応用することに興味を持ったのは、1980年に『理論生物学ジャーナル』に掲載されたポール・エワルドの論文、”進化生物学と感染症の徴候・症状の治療 “を読んだことがきっかけであった。エワルドの研究は、感染症に限らず、多くの医学的問題に対して進化論的な考え方が重要である可能性を示唆していた。ウィリアムズの進化遺伝学に関する一般的な知識には、遺伝性疾患に明らかに影響を与える原理が多く含まれており、老化プロセスの進化に関する彼の初期の研究は、老年学と進化の基本的な関連性を示唆していた。
私たちは出会って間もなく、進化生物学が医学の進歩に貢献する可能性は、この考えを他の 人々に伝えるために本当に努力することを正当化できるほど重要であると、互いに確信しあいまし た。私たちは、他の研究者たちが他の多くの可能性を模索するのを刺激する方法とし て、私たちの理由といくつかの明白な事例を印刷物にすることにした。1991年3月に「The Quarterly Review of Biology」に掲載された私たちの共著「ダーウィン医学の夜明け」が、マスコミや医学、進化生物学の同僚たちから好評を博した後、私たちは、この論文を簡単に拡大して、幅広い読者に興味を持ってもらえるような本にすることができると判断した。
本書では、生物の機能設計を説明するダーウィンの自然淘汰説が、ほぼすべての基礎となっている。私たちが病原体と戦うための適応、私たちの適応に対抗する病原体の適応、私たちの適応のための不適応だが必要なコスト、私たちの身体のデザインと現在の環境との不適応など、自然選択による適応という概念を中心に議論されている。
執筆を進めるうちに、私たちは、ダーウィニズムが医学の進歩に役立つ新しい 方法を発見し続けた。ダーウィン医学は、単なる思いつきではなく、まったく新しい分野であり、わくわくするような新しい展開がどんどん生まれていることが、だんだんわかってきた。しかし、ダーウィン医学はまだ発展途上であることを強調しなければならない。ダーウィン的思考を医学的問題に適用した例を、権威ある結論や医学的助言として受け止めるべきではない。これらは、医学における進化的思考の利用を説明するためのものであり、人々の健康を守り、病気を治療する方法を指導するためのものではない。これは、ダーウィン医学が単なる理論的な試みであると信じているわけではない。ダーウィン医学が単なる理論的な試みだと考えているわけではない。進化論的な問題を追求することによって、人間の健康が明らかに改善されることを、私たちは大いに期待している。そのためには、努力と資金と時間が必要である。その一方で、本書が、人々が自分の病気について別の方法で考え、医師に質問をし、おそらくは反論もするが、医師の指示を無視することはないだろうという刺激になればと願っている。
本書は、「病気とは何か?」本書は、西洋先進国における現在の医学研究や診療を否定するものではない。もし、医学の研究と実践が、物理的、化学的な直接的な原因だけでなく、適応や歴史的な原因についても日常的に考慮されていれば、より良いものになるだろうという確信に基づいている。私たちが求めているのは、現代の医療行為に対する代替案ではなく、むしろ、医学界でほとんど無視されてきた、確立された科学的知識群からの新たな視点なのである。ダーウィン医学が、ある種の正統派に対抗する代替教団と見なされることには、大いに反対である。同様に、私たちの目的は政治的な提言をすることではないが、私たちの推論の一部は、医療や環境政策を策定する人々にとって重要であることが証明されるかもしれないと考えている。
本書は、多くの読者にとって興味深く、有益なものとなるように努めただけでなく、それぞれの専門分野で進化論的な問いを立てている医師や研究者にとって、予備的ではあるが科学的に妥当なガイドとなるように努めたつもりである。多くの医療関係者が、すでにそのような問いを立てていることはよく承知している。しかし、多くの場合、彼らは自分たちの考えを真剣な仮説としてではなく、真剣な調査に値しない単なる憶測として、申し訳なさそうにそうしてきた。われわれはこのような態度にできるだけ強く異議を唱え、本書の例によって多くの科学者が、自分たちの進化論的仮説は正当であり、科学的検証に値することを認識し、その方法は彼らが考えるよりも簡単で決定的なものかもしれないことを期待するものである。本書は、進化論的仮説の検証方法について正式な指導は行わないが、そのような検証の例を数多く示している。
このささやかな本が、医学的な例との関連で、現在のいくつかの進化論的な考えを簡単に垣間見ることができるだけであることを、読者に理解していただければと思う。医学は今や誰もそのごく一部しかマスターできないほど巨大な分野である。内科のような専門分野でさえ、循環器科のようなサブスペシャリティに、急速に分裂している。私たちはどちらも、現代医学に包含される知識のごく一部以上をマスターしているとは言わない。本書のような広範なトピックの議論は、必然的に表面的で単純化されたものにならざるを得ないことを、われわれは十分に承知している。また、専門家の方々には、多少の不正確さを容赦いただければと思う。このようなリスクは、ダーウィン医学の広範な概観の潜在的有用性から、また、読者が自分の体の機能、時には誤作動を進化的に理解することから真の喜びを得られると信じているからだ。
第1章 病気の謎
これほど精巧に設計された身体でありながら、なぜ私たちは病気にかかりやすいのだろうか?もし、自然淘汰による進化が目、心臓、脳などの高度なメカニズムを形成することができるのなら、なぜ近視、心臓発作、アルツハイマー病などを予防する方法を形成しないのだろうか?もし、私たちの免疫システムが100万種類もの異質なタンパク質を認識し、攻撃することができるのなら、なぜ私たちはいまだに肺炎にかかるのだろうか?もし、1本のDNAコイルが、10兆個の特殊な細胞をそれぞれ適切な場所に配置した成体生物の計画を確実にコード化できるのなら、なぜ、損傷した指の代わりを育てることができないのだろうか。もし、私たちが100年生きられるのなら、なぜ200年生きられないのだろうか?
私たちは、個人がなぜ特定の病気になるのかについて、より多くのことを知っているが、なぜ病気が存在するのかについては、まだほとんど分かっていない。高脂肪食が心臓病を引き起こし、日光浴が皮膚癌を引き起こすことは分かっているが、その危険性にもかかわらず、なぜ私たちは脂肪や日光を渇望するのだろうか?なぜ私たちの体は、詰まった動脈や日焼けした皮膚を修復することができないのだろうか?なぜ日焼けは痛いのか?なぜ何でも痛いのか?そして、なぜ私たちは何百万年経っても連鎖球菌に感染しやすいのだろうか?
医学の大きな謎は、精巧に設計された機械の中に、欠点や弱点、その場しのぎのメカニズムに見えるものが存在し、それがほとんどの病気を引き起こしていることだ。進化論的なアプローチは、この謎を一連の答えのある質問に変えてくれる。なぜ、ダーウィンの自然淘汰のプロセスは、私たちを病気にしやすくする遺伝子を着実に排除してこなかったのだろうか?なぜ、ダーウィンの自然淘汰の過程では、病気にかかりやすくする遺伝子を着実に排除してこなかったのだろうか?一般によく言われる答えは、「自然淘汰の力が弱いから」であるが、これは大抵間違っている。しかし、これから説明するように、身体は慎重な妥協の積み重ねで成り立っている。
身体の最も単純な構造には、人間の創造物とは比べものにならないほどの精巧なデザインが施されている。例えば、骨。骨は筒状になっており、重量を最小限に抑えながら、強度と柔軟性を最大限に高めている。骨は鉄の棒よりも強い。骨はその機能に応じて、傷つきやすい部分には厚みを持たせ、筋肉を活用しやすい部分には突起をつけ、繊細な神経や動脈が安全に通るように溝をつけるなど、巧妙に形づくられている。個々の骨の厚さは、強度が必要な部分ほど厚くなっている。曲がるところでは、さらに骨が堆積していくる。骨の中の空洞は、新しい血液細胞の安全な場所として役立っている。
生理学の分野では、さらに驚くべきことがある。例えば、人工腎臓は冷蔵庫のような大きさだが、天然の腎臓のごく一部の機能しか果たさない代物だ。また、人工的に作られた最高の心臓弁を考えてみよう。自然の弁は一生の間に25億回も開閉を繰り返すのに、人工弁は数年しかもたず、閉じるたびに赤血球を押しつぶす。また、私たちの脳は、人生の些細なことを記録し、数十年後に一瞬で思い出すことができる。コンピュータの比ではない。
身体の調節システムも同様に素晴らしい。例えば、食欲から出産まで、人生のあらゆる局面を調整する数多くのホルモンがある。例えば、食欲から出産に至るまで、生命のあらゆる側面を調整する数多くのホルモンは、何重ものフィードバックループによって制御されており、人工の化学工場よりもはるかに複雑な仕組みになっている。また、感覚運動系の複雑な配線についても考えてみよう。それぞれの細胞は視神経を通じて、形、色、動きを解読する脳中枢に信号を送り、次に記憶バンクとリンクしてその画像がヘビであると判断し、恐怖中枢と判断中枢が行動を起こし、運動神経が正しい筋肉を収縮させて手を振り払う。
骨、生理、神経系など、身体には何千もの完成されたデザインがあり、私たちは驚きと賞賛の声を上げている。しかし、これとは対照的に、身体の多くの部分は驚くほど粗雑に見える。例えば、食物を胃に運ぶ管は、空気を肺に運ぶ管と交差しているため、飲み込むたびに気道を塞いで窒息しないようにしなければならない。また、近視を考えてみよう。もし、あなたが近視の遺伝子を持つ不運な25パーセントの一人なら、ほぼ間違いなく近視になり、その結果、自分が虎の餌食になりそうになるまで虎に気づくことはないだろう。なぜ、このような遺伝子が排除されないのだろうか?例えば、アテローム性動脈硬化症。複雑な動脈網は、体の各部分にちょうどよい量の血液を運んでいる。しかし、多くの人は動脈の壁にコレステロールが沈着し、その結果、血流が滞り、心臓発作や脳卒中を引き起こすのである。まるで、メルセデス・ベンツのデザイナーが、燃料パイプに炭酸飲料のストローを指定したようなものだ。
このほかにも、何十種類ものボディデザインが、同じように無能に見える。どれも医学的なミステリーと言えるかもしれない。なぜ多くの人がアレルギーを持つのか?もちろん、免疫システムは有用だが、なぜ花粉を放っておけないのだろうか?それどころか、なぜ免疫系は時に自分自身の組織を攻撃して、多発性硬化症、リウマチ熱、関節炎、糖尿病、エリテマトーデスを引き起こすのだろうか?そして、妊娠中の吐き気もある。将来の母親が、発育途上にある赤ちゃんに栄養を与えるという重責を担っている時に、吐き気や嘔吐が頻繁に起こるというのは、何と理解しがたいことだろう。そして、機能的に理解しがたい普遍的な事象の究極の例である老化を、私たちはどのように理解したらよいのだろうか。
私たちの行動や感情でさえも、いたずら者によって形作られたように思える。なぜ、私たちは体に悪いものを欲しがるのに、純粋な穀物や野菜はあまり欲しがらないのだろう?太りすぎだとわかっているのに、なぜ食べ続けてしまうのか?そして、なぜ私たちの意志の力は、私たちの欲望を抑えようとすると弱いのだろうか?なぜ男性と女性の性的反応は、相互の満足を最大化するように形作られているのではなく、協調性がないのだろうか?マーク・トウェインが言ったように、なぜ私たちの多くは常に不安で、「起こることのない悲劇に悩まされる」人生を送っているのだろうか。最後に、なぜ私たちは幸せを感じにくいのだろうか。長い間追い求めてきた目標を達成しても、満足感ではなく、さらに達成不可能なものへの新たな欲求が生まれるだけなのだろうか。私たちの身体の設計は、非常に精密であると同時に、信じられないほどずさんなものである。まるで、宇宙一のエンジニアが7日ごとに休みを取って、不器用なアマチュアに仕事を回しているようなものである。
二種類の原因
このパラドックスを解決するためには、それぞれの病気の進化的な原因を見つけなければならない。さて、この進化的な病気の原因が、多くの人が思い浮かべる原因とは異なることは明らかである。心臓発作について考えてみよう。脂肪分の多い食事をすることや、動脈硬化を起こしやすい遺伝子を持つことは、心臓発作の主な原因である。これらは生物学者が近因と呼ぶものである。私たちがここで関心を持つのは進化的な原因であり、人間がなぜそのようにデザインされたかをさらに遡ったものである。心臓発作の研究において、進化論者が知りたいのは、なぜ自然淘汰が脂肪欲とコレステロール沈着を促進する遺伝子を排除しないのか、ということである。近接的な説明とは、身体の仕組みや、なぜある病気にかかる人とかからない人がいるのか、ということを扱うものである。進化論的な説明は、一般的に、なぜ人間がある病気にかかりやすく、他の病気にはかからないのかを示すものである。私たちが知りたいのは、なぜ人体のある部分が故障しやすいのか、なぜある病気にはかかり、他の病気にはかからないのか、ということなのである。
近接的説明と進化的説明を注意深く区別することによって、生物学の多くの問題がより明確に理解されるようになる。近接的説明とは、ある形質、すなわち解剖学、生理学、生化学、そして受精卵の 中にあるDNAの断片が与える遺伝的指示から成体個体に至るまでの発達を説明するものである。進化的説明とは、そもそもなぜDNAがその形質を特定するのか、なぜある種の構造をコードするDNAが存在し、他の構造をコードしないのかを説明するものである。近縁的な説明と進化的な説明は代替案ではなく、あらゆる形質を理解するために必要なものである。外耳の近接的説明には、外耳がどのように音を集めるのか、外耳がどのような組織でできているのか、動脈や神経はどのようになっているのか、外耳が胚から成体 になるまでどのように発達するのか、といった情報が必要だろう。しかし、これらの情報がすべてわかったとしても、外耳の構造がどのようにして耳のある生物に有利に働き、なぜ耳のない生物に不利に働くのか、そしてどのような祖先の構造が自然選択によって徐々に形作られて現在の形になったのかという進化的説明が必要なのである。例えば、味蕾の近接的説明では、味蕾の構造と化学的性質、塩、甘、酸、苦を感知する仕組み、そしてその情報をインパルスに変換し、ニューロンを介して脳に伝達する仕組みが説明される。味蕾の進化的説明では、味蕾がなぜ他の化学的特性ではなく、塩味、酸味、甘味、苦味を感知するのか、また、これらの特性を感知する能力が、どのように持ち主が人生に対処するのに役立っているのかを示している。
近接説明は、構造や仕組みについて「何を」「どのように」という問いに答えるものであり、進化説明は、起源や機能について「なぜ」という問いに答えるものである。医学研究のほとんどは、身体のどこかがどのように機能するか、あるいは病気がどのようにその機能を破壊するかという近接説明を求めている。生物学のもう半分は、物事が何のためにあり、どのようにしてそこに到達した のかを説明しようとするものであるが、医学の分野では無視されてきた。もちろん、完全にそうだというわけではない。生理学の主要な仕事は、各器官が通常どのような働きをしているかを解明することであり、生化学の全分野は、代謝機構がどのように働き、何のために働いているかを理解することに専念している。しかし、臨床医学の分野では、病気の進化的説明の探求は、せいぜい中途半端なものにとどまっている。病気は必ず異常であるとされることが多いので、その進化を研究することは、とんでもないことに思えるかもしれない。しかし、病気に対する進化論的アプローチは、病気の進化ではなく、病気にかかりやすくしている設計上の特徴を研究するものである。身体の設計上の明らかな欠陥は、自然界の他のすべてのものと同様に、進化論的説明と近接的説明によってのみ完全に理解することができる。
進化論的な説明は、単なる推測で、知的な興味しかないのだろうか?そんなことはない。例えば、つわりを考えてみよう。シアトルの研究者マージー・プロフェットが示唆したように、妊娠初期にしばしば起こる吐き気、嘔吐、食物嫌悪が、発達中の胎児を毒素から守るために進化したのだとすれば、その症状は胎児の組織分化が始まるときに始まり、胎児が脆弱になるにつれて減少し、胎児の発達を最も妨げる物質を含む食物を避けることに繋がるはずだ。後述するように、実質的な証拠はこれらの予測に合致している。
このように、進化論的仮説は、近接メカニズムに期待されることを予言している。例えば、感染症に伴う鉄分濃度の低下は、感染症の原因ではなく、身体の防御機能の一部であるという仮説を立てれば、患者に鉄分を与えると感染症が悪化する可能性があると予測できる-実際、そうなりうるのである。病気の進化的起源を解明することは、単に知的好奇心を満たすだけでなく、病気を理解し、予防し、治療するための重要な手段であるにもかかわらず、十分に活用されていないのが現状だ。
病気の原因
様々な病気の専門家は、しばしば、ある病気がなぜ存在するのかを自問する。しかし、多くの場合、進化的説明と近接的説明を混同していたり、自分の考えをどのように検証したらよいかわからなかったり、主流から外れていると思われる説明を単に提案することに抵抗があったりする。このような困難は、ダーウィン医学のための正式な枠組みがあれば、軽減できるかもしれない。この目的のために、われわれは疾病の進化的説明の6つのカテゴリーを提案する。それぞれのカテゴリーについては、後の章で詳しく説明するが、この簡単な概要は、この事業の論理を説明し、今後の展開の概観を示すものである。
1. 防御
防御は実際には病気の説明にはならないが、病気の他の症状と混同されることが非常に多いので、ここに挙げておくる。色白の人が重い肺炎にかかると、くすんだ色になり、深い咳をすることがある。この二つの肺炎の兆候は全く別のカテゴリーを表しており、一方は欠陥の現れであり、他方は防御である。皮膚が青いのは、ヘモグロビンが酸素不足になると色が濃くなるためである。この肺炎の症状は、車のトランスミッションのガタンという音に似ている。あらかじめプログラムされた反応ではなく、たまたまの結果であって、特に実用性はない。一方、咳は防御である。これは、気道の異物を排出するために特別に設計された複雑なメカニズムから生じるものである。咳をすると、横隔膜、胸筋、声帯の協調運動によって、粘液や異物が気管から喉の奥に押し上げられ、そこで排出されるか、飲み込んで胃に入り、酸によってほとんどの細菌が死滅する。咳は、体の不具合に対する偶然の反応ではなく、自然淘汰によって形成され、特定の脅威の存在を示す合図を特殊なセンサーが感知すると作動する、協調的な防御機能である。咳は、車のダッシュボードにあるガソリンタンクの残量が少なくなると自動的に点灯するライトのように、問題そのものではなく、問題に対する防御反応なのである。
このような防御と欠陥の区別は、単に学術的な興味にとどまりません。病気を患っている人にとって、これは極めて重要なことなのである。欠陥を修正することは、ほとんどの場合、良いことである。トランスミッションのカチャカチャ音が止まったり、肺炎患者の皮膚が暖かいピンク色になったりするように何かできれば、それはほとんど常に有益なことである。しかし、防御をブロックして排除することは、破滅的な事態を招きかねない。燃料の残量が少ないことを示すランプの配線を切断すれば、ガス欠になる可能性が高くなる。咳を過度にブロックすれば、肺炎で死ぬかもしれない。
2. 感染症
細菌やウイルスの中には、私たちを主に食事として扱うものがあることから、敵と考えることができる。しかし、彼らは単なる害虫ではなく、巧妙な敵なのである。私たちは、彼らの脅威に対抗するために防御策を進化させてきた。そして、その防御策を克服し、さらには自分たちの利益のために利用する方法も進化している。このような果てしなく続く軍拡競争は、私たちがすべての感染症を根絶できない理由や、いくつかの自己免疫疾患について説明するものである。次の2つの章では、これらのトピックを大きく掘り下げていくる。
3. 新しい環境
私たちの体は、アフリカの平原で狩猟と採集を行う小集団生活を送るために、何百万年もかけて設計された。しかし、自然淘汰は、脂肪分の多い食事、自動車、薬物、人工照明、セントラルヒーティングに対応できるように私たちの身体を修正する時間がなかった。このように、私たちの身体設計と環境とのミスマッチが、予防可能な現代病の多くを生み出している。心臓病や乳がんの現在の流行は、悲劇的な例である。
4. 遺伝子
私たちの遺伝子の中には、病気を引き起こすという事実があるにもかかわらず、永続しているものがある。その中には、私たちがより自然な環境で暮らしていたときには無害だった「癖」が影響しているものもある。例えば、心臓病を引き起こす遺伝子のほとんどは、私たちが脂肪分の多い食事に偏り始めるまでは無害だった。近視の原因となる遺伝子は、子供が早い時期から近視の仕事をする文化圏でのみ問題を起こす。老化を引き起こす遺伝子の中には、平均寿命が短かった時代にはほとんど淘汰されなかったものがある。
病気の原因となる他の多くの遺伝子は、実はその遺伝子を持つ本人や、その遺伝子を他の組み合わせで持つ他の個体に利益をもたらすために選択されたものである。例えば、鎌状赤血球症の原因となる遺伝子は、マラリアも予防する。このよく知られた例のほかにも、母親を犠牲にして父親に利益をもたらす、あるいはその逆の性的に拮抗する遺伝子など、多くの例が後の章で説明される。
私たちの遺伝暗号は、常に突然変異によって破壊されている。ごくまれに、こうしたDNAの変化が有益なこともあるが、はるかに一般的なのは、病気を作り出すことだ。このような損傷した遺伝子は、自然淘汰によって常に排除されるか、最小限に抑えられている。このような理由から、代償となる利益をもたらさない欠陥遺伝子は、一般的な病気の原因とはならない。
最後に、個体の犠牲の上に自己の感染を促進する「無法」遺伝子があり、このことは、淘汰が最終的には個体や種ではなく、遺伝子に利益をもたらすように働くことを露骨に示している。個体間の淘汰は強力な進化の力であるから、無法者遺伝子もまた、珍しい病気の原因である。
5. 設計上の妥協
全体として利益をもたらす多くの遺伝子にコストがかかるように、自然淘汰によって保存されるすべての主要な構造変化にはコストがかかる。直立歩行は食べ物や赤ん坊を運ぶ能力を与えてくれるが、背中の問題を抱えやすくなる。身体の設計上の欠陥の多くは、間違いではなく、妥協に過ぎないのだ。病気をより良く理解するためには、設計上の間違いがもたらす隠れた利益を理解する必要がある。
6. 進化の遺産
進化は漸進的なプロセスである。進化は大きなジャンプをすることはできず、小さな変化しか起こさないが、その一つ一つが直ちに有益でなければならない。大きな変化は、人間の技術者でも難しい。ピックアップトラックの人気車種は、ガソリンタンクがフレームの外側にあるため、横からぶつかると火災が発生する。しかし、タンクをフレーム内に納めるには、今あるものを全て設計し直さなければならず、新たな問題が発生し、新たな妥協が必要になる可能性がある。人間の技術者でも、歴史的な遺産に制約されることがある。同様に、私たちの食べ物は、気管の前にあるチューブを通過して胃に到達するため、窒息の危険にさらされることになる。鼻孔を首のどこかに移動させるのがより賢明なのだが、第9章で説明するように、それは決して実現しない。
私たちが言っていないこと
上記のような病気の原因について詳しく説明する前に、いくつかの危険な誤解を避けるために、私たちは努力したいと思う。まず第一に、私たちの事業は優生学や社会的ダーウィニズムとは何の関係もない。私たちは、人間の遺伝子プールが良くなっているか悪くなっているかには興味がないし、種を改良するための行動を強く推奨しているわけでもない。私たちは、人々の間の遺伝的な違いに特に興味があるわけでもなく、私たち皆が共通して持っている遺伝物質により大きな興味がある。
病気に対する進化論的な視点は、サラナク湖にある医師E・L・トルドーの業績を称える銅像に刻まれた古代の医学の目標を変えることはない。”治療すること、時には、助けること、しばしば、慰めること、常に” 医学の目標は常に、種ではなく、病人を助けることである(そして、常にそうであるべきだと私たちは信じている)。この点に関する混乱は、多くの災いを正当化してきた。今世紀初頭、社会ダーウィニズムの思想は、貧しい人々から医療を遠ざけ、資本主義の巨人たちを個人への影響とは無関係に戦わせることを正当化するのに役立った。これらの思想は、種(あるいは人種)を改良するために特定の集団の不妊手術を提唱した優生学主義者の思想と密接に関連していた。このようなイデオロギーはとっくの昔に、当然のことながら悪評を買っている。ダーウィニズムの用語のいくつかを比喩的に使っただけで、生物学者が理解するような理論を使ったわけではない。私たちは決して、医学が自然淘汰を助けるべきだと主張しているわけではないし、生物学が道徳的決定を導くことができると言っているわけでもない。私たちは、病気が良いものであると主張することはない。たとえ、病理学が評価されない利益と関連している多くの例を提供するとしてもである。ダーウィニズムは、私たちがどのように生きるべきか、医師がどのように医療を行うべきかについて、道徳的な指針を与えるものではない。しかし、医学に対するダーウィンの視点は、病気の進化的起源を理解するのに役立ち、この知識は医学の正当な目標を達成するのに非常に有用であることが証明されるであろう。
第2章 自然淘汰による進化
さて、身体の各部分は、他のあらゆる道具と同様に、何らかの目的、すなわち何らかの作用のためにあるのだから、身体全体が何らかの複雑な作用のために存在しなければならないことは明らかである。
-アリストテレス
第1章で述べた謎の解決策は、自然淘汰の働きの中に見出すことができる。自然淘汰のプロセスは基本的に非常に単純で、遺伝子の影響を受けた個体間の変異が、個体の生存と繁殖に影響を与えるときに、自然淘汰が起こる。もし、ある遺伝子が、将来の世代で生存可能な子孫を少なくするような特性をコードしていれば、その遺伝子は次第に排除されていく。例えば、感染症にかかりやすくなる遺伝子変異や、愚かなリスクテイクやセックスへの興味の欠如を引き起こす遺伝子変異は、決して一般化することはない。一方、感染症に強くなる遺伝子、適切なリスクテイクをする遺伝子、妊娠可能な相手を選ぶことに成功する遺伝子は、たとえ大きなコストがかかっても遺伝子プールに広がっていく可能性が高い。
典型的な例として、大気汚染の主要な発生源の風下に住むイギリスの蛾の集団に、暗い翅の色の遺伝子が広がったことが挙げられる。煙で暗くなった樹木の上では、青白い蛾が目立ち、鳥に捕まりやすい。一方、樹皮の色に近い珍しい突然変異型の蛾は、捕食者のくちばしを受けずにすんだのである。木の幹が暗くなるにつれて、突然変異の遺伝子は急速に広まり、薄い翅の色の遺伝子をほぼ置き去りにした。それだけである。自然淘汰には計画も目標も方向性もなく、ただ、その遺伝子を持つ個体の繁殖成功率が他の個体と比べて高いか低いかによって、遺伝子の頻度が増減するだけである。
このような自然淘汰の単純さは、多くの誤解によって隠されてきた。例えば、19世紀にハーバート・スペンサーが唱えた「適者生存」という言葉は、このプロセスを要約したものと広く考えられているが、実はいくつかの誤解を生んでいる。まず、生存することそれ自体には何の意味もない。だからこそ、自然淘汰は、サケや一年草のように、一度だけ繁殖して死んでしまうような生物を生み出してしまった。生存は、後の生殖を増加させる限りにおいてのみ、適応度を増加させる。たとえ寿命が短くなったとしても、生涯の生殖回数を増やす遺伝子は選択される。逆に、生涯の再生産の総量を減少させる遺伝子は、たとえ生存率を高めるとしても、選択によって排除されることは明らかである。
さらに、”適者生存 “の意味があいまいなために、混乱が生じる。生物学的な意味での適者生存は、必ずしも最も健康で、最も強く、最も速いとは限らない。現代社会、そして過去の多くの社会では、傑出した運動能力を持つ個人は、適応度とほぼ相関関係にあるはずの指標である孫を最も多く生み出す個人である必要はないのだ。自然淘汰を理解する者にとって、親が子供の繁殖にこだわるのは当然である。
ある遺伝子や個体が単独で「適合性」(fit)と呼ばれることはなく、特定の環境における特定の種を基準にして初めて「適合性」と呼ばれるのである。一つの環境の中でさえ、すべての遺伝子には妥協がある。ウサギをより恐ろしくさせ、それによってキツネの顎からウサギを守るのに役立つ遺伝子を考えてみよう。ある野原にいるウサギの半分がこの遺伝子を持っているとしよう。この臆病なウサギたちは、隠れることが多く、食べることは少ないので、平均して、大胆なウサギたちよりも少し栄養状態が悪いかもしれない。もし、3月の雪の中でじっと春を待っているウサギの3分の2が餓死し、恐怖心の遺伝子を持たないウサギの3分の1だけがそうなったとしたら、春になったら、ウサギの3分の1だけが恐怖心の遺伝子を持っていることになる。それは淘汰された。数回の厳しい冬によって、ほぼ淘汰されるかもしれない。冬が暖かくなったり、キツネが増えたりすると、逆効果になるかもしれない。全ては現在の環境次第なのである。
自然淘汰は集団ではなく、遺伝子に恩恵をもたらす
多くの人が、飢えたレミングの群れが水死に向かって躍起になる自然映画を見たことがあるだろう。その中で、食料が不足すると、レミングの一部が自分を犠牲にして、少なくとも集団の一部が生き残れるだけの食料を確保するという説明が、朗々とした声で語られる。数十年前までは、このような「集団選択」の説明は専門の生物学者に真剣に受け止められていたが、今は違う。その理由を知るために、二人の架空のレミングを比較してみよう。一人は高貴な人物で、集団が食糧不足になりそうだと察知すると、すぐに近くの小川に飛び込んで死んでしまう。もう一匹は利己的な怠け者で、高貴な人々が自滅するのを待って、得られる限りの食物を食べ、できるだけ頻繁に交尾し、できるだけ多くの子孫を残そうとする。集団の利益のために自分を犠牲にするという行動をコード化する遺伝子はどうなるのだろうか。種にとってどれほど有益な遺伝子であっても、淘汰されてしまうのである。
では、自殺するように見えるレミングの観察はどのように説明できるのだろうか?冬の終わりに食料が不足すると、レミングは大群で移動し、雪解け水でできた水域に遭遇しても、必ずしも停止することはない。しかし、溺死することはめったにない。この映画の制作者は、目的の映像を得るために、ほうきでレミングを密かに水中に追いやる必要があったようだ。これは、理論よりも現実を変えることを好む人間の、両者が対立する場合の劇的な例である 集団レベルでの淘汰が、通常は個人レベルでの淘汰より強い力を持つという特殊な状況もあるが、あまり頻繁には当てはまらない。
『利己的な遺伝子』の著者であるイギリスの生物学者リチャード・ドーキンスが強調しているように、個人は、遺伝子が複製するために作られた器であり、遺伝子が使い果たしたら廃棄されるものと見なすことができる。この視点は、進化が健康で調和と安定のある世界を目指すという一般的な見方を大きく揺るがすものである。しかし、進化はそのような世界を作り出すものではない。しかし、自然淘汰は私たちの幸せなど微塵も考えておらず、遺伝子の利益になるときだけ健康を促進する。不安、心不全、近視、痛風、ガンなどの傾向が繁殖の成功率と何らかの関連があるとすれば、それらは選択され、私たちは純粋に進化的な意味で「成功」しながらも苦しむことになる。
血統の淘汰
私たちは、生殖が自然淘汰によって最大化される適性の本質であることを暗示し、レミングの議論では、自分の犠牲の上に他人を助ける行為をする個人は進化上好まれないことを示した。これらの一般論は、物語の一部分しか語っていない。最終的に重要なのは、将来の世代における遺伝的表現であり、それは子供を作ることによって達成されるのか、あるいは、自分と同じ遺伝子を持つ近親者の繁殖を高めるようなことをすることによって達成されるのか、ということである。
子供の遺伝子の半分は母親の遺伝子と同じであり、半分は父親の遺伝子と同じである。また、兄弟姉妹は、平均してお互いの遺伝子を半分ずつ共有している。祖父母の遺伝子の4分の1は、孫の遺伝子と同じである。いとこは8分の1の遺伝子を共有している。つまり、自分の遺伝子から見ると、妹の生存と生殖は自分の半分、従兄弟のそれは8分の1ということになる。このため、年齢や健康状態など他の条件がすべて同じであれば、親族に援助を与えることによって自分が受ける代償が、親族が受ける恩恵に関係の程度をかけたものより小さければ、淘汰は親族に援助を与えることを好むのである。イギリスの生物学者J. B. S. Haldaneは、弟のために自分の命を犠牲にするかと聞かれ、「いやだ」と答えたという有名な逸話がある。と聞かれ、「いや、一人の弟のためなら」と答えた。しかし、「2人の兄弟のためなら。あるいは8人のいとこのためなら」と言った。この原理と、協力を説明する上でのその重要性が正式に認められるのは、1964年にイギリスの生物学者ウィリアム・ハミルトンが発表した画期的な論文からであった。もう一人の偉大な英国人生物学者、ジョン・メイナード・スミスは、この現象を「近親選択」と命名した。
進化における「いい人が最後に残る」という原則のもう一つの明らかな例外は、親族である必要はない個人間の互恵的な交換の結果である。エルザが靴作りの名人であり、フリッツが優れた革を生産する動物の狩猟の名人であれば、資源の交換は両者に利益をもたらすだろう。つまり、親切にするとお金がもらえるし、逆に親切にするとお金がもらえるのだ。ロバート・トリバースが1971年に発表した互恵理論に関する古典的な論文以来、生物学者は自然界における生物間の協力関係を、互恵的交換または血縁淘汰から生じるものと日常的に解釈してきた。社会生物学は、『社会生物学』の著者であるE・O・ウィルソンや『ダーウィニズムと人間関係』の著者であるリチャード・アレクサンダーといった先駆者の努力によって発展してきた。初期の論争や誤解は、この新しい科学分野での研究の進展によって、ほとんど取り払われた。
自然淘汰はどのように行われるのか?
進化は何らかの計画や方向性に基づいて進行するという誤解が広まっているが、進化にはそのどちらもなく、偶然性の役割によって進化の将来は予測不可能である。生物個体のランダムな変異は、ダーウィン的な適性にわずかな違いを生み出す。ある個体は他の個体よりも多くの子孫を残し、その結果、その個体の適応度を高めた特性が後の世代でより多く見られるようになる。昔々(少なくとも)、熱帯アフリカのあるヒトの集団で突然変異が起こり、マラリアに対する抵抗力をもたらすようにヘモグロビン分子が変化したことがあった。この大きな利点のために新しい遺伝子が広まり、不幸なことに、後の章で述べるように、鎌状赤血球貧血が存在するようになった。
第一に遺伝子変異の発生において、第二にその保有者がその効果を発揮できるほど長く生きるかどうかにおいて、第三にその個体の実際の繁殖成功に影響を与える偶然の出来事において、第四にある遺伝子がたとえある世代で有利であっても、偶然に次の世代で排除されるかどうかについて、最後にあらゆる生物のグループの歴史の中で必ず起こるであろう多くの予測できない環境の変化において、偶然はそれぞれの段階で結果に影響を与える。ハーバード大学の生物学者スティーブン・ジェイ・グールドは、「もし、生物の歴史のテープを巻き戻して、もう一度同じことをやり直したら、結果はきっと違っていただろう」と、鮮やかに表現している。人類が存在しないばかりか、哺乳類のようなものさえ存在しないかもしれない。
私たちはしばしば、自然淘汰によって形成された形質の優美さを強調するが、自然が完全なものを作り出すという一般的な考え方は、慎重に分析する必要がある。進化がどの程度完璧であるかは、何を意味するかによる。もし、「自然淘汰は常に種の長期的な繁栄に最適な道を選ぶのか」という意味なら、答えはノーである。そのためには、集団淘汰による適応が必要であり、これは前述のようにあり得ないことである。もし、「自然淘汰は価値のあるすべての適応を生み出すか」という意味なら、これもまた答えはノーである。例えば、南米のサルの中には、尻尾で木の枝をつかむことができる種がいる。この技はアフリカのいくつかの種にとってもきっと役に立つはずだが、単に運が悪かったために、誰も持っていない。南米のサルの祖先は、何らかの事情で尾を使うようになり、最終的に枝をつかむ能力を獲得したのだが、アフリカではそのような発達はなかったのだ。単に便利だからといって、その形質が進化するとは限らない。
しかし、自然淘汰が完璧に近い形で行われることがある。それは、ある種の量的特徴を最適化する場合である。ある形質が特定の機能を果たす場合、何世代にもわたって微修正を加えながら選択することで、その量的側面が機能的理想に近づいていく傾向がある。例えば、鳥の翼は揚力を得るには十分な長さが必要だが、鳥がコントロールできるようにするには十分な短さが必要である。大嵐の後に死亡した鳥を計測したところ、異常に長い翼や異常に短い翼が予想以上に多く見られた。また、生き残った鳥は、翼の長さが中間のもの(より最適に近いもの)に偏っていることがわかった。
骨の大きさや形、血圧、ブドウ糖の濃度、脈拍、思春期開始年齢、胃酸の量など、数え上げればきりがないほどである。骨の大きさ、形、血圧、血糖値、脈拍、思春期、胃酸など、数え上げればきりがない。自然淘汰が間違いであると考えるときは、むしろ何か重要な考慮事項を見逃している可能性が高い。例えば、胃酸は潰瘍を悪化させるが、制酸剤を飲めば食べ物は消化できる。では、酸は多すぎるのだろうか?胃酸は消化に重要であり、結核の原因となるバクテリアも殺すということを考えると、おそらくそうではないだろう。身体の不完全さを理解するためには、まずその完全さと、その不完全さの基盤となっている妥協点を理解する必要がある。
エンジニアがそうであるように、進化も常に妥協しなければならない。自動車設計者は、火災のリスクを減らすために燃料タンクを厚くすることができるが、ある時点でコストの増加、燃費や加速度の減少のために妥協が必要となる。そのため、衝突事故で燃料タンクが破裂することがあり、この妥協によって毎年何人かの命が奪われている。自然淘汰はすべての特性を同時に完璧にすることはできないが、その妥協点はランダムではなく、最大の純益をもたらすように正確に形成されている。
ヘンリー・フォードがT型フォードで埋め尽くされた廃車置き場を見たときの話である。「このクルマで絶対に失敗しないものはあるのか」と彼は尋ねた。そうだ、ステアリング・コラムは絶対に故障しない」と彼は言った。「それなら、設計し直せ」と彼はチーフエンジニアに言った。もし、一度も壊れないのであれば、それに費やしすぎているに違いない」。自然淘汰も同様に、過剰設計を避ける。もし、あるものが十分に機能し、その欠点が選択的な力にならないのであれば、自然淘汰がそれを改善することはできない。このように、身体のあらゆる部位は、時折遭遇する極限状態に対処するための予備能力を持っているが、その予備能力を超えたときには、あらゆる部位が脆弱になる。絶対にうまくいかないということはない。
ある資源を適度に使うことで大きな価値が生まれることもあれば、大量に使うことでメリットが少なくなることもある。例えば、シチューを作るとき、タマネギは1個より2個の方がいいかもしれないが、10個では高価な割に、余分な利益はほとんどない。このような費用便益分析は、経済学では日常的に行われていることだが、生物学や医学の分野でも有用である。例えば、肺炎に抗生物質を使う場合を考えてみよう。少量の投与では、おそらく検出可能な利益はないだろう。中程度の投与では、コストはかかるが利益ははるかに大きい。一方、大量に投与すると、コストはさらに高くなるが、追加の利益はなく、おそらく大きな危険が伴う。
工学的、医学的な判断にコストと利益が伴うように、進化に伴う遺伝子の変化にもコストがかかる。自然淘汰は弱くも気まぐれでもない。たとえ同じ遺伝子が何らかの病気に対する脆弱性を増大させるとしても、全体的な適性を高めるような遺伝子を選択する。例えば、不安が機能的に望ましい形質であるということはあり得るのだろうか?もし、キツネが大量に発生した年に、ウサギが不安感を持たなかったらどうなるか、考えてみてほしい。老化の原因となる遺伝子でさえ、必ずしも不適応とは限らない。そのような遺伝子は、淘汰が最も進む人生の初期に利益をもたらし、後に生じる老化や避けられない死のコストよりも、適応度にとって重要な利益をもたらすかもしれない。病気をより良く理解するためには、設計上の明らかな誤りがもたらす隠れた利益を理解する必要があるのだ。
進化的仮説の検証
この章はアリストテレスの引用から始まったが、それには真面目な理由がある。アリストテレスは、多くの種類の生物学的研究において特に実りあるものとなっており、医学においても同様に実りあるものとなると期待されている、機能解析の一般的な手順の創始者と考えることができる。もちろん、アリストテレスの考え方と現代の生物学者の考え方には、大きな違いがある。アリストテレスは、あらゆる生物の働きの根底にある物理的、化学的な原理をほとんど理解しなかった。実験が必要だとも思っていなかった。また、自然淘汰の原理も知らず、生物が繁殖に成功するように完全に設計されていることにも気づかなかった。アリストテレスの「それは何のためにあるのか」という問いかけは、人間の手や脳、免疫系に当てはめようとも、今や非常に具体的な科学的意味を持つようになった。「この形質が生殖の成功にどのように寄与してきたのか?身体は全体として何らかの複雑な作用のために存在している、という彼の確信は正しい。その複雑な作用が生殖であることが明らかになったのは、ここ数十年のことである。
多くの人が、形質の機能に関する質問は科学的ではない、つまり「目的論的」あるいは「推測的」であり、したがって科学的調査の対象としてふさわしくない、という考えを持っている。本書で紹介する多くの例が示すように、この考えは間違っている。生物学的形質の適応機能に関する疑問は、解剖学や生理学に関する疑問と同様に、科学的探究の対象となるものである。目や耳、咳の反射といった生物学的形質の適応的意義について問うことは理にかなっている。なぜなら、それらは歴史的プロセスの産物であり、特殊な機能を果たす能力を向上させる形で徐々に改変されてきたからだ。
しかし、このような「なぜ」という問いを立てるとき、私たちは安易に空想的な話を信じてはならない。なぜ鼻が高いのか?きっと眼鏡をかけるためだ。赤ちゃんが意味もなく泣くのはなぜ?きっと肺を鍛えるためだ。なぜ人は100歳までにほとんど死んでしまうのか?それはきっと、新しい個体が生まれる場所を確保するためなのだ。このように、ほとんどあらゆることが推測の対象になり得るが、もしここまでなら、それは科学ではない。問題は質問にあるのではなく、提案された答えに対する十分な調査と批判的思考の欠如にある。
上記の不合理な例は、いくつかの説がいかに簡単に検証され、誤りであることが証明されるかを示している。鼻は眼鏡を支えるために進化したのではないはずだ。大人になってからの肺の健康には、幼児期に泣く必要はないのだから。自然淘汰は集団にそのような利益をもたらすことはできないし、老化の詳細がそのような機能に対する期待に単に合致していないだけだからだ。
他の機能的仮説は非常に簡単に支持されるので、あまり興味を引かない。心臓の構造と作動をよく知る人なら、心臓が血液を送り出していることがわかるだろう。また、咳をすれば気道から異物が排出されること、震えれば体温が上昇することもわかる。歯があれば食べ物を噛めることは、進化論者でなくてもわかる。興味深い仮説とは、もっともらしく、重要ではあるが、明らかに正しいとも間違っているとも言えないようなものである。そのような機能的な仮説は、医学的に重要なものも含め、新しい発見につながることがある。
適応主義的プログラム
人間の属性の機能的理由の研究は、最近「適応主義的プログラム」と名付けられた調査方法に基づいている。人間の生物学の既知の側面の機能的意義を示唆することによって、論理的に他の未知の側面を予測することができるかもしれない。そして、適切な調査によって、これらの特性が「ある」か「ない」かを確認することができる。もしあれば、それは医学的に重要な意味を持つかもしれない。そうでない場合は、仮説を排除し、振り出しに戻ることができる。
ここでは、様々な特徴がどのように適応度に貢献するのかという問題を考えることで、興味深い発見をした3つの例を紹介する。これらはビーバーと鳥に関するもので、医学的な問題には関係ない。この後の章で多くの例を挙げていく予定だ。これらの例は、程度の差こそあれ、適応度に関する直感的な考え方が、たとえ専門の生物学者の直感であっても、必ずしも適切でないことを示すものである。実際の生物を調査することによって検証できる論理的な答えを提供するためには、真剣な、しばしば数学的な理論化が必要なのである。
ビーバーは、池の中や近くにある木を食料と避難場所にする。ビーバーは、歯を使って地面近くの幹を切り開き、水中にない木は水中へ引きずり込み、小屋まで持っていく。ビーバーはどのように木を切り倒すか決めているのだろうか。ミシガン州の生物学者ゲーリー・ベロフスキーが考えた仮説である。「適応的に判断している。つまり、ビーバーにとって価値のある木かどうか、切り倒して移動するのに必要な労力はどのくらいか、家からどれくらい離れているか、などを考慮して経済的に合理的な判断を下している。ベロフスキーが計算したところ、ビーバーは池からの距離が遠くなるほど、より識別しやすくなるはずだ。小さな木は運搬の手間に見合わず、大きな木は伐採と運搬、特に池に浮かべるために森の中を引きずり回す労力に見合わず、拒絶される可能性がある。ベロフスキーは、ビーバーが伐採する木の大きさの範囲は、池からの距離が長くなるにつれて確実に狭くなっていくと予測した。そして、ある時点で、理想的な大きさの木だけが伐採され、それ以降は全く伐採されなくなる。池の近くでビーバーが伐採した木の切り株を観察すると、その予測が裏付けられる。今度、ビーバーの池を見たら、ビーバーの伝説的な産業性だけでなく、優先順位を決める賢さにも感心することだろう。
例えば、森の中で歌う鳥が卵を産み、仲間と一緒に孵化させようとしているとしよう。この繁殖期の成功は、この卵にすべてかかっている。何個産めばいいのだろうか?彼女は種の存続を保証しようとしているのではなく、自分自身の生涯の繁殖の成功を最大化しようとしていることを忘れないでほしい。産卵数が少なすぎるのは愚かなことだが、多すぎるのも、十分な餌がなく雛が死んだり、雛の世話で体力を消耗し、次の繁殖期まで生きられる可能性が低くなるなど、彼女の生涯の繁殖数を減らすことになる。これらのことは森の中のすべての個体に等しく当てはまるが、何個の卵を産むかの判断は鳥によって異なる。ある種の平均が1組に4個の卵を産むとしたら、5個産む組もあれば3個しか産まない組もある。全員が4個に挑戦しているが、数えられない個体もいると結論づけるのか?それとも、卵の数は自然淘汰による最適化の対象にはならないと結論づけるのだろうか。
適応論者は、鳥がもっと評価されるべきだという可能性を検討するまでは、そのような説明を見送る。一般に、卵を3つしか産まない鳥には3つ、4つ産む鳥には4つ、といった具合に最適なのだろうか?簡単な実験がその答えを教えてくれる。4個の卵を産む巣が30個あるとして、無作為に選んだ10個の巣はそのままにしておく。他の10個の巣から卵を1個取り除き(所有者は3個になった)、残りの10個の巣に加える(4個の卵を持つ鳥は5個の卵を持つようになった)。ここで、3つのグループの平均的な成功を測定する:卵の数を自分で選ぶことができたグループと、最初に産んだ卵より1個多いか少ないかしたグループである。
すべての関連要因を注意深く考慮すれば、このような研究の結果は、オックスフォード大学の鳥類学者デビッド・ラック(David Lack)が50年前に出した結論、すなわち鳥は個体の繁殖成功率が最大になるように産卵数を調整する、を正当化するものになるのが普通だ。そのためには、個々の鳥の健康状態や能力、経験などを正確に把握する必要がある。4羽の子鳥に餌を与えることは、3羽の子鳥に与えるよりも困難で危険なことである。より密集した巣にいる子ガメは、巣立ち時の体重が少なく、次の冬を生き延びられる可能性が低いかもしれない。また、年によって状況が異なるため、例年より条件の悪い年は、より密集した巣にとっては特に危険である。このような知識があれば、野鳥のつがいの子育てを観察する楽しみが増える。一般的に、あるいは平均的に正しいだけでなく、彼ら独自の個体として正しい。
クラッチサイズの議論では、最適な子孫の数を考えた。しかし、子孫には雄と雌の2種類があることを無視した。鳥はどちらか一方、あるいは両方を理想的な割合で産むのがいいのだろうか。性比の自然淘汰では、圧倒的に重要なのは、不足する方の性別の子を産むという、適応度を最大化する戦略である。シングルバーによく行く人なら、少数派の性別が交配に有利であることを知っているはずだ。自然界では、メスが不足しているときにオスの子供を産む個体は淘汰される。なぜなら、そのようなオスの多くは子供を産むことができないからだ。オスが少ない場合、メスを産む個体は、オスを産む個体ほど孫を産まない。このような淘汰のプロセスが、オスとメスの数が同じであることの説明となる。このシンプルでエレガントな進化論的説明は、1930年に偉大な進化遺伝学者R.A.フィッシャーによって初めて認識された。もしあなたが、性比が等しいのは、父親からXまたはY染色体をもらう確率が等しいからだと考えているなら、それは正しいが、これは近接した説明なのである。アリやイチジクコバチのように、ここでは説明しきれないほど複雑でありながら、著しく不平等な性比がより複雑な予測と一致している多くの特殊な事例によって、近似的な説明が不十分であることが示されている。
自然淘汰によって、雄と雌の数が全く同じになるのだろうか?いや、そうではない。両性が異なる年齢で成熟すること、死亡率が異なること、男性と女性の親にかかる費用が異なること、その他の要因について詳細に考察すれば、予想されることである。注意深く計算すると、われわれのような性決定と生殖過程を持つ生物では、両親がまとめて息子と娘の養育に同等の資源を費やすと、性比は安定するという結論が得られる。人類やその他多くの集団の人口動態は、この予想にぴったりと合致している。
この後の章で、ビーバーの採餌パターン、鳥類のクラッチサイズの変化の影響、哺乳類の性比を予測するのと同じように、医学的に重要な発見をする際にも現代の自然選択理論が役に立つことを納得していただきたいと思う。推論は常に、健康や病気に関する何らかの事前情報と、進化した適応に関する疑問から始まる。人体のこの特徴は、何らかの適応的な機械の一部なのだろうか?もしそうなら、その機械の残りの部分はどうなっているのだろう?その機械の未知の側面に関する予測を、どのように検証すればよいのだろうか。もし、人間の生物学的特徴のうち、機能的に好ましくないものがあるとしたら、どうして 自然淘汰はその特徴を許すことができたのだろうか?好ましくない形質は、正の形質の代償なのだろうか?石器時代には適応的であった形質が、今では病気の原因になっているのだろうか?自然淘汰が病原菌や寄生虫の適応を向上させるために作用した場合、医学的にはどのような結果をもたらすのだろうか?これらは、進化生物学者が現在日常的に抱いている疑問のほんの一部に過ぎず、これらに答えるための努力は非常に実り多いものだった。
しかし、このような熱意を抑えるために、注意しなければならないことがある。機能に関する質問には、正しい答えが一つではないことがある。例えば、舌は噛むことと話すことの両方に重要であり、眉毛は目に汗が入らないようにするためとコミュニケーションのために重要である。第二に、ある種や病気の進化の歴史は、他の種類の歴史と同じである。私たちの祖先が、何年前に調理やその他の目的で火を使うようになったか、また、その変化がその後どのような進化的影響を及ぼしたかについて、通常の意味での実験は現在では行われていない。歴史は、歴史が残した記録を調べることによってのみ、調査することができる。炭化した骨や焚き火の炭化物も、読み方を知っている人にとっては有益な記録となる。同様に、タンパク質やDNAの化学構造を読み解くことで、今では全く異なる生物間の関係を明らかにすることができるかもしれない。タイムマシンが発明されるまでは、過去にさかのぼって主要形質の進化を見ることはできないが、化石、炭素の痕跡、構造、行動の傾向、タンパク質やDNAの構造などに残された記録から、太古の出来事を復元することは可能である。ある形質の歴史が復元できない場合でも、それが自然淘汰によって形成されたと確信できることは多い。これは、他の種におけるその機能の証拠や、形質の特徴とその機能との一致によって裏付けられる。
したがって、形質の進化的起源と機能に関する仮説は、形質の近接した側面に関する仮説と同様に、検証が必要であり、多くの場合、検証可能である。進化的な仮説の検証には特別な困難が伴うが、それはあきらめる理由にはならない。この本では、進化的な仮説を検証すると言っているのだろうか?そうではない。私たちは推測と事実を切り離すように努力し、ほとんどの例について証拠を引用するが、私たちが提示する証拠によって証明されたと考えられるものはほとんどない。いくつかの例は、問題の異なる側面に関連する異なるデータを持つ多くの研究に基づいているが、これでも不十分なことが多い。
私たちの目標は、特定の仮説を証明することではなく、進化上の疑問が興味深く、重要であり、検証可能であることを示すことである。私たちは、人々が新しい問いを立て始めてくれることを望んでいる。であるから、申し訳ないが、私たちは、病気のさまざまな側面について、進化的な意義の可能性について質問し、しばしば推測に基づいた答えを提供している。私たちの警告にもかかわらず、これらの推測を事実として受け止めようとする人々もいる。おそらく数年後には、ダーウィン医学は一冊の本が書けるほどの確証を得ることだろう。今のところ、私たちの目標は、いくつかの仮説を徹底的に検証することではなく、患者、医師、研究者が、なぜ病気が存在するのかについて新たな問いを立てることを奨励することである。ガートルード・スタインが死の床で言ったように、「答え、答え、答え」である。「答えとは何だろう…それならば、問いとは何だろう」
第3章 感染症の兆候と症状
ネコとネズミの争いで、あなたがネズミの側にいたとしよう。ネズミは猫の臭いが嫌だと言う。餌や求愛や赤ん坊といった重要な事柄に集中できず、ジリジリしてしまうという。あなたは、ネズミが猫の臭いを気にしなくなるように、嗅覚を鈍くする薬を知っている。あなたはその薬を処方するだろうか?おそらくしないだろう。どんなに不快であっても、猫の臭いを感知する能力は、マウスにとって貴重な財産である。猫の臭いの存在は、その爪や歯が間近に迫っていることの合図かもしれず、それを避けることは不快な臭いによるストレスよりもはるかに重要なことなのだ。
もっと現実的な話として、あなたが子供の風邪を治す小児科医だとする。風邪をひくと、鼻水、頭痛、発熱、倦怠感など、子どもが嫌がるさまざまな症状が現れる。アセトアミノフェン(例:タイレノール)は、これらの症状の一部を軽減したり、取り除いたりすることができる。風邪をひいた子供の親に、アセトアミノフェンを飲ませるように言うだろうか?もしあなたが伝統的な医師であったり、同様の症状を緩和するために自分でアセトアミノフェンを使う習慣があるのなら、おそらくそうしていることだろう。これは賢明なことだろうか?アセトアミノフェンと、私たちがネズミのために考えていた薬とのアナロジーを考えてみてほしい。猫の臭いのように、発熱は不快だが有用である。それは、感染と戦うために特別に自然淘汰によって形作られた適応なのだ。
感染症に対する防御としての発熱
ラブレス研究所の生理学者マット・クルーガーは、「発熱が、何億年も前から動物界全体に存続している感染に対する適応的な宿主反応であることを支持する圧倒的な証拠がある」と考えている。彼は、発熱を抑えるために薬を使うことは、時に人を病気にし、死に至らしめることさえあると信じている。その最も有力な証拠は、彼の研究室から得られている。ある実験では、冷血なトカゲでさえも発熱の恩恵を受けることを示した。感染すると、トカゲは体温が2度ほど上がるような暖かい場所を探す。暖かい場所に移動できなければ、死ぬ可能性が高くなる。子ウサギも熱を出すことができないので、病気になると体温を上げるために暖かい場所を探す。大人のウサギは感染すると熱が出るが、解熱剤で熱をさますと死にやすくなる。
発熱は体温調節のミスではなく、高度に進化したメカニズムが作動して起こる。2度の熱を出したラットを非常に暑い部屋に入れると、ラットは冷却機構を作動させて体温を平熱より2度高く保つ。それを涼しい部屋に入れると、その2度の熱を維持するために保温機構を作動させる。体温は発熱時にも注意深く調節されている。サーモスタットが少し高く設定されているだけなのだ。
発熱の価値を示す最も劇的な証拠は、おそらく今世紀初頭のジュリアス・ワグナー・ヤウレグによる研究であろう。彼は、梅毒患者がマラリアに感染すると改善すること、またマラリアがよく見られる地域では梅毒はまれであることに注目し、何千人もの梅毒患者に意図的にマラリアを感染させた。梅毒患者の100人に1人以下しか回復しなかった時代に、この治療法は30パーセントの寛解率を達成し、ワグナー・ヤウレグは1927年のノーベル生理学・医学賞に値する進歩であった。当時は、発熱の価値が今よりもずっと広く認識されていた。
医師は今でも、冗談のように 「アスピリンを2錠飲んで、朝になったら電話してくれ 」と言う。感染症に対抗するための適応として発熱を評価しようとしたヒトの研究は数少ないことを考えると、これはそれほど驚くべきことではない。ある研究では、水ぼうそうの子どもにアセトアミノフェンを与えたところ、プラセボ(砂糖の錠剤)を与えた子どもに比べて、回復に平均で約1日長くかかったという。別の研究では、56人のボランティアが感染性の鼻腔スプレーでわざと風邪をひいた。ある人はアスピリンやアセトアミノフェンを飲み、他の人はプラセボを飲んだ。プラセボ群では、抗体反応が有意に高く、鼻づまりも少なかった。また、ウイルスの感染性飛散の期間も若干短かった。多くの感染症患者の症状を緩和するために多くの薬剤が使用されているにもかかわらず、この種の詳細な研究が少ないのは、不快な症状の適応的側面についての研究が消極的であることを示している。
これが変わろうとしているのかもしれない。ワシントン大学医学部教授のデニス・スティーブンス博士は、「ある状況下で発熱を治療すると、実はその患者が敗血症性ショックを起こす可能性が高くなるという証拠」を挙げている。発熱を抑える薬は、感染に対する体の反応を調節する正常なメカニズムを妨害するらしく、その結果、致命的な事態になる可能性がある。
他の防衛策について述べる前に、ある防衛策の発現が適応的である必要はなく、適応的であっても必須でない場合があることを強調しておきたい。私たちは、発熱を抑える薬を決して服用しないようにと勧めるつもりはない。たとえ多くの研究が、発熱は通常、感染と戦うために重要であると決定的に立証したとしても、発熱を奨励する、あるいは日常的に自然なレベルまで上昇させるという、屈強な方針を正当化することはできないだろう。進化的な観点からは、発熱のような適応がもたらす利点だけでなく、その代償にも注意を払う必要がある。もし、人体が40℃(華氏103度)で活動することに補償的な不利がなければ、感染症が始まるのを防ぐために、常にその温度を維持するはずだ。しかし、この適度な熱にも代償があり、蓄えた栄養を20パーセントも早く消耗し、一時的に男性不妊症になる。さらに高熱が続くと、せん妄や発作を起こし、組織にダメージを与えることもある。また、どのような調節機構もすべての状況を完璧に予測することはできないことも理解しておく必要がある。体温は平均して、感染と戦うために最適なレベルにまで上昇することが期待されるが、調節の精度には限界があるため、熱が上がりすぎることもあれば、下がらないこともある。
たとえ発熱が感染を長引かせるとわかっていても、発熱を抑えたいと思うことはあるだろう。健康の維持・増進だけが医学の目的ではない。ソプラノ歌手のバーバラ・ボニーは、メトロポリタンオペラの『ファルスタッフ』でナネッタを歌うことになれば、たとえ完治が遅れるとわかっていても、喉頭炎を和らげるために薬を飲むことを決断するかもしれない。私たちも、風邪をひいたとき、回復が遅れるかもしれないのに、気分をよくするために薬を飲むかもしれない。
熱の適応的意義に関して重要なことは、熱に干渉する前に、自分が何をしているかを知る必要があるということだ。今のところ、私たちはそれを知らない。もし不快感がすべてであれば、私たちはいつでも不快感を減らすか、なくすかを選択することができる。しかし、熱を下げることで回復が遅れたり、二次感染の可能性が高くなることが多いのであれば、リスクに見合うだけの利益が期待できる場合にのみ、干渉すべきなのである。私たちは、医師と患者が発熱がいつ有用で、いつ有用でないかを判断するのに役立つエビデンスが、医学研究によって早く生み出されることを願っている。
鉄分の摂取を控える
私たちの体には、ほとんどの人が気づいておらず、また医師が無意識のうちに挫折させようとしている、関連した防御機構がある。その仕組みについて、いくつかのヒントを挙げてみよう。慢性結核の患者は、血液中の鉄分のレベルが低いことがわかった。医師は貧血を改善すれば患者の抵抗力を高めることができると結論づけ、鉄剤を投与する。しかし、患者の感染症は悪化した。もう一つの手がかり。ズールー族の男性は鉄鍋で作ったビールをよく飲み、アメーバによる重い肝臓感染症にかかることが多い。一方、マサイ族のアメーバ感染者は10%以下である。彼らは牧畜民で、牛乳を大量に飲む。マサイ族のグループに鉄剤を与えたところ、88%がすぐにアメーバ感染症になった。別の研究では、善意の研究者がソマリアの遊牧民に見られる低レベルの鉄分を補うために鉄分を与えた。その結果、1ヶ月後に38%の人が感染症にかかったのに対して、サプリメントを飲まなかった人は8%であった。
卵は栄養価の高い食品だが、殻が多孔質で細菌が入り込みやすい。では、なぜ卵はそんなに長く新鮮さを保つことができるのだろうか?鉄分は卵黄に多く含まれ、白身には含まれていない。卵白のタンパク質は12%がコンアルブミンという分子で、この分子が鉄としっかり結合しているため、細菌が侵入するのを防いでいるのだ。抗生物質の時代以前は、卵白は感染症の治療に使われていた。
牛乳に含まれるタンパク質はラクトフェリンが20%で、これも鉄と結合するように設計された分子だ。母乳で育った赤ちゃんは、哺乳瓶で育った赤ちゃんより感染症が少ない。また、ラクトフェリンは涙や唾液に多く含まれ、特に傷口は酸性度が高いため、鉄と結合する効率が高い。コンアルブミンを発見した研究者は、体内で鉄を結合する同様の分子が存在するはずだと予想した。そこで、鉄としっかり結合するもう一つのタンパク質として、トランスフェリンが発見された。トランスフェリンは、特別な認識マーカーを持った細胞だけに鉄を放出する。バクテリアは必要なコードを持たないので、鉄を得ることができない。タンパク質欠乏症の人は、トランスフェリンレベルが通常の10%以下になっている可能性がある。もし、トランスフェリンの供給が回復する前に鉄分の補給を受けると、血液中の遊離鉄によって致命的な感染症にかかる可能性が高くなる。
このように、鉄は重要かつ希少な資源である。鉄は細菌にとって極めて重要かつ希少な資源であり、宿主は細菌に鉄を取られないようにするために、さまざまなメカニズムを進化させてきた。感染症にかかると、体は白血球内因性メディエーター(LEM)という化学物質を放出し、体温を上昇させるとともに、血液中の鉄の利用率を大幅に低下させる。また、感染時には腸管での鉄の吸収も低下する。食べ物の好みも変わる インフルエンザにかかると、鉄分の多いハムや卵は食べたくなくなり、紅茶やトーストを好むようになる。これは、鉄分を病原体から遠ざけるのにちょうどいい。しかし、クルーガーが指摘するように、鉄分の低下により、一部の患者には有効であったのかもしれない。
しかし、現在でも、鉄分補給が感染症患者に害を及ぼす可能性があることを知っている医師は11%、薬剤師は6%に過ぎないことが分かっている。サンプル数は少ないが、この研究は、臨床医にいくつかの確立された科学的知見を認識させることの難しさを物語っている。一流の研究者でさえ、この適応のメカニズムについて言及するのを怠ることがある。「The New England Journal of Medicine』誌に掲載された最近の研究では、脳性マラリアの子どもたちに鉄と結合する化学物質を投与すると回復しやすいことが示されたが、この論文には、感染時に鉄を結合する身体の自然なシステムについては述べられていない。鉄結合を制御する進化したメカニズムは、感染症の症状から防御を区別することに注意し、身体の反応が不適応であると結論づけるのを遅らせ、防御反応を無効にすることに慎重になるべきであるという、より広い原則の一つの具体的な例であるに過ぎない。要するに、私たちは身体の進化した知恵を尊重すべきなのである。
戦略と対抗策
生物間の対立を扱うのは、医学研究者だけではない。生態学者や動物行動学者は、捕食者と被食者の関係、交尾の機会をめぐるオス同士の争いなど、さまざまな種類の対立を日常的に扱っている。彼らは、観察された現象が進化的に重要であることを認識し、戦略と戦術、勝者と敗者などの用語を使い、適応主義的なプログラムへのコミットメントを示している。このようなアプローチは、ダーウィニズムに傾倒する生態学者やその他の人々にとって、豊かな実りをもたらすものであった。熱病のような現象に対する同様のアプローチは、私たち全員にとって極めて重要な関心分野であるため、同様に実りあるものとなるはずだ。
寄生虫と宿主との間の争いは戦争であり、感染の兆候や症状はすべて、一方または他方の戦略との関連で理解することができる。発熱や鉄分補給のように宿主に有利なものもあれば、病原体に有利なものもあり、また両者の戦いに付随する効果もある。もちろん、これらの戦略は意識的な思考の産物ではないが、それでも戦略であることに変わりはない。無害なふりをして体内に潜り込む細菌は、むしろ木馬の中に隠れているギリシャ兵のようなものである。感染症の症状が利害の対立に関連している場合、その機能的重要性に基づいて、きちんとカテゴリーに分類される。表3-1は、これらのカテゴリーの概要と本章の構成の指針を示すものである。
表 3-1 感染症に関連する現象の分類
観察例 受益者
- 宿主の衛生対策 蚊を殺す、病気の隣人を避ける、排泄物を避ける 宿主
- 宿主の防御 発熱、鉄分補給、くしゃみ、嘔吐、免疫反応 宿主の損傷修復
- 宿主の損傷修復 組織再生 宿主
- 宿主の損傷に対する補償 歯の痛みを避けるために反対側で噛む 宿主
- 宿主 病原体による宿主組織の損傷 虫歯、肝炎の肝臓への害 どちらもない
- 病原体による宿主の障害 咀嚼不全、解毒作用の低下 どちらでもない
- 病原体による宿主の防御の回避 分子模倣、抗原の変化 病原体
- 病原体による宿主の防御機能への攻撃 白血球の破壊 病原体
- 病原体による栄養の取り込みと利用 トリパノソーマの成長・増殖 病原体
- 病原体の飛散 蚊による新しい宿主への血液寄生虫の移動 病原体
- 病原体による宿主の操作 大げさなくしゃみや下痢、行動の変化 病原体
宿主はどのようにして感染を防ぐのだろうか?第一に、宿主が病原体にさらされないようにすることだ。次に、病原体が体内に侵入しないように障壁を築き、防御し、防御が破れた場合には迅速に修復することができる。もし病原体が外壁を越えて侵入してきた場合、病原体の身元を証明できない細胞にはフラグを立て、侵入経路から追い出すことができる。もし、この防衛線を突破されたら、穴を開け、毒を飲ませ、飢えさせ、殺すために必要なことは何でもすることができる。それでもダメなら、繁殖や拡散ができないよう、壁を作ることもできる。もし彼らがダメージを与えたなら、それを修復することができる。すぐに修復できない場合は、何らかの方法でダメージを補うことができる。このような損傷とその結果生じる機能障害は、宿主にも病原体にも利益をもたらさないものもある。フランスの海岸にある老朽化した爆弾のクレーターのように、古い戦いの付帯的な遺物に過ぎない。
もちろん、病原体も簡単にはあきらめない。私たちの身体は彼らの家であり、夕食だ。私たちは当然のことながら、細菌やウイルスを悪者扱いしているが、これは人間中心的な考えである。私たちの防御は、哀れな連鎖球菌が私たちの体内組織に1マイクログラムでも入るのを防ごうとするが、防御を回避する方法を見つけられなければ、死んでしまう。そこで、私たちの防御のそれぞれに対して、病原体は対抗策を進化させてきた。病原体は、私たちに感染する方法を見つけ、私たちの壁を破る方法を見つける。いったん侵入すると、私たちの監視から隠れ、私たちの防御を攻撃し、私たちの栄養を利用して自分のコピーを作り、そのコピーを体外に出して新たな犠牲者を生み出す方法を見つけるのだが、その際、私たちの防御を逆手に取ることが多い。私たちの防御から逃れるために病原菌が使う巧妙な策略を説明する前に、防御についてもう少し詳しく説明する。
衛生管理
最良の防御は、危険を回避することである。適切な衛生管理は、病原体が最初の足場を築くことを防ぐことができる。本能的に蚊を叩くのは、蚊に刺されるという些細な不快感から逃れるためだけではない。マラリアなど、虫の媒介による重大な病気の予防にもなるのだ。蚊に刺されたときの痒みは、虫の悪さの一部なのだろうか?それは、蚊が私たちの血液を自由に流れるようにするために使う化学物質の偶然の結果かもしれないが、将来刺されないようにするための適応でもある。蚊に刺されても平気な人がいたら、どうなるだろうか。そして、もし蚊に刺されても目立たなければ、蚊がどれだけ成功するか想像してみてほしい。
感染症にかかる可能性のある人との接触を避けようとする私たちの傾向も、同じような意味を持っているかもしれない。同様に、本能的な嫌悪感は、糞便や嘔吐物などの感染源を避ける動機となる。排泄物を他人から遠ざけようとする傾向が、身近な人への感染を防ぎ、そのような習慣に従うようにという社会的圧力が、他人からの感染から私たちを守ってくれるのだろう。感染に対する最善の防御は、病原体を避けることであり、自然淘汰は私たちが距離を置くことを助ける多くのメカニズムを形成してきた。
皮膚
私たちの皮膚は、古代都市を囲む壁のようなもので、強力な保護壁となっている。寄生虫の侵入を防ぐだけでなく、機械的、熱的、化学的な力による傷害から身を守る。発熱など、危険が迫ったときに初めて発動される誘導防御とは異なり、皮膚は常に存在し、常に警戒している。皮膚は丈夫で、それが保護している内部組織よりも、刺し傷やすり傷に対してはるかに抵抗力がある。皮膚は常に上から剥がれ落ち、下から新しく生まれ変わっているので、あちこちに小さな感染症があっても無害だ。指についたインクのシミは数日で消えるが、これはインクが吸収されたり化学変化したりしたのではなく、シミになった細胞が下から上がってきて入れ替わるからだ。このように表皮の入れ替わりが早いため、表面細胞で増殖した真菌や潜在的な病原体は常に取り除かれる。ソテツやヒッコリーも同じような仕組みだ。
皮膚は一般的に優れた防御鎧であるだけでなく、特に優れた防御鎧でもある。足の裏など、鎧を必要とする部位は、生まれたときから皮膚が厚く、丈夫なのである。靴の甲やチェロ奏者の指先など、摩擦が繰り返される部分には、胼胝(たこ)と呼ばれる厚い皮ができる。この適応的な成長、すなわち誘導防衛は、機械的な損傷を最小限に抑えるだけでなく、病原体の侵入口となりうる皮膚の裂け目を防ぐことにもなる。
私たちの最も有用な衛生行動のいくつかは、皮膚のバリアの維持に役立っている。最もわかりやすいのは、不快なものを皮膚に近づけないようにする行動だ。ひっかいたり、毛づくろいをしたりすることで、外部寄生虫を駆除することができる。カリフォルニア大学デービス校の獣医師であるベンジャミン・ハートは、動物の病気を防ぐためにグルーミングがいかに重要であるかを明らかにした。グルーミングができない動物は、すぐにノミ、ダニ、シラミ、ダニに侵され、体重が減り、病気になる。サルの相互グルーミングは、単なる儀式ではなく、予防医療なのだ。
痛みと倦怠感
痒みが防衛的な引っ掻き行為の動機となるように、痛みは逃避や回避につながる適応である。皮膚は、感覚的に言って、痛みに対して非常に敏感である。もし、皮膚が傷ついているのであれば、明らかに何かが間違っているのだから、傷みが止まって修復が始まるまで、他のすべての活動を中止すべきである。また、他の種類の痛みも役に立つ。歯槽膿漏で噛めなくなったという抽象的な認識から、障害のない他の歯で噛むようになるかもしれないが、歯痛という苦痛を伴う痛みの方が、治癒を遅らせたり細菌を蔓延させたりする歯への圧迫をはるかに効果的に防いでくれる。感染や怪我による痛みが続くと、損傷した組織を使い続けることで、組織の再建や細菌に対する抗体攻撃など、他の適応の有効性が損なわれる可能性があるため、適応的なのである。痛みは、自分の体がダメージを受けているときに素早く逃げ出す動機となり、痛みの記憶は、将来同じ状況を避けることを教えてくれる。
甲状腺のような臓器の機能を判断する最も簡単な方法は、それを取り出して、生体がどのように機能不全に陥るかを見ることである。痛みの能力は取り除くことができないが、ごくまれに痛みのない人が生まれてくることがある。そのような痛みのない人生は幸運に思えるかもしれないが、そうではない。痛みを感じない人は、長時間同じ姿勢でいても不快感を感じないし、その結果、そわそわしないので関節への血液供給が悪くなり、思春期には関節が悪くなってしまうのだ。痛みを感じない人は、30歳までにほぼ全員死んでしまう。
一般的な痛みや不快感(医学用語でいう倦怠感)も適応的なものである。痛みは、損傷した部位を使わないようにするだけでなく、全般的に不活発にすることを促す。これが適応的であることは、病気のときは寝ているのが賢明であると信じられていることでも広く認識されている。また、不活発であることは、免疫学的防御、損傷組織の修復、その他の宿主適応の有効性にも有利である。病人の気分を和らげるだけの薬物療法は、これらの効果を阻害することになる。患者がリスクについてよく知らされていて、自分が感じている以上に病気であることを自覚し、特別な努力をする必要がある場合は良いが、そうでない場合は、薬物によって引き起こされる気分の落ち込みが生じる。そうでなければ、薬物による幸福感が、防御的な適応や修復を妨げるような活動レベルにつながるかもしれない。
排出に基づく防御
身体には、呼吸のため、栄養の摂取と老廃物の排出のため、そして生殖のための開口部が必要だ。これらの開口部は、それぞれ病原体の侵入経路となるため、特殊な防御機構を備えている。口の中を常に唾液で洗うことで、ある病原体は殺され、他の病原体は胃の中の酸や酵素によって破壊されるように移動させられる。目は防御化学物質を含んだ涙で洗われ、呼吸器系は抗体と酵素を豊富に含んだ分泌物が喉まで着実に運ばれ、そこで侵入者を殺し、粘液中のタンパク質を再利用することができるように飲み込まれる。耳からは抗菌作用のある耳垢が分泌されている。鼻の中にある鼻甲介という突起は、入ってくる空気を温め、湿らせ、病原体をろ過する大きな表面を提供する。口呼吸をする人は、この防御機能が十分に働かないため、感染症にかかりやすい。鼻と耳には、虫除けのための毛が戦略的に配置されている。
危険が迫ると、体の各開口部の防御力を素早く高めることができる。ウイルス感染で鼻を刺激すると、1日にティッシュ1箱を使い切るほどの大量の粘液が分泌される。この有用な反応を阻止するために、毎年何百万人もの人々が鼻腔スプレーを使用しているが、このような器具の使用が風邪からの回復を遅らせるかどうかを調査した研究は驚くほど少ない。もし、鼻水が風邪の回復を遅らせないのであれば、それは鼻水が防御ではなく、病原体が宿主の生理機能を操作して感染を拡大させる例であることの証拠となる。くしゃみは明らかに防御的適応であるが、すべてのくしゃみがくしゃみをする人にとって適応的である必要はない。くしゃみの中には、ウイルスが自身を拡散させるための適応であるものもあるかもしれない。
気道の奥が刺激されると、咳が出る。咳は、異物を感知し、その情報を脳で処理し、脳の底部にある咳中枢を刺激し、胸部、横隔膜、気道の管の筋収縮を調整する、という精巧なメカニズムによって可能になる。気道の内壁には繊毛という小さな毛が一定のリズムで生えており、病原体を捕捉する粘液を上方に掃き出す。尿路では、定期的な洗浄によって病原体が洗い流され、尿道粘膜の表面にある細胞も、皮膚の細胞のように規則正しく剥がれ落ちていく。膀胱や尿道が感染すると、当然ながら排尿の回数が増える。
消化器官にも特別な防御機能がある。バクテリアの腐敗やカビの繁殖は不快な臭いを発生させるが、その不快さは、臭いのきついものを口に入れたくないというわれわれの適応による。すでに口の中に入っているものが不味ければ、それを吐き出す。味覚受容体は毒である可能性のある苦い物質を検出する。飲み込んだ後、胃の中には毒を感知する受容体があり、特に消化管内で繁殖した細菌が作った毒を感知する。吸収された毒素が循環器系に入ると、血液に直接さらされる唯一の脳細胞である脳の特別な細胞群を通過する。この細胞が毒素を感知すると、脳の化学受容体トリガーゾーンを刺激して、まず吐き気を催し、次に嘔吐を引き起こす。これが、多くの薬物が吐き気を催す理由であり、特に癌の化学療法に使われる毒性の強い薬物がそうである。
循環する毒素はほとんど胃から発生するので、嘔吐がいかに有用であるかは容易に理解できる。吐き気についてはどうだろうか。吐き気の苦痛は、有害な物質をそれ以上食べないようにさせ、その記憶は、その原因となった食品を今後口にするのを躊躇させる。新規の食物を食べた後に吐き気と嘔吐を一度経験するだけで、ラットは数ヶ月間その食物を避けるようになり、人は数年間その食物を避けるようになるかもしれない。この極めて強い一回性の学習は、マーティン・セリグマンという心理学者によって「ベアルネーズソース症候群」と名づけられた。なぜ、病気を引き起こす食べ物に一度触れただけで、これほどまでに強い関連付けができるのだろうか。毒のある食べ物を繰り返し食べた人はどうなるのか、ちょっと想像してみてほしい。
腸管のもう一方の端には、下痢という防御機能がある。下痢を止めたいのは当然だが、防御をブロックしただけで楽になるのなら、何らかのペナルティがありそうだ。テキサス大学の感染症専門家であるH・L・デュポンとリチャード・ホーニックは、まさにこのことを発見した。25人のボランティアに赤痢菌を感染させ、その菌がひどい下痢を引き起こす。下痢を止める薬を投与された人は、そうでない人に比べて2倍の期間、発熱と毒性が持続した。下痢止め薬のロモチールを投与された6人中5人は、便に赤痢菌が混じり続けたのに対し、投与されなかった6人中2人は、便に赤痢菌が混じり続けた。研究者らは、「ロモチールは赤痢症に禁忌である可能性がある」と結論づけた。下痢は防御機構を表しているのかもしれない 」と結論付けている。消費者は間違いなく、よりありふれた下痢に対して、このような薬をいつ飲むべきで、いつ飲んではいけないかを知りたいと思うだろうが、必要な研究はなされていない。下痢を止める薬の副作用、安全性、有効性については何十もの研究があるが、正常な防御を阻害するという主作用の結果についてはほとんど考慮されていない。
生殖器官にはもう一つ開口部が必要で、それは男性の場合、尿路と同じであり、その防御は二重の役割を担っている。女性には別の開口部があり、感染に対する防御に特別な問題を提起している。女性の生殖管は、子宮頸管粘液やその抗菌性など多くの防御機能を備えているが、あまり知られていない防御機能のひとつに、細菌やウイルスが侵入しにくいように分泌物を外に出す通常の動きがある。これらの分泌物は、腹腔から卵管、子宮、子宮頸部、膣を通って外へと着実に移動している。この絶え間ない下流への移動には、ひとつだけ特筆すべき例外がある。精子細胞は、膣から子宮を経て卵管、骨盤内腔へと上流に向かって泳いでいく。精子は人間の細胞としては珍しく小さいが、細菌と比較するとまだ大きい。精子には病原体が付着し、外部から女性の生殖器官の奥深くまで運ばれる可能性がある。
精子が媒介する病原体の脅威が認識されるようになったのは、ごく最近のことである。生物学者のマージー・プロフェットは、月経には相当なコストがかかると指摘し、それゆえ月経には何らかの代償となる利益があるはずだと主張する。その結果、月経の多くの側面が、子宮感染に対する効果的な防御として設計されているようだと彼女は結論づけた。皮膚細胞が剥がれ落ちるのと同じように、子宮の内膜が定期的に押し出されることによって、抗感染症効果が得られる。このことは、月経血が循環血液と異なり、栄養分の損失を最小限に抑えつつ、病原体を破壊する効果が高いという証拠によって裏付けられている。他の哺乳類の月経に関する研究によると、それぞれの種が精子を媒介とする病原体に対する脆弱性に見合った程度に月経を行うことが示唆されている。性行動を大きく隔たった受胎可能期間に限定する種にとっては脅威は小さいが、女性の継続的な性的魅力と受容性は排卵周期とはほとんど無関係である。このような人間の異常なまでの性行動は、第13章で述べるような利点もあるかもしれないが、感染の危険性を大幅に高めることになる。他の哺乳類に比べ、ヒトの月経の量が異常に多いのは、このリスクのためかもしれない。
進化論的仮説は検証される必要があり、また検証できることを何度か述べてきた。ビバリー・ストラスマンは、月経が感染から身を守るという仮説に挑戦している。彼女は、生殖管における病原体の負荷は月経の前後で同じであり、感染症があっても月経は増加せず、特定の種のメスがさらされる精子の量と月経の量との間には一貫した関係がないと主張する。この仮説は、種間の比較や、月経とメスおよび新生児の体重との関係で裏付けられている。明らかに、私たちはこの問題についての最後の言葉を聞いてはいないのだ。
侵入者を攻撃するメカニズム
一般に脊椎動物、特に哺乳類は、驚くほど効果的な免疫学的防御を備えており、それは要するに、注意深く標的を定めた化学戦争のシステムなのである。マクロファージと呼ばれる細胞は、バクテリア、皮膚の汚れ、あるいはガン細胞など、あらゆる外来タンパク質を求めて常に体内を徘徊している。マクロファージは侵入者を見つけると、それをヘルパーT細胞に転送し、ヘルパーT細胞は、その特定の外来タンパク質(抗原)に特異的に結合するタンパク質(抗体と呼ぶ)を作れる白血球を見つけ出し、刺激する。抗体は、バクテリアの表面にある抗原と結合することで、バクテリアに障害を与え、さらに特殊な大型細胞による攻撃のための標識となる。抗原が持続する場合、例えば細菌感染が続くと、その特定の抗体を作る細胞の生産が刺激され、細菌がどんどん破壊されていく。体の一部として正しく機能していると認められたものは、そのままにしておくことができる。それ以外のもの、つまり病気の生物、癌の組織、他の個体から移植された臓器はすべて攻撃される。
細胞はどのようにして自分のものと認識するのだろうか?各細胞の表面には、主要組織適合性複合体(MHC)と呼ばれる分子パターンがあり、これは写真付き身分証明書のようなものである。有効なMHCを持つ細胞はそのままにしておくが、異物や欠損したMHCを持つ細胞は攻撃される。興味深いことに、細胞は感染すると、侵入者のタンパク質をMHCに輸送し、結合させる。明らかに偽造の身分証明書を持つ人のように、そのような細胞は免疫系のキラー細胞の優先的なターゲットとなる。喉の痛みの原因としてよく知られているアデノウイルスは、この防御を回避する方法を発見した。それは、細胞が外来タンパク質をMHCに移動させる能力をブロックするタンパク質を作るのである。要するに、感染した細胞が、自分たちが侵略されたというシグナルを発するのを防ぐのである。
MHCシステムの作動は、生物学的な意味での利他主義の鮮やかな例と言えるだろう。感染した細胞は、体の他の部分のために、破壊のために「志願」する。これは、ペストに感染した兵士が、仲間に感染させる前に自分を殺してくれと頼むようなものである。しかし、この例えは、ある重要な点で間違っている。細胞の仲間は遺伝的に同一であり、その遺伝子を受け継ぐ唯一のチャンスは、生物全体の成功にあるのだ。しかし、兵士は一卵性双生児と同じ穴のムジナであることはめったになく、当然ながら排除のために志願することは少ない。
免疫系の武器は実に恐るべきものである。一般的な炎症、数種類の抗体(それぞれ異なる敵のグループに特化している)、一連の化学物質(補体系)などがあり、そのうちの5つが標的細胞を攻撃し、その膜に穴をあけて消化する。このような武器があるにもかかわらず、一部の侵入者はしぶとく生き残ることができる。細菌の塊が追い出すことも破壊することもできない場合、膜で囲まれて脆弱な組織から遠ざけられていることがある。結核の名前の由来となった結節が最もよく知られている例であるが、回虫やその他の多細胞寄生虫もまた、人類の進化の過程で重要な役割を果たしてきた。
損傷と修復
宿主との競争において、病原体は自らの栄養を確保するために宿主を奪わなければならない。様々な細菌やアメーバ赤痢の原因となる原虫は、酵素を分泌して近くの宿主の組織を消化し、その消化産物を吸収する。また、文字通り宿主の組織を食い破るものもいる。例えば、目の前方に生息するフィラリア虫や、脳内に潜り込む別種の虫、アンジオストロンギルス・カントネンシスの幼虫がそうである。いずれも、炎症を抑制する分泌物で身を守る。また、アフリカ睡眠病などの原因となる原生生物トリパノソーマのように、血流中に生息して血漿から直接栄養を吸収するものもいる。いずれにせよ、寄生虫は宿主から資源を確保し、それを自らの維持、成長、繁殖のために利用している。
このような病原体の活動は、付随的に宿主にダメージを与えるが、このダメージは病原体の適応ではない。サナダ虫が宿主を栄養失調に陥れても何の役にも立たない。マラリア原虫が宿主の血球を破壊しても、何の役にも立たない(寄生虫が使用するために鉄を解放する場合は別かもしれないが)。ほとんどの場合、その逆でなければならない。寄生虫の生存と幸福は、宿主が生存し続け、栄養と避難所を提供し続けることができるかどうかにかかっているのだ。したがって、このような偶発的な被害は、宿主と病原体の双方にとってコストと見なされなければならない。
その代償は宿主資源の全般的な減少である場合もあれば、明らかに局所的な破壊である場合もある。歯根のある骨を攻撃する細菌は、構造的な損傷を引き起こし、おそらくは歯を失うことになる。淋病の原因菌は、関節の結合組織や軟骨を侵食し、機能障害を引き起こすことがある。肝炎ウィルスは肝臓のかなりの部分を破壊し、血液から毒素を取り除くなど、すべての肝機能を低下させることがある。このような機能障害は、病原体の適応がもたらす偶発的な結果に過ぎない。宿主の咀嚼力を低下させたり、走る速度を低下させたりすることは、バクテリアにとって何ら良いことではない。
損傷とその結果生じる機能障害は、概念的に分けて考えることが重要である。損傷は機能障害を引き起こするが、その機能障害自体が、代償的適応と呼ばれる別の宿主適応の原因となることがある。右側で噛むと痛いから左側で噛む、というような微妙な例もあるが、多くの例がある。例えば、病気で傷ついた肺が血液を酸素化するのに弱くなった場合、血中ヘモグロビン濃度の上昇によって、その一部を補うことができるかもしれない。体には、血液中の酸素濃度をモニターする仕組みがある。高地での生活や肺の損傷によって酸素が不足すると、体はエリスロポエチンという赤血球の産生を促すホルモンをより多く作るようになる。
もう一つの明らかな宿主適応は、ダメージの修復である。自然淘汰は、さまざまな組織を再生する能力を、それが通常どれほど有用であるかに応じて調整した。皮膚はしばしば損傷を受けるが、病原体や怪我に対する第一の防御線である。予想されるように、それは素早く再生され、その保護能力を急速に回復させる。その他に再生が早いのは、腸の粘膜や肝臓などの臓器で、これらは腸とオープンなコミュニケーションをとっているため、外界やその感染因子と接触している。これに対して、心臓や特に脳は、ほとんどの病原体がアクセスしにくい。もし、病原体が侵入して深刻なダメージを与えたとしても、通常は致命的であるため、再生能力が役に立つことはほとんどない。
病原体による宿主防御の回避
これまで、われわれは病原体の適応の一種、宿主の体内で栄養を補給する能力についてだけ述べてきた。また、病原体は宿主の破壊、排出、隔離の努力から自らを守る方法を進化させてきたと予想できる。ここで、そのような機構の一つである宿主の防御回避について考えてみよう。
多くの寄生虫は、体内に侵入すると、まず細胞内に入り込む。侵入者は、訪問販売業者が行うのと同じように、何か別のものを提供するように見せかけて、これを達成することができる。狂犬病ウイルスはアセチルコリン受容体に、牛痘ウイルスは上皮成長因子受容体に、まるでホルモンのように結合し、エプスタイン・バー・ウイルス(単核球症の原因となる)はC4受容体に結合して、それぞれ有用な神経伝達物質であるかのように見せる。風邪の原因となるライノウイルスは、気道に並ぶリンパ球の表面にある細胞間接着分子(ICAM)に結合する。リンパ球を攻撃すると化学物質が放出され、ICAMの結合部位が大幅に増えるため、ウイルスが細胞内に侵入するための入り口がたくさんできる。
もう一つの方法は、免疫系を回避することだ。アフリカ睡眠病の原因であるトリパノソーマは、急速に姿を変えることによって、これを実現している。トリパノソーマを制御するのに十分な抗体を作るのに10日ほどかかるが、9日目くらいにトリパノソーマは全く新しいタンパク質の表層を露出させて変装し、抗体による攻撃から逃れる。トリパノソーマは1000種類以上の抗原性被覆の遺伝子を持っているので、宿主である人間の中で何年も生き続け、常に免疫システムの一歩先を行くことができる。他の2つの一般的な細菌も同様の戦略を持っている。髄膜炎や耳の感染症の原因となるヘモフィルス・インフルエンザと淋病の原因となるナイセリア・ゴノラホエは、どちらも表面タンパク質を作る遺伝子機構に欠陥があるように思われるものがある。しかし、この一見したところエラーに見える部分が役に立つ。なぜなら、結果として生じる変異が、私たちの免疫系をランダムな変化に追いつかせなくするからだ。
マラリア原虫は特殊な表面タンパク質を持っており、血管壁に結合して、脾臓で濾過されて死んでしまうのを防いでいる。マラリア原虫のこの結合タンパク質をコードする遺伝子は、1世代あたり2パーセントの割合で変異し、免疫システムがその生物をロックオンできないようにするのに十分な量である。肺炎の原因となる肺炎球菌は、免疫システムを回避するために別のトリックを使っている。肺炎球菌の表面には、白血球がつかめない「滑りやすい」多糖類が付着している。このため、体はオプソニンという化学物質を作り、微生物に結合させて、抗体がつかめるようにする。
また、スパイが敵陣で使う変装のように、化学的な方法で回避することもよくある。細菌や虫の中には、その外面化学的性質が人間の細胞のそれと非常によく似ているものがあり、宿主がそれらを異物として認識することが困難な場合がある。(ヒトと長い間付き合ってきたレンサ球菌は、特にこのトリックに長けている。ある種の菌株に対する抗体が、自分の関節や心臓を攻撃するリウマチ熱の原因となる。脳の大脳基底核の神経細胞を攻撃する同様の抗体攻撃は、制御不能な筋肉の痙攣を特徴とするシデナム舞踏病(Sydenham’s chorea)を引き起こすことがある。興味深いことに、過剰な手洗いや誤って他人を傷つけることへの恐怖を特徴とする精神疾患である強迫性障害の患者の多くが、幼少期にシデナム舞踏病であったという。現在では、強迫性障害に関与する脳領域は、シデナム舞踏病で損傷を受けた領域と非常に近いという証拠が増えつつある。このように、強迫性障害の中には、溶連菌と免疫系の間の軍拡競争に起因するものもある。
今日、性病の原因として最も多いクラミジアは、警察署に隠れているのと同じようなことをする。白血球の中に入り込み、壁を作り、自分が消化されないようにするのだ。マンソニ型のスキストゾーマはさらに進んで、本質的に警察の制服を盗んでいく。アジアで肝疾患の深刻な原因となっているこれらの寄生虫は、血液型抗原を拾うので、免疫システムからは私たち自身の正常な血液細胞のように見えるかもしれない。
宿主の防御機能に対する攻撃
病原体は宿主の防御から身を守ろうとするだけでなく、自分自身の破壊的な武器も持っている。ほとんどの単純な皮膚感染症の原因となる黄色ブドウ球菌は、有用な炎症の最初のステップであるヘーゲルマン因子の働きを阻害する神経ペプチドを分泌している。このペプチドを分泌できない細菌は、感染症を引き起こさない。喉の痛みの原因となる溶連菌も、白血球を殺すストレプトライシンOを分泌している。牛痘の原因ウイルスであるワクシニアは、前述のように、重要な宿主防御機能である補体系を阻害するタンパク質を作っている。なぜ補体系が私たち自身の細胞を攻撃しないのだろうか?それは、私たちの細胞にはシアル酸の層があり、それが補体系による攻撃から細胞を守っているからだ。しかし、ある種の細菌、この場合は腸内に生息する大腸菌のK1株は、シアル酸で自らを覆うことができるため、補体系からの保護を受けることができる。
ある種の細菌に感染すると、血圧が低下し、急速に死に至るショック状態に陥ることがある。ショックは、細菌が形成する化学物質リポポリサッカライド(LPS)により引き起こされる。表面的には、LPSは細菌が私たちに害を与えるために作った毒素のように思えるが、研究者のエドモンド・ルグランが指摘するように、LPSはこの細菌群全体の細胞壁の必要成分であるため、その可能性は低い。宿主は、危険な感染症が存在することを示すこの確実な合図を認識し、強く(時には強すぎるほど強く)反応する。ここで、持ち主に牙をむく防御兵器の一例を紹介しよう。
エイズの原因ウイルスであるヒト免疫不全ウイルス(HIV)は、抗原を免疫系の目に留まらせるヘルパーT細胞の中に潜んでいる。この細胞の外膜にはCD-4というタンパク質があり、これにHIVが結合して細胞の中に入り込む。HIVのこのタンパク質は、ウイルスの壁の深い隙間に隠されていることを除けば、免疫システムに対して脆弱なものである。HIVはヘルパーT細胞を殺すので、被害者は他の感染症や癌にますますかかりやすくなり、最終的にAIDS患者を死に至らしめることになる。
その他の病原体の適応
寄生虫の適応には、まだ二つの関連したカテゴリーがある。病原体が宿主の中でいかにうまく生き延び、増殖しても、それ自身やその子孫を他の宿主に移すための分散メカニズムが必要である。外部寄生虫の場合、これはかなり簡単なことである。例えば、シラミや白癬菌は、人との接触によって容易に伝播する。一方、内部寄生虫の場合は、より大きな問題がある。皮膚に定期的に付着する寄生虫は、他の感受性の高い人と接触する可能性がある。風邪のウイルスや腸内細菌は、手や他の表面に付着し、握手やより親密な接触によって広がる可能性がある。
血液中の微生物は、このような方法では広がらないだろう。多くの場合、昆虫などの媒介物(ベクター)の力を借りてのみ感染する。マラリアがよく知られている例だ。仮に1ミリグラムの血液中に約10匹のマラリア原虫(配偶子細胞)が存在し、蚊が3ミリグラムを吸血すると、約30匹の配偶子細胞を取り込むことになる。蚊の次の仕事は、この豊富な血液を卵に変え、発育に適した環境で受精させ産ませることである。一方、性的に生産されたマラリア原虫の子孫は、蚊の唾液腺に移動し、蚊が次の血液を吸い上げる際に凝固を抑制するための液の中で感染段階に変化する。そして、蚊は知らず知らずのうちに、次の犠牲者にプラスモディアを注入してしまうのである。このように、多種多様な昆虫や生物が、人間の病気を媒介することができる。
もうひとつの寄生虫の適応は、専門的には宿主操作(host manipulation)と呼ばれるものである。寄生虫は微妙な化学的影響を与えることによって、宿主の体の機械を制御し、その機械を宿主ではなく、寄生虫の利益のために使わせることができる。このような例は、多くの生物種で知られている。タバコモザイクウイルスは、宿主に寄生すると、隣接するタバコ細胞の間の孔を十分に拡大させて、ウイルス粒子を通過させ、他の細胞に感染させる。ある種の寄生虫は、そのライフステージをアリと羊の間で交代させる。ちょうど、マラリアが脊椎動物の宿主と蚊の間で交代しなければならないのと同じである。この寄生虫は、アリの神経系のある部位に入り込み、アリを草の葉の上に登らせて離さなくさせるので、アリから羊に効果的に感染させることができる。そのため、アリが羊に食べられる可能性が非常に高くなる。また、カタツムリとカモメを交互に襲う虫もいる。この虫は、浅い沿岸の海底に絡みつくように生えているカタツムリを、高い位置にある岩や砂の上に這い上がらせ、そこに留まらせる。そうすると、カモメに簡単に見つかって食べられてしまう。
狂犬病ウイルスは、病原体が宿主の行動をいかに操るかについて、特に顕著で陰惨な例を示している。狂犬病ウイルスは、通常感染者に咬まれて体内に侵入した後、神経線維に沿って脳に移動し、そこで攻撃性を制御する部位に集中的に作用する。そして、宿主を攻撃させたり、咬ませたりして、他の個体に感染させることができる。また、被害者の嚥下筋を麻痺させるので、ウイルスを含んだ唾液が口の中に溜まり、感染の可能性が高くなり、ついでに被害者が液体で窒息する恐怖を感じるので、この病気はもともと水恐怖症と呼ばれるようになった。
病原体によって操作される人間の最も重要な例は、おそらく細菌やウイルスによって引き起こされるくしゃみ、咳、嘔吐、下痢であろう。感染の歴史のある段階において、この排出は宿主と微生物双方の利益になる。宿主は自分の組織を攻撃する病原体の数が減ることで利益を得、微生物は他の宿主を見つける機会が増えることで利益を得る。このゲームで負けるのは、現在健康でありながら弱い立場にある人たちである。コレラ菌が放出する化学物質が腸からの水分吸収を低下させ、大量の下痢を引き起こす。公衆衛生が十分に発達していない社会では、効果的に伝染病を蔓延させることができる。
私たちは、寄生虫にうまく操られることもあれば、操られることに抵抗することもあり、また、何らかの中間的な解決方法がある場合もある。このような対立のどのような例も、進化的に平衡状態にあり、一貫した結果を持つ可能性が高い。対立は、勝つことで最も得をする敵対者に有利に決定されることが多い。風邪のウイルスを制御するために、誰かが理想とされる2倍の頻度でくしゃみをしているとしたら、それは時間やエネルギーの損失という大きな負担にはならないだろうが、ウイルスが新しい宿主に到達する速度が2倍近くになる可能性がある。これは、まさにウイルスが勝つことを期待するような競争である。ヒトの宿主にとって最適である以上に、病原体が排出機構を誇張することはどの程度あるのだろうか?この問題についての証拠の少なさは、このような進化上の疑問が常々無視されていることを示している。
疾患への機能的アプローチ
本章の最後に、感染症の徴候と症状をその機能に従って分類した表3-1(このページ)について、三つの指摘をしておく。第一に、病気の徴候や症状を機能的に分類することは重要かつ有用である。適切な治療法を選択するためには、その咳などの症状が、患者にとって有益なのか、病原体にとって有益なのかを知る必要がある。また、病原体が宿主を操作しているのか、宿主の防御を攻撃しているのかを知る必要がある。単に症状を和らげるだけでなく、おそらく効果的でないにせよ、病原体を殺そうとするのではなく、その戦略を分析し、それぞれに対抗し、病原体を克服し、ダメージを修復しようとする宿主を支援することができる。第二のポイントは、この分類は実に単純明快であるということだ。
では、3点目だ。この章の考え方は、いつ、誰によって最初に提案されたと思うか?19世紀の医学研究者が、パスツールやダーウィンの考えや、急速に広まる寄生虫の生活史の知識をもとに提案したのだろうか?この表や本章で使用した分類法は、1980年にミシガン大学で、鳥類学者で進化生物学者でもあるポール・エウォルド(現アマースト大学)によって初めて提案されたものである。では、この章の考え方は、いつ頃から医師や医学研究者の標準的な考え方になったのだろうか。この問いに対する答えは、「まだ」である。医師がエバルトによって定式化されたカテゴリーで直観的に考えることがなかったということではない。ただ、その使い方を明確に教えられていないだけで、トレーニングの不足から、感染症について考える際にこれらの基本的な考え方を軽視しがちであるということである。このことは、進化論者と感染症専門家との交流が有益であることを強調した最近のいくつかの会議の議事録に特に顕著に表れている。しかし、この種の教材が通常の医学カリキュラムの一部となるには、まだ何年もかかるだろう。
進化生物学はよく発達した科学の一分野であり、医学的な見識を得る上で大きな可能性を秘めているのに、なぜ医学界はその助けを借りようとしないのだろうか。その理由の一つは、あらゆる教育レベルにおいて、この分野の科学が無視されてきたことにあるのは確かである。宗教上の理由やその他の反対により、ダーウィンが私たち自身や私たちの住む世界 に対する理解に与えた影響は、一般教育では最小限にとどまっている。また、医師や医学研究者の訓練においても、進化論が無視されてきた。この点については、第15章で詳しく説明する。
さらにもう一つの理由は、医学に最も大きな影響を与える進化論的な考え方の多くが、近年になってようやく定式化されたものだからだ。これらの考え方は、一度指摘されれば、単純で、常識と大差ないことが多い。しかし、その重要性が認識されたのはここ数年のことで、物理学や分子生物学の実に複雑で微妙な分野の発展や応用に比べれば、はるかに遅れているのが現状だ。進化生物学の医学その他の分野への応用が、1859年の壮大なスタート以来、なぜこれほ ど遅くなってしまったのか、これは科学史家が最も関心を寄せるべき問題だ。
