Contents
Ukraine and Russia: From Civilied Divorce to Uncivil War
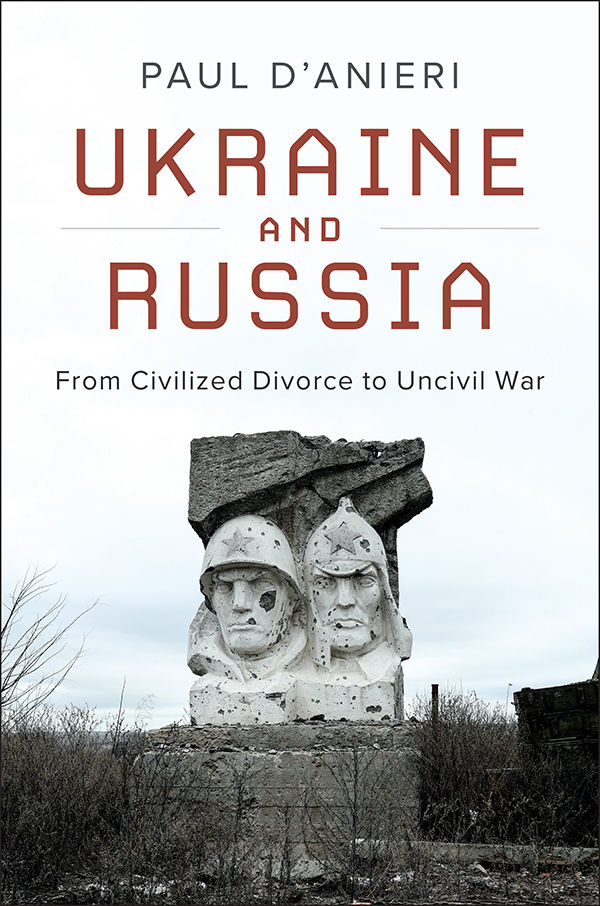
概要
ダニエリは、ソビエト連邦の崩壊によって生じたウクライナ国内、ウクライナとロシア、ロシアと西欧の間の力学を探り、最終的に2014年に戦争に至ったことを明らかにした。時系列で進む本書は、1991年にウクライナがロシアから分離したことで、当時は “文明的離婚 “と呼ばれていたが、現在では多くの人が “新たな冷戦 “と呼ぶものにつながっていることを示す。安全保障のジレンマ、民主化が地政学に与える影響、冷戦後の欧州の相容れない目標という3つの根本的な要因から、紛争は悪化したと主張する。ダニエリは、平和的な状況が浪費されたのではなく、根深い既存の不一致があり、それを埋めることができなかったと主張し、ウクライナ紛争の解決に重要な意味を持つとしている。本書はまた、この戦争が現代の国際紛争のより広いパターンにどのように当てはまるかを示しており、ロシア・ウクライナ紛争、ロシアと欧米の関係、紛争と地政学一般を研究している研究者にアピールするものである。
編集部レビュー
書籍の説明
ダニエリは、ウクライナ、ロシア、西側諸国間の国際紛争の長期的なダイナミクスを探り、ウクライナをめぐる紛争の歴史的な根源を明らかにする。安全保障のジレンマ、民主化が地政学に与える影響、冷戦後の欧州の相容れない目標が、いかに「新たな冷戦」につながっているかを実証している。
レビュー
ウクライナ戦争と東西関係の新たな危機は、誰が、何に起因しているのか?この一見単純な問いに、ポール・ダニエリは単純な答えを求めてはいない。彼の答えは、過去30年間の露・ウクライナ関係の検証に根ざしており、冷戦後の世界におけるロシアとウクライナのエリートたちの理解や利益の追求の仕方に深い違いがあることを指摘しているのである。博識な著作である本書は、1つ以上の研究分野に貢献し、現在の危機の起源に関心を持つすべての人にとって必読の書である
Serhii Plokhy, Mykhailo S. Hrushevs’kyi Professor of Ukrainian History, Harvard University, Massachusetts(ハーバード大学ウクライナ史教授)
ウクライナ、ロシア、西欧の資料や視点を徹底的に考察したダニエリの『ウクライナとロシア』は、今日の紛争の本質と可能な道筋を理解しようとするとき、今や最初に参照すべき本であろう
ヘンリー・ヘイル、ジョージ・ワシントン大学、ワシントンDC
ポール・ダニエリの「ウクライナとロシア。ソビエト連邦崩壊後のウクライナとロシアの関係について、初めて包括的な説明がなされた一冊である。ウクライナとロシアだけでなく、米国や「西側」も含めた国家間の関係の本質に関する理論的議論を、1989年から現在に至るまで深く研究された歴史的叙述と見事に織り交ぜている。野心的なことに、ダニエリは、その説明のために一つの理論を選んだり、一つの国に責任を負わせたりすることに満足せず、正しく国際的要因と国内的要因の間で分析を進め、この歴史の包括的な説明を提供する。ウクライナとロシア』は、社会科学者や歴史学者だけでなく、この激動の関係を理解しようとするすべての人にとって興味深い、素晴らしい読み物である
マイケル・マクフォール、『冷戦から熱い平和へ』の著者。プーチンのロシアで活躍する米国大使
幸運な読者は3冊の本を手に入れることができる。1991年以降のロシアとウクライナの長い紛争のサイクルに注目した初めての大規模な調査、冷戦後の和解の一般的な問題の中でのこのダイナミックの位置づけについてのバランスのとれた評価、そして危機を説明する現実主義者と自由主義者の試みについての興味深い討論である
アンドリュー・ウィルソン(ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン、欧州外交問題評議会
本書はディテールに富んでいるが、この新たな凍結された紛争がどのように発生したかを理解したい一般の読者には非常によくまとまっている。著者はパンチを効かせず、さまざまな議論をわかりやすく並べている
ジェリー・レナバーグ、ニューヨーク・ジャーナル・オブ・ブックス誌
‘…本書は1990年代から2019年までの動向を非常に詳細に説明し、2国間の合意、経済的要因の役割を網羅する…本書はこの厄介な紛争を理解するために、説得力のある事実に支えられた高度な分析を提供している。
T・R・ウィークス、チョイス
なぜウクライナとロシアは1991年以来、実行可能な関係を築くことができないのか?ポール・ダニエリは、ソ連崩壊後のキエフとモスクワの関係の発展を検証し、ウクライナとロシアのアメリカやEUとの関係という広い文脈に置くことで、この問いに答えている
ランシン・シアン、ロシアとユーラシア
ダニエリは「この紛争がどのように、そしてなぜ生じたのか」(2頁)を説明するという初歩的だが重たい課題に挑み、非党派的で思慮深い徹底した分析を提供してい」(同)
パベル・K・バエフ、ジャーナル・オブ・ピース・リサーチ誌
この集中的に研究され、魅力的に書かれた本は、ポスト冷戦の文献に必要かつタイムリーに追加されるものである。IRの研究者は、ダニエリのIR理論の巧みな概観に酔いしれるだろうし、政策立案者は、安全保障のジレンマの効果的な管理に関する貴重な洞察を見いだすだろう…この広く構想され、よくまとめられた本は、学際研究の最高峰を示すものだ
Olena Lennon, Harvard Ukrainian Studies –This text refers to the hardcover edition.
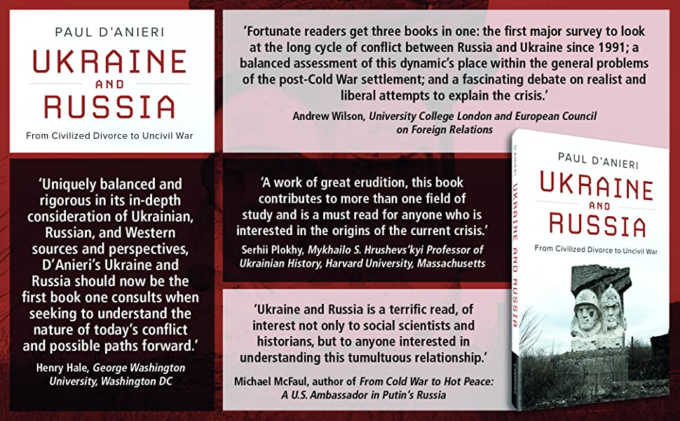
著者について
カリフォルニア大学リバーサイド校政治学・公共政策学部教授。Understanding Ukrainian Politics (2007), Economic Interdependence in Ukrainian-Russian Relations (1999) のほか、国際政治学の教科書として広く使われている著者である。米国ウクライナ研究協会副会長。–本書はハードカバー版である。
ポール・ダニエリ:カリフォルニア大学リバーサイド校の政治学・公共政策学教授。Understanding Ukrainian Politics (2007), Economic Interdependence in Ukrainian-Russian Relations (1999)のほか、国際政治学の教科書として広く使われている著書がある。米国ウクライナ研究協会副会長。
目次
- 地図一覧
- テーブル一覧
- 謝辞
- 1ウクライナをめぐる紛争の根源
- 2新たな世界秩序?1989-1993
- 3希望と苦難、1994年~1999年
- 4独裁と革命、1999年-2004年
- 5改革と反転、2004年~2010年
- 6ヴィクトル・ヤヌコヴィッチと対立への道、2010-2013年
- 7革命から戦争へ、2013年~2015年
- 8おわりに ウクライナ、ロシア、西側 – 冷戦から冷戦へ
- 索引
- 地図
- 0.1ウクライナ、2019年現在ロシアに占領されている地域を示す
- 7.1キエフ中心部、2013年11月~2014年2月
- 7.2支配線(ドネツク州、ルハンスク州)、2019年7月
- 表
- 5.12006 国会議員選挙結果
- 5.22007 議会選挙結果
- 6.12012 国会議員選挙結果
- 7.12014 国会議員選挙結果
1. ウクライナをめぐる対立の源泉
しかし、我々の考えは、狼には餌を与え、羊は安全に保つべきだということだ。
レオ・トルストイ「戦争と平和」
2014年2月27日の夜、クリミアで武装した男たちが国会議事堂と内閣府の建物を制圧し、ロシアの旗を掲げた。翌朝早く、マークされていない制服を着たさらに多くの男たちが、セヴァストポリやシンフェロポリの空港を占拠した。ウクライナの海上警備隊が駐留するセヴァストポリ近郊のバラクラ港をロシア海軍の艦艇が封鎖し、ロシアのヘリコプターがロシアからクリミアへ移動した。18日後、急遽行われた国民投票の結果、プーチンはクリミアをロシア連邦に正式に編入する文書に署名した。
そして4月7日、親ロシア派がウクライナ東部のドネツク、ハルキフ、ルハンスクの政府庁舎を占拠し、地域の独立を問う住民投票を呼びかけた。ウクライナ軍は翌日ハリコフを奪還したが、他の2地域の奪還を目指した結果、ウクライナとロシアの戦争は2015年2月まで続き、その後一部で沈静化した。2019年までに1万人以上が犠牲となった。
1991年に「文明的離婚」として始まった紛争は、冷戦後のヨーロッパで最も危険な危機の一つとなり、その後危機は慢性化した。ウクライナとロシアは多くの歴史を共有しており、1991年のウクライナの独立は流血を伴わずに行われた。また、冷戦時代のような東西の緊張関係もなくなっていた。しかし、2014年初頭には、ウクライナをめぐる意見の相違がロシアとウクライナの武力衝突に発展しただけでなく、ロシアと西側諸国を新たな冷戦と見なすようになったのである。
なぜこのような事態になったのか、そしてそれはなぜなのか。深いつながりのあるウクライナとロシアは、なぜ戦争に至ったのか。そしてその関係は、西側諸国のロシアとの対立をどのように形成するようになったのだろうか。これらの問いにどう答えるかによって、ウクライナの和平、ヨーロッパの安全保障、ロシアとその周辺諸国、欧米との関係の再構築など、これから起こるであろう選択に各方面がどう臨むかが大きく左右される。この紛争をどう理解するかは非常に重要な問題である。しかし、この紛争をロシアのレバニズムに起因すると考える学派、プーチンの独裁的支配を強化するためと考える学派、西側の拡張主義とウクライナの民族主義に起因すると考える学派など、有力な理解は互いに大きく対立している。前2者は、プーチンのロシアと対峙する、あるいは少なくとも封じ込めるという西側の戦略を指摘するものである。3つ目は、ウクライナを支配したいというロシアの欲求を受け入れることで、ロシアの安全保障上の必要性を満たすというものである。
本書では、紛争の根は一般に理解されているよりも深いため、単純な政策変更には抵抗があり、どちらの戦略もうまくいきそうにないことを主張する。2014年に起きた激震は、短期的な引き金だけでなく、深い「地殻変動」の結果であった。ウクライナとロシアの対立は、深い規範的な不一致と利害の対立に基づいており、したがって、簡単に責任を負わせることができる指導者のミスには依存しない。このような不一致は、冷戦後の相互信頼が最も高まった1990年代でさえも関係を悪化させた。
したがって、プーチンがロシアの舞台から去るのを待つだけでは、またEUや米国がより融和的な政策をとるのを待つだけでは、和解は実現しない。平和と安全への回帰には、欧州の安全保障の新しいアーキテクチャーに合意することが必要である。冷戦が終結し、ロシアが民主化した時でさえ、そのようなアーキテクチャーの交渉は不可能だった。独裁的なロシア、深い東西対立、そしてウクライナでの紛争が続いている今、それを見つけるのはさらに難しくなるだろう。
本書の目的は二つに集約される。第一は、この紛争がどのように、そしてなぜ起こったのかを説明することだ。もう一つは、冷戦終結から2015年のミンスク2協定調印までのウクライナ、ロシア、欧州、米国の関係を説明することだ。このようなウクライナ・ロシア関係の概観は存在しないため、年表はそれ自体が目的であり、また、2014年に爆発した問題は冷戦後の初期に浮上し、時間の経過とともに顕著になったというのが本書の主要な主張の一つであるため、紛争を理解する上で不可欠なものである。
冷戦後のビジョンと利害の対立
議論を最も単純なバージョンに煮詰めると 冷戦の終結は、東欧の民主化と、ロシアが「大国」としての地位と近隣諸国への支配を維持しようとすることという、必然的に緊張関係にある2つの勢力の動きを引き起こした。ウクライナは、民主化と独立がロシアの国益に最も挑戦する場であった。この紛争が暴力に発展することは必然ではなかったが、自然解決する可能性もなかった1。
ロシアは大国として、また地域の覇権国家として存続することを決意していたが、ウクライナは、その民族主義者だけでなく、独立にこだわっていたのである。ロシアが大国、地域ヘゲモニーであり続けようとする一方で、ウクライナは、その民族主義者だけでなく、独立に固執していた。ロシアがウクライナを支配することを大国の定義とする限り、ロシアの国家安全保障はウクライナの民主主義や独立と相容れないものであった。それは1991年当時もそうであったし、その後も基本的に変わっていない。
国際政治における伝統的な問題と冷戦後の新しい問題である2つの大きな力学が、ロシア・ウクライナ紛争を欧州の幅広い問題と結びつけ、両者への対処を難しくしているのである。第一に、安全保障のジレンマは、国際関係における永遠の問題であり、一方が自国の安全を守るために必要だと考える措置が、他方からは脅威に映り、行動と反動のサイクルを引き起こすことを意味するものであった。モルドバやグルジアでのロシアの「平和維持」はその一例であった。北大西洋条約機構(NATO)の東方拡大もその一つである。
第二に、民主主義の普及は安全保障のジレンマをもたらし、西側諸国はより安全になったと感じるが、ロシアが認識する国益は損なわれている。西側の指導者たちは、民主主義の重要性を信じており、また民主主義が安全保障を強化すると考えていたため、民主主義とそれを支える制度の拡大を推進したのである。ロシアは民主主義そのものに反対しているようには見えなかったが、新しい民主主義国がNATOやEUに加盟し、ヨーロッパに「再加盟」しようとすることに脅威を感じていた。このプロセスが進めば進むほど、ロシアは憤りを感じるようになり、ロシアの利益認識、国家アイデンティティ、そしてプーチン政権にとって、ウクライナは他のどの国家よりも重要であった。Fyodor Lukyanovは、「彼ら(ロシア人)の考えでは、ロシアの従属的な立場は、ロシアを抑え込み、本来の地位を取り戻すのを阻止しようとする米国の終わりのないキャンペーンの非合法な結果である」2 と書いている。
このような民主主義と地政学の融合は新しいものであったが、それは見慣れたものであった。ロシアが自由民主主義に背を向け、ヨーロッパがそれを受け入れた以上、民主的なヨーロッパと非民主的なヨーロッパの間に何らかの境界線が存在することは必然的なことであった。それはロシアとウクライナの国境なのか、ウクライナとポーランドの国境なのか、はたまた別の場所なのか。中立地帯は、ヨーロッパの民主的な地域と非民主的な地域の間の「緩衝材」となり得るだろうか。しかし、誰もその区域に入りたがらないし、その考え方はヨーロッパの規範と衝突する。ヨーロッパの新たな分断は、ロシアが民主主義を強化し、大国主義を放棄した場合にのみ回避できる。このうち、前者は失敗し、後者は拒否された。歴史上しばしばそうであったように、紛争が自国の領土で繰り広げられたのはウクライナの不運であった。
戦争の原因を探る
紛争が勃発して以来、この紛争に関する多くの文献が生まれたが、それらには3つの特徴がある。第一に、その多くが責任の所在を明らかにすることに重点を置いている。第二に、2013年以降の出来事に焦点を当て、それ以前の出来事は選択的にしか検証していない。第三に、行動の源泉が国際的なものか国内的なものかのいずれかに集中する傾向があり、それらがどのように相互作用するかを調査していないことだ。
欧米で発表された研究の多くがロシアに責任があることを当然視する一方で、少数派はロシア政府に近い立場で、欧米とウクライナがロシアを行動せざるを得ない状況に追いやったという見解を示している。3 責任追及には抵抗があるが、一方を告発することに焦点を当てた研究は、事実を選択的に組み立て、よくて一方的、悪く言えばミスリーディングになる傾向がある。優れた学者でさえ、責任について単純化した表現に頼っている。ジョン・ミアシャイマーは「ウクライナ危機は欧米のせいだ」と言い、アンドリュー・ウィルソンは「ロシア人が猿になった」と書いている4。
責任の所在を明らかにすることは、指導者にかなりの選択の自由があったということになり、彼らが直面した制約を最小化することになる。責任の所在を明らかにすることでよりバランスのとれた著作であっても、指導者が事象を形成する能力を強調し、政策選択に対する国際的・国内的政治的制約を過小評価しがちである。ある著者は西側諸国が行ったことを批判し、他の著者はそれ以上のことを行わなかったと批判する5。当時の議論を検証すると、指導者自身が状況をそのように捉えていないことが多いことが明らかである。政策決定者はしばしば厳しい制約を感じている。ここで展開される説明は、安全保障のジレンマ、民主化の影響、国内政治など、そうした制約を探ることに重点を置いている。
第二に、この紛争に関する研究の多くは、時間的に不完全であった。その多くは、極めて合理的に、2013年11月から2014年春にかけてウクライナで起こった異常な出来事に焦点を合わせてきた。ダニエル・トリスマンは、プーチンのクリミア侵攻の決断に焦点を当て、4つの学派を特定している。ウクライナのNATO加盟の可能性に対応した「守りのプーチン」、ソ連再創造のための幅広いプロジェクトの一環としてクリミアを奪取した「帝国主義のプーチン」、経済衰退に直面して国民の支持を得るためにクリミア併合を利用した「大衆主義のプーチン」、そして素晴らしい機会をとらえた「即興主義のプーチン」である6。
この紛争は、第一次世界大戦がフェルディナント大公の暗殺によってのみ引き起こされたのと同様に、ヤヌコビッチ政権の転覆によってのみ引き起こされたのではない。どちらも、東欧の現状が不可逆的に変化してしまうのではないかという相互の深い懸念が、指導者たちに通常よりもリスクを受容させたのである(2014年は1914年とは異なり、他のヨーロッパ諸国が戦争に急いで参加しなかったことが決定的な違いである)。
この紛争を全体的に理解するには、侵略の長期的な前兆が極めて重要であるため、本書では1991年以降のウクライナ・ロシア関係の変遷を年代順に紹介し、暴力は決して不可避ではなかったものの、ウクライナの地位をめぐる対立がソ連崩壊前に生じ、決して後退することがなかったことを示す。同様に、共産主義の崩壊は冷戦を終結させたが、冷戦後のヨーロッパにおける西側に対するロシアの役割について共通の理解を生み出すことはなかった。こうした意見の相違は時間の経過とともに解消されると考えるのが妥当であろうが、本書で明らかにされたいくつかの力がそれを困難にしている。
第三に、ウクライナとロシアの内政、互いの関係、そして西側との関係に同時に焦点を当てることが困難であるため、関係する関係の複雑さが軽視されてきたことだ。しかし、2004年のオレンジ革命の時点で、ウクライナの国内における多元主義か権威主義かの戦いは、ウクライナのロシアからの自治権拡大への戦いとも、ロシアの西側との対立の勃発とも密接に関連していたからである。この紛争は、単にウクライナの国内紛争が国際化したものでも、ウクライナをめぐって争われた大国間の紛争でもない。
国際紛争の源流を探る
既存の著作の中には、国際紛争に関する膨大な文献を活用しているものはほとんどない。そのような文献を利用することで、この問題を「どこに源を求めるか」という観点から捉え直すことができる7。一つの研究グループは、その説明をロシア政府の内部、つまりプーチン政権そのものの性質に求めている。よくある議論は、プーチンが独裁体制を強化する必要性が戦争への決断の原動力となったというものである。この見方では、プーチンは大きな主体性を持っていることになる8。
もう一つの考え方は、ロシアが内的要因ではなく外的要因に反応したとするものである。その一つは、ロシアが拡張を求めるが、その理由は国内ではなく国際的なものであるとするものである。もう一つは、ロシアは欧米の拡張に反発しているとするものである。これらのアプローチは異なるアクターに責任を負わせるが、どちらも「防衛的リアリズム」と呼ばれる学派に属する。この学派は、攻撃的な「ならず者国家」が存在しない限り、国家は通常、無秩序な国際システムに内在する課題を管理できると仮定するものである。紛争は攻撃性に依存するという仮定から、これらの著者は、どちらか一方が地域の安全保障を損なうような行動をとっていると考える9。
「攻撃的リアリズム」の学派は、より悲観的であり、安全のみを追求する国家が意図せずして他国に安全保障上の脅威を与えるため、国際システムは攻撃的でない国家をも紛争に巻き込むと考えるものである。この見解では、紛争を説明するために侵略者を特定する必要はない。本書は、そのような視点を真摯に受け止める。ロシア、ウクライナ、そして西側諸国は、それぞれが選択した政策について批判される可能性があるが、冷戦後のヨーロッパには、解決できない力学が存在したと私は考える。最終的にロシアが悪いと結論づけたとしても、ロシアが安全保障上の課題を認識し、それが大きな懸念材料となっていたことを認識することが重要である。一部の著者のように、ロシアがウクライナを支配したいという欲求を「正当な利益」とみなす必要はなく、ロシアがウクライナの欧州連合への編入を損失とみなしていたことは認めることができる。同様に、NATOの拡大が誤りであったと考えるとしても、それは他に容易な解決策を持たない安全保障問題への対応であった。
国際的なソースと国内的なソースに注目することは、相互に排他的である必要はない。クリミアの併合は、プーチンにとって国際的な目標と国内的な目標の両方を達成した可能性が高く、また、そうであるがゆえに特に魅力的であった可能性がある。そこで本書では、国際的な要因と国内的な要因がどのように相互作用したかを分析することを目指した。ウクライナの民主化の状況が国際的な志向とどのように相互作用したのか、また、ウクライナ国家が常に脆弱であり、2014年にほぼ崩壊したのに対し、ロシア国家は1990年代の劇的な弱体化を経て、徐々に強化され、2014年までに強力な軍を再建し、ウクライナで非常に効果的な「ハイブリッド」戦争を展開できるようになったことが主要テーマである。
つまり、安全保障のジレンマが国際政治を規定するが、それに対する国家の対応は内的要因に左右されるという「新古典派リアリズム」と呼ばれる学派の考え方と一致している。このアプローチは、一般的な解釈とは異なり、様々な指導者が国際的要因と国内政治の両方から制約を受けていると考えており、多くの分析が彼らに帰しているよりも自由な行動がとれなかったことを認めるものである。言い換えれば、攻撃性や愚かさを非難することには、より慎重であるべきだということだ。この制約を理解するためには、ソ連崩壊後の欧州に存在した安全保障上のジレンマと、ウクライナを中心とする関係各国の国内政治の双方を検証する必要がある。特に、民主化が地政学と融合し、現状打破を繰り返し、西側の核心的価値観とロシアの安全保障観が対立した経緯を理解することが必要である。
アプローチ 歴史的・分析的アプローチ
本書は、歴史学的アプローチと社会科学的アプローチを組み合わせたものである。何が起こったのか、なぜ起こったのかという問いは密接に関連している。そのため、25年以上にわたる出来事をつなぐ力学とパターンを明らかにするために、年代順の物語と一連の社会科学的概念を組み合わせている。本書は、主にアーカイブの資料に基づいているわけではないので、厳密に言えば歴史書ではない。しかし、何が起こったかを説明し、当時の関係者が自分たちの行動をどのように説明したかを見ることに、かなりの注意が払われている。彼らの見解は、当時の発言と、後にウクライナで行われた証言やインタビューから得られている。
1989年以降のウクライナ・ロシアおよびロシア・西側関係の漸進的な変化をたどる物語的説明は、紛争の根底にある力学を明らかにし、この事例と世界政治におけるより広いパターンとのつながりを示す一連の分析的テーマによって構成されている。このアプローチでは、複雑なケースを単一の視点に当てはめることに固執するのではなく、複数の理論を駆使して問題に取り組む理論的折衷主義が必要とされる10。
分析テーマ
2014年に暴力化した紛争は、冷戦後の世界がどうあるべきかという深い意見の相違に根ざしていた。それらの相違は冷戦の終焉とともに生まれ、今日まで続いており、現状がどうであったか、あるいはどうあるべきかというそれぞれの側の認識を構成している。そして、自分たちの考える現状が脅かされそうになると、行為者はより高いリスクを取ることをいとわなかった。冷戦終結後、一見穏やかな環境にもかかわらず、こうした利害の対立が緩和されなかった理由として、3つの力学が挙げられる。第一に、国際政治によく見られる安全保障のジレンマという力学があり、各国が自国の安全を守るためにとった行動が、他国に問題をもたらし、行動する国の意図に対する恐怖を誘発した。第二に、民主主義の普及が問題を大きく複雑化した。新しい民主主義国が欧州の民主的な国際機関であるEUやNATOに加盟しようとしたため、民主化は地政学的に影響を及ぼし、西側は自然で善良なものと見なし、ロシアは脅威と見なしたのである。2004年のウクライナのオレンジ革命で、民主化と地政学の融合はほぼ完了した。さらに、この地域における民主化の進展と後退は、現状が繰り返し破壊され、新たな恐怖と紛争を引き起こすことを意味した。第三に、各国の民主化の程度にかかわらず、国内政治が幾度となく協力と譲歩を阻んだ。米国でもロシアでもウクライナでも、国内政治的には強硬路線より融和路線の方が失うものが多く、得るものが少ないことがほとんどであった。さらに、2000年以降、ロシアが強固な国家を再建したのに対し、ウクライナは弱体で分裂したままだったため、ウクライナが対応に苦慮する中、ロシアはクリミアやウクライナ東部での作戦を成功させることができたのである。
要するに、冷戦の終結はいくつかの問題を解決したが、ロシアとウクライナの相互関係や欧州一般に対する地位など、さらにいくつかの問題を生み出したのである。安全保障のジレンマといった伝統的な安全保障上の課題が残るとともに、民主化と地政学の融合という新たな課題も生まれた。奇妙なことに、冷戦の終結は、米国、ウクライナ、ロシアの有権者やエリートたちに融和的な政策を普及させることはなかった。つまり、利害の対立が強化され、強力で熟練したリーダーシップがあれば対立を抑えることができたかもしれないが、指導者は繰り返し対抗的な国内圧力に直面することになった。
このような力学は、ロシアと欧米の関係やウクライナの役割を説明する際にほとんど無視されてきたが、もしこれを真剣に受け止めるならば、ロシアの目標がウクライナや欧米の目標と衝突したことについて、誰かのせいにしようと難しく考える必要はないだろう。役者は望むと望まざるとにかかわらず、互いのつま先を踏むことを余儀なくされた。戦争が避けられないわけではないが、ある程度の摩擦は避けられず、その結果生じる利害の対立や感情をコントロールするために、並外れたリーダーシップが必要とされたのである。
競合する目標、相容れない現状認識
1989年から1991年にかけて冷戦が終結し、ロシア、ヨーロッパ、アメリカの指導者たちは、緊張が劇的に緩和され、利害や価値観の調和がますます進んでいることを実感した。しかし、ロシアとウクライナの関係は、主権的な対等性に基づくものか、それとも伝統的なロシアの覇権に基づくものか、その予想は大きく分かれた。同様に、西側諸国は冷戦の終結によってロシアが「普通の」ヨーロッパの国になると考えていたが、ロシアは影響圏や安全保障上の拒否権といった特権を持つ大国としての伝統的な役割を維持すると強く信じていた。
現状とは何か、したがってどの変化が「正当」なのか「非合法」なのか、良性なのか有害なのか、そしてどれが他者の悪意や攻撃的意図の表れなのか、行為者は全く異なる理解をしていた。ほとんどのロシア人は共産主義の終焉と冷戦の終結を歓迎したが、ウクライナの喪失は受け入れなかった。1990年代には、ロシアを代表するリベラル派のボリス・ネムツォフでさえ、ロシア企業にセヴァストポリの資産を買わせることで奪還することを提唱している。「ネムツォフの考えでは、クリミアの支配を強めることは、ロシアにとって新たな利益ではなく、回復である。2014年には、同じくリベラルの代表格と目されるアレクセイ・ナヴァルニーが、「ロシア人とウクライナ人の間に全く違いはない」と発言している12。
ロシアがウクライナの喪失に納得できないのは当然である。多くのロシア人にとって、ウクライナはロシアの一部であり、それなくしてロシアは不完全な存在である。この信念は、ウクライナの大部分が数百年にわたってロシア帝国とソビエト連邦の一部であったこと、今日のロシアの起源を中世のキエフに求めるロシアの建国神話、そしてゴーゴリ、トロツキー、ブルガーコフ、ブレジネフなど、ロシア・ソ連の文化や政治においてウクライナ出身者が果たした重要な役割に根ざしたものである。地理学者のジェラルド・トールは「厚い地政学」、エリザベス・ウッドは「想像の地理学」という概念を用いて、ロシアの地政学的状況に対する認識がいかに「近海」でのロシアの政策を形成したかを示している15。
ダニエル・カーネマンがノーベル賞を受賞した「現状維持バイアス」(損失回避)は、心理学や行動経済学で広く研究されている現象である。Kahneman と Amos Tversky が簡潔に表現したように、「損失は利益よりも大きい」16 。行為者は、認識された損失を避けるために、不釣り合いなリスクを取ることを厭わない。国際関係に当てはめると、国家は現状を維持するため、あるいは現状が悪化していると認識した場合には現状を回復するために懸命に努力することになる。ヘンリー・キッシンジャー(Henry Kissinger)も行動経済学ではなく歴史に基づき、大国が現状を受け入れるかどうかが安定の維持に重要であると同様に主張した17。1991 年以降、ウクライナ、ロシア、西側諸国は新しい現状に対する理解が異なっていた。そのため、 それぞれが現状を擁護していると考え、現状を覆そうとする他者の努力を悪意の表れであると見なしたのである。
ウクライナと西側諸国はロシアが冷戦後の現状を覆そうとしていると見ていたが、ロシアは西側諸国がNATOの東方拡大やロシアが支持する政府に対する「有色人種革命」を推進することによって、現状を覆そうとしていると見ていたのである。2005 年に Andrei Zagorsky は「ロシアはもはや変化の台頭を阻止したり抵抗したりすることのできない現状維持の大国として行動している」と嘆いた18 。Kahneman と Tversky が強調したように、この何かを失ったという感覚は特に危険で ある。「自分の損失と和解していない人は、他の人なら受け入れられないような賭けを受け入れる可能性が 高い」。 「キッシンジャーが主張したように、現状が相互に合意されていない状況では、国家は互いを不誠実、不合理、既成の秩序を破壊するものと見なす20 。ウクライナをめぐる外交は、ますますそのような性格を強めている21。
安全保障のジレンマ
国際政治の根底にある力学は頑強で、各国が自国の安全保障を向上させるためにとる措置は、たとえそれが意図したものでなくとも、他国にとっては当然脅威と映る。その結果、自己強化のサイクルに陥ってしまった。ロシアがウクライナ領を主張する中、ウクライナは自国軍の早期増強にこだわり、核兵器も自国領に置くことを検討した。これはロシアだけでなく、米国からも脅威とみなされた。同様に、安全保障を求める中欧諸国は、ロシアが恐れるNATOへの加盟を目指した。ロシア自身の行動も、再び近隣諸国への脅威となりかねないという考えを強めていった。2000年の大統領選を前に、プーチンは有権者に宛てた手紙の中で、次のように述べている。「強いロシアを恐れるのは不合理だが、侮ることはできない。」ロシアの近隣諸国の多くは、最近の歴史的経緯から、強いロシアを恐れるべきであると感じており、ロシアを怒らせれば誰もが大きな犠牲を払うことになるという発言は、警戒を要する脅威として読まれたのであろう。
国際政治の研究者にとって、この悪循環は「安全保障のジレンマ」と呼ばれ、歴史上繰り返されてきた国際政治の問題であり、逃れることは難しい、あるいは不可能である23。冷戦の終結がこの問題を解決したわけではないとの認識もあった。ベルリンの壁崩壊後、John Mearsheimer は、米国が欧州から撤退すれば、安全保障上の不安からドイツは核兵器を保有するようになると予測した24 。この予測が、米国が撤退せず、NATO が解体しなかった理由の一つであるが、NATO 拡大がどこで止まるのか、「西洋が多かれ少なかれ永久にロシアを疎外するまで」にはどこまで行けるのかは不明である、と多くの人が心配している25。この観点からすれば、責められるべきは状況またはシステムであって、この力学に陥った個々のアクターではない。
安全保障のジレンマから逃れるためには、どちらか一方、あるいは両方が、冷戦後の現状として受け入れられていた理解を捨てる必要があった。西側とウクライナは、新しいヨーロッパでは民主主義が規範であり、民主的な制度が自由に発展するという考えを捨てなければならないし、ロシアはウクライナに対する要求をあきらめなければならない。その過程で、双方はより小さな譲歩をする機会があった。最終的な紛争の責任をロシア、ウクライナ、西側のいずれに求めるかは、これらのうちどちらに期待を修正するべきだったか、ひいては冷戦後の欧州のビジョンをどちらがより公正に描いたかによって大きく左右される。
民主主義とパワーポリティクス
冷戦の終結は、東欧におけるほぼ平和的な民主革命による地政学的な大転換であった。西側の指導者たちは、西側の人々が熱狂的に信じていた民主化が、安全保障上も重要な利益をもたらすことを学んだ。しかし、民主化は何度も現状を打破し、そのたびにロシアが恐れる地政学的な帰結をもたらした。当初、民主化した国々はNATOへの加盟を目指した。そして、セルビア、グルジア、ウクライナで親ロシア政権を覆す「色彩革命」が起きた。「さらに、ロシアが自由民主主義よりも強権国家の育成を重視するようになると、西側諸国との間に新たなイデオロギー的な溝が生まれた27。ロシアでは、民主主義は反ロシアの武器とみなされ、その最終的な標的はプーチン政権であった。ロシアが近隣諸国の民主化革命に反発すると、ロシアは積極的に干渉していると見なされたのだ。その結果、ロシアにとって欧米は「修正主義的な国」に見え、欧米にとってロシアは「修正主義的な国」に見えるようになった。
民主主義が安全保障を促進するという考え方は、「民主主義国家間の戦争は不可能であり、したがって民主主義の普及が戦争のできない地域を拡大させる」という「民主主義平和理論」の学術研究によって補強された。この理論は、1980年代以降、欧米の学者たちの間で非常に注目されていた。北大西洋共同体はカントらが描いた平和地帯のように見え、民主主義とその安全保障上の利点がポストコミュニスト諸国に迅速かつ問題なく普及することを望む声が多く聞かれたのである28。
外交政策としての民主化の政治的美徳の1つは、善を行うことと自国の利益を追求することとの間の伝統的な緊張関係を解消することだ。この緊張関係は冷戦時代の米国で特に強く感じられたものである。民主主義の平和は、共産主義に対抗する西側の独裁者を支援するのではなく、民主主義を推進することによって、西側は善を行い、同時に国際的な安全保障を高めることができるという希望を抱かせるものであった。
民主主義の推進は、リベラル派と同様に現実派にも魅力的であった。現実主義者にとって、ヨーロッパにおける民主化の地政学的なインパクトは、ロシア帝国の再興を阻止する一連の自由な国家の誕生であった。民主化と制度拡張の結合的な魅力は「地政学的多元主義」という言葉に集約され、ブレジンスキーは旧ソ連における西側の目標であるべきだと主張したのである。民主主義的平和が理論から実践に移ったのは、西側の影響力を拡大し、ロシアの再主張を牽制するための政策とうまく重なったからでもある29。
リベラル派は民主主義と国際機関の推進を目指し、現実派はロシアが中央ヨーロッパを再び支配することを防ごうとした30。クリントン、ウォーレン・クリストファー、ストローブ・タルボットは NATO 拡大を支持し、ブレジンスキー、ヘンリー・キッシンジャー、リチャード・ニクソンも NATO 拡大を支持していた。反対意見は、ロシアへの影響を懸念するジョージ・ケナンのような少数の批判者に限られていた(ケナンは、1949年のNATO設立当初にも反対していた)。
しかし、ロシアにとって、民主化の地政学的な意味は脅威であり、最大の脅威はウクライナであった。東欧の人々は、市場、民主主義、西ヨーロッパを選択することになる。もし、ロシアが彼らに加わらなければ、孤立してしまう。ロシアの民主主義が疑問視される程度に、そして疑問視されないことはなかったが、ロシアの近隣諸国は脅威と選択に直面することになった。彼らはほぼ間違いなく、独裁的なロシアではなく、民主的な西側諸国と手を結ぶだろう。それは、ロシアの安全保障の概念と「大国」としてのアイデンティティを脅かすものであった。さらに、地政学的多元主義の要は強力な独立国ウクライナであり、ほとんどのロシア人はこれに強く反対していた。西側諸国の指導者たちは、民主化の地政学的意味合いに対するロシアの反論を軽視した。
ロシアは、近隣諸国における地政学的多元主義という概念を明確に否定した。ロシアは、ウクライナを含むポストソビエト地域を支配することが自国の利益と一般善のために不可欠であると考えていた。この地域の一部の国(特にベラルーシとカザフスタン)は、ロシアのリーダーシップの必要性を受け入れ、それを歓迎さえしていた。他の国々(ウクライナ、グルジア、アゼルバイジャン)は、ロシアの優位性の主張に反対した。これらの国家が民主的であれば、ロシアの支配を拒否することになる。
米国と西ヨーロッパ諸国は、ヨーロッパに残る権威主義的な政権の打倒をますます奨励するようになった。2000年10月の「ブルドーザー革命」によるミロシェビッチの失脚は、民衆革命が独裁的指導者を追放し、難解な安全保障問題を解決することが可能であることを示した。スロバキアでは、ウラジーミル・メシアの独裁的な政権が続く限り、EU加盟の進展は遅くなることが明らかにされたのである。スロバキアのエリートはメシアを孤立させ、欧州統合という目標を維持するために彼を政権から追い出した31。
2011年の「アラブの春」の革命の最初の成功は、長年の独裁体制に民主化をもたらし、安全保障上の大きな問題を解消する伝染の力をさらに実証するように見えた(もちろん、より長期的には、「アラブの春」の効果はより低いものであったけれども)。ロシアはこのようなやり方を非合法で危険なものと見なした。セルビアの革命は、ロシアが支援していた政権を、より西側に友好的な政権に置き換えた。グルジアのバラ革命はもっと複雑だったが、サーカシビリ新政権は強い親米・反ロシア派だった。ウクライナはロシアにとってより重要であり、オレンジ革命はプーチンを追い出すモデルになり得ると多くの人が考えていたからである。西側諸国では、公然とロシアでのカラー革命を望む声もあった。
色彩革命の後、一般的な民主化推進と民主革命は、地政学的な競争と絡み合って、切り離すことができなくなった。西側諸国にとって、民主化推進は単なる理想の追求ではなく、混迷を深める世界における影響力争奪のための強力な武器となった。ロシアにとって、民主化の推進は、軍隊による侵略ではなく、抗議行動によって指導者を交代させることによって領土を獲得する、新しい形態の戦争であるように見えた。しかも、その武器はロシアのプーチン政権に向けられたものであるように見える。2014年初頭、抗議運動によってヴィクトル・ヤヌコヴィッチが政権から追われたのも、こうした背景があった。
国内の制約と国家の強さ
紛争を助長する国際的な要因も重要だが、火付け役となったのはウクライナの内政である。ヤヌコビッチ政権の行動がなければ、2014年に軍事衝突に至ったとは考えにくい状況である。2010年に公正に大統領に選出されたヴィクトル・ヤヌコヴィッチは、多くの国民とエリートが受け入れない方法で、同国の政治を根本的に組み替えようとした。このような努力と、ウクライナの民主主義を維持する窓が急速に閉じつつあるとの認識から、統合政策に対する抗議がヤヌコビッチ政権を追放するための努力に変わったのである。より一般的には、国際的な要因がロシア、ウクライナ、その他の主要国の内部勢力と相互作用し、協力関係を損ねたことが、この紛争に関する多くの分析で強調されずにいる。
ウクライナはその独立期を通じて、内部で3種類の均衡を保っていた。第一は、国内の地域間である。ウクライナの地域的多様性は指導者にとっての課題であったが、ポストソビエト地域のほとんどで起こったように、誰かが独裁的な権力を強化することをより困難なものにした。第二に、ロシアと西側の外交政策バランスである。ウクライナが西側とロシアの両方と信頼できる関係を構築していると主張できる限り、両政策の支持者は少なくとも最低限の満足感を得ることができた。第三に、最も重要なことは、ウクライナの寡頭制グループや「一族」の間に存在する多元主義であった。この多元主義がウクライナを民主化したわけではないが、完全に独裁化することを防いでいた33。そして、ウクライナで政治経済的な支配を確立しようとする者が現れると、オリガルヒはこの多元主義を擁護した。このことは、強力なオリガルヒが2004年のオレンジ革命と2013年から2014年にかけてのユーロマイダンの双方を支持した理由を説明している。
2010年の選挙で接戦を制したヤヌコビッチは、権力争いを永久に排除しようとした。憲法裁判所を掌握した彼は、オレンジ革命の危機を解決した大統領の権限を制限する重要な「協定」を無効とするよう、憲法裁判所に働きかけることができた。そして、他の非合法な手段で議会の多数を占めるに至った。これらはすべて独裁を意味する。しかし、より有害なのは、彼が国内の地域的・寡頭的なバランスを覆そうと努力したことだ。経済的なシェアを拡大することで、彼の生存に関わるオリガルヒの連合は縮小し、彼が去ることで利益を得る者の数は増加した。これはオレンジ革命を引き起こしたのと同じ動きであり、EUに対する抗議が政権打倒に向かうきっかけとなった。
ロシアの国内政治における2つの要素、すなわち民主主義の衰退と、ロシアがウクライナに対して何らかの支配権を保持すべきだという考え方の蔓延も、この物語を語る上で欠かせない要素である。ロシアの民主化が進んだことで、欧米諸国はロシアをパートナーとして頼りにすることができなくなった。さらに重要なことは、独裁的な姿勢を強めるロシア政府が、2004年、そして2014年にウクライナで起こったような民主的な抗議運動から、存亡の危機を感じていたことだ。
ウクライナは「本当に」ロシアの一部であるというロシア国内のコンセンサスは、ロシアの政治家にとって、ウクライナにクレームをつけることは常にメリットがあり、その独立を公然と受け入れることはリスクがあることを意味していた。1990年代には、左翼と民族主義者の「赤茶色連合」からの圧力により、ボリス・エリツィンは様々な立場において、そうでない場合よりも厳しい立場を取らざるを得なくなった。そのずっと後、もしプーチンがクリミア併合を命じたとしても、それが大衆的なものでなかったならば、それはあり得なかったと思われる。このことは、ロシアにおける民主主義の衰退が紛争の原因であると分析されてきたのと同様に、より民主的なロシアがウクライナに対してより穏やかな態度をとっていたとは限らないという、これまであまり理解されてこなかった点を提起している。
国内政治の重要性は、ロシアとウクライナにとどまらない。例えば、ポストソビエトの初期、米国と西側諸国はロシアの改革を支援するために、マーシャル・プランの新バージョンで行うか、より強固なもので行うか検討した。その際、「大規模な支援であれば、その後のロシア情勢を変えることができたはずだ」という、もっともらしいが確証のない前提で、わずかな支援を行ったことに対する批判が、今になって多く聞かれるようになった。なぜ、そのチャンスを逃したのか。それは、米国内で政治的に維持できなかったことが大きい。1991年から1992年にかけて米国は不況に見舞われ、米国の指導者たちは「平和の配当」を外交政策から国内支出に振り向けることを望んでいた。対外援助にとってさらに悪いことに、この年は大統領選挙と議会選挙の年である1992年であった。民主党が経済政策でブッシュ大統領を非難していたため、ブッシュ大統領はロシアへの大規模な援助を強く主張することができず、そのような提案は米国議会で行き詰まったことはほぼ間違いないだろう。1993年、ビル・クリントンがホワイトハウスに就任したとき、ロシアの改革はすでに窮地に立たされていたが、彼も同様にロシアへの援助に制約を感じていた。クリントンは米国を不況から救うための国内支出策に注力しており、それとロシアへの大規模な支援策の両方を議会で通すことはできないと言われたのである。
国内政治は、「なぜ、よりよい結果をもたらしたと思われる措置を、関係する政府がとらなかったのか」という、次々と出てくる疑問に答えるのに役立っている。米国が新たなマーシャル・プランに着手しなかったのは、不況と選挙の年だったからである。ロシアは、ウクライナはロシアの一部であると多くのロシア人が考えていたため、ウクライナの独立を認めなかった。ウクライナがロシアへの経済的依存度を下げなかったのは、それを是正するには不人気な改革が必要だったことと、その経済的依存度が腐敗した役人の多くの収入源になっていたためである。
ウクライナとロシアの国家の変遷の対比が特によくわかる。1991年のウクライナの独立は、モスクワのソビエト国家の弱体化と崩壊によって可能になった。このときから、ウクライナもロシアもポスト・ソビエトの新しい国家の建設に奮闘したが、少なくともロシアはソビエトの組織の多くを再利用することができた。1990年代を通じて、両国はその権威を確立し、徴税や法の執行といった基本的な機能を果たすために苦闘した34。両国ともオリガルヒと呼ばれる経済・政治の有力者によって深く浸透していた。しかし、2000年以降、両者の歩みは分かれた。ウクライナは弱く、腐敗し、オリガルヒに浸透した国家を持ち続け、それでも何とか多元的で、かなりの程度、民主的であり続けた。ロシアでは、ウラジーミル・プーチンが権力の「バーティカル」を構築し、報道機関を統制下に置き、オリガルヒの独立性を抑制し、そのすべてが民主主義を犠牲にしている。彼は国家内部の一貫性を高め、社会的アクターに対する国家の統制力を高めた。ロシアが運用可能な強力な軍隊の再建に投資したのに対し、ウクライナはソ連から受け継いだ巨大な軍隊を縮小したが、実行可能な戦闘力への改革に苦心した。ロシアが1990年代に弱体化し、2010年までに大幅に強化されたことはよく知られているが、その弱さと強さの多くは、国家内部の結束とパワー、ひいてはロシアの巨大なパワーリソースを国際的に効果的に発揮できるかできないかの機能であったことを認識することが重要であろう。ロシアの国内的な国家の強さと国際的な自己主張の相関は注目に値する。すなわち、1991年以降、近隣諸国に対する自己顕示欲はほぼ一定であったが、ロシア国内の自己顕示欲は変化し、2000年以降上昇した。
近接した原因
安全保障のジレンマ、民主化と地政学の融合、国内政治の制約によって悪化した、地域に対する相容れない目標と現状認識、これらの要因が紛争の広範な根源を構成していると考えられる。近接・偶発的な要因も強調する必要がある。なぜなら、こうした根本的な緊張要因にもかかわらず、激しい紛争は決して避けられないものではなかったからである。2013年から2014年にかけて、予測不可能で容易に違う方向に進んだ出来事がなければ、ロシアがクリミアを占領し、ドンバスに介入することはなかったかもしれない。
偶発的な出来事をいくつか挙げると、次のようになる。ヴィクトル・ヤヌコヴィッチがEU連合協定に署名していれば、ユーロマイダン抗議運動は起こらなかっただろう(それでもロシアはそのような挫折に反応したかもしれないが)。マイダンで最初に現れた少数の抗議者たちが、殴られたり逮捕されたりするのではなく、無視されていたならば、抗議はおそらく拡大しなかっただろう。ヤヌコビッチ政権が1月16日に一連の抑圧的な「独裁」法を可決していなければ、焦点はヤヌコビッチを政権から追い出すことではなく、連合協定や憲法改正に置かれたままだったかもしれない。もし危機を解決するための合意が、大規模な暴力の後ではなく、その前に成立していたならば、それはおそらく定着しただろう。ロシア、米国、欧州が、デモ隊に拒否された後もその合意への支持を維持していたならば、それでもなお、合意は維持されたかもしれない。ドネツクとルハンスクに暫定政府に忠実な治安部隊がハリコフのように多く存在していれば、初期の分離主義過激派は定着する前に建物から退去させられたかもしれない。そしてもちろん、ロシアの指導者がクリミアの占領やウクライナ東部への介入を選択しなければ、戦争は避けられただろう。要するに、根底にある対立の原因が顕著になっていたにもかかわらず、戦争が始まる時点まで必然性がなかったということだ。
本書の概要
第2章が示すように、冷戦の終結はロシア、ウクライナ、欧米に2つの問題を残した。第一に、ロシアがウクライナの独立を受け入れなかったこと。第二に、1945年から1991年まで続いたヨーロッパの分断に代わる、ヨーロッパの安全保障アーキテクチャの合意がなかったことだ。当初、この2つの問題は、ロシアが自らを「大国」であり、今後もそうであり続けるという一般的な主張においてのみ、ほぼ完全に分離していた。
1991年8月のソビエト連邦崩壊の瞬間から、ロシアは軍事・経済政策を統括する何らかの「センター」を維持・再構築しようとした。ウクライナはこれに反発し、1991年から1994年にかけて、独立国家共同体(CIS)の役割、黒海艦隊とそのセヴァストポリ基地の地位、ウクライナ領内の核兵器の処分をめぐって、ロシアとウクライナは小競り合いを演じた。米露は共同でウクライナに核兵器保有権の放棄を迫り、ウクライナは1994年1月、ようやくそれに応じた。一方、ウクライナ経済は、ソ連時代からの衰退、ソ連統一経済の崩壊、ウクライナ指導者の改革への抵抗などにより、自由奔放な状態であった。
米露関係はこの時期が最も良好であったが、それでもすぐに問題が浮上した。モスクワでは保守派が再結集し、経済改革や西側との連携に抵抗するようになった。ブッシュ、クリントン両政権はエリツィン氏を支持しようとしたが、1991年の出来事を災厄と見なす保守派の影響力が強まるのを警戒していた。1993年のロシア議会の暴力的な解散とその後の議会選挙での保守新党の勝利は、再腰をかけるロシアの脅威を増大させた。
第3章では、1994年から1999年にかけてのウクライナ、ロシア、米国の重要な位置づけの変更が記録されている。1994 年にウクライナが日中韓三国同盟に調印し、核兵器を放棄したことで、米国の支援に対する主要な障害 が取り除かれると同時に、ロシアの保守派がロシアに対する西側の賭けをヘッジすることが賢明であるように 思われた。1994年半ばにウクライナ大統領に選出されたレオニード・クチマはウクライナ東部出身で、ロシアとの貿易を支持し、クリミアの分離主義的な感情を拡散させた。しかし、彼は前任者同様、ウクライナの主権を譲らないことを固く決意した。その代わり、NATOの「平和のためのパートナーシップ」に広く参加するよう、ウクライナを指導した。すでに、ウクライナは西側諸国の対ロシア戦略の一翼を担う存在として認識されるようになっていた。緊張は続いていたが、1997年にロシアがウクライナの国境を認め、ウクライナがクリミアのセヴァストポリの海軍基地をロシアに貸与し、黒海艦隊を分割する「友好条約」を締結したことがウクライナ・ロシア関係の頂点に達したといえる。不吉なことに、多くのロシアの政治家がこの条約に強く反対した。
クリントンやエリツィンの努力にもかかわらず、米露関係は険悪なままであった。米国は、1996年にエリツィンが再選を果たすために、美辞麗句を並べた支援と選挙アドバイザーを提供したが(IMFの新規融資も支援)、この支援とそれに関連した「株式融資」制度は、後にロシアの恨みの種になった。1998年には、アジア金融危機がロシアに波及して大混乱となり、西側の助言が自国経済を蝕んでいることをロシア人にさらに確信させることになった。
一方、ユーゴスラビア戦争は、ロシアの対西側関係を深く腐食させるものであった。クリントンは1994年にNATOの拡大を支持することを約束したが、ユーゴスラビア戦争は、冷戦の終結によってヨーロッパの安全保障問題がなくなるわけではないことを明らかにし、第二に、これらの問題の解決にロシアを当てにできるという考えを弱め、第三に、ロシアの拒否権のない、軍事指揮権を持つNATOだけが平和に対する最大の脅威に対処できることを示すことによって、それを実際に実現する一助となったのである。エリツィン氏は、1994年から1995年、そして1999年にもセルビアを支援しなければならないと考えていた。
第4章は、1999年という重要な年に始まる。3月、NATOは3つの新加盟国を正式に承認し、その2週間後、同盟はセルビアへの空爆を開始した。11月には、ウクライナのレオニード・クチマ大統領が再選され、2004年のオレンジ革命で終焉を迎えた独裁政治への流れが加速された。そして、その年の最後の日にエリツィン大統領が辞任し、プーチン氏が大統領代行として就任し、数ヵ月後には大統領に就任することになった。2001年9月の同時多発テロ以降、ロシアとアメリカはテロ対策で共通認識を持ったが、2003年にはブッシュ政権の決定的な外交政策であるイラクのサダム・フセイン追放戦争にロシアは反対した。
しかし、ジャーナリストのゲオルギー・ゴンガゼが殺害された事件や、クチマがこの事件やその他の悪事に関与しているとする記録は、クチマの反対運動に拍車をかけることになった。欧米はクチマに距離を置き、クチマはプーチンが政治的競争の排除に成功しているロシアとの関係を緊密にすることでそれに対抗した。
2004年のウクライナ大統領選挙で、ロシアはキエフにロシアとの統合を支持する指導者をようやく得ることができたと考えた。プーチンは、個人的に、またロシア政府やメディアの力を借りてヤヌコビッチ氏を支援した。しかし、抗議行動とその後の再選挙の合意によって、ロシアの勝利が一転して痛恨の敗北となった。このエピソードは、他のどのエピソードよりも、ウクライナ・ロシア関係をロシアの対西側関係の中に統合するものであった。
第5章では、オレンジ革命後のユシチェンコ大統領の時代について考察する。オレンジ革命は、国内改革と欧州との統合を約束したが、実現せず、汚職は絶え間なく続いた。オレンジ連合」は激しい対立に発展し、改革を阻害した。ヴィクトル・ユシチェンコはかつての盟友ユリヤ・ティモシェンコを激しく軽蔑し、2004年の選挙を盗もうとしたヴィクトル・ヤヌコヴィッチを2006年の首相に、2010年の大統領に推挙した。
2008年のNATOブカレスト首脳会議では、ウクライナはロシアと西側諸国の緊張の高まりの中心に位置づけられた。米国は、ウクライナにNATO加盟のための「加盟行動計画」を与えることを支持した。米国はウクライナのNATO加盟に向けた「行動計画」を支持したが、ロシアを敵に回したくないドイツとフランスはこの提案を阻止した。ウクライナがいつか同盟に加盟するという妥協案は、西側諸国では弱い慰めの言葉と見なされたが、その後、ロシアと一部のアナリストは、その後のグルジア侵攻と2014年のウクライナ侵攻を誘発した(そして一部では正当化した)ロシアの利益に対する脅威と見なすようになった。
ウクライナのNATO加盟が無期限に延期されたことで、EUとウクライナの関係は、初めて欧米のウクライナとの交流の主軸となった。東方パートナーシップ」プログラムにより、EUとウクライナは連合協定に向けた道を歩み始めた。これに対し、ロシアは独自の統合案を次々と提示した。
第6章では、2010年の大統領選からヤヌコビッチ大統領時代までを分析する。ヤヌコビッチは、実利的な政治家として生まれ変わったかに見えたが、当選後すぐに政治権力の強化、経済資産の蓄積、そしてロシアの支持を得るための劇的な行動を開始した。政治的な強化は、2015年に予定されていた自由な選挙を再び許可しないことを民主的な野党に確信させた。経済的な強化は、ウクライナの多くのオリガルヒを脅かした。振り返ってみると、ユーロマイダンの舞台は整っていたものの、新たな抗議活動が起こることを予想する人はほとんどいなかった。
同時に、ロシアと西側諸国との対立も激化した。2011年、NATOの介入によりリビアのカダフィが失脚し、新たな軋轢が生まれた。アラブの春」は、権威主義的な政権を崩壊させる民衆革命の力をさらに証明し、プーチンを怒らせ、心配させた。2008年のメドベージェフとの「キャスリング」は、プーチンがロシアのエリート政治を支配していることを示したが、2011年と2012年の抗議運動は、プーチンの潜在的な脆弱性を指摘するものだった。民主化と地政学はほぼ完全に融合していたのである。
2013年後半には、ウクライナ、ロシア、西側諸国は、妥協点を見出すことがますます困難な争いに巻き込まれた。ロシアとEUの相容れない統合案は、ロシアと西側のゼロサムゲームを生み出し、ウクライナ人の多くは望まない二者択一を迫られたのである。多くのウクライナ人が支持していた、ロシアとEUの両方と経済的に密接な関係を持つことは、ますます不可能になっていた。また、どちらのブロックにも属さないということも不可能で、孤立すればウクライナの経済はさらに悪化してしまうからだ。2013年11月、ヤヌコビッチは土壇場で、ウクライナはEUとの連合協定に署名しないことを表明した。
第7章では、その決断の余波を検証する。ヤヌコビッチの逡巡は、彼の失脚や侵攻につながる必要はなかった。しかし、ヤヌコビッチ政権は、デモ隊を阻止することなく、デモ隊を激怒させるような措置を繰り返した。2014年2月、デモ隊の射殺をきっかけにヤヌコビッチの支持率は蒸発し、彼は国外に逃亡した。1週間もしないうちに「緑の小人」がクリミアの奪取を開始し、1カ月で併合が完了した。一方、ウクライナ東部の各都市では、政府庁舎の占拠が起こった。しかし、ドネツクやルハンスクでは、ロシア人の支援とウクライナ国家の不在が相まって、分離主義勢力が足場を固めることができた。
クリミア奪取とドンバスへの介入に対する欧州の反応は、エリート層の多くがウクライナよりもロシアを優先し、クリミアに対するロシアの主張にも同調したため、当初は穏やかなものであった。もう一つの予期せぬ出来事、マレーシア航空17便の撃墜事件は、意見を大きく変えた。罪のない人々が殺害され、プーチンが明らかに不誠実な対応をしたことで、ロシアへの支持は減少した。その結果、欧州各国政府は米国と同じ考えで制裁措置を講じることになった。プーチンの行動は、第二次世界大戦直前のヒトラーの行動と比較されることが多くなった。
2014年夏、ウクライナ軍がロシアが支援する反政府勢力をドネツク州で包囲すると脅したとき、ロシアは正規軍を投入して介入した。続く敗走により、ウクライナはロシアの条件による停戦協定を受け入れざるを得なくなった。最初のミンスク合意では、地域自治の拡大など、ウクライナが望まない措置が約束された。2015年2月のロシア支援軍によるドネツク空港の奪取を受け、第2次ミンスク合意では支配線の変更を認めた。それ以降、停戦違反は日常的に行われ、犠牲者は着実に増えている。
第8章では、説明の問題に立ち戻る。どうすれば事態が変わっていたかを問う議論である。戦争を説明し、責任を負わせるためには、もし特定の決断が違っていたら、あるいはある出来事が違っていたら、違った結果になっていただろうと仮定することになる。ここでは、そのような影響を与えたかもしれないいくつかの決定と、誰にもコントロールできなかったと思われるいくつかの出来事や力について評価しようとするものである。制約と責任に関する最も難しい問題は、プーチンのクリミア併合という決断にある。2014年3月に実行された計画は、事前に十分な準備がなされていたようだ。一部のアナリストが主張するように、プーチンはきつく制約されたのだろうか。他にどんな選択肢があったのだろうか。選択肢がなかったという指導者の主張は、しばしば責任を他に転嫁するための戦術になりうる。その他の不測の事態は、巨大な決定から小さなものまで様々である。最も大きなもののひとつは、NATOの拡張の影響である。この決定が本当に紛争を引き起こしたのだろうか。その程度はともかく、明らかに賢明でない決定だったのか、それとも他に迫り来る危険の回避に役立ったのか35 。
重要な結論の一つは、プーチンの退陣を待つという戦略は成功しそうにないということだ。ロシアの大国・地域覇権主義やウクライナに対する主張は、プーチンの台頭以前からあり、ロシアのエリートと民衆の間で広く共有されているものである。つまり、民主化によってロシアがこうした志向を捨てることはないだろうということだ。実際、1990年代には、エリツィンの個人的な力だけがこの課題を支えていた。より広く言えば、民主的平和論から派生した、民主的なロシアは必ず西側と融和に達するという信念は、ロシアの大国志向に真っ向からぶつかるものである。民主主義と地政学の融合は、ロシアが民主化する可能性を低下させ、民主化したロシアがドイツのように近隣諸国を安心させるために力を抑制することに自発的に同意する可能性をも低下させるのである。
まとめ
この説明では、2014年に始まった戦争は、冷戦後の環境における長期的な力と、2013年から2014年にかけてのウクライナ、ロシア、西側の指導者による短期的な決定の両方がもたらしたものであることを強調した。1989年から2014年にかけて、ロシアとウクライナの間に激しい衝突が起こる可能性は段階的に高まっており、2014年までに、ロシアが隣国を侵略することが最善の政策であると判断する可能性がどのように生じたかを理解するためには、この過程を追跡することが必要である。
ソ連崩壊後の環境は冷戦時代とは比較にならないほど穏やかであり、ウクライナの地位など残された対立は時間の経過とともに解消されると考えがちであった。しかし、様々なアクターの現状認識とそれによる安全保障上のニーズを調整することができなかったこと、西側の民主主義制度の普及とロシアの「利益圏」に対する考え方の衝突、融和的な政策をとることの国内コストという三つの大きな要因が重なり、ウクライナの地位は解決されないままとなったのである。逆説的だが、2013年から2014年にかけて、ウクライナの地位が西側かロシアに有利な形で決定的に解決される可能性があったからこそ、双方がリスクを受け入れやすくなったのである。
戦争は起こらなくてもよかったのだが、2014年までにウクライナとロシア、西側とロシアの両者の関係に競争と不信が深く浸透し、この二つの対立が密接に結びついたのである。そうした根本的な対立は、冷戦後の体制に内在するものであり、その理由を知るためには、1989年から1991年にかけて冷戦が終結した驚愕の出来事に立ち戻る必要がある。第2章では、そこから始める。
