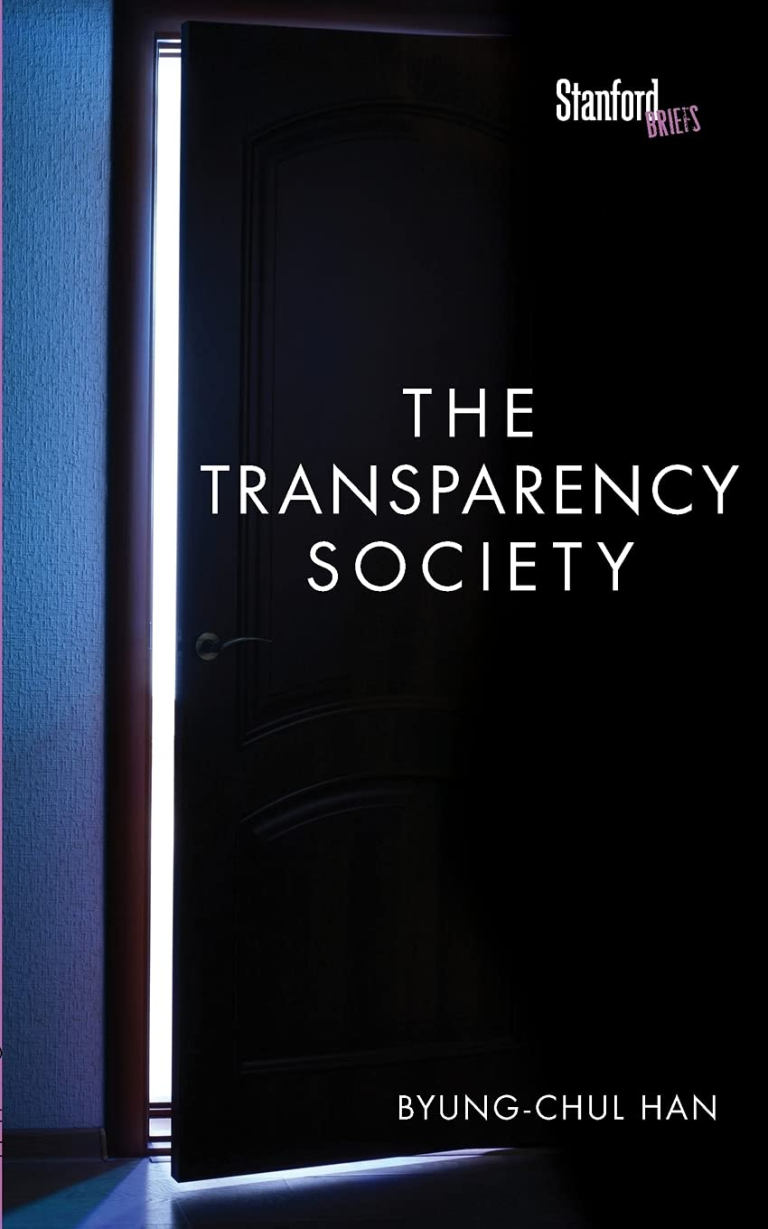スタンフォード大学出版局
目次
- 序文
- 陽性の社会
- 展示の社会
- エビデンス学会
- ポルノグラフィーの社会
- 加速度学会
- 親密さの社会
- 情報の社会
- 暴露の社会
- コントロールの社会
- ノート
前書き
今日、「透明性」という言葉が、政治や経済だけでなく、あらゆる場面で聞かれるようになってきた。より民主的に、より自由に、より効率的に……透明性が求められる。透明性は信頼を生むと、新しいドグマは断言している。しかし、このような透明性の追求は、「信頼」の意味が大きく損なわれた社会で起こっていることが忘れ去られている。
今日のように情報が簡単に手に入るようになると、社会システムは信頼からコントロールに切り替わる。透明性のある社会は、信頼の社会ではなく、コントロールの社会なのである。
すべてがすぐに公開されてしまうと、政治は必ず息切れし、短期的になり、単なるおしゃべりになってしまう。完全な透明性は、政治的コミュニケーションに時間性を与え、ゆっくりとした長期的な計画を立てることを不可能にする。未来に向けたビジョンを得ることはますます難しくなる。そして、成熟するのに時間がかかるものは、ますます注目されなくなる。
トータル・コミュニケーションとトータル・ネットワーキングが進むにつれて、アウトサイダーであること、異なる意見を持つことがこれまで以上に難しくなっているのである。トランスペアレントなコミュニケーションとは、平滑化、平準化の効果を持つコミュニケーションである。それは、同調と均一化をもたらす。他者性を排除する。強制的な適合は透明性から進行する。このように、透明性は支配的なシステムを安定させる。
透明性は、新自由主義的な配剤である。それは、すべてを情報化するために、内側に押し込む。今日の非物質的な生産関係の下では、より多くの情報とコミュニケーションは、より多くの生産性と加速度を意味する。これに対して、秘密性、異質性、他者性は、国境なきコミュニケーションの障害となるものである。それらは透明性の名のもとに解体されるべきものである。
透明性は人間を曇らせる。そこに暴力性がある。無制限の自由とコミュニケーションは、完全なコントロールと監視に切り替わる。ソーシャルメディアもまた、ますます、社会的なものを規律し搾取するデジタル・パノプティカに似てきている。
規律社会では、パノプティコンの住人は、より徹底した監視のために互いに隔離され、話すことも許されなかった。一方、デジタル・パノプティコンの住人は、自らの自由意志で活発なコミュニケーションを行い、自分をさらけ出す。このように、彼らはデジタル・パノプティコンに積極的に協力している。
デジタル管理社会は、自由を徹底的に利用する。それは、自発的な自己発光と自己露出によってのみ可能なのだ。それは自由を利用する。つまり、私的で親密な領域を手放すことへの恐怖が、恥ずかしげもなく自分を見せることの必要性に負けたとき、管理社会は完璧な状態に達する。
透明性とはイデオロギーである。すべてのイデオロギーがそうであるように、それは神秘化され、絶対化された肯定的な核を持っている。透明性の危険性は、このようなイデオロギー化にある。もし全体化されれば、それは恐怖をもたらす。
私は、他人が私について知らないことから生きている。
-ピーター・ハンディーク
ポジティブな社会
「透明性」ほど、現代の言説を支配する流行語はない。とりわけ、情報の自由との関連で強調されて呼び出される。フェティシズムとトータリゼーションの域に達した透明性への要求は、政治や経済の領域にとどまらないパラダイムシフトに遡る。今日、ネガティヴな社会は、ネガティヴなものを漸次解体し、ポジティヴなものに変えていく社会へと変貌しつつある。つまり、透明性のある社会は、まず肯定性のある社会として現れる。
事柄が透明であることは、それがすべての否定性を脱ぎ捨て、平滑化され、資本、コミュニケーション、情報の円滑な流れに統合されることに抵抗しないとき、証明される。行動は、計算可能で、舵取りができ、制御可能なプロセスに従属させられたとき、透明であることが証明される。時間は、容易に利用できる現在の瞬間の連続の中に滑り込むとき、透明となる。このようにして未来は肯定化され、最適な存在となるのである。透明な時間は、運命も出来事も知らない。イメージは、ドラマツルギー、振付、舞台装置、解釈学的な深さ、そして実際、あらゆる意味から解放されたとき、ポルノグラフィとなり、透明となる。ポルノグラフィーは、イメージと目の間の無媒介な接触である。物事は、その特異性を捨て、その価格のみによって表現されるとき、透明であることを証明する。何でも他のものと同一視することを可能にする貨幣は、あらゆる非干渉性、あらゆる特異性を廃絶する。透明性の社会は、同じものの地獄である。
透明性を汚職や情報の自由と結びつける人は、その範囲を認識できていない。透明性とは、すべての社会的なプロセスを支配し、深い変化をもたらすシステム的な強制力なのである。今日の社会システムは、そのすべてのプロセスを透明性の要求に服従させ、運用し、加速させようとしている。加速化の圧力は、否定的なものを解体することの副次的なものである。コミュニケーションは、似たものが似たものに反応し、似たものの連鎖反応が起こるときに、その最大速度に達する。分身や異物という否定性、つまり他者の抵抗は、「同」の円滑なコミュニケーションを乱し、遅らせる。透明性は、他者や異質なものを排除することで、システムを安定させ、高速化させる。このシステム上の強制が、透明性の社会を調整された社会にしている。ここに、その全体主義的な特徴がある。「Gleichschaltungの新しい言葉。透明性 」1
透明な言語は、形式的で、実際、純粋に機械的で、両義性をもたない操作的な言語である。ヴィルヘルム・フォン・フンボルトはすでに、人間の言語に宿る根本的な非透過性を指摘している。
そして、その差は、それがどんなに小さなものであっても、水の波紋のように、言語全体に波及していく。このように、すべての理解は同時に非理解でもあり、思考と感情の一致は同時に乖離でもあるのだ2。
情報のみからなる世界、コミュニケーションとは干渉のない循環を意味し、それは機械に等しいだろう。積極的な社会は、「事象を排除した宇宙における情報の透明性と猥雑性」3 に支配されている。透明性の強制は、人間そのものを平坦にし、システム内の機能的要素にする。そこに、透明性の暴力がある。
明らかに、人間の魂は、他者の視線なしにくつろぐことのできる領域を必要とする。それはある種の不浸透性を要求する。完全な照明がそれを焦がし、ある種の精神的な燃え尽き症候群を引き起こすだろう。透明なのは機械だけである。人生を根本的に構成する出来事と自由は、透明性を認めない。このように、フンボルトは言語についても言及している。
「もし、そのような不可解な現象の可能性を排除しようとするならば、我々は、その出現と変化に関する歴史的真理を侵害することになるであろう」4。
ポストプライバシーのイデオロギーも同様にナイーブであることがわかる。透明性の名の下に、私的領域を完全に放棄することを要求し、それによって、透明なコミュニケーションが実現するとされている。この考え方は、いくつかの誤りを前提にしている。ひとつは、人間の存在は、それ自身に対してさえも透明ではないということだ。フロイトによれば、無意識が肯定し、欲望するものを、自我は遠慮なく否定する。イドは自我に対してほとんど隠されたままである。したがって、人間の精神には亀裂が走り、自我が自分自身にさえ同意することを妨げている。この根本的な溝が、自己を透明化することを不可能にしている。また、人と人との間にも溝がある。このため、対人関係の透明化は不可能である。また、そうしようとしても意味がない。相手の透明性のなさこそが、関係を生かすのである。ゲオルク・ジンメルはこう書いている。
絶対的な知識、完全な心理的探求の単なる事実が、事前の酩酊がなくても我々を酔わせ、関係の活力を麻痺させる。. . . 人間関係の豊饒な深みは、明らかにされるすべてのものの背後にある、より多くの、最終的な何かを感じ取り、それを尊重するものである……。そして、最も親密で、すべてを消費するような関係にあっても、内なるプライバシーを尊重し、秘密を守る権利を可能にする感受性 [Zartheit] と自制心が、単に報われるのである5。
強迫的な透明性には、この同じ「感受性」–それは単に、決して完全に排除することのできない他者性への敬意を意味する–が欠けている。透明性へのパトスが現代社会を覆っている以上、距離のパトスを実践的に理解することが必要であろう。距離と恥は、加速する資本、情報、コミュニケーションの循環の中に組み込まれることを拒む。このように、透明性の名の下に、引きこもるための秘密の空間はすべて取り除かれる。光はそこに溢れ、そして枯渇する。それは、世界をより恥ずかしく、より裸にするだけである。
自律性とは、ある人が他の人を理解しない自由を前提とすることだ。リチャード・セネットは、「理解の平等、透明な平等ではなく、自律性とは、自分が理解していないものを相手の中に受け入れること、つまり不透明な平等である」と述べている6。さらに、透明な関係は、魅力と活力をまったく持たない、死んだ関係であると言えるだろう。人間の存在と共存には、肯定的で生産的な領域があり、透明性への強迫は、それを単に破壊しているに過ぎないのである。その意味で、ニーチェは「新しい啓蒙主義」で「 人間や動物がどんな無知の中で生きているかを認識するだけでは不十分で、無知への意志を持つことを学ばなければならない。このような無知がなければ、生命そのものが不可能であること、この条件下でのみ、生者は自らを守り、繁栄することができることを理解しなければならない」と書いている。7。
例えば直感は、入手可能なデータを超越して、独自のロジックに従う。例えば、直感は利用可能なデータを超越し、独自の論理に従う。今日、増大し、まさに横行する大量の情報は、あらゆる高次の判断を不能にするものである。より少ない知識と情報で、より多くのことを達成できることがよくある。省略や忘却という否定的なことが生産的であることも珍しくはない。透明性の高い社会は、情報や視界の隙間[Lücke]を許容することはできない。しかし、思考もひらめきも空白を必要とする。ちなみに、ドイツ語で幸福を意味する「Glück」はこの空白に由来しており、中世後期までは「Gelücke」と発音されていたそうである。ということは、隙間の否定性を認めなくなった社会は、幸福のない社会ということになる。視覚に隠されているものがない愛はポルノである。また、知識の隙間がなければ、思考は計算へと堕落する。
陽性の社会は弁証法も解釈学も捨て去った。弁証法は否定に基づくものである。したがって、ヘーゲルの「精神」は否定から目を背けることなく、それを自らの内に堪え忍ぶのである。否定は “心の生命 “を養う。ヘーゲルによれば、精神は「否定を直視し、それに寄り添うことによってのみ力を持つ」9 。これとは対照的に、肯定的なものだけを求めて「サーフィン」する者は、無頓着であることが証明される。霊が遅いのは、否定的なものに寄り添い、それを通して働くからである。透明なシステムは、自分自身を加速させるために、すべてのネガティブな要素を排除する。ネガティヴに寄り添うことは、ポジティヴに疾走し、奔放になることにつながる。
また、ポジティブな社会は、ネガティブな感情を許容しない。その結果、人は苦しみや痛みを処理し、それを形にする能力を失ってしまう。ニーチェは、人間の魂の深さ、壮大さ、強さは、まさに否定的なものと過ごす時間に負うところが大きいと言っている。人間の精神もまた、苦痛から生まれる。「不幸のなかにある魂の緊張は、その強さ、……苦痛に耐え、忍耐し、解釈し、利用する際の創意と勇気、そして深さ、秘密、マスク、精神、ずる賢さ、偉大さを培うが、それは苦痛によって、大きな苦痛という訓練によって与えられたものではないか」10 陽性の社会は、現在まったく新しい方法で人間の精神を組織化する過程にある。肯定化の過程では、愛さえも、複雑さも結果も伴わない快感や興奮状態の配列に平板化される。アラン・バディウの『恋愛礼賛』には、出会い系サービス「ミーティック」のスローガンである「恋に落ちることなく恋に落ちろ!」が引用されている。あるいは、「恋するために苦しむ必要はない!」11 愛は家畜化され、消費と快適さのための公式として肯定化される。わずかな傷さえも避けなければならない。苦悩と情熱は否定的なものである。一方では、それらは否定性のない享受に道を譲りつつある。その一方で、疲労、倦怠、憂鬱などの精神的な障害がそれに取って代わり、これらはすべて陽性の過剰に帰着する。
強い意味での理論もまた、否定的な現象である。何が属し、何が属さないかを決定するのである。高度に選択的な語りの様式として、それは区別の線を引く。このような否定性に基づいて、理論は暴力的である。それは「物事が……触れるのを防ぐために」、「混同されたものを区別し直すために」生み出される12 。この点で、理論は、入門者と未入門者を分ける儀式的なものとの境界をなす。今日、膨大な量のポジティブなデータと情報によって、理論が不要になった、つまり、データを比較することがモデルの使用に取って代わったと考えるのは間違いである。理論は否定的なものであり、肯定的なデータや情報より前に位置するものである。データに基づくポジティブ・サイエンスは、理論が終焉を迎えようとしていることの原因ではなく、その結果なのである。理論をポジティブ・サイエンスに置き換えることは不可能である。後者には、そもそも何があるのか、あるいは何がなければならないのかを決定する、決定の否定性が欠けているのである。否定性としての理論は、現実そのものをこれまでとは根本的に異なるものに見せ、現実を別の光で照らし出す。
政治は戦略的行動である。このため、政治は秘密の領域で行われる。完全な透明性はそれを不自由にする。カール・シュミットは、「開放性の仮定」は、「アルカナはあらゆる種類の政治に属するという考え方の中に、その具体的な相手を見つける」と書いている。「政治技術的な秘密は…実際には、私有財産と競争に依存する経済生活にとってビジネスや経済の秘密と同じくらい絶対主義に必要である」13。しかし、そのような場合、政治的行動は単なる演出に過ぎない。シュミットの表現を借りれば、「パパゲーノスの観客」は、秘儀を消滅させる。
18世紀は、自信と貴族の秘密保持の概念に多くを賭けた。そのような勇気を失った社会では、「アルカナ」も、ヒエラルキーも、秘密外交も、それどころか、政治も存在し得ないのである。あらゆる偉大な政治には、”アルカナム “がつきものである。すべては舞台の上(パパゲノスの謁見の前)で行われるのだ14。
つまり、秘密主義の終焉は、政治の終焉にほかならない。したがって、シュミットは政治にさらなる「秘密への勇気」15 を要求する。
透明性の党として、海賊党はポストポリティカルへの動きを続けている。これは脱政治化に等しい。海賊党は反党であり、色のない党である。透明性は無色である。信念はイデオロギーとしてではなく、イデオロギーのない意見としてのみ入り込むことができる。意見というのは、どうでもいいことで、イデオロギーほど包括的でもなければ、浸透的でもない。説得力のある否定性がない。したがって、今日のオピニオン社会は、すでにあるものをそのままにしておく。「流動的な民主主義」は、状況に応じて色を変え、柔軟性を発揮する。海賊党は、無色のオピニオン党である。ここでは、政治は、社会経済関係の枠組みを変更せず、それにしがみついたまま、社会的ニーズを管理することに屈服している。反党である海賊党は、政治的意思を明確にすることも、新しい社会的座標を生み出すこともできないことが証明されている。
強迫的な透明性は、既存のシステムを最も効果的に安定させる。透明性は本質的にポジティブである。それは、現状の政治経済システムを根本的に疑うような否定的な気持ちを抱かない。システムの外側にあるものには目をつぶる。すでにあるものだけを確認し、最適化する。だからこそ、ポジティヴな社会はポストポリティカルな社会と密接に関係している。脱政治化された空間だけが、完全に透明であることを証明する。参照するものがなければ、政治は住民投票の問題へと変質してしまう。
ポジティブな社会の総意は「いいね!」である。Facebookが一貫して「嫌い」ボタンの導入を拒んでいるのは、そのためだ。ポジティブな社会は、ネガティブなことを避ける。コミュニケーションの価値は、情報の量と交換の速さだけで測られる。コミュニケーションの質量は、その経済的価値をも増大させる。否定的な判断は、コミュニケーションを阻害する。「嫌い」よりも「好き」の方が、より早く次のコミュニケーションが生まれる。最も重要なことは、拒絶がもたらす否定性は、経済的に利用できないことだ。
透明性と真実は同一ではない。真実は、他のすべてを虚偽であると宣言することによって、自己を提示し、主張する限りにおいて、負の力である。さらなる情報、あるいは単なる情報の集積は、何の真実も生み出さない。方向性がない、つまりセンスがない。否定的なものがないからこそ、肯定的なものが増殖していく。ハイパーインフォメーションとハイパーコミュニケーションは、真実の欠如、つまり存在の欠如を証明する。情報を増やしても、コミュニケーションを増やしても、全体が明瞭でないという根本的な欠落を解消することはできない。むしろ、それを増大させる。
展示の社会
ヴァルター・ベンヤミンによれば、教化対象にとって「見られること」よりも「現存すること」が「より重要」である1。「教化価値」は存在に依存し、展示には依存しない。聖なるものを立ち入れない部屋に閉じ込め、目に触れないようにすることで、そのカルト的な価値は高まる。例えば、聖母像の中には、ほぼ一年中覆われているものがある。また、ある種の神像には神官しか近づくことができない。分離(秘密、secretus)、囲い込み、隔離によって実現される否定性は、カルト的価値を構成する。陽性の社会では、物は商品となり、存在するために展示されなければならない。カルト的価値は消え、展示的価値が優先される。裸の存在には、展示価値に関する限り、何の意味もない。それ自体に留まっているもの、つまり、あるがままのもの(bei sich verweilt)には、何の価値もないのだ。価値は、モノが見られる限りにおいてのみ発生する。すべてを可視性に委ねる展示の強制は、「遠景の外観」であるオーラを完全に消滅させる。資本主義の成就を告げる展示価値は、マルクス主義の使用価値と交換価値の対立から導き出すことはできない。使用価値でないのは、それが実用の領域から離れているからであり、交換価値でないのは、それがいかなる労働をも反映していないからである。それは、それが生み出す注目によってのみ存在する。
ベンヤミンは、写真の展示価値がカルト的な価値を抑圧していることを指摘する。一方で、カルト的価値は抵抗することなく後退するのではなく、むしろ「人間の表情」の中に「最後の避難場所を見つける」のだとも述べている。したがって、初期の写真において肖像画が中心的な位置を占めているのは偶然のことではない。
死者や不在の愛しい人を想起するカルトの中で、イメージのカルト的価値は最後の砦を見つけるのである。一瞬の表情に、オーラが宿る。最後の時に。これこそが、イメージの哀愁と比類なき美しさなのである。しかし、人間が写真から離れるとき、展示の価値が初めて文化的価値に優越するのである2。
写真から「人間の表情」が消え、それがカルト的な価値を持つようになって久しい。フェイスブックやフォトショップの時代には、「人間の表情」は展示価値しかない単なる「顔」と化している。顔は、「オーラを取り除いた」展示用の顔である3 。表面として、顔は、エマニュエル・レヴィナスが他者を介して超越が現れる特権的な場 所とみなした表情よりも透明であることがわかる。透明性は超越と対立する。顔は「同じもの」の内在性を宿している。
デジタル写真は、あらゆるネガティヴなものを一掃する。暗室も現像も必要ない。ネガが先行することはない。純粋にポジティブである。なること、老いること、死ぬことは、すべて消去された。
(写真は)一般的に紙のような運命(腐りやすい)を持っているだけでなく、たとえより永続的な支持体に取り付けられていたとしても、やはり死を免れないものなのだ。. . . 光や湿気にさらされ、色あせ、弱まり、消えていく4。
ロラン・バルトは、写真を、時間の否定性が構成的な役割を果たす生活様式と関連付けている。ロラン・バルトは、写真を、時間の否定性が構成的な役割を果たす生活様式と関連付けている。それでもなお、写真は技術的な前提条件、この場合、アナログ的な性質と結びついている。デジタル写真は、否定性をますます排除していく、まったく別の生き方の帰結である。それは透明な写真であり、生も死も、運命も出来事もない。運命は透明ではない。透明な写真には、意味的・時間的な密度[Verdichtung]がない。だからこそ、それは何も語らない。
バルトにとって、「this-is-how-it-was」という時間的実体こそが、写真の本質を表している。写真は、過去にあったことを証言する。だからこそ、喪に服すこと[Trauer]がその根本的な気分を構成している。バルトは日付を写真イメージの一部とみなしている。「それは……生、死、世代間のどうしようもない消滅を計算することを可能にするからだ」5 日付は死生観、移り変わりを刻み込んでいる。彼は、アンドレ・ケルテスの写真について、「1931年に撮影された小学生のアーネストは、まだ生きている可能性がある。しかし、どこで、どのように? なんという小説だろう!)6 今日の写真は、完全に展示価値によって満たされ、異なる時間性を示している。それは,否定性とそれゆえの運命を欠いた現在によって決定されるものであり,物語の緊張も,小説[ロマン]の意味での「劇的」なものも認めない.それが表現するものには、ロマンティックなものは何もない。
展示の社会では、あらゆる対象がそれ自身の広告の対象でもある。すべてはその展示価値によって測られる。展示の社会はポルノの社会である。すべてが外側に向けられ、剥ぎ取られ、露出され、脱がされ、見せ物にされている。展示の過剰は、すべてを商品に変えてしまう。「秘密を持たず」、「すぐに食い尽くされる運命にある」7 ものを、資本主義経済は強制的に展示させる。展示の演出だけが価値を生み出し、物事の固有性[Eigenwüchsigkeit der Dinge]はすべて放棄された。それらは暗闇の中で消えるのではなく、過剰な露出によって消えるのだ。「より一般的には、目に見えるものは無名と沈黙の中で終わりを迎えるのではなく、見えるものよりも見えるもの、つまり猥雑さの中に消えていく」8。
ポルノグラフィーは、エロスだけでなく、セックスも破壊する。ポルノグラフィーの展示は、性的な欲望から疎遠にさせる。それは欲望を生きることを不可能にする。セクシュアリティは、女性的な快楽のシミュレーションと、男性的なパフォーマンスとに分解される。展覧会で展示される快楽は、快楽ではない。強迫的な展示は、身体そのものの疎外を伴う。その中に身を置くことは不可能になる。それは、展示することであり、それによって搾取することだ。展示は搾取である。展示の要請は、住まいそのものを破壊する。世界が展示室と化したとき、住居は不可能となる。住居は勧誘[Werben]に屈し、それは注意の資本[Aufmerksamkeitskapital]を高めるのに役立つ。住まいとは本来、「平和であること、平和に導かれること、平和のうちにとどまること[zufrieden sein, zum Frieden gebracht, in ihm bleiben]」を意味する9。展示と実演という容赦ない強制が、この平和を脅かしているのだ。それは展示することができない。ハイデガーが定義するように、物もまた完全に消滅してしまう。それは展示することができない。なぜなら、それはカルト的な価値のみからなるものだからだ。
ハイパーヴィジビリティは猥雑であり、隠されたもの、アクセスできないもの、秘密であるものの否定性を欠いている。ハイパーコミュニケーションの滑らかな流れもまた猥雑である。ハイパーコミュニケーションには、他者性の否定性がない。すべてをコミュニケーションと可視性に委ねようとする強制は猥褻である。身体と魂のポルノ的な展示は猥褻である。
展示の価値は、何よりも美しい外見に依存する。このように、強迫的な展示は、美と健康を達成しようとする強迫観念を生み出す。オペレーション・シェンハイトは、展示価値を最大化することを目的としている。今日の(ロール)モデルは、内的な価値を伝えるのではなく、外的な尺度を伝え、人は暴力的な手段を使ってでも、それに対応しようとする。展示の要請は、可視的なものと外部的なものを絶対化することにつながる。目に見えないものは存在しない。それは展示の価値もなければ、注目もされないからだ。
展示の強制は、見えるものを搾取する。光り輝く表面は、それ自体が透明である。結局のところ、それ以上何も求められない。深い解釈的な構造を持っていない。顔は透明化した表情であり、展示価値を最大化しようとする。展示の強制は、最終的に我々から顔貌と視覚[Gesicht]を奪ってしまう。もはや、見たままであることは不可能なのだ。展示価値の絶対化は、可視性の専制として表現される。イメージの増大は本質的に問題ではなく,問題となるのは,絵にならなければならないという象徴的な強制力である.すべてが可視化されなければならないのだ。透明性の要請は、可視性に従わないものをすべて疑ってかかる。そこにその暴力性がある。
今日、視覚的なコミュニケーションは、感染、中止反応、あるいは反射によって起こる。そこには美的な反省がまったくない。その美化は究極的には麻酔的である。たとえば「好き」という言葉で表現される味覚の判断は、持続的な熟考を必要としない。展覧会的な価値に満ちたイメージには複雑さがない。それらは明確であり、つまりはポルノグラフィである。身体的、精神的な反省のきっかけとなるような壊れ方が全くない。複雑さはコミュニケーションを鈍らせる。麻酔薬のハイパーコミュニケーションは、それ自体を加速させるために複雑さを減少させる。それは感覚的なコミュニケーションよりはるかに速い。感覚は遅い。加速された情報とコミュニケーションの循環を阻害する。したがって、透明性は感覚の不在をともなう。大量の情報とコミュニケーションは、ホラーヴァキュイに由来する。
透明性の社会は、すべての距離を排除すべき否定的なものとしてとらえる。距離は、コミュニケーションと資本の流れを加速させる障害となる。その内なる論理にしたがって、透明性の社会はあらゆる形の距離を排除する。透明性とは結局のところ、「見るものに対する視線の完全な乱れ」、すなわち「売春」であることがわかる10 。距離がないために、知覚は触覚と接触によって進められる。触覚とは、「眼と像の表皮の一致」11 という物理性のない接触であり、ただ一息で済むものである。距離がないため、美的な思索や余韻は生まれない。触覚は、まなざしの美的距離の終点であり、まさにまなざしの終点なのだ。距離の欠如は近接ではない。どちらかといえば、それを破壊する。近接は空間に富んでいるが、距離の欠如は空間を消滅させる。ある種の距離が近接の中に刻み込まれている。したがってその寸法は広い。この意味でハイデガーは、「距離を支える純粋な近さ[reine die Ferne aushaltende Nähe]」を語っている12 が、「遠いものの近さの痛み」13 は、排除されるべき否定性としてカウントされる。透明性は、すべてを近からず遠からずの均一な脱遠隔性に再移動させる[ent-fernt]。
証拠の社会
透明性の社会は、快楽に敵対するものである。人間の欲望の経済の中では、快楽と透明性は両立しない。透明性は、リビドー経済にとって異質なものである。まさに、秘密、ベール、隠蔽の否定性が欲望を煽り、快楽をより強烈なものにする。だからこそ、誘惑者は仮面、幻想、外見と戯れるのだ。強迫的な透明性は、快楽と欲望[Lust]の遊び[Spiel-Räume]のための余地を消滅させる。証拠は推理を可能にするが、誘惑を可能にするものではない。誘惑者は,回り道,脱線,そして間接的に進む道を選ぶ.芸術は曖昧な記号を用いる.
誘惑はしばしば曖昧なコードを使用し,それによって西洋文化の典型的な誘惑者は道徳からのある種の自由の模範となる.なぜなら,両義性と曖昧さは本質的に話し手の意図に関して不確実性を維持する方法だからである.つまり、意味もなく何かを言う能力、一度に複数の意味を暗示する能力である。誘惑者があいまいな表現を使うのは、誠実さや対称性といった規範に責任を感じないからである。これとは対照的に、いわゆる「政治的に正しい」慣行は、契約の自由と平等を最大限に確保するために、透明性とあいまいさの欠如を要求し、その結果、誘惑の伝統的な修辞的・感情的な後光を中和している1。
曖昧さと両義性、謎と謎をもてあそぶことは、エロティックな緊張を高める。透明性や率直さはエロスの終わり、すなわちポルノグラフィーの終わりとなる。したがって、現代の透明な社会が、同時にポルノ社会であることは偶然ではない。また、透明性の名の下に相互の暴露を無制限に要求する「ポストプライバシー」の実践は、快楽と欲望に有害であることが証明されている。
ジンメルによれば、われわれは「単純に、生活の基礎として一定の割合の真実と誤りを必要とするだけでなく、生活の要素のパターンに同じだけの明確さとあいまいさを必要とするように構成されている」2。このことは、透明性がすべての「魅力」[Reiz]を奪い、「幻想がその可能性を取り込むことを禁止する。幻想は、長い目で見て、手に入れ楽しむことによって置き換えられない自己活動なので、どんな現実でもその損失を補うことができない」。ジンメルは続けて、「われわれに最も近い人物の一部でさえ、その魅力がわれわれにとって高揚したままであるためには、曖昧さと不透明さの形で提供されなければならない」3 と述べている。ファンタジーは快楽の経済にとって不可欠である。裸で提供される対象は、それを消してしまう。対象が引き出され、隠蔽されることによってのみ、快楽は沸き起こる。リアルタイムで楽しむのではなく、想像の前奏曲や後奏曲、時間の繰り延べが喜びと欲望を深める。想像や物語の迂回を許さない無媒介の楽しみは、ポルノである。さらに、メディア・イメージの超現実的な過集中と自明性は、ファンタジーを麻痺させ、窒息させる。カントによれば、想像力(Einbildungskraft)は遊びを基礎とするものである。想像力には遊びの余地があり、そこには明確な定義や描画はない。ある種の曖昧さ、不明瞭さを必要とする。理解[Verstand]が自己の透明性を特徴とするのに対し、それ自身は透明ではない。このため、理解もまた、遊びをしない。それは曖昧でない概念に働きかける。
ジョルジョ・アガンベンは『来るべき共同体』の中で、エルンスト・ブロッホがある晩ベンヤミンに語ったメシアの王国についての寓話を紹介している。
「あるラビ(本物の陰謀論者)が、平和の王国を築くには、すべてを破壊したり、まったく新しい世界を始めるだけでは不十分だと言ったことがある。このカップ、この潅木、この石をほんの少しずらすだけで十分であり、そうすることであるべてができる。しかし、この小さなずらしは非常に難しく、その尺度も見つけにくいので、世界に関して言えば、人間には不可能であり、メシアの到来が必要なのである」4。
平和の王国を実現するために、物事はほんの少しずらされる。アガンベンが指摘するように、最小限の変化は事物そのものではなく、その “周縁 “で起こる。不思議なことに、それはそれらを「より輝かせる」(clarior)のである。アガンベンの考え方をさらに推し進めると、微妙な振動が不鮮明さを生み出し、その境界から神秘的な輝きで物事を包み込む。聖なるものは透明ではない。聖なるものは透明ではなく、神秘的な定義の欠如によって定義される。来るべき平和の王国は、透明な社会と呼ばれることはないだろう。透明性は平和の状態ではない。
聖なるものだけでなく、欲望の空間も透明性を提供しない。宮廷恋愛における欲望の対象である女性[frouwe]は、欲望を厚くする「ブラックホール」を提供するのだ。ジャック・ラカンによれば、欲望は「奇妙なことに、プライヴェーションあるいはアクセス不能の扉から導入される」7。彼はこの問題を、イメージが歪んだ状態でしか現れないアナモルフォーゼの「解読不能な形態」になぞらえる8。ラカンによれば、宮廷の愛は「アナモルフィック」である9 。時間的な意味でも、その対象はアナモルフォーシスであり、その対象は「中断された身振りの終わりなき反復としてのみ」達成できる10。それは表象を拒むものである。「ダス・ディンの中に見出されるものは、真の秘密である」11。
透明性は、対称性の条件を表している。したがって、透明性の社会は、すべての非対称的な関係を排除しようとする。後者には、権力も含まれる。権力はそれ自体、極悪非道なものではない。多くの場合、権力は生産的であり、生成的であることが証明されている。権力は、社会の政治的形成のために、余裕と自由な遊びの空間を作り出す。権力はまた、喜びと欲望の生産において重要な役割を果たす。リビディナル・エコノミーはパワーのエコノミーの論理に則っている。人間はなぜ権力を行使しようとするのかという問いに対して、フーコーは快楽の経済を指して答えている。人々の関係が自由であればあるほど、他者の行動を決定したいという欲求は大きくなる。遊びがオープンであればあるほど、つまり、他者の行動を導く様式が多様であればあるほど、快楽は大きくなる。透明性と計算不可能性は、戦略ゲームにおいて重要な役割を果たす。パワーもまた戦略的な遊びである。だから、オープンスペースで展開される。
パワーは戦略的なゲームからなる。我々は、権力は悪ではないことをよく知っている。例えば、性的関係や恋愛関係を考えてみよう。ある種のオープンな戦略的ゲームにおいて、物事が逆転する可能性もある中で、他者に対して力を行使することは、悪ではない。それは愛や情熱、性的快楽の一部なのだ12。
「永遠」を求めるニーチェ的な欲望は、真夜中から湧いてくる。ニーチェは、透明性を信じている限り、われわれは神を廃絶していないと言うだろう。侵入的な視線、一般的な可視化に対して、ニーチェは外観、仮面、神秘、謎、策略、遊びを擁護している。
深遠なるものは仮面を好み、最も深遠なるものはイメージや譬えをも憎む。. . . 愛と贅沢な寛容の行為には、棒を持ち、目撃者を激しく打ちのめすより勧められないものがある。. . 仮面の裏には狡猾さだけでなく、狡猾さの中に多くの優しさがある。. . . 深遠な精神はすべて仮面を必要とし、さらに、すべての深遠な精神の周りには仮面が絶えず成長しているのである13。
深遠な精神は仮面の保護のもとに出現し、仮面は保護皮膚のようにその周囲に成長する。完全に他者である「新」は、「同一」から保護する仮面の後ろでのみ繁栄する。また、狡猾さは悪意とイコールではない。狡猾さは、定言命法に基づく行動よりも効率的であり、暴力的でもない。この意味で、ニーチェは「策略は力よりも優れている(List besser als Gewalt)」と書いている14 。周囲を観察し、手元に与えられた可能性を十分に活用する限り、よりしなやかで柔軟であることがわかる。暴力は、その厳格さゆえに自己顕示的な定言命法よりも多くのものを見ている。暴力は狡猾さよりも真理に近い。したがって、暴力はより多くの “証拠 “を生み出す。ここでニーチェは、より自由な生き方-完全な照明と管理の社会では不可能な生き方-を呼び起こす。それはまた、平等を主張する契約的思考や交換経済によってその進路が決定され得ないという意味でも自由である。
秘密と闇はしばしば魅力を放つ。アウグスティヌスによれば、神は欲望をかき立てるために、意図的に比喩を用い、聖典を曖昧にしたのである。
これらのものは、敬虔な探究者の感覚を働かせるために、あたかも比喩的な衣服で覆われており、裸[nuda]で露出[prompta]していることによって安っぽく見えないようにするためだ。我々が他の場所で学んだことについても同様で,そこでは公然かつ平易に語られていたのです[manifeste]。それらが隠れていたところから引き出されるとき,われわれがそれを発見することによって,何らかの形でそれらは新しくなり,したがってそれらは甘く[dulcescunt]味わうことになる。このように隠されていることは、学びたい人に対する悪意ではなく、むしろ、隠されていることによって、より強くそれらを望み、待ち望んでいたものを見つけることに、より大きな喜びを感じることができるように、さらに強調されるのである15.
図像の衣服は御言葉をエロティックにする。形象の衣服は御言葉をエロチックにする。御言葉を欲望の対象へと昇華させるのだ。形象的な装いは、御言葉を欲望の対象へと高める。隠蔽の否定性は解釈学をエロティクスに変える。発見と解読は、裸で寝そべるような快楽として起こる。それに対して、情報は裸で立っている。言葉の裸は、その魅力をすべて奪い去る。平坦にするのである。神秘の秘術は、透明性を優先して何としても排除しなければならないディアボリズムと等しいものではない。それは象徴主義を生み出し–実際、それは特異な文化的技法であり、(たとえそれが幻想であるとしても)深みを生み出すのである。
ポルノグラフィーの社会
透明性は、美しいものの媒体ではない。ベンヤミンによれば、美は、隠すものと隠されるものが表裏一体であることを必要とする。
美しいものはベールでもベールに包まれた中のものでもなく、むしろベールに包まれたものである。しかし、ベールを脱ぐと、それは限りなく目立たない(unscheinbar)ことが証明される。. . なぜなら、最後の例でヴェールが不可欠であるその対象は、それ以外の特徴を持ってはならないからである。美しいものだけが本質的であり、その外側には何もない-ヴェールをかけることもかけられることも-ので、美の存在の神聖な根拠は秘密にあるのである1。
美は、ヴェールやベールに必然的に縛られる限り、明らかにされることはない。ベールに包まれたものは、ベールの下でのみ自己同一性を保つ。ベールを脱ぐと、それは消滅する。したがって、裸の美などというものは存在しない。「そして、人間の裸体には、あらゆる美を超えた美-崇高なもの、あらゆる創造物を超えた作品-創造主のものが到達している」2 形や物[ゲビルド]だけが美しくありうる。それに対して、裸は、美の特徴である秘密が付着していないとき、形やイメージを持たずに崇高なものとなる。崇高なものは美しいものを凌駕する。しかし、生き物のような裸は、ポルノではない。それは創造主の仕事を指し示すから崇高なのだ。カントにとっても、ある対象が表象、つまりそれを描こうとするどんな努力も超えたとき、崇高なものになる。崇高は想像を超えたところにある[Einbildungskraft]。
キリスト教の伝統では、裸は「神学的な特徴と切り離せない」3。堕落以前、アダムとエバは裸で立つことはなかったが、それは「恵みの衣」「光の衣」4が彼らを包んでいたからである。しかし、罪によって、神の衣が奪われたのである。堕落以前は、アダムとエバは裸ではなかった。したがって、裸は、恵みの衣の喪失を意味する。アガンベンは、神学的な枠組みなしに、裸を概念化しようと試みている。しかし、その過程で、ベンヤミンが考える裸体の崇高さを、ポルノグラフィーの中にも拡張している。ポルノ的な半裸のモデルについて、彼はこう述べている。
美しい顔が微笑みながら裸体を晒しながら言えることはただ一つ、「私の秘密を見たかったのか?私の包容力を確かめたかったのか?それなら、できることなら、すぐに見てほしい。この絶対的な、許しがたい秘密のなさを見よ!」と。. . . しかし、まさに裸体体験における美の幻滅、あらゆる神秘とあらゆる意味を超えた外観の崇高な、しかし惨めな展示こそが、神学的装置を何とか打ち消すことができるのである5.
確かに、ポルノグラフィに掲載された裸体は「惨め」だが、「崇高」とは言い難い。ベンヤミンが美しい外観に対置する崇高さは、あらゆる展示の価値を欠くものである。生物的な崇高さを破壊するのは、まさに展示である。崇高はカルト的な価値を生む。消費者に「媚びる」ポルノグラフィーの顔は、崇高以外の何者でもないことを証明している6。
アガンベンの、処分的なものと自由なヌードとの間の対立は、非弁証法的である。暴力は、仮面や表情といった役割を表情に強制する処分的なものだけでなく、形のないポルノ的な裸体も含んでいるのだ。肉体となった身体は崇高なものではなく、猥雑なものである。ポルノグラフィーのヌードは、アガンベン自身が指摘するように、暴力から生じる肉体の猥雑さとの境界線上にある。「サディストが、ありとあらゆる方法で、他者の身体を、その猥雑さ、つまり、あらゆる優美さの回復不能な喪失を明らかにするような不釣り合いな体勢に追い込もうとするのは、このためである」7。
とりわけ、恩寵[アンムート]はアガンベンのポルノ的な裸体の犠牲になっている。恩寵は、その神学的起源から、慈悲や好意[グナーデ]との境界線上にあるため、彼にとって疑わしいものに思えるのだ。アガンベンは、身体がその優美さを、それを道具とする目的志向の運動に負っているというサルトルの主張を持ち出す。しかし、目的への固執のために、どんな道具も優美さを得ることはない。なにしろ、目的を直接的に追及し、仕事に向かうのだから。それに対して、優美さには、曲がり角や回り道をするものが宿っている。それは、いわば行為を取り囲み、目的の経済性から逃れるような、身振りや形の自由な遊びを前提とする。このように、優美さは、オブジェクト指向の行為と猥雑な裸体の間に生じるのである。この優美な「間」は、アガンベンの手には負えない。自分を見せることもまた、優美さを失わせる。クライストの『マリオネットの劇場について』に登場する青年は、鏡の前に立ち、自分の動きを自分自身に見せ付ける瞬間に、その優美さを失う。ここでは、鏡は、アガンベンのポルノ女優が嬉しそうに覗き込むレンズと同じ効果を生む-それは、彼女が展示されていること以外、何も表現していないのだ8。
アガンベンは、展示が、神学的な決定要因から解放されたヌードを出現させる絶好の機会を提供すると主張する。今や「汚された」それは、新しい用途にアクセスできることを示すはずである。このように、秘密もなく展示された顔は、何も見せないが、見せること自体はできる。何も隠さず、何も表現しない。いわば透明になっているのだ。アガンベンはここに、「純粋な展示の価値」に由来する特異な魅力、「特別な魅力」 を見出している9 。展示は顔を、表現に先立つ場へと空っぽにする。アガンベンは、このような「空っぽの展示」の実践が、新しい形のエロティックなコミュニケーショ ンを生み出すことを望んでいる。
自分が見られていると感じた女性の顔が無表情になるのは、よくある経験である。つまり、視線にさらされているという意識は、意識の中に空白を作り出し、通常顔を動かす表現プロセスを強力に混乱させるのである。ファッション・モデルやポルノ・スターなど、自分を見せることを職業とする人々が身につけなければならないのは、厚顔無恥な無関心である。彼らは見せること自体(つまり、自分自身の絶対的なメディア性)以外、何も見せないのだ。このようにして、顔は展示の価値で破裂するほど積み上げられる。しかし,まさにこの表現力の無効化によって,エロティシズムは,人間の顔という,その居場所のないところに入り込むことになるのである.. . . 具体的な表現力を超えた純粋な手段として示された顔は、新しい用途、新しい形のエロティックなコミュニケーションのために利用できるようになるのだ10。
ここで、遅くとも、破裂するほど展示価値のある顔が、本当に「セクシュアリティの新しい集団的使用」、「エロティックなコミュニケーションの新しい形態」を開くことができるのかどうか、問わねばならない。アガンベンは、このようなヌードは、表現の前段階にあり、いかなる神学的署名からも解放されているため、たとえ「ポルノグラフィーの装置」がそれを中和したとしても、それ自体に「不敬の可能性」を秘めていると指摘している。しかし、アガンベンの仮定に反して、ポルノグラフィーは事後的にセクシュアリティの新たな使用を阻害するものではない。ヌードと共謀するようになった顔はすでにポルノである。その唯一の内容は、露出すること、すなわち、展示されている裸体の自覚を恥じることなく示すことだ。秘密がなく、透明になってしまった裸の顔は、単に露出された状態に還元され、猥褻であることを証明する。破裂するほど展示価値を積まれた顔はポルノである。
アガンベンは、露出それ自体がポルノ的であることを認識していない。資本主義は、あらゆるものを商品として展示し、超可視性に委ねることで、社会のポルノグラフィーを高めている。それは、展示の価値を最大化することを求める。資本主義は、セクシュアリティの他の用途を知らない。アガンベンが求める「セクシュアリティの集団的使用」は、特にポルノ広告において実現される。「ポルノ画像の孤独な消費」は、セクシュアリティの新たな集団的使用の約束に単に「取って代わる」ものではない。むしろ、個人と集団は、ポルノグラフィーのイメージを同じように利用するのである。
とりわけ、アガンベンはエロティックとポルノグラフィックの本質的な違いを認識していない。裸体を直接的に見せることは、エロティックではない。身体のエロティックな場所は、「衣服の隙間」、例えば手袋と袖の間など、皮膚が「二つの縁の間で閃く」ところにある。エロティックな緊張は、ヌードの常設展示からではなく、「出現-消失の演出」から生じる11 。「断続」の否定性がヌードを輝かせる。ベールを脱いだヌードを展示することの積極性は、ポルノ的である。それはエロティックな輝きを欠く。ポルノ的な身体は滑らかである。何も邪魔をしない。中断は両義性、曖昧さを生み出す。この意味不明な曖昧さがエロティックなのだ。しかも、エロティックは秘密や隠蔽の否定性を前提にしている。透明性にはエロティシズムはない。秘密が消え去り、完全な露出と裸になるところから、ポルノグラフィーは始まる。それは、貫通し、侵入する肯定性によって特徴づけられる。
アガンベンは、すべての秘密に神学的な徴候があると疑い、それを「冒涜」しようとする。冒涜とは、秘密のない美しさ、ヌード「優雅さの威信と堕落した自然のキメラを超えた」ヌードをもたらすことを意味する。「説明しがたい包容の中に……秘密はない」。それは純粋な外観として現れる。. . . 裸のマトメは、この意味で、単にこれである: haecce! しかし、エロティックの主題は存在せず、エロティックは haecce! これ以外には何もない」という秘密のない証拠が、ポルノグラフィーを証明する。エロティックには、ディクティックのストレートさが欠けている。エロティックな身振りはディクテイクスとしての資格を持たない。ボードリヤールによれば、誘惑のエロティックな力は、「他者にとって永遠に秘密のままである何か、彼について私が直接知ることは決してできないが、それでも秘密のベールの向こうから私に魅力を行使する何か」の直感を弄する13。ポルノグラフィには、誘惑が起こりうるような距離感がない。エロティックな魅力は、必然的に撤退という否定的な要素を含んでいる。
バルトは写真に二つの要素を見出す。彼は第一の要素をstudiumと呼ぶ。それは、通知を受けるべき情報の拡張された場に関するものである。無関心な欲望、さまざまな興味、取るに足らない趣味の、非常に広い領域」。これは、「好き」ではなく「好き」というオーダーに属する。その判断の形式は、「好き/嫌い」である。力強さや情熱がまったくない。第二の要素である punctum は、studium を突破するものである。それは好きという気持ちを起こさせず、代わりに感情[Ergriffen-heit]と懸念[Betroffenheit]という傷を与える。一元的な写真にはpunctumがない。それらは、studiumの対象だけを提供する。
ニュースの写真は非常によく一元化されている(一元化された写真が必ずしも静謐であるとは限らない)。これらのイメージには,句読点がない.ある種の衝撃-文字どおりトラウマになりうる-はあるが,乱れはない.これらのジャーナリスティックな写真は(一度に)受け取られ,知覚される15.
パンクタム(punctum)は情報の連続性を中断させる。15 パンクタムは情報の連続性を中断させ、裂け目、破れ目として表現する。それは最大限の強度と密度を持つ場所を構成し、定義できない何かが生息している。それは、studium を区別する証拠である透明性をまったく欠いている:「名前をつけられないこと は、障害のよい徴候である。. . . その効果は確かなものであるが、場所を特定することはできない。」
バルトはまた、ポルノグラフィーのイメージも単写真のなかに数えている。それらは滑らかで透明であり、何の断絶も両義性も見いだせない。しかし、亀裂や内的な断絶は、滑らかでも透明でもないエロティシズムを特徴づける。エロティックな写真は、「乱れた、亀裂のある」イメージである17。ポルノグラフィーのイメージは、すべてを外側に向け、それを露わにする。ポルノグラフィーは、内面性、隠蔽性、神秘性を持たない。「照らされた宝石をひとつだけ見せる店のウィンドウのように、それはセックスというただひとつのものの提示によって完全に構成されている:二次的で時期はずれのものが、半分隠したり遅らせたり、気をそらすことは決してできない」18 透明性は、何も隠したり隠さずに、むしろ見るためにすべてを手渡せば卑猥とされる。今日、あらゆるメディアの映像は多かれ少なかれポルノ的である。義務的であるがゆえに、それらには句読点も意味論的強度もない。定着し、傷つくようなものは何もない。せいぜい、”好き “と思わせる対象を提供する程度だ。
バルトによれば、映画的イメージはパンクタムを持たない。句読点は瞑想的な余韻と結びつく。「スクリーンの前では、私は自由に目を閉じることができない。そうでなければ、再び目を開けても、同じイメージを発見することはできないだろう」19。これに対して、一連のイメージは、バルトが言うように、観察者に “連続的な貪欲さ “を強いる。パンクタムは、「懺悔」20 が宿らない、消費的で貪欲な視線から逃れられる。多くの場合、それはすぐには現れず、事後に、余韻のある回想の中でしか現れない。
それなら、その明瞭さにもかかわらず、写真がもはや私の目の前になく、私がそれを思い返したときに、事後的にしかパンクチュームが明らかにならないことがあっても、何も驚くことはない。私は、自分が見ている写真よりも、自分が記憶している写真の方をよく知っているのかもしれない。. . . 私はちょうど,それがどんなに即時的で鋭いものであっても,パンクタムはある種の遅延を受け入れることができる(しかし,決して精査することはできない)ことに気づいていたのである21.
「音楽」は目を閉じているときにだけ始まる。バルトはカフカの言葉を引用している。「我々は、物事を頭から追い出すために写真を撮る。私の物語は、私の目を閉じるための方法なのだ」22 写真から思索的な距離を置いたときにのみ、音楽は鳴る。逆に,無媒介的な接触によって眼とイメージが短絡するところでは,音楽は沈黙する.透明なものは音楽を奏でない。さらに、バルトは、写真は「沈黙」していなければならないと述べている。「沈黙の努力」においてのみ、写真はその punctum を明らかにする。写真は静寂の場を表し、それによって瞑想的な余韻が可能になるのである。ポルノグラフィーの画像には余韻がない。ポルノグラフィーの画像は、露出されているため、耳障りでうるさい。また、時間的な距離もなく、想起を認めない。ポルノは、即座に興奮させ、満足させるという目的にのみ役立っているのだ。
スタヂオは読書を伴う。
政治的な証言として受け取るにせよ、歴史的な名場面として楽しむにせよ、私がこれほど多くの写真に興味を抱くのは、studium によってなのだ。
もし文化が特定の人物、顔、身振り、物語、行動からなるものだとすれば、今日の視覚のポルノグラフィティ化は脱文化として行われることになる。ポルノグラフィ的で脱文化的なイメージは、読むべきものを何も提供しない。それらは、直接的で、触覚的で、感染力のある手段によって、広告のように機能する。それらはポスト熱狂的なものである。それらは、スタディアムが可能となるような距離を与えない。その作用様式は読むことではなく、感染と脱反応を伴う。また、句読点がその中に宿ることもない。それらはスペクタクルの中に空っぽになる。ポルノグラフィーの社会は、スペクタクルの社会である。
加速の社会
サルトルによれば、肉体が単なる肉の事実性に還元されたとき、肉体は猥雑になる。参照するもののない身体は猥雑である-それが方向性を持たず、行為を行わず、状況に適合しないとき。過剰で余剰な身体運動は猥褻である。サルトルの猥褻の理論は、社会的な身体、その過程と運動にも当てはまる。それらは、物語性、方向性、意味を剥奪されたとき、猥褻となる。そして、その余剰と過剰は、肥満、非個性化、ランクの上昇という形で表現される。それらは目的も形もなく溢れ、増殖する。そこに彼らの猥雑さがある。多動、超生産、超通信は猥雑であり、目的を超えて加速する。このような超加速は猥雑であり、もはや何ものも何処も本当に動かさない[bwegen]し、本当に何ものをももたらさない[zuwege]のである。その過剰さにおいて、それはその目標[Wohin]を越えてこぼれ落ちてしまう。この純粋な運動は猥雑であり、ただそれ自身のために加速するのである。「運動は不動ではなく、速度と加速の中に、いわば運動よりも可動的なものの中に消えていく。」
加法は叙述よりも透明である。加法的で物語的でないプロセスだけが、加速を認める。プロセッサーの動作だけが完全に透明であり、それは足し算によってのみ進行するからである。これに対し、儀式や式典は物語的なプロセスであり、加速を免れている。犠牲的行為を加速化しようとするのは、冒涜的である。儀式や式典には、独自の時間性、リズム、機転がある。透明性の社会は、儀式や式典をすべて廃止する。なぜなら、それらは演算化を認めず、情報、コミュニケーション、生産の加速度的な循環を妨げるからである。
計算とは対照的に、思考は自己透過的ではない。思考はあらかじめ計算された道筋をたどるのではなく、自らを開放に賭けるのである。ヘーゲルによれば、思考には否定性が宿っており、それが思考を変容させるものを経験させる。自分とは異なるものになるという否定性は、思考を構成するものであることが証明されている。ここに、常に自己同一的であり続ける計算との違いがある。このような類似性は、加速のための可能性の条件を提供する。否定性は、経験だけでなく、知識[Erkenntnis]も区別する。たった一つの洞察が、存在するものすべて、全体としてのすべてを疑わせ、変えてしまうことがある。情報にはそのような否定性がない。同様に、経験[Erfahrung]は、変容の力を滲み出させるような結果をもたらす。この点で、存在するものをそのままにしておく経験[Erlebnis]とは異なっている。
物語性がないことが、プロセッサーと物語的な出来事である行列を区別している。プロセッサーとは異なり、行列は強い方向感覚を持つ。そのため、猥雑さとは無縁である。プロセッサーもプロセッションも、ラテン語のprocedereという動詞が語源で、”前に踏み出す “という意味がある。プロセッサーは、ナレーションによって緊張感を持たせている。プロセッションは、ナレーションの特別なパッセージを舞台的に演出する。シナリオはそれをマークする。その物語性のために、特定の時間性がそこに宿る。それゆえ、その手続きを加速させることは可能でも意味もない。ナレーションは全く付加されない。一方、プロセッサーの手続きは、すべての物語性を欠く。その活動にはイメージも情景もない。行列とは対照的に、それは何も語らない[erzählt]。それは単に数えるだけである[zählt]。数字は裸である。プロセスも同様にラテン語の動詞 procedere に由来するが、その機能性ゆえに物語性には乏しい。このことは、振付や舞台美術を必要とする物語的なシークエンスとは異なるものである。機能的に決定されたプロセスは、単に舵取りや管理の対象でしかない。社会が猥雑になるのは、「シーンがなくなり、すべてがどうしようもなく透明になってしまったとき」2。
巡礼はしばしば行列という形で頂点に達する。厳密な意味での結末は、ナレーションの中でしかありえない。脱物語化、脱儀式化された世界では、結末は、痛みを与え、不安にさせる断絶[der schmerzt und verstört]にしかならないのである。ナレーションの枠内においてのみ、エンディングは完成として現れることができる。物語性がなければ、結末は常に絶対的な喪失、絶対的な欠落である。プロセッサーはナレーションを知らない。それゆえ、結論に到達することができないことが証明される。巡礼は物語的な出来事である。そのため、旅程はできるだけ早く通過するための通路ではなく、意義に富んだ道程である。道中には、贖罪、癒し、感謝といった意味が込められている。このような物語性のために、巡礼は加速することができない。さらに、巡礼の道は「そこ」への移行である[Dort]。時間的な観点から言えば、巡礼者は幸福や救い[ein Heil]が期待される未来へ向かう途中である。このため、巡礼者は観光客ではない。観光客は現在にこだわり、「今、ここ」に留まる。彼は正しい意味での旅人ではない。彼が旅する道には何の意味もなく、それは注目に値しないからである。観光客は、道の持つ豊かな意義、物語性を何も知らない。道は物語的な活力を失い、空虚な通路となる。この意味上の貧しさ、空間と時間の物語性の欠落は、猥雑である。否定性は、障害物や移行という形で、物語の緊張を構成する。透明性への強制は、あらゆる境界と閾値を解体する。空間は平滑化され、水平化され、空っぽになったとき、透明になる。透明な空間は意味的に貧弱である。意味は閾値と移行においてのみ、実際、障害物を通してのみ生じる。子供の最初の空間体験もまた、閾値の体験である。閾値と移行は、謎、不確実性、変容、死、恐怖のゾーンであると同時に、憧れ、希望、期待のゾーンでもある。その否定性が情熱のトポロジーを構成している。
ナレーションは選択を実践する。物語の道筋は狭く、特定の出来事しか認めない。それによって、肯定的なものが増殖し、非個人化するのを防ぐことができる。現代社会を支配する過剰な肯定性は、物語性との結びつきを失っていることを示している。このことは記憶にも影響を与える。記憶とは物語性によって区別されるものであり、単に加算的に作用し蓄積されるものである。記憶の痕跡はその歴史性ゆえに、常に再配置され、再記述される3。今日、記憶は「あらゆる種類の、あらゆる出自のイメージ、使い古された、使い古された記号が、いかようにも積み上げられる」4 ガラクタ屋、すなわちゴミとデータの山に肯定化されつつある。したがって、歴史は存在しない。ガラクタ屋は記憶することも忘れることもできない。
強迫的な透明化は、モノの香り、時間の香りを消し去る。透明には香りがない。未定義のものを認めない透明なコミュニケーションは、猥雑である。無媒介の反応と脱反応もまた猥褻である。プルーストにとって、「即時的な楽しみ」は美とは無縁のものである。あるものの美しさは、別のものの美しさに照らされて、「ずっと後になって初めて」回想として現れる。スペクタクルの一瞬の煌めき、即時の刺激が美しいのではなく、静かな余韻、時間の燐光が美しいのである。出来事や刺激の素早い連続は、美しいものの時間性を構成しない。美は弟子[ツォーリン]であり、遅咲きである。遅咲きであるがゆえに、香しい美の本質が見えてくる。この本質は、燐光を放つ時間的な層と堆積物からなる。透明なものは燐光しない。
現代の危機は加速度ではなく、むしろ時間性の散乱と解離である。時間的な非同期性は、時間を方向性なくざわつかせ、単なる時間的、原子化された存在の連続に崩壊させる。それによって、時間は加法的なものとなり、すべての物語性が空っぽになる。原子には香りがない。形象的な引力、物語的な重力は、まず原子を香りのよい分子に結合させなければならない。複雑で物語的な形成物だけが、香りを放つ [verströmen]。加速それ自体が実際の問題を表しているわけではないので、解決策には減速は含まれない。減速するだけでは、機転もリズムも香りも生まれない。空虚に陥るのを防ぐことはできない。
親密さの社会
18世紀の世界は「世界劇場」であった。公共圏は舞台のようだった。舞台の距離が、肉体と魂の直接的な接触を妨げていた。演劇的なものは触覚的なものと対立する。コミュニケーションは儀式的な形式とサインによって行われ、それによって魂は解放される。近代では、演劇的な距離はますます放棄され、親密さが好まれるようになった。リチャード・セネットは、「自己の外的イメージと戯れ、そこに感情を投じる」1 という能力を奪ってしまう、宿命的な展開をここに見ている。劇場は表現の場である。しかし、ここでの表現行為は客観的な感情であり、精神的な内面性の現れではない。したがって、それらは表現されるのであって、展示されるのではない。今日の世界は、行為や感情を表象し解釈する劇場ではなく、親密さを展示し、販売し、消費する市場なのだ。劇場は表象の場であり、市場は展示の場である。今日、劇場における表象は、ポルノグラフィーの展示に屈服している。
セネットは「演劇は親密さに対して特別な敵対的関係を持ち、演劇は強い公共生活に対して同様に特別で友好的な関係を持つ」と仮定している2。親密な感情や感覚とは関係のない客観的=公的世界が没落するとき、親密さの文化は上昇する。親密さのイデオロギーによれば、社会的関係は、個人の内的な心理的欲求に近づけば近づくほど、より現実的で、本物で、信頼でき、真正であることが証明される。親密さは、透明性の心理的公式である。人は、親密な感情や感覚を明らかにし、魂を裸にすることで、魂の透明性を獲得できると信じている。
ソーシャルメディアとパーソナライズされた検索エンジンは、インターネット上に絶対的な親密さの空間(Nahraum)を作り出し、ここでは外部が排除されている。ここでは、外部は排除され、自分自身と自分自身の人生だけに出会う。変化を可能にするような否定的なものは存在しない。このデジタルな近さ[Nachbarschaft]は,ユーザーにとって都合のよい世界の一部分だけを提供する.このようにして、公共圏[Öffentlichkeit]は解体され、実際、公共的で批判的な意識は解体され、世界は私有化される。インターネットは親密な領域、あるいは快適な領域へと変貌する。あらゆる距離が排除された近接性は,透明性が表現されるもうひとつの形態である.
親密さの専制は、あらゆるものを心理学化し、個人化する。政治でさえもその支配を免れることはできない。したがって、政治家はもはやその行動によって評価されることはない。その代わりに、一般的な関心が彼らの人物に向けられることになる。公共圏の喪失は空虚さを残し、親密な詳細と私的な事柄がそこに流れ込んでくる。ペルソナを公表することが公共圏の代わりとなる。その過程で、公共圏は展示場と化す。公共圏は共同行動の場からますます遠ざかっていく。
“ペルソナ”(ラテン語でpersona)とは、もともと “仮面 “を意味する。ペルソナは、それを通して聞こえる声(ペルソナーレ)に特徴を与え、実際、声に形と姿を与えている。露出と脱皮の社会である透明化社会は、仮面のあらゆる形態に対して、象徴的な外観に対して働く[シャイン]。また、社会の脱儀式化と脱解釈化が進むと、象徴的な外観の形態が剥奪され、社会が裸になってしまう。主観的な心理状態ではなく、客観的な規則が遊びと儀式を決定する。他者と遊ぶときはいつでも、人はゲームのルールに自分を従属させる。遊びの社交性は、相互の自己開示に基づくものではない。むしろ、人間は互いに距離を保つことで社交的になる。それに対して、親密さは距離を破壊する。
親密さの社会は、儀式化された身振りや儀礼的な行為に不信感を抱く。彼らはそれを外的で不真面目なものとして叩く。儀式は、外在化した表現形式による行為として行われ、脱個人化、脱人格化、脱心理学化の効果がある。儀式に参加する者は「表現行為」3 を実践するが、これは自分自身を展示し、露出させることを意味しない。親密さの社会は、心理学化され、脱儀式化された社会である。告白し、裸になり、ポルノ的な距離感を欠く社会である。
親密さは、情動の主観的な蠢きのための道を作るために、客観的な遊びの余地をなくす。客観的な記号は、儀式的・儀礼的な空間を循環する。この空間は、ナルシスト的にカテキョされることはない。ある点で、この空間は空虚であり、不在であることが証明される。ナルシシズムは、自分自身との距離のない親密さ、つまり自己距離の欠如を表現する。風景的な距離の取り方ができないナルシシズム的な主体が、親密さの社会を形成しているのである。セネットはこう指摘する。「ナルシストは体験に飢えているのではなく、体験に飢えているのだ。セネットによれば、自己愛性障害が増加しているのは、「新しい種類の社会がその精神的構成要素の成長を促し、その条件の外で、単一の自己の境界の外で、公共の場で意味のある社会的出会いの感覚を消し去っているから」5。「親密社会」は、人が自分から逃れ、自分を失うかもしれない儀式的、式典的徴候を排除しているのだ。経験[Erfahrung]とは、他者と向き合うことだ。これに対して、経験[Erlebnis]とは、あらゆる場所で自分自身に出会うことを意味する。自己愛的な主体は、自分を囲い込むことができない。その存在の境界は曖昧になる。その結果、安定した自己イメージは生まれない。自己愛的な主体は、アイデンティティと戯れることが不可能になるほど、自分自身に溶けてしまう。うつ病になったナルシストは、境界のない自己同一性の中で溺れていく。どんな空白も不在も、ナルシストを自分自身から遠ざけることはない。
情報化社会
見てみると、プラトンの洞窟は明らかに劇場として構成されている。囚人たちは、舞台の前にいる劇団員のように座っている。囚人とその背後の火の間には道があり、その道に沿って「人形劇の興行主がその芸を見せる仕切りの上」のような低い壁が続いている1。あらゆる種類の道具、像、石や木でできた人物が運ばれ、仕切りを越えて壁に影を落とし、囚人はうっとりとその影を見つめている。囚人たちは振り向くことができないので、影が話しているように錯覚する。プラトンの洞窟は、一種の影絵芝居である。影を落としているのは、この世に実在するものではなく、すべて演劇の道具である。結局、現実のものの影や映り込みは、洞窟の外にしか存在しないのである。もし、囚人の一人が光の世界に導かれたとしたら、プラトンはこう推測する。
「彼が高いところにあるものを見ることができるようにするには、慣れが必要である。最初は影を、次には人間や他のものの似姿や水面への反射を、そして後にはものそのものを最も容易に見分けることができるだろう」2。
洞窟の中の囚人たちは、現実の世界の影像を見ているのではない。洞窟の中の囚人たちは、現実世界の影像を見るのではなく、彼らの目の前に劇場が展開される。しかも、火は人工的な光である。実際、囚人たちは、情景の幻想によって縛られている。彼らは劇に、語りに身を委ねているのだ。プラトンのアレゴリーは、彼の解釈者が一般的に主張するように、異なる認識様式を表しているのではなく、むしろ、異なる生き方、すなわち、物語と認識の存在様式を表しているのである。プラトンの洞窟は劇場である。洞窟の寓話において、語りの世界としての劇場は、洞察の世界と対立している。
洞窟の中の火は、人工的な光として情景的な幻影を作り出す。それは外観を鋳造する[Schein]。この点で、真理の媒体としての自然光とは異なる。プラトンにとって、光は強い方向感覚を示すものである。それは源である太陽から流れてくる。存在するものはすべて、善の理念としての太陽に向かって秩序づけられている。それは超越的な点を形成し、「存在を超えた」ところにさえ位置する。したがって、それは “神 “とも呼ばれる。存在するものは、この超越にその真理を負っている。プラトンの陽光は階層化する。それは、単なる類似の世界から、感覚的に知覚可能なものを経て、イデアの知性的世界に至るまで、知識に関して段階を設けるものである。
プラトンの洞窟は物語世界である。そこにあるものをつなぐ因果的なつながりはない。一種のドラマツルギー、あるいはシナリオが、物語的手段によって事物(あるいは記号)同士を結びつけている。真理の光は世界を脱話術化する。太陽は単なる外観を消滅させる。ミメーシスとメタモルフォーゼの遊びは、真理に取り組むこと[Arbeit an Wahrheit]にゆだねられる。プラトンは、硬直したアイデンティティを優先して、変化の気配を非難している。ミメーシスに対する彼の批判は、特に外見と戯れに関するものである。プラトンは、見栄えのする表現を一切禁じ、詩人が真理の都市に入ることを否定している。
「もし、……その狡猾さによって、あらゆる形を装い、あらゆるものを模倣することができる男が、展示したい詩を携えて我々の都市に到着したとしたら、我々はひれ伏して彼を神聖かつ不思議で楽しい生き物として崇拝するはずだが、彼に、我々の都市にはその種の男はいない、また、我々の間にその種の男が出現することは合法ではないと言って、彼の頭に没薬を流し、毛皮を冠した上で他の都市に追いやるだろう3」。
同様に、透明な社会は、詩人のいない社会であり、誘惑や変態のない社会である。結局のところ、風景的な幻想、外観の形態、儀式や儀礼の標識を作り出すのは詩人であり、彼は人工物や反芸術物を超現実的で裸の証拠に対峙させるのである。
古代、中世、啓蒙主義に至るまで、哲学的、神学的な言説を支配してきた光の比喩は、強い参照性を提供する。光は井戸や源から湧き出る。神や理性といった存在を義務づけ、禁止し、約束するための媒介となる。その結果、否定性が生まれ、極性化され、対立が生じる。光と闇は同居している。光と影は共にある。善には悪が付随している。理性の光と非理性(あるいは単なる感覚的なもの)の闇は、互いを引き立たせる。
プラトンの真理の世界とは対照的に、今日の透明な社会には、形而上学的な緊張が宿る神の光がない。透明には超越がない。透明な社会は、光のないシースルーなのだ。超越的な源から差し込む光に照らされているわけではない。透明性は、光源から照らされることによって生まれるのではない。透明性の媒体は光ではなく、無光の放射であり、光を与える代わりに、すべてを満たしてシースルーにする。光とは対照的に、それは貫通し、侵入する。さらに、その効果は均質化と平準化であるのに対し、形而上学的な光は階層と区別を生み出し、それによって秩序と方向性を作り出す。
透明性のある社会は情報の社会である。情報とは、すべての否定性を欠いている限りにおいて、そのような現象である。それは、実証され、運用された言語に相当する。ハイデガーはこれを「フレーミング」[Ge-Stell]の言語と呼ぶだろう。話すことは、あらゆる点で存在するすべてのものを徴発できるFramingに対応するよう挑発される」。Framingの中で、話すことは情報に変わる」4 情報は人間の言語を位置づける[stellt]。ハイデガーは「Framing」を支配の観点から考えている。したがって、命令する[Bestellen]、想像する[Vorstellen]、生産する[Herstellen]といった秩序の形象は、権力と支配を意味する。命令することは、存在を物質[Bestand]として位置づけ、想像することは、それを対象[Gegenstand]として位置づける。しかし、ハイデガーのFramingは、今日特徴的な位置づけの形式を包含していない。展示すること[Aus-Stellen]や陳列すること[Zur-Schau-Stellen]は、主として権力の獲得に役立つものではない。権力は,注目(Aufmerksamkeit)というよりもむしろ目的である.原動力はポレモスではなく、ポルノである。権力と注意は共存するものではない。権力を持つことは、他者を意のままにすることであり、注意を求める必要はない。また、注意は自動的に権力を生み出すものでもない。
ハイデガーもまた、支配の観点からしか「絵」を考えていない。
「絵」とは、. 口語的な表現では、何かについて「絵に描いた餅」であるように聞こえるもの。. . 何かについて「絵の中に自分を置く」ことは、物事がそれとともにあるように、存在そのものを自分の前に置くこと、そして、そのように置かれたものとして、それを自分の前に永久に留めておくことを意味する5。
ハイデガーにとって、絵は、人が存在を引き継ぎ、それを堅く保持するための媒体である。この「絵」の理論は、今日のメディアのイメージを説明することはできない。なぜなら、それらはもはや「存在者」を表象しないシミュラクラだからである。それらは「位置づけ」、「自分の前にある」、「常にこのように持っている」という目的を果たすことはない。参照するもののないシミュラクラとして、彼らはいわば独立した存在である。また、権力や支配力を超えて増殖する。いわば、単に「ある」ものよりも、存在と生命に満ちあふれている。今日のマルチメディア化された大量の情報とコミュニケーションは、「フレーミング」よりも「蓄積」6として物事を提示す。
透明性の社会は、真実を欠くだけでなく、象徴的な外観も欠く。真理も象徴的な外観も透けてはいない。虚無だけが完全に透明である。この空虚さを回避するために、大量の情報が流通する。大量の情報とイメージは、空虚さが目立つ中で、充実感を与えてくれる。情報量やコミュニケーション量が増えるだけでは、世界は明るくはならない。また、透明性は透視を意味するものでもない。大量の情報は、真実を生み出さない。情報が増えれば増えるほど、世の中を見渡すことは難しくなる。ハイパーインフォメーション、ハイパーコミュニケーションは、暗闇に光をもたらさない。
啓示の社会
ある意味で、18世紀は現代とまったく同じであった。18世紀は、すでに、暴露と透明性の悲哀を知っていたのである。このように、ジャン・スタロビンスキーはルソーの研究の中でこう書いている。
外見は人を惑わすというのは、1748年当時、ほとんど目新しいテーマではなかった。演劇でも教会でも、小説でも新聞でも、見せかけ、慣習、偽善、仮面がさまざまな形で糾弾された。極論と風刺の語彙の中で、unveil と unmask ほど頻繁に出てくる言葉はない1。
ジャン=ジャック・ルソーの『告白』は、「真実としての公示」の黎明期を特徴づけている。告白』は冒頭から、「あらゆる点で自然に忠実な」人間を示すことを意図している。前例がない」著者の「事業」は、彼の「心」を容赦なく暴露することを含んでいる。ルソーは神に語りかける。「私は自分をありのままに見せたのだ。. . ルソーは神に向かって、「私は、汝自身が見たように、私の秘密の魂(mon intérieur)をさらけ出した」2 と言い、自分の心が透明であることを意味している3 。「彼の心は水晶のように透明で、その中で起こることを何一つ隠すことができない。ルソーは、「すべての感情、すべての思考を共有することによって、誰もが自分のありのままの姿を他者に見せることができる」5ように、「心の開放」を求めている。ここに、ルソーの心の独裁がある。
ルソーの透明性の要求は、パラダイムシフトを告げるものである。18世紀の世界はまだ劇場であった。場面、仮面、人物に満ち溢れていた。ファッションそのものが演劇的だったのである。街着と劇場用コスチュームの間に本質的な違いはなかった。仮面さえもファッショナブルになった。人々は完全に演出に魅了され、舞台上の幻想に身をゆだねていた。女性のヘアスタイル(プフ)は、歴史的な出来事(プフ・ア・ラ・コンンスタンス)や感情(プフ・オ・センチメント)を表現する場面として形作られた。そのために、磁器製の人形も髪に織り込まれた。庭全体や帆を張った船を頭に乗せることもあった。男女ともに顔の一部に赤い化粧を施した。顔そのものが舞台となり、美点(ムーシュ)によって性格が表現されたのである。例えば、目尻につける美点は情熱を表す。また、下唇につければ、素直な性格を表す。身体もまた、表象の場であった。しかし、隠された「内面」、ましてや「心」を偽りなく表現するものではない。むしろ、外見を弄ぶこと、情景的な幻想と戯れることがポイントであった。身体は、服を着せられ、飾られ、記号と意味を与えられる魂のない人形であった。
ルソーは、仮面や役割の遊びに対抗して、心や真実の言説を打ち立てたのである。そして、ジュネーヴに劇場を建てる計画を激しく批判する。演劇は、「自分を偽ること、自分とは別の人格を身にまとうこと、自分とは違う姿を見せること、冷血に熱中すること、思ってもいないことを本当に思っているかのように自然に言うこと、そして最後に、他人の場所を取ることによって自分の場所を忘れること」の芸術である6。表現はポーズであってはならず、透明な心を映し出すものでなければならない。
ルソーでは、完全な透明性の道徳が、必然的に専制に切り替わることを観察することができる。ベールをはぎ取り、すべてを明るみに出し、闇を追い払おうとする透明性の英雄的プロジェクトは、暴力につながるのである。プラトンが理想とする都市を規定した演劇とミメーシスの禁止は、ルソーの透明な社会に全体主義的な特質を印象づける。ルソーが小都市を好むのは、「常に人目にさらされる個人は、生まれながらにしてお互いを検閲する」し、「警察は容易に全員を監視することができる」からである(7)。透明性を求める彼の声は、定言命法へとエスカレートしていく。
道徳のたった一つの戒律が、他のすべての戒律に取って代わることができる。そして、私自身は、自分の家を、その中で起こることが何でも見えるように建てたいと願ったローマ人を、最も価値ある人物と見なしてきた8。
ルソーは、心の透明性を道徳的に要求しているのである。透明な家を持つローマ人は、結局のところ、「道徳の戒律」に従っている。今日、「屋根、壁、窓、ドアを備えた完璧な家」は、すでに「物質的、非物質的なケーブル」によって絶望的に「穴があいて」いる。それは「コミュニケーションの風が吹き抜ける廃墟」と化している9 。コミュニケーションのデジタルな風はすべてを貫通し,それを透明にする.透明性のある社会を吹き抜ける。しかし、デジタル・ネットは、透明性の媒体であっても、道徳的な要請には従わない。いわば、伝統的に神学的形而上学的な真理の媒体である心臓を欠いているのだ。デジタルの透明性は、心臓的ではなく、ポルノ的である。さらに、それは経済的なパノプティカをもたらす。その目的は、心の道徳的な浄化ではなく、最大限の利益、最大限の注目を集めることにある。完全な照明[Ausleuchtung]は最大限の利益を約束する。
支配の社会
1978年、ボードリヤールは「パノプティック・システムの視点的真理」の終焉を経験しつつある、と指摘した1。
テレビの眼はもはや絶対的な視線の源ではなく、コントロールの理想はもはや透明性のそれではない。これは依然として、客観的な空間(ルネサンスのそれ)と専制的な視線の全能性を前提としている2。
この言葉を書いたとき、ボードリヤールはもちろんデジタル・ネットワークのことを知る由もない。現在、我々はパノプティコンの終焉を経験しているのではなく、むしろ全く新しい、無視点的なパノプティコンの始まりを経験しているのである。21世紀のデジタル・パノプティコンは、もはや専制的な視線の全能性をもって、中心点から監視を行わない限り、非視点的なのである。ベンサムのパノプティコンの基本である中心と周縁の区別は完全に消滅している。デジタル・パノプティコンは、遠近法の光学系を一切持たずに機能する。それが効率的なのだ。遠近法を用いた監視よりも、遠近法を用いない透過的な照明[Durchleuchtung]の方が効果的である。なぜなら、それは、誰でもできる、あらゆる場所からすべての人を照らす完全な照明を意味するからだ。
ベンサムのパノプティコンは、規律社会の現象であり、それは改善をもたらすはずのものだった。刑務所、工場、精神病棟、病院、学校はパノプティコンの管理下におかれていた。これらは、規律社会の典型的な制度である。管制塔を中心に円形に配置された独房は、互いに厳しく隔てられているため、居住者はコミュニケーションをとることができない。また、壁で仕切られているため、互いの姿は見えない。ベンサムには、「改善のために、彼らは孤立にさらされている」とある。監督官の視線は独房の隅々まで届くが、監督官自身は乗員から見えないままである。「その本質は、監視員の置かれた状況の中心性と、見られることなく見るためのよく知られた最も効果的な工夫とにある」3 技術的な狡猾さの助けによって、常時監視されているという幻想が実現されている。そこに、権力と支配の構造を構築する視点がある。ベンサムのパノプティコンの住人は監視者の存在を常に意識しているが、デジタルパノプティコンの住人は自分たちは自由だと考えている。
今日の管理社会は、明確なパノプティコン構造を持っている。ベンサムのパノプティコンの住人が互いに孤立しているのとは対照的に、今日のパノプティコンの住人は互いにネットワーク化し、集中的にコミュニケーションをとっている。孤立による孤独ではなく、ハイパーコミュニケーションが透明性を保証している。とりわけ、デジタル・パノプティコンの特殊性は、その住人が自らを展示し、剥き出しにすることによって、その建設と維持に積極的に協力することだ。彼らはパノプティコン市場に自分たちを陳列する。ポルノグラフィーの展示とパノプティコンの管理は、互いに補完し合っている。展示主義と覗き見主義は、デジタル・パノプティコンとしてのネットを養う。つまり、私的で親密な領域を捨てなければならないという恐怖が、恥じることなく自分を見せたいという欲求に変わるとき、管理社会は完全なものになる。
監視技術の絶え間ない進歩に鑑み、未来学者デヴィッド・ブリンは、万人による万人の監視、すなわち監視の民主化を提唱している。それは「透明な社会」を約束するものである。ブリンの言う「透明な社会」というユートピアは、無制限の監視の上に成り立っている。権力関係や支配を生み出す非対称的な情報の流れは排除されるはずである。つまり、ブリンが求めているのは、完全な相互照明である。「下」は「上」によって監視されているだけではなく、「上」は「下」によって監視されている。誰もが他者を可視化し、コントロールできるようにしなければならない。このような完全な監視は、「透明な社会」を非人間的な「支配の社会」に変質させる。
透明性と権力は相容れない。権力は自らを秘密で覆うことを好む。アルカナのプラクティスは、権力が用いる手法の一つである。透明性は、権力の難解な領域を解体する。しかし、相互の透明性は、常に過剰な形態をとる永続的な監視によってのみ達成される。それが監視社会の論理である。完全なコントロールは行動の自由を破壊し、最終的にはGleichschaltungに至る。自由な行動領域を生み出す「信頼」を「管理」に置き換えることはできない。「民衆は支配者を信じ、信頼しなければならない。信頼すれば、絶えず監査、監視、監督を受けずに行動する自由を支配者に与えることができる。このような自律性がなければ、支配者は決して行動を起こすことができない」5。
信頼とは、知ることと知らぬことの間にある状態においてのみ可能である。信頼とは、たとえ無知であっても、他者と肯定的な関係を築くことだ。それは、知識がないにもかかわらず、行動を可能にする。もし、私が事前にすべてを知っていれば、信頼は必要ない。透明性とは、すべての知らないことが排除された状態である。透明性があるところには、信頼が生まれる余地はない。「透明性が信頼を生む」のではなく、「透明性が信頼を壊す」と言うべきだろう。透明性を求める声が大きくなるのは、信頼がなくなったときである。信頼に基づく社会では、透明性への押しつけがましい要求は表面化しない。透明性の社会は、不信と疑惑の社会であり、信頼が失われたからこそコントロールに依存する。透明性を求める声は、社会の道徳的基盤に欠陥が生じ、正直さや高潔さといった道徳的価値がますます意味を失いつつあるという単純な事実を示している。新しい社会的要請として、透明性は新しい地平を切り開く道徳的事例の代わりになっているのである。
透明性の社会は、達成の社会[Leistungsgesellschaft]の論理に完全に従っている。達成主体 [Leistungssubjekt] は、それを強制的に働かせ、搾取する外部支配とは無関係に作動する。人は自分自身の主人であり起業家である。しかし、支配のインスタンスが消えても、真の自由や束縛の不在にはつながらない。搾取する者は同時に搾取される者でもある。加害者と被害者は一体となる。自動搾取は、自由を感じることができるため、他者への搾取よりも効率的であることが証明されている。達成主体は、自由意志による、自己生成的な制約に自らを従わせる。この自由の弁証法は、支配の社会の根底にもある。完全な自動照射は、完全な全照射よりも、自由な感覚が伴うので、より効率的に機能する。
パノプティコンの計画には、何よりも道徳的な動機、つまり生政治的な動機があった。ベンサムによれば、パノプティコンに期待される最初の結果は「モラルの改革」6 であり、さらに「健康の保持」や「教育の普及」、「貧民法のゴルディアスの結び目は切られず、解かれる」7 などの効果がある。しかし、今日の強制的透明化にはもはや明確な道徳的、生政治的要請はなく、何よりも経済的要請がある。自らを照らし出す人々は、完全に搾取に身を委ねている。照明とは搾取である。個々の主体を過剰に露出させることは、経済効率を最大化する。透明な顧客は、デジタル・パノプティコンの新しい囚人、つまり犠牲者なのだ。
透明性の社会では、強い意味でのコミュニティは形成されない。そのかわり、孤立した個人、あるいはエゴの偶然の集まり[Ansammlungen]や群衆[Vielheiten]が出現し、彼らは共通の関心を追求したり、製品ラインを中心に集まったりする(「ブランド・コミュニティ」)。これらの集団は、相互に政治的行動を起こし、「われわれ」を構成することができるかもしれない集会とは異なっている。ブランド・コミュニティのような集まりは、内的な密度をもたない付加的な形成物である。消費者は、自分たちの欲求を誘導し、満足させるために、自発的に全方位的な監視に身をゆだねている。この点で、ソーシャルメディアはパノプティカル・マシンと何ら変わりはない。コミュニケーションと商業、自由と支配が一体となって崩壊する。生産関係を消費者に開放することは、相互の透明性を示唆するが、結局は社会性の搾取であることが判明する。社会的なものは、生産過程の中で機能的な要素に分解され、操作化される。それは、主として、生産関係を最適化するために役立つ。消費者の幻想的な自由は、あらゆる否定的な要素を欠いている。消費者はもはや、システム的な内側に疑問を投げかけるような外部を構成していない。
今日、地球全体がパノプティコンになりつつある。外の空間はない。パノプティコンは完全なものになりつつある。内と外を隔てる壁がない。グーグルやソーシャル・ネットワークは自由な空間として存在しているが、パノプティコンの形態をとっている。今日、監視は通常想定されるような自由への攻撃として起こっているのではない9。むしろ、人々は自発的にパノプティックな視線に身をゆだねている。彼らは意図的に自分たちの姿を消して見せることで、デジタル・パノプティコンに協力しているのだ。デジタル・パノプティコンにおける囚人は、加害者であると同時に被害者でもある。ここに自由の弁証法がある。自由はコントロールの一形態であることが判明する。