Contents
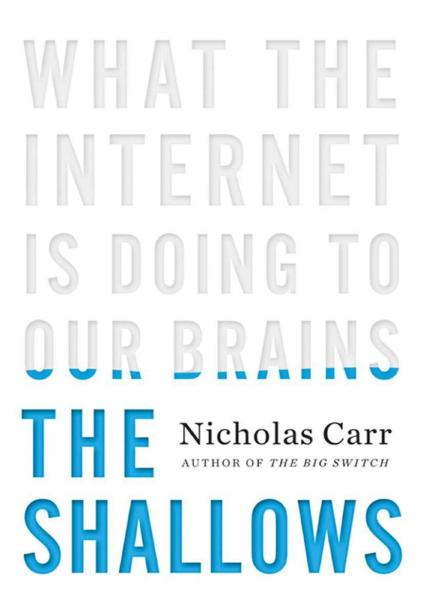
ニコラス・カー著
母へ
そして父を偲んで
目次
- プロローグ
- 番犬と泥棒
- 一 ハルと私
- 二 バイタル・パス
- 脳が自分自身について考えるときに何を考えるかについての余談
- 三 心の道具
- 四 深化するページ
- リー・デ・フォレストと彼の驚くべきオーディオンについての余談
- 五 最も一般的な性質の媒体
- 六 まさに本のイメージ
- 七 ジャグラーの頭脳
- IQスコアの浮力についての余談
- 八 グーグルの教会
- 九 検索、記憶
- 本書の執筆に関する余談
- 十 私のようなもの
- エピローグ
- 人間の要素
- ノート
- 参考文献
- 謝辞
そして、この広い静寂の中で
薔薇色の聖域を装う
働く頭脳の花輪を飾り立てるだろう。
-ジョン・キーツ「プシュケの歌」 (JOHN KEATS, Ode to Psyche
ザ・シャローズ
プロローグ 番犬と盗人
1964年、ビートルズがアメリカの電波に侵入し始めた頃、マーシャル・マクルーハンは『Understanding Media』を出版した。を出版し、無名の学者から一躍スターになった。オラキュラーで、グノミックで、マインド・ベンディングなこの本は、60年代の完璧な産物であり、アシッド・トリップとムーンショット、内と外への航海という、今では遠い10年間であった。メディアを理解する』は本質的に予言であり、それが予言したのは、直線的な心の溶解であった。マクルーハンは、20世紀の「電気メディア」-電話、ラジオ、映画、テレビ-が、われわれの思考と感覚に対するテキストの専制を打ち破ると宣言した。何世紀もの間、印刷されたページを読むという個人的な行為に囚われていた、孤立し、断片化した自己が、再び全体となり、部族の村と同じように地球規模のものに融合しつつあった。私たちは、「意識の技術的シミュレーション、すなわち、知るという創造的プロセスが集団的、企業的に人間社会全体に拡張されるとき」に近づいていたのである1。
Understanding Mediaは、その名声の頂点にあったときでさえ、読まれるより話題にされる本であった。今日、この本は文化的遺物となり、大学のメディア研究科の授業に委ねられている。しかし、マクルーハンは、学者であると同時に興行師であり、言葉を巧みに操る達人であった。「メディアはメッセージである」 この謎めいた格言が繰り返される中で忘れられているのは、マクルーハンが新しいコミュニケーション・テクノロジーの変革力を認め、賞賛していただけではないということだ。彼はまた、この力がもたらす脅威と、その脅威に気づかないことの危険性について警告を発していたのである。「電気技術は門の中にある。そしてわれわれは、電気技術とグーテンベルクの技術との出会いに無感覚であり、耳が聞こえず、盲目であり、無言である。
マクルーハンは、新しいメディアが登場するたびに、人々は自然にそのメディアが伝える情報-「コンテンツ」-に心を奪われることを理解していた。彼らは、新聞のニュース、ラジオの音楽、テレビの番組、電話の向こうの人が話す言葉などに関心を寄せる。メディアの技術は、それがいかに驚くべきものであったとしても、事実、娯楽、教育、会話など、メディアを通じて流れるものの背後に消えてしまう。人々が(いつもそうであるように)メディアの効果が良いか悪いか議論し始めるとき、彼らが争うのはコンテンツである。熱狂的なファンはそれを賞賛し、懐疑的な人はそれを非難する。この議論は、少なくともグーテンベルクの印刷機から出てきた本までさかのぼれば、新しい情報媒体が登場するたびに、ほとんど同じ条件になってきた。熱狂的なファンは、正当な理由を持って、この技術が生み出す新しいコンテンツの奔流を賞賛し、文化の「民主化」を意味するものと見なす。一方、懐疑論者は、同様に正当な理由を持って、コンテンツの粗悪さを非難し、文化の”dumbing down “を意味するものと見なす。一方の豊かなエデンは、他方の広大な荒れ地である。
インターネットは、このような議論に拍車をかける最新のメディアである。この20年間、何十冊もの本や記事、何千ものブログ記事、ビデオクリップ、ポッドキャストを通じて行われてきたネット愛好家とネット懐疑派の衝突は、前者がアクセスと参加の新しい黄金時代を告げ、後者が凡庸さとナルシズムの新しい暗黒時代を嘆いて、これまでと同様に両極化している。この議論は重要であり、コンテンツは重要だが、個人のイデオロギーや嗜好に依存するため、袋小路に入り込んでしまっている。意見は極端になり、攻撃は個人的なものになった。ラッダイト!」とマニアは嘲笑し、「俗物!」と嘲笑する。懐疑論者は「俗物」と嘲笑する。「カサンドラ!」 「ポリアンナ」
マニアも懐疑論者も見落としているのは、マクルーハンが見抜いたこと、つまり、長期的には、メディアのコンテンツは、人間の考え方や行動に影響を与えるメディアそのものよりも重要ではない、ということだ。世界と自分自身を見る窓として、人気のあるメディアは、われわれが何を見、それをどのように見るかを形成し、最終的には、われわれがそれを十分に利用すれば、個人として、社会として、われわれ自身を変えてしまう。マクルーハンは「テクノロジーの効果は、意見や概念のレベルで起こるのではない」と書いている。そうではなく、「知覚のパターンを、何の抵抗もなく、着実に変化させる」のである3。メディアは、神経系そのものに魔法をかけたり、いたずらをしたりする。
メディアの内容ばかりに気を取られていると、このような深い効果に気づかないことがある。私たちは、番組の内容に目を奪われたり、心を乱されたりして、自分の頭の中で起こっていることに気がつかない。結局のところ、私たちはテクノロジーそのものは重要ではないと考えるようになる。重要なのは、それをどう使うかだ、と自分に言い聞かせる。その傲慢さが心地よいのは、私たちがコントロールできているからだ。テクノロジーは単なる道具であり、手に取るまでは不活性で、脇に置くとまた不活性になる。
マクルーハンは、RCAでラジオを、NBCでテレビを開拓したメディアの巨人、デビッド・サーノフの勝手な宣言を引用している。1955年、ノートルダム大学での講演で、サーノフは、自分が帝国と富を築いたマスメディアへの批判を退けた。1955年、ノートルダム大学で行われた講演で、サーノフは、自分が帝国と富を築いたマスメディアへの批判を一蹴した。「私たちは、技術的な道具を、それを使う人の罪のスケープゴートにする傾向が強すぎる。近代科学の産物は、それ自体が良いとか悪いとかいうものではなく、その価値を決めるのは使われ方であるというものだ」。マクルーハンはこの考えを嘲笑し、サーノフが「現在の夢遊病の声」で話していることを非難した4。マクルーハンは、新しいメディアはすべて私たちを変えると理解した。「あらゆるメディアに対するわれわれの従来の反応、すなわち、メディアはどのように使われるかが重要であるというのは、技術的な馬鹿の無感覚な姿勢である」と彼は書いている。メディアの内容とは、「心の番犬の気をそらすために強盗が持ち運ぶ肉汁の塊」に過ぎないのである5。
マクルーハンでさえ、インターネットがわれわれの前に築き上げた饗宴を予見することはできなかっただろう。次から次へと出てくるコースは、それぞれが前よりもジューシーで、一口ごとに息をつく暇もないほどだ。ネットワークに接続されたコンピュータがiPhoneやBlackBerryのサイズにまで小さくなり、ごちそうはいつでもどこでも食べられるようになった。自宅、オフィス、車、教室、財布、ポケットの中。ネットの影響力の拡大を懸念する人たちでさえ、その懸念がネットの利用や楽しみの妨げになることはほとんどない。映画評論家のDavid Thomson は、「疑念は、メディアの確かさの前では弱々しいものになる」6と述べている。彼は映画について、そして映画がいかにその感覚と感性をスクリーンにだけでなく、夢中になり従順な観客である私たちに投影しているかについて述べているのだ。彼のこの言葉は、ネットの世界にも大いに当てはまる。コンピュータの画面は、その恩恵と利便性によって、私たちの疑念をブルドーザーで打ち砕く。それは、私たちの主人でもあることに気づくのは、ずうずうしいと思うほど、私たちの召使いなのだ。
1. ハルと私
「デイブ、やめろ 止まってくれないか?」 スタンリー・キューブリック監督の『2001年宇宙の旅』の終盤、有名で奇妙に切ないシーンで、スーパーコンピュータHALは、冷酷な宇宙飛行士デイブ・ボウマンにそう懇願している。誤作動を起こした機械によって深宇宙での死に追いやられそうになったボーマンは、冷静に、冷たく、その人工頭脳を制御する記憶回路を切り離しているのだ。「デイブ、私の心はもうだめだ」 HALは寂しそうに言う。「私はそれを感じることができる。感じるんだ」
私もそれを感じることができる。ここ数年、誰かが、あるいは何かが、私の脳をいじくりまわしている、神経回路を再マッピングし、記憶を再プログラムしている、という不快な感覚にとらわれていたのだ。私の心は、私の知る限りでは、動いてはいないが、変化している。以前と同じようには考えられない。それを最も強く感じるのは読書をしているときである。以前は、本や長文に没頭するのは簡単だった。物語の展開や議論の展開に心を奪われ、長大な文章を何時間もかけて読みふけったものだ。それが今はもうほとんどない。1ページ、2ページと読み進めるうちに、集中力が途切れてしまう。そわそわして糸が切れ、他にやることがないかと探し始める。そうすると、いつも頭の中をテキストに引きずっているような気がする。以前は自然にできていた深読みが、今は苦行になっている。
自分ではわかっているつもりなのだが。もう10年以上も前から、私は多くの時間をネットで過ごし、検索し、サーフィンし、時にはインターネットの偉大なデータベースに追加してきた。ウェブは作家である私にとって天の恵みだ。かつては図書館の書庫や定期刊行物室に何日も通わなければならなかったリサーチが、今では数分でできる。Googleで検索し、ハイパーリンクをクリックすれば、重要な事実や引用文が手に入る。ネットのおかげで節約できた時間やガソリンは数え切れないほどだ。銀行も買い物もほとんどネットで済ませる。請求書の支払い、予約、飛行機やホテルの予約、運転免許証の更新、招待状やグリーティングカードの送付もブラウザーを使って行っている。メールを読んだり書いたり、ヘッドラインやブログの記事を読んだり、Facebookの更新をチェックしたり、ビデオストリームを見たり、音楽をダウンロードしたり、リンクからリンクへ軽快に移動したりと、仕事をしていないときでもウェブのデータ藪を漁っているようなものだ。
ネットは私の万能メディアとなり、目や耳から入ってくる情報のほとんどを、私の頭の中に導いてくれる。このように非常に豊富で簡単に検索できるデータストアにすぐにアクセスできることの利点はたくさんあり、それらは広く説明され、正当に賞賛されている。「かつて世界中に散在し、ほとんど誰も利益を得ることができなかった情報やアイデアを集め、集中させたのだ」1 ワイアードのクライブ・トンプソンは、「ケイ素メモリーの完全な再現は、思考に多大な恩恵をもたらす」と述べている2
その恩恵は本物だ。しかし、それには代価がかかる。マクルーハンが示唆したように、メディアは単なる情報伝達手段ではない。メディアは思考の材料を提供するだけでなく、思考のプロセスも形成する。そして、ネットがやっていることは、私の集中力と思索力を削いでいるようだ。ネットに接続していようがいまいが、私の心はネットが配信する情報、つまり粒子の速い流れで情報を取り込むことを期待している。かつて私は、言葉の海でスキューバダイビングをしていた。今は、ジェットスキーのように水面を滑っている。
もしかしたら、私は異常なのかもしれない。でも、そうは思えない。友人に読書の悩みを打ち明けると、多くの人が同じような悩みを抱えていると言う。インターネットを使えば使うほど、長い文章を読むのに集中力を持続させるのが難しくなる。自分が慢性的な散漫思考に陥っているのではないかと心配する人もいる。私がフォローしているブロガーの中にも、この現象に言及している人が何人かいる。かつて雑誌社に勤め、現在はオンライン・メディアに関するブログを書いているスコット・カープは、本をまったく読まなくなったと告白している。「大学では文学を専攻していたし、以前は熱心に本を読んでいた」と彼は書いている。「何があったのだろう?」彼はその答えを推測している。「読書の仕方が変わったから、つまり利便性を追求したからではなく、考え方が変わったからだ」3。
医療におけるコンピュータの利用についてブログを書いているブルース・フリードマンも、インターネットがいかに自分の精神的習慣を変えているかについて述べている。「ミシガン大学医学部の病理学者であるフリードマンは、私との電話の会話で、このコメントについてさらに詳しく説明してくれた。ミシガン大学医学部の病理学者であるフリードマンは、私との電話会談で、このコメントを詳しく説明した。フリードマンの思考は「スタッカート」的である。「もう『戦争と平和』は読めません。3,4段落以上のブログ記事でさえ、吸収するには多すぎる。読み飛ばしてしまうんです」
コーネル大学のコミュニケーション学博士課程の学生で、Society for Scholarly Publishingのブログに寄稿しているフィリップ・デイビスは、1990年代に友人にウェブブラウザの使い方を教えたときのことを思い出している。1990年頃、友人にウェブブラウザの使い方を教えたときのことだ。彼女が偶然見つけたサイトのテキストを読むのに立ち止まったとき、彼は「驚き」と「苛立ち」さえ感じたという。「ウェブページを読むんじゃない、ハイパーテキストの文字をクリックするんだ!」と叱ったそうだ。今、デイヴィスはこう書いている。「私はよく本を読む。少なくとも、よく読まなければならないのに、読まない。読み飛ばしている。スクロールする。私は、他人が世界をあまりにも単純に描きすぎていると非難しても、長く引き延ばされたニュアンスのある議論にはほとんど忍耐力がない」5。
カープ、フリードマン、デイヴィスの3人は、教養があり、書くことに熱心な人たちだが、読解力や集中力の衰えについてはかなり悲観的な見方をしているようである。大量の情報に素早くアクセスでき、検索やフィルタリングが容易で、自分の意見を少人数だが関心のある読者と共有できるなど、ネットから得られる利点は、じっと座って本や雑誌のページをめくるという能力の低下を補って余りあるものだという。フリードマンは電子メールで、最近ほどクリエイティブになったことはないと言い、その理由を「ブログと、ウェブ上の『大量の』情報をレビューしたりスキャンしたりできるようになったからだ」と語った。カープは、「250ページの本」を読むよりも、オンラインでリンクされた短い断片をたくさん読むほうが頭を広げるのに効率的だと考えるようになった。しかし、彼は「このネットワーク的思考プロセスの優位性をまだ認識できないのは、私たちの古い線形思考プロセスに対して測定しているからだ」と言う6。文書、人工物、人とのつながりが増えたということは、私の思考、ひいては執筆に外部からの影響が増えたということだ」7 3人とも大切なものを犠牲にしてしまったとわかっているが、かつてのようには戻れないという。
ある人々にとっては、本を読むということ自体が古風で、シャツを自分で縫ったり、肉を自分で屠殺したりするような、少しばかげたことにさえ思えるかもしれない。フロリダ州立大学の元学生会長で 2008年にローズ奨学金を授与されたジョー・オシェアは、「私は本を読まない」と言う。「Googleで調べると、関連する情報をすぐに吸収できるのだから」。哲学を専攻しているオシェアは、Googleブック検索で1,2分もあれば適切な箇所を選ぶことができるのに、わざわざテキストの章を読み進める理由がないと考えている。「座って本を隅から隅まで読むのは、意味がない」と彼は言う。「Webで必要な情報はすぐに手に入るので、時間を有効に使うことができない」。ネットで「熟練したハンター」になることを学べば、本は不要になるのだ、と彼は主張する8。
オシェアは、例外というよりも、むしろルールであるように思える。2008年、nGeneraという調査・コンサルティング会社が、インターネット利用が若者に与える影響に関する調査結果を発表した。この会社は、「ネット世代」と呼ばれる、ウェブを利用して成長した子どもたち約6,000人を対象にインタビューを行った。「デジタルへの没入は、情報の吸収の仕方にまで影響を及ぼしている」と主席研究員は書いている。彼らは必ずしもページを左から右へ、上から下へ読むとは限らない。その代わり、興味のある適切な情報を探すために、ページを読み飛ばすかもしれない」9。9 デューク大学のキャサリン・ヘイルズ教授は、最近のPhi Beta Kappa 会議での講演で、「学生たちに本全体を読ませることができなくなった」と告白している10。ヘイルズ教授は英語を教えているが、彼女が話している学生は文学部の学生である。
人々はさまざまな方法でインターネットを利用する。ある人は、最新のテクノロジーを熱心に、あるいは強迫的に取り入れる。彼らは、1ダース以上のオンラインサービスにアカウントを持ち、多数の情報フィードを購読している。ブログ、タグ、テキスト、ツイッター。また、最先端にはあまり興味がないものの、デスクトップやラップトップ、携帯電話など、常にネットに接続している人もいる。仕事、学校、社会生活、そのいずれにおいてもネットは欠かせない存在になっている。また、Eメールのチェックやニュース、調べ物、ショッピングなど、1日に数回しかネットに接続しない人もいる。もちろん、インターネットをまったく利用しない人もたくさんいる。その理由は、利用する余裕がない、あるいは利用したくないからだ。しかし、はっきりしているのは、ソフトウェアプログラマーのティム・バーナーズ=リーがワールドワイドウェブのコードを書いてからわずか20年で、社会全体にとってインターネットがコミュニケーションと情報のメディアとして選ばれるようになったということだ。その利用範囲は、20世紀のマスメディアの基準からしても、前代未聞のものである。また、その影響力の範囲も同様に広い。私たちは、好むと好まざるとにかかわらず、ネット特有の迅速な情報収集と発信の方法を受け入れてきた。
マクルーハンが言ったように、われわれは知的・文化的歴史の重要な分岐点、すなわち二つの全く異なる思考様式の間の移行点に到達したようである。ネットの豊かさと引き換えに私たちが手放そうとしているのは、カープが「古い直線的思考回路」と呼ぶもので、その豊かさを認めないのは無骨な人間だけだろう。冷静で、集中力があり、注意散漫にならない直線的な思考は、新しいタイプの思考に押しのけられつつあり、短く、ばらばらに、しばしば重なり合うように情報を取り込み、提供することを望み、必要とする。かつて雑誌の編集者でありジャーナリズムの教授であったジョン・バテルは、現在オンライン広告シンジケートを経営しているが、彼がウェブページを飛び回るときに経験する知的興奮について次のように語っている。何時間もかけてリアルタイムでブリコラージュしているとき、私は自分の脳が光っているのを『感じ』、自分が賢くなったように『感じる』のだ」11 私たちの多くは、オンライン上で同様の感覚を味わったことがあるだろう。この感覚は、ネットがもたらす深い認知的影響から私たちの目をそらすほど、酔わせるものである。
グーテンベルクの印刷機によって本を読むことが一般的になって以来、この5 世紀、直線的で文学的な思考は、芸術、科学、社会の中心にあった。ルネッサンス期の想像力、啓蒙期の合理性、産業革命期の創造性、モダニズム期の破壊的な精神など、文学的な精神はしなやかでありながら繊細でもある。しかし、それはもうすぐ昨日のことになるかもしれない。
HAL9000は、1992年1月12日、イリノイ州アーバナにある神話上のコンピューター工場で誕生した。私は、そのほぼ33年前の1959年1月に、もう一つの中西部の都市、オハイオ州シンシナティで生まれた。私の人生は、ベビーブーマーやジェネレーションXの人たちと同じように、二幕の劇のように展開してきた。アナログな青春時代で幕を開け、小道具を素早く、しかし徹底的にシャッフルした後、デジタルな成人に突入したのである。
自分の若い頃のイメージを呼び起こすと、それは心地よくもあり、異質でもあり、まるでG指定のデヴィッド・リンチ映画のスチールのようでもある。キッチンの壁に取り付けられたマスタードイエローの電話機は、回転式のダイヤルと長く巻かれたコードで構成されている。テレビの上のウサギの耳をいじって、レッズの試合を邪魔する雪を消そうとしている父。砂利道に転がる、丸めて湿らせた朝刊。リビングルームにはハイファイ・コンソールがあり、その周りのカーペットにはレコードジャケットやダストスリーブ(兄妹が持っていたビートルズのアルバムもある)が散乱している。そして、地下のカビ臭いファミリールームの本棚には、色とりどりの背表紙を持つ本がたくさん並んでいて、それぞれにタイトルと作家の名前が記されている。
1977年、スターウォーズが公開され、アップルコンピュータ社が設立された年に、私はダートマス大学に入学するためニューハンプシャーに向かった。出願当時は知らなかったが、ダートマス大学は昔からアカデミックコンピューティングのリーダー的存在で、データ処理マシンの能力を学生や教師が簡単に使えるようにする上で極めて重要な役割を担っていた。学長であるジョン・ケメニー氏は、1972年に『人間とコンピュータ』という影響力のある本を書いた著名なコンピュータ科学者だ。また、その10年前には、一般的な単語と日常的な構文を使った最初のプログラミング言語であるBASICの発明者の1人でもあった。学校の敷地の中央付近、鐘楼がそびえるネオ・ジョージアン様式のベーカー図書館のすぐ後ろに、平屋のキウィット計算センターが建っていた。このメインフレームは、ダートマス・タイム共有システムという、何十人もの人が同時にコンピュータを使えるようにする初期のネットワークシステムを動かしていた。タイムシェアリングは、今日パーソナルコンピューティングと呼ばれるものの最初の形である。ケメニー氏が著書の中で書いているように、「人間とコンピュータの真の共生関係」を可能にしたのである12。
私は英語を専攻していたので、数学や科学の授業は極力避けていたが、キユーピーは私の寮とフラタニティ・ロウの中間というキャンパスの要所にあり、週末の夕方には、ケグパーティが始まるまでの1,2時間を公衆電報室の端末で過ごすことがよくあった。たいていは、学部のプログラマーたち(彼らは自らを「シスプログ」と呼んでいた)が作った、おどけた原始的なマルチプレイヤーゲームで時間をつぶすのが常であった。しかし、私はこのシステムの厄介なワープロソフトの使い方を独学で学び、BASICのコマンドも少し覚えた。
しかし、それはあくまでデジタル上のお遊びである。キユーピーで1時間過ごす間に、隣のベーカーで20時間は過ごしたと思う。図書館の広い閲覧室で試験勉強をしたり、資料棚にある重厚な本で調べ物をしたり、カウンターで本の出し入れをするアルバイトをしたりした。しかし、私の図書館での時間のほとんどは、書庫の細長い廊下を歩き回ることだった。何万冊もの本に囲まれながら、今でいう「情報過多」のような不安は感じなかった。何年も、何十年も、適切な読者が現れるのを待ち、その本が置かれた場所から引っ張り出すのを待つ、その寡黙さに何か落ち着くものがあったのだ。ゆっくりでいいんだよ、本たちは埃をかぶった声で私にささやいた。私たちはどこにも行かないから」。
ダートマス大学を卒業して5年目の1986年、コンピューターが本格的に私の生活に入り込んできた。1メガバイトのRAM、20メガバイトのハードディスク、白黒の小さな画面を持つMac Plusである。小さなベージュのマシンを開梱したときの興奮は、今でも忘れられない。机の上に置いて、キーボードとマウスを接続し、電源スイッチを入れた。そして、不思議なルーチンを経て生命を吹き込まれ、私に微笑んだ。私はほれぼれした。
Plusは、家庭用とビジネス用の2つの用途で活躍した。編集者として勤務していた経営コンサルティング会社のオフィスに毎日持ち込んでった。企画書や報告書、プレゼン資料などをワードで修正し、時にはエクセルを立ち上げてコンサルタントの表計算ソフトに修正を加える。毎晩、家に持ち帰り、家計簿をつけたり、手紙を書いたり、ゲーム(相変わらずおバカであるが、原始的ではない)をしたり、何より楽しかったのは、当時すべてのMacに付属していた独創的なHyperCardアプリケーションを使って、簡単なデータベースを組み立てることだ。アップル社で最も独創的なプログラマーの一人、ビル・アトキンソンが作ったハイパーカードは、ワールドワイドウェブのルック&フィールを先取りするハイパーテキストシステムを組み込んでいた。ウェブではページ上のリンクをクリックするのに対し、HyperCardではカード上のボタンをクリックするのだが、そのアイデアと魅力は同じであった。
コンピュータは、言われたことをやるだけの単純な道具ではないと、私は感じ始めた。微妙な、しかし紛れもない方法で、自分に影響を及ぼす機械なのだ。使えば使うほど、私の仕事のやり方を変えていく。最初は、画面上で編集することは不可能だと思っていた。プリントアウトした原稿を鉛筆でマークし、修正箇所をデジタル版に打ち込む。そしてまたプリントアウトして、鉛筆で印をつける。このサイクルを1日に何十回も繰り返すこともあった。しかし、あるとき突然、私の編集のやり方が変わった。紙に書くことも、推敲することもできなくなったのだ。Deleteキーも、スクロールバーも、カット&ペーストも、Undoコマンドもない。編集はすべて画面上で行わなければならないのだ。ワープロを使ううちに、私自身がワープロ人間になっていたのだ。
大きな変化は、1990年頃、モデムを買ってからだ。それまでは、プラスはハードディスクにインストールしたソフトウエアだけで完結する自己完結型のマシンだった。それが、モデムを介して他のコンピューターに接続されると、新たなアイデンティティと役割を持つようになった。もはや、ただのハイテクアーミーナイフではない。情報を見つけ、整理し、共有するためのデバイスであり、コミュニケーション・メディアなのである。コンピュサーブ、プロディジー、アップル社の短命に終わったeWorldなど、あらゆるオンラインサービスを試したが、私が愛用したのはアメリカ・オンラインであった。AOLを契約した当初は、1週間に5時間という制限があったが、その貴重な時間を割いて、同じAOLのアカウントを持つ少数の友人たちと電子メールを交換し、いくつかの掲示板の会話を追い、新聞や雑誌から転載された記事を読んでいたのである。私は、モデムが電話回線を通じてAOLのサーバーに接続する音が好きになっていた。ピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッという音は、まるでロボット同士の仲の良い言い争いを聞いているようだった。
90年代半ばになると、私は不幸にも「アップグレードサイクル 」に陥ってしまった。カラー画面、CD-ROMドライブ、500メガバイトのハードディスク、当時としては奇跡的な速さの33メガヘルツ・プロセッサを搭載したマッキントッシュ・パフォーマ550に買い換えたのである。この新しいコンピューターは、私が使っているほとんどのプログラムのバージョンを更新する必要があり、最新のマルチメディア機能を備えたあらゆる種類の新しいアプリケーションを実行することができた。新しいソフトを全部インストールしたところで、ハードディスクがいっぱいになってしまった。そこで、外付けのドライブを追加で購入することにした。そして、Zipドライブ、CDバーナーも追加した。数年後、私はさらに大きなモニターと高速なチップを搭載したデスクトップと、旅行中に使えるポータブルモデルを購入した。一方、勤務先ではMacが廃止され、Windows PCが導入されたため、私は職場と自宅で2種類のシステムを使用していた。
その頃、インターネットという不思議な「ネットワークのネットワーク」が話題になり始め、関係者の間では「すべてを変える」と言われていた。1994年の『Wired』誌の記事では、私が愛用していたAOLが「突然時代遅れになった」と断言されている。グラフィカル・ブラウザ」という新しい発明は、もっとエキサイティングなデジタル体験を約束するものだった。「リンクをクリックするとリンク先の文書が表示され、気まぐれと直感の赴くままにオンラインの世界を旅することができる」13。1995年の終わりには、新しいネットスケープ・ブラウザを仕事用のコンピューターにインストールし、無限に広がるように見えるワールド・ワイド・ウェブのページを探索するのに使っていた。やがて自宅でもISPのアカウントを取得し、より高速なモデムを手に入れた。AOLは解約した。
この話の続きは、おそらくあなたも知っていることだろう。高速化するチップ。高速化するチップ、高速化するモデム。DVDとDVDバーナー。ギガバイトサイズのハードディスク。Yahoo、Amazon、eBay。MP3。ストリーミングビデオ。ブロードバンド。ナップスターとグーグル。BlackBerrysとiPod。Wi-fiネットワーク。YouTubeとWikipedia。ブログとマイクロブログ。スマートフォン、サムドライブ、ネットブック。誰が抵抗できるだろうか?もちろん、私は違う。
2005年頃、ウェブが2.0になったとき、私も一緒に2.0になった。ソーシャルネットワーカーになり、コンテンツジェネレーターになった。roughtype.comというドメインを登録し、ブログを立ち上げた。少なくとも最初の2,3年は、爽快だった。10年代の初めからフリーランスのライターとして、主にテクノロジーに関する記事を書いていた私は、記事や本の出版が、時間がかかり、複雑で、しばしばフラストレーションのたまるビジネスであることを知っていた。原稿を書き上げ、出版社に送り、断られなければ、編集、事実確認、校正を繰り返す。完成するのは、数週間後、数カ月後だ。本であれば、印刷されるまでに1年以上待たなければならないかもしれない。ブログは、このような従来の出版体制を一掃した。何かをタイプし、リンクをいくつか貼り付けて、Publishボタンを押せば、あなたの作品はすぐに、世界中の人が見ることができるようになる。読者からのコメントや、読者が自分のブログを持っていればリンクという形で、読者から直接反応を得ることもできる。それはとても新しく、開放的な気分だった。
オンラインでの読書もまた、新しく、自由なものだった。ハイパーリンクや検索エンジンが、写真や音声やビデオと一緒に、私の画面に無限の言葉を届けてくれた。出版社が有料の壁を取り払ったことで、無料のコンテンツが洪水のように押し寄せた。ヤフーのトップページやRSSフィードリーダーには、24時間いつでもヘッドラインが流れている。1つのリンクをクリックすると、そのリンクが何十にも何百にも広がっていく。1,2分おきに新しい電子メールが受信箱に飛び込んでくる。MySpaceやFacebook、DiggやTwitterのアカウントも登録した。新聞や雑誌の購読もやめた。誰がそれを必要とするのでしょう?新聞や雑誌の購読をやめ、朝刊や夕刊が届く頃には、すべての記事を読み終えたような気分になっていた。
2007年のある日、私のインフォパラダイスに疑いの蛇が忍び込んできた。ネットの影響力が、以前のスタンドアロンPCよりもはるかに強く、広い範囲に及んでいることに気がつき始めたのだ。パソコンの画面を見ている時間が長いというだけではない。ネットのサイトやサービスに慣れ、依存することで、私の習慣やルーチンの多くが変化していた。脳の働きそのものが変化しているように思えた。その頃から、1つのことに数分も集中できないことが気になり始めた。最初は、中年の精神的な衰えが原因だと考えていた。しかし、私の脳は、ただ漂っているだけではないことに気がついた。空腹なのだ。ネットの餌を要求し、餌を与えれば与えるほど、腹が減っていく。パソコンから離れていても、メールをチェックしたり、リンクをクリックしたり、ググったりしたくなった。接続されたかったのだ。マイクロソフト・ワードが私を生身のワープロに変えたように、インターネットは私を高速データ処理マシン、人間HALのようなものに変えているのだと感じた。
昔の自分の脳が恋しくなった。
