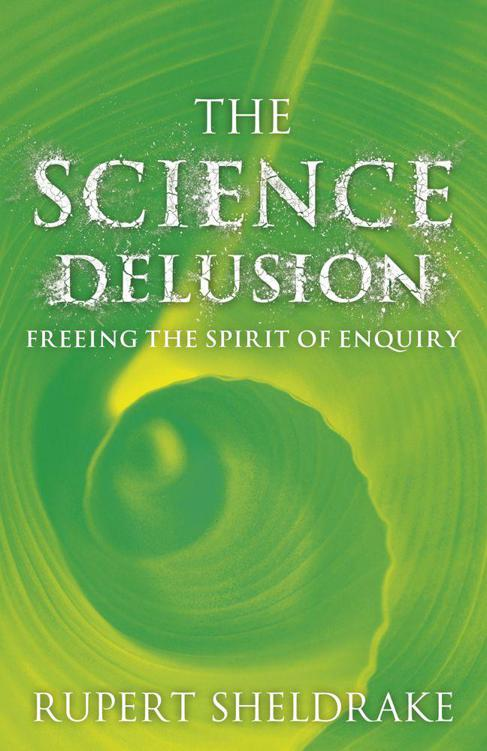
The Science Delusion
サイエンス・デリュージョン
探究心を解き放つ
ルパート・シェルドレイク
私を助け、励ましてくれたすべての人々、特に妻のジル、息子のマーリンとコスモに捧ぐ。
目次
- 序文
- はじめに
- プロローグ
- 1 自然は機械的か?
- 2 物質とエネルギーの総量は常に同じか?
- 3 自然の法則は固定されているのか?
- 4 物質は無意識か?
- 5 自然は無目的か?
- 6 生物学的遺産はすべて物質的か?
- 7 記憶は物質的な痕跡として保存されるのか?
- 8 心は脳に閉じ込められているのか?
- 9 心霊現象は幻想か?
- 10 機械論的医学は本当に効くのか?
- 11 客観性の幻想
- 12 科学の未来
- ノート
- 参考文献
- 索引
序文
私が科学に興味を持ったのは、幼い頃のことだ。子供の頃、私は毛虫やオタマジャクシから鳩、ウサギ、亀、そして犬まで、たくさんの種類の動物を飼っていた。薬草学者、薬剤師、顕微鏡技師であった父は、幼い頃から私に植物について教えてくれた。池の水滴の中の小さな生き物、蝶の羽のうろこ、珪藻の殻、植物の茎の断面図、暗闇で光るラジウムのサンプルなど、顕微鏡を通して不思議な世界を見せてくれたのである。植物を集め、コガネムシやカマキリ、ゲンジボタルなどの生態を記したファーブルの『昆虫記』など、自然史に関する本を読みあさった。12歳になるころには、生物学者になりたいと思っていた。
学校では科学を学び、ケンブリッジ大学では生化学を専攻した。しかし、研究対象は非常に狭く、もっと大きな視野で物事を見たいと思うようになった。ハーバード大学の大学院でフランク・ノックス・フェローシップを受け、科学の歴史と哲学を学び、視野を広げるという、人生を変えるような機会に恵まれた。
私はケンブリッジに戻り、植物の発生に関する研究を行った。博士課程では、植物の成長を制御する上で、死にかけた細胞が重要な役割を担っていることを発見し、「プログラム細胞死」というプロセスで細胞が壊れる際にオーキシンを放出することを明らかにした。成長する植物の内部では、新しい木質細胞が死ぬときに自己溶解し、そのセルロースの壁が、茎、根、葉脈で水を運ぶための微細な管として残る。私は、細胞が死ぬとオーキシンが生成されること、死んだ細胞がさらに成長を促すこと、さらに成長すると死が増え、その結果、さらに成長することを発見した1。
博士号を取得した後、私はケンブリッジのクレア・カレッジの特別研究員に選ばれ、細胞生物学と生化学の研究責任者として、個別指導や実験教室で学生を教えた。その後、王立協会の研究員に任命され、ケンブリッジで植物ホルモンの研究を続け、オーキシンが新芽から根の先端に輸送される過程を研究した。同僚のフィリップ・ルベリとともに、極性オーキシンの輸送の分子基盤を解明し、その後の植物の極性に関する多くの研究の基礎となった。
また、マラヤゴム研究所では、ゴムの木のラテックスの流れが遺伝的に制御されていることを発見し、ラテックス容器の発達に新たな光を当てた3。
ケンブリッジに戻った私は、人間を含む動植物の老化について、新しい仮説を立てた。すべての細胞は老化する。成長が止まれば、やがて死ぬ。私の仮説は「若返り」である。すべての細胞には有害な老廃物が蓄積され、老化が進むが、一方の細胞は老廃物の大半を受け取り絶望的になり、他方は一掃されるという非対称の細胞分裂によって若返った娘細胞を生み出すことができる、と提唱しているのである。すべての細胞の中で最も若返るのは卵子である。植物でも動物でも、2回の細胞分裂(減数分裂)によって卵細胞と3つの姉妹細胞が作られるが、これらはすぐに死んでしまう。私の仮説は、1974年に『ネイチャー』誌の「細胞の老化、成長、死」という論文で発表された4。「プログラム細胞死」、すなわち「アポトーシス」は、その後、がんやHIVなどの病気や、幹細胞による組織再生を理解する上で重要な研究分野となっている。多くの幹細胞は非対称に分裂し、若返った新しい幹細胞と、分化して老化し死んでいく細胞を作り出す。私の仮説は、細胞分裂による幹細胞の若返りは、その姉妹が死という代償を払うかどうかにかかっている、というものである。
私は視野を広げ、世界の最貧困層の人々のためになるような実用的な研究をしたいと考え、ケンブリッジを離れ、インドのハイデラバデラーハイドに近い国際半乾燥熱帯作物研究所で、主席植物生理学者としてヒヨコマメとキマメの研究に取り組んだ5。
その中で私は、動物の胚の発生や植物の成長を制御しているのは、形態形成場と呼ばれる形態形成の場であるという仮説を提案した。私は、これらの場には、形態共鳴と呼ばれるプロセスによって与えられる固有の記憶があることを提案した。この仮説は、入手可能な証拠によって支持され、さまざまな実験的検証が行われた。その結果は、新版『生命の新しい科学』(2009)にまとめられている。
インドからイギリスに戻った後も、私は植物の発生に関する研究を続けた。また、子どもの頃に飼っていたハトに興味を持ち、ホーミングハトの研究も始めた。ハトは何百キロも離れた場所、慣れない土地、さらには海を越えてどうやって家に帰ってくるのだろう?私は、鳩は目に見えないゴム紐のようなフィールドで家とつながっていて、家に向かって引っ張られているのではないかと考えた。磁気感覚はあっても、方角を知るだけでは故郷を見つけることはできない。コンパスをもって未知の土地にパラシュートで飛ばされたら、北の方角はわかるが、自分の家がどこにあるかはわからないだろう。
私は、ハトのナビゲーションは、動物が持つ多くの不可解な力のひとつに過ぎないと考えるようになった。また、テレパシーのように飼い主の帰宅時間を知ることができる犬もいる。これらのテーマについて研究することは難しくなく、お金もかからない。1994年、私は『世界を変える7つの実験』という本を出版し、現実の本質に関する私たちの考えを変えることができる低コストの実験を提案した。その結果は、新版(2002)、および拙著『飼い主の帰宅がわかる犬』(1999年、新版2011)『見つめられてる感』(2003)でまとめられた。
この20年間、私はサンフランシスコ近郊のノエティック・サイエンス研究所のフェローであり、コネチカット州の大学院を含むいくつかの大学の客員教授を務めている。私はこれまでに80以上の論文を査読付き科学雑誌に発表しており、そのうちのいくつかは『ネイチャー』誌に掲載された。また、実験生物学会や科学探査学会をはじめとするさまざまな学会に所属し、動物学会やケンブリッジ哲学協会のフェローでもある。イギリス、ヨーロッパ大陸、南北アメリカ、インド、オーストラレーシアのさまざまな大学、研究機関、科学会議で、自分の研究に関するセミナーや講演を行っている。
私は成人してからもずっと科学者として生きてきており、科学的アプローチの重要性を強く信じている。しかし、私は、科学がその活力、生命力、好奇心の多くを失っていることをますます確信するようになった。独断的なイデオロギー、恐怖に基づく順応性、組織的な惰性が、科学の創造性を阻害しているのだ。
科学者仲間と一緒にいて、私は何度も何度も、公の場と私的な場での議論のコントラストに驚かされた。公の場では、科学者は許される話題の範囲を制限する強力なタブーを強く意識しているが、プライベートでは、しばしばより冒険的な行動に出る。
私がこの本を書いたのは、科学は、自由な探求を制限し、想像力を封じ込めるドグマを超えたとき、よりエキサイティングで魅力的なものになると信じるからだ。
多くの人々が、議論、討論、論争、助言を通じて、このような探究に貢献してくれた。この本は、私を助け、励ましてくれたすべての人々に捧げます。
2005年から2010年までペロット・ウォリック上級研究員を務めたケンブリッジのトリニティ・カレッジ、アディソン・フィッシャーとプラネット・ヘリテージ財団、ワトソン・ファミリー財団とInstitute of Noetic Sciencesから、本書の執筆に必要な資金援助を受けていることを感謝している。また、研究助手のパメラ・スマートとウェブマスターのジョン・ケイトンには、多大な協力をいただいた。
本書は、草稿に対する多くのコメントから恩恵を受けた。特に、Bernard Carr、Angelika Cawdor、Nadia Cheney、John Cobb、Ted Dace、Larry Dossey、Lindy Dufferin and Ava、Douglas Hedley、Francis Huxley、Robert Jackson、Jürgen Krönig、James Le Fanu、Peter Fry、Charlie Murphy.に感謝したい。ジル・パース、アンソニー・ラムジー、エドワード・セント・オービン、コスモ・シェルドレイク、マーリン・シェルドレイク、ジム・スレーター、パメラ・スマート、ペギー・テイラー、クリストファー・ヴァン・トゥルケン、ニューヨークのエージェント、ジム・レヴィン、ホダー・アンド・ストートンの編集者、マーク・ブース、そして私の友人たちだ。
ブース
序文
現代科学の10のドグマ
「科学的世界観」が絶大な影響力を持つのは、科学がこれほどまでに成功を収めたからだ。科学は、技術や現代医学を通じて、私たちの生活のすべてに影響を及ぼしている。私たちの知的世界は、最も微細な物質の粒子から、何千億もの銀河が存在する広大な宇宙まで、知識の膨大な拡大によって変貌を遂げてきたのである。
しかし、21世紀も後半にさしかかり、科学技術の力が頂点に達し、その影響力が世界中に広がり、その勝利が揺るぎないと思われる頃、予期せぬ問題が科学を内側から崩壊させようとしているのである。多くの科学者は、これらの問題がいずれは既成の路線に沿ったより多くの研究によって解決されることを当然と考えているが、私を含む一部の科学者は、これらの問題はより深い倦怠の兆候であると考えている。
本書で私は、科学は何世紀も前から存在するドグマによって妨げられていると主張する。科学はドグマがなければもっと自由で、もっと面白く、もっと楽しいものになるはずだ。
科学的な最大の錯覚は、科学はすでに答えを知っているというものだ。細部はまだ解明されていないが、基本的な問題は解決されているというものだ。
現代の科学は、すべての現実は物質的または物理的であるという主張に基づいている。物質的な現実以外には、現実は存在しない。意識は脳の物理的活動の副産物である。物質は無意識である。進化は無目的である。神は人間の心の中の考えとして、つまり人間の頭の中にだけ存在する。
これらの信念が強力なのは、ほとんどの科学者が批判的に考えているからではなく、そうでないからだ。科学の事実は十分に現実的であり、科学者が使う技術も、それらに基づくテクノロジーもそうである。しかし、従来の科学的思考を支配している信念体系は、19世紀のイデオロギーに根ざした信仰行為である。
本書は親科学的である。私は科学が独断的でなく、より科学的であってほしいと願っている。科学が再生されるのは、科学を束縛するドグマから解放されたときだと信じているからだ。
科学的信条
科学者の多くが当たり前のように信じている10の信条を紹介しよう。
- 1. すべてのものは本質的に機械的である。例えば、犬は複雑な機械であり、自ら目標を持つ生物ではない。人間でさえも機械であり、リチャード・ドーキンスの鮮やかな表現を借りれば「のろまなロボット」であり、脳は遺伝的にプログラムされたコンピュータのようなものである。
- 2. すべての物質は無意識である。内面も主観も視点もない 人間の意識さえも、脳の物質的な活動によって生み出された幻想である
- 3. 物質とエネルギーの総量は常に同じである(宇宙のすべての物質とエネルギーが突然出現したビッグバンを除いては)
- 4. 自然界の法則は決まっている
- 5. 自然は無目的であり、進化には目標や方向性がない
- 6. 生物学的な遺伝はすべて物質的なものであり、遺伝物質であるDNAやその他の物質的な構造で運ばれる
- 7. 心は頭の中にあり、脳の活動にほかならない あなたが木を見ているとき、あなたが見ている木のイメージは、それがあるように見える「外」にあるのではなく、あなたの脳の中にある
- 8. 記憶は脳の中に物質的な痕跡として保存され、死とともに消去される
- 9. テレパシーのような不可解な現象は幻想である
- 10. 機械的な医学だけが、本当に効く医学である
これらの信念は合わせて唯物論の哲学やイデオロギーを構成している。その中心的な前提は、すべてのものは本質的に物質的または物理的であり、心でさえも物質的であるというものである。この信念体系は、19世紀後半に科学の世界で支配的になり、今では当然のこととされている。多くの科学者は、唯物論が思い込みであることに気づいていない。彼らはそれを単に科学、あるいは科学的現実観、科学的世界観と考えているのである。実際に教えられることもなければ、議論する機会もない。一種の知的浸透によってそれを吸収しているのである。
日常的には、唯物論は生き方の一つである
ラディカル・セプシシズムの精神に基づき、私はこれら10の教義をそれぞれ質問に変えてみた。疑う余地のない真実としてではなく、広く受け入れられている前提を探求の出発点としたとき、まったく新しい展望が開ける。例えば、自然は機械のようなもの、あるいは機械的なものであるという仮定は、「自然は機械的か」という問いになる。物質は無意識であるという仮定は、「物質は無意識か?」といった具合に。
プロローグでは、科学、宗教、権力の相互作用に注目し、第1章から第10章では、10のドグマをそれぞれ検証している。各章の終わりには、このテーマがどのような違いをもたらすのか、そしてそれが私たちの生き方にどのような影響を与えるのかを論じている。また、友人や同僚とこのテーマについて議論したい読者にとって、有益な出発点となるような質問をいくつか投げかけている。各章の後には、要約が掲載されている。
「科学的世界観」の信頼性低下
200年以上にわたって、唯物論者は、科学はやがて物理学と化学の観点からすべてを説明するようになると約束してきた。科学は、生物は複雑な機械であり、心は脳の活動に過ぎず、自然は無目的であることを証明してくれるだろう。信奉者たちは、科学的発見が自分たちの信念を正当化してくれるという信仰に支えられているのだ。科学哲学者のカール・ポパーは、このような姿勢を、まだ発見されていないものに対して約束手形を発行することに依存することから「約束物質主義」と呼んだ1。
1963年、ケンブリッジ大学で生化学を専攻していた私は、キングスカレッジのブレナーの部屋に招かれ、クラスメート数人とともに、フランシス・クリックとシドニー・ブレナーとの一連のプライベートミーティングに参加した。クリックとブレナーは最近、遺伝暗号を「解読」することに成功した。二人とも熱烈な唯物論者で、クリックは過激な無神論者でもあった。二人は、生物学には発生と意識という二つの大きな未解決の問題があると説明した。この2つの問題が未解決なのは、この問題に取り組んでいる人たちが分子生物学者ではなく、また、非常に優秀でもなかったからだ。クリックとブレナーは、10年か20年以内にその答えを見つけるつもりだった。ブレナーは発生生物学を、クリックは意識を、それぞれ担当することになった。二人は私たちを誘ってくれた。
二人ともベストを尽くした。ブレナーは、小さな虫である線虫(Caenorhabdytis elegans)の発生に関する研究で 2002年にノーベル賞を受賞している。クリックは 2004年に亡くなる前日、脳に関する最後の論文の原稿を添削していた。彼の葬儀の席上、息子のマイケルは、彼の心を動かしたのは、有名になりたいとか、裕福になりたいとか、人気者になりたいという欲求ではなく、「バイタリズムの棺桶に最後の釘を打ち込むこと」であったと語っている。(バイタリズムとは、生物は本当に生きていて、物理学や化学だけでは説明できないとする理論である)。
クリックとブレナーは失敗した。発生と意識の問題は未解決のままである。多くの詳細が発見され、何十ものゲノムの配列が決定され、脳スキャンはますます精度を増している。しかし、生命と心が物理学と化学だけで説明できるという証拠はまだない(第1章、第4章、第8章を参照)。
唯物論の基本的な命題は、物質が唯一の現実であるということである。したがって、意識とは脳の活動にほかならない。意識は、何もしない影のようなもの、「エピフェノメノン」だろうか、あるいは、脳の活動の別の言い方をしているに過ぎないのである。しかし、現代の神経科学や意識研究の研究者の間では、心の性質についてコンセンサスが得られていない。『Behavioural and Brain Sciences』や『Journal of Consciousness Studies』といった一流誌には、唯物論的教義の深い問題点を明らかにする論文が数多く掲載されている。哲学者のデイヴィッド・チャルマーズは、主観的経験の存在そのものを「難問」と呼んでいる。難しいというのは、それがメカニズムという観点からの説明を拒むからだ。目や脳が赤い光に反応する仕組みがわかっても、赤さの体験は説明できないのである。
生物学や心理学では、唯物論の信頼度は下がりつつある。物理学は救いの手を差し伸べることができるのか?唯物論者の中には、自分たちの希望が19世紀の物質理論ではなく、現代の物理学に依存していることを強調するために、自らを物理主義者と呼びたがる人がいる。しかし、物理主義の信頼度は、4つの理由から、物理学自身によって低下している。
第一に、一部の物理学者は、観測者の心を考慮に入れずに量子力学を定式化することはできないと主張している。彼らは、物理学は物理学者の心を前提にしているので、心を物理学に還元することはできないと主張している2。
第二に、最も野心的な物理的現実の統一理論である超ひも理論とM理論は、それぞれ10次元と11次元を持ち、科学を全く新しい領域へと導いている。不思議なことに、スティーブン・ホーキングが著書『グランド・デザイン』(2010)で語っているように、『「M」が何の略かは誰も知らないようだが、「マスター」「奇跡」「ミステリー」なのかもしれない』のである。ホーキング博士が「モデル依存の実在論」と呼ぶものによれば、異なる理論が異なる状況で適用されなければならないかもしれない。それぞれの理論が現実について独自の見解を持っているかもしれないが、モデル依存現実主義によれば、「理論が重なり合うとき、つまり両者を適用できるときはいつでも、その予測が一致する限り、それは容認される」3。
弦理論やM理論は現在のところ検証不可能なので、「モデル依存の実在論」は、実験によってではなく、他のモデルを参照することによってのみ判断することができる。また、これは無数の他の宇宙にも適用されるが、そのどれもが観測されていない。ホーキング博士が指摘するように
M理論には、内部空間の湾曲の仕方によって、異なる見かけ上の法則を持つ異なる宇宙を可能にする解がある。M理論には、多くの異なる内部空間、おそらく10^500もの内部空間を可能にする解があり、それは、それぞれが独自の法則を持つ10^500の異なる宇宙を可能にすることを意味する … … 私たちの宇宙の明白な法則を、いくつかの単純な仮定のユニークな可能性の結果として説明する単一の理論を作り出すという物理学の本来の希望は、放棄されなければならないかもしれない4。
理論物理学者のリー・スモリンは、著書『The Trouble With Physics』の中で、このアプローチ全体に深く懐疑的であることを示している。弦理論、M理論、そして「モデル依存の実在論」は、第1章で論じたように、唯物論や物理主義、あるいは他のいかなる信念体系にとっても、揺るぎない基盤となっているのだ。
第三に、21世紀に入ってから、既知の種類の物質とエネルギーは、宇宙の約4パーセントしか構成していないことが明らかになった。残りは「暗黒物質」と「暗黒エネルギー」とrkエナジーで構成されている。物理的現実の96パーセントの性質は、文字通り不明瞭である(第2章参照)。
第四に、宇宙人間原理は、ビッグバンの瞬間に自然界の法則や定数が少しでも違っていたら、生物は出現しなかったし、したがって、私たちはここでそれについて考えることもなかっただろうと主張している(第3章参照)。では、神が最初に法則や定数を微調整したのだろうか?創造主である神が新たな姿で現れるのを避けるために、ほとんどの主要な宇宙学者は、M理論も示唆するように、私たちの宇宙は、異なる法則と定数を持つ膨大な数の、おそらく無限の並行宇宙の一つであると考えることを好んでいる。私たちは、たまたま、私たちに適した条件の宇宙に存在しているに過ぎないのだ6。
この多元宇宙論は、「実体は必要以上に増殖してはならない」という哲学的原則である「オッカムの剃刀」、言い換えれば、「仮定はできるだけ少なくすべきである」という究極の違反行為であると言える。また、検証不可能という大きな欠点もある7。さらに、神を排除することにも成功していない。無限の神は、無限の宇宙の神である可能性があるのだ8。
19世紀後半、唯物論は一見シンプルでわかりやすい世界観を提供したが、21世紀の科学はそれを置き去りにした。唯物論は19世紀後半に一見単純明快な世界観を提供したが、21世紀の科学はそれを置き去りにした。その約束は果たされず、その約束手形はハイパーインフレで切り下げられたのである。
私は、科学は、強力なタブーによって維持され、ドグマとして硬化した仮定によって妨げられていると確信している。このような信念は、科学という城塞都市を守っているが、その一方で障壁となっている。
このように、科学は、ドグマとして固まり、強いタブーによって守られている。
プロローグ
科学、宗教、権力
19世紀後半から、科学は地球を支配し、変貌させた。科学はテクノロジーと現代医学を通じて、すべての人々の生活に浸透している。その知的威信はほとんど揺るぎないものである。その影響力は、人類の歴史の中で、他のどの思想体系よりも大きい。その力の大部分は実用的な応用から生まれるが、知的な魅力も強い。原子や分子の中心にある数学的秩序、遺伝子の分子生物学、宇宙進化の広大な範囲など、世界を理解するための新しい方法を提供しているのである。
科学的聖職者
フランシス・ベーコン(1561-1626)は、政治家・弁護士であり、イングランド大法官となったが、誰よりも組織化された科学の力を予見していた。そのためには、自然を支配する力を手に入れることは何も不吉なことではないことを示す必要があった。彼が執筆していた当時は、魔術や黒魔術に対する恐怖が広がっていた。彼は、自然に関する知識は神が与えたものであり、悪魔に感化されたものではないと主張し、それに対抗しようとしたのだ。科学とは、堕落する前のエデンの園にいた最初の人間アダムの無垢な姿に戻ることだったのだ。
ベーコンは、聖書の最初の書物である創世記が科学的知識を正当化すると主張した。彼は、人間が自然について知ることを、アダムが動物に名前をつけることと同一視した。神は、「アダムが彼らを何と呼ぶか見るために、彼らをアダムのもとに連れて来た。アダムがすべての生き物を何と呼んだか、それがその名前であった」(創世記2:19-20)。(創世記2:19-20)これは文字通り人間の知識であり、イブが創造されたのはその2節後だからだ。ベーコンは、人間が自然を技術的に支配することは、新しいことではなく、神から与えられた力の回復であると主張した。ベーコンは、人間が新しい知識を賢く上手に使うことを確信していた。「ただ、人類が、神の遺贈によって与えられた自然に対する権利を回復するように。その行使は、健全な理性と真の宗教によって支配されるだろう」1。
自然に対するこの新しい力の鍵は、組織化された組織的研究であった。ベーコンは『ニュー・アトランティス』(1624)の中で、科学的聖職者が国家全体の利益のために意思決定を行うテクノクラティック・ユートピアを描いている。この科学的な「教団または協会」のフェローたちは長いローブを身にまとい、その権力と威厳が必要とする敬意をもって扱われた。教団の長は、金色に輝く太陽の像の下を、豪華な馬車で移動していた。彼は行列に乗るとき、「民衆を祝福するように、素手を挙げて行った」
この財団の一般的な目的は、「物事の原因と秘密の動きを知ること、そして人間の帝国を拡大し、あらゆることを可能にすること」であった。協会は、爆発物や軍備をテストするための機械や施設、実験炉、植物育種用の庭園、診療所などを備えていた2。
この先見性のある科学施設は、制度研究の多くの特徴を予見させ、1660年にロンドンで設立された王立協会や他の多くの国立科学アカデミーの直接的なインスピレーションとなった。しかし、これらのアカデミーのメンバーはしばしば高い評価を受けたが、ベーコンが想像した原型のような壮大さと政治的な権力を獲得した者はいなかった。彼らの栄光は、死後も殿堂のようなギャラリーでその姿が保存され、継続された。価値のあるすべての発明には、発明者の銅像を建て、自由で名誉ある報酬を与えるからである」3。
ベーコンの時代のイギリスでは(現在もそうだが)、英国国教会は、国教会として国家と結びついていた。ベーコンは、科学者の聖職者もまた、国家の庇護のもとに国家と結びつき、一種の科学の確立した教会を形成することを想定していたのである。そして、ここでも彼は予言的であった。資本主義国でも共産主義国でも、公的な科学アカデミーは依然として科学界の権威の中心である。科学と国家の分離はない。科学者は、確立された聖職者の役割を果たし、戦争、産業、農業、医学、教育、研究などの芸術に関する政府の政策に影響を与える。
ベーコンは、政府や投資家から財政的支援を得るための理想的なスローガンを作り上げた。しかし、科学者が政府から資金援助を引き出すことに成功するかどうかは、国によって異なる。19 世紀後半まで、ほとんどの研究は私費か、チャールズ・ダーウィンのような裕福なアマチュアによって行われていたイギリスやアメリカよりも、フランスやドイツではずっと早くから科学への国家的な資金提供が始まっていたのである5。
フランスでは、ルイ・パスツール(1822-95)が、科学は真理を探究する宗教であり、研究所は人類が最高の潜在能力を発揮するための神殿のようなものであると主張し、大きな影響力をもっていた。
私たちが研究所という表現で呼んでいる神聖な施設に、どうか関心を持ってみよう。それらは富と未来の神殿なのである。そこでは、人類が成長し、より強く、より良くなっていくのです」6。
20世紀初頭までに、科学はほぼ完全に制度化、専門化され、第二次世界大戦後は政府の庇護のもと、また企業の投資によって膨大な発展を遂げた7。熱帯雨林のカブトムシの絶滅危惧種を分類するように、動物に名前をつけることは、優先順位が低い。ほとんどの資金援助は、ベーコンの「知識は力なり」という説得力のあるスローガンに応えるものである。
1950年代になると、組織的な科学がかつてないほどの権力と名声に達したとき、科学史家のジョージ・サートンは、まるで宗教改革以前のローマカトリック教会のような言い方で、この状況を肯定的に表現している。
真理は専門家の判断によってのみ決定されうる。真実は専門家の判断によってのみ決定される……すべては非常に小さなグループによって、実際には一人の専門家によって決定され、その結果は慎重に他の数名によってチェックされる。国民は何も言うことができず、ただ渡された決定を受け入れるだけである。科学的活動は、大学、アカデミー、科学協会によって管理されているが、このような管理は、民衆の管理から可能な限りかけ離れているのである9。
科学的聖職者というベーコンの構想は、今や世界的な規模で実現されている。しかし、自然に対する人間の力が「健全な理性と真の宗教」によって導かれるという彼の確信は、見当違いであった。
全知全能のファンタジー
全知全能という幻想は、科学者が神のような知識の総体を目指すという意味で、科学史に繰り返し登場するテーマである。19世紀初頭、フランスの物理学者ピエール=シモン・ラプラスは、すべてを知り、予測することのできる科学的頭脳を想像した。
自然を支配するすべての力と、自然を構成するすべての実体の瞬間的な状態を、どの瞬間にも知ることができる知性を考えてみよう。この知性が、これらのデータをすべて分析にかけるほど強力であれば、宇宙で最も大きな天体の動きも、最も軽い原子の動きも、一つの公式の中に取り込むことができるだろう。この知性の目には、過去も未来も等しく映っている。
このような考えは、物理学者だけにとどまらない。10 ダーウィンの進化論を広めたトーマス・ヘンリー・ハクスリーは、機械的決定論を進化のプロセス全体にまで拡大したのである。
もし進化の基本的な命題が真実で、生きているものも生きていないものも含めた世界全体が、宇宙の原始的な星雲が構成されていた分子が持っていた力が、明確な法則に従って相互に作用した結果であるとすれば、既存の世界が潜在的には宇宙の蒸気の中にあったことは間違いなく、その蒸気の分子の特性に関する知識から、十分な知性が、例えば1869年のイギリスの動物相の状態を予測することができただろう 11。
決定論が人間の脳の活動に適用されたとき、脳の分子的、物理的活動に関するすべてが原理的に予測可能であるという理由で、自由意志が否定されることになったのである。しかし、この確信は科学的な証拠に基づくものではなく、すべてが数学的法則によって完全に決定されているという仮定に基づくものであった。
今日でも、多くの科学者が自由意志は幻想だと考えている。脳の活動が機械のようなプロセスで決定されるだけでなく、機械的でない自己は選択することができないからだ。例えば、2010年、イギリスの脳科学者パトリック・ハガードは、「神経科学者として、あなたは決定論者でなければならない」と断言した。脳内の電気的、化学的事象には物理法則があり、それに従う。同じ状況であれば、それ以外のことはあり得ない。「そうでないことをしたい」と言える「私」は存在しないのである。12 しかし、ハガードは自分の科学的信念を私生活に干渉させない。「私は科学と私生活をかなり分けて考えている。観に行く映画は今でも自分で決めているようで、脳のどこかで決まっているのだろうけど、運命的なものだとは思っていない」
非決定論と偶然性
1927年、量子物理学における不確定性原理の認識により、物理世界の本質的な特徴は不確定性であり、物理的な予測は確率でしか行えないことが明らかにされた。その理由は、量子現象が波動的であり、波動はその性質上、時空間に広がっているため、ある瞬間にある一点に局在することができず、より厳密に言えば、その位置と運動量がともに正確に知ることができないからだ13。量子論は、統計的確率を扱うものであり、確実なものではない。量子事象の中で、ある可能性が他の可能性よりも高く実現されることは、偶然の産物なのである。
量子的な非決定性は自由意志の問題に影響を与えるか?不確定性が純粋にランダムなものであるならば、そのようなことはない。ランダムに行われる選択は、完全に決定されている場合よりも自由ではない14。
ネオ・ダーウィンの進化論では、遺伝子の突然変異という量子的な事象を通じて、ランダム性が中心的な役割を担っている。新ダーウィン進化論では、遺伝子の突然変異という量子的な偶然性が中心的な役割を果たす。T. H. Huxleyは、進化の過程が予測可能であると信じたのは間違いだった。進化生物学者のスティーブン・ジェイ・グールドは、「生命のテープを再生してみれば、今日の地球は別の生存者たちによって彩られているだろう」と述べている15。
20世紀には、量子過程だけでなく、液体の乱流、海岸の波の砕け方、天気など、ほとんどすべての自然現象が確率的であることが明らかとなった。気象予報士は、強力なコンピューターと人工衛星からの連続的なデータを持っているにもかかわらず、いまだに間違いを犯すことがある。これは、彼らが悪い科学者だからではなく、気象が本質的に細部まで予測できないものだからだ。秩序がないという意味ではなく、正確に予測できないという意味で、天気はカオスなのだ。「カオス理論」とも呼ばれるカオス力学の観点から、ある程度、気象を数学的にモデル化することができるが、これらのモデルは正確な予測をすることはできない16。量子物理学と同様に、日常的な世界においても、確実な予測は不可能である。長い間、機械論的科学の中心的存在と考えられてきた太陽の周りの惑星の軌道でさえ、長い時間スケールではカオス的であることが判明しているのだ17。
19世紀から20世紀初頭にかけて、多くの科学者が強く信じていた決定論は、結局は妄想であったことが判明した。科学者たちがこのドグマから解放されたことで、自然全般、特に進化における非決定性を新たに認識するようになったのである。科学は、決定論への信仰を捨てることで終焉を迎えたのではない。同様に、科学は、いまだ彼らを縛っているドグマを失っても生き残り、新たな可能性によって再生されるだろう。
全知全能のさらなる幻想
19世紀の終わりには、科学的全知全能の幻想は決定論への信仰をはるかに超えていた。dicpsOldsF1888年、カナダ系アメリカ人の天文学者サイモン・ニューコムは、「私たちはおそらく天文学について知り得ることの限界に近づいている」と書いている。1894年、後にノーベル物理学賞を受賞するアルバート・マイケルソンは、『物理科学のより重要な基本法則と事実はすべて発見されており、これらは現在非常にしっかりと確立されているので、新しい発見の結果としてこれらに取って代わられる可能性は極めて低い …… 』と宣言している。1900年には、物理学者であり大陸間電信の発明者でもあるケルビン卿、ウィリアム・トムソンが、しばしば引用される(おそらく偽書だろうが)主張の中でこの最高の自信を表現している:「今、物理学で発見される新しいものは何もない。あとは、もっともっと精密に測定するだけだ」
20世紀には、量子物理学、相対性理論、原子爆弾や水素爆弾に代表される核分裂や核融合、私たちの銀河系を超える銀河の発見、ビッグバン理論(約140億年前に非常に小さく非常に熱い宇宙が始まり、それ以来成長、冷却、進化を続けているという考え)などが現れ、これらの信念は打ち砕かれたのである。
しかし、20世紀末になると、20世紀の物理学の勝利と神経生物学や分子生物学の発見によって、全知全能という幻想が再び煽られるようになったのである。1997年、サイエンティフィック・アメリカンのシニア・サイエンス・ライターであるジョン・ホーガンは、『科学の終焉』という本を出版した。1997年、『サイエンティフィック・アメリカン』誌のシニア・サイエンス・ライター、ジョン・ホーガンは、『科学の終わり:科学時代の黄昏における知の限界に直面する』という本を出版した。多くの著名な科学者にインタビューした後、彼は挑発的な論文を発表した。
科学を信じるならば、科学的発見の偉大な時代が終わったという可能性、いや、その可能性さえも受け入れなければならない。科学とは、応用科学ではなく、最も純粋で偉大な科学、つまり宇宙とその中での私たちの位置を理解しようとする人間の根源的な探求を意味するのだ。これ以上研究を続けても、偉大な発見や革命は生まれないかもしれない、しかし、その成果は漸進的、漸減的にしか得られないだろう19。
ホーガンは、DNAの構造のように、一度発見されたものは、それ以上発見され続けることはない、というのは確かに正しい。しかし、ホーガンは、従来の科学の信条が真実であることを当然のこととして受け止めていた。ホーガンは、最も基本的な答えはすでに知られていると考えていた。本書で紹介するように、これらの答えはすべて、より興味深く、実りある問題に置き換えることができる。
科学とキリスト教
17世紀の機械論的科学の創始者であるヨハネス・ケプラー、ガリレオ・ガリレイ、ルネ・デカルト、フランシス・ベーコン、ロバート・ボイル、アイザック・ニュートンは、皆、キリスト教徒であった。ケプラー、ガリレオ、デカルトはローマ・カトリック教徒であり、ベーコン、ボイル、ニュートンはプロテスタントであった。裕福な貴族であったボイルは、特別に敬虔で、インドでの布教活動に多額の私財を投じている。ニュートンは、聖書の研究に多くの時間とエネルギーを費やし、特に予言の年代測定に関心を持った。彼は、「審判の日」が2060年から2344年の間に起こると計算し、その詳細を『ダニエル書の予言と聖ヨハネの黙示録に関する観察』に記している20。
17世紀の科学は、宇宙は神によって知的に設計され、始められた機械であるというビジョンを打ち立てた。17世紀の科学は、宇宙を、神によって設計され、始められた知性的な機械として捉え、すべては神の心の中にあるアイデアである永遠の数学的法則によって支配されているとしたのである。この機械論的な思想は、第1章で述べたように、中世ヨーロッパで当然とされていたアニミズム的な自然観を否定するものであり、まさに革命的であった。17世紀まで、大学の学者やキリスト教の神学者たちは、宇宙は生きており、神の霊、つまり生命の息吹に貫かれていると教えていた。すべての植物、動物、そして人間には魂がある。星も、惑星も、地球も、天使のような知性に導かれた生きものである。
しかし、機械論はこれらの教義を否定し、自然界からすべての魂を追い出した。物質世界は文字通り無機質で、魂のない機械となった。物質は目的もなく、意識もなく、惑星や星は死んでしまった。物理的な宇宙の中で、機械的でない存在は人間の心だけであり、それは非物質であり、天使や神を含む霊的な領域の一部であった。しかし、ルネ・デカルトは、人間の心は、脳の中央付近の右半球と左半球の間にある松ぼっくりの形をした小さな器官、松果体(しょうかたい)で相互作用していると推測している21。
1633年にガリレオがローマの異端審問で裁かれたことを筆頭に、当初はいくつかの対立があったが、その後、科学とキリスト教は互いの同意のもとに次第に別々の領域に閉じ込められるようになった。少なくとも18 世紀末に過激な無神論者が台頭するまでは、科学の実践は宗教の干渉を受けず、宗教も科学との対立から解放されていた。科学の領域は、人体、動物、植物、星、惑星などの物質的な宇宙であった。宗教の領域は霊的なもので、神、天使、霊魂、人間の魂などである。神、天使、精霊、人間の魂などである。このように、科学と宗教は、多かれ少なかれ平和的に共存していたのである。20世紀後半になっても、スティーブン・ジェイ・グールドは、この取り決めを「一般的合意の健全な立場」として擁護している。彼はこれを「重なり合わない聖職者」の教義と呼んだ。科学の聖域は「経験的な領域:宇宙が何でできているか(事実)、なぜこのように機能するのか(理論)」をカバーする。宗教は、究極的な意味や道徳的価値に関する問題を扱う。
しかし、フランス革命(1789-99)の頃から、過激な唯物論者は、この二重のマギステリアの原則を否定し、知的に不正直なものとして、あるいは、心の弱い者の避難所と見なして、これを排除した。彼らはただ一つの現実、すなわち物質界を認めた。霊的な領域は存在しない。神、天使、精霊は人間の想像の産物であり、人間の心は脳の活動の一部または副産物に過ぎない。自然の機械的な営みに干渉する超自然的な機関も存在しなかった。科学の権威だけが存在する。
無神論者の信念
唯物論は19世紀後半に科学界を席巻し、ヨーロッパにおける無神論の台頭と密接に関係している。21世紀の無神論者は、先達と同様、唯物論の教義を単なる思い込みではなく、確立された科学的事実と受け止めている。
熱力学の第二法則に従って、宇宙全体が蒸気を出す機械のようなものだという考えと結びついた時、唯物論は哲学者バートランド・ラッセルが表現した陽気な世界観に行き着いたのである。
人間は、自分たちが達成しようとしている目的を全く予見していなかった原因の産物であり、その起源、成長、希望や恐れ、愛や信念は、原子の偶然の衝突の結果に過ぎないこと、どんな火も、どんなヒロイズムも、どんな激しい思考や感情も、個人の命を墓を超えて守ることはできないこと。時代のすべての労苦、すべての献身、すべての霊感、人間の天才の真昼の輝きは、太陽系の広大な死の中で消滅する運命にあること、人間の偉業の全神殿は、必然的に廃墟となった宇宙の瓦礫の下に埋没すること、これらすべてのことは、全く議論の余地がないわけではないにしても、非常にほぼ確実であり、これらを否定する哲学は立つことを望めないのである。これらの真理の足場の中でだけ、不屈の絶望の堅固な土台の上でだけ、今後、魂の住まいを建てることができるのだ23
これらの「真理」を信じている科学者がどれほどいるだろうか。疑問の余地なく受け入れている人もいる。しかし、多くの科学者が哲学や宗教的信念を持っているため、この「科学的世界観」は限定的であり、せいぜい半分の真実に過ぎないように思われるのだ。また、科学そのものも、進化論的宇宙論、量子物理学、意識研究などが、標準的な科学のドグマを古めかしく見せている。
科学と技術が世界を変えたことは明らかである。科学は、機械の製造、農業の収穫量の増加、病気の治療法の開発などに応用され、見事な成功を収めている。その威光は絶大である。17世紀のヨーロッパで始まって以来、機械論的な科学はヨーロッパ帝国やマルクス主義、社会主義、自由市場資本主義といったヨーロッパのイデオロギーを通じて世界中に広まっていった。経済や技術の発展を通じて、何十億という人々の生活に触れてきた。科学技術の伝道者たちは、キリスト教の宣教師たちの想像をはるかに超える成功を収めたのである。かつて、ある思想体系が全人類を支配したことはない。しかし、このような圧倒的な成功にもかかわらず、科学は依然としてヨーロッパの過去から受け継いだイデオロギー的な荷物を背負っている。
科学と技術は、それがもたらす明らかな物質的利益のために、ほとんどどこでも歓迎されており、物質主義の哲学はそのパッケージの一部となっている。しかし、宗教的な信念と科学的なキャリアを追求することは、意外な形で相互作用することがある。あるインドの科学者は 2009年に科学雑誌『ネイチャー』に次のように書いている。
インドでは、科学は知識の究極の形でもなければ、懐疑論の犠牲者でもない … … 30年以上研究科学に携わってきた私の観察によれば、インドの科学者の多くは、論文の発表や知名度の獲得といった専門的な事柄で成功を収めるために、神や女神の神秘的な力を呼び起こすことが目立っているようだ 24。
世界中の科学者は、勤務時間中は唯物論の教義がゲームのルールであることを知っている。少なくとも引退する前やノーベル賞を受賞する前であれば、公然とそれに挑戦するプロの科学者はほとんどいない。また、科学の威信をかけ、ほとんどの教養ある人々は、私的な意見がどうであれ、公の場では正統派の信条に従う用意がある。
しかし、科学者や知識人の中には、無神論者に深く傾倒し、唯物論哲学が彼らの信念体系の中心をなしている者もいる。少数派は、福音主義的な熱意で満たされた宣教師になる。彼らは自分たちを、科学と理性のために、迷信、宗教、信心深さの勢力と戦う昔ながらの十字軍だと考えている。このような厳しい対立軸を打ち出したいくつかの本は 2000年代にベストセラーとなった。サム・ハリスの『信仰の終焉:宗教、恐怖、理性の未来』(2004)、ダニエル・デネットの『呪縛を解く』(2006)、クリストファー・ハウンズの『神は偉大ではない:いかに宗教がすべてを毒するか』(2007)、リチャード・ドーキンスの『神の錯覚』(2006)などがあり、2010年までに英語で200万部、その他34カ国語で翻訳されている25。
しかし、唯物論だけを信じている無神論者はほとんどいない。その多くは世俗的なヒューマニストでもあり、神への信仰に代わって人間への信仰を抱いている。人間は科学を通して神のような全知全能に近づく。神は人類の歴史の流れに影響を与えない。人間は、理性、科学、技術、教育、社会改革などを通じて、自分たちの手で進歩を遂げてきた。
機械論的科学は、それ自体、人生に意味があるとか、人類に目的があるとか、進歩が必然であるとかいう根拠を与えない。それどころか、宇宙は究極的に無目的であり、人間の生活も同様であると主張する。バートランド・ラッセルが明らかにしたように、ヒューマニズムの信仰を取り除いた一貫した無神論は、希望の根拠がほとんどない殺伐とした絵を描く。しかし、世俗的ヒューマニズムはユダヤ教とキリスト教の文化の中で生まれ、キリスト教から人間の生命の重要性と将来の救いへの信仰を受け継いだ。世俗的ヒューマニズムは、多くの点でキリスト教の異端であり、人間が神に取って代わったのである26。
世俗的ヒューマニズムは、証明可能な事実よりも進歩に対する心強い信仰で無神論を取り囲むため、無神論を受け入れやすくしている。神による救済の代わりに、人間自身が科学、理性、社会改革を通じて人間の救済を実現するのだ27。
人間の進歩に対するこのような信仰を共有しているかどうかにかかわらず、すべての唯物論者は、自分たちの信念が真実であることがいずれは科学によって証明されると考えている。しかし、これもまた信仰の問題である。
ドグマ、信念、そして自由な探求
既成の信念に疑問を呈することは反科学的なことではなく、科学的知見そのものの中心である。科学の創造的な核心は、自由な発想による探究心である。理想を言えば、科学とはプロセスであり、立場や信念体系ではない。科学者が自由に新しい問いを立て、新しい理論を構築することで、革新的な科学が生まれる。
科学史家であるトーマス・クーンは、その影響力のある著書『科学革命の構造』(1962)の中で、「通常の」科学の時代には、ほとんどの科学者が、パラダイムと呼ぶ現実のモデルや質問の仕方を共有している、と論じている。支配的なパラダイムは、科学者がどのような種類の質問をすることができ、どのように回答することができるかを定義している。通常の科学は、この枠組みの中で行われ、科学者は通常、適合しないものを説明し去る。そして、異常な事実が蓄積され、ある危機を迎える。革命的な変化は、研究者がより包括的な思考と実践の枠組みを採用し、それまで異常として退けられていた事実を取り入れることができるようになったときに起こる。やがて、新しいパラダイムは、通常の科学の新たな局面の基礎となる28。
クーンは、科学の社会的側面に注目し、科学が集団的な活動であることを私たちに思い起こさせることに貢献した。科学者は、仲間集団の圧力や集団の規範に従う必要性など、人間の社会生活における通常の制約をすべて受けている。クーンの議論は主に科学史に基づいているが、科学社会学者は彼の洞察をさらに深め、実際に実践されている科学を研究し、科学者が支援のネットワークを構築し、資源や成果を利用して権力や影響力を増大させ、資金や名声、認知度を競う方法について考察してきた。
ブルーノ・ラトゥール著「サイエンス・イン・アクション」How to Follow Scientists and Engineers Through Society)」(1987)は、この伝統的な研究の中で最も影響力のあるものの一つである。ラトゥールは、科学者が日常的に知識と信念を区別していることを観察している。専門家集団の中にいる科学者は、自分たちの科学分野がカバーする現象について知っているが、ネットワークの外にいる人たちは歪んだ信念しか持っていない。科学者は自分の集団の外にいる人々について考えるとき、どうして彼らはまだそれほど非合理的でいられるのだろうとしばしば思う。
科学者が描く非科学者の姿は暗澹たるものとなる。少数の頭脳が現実とは何かを発見する一方で、大多数の人々は不合理な考えを持ち、少なくとも多くの社会的、文化的、心理的要因の虜となって、時代遅れの偏見に頑強に固執しているのだ。この図式の唯一の救いは、人々を偏見の囚人にしているこれらの要因をすべて取り除くことさえできれば、人々は皆、直ちに、何のコストもかけずに、科学者のように健全な心を持ち、現象を把握することができるということである。私たち一人ひとりのなかに眠っている科学者がいて、社会的・文化的条件を押しのけるまで目を覚まさない 29。
「科学的世界観」の信奉者にとって必要なのは、教育やメディアを通じて一般の人々の科学に対する理解を深めることである。
19世紀以来、唯物論への信仰は実に見事に広まり、何百万人もの人々が、科学そのものをほとんど知らないにもかかわらず、この「科学的」見解に改宗させられてきた。彼らはいわば、科学者が司祭である科学教会、あるいは科学主義の信奉者なのである。無神論者の著名な一般人であるリッキー・ゲルヴェイスは、2010年に『タイム』誌の「世界で最も影響力のある100人」に選ばれた際、このような態度を『ウォールストリートジャーナル』で表現している。ガーヴェイスはエンターテイナーであり、科学者でも独創的な思想家でもないが、無神論を支持するために科学の権威を借りている。
科学は真実を追求する。科学は真実を追求し、差別をしない。科学は真実を追求する。科学は謙虚である。知っていることは知っているし、知らないことも知っている。その結論と信念は、確固たる証拠、つまり常に更新され、アップグレードされる証拠に基づいているのである。新しい事実が現れても怒ることはない。知識の体系を受け入れるのである。伝統だからといって、中世の慣習にしがみつくことはない30。
ゲルヴェの理想化された科学観は、科学史や社会学の文脈からすると、絶望的にナイーブなものである。科学者を、資金や名声のために競争し、仲間からの圧力に縛られ、偏見やタブーに縛られた普通の人々ではなく、真実を求める開かれた人々として描いているのだ。とはいえ、ナイーブな話であるが、私はこの自由な探求の理想を真剣に受け止めている。本書は、この理想を科学そのものに適用してみる試みである。仮定を質問に変えることで、私は科学が本当に知っていること、知らないことを突き止めたいと考えている。私は、唯物論の核となる10の教義を、確かな証拠と最近の発見に照らして見ていく。私は、真の科学者は新しい事実が現れても怒らないだろうし、伝統的だからといって唯物論の世界観にしがみつくことはないだろうと考えている。
私がこのようなことをするのは、探究心が科学的思考を不必要な制限から常に解放してきたからだ
内面からであれ外面からであれ、不必要な制限から科学的思考を解放し続けてきたからだ。科学は、その成功の大きさゆえに、時代遅れの信念に押しつぶされているのだと、私は確信している。
第1章 自然は機械的か?
科学を学んだことのない多くの人は、科学者が動物や植物は機械であり、人間もロボットで、遺伝的にプログラムされたソフトウェアを持つコンピューターのような脳に制御されていると主張することに困惑している。人間は生物であり、動物や植物もそうであると考える方が自然なように思う。生物は自己組織的であり、自分自身を形成し維持し、自分自身の目的や目標を持っている。これに対して、機械は外部の人間の手によって設計され、その部品は外部の機械製造者によって組み合わされ、それ自身は何の目的も目標も持っていない。
近代科学の出発点は、旧来の有機的な宇宙観の否定であった。機械の比喩は、科学的思考の中心となり、非常に広範囲な結果をもたらした。ある意味では、それは非常に大きな開放感であった。新しい考え方が可能になり、機械の発明と技術の進化を促したのである。この章では、この考え方の歴史をたどり、それに疑問を投げかけるとどうなるかを説明する。
17世紀以前は、ほとんどの人が、宇宙は有機体のようなものであり、地球もそうであると当然のように考えていた。古典、中世、ルネサンス期のヨーロッパでは、自然は生きていると考えられていた。例えば、レオナルド・ダ・ヴィンチ(1452-1519)は、この考えを明確にした。「地球には植物の魂があり、その肉は大地であり、その骨は岩の構造であり、その呼吸と脈動は海の干満であると言うことができる」1 ウィリアム・ギルバート(1515-1519)。1 磁気の科学の先駆者であるウィリアム・ギルバート(1540-1603)は、自然界の有機的な哲学を明確にした。「私たちは、全宇宙が生動しており、すべての球、すべての星、そして気高い地球も、その始まりから自らの定めた魂に支配されており、自己保存の動機を持っていると考える」2
1543年に発表した革新的な天動説で、地球ではなく太陽を中心に据えたニコラス・コペルニクスでさえ、機械論者とは言えなかった。彼がこの変更を行った理由は、科学的であると同時に神秘的なものであった。彼は、太陽を中心に置くことで威厳が生まれると考えたのだ。
ある者は世界の光と呼び、またある者は魂と呼び、さらにある者は統治者と呼ぶに値しない。トレミグムプリウスは、これを目に見える神と呼んでいる。ソフォクレスの『エレクトラ』では「全能の者」と呼ばれている。そして実際、太陽はその王座に座り、自分の周りを回る惑星一家を導いている3。
コペルニクスの宇宙論における革命は、その後の物理学の発展に大きな刺激を与えた。しかし、1600年以降に始まった自然界の機械論への移行は、もっと急激なものであった。
何世紀にもわたって、自然のいくつかの側面について、すでに機械的なモデルが存在していた。例えば、イギリス西部のウェルズ大聖堂には、600年以上前に設置された天文時計が今もなお現役で活躍している。時計の文字盤には、地球の周りを回る太陽と月、そして星が描かれている。太陽の動きは1日の時間を表し、時計の内側の円は1カ月に1度回転する月を描いている。また、4分の1秒ごとに、馬上槍試合の騎士の模型が追いかけっこをしたり、男の模型がかかとで鐘をたたいたりして、来場者を楽しませている。
天文時計は、中国やアラブで作られ始めたもので、動力は水であった。1300年頃にヨーロッパで作られ始めた天文時計は、錘と脱進機で動く新しいタイプのものであった。これらの時計はすべて、地球が宇宙の中心にあることを前提としていた。しかし、宇宙が本当に時計仕掛けのようなものだとは誰も思っていなかったのだ。
生物というメタファーから機械というメタファーへの変化が、現在の科学を作り出した。星や惑星の動きは、生命や目的を持った魂や霊ではなく、非人格的な機械的原理によって支配されていたのだ。
1605年、ヨハネス・ケプラーは自身の研究計画を次のようにまとめた。私の目的は、天の機械が神聖な有機体ではなく、むしろ時計仕掛けに例えられるべきであることを示すことである……」さらに、この物理的な概念が、計算と幾何学を通してどのように示されるかを示す」4 ガリレオ・ガリレイ(1564-1642)は、「どうしようもなく不変の」数学的法則がすべてを支配していることに同意している。
時計は自己完結的に動くので、時計の例えは特に説得力があった。時計は、他の物体を押したり引いたりすることはないのだ。同様に、宇宙はその運動の規則性によって仕事を行い、究極の時を告げるシステムである。機械式時計には、さらに隠喩的な利点があった。それは、機械を組み立てることによって知識を得る、つまり「やって知る」ことの良い例となったことだ。機械を作ることができる人は、それを再構築することができる。機械的な知識は力であった。
機械論的科学の威信は、その哲学的基盤から来るものではなく、特に物理学における実践的成功から来るものであった。数学的モデリングは、極端な抽象化と単純化を伴うのが普通であり、人工の機械や物体で実現するのが最も簡単である。数学的力学は、大砲の玉やロケットの軌道のような比較的単純な問題を扱うのに、驚くほど有効である。
その典型的な例がビリヤードボールの物理学で、摩擦のない環境における理想的なビリヤードボールの衝突と衝撃を明確に説明するものである。数学が単純化されているだけでなく、ビリヤードの球自体も非常に単純化された系である。玉はできるだけ丸く、テーブルはできるだけ平らに作られ、テーブルの側面には一様なゴム製のクッションがあり、どんな自然環境とも異なる。比較のために、山の斜面に岩が落ちているのを思い浮かべてほしい。さらに、現実の世界では、ゲームの中でビリヤードの玉がぶつかったり跳ねたりしているが、ゲームのルールやプレイヤーの技量や動機は物理学の範囲外である。玉の挙動を数学的に解析するのは、極端な抽象化である。
生物から生物機械へ
機械的自然観は、17世紀のヨーロッパにおける壊滅的な宗教戦争の中で発展した。数理物理学が魅力的だったのは、宗派間の対立を越えて永遠の真理を明らかにする方法を提供するように思えたからだ。機械論的科学の先駆者たちは、自分たちの目には、自然と神との関係を理解する新しい方法を見つけたように映った。ガリレオはこう言っている。
神は世界を創造するとき、数、幾何学的図形、量的機能の法則に従った徹底的な数学的構造を作り出す。自然は具現化された数学体系なのだ」5。
しかし、そこには大きな問題があった。私たちの経験のほとんどは、数学的なものではない。私たちは食べ物を味わい、怒りを感じ、花の美しさを楽しみ、ジョークで笑う。数学の優位性を主張するために、ガリレオとその後継者たちは、運動、大きさ、重さなど数学的に記述できる「一次的性質」と呼ばれるものと、色や匂いなど主観的な「二次的性質」を区別する必要があった6。彼らは現実の世界を客観的、数量的、数学的なものと考え、生活世界における個人の経験は主観的であり、科学の領域外の意見と幻想の領域であるとした。
ルネ・デカルト(1596-1650)は、機械論的な自然哲学の主要な提唱者である。デカルトは、宇宙全体を数学的な体系として捉え、後に、エーテルと呼ばれる微細な物質が渦を巻く巨大な渦が惑星の軌道を取り囲んでいる様子を思い描くようになった。
デカルトは、ケプラーやガリレオよりもはるかに踏み込んで、機械的な比喩を生命の領域にまで拡大した。彼は、時計、織機、ポンプなど、当時の高度な機械に魅了されていた。少年時代には、スパニエルに追われるキジなど、動物の活動を模した機械模型を設計した。ケプラーが人工の機械のイメージを宇宙に投影したように、デカルトは動物にそれを投影した。犬の心臓の鼓動、消化、呼吸などの活動は、プログラムされたメカニズムである。犬の心臓の鼓動、消化、呼吸などの活動はプログラムされたメカニズムであり、人間の身体も同じ原理である。
デカルトは、生きた犬の心臓を調べるために切り刻み、その観察結果を読者が再現したくなるような形で報告した。「生きた犬の心臓の尖端を切り取って、その空洞の一つに指を差し込むと、心臓が短くなるたびに指を押し、長くなるたびに指を押さなくなることを、まぎれもなく感じるだろう」9。
まず、動物の動きを模倣した人工的なオートマタを想像し、それが十分によくできていれば、本物の動物と見分けがつかなくなるだろうと主張したのだ。
このような機械が、猿や理性を持たない他の動物の器官や外形を備えていたとしても、それらの動物と全く同じ性質を持っていないことを知る術はないはずである 10。
デカルトは、このような主張によって、今日でも正統的な機械論的生物学・医学の基礎を築いた。しかし、17世紀から18世紀にかけては、生命の機械論は、宇宙の機械論ほどには受け入れられなかった。特にイギリス・クライ・アイでは、動物機械の考え方はエキセントリックだと考えられていた11。デカルトの教義は、生体解剖を含む動物への残虐行為を正当化するように思われ、彼の信奉者のテストは、犬を蹴るかどうかだったと言われている12。
哲学者のダニエル・デネットは、「デカルトは……動物が実際に存在すると考えていた」と要約している。哲学者のダニエル・デネットが要約するように、「デカルトは……動物は実際には精巧な機械にすぎないと考えた。. . 人間(そして人間だけ)に知性と意識を与えているのは、機械的でない、非物理的な心だけである。これは実は微妙な見解で、そのほとんどは今日の動物学者なら容易に擁護できるものだが、デカルトの同時代の人々にとってはあまりに革命的なことだった」13。
私たちは、生命の機械論に慣れきっているので、デカルトがいかに抜本的な改革を行ったかを理解するのは難しい。当時の一般的な理論では、生物は生物であり、魂を持った生き物であることは当然とされていた。魂は生物に目的を与え、自己組織化する力を与える。中世から17世紀まで、ヨーロッパの大学で教えられる生命論の主流は、ギリシャの哲学者アリストテレスとそのキリスト教的解釈の第一人者トマス・アクイナス(1225-74年頃)に従ったもので、植物や動物の体内の物質は、その生物の魂によって形作られるとした。アクィナスにとって、魂は身体の形態であった14。魂は、植物や動物が成長する過程で形を整え、成熟した形態に引き寄せる目に見えない型のような働きをするものであった15。
動物や植物の魂は自然なものであり、超自然的なものではない。ギリシャや中世の古典哲学、そしてウィリアム・ギルバートの磁気理論によれば、磁石にも魂が宿っている16。磁石が加熱されて磁性を失うと、動物の死によって魂が離れるのと同じように、磁石から魂が離れるのだ。今、私たちは磁場という言葉で話をする。ほとんどの点で、磁場は古典的、中世的哲学における魂に取って代わる17。
機械論的革命以前は、肉体、魂、精神という3つのレベルの説明があった。身体と魂は自然の一部であった。精神は非物質的なものであるが、その魂を通じて体現された存在と相互作用する。キリスト教神学によれば、人間の精神、すなわち「理性的な魂」は、神の霊に対して潜在的に開かれていた18。
機械論的革命の後、説明のレベルは肉体と精神という 2 つだけとなった。機械革命の後、説明には肉体と精神の二層しかなかったが、自然から魂を取り除くことで三層が二層になり、人間の「理性的魂」または精神だけが残された。魂の廃止は、人類を他のすべての動物から分離し、無生物の機械とした。人間の「理性的な魂」は、人体という機械の中にいる非物質的な幽霊のようなものであった。
理性的な魂は、どのようにして脳と相互作用することができるのだろうか。デカルトは、その相互作用が松果体において起こるのだと推測した19。彼は、魂を松果体の中の小人が脳の配管を制御しているようなものだと考えた。彼は、神経を水道管に、脳の空洞を貯蔵タンクに、筋肉を機械のバネに、そして呼吸を時計の動きに例えた。身体の器官は17世紀の水庭のオートマタのようなものであり、内なる非物質的な人間は泉の番人のようなものである。
外界の物体は、ただそこにあるだけで感覚器官を刺激する。外界のものは、ただそこにあるだけで感覚器官を刺激する……それは、泉の洞窟に入り、知らず知らずのうちに目の前で起こっている動きを引き起こす訪問者のようなものだ。というのも、ある種のタイルを踏まずに入ることはできないので、たとえば、水浴びをしているディアナに近づくと、葦の中に隠れてしまうことになるからだ。そして最後に、理性的な魂がこの機械の中に存在するとき、それは脳に主席し、噴水の管理人のようにそこに留まり、もし彼が何らかの方法で噴水の動きを生み出したり、阻止したり、変化させようとするなら、噴水の管が戻ってくる水槽に配置されなければならない20。
機械論的革命の最終段階は、2 段階の説明を1 段階に減らすことであった。物質と心の二重性の代わりに、物質だけが存在するのだ。これが、19 世紀後半に科学的思考を支配するようになった唯物論の教義である。とはいえ、名目上の唯物論とはいえ、ほとんどの科学者は二元論者であり続け、二元論的な比喩を使い続けていた。
脳の中にいる小さな人間(ホムンクルス)は、身体と心の関係について考える一般的な方法として残っていたが、この比喩は時代とともに変化し、新しい技術に適応していった。20世紀半ば、ホムンクルスは通常、脳の電話交換機にいる電話交換手であり、1949年に出版された『生命の秘密』という本のように、映画館にいるかのように外界の映写された映像を見ていたのである。21 2010年にロンドンの自然史博物館で行われた「あなたが行動をコントロールする方法」という展示では、模型の人間の額にあるパースペックス製の窓から覗くことができた。内部にはダイヤルやコントロールが並ぶコックピット、そして2つの空席があり、おそらくパイロットであるあなたと、もう一方の半球にいる副パイロットのためのものだろう。機械の中の幽霊は明示的ではなく暗黙的であったが、脳の中にいる小さな男たちは、自分たちの脳の中に小さな男たちを抱え込むことになり、無限後退を繰り返すので、明らかにこれは全く説明のつかないことであった。
脳の中に小さな男女がいると考えるのがあまりにもナイーブに思えるのなら、脳そのものを擬人化すればよいのだ。心の本質に関する多くの一般的な論文や書籍は、「脳が知覚する」あるいは「脳が決定する」と述べているが、同時に脳はコンピューターのような単なる機械であると主張している22。例えば、無神論哲学者のアンソニー・グレイリングは、「脳が宗教や迷信的な信念を秘匿する」のはそうなるように「ハードワイヤー」されているためだと考える。
脳は「信念のエンジン」として、そこに流れ込む情報に意味を見出そうと常に努力している。いったん信念を構築すると、ほとんどの場合、その出来事を後にして、説明によってその信念を合理化する。こうして脳は信念に没頭し、裏付けとなる証拠を探しながら信念を強化し、それに反するものには目をつぶってしまう23。
これは、脳というよりも、心についての説明のように聞こえる。グレイリングは、心と脳の関係を問うだけでなく、自分の脳が、信念に反するものには目をつぶるという「生まれつきの」傾向からどのようにして逃れられたのかという問題も投げかけているのだ。実際には、機械論的理論は、機械論的でない心を人間の脳の中に密かに持ち込むからこそ、もっともらしく聞こえるのだ。科学者が唯物論的な理論を提唱するとき、機械論的に操作しているのだろうか?彼自身の目にはそう映らない。彼の議論には常に隠れた留保がある:彼は機械論的決定論の例外なのである。彼は、自分が真実の見解を提示しているのであって、単に脳がそうさせるようにしているのではないと信じている24。
一貫した唯物論者であることは不可能に思われる。唯物論は、多かれ少なかれ、薄く偽装された二元論の余韻に依存しているのである。生物学の領域では、この二元論が、以下に述べるように、分子を擬人化する形を取っている。
機械的自然の神
自然界の機械論は、現在では唯物論を支持するために使われているが、近代科学の創始者たちにとっては、キリスト教を破壊するのではなく、むしろ支持するものだったのである。機械は設計者がいて初めて意味をなす。例えば、ロバート・ボイルは、自然界の機械的秩序を、神の設計の証拠と見なした25。また、アイザック・ニュートンは、「機械学と幾何学に非常に長けている」神をイメージしていた26。
世界という機械がうまく機能すればするほど、神の継続的な活動は必要ではなくなっていったのである。18 世紀末には、天の機械は神の介入を必要とせず、完璧に機能すると考えられるようになった。科学的思考を持つ多くの知識人にとって、キリスト教は神学に道を譲ったのである。最高神が世界機械を設計し、創造し、動かして、自動的に動くようにした。この種の神は世界に介入しないので、神に祈る意味はない。実際、宗教的な行為には何の意味もなかった。ヴォルテールのような啓蒙主義の哲学者たちは、神学とキリスト教を否定することを結びつけた。
キリスト教を擁護する人の中には、機械論的科学の前提を受け入れることで、神学者に同調する人もいた。機械論的神学の最も有名な提唱者は、英国国教会の司祭であったウィリアム・ペイリーである。1802年に出版された彼の著書『自然神学』の中で、彼は、もし誰かが時計のような物体を見つけたとして、それを調べ、その複雑な設計と精度を観察すれば、「ある時間、ある場所に、私たちが実際に見つけ出した目的のためにそれを形成し、その構造を理解し、その使用を設計した人工の者が存在したに違いない」という結論を出すに違いない、と主張した27。目などの「自然の産物」についても同様で、神が設計者であった。
19 世紀のイギリスでは、英国国教会の聖職者たちが、ペイリーと同じ点を強調し、自然史に関する多くの一般向けの本を執筆した。例えば、フランシス・モリス牧師は『英国蝶の歴史』(1853)を書き、フィールドガイドとして、また自然の美しさを伝えるために、豪華な挿絵入りで人気を博した。モリスは、神がすべての人間の心の中に「自然に対する本能的な愛」を植え付けたと考え、これによって老いも若きも「温和な創造主が無限の知恵と全能の技術を駆使して見せる美しい光景」を楽しむことができると考えた28。
このような自然神学を、ダーウィンは自然淘汰による進化論で否定したのである。このような自然神学を、ダーウィンは自然淘汰による進化論の中で否定したのである。そうすることによって、後述するように、彼は生命の機械論そのものを台無しにした。しかし、ダーウィンが巻き起こした論争はいまだに続いており、その最新の形がインテリジェント・デザインである。インテリジェント・デザインの支持者は、脊椎動物の目やバクテリアの鞭毛のような複雑な構造を、一連のランダムな遺伝子変異と自然選択によって説明することは不可能ではないにせよ、困難であると指摘する。彼らは、複雑な構造や器官は、多くの異なる構成要素が創造的に統合されたものであり、それは知的に設計されたものであることを示唆している。しかし、その設計者は神であることは明白である。
デザイン論の問題点は、設計者というメタファーが、外的な心を前提にしていることである。人間は、機械、建物、芸術作品を設計する。同様に、機械論的神学の神、すなわちインテリジェント・デザイナーは、生物の細部をデザインしたものと考えられている。
しかし、私たちは偶然と外部の知性のどちらかを選択することを強いられてはいない。もう一つの可能性がある。生物は、私たち自身と同じように、内的な創造性を持っているのかもしれない。私たちが新しいアイデアを思いついたり、新しいやり方を見つけたりするとき、まずそのアイデアをデザインして、それを自分の頭の中に入れるということはしない。新しいアイデアはただ起こるものであり、誰もその方法や理由を知らない。人間には固有の創造性があり、すべての生物にも大なり小なり創造性があるのだろう。機械には外部の設計者が必要だが、生物には必要ない。
皮肉なことに、植物や動物のデザインは、キリスト教の伝統的なものではない。17世紀の科学に由来するものである。これは、聖書の創世記の第1章にある生命の創造の図と矛盾する。創世記1:11「そして神は言われた、地に草を生えさせ、草は種を蒔き、果樹はその種にしたがって実を結ぶように」とあるように、動物や植物は機械としてではなく、大地や海から発生した自己再生生物として描かれている。創世記1:24では、『神は言われた、地はその種類にしたがって生き物を、家畜を、這うものを、地の獣を、生み出すように』。神学的な言葉で言えば、これらは「媒介的」な創造の行為である。神はこれらの動植物を直接デザインしたり、創造したりはしなかったのである。権威あるローマ・カトリック聖書注解が表現しているように、神は「母なる大地の働きによって」間接的にこれらの動植物を創造したのである30。
自然が再び息を吹き返したとき
啓蒙主義の信奉者たちは、機械論的な科学、理性、人間の進歩に信頼を置いていた。「啓蒙主義」の思想や価値観は、今日でも、教育、社会、政治に大きな影響を及ぼしている。しかし、1780年から1830年にかけてのロマン主義運動では、啓蒙主義に対する反動が広まり、主に芸術や文学の分野で表現された。ロマン派は、理性とは対照的に、感情や美学を重視した。自然は機械的なものではなく、むしろ生きているものだと考えた。こうした考えを最も明確に科学に応用したのは、ドイツの哲学者フリードリッヒ・フォン・シェリングで、その著書『自然哲学のためのアイデア』(1797)は、自然を、対立する力と極性のダイナミックな相互作用として描き、それによって物質は「生かされている」31と述べている。
ロマン主義の中心的な特徴は、機械的な比喩を否定し、自然が生きており、有機的で、発育や発達の過程にあるというイメージに置き換えることであった32。
科学者、詩人、哲学者の中には、生きた自然という哲学を、機械論的神学の設計神というよりは創世記の神のように、自然に生命を吹き込み、自然発生に委ねた神と結びつけた者もいた。また、イギリスの詩人パーシー・シェリー(1792-1822)のように無神論者を自称する者もいたが、彼らは自然の中にある生きた力を疑い、それを宇宙の魂、あるいは万能の力、自然の精神と呼んでいた。また、動物を感覚を持つ存在として尊重し、ベジタリアニズムの先駆的な運動家でもあった33。
このような世界観の違いは、次のようにまとめられる
ロマン主義運動は、西洋文化に永続的な分裂をもたらした。教養ある人々、仕事、ビジネス、政治の世界では、自然は機械的なものであり、経済発展のために利用できる天然資源の無生物的な源であると考えられている。近代経済はこのような基盤の上に築かれているのである。一方、子どもたちは、おとぎ話やしゃべる動物、魔法のような変身など、アニミズム的な雰囲気の中で育つことが多い。詩や歌、芸術作品の中で、生物界は賛美される。自然は、都会とは対照的に、田舎と最も強く結びついており、特に手つかずの大自然によって認識されている。都会人の多くは、田舎に引っ越したい、あるいは田舎に週末用の家を持ちたいと夢見ている。金曜日の夕方、西欧諸国の都市では、何百万人もの人々が車で自然に戻ろうとするため、交通渋滞が発生する。
自然との私的な関係は、自然が生きていることを前提にしている。機械論的な科学者、技術者、経済学者、開発者にとって、自然は無機質で無生物である。自然は人間の進歩の一部として開発される必要があるのである。しかし、同じ人間でも、プライベートでは異なる態度をとることがよくある。西ヨーロッパや北アメリカでは、多くの人が自然を利用して金持ちになり、「すべてから逃れる」ために田園地帯に家を買うことができる。
このような公的な合理主義と私的なロマン主義の区分は、何世代にもわたって西洋の生活様式の一部となっていたが、次第に維持できなくなりつつある。私たちの経済活動は自然から切り離されたものではなく、地球全体に影響を及ぼしているのである。私たちの私的な生活と公的な生活はますます絡み合ってきている。このような新しい意識は、ガイア(母なる大地)に対する一般の人々の意識の復活によって表現されている。しかし、女神は、最も唯物論的な形であっても、科学的思考の表舞台から遠く離れてはいなかった。
進化論の女神たち
進化論の先駆者の一人は、チャールズ・ダーウィンの祖父であるエラスマス・ダーウィンで、彼は自然の重要性を高め、神の役割を縮小しようと考えた34。植物や動物の自然進化は、自然神学と設計者としての神の教義の根底を突いていた。動植物の自然進化は、自然神学や神を設計者とする教義の根幹を揺るがすものであり、新しい生命形態が自然自身によってもたらされるのであれば、神がそれを設計する必要はないのである。エラスムス・ダーウィンは、神は生命や自然に、もともと備わっている創造的能力を賦与し、それが以後、神の導きや介入を受けることなく表現されるようになったと考えた。彼は著書『動物誌』(1794)の中で、次のような問いかけをしている。
すべての温血動物は、偉大なる第一原因によって、生気、新しい部位の獲得力、新しい性向の付与、刺激、感覚、意志、連想の指示、そしてそれによる改良の継続の能力、さらにこれらの改良を世々子孫に伝える能力を備えた一つの生きた糸から生じたと想像するには、あまりにも大胆すぎるだろうか35。
エラスムス・ダーウィンにとって、生物は自己改善するものであり、親の努力の結果は子孫に受け継がれるものであった。同様に、ジャン=バティスト・ラマルクは『動物哲学』(1809)の中で、動物は環境に応じて新しい習性を身につけ、その適応はCdオニオンの子孫に受け継がれることを示唆した。アフリカの乾燥地帯に生息するキリン。
アフリカの乾燥地帯に生息するキリンは、木の葉を拾い食いすることを余儀なくされ、木の葉に到達するために絶え間ない努力をする。このような習慣が長く続いた結果、キリンの前肢は後肢より長くなり、首は6mにも達するほど長くなった36。
さらに、生命に内在する力が、より複雑な生物を生み出し、進歩の階段を上っていったのである。ラマルクは、生命の力の起源を「至高の創造主」に求め、「私たちが見るものすべてに次々と存在を与えるものの秩序」を創造したとした37 エラスムス・ダーウィンと同じく、ロマンチックな神学者であった。ロバート・チェンバースも同様で、1844年に匿名で出版されたベストセラー『創造の自然史』(Vestiges of the Natural History of Creation)で、漸進的進化という考えを一般に知らしめた。チェンバースは、自然界のあらゆるものは、神から与えられた「創造の法則」によって、より高い状態へと進化していると主張した38。チェンバースの研究は、宗教的にも科学的にも議論を呼んだが、ラマルクの理論同様、神の設計者を必要としないため、無神論者にとって魅力的だった。
しかし、チェンバース、ラマルク、エラスムス・ダーウィンは、機械論的神学を弱体化させただけでなく、おそらく無意識のうちに、生命に関する機械論も弱体化させたのである。無生物の機械には、生命の力、自己改良の能力、創造性などはない。彼らの進化論は、進化を神秘化することによって、神の創造性の神秘を解き放ったのである。
チャールズ・ダーウィンとアルフレッド・ラッセル・ウォレスの自然淘汰による進化論(1858)は、進化を神秘化しようとするものであった。自然淘汰は盲目的で非人格的であり、神の代理を必要としない。自然淘汰は、生存に適さない生物を淘汰し、より適応した生物を優遇するものである。ダーウィンの『種の起源』の副題は、「生命のための闘いにおける有利な人種の保存」であった。動物や植物が自発的に変化し、新しい環境に適応していく、その創造性の源泉は動物や植物自身の中にある。
ダーウィンは、この創造的な力について、何の説明も与えていない。ダーウィンは、機械論的神学の設計神を否定し、祖父と同じように、すべての創造性を自然に帰結させたのである。ダーウィンにとって、自然そのものが「生命の木」を生み出したのである。脅威的な繁殖力、自然発生的な可変性、淘汰の力によって、ペイリーが神が行ったと考えたことすべてを自然が行うことができたのである。しかし、自然は天球物理学の時計仕掛けのような無生物で機械的なシステムではなかった。ダーウィンは、「簡潔にするために、私は時々、自然淘汰を知的な力として話すことがある。また、私はしばしば自然という言葉を擬人化してきたが、この曖昧さを避けることは困難であると考えたからだ」39。
ダーウィンは読者に対して、自分の言い回しの意味するところを無視するように勧めた。その代わりに、その意味するところに注意を払えば、自然とは、すべての生命がその子宮から生まれ、すべての生命がその子宮に戻ってくる母である。その母なる大地からすべての生命が生まれ、すべての生命はその母なる大地へと帰っていくのである。創造的であるが、インドの女神カーリーのように破壊的でもある。ダーウィンにとって、自然淘汰は「絶え間なく作用しようとする力」40 であり、「自然淘汰は殺戮によって機能する。歯と爪で真っ赤に染まった自然」という表現は、ダーウィンではなく詩人テニスンのものだが、カリ、あるいは破壊的なギリシャの女神ネメシス、あるいは復讐に燃えるフューリーズに酷似している。
チャールズ・ダーウィンは、祖父のエラスムスやラマルクと同様に、習性の遺伝を信じていた。1940年代以降に発展した新ダーウィン進化論は、チャールズ・ダーウィンの理論とは異なり、後天的な特性の継承を否定している。その代わり、生物は親から遺伝子を受け継ぎ、突然変異、つまり遺伝子にランダムな変化がない限り、その遺伝子をそのまま子孫に受け継ぐとした。分子生物学者のジャック・モノは、この理論を自著『偶然と必然』(1972)の題名にまとめた。
これらの一見抽象的な原理は、ネオ・ダーウィニズムの隠れた女神たちである。チャンスとは、女神フォルトゥナ(幸運の女神)のことである。フォルトゥナの輪は、繁栄と不幸をもたらす。フォルトゥナは盲目であり、古典的な彫像ではしばしばベールや目隠しをして描かれた。モノーの言葉を借りれば、「純粋な偶然、絶対的に自由だが盲目である偶然が、進化の途方もない建造物のまさに根底にある」42。
シェリーは、必要性を「万能の力」、「世界の母」と呼んだ。彼女はまた、「運命」あるいは「宿命」でもあり、古典的なヨーロッパ神話に登場する「三人の運命」は、生命の糸を紡ぎ、割り付け、切り、人間にその誕生と同時に運命を与える存在である。ネオ・ダーウィニズムでは、生命の糸は文字どおり、糸状の染色体の中にあるらせん状のDNA分子が、生まれながらにして人間に運命を与えるというものである。
マット・クニオールのDNAメリヤス主義は、グレート・マザーに対する無意識の崇拝のようなものである。母なるものの原型は、母なる自然、エコロジー、あるいは経済など、さまざまな形をとっており、需要と供給に基づいて乳を与えるように働き、私たちを養い支えている。(これらの言葉のギリシャ語の語源である「エコ」は、いずれも家族や家庭を意味する)原型は、調べたり議論したりすることができないため、無意識のうちにあるときに、より強力になる。
生命は機械的なメタファーから脱却する
進化論は、機械的設計からの議論を破壊した。もし動物や植物が自然変異と自然淘汰によって徐々に進化したのであれば、創造主である神が最初に動物や植物の機械を設計することはあり得なかったのである。
生物は、機械とは異なり、それ自体が創造的である。植物や動物は自然発生的に変化し、遺伝子の変化に対応し、環境からの新たな挑戦に適応する。あるものは他のものよりも変化し、時には本当に新しいものが現れることもある。創造性は生物に内在し、あるいは生物を通して働いている。
どんな機械も、小さな始まりから始まり、成長し、自身の中に新しい構造を形成し、そして自己複製をすることはない。しかし、植物や動物はこれを常に行っている。また、損傷を受けても再生することができる。しかし、植物や動物は、損傷を受けても再生することができる。これらを、通常の物理学と化学によってのみ推進される機械とみなすことは、信仰行為であり、あらゆる外見にもかかわらず機械であると主張することは独断的である。
科学の世界でも、18世紀から19世紀にかけて、生命機械説は、生命論と呼ばれる別の生物学の一派から絶えず挑戦を受け続けていた。生命論者は、生物は機械以上のものであり、真に生命力があり、生きていると考えた。物理学や化学の法則を超えた組織原理が、生物の形態を形成し、目的にかなった行動をとらせ、動物の本能や知性の根底を支えていると考えたのである。1844年、化学者のユストゥス・フォン・リービッヒは、化学者は生物に存在する有機化学物質を分析し合成することはできるが、目や葉を作り出すことはできないと主張し、生命論者の立場を典型的に表現している。認識されている物理的な力のほかに、「要素を新しい形に組み合わせて、新しい特性を獲得する」、つまり、生物の中にしか現れない形や特質があるのだ44。
多くの点で、バイタリズムは、生物は魂によって組織されているとする古い世界観の生き残りであった。バイタリズムはまた、生きている自然に対するロマンティックなビジョンとも調和していた。ドイツの発生学者ハンス・ドリーシュ(1867-1941)のような一部のバイタリストは、この思想の連続性を強調するために、意図的に魂という言葉を使用した。ドリーシュは、非物質的な組織原理が植物や動物に形態と目的を与えていると考えた。彼はこの組織原理を、アリストテレスが魂の内側に目的を持つ側面に対して使った言葉(en = in, telos = purpose)を使って、エンテレケイアと呼んだ。ドリーシュは、胚は目的を持って行動していると主張した。胚の発生が妨げられたとしても、胚は発生しようとする形態に到達することができるのだ。彼は、ウニの胚を二つに切ると、その半分ずつが、半分のウニではなく、小さいながらも完全なウニを生み出すことができることを実験で明らかにした。ウニの胎動は、発生しつつある胚を、さらには胚の分離した部分をも、成体の形へと引き寄せていくのである。
バイタリズムは、機械論的生物学の中では、昔も今も究極の異端である。正統派の見解は、1867年に生物学者T・H・ハクスリーによって明確に表現された。
動物生理学とは、動物の機能または作用に関する教義である。動物の体は、さまざまな力によって動かされる機械であり、自然界の通常の力によって表現される一定の仕事を行うものであると考えるのだ。生理学の最終的な目的は、一方では形態学の事実を、他方では生態学の事実を、物質の分子力の法則から推論することである 45。
この言葉によって、ハクスリーは、1960年代以降の分子生物学の目覚しい発展を予見し、生命現象を物理的、化学的メカニズムに還元するという、これまでにない強力な取り組みを行ったのである。DNAの構造の発見でノーベル賞を受賞したフランシス・クリックは、その著書『分子と人間』(1966)の中で、この課題を明確に示している。彼は生命論を非難し、「生物学における現代的な動きの究極の目的は、実際、すべての生物学を物理学と化学の観点から説明することである」という信念を表明している。
機械論的アプローチは、本質的に還元主義的であり、部分から全体を説明しようとするものである。分子は生物を構成する最小の要素であり、生物学と化学がクロスオーバーする地点だろうから、分子生物学は生命科学の中で高い地位を占めている。分子生物学は、生命現象を「物質の分子的な力の法則」という観点から説明しようとする試みの最前線にあるのである。生物学者が生物を分子レベルにまで還元することに成功すれば、化学者や物理学者にバトンタッチし、分子の性質を原子や素粒子の性質に還元することができるようになるのである。
19世紀まで、ほとんどの科学者は、原子が物質の強固で永久的な究極の基礎であると考えていた。しかし、20世紀になって、原子は、原子核を中心とし、その周りの軌道を回る電子を含む部分から構成されていることが明らかになった。原子核は陽子と中性子からなり、陽子は3個ずつのクォークと呼ばれる成分で構成されている。ジュネーブ近郊のCERNにある大型ハドロン衝突型加速器のような粒子加速器で原子核を分割すると、さらに多くの粒子が出現する。これまでに何百もの粒子が確認されており、さらに大きな粒子加速器でさらに多くの粒子が発見されるだろうと期待する物理学者もいる。
原子の底が抜けてしまったのだ。エバネッセント粒子の動物園では、ランの花の形やサケの跳躍、ムクドリの群れの飛行を説明することはできそうにない。還元論はもはや、他のすべてのものを説明するための確固たる原子的根拠を提供してはいないのだ。いずれにせよ、素粒子がいくつあろうと、生物は全体であり、生物を殺してその化学成分を分析し、部分へと還元することは、生物を生物たらしめているものを単に破壊してしまうだけなのだ。
私が還元主義の限界について考えさせられたのは、ケンブリッジ大学に在学していた頃である。最終学年の生化学の授業の一環として、私のクラスではラットの肝臓に含まれる酵素に関する実験を行った。まず、各自が生きたラットを手に取り、流しの上でギロチンで首を切って「生け贄」にし、その後、切り開いて肝臓を取り出したのである。肝臓をミキサーで粉砕し、遠心分離して、不要な細胞片を取り除いた。そして、水分の画分を精製して目的の酵素を分離し、試験管に入れた。最後に、化学物質を加えて、化学反応の起こる速度を調べた。酵素のことは分かったが、ネズミの生態や行動については何も分からなかった。生化学教室の廊下には、ヒトの代謝経路の化学的詳細を示す壁のチャートがあり、その上部には誰かが大きな青い文字で「自分を知れ」と書いてあったのである。
化学成分で生物を説明しようとするのは、コンピュータを分解して、銅、ゲルマニウム、ケイ素などの構成元素を分析し、理解しようとするようなものである。確かに、この方法でコンピューターについて何か知ることは可能である。しかし、この還元過程では、コンピュータの構造とプログラムされた活動は消えてしまう。化学分析によって回路図が明らかになることはなく、原子構成要素間の相互作用をいくら数学的にモデル化しても、コンピュータのプログラムやそれが果たす目的が明らかになることはない。
機械論者は、生きている動物や植物から目的のある生命因子を追い出し、それを分子的な装いで再発明するのだ。分子生命論の一つの形態は、遺伝子を、DNAのような単なる化学物質のそれをはるかに超えた目的と力を持つ、目的のある存在として扱うことである。遺伝子は分子エンテレケイアとなる。リチャード・クロンは、その著書『利己的な遺伝子』の中で、次のように述べている。
私たちは生存機械であるが、「私たち」とは人間だけを意味するのではない。動物、植物、バクテリア、ウイルスのすべてを包含している。私たちは皆、同じ種類の複製者(DNAと呼ばれる分子)のための生存機械であるが、世界には様々な生計手段があり、複製者はそれを利用するために膨大な種類の機械を作り出したのである。サルは木の上で遺伝子を保存する機械であり、魚は水の中で遺伝子を保存する機械である46。
ドーキンスの言葉を借りれば、「DNAは不思議な動きをする」のである。DNA分子は知的であるだけでなく、利己的で、冷酷で競争的であり、まるで「成功したシカゴのギャング」である。利己的な遺伝子は、「形を作り」、「物質を成形」し、「進化の軍拡競争」を行い、「不死を目指す」ことさえあるのだ。これらの遺伝子は、もはや単なる分子ではない。
外界から遮断された巨大なロボットの中で、曲がりくねった間接経路で外界とコミュニケーションをとり、遠隔操作で外界を操っている。彼らはあなたと私の中にいる。彼らは私たちの身体と心を作り、彼らの保護が私たちの存在の究極の理由である… … 今、彼らは遺伝子という名で呼ばれており、私たちは彼らの生存機械なのだ 47。
ドーキンスのレトリックの説得力は、人間中心主義的な言葉と漫画のようなイメー ジに依存していたのである。彼は利己的な遺伝子のイメージは科学というより、SFに近いと認めつつ48、それを「強力で示唆に富む」メタファーとして正当化している49。
メカニズムの名において生命論的メタファーを最もよく使うのは、「遺伝的プログラム」 である。遺伝的プログラムは、コンピュータのプログラムに明確に類似しており、特定の目的を達成するために人間の頭脳によって知的に設計されたものである。プログラムは目的意識があり、知的で、目標に向かうものである。メカニズムというより、むしろエンテレケイアのようなものである。「遺伝子のプログラム」は、植物や動物が、心のような、あるいは心によって設計された目的のある原理によって組織化されていることを意味する。これは、化学的な遺伝子に知的な設計を持ち込むもう一つの方法である。
もし異議を唱えられたら、ほとんどの生物学者は、遺伝子は単にタンパク質中のアミノ酸の配列を特定するだけであり、タンパク質合成の制御に関与しているに過ぎないことを認めるだろう。遺伝子はプログラムではなく、利己的でもなく、物質を成形したり、形を整えたり、不老不死を目指したりもしないのである。遺伝子は、魚のひれのような特性や、機織り鳥の巣を作る行動のためにあるのではない。しかし、分子生命論はすぐにまた忍び寄る。機械論的な生命論は、誤解を招くような比喩や修辞に堕落してしまった。
多くの人々、特に園芸家や犬、猫、馬などの動物を飼育している人々にとっては、植物や動物が機械ではなく、生物であることは一目瞭然なのだ。
生物の哲学
機械論と生命論がともに17世紀にさかのぼるのに対し、有機体の哲学は、全体論的アプローチまたは有機体論的アプローチとも呼ばれ、1920年代以降に発展してきたものである。その提唱者の一人が哲学者のアルフレッド・ノース・ホワイトヘッド(1861-1947)であり、もう一人が南アフリカの政治家であり学者でもあったヤン・スマッツで、彼の著書『ホーリズムと進化』(1926)は、「創造的進化によって部分の和よりも大きい全体を形成する自然の傾向」50に注目した。
それは、原子や物理化学的構造から、細胞や生物、動物の心、人間の人格に至るまで、宇宙のあらゆる構造的グループ化と合成を説明するものである。これらの構造における合成的な統一性または全体性というすべてが浸透し、常に増加する性質は、他のすべてを基礎づけ、調整する基本的な活動としてのホーリズムの概念、およびホリスティックな宇宙としての宇宙の見方につながる51。
ホリスティックあるいはオーガニックな哲学は、自然の統一性を確認するという点で、機械論と一致する。生物体の生命は、分子や結晶のような物理的システムとは程度は異なるが、種類は異ならない。有機体論は、生物が自らの内部に組織原理を持っていることを強調し、生物は、より単純なシステムの物理学や化学に還元できない単一体であるとして、生命論と同意見である。
有機体の哲学は、事実上、すべての自然を生きているものとして扱う。この点で、機械以前のアニミズムの最新版である。原子、分子、結晶でさえも有機体である。スマッツが言うように、「物質も生命も、原子や細胞においては、秩序だったグループ化によって、私たちが身体や生物と呼ぶ自然の全体が作り出される単位構造からなる」52。むしろ、20世紀の物理学が明らかにしたように、原子は活動の構造であり、場におけるエネルギー的な振動のパターンなのである。ホワイトヘッドの言葉を借りれば、「生物学はより大きな生物の研究であり、物理学はより小さな生物の研究である」53。現代の宇宙論に照らせば、物理学は惑星、太陽系、銀河系、宇宙全体といった非常に大きな生物の研究でもある。
生物の哲学は、自然界のどこを見ても、どのようなレベルや規模であっても、より低いレベルでそれ自体が全体である部分から構成される全体を見出すことができると指摘している。このような組織化のパターンは、図11のように図式化することができる。最小の円は、例えば、陽子内、原子核内、原子内、分子内、結晶内などのクォークを表している。あるいは、最小の円は、細胞内、組織内、器官内、生物内、生物社会内、生態系内の小器官を表している。あるいは、最小の円は、惑星、太陽系、銀河系、銀河団を表している。言語もまた、音素が音節に、単語が単語に、フレーズが文にと、同じような構成になっている。
図11 ホール(ホロン)の入れ子構造
【原図参照】
これらの組織化されたシステムは、すべて入れ子の階層構造になっている。各レベルにおいて、全体は部分を含んでおり、それらは文字通りその中にある。そして、各レベルにおいて、全体は部分の総和以上のものであり、部分単体の研究からは予測できない特性を備えている。例えば、この文章の構造と意味は、紙とインクの化学分析では解明できないし、構成する文字の量(asが5つ、bが1つ、cが5つ、dsが2つ、など)から推測することもできない。構成するパーツの数を知るだけでは不十分で、それらがどのように言葉として組み合わされるか、また言葉同士の関係によって、全体の構造が決まる。
アーサー・ケストラーは、それ自体が全体である部分から構成される全体をホロンと呼ぶことを提唱している
すべてのホロンは、準自律的な全体としての個性を維持し主張することと、(既存の、あるいは進化する)より大きな全体の統合された部分として機能することとの二重の傾向を持っている。自己主張的な傾向と統合的な傾向の間のこの極性は、階層的秩序の概念に内在するものである54。
このようなホロンの入れ子状の階層に対して、ケストラーはホラーキーという言葉を提唱している
このようなホール(全体)は「複雑系」とも呼ばれ、「複雑系理論」、「複雑性理論」、「複雑性科学」と呼ばれる数多くの数学的モデルの対象になっている56。
化学的な例として、6個の炭素原子と6個の水素原子を持つ分子であるベンゼンを考えてみよう。化学的な例として、6個の炭素原子と6個の水素原子を持つベンゼンを考えてみよう。これらの原子は、それぞれ原子核とその周りの電子からなるホロンである。ベンゼンでは、6つの炭素原子が6角形のリング状に結合し、原子間で電子を共有することで、分子全体の周りに振動する電子の雲を作り出している。分子の振動のパターンは、その中の原子に影響を与え、電子は電気を帯びているため、原子は振動する電磁場の中にいることになる。ベンゼンは常温では液体だが、5.5℃以下では結晶化し、その際、分子は格子構造と呼ばれる規則正しい立体的なパターンで積み重なっている。この結晶格子はまた、調和的なパターンで振動し57、振動する電磁場を作り出し、その中の分子に影響を与える。組織のレベルには入れ子状の階層があり、振動する場の入れ子状の階層を通じて相互作用している。
例えば、最初のアミノ酸分子、最初の生きた細胞、最初の花、最初のシロアリコロニーなどである。ホロンは全体だろうから、突然のジャンプによって生じるに違いない。新しいレベルの組織が「出現」し、その「出現特性」は、それまでそこにあった部分の特性を超える。新しいアイデアや新しい芸術作品についても同じことが言える。
発展途上の有機体としての宇宙
哲学者のデイヴィッド・ヒューム(1711-76)は、おそらく今日、宗教に対する懐疑論で最もよく知られている人物であろう。しかし、彼は自然界の機械論的な哲学にも同様に懐疑的であった。宇宙が生物というより機械に近いことを証明するものは何もなかった。自然界に見られる組織は、機械というより植物や動物に類似していた。ヒュームは、機械で設計された神という考えには反対で、代わりに種や卵のようなものから世界が発生した可能性を示唆した。1779年に死後出版されたヒュームの言葉である。
宇宙には(人間が発明した機械以外に)世界の構造にさらによく似た部分があり、したがって、このシステムの普遍的な起源に関してよりよい推測を与えるものである。これらの部品は、動物と植物である。世界は明らかに、時計や編み機よりも、動物や植物に似ている… … そして、植生や生成から生じる植物や動物は、理性と設計から生じる人工的な機械よりも、より強く世界に類似しているのではないだろうか58。
ヒュームの議論は、現代の宇宙論に照らし合わせると、驚くほど先見の明があった。1960年代まで、ほとんどの科学者は、宇宙は機械であり、しかも、最後の熱死に向けて暴走している機械であると考えていた。1855年に発表された熱力学の第二法則によれば、宇宙は次第に仕事する能力を失っていく。ウィリアム・トムソン(後のケルビン卿)の言葉を借りれば、「普遍的な安息と死の状態」で、やがて宇宙は凍りついてしまうのである59。
宇宙学者でローマ・カトリックの司祭であったジョルジュ・ルメートルが、卵や種子に宇宙が起源を持つというヒュームの考えのような科学的仮説を唱えたのは、1927年になってからであった。後にビッグバンと呼ばれるこの新しい宇宙論は、古代ギリシャのオルフィックの創造神話「宇宙の卵」やインドのヒランヤガルバ(原始の金の卵)の神話など、多くの古代の起源に関する物語と呼応していた61。卵は黄身と白身の二つの部分からなる単一体であり、「一」から「多」が出現することの象徴としてふさわしいからだ。
ルメートルの理論は、宇宙の膨張を予測し、私たちの銀河系の外にある銀河が、距離に比例した速度で私たちから遠ざかっていることを発見し、支持された。1964年、宇宙のいたるところにかすかな背景の光、宇宙マイクロ波背景放射が発見され、ビッグバン直後の初期宇宙に残された化石のような光であることが明らかになった。最初の「天地創造的な出来事」を示す証拠は圧倒的なものとなり、1966年にはビッグバン理論が正統派となった。
現在、宇宙論は、宇宙の始まりは非常に小さく、ピンの頭の大きさにも満たない、非常に高温の宇宙であったと語っている。それ以来、宇宙は膨張し続けている。原子核や電子、星、銀河、惑星、分子、結晶、生物など、新しい形態や構造が誕生した。
機械という比喩は、物理学、生物学、医学の分野で科学的思考を妨げてきた。地球もそうだし、樫の木もそうだし、犬もそうだし、あなたもそうだ。
その違いは何だろう?
自分が機械的な宇宙の中で、遺伝子的にプログラムされた機械であると本当に考えられるだろうか?おそらく無理だろう。おそらく、最も熱心な唯物論者でさえも無理だろう。私たちのほとんどは、自分が生きている世界の中で本当に生きていると感じている – 少なくとも週末は。しかし、機械論的世界観に忠実であるために、勤務時間中は機械論的思考が支配している。
自然の生命を認識することで、私たちはすでに知っていること、つまり動物や植物がそれぞれ目的や目標を持った生命体であることを認識することができる。ガーデニングやペットを飼っている人なら誰でも知っていることで、状況に応じて創造的に対応する独自の方法を持っていることを認識できる。しかし、機械的なドグマに従うために自分自身の観察力や洞察力を否定するのではなく、それらに注意を払い、そこから学ぼうとすることができる。
生きている地球との関連で言えば、ガイア理論が、機械的な宇宙の中で孤立した詩的な比喩に過ぎないということがわかる。地球を生命体として認識することは、宇宙のより広い生命を認識するための大きな一歩となる。地球が生命体であるならば、太陽や太陽系全体はどうなのだろうか。太陽系が一種の生命体であるならば、銀河系はどうだろうか。宇宙論はすでに、宇宙全体を、宇宙の卵が孵化して生まれた、一種の成長する超生物として描いているのだ。
このような視点の違いは、直ちに新しい技術製品の範囲を示唆するものではないし、その意味では経済的に有用ではないかもしれない。しかし、この視点の違いは、機械論的なチャンドゥクトが生み出した、自然に対する個人的な体験と科学が与える機械的な説明との間の分裂を癒す上で、大きな違いをもたらす。そして、人間や動物を機械的な世界の中の機械と見なさない伝統文化や土着文化と、科学との間の溝を癒すのに役立つ。
最後に、宇宙は無生物の機械であるという信念を払拭することは、以下の章で論じる多くの新しい問いを開くことになる。
唯物論者への問いかけ
- 機械論的世界観は、検証可能な科学理論なのか、それとも比喩なのか?
- もし比喩であるなら、なぜ機械の比喩は生物の比喩よりもあらゆる点で優れているのか?もし科学的理論だとしたら、どのようにして検証したり反論したりできるのだろうか?
- あなた自身は複雑な機械に過ぎないと思っているのだろうか?
- あなたは唯物論を信じるようにプログラムされてきたのだろうか?
まとめ
機械論は、機械というメタファーに基づいている。しかし、それは単なるメタファーに過ぎない。生物は、分子、植物、動物の社会など、あらゆるレベルの複雑さで組織化されたシステムの、より良いメタファーを提供してくれるが、これらはすべて、一連の包括的なレベルで組織化されている。
各レベルの全体は、下位のレベルの全体である部分の総和を超える。機械論的理論の最も熱心な擁護者でさえ、利己的な遺伝子や遺伝的プログラムの形で、生物の中に目的のある組織原理を忍び込ませている。ビッグバン理論に照らし合わせると、宇宙全体は、ゆっくりと息切れしていく機械というよりも、成長・発展する有機体のようなものである。
第12章 科学の未来
科学は新たな局面を迎えている。19世紀以来、科学を支配してきた唯物論的イデオロギーは、もはや時代遅れである。その本質的な10個の教義はすべて取って代わられた。科学の権威主義的構造、客観性の幻想、全知全能の幻想は、すべてその有用性を失ってしまった。
科学が変わらなければならない理由はもう一つある。機械論的科学と唯物論的イデオロギーはヨーロッパで発展し、17世紀以降ヨーロッパ人が夢中になった宗教論争に強い影響を受けた。しかし、このような関心は、世界の他の多くの地域の文化や伝統とは異質なものである。
2011年、世界の科学技術研究開発費は1兆ドルを超え、そのうち中国は1,000億ドルを費やしている1 アジア諸国、特に中国とインドは、現在、膨大な数の科学技術系の卒業生を輩出している。2007年、理学士レベルの理工系卒業生は、インドで250万人、中国で150万人2 であるのに対し、米国では51万5000人3、英国では10万人4 である。さらに、米国やヨーロッパで学ぶ人の多くは他国出身であり 2007年には、米国の理工系大学院生のほぼ3分の1は外国人で、インド、中国、韓国が大部分を占めた5。
しかし、アジア、アフリカ、イスラム諸国などで教えられている科学は、依然としてヨーロッパの過去によって形成されたイデオロギーに包まれている。唯物論は、科学の技術的応用から説得力を得ている。しかし、こうした応用の成功は、このイデオロギーが真実であることを証明するものではない。ペニシリンはバクテリアを殺し続け、ジェット機は飛び続け、携帯電話は、科学者がより広い自然観に移ったとしても、まだ使えるだろう。
科学がどのように発展するかは誰も予見できないが、「科学」が一つのものではないことを認識することが、その発展を促進すると私は信じている。「科学」は「科学」に道を譲ったのである。物理主義を超えることで、物理学の位置づけが変わってきた。科学が唯物論のイデオロギーから解放されることによって、議論と対話の新しい機会が開かれ、研究の新しい可能性も開かれるのだ。
一つの科学から多くの科学へ
機械論的な科学は、単純で統一された自然観を提供するように思われた。すべてのものは究極の物質粒子から成り、その性質と運動は永遠の数学的法則に支配されているというのである。理論物理学者は今も「万物の理論」を目指しており、素粒子の性質とそれに作用する力という観点から、現実のすべてを説明する統一的な公式ができることを願っている(第1章参照)。すべては最終的に物理学に還元されるのだ。リー・スモリンは、「既知の世界のすべてを説明するのに必要なのは、12個の粒子と4つの力である」と従来の見解を表現している6。
このナイーブで古風な還元主義的信仰は、科学の現実とは全く関係がない。生理学者は血圧を素粒子で説明するのではなく、心臓のポンプ作用や動脈壁の弾力性などを通して説明する。言語学者は、音声が伝わる空気中の分子の素粒子の動きから言語を分析するのではなく、言葉のパターン、文法、意味を研究する。植物学者は、花の進化を、花の中の原子を探ることによって研究するのではなく、花の構造や関係を、現存する種や絶滅した種と比較することによって研究するのだ。物理学者ジョン・ジーマンはこう言っている。
素粒子、化学分子、単細胞生物、多細胞生物、そして自我を持つ人間やその文化的制度に至るまで、複雑さのレベルが上がるにつれて、全く新しい原理に従うシステムを発見することができる。このようなシステムの挙動は、その構成要素の特性からは予測できないため、それらを科学的に記述するためには、異なる「言語」が必要とされる。このように、科学が複数存在することは、私たちの住む宇宙の不可逆的な特徴である7。
多くの科学があり、多くの自然がある。岩石を研究する地質学者と、電波望遠鏡で遠方の銀河を調査する天文学者、タンパク質分子の特性を研究する生化学者、熱帯雨林を研究する生態学者とは、異なる種類の観測を行う8。科学には実験を伴うものもあれば、伴わないものもある。また、そうでないものもある。天文学者は星を操作してその反応を見ることはできないし、古生物学者は時間をさかのぼって大昔の海の堆積物の形成方法を変えることはできない。科学には、理論物理学のように高度に数学的なものもあれば、トンボの分類学のように数学的でないものもある。
「科学」は抽象的なものである。科学者は専門的な分野で仕事をし、学生は一つまたは複数の科学を学ぶ。大学では、さまざまな可能性の中から選択しなければならないのである。例えば、2011年のケンブリッジ大学では、自然科学系の2年生は、以下のリストから3科目を選択しなければならなかった9。
- 動物生物学
- 生化学・分子生物学
- 細胞・発生生物学
- 化学A(主に理論系)
- 化学B(無機、有機、生物)
- ecoini face=”Minlogy
- 実験心理学
- 地質科学A(地表環境)
- 地質科学B(地下プロセス)
- 科学史・科学哲学
- 物質科学
- 数学
- 神経生物学
- 病理学
- 薬理学
- 物理学A(主に量子物理学)
- 物理学B(主に力学、電磁気学、熱力学)
- 生理学
- 植物・微生物科学
これらのコースはそれぞれ、幅広い専門分野をカバーしている。例えば、動物生物学では、生態学、脳と行動、昆虫生物学、脊椎動物進化生物学、進化原理のセクションが設けられている。「科学」を学ぶ人はおらず、科学史や科学哲学を学ぶ人は20%以下である。
学生は、現実の本質に関する一般的な見解を、暗黙の前提や、科学普及者の著作から吸収している。唯物論の教義は明確に教えられていないため、多くの学生や科学者は、自分たちの分野の実践や前提を形成する上で、その影響力に気づいていないのである。例えば、ほとんどの神経科学者は、心は脳の中にあり、記憶は物質的な痕跡として保存される、ということを当然のこととしている。これらの仮定は、自然哲学の一側面として、あるいは検証すべき仮説として扱われるのではなく、標準的なパラダイムあるいは合意された現実の一部であり、逸脱した思考に対するタブーによって保護されているのである。
皮肉なことに、科学が個別の学問分野に細分化されたことが、「科学者」という言葉を生み出す刺激となった。1833年に開催された英国科学振興協会の第3回年次総会で、参加者は自分たちの多様な関心を包括する用語の必要性を訴え、数学天文学者ウィリアム・ホイウェルが「科学者」を提案した。この言葉は、アメリカですぐに成功を収めた。イギリスでは、科学研究はまだほとんどの場合、有閑階級の高価な職業であったため、「科学者」は「man of science」、「naturalist」、「exptst part anerimental philosopher」といった古い言葉に取って代わるには時間が掛かった。しかし、研究が進み、教育が拡大するにつれ、雇用の機会も増え、科学者は次第に有給の専門職となっていったのである10。
科学が力と名声を高めるにつれ、その地位と権威を主張する必要性が生じてきた。科学が力を持ち、威信を高めるにつれて、地位と権威を主張する必要性が生じた。科学史家のパトリシア・ファラは、19世紀の状況を次のように要約している。
威信に飢えた科学者たちは、自分たちが議論の余地のないほど正しい、自分たちの研究室で生み出された知識は反論の余地がないほど正しい、と宣言する権威を欲したのだ。新しい専門分野が発明されたが、そのすべてが科学と呼ぶにふさわしいとは考えられなかった。科学は学問分野に分裂していた。しかし、学問を統制することは、教えることと同様に、統制することを意味した。国境を警備する警察のように、科学者たちは自分たちが支配する大きな領域の中にあるべきテーマと、非合法とされるテーマを決めていたのである11。
現在では何百もの科学的専門分野があり、それぞれに専門学会や学術誌、会議が存在する。専門家は、より多くのことを、より少なく知るようになる、というのは有名な話だが、科学分野ではこのプロセスによって、知識の分野がますます細分化され、それぞれが専門的な出版物を持つようになったのである。2011年には、約25,000の科学雑誌が発行された12。
科学の根底にある哲学的な前提について考えることは、こうした専門家の仕事ではない。歴史家や科学哲学者は、このような哲学的前提について考えるが、彼ら自身は専門分野に属しているため、科学の本質的な問題にはほとんど関心がないものとして扱われることが多いのである。既定では、古い唯物論や物理学のイデオロギーは、ほとんど疑われることなく存続している。物理主義は、すべてのものは究極的には物理学的に説明可能である、と定義しているため、その効果の1つは、物理学を科学のヒエラルキーの頂点に据えることである。
物理主義と物理学
物理学は、シンプルで統一された自然観というビジョンの源であり、物理学者は自分たちの学問が最も基本的で、すべての科学を統合していると考えたがっている。確かに、すべての物質体は量子粒子でできており、すべての物理的過程はエネルギーの流れを伴い、すべての物理的事象は万有引力場が与える時空の枠組みの中で起こっている。しかし、松の木の成長、性ホルモンの影響、ミツバチの社会生活、印欧語の進化、コンピューターソフトウェアの設計など、私たちが知りたいと思うようなことは、物理学のこれらの側面からはほとんど除外されている。
皮肉なことに、自然界を統一するためにすべてを物理学に還元しようとする人々にとって、フィイン=物理学そのものが何十年にもわたって統一を拒んできたのである。量子力学と一般相対性理論という最も基本的な2つの理論は、相容れないものなのだ。一般相対性理論は、惑星、星、銀河といった宇宙の大規模な構造に適用され、4つの「基本的な力」のうちの1つである重力を記述するものである。量子力学は、残りの3つの力(電磁気力、強い核力、弱い核力)を記述するもので、原子や素粒子のスケールで最も正確である。しかし、この2つの理論は異なる仮定から出発しており、長年にわたって両者を統一しようとする努力に抵抗してきた13。
そこで登場したのが、それぞれ10次元と11次元を持つ超弦理論とM理論である(第3章参照)。しかし、物理学に新たな統一性を与える代わりに、膨大な数の可能性のある世界を生み出している。統一性の代償として、宇宙が無秩序に増殖しているのだ。私たち自身のもの以外は、すべて観測されず、観察もできない。一体、どのような統一なのだろうか?それは究極の多元的なものであるように見える。
機械論的な科学では、中世の大学で力学、天文学、光学が研究され、物理学が歴史的に最初に発展してきた。物理学は、ビッグバンという万物の起源と同様に、最も根源的な現実を扱うと主張するため、威信の面でも第一に位置づけられる。しかし、この優先順位は恣意的なものである。他の専門家グループも、自分たちの分野の地位は、それ以上でないにしても、同じくらい高いと主張することができるだろう。意識研究は、物理学が人間の心の中で起こるものであり、完全に人間の意識に依存していることから、優先権を主張することができる。マクスウェル方程式や超弦理論は、独立した事実として「そこに」存在するのではなく、精神的な構築物なのである。
脳科学者は、神経生理学と脳化学がなければ、人間の意識は存在し得ないと主張することができる。社会科学者は、社会がなければ物理学も成立しないと主張し、経済学者は、経済が機能しなければ誰も物理学をやることはできないと主張することができる。一方、生理学者は、脳は身体の一部分に過ぎず、消化、呼吸、循環、手足、感覚器官など、身体全体の協調的な機能に依存していると指摘することができる。発生学者は、発生学的な発達がなければ、そもそも身体も生理も存在せず、したがって物理学者も存在しない、と主張し、遺伝学者は、遺伝子がなければ発生学も存在しない、と主張することができる。
進化学者は、人類の進化的起源を指摘し、生態学者は、すべての生命の相互依存性を強調し、植物学者は、人類と他のすべての動物が最終的に食糧を植物に依存し、光合成の生化学に依存していることを強調することができ、そして物理学者は、太陽物理学と天文学で再び絵に入って、それなしでは光合成が存在しないであろう。エンジニアや技術者は、科学装置がなければ正確な測定はできないし、現代の通信技術やコンピューターがなければ科学は機能しないと主張することができる。などなど。
誰も絶対的な優位性を主張することはできない。すべては相互に関連している。永久に孤立しているものはない。すべてのもの、すべてのレベルのものが相互依存しているのである。これは、仏教の従属起源の教義に非常に似ている。従属起源の教義によれば、すべての現象は、原因と結果の相互に依存する網の中で起こる。
唯物論的な哲学と物理学の優位性は密接に関連している。すべての現実の相互依存と科学の多様性も同様である。科学は依然として統一原理を必要とするが、それは物理学からだけ来る必要はない。
統一原理
力、場、エネルギーの流れといった物理学でおなじみの統一原理と同様に、入れ子状になった階層における組織化の原理がある。システム、有機体、ホロン、あるいはあらゆるレベルの形態的単位は、部分からなる全体であり、さらにその部分は部分からなる全体である。結晶は分子を含み、その分子は原子を含み、その原子は素粒子を含む。銀河団には銀河があり、その銀河には太陽系があり、その太陽系には惑星がある。生物の社会は、動物を含み、臓器を含み、組織を含み、細胞を含み、分子を含み、原子を含む……。(第1章参照)。
形態的共鳴の仮説は、もう一つの統一原理を提供する。すなわち、すべての自己組織化システムは、同種のシステムの集合的記憶を利用している(第3章、第6章、第7章参照)。
しかし、一般原則を見つけると、その一般性ゆえに、具体的な事柄の詳細が見えなくなってしまう。セコイア、海草、ヒマワリはすべて同じ化学元素から成り、光合成によって光のエネルギーを取り込み、入れ子状になった階層的な組織を持っている。しかし、それらを類似させる性質は、それぞれの種が異なる理由を説明することができない。
となると、すべての特殊なものには、自由と個性がある。ジャガイモ畑には、何万本もの遺伝的に同じ植物があり、栽培されたジャガイモはクローンである。しかし、同じ畑で、同じ時期に植え、同じ気候であるにもかかわらず、それぞれの株は隣の株とは異なり、それぞれの株の葉は他のどの葉とも細部が異なっている。同じ葉でも、右と左では葉脈のパターンが違うし、形も微妙に違う。
科学は一般化すればするほど、特殊性を説明しなくなるし、その逆もまた然りである。クォークから銀河まで、塩の結晶からツバメの巣まで、地衣類から言語まで、研究対象があまりにも多様なため、科学には一般原理と多くの専門分野の両方が必要なのである。
科学の権威
科学の権威が持つ問題の一つは、反対意見や議論が危険であることだ。権威を維持する必要性から、意見の相違は通常、舞台裏に隠されている。科学者は、自分たちの客観性が損なわれる可能性があることを、公衆の面前で認めたがらない。トーマス・クーンのパラダイムシフトとしての科学革命の理論でさえ、確立された権威のイメージを維持するものであった。科学革命では、新しいコンセンサスとなる現実が古い現実に取って代わる。地質学の大陸移動論や物理学の量子論のように、当初は革命的だった考え方が新しい正統派になる。これは、独裁的な体制が倒され、民主主義に取って代わられるような稀な政治革命とは異なる。むしろ、ある独裁政権が別の独裁政権に取って代わられるような革命である。
人間の生活の他のほとんどすべての領域では、1つではなく、多くの視点が存在する。多くの言語、文化、国家、哲学、宗教、宗派、政党、ビジネス、ライフスタイルがある。科学の領域だけは、かつてローマ・カトリック教会が主張した独占性、普遍性、絶対的権威という古いエートスをいまだに見出すことができる。カトリックとは「普遍的」という意味である。1517年に始まる宗教改革で、ローマ教会は独占権を失い、今では無神論も含め、多くの教会やイデオロギーが共存している。しかし、普遍的な科学はやはり一つしかない。
17世紀から18世紀にかけて、カトリックとプロテスタントの対立で分裂していた西ヨーロッパでは、宗派を超えた真理への道として、科学と理性の理想が輝き出したのである。啓蒙主義は、このような科学と人間の理性の力を尊重する姿勢と、正統な宗教を見下す姿勢から発展していった。ジョン・ブルックは次のように書いている。
科学は、その結果だけでなく、一つの考え方として尊重された。科学は、過去の誤りを正すことによって、また特に迷信を覆す力によって、啓蒙の見通しを与えてくれたのである。[しかし、科学を宗教に対抗させる人々の動機は、自然研究のための知的自由を獲得することとはあまり関係がないことが多い。自然哲学者(科学者)自身ではなく、社会的・政治的不満を抱く思想家たちが、聖職者の権力に抗して科学を世俗化する力に変えてしまうことが多かったのである14。
科学主義者は、客観的な観察者として世界を見ることで、絶対的な真理を得ようと主張した15。このような理想像のもとでは、科学者は他の人類の失敗から免除されている。この理想像において、科学者は他の人間の失敗から免除され、真実に直接アクセスすることができる。このような理想像において、科学者は他の人間の失敗から免れている。実体のない知識の神話と洞窟の寓話がこのイメージを補強し、科学者聖職者の威光が権威の証となる。
この権威主義的な考え方は、心霊現象や代替医療に関連して最も顕著に見られる(第9章、第10章参照)。これらは、合理的な探求のための有効な分野としてではなく、むしろ異端として扱われる。懐疑的調査委員会のような自称調査委員会は、これらのテーマが立派なメディアで真剣に取り上げられないようにし、資金を奪い、大学の授業科目から排除しようとする。機械論的な医学だけが本当に効くという信念は、政治的な影響を広範囲に及ぼしている。骨パシー、鍼灸、ナチュロパシー、ホメオパシーなど多くの医学があるが、力学的医学だけが「科学的」とされ、国家による権力、科学的権威、財政支援の独占を許されているのだ。
私たちが知っている科学は、客観的な真実という理想に基づいており、一度に一つの勝利した理論しか許さない。だから、科学者は「バイタリズムの棺に最後の釘を打つ」(13ページ参照)、「定常理論の棺に最後の釘を打つ」(67ページ参照)などと言い、異端を退治してほくそ笑んでいるのだ。科学の偽善の多くは、絶対的な真理のマントを引き受けることに由来する。これは、機械論的科学が誕生したときの、宗教的・政治的権力を絶対視するエートスの遺物である。もちろん、科学者の間にも意見の相違はあるし、科学は絶えず変化し、発展している。しかし、真理の独占が理想であることに変わりはない。異論を唱えるものは異端である。公正な公開討論は、科学の文化とは無縁のものである。
啓蒙主義の理想では、科学は人類をより良く変える知識への道であった。科学と理性は前衛的であった。これらは昔も今も素晴らしい理想であり、何世代にもわたって科学者を鼓舞していた。私もそうだ。私は、科学と理性が科学的で合理的であるならば、賛成である。しかし、科学者と唯物論的世界観に、批判的思考と懐疑的調査からの免除を認めることには反対である。私たちは啓蒙主義者の啓蒙を必要としているのである17。
科学的な討論と対話
改革を進める上で重要なのは、科学的機関に討論を導入することだろう。これは簡単で当たり前のことのように思えるかもしれないが、現在そのような討論は非常にまれである。議論はまだ科学の文化に組み込まれていないのである。
本書の大部分を占める潜在的な議論の一つは、生命と心の現象が物理学に還元できるかどうかという問題である。多くの生物学者は、そうできると考えている。しかし、多くの物理学者はもっと疑念を抱いている。生命と心の現象は物理学で説明できるか」というテーマでの討論は、ほとんどすべての大学のキャンパスで起こりうることである。
もう一つ、科学の客観性についても議論が必要だろう。大学や科学研究機関には、科学や理性が唯一客観的な知の手段であると信じている人々が多くいる。リッキー・ジャーヴェイスの「科学は謙虚である」という信条を多くの人が共有している。科学は謙虚であり、自分が何を知っているか、何を知らないかを知っている。多くの大学には、歴史学者、社会学者、科学哲学者も在籍し、科学が実際にどのように機能しているかを研究している。彼らは、科学的客観性という理想が、科学の実践とどこまで一致するかを議論することができる。
そして、本書の第1章から第10章までで論じた唯物論の10の基本的なドグマがある。そして、これらの章の最後に、さらにいくつかの質問を提示したが、そのほとんどは、より専門的な討論や対話のテーマとなり得るものである。
もし科学的な討論が一般市民、大学生活、科学者会議などで普通に行われるようになれば、科学の文化は変わるだろう。一方が正しく、他方が異端であるのではなく、開かれた疑問が普通になっていくだろう。民主政治では、私たちは継続的な多元主義に慣れており、一つの政党が国民の支持を独占することはない。政治的な議論には、少なくとも二つの側面がある。民主主義国家では、全体主義になり民主主義の原理を破壊しない限り、政権与党は反対意見を一掃することはできない。
しかし、討論には限界がある。主なものは、一方が投票に勝ち、他方が負けることである。同様に、裁判でも、双方が自分の言い分を主張するが、判決はイエスかノーか、どちらかの一方になる。このシステムは、実用的な評決が必要な場合に非常に有効である。裁判官と陪審員は、犯罪で告発された人を有罪にするか釈放するかを決めなければならない。国会や議会は、どのような法律を制定するかを決めなければならない。曖昧な法律の塊ではなく、明確な法律が必要なのである。誰もが右側通行(米国、フランス、オーストラリアのように)か左側通行(英国、インド、日本のように)でなければならない。その判断は任意かもしれないが、左か右かでなければならず、左か右かではない。
科学におけるいくつかの決定は、どの分野の研究に資金を提供するか、誰に助成金を与えるか、学術雑誌に掲載する査読付き論文を受理するか拒否するかなど、同様の実際的必要性を持っている。このような決定は通常、非公開で行われるが、決定を下す人々の間で何らかの議論が行われることがよくある。
こうした実務的な議論は、公的なものであれ私的なものであれ、すべて合意に基づく決定に至る必要がある。しかし、ほとんどの状況はもっと曖昧である。科学研究の最前線では、答えがまだわかっていないとき、必然的に不確実性が生じる。例えば、ある10次元の超ひも理論が正しいのか、他の超ひも理論や11次元のM理論が正しいのか、物理学者たちの意見は一致していない。いくつかの異なる理論が共存しており、それぞれに支持者がいる。探索的な分野や不確実な分野では、議論ではなく、対話が最も生産的なアプローチとなる。対話とは、アイデアや意見を交換し、共同で探求していくことである。一方が勝つ必要はないのである。もちろん、科学者の間でも、あらゆる場面で対話や会話が行われているが、もし、最も一般的な対話が科学者の生活の中で定期的に行われるようになれば、正式な議論以上に、開かれた文化を促進することができるだろう。
私の経験では、最も生産的な対話は2,3人の間で行われる19。科学会議の定番である5人から10人の参加者によるいわゆるパネル考察では、ほとんど成果は上がりません。参加者が5 人から 10 人程度で行われるいわゆるパネル考察では、ほとんど何も生まれない。参加者がそれぞれ開会の辞を述べる頃には、議論のための時間は残されていないのが普通で、参加者が多すぎると、明確な焦点が定まらないことが多いからだ。2,3人であれば、もっと早く進めることができる。
科学助成への一般参加
科学は、君主制、共産主義国家、自由民主主義国家のいずれにおいても、常にエリート主義的で非民主的であった。しかし、現在、科学はより階層的になりつつある。19世紀、チャールズ・ダーウィンは、助成金に頼らず、挑発的で独創的な研究を行った多くの独立研究者の一人であった。このような自由と独立は、今日では稀なことである。科学研究費助成委員会が、研究において何が起こりうるかを決定する。その委員会の権力は、政治に長けた年配の科学者、政府高官、大企業の代表者たちの手に集中している。
2000年に英国で行われた政府主催の科学に対する国民の意識調査では、ほとんどの人が「科学はビジネスによって動かされている-結局は金のためだ」と考えていることが明らかになった。調査対象者の4分の3以上が、「ビジネスと関係のない科学者もいることが重要だ」と考えていた。3分の2以上の人が「科学者は一般人の意見にもっと耳を傾けるべきだ」と答えた。このような国民の疎外感を憂慮した英国政府は、「科学、政策決定者、国民の間の対話」に広く国民を巻き込もうとした20。官界では、それまでの科学に対する国民の理解政策から、科学と社会の「関与」モデルへと流行が移行していったのである。国民理解政策は「赤字」モデルに基づいており、単純な事実の教育が鍵であると考えられていた。科学者は一般大衆に真実を伝えるべきであり、そうすれば一般大衆はそれをありがたく受け入れるだろう、というものである。しかし、この方針はうまくいかなかった。イギリス国民は狂牛病は人間にとって何の脅威にもならない、と言われた。そして、実際に狂牛病が発生した。そして、遺伝子組み換え作物は体に良いと言われ、多くの人がそれを信じなかった。ヨーロッパ全土で遺伝子組み換え食品に対する消費者の反乱が起こり、科学への一般理解の推進者はそれを阻止することができなかった。
科学への「一般市民の関与」がその答えになるはずだった。しかし、このようなレトリックの変化は、実際にはほとんど変化をもたらさず、科学への資金援助は以前と同じように行われた。国民の不信感も同様であった。そして2000年代には、よく組織された市民参加型の活動がいくつかあったが、政策決定者は通常それらを無視した21。
エイズ活動家のような患者活動家グループは、すでに研究や治療に大きな影響を及ぼしている22。22 患者団体には多くの種類がある。相互扶助を主とする団体もあれば、高度に政治化された団体もある。しかし、患者団体の中には、製薬会社から資金提供を受けているものもあり、製薬会社は、医療機関に高価な薬品の代金を支払うよう求めるキャンペーンによって利益を得ることができる。しかし、このように一部の患者団体から搾取されているにもかかわらず、これらの団体の多くは、一般市民が技術的な議論に十分参加できることを証明している。
英国癌研究協会、髄膜炎研究財団、脳卒中協会のような医学研究慈善団体は、研究に資金を提供することにより、研究に直接的な影響を及ぼしている。英国にはこのような慈善団体が130団体あり24、合計で医学・医療研究に対する公的支出の約3分の1を拠出している。中には、主に一般人からなる理事会や委員会によって運営されているものもある。
患者活動団体や医療慈善団体の関心は、特定の病気や障害に限定されている。このような強い関心を持たない人々にとって、科学研究に関与する可能性はほとんどないのが現状である。そこで、より広く一般の人々の参加を実現するための実験を提案したい。科学予算の1パーセントを、科学や医学の専門家以外の人々が実際に興味を持つ研究に使うのである。現在、科学予算は、権威ある科学者、企業経営者、政府官僚からなる委員会が設定した議題に従って配分されている。英国では、医学研究評議会、バイオテクノロジー・生物科学研究評議会、工学・物理科学研究評議会などの公的な助成機関がある。英国政府の科学研究予算は年間約46億ポンドである25ので、1パーセントの基金には年間約4600万ポンドが含まれることになる。
科学研究によって答えが得られる問題で、公共の利益になるものは何だろうか。それを知るための最も簡単な方法は、提案を求めることであろう。ナショナル・トラスト、英国養蜂家協会、全国家庭菜園協会、オックスファム、消費者協会、女性協会、地方自治体、労働組合などの会員制組織からの提案が考えられる。これらの団体のニュースレター、専門誌、新聞、オンラインフォーラムなどで、研究テーマが検討される。これらの研究提案は、1%ファンドを管理する団体に提出され、その団体はオープンリサーチセンターと呼ばれる。
オープンリサーチセンターは、科学界の権威から独立し、非政府組織や任意団体を含む幅広い利害関係者を代表する理事会によって運営されることになる。医学研究の慈善団体のように、そのメンバーのほとんどは科学者ではない人々である。この団体は、受け取った提案に基づき、助成金の対象となる研究分野のリストを公表し、提案を募り、通常の方法で専門家の評価を受けることになる。通常の科学予算で賄われている研究への助成は行わない。
この新しい事業は、民主的な意見と市民参加に開かれており、追加支出はないが、人々の科学やイノベーションへの関わり方に大きな影響を与えるだろう26。科学者自身も、より自由に考えることができるようになるだろう。そして、もっと楽しくなるはずだ。
さらに、科学的なプロジェクトに資金を提供する方法として、他の魅力的な方法も考えられる。BBCのテレビ番組「ドラゴンズ・デン」で、起業家が審査員から投資を受けるためにピッチを行うのと同じように、広く一般に関心のある研究の提案を審査員に提出するリアリティ番組が考えられる。科学者と非科学者の両方を含むパネルが、助成金として提供する実際の資金、例えば1パーセントの資金から年間100万ポンドを得ることができるだろう。
資金源の多様性が高ければ高いほど、科学の自由度は高まる。幸いなことに、企業や慈善財団など、政府以外の資金源はすでに多岐にわたっており、中には公的な資金提供機関ではタブーとされている研究分野にも資金を提供しているところがある。財団は政府の資金提供機関よりも新しい状況に適応する自由があり、新しい研究分野の開拓を促進するのに最適な立場にあるのかもしれない。
異文化に学ぶ
私たちが知っている科学は、現実の主観的な側面を扱っているとき、あるいは避けようとしているときに最も弱くなる。バラの香りや楽器の音など、私たち自身が体験してきたものは取り除かれ、無臭の分子構造と振動の物理学だけが残されている。科学は、「私-私」の関係、つまり三人称的な世界観に閉じこもろうとしてきた。そして、「私-あなた」の関係、つまり二人称の体験や、一人称の体験、つまり私たちの個人的な体験は、極力排除してきた。私たちの夢、希望、愛、憎しみ、痛み、興奮、意図、喜び、悲しみなどの内面は、脳波のような電極からの読み取り値や、神経末端の化学物質のレベルの変化、コンピュータ画面上の2次元脳スキャン図に還元される。これらの手段によって、心は「それ」、つまり物体になる。
しかし、心を物体に還元しようとするのではなく、すべての自己組織化システムが主体であるとしたらどうだろうか。第4章で述べたように、哲学者の中には、唯物論は汎心論を含意しており、原子、分子、結晶、植物、動物などの自己組織化システムは、視点や内面、主観的経験を有しているとする者もいる。コンパニオンアニマルを飼っている人の多くは、犬や猫やオウムや馬が、感情や欲望や恐怖といった主観的な経験を持っていることを当然だと思っている。しかし、ヘビはどうだろう?あるいは牡蠣は?植物ならどうだろう。彼らの内面を想像することはできても、それを実現することは難しい。しかし、世界中の伝統的な狩猟採集社会では、人間以外の生物とのコミュニケーションを得意とする人々が、さまざまな動物や植物とつながりをもっている。シャーマンは、自分の心や魂を通して動物や植物とつながり、有益な情報を得ることができる。動物の居場所を知っていると言われ、狩猟の手助けをする。また、どの植物が治癒に役立つのか、あるいは精神を安定させる酒として有用なのかを知っている。
何世紀にもわたって、西洋の科学者や教育を受けた人々の間では、シャーマニズムの知識は原始的、アニミスティック、迷信的なものとして退けられてきた。人類学者はシャーマンの社会的役割を研究してきたが、彼らの多くは、シャーマンが自然界について有効な知識を持っているとすれば、それは主観的なものではなく、「通常の」感覚に基づく手段、あるいは試行錯誤によって得られたものであるとした。もしシャーマンが効く薬草や、アマゾン地方で伝統的に使われているアヤワスカのような幻の酒を発見したとしたら、それは様々な植物を手当たり次第に試してみた結果だと考えているのだ。しかし、シャーマン自身は、この知識は「植物の先生」から得たものだと言っている27。
もしシャーマンが、科学者が全く知らない植物や動物についての学習方法を本当に持っているとしたらどうだろう?もし、シャーマンが、科学者がまったく知らない動植物に関する学習方法を持っているとしたら、どうだろう。彼らは何世代にもわたって自然界を探索し、客観的方法よりも主観的方法に依存する、周囲の世界とのコミュニケーション方法を発見してきたとしたら?ブラジルの人類学者ヴィヴェイロス・デ・カストロは、その違いを次のように要約している。
客観化は私たちのゲームの名前である。他者という形が重要なのだ。アメリカ先住民のシャーマニズムは、これとは正反対の理想に導かれている。知ることは擬人化することであり、知らなければならないものの視点に立つことである。シャーマニズムの知識は、誰か、つまり別の主体である何かを目指している。他者の形態が人である。私がここで定義しているのは、昔の人類学者がアニミズムと呼んでいたものである。この態度は、形而上学の無為な信条をはるかに超えるもので、動物や他のいわゆる自然の存在に魂を帰することは、それらに対する特定の対処方法を伴うからである28。
人類の歴史の大部分において、人々は狩猟採集民として生活し、狩猟の方法を知り、狩猟する動物を深く理解していたからこそ、生き延びてきたのである。どの植物が食べられるか、いつどこで見つけられるかを知っていたからこそ、生き延びることができたのだ。彼らの知識は有効だった。私たちは今でも彼らの発見から恩恵を受けている。そして、これらの植物の薬効に関する知識の多くは、科学が発達する以前の文化において、はるか昔に発見された伝統的なものである。
20世紀の大半、科学的心理学者は、測定可能な行動と定量化可能な反応を研究することによって、外から客観的に心について学ぼうとした。行動主義の典型的な実験では、ケージに入れられたラットが、レバーを押して餌のペレットという報酬を得たり、電気ショックのような罰を避けたりすることを学んだ。最近の研究では、主に脳と脳活動のコンピュータモデルの研究に重点が置かれている。東洋と西洋の神秘主義の伝統では、人々は長い瞑想を通して心の本質を探究し、心のプロセスがどのように働くかを内側から発見してきた。これとは対照的に、学術的な心理学者や認知科学者は、通常、精神的なプロセスを観察したり報告したりする専門的な訓練を受けていない、有給の被験者(一般的には大学生)を使って研究を行う。仏教学者のB.アラン・ウォレスはこう言っている。
内観をアマチュアの手に委ねることで、科学者は心の直接観察が民間心理学のレベルにとどまることを保証している。. . 認知科学者は、心のプロセスを理解することに挑戦しているが、他のすべての自然科学者と異なり、彼らの研究分野を構成する現実を観察するための専門的な訓練を受けていない29。
今日、主にヒンズー教や仏教の伝統に根ざした瞑想の指導者が数多く存在し、科学者の中にも、自分自身の心を自ら探求し始める人がいる30。
心と体の相互作用に関する科学的な調査は、心を内側から調査するのと同じくらい後進的なものである。医学の分野では、プラセボ反応に見られるように、信念が治癒に及ぼす影響について認識されつつあり、バイオフィードバックを用いた研究により、人は血流や指など、通常は無意識に制御されている生理現象を意識的にコントロールできるようになることが分かっている(第10章参照)。しかし、これらの成果は、消化器系や循環器系に遠隔操作可能な自発的影響力を示すインドのヨギの偉業に比べれば、初歩的なものでしかない。彼らがこのような能力を獲得する手段のひとつが、呼吸のコントロールである。呼吸は随意神経系と不随意神経系の両方によって制御されており、ヨギーの呼吸法はその橋渡しをするものであろう31。
中国では、気功の伝統も同様に呼吸法を重視しており、中国の伝統医学や武術に多く応用されている。インドの伝統的なプラーナも中国の気も、英語では「エネルギー」と訳されるが、機械論的な生理学におけるエネルギーの概念とは異なる。生物におけるエネルギー保存の標準的な科学的ドグマには深刻な問題があり(第2章参照)、人間のエネルギーバランスの再検討は長い間待たねばならないのである。この分野では、これらの異なる伝統を新しい統合的な理解に結びつけることが可能かもしれない。
アフリカやインド亜大陸の多くの地域で、女性は重い荷物を頭に載せて、遠くまで運んでいる。東アフリカの女性の研究によると、女性は自分の体重の20%までを「タダで」運ぶことができ、ただ歩くのと比べてエネルギーを余分に消費することはないそうだ。また、バックパックを背負ったアメリカ軍の新兵よりも50%少ないエネルギーで、体重の70%まで運ぶことができる。しかし、特殊な歩き方だけで、この驚くべき効率性を説明できるのだろうか。
また、彼らの能力は、現実的な問題を提起している。なぜ、世界中の体育の授業で、ティーンエイジャーはこの技術を教えないのだろうか。荷物を効率的に運ぶ能力は有用である。現代人は人生のある段階で、空港のような荒れた地形で荷物を運ぶ必要が出てくるかもしれない。このスキルを無視する最大の理由は、社会的地位である。荷物を頭に載せて運ぶ女性は身分が低く、発展途上国に住んでいる。
傲慢さと俗物根性は、科学的教育を受けた現代人のほとんどに、自分たちの文化を含むすべての科学以前の文化に対する優越感を抱かせる。19世紀後半、こうした態度は、進化や社会の進歩という観点から科学的に正当化されるようになった。ジェームズ・フレイザー(nineteen size=「+1」 face=「MinionRegulSmalCapsOldsFigu」>1854-1941)などの人類学者は、人間の信仰はアニミズム、宗教、科学という三つの段階を経て進歩してきたと考えていた。原始社会はアニミズム的で子供っぽく、呪術的な思考が蔓延していた。キリスト教などの宗教は、より高度な進化を遂げたが、まだ原始的な要素を多く含んでいた。しかし、アニミズムも宗教も、人間の究極の理解である科学に取って代わられることになった。
では、なぜ現代人は、アフリカの無学な女性のように、頭に荷物を載せて運ぶことを学ぼうとするのだろうか。また、ヨガや気功のような前科学的な伝統から学ぶべきことがあるのだろうか?また、シャーマンが提供するものは、マンボ・ジャンボ以外に何があるのだろうか?
宗教との新たな対話
科学が唯物論の束縛から解放されるにつれて、多くの新しい可能性が生まれてくる。そしてその多くは、宗教的伝統との対話のための新しい可能性を提起する。
統計調査によると、宗教行事に定期的に参加している人は、そうでない人に比べて長生きし、健康状態が良く、うつ病になりにくい傾向があることが分かっている。また、祈りや瞑想の実践は、しばしば健康や長寿に有益な効果をもたらす(第10章参照)。これらの実践はどのように作用するのだろうか。その効果は純粋に心理学的、社会学的なものなのだろうか?それとも、より大きな精神的現実との結びつきが、より大きな治癒能力やウェルビーイングの向上をもたらすのだろうか。
もし、あらゆる複雑なレベルの生物が何らかの目的をもって生きているとすれば、地球、太陽系、銀河系、さらにはすべての星々にも、それ自身の命と目的があるということになる。そして、宇宙全体がそうである可能性もある(第1章参照)。宇宙の進化の過程には、固有の目的や終わりがあり、宇宙には心や意識があるのかもしれない。宇宙そのものが進化・発展しているのだから、宇宙の心や意識も進化・発展しているに違いない。この宇宙の心は、神と同じなのだろうか。おそらく、神が宇宙の魂や心、あるいは自然の魂として汎神論的な精神で構想されている場合のみである。キリスト教の伝統では、世界の魂は神と同一ではない。例えば、初期キリスト教神学者オリゲン(184-253年頃)は、世界の魂は、世界とその中の発展の過程を生み出した、限りなく創造的なロゴスであると考えた。ロゴスは神の一面であり、神の全体ではなく、その存在は宇宙を超越していた34。もし宇宙が一つではなく、多く存在するなら、神の存在はそれら全てを含み、超越していることになる。
宇宙は進化しており、継続的な創造性の場である。創造性は、神道のように宇宙の起源に限定されるものではなく(第1章参照)、進化のプロセスの一部として、人間の社会、文化、精神を含む自然のあらゆる領域で表現されている。これらの領域で表現される創造性は、究極的には神を源とするものかもしれないが、神を外的な設計思想として考える必要はない。ユダヤ教・キリスト教の伝統では、神は自然界にも創造性を吹き込んでいる。創世記の第1章では、神が大地と海から生命を呼び出した(創世記1: 11, 20, 24)とあるが、これは機械論的宇宙の技術神とはまったく異なるイメージである。また、創造的で進化する宇宙では、標準的なビッグバン理論のように、物質とエネルギーの出現が最初の瞬間に限定される理由はない。実際、宇宙論者の中には、宇宙の継続的な膨張は、普遍的な重力場から、あるいは「真髄場」から「暗黒エネルギー」が継続的に生み出されることによって推進されていると提唱する人もいる(第2章を参照)。
自然界の法則がむしろ習慣のようなもので、自然界の中に固有の記憶があるとすれば(第3章参照)、ヒンズー教や仏教におけるカルマの原理、すなわち自然界の記憶のようなものを暗示する因果の連鎖との関係はどうなるのだろうか。同様に、生物学的遺伝が形態的共鳴と種内の集合的記憶に大きく依存しているとすれば(第6章参照)、これは輪廻転生や再生の教義とどう関係するのだろうか。
もし、心が物質的な痕跡として脳に保存されるのではなく、共鳴のプロセスに依存するのであれば、記憶は死んでも消滅しないかもしれないが、通常、記憶を取り出すための身体は朽ち果ててしまう。では、このような記憶は、何か他の方法で作用し続けることができるのだろうか。すべての宗教が仮定しているように、肉体の死後も、肉体を持たない意識の形態が、個人の記憶(意識的か無意識的か)にアクセスできるのだろうか。
もし心が脳に限定されないとしたら、人間の心は、太陽系、銀河系、宇宙、神の心のような高次の組織システムの心とどのように関係するのだろうか。神秘的な体験は、人間の心と、より大きな、より包括的な意識形態との間のつながりという、見かけ通りのものなのだろうか。
もし、人間の心が、個人的にも集団的にも、神の究極の意識を含む高次の意識と接触したら、進化の過程にどの程度影響を与え、あるいは神の意志に影響を受けることができるのだろうか?進化する生きた宇宙において、人間は孤立した一つの惑星で展開するプロセスの一部に過ぎないのか、それとも人間の意識は宇宙の進化においてより大きな役割を果たし、宇宙の他の部分の意識と何らかの形でつながっているのか?
すべての宗教的伝統は、科学が発達する前の時代に生まれた。科学は、過去に誰も想像できなかったような自然界の姿を、はるかに多く明らかにした。例えば、19世紀になってようやく、生物学的進化と地質学的時間の永遠性が認識され、20世紀になってようやく、私たちの銀河系以外の銀河が発見され、ビッグバンから現在までの時間の広大な広がりが明らかにされたのである。科学は進化し、宗教も進化する。どの宗教も創始者の時代と現在では同じではない。唯物論的世界観による激しい対立や相互不信ではなく、科学と宗教が共に探求することによって、互いに豊かになれる時代が来ているのである。
開かれた問いかけ
唯物論のタブーが力を失えば、新しい科学的な問いを立て、願わくばそれに答えることができるようになる。
本書を通じて、私は研究の新しい可能性を提案してきた。例えば、腰痛、偏頭痛、冷え症などの症状に対する従来の治療法と「代替」治療法に関する比較効果研究の利用(第10章参照)、「ハード」科学において実験者の期待が結果にどれほど大きな影響を与えるかを調べる実験上の実験(第11章参照)、万有引力定数が変化するかを調べる既存データの分析(第3章参照)、動物の予感に基づいて地震や津波が予測できるか調べる大衆参加型の調査(第9章参照)などがある。
また、代替エネルギー技術や「オーバーユニティ」デバイスが実際に機能するかどうかを調べる賞品への挑戦もある(第2章参照)。
もちろん、既存の科学研究は継続される。大きな組織、莫大な資金、そして多くの雇用が関わっている場合には、何も急速に変化することはない。現在、世界中に700万人以上の科学研究者がおり、年間158万件の論文を発表している36。私が言いたいのは、これらの資源のごく一部を新しい問題の探求に充てるということである。私が言いたいのは、こうした資源のうち、新しい問いの探求に費やされているのはごく一部だということである。新しい発見は、従来の研究でよく踏まれてきた道を外れ、ドグマやタブーによって抑制されてきた問いに切り込むことで起こりやすくなるのである。
科学はすでに基本的な問いに答えているという妄想は、探究心を失わせる。科学者は他の人類より優れているという幻想は、科学者が他の誰からも学ぶべきことがほとんどないということを意味する。科学者は他人の経済的支援を必要とするが、自分より科学的教養の低い人間の意見に耳を傾ける必要はないのだ。科学者はその特権的地位と引き換えに、自然に対する知識と権力を提供し、人類と地球を変革するのだ。
唯物論的なアジェンダは、かつては解放的であったが、今では鬱屈したものとなっている。それを信じる人々は、自分自身の経験から疎外され、あらゆる宗教的伝統から切り離され、断絶感や孤立感に苦しみがちである。一方、科学的知識が解き放つ力は、他の種の大量絶滅を引き起こし、私たち自身の種を危険にさらしている。
科学が根本的な答えを知らないことを理解することは、傲慢さよりも謙虚さ、教条主義よりも開放性につながる
知恵を含め、発見され、再発見されるものはまだたくさん残っている。
