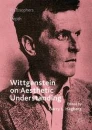link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-40910-8_10
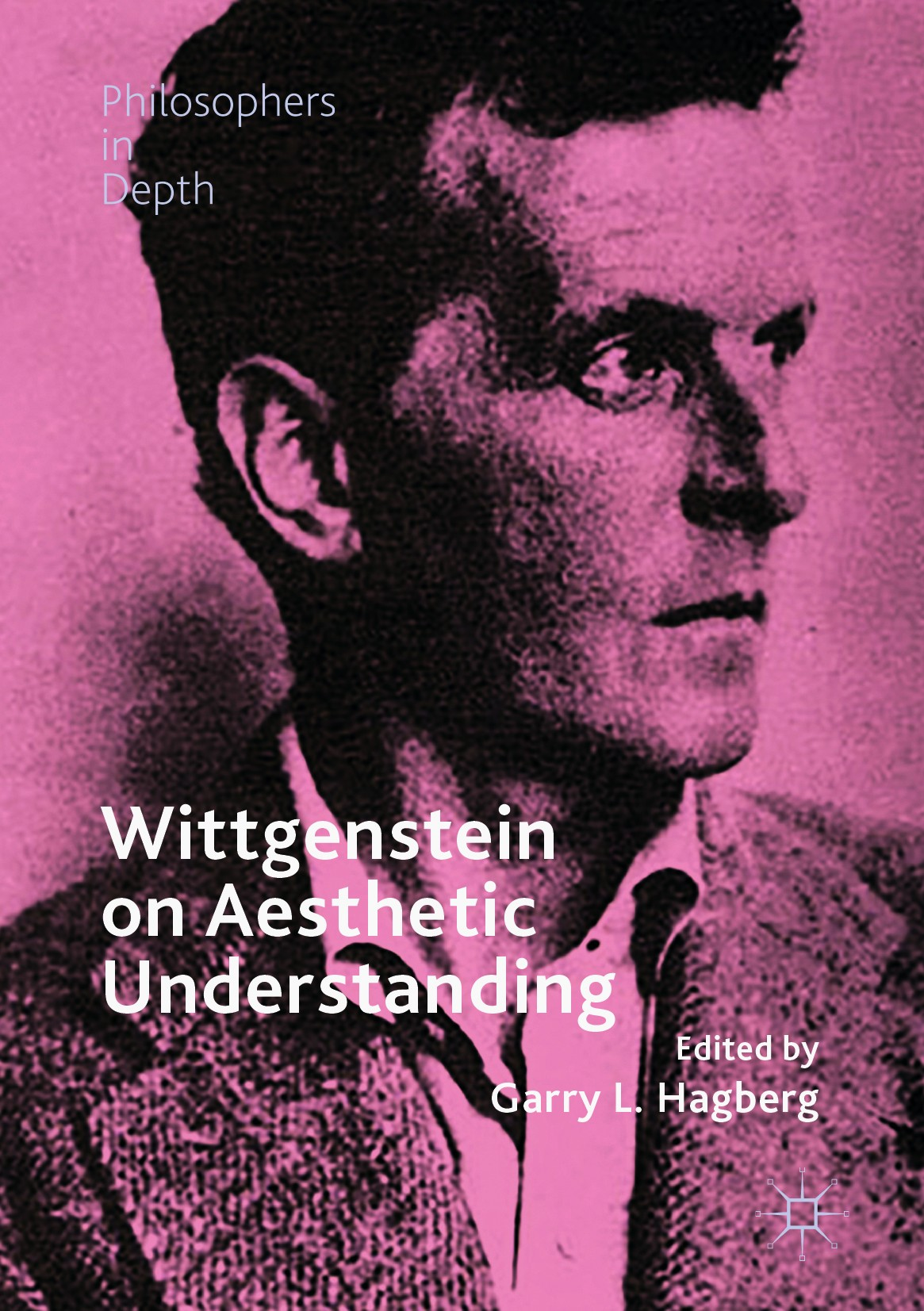
初回オンライン:2017年01月03日
ベルナール・リエ
10.1 表情鈍麻
ジャン=ポール・サルトルの小説『吐き気』を読み進めていくと、語り手であるアントワーヌ・ロカンタンが奇妙な問題に悩まされていることがわかる。それは一見、単に特異な問題に見えるかもしれないが、実は私たちの近代後期に驚くほど一般的になってきた問題である。それは、人間の顔……それも自分の顔が持つ心理的な表情を認識し、理解することが非常に難しいということである。ある日、浴室の鏡を見た彼は、謎めいた、奇妙な、人間離れした光景に目を奪われる。「灰色のもの」と彼は最初に表現したが、彼が見た「もの」は、実は、一見無意味な自分自身の人相という不可解な光景でしかなかった。
私の視線はゆっくりと、疲れ切って私の額や頬を巡ったが、確固としたものは何も見つからず、立ち往生している。明らかに鼻と二つの目と口があるが、どれも意味をなさない、人間の表情さえない。私は自分の顔を鏡に触れるまで近づけた。目も鼻も口も消え、人間らしさはない。熱で膨れた唇の両側には茶色い皺があり、隙間があり、ホクロの穴がある。絹のような白い羽毛が頬の大きな傾斜を覆い、鼻孔から2本の毛が突き出ている:それは地質学のエンボス地図である1。
キーワード:人間の顔 ふつうの言葉 現代思想 表現行動 人間の表情
ロカンタンは、自分の顔の細部を見分けるのに苦労はしないが、その視力は限界に達していることも確かだ。鼻、目、口という顔のパーツは、心理的な「意味」を持たないのだ。つまり、顔の物理的な外見ではなく、顔の表現的な意味に対する盲目である。結局、自分の顔を表情豊かなものとして、したがって完全な人間として見ることができないロカンタンは、その代わりに「月の世界」になぞらえ、その異世界の表面を幻惑的に調査し、「他の人間は自分の顔を評価するのにこれほど困難があるだろうか」と問いかけて、その調査を終了している。(p. 17). 20世紀、そして今21世紀の文学、美術、映画において、顔がどれほど頻繁に–執拗にさえ–登場し、醜態をさらしてきたかから判断するに、ロカンタンの問いに対する答えは間違いなく「イエス」に違いないと私は思う。確かに、人間の顔に対する私たちの関係には何か問題がある、あるいは「困難」があるように思われる。しかし、その困難さは、自分の顔に対する一人称的な評価をはるかに超えて、「顔」という概念そのものの理解にさえ影響を及ぼすことは明らかである。不確かさ、疑い、そして完全な懐疑。結局のところ、これらの種類の知的気分は、顔に関する私たち(そして私たちの文化)の考えを特徴づけるものであり、顔から自分や他の人について何が見えるか見えないか、ではないだろうか?私たちの多くは、人間の顔は、かつてウィトゲンシュタインが示唆したような「肉体の魂」を表現するものではなく、それどころか、奇妙で不気味で不透明なものでさえあるというロカンタンの感覚を完全に理解し、時には共有さえできないのだろうか2。
小説家サルトルがそうであったように、現代の多くの芸術家や作家は、人間の顔の意味や意義に関するこの種の不確実性に美的表現を与えてきた。例えば、ヴィトルド・ゴンブロヴィッチ、イングマール・ベルイマン、アンディ・ウォーホル、シンディ・シャーマン、J・M・コッツェー、トニー・アウスラーといった人物による顔の描かれ方を考えてみてほしい。彼らの作品は、顔という概念がいかに現代において深い問題を孕んでいるかを示す最良の尺度であるといえるかもしれない。しかし、顔に関する現代の不確実性が芸術家や作家にとって美学的に生産的であることを証明したなら、顔の意味の問題もまた、現代の哲学者や批評理論家にとって同様に生産的であっただろう。ウィトゲンシュタイン、レヴィナス、ド・マン、ドゥルーズ、ガタリ(哲学者のサルトルは言うに及ばず):これら後期近代を代表する思想家は皆、顔という概念の意味が、文化的に重要であるだけでなく、ある程度、哲学的な問題であることを認識している。そして、顔の問題に対する彼らの哲学的対応、すなわち、私が「顔の哲学」と呼ぶものこそが、この小論の主題なのである。
顔の哲学は、顔そのものと同様、特に人文科学に携わる者にとって深い本質的な関心を有していると私は考えている。第一に、私たちが研究対象とする文化財の多くにおいて顔の表現が非常に重要であるという理由だけでなく、顔から着想を得た理論的議論、特にレヴィナス、ドゥルーズ、ド・マンの議論が、文学研究、美術史、映画論、ニューメディア研究、宗教研究、さらには建築理論といった人文科学の幅広い分野において大きな影響を与えるようになっているためでもある。実際、顔に関する理論的な議論はここ数十年の間に盛んになり、人文科学のほぼすべての方面で分析や議論を形成している。
一方では、このような理論的興奮は刺激的な知的発展であり、私たちは現在、顔に関する理論を考え、実践するために、目もくらむばかりの数の理論をすぐに手にすることができる。しかし一方で、顔の哲学的意義に関する理解をさらに深めるためには、その膨大な量と多様性が知的障害となる可能性がある。というのも、顔に関する示唆に富む説明は多数存在するが、それらがどのように組み合わされるのか、明確なイメージを持っていないからだ。顔に関する諸説は、互いに補完しあうのか、それとも逆に矛盾するのか、それをどう判断するのか。それぞれの理論の前提、方法論、慣用句があまりにも根本的に異なるため、「顔」という言葉の使い方以外にはほとんど共通点がないように思われることもある。
顔の哲学の一貫した見解を得るためには、様々な説明を整理し、イディオムの表面的な相違を切り取って、明白でない一致と不一致を突き止めるための概念的な地図、つまり明確な概観が必要である。このエッセイの目的は、この重要だが複雑な理論的地形の中で私たち自身を方向付けるために、そのような地図を描くことである。まず重要な歴史的文脈を示した後、私は顔に関する最も影響力のある三つの哲学、すなわちレヴィナス、ドゥルーズ、ド・マンの哲学をマッピングし、最後に、顔や人間の表現に関する考察で、私の考えでは最も前途有望と思われるウィトゲンシュタインに目を向けることにしよう。
10.2 歴史の中の顔デカルトとロマン派
顔の近代哲学を理解するためには、その哲学的前提に歴史的な特徴があることを理解する必要があるが、そのためには、私が近代の表現の危機と呼んでいるものを理解する必要がある。というのも、私の見るところ、顔の概念も表現の概念も、近代において非常によく似た–おそらくは同じ–理論的な危機に見舞われているのである。結局のところ、真偽のほどはともかく、顔は人体の中で最も表情豊かな表面であると一般に考えられている。だから、表現の本質に関する問いが、しばしば顔の本質に関する問いと鏡合わせになり、またその逆の形で声高に叫ばれても不思議ではない。
第一に、デカルトによる「デカルト的」精神像の形成、第二に、デカルトに対する反動として、後のロマン派による人間の表情の価値化である。特に重要なのは、デカルトが人間を複合的な存在として捉え直したことであり、このことは人間の表現についての理解に深い影響を与えた。一方に表現されるもの(感情、情動、思考)があり、他方に知覚可能な表現(身体的な身振りや言語的な発言)があるのである。そして、多くの人にとって、人間の表現を理解するためには推論や解釈が論理的に必要であることは自明の理となる。なぜなら、このような人体像によれば、精神状態の無媒介の知覚などあり得ないからだ。そうでないと主張することは、ある種のカテゴリーミスを犯すことになる。明らかに身体(とその明白な行動)しか存在しないところに、心が見えると主張するのである。同時に、デカルトのシステムが内包する認識論の図式(心と世界のラディカルな区分)は、他の心についての推論や解釈を非常に問題なものに思わせるものであった。デカルトの認識論によれば、心は、彼が「イデア」と呼ぶ、外界の内的表象である心的実体によって作動する。私たちは外界に直接(表象的にのみ)アクセスすることができないので、「他の心」のような理論的存在も含めて、外界に関する私たちの信念は、多少なりとも信頼性のあるつなぎ合わせによる心の構築物であると理解されるようになったのである。そのため、当然のことながら、他人の身体と心、つまり外界と内界をどのようにしたら確実に結びつけることができるのかが、認識論上の厄介な問題となった。こうして生まれたのが、現代の哲学的な「他者の心」の問題である。
デカルトの心についての考え方は、人間の表現についての理解に、もう一つ、同じように重要な結果をもたらした。すなわち、人間の表現は、対象の心の中にすでに完全に存在する心の内容を「伝える」以上のことはできない。したがって、表現行為そのものは、表現される内容に対して実質的な形成効果を持つことができない。したがって、表現は道具的なものとなり、コミュニケーションの機能に完全に従属することになる。
このようなカルテス流の表現に関する思い込みは、広く影響を及ぼした。例えば、画家のシャルル・ル・ブランは、デカルトの哲学体系に基づき、情熱に関する有名な講義を行った。エルンスト・ゴンブリッヒが指摘するように、彼は顔を一種の「楽器板」として捉え、口や眉がそれぞれ内面の状態を示す「外側の」指標として機能していた4。ルブランは、顔の表現のレパートリーが決まっていれば、感情状態のレパートリーが決まっていると考えている。この仮定は、18世紀の人相学者ヨハン・カスパー・ラヴェーターや、現代のポール・エクマンなど、後の多くの顔研究者たちにも共有されるようになった。
また、デカルトの考えは、ホッブズ、ロック、コンディヤックといった近世の哲学者たちにも熱烈に支持された。5デカルトの考え方は、ホッブズやロック、コンディヤックといった近世の哲学者たちによっても熱心に採用され、その強力かつ広範な影響力によって、デカルト的前提は、人間に関する現代の多くの思考方法の根底に入り込んでいる。認知科学からポスト構造主義理論、分析哲学に至るまで、身体とその行動に関する現代の多くの思考を統一している重要かつ基本的なデカルト的仮定は、両者は本質的に表現的、心理的な意味を持たないというものである。例えば、他者を理解するためには「心の理論」が必要だという、現在では一般的な考え方を発展させた認知心理学者、アラン・レスリーの次のような発言を考えてみよう。「他人の(そして私たち自身の)精神状態は感覚から完全に隠されているため、推論することしかできない」6当然ながら、顔の表面も同様である。発達心理学者のアネット・カーミロフ=スミスとジェームズ・ラッセルが簡潔に述べているように、「人間の顔には特に精神的なものはない」7。つまり、顔はその空間構成を変化させることによって、心理的内容を示したり合図したりできるが、顔の表面(肉)はそれ自体、本質的に精神的意味を持たないとされているのだ。デカルトに倣って、身体は完全に身体であり、身体以外の何ものでもない。
しかし、前述したようにデカルトの遺産は二面性を持っており、ここまでは、より支配的な半分とはいえ、近代の表現の運命の半分を取り上げたに過ぎないのである。哲学者のチャールズ・テイラーが「表現-構成」伝統と呼ぶ、デカルトに対するロマン派とポストロマン派の重要な反応もあった8。表現に関するその広範な主張は、言語は不活性ではなく、既成の内容を記述し伝達することに限られないという、欺瞞的に単純な観察から始まっている。それどころか、言語表現は意味論的に創造的であり、まったく新しい種類の意味、そしておそらく最も重要なのは、新しい種類の価値(感情、道徳、美的)を構成することができる。このため、テイラーはこの伝統を「表現的構成的(expressive-constitutive)」と呼んでいる。
この新しいロマン主義的な表現についての考え方をきっかけに、身体的な表現行動の分野全体が、新たに興味深いものとなり、哲学的にも重要な意味を持つようになったのである。表現構成主義の伝統は、言語表現が実は、人間の表現行動のもっと広い分野の単なる部分集合に過ぎないことにすぐに気づいた。この分野には、身体的態度、身振り、そしてもちろん顔の表情といった非言語的な事例の典型的なものが含まれる。そして、この伝統が身体表現の意味性に新たな関心を抱いたことは、心は内面的で私的なものであるというデカルト派の仮定に対する暗黙の疑問と密接に関連していた。表現は不活性ではなく、主体の内部にすでに存在するものを単に明示するものでもないため、表現行為が構成するのに役立つ意味は、存在論的に人間の主体の「内部」に位置づけることはできないことになる。実際、人は、言葉、動作、身振り、声の調子、表情など、自己を表現する方法によって、自己を明らかにするのではなく、構成しているのだ。
表現に関するこのような主張を魅力的だと思うかどうかは別として、この歴史は少なくとも、顔に関する理論的な議論がしばしば持っていると思われる感情的な「電荷」、つまり、明らかに自らが実行していると思われる実存的利害関係を説明するのに役立つだろう。この二つの遺産(デカルト派と表現派)の間の現代的な関係は非常に複雑である。表現についての両方の考え方がまだ生きていて、互いに競争しており、さらに悪いことに、この二つの境界はかなり頻繁に交差している。このもつれた遺産は、表現という考え方が現代の自己概念の多くで非常に重要視されている一方で、私たちの自己イメージのあり方に依然として大きな影響力を持つデカルト的な心のモデルのために、表現がどのように機能し、どのように実在し得るのかさえ理解しがたい状況を私たちに残している。
10.3 理論における顔 レヴィナス、ド・マン、そしてドゥルーズ
このような歴史を経て、20世紀には、人間の顔と表現に関するいくつかの基本的な問いが開かれた。その中で最も重要なものは、大きく3つに分けられる。
第一に、表現面の性質、特に人間の顔の表面についての存在論的な疑問がある。顔は文字通り表現的なのか、それともそう見えるだけなのか。
第二に、表情の意味をどのように理解するかという認識論的な問題がある。私たちは、無媒介的に精神状態を認識できるのか、それとも推論や解釈によってのみ認識できるのか?
第三に、表現の究極的な源泉についての疑問がある。それは、心、主体、人間全体、あるいは、言語、権力、文化など、心理学的なものでさえない、まったく別の何かだろうか。
もちろん、顔についての重要な問いはこれだけではないが、哲学的に最も重要な問いでもある。実際、顔に関する主要な哲学–レヴィナス、ド・マン、ドゥルーズ–が互いにどのように関わるかを知るためには、それぞれの思想家がそれに対してどのような答えを選んだかを見ればよいのである。
たとえば、レヴィナスの人気のある顔の現象学は、身体に関するデカルト的な仮定を大胆に破り、人間の表情が実在することを(問1について)肯定している。実際、レヴィナスは人間の表出性のパラダイムとなる場として顔を頻繁に指摘し、しばしば顔という概念を表出という概念と同一視している。また、問3では、表現の源泉が個々の人間であることを肯定している。しかし、問2においてレヴィナスは、他者の顔の表情を「知覚する」あるいは「理解する」と言えるのかについて、深い疑念を抱いている。
当然のことながら、この疑問はレヴィナスの著作において「顔」という言葉を深く曖昧なものに変質させる。レヴィナスが顔について語る一つの意味によれば、「顔」という言葉は、視覚的・触覚的な知覚が可能な、通常の、経験的な顔を指している。しかし、レヴィナスはフッサールの意図性理論をデカルトの表象主義的認識論の延長として解釈しているため、他者の顔の表情を、認識する自己に由来する概念やカテゴリーに包含させずに認識することはあり得ないと考えているのだ。それゆえ、経験的現象として理解される顔は、仮面や凍りついた「戯画」(p. 198)として、歪んだ形でしか認識できないのである。
しかし同時に、レヴィナスは有名なように、他者の顔の啓示的なヴィジョンの可能性を主張している。しかし、このように理解される顔は、知覚する自己の認知的到達点を絶対に超越しており、したがって、文字通り見ることも触ることもできないものである。レヴィナスによれば、私たちは他者の真の顔を実際に見ることも理解することもできない。むしろ、私たちはその圧倒的な魅力を目撃することしかできない。それは、私たちのモナドのような孤立を打ち砕き、私たちの主観性の自律性そのものを問う奇妙な逆意図性によって迫ってくる。したがって、顔が倫理と密接に関連している。確かに、極限の倫理ではある。レヴィナスの他者の顔は、私たちの意図性を「包み込む」、したがって認識論的に暴力的に把握することを超えて、認識の対象としてではなく、啓示として私たちに襲いかかる。レヴィナスは啓示こそが「表象」に代わる唯一のものだと考えており、認識論に関するデカルト的前提が彼の哲学的選択肢に対する感覚をいかに深く形成しているかを示している。
他方、ドゥルーズとド・マンは、表現の「源」についての質問3に対する根本的に異なる回答から始めることによって、顔についてレヴィナスとは(そして結局はお互いに)全く異なる結論に達している。ド・マンとドゥルーズの両氏は、ポスト構造主義の「主体批判」の典型的な動きとして、デカルトの二元論的な心像を急進させることによって、デカルトの主体論を弱体化させようと試みる。この心像は主体(コギト)を、身体、脳、経験的自己など考える人間に関するあらゆる経験的ものから区別する。デカルトの二元論を(論理的には)極限まで推し進めることで、彼らはデカルトよりもさらに根本的に、経験的、心理学的な残滓、つまり世俗的な自己や自我をほのめかすものを排除して、主体を「浄化」しようとする。「主体の批判」はそれによって、デカルトの「主体」が根本的に非主体的な、あるいは非主体的な基盤の上に成り立っていること、つまり、「誰」は、つまるところ、「何」の一種であることを見いだすのである。しかし、ドゥマンとドゥルーズは、主体の根底にある「何ものか」を全く異なるものとして発見する。
ドゥマンの場合、言語が主体を構成し、その主体は言語の話し手ではなく、いわば言語そのものによって語られる(したがって生み出される)何かであることが明らかにされる。したがって、デ・マンは、デカルト派の主体像だけでなく、ロマン派の言語観をも、その伝統的な表現と構成の関係の理解を反転させることによって、ラディカルに変容させている。人間の表現行為は、もはや新しい意味を構成するものではなく、むしろ、言語がそれ自体で無名に働き、人間の表現の修辞的な「効果」を構成するのだ。この驚くべき逆転は、ド・マンの人間の顔に対する理解に深い意味を持つ。顔の表情は、人間表現のパラダイムとしてではなく、単なる修辞的な「効果」、つまり、ド・マンが有名なプロソポエイアと呼ぶ言葉の綾が生み出す現象的なイリュージョンとしてド・マンは再表現しているのだ。ド・マンが説明するように、「人間は顔を持っているからこそ、他の人間に話しかけ、顔を向けることができる。しかし、完全に自然でも完全に人間でもない言説の様式に身を置いているからこそ、顔を持っている」11。不治の病であるこの状態に対して可能な唯一の治療法は、私たち「主体」は「その代理人ではなく、その産物」であるから、それを祝うことも非難することも無意味である、という皮肉な洞察である。したがって、もし私たちが「顔」を「価値の源泉」に変えようとするならば、私たちは「ナイーブ」であるとドゥルマンは宣言する(p.122)。
ドゥルーズは、ド・マンと同様にデカルト的主体の解体に熱心であるが、ド・マンとは異なり、「表現」の現実を受け入れ、それを自らの(表現主義的)形而上学のまさに中心に据えてさえいる。しかし、ドゥルーズは、表現し、新しい意味を構成するのは人間ではない、という点ではドゥマンに同意している。その代わりに、ドゥルーズが「前個人的特異点」と呼ぶ実体によって機能する奇妙で寓意的な「仮想」世界(「コスモス」ではなく「カオスモス」)が、世界における表現上の意味と意味の真の源である(これらの「特異点」は、ド・マンの説明における言語の役割を担っていたものである)。そして、これらの特異点は、前個人的であり、非人間的であるがゆえに、人間の心の擦れる限界として描かれている認知的地平によって妨げられることなく、根本的に新しい感覚や意味を構成することができる。ドゥルーズは、人間はそれ以外の場合、「表象」によって思考し、伝達することに制限されていると仮定している。表象は(デカルトと同様に)不活性かつ道具的であると彼は考えている。つまり、レヴィナスのように、ドゥルーズは「普通の」人間の認識を本質的にデカルト的な用語で描き続けているのだ。もちろん、ドゥルーズの根本的に偶然的な宇宙では、新しい意味が可能である(例えば、絵画、哲学、映画において)が、それは常に最終的には偶然の出来事の結果であり、むしろ人間個人の表現行為によるものである。
したがって、ドゥルーズにとって、人間の顔の意味ある表現は、(ル・ブランやラヴァテルを想起して)不活性で道具的であるほかないのである。ドゥルーズがフェリックス・ガタリと共著した『千のプラトー』にあるように。「顔は……適切な意味づけができないような表現や接続をあらかじめ中和する場を区切る。ドゥルーズとガタリの顔に関する説明の中心には、彼らが「顔性の抽象的機械」と呼ぶものがあり、それは頭の前面を「顔の単位」で符号化することによって「顔化」し、あらかじめ決められたイデオロギー的「意味」を伝達するものである。ラバターの『人相論』のポストモダン的パロディのように聞こえるが、彼らは「具体的な個性化された顔は、こうした[顔]単位の組み合わせに基づいて生産され、変容する。たとえば、金持ちの子供の顔には、すでに軍隊への召集が見て取れ、ウエストポイントの顎がある」(177頁)と主張している。そして、顔を完全にイデオロギー的なものとしてとらえ、その「解体」を(きわめて論理的に)求めている。
「顔は偉大な未来を持っているが、それは破壊され、解体された場合のみである」(p.171)。こうして、質問3に対する根本的に非主観的な回答から始まったドゥルーズは、(質問1について)表現の現実を一般的に肯定することに終始するが、特に顔についてはそうではない。人間の顔の表情は、むしろ、徹頭徹尾、イデオロギー的であり、顔の真実は、実際、根本的に「非人間的」なのである。「人間の中の非人間的なもの、それが顔というものだ」(p.171)。
10.4 ウィトゲンシュタイン的人相学
これらの主張が奇妙に聞こえるかもしれないが、このような顔に関する理論は、人文科学全体で大きな影響力を持つようになった。それは、顔の複雑な現象学について、私たちの多くが折に触れて抱くであろうある種の直観を、強力に表現しているからだと思う。というのも、私たちは(ド・マンとともに)、自分のパーソナル・アイデンティティ(いわば「顔」の感覚)が不安定な言葉と概念の網でできていて、いつ崩壊するか、溶解するかわからないと感じるとき、つまり、自分の人格と人間性を一挙に失うことを恐れるときがないだろうか。そして、他者の顔を覗き込み、(レヴィナスのように)他者の心を本当に理解しているのか、それとも自分自身がそこに投影した意味を知覚することにとどまっているのかを問うときがあるのではないだろうか。また、ドゥルーズとガタリのように、人種的ステレオタイプを永続させるため、ジェンダー規範を強化するため、あるいは、より多くの商品を販売するために、顔がイデオロギー的目的のために利用される極悪な方法に、どうして周囲を見渡して狼狽を感じないことができるだろうか。これらの説明がこのような直観を力強く語っている限り、私はそれらに異議を唱える気はほとんどない。しかし、これらの説明のどこにも、私たちが他人の顔や自分自身の顔を経験する普通の、日常的な方法、つまり、心や人間性の意味のある表現として経験する方法を適切に説明するものは見当たらない。そのためには、20世紀哲学の分野で、ウィトゲンシュタインとその影響を受けた人々、特にスタンリー・キャベルが占有していた、全く別の場所に目を向ける必要がある。
まず、ウィトゲンシュタインがデカルト的な図式を基本的に拒否していた、と言えるものから話を始める。つまり、よく知られているポスト構造主義のデカルト的主観の批判とは異なり、デカルトの理論の要素を受け入れた上で、それを解体、脱構築していくのだが、ウィトゲンシュタインは、そもそもデカルトの描いた人間とは何かという欠陥のある像を受け入れる必要がないことを私たちに思い起こさせるだけであるのである。人の身体について、あるいは人の心について語るとき、私たちは、見えるものと見えないものの間を行き来する、二つの異なるものについて話しているのではない。デカルトの近代的継承者の中で最も強力な科学的伝統によって広く想定されているように、身体は完全に身体ではなく、むしろ身体は常にすでに心理的生命を表現しているのだ。身体を単なる物質的実体(単なる物質、単なる肉)として考えることは、実は、身体に激しい理論的還元を加えることである。このことを認識していたウィトゲンシュタインは、デカルト的な図式に対する彼の代替案を、まさに有名な一文に集約することができる。「人間の身体は、人間の魂の最良の絵である」13このことから、人間の顔や身体の動きそのものに精神状態そのものを見ることができるという普通の考え方に、論理的な困難はないことがわかる。ウィトゲンシュタインが『ゼッテル』の中で述べているように、「私たちは感情を見る」ウィトゲンシュタインが顔に魅了されたのは、まさにその動きが非常に複雑で微妙であるため、純粋に物理的な「特徴の説明」を「与えることができない」ことが多いからである15。この「非常に重要な」16事実についてウィトゲンシュタインが興味を持ったのは、顔の表情を理解するとなると、それが何の問題も生じないからであり、純粋な物理的データから心理的意味を推測する必要があるならそうしなければならない。顔の心理的表情を純粋に空間的な用語で直接表現できないことが多いので、私たちの心的状態の帰属は推論や解釈のプロセスの間接的な結果でなければならないと考えたくなるのはなぜだろうか。もし、あるプロセスを対比するための「直接的」な代替案がないのなら、なぜ「間接的」と呼ぶのだろうか。おそらく、ウィトゲンシュタインが示唆するように、私たちはただ「感情を見る」ことができるのだろう。
レヴィナス、ド・マン、ドゥルーズについての私の議論を構成するのに用いた三つの一般的な問いを思い出して、私はウィトゲンシュタインの立場をこのように要約する:
彼は、(存在論に関する問1について)顔そのものの内在的表現力、(認識論に関する問2について)その表現の理解可能性、(表現の「源泉」に関する問3)について個々の人間とその顔や身体の表現との密接なつながりを肯定する顔のビジョンを私たちに提供するのである。そして、ウィトゲンシュタインは、「面と向かって」、「彼女はあなたの顔に向かって言ったのか」、「どうして彼は人前で顔を見せることができるのか」、「私はもう彼の顔を見ることができない」といったおなじみの言い回しの中で、通常の言語に埋め込まれたものと非常に似た顔のビジョンを私たちに提供している。
では、ウィトゲンシュタインの立場は、これまで述べてきた様々な顔の哲学とは明らかに大きく異なっている。ウィトゲンシュタインも含めて、顔という概念は、心、自己、表現、外観、意味、理解、人間など、顔に関連する概念とでも呼ぶべき緩やかなネットワークと内的に関連していると理解されている。しかし、ウィトゲンシュタインとは異なり、他の主要な顔に関する哲学のほとんどは、これらの様々な用語の意味や、これらの概念がどのように論理的に相互関連しているかについての通常の理解に懐疑的である。そのため、修正主義的な精神に基づき、顔に関連する概念の意味や全体的な構成を(時には極めて根本的に)変更しようとするのだ。では、ウィトゲンシュタインの顔へのアプローチは、これらの他の理論の理解や評価に影響を与えるべきなのか、またどのように与えるべきなのか、私たちは当然ながら考えなければならない。ウィトゲンシュタインの読み方として有力なのは、彼の著作を、私たちの普通の言葉や概念に対するこれらの異常な理論的修正を否定するものとして捉えることである。この哲学的に「伝統的」な読み方によれば、ウィトゲンシュタインが私たちに提供するのは、私たちの様々な通常の言語ゲームを支配する文法的規則や概念構造を思い出させるものである。このような注意喚起によって、これらの規則の違反に基づく理論的思索を抑制し、あるいは単に否定することができる。したがって、レヴィナス、ド・マン、ドゥルーズが顔(および顔に関連する他の概念)についての主張を、心や身体についての未構築のデカルト的仮定に基づいていることを示すことができる限り、伝統的な考えを持つウィトゲンシュタインの読者は、彼らの理論は単に哲学的混乱の例であると主張することだろう。
しかし、私が取りたいのは、そのようなアプローチではない。スタンリー・カベルに倣って、私はウィトゲンシュタインの著作が、顔に関する主張であれ、その他のものであれ、通常の言語に関する哲学的主張の性質と力について、かなり異なる種類の教訓を私たちに与えてくれるものと考えている。ひとつには、ウィトゲンシュタインにとって、言語は実際には規則や他の種類の形而上学的・概念的構造によって支配されているわけではないことを示すことが、キャベルの研究の継続的な野心となっている。キャベルはウィトゲンシュタインに関する初期のエッセイの中でこう述べている。「日常言語が事実上、あるいは本質的に、規則の構造や概念に依存しないことは、その機能を何ら損なうものではなく、(ウィトゲンシュタインの)後の哲学に描かれた言語像が目指すものである」17先に述べた歴史哲学的な枠組みの中で、キャベルのウィトゲンシュタインは、言語は表現的であり構成的でもあるというロマン派の見解を受け入れ、本質的に創造的でオープンエンドであると言っていいかもしれない。したがって、言葉は固定されたルールに支配された意味を持たない(そして実際、持つことができない)。文法構造が意味を支配せず、固定化することもできないからこそ、言葉は創造的に新しい文脈や用途に投影され、そのように投影されることができる。もちろん、何を言っても意味が通じるわけではないが、何が確信や信念や同意を与えるか、あるいは与えないかを先験的に決定する方法はない。
したがって、通常の言語は、形而上学的な過剰やファンタジーに迷い込んだときに戻ってくるように誘導されなければならない「常識」の空間ではなく、常に壊れやすい間主観的な達成物である。そのため、「いつ何を言うか」についての普通の言葉の主張は、その性質上、脆弱であり、非難や無関心、その他様々な誤作動の可能性があるのである。実際、「いつ何を言うか」についての主張が意味を持つのは、ある種の言葉の意味が疑わしい場合、つまり、リチャード・エルドリッジが言うように、「これらの言葉によって表現される概念の適用が、何らかの形でぼんやりと利用可能であると同時に、減衰したり争われたりする」18場合だけだ。そしてこれは明らかに、近代後期の現代において「顔」と、それに一般的に関連している言葉や概念、特に「表現」の概念について当てはまるのではないだろうか。
カヴェルのウィトゲンシュタイン的な言語観の特徴を強調するために、哲学者アブラム・ストロールがその著書『表面』19の中で肯定しているビジョンと対比させてみたい。ストロールは、「表面」という概念に関する研究を、通常の言語哲学の一例として紹介し、私たちの言葉による生活が規則に支配されているという哲学的に伝統的な見解を受け入れていることを明らかにしている。彼はこの研究を「通常の会話の幾何学」に対する探究と呼び、「表面という概念が特に重要なメンバーである概念の体系」(S、11頁)と表現している。
ここで特に注目したいのは、ストロールが「顔」という概念を「面」という概念の変異株と見なすべきかどうか、つまり「顔」は「面」の一種であるのか、という興味深い考察を行ったカ所である。しかし、「顔」と「表面」という言葉の普通の使い方を調べた結果、「顔を表面の一種と考えることは意味をなさないばかりか、この二つの概念は全く異なる論理を持つ」、つまり、この二つの概念は概念的には全く関連していない、という彼自身が「驚くべき結論」に達する(S、P190)。
ストロールが気づいたのは、「面という概念は、主に人間や動物に適用される意味場に属する概念である」ということである。一方、「表面」という概念は、「主に無生物に適用される語彙構造に属する」「私たちは顔で人間を識別するが、崖は識別さない」とストロールは説明する。人間の顔は、落ち込んでいるとか、喜んでいるとか言えるが、立方体の顔はそうは言えない」表層語について、ストロールは、「無生物の意味論に属する」と指摘している。数学の平面や曲線のような幽霊のような抽象物や、その物質的で動かない対応物である象牙のダイスやピラミッドに適用される」「しかし、『フェイストーク』は本質的に生者と死者、肉と血でできた物体についてである。この2つの概念は、一般に結合しているのではなく、ばらばらになっている範囲を選び出す」(S、191頁)。
ストロールの議論で何が問題になっているのかを知るために、私はストロールの「生者」と「無生物」の区別-顔と表面の間の境界線を示す-を、表現者と非表現者の区別と同義と見なすことを提案する。顔(と生けるもの)は表現的であり、表面(と無生物)はそうではない。これまで見てきたように、カルテス以後の多くの思想家(認知科学者からポスト構造主義の理論家まで)は、この意味的・概念的な区別を尊重しない。その代わりに、顔は本質的に表現不可能な表面とみなされることが多い。しかし、解釈、推論、投影によって、(ある意味で)表現可能な表面とみなされることがある。ストロールは、「顔」と「表面」という概念が異質な現象を抽出すると主張することで、ヴィトゲンシュタインの言うところの「人間の魂の最良の絵としての人間の身体」という特殊な人間像を再確認したいだけなのだろうと思う。通常の言語の根深い概念構造の中では、「顔」と「表面」という概念は意味的に分離していることを思い起こさせることによって、ストロールは、人間の顔についての話に表面の話を拡張しようとする試み(科学的か理論的かを問わず)を拒否する権利があると考えるのだ。
しかし、私は、ストロールでさえ、顔が表面であるという考えに最初の妥当性を見出し、それに反する自分の発見を「驚くべき」としたことに注目せざるを得ない。このことは、非常に重要なことだと思う。先に述べたように、ストロールは自分の発見を、彼が「普通の会話の幾何学」と呼ぶものの根底にある体系的構造を明らかにするものであり、したがって、顔や表面という概念についてどう考えるべきかを思い起こさせるものであるとしている。しかし、もし(キャベルのウィトゲンシュタインが示唆するように)言語がオープンエンドであり、固定的な文法構造を持たないのであれば、ストロールの概念的喚起は明らかに彼の望むような論理力を持ち得ない。
しかし、このことは、ストロールの発見が哲学的な関心を持たないことを意味するものではない。それどころか、キャベツ的な枠組みで再文脈化することで、かえって面白さが増すかもしれない。というのも、ストロールが行ったのは、「顔」と「表面」という二つの概念の関係が、通常の言語そのものの中で変化していく、いわば「音」の変化をとらえることだからだ。二つの概念の間の意味の違いがかすか過ぎて聞こえないうちに、しかし概念の曖昧さはすでに始まっている。実際、現代文化は、人体という表現力のある生身の表面と、モノという無生物の表面の境界が曖昧になり、時には錯乱するような感覚に支配されているのではないだろうか?2002年にクーパー・ヒューイット国立デザイン博物館で開催された「Skin: Surface,Substance+Design」展では、現代文化がまさに顔と表面、肌と物の間の曖昧さに取り憑かれ、ストロールの文法的注意喚起によって巻き戻されている例を数多く見ることができる20。私たちの顔や身体がますます単なる物質的な表面のように見えてくるにつれて、私たちはますます、それ自身の不気味な技術的生命で輝いているように見えるものの世界に囲まれている。まるで、私たちがもはや自信を持って自分の身体の肉体に見出すことのできない表現的生命が、ポストモダン(「ポストヒューマン」とも言う)の世界の商品と建築構造の生ける表面の中でさまざまに不気味な形で回帰せずにはいられないかのようだ。言い換えれば、「表面」という概念の意味的範囲はより広く、より一般的になっており、身体や顔を表面の一種として考えることが、ますます「自然」、つまりより「普通」に聞こえるようになったのである。ストロールの説明が重要なのは、このゆっくりとした意味論的変化を聞き取ることができると同時に、「顔」と「表面」の違いの響きが、その変化の過程でいかに減衰しているかを明らかにするためだ。
普通言語哲学についての私の理解を明らかにした上で、最後に、ウィトゲンシュタインの「顔」に対するアプローチが、レヴィナス、ド・マン、ドゥルーズの理論の理解にどのような影響を与えるべきかという問題に立ち戻ることによって、私は結論づけたいと思う。まず、ウィトゲンシュタインが現代の「顔」の哲学に多大な貢献をしているのは、人間の「顔」の表現力と了解性をいかにして肯定しうるかを示しているからだ。そうすることで、ウィトゲンシュタインは、顔や、顔に関連する表現、心、意味といった概念に対する私たちの通常の理解を根本的に見直そうとする理論家たちの主張に強制されない、哲学的な理由を私たちに与えている。しかし同時に、ウィトゲンシュタインはレヴィナス、ド・マン、ドゥルーズのような理論家の修正的主張を単に拒否する根拠も与えてはいない。なぜなら、ウィトゲンシュタインの言語観を受け入れるならば、「表現」という言葉が意味するものは、きっぱりとした形で固定されることはありえないからだ。それどころか、「表現」という概念は、私たちのあらゆる概念と同様に、私たちの相互主観的な同調の中にのみ「生命」を持っており、それは壊れることも、枯れてしまうこともあり得る。そして、顔の表情を知覚する能力(人間の表情全般を知覚する能力と同様)には、その表情に気づかない、あるいは気づかないという可能性がつきまとう。したがって、私たちが(どのような理由であれ)自分の顔をそのように見ることを選択した場合、人間の顔を本質的に表現的な意味を持たないものとみなすことを止めるものは何もない。実際、冒頭で述べたように、「表情の盲点」は、哲学、科学、芸術など、現代文化において特によく見られる、強力な誘惑であるように思われる。
さらに、キャベルの著作が示唆するように、「表現力の欠如」は、その近縁種である他者の心に対する懐疑と同様に、哲学的に反論できない知的観点を有している。懐疑論に関するキャベルの重要な発見は、懐疑論者の立場が、修正を必要とする単なる知的誤りであるどころか、実際には重要な哲学的真理を表現しているということだった。つまり、概念や規則の枠組みのような、私たちが共に生きることの意味を示す根拠は存在せず、私たち自身が、共通の感覚形成実践に投資し、それを大切にすることによって維持するもろい同調だけが存在するというのである。したがって、私たちの誰もが、そのような脆弱な同調を認めないということを止めるものは何もない。同じ理由で、私たちが自分の顔や体の表現上の意味を認めないことを妨げるものは何もない。しかし、カヴェルもかつて言っているように、「承認の概念は、その成功によってと同様に、その失敗によって証明される」21。そこで私は、顔の表現力を認めないこと、特に現代の理論におけるその否定は、それ自体が、いわば顔を向けることによってその表現力を認める特殊な方法であると言いたいのである。それゆえ、顔の現代哲学を完全に説明するためには、カヴェルのウィトゲンシュタインが重要な役割を果たす必要がある。なぜなら、ウィトゲンシュタインとともに人間の顔の本質的な表現力を認めてはじめて、その否定、拒否、忘却に何がかかっているのかを把握することができるのである。
キャベルはかつて、懐疑主義と人間の表現が絡み合った運命を理解するためには、「人体に対する私たちの態度の説明」、すなわち「懐疑主義の下での人体の運命の想像力」の歴史的研究が必要だと示唆した22。顔に関する近代哲学を徹底的に研究すれば、キャベルが最初に構想した人体のまだ書かれていない歴史に重要な一章を加えることができるだろう。そして、この小論は、近代における顔の運命の想像力の歴史について、その長い章の最初のアウトラインを提供したに過ぎないが、私はいくつかの有望な道筋を描くことができたと思う。