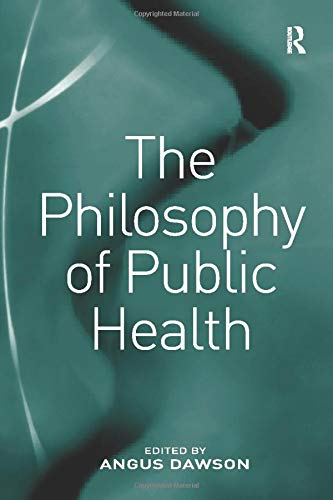
公衆衛生の哲学
公衆衛生は、医療行為の特殊な領域であり、緊急の議論を要する一連の哲学的問題を提起している。公衆衛生の哲学には、公衆衛生における「公衆」とは何を意味するのか、「集団」とは何を意味するのか、といった形而上学的な問いかけが含まれる。
「集団」という概念をどのようにとらえるべきなのか。集団は単なる個人の集合体なのか?また、公衆衛生を考える上で、どのような方法が最も適切であるかというような認識論的な問いも含まれる。経験的な問題と規範的な問題はどのように関連しているのか?
ワクチン接種、パンデミックの脅威、個人の自由に対する制限の可能性、公衆衛生研究、スクリーニング、肥満政策など、倫理的、政治的、社会的に論議を呼ぶ問題も検討されるべきだろう。本書は、公衆衛生の哲学の分野全体にわたって生じる、最も重要な理論的・実践的問題の数々を探求する多様な論文を収録している。
アンガス・ドーソン編著 キール大学(英国)
目次
- 図・表一覧
- 謝辞
- 1 はじめに:公衆衛生の哲学
- 2 公衆衛生における法の役割
- 3 運、リスク、予防
- 4 社会関係資本を促進する義務
- 5 公衆衛生のパフォーマンスを測定するための評価空間について
- 6 グローバルな関心事とローカルな議論。ローカルな生命倫理はいかにして不公正を永続させるか
- 7 開発途上国における健康と私たちのグローバルな責任
- 8 共有責任協定。争いの原因
- 9 反父学主義および公衆衛生政策。製品安全法制の事例
- 10 新生児スクリーニングと「知るべきかどうか」の選択
- 11 眠ることを選択すること
- 12 制約のカテゴリーと自由の道 肥満の問題に対処するための集団的主体性の提案
- 13 公衆衛生研究における等位性
- 14 感染症に関する本を閉じる。生命倫理と生命倫理と公衆衛生へのいたずらな影響
- 15 Common Good Argument and HIV Prevention(公益の議論とHIV 予防)
- 16 伝染病と権利
- T.M.ウィルキンソン インデックス
- 図と表の一覧
- 図 11.1
- 線形モデル 11.2
- 曲線モデル 11.3
- 選択の視点 11.4
- 自律性モデル 13.1
- プラセボ、4回投与スケジュール、3回投与スケジュールの相対的有効性
- 8.1 第一次ムーラン(西オーストラリア州)責任共有協定
謝辞
本編に掲載された論文はすべて 2006年6月30日から7月2日にかけて英国マンチェスターで開催された応用哲学学会年次大会において、「公衆衛生の哲学」をテーマに発表されたものである。このような会議の成功に貢献された講演者、回答者、座長のみんなに感謝する。
また、会議の開催を依頼してくださった応用哲学学会の執行委員会、特にゴードン・グラハム氏とデビッド・アーチャード氏に感謝する。また、このイベントに関連して様々な場面で助けてくださったRichard Ashcroft、Ruth Chadwick、Marcel Verweij、会議をスムーズに運営してくださったマンチェスター大学Chancellorsの皆さん、そして舞台裏で素晴らしい仕事をしてくださったJon Cameronに感謝したいと思う。
最近では、原稿の出版準備に協力してくれたトレバー・キングとルイーズ・アニス、そして執筆に素晴らしい環境を提供してくれたトロント大学倫理学センターに感謝する。また、校正と索引を担当してくれたベブ・サイクスにも感謝する。最後に、アシュゲートの皆さん、特にサラ・チャーターズ、レイチェル・リンチ、アン・キアビー、ポール・クーラムの忍耐力に感謝する。
第1章 はじめに
アンガス・ドーソン キール大学(英国
1. 公衆衛生の哲学
この章では、本書の他の章を紹介するとともに、「公衆衛生の哲学」という考え方の背景と内容を明らかにしたいと思う。論理的な出発点として、「公衆衛生の哲学とは何か」という問いかけがある。しかし、この広範な問いに答えるためには、「哲学」と「公衆衛生」の性質に関する二つの下位問いを解決しなければならない。そこで、まず、「哲学」とは何を意味するのか、ということから始めよう。
*
「哲学」の特定の定義を擁護することは可能なのだろうか。というのも、哲学の意味や範囲自体が哲学的な問題であり、しばしば激しい論争にさらされることがあるからだ。しかし、そのような定義を提示する方法としては、おそらく、大きく分けて3つの方法がある。
ここでは、「方法論」アプローチ、「内容」アプローチ、「態度」アプローチと呼ぶことにする。
まず、方法論アプローチの提唱者は、哲学は特定の方法論の使用を必要とする点で、他の学問と異なると主張する。関連する方法論の候補は枚挙にいとまがないが、(少なくとも英米の哲学の伝統の中では)分析と議論に焦点を当てることが中心である。
第二の「内容」アプローチは、哲学が特定の伝統的な関心事や主題を有していることを示唆するものである。このアプローチの例としては、私たち自身や私たちの世界について根本的な問いを投げかけ、それに答えようとすることに焦点を当てるもの、あるいは、より平凡な形で、哲学は単に下位学問(倫理学、形而上学、認識論、美学など)の羅列であるとするものなどが挙げられる。
第三のアプローチは、哲学は手法やテーマというよりも、 (例えば、疑問や懐疑的な性質の育成を含む)態度であるとするものである。ここでは、ある特定の考え方を強く主張する必要はない。実際、これら3つの見方は厳密には相互に排他的ではなく、さまざまな方法で組み合わせることができる。
さらに、哲学の語源に立ち返り、知恵を愛する、あるいは知恵を求めるという哲学の考え方に目を向けることも、一つの視点であり、きちんとした統一性を提供する方法 であると思われる。確かに、「知恵」という概念の説明で求められているものを追求すると、かなり忙しくなる1。
おそらく、より実際的な定義を採用するのが最善であり、少なくとも上記のアプローチすべてに頷けるような定義が必要だろう。このような考え方では、哲学は、私たちの概念や視点、社会的実践の背後にある基本的な前提に関わるものであると考えることができる。
*
第二に、私たちが「公衆衛生」について語るとき、何を意味するのか、何らかの作業定義が必要だろう。この用語は、文献上、多くの不一致と議論の対象となっているため、これもまた、見かけより難しいものである2。私たちはまず、公衆衛生とは、公衆衛生政策立案者と実践者が行うすべてのことであると規定するかもしれない。
しかし、これは公衆衛生の必要条件でも十分条件でもないという点で、あまりに不正確である。他の人々も公衆衛生に貢献することができるし、公衆衛生の専門家も時には公衆衛生に反して行動することがあるかもしれない。つまり、私たちは必然的に、より概念的なアプローチを採用し、公衆衛生の主要な特徴を選び出そうとすることになるのである。
第一に、行動の対象として「公衆」の健康に焦点を当てること(集団または人口という意味で)、第二に、介入の形態が多くの人々の行動と参加を必要とすること(しばしば政府またはその代表者による協調行動を通じて)3。
*
では、公衆衛生の哲学とはどのようなものなのか、もう少しはっきりさせることはできないのだろうか。そのようなものはあるのだろうか。確かに、このような名称の学問が盛んに行われているわけではない。この名前を冠した学科や講座、研究プログラムもないし、この「トピック」に明確に焦点を当てた文献も驚くほど少ないのである。
実際、公衆衛生の哲学をタイトルに含む論文は、6つしか見つからなかった。ジュリアス・プリンス(1958)による最も古い論文は、公衆衛生のための「公共哲学」と呼ばれる考え方に関心を寄せている。彼の真の関心は、効率性を理由に公務員と関わるという実際的な要件にあるが、民主主義国家において公衆衛生政策を策定し、実施する際に、市民と協議し、関わることは政治的な意味でも重要であると捉えている。
多田羅浩三(2002)の最近の論文は、本来の意味での哲学に関するものではない。5彼はむしろ、一般的な意味での哲学に関心を抱いており、ここでは哲学を、あるトピックに対するアプローチの方法として捉えている。このような考え方は、より専門的な公衆衛生の哲学 (例:公衆衛生にどのようにアプローチすべきか)にも取り入れられるかもしれないが、そうである必要はない。
公衆衛生の哲学に関連する真の核心的問題に取り組んでいるのは、van der MaesenとNijhuis6 7、そしてDouglas Weed8による3つの論文だ。これらの著者はいずれも、公衆衛生実践、政策、研究方法の背後にある仮定を批判し、考え抜く必要性に同意している。
彼らは、公衆衛生における重要な考え方の役割(因果関係や証拠、集団と個人の利益と害の関係、「公共」や「健康」といった中心概念の意味など)を考察し、議論する必要性に共同で焦点を当てている。Weedは、公衆衛生とは何か、何をするのかを考える際に生じる、存在論的、認識論的、倫理的な側面の全てに注意を払うような、公衆衛生の一般哲学を特に明確に要求しているのである。
最後に、『生命倫理百科事典』におけるBeauchampの章(1995)は、公衆衛生の哲学を求めるというよりも、そのような説明の始まりを発展させようとするものであり、この文献への興味深い追加となっている9。
*
しかし、このように文献上では比較的軽視されているにもかかわらず、2 つの意味で「公衆衛生の哲学」と首尾よく呼べるものが確かに存在すると主張したい。第一に、たとえ現在の文献がほとんどないとしても、物理学、生物学、医学の哲学が存在するのと同様に、言説の分野やトピックとして公衆衛生の哲学は確かに存在する。
もちろん、これらの例に比べれば、それほど発展しているわけではないが、将来的にそうなってはいけないという先験的な理由はない。これは、van der MaesenとNijhuis、WeedとBeauchampが論じているテーマである。この学問の具体的な位置づけと内容、そして医学哲学のような他の言説の領域との関係を明確にすることは、この学問の重要な仕事の一部であろう。
第二に、上記の著者が示唆するように、公衆衛生活動(政策と実践の両面で)には、より哲学的な批判と議論を必要とする問題が山積している。哲学の様々な分野(倫理学、認識論、形而上学、社会・政治哲学、さらには美学)の多くは、統計的推論の意味、性質、役割、公衆衛生に対する社会科学の手法の貢献、公衆衛生における原因と結果の意味、病状の発生における生理学的要因と環境要因の相対的役割、危害、リスク、予防といった概念の意味といったテーマについての議論に明らかに関連している。
このような2つの異なる路線を同時に追求できない理由はない。しかし、特定の問題や概念に焦点を当てる後者のアプローチが、近い将来、最も進展する可能性が高いだろう。公衆衛生の一般的かつ統一的な哲学という壮大なビジョンは、まだ先の話かもしれない。
2. 公衆衛生の哲学の豊かさと多様性
本巻の論文は、議論に採用できるトピック、方法、アプローチの幅の広さ、そして公衆衛生の哲学の観点から探求できるテーマの豊かさと多様性を示している。
*
ロビン・マーティンは、公衆衛生における法の機能について論じている。彼女はこの章において、公衆衛生に関連する法の2つの異なる役割の概説と議論に集中している。第一は、公衆衛生政策の実施を支援するツールとして法律が果たすことのできる貢献であり、第二は、権利の法的行使を通じた公衆衛生倫理との関連における法律の役割である。
第一の役割に関しては、立法、刑法、公衆の態度を強制するメカニズムとしての法という3つの方法に焦点を絞って論じている。これらの方法は、それぞれ異なる利点と問題点を示している。本質的に法律は、個人をモニタリングし、調査し、様々な自由を縮小し、除去することができるという点で、強力な道具である。
しかし、制定法から生じる法律は、それが作成された当時の科学的信念や価値観を反映する傾向があるという点で、かなり粗雑な手段である。つまり、2つの点で不適切である可能性がある(今では無関係な問題に関係していること、新しい、以前は想像もつかなかった脅威に対応する手段を持たないこと)。
古い法律は新しい状況に合わせて曲げられるが、新しい法律は危険なほど幅を利かせることができる。私たちは、公衆衛生の目的が何であるかを明確にする必要があり、そうすれば、その目的を達成するために法律を形成しようとすることができる。
しかし、法律は有用である一方で、常に答えとなるわけではなく、それ自体が問題を引き起こすこともあることを認識する必要がある。この点は、マーティンが論じた2番目の問題、すなわち権利の行使に関連する法の役割によく表れている。法は、不法行為や人権に関する法律の適用を通じて、個人を保護するための重要なツールとして機能することができる。しかし、公衆衛生との関連では、そのような権限の行使は、個人を保護する一方で、公衆衛生に有害な影響を与える可能性がある。
*
キャサリン・キングは、「運、リスク、予防」の章において、予防という考え方を真剣に受け止めることが、配分的正義の理論にとって何を意味するのかを探求している。彼女はまず、既存の不利益に対する補償の場合と、将来の不利益を予防する場合とを区別することから始める(ただし、現実には明確な区別ができないことが多いことはすぐに明らかになる)。
キングは、ドゥオーキンの運の平等主義に関する説明に議論の焦点を合わせることにした。なぜなら、ある害の防止(あるいは可能性の低減)は、機会を増大させると考えられるからだ。彼女は、ドウォーキンの理論の資源では、予防という概念を十分に考慮することができないと説得的に主張している。なぜなら、オプションとブルートラッキーの説明は、この概念を捕らえる手段として不十分だからだ。彼女は、2つの理由から、運ではなくリスクの概念を採用することを提案している。
第一に、予防の未来志向性をよりよく捉えることができること、第二に、リスクという考え方は、個人に関係するものとしてだけでなく、個人が属する集団や母集団の特徴として捉えることができることである。このアプローチは、運勢平等主義に関する文献に加えられた興味深いものであり、公衆衛生における正義の関心事に直接関わるものである。
*
パトリシア・イリングワースのソーシャル・キャピタルに関する考察は、社会学や公共政策の文献に由来する概念を取り上げ、それが規範的概念としても理解でき、したがって、公衆衛生における倫理的・政治的問題に取り組む人々の関心を引くものであることを論じており、革新的なものであると言える。
まず、ロバート・パトナムの研究を中心に、この概念の分析が行われた。ソーシャル・キャピタルは、社会活動の可能性、特に信頼や互恵性との関係から不可欠であるとされ、それゆえ、効果的な公衆衛生活動に必要な要件であるとする意見が多い。
イリングワースは、この概念が曖昧であるにもかかわらず、倫理的な概念であると見なすべきであると主張する。なぜなら、それ自身のために追求すべきものであると同時に、それが可能にするもののために、おそらくより重要であるからだ。それは、その存在のために他者との社会的関係を必要とする概念であり、一人では作り出せないし、他者に義務を課すものである。
このことは、Illingworthによれば、ソーシャルキャピタルを育成する義務が個人と組織の両方にあることを示唆している(ただし、これは一応の義務に過ぎないため、他の重要な道徳的配慮と引き換えでなければならない)。ソーシャルキャピタルは、グローバルな正義の議論だけでなく、身近なコミュニティにおける個人の関わり方について、より「ローカル」な関心事に貢献する可能性を持っていると主張されている。ソーシャル・キャピタルの議論とその規範的コミットメントへの示唆が、今後どのように発展していくのか、興味深いところであることは確かである。
*
オニェブチ・アラ氏の章では、法的、社会的、政治的、倫理的な議論から、公衆衛生とは何か、公衆衛生活動のパフォーマンスをどのように評価すべきかという問題へと議論をシフトさせている。彼は、公衆の健康(彼は目的の視点と呼ぶ、集合的な人口の意味での)と健康の公衆(彼は手段の視点と呼ぶ)の2つの側面を含むものとして公衆衛生を考えるべきであると主張する。
公衆衛生活動は、これら2つの側面を測定(およびその観点から評価)する必要がある。公衆衛生のパフォーマンスを測定する現在の試みは、この課題には不十分であるように思われる。Arahは、公衆衛生の成功は、集団内の個人の実際の健康達成度と同様に、機会の提供と配分の観点から測定される必要があると主張している。彼は、このアプローチによって、公衆衛生倫理の枠組みの中で個人と集団に割り当てられる相対的な重みに関連する規範的な議論における緊張をいくらか軽減することができると示唆している。
*
Søren Holmは、グローバル化された生命倫理が正当な目標である一方で、この目標にどのようにアプローチするかについて注意を払う必要があると論じている。危険なのは、自分たちの「ローカル」な倫理的アプローチを全世界に適用する(これが正しいアプローチであると仮定し、そのような適用における論争的特徴を無視する)か、あるいは、ある特定のアプローチが合意であるとされるまさにその事実における権力の役割を認識せずに、「合意」とされる見解を適用するだけであるということである。
ホルム氏は、人権や特定の制度的枠組みや手続きを採用することで、グローバル化した生命倫理を簡単に手に入れることはできないと主張する。彼は、西洋の生命倫理における多くの議論の中心であった自律性の尊重のような原則でさえ、不適切に「グローバル化」される可能性があると論じている。
*
ジリアン・ブロックは、発展途上国から先進国への医療従事者の移動がもたらす影響に焦点を当てている。彼女は、この問題の規模を概説し(多くの国では、現在、労働者を養成するよりも早く労働者を失っている)、この例を用いて、影響を受ける人々に対して先進国が負う義務について、より一般的な問いを投げかけている。
このようなスタッフの移動は、健康に影響を与えるのだろうか?間違いなくそうだ。発展途上国は先進国にスタッフを奪われるだけでなく、先進国の医療を実質的に補助しているのだ。採用政策に関する様々な規範を検討した結果、自発性に焦点を当て、特定の国だけに限定して適用しているため、発展途上国の人々が被る影響の大きさに注意が払われていないことが分かった。
ブロックの主張の結果は、過去の過ちに対する補償を求める積極的な主張であり、おそらくは医療訓練と発展途上国の医療システムの両方への投資に焦点を当てたものであろう。ブロックは、補償コストを負担すべきなのは雇用する側の機関であると主張している。
*
Paula Boddingtonは、Shared Responsibility Agreements (SRAs)を批判的に検証している。彼女は、オーストラリアにおけるSRAの利用、特に原住民の福祉政策との関連に焦点をあてている。
彼女は、これらの協定をめぐって行われた議論を体系的かつ注意深く検証している。しかし、彼女の主張は、こうした他の反論の質がどうであれ、SRAは単純すぎるというもので、取り上げた状況を生み出した因果関係のプロセスの複雑さを捉えることができない。
過去の「失敗」に対する責任は、個人や特定のコミュニティの行動に焦点を当てる傾向があり、歴史的・社会的要因を無視し、不平等や人種差別などの不正の寄与を過小評価したり割り引いたりする。さらに、ボディントンは、SRAに関連して「責任」という言葉が頻繁に使われるが、原因的責任(貢献)と問題(存在するもの)に対処する道徳的責任との間の重要な差異を無視しがちであると論じている。
まさに、誰が責任を負い、行動する義務があるのかが曖昧なまま放置されがちである。Boddingtonは、特定の協定、第一次ムーラン協定に焦点を当て、このようなケースにおける因果関係の複雑さに関連する多くの問題を浮き彫りにしている。
*
カレ・グリルは、消費者製品の安全性の問題に焦点を当て、公衆衛生政策におけるパターナリズムについて論じている。彼は、パターナリズムについて語るとき、ある行為の背後にある正しい理由を特定することに注意を払う必要があると論じている。
グリルは、製品安全規制に関して、製品安全法を歓迎する人がいても、そうでない人がいると考えるには十分な理由があると主張する。このような自由な選択への干渉が歓迎されず、人の善意に訴えて正当化される場合、パターナリズムが存在する可能性がある。
行動の理由に注目することで、その行動が本当にパターナリズム的かどうかを検討することができる。パターナリズムを非難するだけでは、公衆衛生政策に反対するのに十分ではないはずだ。パターナリズムの主張と行為の正当性に関するより一般的な懸念の両方を評価するためには、政策の背後にある理由をより深く探求することが必要である。
*
Niels Nijsinghは、新生児スクリーニング・プログラムの新たな発展から生じる重要な倫理的問題について論じている。この問題は、新しい技術によって、複数の障害を迅速かつ容易にスクリーニングできること、そして、ある検査の結果が別の障害に関する情報を開示するかもしれないため、特定の障害をスクリーニングすることを決めるのが必ずしも容易ではないという事実に関するものである。
彼は、まさにそのようなケースを考え、検査によって供給される情報に対する自律的な権利を持つことが何を意味するかを考察している。もちろん、親は自分の子供がスクリーニング検査を受けることに同意することはできるが、このようなケースに関する決定を情報の選択に関するものと解釈することは意味がないと彼は主張する。
それは、このような場合における情報提供のパラドックスに起因する。情報はポジティブな場合にのみ興味を引くものだが、誰かが知りたがっているかどうかを尋ねることによって、結果がどうなるかをすでに示唆していることになるのである。
*
ベンジャミンとローレン・ヘイルによる、睡眠に関する問題についての学際的な章は、無視されてきた問題についての刺激的かつ独創的な議論である。彼らは、睡眠についてどのように考えることができるかを概念化するための2つの異なるモデル(線形モデルと曲線モデル)を対比し、後者が経験的証拠によりよく適合していることを示唆している。
また、睡眠を考えるための枠組みとして、2つの異なるモデル(「選択観」と「自律観」)を提示している。自律性が自己決定やライフプロジェクトの設定・遂行と結びついていることから、後者の方が好ましいと主張している。
最適な睡眠時間は、健康のためだけでなく、(この意味での)自律性を高めるためにも必要な条件なのだ。このことは、単に睡眠だけでなく、もっと広い範囲に政策や実践の焦点を当てるべきという意味で、公衆衛生活動にも示唆を与えている。
*
Catherine Womackの章では、肥満政策に関連する一連の中核的な問題を検討し、それらがどのように概念化され、対処されるべきかを論じ始めている。前章と同様、この章でも、経験的な文献の議論から生じる一連の哲学的な問題を探求している。
Womackは、多くの研究者が食事と運動に関する個人の行動変容をもたらす方法を模索している中で、肥満に関する規範的な議論を根本的に見直す必要があると論じている。Womackは、このような介入が効果的でないことを証明する十分な証拠がすでにあるため、これが不十分であることが証明されるだろうと示唆している。
彼女は、個人の行動変容に寄与する手段として、革新的な集団的介入について考える必要があると主張している。この章は、公共政策のパラダイム・シフトを可能にするために、経験的証拠との関連で必要な、より深い考察の好例となるものである。
*
Marcel Verweijは、ワクチン接種の研究と政策に関連する一連の倫理的問題について論じている。ここでは、推奨され、以前に研究されたスケジュールから接種回数を減らすことに関心がある(コストまたはワクチン不足の理由から)。
彼は、オランダにおける幼児への肺炎球菌ワクチンの定期接種に関する議論を例にとって、その考察を説明している。コストの問題から、通常4回接種のところを3回接種にする可能性があった。しかし、このような削減されたスケジュールの有効性については問題があった。3回投与対4回投与、または3回投与対プラセボの2つのモデルのいずれかを用いて、無作為化臨床試験で答えを出すことができる。
最初の選択肢は、参加者数と統計的に有意な答えを出すのに必要な時間のため、実行不可能と判断された。しかし、2番目の選択肢である3剤対プラセボは、倫理的な理由から問題があると考えられた。Verweijは、このような場合、等質性は最初に考えられていたほどには関係ないかもしれないと考える理由を探っている。
例えば、このようなワクチン試験は、治療を必要とする患者ではなく、健康な被験者を対象とした予防的介入に焦点を当てたものであるため、医師が患者に対して負っている受益の特別な義務がどのように適用されるかは不明である。
また、社会における公衆衛生の提供の背景が、このような試験の正当化に関係する可能性があるとVerweijは主張するが、正義に関する他の考慮事項も関係する可能性がある。この章は、公衆衛生における倫理的、政策的、方法論的な問題が、いかにすべて織り込まれているかを示す興味深い例である。
*
この章では、フランシスらが生命倫理の発展の歴史的分析を行い、これを用いて、特に感染症に関する倫理的問題だけでなく、公衆衛生という広い分野全般に関する議論も相対的に軽視されてきたことを論じている。この焦点の多くは、初期の生命倫理学が政治的に推進され、市民権の伝統に基づき、インフォームド・コンセントやプライバシーといった問題に焦点を当てていたことに起因している。
彼らは、HIVの流行の出現によってもたらされた再評価の機会を逃し、HIVに関する多くの議論が、それが感染症であるという事実を無視していたことを示唆している。この「例外主義」は、(主に性的)感染様式と、社会から疎外された集団の重要な市民的自由を守る必要性に、(少なくとも発展途上国では)当初から強く着目していたことの両方によって助長された。
HIVの出現以来、Francisらは、公衆衛生活動や伝統に基づく重要な対照的傾向を指摘している。彼らは、このテーマに関する文献での議論は、集団衛生の重要性という考え方に焦点が当てられ、世界レベルでの健康や開発問題に対する多くの人々の関心が高まり、公衆衛生実践者自身が自らの価値観や実践を振り返り、批判する意欲と熱意を持つようになったことによって活性化したと論じている。
彼らは、今こそこれらの伝統をより密接に結びつけるべき時であると主張し、感染症患者を被害者と媒介者の両方として、つまり、病気から逃れることのできない被害者であると同時に、他者を感染させる潜在的な病原体として見るという考えを提示している。
*
Charlotte Paulの章では、公衆衛生の伝統が、予防的な公衆衛生活動のいくつかの側面を批判的に扱うための枠組みを提供するための刺激的な議論が展開されている。彼女は、HIVの予防と、HIV感染を減らす手段としてパートナーの減少に焦点を当てた予防活動の実際の役割(および将来の可能性)について論じている。
性的パートナーの数を減らすことは、確かに個人と集団にとってより大きな保護となる。しかし、この点で人々の行動を変えようとすることに焦点を当てた政策は、激しい批判にさらされてきた。特に性的な事柄に関して、他人がどのように行動すべきかを語ることには、HIV削減に取り組む人々でさえ、大きな抵抗がある。
彼女は、たった一人のパートナーの性行為を増やすだけでも、集団内の全員がHIVに感染するリスクに劇的な影響を与えることが実証できると主張している。ポールは、ウガンダとボツワナにおけるパートナー減少キャンペーンが成功した経験的証拠について述べ、もし私たちが本気で感染のリスクを減らそうとするならば、規範に焦点を当て、それを変えるためのさまざまな手段を模索しなければならないと提言している。
ポールは、地域社会をHIV感染から守るという共通の利益のような、彼女が「共通善の議論」と呼ぶものに焦点を当てている。彼女は、今や公衆衛生の古典となったGeoffrey Roseの研究を用いて、個人の行動が集団の健康に影響を与えうること(そしてその逆もまた然り)を説明している。このような議論は、公衆衛生倫理の議論を将来発展させるための豊富な情報源となるものである。
*
最後に、マーティン・ウィルキンソンの章では、(少なくともいくつかの)権利(自由権、身体的完全性、プライバシーなど)と、公衆を潜在的危害から守ることに焦点を当てた公衆衛生活動との間の明らかな対立を探求している。
彼は、強制的な治療、拘禁、予防活動の根拠となりうるものを議論し、そのような強制の正当化として考えられる3つの異なる理由を探っている。第一に、関連する権利は絶対的なものではなく、(少なくとも状況によっては)覆すことが可能であるということ。
第二に、他人の権利 (例えば、感染しないこと)が重要であり、自衛権のようなものが発動される可能性があること。第三に、感染症の伝播の性質を考えると、個人の権利に焦点を当てると、集団行動の問題が生じるということである。ウィルキンソンは、介入のための恣意的でない閾値を正当化し、害の確率を計算することが困難であるため、最初の正当化には問題があると論じている。
第二の正当化については、自衛という考え方が、他の種類の優先的権利に焦点を当てるよりも強固な反論を提供するため、より有望であると示唆している。しかし、おそらく最も強力なのは第三の正当化であり、関連する集団的問題についての首尾一貫した概念を理解することができれば、特定の個人の行動を尊重することによって生じうる(集団にとって)問題のある結果を食い止める手段としてこれを利用できるかもしれないという点である。
3. 公衆衛生の哲学?
これらの論文の多くは、公衆衛生実践における倫理的問題に集中しており、これはおそらく、発展途上の公衆衛生哲学の最も有力な分野である。公衆衛生倫理は、それ自体、応用倫理学として急速に発展している分野である。しかし、これらの論文のほぼすべてが、議論の過程で経験的主張あるいは経験的証拠に訴えている。
そのような証拠が考慮される場合、公衆衛生の哲学の他の側面を避けることはできない。個人ではなく集団やグループに関連する問題をどのように論じるべきかを考え抜くために必要な認識論的・形而上学的問題は、確かにもっと多くの作業を必要とする。
先に述べたように、実質的な学問分野として公衆衛生の哲学というものは存在しないので、この巻がこのテーマに関する最後の言葉となるには程遠いのは当然である。しかし、この編集集は、ここに探求されるべき重要な問題があるという事実を示しており、この分野が今後どのように発展していくかを見守るのは楽しみなことである。おそらく、いつの日か、本当に公衆衛生の哲学が存在するようになるのだろう。
