Contents
The Oxford Handbook of Causation
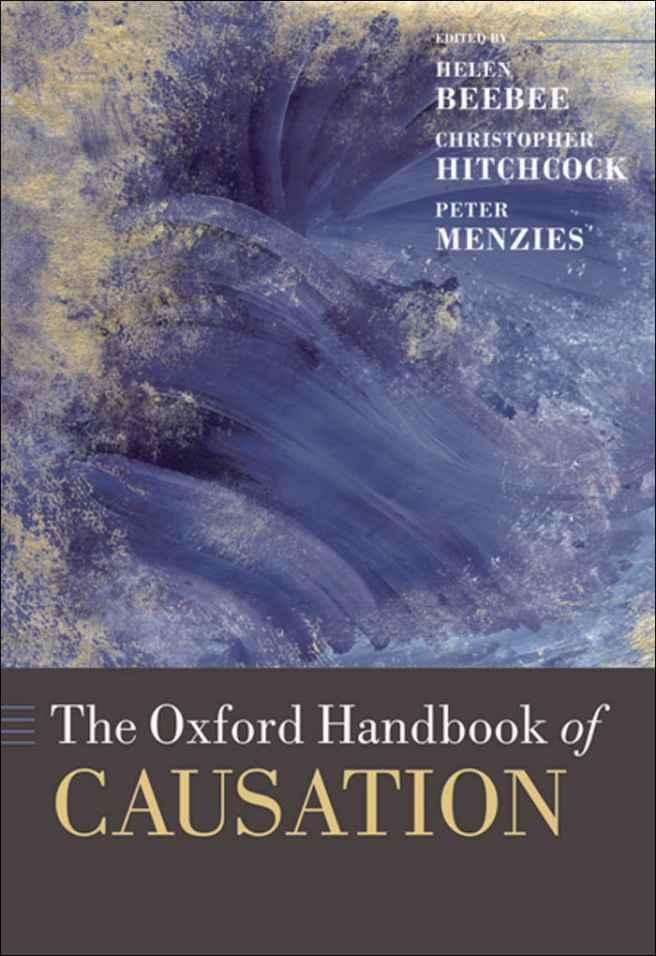
データベース権 オックスフォード大学出版局 (メーカー)
2009年初版
目次
- 寄稿者リスト
- はじめに ハイエン・ビービー、クリストファー・ヒッチコック、ピーター・メンジース
- 第1部 因果関係の歴史
- 1. 古代ギリシャ人 SARAH BROADIE
- 2. 中世の人々 JOHN MARENBON
- 3. 近世 ケネス・クラッターボー
- 4. ヒューム ドン・ガレット
- 5. カント エリック・ウォーキンズ
- 6. 論理的経験主義者 マイケル・ストルツナー
- 第2部 因果関係への標準的アプローチ
- 7. 規則性理論 スタティス・プシロス
- 8. 反実仮想の理論 L. A.ポール
- 9. 確率論 JON WILLIAMSON
- 10. 因果過程論 Causal Process Theories フィル・ドーエ
- 11. エージェンシーと介入主義理論 ジェームス・F・ウッドワード
- 第3部 因果関係に対する代替的アプローチ
- 12. 因果の力と能力 スティーブン・マムフォード
- 13. 反還元主義 JOHN W. CARROLL
- 14. 因果関係モデリング クリストファー・ヒッチコック
- 15. メカニズ ム STUART GLENNAN
- 16. 因果的多元主義 ピーター・ゴドフリ-・スミス
- 第4部 因果関係の形而上学
- 17. 平凡な例と反例 ピーター・メンジース
- 18. 原因、法則、存在 MICHAEL TOOLEY
- 19. 因果関係 DOUGLAS EHRING
- 20. 因果関係の時間的非対称性 ハウ・プライス、ブラッド・ウェスレイク
- 第5部 因果関係の認識論
- 21. 因果関係の認識と推論に関する心理学的考察 デービッド・ダンクス
- 22. 因果関係と観察 ヘレン・ビービー
- 23. 因果関係と統計的推論CLARK GLYMOUR
- 第6部 哲学的理論における因果関係
- 24. 精神的因果関係 セイ・マスレン、テリー・ホーガン、ヘレン・ダリー
- 25. 因果関係、行為、自由意志 ALFRED R. MELE
- 26. 因果関係と倫理 カロリナ・サルトリオ
- 27. 知識と知覚の因果関係理論 ラム・ネータ
- 28. 因果関係と意味内容 FRANK JACKSON
- 29. 因果関係と説明 ピーター・リプトン
- 30. 因果関係と還元 ポール・ハンフリーズ
- 第7部 他の学問領域における因果関係
- 31. 古典力学における因果関係 マーク・ランジ
- 32. 統計力学における因果関係 LAWRENCE SKLAR
- 33. 量子力学における因果関係 リヒャルト・ヒーリー
- 34. 時空間理論における因果関係 カール・ヘーファー
- 35. 生物学における因果関係 サミール・オカシャ
- 36. 社会科学における因果関係 ハロルド・キンケイド
- 37. 法学における因果関係 ジェーン・スタプレトン
- インデックス
はじめに
ヘレン・ビービー クリストファー・ヒッチコック ピーター・メンジース
哲学者は、哲学が存在する限り、因果関係の本質に関心を寄せてきた。あるものが別のものを引き起こしたと言うとき、我々は世界について何を言うのか、また、我々が行う因果関係の主張に答えるものが世界に存在するのか、に関心を寄せてきた。このように注目されているにもかかわらず、因果関係に関する最も中心的な問題である「因果関係とは何か」については、まだほとんど合意が得られていない。例えば、規則性や法則のインスタンス化の問題なのか、反実仮想的な依存性の問題なのか、操作性の問題なのか、エネルギーの伝達の問題なのか。近年行われている因果関係の議論を知っている人なら、膨大な数の理論や反例を知っているので、因果関係の概念を一義的に分析することはできないのではないかと思われる。
もう一つの理由は、因果関係の形而上学的な位置づけについて、著者によって根本的に見解が異なることだ。我々の多くは、例えば素粒子はそうかもしれないが、色は宇宙の基本的な構造には含まれないということに同意している。しかし、因果関係に関しては、そのようなコンセンサスはない。著者によっては、因果関係は世界の比較的非基本的な特徴であり、規則性のような他のより基本的な特徴の観点から理解される特徴であると考える者もいる。ある意味では、因果関係は現実の特徴ではなく、「原因」という概念は、我々が周囲の世界の出来事に投影したり、押し付けるものだと考える人もいる。また、因果関係は基本的なものであり、原理的に因果関係の用語を用いずに記述できる現実の基本的な層という概念は支離滅裂であるか、少なくとも明らかに間違っていると考える人もいる。
第三の理由は、哲学的因果論は、他の多くの哲学的理論がそうでないのと同様に、科学の発展に対する人質となっているという事実である。例えば、ニュートンの天体力学は遠方での瞬間的な作用を仮定しているように見え、量子力学は我々の世界の基本的なプロセスは非決定的であると教えてくれるように見える。どちらの発展も、この世界において原因がどのように作用しうるかについての既存の仮定を覆すものであった。さらに、因果関係についての哲学的理論の多くは、その定式化において、数学的あるいは科学的理論の資源を利用している。確率論的理論は確率論の資源を利用し、因果過程論は特殊相対性理論から概念を借用する、などである。
第四の理由は、因果の概念が様々な文脈で使われ、互いに明らかに互換性のない形で使われていることだ。例えば、物理学者の因果関係の概念は、弁護士の概念とは全く異なるように思われるかもしれないし、また、我々が日常生活で直面する状況に対処する際に用いる通常の概念とは、全く異なるかもしれない。
第五の理由は、因果の概念が哲学の他の領域にとって中心的なものであることだ。倫理学、認識論、そして自由意志、人格、時間、普遍性、自然法則など、形而上学のほぼすべてのトピックに因果関係を訴える哲学的理論が存在するのである。因果関係の理論の選択は、このような他の分野に根本的な影響を及ぼすことがある。原因の定義に時間的優先権を組み込んだ因果論は、時間の方向に関する因果分析の可能性を排除する。省略による因果を排除する理論は、倫理学における帰結主義と相容れない。「ヒューム的」因果分析は、すべての基本的普遍は処分的であるという見解と相容れない、等々である。
本書の各章では、これらの問題やその他の問題を詳細に検討するが、大部分は入門的なレベルから始めているので、学部レベルの学生にも十分あるいはほとんど理解できるはずである。本書の各章は、一般に、既存の文献を調査し、論争の主要なポイントを示すことを目的としているが、同時に、著者による独特の語り口も維持している。積極的で、しばしば論争の的になる立場を描き、擁護しているので、初心者だけでなく、進行中の論争にすでに精通している哲学者にとっても興味深いものとなるであろう。
本書は7つのパートに分かれている。各章の短い抄録とともに、各パートのごく簡単な概要を紹介する。
第I部:因果関係の歴史
第I部では、今日の哲学者が関心を寄せる因果関係をめぐる問題や論争の多くについて、歴史的背景を説明する。例えば、説明と推論の両方における因果の役割は、古代ギリシャ時代から認識されていた。また、我々の先達が関心を寄せていた問題の中には、当然のことながら、かつてのような隆盛を失ったものもあるが(例えば、宇宙を維持するための神の因果的役割)、現代の多くの論争やアプローチは、はるかに古い論争やアプローチにそのルーツを見出し、少なくとも類似性を持っているのである。例えば、因果関係の説明は我々の最も優れた科学に基づくべきであるという考えは、現代の因果過程論の原動力となっているが、ホッブズやボイル、そして20世紀前半にはフランク、シュリック、ライヘンバッハの原動力にもなっている。精神的な因果関係には何か問題があるという考えは、デカルトにはよく知られていたし、因果関係が物質の本質に由来するという考えは、ライプニッツにも、現代の因果力に関する説明にも見出すことができる。
第1章:古代ギリシア人
サラ・ブローディーは、古代ギリシャ哲学におけるギリシャ語の名詞アイティアの役割について論じている。古代ギリシアの哲学者たちの理論的探究において、XにYのアイティアという地位を与えることは、YがXに対してある関係Rに立つことを意味し、この情報によってYがXに照らして理解可能であると主張する資格が与えられる。アリストテレスにとって関係Rとは、構成される関係、そのために存在する関係、あるいはそれによって作られる(あるいはもたらされる)関係であろう。プラトンでは、Xが形であり、Yが形Xに参加しているとき、YはXと必要な関係を持つ。ブローディは、歴史的に支配的な二つの説明モデル、すなわち第一原理からの実証と目的論的代理の役割を検討する。最初のモデルでは、ある事実を説明することは、必要かつ自明な原理から三段論法的にそれを演繹することだ。第二のモデルにおいて、ある対象を説明することは、それがある目的のために、ある代理人によって特定の構造に従って配置されたある物質からどのように構成されているかについての情報を提供することだ。
第2章:メディエーターたち
ジョン・マレンボンは、アラビア、ユダヤ、ラテンの哲学において、1000年以上にわたって議論された因果関係の問題を論じた。アクィナスが『第二の道』で用いた、偶然的原因の連鎖と本質的原因の連鎖という不可解な区別を検討する。この区別は、ペルシアの哲学者アヴィセンナの形而上学的因果関係の教義に遡る。この教義は、唯一の必要存在者である神から因果の連鎖を経て存在が生み出されることに関わるものである。また、11世紀のイスラム哲学者アル・ガザーリーや14世紀のパリの哲学者ニコラス・オブ・オートレコートの研究など、イスラム哲学やキリスト教哲学における機会論的思考の伝統も検証している。この伝統は、自然界における因果的効力や因果的必然性の存在を否定するという点で、現代の因果関係の取り扱いと興味深いつながりをもっている。最後に、13世紀にアリストテレスの著作が再発見される以前の中世思想の工夫を示すものとして、エリウゲナとアベラールの中世初期の因果論が簡潔に述べられている。
第3章 近代初期
ケネス・クラッターボーは、近世における哲学者の因果関係の研究を「家の掃除」と呼んでいる。つまり、物質的原因、最終原因、形式的原因、効率的原因、物質的・非物質的原因、(宇宙の創造者・維持者としての)神など、哲学者に遺された豊富な原因を整理することであった。この時期の中心的な論争は、物体の振る舞いを大きさ、形、動きといった経験的に得られる物質の特徴だけで説明しようとする唯物論的、機械論的、自然主義的な因果の概念(ホッブズ、ガッセンディ、ボイル、ニュートン)と、神(マルブランシュ)、物質の内部性(ライプニッツ)などにより訴える「形而上的」因果の概念の間で行われていると見ることができるだろう。
第4章:ヒューム
ドン・ギャレットが指摘するように、ヒュームの因果論がどのようなものであるかについては、論者の間でかなりの意見の相違がある。つまり、「cがeを引き起こした」というのは、「cに似た事象がeに似た事象と常に結合している」ことを意味するのである。しかし、ヒュームは、因果を単なる定数結合を超えた事象を結びつける現実の関係であるとする因果的実在論者であり、また、必要接続(ヒュームによれば、cのような事象の発生を目撃すればeのような事象が発生すると推論する習慣から生じる)という考え方が因果の主張内容に関与しつつ、心とは無関係な関係には言及しない射影論者として特徴づけられてきた。ギャレットは、ヒュームの抽象的観念一般(因果関係はその一つ)に関する説明から導かれる、新しい代替的見解を提示す。この見解では、必要な接続の印象は、我々が因果的なシーケンスを識別するための一種の「因果的感覚」であるが、必要な接続のアイデア自体は「原因」の意味の一部ではないのである。
第5章 カント
カントは『純粋理性批判』の中で、因果関係の原理は世界の首尾一貫した経験のために必要であり、それゆえに合成的アプリオリ真理の地位を持つと主張した。カントの因果関係の取り扱いは、形而上学全般の取り扱いの手本となった。エリック・ワトキンスの章では、カントがライプニッツやヴォルフといった先行人物に応答していた臨界前の時期から、『純粋理性批判』における因果性の扱い、そして後期の著作における自然科学への因果性の適用に至るまで、因果性に関するカントの思考の展開を追跡している。
第6章 論理的経験主義者たち
ミヒャエル・シュテルツナーは、ウィーン・ベルリン・サークルの3人のメンバーの因果関係の理論について詳しく説明している。フランク、シュリック、ライヘンバッハである。シュルツナーは、マッハによるヒュームの再解釈、新カント主義、デュエムとポアンカレによる慣習主義という3つの哲学的影響を指摘しつつ、彼らが深く関わっていた相対性理論と量子論という物理学の発展や確率論に着目している。論理的経験主義者の因果関係に対する考え方は、彼らがしばしば連想される粗雑な検証主義とはほとんど共通点がないものである。それどころか、伝統的な形而上学を科学的世界観に置き換えるという彼らのコミットメントは、20世紀初頭の科学的発展に対応することを目的とした、洗練された因果関係の説明を発展させることを必要とした。
第2部:因果関係への標準的アプローチ
第II部の各章では、現代の議論の焦点となっている代表的な因果関係の理論を概観する。最初の2章で紹介する規則性理論と反実仮想性理論は、ヒュームの2つの因果関係の定義に起源を持つと言えるが、他の章で紹介する確率論、因果過程、代理・介入論は、より新しい起源を持つ理論である。これらの理論は、因果関係が規則性を持つこと、連続的な過程やmanipulability(操作性)を含むこと、反実仮想的な依存関係や確率的関連性を持つことなど、因果関係の何らかの特徴を出発点としている。そして、これらの特徴的な特徴の観点から因果関係を還元的に分析することを、それぞれの理論が様々な方法で試みている。本編の各章では、これらの理論の成功と失敗を詳細に検討する。どの理論が最も優れた因果理論であるかは、現在も活発に議論されている問題である。
第7章 規則性理論
スタティス・プシロスは「因果の規則性ビュー」(RVC)を論じている。このビューによれば、ある事象が別の事象を引き起こすということは、おおよそ、二つの事象がある規則性をインスタンス化するということになる(ただ「おおよそ」とあるのは、この粗野なビューが因果の説明として成立する可能性を持つためには、様々な点でより洗練させる必要があるためである)。19世紀初頭のスコットランドの哲学者トーマス・ブラウンから、ジョン・スチュアート・ミルやジョン・ヴェンを経て、J・L・マッキーに至るまで、RVCの歴史を概説している。そして、RVCと規則性に基づく法則や説明の説明との関係を明らかにし、RVCが依存する類似性の概念(規則性の存在は、その規則性のインスタンスが該当する何らかの型の特定を前提とするので)や因果関係が非対称関係であるという事実に関する異議に対してRVCを擁護している。プシロス自身は因果的多元主義者であるが、RVCを「次善の策」と考えている。
第8章 反実仮想の理論
L. A. Paulは、David Lewisの古典的な理論から、因果関係の反実仮想説を考察している。これによれば、因果関係は「もし出来事cが起こらなかったならば、出来事eは起こらなかったであろう」という形の反実仮想の観点から理解されることになる。このような反実仮想が真であるとき、ルイスは事象eが事象cに因果的に依存していると言い、cとeが全く異なる事象でありながら、そのような因果的依存の連鎖によって結び付けられているとき、cはeの原因であると言う。概念分析と存在論分析に関するいくつかの一般的方法論問題を概観した後、ポールはこの理論の利点を、共通原因、早期先取、不在を含む因果関係を含む事例にいかにスムーズに適用するかを示して概説している。また、ある種の先取りや過剰決定から生じる特に難解な問題に対する可能な解決策を検討する。
第9章 確率論
確率論的因果論は、因果関係は非決定論と両立しうると考える作家にとって魅力的なものである。初期の確率論的理論の中心的な考え方は、原因がその結果の確率を高めるというものである。ジョン・ウィリアムソンの章では、ライヘンバッハ、グッド、サップスにおけるこの理論の発展がたどられている。また、因果関係をベイズネットで表現する因果関係モデリングにおける最近の研究についても触れている。また、確率論的な理論におけるいくつかの難点についても言及されている。最後に、著者自身が提案する確率論的因果理論である「エピステミック因果性」について論じる。
第10章:因果過程論(Causal Process Theories)
因果過程論は、因果関係を離散的な事象間の関係ではなく、連続的な過程とその間の相互作用で特徴づけようとするものである。因果過程は、因果的な影響を持たない様々な種類の擬似過程と区別されなければならない。Phil Doweの章では、因果過程と相互作用を印可伝達と保存量の観点から特徴づけようとする主要な試みについて論じている。また、因果過程の理論に潜在する様々な問題についても考察している。
第11章:代理人論と介入者論
James Woodwardは、操作に基づく因果関係の説明を、因果関係と人間の行為との関連を強調するagency theoryと、抽象的な介入概念に焦点を当てたinterventionist accountとに分類して概観した。彼は、因果関係の実験的検証において、人間の自由な行動が必ずしも原因を操作する最善の方法ではないことなどを理由に、agency説を批判している。彼は、介入と呼ばれる理想的な原因操作の条件を規定し、いくつかの因果概念を介入という言葉で説明する。例えば、ある変数Xが変数Yと因果関係があるのは、(i)Xの値を変化させる可能な介入があり、(ii)そのような介入下ではXとYが相関する場合のみであるという。ウッドワードは、操作に基づく説明に対して、循環的である、人間中心的であるという標準的な反論に対して、この説明を擁護している。また、人間と非人間における因果関係の学習と判断の経験的心理学から、エージェンシーと介入主義的説明が持つ支持を探っている。
第3部:因果関係への代替的アプローチ
第II部のすべての章は、因果関係の定義や分析を行おうとする理論に関するものである。第III部では、因果関係を考えるためのさらなるアプローチを検討する。これらはすべて、ある種の概念的枠組みを提供する。いずれも因果関係を明確に定義するものではない。しかし、因果と関連する概念、あるいは異なる因果の概念間の関係を明確にし、因果の概念をより広い認識論的・形而上学的枠組みの中に位置づけることによって、これらはすべて因果の概念(あるいは概念)に光を当てようとするものである。
第12章:因果の力と能力
スティーブン・マンフォードは、因果関係に対する力のアプローチの歴史と基本的な主張について述べている。彼は、力あるいは能力の存在論が、ヒュームによって導入された因果関係の伝統的な問題を解決する、いやむしろ解消することができると主張している。伝統的な解釈では、ヒュームは世界を離散的で異なる存在から構成され、因果関係はそのような存在間の偶発的で外的な関係であると考えた。これに対して、力の存在論は、自然における必要なつながりを認める。偶発的に関係する原因と結果の代わりに、力とその表出があり、それらは必要なつながりによって関係する別個の存在であるというのである。ヒュームが因果関係を時間的優先権を伴う非対称的な外部関係として概念化したのに対し、マンフォードは、力アプローチによって因果関係を時間的優先権を伴わない対称的な内部関係として概念化することが可能であると論じている。
第13章 反還元主義
ジョン・キャロルは、因果関係についての反還元主義、すなわち、因果的事実は非因果的事実の観点から分析することはできないという見解を主張する。彼は、例えば因果の方向性や先取り問題などからいくつかの議論を展開し、反還元主義に対するいくつかの反論に応えている:非情報的、懐疑的、存在論的に贅沢、反還元主義者の中心的直観は「弱く、霧がかっている」ことだ。最後に、還元的な分析を発展させたり洗練させたりするのではなく、より広い問題(例えば、他律性や省略による因果関係など)に取り組む最近の文献の傾向について好意的なコメントを寄せている。
第14章:因果関係モデリング
Christopher Hitchcockの章では、統計学や人工知能の分野で開発された、因果関係を表現し、因果関係の推論を容易にするための形式的手法の数々について論じている。本章では、因果関係と反実仮想、介入、確率の関係について、これらの方法がどのような仮定を置いているかを検証している。また、このようなツールを用いて、より具体的な因果関係の概念、特に「実際の因果関係」の概念を定義することを説明する。
第15章 メカニズム
メカニズムとは、文字通り人工の機械を指す言葉であるが、相互作用する部品を持つ複雑なシステムを表す言葉として広く使われるようになった。科学の多くの分野、特に生物科学は、この広い意味でのメカニズムの発見とその表現に大きく関わっている。スチュアート・グレナンの章では、メカニズムに関する哲学的な説明と、メカニズムと他の因果関係の概念との関係について述べている。
第16章:因果的多元主義
第II部において調査された因果関係の理論は、いずれも因果関係の単一の定義を提供しようとするものである。しかし、このような「一元的な因果関係」の概念は存在しないため、「複数説」の支持者は、このプロジェクトは失敗する運命にあると主張している。著者によっては、因果関係には二つの具体的な概念があると提唱している。さらに急進的な立場として、互いに家族的な類似性しか持たない膨大な数の具体的な因果関係概念が存在するとする。ピーター・ゴッドフリー=スミスは、因果関係は「本質的に争われる」概念であり、何が原因としてカウントされるかについての意見の相違は、それ自体がこの概念の本質的な特徴であると示唆して、この章を終える。
第4部:因果の形而上学
因果関係に関する多くの問題は、世界の構成や構造に関する形而上学的な問いと密接に絡み合っている。例えば、どのようなものが因果関係に入るかという問題は、部分的には存在論の問題である。因果関係が物体、事象、普遍の例証、トロピーのどれに関係するかは、これらの実体が真に存在するものであるかどうかによる。同様に、因果関係が自然法則とどのように結びついているかという問題は、法則と因果関係が現実の基本的な構成要素であるかどうか、そしてそれらが最終的に非因果的な事実に還元されるかどうかにかかっている。この場合も、因果関係そのものの本質に関する問題-それは自然をその接合部で刻む自然関係なのか、それとも自然をその接合部で刻む自然関係なのか-が問われる。その時間的非対称性の根拠は何かという、形而上学的な問いかけが中心である。第Ⅳ部の各章では、このような因果関係をめぐる形而上学的な問いを取り上げる。
第17章:決まり文句と反例
因果関係の概念の理論家の多くは、その理論が因果関係についての常識的な決まり文句に対応するものだと考えている。すなわち、因果の概念は自然的関係の概念であり、その意味は、規範的考察から解放された偶発的な事後的関係であり、「自然をその接合部で切り分ける」という意味で客観的で心的に独立した関係であるということだ。ピーター・メンジースは、ほとんどの哲学者は、一つの中心的プラチチュードに暗黙的に同意していると指摘している。メンジースは、この決まり文句は哲学者の神話であり、言語学的、心理学的な証拠によって裏付けられていないと主張する。彼は、この哲学的見解に困難をもたらすものとして、因果関係、原因と結果のもろさ、原因と結果としての不在、原因と背景条件の区別に関する言語学的データを挙げている。彼は、これらの現象は、規範的考察に同調した因果概念の文脈に敏感な対比的説明によって最もよく説明されると主張している。
第18章 原因、法則、存在論
マイケル・トゥーリーは、対立する因果関係の見解が位置づけられる存在論的空間を切り分けるのに有効な方法を提示している。まず、その見解が単一主義的かどうか。つまり、特定の事象間の因果関係は、その事象が包含される因果法則(もしあれば)よりも基本的なものであると考えるかどうかということだ。第二に、還元主義的な見方であるか。つまり、因果関係や因果律は非因果的な事実に還元されるのか?つまり、事実や事象の内在的性質と外的関係を含むだけの状態であり、内在的性質は、そのインスタンス化がいかなる異なる状態の存在も伴わない性質に限定される、という考え方であろうか。トゥーリー自身は、特異論的、非還元論的な説明を擁護している。
第19章 因果関係
ダグラス・エーリングは、因果関係の主な候補として、出来事、普遍の例示、トロフィー、事実、物体(人を含む)、変数の値について考察している。因果関係の一般的特徴(時空間的関連性、内在性、推移性)を考慮すると、トロフィーが最良の候補であることが分かるが、因果関係の統一的説明を必要とする標準的な議論には説得力がないとも論じている。
第20章 因果関係の時間的非対称性
Huw PriceとBrad Weslakeは、因果関係の時間的非対称性-原因は通常、その効果を引き継ぐのではなく、むしろ先行するという事実-について論じている。彼らは、この時間的非対称性の納得のいく説明は、熟慮の時間的非対称性-我々が将来の目的のために行動するが、過去の目的のために行動しないという事実-も説明しなければならないと主張する。彼らは、これらの非対称性を世界の偶発的な特徴に関する仮説で説明しようとする因果関係の反実仮想理論に注目している。例えば、David Lewisの過決定非対称仮説やDavid Albertの宇宙が極めて低いエントロピー状態で始まったという趣旨の過去仮説である。彼らは、これらの仮説の経験的妥当性、および因果と熟慮の時間的非対称性を説明する能力に疑問を投げかけている。また、PriceとWeslakeは、Newcomb問題をめぐる因果的判断理論と証拠的判断理論の論争に関連して、「なぜ熟慮において時間非対称の因果的反実仮想を全く用いないのか」という問いを検討している。彼らは、熟慮を証拠的あるいは非因果的に考えるならば、熟慮の時間的非対称性を、エージェントとしての我々の特徴的な時間的志向性の観点から説明することができると主張する。そして、この主観主義的な熟慮の時間的非対称性の説明を、因果関係の説明にも拡張し、それぞれの根拠を、我々がエージェントとして持つ世界に対する独特の視点に置いているのである。
第5部:因果関係の認識論
世界の因果構造に関する信念はどのようにして生まれるのか、そしてその信念が正当化されるのはどのような場合か。ヒュームに端を発する最近の哲学の標準的な立場は、因果関係は決して認識されるものではなく、過去の規則性に基づいて推論されるだけである、というものである。本節の最初の2つの章は、この主張に対して若干の疑念を投げかけている。しかし、多くの因果関係は統計データに基づいて(つまり、ある種の過去の規則性に基づいて)推論されることは確かである。第3章では、このような推論をどのように、どのような状況で行うべきかという問題を取り上げる。
第21章 因果的知覚と推論の心理学
人間は世界の因果構造を学習し、その知識を推論のさらなるプロセスに用いる。David Danksの章では、このような人間の思考の側面に関する心理学的研究が概観される。これは、ある事象の連続の観察に対する比較的自動的な反応であり、他の情報源から入手できる情報には貫かれていない。もう一つの伝統は、知覚された規則性に基づいて因果関係を推論することに焦点を当てている。より最近の考え方は、因果関係を表現するためにある種の因果モデルを展開することだ。本章では、人間の因果関係理解と他の動物の因果関係推論に関する知見との比較も行う。
第22章 因果関係と観察
ヘレン・ビービーは、因果関係を観察できるかどうかという議論が、因果関係の形而上学に関する議論の中で果たしてきた役割について論じている。そして、心理学者や哲学者によって提示された、因果関係を観察することができるかどうかの判断基準を検討し、観察できるように見える(そして実際にしばしば観察できる)、と結論付けている。しかし、この結論は因果の形而上学にとって興味深い結果をもたらさないことを論じている。
第23章 因果関係と統計的推論
統計学は、量的事実のコンパクトな表現、部分データからのパラメータの推定、確率的仮説の検定、確率的モデルの構築など、さまざまな種類の問題に取り組んでいる。Clark Glymourの章では、統計量に因果関係の解釈を与えることができるのはいつか、また様々な統計手法を用いて因果関係を確実に推論することができるのはいつか、という問題に取り組んでいる。回帰分析のような伝統的な統計手法から、グラフィカルな因果関係モデルの使用など、より最近の発展も取り上げている。最後に、因果関係と統計学の関係について、いくつかのパズルを調査している。
第6部:哲学的理論における因果関係
20世紀の分析哲学の特徴は、因果関係の概念が中心的な役割を担っていることだ。一方では、哲学者たちは、知識、知覚、自由行動、意味内容といった広範な概念を分析し、解明するために、因果関係概念に訴えたのである。他方で、因果概念は、哲学者が探求する多くの概念上のパズルにおいて中心的な役割を果 たしてきた。例えば、倫理学者たちは、殺すことと死なせることの間に区別があるかどうか、ある行為が悪い影響をもたらすと予見される場合でも道徳的に許されるかどうかを検討してきた。心の哲学者たちは、精神状態が、その上位にある脳の状態とは無関係に因果関係を持ちうるかどうかを問うてきた。また、科学哲学者は、すべての説明は因果的説明なのか、低レベルの理論に還元できない高次の理論は創発的な因果構造を許容するのか、といったことを問うてきた。これらの問いはすべて、因果的概念の性質と、哲学的に重要な他の概念との関係についての微妙な問題を背景にしている。第VI部の各章では、これらの問題を詳細に取り上げる。
第24章: 精神的因果関係
Cei Maslen, Terry Horgan, Helen Dalyは、精神的因果関係が存在しないこと、すなわち、精神的状態や性質は因果的に有効ではないことを証明しようとする6つの哲学的論点を調査した。これらの議論の多くは、心的性質の上位にある物理的性質がすべての因果的な仕事をするのだから、心的性質は因果的には無関係である、という考えに基づいている。Maslen, Horgan, and Dalyは、これらの議論に対して、心的性質と物理的性質の間に型同一性を仮定する従来の対応は成功しないと主張する。彼らは、因果関係の主張の真偽は、どの可能世界が調査の文脈で適切とみなされるかに依存するという、文脈主義的因果理論の観点から、これらの問題に対する新たなアプローチを提唱している。この文脈主義理論は、精神的因果関係を脅かす6つの議論にそれぞれどのように答えるかを説明する。
第25章: 因果関係、行為、自由意志
アルフレッド・メレは、行為と自由意志の議論に現れる因果関係の問題を論じている。行為の場合、意図的行為に関する因果説と非因果説の論争が中心となっている。因果説は、意図的行為は代理人の理由(あるいは信念と欲望の組)によって(正しい形で)引き起こされることによって特徴づけられると主張し、反因果説は、行為は理由のためになされるが、理由によって引き起こされるのではないと主張する。メレは、因果的逸脱とエージェントの消失という二つの標準的な問題から因果主義を擁護している。自由意志の場合、古典的な自由意志の問題のバージョンとして、もしエージェントの選択が彼らの信念と欲望によって決定論的に引き起こされるなら、彼らは異なる選択をすることができず、したがって自由意志を欠いているという心配がある。一方、メレは、エージェントの選択は事前の精神状態によって決定論的に引き起こされるとする見解には、「運の問題」があると主張する。つまり、決定論的因果関係は、エージェントがどの選択をするかについて真のコントロールを持つことを妨げるように思われるのである。また、メレは、自由になされた決定は、エージェントの精神状態によってではなく、エージェントによって引き起こされるとするエージェント原因論もまた、運の問題にさらされると論じている。
第26章 因果と倫理
カロリーナ・サルトリオは、倫理学における様々な理論や問題、特に結果主義、殺すことと死なせることの区別、二重効果の教義(ある行為が悪い結果を予見していても道徳的に許されるとする)、そして道徳的責任の概念における因果関係の役割を調査している。また、倫理学における様々な問題が、因果関係の概念に注目することによってどの程度解決されるかを考察している。例えば、帰結主義に対する標準的な反論は、ある行為は一般にあまりにも多くの遠い結果をもたらすので、それらすべてがその道徳的地位に関係するとするものである。サルトリオは、因果の推移性を否定することがこの問題から抜け出す方法を提供すると論じている。これに対して、彼女は、殺すことと死なせることの間の道徳的差異は、行為と不作為の間の因果的地位の差異という観点から説明することはおそらくできない、と主張する。
第27章 知識と知覚の因果理論
ラム・ネータは、哲学者たちは、誰かが外部の物体を知覚することとは何か、知覚によって外部の物事について知ることとは何かを説明するために、因果関係に訴えてきたと述べている。(紛らわしいことに、「知覚の因果理論」という表現は、これらの説明のどちらにも適用されている)。どちらの説明も、外的実体と心的実体との間に存在する因果関係という観点から進められる。根多は、この2つのケースにおいて、理論家たちが外的実体と精神的実体として同定してきたものの種類を列挙している。最後に、経験的知識に関する因果論に対するいくつかの批判を検討する。
第28章 因果関係と意味内容
フランク・ジャクソンは、思考や言語の内容や参照に関する説明の中で、因果関係の概念がどのように扱われてきたかを概観している。彼は、思考の内容は思考と共変する世界の状態であるとする情報的処理と、思考と共変するように選択された世界の状態であるとする選択的処理を批判的に検討する。両者の問題点を指摘した。次に、言語の内容を固有名詞の参照に着目して考察する。名前の記述理論を概説し、クリプキによるこの理論への影響力のある批判を検討し、これらの批判と対称的世界における参照に関する別の反論に対してこの理論を弁護する。そして、参照は情報保存的な参照借用の連鎖によって確保されるというクリプケの代替的因果歴史理論の主要な要素を、いかに記述理論が取り込むことができるかを示している。
第29章 因果と説明
因果関係と説明には密接な関係があるように思われる。我々はしばしば、ある事象がどのように引き起こされたかを示すことによって、その事象がなぜ起こったかを説明する。ピーター・リプトンの章では、因果関係と説明の間の関係を探る。すべての説明は原因を引き合いに出すのか、またすべての原因は説明的なのか、といったことを問うている。また、なぜ原因がその結果を説明し、その逆はできないのかを検証している。最後に、説明的考察がどのように因果推論を促進するかを論じる。
第30章 因果と還元
ポール・ハンフリーズは本章で、還元的関係にあるシステムの間で因果関係がどのように作用するかという問題と、因果関係そのものが還元的な取り扱いに適しているかという問題の二つを取り上げた。具体的には、アーネスト・ネーゲルの理論還元モデルでは、ある理論が別の理論に還元されるのは、最初の理論の法則がブリッジ法則の助けを借りて2番目の理論の法則から演繹されるときである、と述べている。現代の哲学者の中には、上位の性質が下位の性質によってしばしば多重的に実現されるという理由で、このモデル、特にそれが仮定する橋渡し法則に疑問を呈する者もいる。ハンフリーズは、多重実現可能性の主張に対して、ケースバイケースで評価されなければならないと主張し、異議を唱えている。また、物理的領域の外には因果関係が存在しないことを示すとされる2つの議論(排除議論と下向き因果議論)を検討し、これらの議論に対する創発論者の可能な対応策を考察している。最後に、創発の問題に対処するために、キム・ジェグォンによって開発された代替的な還元モデルについて考察する。
第7部:他の学問領域における因果関係
因果関係は様々な形で多くの研究分野に入り込んでいる。中には因果関係の発見を中心的な課題としている分野もある。特に疫学、農学、法医病理学などの応用分野ではそうであるが、より理論的な生物学や物理学の分野でも因果関係の発見が問題となる。物理学では、ホール効果、ラムシフト効果、ゼーマン効果など、これらの因果関係はしばしば「効果」と呼ばれる。また、多くの分野で、明示的または暗黙的に因果関係を示す特定の概念が用いられている。法律では「近接的」な原因について語られ、遺伝学者たちは「特異的」な原因を頻繁に探し求める。進化生物学では、多くの著者が「適合度」、「機能」、「選択」といった概念は因果的な用語で理解されるべきであると主張している。さらに、基礎物理学のいくつかの理論は、因果関係の本質、あるいはどのような種類の因果関係が世界に見出されるかということに帰結するようである。
第31章: 古典力学における因果関係
古典力学は、ニュートンによって開拓され、マクスウェルの研究まで続いている物理学の研究プログラムである。相対性理論や量子力学に取って代わられたとはいえ、古典力学は近似的な理論として今でも広く使われている。古典力学の法則は微分方程式の形式をとっており、この法則が因果関係の解釈に適しているかどうかについては、かなりの議論がある。ラッセルは「(古典)物理学に原因は関係ない」と主張したことで有名である。もう一つの問題は、特に電磁気学における局所性原理の役割に関するものである。古典力学の法則は明示的に確率的なものではないが、多くの著者は古典物理学は不確定性のケースを認めると主張している。最後に、物理学における最小作用原理の役割と、それが目的論の一種を含むかどうかについても論じている。
第32章 統計力学における因果関係
因果関係の非対称性を熱力学第二法則が捉えた時間的非対称性に基づかせようとする試みは多くの著者が行っているが、因果関係と統計力学の関係については他にも重要な論点がある。Larry Sklarの章では、統計力学における非因果的と思われる説明を探求している。第一は現象論的平衡熱力学で用いられる超越的説明の一種である。もう一つは、非平衡熱力学における平衡への接近の説明である。これらの説明では、完全に先験的と思われる確率分布が利用される。
第33章 量子力学における因果関係
量子力学は、ミクロなレベルでの粒子の振る舞いが、マクロな世界での経験から導かれる物体の振る舞いに対する我々の期待に反していることを教えてくれるようである。特に、量子力学は因果的決定論の破綻を要求し、非局所的な因果的影響を認めているように思われる。しかし、その経験的な成功にもかかわらず、量子力学をどう解釈するか、つまり、量子力学が世界の振る舞いについて最も基本的なレベルで何を語っているかをどう理解するかについては、いまだに広く意見の相違がある。Richard Healeyの章では、このような議論が因果関係の理解に及ぼす影響について検討する。
第34章 時空間理論における因果関係
ニュートンの物理学、アインシュタインの特殊相対性理論、アインシュタインの一般相対性理論は、いずれも空間と時間の構造に対して深い意味を持っている。空間と時間の構造は、どのような因果関係が成り立つかを制約している。カール・ヘーファーの章では、これらの関連性を探っている。ニュートンの絶対的な空間と時間の概念は、同時性という絶対的な関係を認めた。この構造の一つの帰結は、理論が因果過程の速度に上限を課さないということだ。実際、ニュートンの理論の枠組みでは、重力は空間的に離れた場所で瞬時に起こる因果関係を含んでいるように見える。これに対して、アインシュタインの特殊相対性理論は、因果関係の速度に上限を課しているように見える。この上限は、ミンコフスキー時空のライトコーン構造として捉えられる。このように、時空の構造と因果関係の可能性には密接な関係がある。アインシュタインの一般相対性理論では、明らかに奇妙な因果的振る舞いをする多くの時空構造が認められている。あるものは閉じた因果曲線を含んでおり、一種のタイムトラベルや自己原因論を可能にする。また、互いに因果的に永遠に隔離された領域を含むものもある。さらに、一般相対性理論は、時空そのものが物質と因果的に相互作用していることを示していると読むこともできるかもしれない。
第35章 生物学における因果関係
サミール・オカシャは、生物学、特に進化論と遺伝学における因果関係の概念の役割を考察している。生物学者による因果関係の理解への貢献を歴史的に概観した後、進化論における因果関係を取り上げている。進化論的説明の因果構造を明らかにするために、ソバーが導入した発生的説明と選択的説明の区別、および形質選択と形質淘汰の区別を援用している。また、エルンスト・マイヤーの機能生物学と進化生物学の区別を利用して、進化論的説明が目的論的であることを明らかにした。最後に、遺伝学における因果関係を見ている。現代遺伝学における「のための遺伝子」という表現の意味を明らかにし、IQなどの認知形質の遺伝率解析をめぐる論争や、発達システム論による遺伝的説明の中心性についての批判を検討している。
第36章 社会科学における因果関係
ハロルド・キンケイドは、社会科学における因果関係の主張に関するいくつかの一般的な問題について論じている。その一つは、社会科学における因果関係の主張は、セテリス・パリバス項によって修飾されなければならないため、検証不可能であるという批判と、社会現象が集合的あるいは非個人的であるために適用されないという批判に関するものであった。キンケイドは、これらの批判が誤った認識であることを主張する。もう一つの問題は、社会科学における原因や説明の様々な特徴的な種類、特に目的論的原因や機能的説明に関するものである。キンケイドは、機能的説明を、生物学的アナロジーに不当に訴えることのない特別な種類の因果的説明として説明する。最後に、因果関係モデル化手法の前提が、多くの社会科学研究に適合しているかどうかという問題について論じている。彼は、因果的モデリングの前提が社会科学の多くの問題に適用できないという事実に対応する方法として、事例研究および事例比較の妥当性を擁護している。
第37章 法律における因果関係
ジェーン・ステイプルトンは、初期の米国現実主義者、ハートとオノレ、マイケル・S・ムーア、弁護士経済学者、リチャード・ライトなど、法律における因果関係の既存の説明について幅広い批判を展開している。彼女の中心的な主張は、法的文脈で用いられる「原因」の概念は、「規範的論争によって汚染されていない」ものでなければならないということだ。例えば、「近因」という概念を用いると、法的責任の範囲に関する規範的な決定ではなく、近因とそうでない原因との間に事実的、世俗的な区別があるかのような印象を与えるため、既存の多くの説明ではこれが達成できない。また、「原因」の意味に関する常識的な直感に訴えることも、規範的な特徴を持ち込む可能性があると彼女は主張する。Stapletonは、因果関係のある言語が法的文脈の中で合法的に使われる用途に合うように、新しい説明を描いている。その目的は、「事件のすべての事実が知られている場合」、「『因果関係』の問題で意見の相違が生じる余地がない」ような因果関係の理解を達成することだ。
