Contents
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8012489/
Front Immunol. 2021; 12: 637087.
2021年3月18日オンライン公開

要旨
衛生仮説は、その30年の歴史の中で、新たな科学的発展による挑戦を受けるたびに、その適応性を示してきたが、これは現在も継続している。このような観点から、本総説では、衛生仮説のさらなる微調整と拡大への影響に関連して、いくつかの新しい発展を選んで論じることを目的としている。
これには、古いTh1/Th2パラダイムに挑戦する、最近発見された自然免疫細胞および適応免疫細胞の役割、多様な病理学的エンドタイプを持つ新しく同定されたアレルギー/喘息の表現型に対する衛生仮説の適用性、環境影響の生体システムへの反映に関わるメカニズムの理解へとつながる、エピジェネティック研究からの知識の増大が含まれる。
さらに、衛生仮説の精神疾患や癌などの他の疾患領域への拡大について簡単に述べ、継続的に発展している衛生仮説は、高度先進国における健康負担をより一般的に説明するものであり、地球規模の変化との関連についても結論付けている。
キーワード:衛生仮説、アレルギー、喘息、非伝染性炎症性疾患、慢性炎症
はじめに
衛生仮説は、その歴史を通じて、科学の革新に挑戦されるたびに、適応性と柔軟性を発揮してきた(1)。この継続的な再検討の過程では、多くの新しい知見を考慮する必要がある。当初提案されたTh1/Th2パラダイムは、現在解明されている新しいクラスのエフェクターおよび制御免疫細胞によって、アレルギー発症に関わるより複雑な免疫ネットワークが指摘され、疑問視されている(2)。
バイオマーカーや詳細な表現型に関する研究により、喘息は一様な疾患であるという理解は変わり、異なる原因によって引き起こされる明確な表現型が支持されるようになった(3)。エピジェネティクスという新しい分野は、「遺伝子と環境の相互作用」というブラックボックスを、伝達メカニズムで埋めることを可能にする(4)。
現在、慢性炎症性疾患と精神疾患や癌などの他の疾患との間に重複するエピジェネティック経路が認識されており、西洋化社会における健康負荷の増大をより広い意味で説明するモデルとして、衛生仮説を拡張する可能性がある(5)。最後に、気候変動が引き起こす世界的な問題は、衛生仮説の結果に影響を与えないわけではない。ライフスタイルの変化は、CO2排出を抑制し、世界の気候を安定させるために実施される対策と密接な関係がある(6)。
免疫学からの挑戦 – 免疫系はより複雑になる
衛生仮説が時間の経過とともに見直されてきたのと同様に(7)、細胞性および液性免疫応答の基礎となるメカニズムに対する我々の認識も、この数十年で根本的に変化してきた。高解像度のフローサイトメトリーやセルソーティング、そして最近ではシングルセルマルチオミクスに基づく解析により、様々な種類の造血細胞の表現型の特徴、機能、そして発生についてより深い洞察が得られるようになった。
Th1とTh2の二元的な反応モデルは、Tリンパ球が高度な可塑性と適応性を特徴とするサブセットの分岐したネットワークであることが発見されたことにより、大きく拡張された(8)。すなわち、坂口の制御性T細胞(Treg)サブセットの発見は、アレルギー性疾患や自己免疫疾患の免疫学的起源や健康な状態での予防を研究する研究者に新しい刺激を与え、これらの疾患に対する新しい戦略を指摘した(9, 10)。
さらに、新しいクラスのエフェクター細胞やその細胞間相互作用が発見され、この分野に関連する証拠が追加された。その一例として、自然リンパ球(ILC)は、アレルギー反応の発現に直接的、間接的に関連し、関与していることが示されており、大きな関心を集めている(11)。
このユニークなクラスのエフェクター細胞は、クローン的に分布する抗原受容体を持たないため、(抗原)非特異的活性化を特徴とする自然免疫細胞に類似しているが、Tヘルパー(Th)様エフェクター細胞活性を発揮する(12)。ILCは、エフェクターサイトカインや転写因子の発現により、3つのグループに分類されている。
ILCは、エフェクターサイトカインや転写因子の発現により、ILC1、ILC2、ILC3の3つのグループに分類される(13)。ILC1はインターフェロンγ(IFNγ)や腫瘍壊死因子α(TNFα)を産生し、Th1細胞と同様にT-betを発現するのに対し、ILC2は転写因子GATA-3の制御下でTh2細胞と同様にIL-5やIL-13などのTh2サイトカインを産生することが可能である。
ILC3はTh17細胞に類似し、IL-17AやIL-22、顆粒球マクロファージコロニー刺激因子(GM-CSF)などを放出する。アレルギー性気道炎症動物モデルやアレルギー性喘息患者において、ILC2は肺や気道の上皮細胞に高い頻度で存在し、2型サイトカインであるIL-5やIL-13を大量に産生することが見出されている(14)。ここ数年、ILC2はアレルギー性気道炎症反応を確立し維持するための初期促進因子として、また肺上皮の修復過程を促進する保護因子として認識されてきた(15, 16)。
* *
衛生仮説とILC系統の機能との間の潜在的な関連は、腸に由来している。免疫細胞と腸内細菌叢との共生的相互作用は、寛容性あるいは病原性の発現に主として決定的な影響を与える。ILC3系は、腸のリンパ濾胞とパイエル板の形成に必須であり、微生物叢とのバランスのとれた共生を維持するために重要であることが示された(17)。
宿主微生物叢は、ILCサブセットの特異性を決定する上で重要な役割を担っている可能性がある。Sepahiらは、ごく最近、食物繊維から生じる短鎖脂肪酸(SCFA)が腸内の微生物発酵によって、一般的なILCサブセットの拡大を誘導することを報告した。
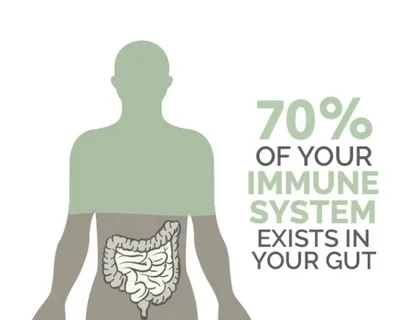
Gタンパク質共役型受容体(GPCR)を介してILCサブセットの拡大を誘発することにより、これらの食事代謝物は局所コンパートメントのホメオスタシスに貢献する(18)。上皮表面の修復と恒常性維持を誘導するもう一つのメカニズムは、微生物叢に反応してIL-22を産生するILC3を介するものである。
上皮細胞が産生するIL-18との相互作用により、IL-22は修復とリモデリングのプロセスの促進だけでなく、腸の恒常性の維持に関与する(19)。微生物と宿主の間のメディエーターとして働くILCは、微生物刺激に対する宿主の初期反応に重要であると認識されている。
環境の変化による課題 -エピジェネティクスは「遺伝子と環境の相互作用」を説明するミッシングリンクとなりうるか?
ごく最近、アレルギー疾患の研究において、免疫系の正常な発達を妨げたり、バランスを崩すような有害な因子が注目されるようになった。室内外の汚染(20, 21)や地球温暖化による環境変化がアトピー性皮膚炎に影響を与えており、遺伝子と環境の相互作用によるエピジェネティックな変化に基づいて、これらのシナリオを衛生仮説の概念に統合する試みが最近行われている(22)。
* *
我々の祖先が人生の大半を屋外で過ごし、自然環境に近かったのとは対照的に、近代以降の主に都市部での生活スタイルは、屋内活動の割合が著しく高いことが特徴である。このような生活習慣の変化は、アレルギー疾患の発症に室内空気組成が潜在的に重要であることを強調し、環境微生物叢の役割をさらに強調するものである(23)。
都市部の家庭の室内空気は、しばしば高レベルのカビに覆われており、気道に有害で、気道炎症および喘息の発症を助長することが分かっている(24)。気候変動に対する意識の高まりと、それに伴うエネルギー消費とCO2排出の削減努力の高まりを背景に、住宅の断熱性能を向上させた住宅におけるこれらの室内暴露に関する現在の研究は、今後起こりうる健康問題を指摘している。

家具から放出される揮発性有機化合物、タバコの煙、多年生アレルゲン、カビなどの濃縮は、免疫系や成長中の肺がこれらの損傷要因に非常に敏感であるため、主に乳児を危険にさらすだろう(25)。すでに胎児は、これらの成分の影響を受けているかもしれない(26)。
このことは、出生前の喫煙による喘息のリスクを評価するために行われた世代を超えたケースコントロール研究において、タバコの煙について例示的に示された。喘息児と非喘息児の祖母と母親に、自身の妊娠中の喫煙習慣について質問したところ、喘息児と非喘息児の祖母の喫煙習慣は、喘息児と非喘息児の祖母の喫煙習慣の2倍であった。その結果、母親の胎児期に祖母が頻繁に喫煙していた家庭では、子供が喘息を発症するオッズ比が2倍になると報告された(27)。

* *
この時点で、衛生仮説は、アレルギーや喘息などの非遺伝性/非伝染性疾患が、環境暴露と与えられた遺伝子型との不適切な相互作用を背景に発症し、特定の(疾患)表現型を形成するという、来るべき一般概念に合致するものであった。前世紀50年代にWaddingtonによって提唱されたいわゆるエピジェネティック・ランドスケープの概念に基づいてはいるものの、エピジェネティック・プログラミングの基盤となる分子メカニズムは、遺伝子と環境との相互作用のシナリオにおける「ミッシングリンク」であった(28)。
エピジェネティックな遺伝子発現制御の分子機構として、DNAメチル化、多様なヒストン修飾、microRNA制御などのメカニズムが発見されたことにより、エキサイティングな新しい研究領域が開かれ、現在も残るアレルギー発症・予防の謎の解明を目指す研究に強い影響を与えている(29-31)。
* *
実際、エピジェネティックなメカニズムは、アレルギー発症のリスクを増大または減少させる環境因子の影響の媒介に関与していることが明らかにされている(4)。親アレルギー的な環境影響は、公害に代表される。例えば、多環芳香族炭化水素(PAH)への高い胎内曝露は、IFNγをコードする遺伝子のプロモーターにおける臍帯血白血球のDNAメチル化の増加と関連していることが示されている(32, 33)。
さらに、末梢血単核細胞から分離したTregでは、PAH曝露量が多いほど、Tregの発生と活性のマスターレギュレーターであるFOXP3をコードする遺伝子のプロモーターでのDNAメチル化が上昇し、その影響は非喘息児よりも喘息児の方が強いことが分かっている(34)。
* *
疫学的研究により、幼少期を特定の農業環境で過ごすことと、小児期のアレルギー発症予防との関連が示された後(35, 36)、様々なタイプの機能的研究により、家畜との接触、生乳の摂取、いわゆる農場塵への暴露など、農業のどの要素がこの観察のメカニズムに関係しているかが明らかにされ始めている。

FOXP3遺伝子の高発現とTregの活性化に関連するFOXP3コード遺伝子座のDNA脱メチル化(37)は、母親の生牛乳摂取と臍帯血(38)、子供の全血と生牛乳の早期摂取に関連している(39)。加工された店乳と比較して、生牛乳の前処理は、食物アレルギーモデルを適用したマウスの疾患の特徴を減少させ、この効果は、重要なT細胞関連遺伝子のヒストンアセチル化パターンの変化によって媒介された(40, 41)。
興味深いことに、未加工の牛乳には、重要なアレルギー関連免疫遺伝子の発現に影響を与える可能性のあるmiRNAが含まれていることが示されており、これが喘息に対する保護効果に寄与している可能性がある(42)。農業環境からいくつかの細菌が分離されており、例えばAcinetobacter lwoffii (A. lwoffii) は、マウスモデルにおいてアレルギー症状の発生を抑制することが実証されている (43) 。

A. lwoffiiを介したアレルギー性気道炎症に対する保護は、マウスモデルでも経母子的に観察され、IFNγ依存性であることが示された。この効果は、子孫の脾臓から分離したCD4+T細胞で観察されたIFNγコード遺伝子のプロモーターでのヒストンH4アセチル化の維持によって少なくとも一部媒介されている(44, 45)。
臨床からの挑戦と動物モデルからの教訓-喘息表現型と衛生仮説
喘息研究の分野で再燃した議論は、2012年のWenzelによる総説で見事に要約されている(46)。喘息患者の臨床的不均質性から、彼女は、喘息患者では基本的な炎症パターンが異なり、それが適用される治療戦略の成否を決定することを強調した。
早期診断と適切な治療により、後に重症の喘息表現型を発症することを防ぐことができるため、喘息を発症するリスクのある子供とそうでない子供を識別する新しい戦略が必要とされている(47)。
Wenzelらは、ある遺伝子型と環境との相互作用の結果としての表現型を臨床的に定義した後、このような表現型の特徴づけと層別治療のための具体的要件を定義するための新しい分子および遺伝子バイオマーカーの必要性を強く訴えている。
Th2が関与するアトピー性喘息と非アトピー性喘息の違いに基づき、年齢とともに変化し、標準的な薬物治療への反応が異なる多くの亜型が定義された。それぞれの表現型を明確に特定する特定のバイオマーカーを探しても、うまくいかないことはすぐに明らかになった。
むしろ、「ディープフェノタイピング」と呼ばれる被験者から収集したすべてのデータを総括することが、複雑な喘息状態の理解を深めることにつながるかもしれない(48)。オミックス時代のディープフェノタイピングは、分析すべきデータの驚異的な増加とともに進行している。
これらのビッグデータセットを扱うために、統計的データの次元削減モデルや機械学習戦略を含む新しいアプローチがますます採用されるようになっている(49, 50)。これらのデータ駆動型アプローチの背後にある考え方は、データコレクションをマイニングし、データの背後にあるこれまでのところ隠されたパターンに基づいてそれらを分類することだ。
仮説のない潜在クラス分析(LCA)アプローチは、喘息(および他のアレルギー性疾患)の表現型を新たに同定したり、提案された表現型を検証するための最も有望なツールの1つである。
最初のLCAアプローチは、成人の喘息患者の2つのコホートで実施された。Sirouxらは、臨床的および個人的特徴に基づいて、2つの独立したコホートで2つの異なる表現型、すなわち、小児期にすでに喘息が確立している重度の表現型と、成人期に始まりより軽度の結果をもたらす第2の表現型について説明した(51)。
これらの結果は、衛生仮説に沿うものであり、幼児期における特定の前提条件が、後年重度の喘息に至る道を開くことを指摘するものである。小児におけるLCA解析では、一過性の喘鳴は病的な影響を及ぼさないように思われるが、現在の止まらない喘鳴エピソードなどの初期の臨床症状は、後年の喘息発症の高いリスクを示すとされ、早期発症とその後の疾患との間の関連性が実証された(52)。
* *
患者研究のデータを用いたLCAアプローチにより、Hygiene Hypothesisで説明できる表現型の喘息症状がある一方で、異なる病理学的起源を持つ他の表現型はこの仮説でカバーできないことが明らかになった(53)。この矛盾は、前臨床の動物実験やヒトのデータに基づく研究において、新しいアプローチにつながった。
免疫学的および組織学的レベルで識別可能な表現型の仮定を証明するために、新しい動物モデルが採用された。感作を主に2型アジュバントであるミョウバン存在下での人工的な腹腔内アレルゲン感作によって行っていた定評あるオバルブミン(OVA)モデルから、より柔軟な標準化ハウスダストマイト抽出物(HDM)経鼻投与に切り替えることで、このような表現型を誘導することが可能となった。
典型的なアレルギー性好酸球優位の呼吸器炎症から好中球の流入のみが支配する気道炎症状態まで、より自然で幅広い炎症表現型を誘発することが可能であった(54-56)。このような柔軟なモデル系により、異なる表現型の発現の基礎となるメカニズムをより深く正確に調査し、Th2およびTh1/Th17駆動型炎症の連続体におけるアレルゲン投与に依存した異なる制御性およびエフェクターT細胞サブセットの編成をよりよく特徴付けることができる。
さらに、これらのマウスモデルは、一般的なアレルゲンと自然な感作経路を用いることで自然の状況をより忠実に模倣しており、アレルギー性および非アレルギー性、さらに軽度および重度の喘息の多様な臨床表現型の理解に役立つようになった (57, 58)。
これらの実験セットアップで異なるエフェクターT細胞応答を切り替えることにより、現在、喘息の臨床症状の理解に重要な知識が加えられている。臨床的表現型の解明に役立つLCAとの組み合わせにより、これらの最近の研究開発は、小児の一過性アレルギー疾患と持続性アレルギー疾患、およびアレルギー性喘息と非アレルギー性喘息をよりよく識別することを強く後押ししている。
この新しい証拠は、現在の衛生仮説の限界を示すものかもしれない。IgEを主成分とするアレルギー性喘息が衛生仮説に合致することは間違いないが、非アトピー性喘息の表現型についてもそれが当てはまるかどうかはまだ不明で、その発症は免疫系の(微生物)教育不足とは異なる要因によってより強く決定されると考えられている。
したがって、衛生仮説をさらに微調整するためには、疾患表現型の誘発に関連する、あるいはアレルギー疾患表現型の異なる炎症症状の間の移行に寄与するだけの環境条件(病原性ウイルスへの幼少期の感染など)と、衛生仮説に沿った疾患の一般的あるいは表現型/エンドタイプ特異的予防に本当につながる条件(43、61)を見分けるための継続的努力が必要である。
塀の上から見た課題-精神疾患と癌における衛生仮説
フランスの科学者バッハは、過去70年の間に、感染性疾患と非感染性慢性炎症性疾患の有病率に一般的に逆相関があるという主要な観察を行った最初の人である(62)。一方、多様な感染性微生物、あるいは無害な微生物に多く暴露され、幼少期に低悪性度の急性炎症を繰り返すと、成人期に低レベルの炎症マーカーを伴う慢性炎症性疾患の有病率が低くなることが分かっている。
逆に、欧米に特徴的な周産期や幼児期の発達段階における高い衛生状態は、後年の慢性炎症性疾患の高い有病率と相関する高いレベルの炎症マーカーに対応する。これらの事実に基づき、乳幼児期に頻繁に起こる低グレードの、ほとんどの場合臨床的に症状のない炎症が、炎症刺激に対する反応のバランスをとり、おそらく適応免疫依存性の調節を適切に形成することにより、成人期への慢性炎症の継続率を減少させるのではないかという仮説が立てられた(23)。
* *
興味深いことに、この観察は、アレルギー以外にも、多発性硬化症、過敏性腸疾患、1型糖尿病など、衛生仮説の傘の下に収まりそうな慢性炎症疾患の広い範囲を考慮している(63)。さらに、ここ数年、欧米諸国における精神疾患の急激な増加を説明するために、同様のアプローチが登場した。

主に大うつ病や双極性障害などの感情障害が、西洋化した世界でますます診断されるようになっている。感情障害や不安障害の患者は、血中や中枢神経系の炎症性サイトカイン、循環CRPの上昇、リンパ球の活性化、炎症性細胞シグナル伝達経路(MAPKやNF-κB)などの炎症状態を反映する特徴を示し、因果関係の問題は鶏か卵かのように残っている(64)。
しかしながら、脳(神経系)と末梢(免疫系)における遺伝的素因とエピジェネティックな修飾に基づき、気分障害と炎症性障害の両方の病態が、それまでは緊密にバランスを保っていた身体の適応システムの恒常性の乱れに基づいて確立されるのかもしれない。
興味深いことに、最近の研究で明らかになったように、腸内細菌叢は精神疾患の発症にも重要な役割を果たしているようである(65)。腸と中枢神経系の相互作用に基づいて、持続的なストレスや虐待は神経系を変化させ、それによって内分泌系の視床下部下垂体軸(HPA)が変化し、コルチゾール放出によって腸内細菌叢を変化させる(66)。

腸内細菌の異常は、血液中のサイトカインバランスの悪化につながり、血液脳関門を通じて炎症性メディエーターやサイトカインが移動した後、脳のミクログリアが活性化される可能性がある(67)。さらに、腸内細菌叢の有益な細菌の分解により、酪酸などの微生物叢由来の産物が失われ、その結果、神経調節回路に直接関与するすべての因子、γ-アミノ酪酸、セロトニン、ドーパミンがダウンレギュレーションし、調節障害となった場合に神経精神疾患の発祥に直接関与する可能性がある(68)。
* *
最後に、このコレクションに別の例を付け加えると、アレルギーからの保護に関与するのと同様のメカニズムが、癌性疾患の予防にも役割を果たすかもしれないという証拠が増えつつある(69)。ある種の病原体への先行感染が、いくつかの腫瘍疾患の発症やさらなる進展を促す可能性があることは疑いない。
しかし、微生物への曝露を介した免疫調節が発癌に及ぼす二律背反的な影響の根本的なメカニズムは今のところよく分かっていないが、最近の様々な研究により、病原体による「良性」の炎症過程が発癌に好ましい影響を及ぼすことも示されている(70)。
一例として、小児白血病の起源は、長い間、幼児期の微生物刺激という文脈で議論されてきた。すでに20世紀末には、小児期の早期感染が、よく訓練され確立された免疫機構を通じて、拡大する異常白血球クローンを排除することにより、小児急性白血病に対して保護的に作用するのではないか、という疑問が浮上した。

グリーブスは、衛生仮説と一致して、「遅延感染仮説」を、豊かな国々で生後2〜5歳でピークに達する小児急性(リンパ芽球性/骨髄性)白血病(ALL/AML)の発症の説明として広めた(71、72)。Greavesは、彼の2ヒットモデルにおいて、出生前に生じた染色体転座または倍数体異常に基づいて、出生前後にすでに前白血病クローンが確立されていることを提案した(1ヒット目)。
その後、幼児期を過ぎて2回目のヒットにより、遺伝子の欠失や突然変異が起こり、ALL/AMLに変化していく。感染症にかかったり、生後早期に豊かな微生物環境にさらされたりした子供たちは、この2回目の異常を防ぐ準備ができているかもしれないが、生後早期に「旧友」との接触を失って免疫系が十分に教育されていない素因を持つ子供たちは、拡大する悪性細胞クローンを排除することができないかもしれない(72)。
この仮説を証明するために、生後3年目までの「保育園通園」を感染の代理人として利用する研究が数多く行われた。この概念については、まだ議論の余地がある。これらの研究の大部分はGreaves仮説に証拠を加えることができたが、よく実施された研究の中には、彼の仮定を支持できないものもあった(73、74)。最近、小児白血病に関する農場効果についてメタアナリシスが行われ、家畜との接触がアレルギーだけでなく小児白血病に対しても予防効果を発揮することが確認された(75)。この研究は、アレルギーと小児がんの予防の両方において、マイクロバイオータが重要な役割を担っていることを示唆しているのかもしれない。

* *
このミニレビューで概説した課題は、衛生仮説の継続的な修正と適応をもたらすかもしれない、さらなる刺激的な議論を喚起することを意図している。このレビューで報告された例は、現在衛生仮説との関連で議論されている科学的トピックのうち、限られた主観的な選択しか記述していないかもしれないことを承知している。
しかし、その根底にあるメカニズムを解明するための説明が、我々の身体の粘膜表面で確立された人間と微生物との密接で有益な関係に言及していることは、すべてのトピックに共通する。このような相互作用により、生体の適応システム(主に免疫系)が適切に形成され、生物全体が様々な悪影響に適切に対処できるようになるのである。この発見は、過去30年間における生命科学の最も基本的な洞察のひとつであると言っても過言ではないだろう。
資金提供
ドイツ肺研究センター(DZL)より資金提供を受けた。オープンアクセスは、ドイツ・フィリップス大学マールブルグ校の図書館から資金提供を受けた。
利益相反
著者らは、本研究が利益相反の可能性があると解釈される商業的または金銭的関係がない状態で実施されたことを宣言する。
