Contents
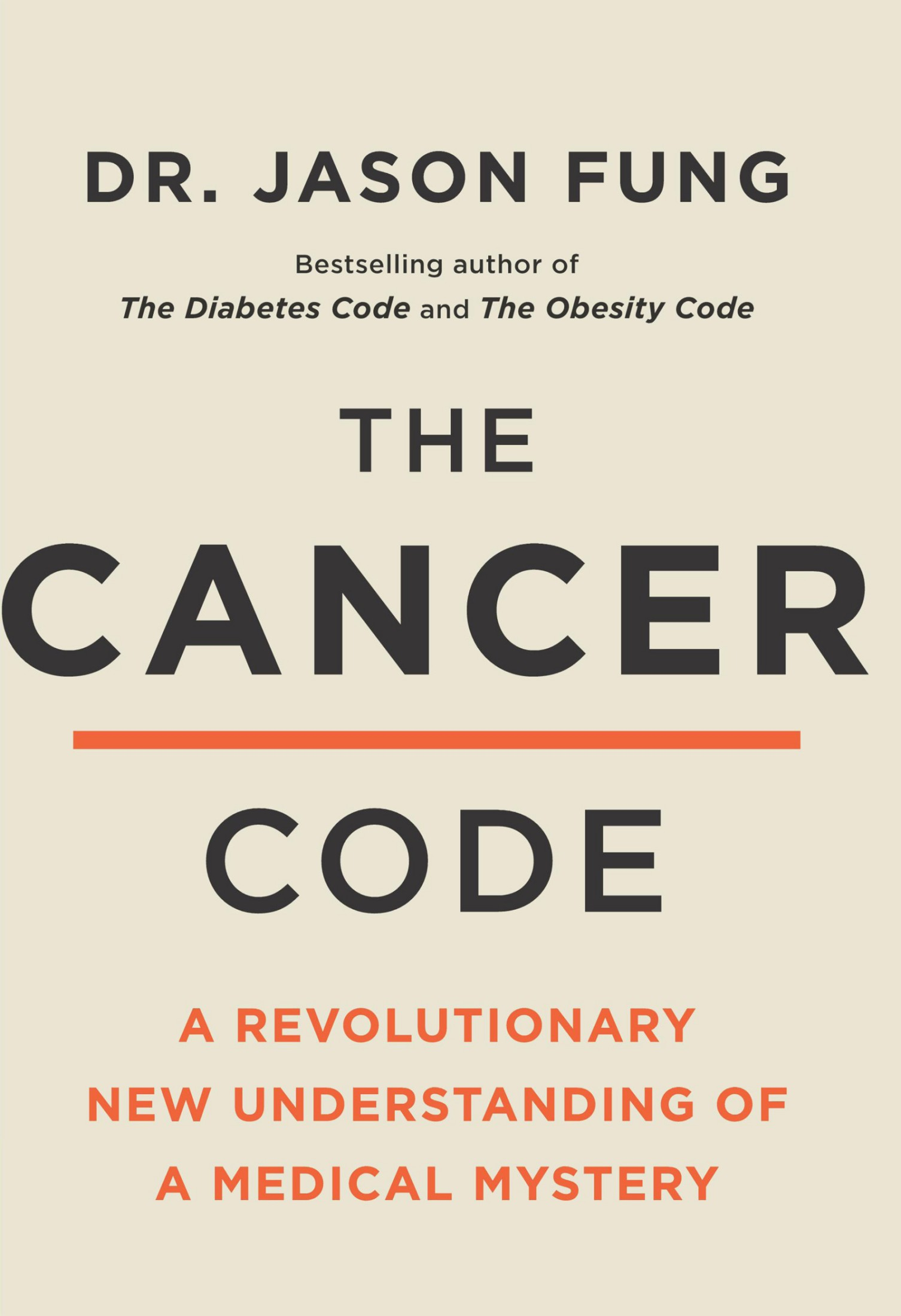
The Cancer Code
目次
- 第1部 過剰な成長としてのがん(がんパラダイム1.0)
- 第1章 塹壕戦
- 第2章 がんの歴史
- 第3章 がんとは何か?
- 第4章 発がん物質
- 第5章 がんはウイルスに侵される
- 第2部 遺伝病としてのがん(がんパラダイム2.0)
- 第6章 体細胞変異説(Somatic Mutation Theory)
- 第7章 癌のプロクラステスベッド
- 第8章 分母の問題
- 第9章 偽りの夜明け
- 第3部 トランスフォーメーション(がんパラダイム3.0)
- 第10章 種と土の話
- 第11章 生命の起源と癌の起源
- 第12章 腫瘍の進化
- 第13章 癌の変容
- 第4部 進行(がんパラダイム3.0)
- 第14章 栄養とがん
- 第15章 高インスリン血症
- 第16章 成長因子
- 第17章 栄養素センサー
- 第5部 転移(がんパラダイム3.0)
- 第18章 ワールブルグの復活
- 第19章 侵略と転移
- 第20章 癌の不思議な話
- 第6部 治療の意味合い
- 第21章 がんの予防と検診
- 第22章 がんの食事による決定要因
- 第23章 免疫療法
- エピローグ
- 備考
- インデックス
- 著者について
献上
美しい妻、ミナ、そして息子のジョナサンとマシューに捧げる。彼らの愛とサポート、そして忍耐に感謝したい。あなたたちなしでは成し遂げられなかったことである。
第1部 過剰な成長としてのがん (がんパラダイム1.0)
第1章 塹壕戦
以前、ある病院の会議で、新しいプログラムのディレクターが過去1年間の成果を発表したことがある。この新しいプログラムには、地域から100万ドル以上の資金が集められ、期待が高まっていた。私は、その場にいた人たちの中で、その成果に感銘を受けた人はいなかったが、自分には関係ないことだし、母から「いいことを言わないなら、何も言うべきではない」と教えられていたので、黙っていた。しかし、それでも「このプログラムは貴重な時間と資源を無駄にした」という思いは消えなかった。
私の周りでは、他の参加者が応援の声をかけてくれていた。よくやった!おめでとう!よくやった!この1年間、ほとんど何もなかったことは誰の目にも明らかなのに、周りの医療関係者のほとんどは、「素晴らしい、素晴らしい」という感情に流されていた。私も含めて、誰も立ち上がって 「The Emperor has no clothes!」と叫ぶことはなかった。
この問題は、私の病院に限ったことではなく、公衆衛生全般で蔓延しているもので、どんな官僚組織でもそうなってしまう。批判的な意見を独り占めすることは、人間関係では有効だが、科学の進歩のためには役に立たない。問題を解決するためには、問題の存在を知る必要がある。そうして初めて、現在の解決策にどのような問題があるのかを理解し、それを改善することができる。命がかかっているのだろうから。しかし、医学研究では、決められたストーリーから外れる意見は歓迎されない。この問題は、肥満、2型糖尿病、そして癌の研究など、あらゆる分野に及んでいる。
肥満症
私たちは、世界の歴史上最大の肥満の流行を目の当たりにしている。世界の肥満に関するどの統計を見ても、そのニュースは暗いものである。1985年、アメリカの州で肥満の有病率が10%を超えていた州は一つもなかった。2016年、疾病管理予防センター(CDC)は、肥満の有病率が20%未満の州はなく、25%未満の州は3つしかないと報告した1!この変化は、過去31年間、つまり一世代で起こったことなので、単に悪い遺伝のせいにすることはできない。明らかに、私たちは、人々が体重を減らし、健康的な体重を維持できるようにするための、介入的で持続可能なソリューションを必要としている。
何十年もの間、私たちは肥満に対する処方箋があると信じて、自分を騙していた。CDCは、「体重を減らすには、摂取したカロリーよりも消費したカロリーの方が多い」と指摘している。体脂肪1ポンドには約3,500カロリーが含まれているため、1週間に約1~2ポンド痩せるためには、1日あたり500~1000カロリー摂取する必要がある。これは、医師や栄養士が世界中で繰り返し、雑誌、教科書、新聞で報告されている、ごく標準的なアドバイスである。私が医学部で学んだ食生活のアドバイスと同じだ。それ以外の方法で体重を減らす方法があると示唆する医師は、大方ヤブ医者とみなされる。しかし、医学界がカロリーにこだわることは、肥満の蔓延に対する成功にはつながっていない。もし私たちが、自分たちの解決策がはるかに、はるかに不十分であることを認めることができなければ、私たちは肥満の増加傾向に対抗する力を失ってしまうだろう。
もっと食べろ、もっと動け」というアドバイスが効かないことを認める人はほとんどいないだろう。しかし、肥満の蔓延を解決するための重要な第一歩は、私たちの欠点を認めることなのである。カロリーを数えろというアドバイスは、有益でも効果的でもない。むしろ、私が主張してきたように、肥満はカロリーの問題ではなく、ホルモンのアンバランスであることを認めなければならない。この真実を受け入れ、実際に効果のある介入策を開発できるように前進しよう。そうしてこそ、この公衆衛生の危機の流れを変えるチャンスがある。経済学者ジョン・メイナード・ケインズは、「The difficulty lies so much in develop new ideas as well as in escaping from old ones. ”と言っている。
2型糖尿病
2型糖尿病の恐ろしい流行は、肥満の流行と密接に関係している。CDCによると、アメリカ人の約10人に1人が2型糖尿病を患っているという。さらに悪いことに、この数字は過去数十年の間に右肩上がりで増えており、救いの手はない(図11参照)。
図11
【原図参照】
2型糖尿病は、インスリンのような血糖値を下げる薬が標準的な治療法である。通常、患者は時間の経過とともに、これらの薬をより多く、より多く必要とする。もし、あなたがより多くのインスリンを摂取しているのであれば、あなたの2型糖尿病がより深刻になっていることは明らかだ。しかし、私たち医療関係者(研究者、医師)は、2型糖尿病は慢性的で進行性の病気であり、そういうものであるという立場を維持しているだけだ。
どれも真実ではない。患者が体重を減らすと、ほとんどの場合、2型糖尿病は改善される。糖尿病患者にもっと薬を処方する必要はなく、食生活を改善する必要がある。しかし、私たちは自分たちの治療法に欠陥があることを認めたくないのである。それは、私たちの研究者や医師が、恐ろしい病気に対して勇敢に前進しているという、合意された物語から逸脱することを意味する。問題を認める?とんでもない。その結果は?疫病が蔓延し続けることになる。肥満の場合と同様、一般的な治療法が許容範囲から大きく外れていることを認めることができなければ、私たちは苦しんでいる人々を助けることができないままになってしまうのである。
癌
ここでようやく、がんの話になる。確かに、私たちはがんに対して大きな進歩を遂げているに違いないね。毎日のように、私たちの先駆的な科学者たちによって発見された、がんのブレイクスルー発見や医学的な奇跡が報道されている。しかし、冷静にデータを見てみると、がん研究の進歩は、他の医学分野のほとんどに比べ、遅れをとっていることがわかる。
20世紀初頭、がんはそれほど注目される存在ではなかった。公衆衛生上の最大の脅威は、肺炎、消化器感染症、結核などの感染症だった。しかし、公衆衛生が改善され、1928年にはイギリスの研究者アレクサンダー・フレミングがペニシリンを発見し、世界を驚かせることになった。そして、アメリカ人の平均寿命が延び、心臓病やがんなどの慢性疾患に焦点が当てられるようになった。
1940年代、米国がん対策学会(ASCC、後の米国がん協会)は、早期発見と積極的な治療の重要性を説いた。ASCCは、子宮頸がんの婦人科スクリーニング検査であるパップスメアを日常的に使用することを提唱した。その結果、子宮頸がんの早期発見により、子宮頸がんによる死亡率は劇的に低下し、見事な成功を収めた。しかし、他のがんによる死亡率は増加の一途をたどった。
そこで、ニクソン大統領は1971年の一般教書演説で、「がんの治療法を見つけるための集中的なキャンペーン」を提案し、がんとの戦いを宣言した。そして、「全米がん法」に署名し、がん研究に16億ドル近くを投入した。当時は、楽観主義が蔓延していた。アメリカはマンハッタン計画で原子時代の到来を告げていた。アポロ計画で月面に人を乗せたばかりだ。しかし、がんはどうだろう。「がんも克服できるはずだ」1976年のアメリカ建国200年祭までには、がんは治る」と熱く語る科学者もいた。
しかし、200年祭が終わっても、ガンの治療法は現実のものとなっていなかった。1981年、「がんとの闘い」が始まってから10年が経った頃、ニューヨーク・タイムズ紙は、この大々的に宣伝された10年間の闘いが「この恐ろしい病気に対して真の進歩をもたらしたのか、それとも75億ドルの贅沢な誤算だったのか」と疑問を呈した2がん死亡数は非情に上昇を続け、過去10年間の努力はその上昇速度を落とすことさえなかった。がんとの戦いは、これまでのところ、完全に敗北していたのである。
ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン誌のコンサルタントやハーバード大学公衆衛生大学院の講師も務める国立がん研究所(NCI)のジョン・バイラー3世博士のような内部の人間にとっては、これはニュースではなかった。1986年、ベイラー博士は『ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン』誌の論説で、がん研究プログラム全体の有効性に疑問を投げかけた3。同論文でベイラー博士は、1962年から1982年にかけて、がんで死亡したアメリカ人の数が56%増加したことを指摘した(図12参照)。人口増加を考慮すると、これはがんによる死亡率が25%増加したことになるが、当時は他のあらゆる疾患による死亡率が急速に低下しており、がん以外の原因による粗死亡率は24%減少していた。Bailar博士は、このデータについて、「がんの治療を改善するための約35年にわたる熱心な取り組みが、臨床結果の最も基本的な指標である死亡に大きな影響を与えたという証拠はない」と指摘した。実際、がん全体に関しても、私たちは徐々に遅れをとっている」と述べている。彼は、「なぜがんは、年齢調整死亡率が依然として上昇している唯一の主要な死因なのか」と声を大にして考えた。
世界で最も著名な医学雑誌に掲載されたがん戦争のインサイダーとして、バイラール博士は事実上、「The Emperor has no clothes!」と叫んでいた。彼は、大失敗した同じ癌のパラダイムを繰り返すことで、茫漠としていた癌研究の泥沼に、新しい考えを呼び起こす必要性を認識していたのである。医学界の失敗を認識したバイラール博士は、がんとの闘いを前進させるための第一歩を勇敢にも踏み出したのである。
図12: 癌による死亡数、1900-2000年。
【原図参照】
しかし、残念なことに、他のがん専門医は、まだ問題を認める準備ができていなかった。バイラール博士の論文は、よく言えば、「erroneous」、悪く言えば、「reprehensible」と呼ばれ、大きな批判を浴びた。学問の世界では、この言葉は最高の冒涜に等しいものだったのだ。彼の動機と知性は、日常的に疑われていた。
NCI所長であったヴィンセント・デヴィータ・ジュニアは、バイラール博士の論説を無責任で誤解を招くとし、バイラール博士自身が「現実から逸脱している」とほのめかした5。また米国臨床腫瘍学会の会長はバイラール博士を「現代の偉大な否定者」と呼んだ。誹謗中傷ストームであったが、統計は否定できない。がんは悪化しているのに、誰もそれを認めようとしない。研究者たちは、このメッセージに対して、メッセンジャーを殺すことで対抗した。死体が山積みになっても、「すべてが素晴らしい」と彼らは言った。
11年後、バイラー博士が「Cancer Undefeated(がんは敗北しない)」と題した続報を発表したときにも、ほとんど変化はなかった。6 1982年から1994年にかけて、がんによる死亡率はさらに2.7%増加していた。がんとの戦いは、敗戦どころか、大虐殺をもたらしたのである。しかし、がんの世界では、問題があることを認めることができなかった。確かに、注目すべき成功例もあった。小児のがん死亡率は、1970年代から約50%減少していた。しかし、がんは老化の代表的な病気であり、これは小さな小競り合いでの大きな勝利であった。1993年のがんによる死亡者数529,904人のうち、小児はわずか1,699人(3%)である。がんは私たちの顔面に強烈なアッパーカットを食らわせ、私たちはその派手な髪型をとかしただけだったのである。
1980年代から90年代にかけて行われた遺伝学の研究によって、がんとの戦いは再び活性化された。がんは遺伝子の病気である。がんの遺伝的弱点を見つけることに力を注ぎ、がんとの戦いに新たな戦線が開かれたのである。数百万ドル規模の大規模な国際共同研究により 2003年にヒトゲノム解析プロジェクトが完了した。研究者たちは、この遺伝子地図が、がんに対する勝利のバトルプランになると確信した。しかし、意外なことに、このプロジェクトは、がんを克服することにほとんど貢献しなかった。2005年、さらに野心的なプログラム、キャンサーゲノムアトラス(TCGA)が開始された。何百ものヒトゲノムをマッピングして、がんの弱点を明らかにしようとしたのである。しかし、このような大規模な研究が行われる一方で、がんは水面下で平穏に進行していった。
私たちは、人間の知恵と巨額の研究費、そして資金を投入して、がんの不屈の殻を破る新兵器を作り上げた。私たちは、がんとの戦いはハイテクを駆使したスマートな武器による戦いになると信じていた。しかし、それは第一次世界大戦の塹壕戦のようなもので、前線は動かず、戦争は長引き、目立った進展はなく、死体は山積みになった。
がん治療の停滞は、他の医学分野でのめまぐるしい進歩とは対照的である。1969年から2014年にかけて、米国では人口が増加しているにもかかわらず、心臓病による総死亡者数は約17%減少した。しかし、がんはどうだろう。同じ期間に、がんによる死亡者数は84%も増加したのである(図13参照)。
図13
【原図参照】
2009年、ニューヨーク・タイムズ紙は、このような現実を反映した見出しを掲げた: 「1950年から2005年にかけて、がんの死亡率はわずか5%しか減少していない。一方、心臓病の死亡率は64%減少し、インフルエンザや肺炎は58%減少している。DNAの二重らせんを発見したノーベル賞受賞者のジェームズ・ワトソンは 2009年にニューヨーク・タイムズ紙に寄稿した意見書の中で 2006年にがんによって死亡したアメリカ人は56万人で、「戦争」が始まる前年の1970年より20万人多く死亡したと悔しがっている8。
がんとの戦いは、資金不足で停滞しているわけではない。国立がん研究所の2019年の予算は57億4000万ドルで、すべて税金から捻出されたものだ10 非営利団体は、雨後のキノコのように増殖している。あるカウントでは、がん専門のNPOは、心臓病、エイズ、アルツハイマー病、脳卒中を合わせた数よりも多い。アメリカ癌協会では、「大義」のために年間8億ドル以上の寄付を集めている。
しかし、ニュースで耳にするがんのブレイクスルー治療法はどうなのだろう?その資金が命を救っているのでは?確かに、治療法は進歩しているし、これらの治療法は確かに変化をもたらしている。しかし、あなたが思っているほど多くの命を救っているわけではない。
抗がん剤は、毒性が少なく有効性が認められれば、FDA(米国食品医薬品局)から承認される。しかし、有効性にはさまざまな定義があり、そのすべてに命を救うことが含まれているわけではない。残念ながら、1990年から2002年にかけて11、FDAが承認した抗がん剤のうち、68パーセントが、必ずしも生命予後の改善を示さないものだった。もしこれらの薬が生存率を向上させなかったとしたら、何の役に立つのだろうか。最も一般的な承認理由は「部分腫瘍反応率」と呼ばれるもので、薬が原発腫瘍の体積を50%以上縮小させたことを意味する。しかし、この数値が生存率にほとんど関係ないことを考えると、かなり良いように思える。
がんが致命的なのは、がんが広がる性質、つまり転移する性質があるからだ。がんが致命的なのは、動くからであって、大きいからではない。転移しないがんは、重大な病気を引き起こすことがほとんどないため、「良性」と呼ばれる。一方、転移するがんは、殺傷能力が高いため、「悪性」と呼ばれる。
例えば、50歳代の約2%がかかるといわれる脂肪腫は、脂肪細胞の良性がんである。脂肪腫は大きくなると、体重が50キロになることもある。しかし、これほど大きくなっても、この良性がんが生命を脅かすことはない。しかし、皮膚がんの一種である悪性黒色腫は、わずか1.5kgの重さにもかかわらず、転移する性質があるため、何千倍もの命にかかわる。多くのがんは、一度鎖を外すと止められなくなる。
そのため、手術や放射線などの局所的ながん治療は、がんが転移してしまうと、その効果は限定的である。外科医は、がんを「全部取る」ために、あらゆる手段を駆使する。がん患者の正常な組織を大量に切り取って、少しでもがん細胞の匂いを消そうとする。がんの手術は転移を防ぐために行うのであって、がんが大きくなりすぎたから行うのではない。抗がん剤が腫瘍を縮小させるかどうかは、患者の生存率には関係ない。腫瘍の半分を破壊する薬は、手術で半分のがんを取り除くのと同じで、つまりほとんど役に立たない。癌の半分を取ることは、癌を全く取らないことに勝るとも劣らないのだ。
しかし、新薬の大半は、この「有効性」という疑わしい指標のみに基づいて承認されている。1990年から2002年までの間に、45の新薬に対して71の新薬承認がなされた。その中で、命を救うことが証明されたのはわずか12品目で、ほとんどが数週間から数カ月しか命を延ばせなかった。同じ時期に、691本の論文に「ガン・ブレイクスルー」という言葉が登場した。奇妙な計算ではこうなる: 691のブレークスルー=71の抗がん剤承認=45の新薬=12は、患者の生命をほとんど延長しなかった。
がんとの戦いにおけるこれらのピカピカの新兵器はすべて、壊れた剣に宝石をちりばめたようなものであった。2000年代半ばには、がんとの闘いに対する希望は急速に失われつつあった。ところが、不思議なことが起きた。私たちは勝ち始めたのである。
新たな夜明け
悲喜こもごもの中、希望の兆しが見えていた。年齢と人口増加率で調整したがん死亡者数は、1990年代前半をピークに、現在は着実に減少している。何が変わったのだろうか?1960年代から一貫して公衆衛生当局が推進してきた禁煙の取り組みが功を奏した面もあるだろう。しかし、がんを理解するためのパラダイムが徐々に変化し、それが新しい治療法につながり、最近の、そしてこれからも続くであろう進歩の原動力となっている。
がん研究において最も差し迫った問題は、「がんとは何か」という最も捉えどころのないものである。この数十年にわたる戦争で、私たちは古代の敵を知らなかっただけなのである。マンハッタン計画では、原子の分裂という明確な目標があった。第二次世界大戦では、アドルフ・ヒトラーという明確な敵がいた。アポロ計画には、月に人を送り、運が良ければ生きて帰ってくるという具体的な任務があった。しかし、ガンとは何だったのか。それは、何百種類ものバリエーションを持つ、漠然とした敵であった。貧困、麻薬、テロとの戦いのように、曖昧な思想に基づく戦争は、一般的に挫折に終わる。
問題を解決するために、間違った角度からアプローチしても、解決する見込みはない。正しい方向を向いていなければ、いくら速く走っても目的地にたどり着くことはできない。本書は、がんという物語を探求するものである。がんの治療法を提示するためのものではない。今のところ、それはまだほとんど不可能である。その代わり、私の目的は、人間の病気という最大の謎を理解するための驚くべき旅を記録することである。それはおそらく、科学界で最も奇妙で最も興味深い物語である。がんとは何なのか?どのようにして発生したのか?
過去100年の間に、がんに対する私たちの理解は、3つの大きなパラダイムシフトを経た。まず、私たちはがんを過剰な成長の病気だと考えていた。確かにその通りなのだが、これではがんが増殖する理由を説明できなかった。次に、私たちは、がんは過剰な成長を引き起こす遺伝子の突然変異の蓄積による病気であると考えた。これも確かにそうなのだが、なぜ遺伝子の変異が蓄積していくのかが説明できなかった。最近になって、がんに対するまったく新しい理解が生まれた。
がんは、ありえないことに、私たちがこれまで直面したことのない病気なのである。感染症でもない。自己免疫疾患でもない。血管の病気でもない。毒素の病気でもない。がんは、もともと私たち自身の細胞に由来するものでありながら、外来種に発展していくのである。このような理解のパラダイムから、新薬が開発され、初めてこの塹壕戦に終止符を打つことができるようになったのである。
第2章 癌の歴史
癌は、古代エジプト人の時代から認識されていた先史時代の病気である。1930年に翻訳されたエドウィン・スミス・パピルスには、紀元前2625年頃に生きたエジプトの医師イムホテプの医学的教えが記されている。そこには、冷たくて硬い「乳房の膨隆した塊」の症例が記されている。
感染症や膿瘍は通常、炎症を起こしており、触ると温かく痛みを感じる。それに対して、この腫瘤は硬く、冷たく、痛みもなく、もっと悪いものであることがわかる。治療法については、著者は何も考えていない。紀元前440年頃に書かれたギリシャの歴史家ヘロドトスの記述によると、ペルシャの女王アトッサは炎症性乳がんを患っていたようだ。ペルーの千年前の墓地では、ミイラ化した遺体に骨腫瘍が見られ、乾燥した砂漠の気候によって保存されていた。考古学者ルイス・リーキーが発掘した200万年前の人間の顎骨には、血液の異常ながんであるリンパ腫の痕跡があった1。
癌は、少なくとも人類が誕生して以来、常に存在する敵としてこの地球を歩いてきたのである。その寿命の長さは、病気の中でも独特なものである。病気は、生まれては消えていく。天然痘や黒死病は、かつて世界を荒廃させたが、現代の健康問題からはほとんど姿を消した。しかし、がんはどうだろう。がんは初めから存在した。中世にもあった。そして、今もなお、かつてないほど悪化している。
数千年にわたる医学の進歩にもかかわらず、がんは私たちをむしばんでいる。古代にがんが少なかったのは、がんが老化の病気であり、平均寿命が短かったからだろう。飢饉や疫病、戦争で人々が若くして死んでいくのであれば、がんは大した問題ではない。
近代医学の父と呼ばれるギリシャの医師ヒポクラテス(紀元前460年頃~紀元前370年頃)は、古代の敵を「蟹」を意味するカルキノスという言葉で適切に名付けたのだろう。これは、がんというものを驚くほど鋭く、正確に表現している。顕微鏡で見ると、がんは本体から何本もの棘(トゲのようなもの)を出して、隣接する組織を粘り強く掴んでいる。がんは、その名の通り、体内をあちこちに移動することで、他の致命的な病気と区別している。太ももの切り傷が頭の切り傷に転移することはないが、肺のがんが肝臓のがんになることは簡単にある。
紀元2世紀、ギリシャの医師ガレンは、がんが硬い結節として発見されることが多いことから、「腫れ」を意味するオンコスという言葉を用いて、がんを表現した。この語源から、oncology(がんの科学)、oncologist(がんの専門家)、oncologic(がんに関連する)という言葉が派生している。ガレンはまた、癌を表す接尾辞として-omaを用いた。したがって、hepatomaは肝臓のがんである。肉腫は軟部組織のがんである。メラノーマは、メラニンを含む皮膚細胞のがんである。医学書『De Medicina』を著したローマの百科全書学者ケルスス(紀元前25年頃~紀元50年頃)は、ギリシャ語のkarkinosを英語のcancerに翻訳した。腫瘍という言葉は、異常な細胞が局所的に増殖したものを表すのに使われ、良性も悪性もある。
がんは、最初、組織の過度な成長、無秩序な成長、制御不能な成長と理解された。正常な組織には、明確な成長パターンがある。例えば、正常な腎臓は、生まれてから大人になるまで成長し、その後停止する。その後、他の病気が介在しない限り、その大きさを維持するのみである。正常な腎臓は、腹腔全体を占めるほど大きくなるまで、生涯にわたって成長を続けることはない。しかし、がん細胞は死ぬまで、あるいはあなたが死ぬまで成長し続ける。
がんは通常、良性がんと悪性がんに分けられる。良性のがんは大きくなるが、転移することはない。例えば、脂肪腫や皮膚の基底細胞がんがある。これらが巨大化することもあるが、良性のがんは死に至ることは少ないので、過剰に心配することはない。がんによる死亡の大部分を占めるのは、移動して広がる能力、すなわち転移である。
悪性がんは、私たちが通常がんとして考えているもので、本書では悪性がんだけを考えている。多くの種類のがん(乳がん、大腸がん、前立腺がん、肺がん、骨髄腫など)は、一般にその発生細胞から名前がつけられている。体内の細胞の種類と同じ数だけ、がんの種類もあると思われる。これらのがんは、無制限に増殖し続けるものと、発生した部位から離れ、離れた部位に再増殖するものがある。
すべてのがんは、正常な細胞から発生する。乳がんは、正常な乳房の細胞から発生する。前立腺がんは、正常な前立腺細胞から発生する。皮膚がんは、正常な皮膚細胞から発生する。これが、がんの厄介なところであり、異常なところである。がんは外敵ではない。がんは外敵ではなく、内部からの反乱なのである。がんとの闘いは、自分自身との闘いでもある。
がんの種類はそれぞれ違うが、本書では、がんの違いではなく、共通点に着目して、がんの成り立ちを全体として論じようとした。これが本書の根本的な問いである: ある人がある状況で正常な細胞をがん細胞に変え、ある人がそうでないのはなぜか。言い換えれば、何が癌を引き起こすのか?
古代ギリシャでは、すべての病気は血液、痰、黄胆汁、黒胆汁の4つの体液のバランスが崩れることによって起こるとする体液性疾病説が信じられていた。炎症は血の過剰、膿疱は痰の過剰、黄疸は黄胆の過剰が原因である。癌は黒胆の内的過剰と考えられていた。黒胆の局所的な蓄積は、腫瘍として現れ、結節として触知することができた。しかし、この病気は全身に及ぶ全身性の過剰症である。
そこで、がんの治療は、この過剰な黒胆汁を取り除くことを目的とし、古くからある瀉血、瀉下、下剤などを用いた。癌は全身病だろうから、腫瘍を局所的に切除することはできない。これは、古代の医師たちの驚くべき洞察であり、多くのがん患者を手術から救うことになった。殺菌剤、麻酔薬、鎮痛剤がない時代には、がんで死ぬより手術で死ぬほうが多かったのである。
体液性癌説は何世紀にもわたって存続したが、大きな問題があった。4つの体液のうち、血液、リンパ液、黄胆汁の3つは確認できたが、黒胆汁はどこにあったのか?しかし、黒胆汁はどこにあるのだろうか。医師たちは、何度も何度も探したが、黒胆汁は見つからなかった。黒胆汁が局所的に出てきたと思われる腫瘍を調べても、何も出てこない。もし黒胆汁が癌の原因なら、それはどこにあるのだろう?
1700年代になると、体液説に代わってリンパ説が登場した。がんは、リンパがうまく循環せずに滞留し、発酵・変性することで発生すると考えられていた。しかし、この理論には、がんの性質について驚くほど鋭い見解が含まれていた。まず、がん細胞は体内の正常な細胞が変質したものであることを認めた。そして、がんがリンパ液の流れやリンパ節を伝って広がっていく性質があること。
顕微鏡と、組織サンプルを染色するための信頼性の高い染料が開発されたことで、科学はまた大きく飛躍することになった。1838年には、体液ではなく細胞に焦点を当てたブラステマ理論が確立された。ドイツの病理学者ヨハネス・ミュラーは、がんはリンパ液が原因ではなく、細胞から発生することを示した。彼は、がんは細胞と細胞の間にある出芽要素、すなわち「ブラステマ」に由来すると考えた。同じ年、病理学者のロバート・カースウェルは、広範囲に広がるいくつかのがんを調査し、がんが血流に乗って移動する可能性を初めて示唆した。
がんは単なる細胞であり、奇妙な形の細胞ではあるが、その増殖は制御不能であった。これが、私が「がんパラダイム1.0」と呼ぶ、がんを理解するための最初の偉大な近代的パラダイムである。過剰な増殖の病気である。問題が過剰な成長であるならば、それを殺すことが明白な解決策となる。この論理は、手術、放射線、化学療法を生み出し、現在でも多くのがん治療プロトコルの基礎となっている。
外科手術
アレキサンドリアのレオニダスが、乳がんの手術について、がん組織をすべて取り除き、健康な組織を残すという、論理的で段階的な手術を説明したのが、がんの外科的治療の始まりである。しかし、出血を防ぐための焼灼術があったとはいえ、手術は危険と隣り合わせだった。手術器具は滅菌されていない。手術器具は滅菌されておらず、術後に感染症にかかったとしても、抗生物質はない。私たちのほとんどは、このような古代の外科医に、身体はおろか、髪も切らせないだろう。1653年に発明された特に不気味なものは、患部の乳房を切断するための乳房ギロチンである。
近代的な麻酔と消毒の出現により、手術は野蛮で儀式的な犠牲から、かなり合理的な医療行為へと変化した。古代ギリシャでは、がんは全身疾患として扱われていたが、19世紀の医師たちは、がんを手術に適した局所疾患として捉えるようになった。つまり、がんは手術が可能な局所的な病気であると考えたのである。手術の技術や知識が進歩するにつれて、ほとんどすべての症例で局所腫瘍切除術が選択できるようになった。しかし、その手術が有効かどうかは別問題である。
がんは必ず再発し、たいていは切開した場所にできる。がんはカニと同じで、目に見えない微細なペンチを隣接する組織に送り出す。この微小な癌の残骸が、どうしても再発につながる。そこで医師たちは、「少しの手術がいいなら、たくさんの手術はもっといいのではないか」という新説を唱え始めた。
1900年代初頭、ウィリアム・ハルステッド博士は、乳がんを「根こそぎ」除去するために、どんどん過激な手術を行っていった」ラディカルという言葉は、「根治的乳房切除術」や「根治的前立腺切除術」のように、ラテン語で「根」を意味する言葉に由来する。ハルステッドは、患部の乳房に加え、胸壁、大胸筋、リンパ節など、がんの芽があるかもしれない正常組織を広範囲に切除した。合併症は恐ろしいが、それに見合うだけの価値があると考えた。根治的乳房切除術は、体型が崩れて痛みを伴うかもしれないが、がんが再発すれば死に至る可能性もある。侵襲の少ない手術は、誤った優しさだとハルストは考えていた。この手術は、その後50年間、乳がんの標準的な外科治療となり、乳房ギロチンがそれに比べてほとんど人道的に見えるようになった。
ハルステッドの結果は、非常に良くも悪くもあった。局所のがんは極めて良好であった。一方、転移したがんは、極めて悪い結果となった。がんが転移した後では、手術の程度はほとんど関係なかったのである。1948年には、より低侵襲な手術で、ハルステッドの方法と同様の局所的な病勢コントロールが可能であり、手術による合併症はほんのわずかであることが、研究者によって示された。
1970年代には、術前のX線検査やCT検査によって転移を早期に発見できるようになり、不必要な手術を防ぐことができるようになった。また、腫瘍の位置を把握することで、メスを入れる前に、どの程度まで手術が必要かを正確に判断できるようになった。現在では、がんが早期に発見されれば、このような標的を絞った手術で治癒する可能性があることが分かっている。また、技術の進歩により、手術の合併症は確実に減少し、手術による死亡者数は1970年代から90%以上減少している2。手術はがんに対する重要な武器であることに変わりはないが、適切な時期に、適切な状況においてのみ行われるものである。
放射線
1895年、ドイツの物理学者レントゲンは、高エネルギーの電磁波であるX線を発見し、この発見により1901年にノーベル賞を受賞した。この目に見えないX線は、生体組織を損傷し、死に至らしめる可能性があった。そのわずか1年後、アメリカの医学生エミール・グラッブが、進行した乳がんの患者にX線を照射し、放射線腫瘍学の先駆者となった3。真空管メーカーでもあったグラッブは、自分の手をこの新しいX線技術にさらして炎症性発疹を起こし、上級医に見せた。組織の損傷に気づいた医師は、この新しいX線が他の治療にも使えるのではないかと提案し、全身性エリテマトーデスや癌がその候補に挙がってきた。幸運なことに、グラッブはその時、全身性エリテマトーデスと乳癌の両方を患う患者の世話をしていた。1896年1月29日、彼は乳がんを1時間、X線源に曝した。1時間!現代のX線治療では数秒で終わる。自分の手が傷ついたことを思い出し、グラッブは乳がんの周囲を近くの中国茶箪笥にあった鉛のシートで保護する配慮をした。もし、彼がお茶を飲む習慣がなかったら……と思うと、ゾッとする。
一方、同じ年、フランスでは、物理学者アンリ・ベクレルと伝説の科学者マリー・キュリー、ピエール・コーリーが放射線の自然放出を発見し、この3人はノーベル賞を受賞することになる。1901年、ベクレルが純ラジウムの管をウエストコートのポケットに入れていたとき、管の下の皮膚にひどい火傷があることに気づいた。パリのサンルイ病院の研究者たちは、彼のラジウムを使って、より強力で精密なX線治療を開発した。1913年には、放射線の質と量をコントロールする「熱陰極管」が登場し、病変が疑われる部位に無造作にX線を照射するのではなく、初めて線量測定が可能になった。
1900年から1920年までの放射線腫瘍学の初期は、効率的なドイツ人によって支配され、数回の大量の苛烈な放射線による治療が支持された。その結果、見事な寛解と副作用が見られたが、永続的な治癒はほとんど見られなかった。1927年、フランスの科学者たちは、1回の大量の放射線が皮膚に害を与え、その下にある癌にはあまり影響を与えないことに気づいた。その代わり、少量の放射線を何日もかけて照射すれば(分画放射線治療と呼ばれる)、表面の副次的な損傷をそれほど受けずに、埋もれているターゲットに当てることができる。これは、がん細胞が周囲の正常な組織よりもX線による損傷を受けやすいためだ。
この感受性の違いを利用して、がん細胞を優先的に殺し、正常な細胞は傷つけずに回復させるというのが、分画放射線治療である。これは、現在でも放射線治療の主流となっている方法である。1970年代には、ニクソン大統領の「がんとの戦い」によって、このハイテク治療法の開発に必要な資金が提供された。
しかし、手術と放射線治療の最大の問題点は、いずれも局所療法であることである。がんが局所にとどまっていれば、これらの治療法は有効だが、がんが転移した場合は、これらの局所的な治療法では回復の見込みはほとんどない。そこで、化学物質(薬物)を使った全身治療法の開発が並行して進められた。
化学療法
広範囲に及ぶ癌の論理的な解決策は、全身的で選択的な毒素である「化学療法」を投与することで、癌細胞が潜む場所を破壊し、正常細胞は比較的無傷のまま残すことであった。1935年、後に国立がん研究所に統合されるがん調査室は、3,000種類以上の化合物を用いたがん治療薬のスクリーニングを計画的に行った。しかし、臨床試験にこぎつけたのはわずか2種類で、いずれも毒性が強すぎて失敗した。選択性の高い毒素を見つけるのは簡単なことではなかった。
1917年、ドイツで初めて使用された窒素マスタードガスは、かすかにコショウのような臭いがすることから名付けられた。1918年にノーベル賞を受賞した天才化学者フリッツ・ハーバーが開発したこの猛毒ガスは、皮膚から吸収され、水ぶくれを作り、肺を焼く。被害者はゆっくりと死んでいき、致命的な旅を終えるのに6週間もかかる。
興味深いことに、マスタードガスは、骨髄と白血球の特定の部分のみを破壊するという特異な性質を持っている5。つまり、選択性のある毒である。1929年、タールの発がん性を研究していたイスラエルの研究者アイザック・ベレンブラムは、マスタードガスに刺激性を加えてがんを誘発しようとしたが、逆説的にがんは退縮した6。
エール大学の2人の医師は、非ホジキンリンパ腫と呼ばれる癌の異常な白血球を殺すために、この選択的毒物を治療的に使うことができるのではないかと考えた。この48歳の男性は、放射線抵抗性の進行したリンパ腫で、顎と胸に腫瘍があり、飲み込むことも腕を組むこともできないほどだった。他の選択肢はなく、彼は秘密の実験的治療に同意した。
1942年8月、J.D.は、当時「サブスタンスX」としか呼ばれていなかったマスタードガスを初めて投与された。7 4日目に、彼は改善の兆しを見せ始めた。しかし、1カ月後、リンパ腫が再発し、1942年12月1日のJ.D.のカルテには、1つの記述があった: 「死亡」である。それでも、このコンセプトが有効であることを証明する、素晴らしいスタートであった。化学療法という治療法が誕生したばかりであったが、戦争の制限により、その結果が発表されたのは1946年であった。クロラムブシルやシクロホスファミドといったマスタードガスの誘導体は、現在でも化学療法薬として使用されている。
もう一つの化学療法は、葉酸の代謝を利用したものである。葉酸は必須ビタミンB群の一つで、新しい細胞の生成に必要である。体内で不足すると新しい細胞が作れなくなり、がんのように増殖の早い細胞に影響を与える。1948年、ハーバード大学医学部の病理学者シドニー・ファーバーは、ある種の小児白血病の治療に葉酸遮断薬を使用する先駆者となった9。しかし、がんは必ず再発する。
化学療法の開発はさらに進んだ。1950年代には、いくつかの希少ながんに対して、注目すべき成功があった。国立がん研究所の研究者であったミン・チウ・リー博士は、1958年、化学療法のレジメンによって胎盤の腫瘍である絨毛がんが数例治癒したと報告した10。彼は、ニューヨークのメモリアル・スローン・ケタリング病院に戻り、化学療法に関する彼の洞察は、後に絨毛がんや転移性精巣がんで証明されることになる。
複数の種類の化学療法剤が開発されたことで、選択肢が増えた。一種類の毒で十分でないなら、複数の毒を組み合わせて、どんながん細胞も耐えられないような化学カクテルを作ったらどうだろう。1960年代半ばには、エミール・フライリッヒとエミール・フライの両博士が、4種類の薬剤を組み合わせて白血病の子どもたちに投与し、最終的に寛解率を当時としては破格の60%にまで高めた11。また、進行ホジキン病の寛解率はほぼゼロからほぼ80%に急上昇した12。事態は好転していた。化学療法は、「毒物」から「薬物治療」へと飛躍的に進歩したのである。
化学療法薬の多くは選択的毒物で、増殖の早い細胞を優先的に殺す。がん細胞は成長が早いので、化学療法に特に弱いのである。運が良ければ、患者を殺す前に癌を殺すことができる。毛根や胃腸の粘膜など、成長の早い正常な細胞も巻き添えを食って、よく知られた副作用であるハゲや吐き気・嘔吐につながった。新しい薬、例えば標的抗体の多くは、古典的な薬に関連する否定的な意味合いを持つため、「化学療法」と呼ばれることはあまりない。
がんのパラダイム1.0
癌の最初の大きなパラダイム、私が癌のパラダイム1.0と呼ぶものは、癌を細胞の無秩序な増殖とみなしている。もし問題が成長しすぎることであれば、解決策は殺すことである。殺すためには、切る(手術)、焼く(放射線)、毒を盛る(化学療法)など、細胞の大量破壊兵器が必要である。局所がんであれば、局所的に破壊する方法(手術や放射線)を使えばいい。転移したがんに対しては、全身的な毒物(化学療法)が必要である。
がんパラダイム1.0は、医学的には大きな進歩だったが、最も根本的な問題には答えていなかった: この無秩序な細胞増殖の原因は何なのか?癌の根本原因は何だったのか?このことを理解するためには、「がんとは何か」を知る必要がある。
第3章 癌とは何か?
伝説的な生物学者チャールズ・ダーウィンは、「ランパー・スプリッター問題」と呼ばれる問題を論じた最初の科学者として知られている1。19世紀初頭、分類は自然科学研究の基本的な部分であった。生物学者は、新しい動物や植物の標本を求めて地球を一周していた。生物学者は、新しい動物や植物の標本を求めて地球を一周し、注意深く観察した後、これらの標本を種、科、門、王国といった科学的カテゴリーに分類した。
このカテゴリーを作る際に、対立したのが「括る派」と「分ける派」である。ある動物を一つのカテゴリーにまとめるべきか、それとも別々のカテゴリーに分けるべきか。例えば、ヒト、クマ、クジラは哺乳類としてひとくくりにできるが、陸上で生活するか水中で生活するかで分けることも可能である。ひとくくりにすると分類の数が減り、分割すると増える。どちらも異なるが重要な情報である。分割が個体差を強調するのに対し、一括は類似性を強調する。
がんという言葉は、単一の病気を指すのではなく、特定の性質によって関連する多くの異なる病気の集合体を示している。定義にもよるが、少なくとも100種類以上のがんが存在すると言われている。伝統的に、がん生物学者は、がんをその起源となる細胞に基づいて別個の病気とみなす、スプリッターであった。がん細胞は正常なヒトの細胞から派生したものであるため、元の細胞の特徴を多く残している。例えば、乳がん細胞は健康な乳房細胞と同じように、エストロゲンやプロゲステロンなどのホルモン受容体を持つことがある。前立腺がん細胞は、健康な前立腺細胞と同じように前立腺特異抗原(PSA)を産生し、血液で測定することができる。
人体のほぼすべての種類の細胞が、癌化する可能性がある。固形臓器や組織のがんがあり、肺がん、乳がん、大腸がん、前立腺がん、皮膚がんなどが代表的である。また、血液のがんもあり、単一の大きな腫瘍(がん細胞の塊)を示さないことから、「液状」がんと呼ばれることもある。これには、白血病、骨髄腫、リンパ腫などの病気がある。白血病、骨髄腫、リンパ腫などの病気があり、細胞の種類によってがんの種類も異なり、自然経過や予後も異なる。乳がんと急性白血病とでは、挙動も治療法も全く異なる。そのため、がんを個々の病気に分けて考えることは治療に役立つが、そうすることで、共通点ではなく、相違点を強調することができる。さまざまな種類のがんの特徴に注目すると、がんという単一の存在の謎の解明に近づけないのである。
著名ながん研究者であるダグ・ハナハンとロバート・ワインバーグは、がんはある種の性質によって統合された異なる疾患の集合体であることを認識していた。しかし、その性質とは何なのだろうか。がんに関する膨大な文献の中で、がんがどのように似ているかを説明するために、少数の原則を分類することはまだ誰もしていなかった。2000年、著者たちは、悪性化に関する原則を体系化することを決意し、『Cell』誌に「The Hallmarks of Cancer」と題する重要な論文を発表した2。著者たちは、自分たちの研究はすぐに無名になると考えていたため、ほとんど期待しなかった。
しかし、この論文は、がん研究の歴史において最も影響力のある論文となった。それは、がんを多くの特殊な病気としてではなく、一つの病気として理解するための基礎を築いたことである。ハナハンとワインバーグは、分裂の海の中で一括りにされる存在になったのである。彼らは、「何ががんを……がんたらしめるのか」という重要な問いを投げかけた。がんをがんたらしめるものは何か?
癌の特徴
2000年にHanahanとWeinbergが行った最初のレビューでは、ほとんどのがんに共通する6つの特徴的な点が挙げられた。2011年には、さらに2つの特徴が特定され、追加された。3 何百種類ものがんがあるにもかかわらず、すべてのがんはこれら8つの共通点のほとんどを共有しており、これらはすべてがん細胞の生存に不可欠な特徴である。この8つの特徴のほとんどがなければ、がんはもはやがんではない。
がんの8つの特徴
- 1. 増殖シグナルを持続させる;
- 2. 成長抑制因子を回避する;
- 3. 細胞死に抵抗する;
- 4. 複製可能な不老不死を可能にする;
- 5. 血管新生を誘導する;
- 6. 浸潤と転移を活性化する;
- 7. 細胞エネルギーの調節、および
- 8. 免疫破壊を回避する。
特徴1:増殖シグナルを持続させる
最初の特徴は、間違いなく最も基本的なことだが、がん細胞が複製と成長を続けるのに対し、正常細胞はそうではないということである。人体には何兆個もの細胞が存在するため、その成長は厳密に制御され、調整されなければならない。幼少期から青年期にかけては、新しい細胞の誕生が古い細胞の死を上回るため、子どもは大きくなる。大人になると、新しい細胞の数が古い細胞の死と正確に一致するようになり、全体の成長が止まる。
この微妙なバランスが崩れたのが、がんであり、がん細胞は増え続け、腫瘍と呼ばれる異常な集合体になってしまう。正常な細胞の成長は、遺伝子によって制御されたホルモンの経路によって厳密に制御されている。遺伝子には、がん原遺伝子と呼ばれる成長を促進する遺伝子と、がん抑制遺伝子と呼ばれる成長を低下させる遺伝子がある。この2種類の遺伝子は、車のアクセルとブレーキのような役割をしている。プロトオンコジーンは、成長を加速させる。腫瘍抑制遺伝子は、成長を減速させる。通常、これらの遺伝子は互いにバランスを取りながら機能している。
がん原遺伝子が過剰に活性化され(アクセルを踏むようなもの)、がん抑制遺伝子が抑制され(ブレーキペダルから足を離すようなもの)、異常な成長が起こることがある。創傷治癒のような特定の正常な状況では、成長経路は短期間活性化される。傷が治れば、増殖は再び鈍化して中立になるはずだ。しかし、がん細胞はこの増殖シグナルを維持し、もはや有利でなくなっても成長を続ける。遺伝子変異によってがん原遺伝子が過剰に活性化されると、がん遺伝子と呼ばれるようになる。最初に確認されたがん遺伝子は、肉腫と呼ばれる軟部組織のがんを引き起こすことからsrcと呼ばれ、1970年代に発見された。
がんは、SF映画「ブロブ」の主人公のように、成長した細胞が巨大な塊となって、あらゆるものを吸収していくだけの存在ではない。がん細胞は、大きな腫瘍に成長するまでに多くの困難に直面し、さらに転移する際にはさらに多くの困難に直面する。転移するためには、がんが増殖し、新しい血管を増やし、そして分裂する必要がある。一つの遺伝子変異がこれら全てを行うことは通常不可能であり、それゆえ他の特徴が必要となる。
特徴2:成長抑制因子の回避
私たちの体の中には、細胞の増殖を積極的に抑制する正常な遺伝子が多く存在する。最初の癌抑制遺伝子(Rb)は、小児の稀な眼球がんである網膜芽細胞腫で発見された。Rb遺伝子を不活性化する遺伝子変異は、細胞増殖のブレーキを解除し、成長を有利にするため、がんの発生を促進する。
がんにおいて最もよく影響を受ける遺伝子のいくつかは、p53を含む腫瘍抑制遺伝子であり、ヒトのがんの最大50%で変異していると推定される。乳がん1型、2型と呼ばれる有名な癌抑制遺伝子は、通常BRCA1、BRCA2と略され、乳がん全体の5パーセントに関与していると推定されている。
特徴3:細胞死に抵抗する
組織全体の成長とは、単純に、どれだけの細胞が作られ、どれだけの細胞が死ぬかの差である。正常な細胞が古くなったり、修復不可能な損傷を受けたりすると、アポトーシスとして知られるプロセスでプログラムされた細胞死を起こす。この正常な細胞の賞味期限は、細胞の自然なターンオーバーを可能にすることで、私たちの体をスムーズに動かしている。例えば、赤血球は平均3カ月間しか生きられないが、その後、新しい赤血球と入れ替わるために死ぬ。肌の細胞は数日おきに入れ替わる。車のエンジンのオイル交換のようなものである。新しいオイルを入れる前に、まず古いオイルを抜かなければならない。体内では、古くなったり傷ついたりした細胞を淘汰して、新しい細胞が入れ替わるスペースを確保する必要がある。アポトーシスとは、細胞が耐用年数を超えたときに、秩序正しく廃棄されることである。
細胞の死には、壊死とアポトーシスがある。壊死は、意図的でない、制御不能な細胞死である。誤ってハンマーで指を打った場合、細胞は無造作に無秩序に殺される。卵が歩道にぶつかったときのように、細胞の中身が飛び散る。これは大混乱で、体が懸命に掃除しなければならない重大な炎症を引き起こす。ネクロシスは、可能な限り避けるべき有毒なプロセスである。
アポトーシスは、エネルギーを必要とする活動的なプロセスである。アポトーシスとネクローシスの違いは、計画的に素敵なディナーパーティーを開くか、パートナーが20人の騒がしい同僚を予告なしに家に連れてくるかの違いに似ている。どちらも大規模な夕食会だが、一方は注意深くコントロールされた楽しいものであり、もう一方は多くの混乱と怒号が飛び交い、最終的に誰かがソファで寝てしまうのである。
アポトーシスとは、細胞の削除を制御するメカニズムで、すべての多細胞生物に共通するものである。古い細胞(皮膚細胞など)を死なせて新しい細胞に置き換えることで、個々の細胞は死ななければならないが、生物全体としては若返る。過剰な成長を避けるためには、古い細胞を除去する数と、新しい細胞との交換数のバランスを注意深く保つ必要がある。がん細胞はアポトーシスに抵抗するため、細胞分裂と細胞死のバランスが変化し、過剰な成長を許してしまう5。
特徴4:複製可能な不老不死を可能にする
1958年、科学のドグマは、実験室で培養された人間の細胞は、自己を無限に複製できるため不死身であると受け入れていた。栄養液の中にいる菌やバクテリアは、無限に自己複製ができるのだ。しかし、ペンシルベニア大学ウィスター研究所の科学者レナード・ヘイフリックは、何をやっても人間の細胞を一定の寿命以上に生きさせることができなかった。彼は当初、初歩的なミスではないかと心配した。栄養の与え方が悪いのか、老廃物を適切に除去していないのか。しかし、何をやっても細胞を長生きさせることはできなかった。
老化と癌の両方を理解する上で非常に重要なこの発見は、すぐに科学界に受け入れられるものではなく、ヘイフリックによれば「10年か15年の痛みを伴う年月」をかけて、一般的に受け入れられるようになった。ヘイフリックは、「半世紀も前の信念を打ち砕くのは、科学の世界でも容易なことではない」と悔しそうに振り返った7。この細胞の寿命の限界は、現在ではヘイフリック限界と呼ばれている。
細胞は、一般的に40回から70回しか自己複製できないが、その後に停止する。ヘイフリックはこれを、染色体のある核の中で起こる細胞の老化と正しく解釈した。ノーベル賞受賞者のエリザベス・ブラックバーンとキャロル・グライダーは、その後、染色体の末端にあるキャップであるテロメアを用いて、細胞がヘイフリック限界に向かって複製回数を「カウント」していることを実証した。テロメアのキャップは、細胞分裂の際にDNAを保護するもので、1回ごとにテロメアが短くなる。テロメアが短くなりすぎると、細胞は分裂できなくなり、アポトーシス(プログラムされた細胞死)が活性化される。このプロセスは、癌の無秩序な増殖に対する自然な保護となる。細胞の年齢は、年ではなく、細胞の複製回数でカウントされる。
正常な細胞は死を免れないが、がん細胞は不死身である。細菌のようにヘイフリック限界に縛られることなく、無限に複製することができる。がん細胞はテロメラーゼという酵素を産生し、染色体の末端にあるテロメアの長さを増加させる。テロメアキャップは決して摩耗しないので、細胞は好きなだけ分裂を続けることができる。これにより、細胞の自然な老化プロセス(老化)と、時限的な細胞死(アポトーシス)の両方が阻止される。細胞培養では、がん細胞を永遠に増やし続けることができる。
今ではよく知られた話だが、私たちのがんに対する理解は、ヘンリエッタ・ラックスという女性に多大な恩義を感じている。1951年10月4日、ラックスは子宮頸がんのため、ジョンズ・ホプキンス病院で31歳の若さで亡くなった。彼女の同意なしに体内から取り出されたがん細胞は、その後、医学に革命をもたらした。科学者たちは初めて、人体の外で細胞株を無期限に増殖させたのである。ラックスの名を冠したこのHeLa細胞は、ワクチン、遺伝学、医薬品開発、癌の研究に利用されてきた。5,000万トン以上のHeLa細胞が培養され、6万本以上の科学論文に掲載された8。
正常な細胞は、ヘイフリック限界に達した後、それ以上分裂することができない。がん細胞は、デジタルファイルのように増殖する。がん細胞は、デジタルファイルのように複製される。オリジナルに100パーセント忠実に送信または複製することができる。生物から見れば、欠陥のある細胞や古い細胞ラインを殺すことで、物事がスムーズに進むようになる。洋服に穴が開いたら、捨てて新しいものを買う必要がある。その方が、1970年代の古くて色あせた、破れたベルボトムを履き続けるよりずっといい。細胞は寿命が来ると、殺されて入れ替わる。がん細胞はこのアポトーシスのプロセスを回避して、複製可能な不老不死を実現する。
特徴5:血管新生の誘導
血管新生とは、新しい血管を作り、酸素や栄養素を取り入れたり、老廃物を排出したりするプロセスのことである。腫瘍が成長するにつれて、新しい細胞は血管から離れた場所に位置するようになる。これは、郊外の分譲地の新しい家が幹線道路から離れた場所にあるのと同じだ。新しい家には新しい道路が必要であり、新しい癌細胞には新しい血管が必要なのである。
血管新生には、多くの異なる種類の細胞の成長シグナルが緊密に連携することが必要である。例えば乳がんは、既存の血管から遠く離れた場所で新しい乳がん細胞を作り続けることはできない。例えば、乳腺腫瘍は、既存の血管から離れた場所で新しい乳がん細胞を作り続けることはできない。これには、新しい平滑筋細胞、結合組織、内皮細胞(裏打ち)を成長させることが必要で、腫瘍が成長するためには、信じられないほど複雑な作業が必要なのである。
特徴6:浸潤と転移の活性化
がんは、他の組織に侵入して転移する能力が致命的であり、がんによる死亡の90パーセントを占めると言われている。この転移が確立されると、元の腫瘍がどうなるかはほとんど問題にならない。転移しないがんは、治療が簡単で、ほとんど死亡することがないため、良性がんと呼ばれている。良性がんは、これまでに挙げた他の5つの特徴をすべて兼ね備えている。転移する能力がなければ、がんは深刻な健康上の懸念というより、厄介な存在である。
転移は、おそらく最も難しい特徴であり、複数の複雑な介在するステップを完了する必要がある。転移したがん細胞は、通常、接着分子によって強固に結合されている周囲の構造から、まず脱却しなければならない。例えば、乳腺細胞が血液や肺の中に浮遊しているのを見かけることがないのはそのためだ。解放されたがん細胞は、血流の旅を生き延び、転移部位という、自分の家とは全く異なる異質な環境でコロニーを形成しなければならない。転移経路の各段階で、がん細胞はまったく新しいスキルを身につけ、既存の経路を何度も遺伝子変異させる必要があり、非常に複雑である。これは、人間が宇宙服を着ないで火星の表面を歩き、成功することを期待するようなものである。
古典的には、転移は癌の自然史の後半に起こるもので、原発巣が長く成長した後に起こると考えられている。癌が血液中に癌細胞を排出し始めるまでは、癌は比較的局所的で無傷であると長い間考えられていた。しかし、新しい証拠によると、微小な転移は早い時期に元のがんから排出されるかもしれないが、これらの排出された細胞は通常生き残ることはない。
*
エマージング・特徴
2011年、HanahanとWeinbergはそのレビューを更新し、2つの新たな特徴、そして2つの実現可能な特徴、つまりがん細胞がその特徴を獲得することを容易にする特徴を追加した。最初の特徴として、ゲノムの不安定性と突然変異が挙げられる。がんは正常な遺伝子を変異させることでその特徴を獲得するが、不安定な遺伝物質がこれを容易にする。第二の特徴は、腫瘍を促進する炎症である。炎症反応は、組織の損傷や刺激に対する自然な反応である。これは通常、防御反応だが、場合によっては、がんの進行を促進することもある。
*
特徴7:細胞エネルギー制御の調整
細胞は、毎日何百もの家事をこなすために、信頼できるエネルギー源を必要としている。細胞のエネルギーは、アデノシン三リン酸(ATP)と呼ばれる分子に蓄積されている。グルコースをエネルギーとして代謝するには、酸素を使う方法(好気性呼吸)と酸素を使わない方法(嫌気性発酵)の2つがある。酸化的リン酸化(OxPhos)と呼ばれる化学的プロセスは、最も効率的なエネルギー抽出方法である。このプロセスでは、グルコースと酸素を一緒に燃やして36個のATP分子と、老廃物である二酸化炭素を生成し、吐き出す。OxPhosは、細胞の「発電所」と呼ばれるミトコンドリアと呼ばれる部分で発生する。
酸素が利用できない場合、細胞は解糖と呼ばれる化学プロセスを用いてグルコースを燃やすが、その際、乳酸の形をした廃棄物とともに、わずか2つのATP分子しか生成さない。適切な状況であれば、酸素を必要とせず、より効率的にATPを生成できるこの方法は、合理的なトレードオフと言える。例えば、スプリントのような高強度の運動には大量のエネルギーが必要である。血流が不十分で酸素が行き渡らないため、筋肉は嫌気性(酸素を必要としない)解糖を行う。このとき発生する乳酸が、激しい運動でおなじみの筋肉痛の原因である。酸素がない状態でもエネルギーを作り出すが、グルコース1分子あたり36個のATP分子を生成するのではなく、2個のATP分子を生成するのみである。そのため、筋肉が疲れる前に遠くまで疾走することはできず、立ち止まって休まなければならない。血流が十分になって乳酸の蓄積を取り除くと、回復し始める。
ミトコンドリアのOxPhosは、グルコース1分子に対して、解糖に比べ18倍ものエネルギーを生成することができる。この効率の良さから、正常な細胞は十分な酸素があれば、ほとんどOxPhosを使う。しかし、がん細胞は不思議なことにそうではない。これは新しい発見ではなく、歴史上最も偉大な生化学者の一人であるオットー・ウォーバーグが1927年に初めて報告したものである。この代謝の再プログラミングは、癌の約80%で起こり、ワールブルグ効果として知られている。
ワールブルグ効果(好気性解糖)はエネルギー効率が悪いため、がんは代謝を維持するためにはるかに多くのグルコースを必要とする。それを補うために、がん細胞は細胞表面にGLUT1というグルコーストランスポーターを多く発現させる。これにより、がん細胞が血液中のブドウ糖を細胞内に移動させる速度が速くなる。陽電子放射断層撮影法(PET)は、がん細胞のグルコースに対する好意性を利用したものである。放射能で標識されたブドウ糖を体内に注入し、細胞がそれを取り込む時間を設ける。スキャンによって、ブドウ糖をより活発に取り込む部位が明らかになる。この「ホットスポット」が、がんの活動性を示す証拠となる。
これは非常に興味深いパラドックスである。急速に成長するがんは、より多くのエネルギーを必要とするはずなのに、なぜわざわざ効率の悪いエネルギー生成経路を選ぶのだろうか。これは、まったくもって興味深い異変である。
特徴8:免疫の破壊を回避する
免疫系は、がん細胞を積極的に探し出し、破壊する。例えば、正常な免疫系のナチュラルキラー細胞は、血液中を常にパトロールして、細菌、ウイルス、がん細胞などの外敵を探し回っている。このため、HIV陽性者や免疫抑制剤を服用している人(移植患者)など、免疫力が低下している患者は、がんを発症しやすいと言われている。
がん細胞が生き残るためには、がん細胞を殺すように設計された免疫システムを、どうにかして回避しなければならない。組織の中で成長している間は、腫瘍は、その組織に侵入しなければならない免疫細胞からある程度遮蔽されているかもしれない。しかし、がんが血液中に広がると、がんは直接さらされ、常に敵対的な免疫細胞に囲まれることになる。
がんの定義
8つの特徴とは、がんだろうかないかを区別する特徴的な行動に関する最高の科学的コンセンサスを表している。異なるがんを一つの病気として括ることで、細部は失われるが、全体像を把握することは容易になる。例えば、この8つの特徴は、さらに4つに単純化することができる(図31参照)。
次のような場合、がんであると考えることができる:
成長する-増殖シグナルを維持し(特徴1)、成長抑制因子から逃れ(2) 、細胞死に抵抗し(3) 、血管新生を誘発する(5) ;
不死である-複製性不死を可能にする(4);
動き回る-浸潤と転移を活性化し(6) 、免疫破壊を回避する(8) ;および
ワールブルグ効果を利用する-細胞のエネルギーを調節する(7)。
図31
【原図参照】
場合によっては、細胞がこれら4つの特徴を発現するために、数十、あるいは数百の遺伝子変異が必要とされることもある。しかし、がんの特徴を説明するだけでは、なぜ(原因)、どのように(メカニズム)がんが発生するのか、何もわからない。
多くの人が「がんの原因はわからない」と思っているが、実は、すでに多くのことがわかっている。
第23章 免疫療法
私はマイケル・ジョーダンに勝てる。タイガー・ウッズにも勝てるよ。なんだそれは、とおっしゃるだろう。私が正気を失っているのではないかと思われるかもしれない。そんなことはない。本当に簡単なことなのである: バスケやゴルフで勝負するのではなく、医学生理学的な勝負を挑むのである。マイケル・ジョーダンにバスケで挑むなんて、どうかしている。ゴルフでタイガー・ウッズに挑むなんて、とんでもない。古代中国の戦略家、孫子は紀元前5世紀に『兵法』の中で、「戦争では、強いものを避け、弱いものを攻撃するのが道である」と書いている。
この哲学は、がん治療にどのように適用されるのだろうか?これまでのがんのパラダイムは、がんの弱点ではなく強みを攻撃することに重点を置いていたため、すべて失敗した。
がんのパラダイム1.0では、がんを過剰増殖の病気と捉え、その核となる強みは、世の中のどんなものよりもよく成長し、生き残ることであるとした。私たちは、がんを殺そうとしたが、がん自身のゲームに付き合っているようなものだった。注目すべき成功例もあったが、このアプローチの限界はすぐに悟られた。私たちは、この病気の主な強みを正面から攻撃したのである。勝つこともあったが、負けることも少なくなかった。がんは再発すると、それまでの治療法に抵抗力を持ち、成長を続ける。がんは時空を超えて進化するが、私たちの治療はそうではない。
がんは無心に成長する機械ではなく、自らの生存を賭けてダイナミックに進化する種なのである。化学療法は、細胞増殖をターゲットにしたものであり、生物にとって最も基本的な能力である。しかし、40億年にわたる進化の過程で、がん細胞はこの究極の生存競争に備えることができたのである。化学療法が標的とする成長経路は、がん細胞にとって最も脆弱で、最も冗長な能力である可能性が高い。
がんパラダイム2.0では、がんは基本的にランダムに蓄積された遺伝子変異の病気であると考えられていた。この変異をブロックすれば(あるいはせいぜい2つか3つの変異をブロックすれば)、がんは治癒する。大きな成功例もあったが、やはりこのアプローチの限界はすぐに明らかになった。何が起こったのだろうか?もう一度言うが、私たちはがんの強みを生かして攻撃していたのである。がんは常に変異している。そこで、その変異を阻止する方法を考案しようとしたのである。ゴルフでタイガー・ウッズを打ち負かそうとするようなものである。
ある経路を遮断すれば、がんはたいてい別の経路を見つけることができる。がん細胞を究極の生存者にする突然変異は、ランダムではなく、腫瘍の進化のプロセスによって引き起こされたのである。がんの進化・生態学的パラダイムは、一部のがん治療が失敗する理由を説明するが、同時に、より戦略的な新しい方向性を示すこともできる。がんは、自らの存在意義を賭けて戦う侵略的な種である。
幸いなことに、私たちは外敵に対する多角的な防御策を進化させていた。この戦争に勝つための論理的な戦略は、私たち自身が生まれながらにして持っている防御機能である免疫システムを強化することである。
コーリーの毒素
1829年、進行性の乳がんを患う女性が手術を拒否した。18カ月間癌と闘い、寝たきりで悪液質で死にかけた時、高熱が出た。がんは炎症を起こしていたので、医師は腫瘍を数カ所切開して液体を取り除いた。すると、8日後にはがんが3分の1に縮小し、4週間後には跡形もなくなっていたのである。何が起こったのか?感染症が彼女のがんを治したのか1
1867年、ドイツの医師ヴィルヘルム・ブッシュは、ある女性患者の首にできた不治の腫瘍を焼灼した。その際、連鎖球菌による皮膚感染症「丹毒」を患っていた患者の隣に寝かせた。すると、たちまち腫瘍が小さくなっていった。1882年、同じドイツの医師フリードリッヒ・フェーライゼンがこの治療法を繰り返し、一定の成果を上げた。また、クロストリジウム菌の感染症であるガス壊疽に感染した患者でも、がんの寛解が確認されている。
私たち自身の免疫システムががんと闘うことができるという考えは新しいものではない。悪性腫瘍の自然退縮はまれだが、約10万人に1人の割合で発生し2、ほぼすべての種類のがんを対象としている。自然退縮とは、医療行為によらず、がんの一部または全部が消失することである。自然退縮は、感染症やワクチン接種による急性熱性疾患に伴って起こることが多い。
このような偶然の治癒をきっかけに、初期の医師たちは、不治の病であったがんに対して、原始的な免疫療法を行うようになった。古代エジプトの医師イムホテップ(紀元前2600年頃)は、がんの患部を湿布で包んだ後、切開することを提案した。皮膚から細菌が侵入して感染を起こし、その結果、がんが治癒することもあった。19世紀になっても、がん治療のための意図的な感染症が処方され続けていたのだ。手術の傷口は、感染を促進するために故意に開いたままにされた。膿性の爛れは、敗血症のドレッシングで意図的に感染させた4。
1880年代、ニューヨークに移住したドイツ人のフレッド・スタインは、首筋に急速に成長する腫瘍を発症した。1880年、ニューヨークに移住したドイツ人のフレッド・スタインは、首筋に急速に成長する腫瘍を発見した。このままでは「万病の元」になってしまう。しかし、運命の出会いがあった。スタインが顔面丹毒を発症したのだ。抗生物質がまだ開発されていなかったのだ。信じられないことに、スタインの免疫システムは感染症を撃退しただけでなく、ガンも破壊した。
1891年、アメリカの外科医ウィリアム・コーリー博士がフレッド・スタインを探し当てた。コーリー博士は、身体に本来備わっているがん退治の能力に興味を持ち、その後何十年もかけて、免疫系にがん退治をさせるよう説得した。コーリー博士は、患者にレンサ球菌を接種して丹毒を誘発し、免疫系を刺激した。コーリー博士は、この免疫反応が悪性腫瘍にも及ぶことを期待したのである。このような原始的な治療法の結果は一貫していなかった。大きな成功もあったが、恐ろしい失敗もあった。抗生物質がなかった時代、意図的に人を感染させることは、特に勝てる戦略ではなかった。
しかし、コーリー博士はめげなかった。問題は効能ではなく、毒性だったのだ。彼は、他の細菌(Serratia marcescens)を加え、投与前に熱で不活性化することで、処方に手を加えた。現在ではコーリーの毒素と呼ばれるこの処方は、最終的にリンパ腫、骨髄腫、癌腫、黒色腫などの手術不可能な癌患者1000人以上の治療に使用された。コーリーの毒素は、毎日腫瘍に直接注射され、1~2カ月間投与された後、徐々に投与量を減らしていった。
その結果、驚くような結果が出た。以前は手術ができなかった肉腫の半数以上が完全寛解を示し、患者は5年以上生存した。20年後でも、21パーセントの患者にがんの痕跡がなかった。当時としては、これは奇跡的としか言いようがない。興味深いことに、この治療法は進行した病気にも使われた。免疫システムは、たとえがんが広がっていても、体内のどこでも見つけて攻撃することができるからだ。
コーリー自身は、自然退行を誘発するためには発熱させることが最も重要であると強調していた。コーリーの毒素が最後に使われたのは1980年、中国で末期の肝臓がん患者を34週間にわたって治療した。その結果、症状は完全に消失した。化学療法とがんの遺伝的パラダイムの出現により、コーリー毒素は歴史の教科書の中でしか見られなくなり、何十年もの間、がん免疫療法という考え方は脇に追いやられた。

IMMUNEエディティング
がんが自然に退縮することがあるということは、私たちの体に内在する力が、がんを予防し、破壊することができるということを示唆していた。1909年、ドイツの科学者ポール・エーリッヒは、がんに関する根本的な新説を提唱した。エーリッヒは、がんは比較的まれであるという一般的な考え方に反して、がん細胞は比較的よく見られるが、現在では免疫系として知られている宿主の内在的な防御によって、それ以上の害を及ぼさないようにしていると推測した7。
この仮説は、1970年にノーベル賞を受賞した免疫学者フランク・バーネット卿8によってさらに洗練され、悪性腫瘍の遺伝子変化は決して珍しいものではないと示唆された。バーネットは、免疫系が体を正常に保つための日常的な監視の一環として、これらの危険な細胞を排除していると提唱した。バーネットは、「腫瘍細胞の小さな集積が生じ、……腫瘍の退縮とともに効果的な免疫反応を引き起こし、その存在を臨床的に示唆することはない」と書いている9。がん細胞は絶えず発生しているが、生来の免疫防御機能によって一掃されている。この免疫監視の概念はさらに拡張され、現在では免疫編集と呼ばれ、排除(免疫監視)、平衡、脱出の3段階から構成されている。
排除(Elimination)
社会は、警察や麻薬取締機関のような専門部隊を定期的に雇い、自分たちの中にいる破壊的な要素を探し出し、破壊する。同様に、人間の免疫システムは、ウイルス、細菌、そして癌細胞などの破壊的な要素を探して、定期的に全身をパトロールする特殊な細胞を使用している。そして、傷ついた細胞の中に、がん化する可能性のあるものを見つけると、その細胞を徹底的に殺す。これにより、がんの脅威が広がる前に素早く排除される。
体内のすべての細胞は、毎日2万回以上のDNA損傷イベントを経験していると推定されている10!慢性的な亜致死性の細胞損傷は珍しいことではなく、日常的に起こっていることなのである。煙、大気汚染、ウイルス、細菌、放射線など、一般的なダメージの原因となっている。幸いにも、私たちの細胞は強力なDNA修復経路を進化させていた。しかし、バランスが細胞損傷に傾いてしまうと、これらの修復メカニズムが対処できなくなる可能性がある。傷ついた細胞はすべて癌化する可能性がある。ある程度のダメージを受けた細胞は、アポトーシスによって除去されるか、免疫システムによって破壊されるのがよいだろう。
HIV感染や薬物など、免疫力が低下すると、細胞はがんになりやすくなる。また、免疫系は加齢によっても低下するため、がんのリスクが加齢によって大きく上昇する理由にもなっている。免疫系ががん細胞を完全に駆逐できるほど強くない場合、がんの排除から平衡へと移行する。
平衡状態
2004年、肺線維症の64歳の男性が単肺移植を受け、臓器拒絶反応を防ぐために標準的な高用量の免疫抑制を受けた。1年後、息切れと咳が出現した。右肺の結節が転移性メラノーマと判明し、いくつかのリンパ節も確認された。
癌だ!この人はメラノーマにかかったことがなかったのに、なぜ今になって肺にメラノーマが広がっているのか?皮膚の検査をしても、メラノーマは発見されなかった。恐る恐る、医療チームは肺の提供者の病歴について詳しく聞いた。
ドナーは51歳の女性で、外傷で亡くなっていた。病歴は特に問題なかったが、さらに調べると、1つの問題が見つかった。21歳のとき、この女性はメラノーマを除去する手術を受けたことがある。それ以後は治療も必要なく、再発もない。がんは何年も前に完治したと思われ、移植チームが知っていたとしても、臓器提供の対象にはならない。臓器摘出時、彼女の肺は全く正常で健康な状態に見えた。
さらにDNA検査を行ったところ、レシピエントのメラノーマは本当に肺の提供者から出たものであることが確認された。この場合、ドナーの肺には、臨床症状がないにもかかわらず、微小な癌のスリーパーセルが生き続けていた。がんは、30年もの間、女性の免疫システムによって抑制され、眠っていたのである。がん細胞は、免疫システムによる根絶を免れたが、それ以上広がるほど強くはなかった。膠着状態だったのだ。彼女の肺が免疫抑制下のレシピエントに移植されたとき、がんと免疫システムの間の微妙な均衡は、決定的にがんに有利に振られた11。
免疫編集の均衡の段階では、がん細胞のポケットが生き残るが、免疫系による抑制のために増殖することはできない。潜伏がんは、何年も何十年も眠っていることがある。がんが成長しようとする努力と、その成長を抑えようとする免疫系の努力が一致する。がんを増殖させようとする力と、それを抑えようとする免疫の力は、同じように釣り合っている。
脱出
一般に加齢とともに免疫力は低下し、時にはがんを封じ込められなくなることもある。このように、外来種であるがんと免疫システムとの闘いでは、がんが有利になる。免疫システムによる抑制から逃れられる。
このままでは、がんは成長し続け、さらに転移を起こす。このとき、免疫系を強化することで、私たちに有利なバランスになる可能性がある。これが、がん医療の次なるフロンティアである免疫療法への期待である。
(免疫療法)
初期の頃
1929年、ジョン・ホプキンスの医師たちは、結核を患う患者が、なぜかがんから守られているように見えることに注目した。結核は世界の多くの地域で流行しており、結核菌と呼ばれる増殖の遅い細菌によって引き起こされる。ほとんどの抗生物質に耐性があり、今日でも、1912年に初めて発見された薬であるイソニアジドを中心に治療が行われている。結核は広く蔓延し、ほとんど治癒しないため、19世紀には多くの療養所が設立され、患者は隔離された。有効な治療法がなかったため、1921年に近縁のマイコバクテリウム・ボビス菌を用いたバチルス・カルメット・ゲラン(BCG)ワクチンの開発に大きな関心が集まった。
1950年代に行われた動物実験では、BCGワクチンががんを予防する効果があることが示唆された。1976年には、ヒトの表在性膀胱がんを効果的に治療することが証明された13。1990年には、膀胱鏡で膀胱に直接BCGを注入することが、膀胱がんの治療法としてFDAに認可された。
早期の膀胱がん患者の71%がBCG治療に反応するという驚異的な成績で14、現在の膀胱がんの第一選択治療となっている。この結核ワクチンが表在性膀胱癌にどのように作用するかは、全く未知数であった。しかし、BCGが表在性膀胱癌にどのように作用するのかは、全くわかっていなかった。BCGは免疫系を強く刺激し15、その結果、がん細胞の認識と破壊が促進された。
1992年、インターロイキン2(IL-2)治療の開発により、がん免疫療法への関心が再び高まった。IL-2は、免疫系に不可欠なT細胞を狂喜乱舞させ、がん細胞はその集中砲火の中で死滅した。しかし、IL-2は免疫系を全般的に活性化させるため、発熱、悪寒、吐き気、下痢などの副作用も多く見られた。最終的に、IL-2による治療はメラノーマ患者の約6%にしか効果がないと判断されたが、約2%の患者がその副作用で死亡している。
現代の免疫療法
ノーベル賞受賞者のジェームズ・アリソン博士は、母をリンパ腫で、叔父を肺がんで、兄を前立腺がんで亡くし、がんに対する深い恨みを持っていた。1978年、アリソン博士は、T細胞が腫瘍を攻撃する仕組みについて研究を開始し、がん免疫学が評判の高い分野とされるずっと以前から、その先駆者的存在となっていた。
人間の免疫系には多くの種類の細胞が存在する。その中でもT細胞は、病原体を破壊するために作られた致死性の高い細胞で、プロの殺し屋である。そのため、身体はこの致命的な武器を厳しく管理している。T細胞は、病気や感染した細胞は殺すが、正常な細胞は放っておかなければならない。T細胞は野放しにすると、体を破壊しかねない。全身性エリテマトーデスや関節リウマチなどの自己免疫疾患は、免疫システムの過剰反応によって引き起こされる。目標は、すべての侵略者を殺すが、友好的な攻撃を避けることである。そのためには、免疫系が「自分」と「自分以外」の組織を正確に区別する必要がある。核ミサイルのように、健康な免疫システムは高い殺傷力を持ちながら、しっかりと制御されなければならない。そのために、ポジティブコントロールとネガティブコントロールの両方を使用する。
核ミサイルを発射するには、2つのキーを同時に作動させ、誤発射の可能性を低くする必要がある。それが起動のためのポジティブコントロールの仕組みであり、さらに防御のために、緊急時に直ちに発射を中止させるためのネガティブコントロール、「キルスイッチ」がある。ハリウッドのアクション映画では、人口密集地を焼き尽くそうとするミサイルを、主人公が残り1秒で解除するという、キルスイッチの登場シーンが目立つね。人間のT細胞も同じような働きをする。T細胞が発動するためには、2つの受容体が同時に活性化される必要がある。T細胞は腫瘍抗原と、コスティミュレイトリー受容体CD28として知られる第2のスイッチの両方を検出しなければならない。
アリソンの研究当時、もう一つの保護層であるネガティブコントロール、すなわちキルスイッチを疑う者はまだいなかった。1990年代、アリソンは、細胞傷害性Tリンパ球関連タンパク質#4 (CTLA-4)と呼ばれる新しく報告された受容体を研究していたが、ほとんどの研究者がT細胞活性化因子であると信じていた。アリソンは、CTLA-4が活性化スイッチではなく、殺傷スイッチであることを認識し、ブレークスルーを果たした。T細胞が殺傷スイッチを持つという可能性は、それまで考えられなかったことだった17。
もし両方の「GO」シグナルがあれば、T細胞はランボーモードに入り、敵、特にがん細胞の破壊を開始することになる。殺しのスイッチであるCTLA-4は、T細胞のチェックポイントとして機能する。CTLA-4は、T細胞にとって最終的な判断材料となる。もしCTLA-4が作動しなければ、T細胞は核攻撃を開始する。もし、キルスイッチが作動すれば、免疫攻撃は停止してしまう。がん細胞は、このキルスイッチを模倣することで、致死率の高いT細胞を回避している。
つまり、このキルスイッチを無効化できれば、T細胞のがん細胞に対する総攻撃を解き放つことができる。1996年までにアリソンは、CTLA-4を阻害するモノクローナル抗体を作製し、世界初のチェックポイント阻害剤とした。しかし、抗体を投与しなかったマウスの腫瘍はどんどん大きくなっていった。アリソンは、「完璧な実験だった」と振り返る。100%生きているのと、100%死んでいるのでは、雲泥の差である」
この抗体はイピリムマブと呼ばれるようになり、2011年に転移性メラノーマの治療薬としてFDAから承認された。イピリムマブは、あらゆるタイプの薬剤で初めて進行性メラノーマの生存期間を改善し、がん免疫療法の概念を証明するものとなった。イピリムマブの投与を受けた転移性メラノーマ患者の20%以上が、10年後も生存していたのである19。イピリムマブの投与期間がわずか3カ月であることを考慮すれば、この結果はさらに驚くべきものである。イピリムマブの投与期間がわずか3カ月であることを考えると、この結果はさらに驚くべきものである。このような耐久性のある反応は、癌のもどかしい進化能力のために、腫瘍学ではほとんど知られていない。
しかし、CTLA-4は、ヒトの免疫系における唯一のT細胞キルスイッチではない。1992年、京都大学の本庶佑博士は、プログラム細胞死タンパク質1(PD-1)と呼ばれる別のT細胞殺傷スイッチを発見した。正常な健康な細胞は、免疫の攻撃から身を守るためにPD-1を表面に発現している。例えば、胎児の細胞はPD-1で覆われていて、ママの免疫細胞から身を守っている。
がん細胞も同じ手口で、PD-1を大量に分泌して正常な細胞になりすまし、免疫システムからの攻撃から身を守る。PD-1をブロックする抗体があれば、殺傷スイッチが入り、T細胞は隠れていないがん細胞を狙い撃ちできるようになる。2012年までに、PD-1に対する第二のチェックポイント阻害剤がヒトのがんにおいて有効であることが証明され、2014年にFDAによって承認された。これらの薬剤は、メラノーマ、肺がん、腎臓がんなど、さまざまな腫瘍に対して有効だった。本庶とアリソンは、「がん治療のためのまったく新しい原理を確立した」20として、2018年のノーベル生理学・医学賞を共有することになる。PD-1阻害抗体とCTLA-4阻害抗体を組み合わせることで、さらに効果的な治療ができるかもしれない21。
もう一つの有望な免疫療法は、養子縁組T細胞移植と呼ばれる技術である。この治療法では、患者自身のT細胞を抽出し、研究室で増殖させる。キメラ抗原受容体(CAR-T)と呼ばれるがんを標的とするシステムがT細胞に取り付けられ、再び患者に移植される。この活性化された致死性のT細胞は、精密誘導ミサイルのように患者の特定のがんを狙い撃ちする。CAR-Tの最初の2つの治療法は、2017年にFDAの承認を受けた:白血病の治療のためのtisagenlecleucelと、リンパ腫の治療のためのaxicabtagene ciloleucelである22。新しいキメラ抗原を患者のT細胞に取り付けることができるので、CAR-Tは薬剤というよりも送達プラットフォームと言える。理論的には、CAR-Tはあらゆるがんをターゲットにする機会を提供することができる。
免疫療法には、従来の治療法とは異なるいくつかの固有の利点がある。まず、がんは常に環境とともにダイナミックに進化している状態である。薬物は静的な標的を攻撃し、進化することはない。そのため、がんは薬剤の周囲に簡単に張り付き、耐性を発達させ、これらの治療法を時間の経過とともに効かなくしてしまう。免疫系が強化されると、ダイナミックなシステムとして、がんの動きにうまく対応できるようになる。免疫系は、がんとともに調整し、進化することができる。
第二に、免疫系は記憶を持っているため、再発を防ぐことができる可能性がある。子供の頃に麻疹の予防接種を受けると、免疫系はこのウイルスを記憶し、生涯にわたって予防することができる。それと同じように、メラノーマの患者でも、免疫力が高まることで生存期間が延びるケースがある(おそらく、この記憶効果によるものと考えられる)。
第三に、免疫療法は標準的な化学療法に比べ副作用が少ないことである。従来の化学療法は毒性が強く、がん細胞を通常の細胞よりもわずかに速く殺すように設計されている。免疫療法は、体内で異質なものとして識別された細胞を除いて、本質的な毒性は持っていない。
第四に、免疫療法は全身療法であることである。これは、がんが全身性の病気であることから非常に重要である。転移は病気の初期に起こるので、全身療法は全身にある潜在的な微小転移を治療することができる。免疫系ががん細胞をロックオンして破壊することができるので、手術や放射線などの局所治療のように手動でターゲットを絞る必要がないのである。また、全身的な治療であるため、がんが転移した後、病気のかなり後期でも免疫療法が有効である可能性がある。コーリー博士は、免疫療法が始まった当初から、この全身的な効果が末期のがん患者に恩恵をもたらす可能性があると見ていた。
しかし、手頃な価格で購入できることは、免疫療法の利点の一つではない。これらの治療が法外な価格であることを考えると、多くの医療機関はこれらの先進的な薬剤を使用することの実現可能性に疑問を抱いている。一人親方制の場合、数人の命を救うために必要なコストと、他のこと(例えば、病院のベッドの増設、看護ケアの増設、在宅ケアの増設など)とのバランスを取る必要がある。これは簡単な問題ではないし、本書の範囲を超えているが、近い将来、医療に関する議論の最前線に立つことになる問題である。
アブスコパル効果
2008年、外科的治療を受けたメラノーマの33歳の女性がPET検査を受けたところ、新たに2cmほどの肺結節が見つかった。がんが再発していたのである。肺の一部を切除し、化学療法とイピリムマブによる維持免疫療法を開始したところ、一時的にではあるがメラノーマは寛解に向かった。2010年には、脾臓、胸、肺の裏(胸膜)に新たな転移が認められた。背骨に近い痛みを伴う病変は、放射線分割で治療した。予想通り、脊椎の転移は縮小したが、驚くべきことに、脾臓と胸部の転移も、放射線照射の範囲外であるにもかかわらず、縮小した23。
2012年にNew England Journal of Medicine誌に掲載されたこの症例報告は、1973年に初めて観察された「アブスコパル効果」と呼ばれる現象を再発見させるものだった。アブスコパル24とは、ラテン語の接頭辞ab-に由来し、「屁」を意味し、「標的」を意味する-scopus-25に由来する。アブスコパル効果とは、意図した対象から遠く離れた場所に結果をもたらすことである。放射線治療は、がん組織や邪魔な組織を焼き払う。また、予期せぬことに、照射していない転移病変が治療部位から遠く離れた場所で再発することもある。
放射線は通常、照射された領域内の細胞のみに影響を与える。しかし、ごく一部のケースでは、その部位の外側、さらには遠く離れた場所にあるがん細胞も治療に反応することがある。このような結果は歴史的に稀であり、少なくとも免疫療法の時代まではそうだった。1969年から2018年までの医学文献によると、アブスコパル効果は94例報告されているが、驚くべきことに、その半数は現代の免疫療法の時代である過去6年間の報告である26。免疫療法と併用すると、放射線は、2つの治療法の単独投与で期待される利益をはるかに上回る効果的な全身性抗腫瘍反応を誘発する可能性がある。最近の研究では、免疫療法と放射線治療を受けた転移性固形腫瘍患者の27%にこのアブスコパル効果が認められた。27 免疫療法の普及により、アブスコパル効果は非典型的な現象から、がん患者全体の4分の1以上に恩恵をもたらす可能性がある現象に変わった。
この現象は一見奇妙に思えるが、がんの進化論的パラダイムは、アブスコパル効果がなぜ起こるかを理解するのに役立つ。放射線は細胞のDNAを損傷し、壊死させる。この無秩序な細胞死は、歩道に落とされた生卵のように、細胞の一部を組織内に飛び散らせる。通常、核の中にしっかりと収められているDNAが突然露出し、この非常に炎症性の高い状態は、混乱を一掃するために免疫細胞を引き寄せる。さらに、免疫系は似たような細胞を探して破壊するように仕向けられる。
しかし、がん細胞はPD-1やCTLA-4を使って身を隠し、十分な免疫反応を引き起こさないため、守られている。放射線治療と免疫療法の両方を受けると、免疫系は活性化するだけでなく、クロークされていないがん細胞を特異的に殺すように促される。この相乗効果がアブスコパル効果につながる。放射線による局所的な細胞損傷は、ワクチンのように作用し、活性化した免疫系を誘導ミサイルのようにDNAの標的に向かわせる。しかし、正しい投与法を用いることが重要である。
通常、放射線にさらされたDNAは、TREX1という細胞内酵素によって浄化される。この酵素は、ティラノサウルス・レックスという恐竜の種類にちなんで名付けられたもので、問題の拡大を防ぐために、その辺に転がっている迷子DNAを貪欲に食べ尽くす。放射線量が高いとTREX1が活性化し、野良DNAを破壊し、免疫系の活性化を防ぎ、アブスコパル効果を低下させる28。TREX1の活性化を避けるために十分に低いまま、時間をかけて拡散した(分画)少量の放射線は、アブスコパル効果をもたらすのに有効であると考えられる29。
2019年、アブスコパル効果を対象とした初の小規模対照ヒト試験が発表された30。すべての患者は免疫療法で治療され、追加の放射線を照射するかしないかに無作為に割り付けられた。放射線を受けた患者は客観的奏効率が2倍になり、全生存期間中央値は7.6カ月から15.9カ月に2倍以上増加した。登録された患者数が少なかったため、これらの結果は統計的に有意ではなかったが、それでも勇気づけられるものであった。
平均的なアスリートと殿堂入りしたアスリートの違いは、後者が周囲の人々をより良くする能力を備えているかどうかである。免疫療法は、それ自体が有効であるだけでなく、他の古い治療法をより良くするものであるため、がん医療の未来を象徴するものである。
適応療法
標準的ながん治療の最大の問題は、がん細胞を殺さないことではない。問題は、がんが耐性を獲得することである。化学療法、放射線療法、ホルモン療法はいずれもがん細胞を殺すが、同時に耐性に有利な自然な選択圧も働かせる。これらはすべて、治療と殺戮の両方の可能性を持つ、本質的に諸刃の武器である。癌の進化論的パラダイムは、癌を根絶する必要があるのか、それとも癌の個体数をコントロールすればいいのか、という重要な問題を提起している。
1989年、がん研究者のロバート・ガテンビーは、腫瘍の進化というアイデアに魅了された。がん細胞は資源をめぐって競争しているのだ、と。1920年代から使われている数学的モデルは、過酷な条件下で集団がどのように成長していくかを説明してきた。例えば、ロトカ・ヴォルテラ方程式は、カンジキウサギとそれを餌とするオオヤマネコの集団の成長をモデル化したものである。Gatenbyは、この方程式をウサギではなく、がん細胞の集団に適用し、数理腫瘍学の分野を切り開いた31。
外来種の集団は、癌と同じように、分散、増殖、移動、進化を伴う。例えば、農作物を食べる害虫は、食べ物が簡単に手に入るようになると、急速に成長する。農薬は害虫を駆除するが、必然的に、最も強力な農薬(例えば、悪名高いDDT)に対してさえも耐性ができる。癌細胞もまた、最も強力な化学療法に対して耐性を獲得する。農薬が薬剤耐性に有利な自然選択圧として働くため、蔓延する害虫の根絶に成功することはまれである。このような抵抗性を持つ害虫は、競争が少なくなるため、繁殖する。
例えば、10億匹のイナゴに殺虫剤を散布して、99.9%減の100万匹にしたとする。100万匹になったイナゴは、餌を得るための競争相手がいなくなり、指数関数的に個体数を増やし始める。最終的には、10億匹の農薬耐性イナゴが誕生する。がん細胞も同じだ。化学療法で99.9%のがん細胞を死滅させることができるが、生き残った細胞は競争相手が減るため、増殖するための資源は十分にある。また、新しいがん細胞の集団は、治療抵抗性を持っている。
化学療法の標準的な治療方針は、最大耐用量(MTD)を投与すること、つまり、患者を死なせずに可能な限り多くの化学療法を行うことである。Gatenbyがこの戦略を数学的にモデル化したところ、ほぼ毎回耐性が生じ、最終的に治療が失敗に終わった32。
2014年、Gatenbyは数学的モデリングに基づき、適応療法と呼ばれる有望な新戦略をテストした。転移性がんに対して「殺すために治療する」戦略が効かないのであれば、「封じ込めるために治療する」戦略が有効かもしれないと彼は考えた。MTDでがんを絨毯爆撃するのではなく、ある一定以上のがん活性がある場合にのみ選択的に化学療法を行い、がんを根絶するのではなく、管理しようとしたのである。試験研究の結果は、驚くべきものだった。適応療法、つまり高価な化学療法剤を半分以下の量で使用することで、生存率が64%向上したのだ33。
癌の耐性株は、その耐性を維持するために、より多くのリソースを割かなければならない。自然淘汰圧として作用する薬剤がなければ、薬剤耐性株は不利であり、比較的役に立たない薬剤耐性形質を維持するために貴重な資源を使用することになる。これらの結果は予備的なものだが、新しいがんパラダイムを利用した革新的な研究の種類を浮き彫りにするものである。場合によっては、がんを根絶するのではなく、コントロールすることで、より良い結果を得られるかもしれない。スラムダンクを狙うのではなく、簡単なレイアップをした方が得点になることもある。
結論
免疫療法、アブソーパール効果、適応療法は、がんの進化のパラダイムが明らかにした新しいがん戦略の例だ。免疫療法を支える技術は革命的であり、未来は明るいのだが、まだそれは到来していない。2002年から2014年の間にFDAによって承認された薬剤の数にもかかわらず、固形がんの全生存期間の改善はわずか2.1カ月である34。それでも、ここ数十年で初めて、楽観視できる理由がある。
進化生物学の教訓をがんの理解に応用することで、治療の未来に新たな希望がもたらされる。私たちは、がんを克服することができるのだろうか?しかし、私たちの古くからの敵に対する新たな理解は、この暗い暗いトンネルの終わりに光をもたらせてくれることだろう。
エピローグ
がんは、医学の最も深い謎である。医学は、私たちを苦しめる他の多くの病気の原因を長い間解き明かしてきた。感染症は、細菌、ウイルス、真菌によって引き起こされる。動脈の閉塞は、心臓病、脳卒中、末梢血管疾患の原因となる。
嚢胞性線維症は遺伝病である。痛風は尿酸が過剰になることで起こる。一般的な病気の中では、がんが突出している。何が原因なのか?なぜ存在するのか?いったい何なのか?
私たちは、がんを理解するために、3つの大きなパラダイムを経ていた。がんのパラダイム1.0では、がんは過剰に成長する病気であると考えられていた。がんのパラダイム2.0では、がんは過剰な成長を引き起こすランダムな遺伝子変異の病気であると考えられていた。この2つのパラダイムは、がんの物語を理解する上で重要な役割を果たしたが、不十分なものだった。しかし、「がんパラダイム3.0」は、人類の誕生から多細胞生物の誕生に至るまで、がん発生の謎を追究し、この興味深い敵の新たな姿を明らかにした。
がんの種は、すべての多細胞生物のすべての細胞の中にある。がんは、細胞が生き残るための闘争(トランスフォーメーション)によってもたらされる、以前の遺伝的なプレイブックへの回帰(アットアビズム)である。その種が繁殖するかどうかは、環境(土壌)に依存する。進行の最も重要な側面は、身体の成長経路であり、それは栄養素を感知する経路でもある。
成長の病気は代謝の病気である。代謝の病気は、成長の病気である。がんは、進化と生態の病気なのだ。まだまだ発見があることは間違いないが、この新しいパラダイムは大きな飛躍を意味する。
このようながんに関する新しい知見は、新しい治療法をもたらす。検診プログラムの利点と限界を理解することで、私たちはようやく、がんやがんによる死亡率の減少を目の当たりにすることができるようになった。私たちは、細胞大量破壊兵器が諸刃の剣であることを認識し、その精度を高めている。もしかしたら、私たちは常にがん細胞を根絶する必要はないかもしれない。私たちは、がん細胞を追い詰め、どこに隠れていても殺すことができる、全身性の新しい免疫兵器を開発しようとしている。
しかし、1つの巨大な新しい障害が発生した。急増する肥満の危機は、乳がんや大腸がんなど、肥満に関連するがんの発生率を高めている。ほとんどのがんが徐々に減少していく中、これらのがんは増加している。しかし、まだ楽観できる理由がある。栄養は、肥満に関連するがんに対する私たちの最大の武器である。食生活を見直すことで、その脅威を軽減することができる。
新たな希望
がん医療は、科学界と医学界がそれぞれのパラダイムをゆっくりと歩んできたため、何十年もの間、ニュートラルな状態にとどまっている。しかし、私は未来に希望を抱いている。なぜなら、私たちの新しい理解は、これまで想像もしなかったような方法で進歩を促すことができるからだ。がんは、私たちが医学の世界で直面する他のどんな病気とも違うものである。がんの物語はSFよりも奇妙であり、私たちを正しい道へと導くために、宇宙生物学者の力強い洞察が必要だったのである。
がん医療の新しいパラダイムが確立されたことで、ここ数十年来のがんとの戦いが、初めて真の意味で前進する可能性が出てきたのである。新しい希望が生まれる。新しい夜明けがやってくる。
研究者、医師、患者、家族など、がんに関わるすべての人々にとって、本書がこの最も深い医学的謎に少しでも光を当てる一助となれば幸いである。
著者について
DR. ジェイソン・ファングは医師であり、作家であり、研究者である。科学的根拠に基づいたブレイクスルー著書「The Diabetes Code」「The Obesity Code」「The Complete Guide to Fasting」は100万部以上を売り上げ、2型糖尿病、減量、ファスティングに関する従来の常識に挑戦している。ファング博士はまた、ファスティングで自然に体重を減らし、2型糖尿病を回復させるプログラム、ファスティング・メソッド(TheFastingMethod.com)の共同設立者でもある。ファスティングに関する彼の研究は、CNN、ニューヨークタイムズ、TIME、アトランティック、フォーブス、トロントスター、その他多くのメディアで引用されている。
