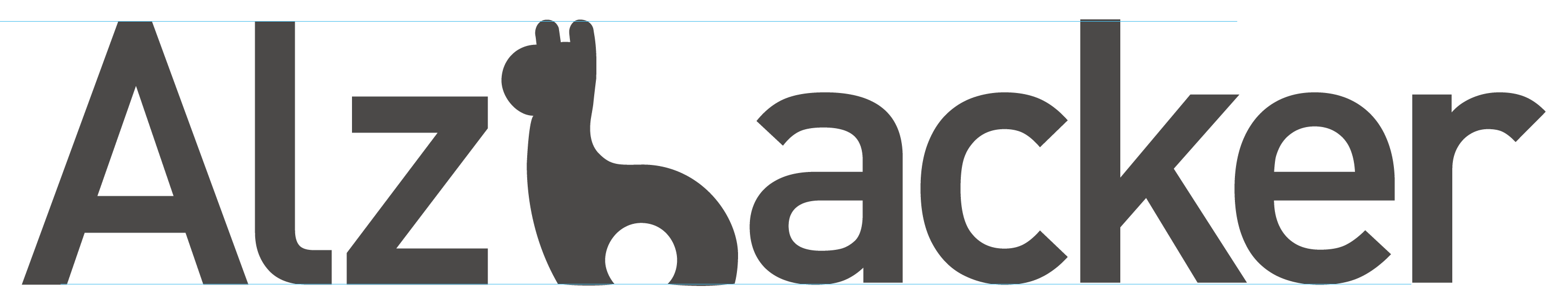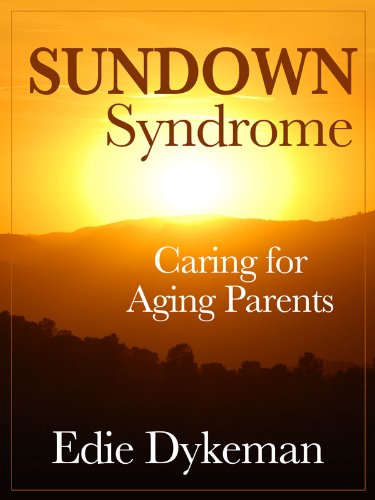Contents
そして、太陽が沈んだ後のたいていの夜で、ある種の魔法が認知症の国で始まるのである。
書籍「Wonders in Dementialand」より
夕暮れ症候群(日没症候群) Sundowning
概要
夕暮れ症候群の多用な定義
「夕暮れ症候群」は明確には定義されておらず、認知症患者だけに使用する研究者ともいれば、認知症障害がない高齢者にこの説明を用いる研究者も存在する。
また心理的症状も広く含まれており、せん妄との区別が微妙になる。
症状が増加する時期も日没前後の夕方に限定することもあれば、夜間を含める場合もあり研究者で意見が一致しない。
評価テストの不在
夕暮れ症候群は昔から医療関係者や認知症支援者に知られている臨床概念であるが、夕暮れ症候群を評価する専用ツールは開発や検証が行われておらず、研究も進んでいない要因となっている。(ランダム化比較試験はまだ行われていない)[R]
有病率
アルツハイマー病協会によるとアルツハイマー病と診断された患者の20%が、夕暮れ症候群を経験する[R]。66%との報告もある。[R]
血管性認知症、前頭側頭型認知症、レビー小体型認知症に関しても報告されている。[R]
患者の年齢、性別、人種に関する有病率には一貫したデータが存在しない。
いくつかのデータは日没の異なる季節的発生を示唆しており、秋または冬の時期の発生率が高いことが観察されている。[R]
症状
- 自然の光が薄れ始め、影が増すにつれて、混乱が増加する。
- 動揺と気分のむら。混乱によって強く苛立ち、雑音によって悪化する場合がある。叫んだり、介護者に怒りを向ける患者は珍しくない。
- 太陽が沈むにつれて精神的、肉体的疲労が増加する。この疲労によっていらいらを募らせる。
- 振戦の増加、コントロールできなくなることがある。
- 寝る際に落ち着きのなさが増すことがある。多くの場合、落ち着きのなさは本人の混乱を引き起こし、歩き回ったり、徘徊などの行動につながることがある。
- 夜間の恐怖
- 膀胱失禁
- 不安
- めまい
[R]
夕焼け症候群の原因
原因は特定されておらず、概日リズムの混乱が夕暮れ症候群を増加させることがいくつかの研究で示唆されている。
夕暮れ症候群の要因 まとめ
神経生物学的要因 視交叉上核の変性
- メラトニン生産の減少
- 概日リズムの混乱
- コリン作動性神経伝達障害
- HPA軸の調節不全
薬理学的因子
- 抗精神病薬
- 抗コリン作用薬
- 抗うつ薬
- 催眠剤
生理的要因
- 疲労
- 空腹・飢餓
- 満たされていない身体的または心理的な欲求
- 体温の日内変動
- 血糖値の日内変動
- 血圧の日内変動
医学的要因
- 睡眠障害
- 感覚の剥奪
- 疼痛
- 気分障害、気分変動
- 認知障害(失語症など)
環境要因
- 不十分な量の光暴露
- 居住施設の患者あたりの少ない介護職員
- 在宅介護者の頻度の高い不在
- 介護者の疲労
- 環境からの過剰刺激(ノイズや混乱状況)
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5187352/
夕暮れ症候群への治療アプローチ
夕暮れ症候群を引き起こす要因が様々にあることを考えると、多段階の複合的なアプローチが採用されるべきである。
DICEアプローチ[R]
認知症患者の行動症状への非薬理学的な多段階アプローチ、[R]
非薬理学的アプローチをまず選択
認知症に関わる介護者、看護師、医療関係者など間ではよく知られている症状だが、日没に関する定義の合意が得られていないため、診断のための標準化された基準は策定されていない。非薬理学的なアプローチを第一選択として検討するべきだとの合意が増しつつある。[R]
メラトニン
メラトニン産生の低下
一般的にヒトの体内では、日没はドーパミンレベルが低下し、睡眠に向けてメラトニンを産生するための生化学的な作用が起こるが、認知症ではメラトニン産生が低下し、神経伝達物質を妨害する可能性がある。[R]
メラトニン投与研究
メラトニン9mgの投与 日没12人の患者の寛解; 2つの場合の減衰。ベースラインから治療終了までの睡眠の質の大幅な改善[R]
認知症の高齢者介護施設入所者11人 21日間、一日3 mg 日没時の興奮の大幅な減少[R][R]
![]() メラトニンサプリメントのタイプ・用法(認知症・アルツハイマー)
メラトニンサプリメントのタイプ・用法(認知症・アルツハイマー)
光療法(夕方)
退役軍人病院の研究病棟にいる日没行動と睡眠障害を有するアルツハイマー病の入院患者10人。患者は午後7時から午後9時までの夕方2時間明るい光(パルス)に暴露。患者10人中8人で改善が示された。[R]
メラトニンと光療法の組み合わせ [R]
光療法のメタアナリシス[R]
日々の生活をルーチン化
- 食事や起床時間など決まったスケジュールを維持する。毎日のルーチンを遵守する。
- 病院へ行く、旅行する、朝や午後早めに入浴するなど、多くの活動的な行動を計画する。
夕方の刺激を避ける
- 不要なノイズ(訪問者からのノイズ、大音量スピーカー、料理の叩き、大声でのスタッフの会話など)を最小限にする。
- 夕方の過度の感覚刺激(聴覚と視覚の両方)を回避する。
- 午後の昼寝を中止
アセチルコリンエステラーゼ阻害剤
コリン作動性の異常
視交叉上核(SCN)はコリン作動性の刺激に対して高い感受性をもっており、アセチルコリンの変性は、日没症候群の根本的なメカニズムとして示されている。[R]
メタアナリシス コリンエステラーゼ阻害剤は、アルツハイマー病患者のBPSDの減少を有意にもたらす。[R]
![]() アセチルコリンエステラーゼ阻害剤(抗認知症薬・AChE阻害薬)が誘導する睡眠・概日リズム障害
アセチルコリンエステラーゼ阻害剤(抗認知症薬・AChE阻害薬)が誘導する睡眠・概日リズム障害
HPA軸の調節異常
コルチゾール
日没症候群を示すアルツハイマー病患者は、日没症候群を示さない患者よりも有意に高いコルチゾールレベルを有する。[R]
![]() HPA軸とアルツハイマー病
HPA軸とアルツハイマー病
向精神薬の中止
また認知症の神経精神症状(NPS)の管理を行うために向精神薬などが頻繁に使用されるが、重大な副作用により利益を相殺してしまうことがいくつかのケースで実証されている。[R]
夕暮れ症候群の症状に対してベンゾジアゼピン、睡眠薬などの使用を支持する証拠はなく、むしろ逆説的に行動障害(NPS)の増加と関連している。[R]