Contents
Physical Exercise as Personalized Medicine for Dementia Prevention?
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6563896/
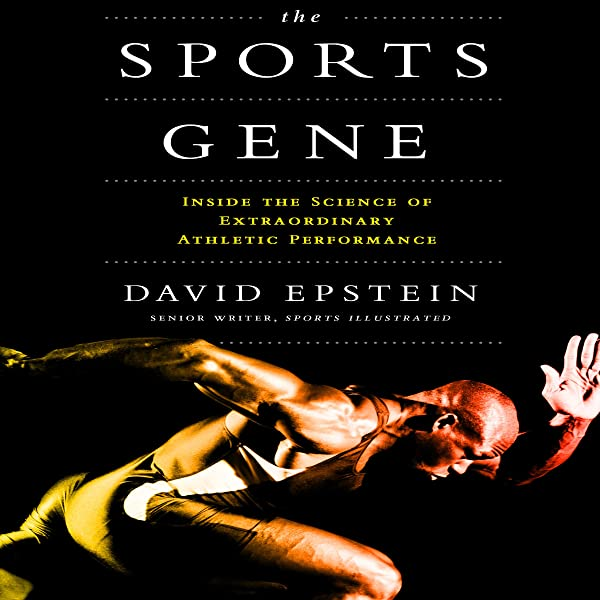
Patrick Müllers、 1 、 * Marco Taubert、 2 、 3 and Notger G. Müller 1 、 3 、 4
要旨
観察研究を中心としたエビデンスの蓄積は、定期的な身体活動などの生活習慣因子が認知症の潜在的な危険因子を修飾するという考えを支持している。この相互作用のメカニズムについては、介入研究の結果から、運動が脳の神経可塑性の変化を誘導することが示されている。
しかし、研究結果を詳しく見ると、観察された効果には個人間で大きなばらつきがあることが明らかになっている。この不均一性は、身体運動の生理学的アウトカムパラメータ(VO2ピーク)や脳への影響について、「反応する人」と「反応しない人」がいることに由来すると考えられる。
このことから、一般的な運動プログラムの推奨は「ワンサイズ・フィット・オール」のアプローチではないことがわかる。その代わりとして、定期的な運動の潜在的な神経可塑性と予防効果を最大化するために、運動は個人に合わせて調整されるべきであることを提案する。これらの調整は、個人のパフォーマンスレベルを考慮し、運動の質(種類)と量(強度、持続時間、量)の両方に影響を与えるべきである。
キーワード:運動、認知症、神経可塑性、個別化医療、レスポンダー
序論
最近の予測によると、世界の認知症患者数は現在の47人から 2050年までに1億3、130万人に増加すると予測されており(Prince er al)。 最近では、200件以上の新薬の臨床試験が失敗に終わっており、疾患修飾薬の開発への期待は薄れてきている(Schneider er al)。 このような状況の中で、健康老化の概念がますます重要になってきている。
因果関係のある薬理学的治療の見通しが立たないため、認知症研究は現在、予防戦略として機能する修飾可能なリスク因子および生活様式因子に向けられている(Kivipelto et al 2018a)。Nortonら(2014)は、アルツハイマー病の世界的有病率の3分の1が修正可能なリスク因子に関連していると推測している。他の要因の中でも特に身体的不活発、過体重、高血圧、糖尿病が修正可能な危険因子として同定されている。後者は、様々な予防戦略の機会を提供している。計算モデルによると、10年間で10%の危険因子の減少は、2050年までに世界のアルツハイマー病の有病率を8.3%減少させることにつながるとされている(Norton er al)。、 2014)。さらに、認知症の発症を5年遅らせることで、罹患者数を50%近く減少させることができ(Sperling et al 2011)、公衆衛生に重要な影響を与えると考えられる。
疫学研究の系統的レビューでは、定期的な身体活動(主に座りっぱなしの行動ではなく)が認知症リスクに強く影響することが示唆されている(Hamer and Chida、 2009; Sofi er al)。 例えば、Hamer and Chida(2009)は、認知症ではない参加者163、797人を対象とした16件の前向き研究を含むメタアナリシスで、身体活動がすべてのタイプの認知症リスクを26%、アルツハイマー病リスクを45%低下させることと関連していることを示している。
しかし、無作為化対照介入では、運動の認知と脳への効果については混合した知見が報告されており、認知症に対する予防力に若干の疑問が投げかけられている(Müller et al 2017)。まとめると、現在の研究では、アルツハイマー病の前臨床段階および初期臨床段階では、介入がより有益であることが示されている(Forbes et al 2015; Brini et al 2018)。ほとんどの認知症症例の多因子性については、現在行われている大規模なマルチドメイン試験[MAPT(Andrieu et al 2017)、PreDIVA(van Charante et al 2016)、FINGER(Ngandu et al 2015)]では、生活習慣の介入が認知機能、ひいては認知症予防に及ぼす効果を調査している。これまでのところ、認知症リスクのある参加者の認知機能に対する有益な介入効果が明らかになったのはFINGER試験のみである(Ngandu et al 2015)。これらの効果が参加者の認知症の後の発症に影響を与えるかどうかはまだ明らかになっていない。実は、世界的な取り組みであるWorld Wide Fingersは、認知症予防研究を進めることを目的としている(Kivipelto et al 2018b)。
身体運動に対する個人の対応
数多くの疫学的研究、横断的研究、および介入研究は、定期的な身体活動が健康全般および特に脳の健康にプラスの効果をもたらし、認知症のリスクを低下させる可能性があることを示している(Hamer and Chida、 2009; Sofiら、 2011; Briniら、 2018; Liu-Ambroseら、 2018)。しかし、研究を詳細に分析すると、結果の個体間ばらつきが大きいことがしばしば明らかになる(Müller er al)。、 2018)。
身体運動に対する個人の反応は、1980年代以降、スポーツ科学において注目されてきた(Rankinen and Bouchard、 2008)。特に持久力や筋力トレーニングの文脈では、同一の運動やトレーニング変数に対する個人の生理的適応が異なることを示す強い証拠がある(Buford et al 2013年;Weatherwax et al 2016)。このような個人差の大きさに基づいて、人間は特定の運動に関して「反応する人」と「反応しない人」に分けられている(Buford er al 2013)。
ここでは、「応答者」とは利益を得る被験者と定義され、「非応答者」とは、同じ刺激の下でパフォーマンスが変化しないか、あるいは悪化する場合がある(Bouchard and Rankinen、 2001)。しかし、「レスポンダー」という用語は現在議論されているところである。
例えば、Booth and Laye (2010)は、いわゆる非応答者と呼ばれる人は、低い程度ではあるが訓練効果を示すという事実を考慮して、「非応答者」という用語を「低感度」という用語に置き換えるべきであると提案している。
個別化医療としての身体運動
個別化医療とは、遺伝学、人体統計学、バイオマーカー、環境などの個人差に基づいて、薬理学的な薬物治療や予防介入を行うアプローチのことである。これにより、「個別化医療」、「精密医療」、「個別化医療」という用語が同義語として用いられることが多い。特にがん領域では、長年にわたり個別化治療が成功している(Shin er al)。 現在では、認知症研究においてもこのアプローチが普及してきており、例えばHampelら(2017)。
スポーツ科学からの身体運動に対する生理的適応の個人間の多様性の観察に言及すると、「反応者」と「非反応者」の概念は、提案されている認知症に対する身体活動の神経保護・予防因子にも根本的な意味を持つと考えられる。
この点では、次のような疑問が生じる。
- (1) 身体的トレーニングに対する反応の個人間の大きな不均一性は、どのような要因によって引き起こされているのか?
- (2)個人の反応性によってすべてのアウトカムが等しく影響を受けるのか、
- (3)ほぼすべての人が効果を実感するように、非反応性を克服するにはどうすればよいのか、ということである。
以下では、これらの疑問について簡単に述べていく。
1.どのような要因が、フィジカル・トレーニングに対する反応の個人間の大きな不均一性の原因となっているのであろうか?
認知症(および他の疾患)のリスクと同様に、運動に対する個人の生理的反応は、付随する修正可能な要因(例えば、食事)と修正不可能な要因(例えば、遺伝学、性別;Bouchard and Rankinen、 2001; Rankinen and Bouchard、 2008; Booth and Laye、 2010; Sparks、 2017)によって調節されている。
後者については、現在のところ、150以上の遺伝的マーカーがエリートアスリートのステータス(Ahmetov et al 2016)およびトレーニングの反応(Bray et al 2009)と関連している。さらに、いくつかの一塩基多型がトレーニング反応に関連していることが確認された。
HERITAGE(HEalth、 RIsk factors、 exercise Training And Genetics)研究(Bouchardら、 1999; Timmonsら、 2010)の結果は、運動に対する生理学的反応の個人間変動が、他の原因の中で、遺伝的要因に基づいていることを示している。ここでは、21の一塩基多型がVO2ピーク変動の49%を占めていた(Bouchard et al 2011)。
興味深いことに、VO2ピークは高齢者の脳機能と関連している(Erickson et al 2009、2011)。Timmonsら(2010)は、VO2ピークを予測する29のRNAシグネチャーに基づく分子分類を提案しており、11の一塩基多型がVO2ピークの変動の23%を説明している。
しかし、パーソナライズされたレジスタンストレーニングのために遺伝的ベースのアルゴリズムを使用した介入研究は1件のみである(Jones et al 2016)。全体として、遺伝子型と運動応答の間の関連性のいくつかの側面はまだ不明である(Mann et al 2014)。
2.すべてのアウトカムは、個人の応答性の状態によって等しく影響を受けるのであろうか?
抵抗力トレーニングと持久力トレーニングの両方とも、個人間で結果に大きな差があり、さらに、個人内では、異なる変数間で結果に一貫性がないことが多く、同じ人がある領域ではトレーニングによって誘導された効果を示し、他の領域では効果がないことがある(Vellers er al 2018)。
例えば、12週間のレジスタンストレーニングを行った後、Hubalら(2005)は、若年成人の平均的な筋サイズと筋力が増加したと報告している。しかし、よく見ると、筋サイズの増加は-2~+59%、筋力の増加は-32~149%の間で変動していることがわかる。同様の結果は、持久力介入に続いて報告されている(Bouchard et al 1999; Bouchard and Rankinen、2001)。
さらに、Karavirtaら(2011)は、高齢者を対象とした持久力と筋力の複合トレーニングに対する個人の反応の幅の広さを観察した。21週間の介入後、心肺体力(VO2ピーク)の向上は-8~42%、筋力(最大等尺性両脚伸展)の向上は-12~87%と幅があった。
他の試験では、若年者(Kohrt et al 1991;BouchardおよびRankinen、2001)および高齢成人(Chmelo et al 2015;Ross et al 2015)における運動訓練に対するVO2ピーク応答に関して、同様の個人間不均一性が示されている。
さらに、他の心呼吸器(例えば、血圧、労働負荷時の心拍数)および代謝(例えば、インスリン感受性、コレステロール)パラメータもまた、運動への適応において強い個人間差を示している(Bouchard and Rankinen、 2001; Fritz er al)。 この個人差は、運動が認知症の神経保護や予防に及ぼす影響に根本的な影響を与える可能性がある。
これらの危険因子に対する身体運動の反応がない場合、認知症リスクに対する身体運動のプラスの効果を回避する可能性がある。性別(Barha et al 2017a)またはAPOE(Berkowitz et al 2018)のような他の側面が身体活動の効果に影響を与える可能性がある。
それにより、心血管、神経筋、およびバランストレーニングは、高齢者における認知パフォーマンスおよび神経可塑性を異なる形で改善する(Voelcker-Rehage et al 2011; Voelcker-RehageおよびNiemann、2013; Levin et al 2017)。認知機能に対する身体運動介入後の個体間変動に関する研究は少ない。
Heiszら(2017)は、6週間の運動、認知機能、または複合トレーニングにより、若年成人の記憶機能の全般的な改善がもたらされたと報告している。より詳細には、心血管系の改善が大きかった個体は、脳由来神経栄養因子(BDNF)とインスリン様成長因子-1(IGF-1)のレベルの増加も大きかった。
さらに、複合トレーニング群で運動に高い反応を示した人は、運動単独の場合と比較して記憶力が向上していた。
3.このような個人間の不均一性をどのように説明すれば、(ほぼ)すべての個人で最適な結果を得ることができるのであろうか?
臨床的に関連性のある「非反応者」または「低感受性者」のグループが存在するという仮説に続いて、与えられた運動プログラムの変更(例:運動の種類、運動時間、運動量、運動強度)がトレーニング効果の欠如を克服できるかどうかという問題が提起されている。
現在行われている研究の中には、運動強度および/または運動量を増加させることによって、非反応状態を緩和できることを示すものもある(Bonafiglia et al 2016;Lundby et al 2017;MonteroおよびLundby、2017)。
例えば、MonteroとLundbyは、週に1~2回しかトレーニングを行わない場合よりも、週に4~5回トレーニングを行った場合の方が、非反応者の割合が低いことを示している。認知機能への影響については、最適な用量と反応の関係はまだほとんどわかっていない。脳機能に対するトレーニング効果のメディエーターとして考えられるのは、異なる経路で神経可塑性を高めるBDNFである(Brigadski and Leßmann、 2014)。
BDNFの排泄は乳酸によって誘導され(Schiffer et al 2011)、末梢血乳酸値は認知機能の改善と相関することも示されている(Lee et al 2014年;Tsukamoto et al 2016)。したがって、運動介入は、乳酸、およびその結果としてBDNFを増加させるのに十分な集中的なものでなければならない。
しかし、特に高齢者においては、古典的な運動介入は、乳酸塩の蓄積と関連する第二換気閾値(VT2)レベルを達成することはほとんどない。高強度インターバルトレーニング(HIIT)を高強度かつ低負荷で行うことは、より多くの反応者を獲得するための方法であると考えられる。
高齢者や慢性疾患の患者であってもHIITトレーニング戦略のポジティブな効果と安全性については、かなりのエビデンスが蓄積されている(Ross et al 2016)(例:慢性心不全、COPD、糖尿病)。
今後の推奨事項
実際、個別化医療は、医療用医薬品に対する個人の反応の異質性に第一の関心事である。しかし、個別化された予防運動戦略の必要性も急務である(Buford et al 2013; Berkowitz et al 2018)。これにより、個別化された運動プログラムは、トレーニングの効率を高め、より多くの個人でより多くのアウトカム変数を改善することができるだろう。
今後の介入研究では、遺伝子解析により、潜在的な “反応者 “と “非反応者 “を特定するのに役立つ可能性がある。さらに、個別化された運動トレーニングプログラムは、特に個人の特定の弱点を特定するために、複雑なパフォーマンス分析に基づくべきである。
提案されたパーソナライズされた運動プログラムのより詳細な推奨事項を提供し、ワンサイズフィットオールのアプローチを克服するためには、さらなる研究が必要である(Barha er al)。、 2017b)。
