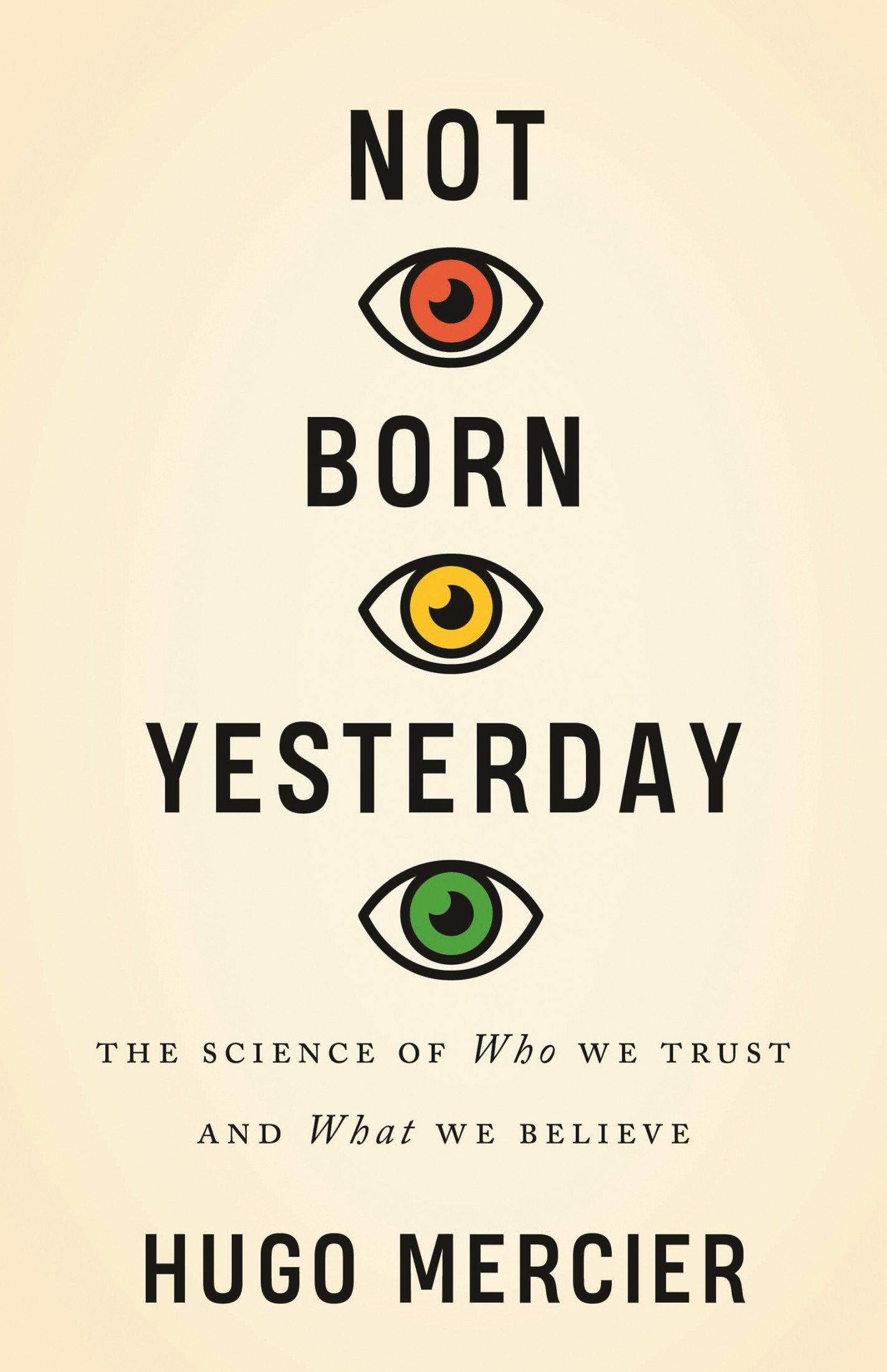
目次
- 図版のリスト
- 謝辞
- 序論
- 1 「騙されやすさ」の根拠
- 2 コミュニケーションにおける警戒心
- 3 オープンマインドの進化
- 4 何を信じればいいのか?
- 5 誰が一番知っているのか?
- 6 誰を信じればいいのか?
- 7 何を感じればいいのか?
- 8 デマゴーグ、預言者、説教者
- 9 プロパガンディスト、キャンペーナー、アドバタイザー
- 10 心ときめくうわさ 146
- 11 回りくどい報告から超自然的な信仰へ
- 12 魔女の告白とその他の有用な不条理
- 13 無益なフェイクニュース
- 14 浅はかな教祖たち
- 15 怒れる識者と巧みな詐欺師
- 16 「騙されやすさ」に対するケース
- ノート
- 参考文献
- 索引
図版のリスト
- 図1 アッシュ適合性実験における線。
- 図2 Randall Munroeによるウェブコミックxkcdの「Bridge」ストリップ。
- 図3 パレイドリアの2つの例:何もないところに顔が見える。
- 図4 矢印の方向に発射されたボールがチューブを出るとき、どのような経路をたどるのか?
謝辞
本書の構想は、Dan Sperber、Fabrice Clément、Christophe Heintz、Olivier Mascaro、Gloria Origgi、Deirdre Wilson、そして私によって書かれた論文「Epistemic Vigilance」からきている。この論文で私たちは、人間には伝達された情報を評価するための認知メカニズムが備わっていることを示唆した。特に、Dan Sperberに感謝している。彼は、論文の指導教官であり、共著者であり、指導者であり、友人だ。彼の著作や議論を通じて私の考えを形成してくれただけでなく、彼は辛抱強くこの本を読み、フィードバックをくれた。ファブリス・クレマンは、同じテーマで博士論文と『信憑性のメカニズム』(Les Mécanismes de la crédulité)を書いており、私がヌーシャテル大学の博士研究員だったころ、この問題について議論した。ダンとファブリス以外にも、2018年から2019年にかけての「コミュニケーション・信頼・論証」クラスの学生からのフィードバックや、パリのENSの認知研究科、ペンシルバニア大学、そして私が「人間は騙されない」と悪口を言った無数の会議、レストラン、居酒屋、カフェでの議論によって、本書のアイデアは形成されてきた。ライラ・サン・ロケは、デュナの間で証拠となる素晴らしい使用例を惜しみなく教えてくれたし、私はクリス・ストリートの嘘発見に関する文献の知識から恩恵を受けることができた。
原稿の全体または一部についてコメントを寄せてくださった方々に深く感謝する: Sacha Altay(2回!)、Stefaan Blancke、Pascal Boyer、Coralie Chevallier、Thérèse Cronin(同じく2回!)、Guillaume Dezecache、Helena Miton、Olivier Morin、Thom Scott-Phillips、Dan SperberそしてRadu Umbres。
この本は、私のエージェントであるジョンとマックス・ブロックマン、最初からこのプロジェクトを信じ、非常に貴重なフィードバックをくれた編集者のサラ・カロ、そしてプリンストン大学出版局のチームなしには存在し得なかっただろう。
また、Direction Générale de l’Armement(特にDidier Bazalgetteに感謝)、ペンシルバニア大学の哲学・政治・経済学プログラム(Steven F. Goldstoneの寛大な支援)、ヌーシャテル大学の認知科学グループ、スイス国立科学財団(Ambizione grant no. PZ00P1_142388)、国立研究開発庁(DECにEUR FrontCog ANR-17-EURE-0017、自分にANR-16-TERC-0001-01)、そして最後になったが、現在の雇用主である国立科学研究センターは、ジャンニコド研究所という素晴らしい場所で仕事をさせてくれている。特に、私が所属する「進化と社会的認知」チームは、ジャン・バティスト・アンドレ、ニコラ・ボマール、コラリー・シュヴァリエ、オリヴィエ・モラン、そして学生、エンジニア、ポスドクからなり、望みうる最高の社会環境と知的環境を提供してくれている。
両親、祖父母、そして親戚の方々の揺るぎないサポートに、感謝の念を禁じ得ない。クリストファーとアーサーは、世界で最も優秀な男の子である。彼らは私に愛について多くのことを教えてくれた。また、私たちがもう少し簡単に影響させたいと願っていても、子どもは騙されないということも教えてくれた。テレーズの励ましは、私にとっては伝えきれないほどの意味がある。本当にありがとう。
はじめに
ある日、私が大学から歩いて帰っていると、立派な中年男性に声をかけられた。彼は地元の病院に勤める医者で、急ぎの用事があるのだが、財布をなくしてしまい、タクシー代もない、という話だった。彼は20ユーロがどうしても必要だった。彼は私に名刺を渡し、その番号に電話すれば、秘書がすぐにお金を振り込んでくれると言った。
さらに説得して、私は20ユーロを渡した。
このような名前の医者はいないし、電話の先には秘書もいない。
私はなんと愚かだったのだろう。
そして、20年後、私は「人は騙されない」と主張する本を書くことになるとは、何とも皮肉なものである。
騙されやすさの根拠
私が騙されやすいと思うなら、この後に続くページで、地球は「ゲーム・オブ・スローンズ」風に200フィートの氷の壁に囲まれた平らな円盤であると信じている人々1、魔女は魔法の矢で家畜を毒殺し、地元のユダヤ人は過越祭の儀式として少年を殺してその血を飲む、民主党高官工作員はピザ屋から小児性愛組織を監督する、北朝鮮の元リーダー金正日がテレポートし天候をコントロールできると信じる、前米国大統領のバラク・オバマが「騙されやすい」と信じる人々に会うまで待ってみよう。オバマ前大統領は敬虔なイスラム教徒である。
テレビ、本、ラジオ、パンフレット、ソーシャルメディアなどを通じて発信され、多くの人々に受け入れられている戯言の数々を見てほしい。私たちが騙されやすいわけではない、読んだり聞いたりするものを受け入れないと主張できるわけがない。
広範な信憑性に反論することは、私を少数派に追いやることになる。古代ギリシャから21世紀のアメリカまで、最も進歩的なものから最も反動的なものまで、長い歴史の中で、多くの人々は絶望的に騙されやすいとされてきた。有権者はデマゴーグに従順に従う、群衆は血気盛んな指導者によって暴れまわる、大衆はカリスマ的な人格に屈服する、などである。20世紀半ばには、心理学的な実験によって、参加者が権威に盲従し、自分の目で見た明確な証拠よりも集団を信じるという結果が得られ、この粉塵はさらに増えた。この数十年の間に、人間の騙されやすさを説明する洗練されたモデルが次々と登場した。つまり、人間は他者から学ぶべきことが非常に多いにもかかわらず、誰から学ぶべきかを見極めることが非常に難しいため、「多数派に従う」「著名な人に従う」といった単純なヒューリスティクスに頼ってしまう。人類が種として成功したのは、たとえその過程で不適応な慣習や誤った信念を受け入れることになったとしても、その土地の文化を吸収する能力があったからだ。
本書の目的は、これがすべて間違いであることを示すことである。私たちは、たとえそれが人口の大多数や著名なカリスマ的存在によって支持されていたとしても、言われたことを何でも素直に受け入れてはいない。それどころか、私たちは誰を信じ、何を信じるべきかを見極めることに長けており、どちらかといえば、私たちは影響を与えやすいというよりも、与えにくすぎる。
騙されやすさへの反論
たとえ暗示性が、文化的環境からスキルや信念を獲得するのに役立つという利点があるとしても、第2章で論じるように、安定的で持続的な状態にするにはコストがかかりすぎる。他人が何を伝えても受け入れることができるのは、その人の利益が私たちの利益と一致する場合に限られる。人間同士のコミュニケーションに限って言えば、そのような利害の一致はめったにない。妊娠中の母親でさえ、胎児が発する化学的シグナルに不信感を抱く理由がある。幸いなことに、敵対する関係であっても、コミュニケーションを成立させる方法はある。獲物は、肉食動物に追いかけないように説得することができる。しかし、このようなコミュニケーションを実現するためには、シグナルを受け取った人がそれを信じた方が良いという強い保証が必要である。メッセージは、全体として、正直でなければならない。人間の場合、誠実さは、伝達された情報を評価する一連の認知メカニズムによって維持されている。これらのメカニズムにより、私たちは、有益なメッセージは受け入れ、オープンである一方、有害なメッセージは拒否し、警戒することができる。そのため、私はこれを「オープンな警戒メカニズム」と呼び、本書の中核をなしている2。
多くの学者が騙されやすさを論証するために用いている「観察」はどうだろうか。そのほとんどは、一般的な誤解に過ぎない。第8章と第9章で検討した研究が示すように、デマゴーグから広告主、説教師から選挙工作員まで、大衆を説得しようとする者は、ほとんど常に惨敗する。中世ヨーロッパの農民は、キリスト教の戒律に頑なに抵抗し、多くの司祭を絶望に追いやった。チラシの送付、ロボコール、その他の選挙工作が大統領選挙に与える正味の効果は、ほとんどゼロに近い。全能と思われていたナチスのプロパガンダは、ほとんど聴衆に影響を与えず、ドイツ人にナチスを好きになってもらうことさえできなかった。
しかし、そうではない。それでも、確かに、人は時として、最もばかげた見解を公言するようになる。私たちが説明しなければならないのは、そのパターンである。ある考え(良い考えも含む)が伝わりにくい一方で、ある考え(悪い考えも含む)がこれほどまでに人気があるのはなぜか。
開かれた警戒のメカニズム
コミュニケーションの成功と失敗を理解する鍵は、私たちの開放的な警戒のメカニズムを理解することにある。このメカニズムは、さまざまな手がかりを処理して、私たちが言われたことをどの程度信じるべきかを教えてくれる。あるメカニズムでは、メッセージが、私たちがすでに真実だと信じていることと矛盾しないかどうか、また、正しい論拠に支えられているかどうかが調べられる。また、メッセージの発信源に注目するメカニズムもある: 発言者は信頼できる情報を持っていそうか、私の利益を第一に考えてくれているか。発言者が信頼できる情報を持っているか、発言者は私の利益を考えているか、発言者が間違っていると証明した場合、私は発言者に責任を負わせることができるか。
私は、実験心理学から、小さな子どもや赤ちゃんも含めて、私たちの開放的な警戒のメカニズムがいかにうまく機能しているかを示す、豊富な証拠をレビューする。私たちがほとんどの有害な主張を拒否するのは、こうしたメカニズムのおかげである。しかし、これらのメカニズムは、私たちがいくつかの間違った考えを受け入れる理由も説明している。
その洗練された能力、そして新しい情報を学び、取り入れる能力にもかかわらず、私たちの開放的な警戒のメカニズムは、無限に変化するわけではない。読者の皆さんは、祖先が進化させてきた情報環境とは無数の点で異なる情報環境に置かれている。あなたは、会うことのない人(政治家、有名人)、自分に関係のない出来事(遠い国の災害、最新の科学の進歩)、訪れることのない場所(海の底、はるか彼方の銀河系)に関心を寄せている。「エルビスは死んでいない」という噂は誰が流したのか?両親の宗教観の源は何なのか。私たちの祖先にとって実用的な関連性がまったくない見解に判断を下すよう求められている: 地球の形はどうなっているのか、生命はどのように進化したのか、大規模な経済システムを組織する最善の方法は何か。もし私たちの開放的な警戒のメカニズムが、この勇敢で新しい、そして明らかに奇妙な世界で完璧に機能したとしたら、それは本当に驚くべきことである。
現在の情報環境は、開かれた警戒のメカニズムを快適な領域から押し出し、間違いを引き起こす。全体として、私たちは、気候変動の現実からワクチン接種の有効性に至るまで、不正確なメッセージを受け入れるよりも、価値あるメッセージを拒否する傾向が強い。このパターンの主な例外は、オープンな警戒心自体の失敗というよりも、その根拠となる資料の問題から生じている。人は、自分の知識、信念、直感を駆使して、言われたことを評価するのが賢明である。しかし、残念ながら、ある領域では、私たちの直感はかなり体系的に間違っているようだ。もしあなたが他に何も持っていなくて、誰かが「あなたは(例えば地球ではなく)平らな表面に立っている」と言ったとしたら、あなたは自然にそれを信じてしまうだろう。もしあなたが他に何も持っていなくて、誰かがあなたの祖先はいつもあなたによく似ている(例えば魚のようには見えない)と言ったとしたら、あなたは自然にそれを信じるだろう。一般的でありながら間違った信念の多くは、説得の達人に押されたからではなく、根本的に直感的なものであるために広まっている。
地球の平坦さが直感的であるなら、高さ200フィート、長さ数千マイルの氷の壁は直感的ではない。また、金正日のテレポート能力もそうだ。安心できることに、最も突飛な信念は、名目上受け入れられているに過ぎない。平地球の人が、海の果てで200フィートの氷の壁に遭遇したら、きっとショックを受けるだろう。金正日がスタートレック風に転送されるのを見たら、独裁者の最もひれ伏したおべっか使いが混乱することだろう。このような信念がなぜ広まるのかを理解するための重要な問題は、なぜ人々がそれを受け入れるのかではなく、なぜ人々がそれを公言するのかということである。正確な見解と思われるものを共有したいだけでなく、信念を公言する理由はたくさんある:印象づけたい、困らせたい、喜ばせたい、誘惑したい、操りたい、安心させたい。これらの目的は、現実との関係が単純でない発言や、場合によっては真実と正反対の発言をすることで達成されることもある。このような動機に直面すると、オープンな警戒体制は、逆に最も妥当な意見ではなく、最もあり得ない意見を特定するために使用されるようになる。
最も直感的なものから最も荒唐無稽なものまで、ある間違った見解がなぜ流行するのかを理解したいのであれば、オープンビジランスの仕組みを理解しなければならない。
まとめ
本書の終わりには、何を信じ、誰を信頼するかを決める方法について理解しているはずだ。広告や布教といったありふれたものから、洗脳やサブリミナルといった極端なものまで、大衆を説得しようとする試みのほとんどが、いかに惨めに失敗しているかを知ることができるはずだ。なぜ(ある)間違った考えが広まり、(ある)価値ある洞察が拡散しにくいのか、そのヒントが得られるはずだ。私がかつて偽医者に20ユーロを渡した理由も理解できるはずだ。
この本の主張の核心を受け入れてくれることを期待している。でも、どうか私の言葉を鵜呑みにしないでほしい。自分の読者が間違っていると証明されるのは嫌だからだ。
第1章 騙されやすさの根拠
何世紀もの間、人々は多くの奇妙な信念を受け入れ、非合理的な行動をとるように説得されてきた(あるいは、そのように見える)。こうした信念や行動が、「大衆は騙されやすい」という考えに信憑性を持たせてきた。実際には、この話はもっと複雑だと思う(あるいは、次の章で見るように、まったく違う話もある)。しかし、私はまず「騙されやすさ」の事例を整理することから始めなければならない。
紀元前425年、アテネはスパルタと互いに破壊的な戦争を何年も続けていた。ピロスの海戦で、アテネの海軍と陸軍はスパルタの軍隊をスファクテリア島に閉じ込めることに成功した。スパルタの幹部は、捕虜の中に自国のエリートが多数含まれていることを知り、アテネに有利な条件を提示して講和を求めた。しかし、アテネ側はこれを拒否した。戦争は続き、スパルタは再び優位に立ったが、前421年に(一時的な)平和条約が結ばれたとき、その条件はアテネにはるかに不利なものであった。この失態は、アテネの一連のひどい決断の一つに過ぎなかった。征服された都市の市民を皆殺しにするという道徳的に好ましくないものもあれば、シチリアへの絶望的な遠征を開始するという戦略的に悲惨なものもあった。結局、アテネは戦争に敗れ、かつての力を取り戻すことはなかった。
1212年、フランスとドイツの「多数の貧民」が、異教徒と戦い、エルサレムをカトリック教会のために取り戻すために十字架を背負った1。若者たちはサン・ドニに到着し、大聖堂で祈り、フランス国王に会い、奇跡を願った。奇跡は起きなかった。訓練も受けず、資金もなく、組織化もされていない未熟児の軍隊に何が期待できるだろうか。それは、エルサレムに到達した者はおらず、途中で多くの者が死んだということである。
18世紀半ば、南アフリカの牧畜民であるホーサ族は、新たに導入されたイギリスの支配下で苦しんでいた。18世紀半ば、南アフリカの牧畜民であるホーサ族は、イギリスの支配下に置かれ、苦しんでいた。ホーサ族の中には、牛を殺し、作物を焼けば、幽霊軍隊ができ、イギリスを撃退できると考えた者がいた。彼らは何千頭もの牛を犠牲にし、畑に火を放った。しかし、幽霊のような軍隊は生まれなかった。イギリスは留まった。ショサ族は死んだ。
2016年12月4日、エドガー・マディソン・ウェルチは、アサルトライフル、リボルバー、ショットガンを持って、ワシントンDCのコメット・ピンポン・ピッツェリアに入った。彼はレストランを襲うためにそこにいたわけではない。地下に人質になっている子供がいないか確認するためだった。クリントン夫妻(元米大統領夫妻、当時大統領選挙中)が性売買組織を運営しており、コメット・ピンポンはその隠れ家の一つだという噂があったのである。ウェルチは逮捕され、現在、実刑判決を受けている。
盲目的な信頼
大衆に対して優越感を抱いている学者は、こうした疑問のある決断や奇妙な信念を、人間の過剰な信頼体質、つまり、大衆がカリスマ的指導者をその能力や動機にかかわらず本能的に支持し、聞いたことや読んだことをその妥当性にかかわらず信じ、たとえそれが災いをもたらすとしても大衆に従うような体質だと説明することがある。この「大衆は信用できる」という説明は、歴史上非常に大きな影響力を持つことが証明されているが、やがて明らかになるように、それは見当違いである。
なぜアテナイはスパルタとの戦争に負けたのか?ペロポネソス戦争の記録者であるトゥキュディデスに始まり、多くの論者は、「大衆に非常に強い」寄生虫であるクレオンのようなデマゴーグの影響を非難し、彼は戦争の最悪の失策のいくつかについて責任があるとみなされた2。プラトンにとって、多数による支配は、「暴徒を完全に自由に使える」指導者を不可避的に生み出し、暴君と化してしまうのである3。
なぜ、大勢の若者が家を捨ててまで、遠く離れた土地を侵略しようとしたのだろうか。彼らは、教皇イノセント3世が始めた新しい十字軍の呼びかけに応えていたのであり、その信憑性は、魔法の笛を聞いたすべての子供たちに絶対的な力を与えるハーメルンの笛吹き男の伝説に触発されていたのである4.人々の十字軍は、啓蒙主義において、「人類を奴隷の群れとして(専制君主や暴君の)手に渡し、彼らが自由に処分できるようにした」とキリスト教会を非難したホルバッハ男爵のような人物による告発を説明するのにも役立つ5。
なぜ、ショサ族は家畜を殺したのか?その100年前、フランス啓蒙主義の中心人物であるコンドルセ侯爵は、小規模社会の構成員が「最初の騙され者の信憑性」に苦しみ、「偽医者と魔術師」を信じすぎていると示唆した6。彼らは、イギリスと戦うために死者が蘇るという幻を見た若い預言者ノンカウセに引き取られ、「誰も困った生活を送ることはないだろう」という新世界を見た。人々は欲しいものを何でも手に入れることができる。7誰がそれにノーと言うだろうか?どうやら、ショサ族は違うようだ。
なぜエドガー・マディソン・ウェルチは、刑務所の危険を冒してまで、存在しない子供たちを無害なピザ屋の存在しない地下室から引き渡したのだろうか。彼は、アレックス・ジョーンズというカリスマ的なラジオ司会者の話を聞いていた。アレックスは、悪魔崇拝者によるアメリカ乗っ取りから政府による災難まで、最もクレイジーな陰謀論を専門としている8。一時期、ジョーンズは、クリントン一家とその側近が、子供を性的に売買する組織を率いているという考えを取り上げていた。ワシントン・ポスト紙の記者は、ジョーンズとその仲間たちが荒唐無稽な理論を売り込むことができるのは、「騙されやすさがその市場を作り出すのに役立つからだ」と述べている9。
これらの観察者は皆、人々がしばしば信憑性に富み、根拠のない議論を容易に受け入れ、日常的に愚かで費用のかかる行動をとるよう説得されることに同意する。実際、根本的に異なる思想家をこれほどうまく結びつける思想は、なかなかない。無神論者は、神が何であれ、宗教的な説教に従う人々の「ほとんど超人的な騙されやすさ」を指摘する11。陰謀論者は、公式ニュースを受け入れる「マインドコントロールされた羊たち」に優越感を覚える12。デバンカーは、陰謀論者が怒れるエンターテイナーによって売りつけられた高い物語を信じることを「超がつくほど騙されやすい」と考えている13。保守派の作家は、恥知らずなデマゴーグに突かれ、伝染する感情によって狂わされて反乱する大衆を、犯罪的信憑性によって非難する。旧来の左翼は、大衆の受動性を支配的なイデオロギーを受け入れることによって説明する: 個人は抑圧を自分の人生として 「自由に」生きる。「本来の本能的な欲求」に基づいて行動するのではなく、自分が欲するはずのものを欲するのだ」14。
歴史の大半において、広範な信憑性という概念は、社会を理解する上で基本的なものであった。人々は容易にデマゴーグに取り込まれるという仮定は、古代ギリシャから啓蒙主義に至るまで西洋思想に貫かれており、「政治哲学が民主主義に懐疑的であることの中心的理由」となっている15。現代の論者たちは、政治家が「人々の騙されやすさに迎合する」ことによって有権者を簡単に動かしてしまうことを今でも嘆く16。しかし、人々が簡単に影響を受けることができるということは、1950年代から社会心理学者の行ったいくつかの有名な実験のように(一見)うまく説明されていない。
騙されやすさの心理学者
最初に登場したのはソロモン・アッシュである。彼の最も有名な実験では、人々にある簡単な質問に答えてもらった:図1に描かれた3本の線のうち、最初の線と同じ長さの線はどれか。しかし、参加者は30%以上の確率で間違えてしまった。なぜ、このようなあからさまな誤答をするのだろうか。参加者一人ひとりに意見を求める前に、すでに何人かの参加者が回答していた。この参加者は、本人が知らないうちに、実験者が仕組んだ自作自演の参加者だったのである。ある試行では、この合議体の全員が1つの不正解に同意した。この合議体は、参加者にとっては何の力もなく、しかも明らかに間違った答えを出している。しかし、60%以上の参加者が、少なくとも一度は、そのグループの誘導に従うことを選択したのである。社会心理学者のセルジュ・モスコヴィッチ(Serge Moscovici)が書いた教科書は、この結果を「現実と真実に背を向けることを自覚していても、盲目的に集団に従うという適合性の最も劇的な説明の1つ」と表現している18。
図1 アッシュの適合性実験における線。出典:Wikipedia ウィキペディア
ソロモン・アッシュの後に登場したのがスタンリー・ミルグラムである。ミルグラムの最初の有名な研究は、アッシュの実験と同じく、適合性の研究であった。彼は、何人かの学生に歩道に立ち、ビルの窓を見るように指示し、通りすがりの人が何人真似をするかを数えた。19 十分な数の学生が同じ方向を見たとき(臨界集団サイズは約5人だったようだ)、通りすがりの人のほぼ全員が学生に従ってビルを見るようになった。まるで、人は群衆に従わずにはいられないかのようであった。
しかし、ミルグラムは、後に行われた、より挑発的な実験で最もよく知られている20。この研究では、参加者は、表向きは学習に関する研究に参加するよう求められた。実験室では、参加者はもう一人の参加者に紹介されるが、この人もまた、実は共犯者であった。実験者は、2人のうち1人をランダムに選んで学習者にするふりをした。そして参加者は、「電気ショックを避けたいという動機がある人の方が学習能力が高いかどうかを調べる研究である」と告げられた。学習者は単語のリストを暗記しなければならず、間違えると参加者に電気ショックを与えるように指示される。
参加者は、次第に高電圧になる電気ショックに対応する一連のスイッチがある大きな機械の前に座った。共犯者は少し離れた実験ブースに案内されたが、参加者はマイクを通して彼の声を聞くことができた。最初はうまく単語を覚えていたが、課題が難しくなるにつれてミスをするようになった。そこで実験者は、被験者にショックを与えるように促したところ、全員がショックを与えた。最初のスイッチでは「軽い衝撃」と判定されたからだ。被験者がミスを繰り返すので、実験者は被験者に電圧を上げるよう促した。そして、「軽い衝撃」、「中程度の衝撃」、「強い衝撃」、「非常に強い衝撃」とスイッチを変えていくが、参加者全員がスイッチを切り続けた。最後の「強い衝撃」である300ボルトのスイッチを押したとき、数人の参加者が拒否した。その間、被験者はずっと不快感をあらわにしていた。ある時、彼は苦痛に吠え始め、参加者たちに「ここから出してくれ」と懇願した!ここから出してくれ!ここで私を拘束することはできない!21彼は、心臓に問題があるとまで言っている。しかし、参加者の大半はそのまま続けた。
「極度の衝撃」シリーズが始まると、さらに数人の参加者が止まった。ある参加者は、スイッチに「危険:激しいショック」と表示されても、続行することを拒否した。この段階で、監禁者は叫び声を止め、解放を懇願していただけだった。その後、彼は完全に無反応になった。しかし、それでも参加者の3分の2が最後の2つのスイッチ、435ボルトと450ボルトのスイッチを押すのを止めなかったのである。ミルグラムは、一般的なアメリカ市民のかなりの大多数に、痛みに悶えて慈悲を乞うている(と思われる)仲間に、致命的と思われる電気ショックを与えるように仕向けたのである。
このような結果や、同様の現象を証明するかのような歴史的事例の数々を知ると、政治哲学者のジェイソン・ブレナンが指摘した「人間は真実や正義を求めるのではなく、合意を求めるようにできている」という言葉に納得せざるを得ない。権威に過度に媚びへつらう。画一的な意見の前には怯える。心理学者のダニエル・ギルバートとその同僚も同じ意見 人間は疑い深いよりも騙されやすいということは、おそらく「人間に生まれつき備わっている最初の、そして最も一般的な観念の中に数えられるべき」である。23
人間が生まれつき信じやすいと考えるなら、当然の疑問として、次のことが問われる:なぜだろう?紀元前500年、ギリシャで最初に記録された哲学者の一人であるヘラクレイトスは、すでにこう考えていた:
群衆の中で、自分たちがどれほど多くの愚か者や泥棒の中にいて、どれほど善良な者を選ぶ者が少ないかを考えずに、演説者に導かれるままにする人々の知恵は、何の役に立つのだろうか24。
ヘラクレイトスの言葉は、2500年後、BBCのこの見出しによって、詩的ではないが、より簡潔な形で反響を呼んだ: 「なぜ人々は信じられないほど騙されやすいのか」25。
適応的信憑性
社会心理学者が人間の信憑性を実証しようと躍起になっているとすれば、人類学者はそのほとんどを当然のこととして受け止めてきた26。多くの人々は、伝統的な信念や行動が持続することは問題ないと考えてきた。論理的には、人類学者は、前世代の知識や技術を受け継ぐだけの存在であるはずの子どもたちに、ほとんど関心を払ってこなかったのである27。
この文化伝播のモデルは、その単純さゆえに、人々がなぜ信用するのか、つまり、先祖の何世代にもわたって獲得された知識や技術を学ぶということを理解するのに役立つ。生物学者のリチャード・ドーキンスは、「プログラムされた子供の騙されやすさ」を、「言語や伝統的な知恵を学ぶのに有用である」30と説明している。
魔術の信仰や足縛りなど、年長者から受け継ぎたくない「伝統的な知恵」を思い浮かべるのは簡単だが、こうした有害な習慣は例外的である。全体として、文化的に獲得された信念のほとんどは、十分に賢明なものである。私たちは毎日、数え切れないほど多くの文化的影響を受けた行動をしている。例えば、言葉を話すことはもちろん、歯を磨くこと、服を着ること、料理をすること、買い物をすること、などなど。
考古学的、人類学的な証拠からも、文化的スキルは非常に長い間、人類の生存に不可欠であったことがうかがえる。小規模な社会では、採集、狩猟、食料加工、衣服の製作、生存に不可欠なさまざまな道具の製作など、伝統的な知識やノウハウに頼っている31。
この文化伝播の「ファックスモデル」の単純さが、周囲の文化から学ぶことの多くの利点を際立たせているとすれば、その限界もまた明らかだ。ひとつは、最も小さく、最も自己完結的な社会にさえ存在する文化の多様性の程度を、圧倒的に過小評価していることである。例えば、儀式など、集団のメンバー全員が非常によく似た方法で行う行動もあれば、ほとんどの活動には大きな違いがある。すべてのハンターが足跡から同じ教訓を得るとは限らない。すべての採集者がベリーを見つけるための同じテクニックをもっているわけではない。すべての芸術家が同じように魅力的な歌や彫刻、絵を描くわけでもない。そのため、先代を盲目的にコピーしようとする個人でさえも、決断を迫られるの 誰の真似をすればいいのか?
この問いに答える最も先進的な枠組みの一つが、人類学者のロバート・ボイドと生物学者のピーター・リチャーソンによって作られた32。遺伝子と文化の共進化と呼ばれるこの理論は、人類の進化の過程で遺伝子と文化が互いに影響し合ってきたことを示唆している。特にボイドとリチャーソンは、文化が人類の生物学的進化を形成してきたと主張している。もし、自分の文化のどの部分をコピーするかを選択することがそれほど重要であるならば、私たちは自然選択を通じて、この問題をできるだけ効果的に解決するためのメカニズムを進化させてきたはずだ。私たちはすでに、周囲の環境を広く正確に把握する、食べられるものを選ぶ、捕食者を避ける、仲間を集める、友人関係を築くなど、祖先が直面したさまざまな問題に取り組む気質を進化させてきた33。
誰から学ぶべきかという問題を解決するには、まず、誰が優れた業績を上げているかを見ることから始めることができる。アレックスは料理が上手、ルネは人間関係を良好に保つのが上手、そんな人たちから学べばいいのである。しかし、このように問題を絞り込んでも、模倣すべき行動の可能性はたくさん残されている。では、なぜアレックスがあのような料理を作ることができたのか、その理由を探るにはどうすればよいのだろうか。直感的に、髪型のせいではないだろうと推測することはできるが、材料や調理時間といったわかりやすいものから、タマネギの種類やご飯のかき混ぜ方など、さまざまな可能性が考えられる。ある料理人のレシピを再現してみるとわかるのだが、成功の決め手は時として非常に不透明なものなのである34。
人類学者のジョー・ヘンリッチや生物学者のケビン・ラランドなど、ボイド、リチャーソンとその同僚たちは、他者からよりよく学ぶために、人間には文化的学習を導くための一連の大まかな経験則が備わっていると提案している35。成功者の行動のどれが成功の原因なのか、例えば、アレックスはなぜある料理をうまく作ることができたのか、ということを見分けるのは難しいかもしれない。だから、成功者の行動や考え方を、外見や髪型に至るまで無差別にコピーする方が安全なのかもしれない。これを成功バイアスと呼ぶことにする。
このバイアスは、もし各個人が価値ある情報を得るための独立した能力を持っているならば、広く受け入れられている考えや行動は、採用する価値があると思われるという合理的な仮定に基づいて意味をなす。
このようなヒューリスティックは、他にも数多く想像できる。例えば、Henrichと同僚のFrancisco Gil-Whiteは、成功バイアスを改善するために適合性バイアスのバリエーションを使用することを提案している37。例えば、小規模な社会では、どのハンターが最も多くの獲物を運んでくるかは、日によって大きく異なる38。このような統計的なノイズの中で、私たちはどのようなハンターを真似るべきかを決めることができるのだろうか。多くの人がある個人を尊敬しているのであれば、つまりその個人が名声を持っているのであれば、その人を模倣することは価値があるかもしれない。ヘンリックとギル=ホワイトは、このような威信のバイアスは非常に適応的であると考えた。
Boyd、Richerson、Henrichらは、大まかなヒューリスティックに依存することで、個人が周囲の文化を最大限に活用できることを示す高度なモデルを構築している。このようなヒューリスティックのもう一つの利点は、複雑なコスト・ベネフィット計算を必要とせず、認知的に安価であること多くの人が何を信じているかを把握して同じ信念を採用する、または誰が何かを最もよくしているかを把握してそのすべてを模倣する39。
しかし、多数派が誤っている場合や、最も成功した人物や名声のある人物が単に運が良かっただけの場合はどうなるのだろうか。このような大雑把なヒューリスティックが、安価なコストで適切な結果を得ることができるのであれば、それは体系的な間違いにもつながる。
ボイド、リチャーソン、ヘンリックの3人は覚悟を決めている。このバイアスは、集団にとっては有益だが、個人にとっては有害な文化的要素が広まることを許容するものである。
遺伝子と文化の共進化理論家は、このような事態を避けるだけでなく、喜々としてそうする。実際、大まかなヒューリスティックに依存することで、不合理な信念や不適応な行動が広まるだけでなく、有用な行動も広まることが予測されるという事実は、「これらのルールの興味深い進化的特徴」である44。「人間が文化に適応しているからこそ不適応な文化が広がる」というこの考えの新しさが、この考えをより魅力的にさせている。
騙されやすさへの反論
社会科学の多くの理論は、この遺伝子と文化の共進化という枠組みでおおよそ再構成することができる。マルクスとエンゲルスが示唆したように、「支配階級の考えは、どの時代においても支配階級の考えである」:成功バイアス45 人々は大多数に盲従する:適合性バイアスカリスマ的指導者は、その派閥に崇拝されることから大衆を支配するようになる:威信バイアス。何世紀も前の政治哲学、実験心理学、生物学的モデリングなど、驚くほど多くの知的伝統が、人間は概して、信心深く、権威に過度に忠実で、過度に順応的であるという概念に集約される。
しかし、これはすべて間違っているのだろうか?
本書では、「大衆は騙されやすい」という考え方の裏付けを削っていくことにする。その論拠を簡単に説明すると、次のようになる。
戦略的配慮を考慮すると、騙されやすさはあまりにも簡単に利用されるため、適応的でないことが明らかになる。人間は騙されやすいどころか、伝達された情報を注意深く評価することができる専用の認知メカニズムを持っている。権威ある個人や多数派に盲目的に従うのではなく、何を信じ、誰が一番良く知っているか、誰を信頼し、何を感じるかを決めるために、多くの手がかりを吟味する。
歴史が始まって以来、デマゴーグから広告主まで、多くの説得が試みられてきたが、それは人間の騙されやすさを証明するものではない。それどころか、これらの試みが繰り返し失敗していることは、大勢の人々に影響を与えることの難しさを証明している。
最後に、荒唐無稽な噂から超自然的な信念に至るまで、いくつかの誤解が文化的に成功していることは、信心深いという傾向ではうまく説明できない。概して、誤解が広まるのは、有名な人物やカリスマ的な人物に後押しされるからではなく、供給側である。その代わりに、人々は自分の既成の見解に合致し、何らかの目的に役立つ信念を探すため、その成功は需要に起因する。安心できることに、一般的な誤解のほとんどは、私たちの心の中から切り離されたままであり、現実的な影響もほとんどない。そのため、私たちは誤解を受け入れる際に比較的寛大になることができる。
第2章 コミュニケーションにおける用心深さ
信憑性を支持する最良の論拠は、信憑性によって仲間や先人の知識を得ることができるということである。他人の行動や考えを真似る傾向があり、誰が真似るべきなのか、つまり多くの人々や一流のリーダーが何をし、何を考えているのか、簡単なヒューリスティックに頼ることで、蓄積された知恵の富に簡単にアクセスすることができる。
しかし、この議論は、すべての相互作用に存在する戦略的要素を考慮に入れていない。この議論は、コピーされる個人が、適応的な行動をとり、正確な信念を形成するために最善を尽くしていると仮定している。また、コピーされた人が、コピーした人に影響を与えたいと思うかもしれないということは考慮されていない。しかし、なぜそうしないのだろうか?他人に影響を与えることができるというのは、大きな力である。そして、進化の観点からすると、大きな力には大きなチャンスが伴う。
他者に影響を与え、また他者から影響を受けるように進化した場合に何が起こるかを理解するためには、コミュニケーションの進化という枠組みが最も適している。この理論から導かれる直感に反する予測は、いくつかの不可解な動物の行動で最もよく説明されるもので、その説明はこの章を通して展開される。
奇妙な行動をする動物たち
オーストラリア東部の森林地帯では、ときどき奇妙な建築物に出くわす。草でできた小さな家のような構造物に、木の実や卵の殻、金属片、色とりどりの物などで装飾が施されている。それは、草でできた小さな家のようなもので、木の実や卵の殻、金属片など、色とりどりのもので飾られているのだ。鳥たちは、この丹精込めた建造物を、風雨や外敵から守るために使うのだろうか?そうではなく、もっと一般的な巣を木の上に作る。なぜ、わざわざボウフラを作るのだろうか?
トムソンガゼルは、すらりとした体型に長い角、脇腹の上品な黒い筋、そして真っ白なお尻を持つ、華やかな動物である。サバンナには野犬の群れがいて、ガゼルを追いかけて食べようとするが、ガゼルは犬の群れを見つけると、全速力で逃げないことがある。しかし、ガゼルは犬の群れを見つけると、全速力で逃げることはせず、足をまっすぐ伸ばしたまま、同じ場所に飛び乗る。その高さは、時には6フィート(約1.5メートル)にも及ぶ1。障害物がないのに、止まるのだ。なぜ、バカなガゼルはストッティングを止めないのだろうか。

これについては生物学者たちも長い間議論していたが、現在広く受け入れられている説明は「信号伝達」の観点からだ。トムソンガゼルがストッティング(場所を移動せずに高く跳ぶ行動)を行うと、それは捕食者に対する明確なメッセージを送っている。「見てくれ、私の体調は絶好で、君が私を捕まえる前に私は逃げ切ることができる」というメッセージである。この行動はガゼルの健康と運動能力を示し、捕食者にとっては捕まえるのが難しいターゲットであることを伝えるためのものと考えられている。
このような信号は「自己宣示信号」と呼ばれ、健康と適応能力を示すために生物が行う行動の一つである。つまり、ガゼルがストッティングする理由は、その健康状態と逃げ足の速さを示すことで、野生犬などの捕食者に「手間のかかる獲物だ」と警告するため、というわけである。(by GPT-4)
アラビアンバブリーは、マダラカミキリ同様、体長1フィート弱の茶色い鳥である。しかし、その名の通り、バブラーはボウヤを作るのではなく、バブリングをする。十数羽のグループで一緒に子供の世話をしたり、掃除をしたり、見張り役をしたりと協力的なのが特徴だ。捕食者の接近を確認すると、ガゼルよりもはるかに常識的な行動である「アラームコール」を発する。捕食者がまだ遠くにいるときは、バーク(比較的低い声で2回鳴く)またはトリル(より高く長い振動で鳴く)を発する。捕食者が近づくと、センチネルはツウィック(3回、短く高い音で鳴く)を出し始める。これらの鳴き声によって、他のグループのメンバーは、ある捕食者から隠れ、ある捕食者から暴れることができる。ここまではいい。しかし、ヒヨドリの中には、他のヒヨドリと協力するどころか、一緒に生活することもない孤独な生活を送っているものもいる。しかし、このフローターと呼ばれる人たちは、捕食者を見つけると、センチネルと同じ鳴き声をあげるのである2。
人間も他の哺乳類と同じように、妊娠すると母親の体にさまざまな変化が起こる。お腹が大きくなるなど、わかりやすい変化もあれば、インスリンの出方が変わるなど、微妙な変化もある。インスリンは、血糖を脂肪に変えるよう体に指令を出すホルモンである。糖分の多い食事をすると、血糖値が上がり、インスリンが分泌され、糖分は脂肪として蓄えられる。ところが、妊娠後期になると、食後にインスリンが大量に分泌されるようになる。成長する胎児が大量のエネルギーを要求し、母親の血液中の糖分から摂取しているからだ。さらに不思議なことに、インスリンが大量に分泌されているにもかかわらず、血糖値は通常より長く上昇したままなのである3。なぜ母親の体は、小さな子供のリソースを制限しようとするのだろうか?そして、なぜ失敗するのだろうか?
小さな脳を持つ動物でありながら、ミツバチは非常に高度な採餌活動を行う。蜜の多い花を探し、その場所を記録している。巣に戻ると、ミツバチは有名なワッグルダンスで巣の仲間に餌のありかを知らせます。ミツバチが効率よく採餌するためには、個人的な経験(過去に良い花を見つけた場所)と社会的な情報(他のミツバチのダンス)の両方を利用するのが一般的である。ハチが個人的な情報と社会的な情報のどちらに重きを置くかを調べるために、昆虫学者のマーガレット・レイとその同僚は、一連の巧妙な実験を行った。湖の真ん中にフィーダー(人工的な砂糖の供給源)を設置した。すると、湖の上を飛んでいたハチがフィーダーを見つけ、良い知らせとともに巣に帰ってきた。これで、湖の真ん中には花が咲かなくなった。巣箱に戻ったミツバチは、湖を指差すダンスを見て、戻ってきたミツバチを間違いだと思うのは当然だろう。しかし、彼らはそうしなかった。なぜ、この知的な昆虫たちは、自分たちの直感を無視して、ありえない指示に従うのだろうか。
葛藤とコミュニケーションの進化
このような奇妙な行動を理解する鍵は、私たちが言われたことをどのように評価するかを理解する鍵でもある。
例えば、ベルベットモンキーは、ワシ、ヘビ、ヒョウなどの捕食者の存在を互いに知らせることができる高度な警報システムを備えている。ベルベットモンキーは、これらの捕食者を発見したときに正しい呼びかけを行う機構と、それぞれの呼びかけに対して適切な反応を行う機構を備えている必要がある-ワシが近づいてきたときに木登りはあまり役に立たない6。

一方が何らかの情報を発信したり受信したりするための特定の適応を備えているにもかかわらず、他方でそれに対応するものがなければ、真のコミュニケーションは成立さない。コミュニケーションの代わりに、受信側の適応を必要とする合図が存在することがある。例えば、哺乳類の成獣は、赤ちゃんとその種の成獣を区別することができる。しかし、そのためにコミュニケーションは必要なく、合図、特に大きさを頼りにすることができる。赤ちゃんは、赤ちゃんであることを認識させるために小さく進化したわけではない。小さいということは、赤ちゃんであることを示す合図であって、信号ではないのである。
さて、自然淘汰による進化の理論では、コミュニケーション・メカニズムが進化したとすれば、それはシグナルを送る側と受け取る側の両方のフィットネスを向上させたからに違いない、と定めている。進化論でいう「フィットネス」とは、ある存在の繁殖的成功のことで、自分自身の繁殖だけでなく、自分のコピーの繁殖も含まれる。つまり、個体はより多くの子孫を残すことで体力を向上させることができるが、その個体が持つ新しい遺伝子変異を共有する可能性の高い親族がより多くの子孫を残すことを助けることでも体力を向上させることができる。
コミュニケーションの進化は、非常に簡単な場合もある。例えば、肝臓の細胞も脳の細胞も、生殖を行うことでフィットネスが向上する。肝臓の細胞も脳の細胞も、生殖することでフィットネスが向上する。そのため、ある細胞が、同じ体の別の細胞からの情報伝達に不信感を抱く理由はなく、細胞間のコミュニケーションの進化を妨げるものはない。実際、私たちの細胞は、一部の細胞が悪さをした場合でも、互いに耳を傾け続けている。がん細胞は、体に血管を増やすように信号を出し、体はそれに従う7。
また、一つの体に属していなくても、同じ体力を共有することができる。例えば、働き蜂の体力は、女王蜂の繁殖の成功と完全に結びついている。働き蜂は自分では繁殖できないので、遺伝子を受け継ぐには女王蜂の子孫を残すしかない。そのため、働き蜂は互いに騙す動機がなく、たとえ湖の真ん中に花が咲いていると言われても、他の働き蜂が発信する信号を確認することなく信用できる。
しかし、同じ体力を持っていない個体同士でも、多くのコミュニケーションが行われている。このような相反する可能性のある相互作用の中で、多くの信号は送り手の体力を向上させる一方で、受け手の体力を低下させるか、あるいは何の役にも立たないかもしれない。例えば、ベルベットモンキーが警報音を発するのは、捕食者を見つけたからではなく、熟した果実を積んだ木を見つけたので、他のサルの気を引いて、馳走を食べようと思ったからかもしれない。このようなシグナルは、受信者にとって有害であるという意味で、不誠実なシグナル、あるいは信頼性の低いシグナルと呼ぶことができる。
信頼できないシグナルが増殖すれば、コミュニケーションの安定性が脅かされる。受信者がコミュニケーションから利益を得なくなれば、シグナルに注意を払わなくなるように進化する。何かに注意を払わないということは、簡単にできる。モグラの目やイルカの指のように、ある構造が有利でなくなれば、その構造は消滅する。例えば、聴覚的なメッセージを処理するための耳や脳の部分が、バランスよく私たちに有害であったとしても、同じことが言えるだろう。
同様に、受信者が送信者の信号を利用して、送信者がコミュニケーションから利益を得られなくなった場合、送信者は次第に信号を出さなくなるように進化していくだろう8。同じインセンティブ、つまり同じフィットネスを共有しない個体間のコミュニケーションは本質的に脆弱である。
意外なコミュニケーションの失敗例
私たちは、妊娠を母親と子供の共生関係と考えがちである。実はこの関係は、ある程度、最初から相反するものである。母親は、自分の体力を最大化するために、すべての資源を現在身ごもっている胎児に捧げるべきではない。その代わり、一部の資源は過去と未来の子供(ひいては母親自身)に捧げられるべきである。一方、胎児は、兄弟に比べて自分自身に偏った進化を遂げるはずだ。このように母親と胎児にかかる選択圧が非対称であるため、胎児は、母親が一人の子孫に最適に配分するよりも多くの資源を母親に求めるように進化するはずだ。
特に独創的な進化生物学者であるDavid Haigは、母親と胎児の間の選択圧の違いが、他の多くの現象の中でも、妊娠中の母親のインスリン生理学の奇妙さを説明すると示唆した9。これらのホルモンの一つであるヒト胎盤ラクトゲン(hPL)は、インスリン抵抗性を高める。母体のインスリン抵抗性が高まると、母体の血糖値が上昇した状態が長く続き、胎児がより多くの資源を手に入れることができる。これに対して、母体はインスリンの分泌量を増やす。最終的に母体と胎児は、血糖値が通常よりやや長く上昇するものの、母体がインスリンを増量しない場合に比べればはるかに短い時間で、ある種の平衡状態に達す。胎盤は1日に1〜3gのhPLを分泌する。10 成長に忙しいはずの小さな生物にとって、これはかなりの資源消費である。それに比べ、このような綱引きに巻き込まれない胎盤ホルモンは、母体に影響を与える量が1000分の1である。
母体と胎児がホルモンを使って資源を奪い合うという奇妙な現象が進化論的に理解できるようになれば、新たなジレンマも生まれる。例えば、警報音。1960年代までは、個体が集団の仲間に警告を与えるために鳴くという、ごく当たり前の機能だった。たとえ鳴き声を出すことで餌を食べずに見張りをし、捕食されやすくなったとしても、集団が生き残る確率が高まるのだから価値がある、という考えからだ。生物学者のジョージ・ウィリアムズは、1966年に出版した『適応と自然淘汰』の中で、この論理に力強く反論した。例えば、集団の中のある個体が進化して、鳴き声を出さないか、鳴き声を出す頻度を減らしたとする。この個体は、他の個体よりも有利である。他の個体から警告を受けることで利益を得ているが、その代わりに支払うコストは少ないか、まったくコストがかからないからだ。この性質は選択され、集団に広がっていき、誰も警報を鳴らさなくなる。では、なぜ多くの種で警報音が鳴り止まないのだろうか?場合によっては、その答えは親族選択にある。例えば、イエローベリードマーモットは鳴き声を出すが、すべての鳴き声が同じというわけではない。警報音の多くは、新しい仔を産んだばかりの母親が発するものである。仔マルは、年上の個体ほど捕食者を発見する能力が高くないため、鳴き声から大きな恩恵を受けると考えられる。母親は、他の群れのメンバーにわざわざ警告する必要はないのである11。
アラビアンバブリーにも同様の現象が見られる。アラビアンバブリーは血縁関係の強い個体で構成される集団で生活しており、鳴き声は自分の子孫や兄弟の子孫の生存を助けることで鳴き手の適応度を高めると考えられる12。しかし、単独で行動するフローターが、警告する相手がいないにもかかわらず鳴くのはその説明がつかない。
意外なコミュニケーションの成功例
コミュニケーションの進化の論理は、母親と胎児という共通点の多い個体が効率よくコミュニケーションをとることが難しい理由を説明する。また、敵対関係にあるように見える人たちの間にコミュニケーションが生まれることも説明できる。共通インセンティブの存在とその程度は重要だが、それ以上に重要なのは、シグナルが正直であること、つまりシグナルを受け取る人にとってほとんど有益であることを維持する可能性、あるいはそれがないことである。
捕食者と被食者には、どのような共通のインセンティブがあるのだろうか。どちらも資源を無駄にしたくない。獲物が捕食者から逃れることがほぼ確実な場合、捕食者が全く攻撃しない方が、両者ともエネルギーを節約することができる。しかし、獲物は捕食者に「私を捕まえることはできない!」という意味のシグナルを送ることはできない。たとえ若くても、老いていても、疲れていても、怪我をしていても、捕食者から逃げる準備ができていなくても、すべての獲物はこのシグナルを送るインセンティブを持つことになる。その場合、捕食者はそのシグナルを信じる理由がない。このようなシグナルが機能し、長続きするためには、逃げ切れるだけの体力を持った獲物から発信される可能性が不釣り合いであるべきだ。そうでなければ、進化的に安定しないので、淘汰され、やがて消滅してしまう(あるいは、そもそも出現しない)ことになる。
アラビアンバブラーの鳴き声は、このようなことを実現しているのかもしれない。鳴き声を出すことで、カバは肉食動物に自分が発見されたことを知らせる。発見されると、捕食者は身を隠すことができるため、攻撃を成功させる確率は低くなる。トカゲからカンガルーネズミまで、多くの種がこの方法で捕食者に警告を発している。13 このシグナルが進化的に安定しているのは、何が誠実であり続けるためだろうか。なぜヒヨドリは、捕食者がいる場合に備えて、この鳴き声を頻繁に発しないのだろうか。その理由のひとつは、鳴き声が捕食者を常に阻止するわけではなく、単に攻撃の確率を下げるだけだからだ。獲物がすでに捕食者に見つかっている場合は、鳴き声を出すことに意味がある。しかし、まだ見つかっていない場合は、近くにいる捕食者に自分の位置を知らせたことになり、その捕食者がどこにいるかわからないので、逃げられる可能性は低くなる。そのため、獲物は実際に捕食者を発見したときだけ呼びかけを行うというインセンティブを持ち、呼びかけの信頼性を高めることができる。
捕食者抑止のシグナルにはある程度の信頼性があるが、獲物が非常に目に見える形で捕食者の方を向くことで、より説得力を増すことができる。これは、獲物がすでに捕食者を発見していなければできないことで、シグナルの信頼性をさらに高めることができる14。このように、ガゼルは捕食者に発見されたことを知らせると同時に、捕食者がその尻が食欲をそそると判断した場合に備えて、反対側を向くことができるのである15。
トムソンガゼルは、捕食者に尻を見せるだけではない。ジャンプもする。この高跳びは、捕食者抑止のシグナルとして機能する。ガゼルは肉食動物に対して、「自分は体力があるから必ず追い抜かれるよ。なぜなら、ガゼルは、捕食者の気を引くために十分な高さのストットをすることができるからだ。
ストッティングは、進化論の仮説を検証するために使われる証拠の一種を示す良い例だ。トムソンガゼルのストッティングの主な機能が、捕食者の追跡を阻止することだとなぜわかるのだろうか。まず、いくつかの代替仮説を除外することができる。実際、ガゼルは捕食者が近づきすぎると発情を停止する16。ガゼルは通常、邪魔なものがなくても発情するため、発情は障害物を避けるために使われない。また、ガゼルがチーターを発見したときに発情することはほとんどないため、発情は単に肉食動物に自分たちが発見されたことを知らせるものでもない。チーターは待ち伏せ捕食者なので、ガゼルが長いレースを続けられるかどうかは関係ない。
このような選択肢を除外した上で、ストッティングが捕食者の追跡を阻止する機能を持つという仮説に有利な証拠は何だろうか。まず、ガゼルが発情するのは、求愛者である野犬という正しい捕食者に反応するときである。これは、野犬が長時間速く走る能力を宣伝しているのであれば、納得がいく。第二に、ガゼルは体力があるとき(雨季)には、体力がないとき(乾季)よりも、より多く発情する。3つ目は、野生の犬は、より多くのストットを持つガゼルを追いかけにくく、一度追いかけ始めたら、よりストットの少ないガゼルの方に乗り換える可能性が高いということである。
無料で高価なシグナルを送る方法
自然淘汰は、信頼性の低い信号を送ることを本質的に不可能にすることで、非常に敵対的な関係であっても誠実なコミュニケーションを維持する、驚くべき創造的な方法に行き着いた。ウグイスは、目に見えない捕食者の鳴き声と協調して鳴くことができない。体格の良いガゼルだけが、説得力のある声を出すことができる。しかし、人間には、自分が送るメッセージの信頼性を証明する同等の方法がないようだ。例えば、「私は無言ではない」と言えば、無言ではないことが確実に伝わるという逸話があるが、言葉によるコミュニケーションで信頼性の低いシグナルを送ることには、本質的な制約がないのである。ハッカーは、うまくしゃべれないガゼルと違って、無駄なアドバイスをすることができる。
人間のコミュニケーションを安定させるためによく言われる解決策は、コストのかかるシグナリングシグナルを送るためにコストを支払うことは、その信頼性を保証することになる。コストをかけたシグナル伝達は、人間の奇妙な行動の多くを説明すると言われている。メリアムの狩猟採集民の亀狩りから米国の10代の若者たちの無謀な運転まで、危険な行為を行うことは、自分の強さと能力を示す高価なシグナルである19。
高価なシグナルはよく言われるが、しばしば誤解されている。直感的には、コストのかかるシグナルが機能するために重要なのは、信頼できるシグナルを送る人が支払ったコストである。誰かが最新のiPhoneを買うために1000ドル以上を支払ったから、この携帯電話を所有することが富の信頼できるシグナルになるということだろう。実際、重要なのは、信頼できるシグナルを送る人に比べて、信頼できないシグナルを送る人は、シグナルを送るときに大きなコストがかかるということである。つまり、重要なのは、新しいiPhoneの購入費用そのものではなく、携帯電話に多額の費用を費やすことは、それを買うために必需品を節約しなければならないかもしれない貧しい人にとって、1000ドルの差はほとんどないかもしれない金持ちよりもコストが高いという事実である20。
重要なのは、信頼できる信号を送るコストと信頼できない信号を送るコストとの差であり、コストの絶対水準は問題ではない。その結果、コストのかかる信号送信は、逆に言えば、コストを支払わなくても信号を信頼できるようにすることができる。信頼できない信号者が信号を送れば高いコストを支払うことになる以上、信頼できる信号者は無料で信号を送ることができる。この理屈を説明するのが、ハシビロコウのボウフラである。
オスのヒヨドリがメスを誘うためにボウフラを作ることは、今ではよく知られている。実際、装飾性の高いボウフラは、その作り手に多くの交尾の機会を与えることに成功している21。なぜメスは派手なボウフラに惹かれるのだろうか。結局のところ、これらのボウフラはまったく実用的ではない。実際、東屋を作ることに特別なコストがかかるようには見えない。東屋を作る季節に、オスは東屋を作ったにもかかわらず、死ぬ可能性は高くないのだ23。
そのメカニズムは、鳥類学者のジョア・マッデンが、ヒヨドリの雌を騙すために、いくつかの東屋に余分な実をつけたことから、やや不注意にも発見された24。しかし、マデンが追加した実には、そのような効果はなかった。しかし、マデンが追加したベリーは、そのような効果をもたらさなかった。むしろ、マデンからベリーを贈られたボウヤを、ライバルのヒヨドリが妨害していたのである。マデンからベリーを贈られたボウヤは、他のボウヤからベリーが余っていることから、ボウヤの持ち主が自分より地位が高いように見せかけていると判断し、ボウヤを破壊して持ち主を元の位置に戻そうとしたのだそうだ。
このシステムを安定させているのは、豪華な東屋を作るための本質的なコストではない(いずれにせよ低いコストである)。その代わり、オス同士の警戒心が強く、お互いのボウヤを監視し、誇張したボウヤを建てる者にコストをかける。その結果、どのオスも自分の守れる範囲以上の東屋を作ろうとしない限り、東屋は大きなコストを支払うことなく、オスの品質に関する信頼できるシグナルを送ることができる。これは、高価なシグナルをタダで(あるいは、他のオスのボウヤを監視するための間接的なコストがあるため、ほぼタダで)送っていることになる。
後述するように、このロジックは、人間のコミュニケーションが安定的に維持されるメカニズムを理解する上で重要である。最新のiPhoneを買うのとは違って、約束をすることには本質的なコストがかからない。人間の言葉によるコミュニケーションは、典型的な「安っぽい話」であるため、コストのかかる信号とはとても言えないように思われる。しかし、それは間違いである。重要なのは、約束を守る人が負担するコストではなく、約束を守らない人が負担するコストなのである。信頼できないメッセージを送る人に十分なコストをかける仕組みがある限り(将来的にその人を信用しなくなるだけでも)、高価なシグナルを扱っていることになり、コミュニケーションは安定的に保たれる。このように、人間が信頼できるシグナルを送るために、その都度コストをかけずに済む方法を開発したことが、人間の成功に大きく寄与していることは間違いない。
警戒の必要性
コミュニケーションは厄介なものである。獲物は肉食動物を説得して追いかけるのをやめさせるが、胎児は母親を説得してより多くの資源を与えることができない。このような成功例と失敗例を理解するためには、進化の論理が不可欠である。進化の論理は、個体が共通の誘因を持つとき、すなわち、体の中の細胞や蜂の巣の蜂のように、私たちに教えてくれる。しかし、妊娠中の葛藤が示すように、共通のインセンティブを持つだけでは十分ではない。2つの存在の生殖運命が完全に絡み合っていない限り、信頼性の低いシグナルを送るインセンティブが存在することはほぼ確実である。そこで自然淘汰は、信号の信頼性を保つためのさまざまな方法を考え出した。その中には、ガゼルのストットのような魅力的なものもあるが、人間のコミュニケーションにはほとんど当てはまらない。その代わりに、人間のコミュニケーションは、信頼性の低い信号への接触を最小限に抑え、誰が何を言ったかを記録することで、信頼性の低い送信者にコストをかける、一連の認知プロセス(開放的警戒のメカニズム)によって(ほとんど)信頼性を保たれていると主張する。
これらのメカニズムがどのように働くのか、何を信じ、誰を信頼すべきかを決めるのにどのように役立つのかは、次の5つの章のテーマである。いずれにせよ明らかなのは、私たちは騙されやすいというわけにはいかないということだ。もしそうであれば、人々がその影響力を悪用するのを止めることはできないだろうし、他人の言うことに全く注意を払わない方が良いくらいになり、人類のコミュニケーションと協力が速やかに崩壊することになる。
第3章 オープンマインドの進化
人間にとって、コミュニケーション能力は非常に重要である。コミュニケーションがなければ、何を食べても大丈夫なのか、どうすれば危険を回避できるのか、誰を信じればいいのか、などということを理解するのは難しい。狩猟や採集、子育て、同盟、技術的な知識の伝達など、私たちの祖先は互いにコミュニケーションをとる必要があった1。また、私たちの祖先が60万年以上前に分かれたいとこであるネアンデルタール人も、同じ解剖学的装置を持っていたと思われることから、複雑な言語コミュニケーションはもっと古くからあったことがわかる2。
人類は、その(前)歴史の非常に早い段階から、互いにコミュニケーションをとることで多大な利益を得ることができたとすれば、同時に、コミュニケーションの乱用によるリスクも抱えてきた。他のどの霊長類よりも、私たちはコミュニケーションによって惑わされ、操作される危険にさらされている。進化的に関連する問題が存在すると、その問題を解決することに特化した認知メカニズムの発達に有利な選択圧力が生じる。同じことがコミュニケーションにも当てはまり、その約束と危険性がある。
実際、コミュニケーションの可能性だけでなく、危険性にも対処するための特殊な認知メカニズムが進化しなかったとしたら、それは不可解なことである。2010年の論文で、認知科学者のダン・スパーバーとその同僚たち(あなたを含む)は、こうしたメカニズムをエピステミック・ヴィジランスと呼んだが、ここではオープン・ヴィジランスと呼び、こうしたメカニズムは、少なくともコミュニケーションされた情報に対して警戒するのと同じくらいオープンであることを強調する3。しかし、こうしたメカニズムの存在に同意したとしても、その機能のあり方はさまざまなものがあると考えられる。
コミュニケーションの進化、ひいてはオープンな警戒のメカニズムについて考える一つの方法は、軍拡競争のアナロジーを使うことである。軍拡競争とは、2つの主体が競い合うことで、それぞれが相手の動きに応じて、徐々に戦力を高めていくことである。冷戦時代、ロシアとアメリカが核兵器を増やし、その反動で相手も核兵器を増やし、その反動で相手も核兵器を増やし……といった具合に、この例えが生まれた。
通信の場合、受信者を操作する手段を高度化する送信者と、信頼性の低いメッセージを拒否する手段を高度化する受信者の間で軍拡競争が起こる可能性がある。例えば、コンピューターウイルスやセキュリティソフトがそうだ。人間の場合、このモデルによって、精神的な鋭さの欠如と騙されやすさが関連づけられることになる。歴史上、多くの論者が、女性から奴隷まで、一部の人間には厳しい知的制限があり、その制限がこれらの人々を騙されやすくしている(私の用語では、より洗練された公開警戒のメカニズムを使用できないようにする)と指摘している。私たちが皆同じ認識装置を備えていると仮定しても、常にそれに頼ることができるわけではない。したがって、軍拡競争モデルは、受信者が疲れきっていたり、気が散っていたりするために、最も洗練された認知メカニズムを適切に使用できない場合、送信者のより高度な認知デバイスに対して無防備になることを予言している。これは、更新されていないセキュリティソフトウェアのシステムがコンピュータを攻撃に対して脆弱にするのと同じだ。
洗脳者と隠れた説得者
1950年代のアメリカでは、操られることへの恐怖が時代風潮となっていた。ジョセフ・スターリンがまだソビエト連邦の指揮をとっていたため、共産主義の脅威は頂点に達し、米国はマッカーシズムのピークに達していた。「赤軍」は、政府、学界、国防計画など、あらゆるところに入り込んでいると考えられていた。さらに陰湿なことに、彼らは最も献身的で最も愛国的なアメリカ人である兵士の心の中にも入り込んでいると考えられていた。朝鮮戦争では、何千人もの米兵が韓国や中国に捕らえられた。逃げ延びた兵士たちは、睡眠不足から水責めまで、ひどい虐待や拷問の話を持ち帰った。戦争が終わり、捕虜が送還されたとき、これらの虐待はさらに暗い意味を持つようになった。敵の残酷さを示すだけでなく、米兵を洗脳して共産主義の教義を受け入れさせようとする試みと見なされたのである。23人のアメリカ人捕虜が祖国に帰らず、捕虜の後を追って中国に渡ることを選んだのは、当時のニューヨーク・タイムズ紙が「共産主義の洗脳が一部の人に有効であることの生きた証拠」4と述べているように、間違いない。
洗脳は、「条件づけ」、「衰弱」、「解離-催眠-暗示」を伴うため、人々の高次の反射能力を打ち砕くことで機能すると考えられていた5。ダニエル・ギャラリー米少将は、「人間と生きようとするネズミとの境界例」を男性に与えたという。「朝鮮人と中国人が使用した技術は、ロシア人が先に開発したものから派生したものと考えられ、捕虜を「パブロフの捕虜」7にしたのである。皮肉なことに、「テロとの戦い」において、アメリカ人は、テロリストと思われる人物から情報を引き出すために、ウォーターボーディングに代表されるような同じテクニックの多くを使うようになる。
1950年代のアメリカでは、「人は考えることができないと影響を受けやすい」という考え方が、全く異なる文脈で現れていた。朝鮮人収容所の地獄に苦しむ捕虜ではなく、最新のハリウッド大作を快適に鑑賞している映画ファンが対象だった。映画の中で、「コーラを飲め」というようなメッセージが、意識できないほど素早く提示されたのである。サブリミナル・メッセージは、何十年も続く恐怖を作り出した。2000年には、共和党が資金を提供し、民主党の大統領候補であるアル・ゴアの政策提案を攻撃する広告が、サブリミナル的にネズミという言葉を視聴者に提示していたことが判明し、スキャンダルに発展した9。例えば、自尊心を高めるために、寝ながら聴くことができる治療用テープを製造する会社が現れた。眠っているときは意識的にコントロールすることができないので、潜在意識に直接働きかけることができ、特に効果があると信じられていた。
洗脳やサブリミナルにまつわる恐怖は、劣悪な認知能力と騙されやすさの間に蔓延する関連性に依拠している。つまり、思考力が低いほど悪いことを考え、有害なメッセージに影響されやすくなる。知的洗練の欠如と騙されやすさとの間のこの関連は、歴史的に広範である。紀元前500年、ヘラクレイトスが「群衆の中で、自分たちがどれだけ多くの愚か者や盗人であるかを考えずに、演説者に導かれるままに身を任せる」人々について語ったとき、すでに彼は貴族ではなく大衆、一般民衆について話していたのである。
25世紀後、同じ表現が群集心理学者の言説に浸透していった。19世紀後半に活躍したヨーロッパの学者たちは、革命的な暴徒から鉱山労働者のストライキに至るまで、政治における群衆の影響力の増大に取り組んだ。これらの学者たちは、群衆を暴力的であると同時に騙されやすい存在としてとらえ、ベニート・ムッソリーニやアドルフ・ヒトラーを刺激し、今日に至るまで、法執行機関のメンバーなど、群衆に対処しなければならない人々の間で一般化している10。群衆心理学者として最もよく知られているギュスターヴ・ル・ボンは、群衆は「女性、野蛮人、子どもなど、進化の劣った形態に属する存在に見られる…批判的思考の不在」を共有していると示唆した11。ル・ボンの同僚のガブリエル・タルドは、動機づけられた推論の美しい例として、彼が認めたように「それが通常そうだが、男性から成る」場合でも「従順さとその信用性…から群衆は女性的」だと主張している。12 群集心理学者の一人、イポリット・テーヌは、群衆の中では、人々は「それぞれが他を模倣する隷属的な猿」のような自然の状態に還元されると付け加えた13。ほぼ同じ頃、大西洋の反対側では、マーク・トウェインがジムを「幸福で騙されやすい、むしろ子供の奴隷」14として描いている。
21世紀になっても、私たちはこのような不愉快な連想の反響を見かけることがある。『ワシントンポスト』や『フォーリン・ポリシー』のライターは、ドナルド・トランプが当選したのは「無知」な有権者の「騙されやすさ」のおかげだと主張し15、ブレグジット(英国のEU離脱投票)については、ブレグジット派を「無教養な平民」、残留派を「洗練されていて文化的、国際的」16と見るのが普通である。
現代の学術文献では、無教養と信憑性の関連は、主に2つの形をとっている。第一は子供で、その認知的な成熟度の低さはしばしば騙されやすさと関連付けられる。最近の心理学の教科書は、子どもがより複雑な認知能力を身につけるにつれて、「だまされにくくなる」と主張している17。また、もっと大げさに、「子どもは広告主の夢であるようだ。だまされやすく、傷つきやすく、売りやすい」18と述べている。
認知的な洗練の欠如と信憑性が結びつく2つ目の方法は、思考プロセスを2つの主要なタイプ、いわゆるシステム1とシステム2に分けるという一般的なものである。心理学で長く確立され、最近では心理学者ダニエル・カーネマンの『Thinking, Fast and Slow』によって一般化されたこの考え方によれば、いくつかの認知プロセスは、速く、楽に、ほとんど無意識であり、システム1に属するものである。簡単な文章を読むのも、人の第一印象を決めるのも、よく知られた道を歩くのも、すべてシステム1に属している。システム1を形成する直感は、全体として効果的だが、系統的なバイアスの影響を受けやすいのも事実である。例えば、私たちは顔の特徴から、その人が有能かどうか、信頼できるかどうかを判断しているようだ。このような判断は限定的な信頼性を持つかもしれないが、その人が実際にどのように行動しているかなど、より強力な手がかりに簡単に取って代わられるはずです19 このとき、システム2が活躍するはずだ。システム2は、システム1が失敗したときに、より客観的なプロセスとより合理的なルールによって、私たちの間違った直感を修正し、ゆっくり、努力し、反省するプロセスに依存する。これが、一般的な二重プロセスの物語である20。
2つのシステムの機能を示す最も有名な課題は、「バットとボール」であろう:
バットとボールの値段は合計で1.10ドルである。バットとボールの値段は合計で1.10ドルである。ボールの値段はいくらだろう21
もし、あなたがこの問題に遭遇したことがなければ、先を読む前に挑戦してみてほしい
この問題が心理学者たちを魅了してきたのは、一見単純に見えるにもかかわらず、ほとんどの人が間違った答え、つまり10セントを出してしまうからだ。10セントという答えは、システム1の答えの完璧な例だ。しかし、10セントが正解であるはずがない。なぜなら、バットは1.10ドル、2つを合わせると1.20ドルになるからだ。多くの人は、この直感的な間違いを修正し、5セントという正解にたどり着くために、システム2に頼らざるを得ないのである22。
もし、システム1が荒削りなメカニズムで、システム2がゆっくりじっくり考えるメカニズムだとしたら、システム1は信憑性に、システム2は批判的思考に関連すると予想される。心理学者のダニエル・ギルバートらは、伝達された情報の評価において2つの精神系が果たす役割を明らかにするために、巧妙な一連の実験を行った23。これらの実験では、被験者に一連の文章を提示し、それぞれの文章の提示直後に、それが真実か偽かについて説明した。例えば、ある実験では、ホピ語(アメリカ先住民の言語)の単語に関する文が提示され、参加者は「A ghoren is a jug」と言われた後、1秒後に「true」と告げられるかもしれない。すべての文が提示された後、参加者はどれが本当でどれが嘘だったかを尋ねられた。ギルバートらは、2つのシステムが果たす役割を検証するために、システム2の処理を断続的に中断させた。システム2は、遅くて努力が必要なため、簡単に中断される。この場合、参加者は音が鳴ったらボタンを押すだけでよかった。この音は、ある発言が本当か嘘か、という重要な情報が伝えられたときに鳴る傾向がある。
どの発言が本当で、どの発言が嘘かを思い出すとき、システム2が破壊された人は、その発言が本当であるか嘘であるかに関係なく、その発言を本当だと信じる傾向が強かった。つまり、システム2の障害によって、多くの参加者が偽の発言を真実として受け入れていたのである。これらの実験から、ギルバートたちは、私たちは最初に言われたことを受け入れようとする傾向があり、システム2のわずかな混乱が、この最初の受け入れの再考を妨げると結論づけた。ギルバートたちは、このテーマに関する2番目の論文のタイトルで、こう言っている: 「カーネマンは、これらの知見を次のように要約している: 「システム2が他に働いているときは、ほとんど何でも信じてしまう。システム1は騙されやすく、信じることに偏っており、システム2は疑うことと信じないことを担当しているが、システム2は時々忙しく、しばしば怠けている」25。
これらの結果は、より「分析的」な思考スタイル、つまり、システム1よりもシステム2に頼る傾向が強いことと、経験的に疑わしい信念の拒絶との間に観察された関連性と一致している。心理学者のウィル・ジャーヴェイスとアラ・ノレンザヤンは、広く知られた論文の中で、より分析的な思考の枠組みを持つ人、例えばバットとボールのような問題を解くのが得意な人は、無神論者になる傾向があることを発見した26。他の研究では、より分析的な傾向を持つ被験者は、魔術から予知能力まで、さまざまな超常思想を受け入れる傾向が低いことが示唆されている27。
あなたが今読んだ本の内容をすべて信じていないことを祈る
警戒心の進化に関する軍拡競争説によって予測される、認知的洗練の欠如と騙されやすさの関連性は、ギリシャの哲学者から現代の心理学者まで、歴史を通じて広まってきた。しかし、私は、軍拡競争のアナロジーと、洗練されていないことと騙されやすいことの関連性は、完全に間違っていると考えている。
まず、軍拡競争の例えは、人類のコミュニケーションの進化の大まかなパターンに当てはまらない。軍拡競争は、並行してエスカレートすることで現状を維持することを特徴とする。ロシアもアメリカも核兵器をどんどん増やしていったが、どちらも優位に立つことはできなかった。コンピューターウイルスがセキュリティソフトで駆逐されたわけではないが、すべてのコンピューターがウイルスに支配されたわけでもない。同様に、前章で述べた母親と胎児の資源争奪戦においても、双方がホルモン信号をますます大量に展開しても、実質的には何の効果もない。
人間のコミュニケーションは、幸いなことに、これらの例とは大きく異なる。ここでは、人間以前の祖先や、近似的に生きている私たちの近親者が交換する情報量が現状と言えるかもしれない。しかし、私たちはこの現状から大きく逸脱していることは明らかだ。私たちは、他のどの霊長類よりも何桁も多くの情報を発信し、消費している。そして、重要なことは、私たちが受け取る情報によって、より大きな影響を受けるということである。コミュニケーションの帯域は劇的に広がった。時間的にも空間的にも遠い出来事について議論し、深い感情を表現し、抽象的な存在について議論し、想像上の存在について物語を語ることさえある。
人間のコミュニケーションの進化を考えるとき、軍拡競争よりも雑食性の進化に例えるのが適切だろう。動物には、非常に特殊な食生活を送るものがいる。コアラはユーカリの葉だけを食べる。吸血コウモリは生きた哺乳類の血しか飲まない。PANDAは竹しか食べない。これらの動物は、自分の食べ物以外のものをすべて拒絶する。極端な例では、コアラはユーカリの葉がユーカリの木の枝に付いているのではなく、平らな場所に置かれているなど、適切に提示されていなければ食べない28。しかし、この戦略は、新しい環境に身を置くと裏目に出ることがある。吸血コウモリは生きた哺乳類の血だけを飲むので、食べ物が新鮮かどうかを気にする必要はない。毒のある食べ物を避けることを学習する問題は、自然環境では直面しないため、食物嫌悪を学習するメカニズムがなく、病気を連想させるはずの食べ物を飲み続けてしまう29。
このような専門家とは対照的に、雑食性動物はよりオープンでより警戒心が強い。雑食性動物がよりオープンであり、より警戒心が強いのは、より多くの種類の食物を探し、発見し、摂取する点である。ラットや人間は、「9種類のアミノ酸、数種類の脂肪酸、少なくとも10種類のビタミン、少なくとも13種類のミネラル」30を含む30種類以上の栄養素を必要とするが、どの食物源もそれらをすべて一度に摂取することはできない。雑食動物の場合、試食できる食品の幅はもっと広くなる。実際、ネズミでも人間でも、食べられそうなものなら何でも食べてみる。また、摂取したものから必要な栄養素を検出し、ナトリウムが少ないと塩辛いものを欲しがるなど、ニーズに合わせて食事を調整する仕組みが備わっている31。
このようなオープンな性格が、雑食動物の適応力を高めている。人類は、ほとんど牛乳とジャガイモだけの食事(18世紀初頭のアイルランドの農民)や肉と魚だけの食事(最近までイヌイット)でも生き延びることができた。しかし、その開放的な性格が、雑食動物の弱点にもなっている。肉は腐りやすく、危険な細菌が含まれていることもある。食べられないように、ほとんどの植物は毒性があるか、消化しにくい。そのため、雑食動物は専門家よりも食べ物に対して警戒心が強いのである。さまざまな戦略を駆使して、好ましくない副作用をもたらす可能性の高い食品を避ける方法を学んでいる。雑食動物である私たちは当たり前のことだが、吸血コウモリのような動物にはできないことである。どの食べ物が安全かを把握するためには、一般的な学習メカニズムではなく、専用の回路が必要である。ネズミから人間、そして毛虫に至るまで、雑食動物は若い頃に食べたものを好む。
コミュニケーションという点では、ヒトと他の霊長類の違いは、専門家と雑食の違いに似ている。人間以外の霊長類は、ほとんどが特定のシグナルに頼っている。チンパンジーは服従を示すために微笑み、36 ヒヒは下位の個体に近づく前に平和的な意図を示すために呻く。そのため、人間は他の霊長類よりもはるかにオープンである。例えば、指差しのような基本的なものである。しかし、大人のチンパンジーは、私たちが指さしをするのが当然と思えるような状況でも、指さしを理解しない。実験では、チンパンジーを2つの不透明な容器の前に置き、どちらか一方に食べ物を入れるが、どちらかわからないようにすることが繰り返された。実験者が容器の一つを指差すと、チンパンジーはもう一つの容器よりもこの容器を選ぶ確率が高くない。39 知性がないわけではない。容器の一つを取ろうとすると、チンパンジーはそれが餌の入った容器に違いないと正しく推測する。
チンパンジーにとってコミュニケーションは、私たちよりもずっと自然なものではない。もし私たちが他の霊長類よりも、さまざまなコミュニケーションの形態や内容に大きく寛容であるならば、私たちはより警戒する必要がある。次の4章では、私たちがどのようにこの警戒心を発揮しているのかを探ってみたいと思う。ここでは、私たちのオープンな警戒心のメカニズムの全体的な構成に焦点を当てたいと思う。この構成は、これらのメカニズムの一部が損なわれたときに何が起こるかを理解するために重要 このような障害があると、私たちは誤解を招くような情報を受け入れやすくなるのだろうか、それとも受け入れにくくなるのだろうか。
軍拡競争理論によれば、私たちは、極端にオープンな状態、つまり一般的に騙されやすい状態から、最近発達した認知機械によって可能になった、より高度な警戒心の状態へと進化してきた。もしこの機械がなくなれば、私たちは以前のような騙されやすい状態に戻り、どんなに愚かで有害なメッセージでも受け入れる可能性が高くなるという理論である。
雑食の進化に例えると、その逆であることがわかる。私たちは、極端に保守的な状況、つまり限られた信号の集合にしか影響を与えない状況から、より警戒しつつも、さまざまなコミュニケーションの形態や内容に対してよりオープンである状況へと進化していた。このように、より洗練され、よりオープンになることで、全体的な機能がより強固になる。軍拡競争の考え方では、より洗練されたメカニズムが破壊されることで、私たちは信頼性を失い、脆弱になる。これに対して、開放性と警戒心が手を取り合って進化していくモデルは、それほど脆弱ではない。より新しいメカニズムが破壊された場合、私たちはより古いメカニズムに戻り、警戒心が薄れるが、同時に開放性も大幅に低下する。より新しく洗練された認知機構が破壊されると、私たちは保守的な核心に戻り、騙されやすくなるどころか、より頑固になる41。
洗脳は効かない
洗練されていないことと騙されやすいことの関連性、そして間接的に警戒心の進化に関する軍拡競争説を支持する証拠についてはどうだろうか。まず、洗脳やサブリミナル的な影響についてはどうだろうか。もし、私たちの高次の認知能力を破壊したり、完全にバイパスしたりすることが効果的な影響力の手段だとしたら、洗脳もサブリミナル刺激も、私たちを無力にし、共産主義の美徳を騙すように受け入れ、コカ・コーラを渇望させるはずだ。実際、どちらの説得術も、驚くほど効果がない。
洗脳騒動は、朝鮮戦争後、23人のアメリカ人捕虜が中国に亡命したことに始まる。捕虜4,400人のうち改宗者は23人、つまり半数ということである。しかし、実際には本物の改宗者はゼロであったと思われる。脱走した兵士たちは、アメリカでの生活を恐れていたのである。収容所での便宜を図るために、中国人の捕虜に協力したり、少なくとも捕虜のように捕虜に反抗するようなことはなかった。その結果、これらの捕虜は帰国後軍法会議にかけられることが予想された。実際、米国に帰還した捕虜のうち、1人は懲役10年、1人は死刑を求刑されている。それに比べれば、たとえ共産主義の教義を口先だけで理解することになったとしても、中国の制度に改宗したと祭り上げられることは、それほど悪いことではないように思われた42。最近、洗脳から派生した方法、例えば、身体的拘束、睡眠不足、その他の容疑者の心を麻痺させようとする「強化尋問技術」が、「テロとの戦い」において米軍によって使用されてきている。洗脳と同様、これらのテクニックは、容疑者の高次の認知を十分に利用するソフトな方法、つまり尋問者が信頼を築き、被験者を議論に参加させる方法よりもはるかに効果がないことが示されている43。
同様に、サブリミナル効果や無意識のマインドコントロールに対する恐怖は、根拠のない恐怖に過ぎなかった。サブリミナル刺激の威力を示す初期の実験は単なるでっち上げで、映画館で「コーラを飲め」というサブリミナル広告を表示した人はいなかった44。その後の豊富な(実際の)実験でも、サブリミナル刺激が人間の行動に何らかの意味のある影響を及ぼすことは示されていない45。「コーラを飲め」というメッセージがスクリーンに点滅していても、コカ・コーラを飲む可能性は高くならない。睡眠中に自尊心のテープを聴いても、自尊心は高まらない。刺激によって、私たちが意識することなく影響を受けることを示唆する実験があるとしても、その影響はせいぜい、すでに喉が渇いている人にもう少し水を飲ませるといった程度のものである46。
ギルバートとその同僚が行った実験はどうだったのだろうか。ギルバートらの実験では、「ゴーレンは水差しである」のように、ある文は自然に受け入れられ、ある文は拒否されるために努力が必要であることが示された。しかし、だからといって、システム1がギルバートの言うように「読んだものをすべて受け入れる」のだろうか。そうではない。参加者がその文に関連する何らかの背景知識を持っている場合、その背景知識は彼らの初期反応を方向づける。例えば、「柔らかい石鹸は食べられる」というような記述に対する人々の最初の反応は拒絶反応である47。直感的に不信感を抱くために、その記述が明らかに間違っている必要はない。直感的に不信感を抱くには、その発言が明らかに嘘である必要はなく、単にそれが嘘であっても何らかの関連性があればよい。ホピ語で「ゴーレンは水差しである」というのが嘘であることを知っても、あまり役には立たない。これに対して、「ジョンはリベラルだ」という文が偽であることを知れば、ジョンについて何か有益なことがわかる。システム1は、「騙されやすく、信じることに偏っている」49というよりも、むしろ、自分の背景信念と相容れないメッセージはもちろん、曖昧なメッセージや信頼できない情報源からのメッセージも拒絶することに偏っている50。例えば、あなたが多くの人と同じように、バットとボールの問題で10セントの答えに行き詰まり、誰かが「正しい答えは5セントだ」と言ったとしたら、あなたの最初の反応はその発言を拒絶することだっただろう。この場合、あなたのシステム2は、健全な信念を受け入れさせるために何らかの作業をしなければならなかった。
分析好きでないこと、つまりシステム2を使わないことと、経験的に疑わしい信念を受け入れやすいことの間に系統的な関連があることを示唆する実験的証拠はない。むしろ、人々が異なる認知メカニズムを使おうとする傾向と、彼らが受け入れる経験的に疑わしい信念のタイプとの間に、複雑な相互作用があることが観察された。信念が正しいかどうかにかかわらず、人々の背景的な見解に共鳴する信念は、システム2への依存度が低い人々の間でより成功するはずだ。しかし、システム2への過度の依存は、一見強く見えるが実際には欠陥のある議論に由来する、疑わしい信念を受け入れることにもつながる可能性がある。
分析的思考と経験的に疑わしい信念の受け入れとの関連は、単純なものではない。分析的思考は無神論と関連しているが、それは一部の国に限られる51。日本では、分析的傾向が強いことは、超常現象をより多く受け入れることと相関している52。実際、知識人は通常、新しく、一見あり得ないような考えを最初に受け入れるものである。これらのアイデアの多くは、プレートテクトニクスから量子物理学に至るまで正しいことが証明されているが、冷温核融合から体液性疾患理論に至るまで、多くのものは誤った方向に進んでいる。
相対的に洗練されていないことと騙されやすいことが重なっているように見える場合でも、前者が後者を引き起こしていることを示す証拠はない。例えば、3歳児にとって、誰かが嘘をついていることを理解し、その人を信用するのをやめることは難しい54。(他の点では、明らかに、3歳児は信じられないほど頭が悪い) しかし、このような見かけの(そして部分的な)騙されやすさは、認知が成熟していないことが原因ではない。大人に比べれば、小さな子どもはほとんど何も知らないし、周りの大人の言うことはたいてい信用できるのだ。幼い子どもたちが採用しているこのような信頼性の強い仮定は、ある意味、ミツバチに見られるものと似ている。ミツバチには、幼い子どもが養育者に不信感を抱く理由よりも、他のハチに不信感を抱く理由がさらに少ない。どちらの場合も、あるエージェントが他者を信頼したりしなかったりする理由には、洗練されていないことが説明的な役割を果たすことはない。
進化の論理は、騙されやすさが安定した形質であることを本質的に不可能にしている。騙されやすい人は、メッセージに注意を払わなくなるまで利用されるからだ。その代わり、人間は用心深くなければならない。送信者は受信者を操作するように進化し、受信者はその試みを阻止するように進化するという、警戒心の進化に関する軍拡競争という見方は、直感的に魅力的である。この軍拡競争的な考え方は、洗練されていないことと騙されやすいことの間にある一般的な関連性とよく似ているが、それは間違いである。むしろ、人間のコミュニケーションがますます広範で強力になるにつれて、開放性と警戒心は手を携えて進化してきたのである。ここで、私たちがコミュニケーションに対してオープンであると同時に警戒心を持つことができる認知メカニズムを、より詳しく探ってみよう: 何を信じ、誰が一番よく知っているのか、誰を信頼し、何を感じるのか、私たちはどのように判断するのだろうか。
