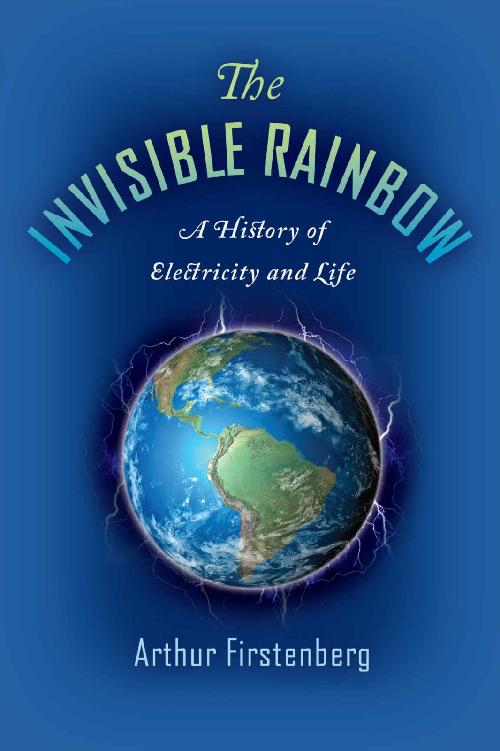
友人であり、指導者であり、旅人であったペルダ・リーベイの思い出のために。
著者ノート
読みやすくするために、注釈は最小限にとどめた。しかし、本文中で言及したすべての資料は、巻末の書誌に掲載されており、私が参照した他の主要な著作物も掲載されている。特定のテーマに関心をお持ちの方のために、参考文献は通常のアルファベット順ではなく、章ごとに、またいくつかの章ではトピックごとに整理されている。
A.F.
目次
- プロローグ
- 第1部 はじめに。..
- 1. 瓶の中に閉じ込められた
- 2. 耳が聞こえない人、歩くのが不自由な人
- 3. 電気の感度
- 4. 通らない道
- 5. 慢性電気疾患
- 6. 植物の行動
- 7. 急性電気障害
- 8. ワイト島の謎
- 9. 地球の電気包囲網
- 10. ポルフィリンと生命の基礎
- 第II部 ……現在に至るまで
- 11. イライラする心臓
- 12. 糖尿病の変貌
- 13. がんと生命の飢餓
- 14. 仮死状態
- 15. 電気の音が聞こえるって?
- 16. ミツバチ、鳥、木、そして人間
- 写真
- 17. 盲目の国で
- ノート
- 書誌事項
- 著者について
プロローグ
昔々、嵐の後に空に見える虹は、すべての色を表していた。私たちの地球はそのように設計されている。私たちの上空には、宇宙からのX線やガンマ株と一緒に、より高い紫外線を吸収する空気のブランケットがある。今日、私たちがラジオ通信に使っているような長い電波も、かつてはなかった。というより、ごく微量にしか存在しなかったのである。宇宙電波は、太陽や星からやってくるが、そのエネルギーは、同じく天界からやってくる光よりも1兆分の1も弱い。そのため、生命は電波を見ることができる器官を発達させることができなかった。
さらに長い波、稲妻が発する低周波の脈動も目に見えない。雷が光ると、一瞬、空気中にその波が充満するが、一瞬で消え、世界中に反響して、太陽の光の約100億分の1の弱さになる。私たちはこれを見るための器官も進化させてはいない。
しかし、私たちの体は、その色があることを知っている。私たちの細胞がささやく高周波のエネルギーは、限りなく小さいけれど、生きるために必要なものである。私たちの思考や動作の一つひとつが、低周波の脈動に包まれている。1875年に初めて検出されたこの囁きも、生命維持に必要なものだ。今日、私たちが使っている電気は、何気なく電線を通して送ったり、空中に流したりしている物質だが、1700年頃に生命の性質であることが確認された。その後、科学者たちは電気を取り出し、無生物を動かすことを学んだが、目に見えないため、生命界への影響を無視したのである。しかし、生命が誕生したときには存在しなかったものであるため、私たちはまだそれを見ることができないのである。
私たちは今日、ここに存在しない、その起源を知らない、その存在を当然と思い、もはや疑うこともない、数々の破壊的な病気と共存している。それらがないときの感覚は、私たちがすっかり忘れてしまった生命力の状態なのである。
人類の6分の1が苦しんでいる「不安障害」は、電信線が初めて地球を一周した1860年代以前には存在しなかった。1866年以前の医学書には、その兆候は全く見られない。
現在のようなインフルエンザは、1889年に交流電流とともに発明された。インフルエンザは、いつも私たちのそばにいる、なじみの客人のようなものである。1889年当時、この病気の患者を診たことのない医師が大勢いた。
1860年代以前は、糖尿病は非常に珍しい病気であり、生涯に1人か2人以上の患者を診る医師はほとんどいなかった。糖尿病の患者も、かつては骨格が痩せていた。肥満の人は発症しない。
当時の心臓病は、事故による溺死に次いで25番目に多い病気であった。乳幼児や老人の病気だったのだ。それ以外の人が心臓を悪くするのは異常なことだ。
がんも非常にまれな病気であった。電化されていない時代には、タバコを吸っても肺ガンになることはなかった。
これらの病気は、文明がもたらしたものであり、私たちが利用した力をその正体として認識しようとしないために、動物や植物の隣人にも与えてしまったものである。家の配線に流れる60サイクルの電流、コンピューターの超音波、テレビの電波、携帯電話のマイクロ波、これらは私たちの血管を流れ、私たちを生かしている目に見えない虹の歪みに過ぎないのである。しかし、私たちは忘れてしまっているのである。
今こそ、思い出すべき時なのである。
第1部
1. ボトルの中に閉じ込めた
「ライデンの実験」は世界的な大流行となり、どこに行ってもその効果を体験したかと聞かれるようになった。1746年のことだ。場所は、イギリス、フランス、ドイツ、オランダ、イタリアのどの都市でもよかった。数年後、アメリカでも。まるで天才児がデビューするように、電気が登場し、西欧諸国はこぞってその演奏を聞きに来た。
彼の助産婦であるクライスト、クネウス、アラマン、ミュッシェンブルックは、その衝撃で息を呑み、血を沸かし、麻痺させることができる恐ろしい子供を誕生させたと警告を発した。国民はもっと耳を傾け、慎重になるべきであった。しかし、科学者たちの色とりどりの報告は、もちろん群衆を勇気づけるだけだった。
ライデン大学の物理学教授ピーテル・ファン・ミュッシェンブロックは、いつものように摩擦装置を使っていた。ガラス球を高速で回転させながら、手でこすって「電気流体」、つまり今日私たちが知っている静電気を発生させるのである。天井から絹の紐で吊るされた鉄の砲身は、地球儀とほぼ接触している。これは「主伝導体」と呼ばれ、通常はこすって回転するガラス球から静電気の火花を出すために使用された。
1746年、「Mémoires de l’Académie Royale des Sciences Plate 1, p.23」より線刻画
原文参照
しかし、当時の電気は、その場で作らなければならず、保存する方法もないため、用途が限られていた。そこで、マッシェンブロークたちは、世界を変えるような独創的な実験を考案した。主電導体のもう一方の端にワイヤーを取り付け、それを水で満たした小さなガラス瓶に差し込んだ。電気を流すと、その電気を瓶の中に貯めることができるのかどうか。そして、この試みは予想以上に成功した。
マッシェンブロークは、パリの友人に宛てて「新しい、しかし恐ろしい実験についてお話ししよ。」彼は右手に瓶を持ち、もう片方の手で銃身から火花を出そうとした。「突然、右手に衝撃が走り、全身が雷に打たれたように震えた。ガラスは薄くても割れず、手も飛ばされなかったが、腕と体全体が表現できないほどひどい衝撃を受け」 発明の仲間である生物学者のジャン・ニコラ・セバスチャン・アラマンも、この実験を行ったとき、「とんでもない衝撃」を感じたという。「あまりの衝撃に、しばらくの間、息ができなかった」。右腕の痛みもひどく、後遺症が残るのではないかと心配になったほどだ2。
しかし、このメッセージの半分しか世間には伝わっていない。しかし、この実験によって人々が一時的に、あるいは後遺症が残るほど傷つき、死に至る可能性があるという事実は、その後の一般的な興奮の中で失われてしまった。そればかりか、すぐに嘲笑され、不信感を抱かれ、忘れ去られてしまった。当時も今も、電気が危険だと言うことは社会的に認められていない。ちょうど20年後、酸素の発見で有名なイギリスの科学者ジョセフ・プリーストリーは、『電気の歴史と現状』を書き、「臆病な教授」マッシェンブルックと最初の実験者たちの「誇張した説明」を嘲笑した3。
警告を発したのは発明者たちだけではなかった。ドイツのライプチヒでギリシャ語とラテン語の教授をしていたヨハン・ハインリッヒ・ウィンクラーは、その話を聞くや否や、この実験を試してみた。「私は自分の体に大きな痙攣を発見した」と彼はロンドンの友人に手紙を書いた。「血の巡りが悪くなり、高熱が出るのではないかと心配になり、やむなく冷やす薬を使った。そのため、熱病を恐れて、冷やす薬を使わなければならなかった。この薬で二度ほど鼻血が出たが、これは私の嫌いなタイプである。妻は2回だけ受けたが、その後衰弱してほとんど歩けなくなった。一週間後、彼女は一度だけ閃光を受けたが、その数分後に鼻血が出た」。
ウィンクラー氏は、この体験から「電気は生者に与えてはいけない」という教訓を得た。そして、自分の機械を大きな警告の標識に変えた。「ベルリンからの新聞に、「鳥に電気ショックを与えて、大きな痛みを与えたという記事を読んだ」と書いている。私はこの実験を繰り返さなかった。生き物にこのような苦痛を与えることは間違っていると思うからだ。そこで彼は、鉄の鎖を瓶に巻きつけ、銃身の下にある金属片につなげた。「そして電気を流すと、パイプから金属の上に飛ぶ火花はとても大きく、とても強いので、(昼間でも)50ヤード離れたところでも見ることができ、聞くことができる。そして、その音は聞く人を驚かせるのである」。
しかし、一般市民は彼の計画通りには反応しなかった。フランスの王立科学アカデミーの会議録に掲載されたミュンヘンブルックの報告や、ロンドン王立協会の『哲学論文集』に掲載された彼の報告を読んで、ヨーロッパ中の何千人もの人々が、電気の快楽を味わおうと列をなしていたのである。
神学者から物理学者に転身したジャン・アントワーヌ・ノレ修道院長は、ライデン瓶の魔法をフランスに持ち込んだ。彼は、何十人、何百人もの人々に一度に電気を流し、互いに手をつないで人間の鎖を作り、大きな輪にして両端を近づけることで、人々の飽くなき要求に応えようとした。そして、その両端を結ぶ大きな輪を作り、その輪の一方に自分が入り、もう一方の輪の人が瓶を持つ。突然、修道院長がフラスコに差し込んだ金属線に手で触れて回路を完成させると、たちまち衝撃が全列に同時に伝わった。電気は社会的なものとなり、世界は「エレクトロマニア」と呼ばれるようになった。
ノレが同じ装置で魚やスズメを感電死させたことがあっても、群衆は全く動じなかった。ベルサイユ宮殿では、国王の面前で、240人のフランス軍兵士が互いに手を取り合っているところに感電させた。パリのカルトゥジオ会修道院では、修道士たちが周囲1キロ以上の円形に広がり、それぞれが隣人と鉄線で結ばれていた。
この体験は大変な評判となり、一般の人々から「行列に並んだり、医者にかかることなく電気ショックが受けられない」という不満が出始めた。そこで、誰もが気軽に購入でき、しかも安価に楽しめる携帯型電気スタンドが求められるようになった。そこで開発されたのが、「インゲンハウス・ボトル」である。小さなライデン瓶にニスを塗った絹のリボンをかけ、ウサギの皮でニスをこすって瓶に充電するもので、見た目も優雅なケースに収められていた(4)。
これは、ライデン瓶を杖に見せかけて、こっそり充電し、友人や知人を騙して触らせることができるもので、「あらゆる懐具合に合わせた価格」で売られていた5。
また、「電気キス」という娯楽もあり、これはライデン瓶の発明に先立って行われたものだが、その後、より刺激的なものになった。ゲッティンゲン大学の生理学者アルブレヒト・フォン・ハラーは、このようなパーラーゲームが「カドリーユに取って代わった」と信じられないようなことを言い放った。「女性の指が、鯨骨のペチコートが、真の稲妻の閃光を放ち、その魅力的な唇が、家に火をつけるなんて信じられるだろうか 」と彼は書いている。
1750年頃の線刻画、Jürgen Teichmann, Vom Bernstein zum Elektron, Deutsches Museum 1982に複製。
原文参照
ドイツの物理学者ゲオルク・マティアス・ボースは、彼女は「天使」であり、「白鳥の首」と「血の冠をかぶった胸」を持ち、「一瞥して心を奪う」存在だが、危険を冒して近づくべき相手であると書いている。彼は彼女を 「Venus Electrificata 」と呼び、その詩はラテン語、フランス語、ドイツ語で出版され、ヨーロッパ中に知れ渡ることになった。
もし人間が彼女の手に触れるだけで
そのような神の子の、ドレスにさえも。
火花は同じように四肢を焼き尽くす。
痛くても、またそれを求める。
ベンジャミン・フランクリンでさえも、指示を出さざるを得なかった。「AとBを蝋の上に立たせるか、Aを蝋の上に、Bを床の上に立たせ、一方に電気を流したフィアラを渡し、もう一方に電線を握らせると、小さな火花が出るが、唇が近づくと打たれてショックを受けるだろう」6。
裕福な女性たちは、自宅でこのような催しを行った。彼らは、楽器職人を雇い、大きくて華麗な電気機械を作らせ、ピアノのように飾った。裕福な人々は、サイズやスタイル、価格もさまざまな既製品を購入した。
電気は、娯楽の他に、生命力と同一視され、主に医療用として利用された。電気機械もライデン瓶も、病院や時代の先端を行く医師たちのオフィスに置かれていた。また、医学的な訓練を受けていない「電気技師」が開業し、患者を治療することも多くなった。1740年代から1750年代にかけて、パリ、モンペリエ、ジュネーブ、ベニス、トリノ、ボローニャ、ライプチヒ、ロンドン、ドーチェスター、エディンバラ、シュルーズベリー、ウースター、ニューカッスル・アポン・タイン、ウプサラ、ストックホルム、リガ、ウィーン、ボヘミア、ハーグで医療電気を使っている開業医がいたと言われている。
フランスの有名な革命家で医師のジャン・ポール・マラも電気を使い、「医学的電気に関する覚書」という本を書いている。
フランクリンはフィラデルフィアで患者を電気で治療した。そのため、静電気治療は後に19世紀には「フランクリニゼーション」と呼ばれるようになった。
メソジスト教会の創設者であるジョン・ウェスレーは、1759年に「Desideratum; or, Electricity Made Plain and Useful」という72ページに及ぶ小冊子を出版している。彼は電気を、神経系、皮膚、血液、呼吸器系、腎臓の病気に使用する「世界でまだ知られていない最も高貴な医学」と呼んだ。「地上に立っている人は、ロジンの上に立っている電気を帯びた人に簡単にキスすることはできない」と付け加えざるを得なかった7。ウェスリー自身、メソジスト運動の本部やロンドン周辺の他の場所で、何千人もの人々に電気を流したのである。
そして、店を構えていたのは著名な人物だけではなかった。ロンドンの医師ジェームス・グラハムが1779年に書いたように、医療用でない多くの人々が医療用の機械を買ったり借りたりしていた。「この大都会のほとんどすべての通りで、床屋、外科医、歯切り屋、薬屋、あるいは電気技師になった普通の機械工を見ると、私は自分の仲間のために恐怖に震える」8。
電気は子宮を収縮させることができるため、中絶を行う方法として暗黙の了解となった。例えば、ロンドンの電気技師フランシス・ラウンズは、「無月経のために」貧しい女性を無料で治療すると宣伝し、大規模な診療所を経営していた9。
第6章で述べるように、農家でも農作物に電気を当てる実験を始め、農業生産の改善策として提案するようになった。
この知識は、今日の医師たちが認識しているよりもはるかに広範で詳細なものであり、患者への影響を日々目にしながらも認識されておらず、そうした知識が存在したことさえ知らないのだ。このような情報は、個人の経験を綴った手紙、新聞や雑誌に書かれた記述、医学書や論文、学会で読まれた論文、新しく創刊された科学雑誌に掲載された記事など、公式・非公式なものである。
1740年代には、『Philosophical Transactions』に掲載された全論文の10パーセントが電気に関連するものであった。また、その世紀の最後の10年間には、権威あるラテン語の雑誌『Commentarii de rebus in scientis naturali et medicina gestis』の電気に関する記事の70パーセントが、電気の医学的用途や動物や人間への影響に関連するものであった10。
しかし、水門は大きく開かれ、電気に関する熱狂の奔流は妨げられることなく押し寄せ、今後数世紀の間、注意深さを岩に押しつけ、危険の兆候を多くの流木のように粉砕し、知識の全範囲を消し去り、発明史の単なる脚注に貶めていったのである。
2. 耳が聞こえない人、歩くのが不自由な人
ビルマ・エレファントは、伐採キャンプで働いても、森で自由に歩いても、同じ遺伝子を持っている。しかし、そのDNAはその生命の詳細を教えてはくれない。それと同じように、電子は電気について何が一番面白いかを教えてはくれない。電気も象と同じように、私たちの重荷を背負い、大きな荷物を運ぶことを余儀なくされ、飼育されている間に、その行動を多かれ少なかれ解明してきた。しかし、私たちは、野生のゾウの生活について重要なことをすべて知っていると信じてはならない。
雷や稲妻の源は何だろう?雲が電気を帯びて、その怒りを地上に放出するのは何だろう?科学はまだ解明していない。地球にはなぜ磁場があるのか。櫛でとかした髪が縮んだり、ナイロンがくっついたり、パーティーの風船が壁にくっついたりするのはなぜだろう。この最も一般的な電気現象は、まだよく分かっていない。私たちの脳の働き、神経の働き、細胞のコミュニケーションはどのように行われているのだろうか。私たちの体の成長は、どのように振り付けられているのだろうか?私たちはまだ根本的に無知なのだ。そして、本書が提起する「電気が生命に与える影響とは何か」という問いは、現代の科学が問うことさえしないものである。現代の科学が関心を寄せるのは、人間が浴びる電気を、細胞を焼いてしまうような低いレベルに抑えることだけである。致死的でない電気の影響は、科学の主流はもはや知りたくないことなのだ。しかし、18世紀には、科学者たちはその疑問を投げかけるだけでなく、答えを出し始めている。
初期の摩擦機械は、1万ボルト程度まで充電することができた。これは、刺すようなショックを与えるには十分だが、当時も今も、危険だと考えるほどではない。ちなみに、人が合成繊維のカーペットの上を歩くと、3万ボルトの電圧が体に蓄積される。それを放電すると、チクチクするが、死ぬことはない。
1パイントのライデン瓶は、0.1ジュールのエネルギーを含む、より強力なショックを与えることができるが、それでも危険と考えられているものより約100倍少なく、心停止した人を蘇生させるために除細動器が日常的に与えているショックより数千倍少ないのである。現在の主流派科学では、18世紀に使われた火花、衝撃、微小電流は健康に影響を与えないはずである。しかし、影響はあったのである。
あなたが1750年に関節炎で苦しんでいた患者だと想像してほしい。電気技師は、地面から十分に絶縁されたガラスの脚を持つ椅子にあなたを座らせるだろう。これは、あなたが摩擦装置に接続されたとき、「電気流体」を地球に排出するのではなく、体内に蓄積させるためである。電気屋さんの考え方、病気の程度、電気に対する耐性などによって、いろいろな「電気治療」が行われた。最も穏やかな「電気風呂」では、主電源につながった棒を手に持って、数分から数時間、機械を回し続け、電荷を体中に伝え、電気的なオーラを身にまとわせるのである。これは、カーペットの上で足を動かすと、知らず知らずのうちに体に電荷が蓄積されるのと同じである。
こうして 「浴びせ」をした後、機械を止めて 「電気風」を浴びせることもある。電気は、尖った導体から最も容易に放電する。そのため、接地された先の尖った金属や木製の杖を痛みのある膝に近づけると、身体に蓄積された電荷が膝から接地された杖にゆっくりと放散され、小さな風のような感覚を再びほとんど感じないだろう。
より強力な効果を得るために、電気技師は先端が丸くなった杖を使い、連続電流の代わりに膝から実際の火花を出すかもしれない。また、足が麻痺しているなど症状がひどい場合は、小さなライデン瓶に電気を流して、足に強い衝撃を与えることもあった。
電気には、ガラスをこするとできる「硝子電気」と、硫黄や樹脂をこするとできる「樹脂電気」がある。電気屋さんでは、健康な体の表面にあるプラスの電気で治療することが多いようだ。
電気治療の目的は、体の電気的なバランスを崩すことによって健康を増進させることだ。この考え方は、確かに新しいものではなかった。世界の別の地域では、自然の電気を利用した治療が何千年にもわたって発展してきたのである。第9章で紹介する鍼は、大気中の電気を体内に送り込み、正確にマッピングされた経路を通り、他の鍼を通して大気中に戻り、回路を完成させるのである。それに比べると、欧米の電気療法は、コンセプトは似ていても、ハンマーのような器具を使った、まだ始まったばかりの科学だった。
18世紀のヨーロッパの医療は、ハンマーだらけでした。リウマチを治すために従来の医者にかかると、血を流され、瀉血され、吐かれ、水ぶくれにされ、さらには水銀を投与されることも予想されたのである。だから、電気屋に行くというのは、とても魅力的な選択肢に思える。そして、20世紀初頭まで、その魅力は続いていた。
ヨーロッパではアントン・メスマーがいわゆる「磁気」療法を、アメリカではエリシャ・パーキンスが「電気」トラクター(長さ3インチの金属製の鉛筆で体の不調な部分を通過させる)を流行らせた。どちらも実際の磁石や電気はまったく使っていないが、この2つの方法は、一時期悪評を買った。世紀半ばには電気が再び主流となり、1880年代には1万人のアメリカの医師が患者に施療を行うようになった。
電気療法は、20世紀初頭には、ついに永久に人気がなくなってしまった。電気は、もはや生物に関係するような微妙な力ではなく、ダイナモのようなものであった。電気は発電機であり、患者を治療するのではなく、機関車を走らせたり、囚人を処刑したりすることができる。しかし、世界が電化される1世紀半も前に、摩擦機によってもたらされた火花は、全く異なる意味をもっていた。
電気が大小の病気を治すことがあったのは間違いない。およそ2世紀にわたる成功の報告は、時に誇張されていたこともあったが、そのすべてを否定するには、あまりにも数が多く、多くの場合、詳細で実証的なものであった。電気があまり評判の良くなかった1800年代初頭でさえ、無視できない報告が続々と出てきた。例えば、ロンドンの電気診療所では、1793年9月29日から1819年6月4日の間に、8,686人の患者を電気治療のために受け入れている。このうち、3,962人が「治癒」、さらに3,308人が「緩和」して退院したと記録されており、成功率は84パーセントであった1。
この章では、必ずしも有益とはいえない効果に焦点を当てるが、18世紀の社会がなぜ今日のように電気に夢中になったかを覚えておくことは重要である。ほぼ300年にわたり、電気がもたらす利益を追い求め、その害を否定する傾向があった。しかし、1700年代から1800年代にかけて、電気が医療に日常的に使われていたことは、少なくとも電気が生物学と密接に関係していることを常に思い起こさせるものであった。ここ西洋では、生物学としての電気は今日でも未熟であり、その治療法さえも長く忘れ去られている。その一つを思い出してみよう。
耳の聞こえない人に聞こえるようにする
1851年、神経学者ギョーム・ベンジャミン・デュシェーヌ・ド・ブローニュは、今日ではほとんど記憶されていないことで、その名を知られるようになった。医学史に名を残す彼は、決してヤブ医者ではなかった。彼は、現在でも使われている近代的な身体検査法を導入した。彼は、診断のために生きている人間から生検を行った最初の医師である。ポリオの正確な臨床的記述を初めて発表した。デュシャンヌ型筋ジストロフィーを筆頭に、彼が発見した多くの病気に彼の名前がつけられている。彼はこれらすべてのことで記憶されている。しかし、彼の時代には、聴覚障害者のための研究によって、やや不本意ながら注目される存在となった。
デュシェンヌは耳の解剖学に詳しく、実際、中耳を通る鼓索という神経の働きを解明するために、数人の聴覚障害者に電気実験の被験者となることを志願させたのである。すると、思いがけず聴力が向上したため、聴覚障害者の中からパリに治療を受けに来たいという声が殺到した。そこで彼は、研究のために考案した、外耳道にぴったりとフィットする刺激電極の入った器具を使って、大勢の神経難聴者を治療するようになった。
その方法は、現代の読者から見れば、何の効果もないように思えるかもしれない。彼は、患者にできるだけ弱い電流のパルスを、半秒間隔で、一度に5秒間流した。その後、電流の強さを徐々に上げていったが、決して痛くない程度に、また一度に5秒以上電流を流すことはなかった。10歳の時から耳が聞こえなかった26歳の男性、9歳の時にはしかにかかって以来耳が聞こえなくなった21歳の男性、マラリアのために投与されたキニーネの過剰摂取で耳が聞こえなくなった若い女性、その他多くの部分的または完全な難聴者が、この方法で数日から数週間のうちに良好な聴力を回復した2。
その50年前、ドイツのイエバーで、ヨハン・シュプレンガーという薬屋が、同じような理由でヨーロッパ中に名を知られるようになった。シュプレンガーは、ベルリンの聴覚障害者研究所長から非難されたが、聴覚障害者から治療の依頼が殺到し、その成果は裁判でも証明された。彼の成果は裁判資料にもなり、その方法は同時代の医師たちによって採用された。彼自身、40人以上の聴覚障害者(生まれつきの聴覚障害者も含む)の聴力を完全に、あるいは部分的に回復させたと報告されている。彼の方法は、デュシェンヌの方法と同様、非常にシンプルで穏やかなものであった。患者の感度に合わせて電流を弱くしたり強くしたり、1秒間隔の短いパルス電気を片耳4分間流すという治療法である。電極は、トラガス(耳の前の軟骨)に1分、外耳道の内側に2分、耳の後ろの乳様突起に1分、それぞれ当てていた。
シュプレーガーより50年も前に、スウェーデンの医師ヨハン・リンドフルトは、ストックホルムから、32年間耳が聞こえなかった57歳の男性、最近難聴になった22歳の青年、生まれつき耳が聞こえない7歳の少女、11歳から耳が聞こえにくい29歳の青年、左耳の難聴と耳鳴りの男性に2ヶ月間で聴力が完全にまたは部分的に回復したと報告している。リンドフルトは、「すべての患者は、単純電流または電気風という穏やかな電気で治療された」と書いている。
1752年当時のリンドハルトは、摩擦機械を使用していた。その半世紀後、シュプリンガーは、今日の電池の前身である電気杭からガルバニ電流を流していた。その半世紀後、デュシェンヌは誘導コイルによる交流電流を使った。また、イギリスの外科医マイケル・ラ・ボームも、1810年代にフリクションマシン、その後ガルバニック電流を使い、成功を収めている。彼らに共通しているのは、治療が簡潔でシンプル、かつ無痛であることにこだわっていることだ。
電気を見る、味わう
初期の電気技師は、聾や盲などの病気を治そうとした以外に、電気が五感で直接感じられるかどうかに強い関心を持っていた。現代の技術者が関心を持たず、現代の医師も知らない問題だが、その答えは電気過敏症に悩む現代人全てに関係する。
後に探検家となるアレキサンダー・フォン・フンボルトは、まだ20代前半の頃、この謎を解明するために自らの肉体を提供した。彼は、オリノコ川を遡り、チンボラソ山の頂上まで行く長い航海に出るまで数年かかった。その後、半世紀を経て、彼は5巻からなる『コスモス』(現存するすべての科学的知識を統一する試み)の執筆に取り掛かったのである。しかし、バイエルン州バイロイトで鉱山監督をしていた青年は、暇さえあれば、その時々の中心的な疑問について考えていた。
電気は本当に生命力なのか?アイザック・ニュートンの時代から、ヨーロッパの人々の心の中にあったこの疑問は、突如として、高尚な哲学の世界を飛び出して、一般庶民の食卓で、その子供たちが選んだ答えとともに生きていかなければならない議論に突入していった。異種金属を接触させて電流を発生させる「電気電池」がイタリアで発明されたばかりだった。この発明が意味するところは大きい。かさばるし、高価だし、信頼性に欠けるし、大気の状態にも左右される摩擦機械は、もはや必要ないかもしれない。電信機は、すでに一部の先見の明のある人たちによって設計されていたが、これからは実用化されるかもしれない。また、電気流体の性質に関する疑問にも答えが出るかもしれない。
1790年代初め、フンボルトはこの研究に熱中していた。彼は、この新しい電気の形を、自分の目、耳、鼻、味覚で感じることができるかどうかを確かめたいと思ったのである。イタリアのアレッサンドロ・ボルタ、イギリスのジョージ・ハンターやリチャード・ファウラー、ドイツのクリストフ・プファッフ、デンマークのピーター・アビルゴールなど、同じような実験をしている人がいたが、フンボルトほど徹底的に、熱心に研究している人はいない。
今日、私たちは9ボルトの電池を何気なく手で扱うことに慣れていることを考えよう。また、何百万人もの人が、口の中の詰め物に銀や亜鉛、金や銅などの金属を入れたまま歩き回っていることを考えてみてほしい。そして、フンボルトの次のような実験を考えてみてほしい。亜鉛を1個、銀を1個使って、約1ボルトの電気張力を発生させたのである。
「生来怠け者の大型狩猟犬は、亜鉛片を口蓋に当てるのを非常に辛抱強く待ち、別の亜鉛片を最初の亜鉛片と舌に接触させる間、完全に平静を保っていた。彼は上唇を痙攣させ、非常に長い間自分自身を舐めていた。その後、亜鉛の破片を見せると、彼が経験した印象を思い出し、怒るので十分だった。
電気が簡単に知覚できること、そしてその感覚が多様であることは、今日のほとんどの医師にとって驚きであろう。フンボルトは、自分の舌の上部を亜鉛の破片で、その先を銀の破片で触ると、強い苦い味がした。銀の破片を下に移すと、舌が火傷した。亜鉛を奥に、銀を手前に動かすと、舌が冷たくなる。亜鉛をさらに奥に動かすと、吐き気を催し、時には吐いてしまうこともあった。この感覚は、亜鉛と銀を互いに金属的に接触させると、必ず起こるのである3。
視覚の感覚は、同じ1ボルトの電池を使って、4つの異なる方法によって、同じように簡単に引き出された:片方の湿ったまぶたに銀の「電機子」を当て、もう片方に亜鉛を当てた場合、片方を鼻孔に、もう片方を目に当てた場合、舌に一つ、目に一つ、さらには舌に一つ、上の歯茎に一つ当てた場合である。どの場合にも、二つの金属が触れ合った瞬間に、フンボルトは閃光を見たのである。この実験を何度も繰り返すと、彼の目は炎症を起こしてしまった。
イタリアでは、電気電池の発明者であるボルタが、1組の金属ではなく、30組の金属を両耳に電極を付けて、音の感覚を引き出すことに成功した。電解質として水を使い、当初彼が「パイル」に使った金属で、20ボルト程度の電池であったと思われる。ボルタは、中耳の骨に機械的な影響を与えたと思われるパチパチという音を聞いただけで、脳への衝撃が危険であることを恐れて実験を繰り返さなかった(4)。
心臓を速くし、心臓を遅くする
ドイツに戻ったフンボルトは、同じように一片の亜鉛と銀を手に、次は心臓に目を向けた。フンボルトは兄のヴィルヘルムとともに、著名な生理学者の指導のもと、キツネの心臓を取り出し、その神経線維の1本を準備し、心臓そのものに触れることなく電機子を当てることができるようにした。「金属に触れるたびに心臓の脈動は明らかに変化し、その速さ、特に力、高揚が増大した」と記録している。
次に兄弟は、カエル、トカゲ、ヒキガエルで実験した。解剖した心臓が1分間に21回動くとすると、電流を流した後の心臓は1分間に38〜42回動いた。また、5分間停止していた心臓も、2つの金属に触れるとすぐに鼓動が再開された。
フンボルトはライプチヒの友人と一緒に、ほとんど脈を打たなくなった鯉の心臓を刺激して、4分に1回だけ脈を打たせた。心臓をマッサージしても効果がないことがわかったが、溶融亜鉛メッキを施すと、1分間に35回の拍動を取り戻した。二人は、一対の異種金属で繰り返し刺激することによって、ほぼ25分間心臓の鼓動を維持した。
また、フンボルトは、足を上げて仰向けに目を閉じて、ピンを刺しても反応しない瀕死のコガタスズメバチを蘇生させたこともある。「急いで亜鉛の小皿をくちばしに、銀の小片を直腸に入れ、すぐに鉄の棒で2つの金属の間を通電させた」と彼は書いている。その瞬間、鳥は目を開け、立ち上がり、翼を打ち鳴らした。そして、6〜8分ほど呼吸をした後、静かに息を引き取ったのである」5。
しかし、フンボルト以前にも、電気が人間の脈拍数を増加させることは、多くの研究者によって報告されていた。ドイツの医師クリスチャン・ゴットリーブ・クラッツェンシュタイン6とカール・アブラハム・ゲルハルト7、ドイツの物理学者セレスタン・スタイグルナー8、スイスの物理学者ジャン・ジャラベール9、フランスの医師フランソワ・ボワジエ・ド・サウバージュ・ド・ラクロワ10、ピエール・モードユット・ド・ラ・バレンヌ11、ジャン=バプティスト・ボヌフォワ12。 12 フランスの物理学者ジョセフ・シゴー・ド・ラ・フォン13、イタリアの医師エウセビオ・スガリオ14とジョヴァン・ジュゼッピ・ヴェラッティ15は、電気風呂がプラスの電気を使った場合、1分間に5から30回脈拍が増加すると報告した観察者の一人であった。マイナスの電気は逆効果であった。1785年、オランダの薬剤師ウィレム・ファン・バーネベルトは、9歳から60歳までの男性、女性、子供43人を対象に169回の実験を行い、プラスの電気を浴びると平均5%、マイナスの電気を浴びると3%の脈拍の増加が見られた16。
しかし、これはあくまで平均値であり、電気に対する反応は二人一組で同じではない。ある人の脈拍は1分間に60回から90回に増え、ある人の脈拍は常に2倍になり、ある人の脈拍はかなり遅くなり、ある人は全く反応しなかった。ある人は脈拍が1分間に60〜90回上がり、ある人は2倍になり、またある人は脈拍がかなり遅くなり、ある人は全く反応しなかった。
「愚かな行為」
18世紀末には、電気流体(通常は正電荷)が人体に及ぼす影響について、基本的な知識が蓄積されるようになっていたのである。18世紀末には、電熱流体(通常は陽タイプのもの)が人体に及ぼす影響についての基本的な知識が蓄積されていた。体内のあらゆる分泌物を増加させる。電気は唾液を分泌させ、涙を流させ、汗を流させた。耳垢や鼻の粘液の分泌を促した。胃液を分泌させ、食欲を増進させる。乳を漏らし、月経血を出す。排尿を盛んにし、腸を動かす。
このような作用のほとんどは、電気療法に有効であり、20世紀初頭までその効果が持続した。その他の作用は、純粋に好ましくないものであった。通例、頭痛、吐き気、脱力感、疲労感、動悸が生じる。時には息切れ、咳、喘息のような喘鳴を引き起こすこともあった。また、筋肉痛や関節痛、時には精神的な落ち込みを引き起こすこともあった。電気は通常、腸を動かし、しばしば下痢を起こしたが、繰り返し通電すると、便秘になることもあった。
電気は眠気と不眠を引き起こした
フンボルトは、自分自身の実験で、電気が傷口からの血流を増加させ、水疱から多量の血清を流出させることを発見した18 ゲルハルトは、1ポンドの新鮮な血液を2等分し、それを横に並べて、片方に電気を流した。パリの有名な病院、オテル・デューの薬剤師、アントワーヌ・ティライエ・プラテルは、電気は出血の場合には禁忌であると言っている20。すでに述べたようにウィンクラー夫妻は、ライデン瓶の衝撃で鼻血を出した。1790年代には、リンパ系の機能を発見したことで知られるスコットランドの医師で解剖学者のアレキサンダー・モンローが、目に光の感覚を引き出そうとすると、たった1ボルトの電池で鼻血が出たという。「モンロー博士はガルバニズムに非常に興奮しやすく、亜鉛を鼻の窩に非常に優しく挿入し、舌に当てた電機子に接触させると、鼻から出血した。出血はいつも光が現れた瞬間に起こった」。1800年代初頭、ストックホルムのコンラッド・クエンセルは、ガルバニズムが「頻繁に」鼻血を引き起こすと報告している22。
Abbé Nollet, Recherches sur les Causes Particulières des Phénomènes Électriques, Parisの線刻画。Frères Guérin, 1753
ノレは、これらの効果のうち少なくとも1つは、電界の中にいるだけで発汗が起こることを証明した。摩擦機と実際に接触する必要さえなかったのだ。彼は、猫、ハト、数種類の鳴禽類、そしてついに人間にも電気を流したのである。その結果、皮膚からの水分の蒸発が促進され、体重の減少が確認された。さらに、500匹のイエバエをガーゼで覆った瓶に入れて4時間電気を流したところ、同じ時間で電気を流さない場合に比べて4粒も多く体重が減ったことが分かった。
そこでノレは、電気を流した金属製のかごの中の被験者を、かごの下の床に寝かせることを思いついた。ノレは、電気を流した鉢に植えた苗の成長が早くなることも観察していた。「最後に、「電気を流した金属製のかごの近くのテーブルに5時間座らせた」とノレは書いている。その若い女性は、実際に電気を流したときよりも4½ドラムも体重が減ったという23。
このように、ノレは1753年当時、直流電場(今日の主流科学では何の効果もないとされる電場)への曝露による重大な生物学的影響を報告した最初の人物であった。彼の実験は、後にバイエルン州インゴルシュタット大学の物理学教授であるシュタイグルナーによって、鳥を使って再現され、同様の結果が得られている24。
表1は、初期の電気技術者が報告した、電荷や直流小電流が人間に与える影響の一覧である。電気に敏感な現代人なら、すべてとは言わないまでも、そのほとんどを認識できるだろう。
表1 – 18世紀に報告された電気の効果
治療効果および中立的効果
非治療効果
- 脈拍の変化
- めまい
- 味覚、光、音の感覚
- 音
- 吐き気
- 頭痛
- 体温の上昇
- 神経過敏
- 痛みの緩和
- 過敏症
- 筋緊張の回復
- 精神錯乱
- 食欲増進
- 抑うつ
- 精神的な高揚感
- 不眠症
- 鎮静
- 眠気
- 発汗
- 疲労感
- 唾液分泌
- 虚弱体質
- 耳垢の分泌
- しびれ・ピリピリ感
- 粘液の分泌
- 筋肉痛・関節痛
- 月経・子宮収縮
- 収縮
- 筋肉の痙攣、けいれん
- 腰痛
- 乳汁分泌
- 心臓の動悸
- 流涙症
- 胸痛
- 排尿
- 疝痛
- 排便
- 下痢
- 便秘
- 鼻血・出血
- かゆみ
- 震え
- 痙攣(けいれん
- 麻痺(まひ
- 発熱
- 呼吸器感染症
- 息切れ
- 咳
- 喘ぎ、喘息発作
- 目の痛み、脱力感、疲労感
- 耳鳴り
- 金属味
3. 電気的感受性
「私はほとんど電気実験をあきらめた」。この言葉の作者は、自分が電気に耐えられないことを指して、交流電流や電波のある現代ではなく、静電気しかなかった18世紀半ばにこの言葉を書いているのである。フランスの植物学者ダリバールは、1762年2月の手紙の中で、その理由をベンジャミン・フランクリンに打ち明けている。「まず、さまざまな電気ショックが私の神経系を強く攻撃し、腕に痙攣性の震えが残っていて、グラスを口に運ぶことがほとんどできない。もうひとつ気づいたことは、手紙に封をするのがほとんど不可能だということだ。スペイン蝋の電気が私の腕に伝わり、震えが増すのだ」。
ダリバールだけではない。ベンジャミン・ウィルソンが1752年に出版した『電気論』は、イギリスにおける電気の普及に貢献したが、彼自身はあまりうまくいかなかったようである。「このような衝撃を数週間にわたって頻繁に繰り返した結果、私はついに衰弱し、小瓶の中のごく少量の電気物質が私に大きな衝撃を与え、尋常でない痛みを引き起こすようになった」と彼は書いている。そのため、これ以上試すのをやめざるを得なかった」と書いている。当時の基本的な電気機械であるガラス球を手でこするだけでも、「非常に激しい頭痛に襲われた」のである1。
ドイツで初めて電気だけをテーマにした本「Neu-Entdeckte Phænomena von Bewunderns-würdigen Würckungen der Natur」(1744年、「自然の不思議な働きに関する新発見の現象」)を書いた彼は、次第に身体の片側が麻痺していった。電気工学の最初の殉教者と呼ばれるニュルンベルクの数学教授ヨハン・ドッペルマイヤーは、頑固に研究を続け、1750年に電気実験の後、脳卒中で死亡した2。
この3人の科学者は、電気革命の誕生に貢献したが、彼ら自身が参加することはできなかったのだ。
フランクリンも、電気工学の研究をしていた時期に神経系の持病を発症し、生涯にわたって定期的に再発を繰り返した。痛風にも悩まされたが、それ以上に心配だったのは、この問題であった。1753年3月15日、彼は頭の痛みについて書き、「これが足であったら、もっとよく耐えられると思うのだが」と述べている。1757年にロンドンに滞在していたときにも、5ヶ月間ほど再発が続いた。彼は、「めまいと頭の中の水泳」、「ハミングのような音」、「視界を妨げる小さなかすかな光」について医師に手紙を書いている。激しい寒気」という言葉は、彼の手紙の中にたびたび出てくるが、たいてい同じような痛み、めまい、視力の問題を伴っている3。
シャルトル・コレージュ・ロワイヤルの物理学教授で、1748年に『電気に関する新しい論文』(Nouvelle Dissertation sur l’Électricité)を著したジャン・モランは、いかなる形でも電気に触れることは健康に良くないと考えており、それを示すために摩擦機ではなく、ペットの猫で実験を行ったことを述べている。「大きな猫をベッドの上に寝かせた。「擦ってみると、暗闇の中で火花が散るのが見えた」。彼は30分以上これを続けた。「その火花が大きくなり、ヘーゼルナッツほどの大きさの球体になった。その球体に目を近づけると、すぐに目を刺すような痛みを感じたが、体の他の部分には衝撃はなかった。 “4
このような反応は、決して科学者に限ったことではなかった。電気には副作用があり、ある種の人々は、他の人々よりも非常に敏感で、説明のつかないほどであった。「1780年、ラングドック出身の物理学者ピエール・ベルトロンが、「人工電気が最も大きな印象を与える人がいる。この両極端の間には、人間という種の多様な個体に対応する多くのニュアンスが存在する」5。
シゴー・ド・ラ・フォンは、人間の鎖を使った数々の実験を行ったが、同じ結果が出ることはなかった。「電気が不幸なものであったり、非常に有害であったりする人々がいる」と彼は宣言した。「この印象は、電気を体験する人の器官の性質、神経の感受性や過敏性に関連しており、多くの人からなる鎖の中で、厳密に同じ程度の衝撃を体験する人はおそらく二人もいないであろう」6。
医師であったモーダイトは、1776年に「体質の表れは、脳と脊髄と各部位の間の神経によるコミュニケーションに大きく依存する」と提唱した。このコミュニケーションがあまり自由でない人、あるいは神経の病気を経験した人は、他の人よりも大きな影響を受ける」7。
この違いを説明しようとする科学者は、他にほとんどいなかった。太っている人と痩せている人、背の高い人と低い人がいるのと同じくらい普通の事実だが、電気を治療として提供したり、人々を電気にさらす場合には、考慮しなければならない事実として報告されただけであった。
人間の鎖を普及させ、電気を広めたアッベ・ノレでさえ、このような人間の状態のばらつきについて、運動の当初から報告している。彼は1746年に「特に妊娠中の女性や繊細な人は、電気にさらされてはならない」と書いている。そして後に 「すべての人が電気の実験に等しく適しているわけではない、その美徳を刺激するにも、それを受けるにも、最終的にその効果を感じるにもだ」8。
1749 年、イギリスの医師ウィリアム・ステークレーは、すでに電気の副作用に精通して おり、その年の 3 月 8 日にロンドンで起きた地震の後、「関節の痛み、リューマチ、病気、頭痛、背中の痛み、 ヒステリー、神経障害…まさに電気に触れたときのようだ」と感じた人がいたことを確認し、 一部の人には致命的だと証明した(9)」 地震には電気現象が大きな役割を果たすはずだという結論を出している。
そして、フンボルトは、人間の異常な変化に驚き、1797年に「電気刺激に対する感受性と電気伝導性は、生体と死体の現象が異なるように、個人によって大きく異なることが観察される」10と書いている。
この「電気感受性」という言葉は、今日も使われているが、ある真実を示しているが、ある現実を隠している。実は、誰もが同じように電気を感じたり、伝えたりしているわけではないのだ。もし、多くの人が、電気感受性のスペクトルがいかに広いかを知れば、フンボルトのように、また、私のように、驚嘆する理由があるだろう。しかし、私たちの間にどんなに大きな違いがあっても、電気は私たちの一部であり、空気や水と同じように生命に必要なものであるというのが、隠された現実である。電気は、空気や水と同じように、私たちが生きていくために必要なものなのである。
今日、電気に敏感な人たちは、送電線、コンピューター、携帯電話について文句を言っている。このようなテクノロジーによって偶発的に体内に蓄積される電気エネルギーの量は、18世紀から19世紀初頭にかけて電気技師が利用した機械によって意図的に蓄積された量よりはるかに多い。例えば、平均的な携帯電話は、1秒間に約0.1ジュールのエネルギーを脳に供給している。1時間の通話で360ジュールである。これに対して、1パイントのライデン瓶を完全に放電させたときの最大エネルギーはわずか0.1ジュールである。ボルタが耳の穴に取り付けた30本の電気杭でさえ、そのエネルギーをすべて体に吸収させたとしても、1時間で150ジュール以上は出せないだろう。
また、コンピュータの画面には、古いデスクトップコンピュータも新しいワイヤレスノートPCも、使っているうちに何千ボルトもの静電気が蓄積され、その一部が画面の前に座ったときに体の表面に付着することも考えてみよう。しかし、電気風呂に週40時間も入っていた人はいない。
電気治療は時代錯誤なのだ。21世紀の今、私たちは好むと好まざるとにかかわらず、電気治療に携わっている。かつては時折使用することが有益であったとしても、永久に浴び続けることはそうでないだろう。そして、電気の生物学的影響を見極めようとする現代の研究者は、水の影響を見極めようとする魚に少し似ている。18世紀の先人たちは、世界が水浸しになる前だったので、その影響を記録するのに非常に有利な立場にあったのである。
フンボルトが指摘した第二の現象は、現代技術や現代医学にも大きな影響を与える。電気の影響を受けやすい人と受けにくい人がいるだけでなく、電気を通す能力や体の表面に電荷が溜まりやすいかどうかにも個人差が極めて大きい。ある人は、動いたり、呼吸をしたりするだけで、どこにいても電荷を集めずにはいられない。スコットランドの作家パトリック・ブライドンが旅先で耳にしたスイス人女性のように、彼らは歩く火花発生器であった。ブライドンは、彼女の火花や衝撃は「晴れた日や雷雲が通過するときに最も強く、空気中にはその液体が豊富にあることが知られている」と書いている11。
また、逆に、手をよく湿らせても電気の通りが悪く、人の鎖の中にいると電流が途切れてしまうような、人間不導体も発見された。フンボルトは、この種の実験を、いわゆる「仕込み蛙」を使って何度も行っている。8人の連鎖の片方の人がカエルの坐骨神経につながった針金を握り、もう片方の人がカエルの大腿部の筋肉につながった針金を握ると、回路の完成によって筋肉が痙攣するのである。しかし、この連鎖のどこかに不導体となる人間がいると、そうはならない。フンボルトは、ある日、熱を出して一時的に不導体となり、この鎖を中断してしまった。彼はまた、その日の電流で目の閃光を引き出すこともできなかった12。
1786年のアメリカ哲学会論文集には、ヘンリー・フラッグが、リオ・エスキボ(現在のガイアナ)で行われた、多人数の鎖で電気ウナギの両端をつかむ実験について、同じような内容の報告をしている。フラッグは、「体質的に電気流体の印象を受けにくい人がいた場合、その人は魚と接触した瞬間に衝撃を受けなかった」と書いている。フラッグは、フンボルトと同じように、実験時に微熱のあったそのような女性のことを述べている。
このことから、18世紀の科学者たちは、電気的感度と電気伝導度の両方が、その人の健康状態全般を示す指標であると仮定したのである。ベルトロンは、ライデン瓶が発熱している患者から弱々しい火花を出すのと、健康な人から同じ火花を出すのでは、より遅いことを観察した。寒気がするときには、その逆で、患者が超伝導体になったように見え、その人から出る火花は通常より強くなった。
ベンジャミン・マーティンによれば、「天然痘の患者は、いかなる手段によっても電気を流すことができない」13。
しかし、以上のような観察にもかかわらず、電気的感受性も電気伝導度も、健康か悪いかの信頼できる指標とはならなかった。ほとんどの場合、それらはランダムな属性であるように思われる。たとえば、マッシェンブロックは、『物理学講座』の中で、3人の人物を取り上げているが、その人物は、いかなるときにも、まったく電気を通すことができなかったという。一人は元気で健康な50歳の男性、二人目は健康でかわいい40歳の二児の母、そして三人目は23歳の下半身不随の男性であった14。
年齢と性別が関係しているようである。ベルトロンは、電気は幼児や老人よりも壮年の若い男性に大きな影響を与えると考えた15。スガリオによれば、「一般に女性は男性よりも容易に、また良い方法で感電するが、一方または他方の性別では、激しい硫黄のような気質が他よりも優れており、老人よりも若者の方が優れている」17 という。 モランによれば、「大人や、より頑健な気質の人、より熱血漢の人、より火のような人は、この物質の動きにも影響を受けやすい」18 このように、元気な若者が何らかの形で他の人より電気に弱いという初期の観察は意外に思えるかもしれない。しかし、この観察が、特にインフルエンザの問題をはじめ、現代の公衆衛生問題にとって重要であることは、後に述べるとおりである。
電気に敏感な人々の典型的な反応を詳しく説明するために、ベンジャミン・ウィルソンが1748年に25歳の時に志願して電気を浴びた使用人の体験談を選んでいる。ウィルソン自身、電気に敏感であったから、当然、他の研究者よりもその影響に敏感であった。電気に敏感な現代人なら、何日も続く後遺症も含めて、その効果のほとんどを認識できるだろう。
ウィルソンは、「第1回と第2回の実験の後、彼は気分が落ち込んで、少し気分が悪いと訴えた」と書いている。4回目の実験の後、彼は非常に暖かくなり、手と顔の静脈が大きく腫れ上がった。脈拍は普通より速く、心臓に激しい圧迫感を感じ、この症状は他の症状とともに4時間近く続いた。乳房を開いてみると、かなり炎症を起こしているように見えた。また、頭が激しく痛み、眼と心臓に刺すような痛みがあり、全身の関節が痛むという。静脈が膨張し始めると、首を絞められたり、ストックで首を締めつけられたりしたときのような感覚を訴えた。実験が始まって6時間後には、これらの訴えはほとんど無くなった。関節の痛みは翌日まで続き、その時は衰弱を訴え、風邪をひかないかと非常に心配した。3日目にはすっかり回復した。
ウィルソンは、「彼が受けた衝撃は、普通の人が手をつないで遊戯の回路を完成させるときに受ける衝撃に比べれば、取るに足らないものであった」と付け加えている(19)。
1748年以前に電気に触れるのをやめたモランも、その悪影響について詳しく述べている。「樹脂のケーキや羊毛のクッションの上で電気を受けた人は、しばしば喘息患者のようになる」と彼は観察している。また、30歳の青年が電気を受けた後、36時間熱にうなされ、8日間頭痛に悩まされたという事例も報告されている。そして、リューマチや痛風を患った人を対象にした自らの実験から、「皆、前よりずっと苦しくなった」と結論づけ、医療用電気を非難した。「電気がもたらす症状は、自分自身を危険にさらすことが賢明でないものである。特に、ライデン瓶の医療利用には否定的で、手に湿疹のある人が、たった2オンスの水の入った小さな瓶から電気ショックを受けたところ、手の痛みが1ヵ月以上も続いたというエピソードを語っている。「それ以来、彼は電気現象の鞭打ち少年になることをあまり望まなくなった」とモランは述べている20。
電気が害になるよりも害になる方が多いかどうかは、当時を生きる人々にとって些細な問題ではなかった。
電気に敏感なモランとそうでないノレは、電気時代の幕開けに、この世界の未来を巡って対立したのである。この論争は、当時の書籍や雑誌で大々的に取り上げられた。電気は、まず第一に生物の持つ性質であり、生命維持のために必要なものであることが知られていた。モランは電気を、生物を含む物質体を取り囲み、接近して他者に伝える大気、呼気のようなものと考えていた。モランは、電気はある場所から別の場所へ流れる物質であり、別の場所からさらに流れ込まない限り流れ出ない物質であり、人類が獲得した物質で、世界中のどこへでも自由に送ることができるというノレの考え方に恐れをなしたのである。ライデン瓶の発明からわずか2年後の1748年、この議論が始まった。
ノレは、驚くべき正確さでこう予言した。「たとえかなり離れた場所にいても、動かさず、迷惑をかけず、多数の人体に同時に電気の効果を感じさせることは簡単だ。この力は、鎖や他の連続した物体によって、非常に簡単に遠くまで伝えられることがわかっているからだ。普通の産業が発明できるような、もっと簡単な手段がたくさんあれば、これらの効果は全世界の手の届くところにあり、その利用は望む限り拡大されるに違いないのである。 」21
モランはショックを受けた。傍観者たちはどうなるのだろう、と彼はすぐに考えた。「全宇宙、少なくとも巨大な球体を、小さな電気火花がパチパチと鳴るだけのために、あるいは鉄棒の先に長さ5,6インチの光輪を形成するために、作動させ、運動させることは、まさに意味なく大騒動を引き起こすことになる。電気物質を最も密度の高い金属の内部に浸透させ、明らかな原因もなく放射させることは、おそらく良いことを言うのだろうが、全世界が賛成しないだろう」22。
ノレは皮肉たっぷりに答えた。「私が地球儀の近くから流れ出した物質が、例えば中国でどのように感じられるか。しかし、それは非常に重要なことなのである。モリン氏がよく言っているように、観客である生身の人間はどうなるのだ!」23。
新しい技術を賞賛する代わりに警告を叫んだ他の預言者たちと同様、モランは当時、最も人気のある科学者ではなかった。ある近代史家が、彼を「尊大な批評家」、電気学の先覚者ノレに「対抗」した「グラディエーター」と非難するのを見たことがある24 が、二人の違いはその理論と結論にあり、事実にあったのではない。しかし、二人の違いは、理論や結論にあったのであって、事実ではなかった。電気の副作用は、誰もが知っていることであり、それは20世紀の夜明けまで続いたのである。
ジョージ・ビアードとアルフォンソ・ロックウェルの1881年の権威ある教科書「医学と外科学電気」では、これらの現象に10ページが費やされている。電気に弱い人を「感電性」electro-susceptibility 、電気を異常に感じる人を「感電性」electro-sensibilityと呼んでいる。モランの警告から130年後、この医師たちはこう言った。「電気が常に傷害を与える人がいるが、その影響の唯一の違いは、前者が後者より傷害が少ないということだ。電気治療の技術や経験がすべて無駄になる患者もいる。彼らの気質は電気と調和しない。麻痺、神経痛、神経衰弱、ヒステリー、特殊な臓器の障害など、患者の病名や症状が何であるかは関係ない。頭痛や背中の痛み、イライラや不眠、全身倦怠感、痛みの興奮や増大、脈拍の過剰興奮、風邪をひいたような悪寒、痛み、硬直、鈍痛、大量の発汗、しびれ、筋肉の痙攣、光や音の感受性、金属味、耳鳴りなど、注意すべき症状は前世紀と同じであった。
ビアードとロックウェルは、電気に弱いのは家系によるものだと言い、性別と年齢については、初期の電気技師が行ったのと同じような観察を行った。
また、フンボルトと同じように、電気に鈍感な人たちにも驚かされた。「彼らは、「電気に無頓着な人もいる。彼らは、ほとんどどんな強さの電流でも、頻繁に、長時間かけても、良い影響も悪い影響も受けずに耐えることができる。電気が無限に流れても、電気が飽和しても、少しも良くも悪くもならないのである」。しかし、その人が電気と仲良しなのか、そうでないのかを判断することはできない。「ある女性は、非常に繊細な人であっても、大量の電気に耐えることができるし、非常に丈夫な男性であっても、まったく耐えることができない人もいる」25 と彼らは観察している。
電気が健康に影響を与えることを認識している現代の医師の多くが言うように、電気は普通のストレス要因ではなく、電気に対する脆弱性が健康状態の指標になると考えるのは誤りである。
しかし、1892年に耳鼻科医のオーギュスト・モレルが、健康な被験者の12パーセントは、少なくとも電気の聴覚的影響に対して低い閾値を持っていると報告している。つまり、人口の12パーセントは、何らかの方法で、非常に低いレベルの電流を聞き取ることができたのである(おそらく現在もそうであろう)。
気象感度
電気的な感性とは異なり、人間の天候に対する感性の研究は、メソポタミアで5千年、中国やエジプトでも同じように長い歴史がある。ヒポクラテスは、紀元前400年頃に書かれた『空気、水、場所に関する論文』の中で、人間の状態は、住んでいる場所の気候やその変動に大きく左右されると述べている。これは、いくら無視され、資金が不足しているとはいえ、主流の学問である。しかし、この学問の名前である「生物気象学」には、公然の秘密が隠されている。民族の違いに関係なく、あらゆる人口の約30パーセントが天候に敏感であり、したがって、この分野のいくつかの教科書によれば、電気に敏感である26。
国際生物気象学会は、1956年にオランダの地球物理学者ソルコ・トランプによって設立され、本部は、2世紀以上前に電気時代の幕開けとなった都市、ライデンに置かれた。その後、携帯電話会社が研究者に圧力をかけ、長い間確立されてきた科学分野を否定し始めるまでの40年間27、生物電気と生物磁気は集中的に研究され、学会に常設されている10の研究会のうちの1つに選ばれていた。1972年には、オランダで “自然界の電気、磁気、電磁場の生物学的影響” に関する国際シンポジウムが開催された。1985年には、International Journal of Biometeorologyの秋号が、大気イオンと大気電気の影響に関する論文に完全に割かれた。
フェリックス・ガッド・スルマンは、「電気過敏症の患者を精神科の患者として扱うのは、非常に不当なことだ」と書いている。スルマンはエルサレムのハダサ大学医療センターの医師であり、同医学部の生物気候学ユニットの主任であった。1980年に『空気イオン化、電場、大気圏、その他の電気現象が人間と動物に及ぼす影響』と題する400ページのモノグラフを出版した。スルマンは、他の医学・技術分野の15人の同僚とともに、15年間にわたり935人の気象過敏症の患者を調査した。その中で、最も興味深い発見は、これらの患者の80パーセントが、天気の変化が起こる12時間から48時間前に予知できたというものであった。「予知能力者たちは皆、天候の変化の前に起こる電気的変化に敏感であった」とスルマンは書いている。「彼らは、電気の速さで自然にやってくるイオンや大気に対して、セロトニンの放出によって反応したのである。
気象感応は、何世紀にもわたる不正確な医学的伝聞の壁の中から生まれ、実験室での厳密な分析という光にさらされつつあったのだ。しかし、このことは、生物気象学の分野を、新たな技術的ダイナモとの衝突の軌道に乗せることになった。もし、地球上の人口の3分の1がイオンの穏やかな流れや大気の微妙な電磁波の気まぐれに敏感だとしたら、コンピューター画面からの絶え間ないイオンの川や、携帯電話、ラジオ塔、電線からの放射線の乱流は、私たちに何をもたらしているのだろうか。私たちの社会は、その関連性を理解しようとしない。実際 2008 年 9 月に東京で開催された第 19 回国際生物気象学会議では、スイス連邦工科大学物理学部のハンス・リッチナー教授が立ち上がり、携帯電話は危険ではなく、その電磁場は大気からのもの よりはるかに強いので、何十年にもわたる研究は間違っており、生物気象学者はこれ以上電場と人間の相互作用 を研究するべきではないと同僚たちに語ったのである29。言い換えれば、私たちは皆、携帯電話を使っているので、したがって、携帯電話は安全であると推定しなければならず、したがって、何百もの研究所で報告されてきた単なる大気圏の電場による人、植物、動物への影響はすべて起こりえなかったのだ!ということだ。長年にわたって生物気象学を研究してきたオンタリオ州のローレンシャン大学教授、マイケル・パーシンガーが、「科学的方法は放棄された」と言うのも無理はないだろう30。
しかし、18 世紀には、電気技師がその関連性を明らかにした。摩擦機に対する患者の反応は、古代の謎に新たな光を当てたのである。この問題は、モーデュイットによって整理された。「人間も動物も、嵐の日には一種の脱力感や気だるさを感じるものだ。この落ち込みは嵐の前の瞬間に最大となり、嵐が去って間もなく、特にある程度の量の雨が降ると減少し、嵐とともに消滅して終わる。この事実はよく知られていて重要であり、医師は長い間、十分な説明を見出すことができずにいた」31。
ベルトロンは、その答えが今、目の前にあると言った。「大気中の電気と人工的な電気は、同じ液体に依存しており、動物経済に対してさまざまな効果をもたらす。浴室で絶縁され、電気を流された人は、過剰に電気を流された大地の上に立つ人に相当する。両者とも電気流体で過剰に満たされる。機械が作る電気回路は、天と地が作る大回路の小宇宙である」32。
イタリアの物理学者ジャンバティスタ・ベッカリアは、地球規模の電気回路を驚くほど現代的な言葉で表現している(第9章参照)。「雨を降らせる雲は、地球の電気を帯びている部分から、電気を使い果たした部分へと拡散し、雨を降らせることで両者の間の均衡を回復させる」33 と書いている。
このことを発見したのは、18 世紀の科学者が最初というわけではない。紀元前4世紀に書かれた黄帝内経の中にある中国医学のモデルも同様である。実際、「気」が電気であること、「陰」と「陽」が陰性と陽性であることを理解すれば、言葉はほとんど同じで、「清らかな陽は天をなし、濁った陰は地をなす。地の気は昇り雲となり、天の気は下り雨となる」34。
気象に敏感で、電気にも敏感な人物として、バイロン卿、クリストファー・コロンブス、ダンテ、チャールズ・ダーウィン、ベンジャミン・フランクリン、ゲーテ、ヴィクトル・ユーゴー、レオナルド・ダ・ヴィンチ、マーティン・ルーサー、ミケランジェロ、モーツァルト、ナポレオン、ルソー、ボルテールなどが有名である35。
著者について
科学者でありジャーナリストでもあるアーサー・ファーステンバーグは、このテーマをめぐるタブーを取り払う世界的な運動の先頭に立つ。コーネル大学で数学の学位を取得後、1978年から1982年までカリフォルニア大学アーバイン校の医学部に在籍。レントゲンの過剰摂取による怪我で医師としてのキャリアを絶たれる。その後、38年間、電磁波の健康影響や環境影響に関する研究者、コンサルタント、講演者、ヒーリングアートの施術者として活躍。
