Ignorance, Power and Harm Agnotology and The Criminological Imagination
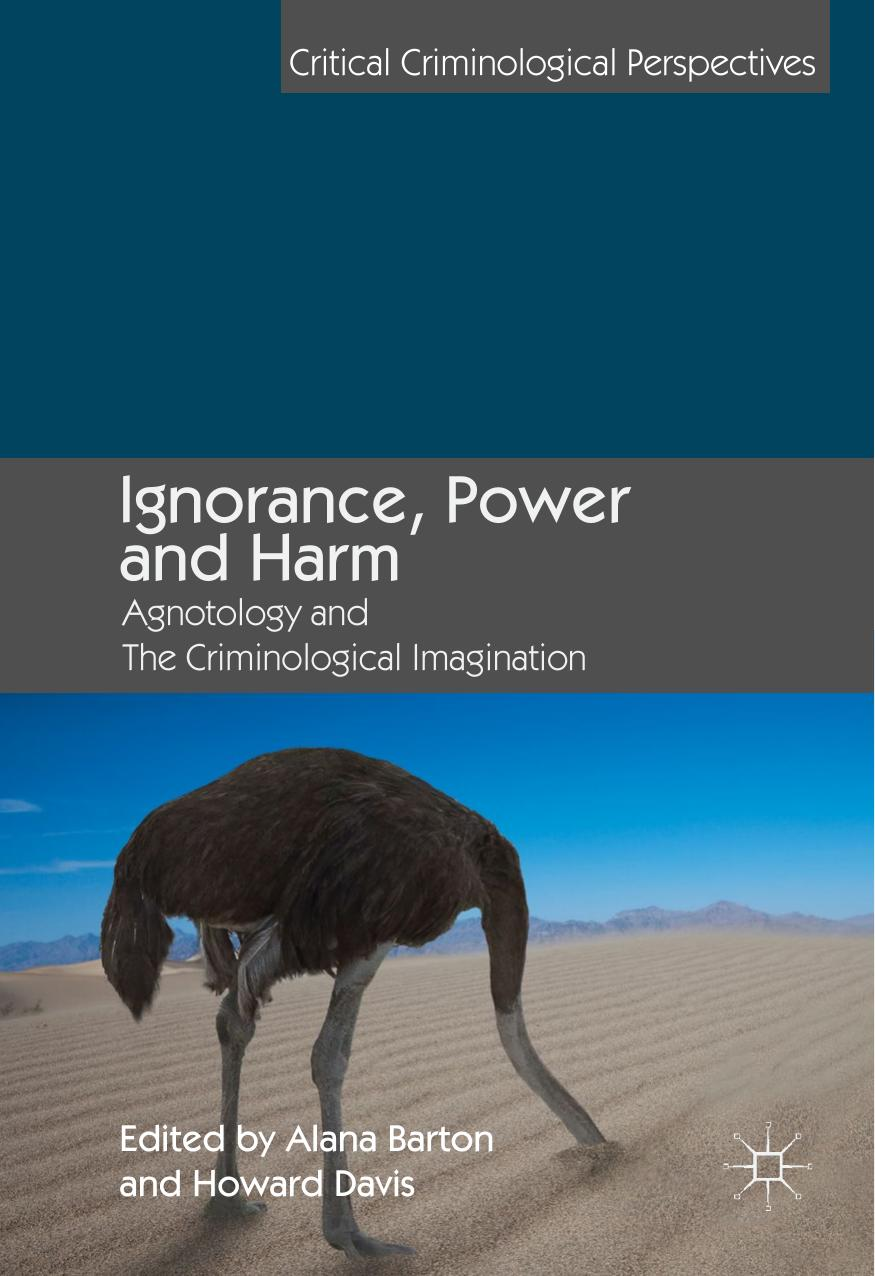
アラナ・バートン – ハワード・デイビス編集部
無知・権力・害悪
アグノトロジーと犯罪学的想像力
目次
-
- 1 はじめに
- 2 アグノトロジーと犯罪学的想像力
- 3 対反乱戦、帝国、そして無知
- 4 無知のイデオロギーとメカニクス アイルランドにおける児童虐待 1922-1973
- 5 危機のフレーミング 民間資本による救済
- 6 マオリ族の収監に対する無知を管理する
- 7 国境の(誤った)管理、無知、そして否定 139
- 8 気候変動の否定:「無知を再び偉大にする」 163
- 9 壮大な法律と秩序 写真、社会的害悪、そして無知の生産 189
- 10 刑罰と歴史的否定。刑務官と刑務所内の暴力に関する「常識的」な理解の問題化
- 索引 239
- 寄稿者
- ノート
アラナ・バートンはエッジヒル大学の犯罪学研究者である。刑務所と「刑務所ツーリズム」、緊縮財政と「貧困層との戦争」、犯罪学的想像力の概念、「診断」研究に関心を持ち、研究論文を発表している。著書にFragile Moralities and Dangerous Sexualities (2005)、共編著にExpanding the Criminological Imagination (2007)がある。彼女の研究は、Howard Journal、British Journal of Community Justice、Crime, Media, Cultureなどの雑誌に掲載されている。刑務所と大学間の教育経路の確立に取り組むLearning Togetherプロジェクトにも携わっている。
ヴィクトリア・キャニング:英国オープン大学の講師、経済社会研究評議会 (ESRC)社会政策・犯罪学部門の「未来の研究リーダー」フェロー。Prisons, Punishment and Detention」ワーキンググループのコーディネーター、Statewatchの評議員、「Gendered Harm and Structural Violence in the British Asylum System」(2017)の著者でもある。Migrant Artists Mutual Aidと密接に連携し、彼らと「Strategies for Survival, Recipes for Resistance」(2017)を共同編集し、Danish Institute Against Tortureと「Gendered Experiences of Social Harm in Asylum: Exploring State Responses to Persecuted Women in Britain, Denmark and Sweden」というプロジェクトでパートナーになっている。
ハワード・デイビス:エッジヒル大学犯罪学上級講師。以前はソーシャルワーカーとして、児童保護、トラウマ、死別などの分野に携わっていた。研究・教育上の関心は、国家・企業による被害、急性・慢性災害の犯罪学的・被害者学的側面、メディアと国家による「緊縮財政」の正当化、高等教育における新自由主義の影響などである。彼の研究は、British Journal of Social Work、Disasters、British Journal of Criminologyを含む様々なジャーナルに掲載されている。
Alex Dymock 英国ロンドン大学ロイヤルホロウェイ校の犯罪学・法学講師。イメージの表象と消費の政治学への関心は、ポルノグラフィーの法的規制に関するキャンペーン活動に由来する。また、英国映画協会 (BFI)、カーゾン・シネマ・ソーホー、サザーク・レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー (LGBT)ネットワークでポルノについて講演し、内務特別委員会に証拠書類を提出したこともある。
Anthony Keatingは、エッジヒル大学のBSc(優等学位)犯罪行動心理社会的分析プログラムのリーダーである。独立後のアイルランドにおいて、弱い立場の子どもたちを保護することができなかった背景には、アイデンティティ、文化、コミュニケーションがどのような役割を担っているのかを探り 2002年にダブリンシティ大学にて博士号を取得した。その後、アイルランド政府のポスドク研究員として、20世紀アイルランドにおける性犯罪を研究し、特に、その原因、性質、程度を否定し、難解にしようとする公式・非公式の検閲に焦点をあてた。
マーク・マクガバンは、英国のエッジヒル大学の社会学教授である。特に北アイルランドにおける政治的暴力、紛争、紛争後の移行に関する研究に力を入れており、紛争後の人権、真実、正義の問題に取り組むコミュニティグループや国内外のNGO、弁護士との調査に長年携わってきた。北アイルランド紛争時の英国政府とロイヤリストの共謀の性質と程度を調査しており、このテーマに関する書籍が近日出版予定。Ardoyne: The Untold Truth (Beyond the Pale: 2002)の共著者であり、Sociology, Law and Society, Critical Studies on Terrorism, Race and Class, Terrorism and Political Violence and State Crimeなど幅広い国際ジャーナルで発表している。
リキ・ミハエレ (Ngāti Kahungunu)は、ビクトリア大学ウェリントン校 (VUW)で博士論文のために「刑務所システムにおけるマオリ文化的アイデンティティの利用に関するカウパパ・マオリ分析」に従事した。2016年から2017年まで、VUWの犯罪学研究所のラザフォード・ディスカバリー・フェローシップ・プロジェクトのポストドクトラル・フェローを務める。
デイヴィッド・スコット (David Scott)は、英国The Open Universityに勤務。2009年から2012年までEuropean Group for the Study of Deviance and Social Controlのコーディネーターを務め、Howard Journal of Crime and Justiceの元編集長、Justice, Power and Resistance誌の共同創刊編集者でもある。イングランドとウェールズに新たに6つのメガプリズンを建設することに反対するキャンペーンの主要な主催者の一人であり、2018年6月にロンドンで開催される刑廃止に関する国際会議 (ICOPA)の共同主催者である。最近の著書には、Controversial Issues in Prisons(2010)、Prisons and Punishment(2014)、Emancipatory Politics and Praxis(2016)、Against Imprisonment(2018)などがある。
Elizabeth Stanley ヴィクトリア大学ウェリントン犯罪学研究所のリーダー兼ラザフォード・ディスカバリー・フェロー。国家犯罪、人権、拘禁、社会正義を中心に研究している。著書に「拷問、真実、正義」、「国家犯罪と抵抗」(ジュード・マッカロクとの共著)、「地獄への道」などがある。The Road to Hell: State Violence against Children in Post War NZ(地獄への道:戦後ニュージーランドの子どもに対する国家暴力)」など。
スティーブ・トムズ:英国オープン大学犯罪学教授。企業や国家による犯罪や被害の発生、性質、規制について長年関心を持ち、これらの問題に関して幅広く出版している。近著に「Social Protection After the Crisis(危機後の社会保護)」がある。Regulation Without Enforcement (2016)」がある。英国のハザード運動や雇用権利研究所と長く連携しており、Inquestの評議員・理事を務めている。
Reece Walters クイーンズランド工科大学司法学部教授、犯罪・司法研究センター所長。ニュージーランドや英国政府の顧問に任命され、銃規制、放送規制、犯罪防止を含む様々な問題を検討する諮問委員会のメンバーでもある。現在は、国家や企業が権力や利益のために食料、水、空気を操作・利用する方法など、「生活に不可欠なもの」に対する犯罪や被害に焦点を当てた研究を行っている。この分野で、Eco Crime and Genetically Modified Food (2011), Emerging issues in Green Criminology (2013) with Tanya Wyatt and Diane Solomon, and Water, Crime and Security in the Twenty-First Centuryなどの書籍を出版している。Too Dirty, Too Little, Too Much(2017)Avi Brisman, Nigel South, Bill McClanahanと共著。
ホリー・ホワイトは、チェスター大学の社会学・犯罪学講師。彼女の研究関心と出版物は、貧困の物語を中心に、特に不正確で有害な言説に挑戦するものである。シティズンズ・アドバイスのアドバイザー兼社会政策コーディネーターを務め、「寝室税」などのキャンペーンを支援。また、ウェスト・チェシャーのフードバンクでボランティア活動を行い、同チャリティーのリサーチ&アドバイザリー委員会の共同設立者でありコーディネーターでもある。また、European Group for Deviance and Social Controlの編集集団の一員でもあり、2017年には、Emerging Voicesと題した大学院生と初期キャリア研究者のエッセイのグループ初のコレクションを共同編集している。
1 はじめに
アラナ・バートン、ハワード・デイビス Ryan Beckwith(2018)によると、アメリカ合衆国大統領ドナルド・トランプは最近、ニューヨーク・タイムズのインタビューに応じ、75秒ごとに事実と異なることを発言していたとのことである。ワシントン・ポストの調べでは、就任から347日間で1950件の虚偽または誤解を招くような主張をしていた。また、これらは小さな「虚偽」でもなかった。トランプ氏は例えば、前任のバラク・オバマ氏は米国生まれではないと主張し、トランプタワーを盗聴したと主張した。野党民主党がロシアと共謀していると非難し、何百万人もの人々が違法に投票したと宣言した。トランプ氏によると、9月11日のテロを数千人が屋上で祝い、選挙戦にスパイが仕込まれ、共和党のライバル候補テッド・クルーズの父親がケネディ大統領暗殺に関与していたという。
トランプ当選の1年前、ブレグジットの国民投票の結果が約半世紀にわたる英国の政策の最も重要な転換を告げた翌朝、英国独立党 (UKIP)のナイジェル・ファラージ党首が全国放送に出演し、ブレグジット後は国民保健サービス (NHS(英国保健医療局))に週3億5000万ポンドが使われるという重要な選挙公約は「間違い」だったと発表した(ストーン2016a)。彼はまた、個人的にその主張を支持したことを否定したが、翌日、彼がまさにそれを行ったことを示すビデオ映像が出てきた-そのための資金は週350ポンドを超えると実際に述べている (Stone 2016b)。
ブレグジット投票とトランプ当選の衝撃は(少なくとも政治専門家やオピニオンシェイパーにとっては)、誤情報と嘘が民主的な政治プロセスを損なっているのではないかという懸念を高めている。選挙期間中に、おそらくは外国勢力が関与した偽のストーリーが目立つようになり、さらに、ソーシャルネットワークのユーザー個人を対象にしたストーリーを形成するために個人データが使用されたという証拠が現れたことで、「ポスト真実」政治の新しい時代に入ったという見方が強まっている。そして、虚偽の「事実」や誤った推論を生み出す、新たな、そして非常に憂慮すべき事態が発生していることは確かである。そのうちのいくつかは技術的なもので、企業、国家、個人がデータを収集し、誤用するための前例のない、加速する産業的能力に関連するものである。捏造、偽造、普及はかつてないほど容易になっている。「全体主義」の支配の可能性はかつてないほど大きくなっている。オーウェルや、それこそスターリンが夢見たものをはるかに超えているのだ。
その他の非技術的な発展もまた、深く憂慮すべきものである。それらは前例がないわけではないかもしれないが、だからといって心配が少ないわけではない。例えば、民主主義国家における政治指導者は、嘘をついたことが判明した場合、代償を支払わなければならないというような政治規範や期待に変化が生じているようである。自分たちの」リーダーが不正や腐敗を露呈しても、皮肉にも「フェイクニュース」として一笑に付すことができるというのが、それぞれの「中の人」グループの側の期待になりつつあるようである。多くの人にとって、証拠も理性も意見や偏見には勝てないということが明らかになった。政治家の中には、聴衆に迎合するために道化のようなおどけ方をする者も確かにいる。ここでは、「上からの」無知を生み出すことと、「下からの」明確な証拠を積極的に無視することが一致している。当然のことながら、現在の金融、経済、社会、環境危機に関する無知の製造は、富裕層や超富裕層の心や銀行口座に密着した、より狭い範囲に焦点を絞った部門別キャンペーンで展開される戦略の上に築かれている。それは、タバコ、気候変動、金融、労働者の健康と安全、不平等など、利益追求の規制を脅かす運動を信用しないようにする長年のキャンペーンを利用し、それを基礎にしている。これらを総合すると、知識と理解を損ない、その後に続く害をもたらす、これらの現在の攻撃の緊急性は、本書の寄稿者たちにとって重要な動機付けとなった。
しかし、「フェイクニュース」(この言葉を皮肉にも流行らせた張本人がいる)、あるいはより広く無知の生成と利用を新しいものと見なさないことが重要である。2008年の危機のはるか以前から、新自由主義がその約束を果たすことができない慢性的な失敗は、「スピン」、マスメディアのコンプライアンス、新自由主義そのものへの「進歩的」政治の屈服といった組み合わせによって、ますます管理されるようになっていた (Streeck 2016)。しかし、もちろん、意図的な無知の製造には、過去数十年よりもはるかに長い、そしてはるかに暗い歴史がある。一例を挙げると、19世紀末、ベルギー王レオポルド2世は帝国を築こうと決意した。ヨーロッパ諸国がアフリカの広大な土地を手に入れた「アフリカ・スクランブル」の中で、レオポルドはコンゴ盆地の「未開拓地」に入植した。アメリカやヨーロッパの同時代の人々の間では、レオポルドの試みに対する反応は、当初は圧倒的に肯定的であった。アダム・ホックスチャイルドが指摘するように(2006: 92)。
レオポルドは新しい植民地でのキリスト教宣教師の支援で多くの賞賛を得た。彼は奴隷貿易を激しく非難することで人々に感銘を与え、由緒あるイギリスの人権団体であるアボリジニー保護協会の名誉会長に選出された。国王は大満足で、ブリュッセルを主要国による反奴隷会議の開催地として選んだ。
そこで行われたのは、ヨーロッパ植民地史上最悪の残虐行為であった。ベルギー政府の委員会は、ゴムと象牙の略奪のために奴隷にされたレオポルドの領地の人口が半減したと結論づけた。Hochschildが結論付けているように、「このことは、推定によれば、レオポルド時代とその直 後に、領土の人口がおよそ一千万人減少したことを意味する」(ibid.: 233 強調)。
植民地虐殺の発生、否定、最小化、正当化の例は他にも多くあるが (例えば、Davis 2017; Woolford and Benvenuto 2015; Lawson 2014; Guettel 2013;
Kreike 2012; Bellamy 2012; Groen 2012; Morgan 2012; Raben 2012;
Shaw 2011; O’Regan 2010; Madley 2004, 2005)、コンゴのケースはいくつかの理由で興味深いものである。第一の理由は、一世紀以上前であっても、レオポルドの活動には驚くほど「近代的」な要素があったことである。この特殊な植民地的蛮行の暗い核心にある経済的緊張は、他の場所での国家と企業による害悪とよく似ている (Ward 2005を参照)。しかし、現代の目から見れば、レオポルドのコンゴの獲得と搾取は、抜け目のない二枚舌の広報活動によって実現され、隠蔽されたという点で、同様に興味深いものである。ヨーロッパの強国はアフリカに独自の野心を抱いており、レオポルドは当初、ベルギー国内で彼の事業に対する民衆の支持を得られなかった (Hochschild 2006)。そこでレオポルドは、自らの野望を純粋に人道的なものであるとする、非常によく知られた広報戦略を考案した。これは、メディア管理、国営企業の巧妙な手口、賢明な資金提供や賄賂、政治的ロビー活動、有名人の推薦などを組み合わせて、アフリカ人、アメリカ人、ヨーロッパ人を欺くことに成功した(同書)。レオポルドは、彼の計画を頓挫させる恐れのあるセックス・スキャンダルを黙殺する必要さえあった。彼はキリスト教の博愛と「アラブの奴隷商人」に対するアフリカの脆弱性という言説を利用することができた。その後の大量虐殺、人道に対する罪、その他の集団的被害と同様、レオポルドの戦略の成功は、関係者が見たもの、疑ったものを故意に無視する能力によるところが大きい。レオポルドの奴隷化と何百万人ものアフリカ人の死は、やがてリバプールの船員、E・D・モレル(レオポルドに対する世界的なキャンペーンを開始)の注意を引くことになるが、他の多くの人々は、彼と同様に、コンゴからの船がゴムや象牙を積んでアントワープに到着しても、戻ってきた船にはそれらの代金を支払う手段がないことに気づいていたに違いない。むしろ、その積荷は支配のための人的・技術的手段であった。しかし、もし彼らが気づいていたとしても、他の人々は行動しなかった。無視したのだ。そして、彼らは歴史によって不当に無視された。歴史は、戦いの騒音や偉大な演説の言葉によって作られるのと同様に、沈黙の周りにも作られる。
19世紀後半にレオポルドがベルギー領コンゴを個人的に獲得した例を取り上げる第二の理由は、国家と企業の欺瞞がもたらす最も極端な結果を示す、本当に恐ろしい一例だからだ。この種の恐ろしい犯罪の例に漏れず、死者の数は正確には分からない。しかし、死んだ人間の数が1000万人以上であろうと、1000万人以下であろうと、この犯罪の不可解さは、無知の製造が「単なる」学術的問題や「リベラル」あるいは「学術的」意見の問題ではないことをはっきりと例証している。現代の主要な役者が道化のようにふざけてはいても、笑い話でもなければ、自称エリートの間で行われる政治的なゲームでもないのだ。歴史は、それが生と死の問題であることをはっきりと示している。私たちのゼミの観点からは、明らかに犯罪学的な問題であることは、言うまでもないだろう。
レオポルドの犯罪について指摘すべき第三の点は、他の大量殺戮の加害者と同様、深く埋め込まれた非人間的なイデオロギーを利用することができたという点である。Stan Cohen(2001)が解釈的、特に暗示的と呼ぶレオポルドの残虐行為の否定は、人種的な虚偽が広く受け入れられることによってのみ可能であった。この場合、当時もその後も、他の人々と同様に、「与えられた特性によって、人間に通常課される道徳的・法的保護から排除されるべき特定の集団が存在する」(ベラミー 2012: 161)という信念があったのだ。近年、アウトサイダーや「他者」としての地位を利用した人間の欺瞞や自己欺瞞の能力が、これまでと同様に衰えていないことは、おそらく一部の人々にとって衝撃的な事実であっただろう。
レオポルドが亡くなってから100年の間に、多くの点で人間の理解は飛躍的に進歩し、深化し、拡大したが、無知な世代が利用できる技術、戦略、テクニック、リソースもまた進歩した。特に、無知を生み出すメーカーを含む情報形成者のための研究やトレーニングを提供する、まったく新しい学問分野が生まれた。科学者たちは、特別な利害関係者に買収され、その活動に科学的、疑似科学的な「隠れ蓑」を提供する意志があることを繰り返し示してきた。国家や企業の害が最終的に明らかになった場合、広報の「危機管理」専門家が戦略と戦術を監督し、「風評被害」の回避や最小化が目標となる。この世界では、危害は二の次で、いかにしてそれを知覚させるかが重要となっている。
表象、認識、欺瞞の分野は、もちろん犯罪学にとって新しい分野ではない。国家の犯罪を隠蔽し、責任を回避するための沈黙と否定は、近年、とりわけCohen(2001)、Hallsworth and Young(2008)によって冷静に検討されてきた。Tombs and Whyte (2003)は、国家や企業の有害な行為に関する説明の無効化について研究している。また、公的機関の有害かつ犯罪的な行為の隠蔽 (Scraton 1999; Shaw and Coles 2007)や、無実の人に対する欺瞞的な処罰 (Naughton 2007, 2014)を暴露した研究もある。ポール・ギルロイは「アグノトロジー」と「アグノポリティクス」という言葉を用いて、「新しい人種差別」の生産における無知と権力の関係(2006a)と「情報が紛争の要素として軍事作戦の内部に留まる、一見無限に続く戦争の遂行」(2006b)を表現している。より広く、真実でないことを伝えるメディアの広範な分析があり、同様のトピックをめぐって執筆した著者たち (Theodor Adorno, Hannah Arendt, Zygmunt Bauman, Danny Dorling, Frank Furedi, Henri Giroux, Joseph Stiglitzなど)が、「犯罪」と社会害の病因に関する無知を暴露して、その加害者に挑戦しようとする犯罪学者に受け入れられている。
この巻の各章は、犯罪や被害に対する責任を最小化したり否認したりするために権力者が用いる難読化、中立化、否認の方法を明らかにするという伝統を引き継いでいる。その目的は2つある。第1に、この分野における既存の実証的・概念的研究を、アグノトロジーの理論的枠組みの中で統合・発展させること。第2に、この枠組みを犯罪学という学問分野にとって重要な分析ツールとして確立することである。
次章では、ホリー・ホワイトとともに、「アグノトロジー」の概念的枠組みを設定し、ゼミ的犯罪学の展開におけるその有用性について考察している。著者らは、2つのケーススタディをもとに、大衆の害がどのように隠蔽され、否定され、あるいは中和されるかを説明している。最初の事例は、アスベストの使用をめぐって企業が構築したアグノシスであり、企業がいかにして何十万人もの人々を殺しながら、刑事罰を免れることができるかを実証している。2つ目の事例では、ホロコーストと、国家が生み出したこの最も極端な形の被害におけるアグノシスの役割について考察している。その規模にもかかわらず、また他の学問分野からの注目度とは対照的に、犯罪学はこの犯罪について驚くほど沈黙したままであった。著者らは、想像力豊かな犯罪学のゼミの中心的な目的、すなわち、重大な、しばしば致命的な被害を理解し、それと闘うことは、無知の構築、普及、受容に体系的かつ厳格な注意を払わずに行うことはできない、と主張する。
第3章では、マーク・マクガヴァンが、帝国の組織的暴力の実践としての対反乱軍が、無知、疑い、偽情報を生み出すことによって、いかに効果的に機能しているかを探っている。彼はまず、このような国家的危害の理論と実践を理解する手段として、人種、帝国主義、無知の間の重要なつながりを提示す。さらに、帝国戦争や過去の犯罪が「組織的忘却」の対象となり、そのような国家行動の再発に対する支持を生み出し維持する方法を検討する。米軍の人間地形システム (HTS)を例に、「テロとの戦い」の一環である対反乱戦における無知の文化的生産における社会科学そのものの役割を解き明かしている。
第4章では、アンソニー・キーティングが、1922年から1973年までのアイルランドの「ルックド・アフター」された子どもたちの制度的虐待に着目している。彼は、教会や国家といったポストコロニアルのエリートたちが、建国神話(宗教性、純粋性、美徳にまつわるもの)とアイルランド自由国の正当性を維持しようと決意し、否定と無知の政治・社会文化を確立したことを探求している。その目的は、性的搾取、「道徳」、社会状況にまつわる不快な真実に対する一般の認識を封じ込め、無効にすることだった。このような肯定の戦略は非常に強力であったため、それに異議を唱える者は、誹謗中傷され、恐れられ、事実上「非国民化」されてしまった。キーティングは、アイルランドの工業学校と少年院の子どもたちは、その存在そのものが、注意深く構築されたこの無知の枠組みに対する損傷であり、その後の「他者化」によって、その後何十年も抑制されないまま虐待の対象となった、と論じている。
スティーブ・トムズは、第5章で 2007年に起こった金融・経済危機の余波について述べている。彼は、責任者から非難をそらし、新自由主義的秩序を「救わなければならない」ものとして再構成するために、この新自由主義的大災害の原因と性質が、経済的、法的、政治的、社会的無知の構築を通じて、どのように再定義されたかを分析している。金融「救済」の結果は、すでに社会的弱者であった人々によって最も鋭く感 じられることになった。しかし、Tombsが論じているように、(特にイギリスにおいて)この戦略に対する政治的・民衆的同意は、誘導された不寛容と意図的なごまかしに依拠した非難とフレーミング技術を通じて集められ、世界を組織し理解する方法として新自由主義が支配し続ける根拠となった。
第6章は、エリザベス・スタンリーとリキ・ミハエレによる、ニュージーランドのマオリ人囚人の「刑の捕らえ方」の分析である。著者らは、マオリの投獄が、複数の権力の場において、組織的に管理された様々なレベルの無知を通じて、いかに常態化し、永続化したかを考察している。彼らは、マオリ族の投獄を促し、制度的な不利と疎外を根付かせる新植民地的文脈を不明瞭にするために構築された、診断達成の3つの方法(マオリ族の病理化、矯正の利益とプロセスに合わせたマオリ文化の再組み立て、「犯罪」の説明としての構造的不利、制度化した人種主義、国家の暴力の否定)に焦点を当てる。ミハエレとスタンレーは、代替的な知識と行動の生産を通じて、いかに無知に抵抗しうるかについて考察し、締めくくっている。
第7章では、ヴィクトリア・カニングが、2015年から難民キャンプの規模が拡大し、ヨーロッパの国境で難民の死亡者数が増加したいわゆる「難民危機」に対するイギリスの対応を検証している。彼女は、紛争への関与、武器取引、経済的不安定性の創出を通じて、この人道的大災害の形成に英国(特にイギリス)が果たした役割を批判的に分析する。さらにキャニングは、厳しい国境管理の拡大が、難民の移動と国境での死の現実をあいまいにし、その結果、こうした人間の苦しみの事例に対する無知と集団的否定の感覚を助長してきたと論じている。言い換えれば、アグノシスは、知らないことが不可能になったときでさえ、英国が「知らない」という感覚に浸ることを可能にしてきた。
第8章では、地球規模の気候変動にまつわる無知の範囲と力を探る。この章では、リース・ウォルターズが、気候変動否定の言説、特定の政界や企業業界に蔓延するその言説、そして地球にとって壊滅的となりうるその結果について精査している。強力なエリートが作り出した「アグノジア」に焦点を当て、気候変動に対する嫌悪感や否定は、環境が政治的・利益的目的のために利用されるための手法であると論じている。ウォルターズは、気候変動の否定は、ある人々にとっては、「意図的な殺人」あるいは「エコサイド」の行為と見なされうることを指摘し、犯罪学という学問、特にグリーン犯罪学という下位学問が、この破壊的ともいえる無知の構築にいかに挑戦できるかを考えている。
第9章では、アレックス・ダイモックが、無知に関する研究が、犯罪学における近年の「視覚的転回」を批判的に評価する上でいかに有用であるかに焦点を当てて、理論的な領域での議論を続けている。視覚的犯罪学者は、被害、特に国家によって永続化された被害についての視覚的証拠が、公式の物語に対抗する言説を生み出す可能性があると主張してきた。ダイモックは、古典的な写真と観衆の理論の再検討と分析を通じて、この主張に対して二つの面から反論している。第1に、被害や苦悩の写真はしばしば、単に公式や国家の視点を再現しているか、さもなければ、見る者にとってあまりにも耐えがたく、実際に「見たくない」欲求を引き起こすものである、と彼女は仮定している。したがって、このような場合、イメージは知識を提供するのではなく、むしろ無知を生み出すかもしれない。第2に、視覚的イメージは支配的な理解に挑戦し、解放する可能性を持っているかもしれないが、ダイモックは、その力を担うのは写真そのものではなく、むしろ意味の能動的生産者である視聴者であることを思い起こさせる。もし、鑑賞者の参照枠が公式の物語に影響されるなら、彼らのイメージの解釈は、知識と同じくらい、あるいはそれ以上に「無知」によって形作られる可能性があるのだ。
本書は、刑事司法という「日常的」な領域に焦点を移して締めくくられる。アグノトロジー的ゼミオロジーは、権力者による大規模な犯罪、グローバルな構造や慣行がもたらす広範な被害、ひいては犯罪学者にとって犯罪学そのものの本質的な概念基盤を精査するよう迫る一方で、アグノシスが日常的な刑事司法の機能や被害を支えているという事実を見失いがちである。第10章では、David Scottが刑務官の数と囚人の暴力の間にある「因果関係」を「刑事的アグノシス」の一形態として考察しているのが好適である。彼は、Cohen(2001)とMathiesen(2005)の仕事を引き合いに出しながら、深く埋め込まれた刑事隔離の害と暴力に関する歴史的・現代的証拠を検証し、批判を無力化するために、さらには(刑務所や刑務官の暴力などの)有害な実践が「現在において孤立」するように、「沈黙」技術がいかに展開されるかを探っている。
まとめると、「無知の生成」が犯罪学にとって中心的な重要性を持つ理由と方法について、「無知の生成」の現在的・歴史的意義の両方に留意しつつ、ここで提供するのは様々な視点である。この巻の著者はゼミオロジー的な方向性を共有しており、犯罪や犯罪性の国家的定義を単に受け入れるのではなく、批判し、ミクロ、メゾ、マクロの各レベルで発生し、影響を与え、説明される害に注意を向けている。このような観点から、無知とその生成に対する持続的な批判が犯罪学的に重要であり、緊急性を持っていることを強調するのが本書の狙いである。
