FROM ELECTRONS TO ELEPHANTS AND ELECTIONS
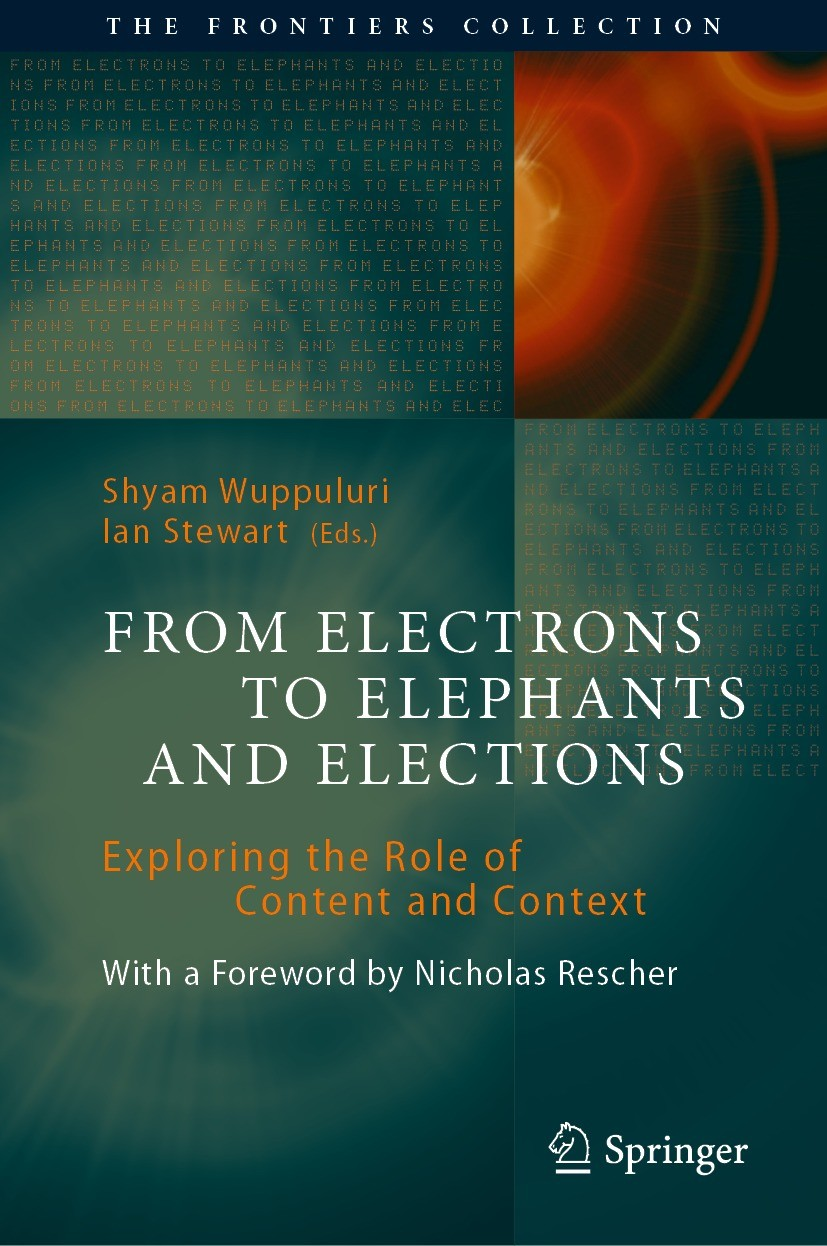
フロンティアーズ・コレクション・シリーズ編集部
Avshalom C. Elitzur, Iyar, Israel Institute of Advanced Research, Rehovot, Israel Zeeya Merali, Foundational Questions Institute, Decatur, GA, USA
マキシミリアン・シュロスハウアー(米国オレゴン州ポートランド市、ポートランド大学、物理学科
マーク・P・シルバーマン(米国コネチカット州ハートフォード、トリニティ・カレッジ、物理学教室
ジャック・タジンスキー アルバータ大学物理学科(カナダ、アルバータ州、エドモントン
リュディガー・ヴァース(ドイツ、ライインフェルデン・エヒターディンゲン、レダックション・アストロノミー・物理・ビルド・デア・ウィッセンスシャフト
このコレクションは、現代の科学と学問の最前線における挑戦的で未解決の問題、およびそれに関連する哲学的な議論に焦点を当てた書籍である。しかし、一般的な研究論文とは異なり、科学的な知識を持つ非専門家が、より深い意味や魅力的な問題を理解できるような形で、テーマを提示するよう心がけている。このシリーズは、現代の科学と研究に対する基礎的かつ学際的なアプローチの必要性を反映している。さらに、このシリーズは、あらゆる分野で活躍する研究者が、自分の専門分野を超えて、重要な問題やおそらく論争の的になるであろう問題について熟考することを奨励することを意図している。量子物理学、相対性理論からエントロピー、意識、言語、複雑系まで、Frontiers Collectionは読者自身の知識のフロンティアを押し広げる刺激となることだろう。
Shyam Wuppuluri Ian Stewart
イアン・スチュワート 数学研究所 英国 ウォーウィック大学 コヴェントリー校
自然界は、粒子、原子、分子、凝集体、細胞、システム、生物、コミュニティ、言葉、文章、段落、書籍など、階層的に組織化されており、その集合体としての複雑さが増している。このようなシステム階層の各レベルには、そのレベルに包含される現象を説明する特徴的な規則性と法則がある。多くの場合、あるレベルで起こっている現象は、その下位レベルの構成要素のものから導き出され、それによって説明することができる。しかし、いつもそうとは限らない。どこでも、下位レベルの現象の手口では説明できない特徴的な革新であることで出現する条件や操作様式に遭遇するからだ。したがって、すべての集団行動が個人の心理学で説明できるわけではないし、社会的選択のすべてが個人の選好に還元されるわけでもない。システム的な複雑さは、構成要素に歯止めをかけた「還元的説明」の邪魔をする。(数学的論理学でも、個々の構成要素が重要な因子を持っていたのに、この因子がすべてに行き渡っているというシステム的一般論が誤りであり、それぞれからすべてへの移行が不適切であるという、オメゲインコンシステントなシステムに遭遇する)。
このような還元抵抗性のある創発的な高次の現象は、われわれの科学理解にとって深い意味を持つ。なぜなら、ここでの科学的理解という課題は、はるかに困難なものになるからだ。最下層の階層に対する認知的把握が十分であれば、それらの上位の階層について心配する必要はない。それ自体はどんなに面白くても、システム的な統合や全体論的な合成はもはや不要なのである。しかし、一般的にはそうではないので、階層的な同意によって理解の要求は指数関数的に増大し、それに応じて科学的理解の課題も増大する。
創発の現象学は、それに応じて、科学に対する理解そのものを変容させる。基本を理解することで必要なことがすべて達成されるパラダイム科学としての幾何学という古典的なギリシャのモデルは、まったく異なる科学的理解のモデルが求められるようになり、成り立たなくなるのである。
前書き
本書は、このような状況が科学的努力の範囲においていかに繰り返し生じているかを示し、自然界と社会界のあり方に関する探究の全範囲にわたって照明的なライトモティーフを構成しているのである。
米国、ピッツバーグ 2022年2月
ニコラス・レッシャー
私たちは巨人の肩に乗った小人にすぎず、巨人よりも遠くを見ることができる。しかし、私たちの視力の鋭さや身長の高さによってではなく、私たちがその巨大な塊の上に持ち上げられ運ばれているからだ。
-シャルトルのベルナール
これだけのボリュームを揃えるのは容易なことではない。まず、協力いただいたみんなにお礼を申し上げたい。時系列で説明しよう。私がアルバート・アインシュタイン奨学金のためにこのプロジェクトに取り組み始めたとき、予備的な構成と関心のある著者のリストを手に、イアン・スチュワート教授に、共同編集者としてこの試みに参加する気があるかどうか尋ねた。教授は、私が選んだ「電子、象、選挙から」というタイトルに「Je ne sais quoi」なものを感じると言って、このプロジェクトに参加することを快く承諾してくださっただけでなく、さまざまな分野の知識に通じていることから、このプロジェクトの内容と文脈をすぐに理解して、彼が長い間考えてきた内容と文脈の関係について思い出し、実際に触れてくださったのである。彼の励まし、支援、親切に感謝する。そして、この巻のために快く序文を提供してくださったニコラス・レッシャー教授に謝意を表したい。アンジェラ・ラヒー博士は、私がシュプリンガー社から出版を始めたときから、常に励ましてくれる存在だった。彼女の貴重なインプット、絶え間ないサポート、そして親切心をここに謝意を表す。また、Springerの編集スタッフの方々には、組版の際にサポートしていただいたことに感謝する。
本書が前例のない時期に出版されたことを考えると、著者の皆さんの努力と時間に心から感謝する。John Heil 教授、Gianfranco Minati 教授、Luciano Boi 教授、Ehtibar Dzhafarov 教授には、非常に協力的で励まされたことに、心から感謝する。Jose Acacio de Barros 教授、Decio Krause 教授、Nana Last 教授には、私の別の巻の執筆を快く引き受けてくれて、共同作業を行うことができたことに感謝したい。また、グラハム・プリースト教授には、本書への寄稿を快諾してくれて、大変感謝している。彼の著書は、私にとって、また他の多くの人々にとっても、実践的な知恵の宝庫となっている。また、Tim Maudlin教授の厚意と寄稿に感謝する。Denis Noble教授のサポート、知恵の言葉、そして温かさに深く感謝する。また、Leonardo Chiatti教授の厚意に感謝するとともに、彼のご縁と友情にとても感謝している。この研究の多くは、アルバート・アインシュタイン・フェローシップの間に行われたもので、その意味でも、私を信頼してくれたスーザン・ニーマン教授と他の理事会のメンバーに感謝したいと思う。特にスーザンには、辛抱強く返信し、人生の様々な事柄についてインスピレーションを与えてくれる視点を共有してくれたことに感謝している。また、アインシュタイン・フォーラムのスタッフの方々のホスピタリティと温かさは、私にとって忘れることのできないものだった。また、私を励ましてくれたデイヴィッド・シュルマン教授、そして私たちが尊敬する平和活動家であることに感謝している。ロレイン・ダストン教授とウェンディ・ドニガー教授は、私にとても寛大で、感謝してもしきれないほどである。また、カプスでの滞在を忘れられないものにしてくれたクリスティナ・カウフマン博士にも大変感謝しているし、カプスや周辺の人々が私に愛と思いやりをもって接してくれたことにも感謝している。最後に、現実の複雑なつながりに気づかせてくれたThích Nhâ´t Ha. nhとTâm Liên Ðàiには、言葉では言い表せないほどの感謝の気持ちを伝えたいと思う。絶望の淵に立たされたとき、私は何度もNhâ´t Ha. nhの本に戻り、希望、慰め、意味を探したが、それらはずっと私の避難所として機能していたのである。波は波の人生を生きていると同時に、水の人生も生きている。あなたが呼吸するとき、あなたは私たち全員のために呼吸している」Nhâ´t Ha.nhは書いている。私たちがそう呼吸し続け、私たちの人生すべてが重要であることを互いに安心させ、行く先々で喜びと幸福を広げられますように。
アインシュタインハウス、カプース・シャム・ウップルリ
この巻の文脈
電子、象、選挙…何がそれらをつなぐのだろうか?オックスフォード英語辞典の10ページ以内に出てくる3つの単語は別として?その語源を調べてみると、ほとんどわからない。エレクトロン」は古代ギリシャ語の「ἤλεκτρον」が語源で、琥珀を意味する。エレファント」はラテン語のelephantusに由来するが、その起源は謎に包まれており、おそらくアフリカのものであろう。Election」はラテン語のeligere(選び出す)から来ている。それなら、もっと分かりやすい。
このエッセイ集で彼らを結びつけているのは、基礎物理学と私たちの住む世界との関係という、深い哲学的な問題である。私たちの多くは象を見たことがあり、また象に乗ったこともあるだろう。また、有権者や候補者として選挙に参加したこともあるだろう。琥珀を見たことがある人、持っている人は多いが、電子を見たことがある人はいない。物理学者でさえもだ。私たちは電子の存在を間接的に推測し、象の奥底には膨大な数の電子があると推論している。同様に、すべての選挙の奥底には多数の有権者がいるが、やはり物理学は、すべての有権者の奥底に膨大な数の電子が存在することを教えてくれる。象の電子は約10^31個と推定されるが、そのほとんどは原子に束縛されており、有権者の電子はわずか10^29個に過ぎない。
このようなことは、現在では特に問題視されることはない。しかし、電子のような粒子が、あらゆる物質的対象(特に象、選挙人、そしてその行動を通じて選挙)を支えているので、物質世界全体は、その豊かさと多様性において、17種類の「基本」粒子が、少数の基本規則に従って膨大な数の相互作用を行っている結果であるという議論については、議論の余地が残っている。かつてはこのような規則を「自然の法則」と呼んでいたが、この言葉は主張が強すぎるため、現在では使っていない。かつては法則であったものが、今ではしばしばモデルという地位に格下げされる。実際、今日の素粒子物理学で最も基本的な法則は、「標準模型」と呼ばれる低次元なものである。
下等な電子から壮大なパチスロに至る推論の連鎖は、長く、複雑である。電子と同様の粒子が結合して原子ができ、それがアミノ酸やDNAなどの分子を作り、タンパク質などの生体分子を作り、染色体やミトコンドリアや核を作り、細胞を作り、心臓や肺や皮膚や鼻などの臓器を作り、象を作る、というように「ボトムアップ」的にたどることができる。あるいは、同じシーケンスを「トップダウン」で、ゾウから電子に渡すと見ることもできる。大雑把に言うと、科学的発見の多くはトップダウンで行われ、科学的説明の多くはボトムアップで行われる。つまり、今回のタイトルは、科学における推論過程とその人間の知識への貢献についてであるが、人間の知的探求のどの分野でも、人文科学、社会科学、芸術の貢献と同じ哲学的な問題が発生するからだ。
このような因果関係の順序は、還元主義を例証するもので、全体の振る舞いをその構成部分の振る舞いから推測し、これらの部分がどのように相互作用するかを考えるものである。科学的方法は、還元主義的に発展してきた。実際、「基本的な」粒子が基本的であるという意味は、還元主義の方法論を反映している。ここで疑問が生じる。そうでなければならないのか?どのような代替案があるのだろうか?還元主義はどの程度成功しているのだろうか?10^31 個の電子から 1 頭の象まで、因果関係のある連鎖を構築することができるのか?電子について十分な知識があれば、象を予測することができるのだろうか?
このような問いは、他の関連する問いを刺激し、内容、文脈、創発、還元主義、全体論といった、緩く結びついた抽象的な概念に注意を向けさせる。生命、意識、自由意志、言語、量子の奇妙な不確定性、広大で謎めいた宇宙など、人間の存在に関わる大きな問題に注意を向けさせる。私たちは現在、これらの問題をどのように理解しているのだろうか?私たちの知識にはギャップがあるのだろうか?どうすればいいのだろうか?この巻では、これらのことについて、さまざまな分析がなされている。このあと数ページにわたって、いくつかの重要な特徴をまとめていくるが、その前に、本書の文脈を理解するために、個人的なことを少し述べさせてほしい。
約30年前、私は自分の興味をそそる問題の多くが、「内容と文脈の関係」という深いテーマのバリエーションとして捉えることができることに気づいた。当時は、数学者や科学者が、非線形力学系の振る舞いという、全く新しい方法で自然界を理解しようとしていた時期だった。非線形力学系とは、大雑把に言うと、2回入力しても2回出力できないような系のことである。しかし、現実の世界は非線形であることが多い。例えば、1つの錠剤が体に良いとしても、2つの錠剤は体に2倍良いとは限らず、むしろ殺してしまうかもしれない。1袋の肥料で農家の収穫が10%増えたとしても、2袋では20%増えるとは限らず、むしろ減ってしまうかもしれない。道路が1本増えると、交通渋滞は減るどころか、さらにひどくなる。地球全体の平均気温が上昇しても、地球上のすべての場所が常に少しずつ暖かくなるわけではない。大規模な熱波や寒波、大洪水が起こる。しかし、進化の生存は正確な対応よりも迅速な対応に依存することが多いため、人間の既定の思考はしばしば迅速で、汚く、執拗なまでに直線的である。
さらに、20世紀以前は、応用数学と数理物理学のほとんどのモデルが線形数学に基づいていた。その理由は簡単だ。線形問題は数学的に扱いやすい。非線形の問題は、少なくとも、明示的な公式と手作業による計算という伝統的な手法では、そうではない。だから、科学は、振り子の小さな揺れ、浅い水の波、ゆっくり動く物体など、現実を直線的に近似するものばかりだった。質量が無視できるゾウでさえも。もちろん、非線形の分野でも成功はしていた。その代表的なものが、ニュートンの重力の法則と、火星の軌道が楕円であるというヨハネス・ケプラーの発見に対するニュートンの説明だろう。もちろん、ニュートンの重力の法則や、火星の軌道が楕円であることを発見したヨハン・ケプラーの説明などがその代表例だが、線形分野での大きな進歩に比べれば、こうした成功は稀なことだった。
しかし、1960年頃になると、その状況は一変する。ポアンカレによる三体問題におけるカオスの発見など、19世紀末から20世紀初頭にかけての理論的進歩が、電子計算機の急速な高速化・高性能化により、一気に実用化されたのである。従来の方法では解けなかったモデルも、新しい技術や総当りの計算で簡単に解けるようになった。非線形システムの直感に反する性質は、すぐに避けられないものになった。最初はほとんど理解できないように見えた非線形システムも、コンピュータの画面からは直視できるようになったのだ。単純な方程式が、数学的に理想的な無限に複雑な振る舞いをするようになったのである。カオス」や「複雑適応系」といった専門用語が広く使われるようになった。科学者たちは、世界は想像していたよりもずっと複雑で、ずっと面白く、ずっと不可解なものであることに気づくようになったのである。特に、複雑系と創発現象に注目が集まった。創発現象とは、相互に関連したシステムが、その構成要素の振る舞いを超越したかのように振る舞うことである。例えば、象の持つ属性は、電子の量子物理学とは一見無関係に見える。しかし、多くの物理学者は、象の属性は原理的には量子世界のルールの結果であると主張する。より正確に言えば、象は量子の法則に背くことはできないということだ。
今日の科学の多くは還元主義的である。象が一番上で、電子が一番下というように、「記述のレベル」の比喩が横行している。つまり、あるレベルの振る舞いを、より低いレベルの相互作用する構成要素に還元することによって説明するのである。化学は分子に還元され、原子に還元され、電子、陽子、中性子に還元され、さらにクォークに還元される。生態系は生物の集団で説明され、生物は遺伝学で説明され、遺伝学はDNAとタンパク質で説明され、さらにそれが分子、原子、電子などで説明される。電子が象の行動を決定するが、象は電子の物理に影響を与えることができない。というわけで、言われている。
実際には、このような還元は、逆に、下位のシステムが、還元された上位のシステムを本当に説明していることを示すよりも簡単に達成される。例えば、水素を超える原子の性質を、量子方程式を使って厳密に計算する方法は知られていない。ヘリウムでさえもそうだ。分子の挙動は、その原子から完全に信頼性を持って推測することはできない。タンパク質がどのように折り畳まれるかは、アミノ酸配列から厳密に計算することはできない。ゲノムから生物の表現型を推測することは絶望的である。銀河のダイナミクスは、構成する星を点質量に単純化しても、その星に重力が働く力から数値的に計算することはできない。電子から象に至る鎖は、巨大なリンクで構成されているかもしれないが、そのつながりは弱い。
創発の概念は、このような難しさを反映している。極端な例では、電子と象の間の因果関係を否定し、還元主義の根幹を揺るがすことになる。最も一般的な形は、原理的には因果関係があるが、あまりに複雑で、実際には詳細に記述することが不可能であることを認めるものである。原理的には1031個の電子が象を意味するとしても、素粒子物理学の方程式を使って計算することは誰にもできないのだ。どのような定義であれ、低レベルの記述が高次のレベルで観察されるものを含意していることを示唆する説得力のある証拠が、高い信憑性をもって存在することがよくある。しかし、このような推論は常に部分的であり、数学的厳密さを欠き、その妥当性に疑問の余地がある近似値や仮定に基づいている。結局のところ、厳密な論理的推論であるべきものが、信仰の飛躍に取って代わられてしまうのである。数学者の用語でいうところの「手探り」である。
3番目の要素に貢献する例として、選挙がある。原理的には、各投票者の判断は、その人の脳内の電子(とその他のもの)の複雑な流れの結果である。十分な事前知識があれば、十分に大きな系に対してシュレーディンガー方程式を解くだけで、各投票者の判断が予測できる。最終的な結果は、これらすべての電子の流れから、どういうわけか導き出される。しかし、まともな神経の持ち主なら、この方法で次の大統領を予測することはできないだろう。その計算は、最速のスーパーコンピューターでさえも、その能力を無限に超えてしまうからだ。電子から大統領候補に至るまで、広く受け入れられている科学理論の明確な連鎖があるかもしれないが、その連鎖のすべてのリンクは、証明されていない信念の上に成り立っているのである。
これとはまったく逆のアプローチとして、全体論的(またはトップダウン)な考え方がある。生態系や生物を全体として考え、同じスケールでパターンを探す。銀河系を4,000億個の点群(星)としてではなく、独自の性質(渦巻きや楕円)を持つそれ自体の物体としてモデル化する。ハリケーンを小さな流体粒子の連続体としてではなく、湿った空気と水蒸気の構造化された形態としてモデル化する。選挙を有権者の嗜好の確率分布と大衆心理の観点からモデル化する。象を環境と相互作用する知的な自律的なエージェントとしてモデル化する。興味のある現象と同じスケールのパターンを求める。
還元主義が主に内容を重視するのに対して、全体論的モデルは文脈をより重視する。この巻の論文は、両者の関係や、創発など両者が絡み合う問題を、非常に多様な視点から考察している。私が思うに、少なくとも重要なポイントは、還元主義と全体主義、内容と文脈は対立する哲学ではない、ということだ。この2つは両立させることが大切なのだ。2つのツールがあるのに、なぜ1つに絞る必要があるのだろうか。
「盲人と象」 (Blind Men and Elephants)
1990年、私の哲学的啓示に話を戻そう。カオスの数学に興味を持っていた私は、生物学者のジャック・コーエンとの出会いをきっかけに、2018年に彼が亡くなるまで続く共同研究が始まった。分野は違えど、私たちはSFファンダムから科学哲学に至るまで、多くの共通の関心を見いだした。私たちは一緒に、『カオスの崩壊』と『現実の形象』を皮切りに、いくつかの共著でカオス、複雑性、創発といった問題を考察した。すべてはその最初の会合で、ジャックから興味深い質問を受けたことから始まった。もし非線形システムが非常に複雑で予測不可能であり、しかもどこにでもあるとしたら、生物はどのように機能するのだろうか?この無邪気な疑問は、私たちの予想をはるかに超える深淵なものだった。本書に寄稿された論文を検討する前に、ジャックの初期の洞察の一つを紹介することで、その舞台を整えたいと思う。それは、SF雑誌に掲載されたある漫画に触発されたものだった。この漫画ではなく、次の漫画だ。しかし、まずはこの漫画から始めなければならない。
盲人と象、バージョン1
この物語はご存じだろう。この話は古代インド亜大陸で生まれたもので、最も古いバージョンの一つは仏教のテキスト「ウダーナ6.4」に出てくる。象に出会ったことのない数人の盲人が、未知の物体に触れ、その推理を報告する。一人は縄、もう一人は木、三人は壁、四人は葉っぱ、五人は槍、六人は蛇だと言う。
通りかかった賢者が言う、「ああ、これならわかる。それは象だ」と言った。
ウィキペディアを引用するとこのたとえ話の教訓は、人間は自分の限られた主観的な経験に基づいて絶対的な真実を主張する傾向があり、他の人々の限られた主観的な経験も同様に真実であるかもしれないことを無視するということである」。これは社会的相対主義の端的な一節だが、的外れだと思う。盲人と象の教訓は、賢者が本当に賢かったかどうかにかかっているのである。
この解釈を、SF雑誌の漫画と対比させてみよう。この漫画はほとんど同じストーリーを語っているが、ひねりが加えられている。4人の盲人がそれぞれ、対象物を象だと宣言する。実は、一人は蛇を、もう一人は木に、三人は壁に、四人はロープを持っているのである。
盲人と象、バージョン2
ジャックは、この2つの漫画は、内容と文脈が重要だと教えてくれた。内容、つまり盲人の体験はどちらも同じである。しかし、最初の漫画では、彼らが想定している文脈に象が含まれていないため、それぞれの個別の体験を、彼らが知っている文脈の中で、できる限り解釈しているのである。2番目の漫画では、文脈に象が含まれているので、盲人は自分の経験を象でないにもかかわらず、象だと解釈する。賢者が正しい文脈を想定していれば、彼の合成は正しいが、そうでなければ正しくない。
科学は、両方の意味で捉えることができるのだ、とジャックは提案した。最初の漫画は、電子という概念がまだ確立されていなかった素粒子物理学の初期を描いている。古代ギリシャ人は、毛皮にこすりつけると琥珀が小さな物体を引き寄せることを経験した(冒頭で述べたように、古代ギリシャ語で琥珀はἤλεκτρονといいる)。1700年代、シャルル・フランソワ・デュ・フェイは、羊毛とこすった琥珀が帯電した金箔を引き付けるのに対し、絹とこするとガラスがはじき返すことを見いだした。彼は、絹で擦ったガラスから出る硝子液と羊毛で擦った琥珀から出る樹脂液の2つの液体を解釈していた。この2つの流体は、結合すると中和されるため、彼はこれを電気と呼んだ。その10年後、ベンジャミン・フランクリンは、電気は1つの流体で、プラスとマイナスという相反する2つの状態で存在することができると考えた。この流体は、電荷を「運ぶ」ものであり、電荷が過剰になることもあれば、不足することもある。ジョージ・ストーニーは、電気分解の実験を行い、電気「流体」は連続体ではなく、「単一の明確な量」の電気が存在し、それは1つのイオンにかかる電荷であると考えたのである。しかし、彼はこの電荷が原子に永久に付着しているとも考えていた。1881年、ヘルマン・フォン・ヘルムホルツは、この観測結果を「電気の原子のような振る舞い」の証拠と解釈した。ストーニーはこれらの素電荷をエレクトロリオンと名付けたが、すぐに電子と改名した。
最初の漫画のように、盲人たちは自分たちの観測結果を全く違ったように解釈していた。ある者は引力を感じ、別の者は2つの流体を感じ、3人目は1つの流体に2つの反対の性質があり、4人目は流体よりも粒状のもの、5人目はたくさんの原子のようだが異なるものであった。その時、一人の賢者(ジョセフ・ジョン・トムソン卿、他の何十人もの研究者の研究を基にした)が混乱を切り抜け、これらのバラバラな観測結果を、負の電荷を帯びた非常に小さな粒子という一つのものに統合したのである。これで盲人たちは、自分たちが喩えていた象を、それ自体が電子であると認識することができるようになったのである。ストニーが使っていた名前と同じだが、またしても解釈が違う。
しかし、これで終わりではない。量子力学の登場により、それまで波動と考えられていた光が、時に粒子である光子のように振る舞うようになった。逆に、粒子と思われていた電子が、波のように振る舞うこともある。つまり、最小スケールの物質は、波であると同時に粒子である可能性があるのだ。今日の見解は、さらに微妙に、技術的に異なっている。賢者は移動し、その家庭的な知恵は、不明瞭な警告で覆われ、数式で覆われている。
2つ目の漫画は、このような一連の推論に疑問を投げかけている。異なる認識の解決は、その内容が中心である。暗黙の前提は、同じ「それ」がすべての観察を説明するということであり、琥珀を羊毛でこする、電気分解を行うという全く異なる実験の文脈は、「それ」そのものには影響を与えず、「それ」をどう観察するかにのみ影響を与えるということである。もしこの仮定が誤っていれば、私たちはいくつかの未知なるものを同一視し、幻影を作り出していることになる。哲学的な問題は、「電子」が実際に存在するかどうかということである。それとも、2番目の漫画のように、異なる属性が組み合わされて、一つの根本的な原因があるかのように錯覚している世界なのだろうか?
物理学者は統一性を好む。アインシュタインは晩年、相対論的重力理論と量子物理学という2つの偉大な物理理論を1つの統一された場の理論にまとめようとした。しかし、アインシュタインも他の誰も成功させていない。しかし、超弦楽器、量子重力など、その探求は、むしろより熱烈に続けられている。一方、宇宙は、ジャックと私が「ガラスの動物園」と呼んでいるようなものかもしれない。それぞれの現象は、限られた有効性を持つ理論によって説明可能であるが、それらの理論の根本的な統一は不可能なのだ。バネッシュ・ホフマンが『量子論の奇妙な話』の中で書いているように、かつて科学者たちは「月曜日、水曜日、金曜日は光を波として、火曜日、木曜日、土曜日は粒子として見なければならないと悲痛な面持ちで訴えて回ったものだ。日曜日はただ祈るのみ」。ガラスの動物園のような世界では、それが精一杯なのだ。
電子については、物理学の判決は明確であり、大きな反響を呼んでいる:電子は、ある意味で実在する物体である。哲学者はこの結論に異論を唱えるかもしれないし、その根拠を問うかもしれない。しかし、同じ概念で多くの多様な観測や実験が説明できるので、物理学の観点からは、「電子」は明らかに存在するのである。より正確には、電子という統一的な概念が、すべての観測や実験が意味をなすような、一貫した数学的文脈を提供しているのである。そして、これこそが物理学者の言う「存在する」という意味なのだ。電子を直接観測することはできないが、いくつかの独立した証拠を使って、この意味での電子の存在を推測することができる。ちょうど、太陽の内部が空洞で、冷たく、適切な放射線を発する異質な力場に囲まれているかもしれないのに、そこに行ったことがないのに非常に高温であると推測するのと同じである。
現代科学の他の基本的な概念についても、同様の問いを投げかけることができる。今日の象の鳴き声が明日のレンガの壁やロープに変わるかもしれない、というような熱烈な説を見つけるのは難しいことではない。歴史的な例を挙げればきりがない。物質がどのように燃えるかという初期の実験は、燃える物体から未知の物質であるフロギストンが放出される証拠と解釈された。1667年に提唱されたフロギストン説は、わずか1世紀余りの間、常識とされていた。その後、燃焼したものは、燃焼していないものよりも重くなることが判明し、燃焼による生成物をすべて考慮した上で、フロギストン説を採用することになった。つまり、フロギストンとは「負の酸素」なのだ。実際、一時期、酸素は「脱フロギストン空気」と呼ばれた。
最近になって、宇宙論者は何年もかけて(そして巨額の資金を投じて)「暗黒物質」の直接的証拠を探している。暗黒物質は、銀河やその他の天体の様々な重力異常を説明するために存在しなければならないと信じられている。暗黒物質は、従来の「バリオン」物質の5倍はあるはずなのに、まだ見つかっていないのだ。しかし、今のところ、宇宙論の壁やロープや蛇は、「暗黒物質」と名付けられた存在として一括りにされている。これは、電子のような天才的な一撃かもしれないし、宇宙のフロギストンかもしれない。時間が経てば分かることだ。
科学は、文脈よりも内容に注目する習性がある。20世紀後半における分子生物学の成功は、生物の形態や行動の唯一の説明として、遺伝子を過度に強調することにつながったが、現在ではその傾向が逆転している。暗黒物質に関連する文脈は、ほとんど例外なく、アルバート・アインシュタインの一般相対性理論、あるいは、適切な場合には、より古いニュートン重力理論であると仮定されており、これは、しばしば計算上全く適切なものである。この文脈に疑問を持たなければ、暗黒物質という仮説に至った観測結果は不可解なものとなってしまう。この文脈では、これまで知られていなかった粒子によって形成された目に見えない物質が最も妥当な説明となるため、誰もがこの驚くべき新種の物質を探すことになる。この文脈に疑問を持つ人はほとんどおらず、疑問を持った人が、もっともらしい代替案を提案したり、暗黒物質理論の難しさを指摘したりしても、ほとんど無視される。
この部分の議論を終えるために、3つ目の漫画について説明しよう。10^31 人の盲人が象を観察するというもので、描くのは難しいだろう。その全員が「これは電子だ!」と言うのである(陽子や中性子を知覚する人の数を同様に増やせば、より完全な表現が得られる)。あるいは、すべてをクォークなどに還元することもできる)。これらは間違いなく正しいのだが、重要な問題が残されている。このことは、象について何を物語っているのだろうか?
この巻の内容
内容/文脈の関係は、物理学や生物学においてのみ重要なのではない。むしろ、社会科学、人文科学、芸術において、より重要である。そして、このことが最後に、この序文の主旨につながるのである。これまで、この巻の背景について考察してきたが、次にその内容を要約したいと思う。
寄稿者は、哲学者、あらゆる種類の科学者、数学者、論理学者、人文科学の専門家など、さまざまな分野の人々である。彼らのエッセイは、伝統的な学問の境界を横断し、伝統的な知恵に推測を混ぜ、多くの実務家が事実として受け入れてきたことに疑問を投げかけ、古い証拠を新しい方法で解釈している。また、その視点も多種多様だ。このような折衷的なコレクションに課される秩序は人為的なものにならざるを得ないが、私はあえて12の重複するカテゴリーに分類してみた。多くの論考は、これらのうちのいくつかを組み合わせて取り上げているが、その場合は、最も目立つ、あるいは最も便利なカテゴリーに位置づけることにする。還元論、全体論、文脈、創発、因果関係、確率、物理学・数学、量子、計算、生物学・医学、社会学、芸術である。この分類を横断する重要なストランドとして、哲学や創造性などがある。
還元主義
すでに述べたように、最近までほとんどの科学は還元主義的な精神を持っており、それはほとんど既定路線であった。物事の内部を観察し、その機能を理解することは、目覚しい成果をもたらしてきた。しかしながら、この巻の著者の多くは、包括的な哲学としての還元主義に批判的である。
マリオ・デ・カロは、方法論の指針としての還元主義と、原理的には還元が常に可能であるという広範な主張としての還元主義とを区別しているのが貴重である。その例として、化学から物理への還元を挙げているが、これはおそらく最も明確であるべきケースである。彼はまた、この極端な還元主義を、宇宙のあらゆるものは同じように説明可能であるべきだという一元論になぞらえている。ジャンフランコ・ミナーティは、明確に定義された「記述のレベル」という観点からの還元主義への標準的なアプローチが妥当かどうかを問い、不完全性がこの比喩を拒否する理由の一つであることを示唆している。これに対して、テリー・ホーガンは還元主義を支持する論陣を張り、ミクロの物理現象が一義的であり、したがって宇宙の歴史はミクロの歴史の必然的帰結であるに違いないと主張する。
ホーリズム
これは還元主義に代わる標準的な考え方で、この巻に収められているすべてのものと同様に、この言葉もさまざまな解釈が可能である。「全体」に焦点を当てるよう人々に促すのは簡単で、そのアドバイスに反論するのは難しい。しかし、「全体」が実際に何であるかを決定し、それを受け入れ、理解する方法を見つけ出すのは、より困難である。ジョン・ハイルは、還元主義の願望とその成果の間のギャップを指摘し、全体論的な代替案を検討し、全体論は創発を伴う必要はないが、創発は強い還元主義を拒否する重要な理由であることを示唆している。一方、スヴェン・オヴェ・ハンソン (Sven Ove Hansson)は、「ホーリズム」という言葉が、例えば、生まれ変わった後の子供の見通しを良くするために予防接種を拒否するといった、疑似科学的な主張を正当化するために誤って使用されていると批判している。彼は、このような態度は、「全体」が識別可能であり、閉じたシステムを形成しているという信念に起因すると考えている。
識別し、決して修正する必要のない閉じたシステムを形成することができると信じているからだ。
コンテキスト
多くの実世界のシステムは、その内容だけでは純粋に理解できないことがますます明らかになってきている。これは標準的な還元主義に挑戦し、コンテキストの役割を強調する。
故ジャック・コーエンのエッセイは、1990年のNovacon Special Are You Content in Your Contextから編集された形で再現され、コンテキストは少なくともコンテンツと同じくらい重要であるという彼の信念を説明している。彼は、遺伝学を例に情報と意味を対比させ、SFにおけるコンテクストの役割を探求している。「フェン」(彼らの専門用語でSFファン)でない読者のために編集上の注釈を加えた。エーリッヒ・ラストは、数理論理学の体系を文脈依存性と関連づけ、特に相互依存的な理論と意味の関係を調査している。オタビオ・ブエノは、数学者がしばしば否定する、定理が文脈にどの程度依存するかという数学的なトピックを考察している。Hildegard Meyer-Ortmannsは、現代の非線形力学の理論によって提供される統一的な数学的説明を持つ、異なる文脈における創発現象について考察している。数学はその内容を提供し、その変数の解釈は結果を異なる文脈に適応させる。ロバート・ビショップは、同様のテーマを探求し、すべての自然現象におけるコンテクストの重要性を強調し、コンテクスト創発が構成要素とコンテクストとの間の相互作用をいかにとらえることができるかを示している。
創発
このテーマは本書で議論される多くの問題の中心であり、他の見出しで議論される多くのエッセイにも登場する。ある思想家にとっての創発は、別の思想家にとっては何でもないものであるが、すべての用法は、その振る舞いが構成要素の振る舞いを超越しているように見えるシステムを指している。その違いは、「超越する」に付与された意味と、外観がどの程度まで有効であるかによって生じる。
ジェームズ・ミラーは、言語における創発について考察している。ここでは、真偽のようないくつかの性質は、文のような高レベルの構造でのみ意味を持つ。つまり、単一の単語を真偽に分類することはできない。彼は、このような存在論的に創発される性質が、どの程度まで低レベルの形式に内在しているのかを問うている。アルトゥーロ・カルセッティも言語学を扱い、意味の起源、人間の認識と創造性に焦点を当てる。ティモシー・オコナーは、還元主義科学の成功は、われわれが観察するすべてのものが初歩的な物理的プロセスを通じて生じることを示しているが、より複雑な物体の振る舞いが、これらの基本プロセスの一部の粗粒化されたバージョンに過ぎないと推論するのは誤りである、と指摘している。基本的な要素の新しい構成が生まれると、真に新しいプロセスや力を生み出すことができる。カール・ジレットは、科学における還元主義と創発主義の支持者間の歴史的な論争を、タンパク質の形態と機能などの明確な例とともに調査している。彼は、還元主義を正当化することはできないと主張し、そのような論争を解決する方法を提示している。アレクサンダー・カルースは、明らかに創発的な現象が、ミクロの潜在的な挙動、すなわち特定の複雑な状況においてのみ生じる場合、構成要素の部分の挙動と有意に関連づけることができるのはどのような場合か、と問いかけている。もしそうであれば、その現象は真に創発的なものではないとみなされることが多い。彼は妥協的な立場を提案している。Michael Silbersteinは、ネットワーク神経科学、認知、心理学における文脈的創発の役割を調査し、マルチスケールの文脈的制約の基本的重要性を強調している。Michael Tyeは、意識における創発の役割を、関連する素粒子の供給を受け、それらを組み立てて象の正確なコピーを作ることによって、原理的に象を作ることができるかどうかを問うことによって探求している。彼は、意識という「難問」が障害となる可能性を示唆し、意識は創発現象ではなく、宇宙の基本的な特徴であることを述べている。意識のある電子が意識のある象を生む。
因果関係
哲学者たちは、少なくとも古代ギリシャの時代から因果関係の意味と性質について議論してきた。近因(雨の中に出れば濡れる)と極因(水は水素と酸素から生成される、水素はビッグバンに遡る、酸素は星の核反応で生成された、など)には違いがある。還元論は宇宙の微細構造に究極の原因を求めるが、その因果関係の連鎖を握っているのは、還元論が好きなように装っているよりも弱い。因果関係には、内容だけでなく文脈も含まれる。相対性理論と量子論は、因果関係についての素朴な見解に独特の疑念を投げかけている。
Graham Priestは、仏教哲学における因果関係の歴史的見解を調査し、還元主義と全体主義の問題に特別な注意を払った。George EllisとJonathan Kopelは、上向きの創発と下向きの因果の相互作用が、適応的モジュールを通してどのように複雑性を生み出すかという、異なる視点から因果関係に取り組んでいる。下層から上層への純粋なボトムアップの創発の説明は、基礎となる物理学が完全であることを前提としているが、これは決して実現しない。因果の閉鎖もまた、より高いレベルからより低いレベルへのトップダウンの効果を含んでいる。COVID- 19はその一例を示している。Tim Maudlinは「トップダウン」の因果関係を検証している。この概念は、何がトップで何がボトムか、そして何が因果関係であるかに依存する。アリストテレスへの言及は、これらの問題に光を当てている。
確率
不確実性を解決し、定量化するための最も強力な数学的ツールは確率論である。その手法は十分に確立されているが、その解釈については、頻出論者(確率は長期的な割合)とベイズ論者(確率は信念の度合い)の間で現在も行われている議論に見られるように、そうではない。よくあることだが、われわれは確率を計算する方法は知っているが、それが何であるかは知らないのである。3つのエッセイでは、文脈が確率の見方にどのように影響するかを論じ、新しい技術や概念を提案している。
Ehtibar Dzhafarovは文脈の論理に関する研究をレビューし、確率変数の性質、確率論と決定論のような確率論の基本的な哲学的問題にそれを適用している。また、文脈の論理をベイズ確率、視覚的錯覚、論理的パラドックスに適用する新しいアイデアについても述べている。Sergio Chibbaro, Lamberto Rondoni, Angelo Vulpianiは、統計力学とハミルトン系という特殊な文脈で、確率の概念と実験結果の解釈の関係について研究している。この研究は、微視的に可逆な系で起こるエントロピーの増加のような不可逆な巨視的変化という長年の問題に光を当てている。Andrei Khrennikovは、量子確率の物理学以外の分野への応用をレビューしている。文脈に依存するこの確率概念は、人間など、文脈に依存する他のシステムにも光を当てることができる可能性がある。このような応用には、固有の曖昧さや不確実性が伴うが、文脈依存の確率計算の動機づけにもなる。
物理学と数学
著者の中には、数学と科学の特定の分野に議論を置き、提起された問題により具体的な様相を与えている者もいる。このカテゴリーには、金属、電子、量子重力、素粒子物理学、化学分子などを取り上げたエッセイが含まれる。いずれの場合も、ミクロ構造とマクロ構造の関連性、そしてそれが理解を助けるかどうかが重要な問題である。
トム・ランカスターは、物性物理学、特に金属の物理学に焦点を当てている。金属は人類の文明に大きな影響を与えたが、量子物理学の観点から金属を深く理解することができるようになったのはごく最近のことである。電子は単なる粒子としてではなく、システムの他の部分との相互作用によって「着飾った」準粒子であり、それが電子のコンテクストとなる。この例は、宇宙に関する他の研究にも教訓を与えてくれる。カレン・クラウザー (Karen Crowther)は、最近の量子重力の進展を検証し、アインシュタインの意味での時空は基本的なものではないことを示唆している。アインシュタインのいう時空は基本的なものではなく、時空そのものではない実体間の関係から生まれるものである。このような理論を構築する試みには、トップダウンとボトムアップの両方の戦略が用いられている。しかし、典型的な「レベル」という整然としたメタファーは、この分野では必ずしも意味をなさない。レオナルド・キアッティが選んだ分野は素粒子物理学で、通常、還元主義の中心的な例と見なされている。彼は、基本的な粒子の「本当の」性質が理解されていないことを指摘し、実際、量子モデルに対する通常のアプローチは、そのような疑問を投げかけるものではないとしている。これらの問題により、局所的な構造と大域的な構造およびプロセスの関係を探求することができる。
量子的なもの
上記の何人かの著者は量子物理学の問題を考察しているが、次のグループの論文は、量子力学の根本的な性質がもたらす深い科学的・哲学的問題に、より明確に焦点を合わせている。その中には、明らかに還元できない不確実性、波動関数の意味(もしあるとすれば)、量子測定の問題などがある。観測の簡潔で単純な数学的定義は、実際に使用される複雑な巨視的装置とどのように関連するのだろうか?
イグナシオ・リカタは、科学の限界について、量子論で議論の的になっている、実験で観測値が測定される過程を例にとって論じている。このプロセスは、実際の実験だけでなく、モデルの選択にも影響される。なぜなら、モデルは観測結果を解釈するためのコンテキストを提供するからだ。科学の構造には、複雑な推論のネットワークがあり、そのすべてがシステム的な不確実性を伴っている。アルカディ・プロトニツキーは、量子論が科学者の空間、時間、物質に対する見方をどのように変えたかについて、歴史的なサーベイを行っている。量子の不確実性は、下から上への決定論的なつながりがないため、還元主義的な考え方の適用に制限を課すものである。一方、量子力学は全体論的なアプローチにも向いていない。そのため、量子論は物理学と哲学の両分野で異なる考え方をすることになる。ミシェル・プラナは、量子観測の問題を、数学的に技術的な方法で斬新に扱っている。彼は、自由群における「言葉」(数列記号)という「言語」を使っている。自由群における「言葉」は、量子力学の基本である作用素の可換量に対応する。言葉は4次元多様体のパスに対応し、一種のエキゾチックな時空である。測定は、関連するが異なる多様体に対応する。その結果、一種の量子論理、「エキゾチックな非文脈性」が生まれる。ルチアーノ・ボイは、幾何学、位相、不変量の観点から、トポロジカル量子場の理論と弦理論における現在のアイデアをレビューしている。結び目とリンクの不変量と物理的な観測値との関連を示唆する結び目理論における最近のブレークスルーとの関係についても論じている。これは、Peter Guthrie Taitによる古い提案を現代風にアレンジしたもので、オリジナルの「渦原子」形式では長い間信用されていなかった。彼はまた、時空間のファジーさについても考察している。José Acacio de Barros, Federico Holik and Decio Krauseは、量子力学において文脈と内容がいかに問題を引き起こすかについて議論している。彼らはこの問題が素粒子に対して持つ奇妙な意味を探求し、素粒子を標準的な数学を用いた研究に適さないものにしてしまい、その結果新しい数学的アイディアが必要となるのである。
計算
計算のような具体的なものが、深い哲学的問題を引き起こすのは奇妙に思えるかもしれないが、このテーマの歴史は、適切な問いが投げかけられたとき、それが必然であることを論じている。計算可能性の本質もその一つで、アラン・チューリングを停止問題がアルゴリズム的に決定不可能であることの発見へと導いた。彼の人工知能への関心は、現在、ディープラーニングなどの手法によって開花し、アルゴリズムは日常生活に無数の影響を及ぼし始めている。計算の応用は、今や社会的、哲学的に深刻な問題を投げかけている。量子コンピュータの可能性は言うまでもないが。..。
サムソン・アブラムスキーは、パラドックスとその解決法である偏愛の概念について、ある視点を提示している。彼はこれを、古典計算と、十分に柔軟な計算システムはすべて等価であるというチャーチ・チューリングのテーゼ、そして、偏愛が数学的形式主義の帰結である量子計算の二つの設定で説明する。イルッカ・ニーニルオトは、現在大きな関心を集めているもう一つの計算問題、ディープラーニングと人工知能について考察している。彼は哲学的な観点からAIの学習過程を考察し、ヒューバート・ドレフュスのAI批判を再考する。トーマス・フィルクは、関連する数学的構造として、典型的な複雑適応系であるニューラルネットワークを分析する。ニューラルネットワークは、そのサイズに応じて、コンテンツとコンテキストの間を補間するものと見なすことができる。リカレントネットワークは非古典力学のように振る舞い、記憶効果を持つ。また、量子力学のベルの不等式に違反するように訓練することもでき、通常、量子の不確実性の決定論的説明を排除すると考えられている。遺伝的アルゴリズムはダーウィンの進化に似ている。
生物学と医学
生命科学ほど、還元論的説明が直面する難問はない。「生命とは何か」という基本的な疑問さえ、パンドラの箱(「パンドラの倉庫」という比喩がより適切かもしれない)を開けてしまうのである。分子生物学が数十年にわたり大きく発展してきたにもかかわらず、単一の細胞でさえ、むしろこれまで以上に謎に包まれるようになってきた。生物体や生態系は言うに及ばずである。これは、二重らせんの発見によって開かれた驚くべき進歩を否定するものではないが、私たちがまだどれほど遠くまで旅をしなければならないかを示している。ジョン・ビックルは、伝統的な全体論的心理学の考え方が、神経科学的な分子・細胞認知の分野と接点を持つ問題を探っている。つまり、神経細胞や生化学から高度な脳機能がどのように生まれるか、という問題である。彼は、この場合、異なる「レベル」間のリンクには多くの望みが残されていることを観察している。レイモンドとデニス・ノーブル卿は、ミクロレベルの説明が特権的であるという還元主義的な仮定とは逆に、特定の因果的レベルが一義的であるとすることはできないという考えを、素人にもわかるように紹介してくれている。彼の考えでは、代理性や意識は、より高いレベルでの機能的制約から生じるものであり、幻想ではなく、現実のものである。ダニエル・デネットは、知的行動を担う脳内の機械について、推測的ではあるが洞察に満ちた考えを示しており、知的行動には予見と自己モニタリングが不可欠であることを示唆している。理性的な熟慮者は、起こらない問題について心配し、それを防ぐために行動を起こすので、ほとんどの場合、心配することになる。彼は、これらの考えが知的ロボットの設計に与える影響を探る。ルチアーノ・ボイは、この問題の最も不可解な例の1つである、生物の遺伝学と分子構造がその成長と進化にどのように関係しているかを検証している。マクロレベルの形態学には独自の構造とパターンがあり、それは最終的には遺伝子と分子に由来するものであるが、ミクロレベルを参照しなくても理解し利用することができる、と提案している。事実上、この提案は、遺伝子の「情報」を非線形力学に置き換えるものである。Marta BertolasoとHéctor Velázquezは、還元主義と全体論的手法の間の緊張が、通常は内容と文脈の間の依存関係として見られる生命科学においてますます明白になってきていることを指摘している。複雑さはどこにでもあり、生命の本質と起源を研究することは、必然的にこの緊張をもたらす。彼は、すべてを分子に基づくような普遍的な還元主義から、「特殊の哲学」へと焦点を移すべきであると提案し、癌などの例を挙げている。マルコ・ブゾーニ、ルイジ・テシオ、マイケル・スチュアートは、医師がマクロレベル(患者)とミクロレベル(薬物や遺伝学)の両方の知識と方法を組み合わせる必要があるとして、議論をさらに医学的な領域へと進めている。基本的な問いは、「病気とは何か」、「どのように治療すべきか」である。彼らは、実験パラダイムをホリスティックな「補完」医学に有益に適用できることを提案しているが、この提案は、その実践者のほとんどが拒否するか無視するものである。Manuel Rebuschiは、精神分裂病という一つの例を取り上げている。ここでは、患者との会話を解釈することが必要であり、それには文脈が含まれる。架空の会話を分析することで、病気とその対処法の両方に光を当てている。
社会学
「それでは汝自身を知れ、神がスキャンすると思うな、人類の適切な研究は人間である」。詩人アレクサンダー・ポープは、1733-4年の『人間についてのエッセイ』の中でそう書いている。1733-4年、詩人アレクサンダー・ポープが「人間についてのエッセイII」でこう書いている。何世代もの科学者が人間性以外のものを研究してきた。他の科学者も人間性を研究してきたが、人間性のレベルではなかった。社会科学者はそのギャップを埋め、ここでの「人間」(Man)という言葉が性差別的であることを正しく認識させる。(社会学は、人間の状態に対する鋭い洞察を提供するが、管理された実験を行うことの難しさなど、巨大で避けられない障害に悩まされている。それゆえ、社会学は文脈や創発といった問題に真正面から向き合っている。
フリーデル・ヴァイナートは、社会科学の説明をどのレベルで行うべきかについて、2つの学派の間で交わされた議論を考察している。重要な要因は、社会的単位における個人の行動なのか、それともその個人に影響を与える社会的要因が重要なのか。妥協的な立場としては、問題の性質に応じてレベルを選択することであるが、場合によっては、マクロレベルの説明が避けられないこともある。Diederik AertsとMassimiliano Sassoli de Bianchiは、熱力学や進化などの基礎科学と、物質、生命、人間文化などの側面との関連性を研究している。アーウィン・シュレーディンガーの『生命とは何か』の先駆的な足跡をたどり、熱力学の第二法則が生物と文化にどのように関係しているかを論じている。Annika DöringとJosé Garcíaは、文化、特に、認識されていない文化の違いの落とし穴についても論じている。岡倉覚三の『茶の本』とマルティン・ハイデガーの『存在と時間』を対比させている。この2つの作品にはかなり多くの共通点があり、ハイデガーが和子の作品を参考にしたのではないかという見方もある。ここで、この共通点は表面的なものであり、二人の作家は似たような言葉を使いながら根本的に異なる意味を持ち、内容は似ているが文脈は異なるということが指摘される。東洋と西洋の文化の違いを理解することで、このような誤解を正すことができる。
芸術
歴史的に見れば、人類の歴史の大部分において、芸術と科学は密接な関係にあった。初期の洞窟画家は、マンモスの輪郭をスケッチするだけでなく、顔料やオイルランプを自分で作らなければならなかった。啓蒙時代には、科学者と芸術家が日常的に顔を合わせ、それぞれが相手に影響を与えた。20世紀になると、この2つの活動領域は様々な形で分離されるようになった。例えば、学校には科学の流れと芸術の流れがあることがよくある。多くのアーティストや科学者は、今でもこの分離を受け入れているが、そのギャップを埋めるバンドが再び増えてきている。
ナナ・ラストは、ポストモダニズムの「テキストとしての建築」からデジタル時代の「アルゴリズムとしての建築」への移行に触発されて、建築の考え方が大きく変化したことを教えてくれた。これは、全体計画から始めて後で細部を追加するのではなく、後発の細部から全体の構想に情報を伝達することを可能にし、設計プロセスを一変させたのである。ジョン・バロウのエッセイは、2020年に早すぎる死を迎える直前に書かれたもので、科学と芸術のつながりに対する彼の生涯の関心が反映されている。ここでは、どちらの活動にも複雑さが伴うことを指摘し、物理学が好む複雑系の1つである「砂山」を考察している。砂山は、砂粒のレベルでは非常に複雑であるにもかかわらず、砂山全体のレベルでは非常に単純であるという例だ。演奏の魅力は、このような全体的な堅牢さにあり、微細な構造の違いによって、より興味深いものとなっていることを示唆している。
単純、複雑、多重
どの著者の、どの主張に賛同するかは人それぞれであり、論理的に考えて、すべてに確実に賛同することはできない。だからこそ、この一冊が存在する。だからこそ、私たちはすべての論考を読み、その筋道を理解しようとする必要がある。
最後に、ジャック・コーエンとの共同作業のもう一つの要素であるSFからヒントを得て、すべてをすっきりとまとめたいと思う。1960年代から70年代にかけて最も活躍した偉大なSF作家の一人に、サミュエル・R・ディレイニーがいる。彼の作品は、このジャンルに馴染みのない人たちが「SF」の全体を構成していると信じている、陳腐な銃撃戦のような宇宙戦ではない。実際、そのような形容に当てはまるものはほとんどない。多くの優れたSFと同様、ディレイニーの小説は、想像力に富んだ文脈ではあるが、人間の状態についての思慮深く洞察に満ちた探求である。特にSFを読んだことがない人には、この巻のテーマについて多くのことを語っているので、手に入れることをお勧めする。ジェイムズ・ジョイスの『フィネガンズ・ウェイク』が未完の文章を完成させて終わるように、この作品は短く、巧妙で想像力に富み、表面的には循環した構造になっている。しかし、ディレイニーの構造はそれほど単純ではない。実際、彼の小説は、それ自体が多重構造であることを明確に宣言している。そして、それによって一つの物語が始まる。..。物語は、リースという僻地にある惑星に住むジョーという少年が主人公である。彼は、銀河の行政の中心であるエンパイア・スターに向かう途中、墜落した有機体型巡洋艦の唯一の生き残りであるトリトフ人の結晶体ジュエルと出会う。乗組員の一人は、ジョーにエンパイア・スターへのメッセージを伝えるには十分な時間だったが、そのメッセージが何であるかを伝えるには十分でなかった。しかし、そのメッセージの内容をジョーに伝えることはできなかった。「Lllを解放するために誰かが来た」というものだった。この巨大な知的生物は、文明全体を再建する能力があるため奴隷として飼われており、その仕返しとして、所有者全員を救いようのないほど悲しませるのだという。Joはまた、誰かがLllを解放するためにやって来るまで、このメッセージを届けてはいけないことも知るが、これは明確ではない。
とにかく、これがフレーム(文脈)である。私が論じたい具体的な内容の要素は、ディレイニーのワイドスクリーン・バロックのたとえ話の中の小さなディテールであり、知覚を持つ存在の精神的プロセスについての連続したテーマである。すなわち、それらは主に3つのタイプに分けられる:単純、複雑、多重。ある人に「この世で一番大切なものは何か?と聞けば、単純なものであれば答えるだろう。もう一つのテストは、質問をするかどうかだ。シンプレクスの人はめったに質問しない。このように、宇宙のすべての知識をアルファベット順にカタログ化するという壮大なプロジェクトの真っ只中にある測地測量局の住人は、非常に知的であるが、絶望的にシンプレックスである。その証拠に、彼らのプロジェクトは彼らのすべてであり、それが賢明であるかどうか、実現可能であるかどうか、価値があるかどうかを自問することはない。複雑な知性は、同じ物事について異なる人々や文化が異なる意見を持ちうること、一方が間違っていて他方が正しいということはないこと、そして新しい知識がいつでも現れうることを理解することができる。多面的な知性は、物事を多くの視点から同時に考察する。一見矛盾した、あるいは混乱した大量の情報に直面したとき、多面的人格は、問うべき正しい質問がわかるまで、自分の認識を秩序立てるのである。
還元主義と全体主義だけでは、すべてのイズムがそうであるように、どちらもシンプレックスである。ある考え方の優位性を主張し、他のすべての考え方を排除することは、その主張がいかに巧妙に表現されたとしても、どうしようもなくシンプレクスなのである。ディレイニーの登場人物であるランプ(言語的に偏在するマルチプレックス)が言うように、「知性とプレキシティは必ずしも一緒にならない」のである。この本の中のほとんどのエッセイは複雑であり、著者によっては他の著者と平気で矛盾しているので、この本自体が複雑であることは間違いない。実際、適切な心構えで取り組めば、このコレクション全体が多面的であることは間違いない。自分の認識を多面的に整理するだけで、すべてがどのように組み合わされるかが理解できるだろう。
イアン・スチュワート
ユニバーシティ・プレス
目次
- コンテクストを設定する
- あなたは自分の文脈の中で満足しているか? 3 ジャック・コーエン
- 存在のインクリメンタルな連鎖 11 ジョン・ハイル
- 言語学には(弱い)創発が必要なのか? 23 J. T. M. ミラー
- 文脈的意味と理論的依存性 39 エーリッヒ・H・ラスト
- 科学的自然主義とその欠点 65 マリオ・デ・カロ
- 科学的創発主義と相互主義革命 新しい自然観、新しい方法論
- 新しい自然観、新しい方法論、新しいモデル 79 カール・ジレット
- 仏教哲学における因果関係 99 グラハム・プリースト
- リアルワールドにおける因果関係の現実的な見方 117 ジョージ・F・R・エリスとジョナサン・コペル
- 頂点はどこにあるのか、そして何が倒れる可能性があるのか? 135 ティム・モードリン
- 複雑性の特異な非還元主義的性質としての多重性、論理的開放性、非完全性、準完全性 151 ジャンフランコ・ミナーティ
- マイクロレイテンシー、ホーリズム、創発 175 アレクサンダー・カルース
- エナクティブ・リアリズム. 新しい理論的統合の初見 195 アルトゥーロ・カルセッティ
- ホーリズムとシュードホーリズム 215 スヴェン・オヴェ・ハンソン
- 説明的創発,形而上学的創発,物理学の形而上学的優位性 229 テリー・ホーガン
- コンテクスチュアル・エマージェンス (Contextual Emergence).構成要素、文脈、意味 243 ロバート・C・ビショップ
- 数学/理論物理学
- 内容、文脈、文脈性の基礎 259 エチバル・N・ジャファロフ
- 数学における内容、文脈、自然主義 287 オタビオ・ブエノ
- 複雑系の文脈における数学的内容の共有 307 ヒルデガルト・マイヤー=オルトマンズ
- 統一されてはいるが統一されていない。私たちの豊穣な宇宙 329 ティモシー・オコナー
- 統計力学における確率、典型性、創発 339 セルジオ・チッバロ,ランベルト・ロンドニ,アンジェロ・ヴルピアーニ
- 金属: 現代物理学のモデル 361 トム・ランカスター
- 時空間の創発 コンテンツとコンテクストの区別を崩壊させるか? 379 カレン・クラウザー
- トポロジカル量子場理論と幾何学から物理的時空の創発。幾何学と物理学の相互作用に関する新たな洞察 403 ルチアーノ・ボイ
- 電子とコスモス 電子と宇宙:断片的な物体の宇宙から素粒子の世界へ 425 レオナルド・キアッティ
- 「自然法則における原子性の新しい特徴」還元論に対抗する量子論 445 アルカディ・プロトニツキー
- 量子論的現実における幾何学的およびエキゾチックな文脈性 469 ミシェル・プラナ
- 量子的同一性、内容、文脈。古典的論理学から非古典的論理学へ 489 J. アカシオ・デ・バロス、フェデリコ・ホリック、デシオ・クラウゼ
- 量子物理学、認知、心理学、社会科学、人工知能における文脈上の確率 523 アンドレイ・クレンニコフ
- 認知科学・計算機科学
- 全てから生まれるものはない:ソフトウェアタワーズと量子タワー 539 サムソン・アブラムスキー
- ニューラルネットワークの量子的な振る舞い 553 トーマス・フィルク
- 概念、専門家、そしてディープラーニング 577 イルッカ・ニーニルオト
- インテリジェンスへの道筋。過度な単純化と自己モニタリング 587 ダニエル・C・デネット
- 文脈は王である。ネットワーク神経科学、認知科学、心理学における文脈の創発 597 マイケル・シルバーシュタイン
- 電子から象まで コンテキストと意識 641 マイケル・タイ
- つのレベルが衝突するとき 653 ジョン・ビックル
- 生物学
- 生物界におけるエピジェネティクスと因果性についての考察 675 ルチアーノ・ボイ
- エージェンシーは分子に還元できるか? 699 レイモンド・ノーブルとデニス・ノーブル
- 生命の認識論 関係存在論に基づく生命体の理解 719 マルタ・ベルトラスソとエクトル・ベラスケス
- 病気/疾患論争における全体論と還元論 743 マルコ・ブッツォーニ、ルイジ・テシオ、マイケル・T・スチュアート
- 文脈、フィクション、そして統合失調症について 779 マニュエル・レブスキ
- 人文科学と社会科学
- 社会的・社会的事実の説明について 799 フリーデル・ヴァイナート
- 物質、生命、人間文化の不可逆的旅路について 821 ディエデリック・アールツ、マッシミリアーノ・サッソリ・デ・ビアンキ
- 建築とビッグデータ。規模から容量へ 843 ナナ・ラスト
- 存在か、それともお茶か? 861 アニカ・ドーリング、ホセ・オルドネス・ガルシア
- 芸術は批評的である875 ジョン・D・バロウ
