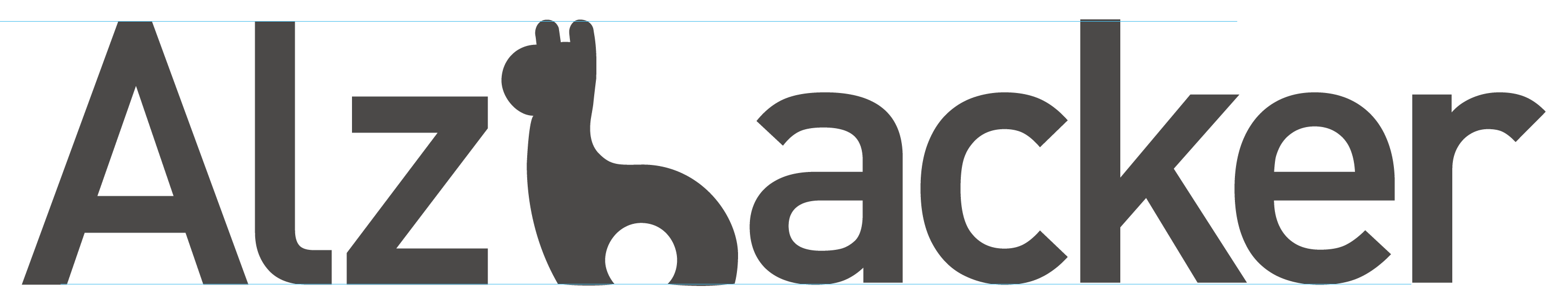Contents
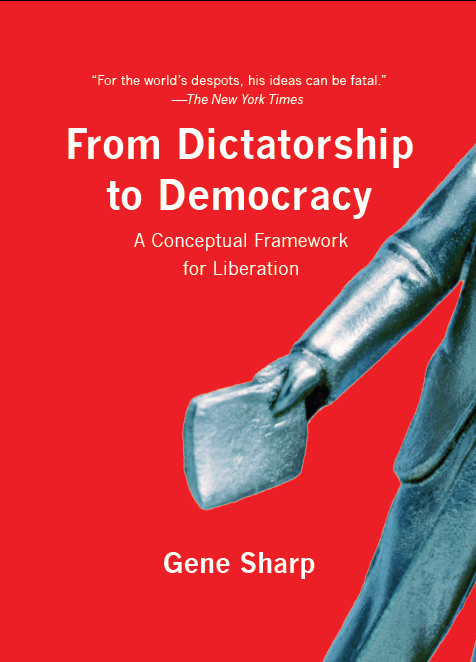
ジェネ・シャープ
From Dictatorship to Democracy: A Conceptual Framework for Liberation
米国での発行:The New Press, New York, 2012
目次
- 謝辞
- 著者ノート
- 序文
- 1 独裁政治と現実的に向き合うために
- 継続する問題
- 暴力による自由?
- クーデター、選挙、外国人の救世主?
- 厳しい現実に直面する
- 2 交渉の危険性
- 交渉のメリットと限界
- 交渉による降伏?
- 交渉における権力と正義
- 「合意できる」独裁者
- どのような平和か?
- 希望の理由
- 3 権力はどこから来るのか?
- 「猿の親分」の寓話
- 政治権力に必要なもの
- 民主的権力の中心
- 4 独裁体制には弱点がある
- アキレス腱を見極める
- 独裁の弱点
- 独裁の弱点を攻める
- 5 権力の行使
- 非暴力闘争のしくみ
- 非暴力的な武器と規律
- 開放性、秘密性、高水準性
- 力関係の転換
- 変化の4つのメカニズム
- 政治的反抗の民主化効果
- 非暴力的闘争の複雑性
- 6 戦略的計画の必要性
- 現実的な計画
- 計画策定へのハードル
- 戦略的計画における4つの重要な用語
- 7 戦略計画の立案
- 手段の選択
- 民主化のための計画
- 外部からの支援
- 大戦略の策定
- キャンペーン戦略の立案
- 非協力思想の普及
- 弾圧と対抗措置
- 戦略プランの遵守
- 8 政治的反抗の適用
- 選択的抵抗
- 象徴的な挑戦
- 責任の分散
- 独裁者の権力を狙う
- 戦略の転換
- 9 独裁体制の崩壊
- エスカレートする自由
- 独裁体制の崩壊
- 責任ある成功の処理
- 10 永続的な民主主義のための土台作り
- 新たな独裁の脅威
- クーデターの阻止
- 憲法起草
- 民主的な防衛政策
- 功労者としての責任
- 付録
- 非暴力行動の方法
- ノート
- 謝辞
- 著者ノート
謝辞
このエッセイの原版を執筆している間に、私はいくつかの恩義を感じた。1993年の私の特別補佐官であったブルース・ジェンキンスは、内容や表現上の問題点を指摘し、計り知れない貢献をした。また、難しい考え(特に戦略に関するもの)をより厳密に、より明確に提示し、構造を再編成し、編集を改善するよう、鋭く提言してくれた。
また、Stephen Coadyの編集協力にも感謝している。クリストファー・クルーグラー博士とロバート・ヘルベイ博士からは、非常に重要な批評と助言をいただいた。Hazel McFerson博士とPatricia Parkman博士は、それぞれアフリカとラテンアメリカの闘争について情報を提供してくれた。しかし、そこに含まれる分析と結論は、あくまでも私の責任である。
近年、翻訳に関する特別なガイドラインが作成されたが、これは主にJamila Raqibの指導と、それ以前の年から学んだ教訓によるものである。これは、これまでこの分野の明確な用語が確立されていなかった言語において、正確性を確保するために必要なものである。
著者のコメント
『独裁から民主へ』は、ビルマ民主派の著名な亡命者であり、当時『新時代誌』の編集者であった故ウティン・マウン・ウィンの依頼により執筆されたものである。
この文章の作成は、非暴力闘争、独裁体制、全体主義体制、レジスタンス運動、政治理論、社会学的分析などに関する40年以上の研究と執筆に基づくものであった。
ビルマのことをよく知らない私は、ビルマだけに焦点を当てた分析を書くことはできなかった。そのため、一般的な分析を書かざるを得なかった。
この論文は、1993年にタイのバンコクで、ビルマ語と英語のKhit Pyaingに分割して掲載されたのが始まりである。その後、両言語の冊子として発行され(1994)、再びビルマ語で発行された(1996年、1997)。バンコクで発行された冊子版は、ビルマ民主化委員会の協力のもとに発行された。
この冊子はビルマ国内だけでなく、他の地域の亡命者やシンパの間でも密かに配布された。この分析は、ビルマの民主主義者や、ラングーンにあるビルマ人支配の中央政府からの独立を望むビルマの様々な民族グループのためにのみ使用されることを意図したものであった。(ビルマ人は、ビルマの支配的な民族である)。
私はこの分析が、権威主義的あるいは独裁的な政府を持つどの国にも当てはまるとは思っていなかった。しかし、近年、この本を自国語で翻訳し、配布しようとした人たちの間では、そのように受け止められているようである。まるで自分の国のために書かれたかのような内容だと、何人もの人が報告している。
ラングーンの軍事独裁政権SLORCは、この出版物を非難するのに時間をかけなかった。1995年と1996年に激しい攻撃が行われ、その後も新聞、ラジオ、テレビで続けられたと言われている。2005年に至っては、禁止されたこの出版物を所持していたというだけで、7年の禁固刑を言い渡された。
他国への普及活動は行われなかったが、翻訳・配布が独自に行われるようになった。バンコクの書店のウィンドウに飾られていた英語版をインドネシア人留学生が買い求め、持ち帰った。そして、インドネシア語に翻訳され、1997年にインドネシアの大手出版社から、アブドゥルラフマン・ワヒッド氏の序文付きで出版された。彼は当時、3,500万人の会員を持つ世界最大のイスラム教組織ナドラトゥル・ウラマのトップで、後にインドネシア大統領になった人物である。
この間、アルバート・アインシュタイン研究所の私のオフィスには、バンコクの英語版冊子からコピーしたものがほんの少ししかなかった。数年間は、問い合わせがあったときにコピーを取っていた。その後、カリフォルニアのMarek Zelaskiewzが、Milošević氏の時代にそのうちの1部をベオグラードに持ち帰り、Civic Initiativesという団体に渡した。それをセルビア語に翻訳して出版したのである。ミロシェビッチ政権崩壊後、私たちがセルビアを訪れた際、この小冊子が反対運動に大きな影響を与えたと聞いた。
また、元米国陸軍大佐のロバート・ヘルヴィーがハンガリーのブダペストで、約20人のセルビアの若者たちに非暴力闘争の本質と可能性についてワークショップを行ってくれたことも重要であった。ヘルベイ氏はまた、『非暴力行動の政治学』の全集を彼らに渡した。この人たちが、ミロシェヴィッチを倒した非暴力闘争を率いたオトポールの組織となったのである。
この出版物の認知度が国から国へとどのように広がっていったかは、通常、私たちにはわからない。近年、ウェブサイト上で公開されていることも重要だが、それだけが要因ではないことは明らかだ。このようなつながりをたどることは、大きな研究プロジェクトになるだろう。
『独裁から民主へ』は重い分析であり、簡単に読めるものではない。しかし、大きな作業と費用を必要としながらも、少なくとも28の翻訳(2008年1月現在)が準備されるほど、重要なものであると判断されたのである。
この出版物の印刷物やウェブサイトでの翻訳には、以下の言語が含まれている。アムハラ語(エチオピア)、アラビア語、アゼリ語(アゼルバイジャン)、インドネシア語、ベラルーシ語、ビルマ語、チン語(ビルマ)、中国語(簡体字・繁体字)、ディベヒ語(モルディブ)、ペルシア語(イラン)、フランス語、グルジア語、ドイツ語、ジンポー(ビルマ)、カレン語(ビルマ)、クメール語(ビルマ)。カレン語(ビルマ)、クメール語(カンボジア)、クルド語、キルギス語(キルギス)、ネパール語、パシュトー語(アフガニスタン、パキスタン)、ロシア語、セルビア語、スペイン語、チベット語、ティグリニア語(エリトリア)、ウクライナ語、ウズベク語(ウズベキスタン)、ベトナム語である。その他にも数種類が準備中である。
1993年から2002年の間に、6つの翻訳があった。2003年から2008年までの間に、22の翻訳があった。
このように翻訳された社会や言語が多様であることは、この文書に最初に出会った人が、その分析結果を自分たちの社会と関連づけることができたという暫定的な結論になる。
ジーン・シャープ
2008年1月
アルバート・アインシュタイン研究所
マサチューセッツ州ボストン
序文
私が長年にわたって抱いてきた主要な関心事の一つは、人々がどのようにして独裁政治を阻止し、破壊することができるのかということであった。これは、人間がそのような政権に支配され、破壊されてはいけないという信念から培われたものである。この信念は、人間の自由の重要性、独裁の本質(アリストテレスから全体主義の分析者まで)、独裁の歴史(特にナチスとスターリン体制)を読むことによって強化されてきた。
長年にわたり、私はナチスの支配下で生き、苦しんだ人々と知り合う機会があった。その中には強制収容所から生き延びた人々もいる。ノルウェーでは、ファシズムの支配に抵抗して生き延びた人々に会い、亡くなった人々の話を聞いた。ナチスの魔の手から逃れたユダヤ人や、彼らを助けた人たちと話をした。
各国の共産主義支配の恐ろしさについては、個人的な接触よりも書物から学んだことが多い。これらの独裁体制は、抑圧と搾取からの解放という名目で強要されたものだろうから、その恐怖はひときわ痛烈なものであった。
最近になって、パナマ、ポーランド、チリ、チベット、ビルマなど、独裁政権下の国々を訪問し、今日の独裁政権の現実がよりリアルに伝わってきた。中国共産党の侵略と闘ったチベット人、1991年8月の強硬クーデターを倒したロシア人、軍事政権への復帰を非暴力で阻止したタイ人などから、独裁の陰湿さについてしばしば悩ましい視点を得ることができた。
残忍な行為に対する哀しみと憤り、そして信じられないほど勇敢な人々の冷静なヒロイズムへの賞賛は、危険がまだ大きいにもかかわらず、勇敢な人々の反抗が続いている場所を訪れることで強められることがあった。ノリエガ政権下のパナマ、ソ連の弾圧が続くリトアニアのビリニュス、北京の天安門広場、自由のお祭り騒ぎとあの運命の夜に初めて装甲兵員輸送車が進入した時、そして「解放されたビルマ」のマネープローの民主反対派のジャングル司令部などであった。
ビリニュスのテレビ塔と墓地、人々が銃殺されたリガの公共公園、ファシストが列をなして抵抗者を射殺した北イタリアのフェラーラ中心部、若くして亡くなった人々の遺体で埋められたマネルプラウの簡素な墓地など、戦没者の跡を訪れることもあった。どの独裁政権も、このような死と破壊を後世に残していくものなのだと、悲しい思いがした。
こうした懸念や経験から、専制政治を阻止することは可能かもしれない、独裁政治に対する闘争を成功させるには、互いに大量虐殺することなく、独裁政治を破壊し、灰の中から新しい独裁政治が立ち上がらないようにできるかもしれない、という強い希望が生まれた。
私は、苦しみや命の犠牲をできるだけ少なくして独裁政権を崩壊させる最も効果的な方法について、慎重に考えようとした。そのために、私は長年にわたる独裁政権、レジスタンス運動、革命、政治思想、政府制度、そして特に現実的な非暴力闘争についての研究をもとに、この出版物を作成したのである。
この出版物はその結果である。完璧とは程遠いものであることは確かである。しかし、おそらく、そうでない場合よりも強力で効果的な解放運動を生み出すための思考と計画を支援するいくつかのガイドラインを提供するものである。
必然的に、そして意図的に選択したことだが、この小論の焦点は、独裁政権をいかにして破壊し、新たな独裁政権の台頭を防ぐかという一般的な問題に当てられている。私には、特定の国について詳細な分析と処方箋を作成する能力はない。しかし、この一般的な分析が、独裁的支配の現実に直面している、残念ながらあまりにも多くの国の人々の役に立つことを願っている。彼らは、自分たちの状況に対してこの分析が有効だろうかどうか、また、この分析の主要な勧告が自分たちの解放闘争にどの程度適用できるか、あるいは適用できるかを検討する必要がある。
この分析のどこにも、独裁者に逆らうことが簡単で、費用のかからない努力であると想定しているものはない。すべての闘争の形態には複雑さとコストがある。独裁者と戦うことは、もちろん犠牲を伴う。しかし、この分析が、レジスタンス運動の指導者たちに、犠牲者の相対的なレベルを下げつつ、有効な力を高めることができるような戦略を考えるきっかけになればと願っている。
また、この分析は、特定の独裁体制が終了すれば、他のすべての問題も消滅するという意味に解釈されるべきではない。ある政権が倒れたからといって、ユートピアが到来するわけではない。むしろ、より公正な社会的、経済的、政治的関係を築き、他の形態の不正や抑圧を根絶するための努力と長い努力への道が開かれる。独裁体制がどのように崩壊しうるかについてのこの短い考察が、人々が支配のもとに生き、自由になることを望んでいるあらゆる場所で役に立つことを、私は願っている。
ジーン・シャープ
1993年10月6日
アルバート・アインシュタイン・インスティテュート
マサチューセッツ州ボストン
第1章 独裁政治に現実的に立ち向かう
近年、内外のさまざまな独裁政権が、反抗的で動員された民衆に直面したときに崩壊したり、つまずいたりした。多くの場合、独裁体制は強固で難攻不落と見られているが、これらの独裁体制の中には、政治的、経済的、社会的な人々の協調的な反抗に耐えられないと証明されたものもある。
1980年以降、エストニア、ラトビア、リトアニア、ポーランド、東ドイツ、チェコスロバキア、スロベニア、マダガスカル、マリ、ボリビア、フィリピンでは、人々の非暴力による抵抗の前に独裁政権が崩壊した。非暴力抵抗は、ネパール、ザンビア、韓国、チリ、アルゼンチン、ハイチ、ブラジル、ウルグアイ、マラウィ、タイ、ブルガリア、ハンガリー、ナイジェリア、旧ソ連各地などで民主化への動きを加速させた(91年8月の強硬クーデター未遂の敗北に重要な役割を演じた)。
また、近年では中国、ビルマ、チベットで大規模な政治的反抗1が起こっている。これらの闘争は、支配的な独裁政権や占領に終止符を打つことはできなかったが、それらの抑圧的な政権の残忍な性質を世界社会に暴露し、このような闘争の形態について人々に貴重な経験を提供したのである。
貧困、犯罪、官僚の非効率性、環境破壊は、しばしば残忍な政権の遺産である。しかし、これらの独裁政権の崩壊は、抑圧の犠牲者の苦しみの多くを最小限に軽減し、より大きな政治的民主主義、個人の自由、社会正義を備えたこれらの社会の再建への道を開いたのである。
継続する問題
この数十年、世界には民主化と自由を求める傾向が確かにあった。政治的権利と市民的自由の状況について毎年国際的な調査を行っているフリーダムハウスによると、「自由」と分類される国の数は近年著しく増加している2。
しかし、このような良い傾向の一方で、依然として多くの人々が専制的な環境の下で暮らしていることも事実である。2008年現在、世界人口66億8000万人のうち34%が、政治的権利や市民の自由が極端に制限された「Not Free」3と呼ばれる国に住んでいる。Not Free “に分類された42カ国は、ビルマなどの軍事独裁政権、サウジアラビアやブータンなどの伝統的な抑圧的君主制、中国や北朝鮮などの支配政党、チベットや西サハラなどの外国人占領者によって統治されているか、あるいは移行状態にある。
今日、多くの国が経済的、政治的、社会的に急速に変化している。近年、「自由」な国の数は増えているが、このような急速な根本的な変化に直面した多くの国が、逆に新しい形の独裁を経験する危険性が大きい。軍閥、野心家、選挙で選ばれた人、教条的な政党などが、繰り返し自分たちの意志を押し通そうとする。クーデターはよくあることであり、今後もそうあり続けるだろう。基本的人権と政治的権利は、これからも多くの人々に否定され続けるだろう。
残念ながら、過去はまだ私たちとともにある。独裁の問題は根深い。多くの国の人々は、国内由来か国外由来かを問わず、何十年、何百年にもわたって抑圧を経験してきた。多くの場合、権威者や支配者に対する疑う余地のない服従が長い間植えつけられてきた。極端な例では、社会的、政治的、経済的、さらには宗教的な制度が、国家の統制の及ばないところで、意図的に弱められ、従属させられ、あるいは国家や与党が社会を統制するために用いる新しい体制的な制度に取って代わられたりもしている。国民はしばしば、自由を得るために協力することも、互いに打ち明けることも、自発的に何かをすることもできない、孤立した個人の塊にされてきたのである。
その結果、人々は弱くなり、自信を失い、抵抗することができなくなる。独裁政権への憎しみや自由への渇望を、家族や友人とさえも共有することができないほど、人々は怯えている。恐怖のあまり、大衆の抵抗を真剣に考えることもできない。いずれにせよ、何の役に立つのだろうか。それどころか、目的なき苦しみと希望なき未来に直面している。
現在の独裁政権の状況は、以前よりずっと悪くなっているかもしれない。過去には、抵抗を試みた人々もいたかもしれない。短期間の集団抗議行動やデモが起こったかもしれない。一時的に精神が高揚したこともあっただろう。また、個人や小さな集団が、勇敢ではあるが非力なジェスチャーを行い、何らかの原則を主張したり、単に反抗したりしたこともあっただろう。しかし、その動機がいかに崇高なものであったとしても、独裁体制を破壊するために必要な人々の恐怖心と服従の習慣を克服するには不十分な場合が多い。悲しいことに、そのような行為は、勝利や希望どころか、かえって苦しみと死を増大させるだけだったかもしれない。
暴力による自由?
このような状況で何ができるのだろうか。明らかな可能性は役に立たないように思える。憲法や法律の壁、司法判断、世論などは独裁者にとっては無視されるのが普通である。当然ながら、残忍な行為、拷問、失踪、殺人に反応し、人々はしばしば、暴力だけが独裁を終わらせることができると結論づけた。怒った犠牲者たちは、不利な状況にもかかわらず、自分たちのできる限りの暴力と軍事力で残忍な独裁者に対抗しようと組織することもあった。これらの人々はしばしば、苦しみと命という大きな犠牲を払って勇敢に戦ってきた。彼らの功績は時に目覚しいものがあるが、自由を勝ち取ったことはほとんどない。暴力的な反乱は残忍な弾圧を引き起こし、民衆を以前より無力にすることがしばしばある。
しかし、暴力的な選択肢のぜひはともかく、1つだけはっきりしていることがある。暴力的な手段を信頼することは、抑圧者がほぼ常に優位に立つタイプの闘争を選択することになるのだ。独裁者たちは、圧倒的に暴力を行使する能力を備えている。このような民主主義がどんなに長く、あるいは短期間に続けられたとしても、最終的には厳しい軍事的現実から逃れられなくなるのが普通である。独裁者は、ほとんどの場合、軍備、弾薬、輸送、軍備の規模において優位に立っている。勇敢にも、民主主義者たちは(ほとんど)敵わない。
従来の軍事的反抗が非現実的であると認識される場合、反体制派の中にはゲリラ戦を支持する者もいる。しかし、ゲリラ戦が抑圧された住民に利益をもたらし、民主主義を実現することは、たとえあったとしても、ほとんどない。ゲリラ戦は、特に、自国民の犠牲が膨大になる傾向が非常に強いことを考えると、明白な解決策ではない。この技術は、理論や戦略的分析の裏付けがあり、時には国際的な裏付けがあるにもかかわらず、失敗に対する保証にはならない。ゲリラ闘争はしばしば非常に長く続く。一般市民はしばしば支配者である政府に追いやられ、甚大な人的被害と社会的混乱に見舞われる。
ゲリラ闘争が成功した場合でも、長期的に構造的に重大な負の影響を及ぼすことが多い。即座に、攻撃された政権はその対抗措置の結果、より独裁的になる。ゲリラが最終的に成功した場合、拡大した軍事力による中央集権的影響と、民主主義社会の確立と維持に不可欠な社会の独立団体・機関の闘争による弱体化・破壊によって、結果として新体制は前体制より独裁的になることが多い。独裁政権に敵対する人々は、別の選択肢を探すべきである。
クーデター、選挙、外国の救世主?
独裁政権に対する軍事クーデターは、特に好ましくない政権を排除するための最も簡単で迅速な方法の1つに見えるかもしれない。しかし、その手法には非常に重大な問題がある。最も重要なことは、政府と軍隊を支配するエリート層と住民の間に存在する権力の偏在をそのままにしておくことである。特定の人物や徒党を統治する立場から排除することは、ほとんどの場合、別のグループがその座につくことを可能にするだけである。理論的には、この集団は行動が温和になり、民主的な改革に対して限定的にオープンだろうかもしれない。しかし、その逆のケースもあり得る。
新しい徒党は、その地位を固めた後、古い徒党よりも冷酷で、より野心的であることが判明するかもしれない。その結果、新しい徒党は-希望を託されたかもしれないが-民主主義や人権を気にすることなく、やりたい放題になるであろう。それは、独裁の問題に対する答えとしては容認できない。
独裁政権の下では、重要な政治的変化の手段として選挙を利用することはできない。旧ソ連が支配した東欧圏の独裁政権のように、民主的だろうかのように見せかけるために、選挙を行った政権もある。しかし、そのような選挙は、独裁者が選んだ候補者を国民が支持するために、厳格に管理された国民投票に過ぎなかった。圧力を受けた独裁者は、時には新しい選挙に同意することもあるが、その後、民間の傀儡を政府の役職に就かせるために選挙を不正に操作することもある。1990年のビルマや1993年のナイジェリアのように、反対派の候補者の出馬が認められ、実際に当選した場合、結果は単に無視され、「勝者」は脅迫、逮捕、処刑にさらされるかもしれない。独裁者たちは、自分たちを王座から引きずり下ろす可能性のある選挙を許可するような商売はしていない。
現在、残忍な独裁政権の下で苦しんでいる人々、あるいはその直接的な支配から逃れるために亡命した人々の多くは、抑圧された人々が自らを解放できるとは考えていない。彼らは、自分たちの国民は他人の行為によってしか救われないと期待している。このような人々は、外部の力に信頼を置いている。彼らは、国際的な援助だけが独裁者を倒すのに十分な力を発揮できると信じている。
抑圧された人々が効果的に行動できないという見方は、ある期間においては正確であることもある。前述のように、しばしば抑圧された人々は、冷酷な独裁者に立ち向かう自信もなく、自分たちを救う方法も知られていないため、闘う気がなく、一時的に闘うことができないのである。したがって、多くの人が解放への希望を他者に託すのは理解できる。その外部の力とは、「世論」であったり、「国連」であったり、「特定の国」であったり、「国際的な経済・政治制裁」であったりする。
しかし、このように外部の救世主に頼ることには、重大な問題がある。このような自信は、全く見当違いかもしれない。通常、外国の救世主は来ないし、もし外国が介入してきたとしても、おそらく信用してはならない。
外国の介入に依存することに関するいくつかの厳しい現実をここで強調する必要がある。
- しばしば外国は、自国の経済的、政治的利益を高めるために独裁政権を容認し、積極的に援助することさえある。
- 外国はまた、別の目的を犠牲にしてでも、抑圧された人々の解放を支援するという誓約を守る代わりに、喜んでその人々を売り渡すかもしれない。
- 一部の外国は、自国の経済的、政治的、軍事的支配を得るためだけに、独裁政権に反対する行動をとる。
- 外国が積極的に関与するのは、国内のレジスタンス運動がすでに独裁政権を揺るがし始め、それによって政権の残忍な性質に国際的な関心が向けられた場合に限られる。
独裁体制は通常、主に自国内の権力分布のために存在する。独裁政権が深刻な問題を引き起こすには、国民と社会があまりにも弱く、富と権力があまりにも少数の手に集中している。独裁体制は、国際的な行動によって恩恵を受けたり、多少弱まったりすることはあっても、その継続は主として内的要因に依存している。
しかし、国際的な圧力は、それが強力な内部レジスタンス運動を支えている場合には、非常に有効である。例えば、国際的な経済ボイコット、禁輸、国交断絶、国際機関からの追放、国連機関による非難などは、大きな助けとなる可能性がある。しかし、内部でのレジスタンス運動が強くない限り、こうした他者による行動は起こりにくい。
厳しい現実を直視する
結論は難しい。独裁政権を最も効果的に、最小のコストで崩壊させようとする場合、4つの課題がある。
- 抑圧された人々自身の決意、自信、抵抗の技術を強化しなければならない。
- 抑圧された人々の独立した社会集団と組織を強化しなければならない。
- 強力な内部抵抗勢力を作り出さなければならない。
- 解放のための賢明な大戦略計画を立て、それを巧みに実行に移さなければならない。
解放闘争は、闘争集団の自立と内部強化のための時間である。チャールズ・スチュワート・パーネルが1879年と1880年のアイルランド家賃ストライキキャンペーンで呼びかけたように。
政府に頼っても無駄だ……自分たちの決意に頼るしかない……共に立ち上がることで自らを助け、自分たちの中の弱い者を強化し、自分たちを束ね、組織し……、必ず勝つ……この問題を解決のために熟したとき、そのときに初めて解決される」4
強い自立した勢力に対して、賢明な戦略、規律ある勇気ある行動、真の強さが与えられれば、独裁体制はやがて崩れ去るだろう。しかし、最低限、上記の4つの要件が満たされていなければならない。
以上の議論が示すように、独裁からの解放は、最終的には人民の自力によるものである。先に挙げた政治的反抗、すなわち政治的目的のための非暴力闘争の成功例は、民衆が自らを解放するための手段が存在することを示しているが、その選択肢は未発達なままである。この選択肢については、次の章で詳しく検討する。しかし、その前に、独裁政権を解体する手段としての交渉の問題を見ておく必要がある。
第2章 交渉の危険性
第1章で調査したように、独裁政権と対峙する際の深刻な問題に直面したとき、ある人々は、受動的な服従に陥るかもしれない。また、民主主義が実現する見込みがないと判断し、「和解」「妥協」を通じて、明らかに永続的な独裁体制と折り合いをつけるしかないと考える人もいるだろう。「和解」「妥協」「交渉」を通じて、何らかの前向きな要素を救い出し、残忍な行為を終わらせることができるかもしれない、と期待している。表面的には、現実的な選択肢を欠いたその考え方に魅力がある。
残忍な独裁政権と真剣に闘うことは、決して楽しいことではない。なぜ、そんなことをしなければならないのか。誰もが理性的になり、話し合い、独裁を徐々に終わらせる方法を交渉する方法を見つけることはできないのだろうか。民主主義者たちは独裁者たちの人間としての共通感覚に訴え、彼らの支配を少しずつ減らしていき、最後には民主主義の確立に完全に道を譲るように説得できないのだろうか?
真実は一方にあるのではない、と言われることがある。民主主義者たちは独裁者たちを誤解しているのではないか、独裁者たちは困難な状況の中で善意から行動しているのではないか。あるいは、独裁者たちは、励ましと誘惑さえあれば、国が直面している困難な状況から喜んで脱するだろうと考える人もいるかもしれない。独裁者たちに、誰もが得をする「ウィン・ウィン」の解決策を提示することができるのではないか、と言うのである。民主的な野党が交渉によって平和的に紛争を解決しようとするだけなら、さらなる闘争のリスクや苦痛は必要ないと言えるかもしれない(熟練した人物や別の政府によって支援される可能性すらある)。その方が、たとえ軍事戦争ではなく非暴力闘争によって行われるものであっても、困難な闘争より望ましいのではないだろうか。
交渉のメリットと限界
交渉は、紛争におけるある種の問題を解決する上で非常に有用な手段であり、それが適切である場合には軽視したり拒否したりすべきではない。
根本的な問題がなく、したがって妥協が受け入れられるような状況では、交渉は紛争を解決するための重要な手段となり得る。賃上げを求める労働争議は、紛争における交渉の適切な役割を示す良い例である。交渉による解決は、争う側のそれぞれが当初提案した金額の中間のどこかで増額を提供することができる。しかし、合法的な労働組合をめぐる紛争は、残酷な独裁政権の存続や政治的自由の確立をめぐる紛争とは全く異なるものである。
宗教上の原則、人間の自由の問題、あるいは社会の将来の発展全体にかかわる基本的な問題である場合、交渉によって相互に満足のいく解決に到達する方法はない。いくつかの基本的な問題については、妥協があってはならない。民主主義者に有利な力関係の転換のみが、問題となる基本的な問題を適切に保護することができる。そのような転換は、交渉ではなく、闘争を通じて行われるであろう。交渉は絶対にやってはいけないというのではない。ここで言いたいのは、強力な民主的反対勢力が存在しない場合、交渉は強力な独裁政権を排除する現実的な方法ではないということである。
もちろん、交渉はまったく選択肢になりえないかもしれない。自分の地位に安住している強固な独裁者は、民主的な反対勢力との交渉を拒むかもしれない。あるいは、交渉が始まっても、民主的な交渉相手が姿を消し、二度と連絡が取れなくなる可能性もある。
交渉による降伏?
独裁政治に反対し、交渉に賛成する個人や団体は、多くの場合、善良な動機を持っていることだろう。特に、残忍な独裁政権に対して最終的な勝利を得ることなく何年も軍事闘争を続けてきた場合、どんな政治的説得力を持った人であれ、すべての国民が平和を望むのは理解できることである。特に、独裁者が明らかに軍事的に優位に立ち、自国民の破壊と死傷にもはや耐えられない場合、民主主義者の間で交渉が問題となる可能性が高い。そうなると、暴力と反暴力の連鎖に終止符を打ちつつ、民主主義者の目的をある程度達成できるかもしれない他のルートを探りたいという強い誘惑に駆られることになる。
独裁者が民主的野党との交渉を通じて「平和」を提案することは、もちろん、かなり不誠実なものである。暴力は、独裁者自身が自国民への戦争をやめさえすれば、直ちに終わらせることができる。彼らは交渉なしで自分たちの主導で、人間の尊厳と権利の尊重を回復し、政治犯を解放し、拷問をやめ、軍事行動を停止し、政府から撤退し、国民に謝罪することができる。
独裁体制は強力だが、苛立たしい抵抗勢力が存在する場合、独裁者は「平和」を作るという名目で、反対勢力と交渉して降伏させることを望むかもしれない。交渉の呼びかけは魅力的に聞こえるかもしれないが、交渉の場には重大な危険が潜んでいる可能性がある。
一方、反対勢力が極めて強く、独裁体制が真に脅かされている場合、独裁者は自分たちの支配力や富をできるだけ多く救うために交渉を求めるかもしれない。いずれの場合も、民主主義者は独裁者の目標達成を助けてはならない。
民主党は、独裁者が交渉のプロセスに意図的に仕掛けるかもしれない罠に注意しなければならない。政治的自由の基本的な問題が絡んでいるときに交渉を求めるのは、独裁者の暴力が続く一方で、民主主義者が平和的に降伏するように仕向けるための努力かもしれないのである。このようなタイプの紛争では、交渉の唯一の適切な役割は、独裁者の権力が効果的に破壊され、彼らが国際空港への個人的な安全通路を求める決定的な闘争の終わりに発生する可能性がある。
交渉における権力と正義
この判断が交渉に対するあまりに厳しいコメントに聞こえるなら、おそらく交渉に関連するロマンティシズムはいくらか控えめにする必要があるのだろう。交渉がどのように行われるかについて、明確な思考が必要である。
「交渉とは、両者が対等な立場で話し合い、対立の原因となった相違点を解決することを意味しない。二つの事実を覚えておかなければならない。第一に、交渉において、交渉による合意の内容を決定するのは、対立する見解や目的の相対的な公正さではないことである。第二に、交渉による合意の内容は、それぞれの側の力量によって大きく左右される」
いくつかの難しい問題を考慮しなければならない。もし相手側が交渉の席で合意に至らなかった場合、各側は後日、その目的を達成するために何ができるのか。合意が成立した後、相手側が約束を破り、合意にもかかわらず、利用可能な戦力を使って目的を奪取した場合、各側は何ができるのか?
交渉の場では、争点となる問題のぜひを評価することで和解が成立するわけではない。それらは大いに議論されるかもしれないが、交渉における真の成果は、対立するグループの絶対的、相対的な力の状況の評価から生まれる。民主主義者は、自分たちの最低限の主張を否定されないようにするために何ができるのか。独裁者は、民主主義者を無力化し、支配力を維持するために何ができるのか。つまり、合意が成立するとすれば、それは両者の力量を比較し、オープンな闘争がどのように終わるかを計算した結果である可能性が高い。
また、合意に至るために、それぞれが何をあきらめるかということにも注意を払わなければならない。交渉が成功した場合、妥協、つまり相違点の分割が行われる。それぞれの側が望むものの一部を手に入れ、目的の一部をあきらめる。
極端な独裁政権の場合、民主化推進勢力は独裁者に何を譲ればいいのだろうか。独裁者のどのような目的を民主化推進派は受け入れるべきなのだろうか?民主主義者は、独裁者(政党であれ、軍部の陰謀であれ)に、将来の政府における憲法で定められた永続的な役割を与えなければならないのだろうか?それのどこに民主主義があるのだろうか?
交渉がすべてうまくいったと仮定しても、その結果、どのような平和がもたらされるのかを問う必要がある。その結果、民主主義者が闘争を始めた場合、あるいは続けた場合よりも、生活は良くなるのだろうか、それとも悪くなるのだろうか?
「合意できる」独裁者
独裁者は、権力、地位、富、社会の再構築など、さまざまな動機と目的をもって支配に臨むことができる。しかし、彼らが支配的な立場を放棄すれば、これらのどれもが果たされないことを忘れてはならない。交渉の場では、独裁者は自分たちの目標を維持しようとする。
独裁者が交渉でどのような約束をしようとも、独裁者は民主的敵対者から服従を得るために何でも約束し、その約束を堂々と破る可能性があることを、誰も忘れてはならない。
もし民主主義者が、弾圧から解放されるために抵抗を止めることに同意するならば、彼らは非常に失望することになるかもしれない。抵抗の停止が弾圧の軽減をもたらすことはほとんどない。いったん内外の反対運動という抑制力がなくなると、独裁者は抑圧と暴力を以前より残忍なものにする可能性さえある。民衆の抵抗の崩壊は、しばしば独裁者の支配と残忍性を制限してきた対抗力を取り除く。そうなれば、暴君は誰に対しても前進することができる。「暴君は、私たちが抵抗する力を欠いているものだけを与える力を持っているからだ」とクリシュナラル・シュリダラニが書いている5。
根本的な問題が絡む紛争を変えるためには、交渉ではなく、抵抗が不可欠である。ほとんどすべての場合において、独裁者を権力から追い出すために抵抗を続けなければならない。成功の鍵は、和解の交渉ではなく、最も適切で強力な抵抗の手段を賢く利用することにある。後ほど詳しく説明するが、政治的反抗、すなわち非暴力闘争は、自由を求めて闘う人々が利用できる最も強力な手段である、というのが私たちの主張である。
どのような平和か?
もし独裁者と民主主義者が平和について全く話さないのであれば、極めて明確な思考が必要である。なぜなら、そこには危険が伴うからだ。「平和」という言葉を使う人のすべてが、自由と正義のある平和を望んでいるわけではない。残酷な抑圧に服従し、何十万人もの人々に残虐行為を働いた冷酷な独裁者に受動的に黙認することは、真の平和とは言えない。ヒトラーはしばしば平和を訴えたが、それは彼の意志への服従を意味した。独裁者の平和は、しばしば牢獄や墓場の平和以上のものではない。
危険はほかにもある。善意の交渉者は時として、交渉の目的と交渉プロセスそのものを混同してしまう。また、民主的な交渉人、あるいは交渉支援のために受け入れた外国の交渉専門家が、国家の掌握、人権侵害、残虐行為によってそれまで否定されてきた国内外の正当性を独裁者に一挙に与えてしまうこともある。この正当性がなければ、独裁者はいつまでも支配を続けることはできない。平和の推進者は、彼らに正統性を与えてはならない。
希望の理由
前述したように、野党指導者は民主化闘争の絶望感から交渉を進めざるを得ないと感じているかもしれない。しかし、そのような無力感は変えることができる。独裁体制は永久に続くものではない。独裁者の下で暮らす人々は弱いままでいる必要はなく、独裁者がいつまでも強力であることを許す必要はない。アリストテレスは昔、「…王政と専制は他のどの憲法よりも短命である…丸い専制国家は長くは続かない」と述べている(6)。その弱点は悪化し、独裁者の権力は崩壊する可能性がある。(第4章では、これらの弱点についてより詳細に検討する)。
最近の歴史は、独裁者の脆弱性を示しており、独裁者が比較的短い期間で崩壊することを明らかにしている。ポーランドでは共産党独裁政権を崩壊させるのに10年(1980-1990)必要だったが、東ドイツとチェコスロヴァキアでは1989年に数週間でそれが起こった。1944年のエルサルバドルとグアテマラでは、定着した残忍な軍事独裁者に対する闘争は、それぞれ約2週間を要した。イランでは、軍事的に強力な国王の政権が数ヶ月で崩壊した。フィリピンのマルコス独裁政権は1986年に数週間で民衆の力の前に倒れた。反対勢力の強さが明らかになると、アメリカ政府はすぐにマルコス大統領を見捨てた。1991年8月にソビエト連邦で起きた強硬クーデターは、政治的反抗によって数日で阻止された。その後、長い間支配されていた多くの構成国が、わずか数日、数週間、数ヶ月で独立を取り戻した。
暴力的手段は常に即効性があり、非暴力的手段は常に膨大な時間を要するという古い先入観は、明らかに妥当ではない。根本的な状況や社会の変化には多くの時間を要するかもしれないが、独裁政権に対する実際の闘いは、非暴力的な闘いによって比較的早く起こることもある。
交渉は、一方では殲滅、他方では降伏という戦争を続けることに対する唯一の代替手段ではない。今挙げた例や第1章で挙げた例は、平和と自由の両方を望む人々にとって、政治的反抗という別の選択肢が存在することを物語っている。
第3章 権力はどこから来るのか?
自由と平和を両立させる社会を実現することは、もちろん簡単なことではない。戦略的な技術、組織、計画が必要である。そして何よりも、権力が必要である。民主党は、自らの権力を効果的に行使する能力なしに、独裁政権を崩壊させ、政治的自由を確立することは望めない。
しかし、どのようにしてそれが可能になるのだろうか。独裁政権とその巨大な軍事・警察網を破壊するのに十分な、民主的野党の動員可能なパワーとはどのようなものだろうか。その答えは、これまで無視されてきた政治権力についての理解にある。この洞察を学ぶことは、実はそれほど難しい作業ではない。いくつかの基本的な真理は非常に単純である。
「猿の親分」の寓話
例えば、14世紀の中国の劉基の寓話は、この無視されがちな政治権力に関する理解の概要をよく表している7。
封建国家である楚で、ある老人が猿を飼うことで生き延びていた。朱の人々は老人を「朱公」(猿の親分)と呼んだ。
毎朝、老人は中庭に猿を集め、長男に命じて他の猿を山に連れて行き、藪や木から果物を採らせた。そして、その収穫の10分の1を老人に渡すという決まりがあった。これを怠ると鞭で打たれるのだ。猿は皆、苦しくても文句は言わなかった。
ある日、一匹の小猿が他の猿に尋ねた。「老人は果物の木や茂みを全部植えたのか?」
すると、他の猿たちは 「いや、自然に生えたんだ」
小猿はさらに尋ねた「老人の許しなしに果実を取ってはいけないのか?」
他の猿たちは答えた「いや、みんなとることができるさ」
小猿は続けた「それなら、なぜ老人に仕えなければならないんだ?」
小猿が言い終わらないうちに、すべての猿がハッと悟り、目を覚ました。
その日の夜、老人が寝静まったのを見て、猿たちは自分たちが閉じ込められていた柵をすべて壊し、柵を完全に破壊してしまった。さらに、老人が蓄えていた果物も奪って、すべて森へ持って行き、そのまま帰って来なくなった。老人はついに餓死してしまった。
Yu-li-zi 曰く、「世の中には、正義ではなく、策略で民を支配する者がいる。猿の親分と同じではないか。彼らは自分の頭の悪さを自覚していない。民衆が悟りを開くと、彼らの策略はもはや通用しなくなる」
政治力の必要な源泉
原理は簡単だ。独裁者は、支配する人民の援助を必要とし、それがなければ政治権力の源泉を確保し維持することはできない。政治的権力の源泉には次のようなものがある。
- 権威:体制が正当であり、それに従う道徳的義務があると民衆が信じること。
- 人的資源:支配者に従順で、協力的で、援助的な人物や集団の数と重要性。
- スキルや知識:政権が特定の行動をとるために必要とし、協力する人物や集団が提供するもの。
- 無形的要素:人々を支配者に従わせ、援助させる心理的・思想的な要素。
- 物質的資源:支配者が財産、天然資源、金融資源、経済システム、通信・輸送手段をどの程度まで支配・利用できるかの度合い、および
- 制裁:体制が存在し、政策を遂行するために必要な服従と協力を確保するために、不従順な者や非協力的な者に対して、脅したり、適用したりする処罰のことである。
しかし、これらすべての源泉は、政権の受容、住民の服従、無数の人々や社会の多くの機関の協力に依存している。これらは保証されていない。
全面的な協力、服従、支持は、必要な動力源の利用可能性を高め、その結果、いかなる政府の権力能力も拡大させることになる。
一方、侵略者や独裁者に対する民衆や組織の協力がなくなると、すべての支配者が依存する力の源の利用可能性が低下し、断ち切られる可能性がある。このような力の源泉を利用できなければ、支配者の力は弱まり、最後には消滅してしまう。
当然ながら、独裁者は自分たちの能力を脅かすような行動や考えには敏感である。従って、独裁者は、従わない者、ストライキをする者、協力しない者を脅し、罰する可能性が高い。しかし、それで終わりではない。抑圧は、たとえ残虐であっても、体制が機能するために必要な服従と協力の度合いを再開させるとは限らない。
抑圧にもかかわらず、権力の源泉を十分な時間にわたって制限または切断することができれば、最初の結果は、独裁政権内の不確実性と混乱になるかもしれない。その後、独裁者の力が明らかに弱まる可能性が高い。時間の経過とともに、権力の源泉の差し止めは、政権の麻痺と無力化をもたらし、ひどい場合には、その崩壊をもたらす。独裁者の権力は、ゆっくりと、あるいは急速に、政治的飢餓から死んでいくだろう。
どのような政府においても、自由や専制の程度は、臣民の自由であろうとする相対的な決意と、臣民を奴隷にしようとする努力に抵抗する意志と能力を大きく反映するものであるということになる。
一般的な意見とは異なり、全体主義的な独裁者であっても、その支配する人口や社会に依存している。政治学者のカール・W・ドイチュが1953年に指摘したように。
全体主義的権力は、それがあまり頻繁に使用される必要がない場合にのみ強力である。もし、全体主義的な権力が、常に全人口に対して行使されなければならないのであれば、その権力が長く続くことはないだろう。全体主義体制は、他のタイプの政府よりも臣民を扱うのに多くの権力を必要とするため、そのような体制は、国民の間に広く、信頼できる遵守習慣を必要とし、さらに、必要な場合には、少なくとも国民のかなりの部分からの積極的支援を当てにできなければならない8。
19世紀の英国の法学者ジョン・オースティンは、不満を抱く国民に直面する独裁者の状況を説明した。オースティンは、国民の大半が政府を破壊することを決意し、そのために弾圧に耐えることをいとわないとすれば、政府を支持する者を含む政府の力は、たとえ外国の援助を受けても、憎まれた政府を維持することはできない、と主張した。反抗的な国民を永久に従順と服従に押し戻すことはできない、とオースティンは結論づけた9。
ニッコロ・マキャベリはずっと以前に、「…大衆を全体として敵とする王子は、決して自分を安泰にすることはできず、その残虐性が大きければ大きいほど、その政権は弱くなる」10と主張していた。
これらの洞察が実際に政治的に応用されたのは、ナチスの占領に抵抗した英雄的なノルウェー人、そして第1章で引用したように、共産主義の侵略と独裁に抵抗し、ついにヨーロッパでの共産主義支配の崩壊に貢献した勇敢なポーランド人、ドイツ人、チェコ人、スロバキア人やその他の多くの人々によって実証されている。もちろん、これは新しい現象ではない。非暴力による抵抗の例は、少なくとも紀元前494年、平民がローマの貴族たちの主人から協力を取りやめたときにまで遡る11。非暴力による闘いは、ヨーロッパだけでなく、アジア、アフリカ、アメリカ、オーストラリア、太平洋諸島の各地で、人々によって様々な時期に採用されてきた。
したがって、政府の権力をどの程度まで制御するか、あるいは制御しないかを決定する最も重要な要因は、次の3つである。(1)政府の権力に制限を加えようとする民衆の相対的欲求、(2) 権力の源泉を一括して排除しようとする臣民の独立組織や制度の相対的強さ、(3) 同意や援助を差し控える民衆の相対的能力である。
民主的権力の中心
民主主義社会の特徴の一つは、国家から独立した多数の非政府組織や団体が存在することである。例えば、家族、宗教団体、文化団体、スポーツクラブ、経済団体、労働組合、学生会、政党、村、町内会、園芸クラブ、人権団体、音楽グループ、文学会などである。これらの団体は、自らの目的を果たすとともに、社会のニーズを満たすためにも重要である。
さらに、これらの団体は大きな政治的意義を持っている。人々が社会の方向性に影響力を行使し、他のグループや政府が自分たちの利益、活動、目的を不当に侵害すると見なされたときに抵抗するための集団的、制度的基盤を提供している。このような集団の一員ではない孤立した個人は、通常、社会の他の部分に大きな影響を与えることができず、ましてや政府、ましてや独裁国家に影響を与えることはできない。
その結果、そのような機関の自律性と自由を独裁者が奪うことができれば、国民は相対的に無力となる。また、これらの機関自体が中央政権によって独裁的にコントロールされたり、新たにコントロールされたものに置き換えられたりすれば、個々の構成員と社会のそれらの領域の両方を支配するために利用される可能性がある。
しかし、もしこれらの独立した市民組織(政府のコントロールの外にある)の自律性と自由を維持または回復することができれば、政治的反抗の適用にとって非常に重要である。独裁体制が崩壊または弱体化した引用例の共通の特徴は、国民とその機関による勇気ある大衆的な政治的反抗の適用であった。
このように、権力の中心は、国民が圧力をかけたり、独裁的な支配に抵抗したりするための制度的な基盤を提供する。将来的には、自由な社会にとって不可欠な構造的基盤の一部となるであろう。したがって、その独立と成長の継続は、しばしば解放闘争の成功のための前提条件となる。
もし独裁政権が社会の独立した組織を破壊するか統制することに大きく成功したならば、抵抗勢力にとって、新しい独立した社会集団や組織を作り出すこと、あるいは生き残った組織や部分的に統制された組織に再び民主的統制を与えることが重要になるであろう。1956年から1957年にかけてのハンガリー革命では、多数の直接民主主義評議会が出現し、数週間にわたって連合体としての制度と統治を確立するために結合することさえあった。ポーランドでは、1980年代後半に労働者が非合法の連帯組合を維持し、場合によっては共産党が支配する公式の労働組合の統制を引き継いだ。このような制度的発展は、非常に重要な政治的帰結をもたらす可能性がある。
もちろん、独裁体制を弱体化させ、破壊することが容易であることを意味するものではないし、すべての試みが成功することを意味するものでもない。なぜなら、独裁者に仕える人々は、民衆に協力と服従を再開させるために反撃に出る可能性が高いからだ。
しかし、上記の権力に関する洞察は、独裁体制を意図的に崩壊させることが可能であることを意味している。特に独裁国家は、巧みな政治的反抗に対して非常に脆弱な特殊性を持っている。その特徴をもう少し詳しく見てみよう。
続きは購入した方のみアクセスできます。
第9章の冒頭 大文字Tから始まり大文字Dで終わるスペース、ハイフンを含む39文字のセンテンス
付録 非暴力行動の方法
非暴力による抗議と説得の方法
正式な声明
- 1.スピーチ
- 2.反対・支持の書簡
- 3.団体・組織による宣言
- 4.署名入りの公文書
- 5.起訴状や意思表示
- 6.団体または集団による請願書
より多くの人々とのコミュニケーション
- 7.スローガン、風刺画、およびシンボル
- 8.バナー、ポスター、掲示物
- 9.リーフレット、パンフレット、書籍
- 10.新聞、雑誌
- 11.レコード、ラジオ、テレビ
- 12.スカイライティング、アースライティング
団体代表
- 13.代理人
- 14.模擬表彰
- 15.団体ロビー活動
- 16.ピケッティング
- 17.模擬選挙
象徴的な公的行為
- 18.国旗・シンボルカラーの掲揚
- 19.シンボルの着用
- 20.祈り・礼拝
- 21.象徴的な物の運搬
- 22.抗議行動
- 23.所有物の破壊
- 24.シンボルライト
- 25.肖像画の展示
- 26.抗議としてのペイント
- 27.新しいサインと名前
- 28.象徴的な音
- 29.シンボリックな再生
- 30.無礼なジェスチャー
個人への圧力
- 31.役人に取り憑く
- 32.役人を挑発する
- 33.友好的な関係
- 34.前夜祭
演劇・音楽
- 35.ユーモラスな寸劇や悪ふざけ
- 36.演劇・音楽の上演
- 37.歌唱
行列
- 38.行進
- 39.パレード
- 40.宗教的な行進
- 41.巡礼
- 42.モータースケード
死者を悼む
- 43.政治的喪に服す
- 44.模擬葬儀
- 45.見せしめ的な葬儀
- 46.埋葬地でのオマージュ
公的集会
- 47.抗議または支援のための集会
- 48.抗議集会
- 49.カモフラージュされた抗議集会
- 50.ティーチイン
撤退・放棄
- 51.ウォークアウト
- 52.サイレンス
- 53.名誉の放棄
- 54.背を向ける
社会的不協力の方法
人の排斥
- 55.社会的ボイコット
- 56.選択的社会的ボイコット
- 57.リシスト制不行動
- 58.破門
- 59.インターディクト
社会的行事、慣習、制度への非協力
- 60.社会活動・スポーツ活動の停止
- 61.社会活動のボイコット
- 62.学生ストライキ
- 63.社会的不服従
- 64.社会制度からの離脱
- 63.社会制度からの離脱(Withdrawal from the social system
- 65.家庭内引きこもり
- 66.全面的個人非協力
- 67.労働者の逃亡
- 68.サンクチュアリ
- 69.集団的失踪
- 70.抗議移住(ヒジュラート)
経済的非協力の方法
(1)経済ボイコット
消費者による行動
- 71.消費者のボイコット
- 72.ボイコットされた商品の不消費
- 73.緊縮財政政策
- 74.家賃の不払い
- 75.賃貸拒否
- 76.国内消費者ボイコット
- 77.国際的な消費者ボイコット
労働者・生産者の行動
- 78.労働者ボイコット
- 79.生産者ボイコット
中間業者による行動
- 80.仕入先・問屋ボイコット
オーナー、経営者の行動
- 81.商人ボイコット
- 82.物件の賃貸・売却拒否
- 83.ロックアウト
- 84.産業援助の拒否
- 85.商人によるゼネスト
金融資源保有者の行動
- 86.銀行預金の払い戻し
- 87.手数料、会費、賦課金の支払い拒否
- 88.債務または利息の支払い拒否
- 89.資金・信用の断絶
- 90.収入拒絶
- 91.政府貨幣の拒否
政府による措置
- 92.国内禁輸
- 93.貿易業者のブラックリスト化
- 94.国際的な売り手側からの禁輸措置
- 95.国際的な買い手の禁輸措置
- 96.国際貿易禁止令
経済的非協力の方法
(2) ストライキ
シンボリックストライキ
- 97.プロテスト・ストライキ
- 98.クイック・ウォークアウト(落雷)
農民ストライキ
- 99.農民ストライキ
- 100.農業労働者ストライキ
特殊な集団によるストライキ
- 101.強制労働の拒否
- 102.囚人ストライキ
- 103.工芸品ストライキ
- 104.専門職ストライキ
通常の産業別ストライキ
- 105.事業所ストライキ
- 106.産業別ストライキ
- 107.同情的ストライキ
制限付きストライキ
- 108.詳細ストライキ
- 109.Bumperストライキ
- 110.スローダウンストライキ
- 111.ワーキング・トゥ・ルール・ストライキ
- 112.病欠報告(シックイン)
- 113.辞職によるストライキ
- 114.限定ストライキ
- 115.選択的ストライキ
- 116.多業種ストライキ
- 116.ゼネリックストライキ
- 117.ゼネスト
ストライキと経済封鎖の組み合わせ
- 118.ハルタル
- 119.経済封鎖
政治的非協力の方法
権力に対する拒絶
- 120.忠誠の差し控え、撤回
- 121.公的支援拒否
- 122.抵抗を主張する文学・演説
市民の政府への非協力
- 123.立法府のボイコット
- 124.選挙のボイコット
- 125.政府の雇用・役職のボイコット
- 126.政府の部局、機関、その他の組織に対するボイコット
- 127.政府系教育機関からの離脱
- 128.政府支援組織のボイコット
- 129.強制捜査機関への援助拒否
- 130.自国の看板・標識の撤去
- 131.任命された官吏の受諾拒否
- 132.既存機関の解散拒否
服従に代わる市民の選択肢
- 133.不本意な服従、遅い服従
- 134.直接の監視がない場合の不服従
- 135.大衆的不服従
- 136.見せかけの不服従
- 137.集合・集会の解散拒否
- 138.座り込み
- 139.徴兵・強制送還への非協力
- 140.隠れる、逃げる、身分を偽る
- 141.非合法な法律への民事不服従
- 142.政府関係者による行動
- 142.政府側近の選択的援助拒否
- 143.指揮系統・情報系統の遮断
- 144.時間稼ぎ・妨害
- 145.一般行政非協力
- 146.司法非協力
- 147.執行機関の意図的な非効率・選択的非協力
- 148.反乱
国内での政府行動
- 149.準法規的回避・遅延
- 150.政府構成単位の非協力
国際的な政府の行動
- 151.外交官やその他の代表の交代
- 152.外交行事の遅延・中止
- 153.外交上の承認保留
- 154.国交断絶
- 155.国際機関からの脱退
- 156.国際機関への加入拒否
- 157.国際機関からの除名
非暴力による介入の方法
心理的介入
- 158.風雨への自己暴露
- 159.断食
(a)道徳的圧力の断食
(b)ハンガー・ストライキ
(c)サティヤグラフィック断食
- 160.逆転裁判
- 161.非暴力的な嫌がらせ
- 162.物理的介入
- 162.座り込み
- 163.スタンドイン
- 164.ライドイン
- 165.ウェイドイン
- 166.ミルイン
- 167.プレイイン
- 168. 非暴力による空襲
- 169.非暴力空襲(Non-violent air raids)
- 170.非暴力的侵攻
- 171.非暴力的妨害(Non-violent interjection)
- 172.非暴力的妨害(Non-violent obstruction)
- 173.非暴力的占領(Non-violent occupation)
社会的介入
- 174.新たな社会的パターンの構築
- 175.施設の過負荷
- 176.ストールイン
- 177.スピークイン
- 178.ゲリラ劇場
- 179.代替的社会制度
- 180.代替コミュニケーションシステム
経済的介入
- 181.逆ストライキ
- 182.滞在型ストライキ
- 183.非暴力的土地収用
- 184.封鎖への反抗
- 185.政治的動機による模造品製造
- 186.先買い
- 187.資産の差し押さえ
- 188.ダンピング
- 189.選択的庇護
- 190.代替市場
- 191. 191.代替輸送システム
- 192.代替経済制度
政治的介入
- 193.行政システムの過負荷
- 194.秘密工作員の身元公開
- 195.投獄を求める
- 196.中立的な法律への民事不服従
- 197.協調なきワークオン
- 198.二重主権と並行政府