Contents
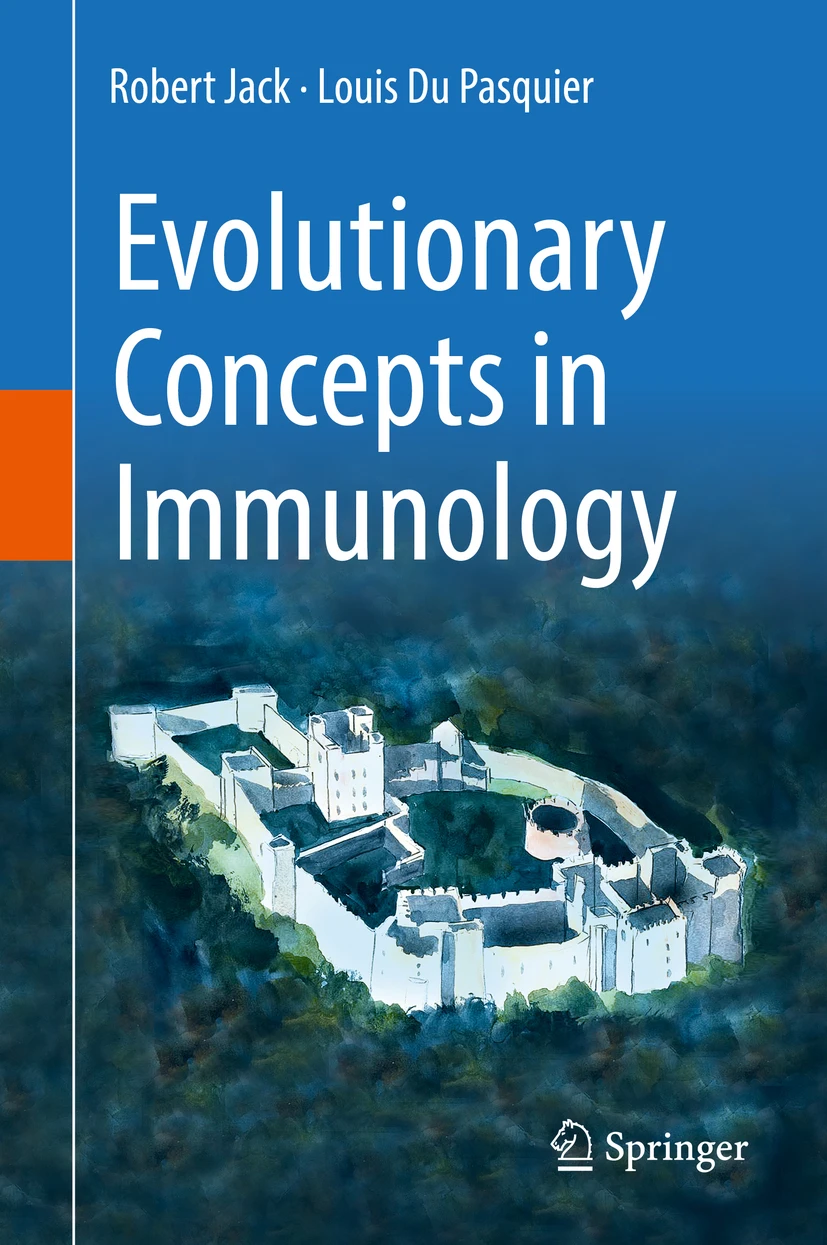
ロバート・ジャックとルイ・デュ・パスキエ免疫学の進化論的概念
1st ed(June 14,2019);Springer Nature Switzerland AG;145 pages(hardcover)
Danka Grčevićのレビュー
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6852142/
医学の分野 免疫学、生物学
フォーマットハードカバーブック/電子ブック
聴衆免疫学は急速に発展している分野であり、生物学、血液学、感染症など幅広い生物医学および臨床分野の研究者、臨床医、学生にとって大きな関心事である。本書は、「免疫防御システムを形成した、また形成しつつある力」を理解するために、進化の観点から免疫学に取り組んでいる。内容を十分に理解するためには、読者は両分野の基本的な知識を持っていることが有益である。
目的 著者が強調するように、本書は進化や免疫学を包括的にカバーしようとするものではなく、「ある免疫現象を進化の文脈の中で紹介する」ものである。そのため、本書は退屈な事実の集まりではなく、「特定の問題についてもっと知りたいと思う人たちに出発点を提供する」ことを目的としている。
内容 本書は6つの章に分かれている。進化を促すもの」、「単細胞生物からメタ動物への免疫」、「先天性免疫」、「個人主義の勝利」、「体細胞生成型適応免疫系の進化」、「あとがき」の6章からなる。体性適応免疫系の進化」、「軍拡競争の裏側」、「あとがき」、「付録」、「索引」の6章で構成されている。
第1章では、遺伝、突然変異、遺伝的ドリフト、組換えなど、免疫学の文脈でさらに議論されるであろう基本的な進化の過程について簡単に概観している。この章では、Thomas Malthus、Charles Darwin、Herbert Spencer、Ernst Mayrなどによる、進化を理解する上で基本となる仮定に言及している。この章は、「免疫の進化」という小見出しで終わり、免疫系における具体的な進化メカニズムに言及している。この章では、著者が説得力を持っていくつかの興味深い点を提起しており、読者はこの本の残りの部分を読んでみたくなる。
第2章では、単細胞生物から後生動物に至る免疫系の発達を扱っている。系統の制限、自己の認識、免疫機構の動員といった概念が、例とともに提示されており、図版は比較的少ないものの、文章を理解しやすくしている。この章の終わりには、免疫反応の自然免疫と適応免疫への極性という重要な概念について述べられており、この2つのシステムは「劇的に異なる」と同時に、共通の目標を達成するためにしっかりと統合されているという、チャールズ・ジェインウェイの」seminal remark”に言及されている。
第3章では自然免疫を扱い、まず自然免疫系の組織について説明し、次に進化の過程を主に自然免疫受容体に焦点をあてて解説している。いくつかの小見出しで、遺伝子の複製、改変、エクソン/イントロンスワップなどのメカニズムが説明されており、進化の過程で、潜在的脅威を認識することのできる多様な細胞内・細胞外受容体が生み出されたことがわかる。病原体の認識に加え、自然免疫系は受容体によって開始されたシグナルを伝達し、食作用に基づく「破壊手段」を生み出すことができる」後生動物が進化する以前に存在した単細胞生物」でも有効であったのだ。
第4章では適応免疫について紹介し、抗原を認識して防御反応を起こせるようになるには、自然免疫以上のものが必要であることを解説している。進化の観点から、「自然免疫系は常に生殖細胞系に基づくのに対し、適応免疫系は常に体細胞系の適応に基づくという決定的な違いがある」という。このような「免疫系の体細胞進化」の重要なメカニズムが、免疫受容体、レパートリーの形成、リガンド結合などに関連して説明されている。著者らの重要な観察は、進化が突然「軌道修正」され、無顎類と顎口類における「適応免疫の抗原特異的受容体の進化における例外的な出来事」が生じたということである。
第5章では、免疫系と病原体の「戦い」が描かれている。生得的・適応的な「武器」で武装した後は、敵と対峙してその能力を試さねばならない。しかし、進化とは厄介なもので、「宿主の効果的な防御行動は、病原体の新しい病原性戦略の進化を促す淘汰圧を与えるだけ」であり、まさに「軍拡競争」となってしまう。言い換えれば、病原体は決して無力ではないのだ。進化の過程で、病原体は自然免疫系や適応免疫系に対抗するさまざまな戦略を開発してきた。著者らはこれを、「検出ハードウェアの破壊」、「死んだふり」、「免疫学的未来への潜伏」と名付けている。
後書きには、結論と、免疫の進化に関する著者の意見の要約が収められている。重要なハイライトは、「免疫の進化は永久革命の原則に従っている」ので、「全く同じ」ものはないということである。免疫系は、病原体の病原性メカニズムの進化に追随して、常に変化している。この観点からすると、私たちの「現在の理解は、現在のスナップショットに過ぎない」ということになり、後世に多くの課題を残すことになる。
見どころ 本書はどちらかというと簡潔で、量を犠牲にしてオリジナリティを追求したものである。言葉遣いは一般的な科学的なものではなく、型にはまらない面白い方法で、独自の視点を提供している。著者は議論されている現象の例を挙げており、議論を追いやすくしている。また、進化学や免疫学の分野における代表的な著作の引用と、科学的な事実や個人的な意見とを組み合わせて、非常に興味をそそる文章を作り出している。著者が強調するように、「免疫は、病原体に対する防御を提供するという一見単純な第一の役割が、無数のifやbutでヘッジされている」のである。つまり、この本の役割は、私たちにインスピレーションを与え、もっと勉強しようという気にさせることなのである。
関連する読み物 各章の終わりには、本文に関連する文献リストと、さらに読み進めるためのリストを掲載し、読者にさらなる学習と広い視野を提供する。
序文
ロバート・ジャック-ルイ・デュ・パスキエ
免疫学における進化論的概念
ドブザンスキーのスローガン、「生物学において、進化の観点以外には意味をなさない」[1]は、多くの学生にとって理解しがたい複雑なテーマである免疫学に特に強く当てはまる。本書は、そのような学生のために書かれたものである。本書は、免疫学の教科書でもなければ、進化論の教科書でもない。むしろ、進化の力が系統を越えてどのように免疫系を形成してきたかを示そうとするものである。
この試みにおいて、私たちは、昔からのジレンマに陥っている。「より多く、より少なく、より多く」説明することで、結局は何もないことについてすべてを提示することになるか、あるいは、「より少なく、より多く」説明することで、結局は何もないことについてすべてを提示することになるか、である。私たちは、危険な中道を選んだ。私たちは、包括的であろうとはしない。その代わりに、私たちは、ある種の免疫現象を進化的な文脈で紹介することにした。しかし、付録でより多くの事例をまとめ、視野を広げようと試みている。これらの例は、このテーマの広さを示し、もう少し深く掘り下げたい人のためのキーワードを提供することを意図している。同様に、私たちが議論しているデータを提供している重要な論文のすべてを引用しているわけではない。引用するのは、いくつかの「古典的」な論文と、よく書かれたわかりやすいレビューに限定している。付録と同様、特定の問題についてより詳しく知りたい人のための出発点となるようなものである。
ドイツ、グライフスワルトRobert Jack
スイス・バーゼル市ルイ・デュ・パスキエ
目次
- 1 進化を動かすものは何か?
- 1.1生物学における「どのように」「なぜ」?
- 1.2種 変異の重要性
- 1.3種 淘汰の重要性
- 1.4適性(適応度)の概念
- 1.5遺伝子
- 1.6変異と変異種
- 1.6.1ソーマと生殖細胞における突然変異
- 1.6.2突然変異の機能的分類
- 1.7遺伝的浮動(Genetic Drift)
- 1.8組み換え
- 1.9宿主-病原体相互作用は武器競争である
- 1.10「ジェネレーションギャップ」
- 1.11免疫の進化
- 2単細胞生物から後生動物への免疫の進化
- 2.1生殖細胞系とソーマ
- 2.2ファゴサイトーシス(貪食) 古い習慣が制限されるようになる
- 2.2.1後生動物における貪食能の系統的制限
- 2.2.2病原体に利用されるプロの貪食細胞
- 2.2.3病原体は貪食能力を再活性化し、利用することができる
- 2.2.4後生動物における貪食能力の多様化
- 2.2.5オートファジー:真核生物のファゴサイトーシスのいとこ
- 2.3後生動物は細胞の社会である 自己”の重要性
- 2.3.1「アポトーシス自己」の認識
- 2.3.2壊死的自己の認識
- 2.3.3協力だけでは不十分なとき「がん化した自分」の認識
- 2.4基底無脊椎動物における動かない”上皮性”免疫
- 2.5複雑な後生動物における免疫防御は移動可能でなければならない
- 2.6免疫の二刀流 「自然免疫と適応免疫
- 2.6.1脊椎動物における「適応性の問題」特異性はいくつあるのか?
- 2.6.2メチニコフの遺産
- 2.6.3ファゴサイトーシスとジェインウェイの”Dirty Little Secret」
- 3因習的免疫
- 3.1自然免疫系の構造
- 3.2自然免疫レセプターの進化
- 3.2.1遺伝子の複製
- 3.3複製と改変による遺伝子ファミリーの進化:Toll-Likeレセプター
- 3.3.1ショウジョウバエのToll-1
- 3.3.2哺乳類Toll-Likeレセプター
- 3.4エクソンとイントロン ドメインを入れ替えて新しいタンパク質を作る
- 3.4.1エクソンシャフーリング 新しい遺伝子の獲得速度を速める
- 3.4.2エクソンスプライシング 1つの遺伝子で多くの成果物を生み出す
- 3.4.3適応的イントログレッション
- 3.5細胞外自然免疫レセプターとそのターゲット
- 3.5.1細胞外微生物の表面構造を標的とするレセプター
- 3.5.2原核生物表面の分子パターンを標的とするレセプター
- 3.5.3内生ベイトの提供
- 3.6細胞内自然免疫レセプターとそのターゲット
- 3.6.1核酸の位置を感知する:APOBEC3G
- 3.6.2 DNAの局在濃度を感知する:cGASとSTING
- 3.6.3 RNAの微細構造を感知する RIG-I
- 3.6.4細胞内細菌病原体の検出
- 3.6.5内在性の”危険”シグナルの検出
- 3.6.6「ミッシングセルフ」と「ナチュラルキラー細胞」レセプターの進化
- 3.7コメンサルとの共生
- 3.8受容体-リガンド相互作用を超えて 計算装置としての免疫システム
- 3.8.1シグナル伝達
- 3.9出力
- 3.9.1細胞運動と炎症反応
- 3.9.2補体を介した貪食作用
- 3.9.3プログラムされた細胞死
- 3.10誰がもっと必要なのか?
- 4個人主義の勝利体細胞で作られる適応免疫系の進化
- 4.1核酸センサーを利用した適応システム
- 4.1.1細菌のCRISPR-Cas
- 4.1.2真核生物のRNA干渉
- 4.1.3 RNA干渉を利用した適応免疫系の進化
- 4.2タンパク質センサーを利用した免疫システムの体細胞進化
- 4.2.1タンパク質を利用した2種類の適応免疫系
- 4.2.2リンパ球とそのレセプター
- 4.3アグナサン適応免疫レセプターの体細胞形成
- 4.3.1鍵となる酵素:AID類似のシチジンデアミナーゼ
- 4.3.2受容体分子の構造
- 4.3.3耐性
- 4.4刺胞動物の適応型免疫受容体
- 4.4.1免疫グロブリンスーパーファミリードメイン
- 4.4.2トランスポゾン”Transib “は顎口動物におけるすべての抗原特異的受容体の構造に寄与していた
- 4.4.3刺胞動物免疫受容体の抗原結合部位
- 4.5 RAGとその限界
- 4.5.1多くのレセプターと多くのガラクタの狭間
- 4.5.2 RAGの組換え 4.5.2 RAG組み換え:包括的な適応レパートリーを構築するための中途半端な試行錯誤
- 4.5.3 B細胞系におけるリガンド結合と「耐性」
- 4.5.4アレリックの排除
- 4.6 T細胞系におけるリガンド結合
- 4.6.1 MHC複合体とペプチドキャリアー分子
- 4.6.2なぜ2種類のMHC-ペプチドキャリアー分子が存在するのか?
- 4.6.3 TCRはペプチドとMHC分子の複合体を認識する
- 4.7どのTCRが有用か」?正の選択」
- 4.8胸腺におけるT細胞の「負の選択」
- 4.8.1すべての”自己”ペプチドを提示すること
- 4.8.2 MHCクラスIIに「自己」ペプチドを発現させる
- 4.9胸腺におけるT細胞淘汰の代償
- 4.10 TCRとMHC分子の共進化
- 4.11中心的寛容の後のレパートリーの変化 BCRの体細胞超変異
- 4.12中心的寛容の後の生活 末梢性寛容とリンパ球の活性化
- 4.12.1「2つの鍵」によるフェイルセーフ戦略
- 4.12.2 T-レギュレーター細胞
- 4.13レセプターレパートリーを超えて:リンパ球のエフェクター機能
- 4.14刺胞動物における適応記憶
- 4.15刺胞動物の適応的免疫レパートリー形成の多様性
- 4.16アグナサンと棘皮動物の適応免疫系の進化的関係
- 4.16.1ホモロジーとアナロジー
- 4.16.2斜め上からの進化と「深い相似性」
- 4.16.3適応型ニッチ
- 4.16.4造血とリンパ球の起源
- 4.16.5胸腺と「チモイド」
- 4.16.6免疫におけるAID様シチジンデアミナーゼ機能の進化
- 4.16.7無羊膜類と顎口類との最後の共通祖先
- 4.1核酸センサーを利用した適応システム
- 5武器競争の裏側
- 5.1病原体との折り合い
- 5.2自然免疫系に対抗する病原体の戦略
- 5.2.1自然免疫受容体のレパートリーから身を隠す
- 5.2.2自然免疫反応の妨害
- 5.3適応免疫系を回避する病原体戦略の例
- 5.3.1適応免疫の検出ハードウェアを破壊する
- 5.3.2死んだふりをする
- 5.3.3免疫学的未来に隠れる
- 6あとがき
- 付録
- 付録A:メタゾアの簡略な分類
- 付録B:免疫受容体とその共通ドメイン
- 付録C:cGAS、STING、環状ジヌクレオチド
- 付録D:免疫グロブリンスーパーファミリーのドメイン付録E:インターカラリーエボリューション参考文献
- 索引
第1章 何が進化を促すのか?
1.1生物学における「どのように」「なぜ」?
本書では、免疫防御システムを形成し、また形成しつつある進化的な力のいくつかを見ていくことにする。しかし、その前に、進化のプロセスの基本的な特徴をいくつか見ておくことは理にかなっている。その手始めとして、当時ハーバード大学の動物学教授であったエルンスト・マイヤーが1961年に『サイエンス』誌に発表したエッセイが最適だろう[1]。この論文でメイヤーは、オフィスの窓の外を夏の間ずっと飛び回っていた小鳥が、秋が近づくと飛び立って南へ飛んで行ったという事例を考察している。メイヤーは、このような現象に対して、2つのタイプの問いがあると指摘した。1つは、彼が「どうやって」という質問である。小鳥はどうやって一年の終わりが近いことを知るのだろう?どうやって南へ飛んでいくのだろう?たとえば、日が短くなることや、一日の平均気温が徐々に下がっていくことを、何らかの適切な受容システムを使って感知するのだろう。そして、この信号を脳が解釈できる電気インパルスに変換し、小鳥が正しい方向に飛び立つよう促す出力信号を発生させなければならない。この「どのように」という問いに対する答えを見つけるには、一生かかっても足りないほど魅力的な研究が必要であり、その結果は分子や生化学的、神経回路的な用語で表現されることになる。分子や経路は、多くの科学者がその生涯の大半を費やして扱うものだからだ。
しかし、マイヤーは、もう一つのタイプの問い、すなわち「なぜ」という問いがあることを指摘した。なぜ、小鳥は南へ飛んでいくのだろう?その答えは、一般論として、虫を食べる鳥だから南に飛ぶのであり、冬のマサチューセッツにはあまり虫が飛んでいないからだ。したがって、私たちは「南へ飛ぶ者の生き残り」のケースを扱っている。これは、ダーウィンの進化論の問題であり、その基本的な構成要素は、ランダムな突然変異、遺伝的ドリフト、組み換え、自然選択による変異である。「どのように」という問いは、ゲノムに格納された情報がどのように表現され、利用されるかに関わるものである。これに対して、「なぜ」という疑問は、ゲノムがどのようにして今の形になったのかに関わるものである。最近の優れた免疫学の教科書であれば、「どのように」という質問に対する答えがたくさん載っている。私たちの目的は、その代わりに、免疫防御の背後にある「なぜ」という問いについての入門書を提供することである。
1.2 変異の重要性
19世紀以降、生物学者の主要な仕事の一つは、生物を体系化し、異なる種に分類することであった。当時は、形態学がその主要な手段であった。しかし、ある人にとっての決定的な形態の違いが、別の人にとっては単なる細部に過ぎないということが問題になった。当然のことながら、種の割り当てや、種、品種、レースの位置づけをめぐって激しい論争が繰り広げられた。多くの学者たちが、この問題でキャリアを積んだり、破ったりした。
ダーウィンはビーグル号での経験から、重要なのは種の構成員の「同一性」ではなく、それぞれの構成員が共通のテーマの変異種であるという事実に気づき、このゴルディアスの結び目を切り開くことに成功した。この結論に達したのは彼が初めてではなかったが、これをブレイクスルー突破口としたのは、これらの変異種の中には、他の変異種よりも環境に適したものがあるはずで、したがって生存競争において有利になるはずだということを悟ったからであった。しかし、この「ある種の構成員は、すべて共通のテーマによる変異種である」という認識には、代償が必要であった。「種の起原」の著者である菅原義偉は、その著書の冒頭で、何が種で何が種でないかを明確に区別する基準を持っていない、と言わざるを得なかった。「種の起源」の第2章で、彼はこう書いている。
私は、種という言葉は、便宜上、互いによく似た個体の集合に任意に与えられたものであり、より明確でなく、より変動的な形態に与えられる多様性という言葉と本質的に異ならないと考えている。多様性という用語も、やはり単なる個体差と比較して、便宜上、恣意的に適用されるものである。
形態学的な種の定義を、2つの個体が受胎可能な子孫を残す能力に基づくもので補おうという試みは、ほとんどうまくいかなかった。ダーウィンはこのことを次のようにまとめている。
最後に、植物と動物の交配に関するすべての確認された事実を見ると、最初の交配でも雑種でも、ある程度の不妊は極めて一般的な結果であると結論づけることができるだろう。
したがって、交配における不稔性は、種という用語を定義するために用いることのできる一般的に適用可能な基準とはいえない。
その後、生物学が大きく発展したにもかかわらず、「種」という言葉の定義について、これ以上語られることはあまりない。この言葉は、誰もが多かれ少なかれ理解しているにもかかわらず、誰も正確に定義することができない、不思議な言葉の一つであったし、今もそうである。しかし、正確な定義がないことは大きな障害にはならず、個体間の性格の変異が進化の中心的要素の一つであるというダーウィンの認識に比べれば、取るに足らないことなのである。
1.3 種淘汰の重要性
個体間の変異は進化の鍵の一つであるが、変異それ自体には何の価値もない。変異は、どの変異種が将来の世代に最も貢献するかを自然淘汰が選択できるような状況においてのみ有用である。例えば、深海魚のシーラカンスは、4億年前の化石と同じ姿をしているため、しばしば「生きた化石」と呼ばれる。もちろん、これはジャーナリスティックな比喩に過ぎない。この魚のゲノムも、他のあらゆる生物のゲノムと同様に、この何百万年もの間、突然変異を積み重ねてきたのだから。しかし、海の底では、環境変化があまり起こっていないため、新しい環境に適応させる選択圧がほとんどなく、適切な突然変異を積極的に選択することによって、形態的変化の進化を促してきた。したがって、進化は、突然変異による変化だけでなく、淘汰にも依存することになる。突然変異は一銭にもならない。突然変異を進化的に重要なものにするのは選択である。
1.4 適性(Fitness)の概念
マイヤーの昆虫食の小鳥の物語は、南への飛翔だけで終わらない。一旦南へ飛翔した小鳥は、南の昆虫を食べて太り、相手を見つけ、次の春には家族を作るために再び北へ飛翔していった。そして、翌年の春、再び北へ飛んで行き、家族を作るのだ。他の小鳥たちも同じように子育てをし、晩春には個体数が爆発的に増えた。1798年にマルサスが発表した『人口原理』以来、私たちはこの物語がハッピーエンドであってはならないことを知っている。限られた数の昆虫を餌にしなければならないので、雛の一部は餓死し、他の雛は病気にかかり、残りの雛のほとんどは捕食動物に食われて太る。そして、その年の春に自分の家族を持つことができるのは、ごくわずかである。
では、誰が生き残るのか?そして、誰が死ぬのか?
そして、なぜ?
「適者生存」というキャッチーなフレーズは、1864年にイギリスの哲学者スペンサーが初めて提案したものである。しかし、この批判は誤りである。なぜなら、この議論における「適性」という言葉は、身体的適性ではなく、常に遺伝的適性を指していることを理解していないからだ。ゲノムの遺伝的適性を決定するのは、その塩基配列であり、したがって、それが次の世代に受け継がれる確率を決定するのは、塩基配列なのである。何らかの理由で現在の環境に適しているゲノムは、生存者の集団の中から発見される確率が高くなる。ダーウィンが「生存のための闘い」と呼んだものにおいて、ほぼ必然的に勝者となる。
多くの場合、生物が直面する問題の解決には、妥協とトレードオフが必要であり、多くの異なる要請を考慮しなければならない。例えば、線虫の線虫は自家受精する雌雄同体で、まず精子を作り、それを蓄えることで生殖生活を始める。精子を作った後は、卵を作ることに切り替える。この卵は、貯蔵されている精子を用いて受精する。重要なのは、貯蔵されている精子の数によって、この虫が産める子供の数が制限されることである。したがって、精子を余分に作る突然変異種は、より多くの子孫を残すことができ、より多くの子孫を残せば、より高い適応度につながるはずなのであるが、奇妙なことに、そうではない。線虫はバクテリアを食べることで生存しており、その旺盛な食欲のために、餌はすぐに枯渇してしまうのである。成功する線虫は、早く食べて、すぐに子供を作り始めるものである。突然変異種の線虫は、精子を余分に作るために費やした時間を、受精卵を作るための競争で失ってしまうのだ。突然変異種の卵は、野生型の仲間よりも遅く産み落とされ、この卵が孵化する頃には、野生型のライバルは利用可能な食料を食べ尽くしてしまっている。この場合、より多くの子孫を残す能力が、より大きな適性につながるわけではなく、その逆である[2]。
より単純なケースであっても、「適者生存」が成立するのは、選択圧と突然変異率のスペクトルの一部だけである。選択圧が低いときには、それほど有害でない突然変異でも生き残る可能性がある。同様に、ペルム紀末の大規模な環境破壊で海洋種の90%以上が絶滅したように、選択圧が突然過剰になると、生存可能な突然変異率では適切な適応的変化を生み出すことはできない。しかし、この両極端の間で、ある種が環境の変化を長期間にわたって生き延びることができるかどうかは、集団に存在する変異種を自然淘汰することによって決定される。現在の環境に有利な突然変異を蓄積した、遺伝的に適合した対立遺伝子が成功することになる。必要な有益な突然変異を蓄積できなかったものは消滅する。
1.5遺伝子
19世紀の進化論者にとっての最大の問題の一つは、遺伝のメカニズムについて誰も何も理解していなかったことである。遺伝情報の性質は謎であり、それを変化させるランダムな突然変異の力も全く未知であった。しかし、現在では、DNA、染色体、遺伝について多くのことが分かっており、すべてが変わってきている。DNAの情報がどのようにして細胞の生化学的な働きをするタンパク質に変換されるのか、また、DNAの変化がどのようにしてタンパク質の構造や発現を変化させるのかについて、明確な見解が得られている。また、突然変異が、DNAにコードされた情報の変化を引き起こすことによって、遺伝の中心分子であるDNAの機能をどのように変化させるかについても、かなり分かってきている。
タンパク質の構造を定義している遺伝情報を変更すれば、悲惨な結果になる可能性があることは想像に難くない。しかし、突然変異はゲノム全体にわたって(多かれ少なかれ)ランダムに誘発され、ヒト染色体のDNAに含まれる全塩基のうち、直接タンパク質をコードするものは約2%に過ぎないので、ほとんどの突然変異はゲノムの非コード領域に影響を及ぼすことになる。しかし、そのような突然変異が必ずしも無害であるとは限らない。しかし、細胞内で重要な働きをする多くの種類のRNA分子がここにコードされており、プロモーター、エンハンサー、サイレンサー、遺伝子座制御領域など、転写される配列が発現の程度を制御していることは明らかである。このような配列に干渉する変異は、劇的に悪い影響を与える可能性がある。
ここまでの文章は、「遺伝子」という言葉を使わないようにするために、かなり不格好な表現で苦労している。その理由は非常に単純である。既知のあらゆる事態を考慮し、現在の「遺伝子」という言葉の定義を、ゲノムのほとんどすべての配列を除外できないほど広範かつ曖昧な言葉で表現しなければならない。「遺伝子」は「種」と同様、誰もが理解していながら、誰も正確に定義することができない言葉の一つである。本書では、タンパク質やRNAの発現を制御するために必要なゲノムの配列を指す言葉として、「遺伝子」という言葉をやや緩やかに使うことにする。
多くの異なる動物の完全なゲノム配列を解析することによって、これらの生物がどれくらいの数の遺伝子を含んでいるかが、おおよそわかる。ヒトとマウスのゲノムにはおよそ2万個の遺伝子が含まれており、その他にも扁形動物マクロストマム・リグナノなど、多くの動物のゲノムが含まれている。2万個という数字は大きいのだろうか?それは、「一本の糸の長さはどれくらいか?と聞くようなものだ。しかし、鏡を見ながら、たった2万個の遺伝子を使って、あなたが見ているような人間を作ることができるかどうか聞いてみれば、ある種の答えが得られるかもしれない。この2万個の遺伝子は、私たちの細胞を、その内部で起こっているすべての複雑な代謝過程とともに構築しなければならない。また、これらの細胞を組織や臓器に組織化しなければならない。また、環境を感知し、予期せぬ出来事に最適に対応する能力を提供しなければならない。このような仕事内容であれば、2万個の遺伝子の指示は決して多いとは言えない。現実には、生命は遺伝子のわずかな差で動いている。
平たいミミズと人間の遺伝子の数はほぼ同じであり、その多くは両生物で同じ機能を果たしている。動物の複雑さを増すには、遺伝子の数を増やすのではなく、持っている遺伝子の発現と機能の統合と調整の度合いを増すことであることは明らかである。数よりもむしろ、統合が重要なのだ。
1.6突然変異と変異種
ダーウィンがブレイクスルー発見をした表現型の変異は、DNAの構造を変化させる自然発生的なランダム突然変異によるものであることが、ダーウィンから1世紀半以上たった今、私たちの知るところとなった。突然変異という言葉は、癌や破壊や死を連想させるため、評判が悪い。しかし、突然変異は、それらに加えて、進化の中心的な原動力の1つである。突然変異は常に起こっており、すべてのゲノムは常に新しい突然変異を獲得している。このプロセスは「遺伝的ドリフト」と呼ばれている。この遺伝的ドリフトが、自然淘汰のための選択肢となる変異の源となる。
突然変異はどこから来るのだろうか?例えば、細胞分裂の前に染色体が複製される過程で、必然的に起こるエラーがある。この複製プロセスは驚くほど正確である。しかし、生命に完璧はなく、2倍体のヒトの細胞が分裂するたびに6,000,000,000塩基の新しいDNAが合成されるので、1つや2つの奇妙なエラーは必ず発生することになる。私たち一人ひとりが1個の受精卵細胞から人生をスタートし、成人した人間は約10^14個の体細胞から構成されていることを考えると、あなたや私の人生において、非常に多くの複製が行われてきたことがわかるだろう。なぜなら、リンパ球、骨髄系細胞、上皮系細胞など、体内の多くの細胞系列は、一生の間に急速に入れ替わるからだ。
同じように、DNAの情報がRNAにコピーされる転写の過程も、突然変異を誘発する可能性がある。また、熱、乾燥、電離放射線、環境化学物質など、核酸を変化させる外的要因も同様である。もちろん、突然変異による損傷を検出し、修正する高度なシステムなしには、生命は長くは続かないだろう。デイノコッカス・ラジオデュランス(Deinococcus radiodurans)菌や、サソリやゴキブリのような節足動物の中には、大量の放射線にさらされても繁栄できるものがあるように、必要に応じて、これらの修復機構は驚くべき程度に調整、最適化することができる。
1.6.1ソーマと生殖細胞における突然変異
突然変異がどの細胞で起こるかは大きな違いである。「生殖細胞」、すなわち卵子や精子の生成に関与する細胞で生じた突然変異は、将来の世代に受け継がれるため、この種の突然変異は個人間の遺伝的変異の原因となる。これに対して、肝臓細胞、神経細胞、筋肉細胞など、身体の正常な体細胞で生じた突然変異は、個人の生命に影響を与えるかもしれないが、次の世代に引き継がれることはないから、一般に進化上の関心は持たれないと考えられている。
このような突然変異は、生殖細胞によってコード化された遺伝的未来の一部となることはなく、後天的特性の遺伝性に関するラマルクの仮説が、わずかな例外を除いて(第4.1.3節参照)、成り立たないのは、このためである。体細胞突然変異に進化的意義がないとは言いない。小児癌の原因となるような突然変異は、その個体が繁殖する確率を劇的に低下させ、その結果、遺伝的未来に貢献することになるからだ。一方、体細胞突然変異には、それ自身は遺伝しないけれども、個体の適応度に大きな正の効果を与え、したがって、進化上かなりの重要性を持つ大きなクラスが存在する。それは、脊椎動物の適応免疫系における体細胞突然変異で、リンパ球の抗原レセプターを変化させるものである(第4章で説明する)。体細胞変異を利用したこの最も珍しい例は、脊椎動物の免疫系に、病原体との闘いにおける強力な武器をもたらした。この強力な武器に対抗するために、体細胞変異に依存する病原体戦略を開発した病原体があっても、おそらく驚くには値しないだろう[4]。
1.6.2突然変異の機能的分類
すなわち、負の淘汰を受ける有害な突然変異、何の効果もなく、したがって自然淘汰によって無視される中立的または沈黙の突然変異、そして最後に、最も小さなグループである正の淘汰を受ける有利な突然変異である。これらの突然変異を想像する最も簡単な方法は、タンパク質をコードする一本のDNAを考えることだ。このタンパク質は、酵素として、あるいは構造体として機能するためには、正確に定義された三次元の形に折り畳まれていなければならない。タンパク質のアミノ酸配列に変異が生じると、正しい形に折り畳むことができなくなり、その場合、そのタンパク質は本来の役割を果たせなくなる可能性がある。もし、その仕事が生物の生命維持に不可欠であれば、その突然変異は明らかに有害であり、自然淘汰によって、この種の突然変異が集団の中で広く普及しないようにすることができる。しかし、タンパク質をコードする塩基配列の順序を変えるような突然変異が、必ずしもすべて災いをもたらすわけではない。これには二つの理由がある。第一は、ほとんどのタンパク質では、アミノ酸の変化を受け入れても機能に悪影響が出ない位置があるということである。このような中立的な突然変異は、基本的に自然淘汰には見えないので、許容されることになる。第二のタイプの突然変異は、同様に自然淘汰には本質的に見えないもので、いわゆるサイレント・ムーティションと呼ばれるものである。これは、核酸コードが三重コードであり、メッセンジャーRNAの3つの塩基がタンパク質の各アミノ酸を規定するために生じるものである。なぜなら、64個の三重項(コドン)が存在するのに対し、アミノ酸は20個程度しか存在しないからだ。そのため、アミノ酸の多くは複数のコドンを持つという意味で、コードは縮退している。例えば、ロイシンというアミノ酸は6つの異なる3連符でコードされており、これらの3連符で可能な塩基変化の1/3は、ロイシンのコドンを別のものに交換する結果になる。タンパク質をコードする領域におけるこのような突然変異は、その位置のアミノ酸の変化をもたらさないので、明らかにタンパク質の構造を変えることはなく、それ故、通常、沈黙の突然変異と呼ばれる。
このような突然変異は確かに「沈黙の」突然変異であるという主張は、おそらくほとんどの場合において正しいが、2つの注意点がある。一つは、タンパク質合成装置でアミノ酸を所定の位置に運ぶのに必要な転移RNAは、細胞内にすべて同じ濃度で存在するわけではないので、サイレント変異が起こると、豊富なtRNAの代わりに希少なtRNAが使用され、その結果、タンパク質鎖が合成される速度が変化する可能性があるということである。その結果、タンパク質鎖の合成速度が変化し、タンパク質が正しい形に折りたたまれる際に悪影響を及ぼす可能性がある。最近行われた大規模な塩基配列解析の結果、ヒトの集団において、稀少なtRNAの使用に対する負の選択の証拠が見つかったことから、ほとんどの場合、これは大きな問題ではないことが示唆されている[5]。
このような突然変異の「沈黙」に対する第二の注意点は、突然変異がタンパク質の進化可能性という特性を変えてしまう可能性があるということだ。あるタンパク質が、特定の位置にロイシンをコードする三重項UUAを持つとして、その遺伝子が一塩基のサイレントチェンジを受け、コドンがUUGとなり、これもロイシンをコードするようになったとしよう。さらに、将来のある時点で、環境の変化により、この位置にロイシンではなくトリプトファンがあった方が、生物にとってずっと良い状況になったとしよう。トリプトファンはUGGという三重項によってのみコードされているので、UUGコドンを使ってロイシンをコードする変異種は、このUGGコドンに1塩基置換することによって容易に変異させることができる。UUAコドンを使ってロイシンをコードする変異種には問題がある。それは、1回の突然変異ではなく、2回のランダムな突然変異が起こる必要があり、それははるかに遅いプロセスとなる。そのため、UUGを持つ変異種は、変化した条件に対応するために、より容易に適応することができる。このように、いわゆるサイレント・メイテーションは、決して常にゲノムに対する取るに足らない変化というわけではない。
有利な突然変異は最後に出てくるが、これは圧倒的に小さなグループであり、大多数の突然変異は中立的か、あるいは劇的に変化しているからだ。とはいえ、もし有利な突然変異が生じれば、自然淘汰はその突然変異を集団に広めることを支持する。その速度は、その突然変異がもたらす有利さの程度に依存する。例えば、牛乳に含まれるラクトースに対する大人の人間の正常な不耐性を克服する突然変異は、牛を飼う社会で何度も独立して生じている。同様に、マラリア原虫の感染によって引き起こされるマラリアに対して、ある程度の抵抗力を与える突然変異が、過去1万年ほどの間に何度も生じ、正選択されてきた。最もよく研究されているのは、ヘモグロビンのβ鎖をコードする遺伝子の1塩基の変化で、ポリペプチド鎖の7位の正常なグルタミン酸残基の代わりにバリン残基が置換されるものである。この変異がホモ接合体である人は、鎌状赤血球貧血を患う。これは、変異したヘモグロビン鎖が、特に低酸素濃度下で凝集する傾向があるために、生命を脅かす可能性のある状態である。凝集したヘモグロビンは赤血球を変形させ、循環の中で凝集と溶解を起こしやすくする。さらに、これらの変形した赤血球は脾臓の赤血球品質管理システムにより除去される。その結果、貧血を起こすとともに、脾臓に大量の負荷がかかり、この臓器が破壊されることがある。一方、ヘテロ接合体では、正常なヘモグロビンβ鎖の存在が変異型の凝集傾向を改善するため、これらの深刻な臨床的影響はない。酸素圧が非常に低いとき、例えば赤血球が代謝の活発なマラリア原虫に感染して、まるで明日がないかのように酸素を使い果たすときだけ、赤血球はヘモグロビンの凝集による有害な影響を受けるのだ。このように、マラリア感染の血液段階において、変形した感染赤血球は早期に除去される傾向にあり、患者の死亡率を著しく低下させることにつながっている。この例は、進化の相互作用の複雑さを示している。ヘテロ接合体の個体は、マラリアに対する抵抗性という点で大きな利点を得ているが、その代償として、ホモ接合体の兄弟姉妹の寿命が著しく短くなる。
これまで、「変異種」と「突然変異」という言葉は、ほとんど同じように使われてきた。答えは、根本的な違いはない。通常、「変異種」という言葉は、人口の1%以上のゲノムに存在する配列要素を表すのに使われる。このような配列は、それ自体が確立されているため、容易に検出することができる。100人に1人以下の割合で存在する変異種は、「突然変異」と呼ばれる。これらは最近生じた配列で、まだ正の選択を受ける機会がない場合もあれば、ある程度有害な配列で、自然選択によって排除されつつある場合もある。
1.7遺伝的ドリフト
生物はそのゲノムにランダムな突然変異を蓄積する。このプロセスを遺伝的ドリフトと呼ぶ。このことは、ルリアとデルブリュックによって行われた古典的な実験で初めて明らかにされた。この実験では、病原性ウイルスによる攻撃に対する細菌の抵抗性の獲得は、ウイルスとの戦いに先立って、通常の細菌集団の数個に偶然に生じることが示された。もし、ウイルスが近くにいなければ、その突然変異は適性上の利点をもたらさないので、むしろすぐに淘汰されてしまうだろう。しかし、もし、ウイルスがたまたま通りかかったならば、耐性を与えるランダムな突然変異を持つ少数の個体が生き残り、他の個体はすべて死滅する[6]。ルリアとデルブリュックの実験は、進化上の問題が生じたとき、生物はその解決策を見つけるために意図的に動き出すわけではない、という極めて重要なポイントを突いている。その代わり、解決策は、ランダムな突然変異という形で、すでに集団の中に潜んでいる。これは、私たちが日常生活で問題に対処する方法とは全く異なるものである。私たちは問題に直面したとき、それを合理的に分析し、可能な限り最善の解決策を設計しようとする。問題から解決策へと向かうのである。しかし、進化はその逆である。解決策の可能性は、集団の一部のメンバーのゲノムの突然変異という形で存在し、適切な問題が現れるのをただ待っている。
真核生物は、二つの理由から、原核生物に比べ、軽度の有害な突然変異の保持に優れている。第一に、原核生物がハプロイドであるのとは対照的に、真核生物は少なくともそのライフサイクルの一部において二倍体であり、従って、それぞれの遺伝子に二つの異なるコピーを持っており、一つは母親から、もう一つは父親から受け継いでいる。常染色体の遺伝子の大部分については、1つのコピーを破壊しても、目に見えるような影響はほとんどない。このため、真核生物のゲノムは、ハプロイド生物のゲノムに比べて、遺伝的ドリフトを許容する能力がはるかに高い。第二の理由は、自然淘汰がレースであるということである。例えば、あなたが200mの距離を走るとき、最初にゴールする3人の中に入るかどうかは、あなたのスポーツ能力にもよるが、あなたのライバルが誰なのかにも大きく依存する。仮に全人類をスタートラインに並べたとして、あなたが1位、2位、3位でゴールする確率は限りなく小さくなるはずだ。しかし、このレースでランダムに10人の人類を選んだとしたら、状況は大きく変わる。私は、その中の一人かもしれないが、走ることを考えただけで青ざめてしまう。もう一人は、生後5カ月の元気いっぱいの選手かもしれないが、あなたにとって大きな問題にはならないだろう。つまり、ランダムに選ばれたスターターの人数を制限することで、メダルを獲得できる可能性が非常に高くなる。要は、自然淘汰はレースなので、その効果は母集団の大きさに正比例する。ここでは生殖細胞による伝達の話をしているので、「集団」という言葉は、全人口のうち生殖に関与している割合を指す。細菌やウイルスの集団は実に巨大であり、集団の各メンバーは繁殖を試みている。そのため、自然淘汰は非常に効果的であり、遺伝子産物は選択された特定の機能を遂行するために最適化されることになる。同様に、ランダムな遺伝的ドリフトによって獲得された軽度の有害な突然変異であっても、競争が激しく適者のみが生き残るこの巨大な集団では、速やかに淘汰されるだろう。一方、真核生物では、有効な集団サイズが小さいため、自然淘汰はそれほど厳しくなく、軽度の劇症突然変異が生殖細胞に蓄積される可能性がある。したがって、2倍体の真核生物における遺伝的ドリフトは、ほとんどの原核生物に比べ、はるかに多くの突然変異を許容することになる。その結果、私たちは、より多くの潜在的な解決策を持ち、適切な問題がやってくるのを待つことになる。
真核生物に蓄積された生殖細胞由来の突然変異の大規模な貯蔵は、単に理論的な可能性だけではない。なぜなら、ゲノムの配列決定によって、ヒトの遺伝子に多数の変異種が存在することが証明されたからだ。少なくともコード領域では、平均して8塩基対に1つの変異種が見つかっている。実際、この文章を読んでいる人は、少なくとも、突然変異によって片方のコピーが破壊された遺伝子を85個、両方のコピーが破壊された遺伝子を35個持っていることになる。しかし、これだけではない。スーザン・リンドクイストとその共同研究者たちは、ショウジョウバエで、遺伝的ドリフトによって多くの遺伝子が変異を受け、その結果、タンパク質産物が、まだ機能しているものの、ほとんど文字通りバラバラになっていることを示した[7]。これらの遺伝子産物は、最適化とは程遠いものである。構造的な欠陥のために、選択された仕事を完璧にこなすことはできないかもしれないが、同じ意味で、最適化された構造よりも、新しい機能を獲得するチャンスがはるかに高いかもしれない。このような変異種はすべて、あらかじめ形成された「潜在的な解決策」と見なすことができる。このことは、適応免疫系(第4章参照)ほど明確なものはない。骨髄の幹細胞から新たに生成されるリンパ球の一つ一つが、新しい変異型抗原受容体を産生するからだ。その結果生じる膨大な数の変異型受容体のクローンは、あらゆる病原体を検出するために利用できる、あらかじめ形成された溶液と考えることができる。
1.8 組み換え遺伝的
ドリフトのために、突然変異は常に蓄積されている。これらの突然変異のうち有益なものはほとんどなく、多くは率直に言って劇症である。このことは問題を提起している。突然変異は常に起こっているのだから、常に増え続ける有害な突然変異をどうしたらよいのだろうか。必須遺伝子の発現を完全に破壊してしまうような突然変異については、答えは明らかである。そのような致死的な突然変異を持つ生物は単に死ぬので、その突然変異は集団から除去される。しかし、より興味深く、またより一般的な現象は、致死的ではないものの、軽度な致死性を持つ突然変異の場合である。このような有害な突然変異は、必然的にゆっくりと蓄積されていくる。この恐ろしいシナリオは、アメリカの遺伝学者ヘルマン・ミュラーによって最初に指摘され、ミュラーのラチェットとして知られるようになった。その基本的な考え方は、時間が経つにつれて、各個人の中に完璧とは言い難い遺伝子の数が徐々に、連続的に、不可逆的に増えていくというものである。もし、このまま何もしなければ、必然的に絶滅することになる。では、どうすれば絶滅を回避できるのだろうか?
ミュラーは、この問題を解決するために、有性生殖とそれに伴う減数分裂による組換えが、有害な突然変異を除去する機会を提供することを提案した(図11)。この図は、単一の染色体を持つ仮想的な生物でこれを示している。各個体は、母親から1本、父親から1本の染色体を受け継いでいる。減数分裂の際、ランダムな組換えにより、ハプロイド卵または精子が形成される前に染色体情報の再配列が行われる。しかし、幸運な組換え現象が起きると、突然変異の負荷が大幅に減少した卵や精子が得られることがある。ミュラー・ラチェット・パラドックスの解決は、性の進化を促す主要な選択力であったと広く信じられている。
しかし、組換えは、単に自然淘汰が有利な突然変異を甘受し、不利な突然変異を除去することを可能にするだけではない。遺伝子は典型的なチームプレーヤーであるため、組換えは驚くべき結果をもたらすことがある。人間は、2万個の遺伝子が統合されたチームとして形成されていると考えることができる。これらの遺伝子のほとんどは変異種または「対立遺伝子」として集団に存在するため、一卵性双生児を除いて、どのチームも同じではない。世代を経るごとに、組換えによってチームの構成が揺らぎ、2万個の遺伝子の対立遺伝子の新しい組み合わせが生まれ、その結果、ユニークな新しい個体が誕生する。
この意味で、ヒトゲノムの2万個の遺伝子は、遺伝子のカードハウスを形成していると考えることができ、カードを取り除いたり、形や大きさを変えたりすると、構造全体に反響が起こる可能性がある。このため、遺伝学的に定義された多くの形質の分析に支障をきたしている。このことは、人間の身長のような通常の特性にも表れている。この場合、表現型の約80%は遺伝性であり、したがって遺伝的要因によるものである。残りは栄養などの環境要因によるものである。大規模な遺伝子マッピング実験から、身長のばらつきの約10%は約180の遺伝子の発現と関連しており、残りの部分は1000以上の遺伝子が寄与していることが示されている[8]。従って、ある個人の身長を、その遺伝子を見るだけで決定しようとするのは、かなり絶望的な仕事である。
このことを人間の健康という観点から見てみると、必須タンパク質の機能が失われたり変化したりする突然変異は、遺伝性疾患、すなわち遺伝性の疾患を引き起こす可能性があることが明らかになる。単一遺伝子の破壊が原因である「単発性」ヒト疾患は、1500種類以上知られている[9]。しかし、これらの疾患の多くは極めて稀である。それよりもはるかに多いのは、統合失調症、関節リウマチ、炎症性腸疾患など、身長と同様に多数の遺伝子の相互作用が関係する病気である。このような場合、「病気」とされる対立遺伝子の一部は、正常な変異種であるにもかかわらず、たまたまゲノム上の適切でない場所に配置されたに過ぎない可能性がある。
フランスの分子生物学者フランソワ・ジャコブは、この点を次のように表現している。「新奇なものは、それまで見たこともないような古い材料が組み合わさって生まれる。新しいものを生み出すには、組み換えることである」[10]。
1.9宿主-病原体相互作用は腕力勝負である
本書では、病原体の攻撃から生き延びることができることによる適応度・ベネフィットに焦点を当てることにする。ヒトの病原体について考えるとき、病原体が私たちにしていることは、何も個人的なことではないことに気付くとよいかもしれない。彼らが欲しいのは、平和と静けさ、そして病原体の赤ちゃんを育てるのに十分なエネルギーと資源だけなのだ。問題は、彼らが私たちをエネルギーや資源の供給源と見なしていることである。エネルギーと資源を、子孫を残すという最も重要な任務から防衛に振り向けなければならない。資源をめぐる種間の競争も、中途半端な結婚も、そして特に宿主と病原体の相互作用も、すべてこの一般的な仕組みに従っているからだ。その結果、私たちの免疫システムは、私たちが感染を回避したり克服したりするのを助けると同時に、病原体に選択的圧力をかけ、新しい病原性メカニズムの進化を促している。そして、その病原体が宿主に選択的な圧力をかけ、免疫系の進化を促す。その結果、病原体と宿主の間で、絶え間ない軍拡競争が繰り広げられる。
1.10 “ジェネレーションギャップ”について
病原体は、有用な突然変異という形で新しい病原体戦略を蓄積し、それが自然選択によって集団の中に固定化される。一方、宿主である私たちは、病原菌の攻撃対象として、適切な抵抗力を身につけなければならないが、この抵抗力もまた、ランダムな突然変異によって獲得される。これらのことから、私たちは遺伝学的な宿題をこなし、病原体の新しい病原性戦略に、より新しい相補的な抵抗性戦略で対抗している限り、問題はないだろうと考えるかもしれない。しかし、この闘いには恐ろしい非対称性が存在する。それは、突然変異が進化的に意味を持つためには、一般に、生殖細胞系列に固定され、ある世代から次の世代へと受け継がれなければならない、というものである。つまり、大まかな第一近似値として、固定化の速度、ひいては進化の速度は、時間、日、週単位ではなく、世代単位で測られる。しかし、多くのウイルスや一部のバクテリアの世代時間は20分程度であるのに対し、私たちの世代時間はせいぜい20年である。つまり、20分と20年の差は525,000倍強となり、非常に大きな「世代間ギャップ」が存在することになる。したがって、このような病原体は、私たちが生殖細胞系列にコードされた潜在的な抵抗性戦略で対応するよりも50万倍も速く、遺伝性の潜在的な病原性戦略を新たに進化させることができる。このように病原体が進化的に非常に有利であることを考えると、私たちはいったいどうやって生き延びてきたのだろうかと疑問に思うかもしれない。
この問いには少なくとも2つの答えがある。一つは、すべての真核生物に当てはまることで、真核生物は原核生物に比べて遺伝的ドリフトによって生じた突然変異をはるかに多く保持することができるという事実に基づいている。したがって、真核生物は、将来の問題に対する潜在的な遺伝的解決策を大量に保有しており、このことが、少なくとも部分的には、世代数の短い病原体に有利となるはずの天秤を均等化させているのだろう。
もう一つは、原核生物の病原体が世代間ギャップによって非常に有利な立場にあるにもかかわらず、私たちはどうやって生き延びているのかという疑問に対する、全く異なる答えが適応免疫システムによって生まれた。適応免疫では、生殖細胞から細胞体へ淘汰を移すという単純だが効果的なトリックによって、世代間ギャップが本質的に解消される。このプロセスについては、第4章でより詳しく述べる。
1.11免疫の進化
最初の自由生活型真核生物は、おそらく単細胞のアメーバ状の生物で、浅い沿岸海域を這い回り、出くわしそうなバクテリアを食べていたと思われる。このような小さな生物は、もちろんエネルギーや代謝資源のエルドラドであったろうし、そうでなければむしろ荒涼とした環境であったろうから、近隣のあらゆるウイルスやバクテリアの自然な標的となったであろう。そのため、アメーバは近隣のウイルスやバクテリアの格好の標的となったことだろう。初期の単細胞真核生物が直面した課題を過小評価してはならない。なぜなら、彼らは数多くの全く異なる種類の脅威に同時に対処することを余儀なくされたからだ。トランスポゾン、ウイルス、バクテリア、その他の捕食者すべてが彼らの存在を脅かし、その作用機序が大きく異なる複数の防御戦略の選択を促したことだろう。免疫防御においては、どんなに奇妙な戦略であっても、それが機能し、その結果、適応度の向上につながるものであれば、歓迎され、採用されることになる。その一例が、自由生活するアメーバがウイルスによる破壊から個体群を守るために用いている手段である。アメーバは、巨大なミミウイルスに攻撃され、細胞質内にウイルス工場と呼ばれる施設を作られる。この工場でミミウイルスは子孫を作り、宿主であるアメーバ細胞は溶解される。しかし、ミミウイルスの生活はバラ色ではない。アメーバの細胞質にあるミミウイルスの「工場」に忍び込んだ小型のマウイルスに攻撃され、そこに集中するリソースをハイジャックされてしまうからだ。さらに、アメーバの中には「敵の敵は味方」とばかりに、ミミウイルスを自分のゲノムに組み込んでしまう種もある。ミミウイルスがこのようなアメーバを攻撃すると、組み込まれたマウイルスは活性化され、ミミウイルスとマウイルスの両方の粒子が形成されるように複製を開始する。感染したアメーバ細胞は死滅するが、大量に生成されたマウイルス粒子によって、隣接するアメーバへのミミウイルス感染の効果は2〜3桁減少する[11]。このようにして、アメーバはミミウイルスの天敵を捕まえて、自分たちの集団を守っている。
少しでも役に立ちそうなことは何でもやってみようという姿勢が、免疫系の最初の多様性に拍車をかけ、その後の数多くのバリエーションを生み出す舞台となったのだろう。アメーバは、それが何であれ、まず第一に、這い回る免疫系である。もちろん、免疫防御が分子レベルでどのように発展してきたかは分からないが、その大枠はかなり明確に分かっている。なぜなら、免疫の歴史は、巧妙さを増す病原体の毒性戦略に対するパニック反応の長い一連の流れだからだ。少しでも役に立ち、宿主の適応度を向上させるような新しい抵抗メカニズムは、ランダムな突然変異と自然淘汰によって磨かれ完成され、免疫兵器に組み込まれるようになる。免疫防御に関わる遺伝子がゲノムの中で最も速く進化する要素の一つであるという事実は、進化の過程でこのようなことが何度も起こったこと、そしてこの過程に終わりがないことを示している。
免疫系は、資源の投入と適応度との最適な妥協点がしばしば予期せぬ形で模索される比類なき例である。しかし、病原体に対する防御という、一見単純に見える免疫の主な役割は、無数の「もし」や「しかし」で囲い込まれている。病原体の攻撃の初期段階では、分子的な考察をしたり、考え直したりしている暇はない。必要なのは、すぐに適用できるハードウエアで構成された自然免疫反応なのである。しかし、その一方で、病原体はどのような防御機構も回避する方法を進化させる可能性がある。そのため、生得的な防御機構は、理想的には冗長で、多様で、別の分子カテゴリーに基づいたものでなければならない。このようなシステムが必要なスピードで機能するためには、ハードワイヤーによる反応だけでなく、ある種の記憶も重要な要素となる。一度直面し、克服した脅威の性質を思い出す能力があれば、二度目の対処が容易になるからだ。さらに、防御システムは迅速なだけでなく、適切であることが極めて重要である。防御システムは、病原菌を効果的に中和し、共生生物、常在菌、「自己」組織を攻撃しないようにしなければならない。最小限の遺伝子数でこれらすべてを実現し、しかも環境条件が急速に変化することが多い中で、種の中の各個体が生き残るための最良のチャンスを与えなければならない。特に、病原体に比べて世代時間が長い動物では、生殖細胞系列で適切な抵抗力を獲得することは危険な賭けとなる。そこで、免疫は生殖細胞系列だけでなく、体細胞系列の適応メカニズムを利用して、その賭けをヘッジする手段を進化させた。
適応度の最大化には、生存して繁殖力のある子孫を残す数を最大化することが含まれる。この生殖に不可欠な事業から資源を奪うような活動は、必然的に適応度の低下につながる。このような観点から見ると、免疫とは、まるで明日がないかのようにエネルギーと資源を浪費する、驚くほど無駄の多いシステムであるように思われる。例えば、ヒトの場合、顆粒球やリンパ球などの免疫細胞は毎日何億個も作られるが、ほとんどすぐに破壊され、使われなくなる。これには膨大なエネルギーと資源が投入されるため、「もっといい方法があるはずだ」という思いに駆られることが多い。しかし、それは有用な観点ではない。免疫は進化的に安定した戦略である。なぜなら、免疫によって得られる適応度利益は、明らかに資源を浪費することによって生じる適応度損失を補って余りあるものだからだ。本書の残りの部分では、時に奇妙に見える免疫のメカニズムによって達成される、資源の消費と適応度との間のこのバランスについて見ていくことにする。
第5章 軍拡競争の裏側
第3章と第4章を読むと、病原体はもうとっくに問題ではなくなっているはずだ、と思うのも無理はないだろう。結局のところ、免疫受容体のレパートリーは、あらゆる種類の病原体を「見る」ために選択されたものであり、その情報が生み出す強力なエフェクター機構は、すべての侵入者を確実に破壊できるはずなのだ。宿主と病原体の相互作用は常に軍拡競争であり(1.9節参照)、宿主による効果的な防御行動は、病原体の新しい病原性戦略の進化を促す選択圧にしかならないからだ。そして実際、ランダムな突然変異と淘汰によって、病原体は免疫系の受容体を回避し、その後のシグナル伝達経路を妨害し、補体、顆粒球、CD8+Tキラー細胞などの末端エフェクターシステムから逃れるためのあらゆる種類の方法を獲得してきた。そして、新しい病原体の病原性戦略は、宿主の新しい抵抗機構を選択する原動力となる。これは、あるときは病原体が、またあるときは宿主が、短期間のうちに優位に立つための終わりのない闘いである。
病原体と宿主の間の闘いでは、双方に明確な優先順位がある。このR0は、1人の感染者から派生する二次感染者の数として定義される。R0が1.0より小さければ、病気の広がりは限定的である。しかし、R0が1.0より大きい場合、感染宿主の数は増加し、値が高いほど流行する可能性が高くなる。どのような病原体であっても、R0は病原体の感染メカニズム、免疫防御に直面して宿主の中でライフサイクルを完了する能力、宿主の集団構造など多くの要因に依存する。
若くて愚かな病原体は、宿主を苦しめ、やがて死に至らしめるような毒性攻撃を行うかもしれない。この場合、病原体は、R0値を1.0より大きくするためには、新しい犠牲者を得るための方法を素早く見つけなければならない。例えば、肺ペストの原因菌であるYersinia pestisは、このような経路を辿っている。しかし、宿主の集団の構造が、病原体の攻撃を和らげることで宿主の適応度を向上させることができる場合がある。宿主の寿命が延び、病原体が次の犠牲者を見つけるまでの時間が長くなる。このようなシナリオは、1950年代のオーストラリアで、ウサギの個体数をコントロールするために、毒性の強い粘液腫症ウイルスが大陸中に意図的に放たれたときに、リアルタイムで確認された。最初に放たれたウイルス株は、感染から死亡までの平均時間が11日という「99.5%の殺傷力」を持つものであった。しかし、この毒性レベルはウサギの個体群構造に最適ではなく、感染から死亡までの期間が23日にまで増加した変異型「90%キラー」がすぐに出現し、野生では初期株に代わって自然選択された[1]。
病原体の毒性が低下し、感染可能な期間が延びると、宿主集団が何らかの方法で病原体を許容しないまでも、少なくとも武装中立の状態で共存することを学習し、生存様式を確立することにつながるかもしれない。黄色ブドウ球菌はこの種の例である。黄色ブドウ球菌は、人類の3分の1の鼻の中に永久に、しかし静かに生息しており、さらに3分の1の鼻の中には断続的に存在している。通常、黄色ブドウ球菌は何の害も及ぼさないが、生理的ストレスや免疫力の低下があると、全身性の敗血症を引き起こし、死に至らしめる怪物と化すことがある[2]。
5.1病原体と折り合いをつけること
宿主にとって、感染に伴う適応度低下を回避する一つの方法は、病原体に出会うリスクを減らすように生活を組み立てることである。線虫C. elegansは、細菌を「食用」か「おそらく病原体」のどちらかに分類している。この区別がどのようにしてなされるのかはよくわかっていないが、線虫は神経細胞で発現するTLRドメインを含むタンパク質の助けを借りて、皿の上で病原体セラチア菌が増殖している場所を積極的に回避することに成功している[3]。同様に、キイロショウジョウバエの幼虫は特定の病原体に汚染された食物を避けるし[4]、人間も性感染症を避けるためにコンドームを使用するなど、このような戦略をとっている。しかし、危険な行動を避けることで常に病原体を抑えることができるわけではない。よく知られているのは結核菌で、この病原体を獲得するための主な危険因子は呼吸である。
宿主が病原体を避けることができない場合、第二の方法として、双方の利益になるような取り決めをすることが考えられる。例えば、ミジンコの仲間であるオオミジンコが、細菌の病原体であるPasteuria ramosaに感染した場合である。病原体を食べてミジンコの腸に付着するところから感染が始まる。Pasteuriaが付着する構造物は多形であり、病原体の異なる株は、この多形のうちの一つまたは別のものを認識する能力を進化させてきた。このようにして、ミジンコの多型耐性対立遺伝子は、細菌の多型病原性対立遺伝子と一致するようになる。ミジンコの特定のクローンが拡大すると、やがてその病原体遺伝子と一致する菌株に攻撃されるようになる。この感受性の高いミジンコの集団は、それに適合する病原体の集団とともに、ミジンコが破壊されることで崩壊し、現在の病原体に耐性を持つ、それまでマイナーだった系統に取って代わられることになる。このミジンコの集団は、遅かれ早かれ、今度は病原体に適した毒性対立遺伝子を持つ菌株に見つかり、攻撃されるようになる。このいわゆる負の周波数依存淘汰は双方にとって有利な状況である。病原体のどの株も、不均質なミジンコ集団のすべてのメンバーに感染することはできないし、同様に、多型のパスツリア株のすべてに耐性を持つミジンコも存在しないからだ。その結果、Pasteuria ramosaによってミジンコが全滅することはなく、Pasteuria ramosaが攻撃するミジンコを使い果たすこともない[5]。
第三のアプローチは、「殺し屋」戦略であると言えるかもしれない。『種の起源』の第4章で、ダーウィンは「自然淘汰ができないことは、ある種の構造を、他の種の利益のために、何の利点も与えずに修正することである」と指摘している。しかし、ある種が別の種を自分の目的のために奴隷化し、無慈悲に利用することは実際に起こり得ることである。例えば、トキソプラズマ・ゴンディという原虫は、ネズミを含む多くの温血動物に寄生するが、有性生殖期を終えるのは猫だけである。したがって、トキソプラズマにとって、最後は猫の中に入ることが利益になる。この目的を支えているのが、感染したげっ歯類が猫に対する恐怖心を失うようにする能力である。恐怖心を失ったネズミは、やがて猫の餌となり、猫の腸管上皮にトキソプラズマを送り込むのである。このやり方は、ブラジルの蛾Thyrinteina leucoceraeの毛虫の場合に極致に達する。寄生蜂がこの蛾の毛虫に卵を産み付ける。この卵は幼虫に成長し、やがてイモムシの表皮に穴を開けて出てきて蛹になる。この時、スズメバチの蛹は無防備なため、他の昆虫に食べられてしまう。しかし、スズメバチの幼虫のうち数匹はイモムシの中に残され、よくわからない方法でイモムシの心を乗っ取り、ゾンビガードに変えてしまう。イモムシは餌を食べるのをやめ、代わりに蛹の上に立ち、近づいてくる虫に激しく頭を振りかざす。野外実験では、これによってスズメバチのサナギの捕食が約50%減少した。1週間後、スズメバチが蛹の中から出てくると、ゾンビは死んでしまう[6]。同様の現象は、免疫防御戦略でも見られる。1.11節で、ミミウイルスがアメーバを攻撃して殺すという状況を説明した。アメーバの中には、ミミウイルスが子孫を形成する細胞質部位に寄生するマウイルスの助けを借りて、これに対抗する株もある。アメーバはマヴィルスのゲノムを自分のDNAに組み込み、ミミヴィルスが宿主を攻撃するまで、組み込まれたマヴィルスは静かに待機している。ミミウイルスの転写因子は、この組み込まれたマビウイルスのサイレントコピーを活性化し、アメーバの細胞質内のミミウイルス集合部位を攻撃する。他の昆虫の幼虫に卵を産み付ける寄生蜂の多くも、同じようなシステムを用いている。彼らは、自分のゲノムに組み込まれた「家畜化された」ウイルスを利用して、宿主の免疫防御システムをダウンレギュレートする様々な異なる病原性戦略を生み出し、寄生した宿主の中で子孫を守る[7]。
5.2自然免疫系に対抗する病原体戦略
病原体は、自らの適応度を最大化するために、病原性と感染性のバランスを取るように働いており、この方程式における主要な要因は、もちろん宿主の免疫防御に対抗する能力である。どの病原体も、少なくともある程度は免疫の裏をかく方法を見つけており、その方法はそれぞれ異なっている。ランダムな突然変異と淘汰が、病原体の毒性戦略をどのように最適化するかについて、一般的な概念はほとんどない。しかし、少なくとも脊椎動物では、病原体の戦略を、自然免疫からの回避のみを目的とするものと、適応免疫からの回避というはるかに野心的な目標を目的とするものとに大別することができる。ほとんどのヒトの病原体は、おそらくその両方を行おうとしており、その目的を達成するために複数の病原性メカニズムを用いている。つまり、病原体の病原性を見ることは、むしろ膨大な細部のリストに直面することになる。とはいえ、これらの詳細は最終的には生死にかかわる問題であるため、いくつかの例を見てみる価値はあるだろう。
5.2.1自然免疫受容体のレパートリーから隠れる
病原体の間で人気のある戦略の1つは、自然免疫で利用可能な限られた数の微生物検出レセプターから見えなくなる方法を見つけることだ。多くの病原性細菌は、粘性のあるコーティングで表面全体を覆うカプセルを作るという簡単な手段でこれを実現している。この厚いネバネバしたカプセルは一般に多糖類でできているが、今回もまた避けられない例外がある-この場合は重合グルタミン酸でできたバシラス・アンソラシスである。カプセルは、自然免疫受容体によって検出されるはずの微生物表面のリガンドを覆い隠し、カプセルに入った細菌を見えなくしてしまう。さらに、マクロファージや樹状細胞は表面のぬるぬるした部分に「歯が立つ」ことが難しいため、貪食されにくく、適応反応を起こすのに必要なペプチド-MHC複合体が作られないため、適応免疫も阻害される。莢膜は重要な病原性の特徴であり、莢膜を失うと病原性が低下するか消失する。とはいえ、自然淘汰は決してタダ飯を食わせるものではない。なぜなら、カプセルは宿主組織との相互作用に必要な細菌の表面構造を覆い隠すので、病原体自身の病原性メカニズムの幅を狭めるからだ。
おそらく、カプセルにはこのような代償があるため、一部の細菌性病原体は、同じ目的を達成するために、より思い切った方法を進化させてきたのだろう。免疫防御は、「オール・オア・ナッシング」ではなく、病原体の毒性と宿主の抵抗力の微妙なバランスの上に成り立っている。このバランスをわずかに、しかし決定的に有利にするために、病原体は完全に見えなくなってしまう必要はない。一瞬、ピントがずれてしまうだけで十分なのだ。このような例として、ペストの原因菌であるエルシニア・ペスティスが挙げられる。エルシニア・ペスティスは、古代、中世、19世紀の3回、パンデミックを引き起こした。このうち、最もよく知られているのは、中世の大流行である。1346年、モンゴル軍がクリミア半島の黒海沿岸にあるジェノバの港町カッファを襲ったとき、初めてその存在が明らかになった。この都市は大きく、2つの同心円状の城壁で守られており、海からの供給も可能であったため、包囲は長引いた。1347年の春、突然の伝染病で金色の種族が壊滅し、戦いは収束した。モンゴル軍は包囲を放棄したが、その前に死んだ仲間を城壁の上から投擲し、町に病気を持ち込んでしまった。カッファの市民は何千人も死亡し、ここから黒死病はヨーロッパに容赦ない行進を始めた[8]。
ペストには大きく分けて、肺炎型と敗血症型の2種類がある。この2つの型はR0値が非常に異なっている。ペストは、最も一般的なものである。感染したネズミからノミが感染することによって広がる。この病気は深刻で、治療しなければ10日以内に多くの犠牲者が死ぬ。しかし、ペストは一般的にR0が限られているため、大流行するような病気ではない。パンデミックは、エルシニア・ペスティスがペストの犠牲者の肺に到達して大当たりしたときに発生する。この時、病気は肺炎型に変化し、エアロゾル感染によって急速に広がっていく。この肺炎型はノミによる感染よりもはるかに効率的であるため、3大パンデミックを引き起こしたのはこの肺炎型であった。しかし、少なくとも当初は、最も一般的なのはペストであり、エルシニア・ペスティスには問題がある。R0値が1.0を超えるためには、急速に増殖する必要がある。なぜなら、この菌は媒介としてノミに依存しており、ノミは大量の血液を飲まないからだ。しかし、ノミは大量の血液を飲まない。ノミが血液を飲むと、ペストの被害者の血液中に膨大な数の細菌が存在することになる。そのためには、エルシニア・ペスティスが可能な限り高速で複製される必要がある。適応免疫系が働く前の10日間ほどで、感染のサイクルを完了させなければならないからだ。この競争に勝つために、エルシニア・ペスティスは印象的な病原性因子を備えている[9]。最も早く作用する因子の一つは、LPS分子のリピドA部分の構造変化に着目したものである。
リピドAはLPSの生物学的活性成分であり、TLR-4システムによって認識される(3.5.1項参照)。通常6本の脂肪酸鎖を持つため疎水性であり、これらはその作用に不可欠である。LPSの生合成の際、細菌はこの6本の脂肪酸鎖を2段階で付加する(第1段階:4本、第2段階:2本)。エルシニア・ペスティスでは、最後の2本の脂肪酸鎖を付加するアシルトランスフェラーゼ酵素は温度に敏感である。ノミの体温は26℃前後と推定され、そこで通常のヘキサアシル型LPSを生産することで十分に機能する。しかし、宿主であるヒトの体温が37℃まで上がると、酵素は活性を失い、疎水性の脂肪酸鎖を4本持つLPSが形成されるだけである。この「テトラアシルリピッド-A」型は、ヒトのTLR-4を刺激することができない。ペストのマウスモデルと、中世のパンデミックに関連したエルシニア・ペスティスのバイオバルを使って、この温度感受性アシルトランスフェラーゼを大腸菌の非温度感受性バージョンに置き換えるだけで、Y. pestisが致死的病原体から無害な細菌に変わることが示された[10](英語)。ここで留意すべきは、エルシニア・ペスティスの存在を検出できる自然受容体は、決してTLR-4だけではない、ということだ。しかし、TLR-4の故障は、おそらくシグナル伝達ネットワークで行われている計算を混乱させることによって、病原体に有利なスタートを与え、その結果、TLR-4からの入力がなければ、他の受容体は脅威に対して適切かつタイムリーな防御を行うことができなくなる。一方、エルシニア・ペスティスがTLR-4による検出をかわすことができなければ、他のすべての病原性メカニズムがそれを救うことはできない。この意味で、テトラアシルリピドAは、黒死病の流行を可能にした分子であった。胃潰瘍を引き起こし、胃癌の発生に関連するヘリコバクター・ピロリなどの他の病原体も、ヘキサアシルリピドAをテトラアシル型に変換することにより、そのLPSがTLR-4受容体システムから見えなくなることを利用することを学習した。
5.2.2自然免疫反応の妨害
カプセルの形成によって自然免疫系の受容体を見えなくしたり、テトラアシルLPSの使用などのトリックによって個々の受容体をかわすことは、病原体が自然免疫から逃れるために用いる手段の1つである。もう一つは、初期の感染症の検出を協調的な反応に変換する情報処理システムをハッキングすることである。このシステムは、反応する各細胞で働くシグナル伝達経路から、これらの細胞が他の細胞と情報を共有するためのサイトカインや他の分子まで広がっている。この情報処理ネットワークは病原体にとって格好の標的であり、病原体によって操作されていない細胞内シグナル伝達経路や細胞間情報伝達系はおそらく一つもないだろう。
末端エフェクターシステムもまた、病原体によって破壊されてきた。ファゴサイトーシスはその一例である。ファゴサイトーシスは、侵入してきた微生物の破壊に用いられる主要なメカニズムであるが、すべての病原体がファゴサイトーシスを避けようとするわけではなく、細胞内に自分たちのためのニッチを確立するためにファゴサイトーシス経路をハイジャックするものもいる。このような病原体は、一旦ファゴサイトーシスに取り込まれると、エンドソームとリソソームの融合から何とか逃れなければならない。その方法は一つではない。Listeria monocytogenesのように、エンドソーム膜を溶かして細胞質へ逃れるものもある。一方、サルモネラ菌は、全く異なる方法でリソソームの手による死を回避する。エンドソームからメディエーターを放出し、エンドソームとリソソームの融合に必要な細胞の微小管系をブロックすることで、エンドソームを安全な場所に変えるのだ[11]。このようにして、サルモネラは、リソソームだけでなく、細胞質内のすべての自然免疫受容体からも安全な、細胞内の複製ニッチを確立する。エンドソーム膜のタンパク質NRAMP-1は、エンドソーム液胞から2価の陽イオンを汲み上げ、細菌に不可欠な成長因子を与えないようにするのだ。サルモネラ菌のような病原体は、2価の金属イオンを非常に高い親和性で結合できるシデロフォアという低分子を合成して分泌することでこれに対抗する。そして、細菌は受容体を用いて、金属イオンを除去することができたシデロフォア分子を結合し、体内に取り込むのである。このことから、エンドソームが昔も今も主要な戦場であり、サルモネラのような細菌性病原体は、宿主がそのニッチでの生活をできるだけ不愉快なものにしようと努力する一方で、自分のニッチを住みよいものにしようと絶えず奮闘しなければならないことがわかるだろう。
5.3適応免疫の回避を図る病原体の戦略例
脊椎動物の宿主の中で10〜12日以上生存することを必要とする感染サイクルを進化させた病原体は、適応免疫を回避する能力を身につけなければならない。適応システムもまた、細胞内および細胞間の情報処理に依存しており、病原体は様々なレベルでこれらの情報処理を妨害する手段を進化させてきた。また、αβT細胞の受容体はペプチドという形で間接的に標的を検出するため、適応免疫から構造を隠そうとする試みはより困難である。ほとんどの病原体に対する適応免疫からのメッセージは、ジョー・ルイスのスローガンである「逃げることはできても、隠れることはできない」に集約される。しかし、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)、ヒトサイトメガロウイルス(HCMV)、結核菌、トリパノソーマ・ブルセイなどの病原体は、適応免疫の前になんとか隠れ、生き延びようと工夫している。これらの病原体が用いる典型的な戦略は、「ブルートフォース」、「死んだふり」、「未来に隠れる」という見出しで要約することができ、もちろん多くの病原体はこれらのうちの一つ以上を同時に用いている。いくつかの例を見る前に、病原体が適応免疫を回避するメカニズムについては、研究が困難な分野であることを指摘しておく必要がある。免疫とは、組織化されたリンパ組織で情報を交換する多くの異なる種類の細胞が関与する複雑なシステムであり、これらのプロセスは試験管内試験の実験では十分にモデル化することができない。しかし、動物実験にも限界がある。というのも、異なる種の免疫システムは、異なる環境、ひいては異なる病原体に対処するために選択されたものだからだ。ヒトのすべての感染症が、動物実験で正確にモデル化できるわけではない。
5.3.1適応免疫の検出ハードウェアを破壊する
病原体が長期間の感染を成立させるために用いる戦略の一つは、適応免疫系を直接攻撃することである。この種のものとしては、おそらくHIVが最もよく知られている。HIVは、適応免疫の中心的な制御細胞である活性化CD4+T細胞に感染して破壊することによって、頸動脈を直接狙うのである。そうすることによって、ウイルスは未治療の患者において、感染と戦うための適応免疫の能力が徐々に低下していくのを確実にする。
HCMVも適応免疫の裏をかくことができるが、HIVに比べるとより巧妙な方法を用いている。HCMVは実際に適応免疫を回避することはできないが、適応免疫を遅らせることはできる。そのためにHCMVが用いるメカニズムの中で最も重要なものは、ウイルス感染細胞を破壊するCD8+Tキラー細胞の効果を低下させるものである(Sect.4.12.1)。キラーT細胞は、感染細胞の表面に発現しているMHC-Class I-ウイルスペプチド複合体を検出する。これらの複合体は、生産的に感染した細胞内に存在するウイルスタンパク質がプロテアソームによってペプチドに分解され、「TAP」複合体によって小胞体に運ばれてMHC-クラスI分子に結合し、細胞表面に移動することで形成される。HCMVはこれらのプロセスをいくつかの点で妨害し、感染細胞上に十分なMHC-Class-I複合体が発現しないようにし、CD8+キラーT細胞からは本質的に見えないようにする。一見すると、病原体側の必勝法のように思えるが、多くのウイルスがこのようなことを行うため、自然淘汰によって「ナチュラルキラー」(NK)細胞からなる自然免疫系がバックアップされるようになったのは驚くことではない。NK細胞はT細胞やB細胞レセプターを発現しないリンパ球で、その代わりにMHC-Class-I分子(3.6.6項参照)を認識する一連の自然免疫系レセプターを発現している。彼らは体内をパトロールして、表面にMHC-Class-Iを発現しているかどうか、他の細胞をスクリーニングする。もし、MHC-Class-Iを発現していない細胞に出会ったら、それはウイルスに感染した細胞ということになり、NK細胞はその細胞を殺すことになる。しかし、HCMVは、その産物が感染細胞の表面で発現し、あたかもMHC-Class-I分子のように見える遺伝子を進化させ、反撃に出た。そして、それは延々と続く。
5.3.2死んだふり
適応免疫の注意を避けようとする病原体は、潜伏感染を成立させることによって、できるだけ目立たないようにしようとするかもしれない。潜伏感染は、理想的には、何らかの細胞の種類や構造の中に静かに潜んで見えなくなる。しかし、潜伏感染に成功すればするほど、新しい宿主に感染する可能性は低くなる。おそらくこのような理由から、この戦略をとる病原体は宿主の中で2つの集団を維持する傾向がある。1つは潜伏状態にあり、もう1つの活発な集団は適応免疫の危険にさらされながら、移動するチャンスをうかがっている。その結果、この2つの集団の利害が少しづつずれていくことになるかもしれない。活動的な病原体集団は進化の行き詰まりを迎え、新しい宿主の存在を忘れ、代わりに現在の宿主の新しい細胞に感染する能力でその成功を計るかもしれない。これとは対照的に、潜伏病原体集団は、おそらく活動中の病原体集団から、免疫が少し低下していることを示す何らかのサインを待ち、今こそ目を覚まして新しい宿主に感染するチャンスを掴もうとするかもしれない。HIVがとる感染戦略には、ある程度このような分岐が見られる。HIVは感染時にCD4+T細胞に感染するが、そのような細胞がすべて等しく扱われるわけではない。いくつかのCD4+メモリーT細胞は潜伏感染しているかもしれない-それらは「死んだふり」をしているウイルスを含んでいる。しかし、感染した細胞の大半は生産的に感染しており、したがって新しい細胞を感染させるウイルスを絶えず作り続けている。なぜなら、HIVの感染は非常に変異しやすいプロセスだからだ。
HIVは新しい細胞に侵入すると、まずウイルスにコードされた逆転写酵素を使ってRNAゲノムをDNAに変換する。ライフサイクルのこの段階では、その逆転写酵素がエラーを起こしやすいため、致死的なレベルの突然変異を拾ってしまう危険性がある。さらに、逆転写の際にウイルスゲノムに変異を導入する宿主のAPOBEC3Gシチジンデアミナーゼは、HIVのvif遺伝子の産物によって破壊されるが、このプロセスは不完全で、APOBEC3Gの変異原性効果は減少しても消滅しない。このように、ウイルスが新しい細胞に感染するたびに変異が起こり、変異種は生き残る能力によって選択され、新しい細胞に感染するようになる。現在の宿主の中で長期的に生存するために最適化しても、最適な感染のための理想的な特性を生み出すとは限らない。このことは、宿主内での超変異によるHIVの進化の速度が、疫学的なレベルで追跡した場合に、HIVの配列の進化の速度よりも速い理由を説明することができるかもしれない[12]。
結核菌は、ヒトを殺す最大の細菌であるが、死んだふりをすることで適応免疫を回避する第2の病原体でもある。人間の3人に1人が感染していると推定されるが、感染者の約90%は何の症状も示さない、つまり潜伏感染していると言われている。なぜだろう?結核菌は通常、マクロファージが病原体を貪食し、T細胞が反応することによって制御されている。マクロファージは結核菌を消化不良と判断し、肉芽腫と呼ばれる組織化された構造物を作る。肉芽腫は、脊椎動物、無脊椎動物を問わず、多くの生物が病原体や無生物の粒子を包み込んで封じ込めるために利用する。1つの宿主種内で異なる課題に応答して、異なるタイプの肉芽腫が形成される。そして、与えられた課題に対する応答は、異なる宿主種で異なることがある[13]。
ヒトの肺で結核菌を包む肉芽腫は、マクロファージとT細胞の両方を含み、線維性被膜に囲まれていることもある。肉芽腫の中心部は実質的に無酸素状態であり、死細胞で満たされていることもある。このような構造の形成は、病原体を制御するための素晴らしい宿主の計画のように聞こえるが、病原体は、この一見馬鹿にできない宿主反応に対抗するために、驚くほど多くのメカニズムを進化させてきた[14]。第一に、結核菌は、肉芽腫という非友好的な環境の中で休眠状態で生き残る、実に驚くべき能力を持っている。第二に、この潜伏感染状態においても、しばしば「スカウト」と呼ばれる活性のある菌が肉芽腫の外側に存在していることである。このように、潜伏感染とは、免疫系、活動的な「斥候」、および肉芽腫の中の休眠細菌の間のバランスのことである。このバランスが崩れると、例えばHIVによって免疫力が低下した場合、再活性化し、病気になる可能性がある。この再活性化がどのように行われるかは議論の余地があるが、活動的な偵察隊が可溶性の「蘇生促進因子」を分泌し、休眠状態の細菌の再活性化を助けているのかもしれない。このような戦略によって、結核菌は限りなく完全な病原体に近づいており、それが対策を難しくしている。
また、ヒトの病原体で死んだふりをすることがあるのがHCMVである。経済先進国では人口の40%以上、低開発国では100%近くが感染している。HCMVはヒトに特異的であり、細胞株を用いた研究の価値は低く、また適切な動物モデルもないため、この病原体の感染サイクルを研究することは非常に困難である。しかし、このウイルスがヒトの多くの異なる細胞型に感染することは明らかであり、その結果も細胞型によって異なることも明らかである。造血前駆細胞のようなある種の細胞では、ウイルスは潜伏感染を確立し、「死んだふり」をする。しかし、他の細胞型では、新しいウイルス粒子が生産されるという意味で、感染は生産的であり、健康な個人では、尿や唾液中にウイルスが分泌されても、感染の明らかな兆候はない[15]。このように、ウイルスは拡散することができるが、同時に免疫系とのバランスを確立することで、生涯にわたって不顕性感染が可能な状態にある。もし、移植患者やAIDS患者のように、免疫系の機能不全によって宿主と病原体の間のバランスが崩れると、ウイルスは制御不能に陥り、生命を脅かす病気を引き起こす可能性がある。
5.3.3免疫の未来に隠れる
適応免疫から逃れるために病原体が用いる第三の戦略は、常に形を変え、免疫がそれを認識する受容体を持つリンパ球を選択し拡大する頃には、別のものに変わっているようにすることである。HIVは、逆転写の際にゲノムを超変異させることで、免疫の考えつくあらゆるものに対する変異種を生み出して、これを回避している。しかし、このやり方は、ある種の真核生物の寄生虫が採用する「抗原変異」戦略において、最高の形となる。
アフリカ睡眠病は、ツェツェバエが媒介する真核生物の病原体トリパノソーマ・ブルセイに感染することで発症する。この単細胞寄生虫は、感染者の血液中を泳ぎ回り、鞭毛を使って自らを推進させる。細胞内や肉芽の中に隠れることがないため、自然免疫や適応免疫のあらゆる武器にさらされる。それにもかかわらず、トリパノソーマは生き延びている。では、なぜトリパノソーマは生き延びることができるのだろうか?その答えは、自然免疫にも適応免疫にも耐性を持つように選択された表層の性質にある。血液中のトリパノソームは、「可変表面糖タンパク質」(VSG)のコピーで覆われている。VSG分子は細長いので、トリパノソーマの表面にある他のすべてのものを免疫系から物理的に遮蔽している。免疫系が見ることができるのは、細長いVSGタンパク質分子の外側の先端だけであり、これは自然免疫系のペントラキシン、コレクチン、フィコリンなどの標的にはならない。また、自然抗体も、補体の活性化と寄生体の破壊につながるかもしれない。しかし、トリパノソーマは、このような攻撃から逃れるための手段を進化させてきた。トリパノソーマは表面の分子を高速でリサイクルすることによって、その攻撃を免れているのだ。トリパノソーマは鞭毛によって血液中を移動しながら、表面のVSG分子を鞭毛に向かって常に後方に押し流し、細胞内に取り込み、表面にリサイクルしている。このようにして、表面のVSGプールをすべてひっくり返すには、わずか12分強しかかからない。さらに、VSG分子に結合したタンパク質は、帆のような働きをするので、トリパノソーマの表面を流れる液体の流れによって、より速い速度で鞭毛の方向に押し戻される。このため、自然抗体や受容体が結合したVSG分子は、推定120秒以内に表面から排除される。
このように、トリパノソーマは自然免疫についてはほとんど心配する必要がないのだが、適応免疫については別問題である。トリパノソーマは、VSGで覆われた表面を適応免疫から見えなくすることは困難であり、それをしようともしない。実際、VSG分子は立派な免疫原であり、宿主はこれに対して強い抗体反応を起こす。この抗体はトリパノソーマの表面を飽和状態にし、寄生虫の死を防ぐのに十分な速さで掃き寄せることができない。トリパノソーマの大部分は死滅するが、ごく一部の集団は、抗体が役に立たない変異型VSG構造を常に生成している。この新しいVSG構造を持つトリパノソーマの集団は、免疫学的未来に「エスケーパー」している。この「エスケーパー」集団は急速に拡大し、免疫系は再び新しいVSGに対する抗体を作り始める。しかし、その準備が整うやいなや、集団のごく一部が、再び新しいVSG構造を発現し始める。このようにトリパノソーマは、常に新しいVSG構造を作り出さなければならない。そのために、VSGをコードする約2000の遺伝子を集めてスタートする。しかし、生成可能なVSG分子の数は、この数から想像されるよりも非常に多い。なぜなら、これらの2000の遺伝子(その多くは擬似遺伝子)の情報は、遺伝子変換によって混ぜ合わせ、ハイブリッドVSGを生成することができるからである[16]。要するに、これは無脊椎動物が適応免疫防御システムを形成するために用いた遺伝的トリックの鏡像である(Sect.4.3)。
宿主と病原体の相互作用という観点から、宿主の抵抗性因子と病原体の病原性因子がともに体細胞超変異によって生成されているこの状況を、ミジンコとその細菌病原体パスツーリアとの相互作用と比較すると、それぞれの集団内に「ある」多形の病原性因子と抵抗性因子に基づいている点が興味深い。ミジンコとパスツリアの相互作用では、どちらの側にも時間的な優位はなく、結果として負の周波数依存性淘汰が両者の利益のために働くことになる。しかし、競合する多型遺伝子のセットを体細胞超変異によって生成されたリガンドと受容体に置き換えると、全く異なる結果がもたらされる。宿主はそれに応えなければならないが、適切な適応免疫系受容体を発現するリンパ球の選択と増殖に要する時間によって決定される遅れをもって応じることになる。この遅れが、適応免疫の受容体生成の仕組みに内在するもので、これがトリパノソームに切り札を与え、薬がない限り睡眠病を必然的に致命的なものにしている。
第6章 序文
ここで、最後に、「生物学は進化の観点からでなければ意味をなさない」というドブザンスキーの前提に立ち返ることが適切であろう。これは本当に免疫に当てはまるのだろうか?私たちはそう考えている。進化的なアプローチによって得られる光の価値は、「類似の」システムから得られた洞察が、哺乳類の免疫系がどのように機能するかについての私たちの理解を進めるという規則性の中に見出すことができる。しかし、進化の光はスポットライトではなく、むしろ拡散光源であり、ある面では意味をなしていても、ある面では光に乏しいままなのである。このような暗い部分は、系統発生における絶滅が一因であり、MHC分子の起源や、無顎類から顎口類への適応免疫の転換など、多くの特殊な疑問に対する答えは、進化の時間の霧の中に埋もれてしまったままになっている。また、無脊椎動物のシステムは二次的なものであると考えられがちであるため、ほとんど未解明のままであることも一因である。
しかし、明るい場所では、照明のおかげで、免疫防御システムの奇妙な構造の意味を理解することができる。免疫の進化は、病原体と宿主との間の軍拡競争によるところが大きく、病原体の病原性メカニズムが新しくなるたびに、宿主の病原性戦略の選択が促され、それがまた新しい病原体の病原性メカニズムの選択を促し、・・・という具合に、どんどん進化していった。このように、免疫の進化は整然としたものではなく、病原体と宿主の両方が、生命を脅かす緊急事態から次の緊急事態へと、いかによろめきながら進んでいくかという物語である。そして、命がけで戦っているとき、人は最もエレガントな解決策を考えるのではなく、ただその辺に転がっているものを手に取り、武器として使えるかどうか試してみるのだ。この意味で、進化のトレードマークは、古い遺伝子を借りてきて、新しい問題を解決するためにそれを改修することである。
借りた遺伝子に突然変異で手を加えることもあれば、複数の異なる古い遺伝子の断片をエクソンシャフーリングして、新しい機能を作り上げることもある。借用と組み換えは、攻撃を受けているゲノムに、病原体に対抗するための新しい手段を考え出す可能性を与えてくれる中心的な資源である。このような解決策は、私たちにとっては実に奇妙に思えるかもしれない。
エンジニアやシステムアナリストが、病原菌の攻撃という問題に対する解決策として、驚くほど無駄の多いRAG組み換えプロセスを提案したら、その場で袋叩きにされることだろう。しかし、進化はシステムの優雅さには興味がない。進化が適用する唯一の基準は、「それが機能するかどうか」である。そして、時には非常に奇妙なものが実際に機能することがある。RAG組み換えが「うまくいく」のは、それがもたらす「賢さ」の代償が、適応的免疫系がもたらす「賢さ」の利益と釣り合う以上であるという意味においてである。
免疫の進化は「永久革命」の原則に従っている。何事も全く同じではいられない。分子はそのままでも、その機能は変化する。例えば、抗ウイルス性のcGAS-STING経路は、系統の広い範囲にわたって抗ウイルス防御システムとして機能してきたが、その機能のメカニズム的基盤は、無脊椎動物から脊椎動物へと劇的に変化してきた。同様に、Tollファミリーの分子は、無脊椎動物でも脊椎動物でも自然免疫において重要な役割を果たしているが、ショウジョウバエにおけるTollの役割は、脊椎動物におけるTLRの役割と大きく異なっている。
同時に、この革命的な原理は、冗長性という保守的な原理によって穏健化されている。無脊椎動物におけるRNAiに基づく適応的な抗ウイルス防御は、生来のcGAS-STING経路によって支えられている。この経路は、やや異なる形で、脊椎動物におけるCD8+T細胞に基づく適応的な抗ウイルス防御も支えている。このようなことを認識することは、学生たちが免疫学を神秘的なものと見なさず、詳細の塊としてではなく、むしろ生物学の現在最も魅力的で挑戦的な側面の一つとして見るのに役立つことだろう。
なぜなら、免疫学は病原体の進化を追跡しながら常に変化しており、今日の免疫学者の子供や孫が将来、必ず有益な職に就き、より新しい魅力的な問題を解決することが保証されるからだ。
ベルリンとバーゼル、2019年1月
