Contents
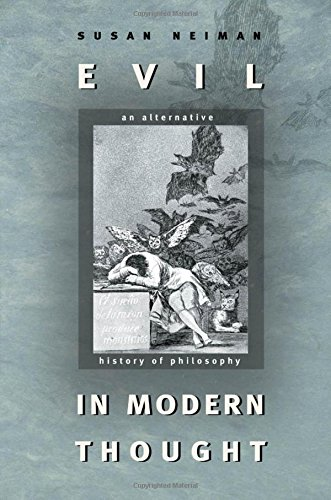
Evil in Modern Thought: An Alternative History of Philosophy
目次
- 謝辞
- はじめに
- 第1章 天からの火
- 神の擁護者たちライプニッツと教皇
- 心のニュートンジャン=ジャック・ルソー
- 分裂した知恵。イマヌエル・カント
- 現実と理性:ヘーゲルとマルクス
- おわりに
- 第2章 建築家を糾弾する
- 原資料バイユの辞書
- ヴォルテールの運命
- 理性の無力さデイヴィッド・ヒューム
- トンネルの終わりサド侯爵
- ショーペンハウアー:法廷としての世界
- 第3章 幻影の果て
- 永遠の選択贖罪をめぐるニーチェ
- 慰めについて フロイトvs.プロヴィデンス
- 第4章 ホームレス
- 地震 なぜリスボンなのか?
- 大量殺人 なぜアウシュビッツなのか?
- 喪失感 近代神話に終止符を打つ
- 意図 意味と悪意
- テロリズム 9月11日以降
- 残されたものカミュ、アーレント、批評理論、ロールズ
- 原点 十分理性
- あとがき
- 備考
- 書誌事項
- 索引
スーザン・ニーマン
プリンストン大学出版局
プリンストン・アンド・オックスフォード
世界で起こったことは理性にも適合して起こったという大前提は、哲学史に真の関心を最初に与えるものだが、それは別の形でしかない摂理への信頼にほかならない。
-ヘーゲル、『哲学史講義』序文
謝辞
この本を書く時間を与えてくれたのは、いくつかの機関による重要な支援であった。シャローム・ハルトマン研究所は、イスラエル国内で最も働きやすい場所を提供してくれただけでなく、研究に時間を割くことができるフェローシップを提供してくれた。ACLSのシニアフェローシップのおかげで、1999年から2000年にかけて執筆の大部分を終えることができた。幸運にも、ロックフェラー財団のおかげで、ベラッジオのヴィラ・セルボーニで最終章の下書きをすることができた。
いくつかの文章の初期バージョンは、以下のエッセイに掲載されている。Metaphysics to Philosophy: Rousseau and the Problem of Evil,” in Reclaiming the History of Ethics: また、「エルサレムにおける神学」(Hannah Arendt in Jerusalem, ed. S. Ascheim), 「Theodicy in Jerusalem」, in Hannah Arendt in Jerusalem, ed. A. Reath, 1997), ”Metaphysics to Philosophy: Rousseau and Problem Evil,” in Reclaiming History of Ethics: Essays for John Raws, ed. S. Ascheim (University of California Press, 2001); and 「What Is the Problem of Evil?」 in Rethinking Evil: Contemporary Perspectives, ed. M. P. Lara (University of California Press, 2001). M. P. Lara (University of California Press, 2001)に収録されている。
この本は長い間制作されていたものであり、この本の制作が始まる前に負った負債を認める機会を与えてくれるものである。私のやり方に全面的に賛成してくれる人はいないが、私に哲学のやり方を教えてくれた人たちに感謝したいと思う。時系列で言えば、分析哲学のリソースを用いて、彼が「全体像」と呼ぶものを明らかにしてくれたバートン・ドレブン、英語圏の哲学に文化のためのスペースを作ってくれたスタンリー・キャベル、哲学史が単に哲学のためのアーカイブではなく、その一部であることを示してくれたジョン・ロールズ、啓蒙主義の短所を十分に認識しながらその長所を維持してくれたマルガリータ・フォン・ブレンダーノ、神学的な疑問を哲学的な議論のための公然のものにしてくれたジェイコブ・トーベスに恩義を感じている。また、多くの友人や同僚がこの原稿を読み、重要な批評と励ましを与えてくれた。Richard Bernstein、Sander Gilman、Moshe Halbertal、Eva Illouz、Jeremy Bendik Keymer、Claudio Lange、Jonathan Lear、Iris Nachum、James Ponetには、多少なりとも深くお世話になったつもりである。彼は、初期の段階から、ここで論じた問題について私がより明確に考えることができるよう、数え切れないほどの時間を費やしてくれた。最後に、イアン・マルコムは素晴らしい編集者であり、その洞察と関与は、本書の最終的な形状の改善に大きく貢献した。ガブリエーレ・カールは専門的で温かみのある秘書的サポートを提供し、アンドレアス・シュルツは参考文献の作成に貴重な助力を与えてくれた。
私の子供たちは、この本の執筆中、いつも以上に負担を強いられたが、いつも以上に優雅にそれをこなしてくれた。私の仕事に忍耐と愛情を注いでくれた彼らへのささやかな感謝として、献辞を捧げます。
はじめに
私たちにとって最も重要な物事の側面は、その単純さと親しみやすさ故に隠されている。(そして、このことは、ひとたび目にすれば、最も印象的で最も強力なものに心を打たれないことを意味している。
-ウィトゲンシュタイン『哲学的考察』129番
18世紀はリスボンという言葉を、今日のアウシュビッツという言葉を使うのと同じように使っていた。このような乱暴な表現にどれほどの重みがあるのだろうか。世界における最も基本的な信頼、文明を可能にする基盤の崩壊を意味するには、地名以上のものは必要ない。それを知った現代の読者は、「地震がこれほど大きな被害をもたらす時代でよかった」と、切ない気持ちになるかもしれない。1755年のリスボン地震は、リスボン市とその住民数千人を破壊し、啓蒙主義を東プロイセンまで揺るがした。イマニュエル・カントという無名の小学者が、ケーニヒスベルクの新聞に地震の本質に関する3つのエッセイを書いた。カントは一人ではなかった。この地震に対する反応は、広範かつ迅速であった。ヴォルテールとルソーは、この地震をめぐってまたもや喧嘩をし、ヨーロッパ中のアカデミーがこの地震をテーマに懸賞論文を出し、6歳のゲーテは初めて疑念と自覚を持ったという話もある。震災はヨーロッパの優秀な頭脳に影響を与えたが、それは彼らだけにとどまらなかった。大衆の反応は、説教、目撃者のスケッチ、非常にひどい詩など多岐にわたった。その数は、現代のマスコミにため息をつかせ、フリードリヒ大王が、震災の数ヵ月後にカーニバルの準備を中止するのはやりすぎだと皮肉ったほどであった。
これに対して、アウシュビッツは比較的冷静であった。哲学者たちは唖然とし、アドルノが最も有名に述べたように、沈黙が唯一の文明的反応であった。1945年、アーレントは、悪の問題が戦後のヨーロッパの知的生活の根本的な問題になるだろうと書いたが、そこでも彼女の予測はまったく的外れであった。この問題については、アーレント自身以外の主要な哲学的研究は英語で発表されておらず、ドイツ語やフランス語のテキストは驚くほど斜に構えていた。歴史的な報告や目撃者の証言は前例のないほど大量に登場したが、概念的な考察は遅々として進まなかった。
哲学者たちがこのような大きな出来事に気づかなかったということはありえない。それどころか、哲学的考察が行われなかった理由の一つに、課題の大きさが挙げられている。ナチスの死の収容所で起こったことは、人類の歴史の中で他に類を見ないほど絶対的に悪であり、人間の理解能力を無視したものだった。しかし、アウシュビッツの独自性と規模の大きさを問うこと自体、哲学的なものである。この問題を考えることは、カントやヘーゲル、ドストエフスキーやヨブ記へと私たちを導いてくれるだろう。アウシュビッツと他の犯罪や苦しみとの関係を問うまでもなく、アウシュビッツを、現代哲学ではほとんど検討されることのない種類の悪の典型として捉えることができるだろう。リスボンでの地震とアウシュビッツでの大量殺人に対する知的反応の違いは、事象の性質だけでなく、私たちの知的構成の違いでもある。何が哲学的問題で何が哲学的反応か、何が緊急で何が学術的か、何が記憶の問題で何が意味の問題か-これらはすべて変化する可能性がある。
本書は、啓蒙主義の初期から20世紀後半に至るまで、自己とその世界における位置についての私たちの理解において生じた変化を追跡するものである。リスボンやアウシュビッツに対する知的反応を研究の中心的な柱とすることは、近代の始まりと終わりを位置づける方法である。疑問と危機のポイントに焦点を当てることで、私たちの指針となる前提が崩れる地点で何がそれに挑戦するのか、つまり、私たちの世界に対する感覚を脅かすものは何かを検証することができる。また、この焦点は、本書の中心的な主張の一つである「悪の問題は現代思想の指導的な力である」ことの根底にもある。哲学史の現代版では、この主張は理解不能というより、むしろ誤りであると見なされていることだろう。なぜなら、悪の問題は神学的なものであると考えられているからだ。古典的には、この問題は次のような問いかけとして定式化されている。善良な神が、どうして罪のない苦しみに満ちた世界を創造することができようか?このような問いは、イマニュエル・カントが、神は古典的形而上学の他の多くのテーマとともに、人間の知識の限界を超えていると主張して以来、哲学の門戸を閉ざしてきたのである。大西洋の両岸の哲学者がひとつにまとまっているとすれば、それは、カントが今後、哲学的に神について言及するだけでなく、他のほとんどの種類の基礎をも禁止しているという確信だろう。この観点からすれば、リスボンとアウシュビッツを比較することは単なる間違いに過ぎない。その間違いは、18世紀に悪という言葉が、人間の残酷な行為と人間の苦しみの両方を指すものとして使われたことを受け入れてしまうことにあるようだ。この間違いは、両方の責任を神に委ねることを厭わない神学者のグループにとっては自然なことかもしれないが、それ以外の私たちを混乱させるものではないはずだ。この考え方では、リスボンとアウシュビッツは全く異なる種類の出来事である。リスボンは、保険会社が自然災害と呼んでいるようなもので、人間の行為の範囲から除外するためのものである。こうして、人間は自然災害を引き起こしたり補償したりするだけでなく、実際的・技術的な面を除いて、自然災害について考える責任さえも免除される。地震や火山、飢饉や洪水は、人間の意味の境界線上に存在する。私たちは、それらをコントロールするために必要なことだけを理解しようとする。伝統的な、つまり前近代的な論者だけが、それらに意味を見出そうとする。それに対して、アウシュビッツは、今日、私たちが悪という言葉を使うとき、その意味するところをすべて表している。
つまり、説明や償いの余地のない絶対的な悪事なのである。もし、リスボンが引き起こした悪の問題があるとすれば、それは正統派にしか起こりえないことである。アウシュビッツが提起した悪の問題は、全く別のものに見える。人間はどうして、合理的かつ理性的な規範の両方を徹底的に侵害するような行動を取ることができるのか?このように、問題が全く異なるものであるという感覚が、現代の意識を特徴づけている。現在では自明のことと思われている自然悪と道徳悪の鋭い区別は、リスボン地震の頃に生まれ、ルソーによって育まれた。この区別の歴史と、問題が分離されることを拒否した方法をたどることが、本書の目的の一つである。
近代をリスボンに始まるものとして位置づける中心的な理由は、まさにその責任を明確に分担しようとする試みにある。この試みをよく見てみると、その皮肉がすべて明らかになる。哲学者たちはルソーのノスタルジアを常に非難していたが、ヴォルテールの地震に関する議論は、ルソーの議論よりもはるかに多くのことを神の手にゆだねていたのである。そして、ルソーが歴史や心理学という近代科学を発明したのも、震災がもたらした問題に対処するためであり、それは神の秩序を守るためであった。皮肉なことに、リスボン以後に生まれた意識は、成熟への試みであった。啓蒙が自分の頭で考える勇気であるならば、それは自分が投げ出された世界に対して責任を負う勇気でもある。それ以前の時代に自然悪と呼ばれていたものを道徳的悪と根本的に分けることが、このように近代の意味の一部であったのである。アウシュビッツがその終わりを示すとすれば、それは私たちの恐怖を示すということである。近代的な悪の概念は、世界の状態を神のせいにするのをやめ、自分たちで責任を取ろうとする中で発展してきた。悪の責任を人間に委ねれば委ねるほど、その種族はそれを引き受けるに値しないように思われた。私たちは方向性を失ったままになっている。知的な教育機関に戻ることは多くの人にとっての選択肢ではないが、成長するための希望は今や空虚に見える。
哲学の歴史は、国家や個人の歴史と同様に、私たちがある瞬間に立っている前提の交わりを当然視してはならないことを教えてくれるはずだ。このことを学ぶことは、哲学が常に目指してきた自己認識の重要な一部である。しかし、哲学史は、十分に歴史的である場合にのみ、そのような知識を獲得することができる。しかし、哲学史は、あたかも私たちの星座やカテゴリーが自明だろうかのように扱われることが少なくない。大まかに言えば、神学的時代から形而上学的時代、科学的時代へと進むというコントの知的歴史観に、私たちはおそらく同意する。このような考え方に立てば、リスボン地震で世界が崩壊した思想家たちは、啓蒙主義のナイーブさへの確信をすべて確認することになる。せいぜい、神学と形而上学の境界線上にいた時代にふさわしい知的未熟さの表れとして、彼らの反応は古風に見えるだけだ。もし、世界が善良で強力な父親によって支配されていると信じるならば、その秩序が理解できるほど公正であると期待するのは自然なことである。その信念を捨てれば、どんな期待も子供じみた空想の残滓に過ぎない。したがって、リスボンが引き起こした知的な衝撃波は、それが注目されたとしても、自力で生きることを学んだ、より悲しくも賢明な時代の産みの苦しみと見なされる。
このような見方は、それ自体、歴史的なものである。というのも、悪の問題を無神論者の用語で述べることほど簡単なことはない。例えば、ヘーゲルへの反論として、「実在は理性と同一ではないだけでなく、両者は関係すらない」と述べることができる。このような観察を行うには、理論は必要ない。数分以上続く世界の観察であれば、何でもいいのである。このようなことが起こってはならないと判断するたびに、私たちは悪の問題へとまっすぐにつながる道に足を踏み入れている。この問題は、厳密に言えば、神学的な問題であると同時に、道徳的な問題でもあることに注意してほしい。倫理学と形而上学、認識論と美学が出会い、衝突し、手を上げる地点と呼ぶことができる。問題は、私たちがその中で考え、行動するためには、世界の構造がどのようなものでなければならないかという問題である。このような疑問は、すぐに歴史的なものになる。なぜなら、最も説明を求めているのは、道徳的判断がどのように正当化されるかではなく、明らかに正当化される判断が、なぜ過去に無視されたのか、だろうからだ。説明を求め始めると、堕落のような神話から、ヘーゲルの現象学のような形而上学に行き着くこともある。大切なのは、その始まりの場所が至って普通であることである。
私は、哲学が始まる場所こそ、哲学が停止する恐れがある場所だと考えている。なぜなら、この場所には、従来、現代哲学の原動力とされてきた懐疑的な認識論的問題よりも、もっと自然で、緊急で、広く行き渡った問いが含まれているからだ。棒が水の中で屈折して見えることに気づいたり、夢があまりに鮮明で、その対象の一つを掴みたくなって、一瞬、眠気を催す半意識になったりすることで、外観と現実の違いについて心配し始めることはあり得ることだろう。しかし、あなたはベッドの中で目を覚まし、必要なら自分の顔を叩き、本当に疑わしいなら水から棒を引き抜く。悪の問題がそれほど簡単に払拭されるのであれば、何百年もの哲学に費やされた膨大な労力は説明の必要がないだろう。
近代哲学は認識論が中心であり、私たちの表象を根拠づけるという欲求に駆られているという図式は非常に根強く、一部の哲学者は、その努力を単に無駄にしたと断じる覚悟でいる。例えば、ローティは、現代哲学の歴史に関する標準的な説明を否定するよりも、現代哲学を完全に否定する方が簡単だと考えている。ローティの語り口は他の論者よりも極論的だが、20世紀後半に多くの哲学科で語られた物語の極論版といえるだろう。その物語とは、拷問を受けながら興味が薄れていくようなものである。哲学は、ある種の人々と同様、中年期に入ると、確実なものと引き換えに、退屈を受け入れるようになった。形而上学-現実の基本的な構造の記述-として始まったものは、認識論-私たちの知識の基礎に立脚しないまでも、それを追跡しようとする試み-として終わった。
文学的な理由だけでは、この物語には欠陥がある。なぜなら、どこの国でもドラマチックな展開の中心となるもの、つまり説得力のある動機が欠けているからだ。自然科学者と区別したいという時代錯誤な願望を除けば、この物語は意図せずに行動する哲学者たちの物語である。初期の形而上学的探求の根拠は、その後継者の動機と同様、ほとんど不透明である。どちらの場合も、偉大な思想家たちが、物事のあり方に関する非常に一般的な疑問を調査することに、純粋な好奇心から行き詰まったに過ぎないのである。デカルト自身が知っていたように、狂人以外は、私たちの表象がすべて夢だろうかもしれないと本気で考えることはないのである。カントは、『純粋理性批判』を通じて、哲学者が何の成果ももたらさないテーマに対して無尽蔵の努力を払っているのは、何か理由があるに違いないと書いている。彼は、その労苦は純粋な思索だけでは導ききれないと考えた。哲学の仕事は、緊急性のない目的や問題によって進められるには、あまりにも困難であり、あまりにも苛立たしいものなのである。
思索的な労苦は実際的な目的によって動かされるというカントの結論は、狭く読まれてはならないのである。最後に、私が主張したいことは、哲学史は認識論に加えて倫理学にも関心を寄せていたということである。もちろん、倫理学史に関する現代の研究がよく示しているように、そうであった。しかし、悪の問題は、哲学を、つながっているかどうかわからない領域に分けようとする20世紀の試みが絶望的であったことを示している。このことを理解するためには、スピノザやヘーゲルのような、明らかに全体主義的な作家を考慮する必要はないだろう。最も懐疑的な経験主義者であるヒューム自身、立ち止まるべきだろう。ヒュームはどのような奇跡を疑えというのだろうか。どのような習慣を守ることを望んだのだろうか。20世紀の哲学は、パズルと問題を混同してしまうという点で、特別なものではない。これは、哲学の原点である意見を問うという衝動の一部であるとも言える能力である。中世の哲学は、単に生と死に関する問題ではなく、永遠の生と死に関する問いが、いかに実体に関する問いに転化し得るかを明らかにした。詭弁やスコラ哲学の危険性は、哲学の可能性そのものに存在する。新しいのは、こうした危険性ではなく、プラトンからニーチェに至る哲学者たちにとって異質であったであろう、主題の断片化なのである。この断片化が、悪の問題をありのままに見ることを妨げている。世界には正義も意味もないという事実は、世界の中で行動し、世界を理解する私たちの能力を脅かす。世界が理解可能であるという要求は、実践的理性と理論的理性の要求であり、哲学が提供するよう求められている思考の根拠となるものである。この問題が倫理的なものなのか、それとも形而上学的なものなのかは、重要ではないのだが、決定不可能であり、哲学的な問題として捉えることが困難な場合もある。一般論として述べれば、これは不幸な記述に過ぎない。これが問題でないのなら、哲学が答えを出せないのも無理はない。しかし、哲学はその歴史の大半において、悪の問題を定式化しようとする試みを繰り返してきており、それは悪の問題に答える試みと同じくらい重要なものである。
私がこれから主張することを要約してみよう。
- 1. 18世紀と19世紀の哲学は、悪の問題によって導かれた。多くの短い文章と同様、この文章も単純すぎます。しかし、哲学史を理解するための組織的な原理として、悪の問題は他の選択肢に比べて優れていることを示したいと思っている。悪の問題は、より包括的で、はるかに多くのテキストを包含し、著者の意図に忠実であり、より興味深いものである。ここでいう興味とは、単に美的なカテゴリーというだけでなく、説明的なカテゴリーでもあり、カントの問いに答えるものである。純粋な理性は、何が目的でも結果でもないような努力に駆り立てるのだろうか。
- 2. 悪の問題は、神学的あるいは世俗的な言葉で表現することができるが、基本的には世界全体の理解可能性に関する問題である。したがって、倫理学にも形而上学にも属さないが、両者の間に位置するものである。
- 3. 自然悪と道徳悪の区別は、それ自体、議論の過程で発展した歴史的なものである。
- 4. どのような種類の悪が問題になっているかにかかわらず、初期啓蒙主義から現代に至るまで、2種類の立場が見られ、それぞれ認識論的な関心よりも倫理的な関心によって導かれている。ルソーからアーレントまで、悪を理解できるようにすることが道徳的に要求されると主張するもの。もう一方は、ヴォルテールからジャン・アメリに至るまで、道徳は私たちがそうしないことを要求していると主張している。
私自身は、後者の主張の影響力を認めつつも、前者の考え方に共感する傾向がある。つまり、18世紀が直面していた悪の問題は、私たちの時代とはあまりにも異なっていたため、両者を比較すると、概念的な混乱だけでなく、道徳的な混乱も伴うというのである。リスボンとアウシュビッツを比較することは、間違いではなく、とんでもないことに思えるかもしれない。なぜなら、後者を多少なりとも自然災害と見なし、建築家を免罪符とするか、創造主を最悪の犯罪者と比較するか、そのどちらかになる恐れがあるからだ。アウシュビッツの司令官の贖罪を考えることと、無神論者でさえ保持したいと思う神のイメージの侵害とでは、どちらが悪いとは言い難い。そのため、この二つの出来事は、孤立した発言を除けば、それぞれの時代の世界観の崩壊を象徴するものとして放置され、どうして一方から他方へと移行したのかという問題には触れられてはいない。もし、理解に対する不安が保存されるのが正しいと思われるなら、それが探求を妨げず、むしろ形成されることを私は信じている。
本書が提供しない多くのものの中に、悪の定義や、悪の行為を単に非常に悪い行為と区別するための基準がある。これは倫理書の課題かもしれないが、悪の問題は別のことに関係している。ある行為を「悪」と呼び、別の行為を「人道に対する罪」と呼ぶことの違いは何なのだろうか。ある行為を悪と呼ぶのと、別の行為を人道に対する罪と呼ぶのとでは、何が違うのだろうか。両者はしばしば入れ替わることがある。しかし、犯罪とは、私たちが予防はしないまでも、少なくとも罰するための手続きを持っているものである。このことは、犯罪には順序があり、私たちの経験の他の部分に何らかの形で適合させることができる、と言っている。ある行為を悪と呼ぶことは、それができないことを示唆することであり、それによって、私たちが世界の中で自分自身を方向付けるために必要な、世界に対する信頼を脅かすことになる。私は、悪は比較することはできないが、区別する必要があると主張する。9月11日に起こったことはある種の悪であり、アウシュビッツで起こったことは別の種類の悪である。その違いを明確にすることは、悪をなくすことにはならないが、悪に対する私たちの最悪の反応を防ぐことには役立つだろう。
善悪を判断する絶対的な基準が失われたことを嘆くのは、ニーチェから1世紀も経てば不要になるはずだが、毎日のように誰かがそれを行っているようである。人文科学の講義を担当したことのある人なら、善や悪といった言葉は、文化によって異なる使われ方をしているため、時代遅れであることを知った学生にほぼ全員が出会ったことがあるはずだ。しかし、一般的な倫理原則に確信が持てる人はほとんどいない一方で、特定の倫理的パラダイムには確信を持っている人がほとんどであることに気づかぬまま、今日に至っているのではないだろうか。価値の一般的な基礎についての確信が失われても、その特定の例についての確信に影響を与えることはなく、おそらく全く逆であろう。3世紀前、価値観の基盤がより強固であったと言われる時代には、公共の場での拷問死が広く受け入れられていた。今日では、原則の違いにかかわらず、拷問はかなり普遍的に非難されている。ルワンダやボスニアが示しているように、普遍的な非難はほとんど何の価値もないかもしれない。私が言いたいのは、理論と実践の関係ではなく、一般原則と特定のパラダイムの関係についてである。拷問や大量虐殺が間違っていると証明する一般原則は存在しないかもしれないが、だからといって、それらを悪のパラダイムと見なすことを妨げるものではない。
したがって、私はそのような例があり、それらは時代とともに変化していくものと考えているが、それらを正当化したり、基準を示したりすることには全く興味がない。たとえ、他の時代が大切にしていたと想像されるような一般原則がないとしても、私の目的にはこれで十分である。悪の本質的な性質が定義できるとは思えないので、私はむしろ、悪が私たちに何をするのかを追究することに関心がある。もし、何かを悪と指定することが、世界への信頼を打ち砕くという事実を示す方法であるなら、私が調べたいのは、原因よりもむしろその効果なのである。従って、私は悪そのものを定義することよりも、悪の問題を解決することのほうに関心がある。私の関心はむしろ、悪の問題に対する理解の変化が、私たち自身に対する理解や、世界における私たちの位置づけの変化について、何を明らかにするのかを探ることにある。私は、哲学の歴史を検証することは、哲学そのものに関わることであるという、共通の前提の下に研究を進めている。従来の知的歴史学では、歴代の思想家の悪に関する記述を年代順に並べ、その影響源やパターンを追跡することが行われていた。また、従来の哲学研究は、競合する諸説の成否を評価し、より優れた説を提示しようとするものだった。私の目的はそれとは全く異なり、啓蒙主義時代から3世紀を経て、私たちがどのような人間になったかを理解する手段として、悪の問題に対する様々な反応を利用することである。
本書は、哲学史の中で奇妙に無視されてきた興味深いトピックの研究として始まった。しかし、すぐにその枠を打ち破ろうとする勢いを見せた。もし私の考えが少しでも正しければ、悪の問題は非常に広範であり、これを網羅的かつ体系的に扱うには、哲学史の大半を網羅的かつ体系的に扱う必要があるのだろう。単に正しい名前を列挙するだけでは、絶望的と思われるかもしれない。私は、そのような試みをする代わりに、いくつかの選択をした。第一に、私は議論を啓蒙主義に始まる時期に限定し、啓蒙主義はバイユの『辞書』が出版された1697年に始まったとした。それ以前の年代を設定するのには、それなりの理由がある。ひとつは、近代哲学の祖とされるルネ・デカルトという人物にグノーシス的なイメージを探るためだろう。デカルトの邪悪な悪魔は、思考実験ではなく、脅威なのだ。その後継者である「大桶の中の脳」とは異なり、悪魔は現実の問題であった。もし、この世界が、私たちを苦しめ、錯覚させることを目的とした存在によって創られたとしたら、どうだろう?神はそのように見えることがあることを知っている。デカルトの不在が問題であるとすれば、スピノザの不在はもっと問題かもしれない。しかし、プラトンも同様である。悪の問題を研究するために一生を費やしても、それ以上のものはないだろう。その代わり、私は、私たちが私たちであることを最もよく認識できるようになった時期の初めからの展開に限定して議論することにしている。もしベイユが書いたように、歴史が犯罪と不幸の歴史であるならば、それを理解しようとする試みは虚偽であるだけでなく、嘲笑される運命にある。啓蒙主義がベイユの誤りを証明する圧力のもとに始まったと見るのは、一つの選択ではあるが、恣意的な選択ではない。
このような制約の中でさえ、この研究は網羅的なものにはなりえず、そのことを示すために、私は非時系列的な形式を選択した。私の関心は、ルソーの『第二談話』とアーレントの『エルサレムのアイヒマン』を結びつけるような思想の展開にあるのだが、私はそうした展開を主題的に探求していた。つまり、私たちが経験する秩序とは別の、より良い、真の秩序が存在するのか、それとも、私たちの感覚が突きつける事実がすべてなのか、というように、出現の本質に関する見解によって思想家たちをグループ分けしている。現実は存在するものだけで完結しているのか、それとも存在しうるものすべてに対して余地を残しているのか。一つの大きな問題に対するスタンスによって哲学者を分けるのは乱暴な分け方であり、奇妙な同盟関係を生み出す。経験によってもたらされる惨めなものに加えて秩序を見出すことを主張した哲学者の中には、ライプニッツ、ポープ、ルソー、カント、ヘーゲル、そしてマルクスが含まれる。また、外見を超えるものの実在を否定した人たちとして、バイエル、ヴォルテール、ヒューム、サド、ショーペンハウアーを取り上げる。ニーチェとフロイトは、どんなに広義に解釈しても、どちらの区分にも当てはめることはできないが、十分に類似した問題を提起しているので、それぞれの章に値すると思う。最終章で論じるように、20世紀は哲学に特有の問題を提示している。伝統の分断は、カミュ、アーレント、アドルノ、ホルクハイマー、ロールズが示すような断片的な反応に反映されるだろう。
このように哲学者をグループ分けすることは、哲学者間の多くの決定的な差異を見落とすことになる。しかし、この分類は、合理主義者と経験主義者に分けて考えることほど粗雑なものではないし、この分類は部分的に同列に扱われるものである。後者は、現代哲学の主要な問題が知識論に関する問題であると考える人々には、より自然なことだと思われるだろう。このような問題を主な関心事とするならば、哲学者は、知識の主な源泉が理性だろうか経験だろうかによって分類され、哲学者間のその他の違いは付随的なものと見なされることになる。しかし、この区分は、それを克服したとされるカントや、哲学史そのものに最も思想を傾けた近代哲学者ヘーゲルにとって、自明なものではなかった。『純粋理性批判』にとって、哲学史上の最初の論争は、外観と現実に関するもので、観念と経験のどちらが最終的な訴えの法廷となるのか、というものである。この問いは、哲学史の中でプラトンにまで遡る。外観と現実の違いに関する論争に拍車をかけたのは、世界が私たちの見たとおりにならないかもしれないという不安ではなく、むしろそうなってしまうのではないかという恐怖だった。
第1章で取り上げた思想家の多くは、互いに付き合いを拒否するようになる。しかし、時折、憂鬱な気分になることはあっても、全員が、私たちが経験している秩序よりも良い秩序に対する何らかの希望で結ばれている。対照的に、第2章で取り上げた人々は、ショーペンハウアーの途方もない悲観主義で締めくくられた、輝かしく明るい荒涼とした雰囲気を共有している。ニーチェとフロイトは、自分たちよりも前に行われたこのテーマに関する議論や、それ以降に私たちが掴みたくなるような藁に対しても、ある種の英雄的な軽蔑の念を抱き続けている。20世紀の悪の思想を示すために選ばれた思想家たちは、もろさや畏怖の念から生まれた謙虚さを示している。思想家たちは、形而上学に属する用語(出現の現実をどのように見ているか)と心理学に属する用語(世界に対して根本的に希望的な姿勢をとる余地があるか)に分類することができる。私は、悪の問題にはその両方についての思考が必要であると主張する。哲学的言説の構成方法は、悪の問題が問いかける最も重要なものではないが、最も容易に変えることができるものであることは間違いない。
一般に、私は正典の主要な人物に焦点を当てる。このことは、取り上げる問題が伝統にとって末梢的なものではなく、最も中心的な思想家たちの仕事にとって基本的なものであるという事実を強調するものである。これが通常の哲学史であれば、フィヒテやシェリングを論じずにカントからヘーゲルへの移行を説明したり、フォイエルバッハを論じずにヘーゲルからマルクスへ移行することは無責任なことだろう。私はその両方をやってしまったし、おそらくもっと悪いこともやっただろう。私の関心は、著者間の因果関係をたどることよりも、ある種の一般的な展開がどのように意味を持つかを示すことにある。そのためには、特に刺激的で重要な仕事のサンプルを選び、それが他の部分を照らしてくれることを期待すれば十分だろう。しかし、何百もの豊かで影響力のあるテキストは、それによって無視されることになり、選択はもっと違ったものになったはずだ。哲学史は悪の問題に深く関わっているため、問題はどこから始めるかではなく、どこで止めるかということなのである。哲学史は悪の問題に深く関わっており、問題はどこから始めるかではなく、どこで止めるかである。完全なものにしようとすると、最初から失敗する運命にある。本書は、探究心を枯渇させるのではなく、むしろ探究心を開くものであれば、その目的を達成したことになる。
本書をオルターナティブな哲学史と呼ぶのは、そのスタイルや手法と同様に、その目的も異なるからだ。ある匿名の読者の好意的な表現によれば、その目的の一つは、哲学的な問いかけの本当の根源に学問を向け直すことである。この比喩のおかげで、何らかの形で、悪の問題が現代哲学の根源であることを論証できるようになったことを、私は感謝している。ひとたび生命を吹き込まれた哲学的言説は、それ自体で成長し、その枝はあらゆる方向に伸びたり、絡まったりする可能性がある。したがって、ここで提起された問題とはほとんど関係のない思想の流派全体が発展することもあり得る。カント、ヒューム、ヘーゲルはいずれも、何世紀も後にそれらを読んだ哲学者たちに、言語と世界の関係、あるいは知識の基礎について考えさせるような問いを提起している。しかし、私が主張するように、こうした問いが彼らの思想の中心にあるわけではないというのであれば、私たちは自らの哲学的風景をこれまでとは違った形で捉えなければならない。
本書は、単にプロの哲学者にもそうでない人にも興味を持ってもらえるようにというだけでなく、その歴史の大半を通じて、哲学そのものがプロの哲学者にもそうでない人にも興味を持ってもらえるものであったことを示すことを目的としている。他の多くの人々と同様、私も生と死に関する事柄を研究するために哲学の世界に入ったが、プロになるにはそれを忘れる必要があると教えられた。しかし、学べば学ぶほど、その逆で、哲学の歴史は、私たちを哲学に引き付けるような問いかけによって動いているのだという確信を深めていった。このため、私は、哲学の正式な教育を受けていない方にも理解できるよう、メモや学問的な装置は最小限にとどめて執筆してまいりました。レッシングとメンデルスゾーンが詩と形而上学の関係についての国際懸賞論文を共同執筆し、カントが18世紀版『ニューヨーク・レビュー』に寄稿し、サドがバスティーユでルソーの本を送ってくれるよう頼んだあの啓蒙時代の精神に則り、本書は仮の希望を持って書かれたものである。
プリンストン・クラシックス版への後書き
10年以上経ってから『現代思想の悪』を読み返すと、喜びがこみ上げてくる。特に長い第一章を執筆している間は、概念的な葛藤が激しく、脳が悶えるようだったことを覚えている。現在では、当時苦労した遷移が自然であり、避けられない議論であるように思える。それでも私は、あとがきで、この本を今日書くとしたら違った書き方をしたであろう部分を探る機会を得たことに感謝している。
第一は、簡単に改善できることだ。この本の主題が西洋の近代思想であることを明確にするべきだったのである。多くの読者から、なぜある思想家を無視したのかという質問が寄せられたが、その答えはたいてい簡単で、この本に一生をかけたくありませんでしたので、戦略的な選択をせざるを得なかったのである。私の本来の目的は、近代西洋哲学の古典的なテキストに新しい物語を提示することだったから、私は慣習にとらわれないようにする傾向があった。フォイエルバッハやキルケゴールよりも、カントやヘーゲルが悪の問題に中心的な関心を抱いていたことを示す方が重要だったのである。哲学の焦点を認識論的問題から緊急の問題へと移すためには、西洋哲学史の真摯な研究において無視できない哲学者たちを読み直すことの方が、他の哲学者を正典に加えることに固執するよりも重要だったのである。とはいえ、アダム・スミスの見えざる手や、ダーウィンの目的論に見られるプロビデンスの響きは、とても重要であり、それらを探求しておけばよかったと思う。悪を理解するために時間を費やしたことのある人なら誰でも、自分の考察がどんなに未完成であっても、単に立ち止まらなければならない瞬間について知っていることだろう。最初の序文で書いたように、私の望みは探求の道を探し尽くすことではなく、それを開くことだった。
とはいえ、私自身の探求が西洋の思想家に限定されており、私の力量では到底及ばない伝統全体を除外しているという事実を明確に示すべきだった。ある寛大な読者が書いてくれたように。
人間の状態に対処する方法として、ヨーロッパ哲学を研究すれば十分だと公然と主張する人は、今ではほとんどいないだろう。この言葉自体、時代遅れのように聞こえる。ニーマンは、漠然とした境界を持つ「私たち」を呼び出すことでこの問題を回避し、「私たち」にとっての意義を示唆する一方で、人間についての普遍的な主張を避けている。しかし、ヨーロッパだけが関係する「私たち」は、おそらくもう存在しないのだ1。
私は気を引き締めた。この指摘は、この本が完成した2001年当時、私にとって異質なものではなかったはずだが、それを明確にする必要性を感じなかったことが印象的である。パーキンズが示唆した、ヨーロッパだけが関係する人々はもはや存在しない、というのは、グローバリゼーションの好ましい結果の一つである、より強固な普遍主義の印として、もしかしたら道徳的進歩の印としてさえ捉えることができるのではないだろうか?
□ □ □
第二の修正は容易である。『エルサレムのアイヒマン』が出版されて以来、アーレントの中心的なテーゼを覆すことに執着する研究が殺到している。私たちは、悪を行うには悪を行う意図が必要だと考えることに慣れているため、アーレントがアイヒマンの悪意を否定したことは、彼を免罪する方法だと今でも一般に考えられているし、ユダヤ人評議会の役割という一見無益な紹介は、犠牲者自身を非難しているかのように思われる。どちらも事実ではない。ユダヤ人評議会は、同じセクションで彼女が取り上げたドイツのいわゆる内地移住者とともに、アイヒマン自身が取り上げられたのと同じ理由、つまり、意図ではなく判断が道徳的行動の中心であり魂であることを示すために取り上げられている。ユダヤ人評議会の議長の立派な動機から、内部移住者の大半の疑わしい動機、アイヒマンが裁判で演じたような官僚の粗末だが品性のない意図まで、地獄への道はあらゆるもので舗装されていたのである。目的地が重要なのであって、舗装は二の次である。世界に影響を与えるのは、あなたの意図したことではなく、あなたが行ったことなのだから。
ホロコーストは、大量殺人の他の多くの例と同様に、特に熱心なファシストでもなく、まったくファシストでもないが、最も考えずに最も楽になれる命令があればそれに従うという何百万人もの人々の参加なしには起こり得なかったのである。この教訓は、私たちが今日直面するあらゆる道徳的・政治的闘争を理解するために不可欠なものであり、繰り返し考えなければならないものである。
しかし、この教訓はアドルフ・アイヒマンには当てはまらない。ベッティナ・スタングネスの『アイヒマン・ビフォア・エルサレム』は、綿密な歴史研究と哲学的洞察力によって、裁判を傍聴したほぼすべての人と同様に、アーレントが証人席でのアイヒマンの演技に引き込まれたことを明らかにしている。スタングネスは、アイヒマンが嘘の名人であり、ガス室に入る直前に、囚人に衣服をかけた釘の番号を覚えさせることによって、抵抗につながる疑惑を防ぐ心の余裕を持っていたことを示している。このSS将校は、裁判では、退屈で思慮のない出世主義者を装っていたが、内心では、自分が頭の悪い官僚であるとの指摘に憤慨していた。それどころか、彼はアルゼンチンでは、ユダヤ人の滅亡に献身した強力で硬い軍人だろうかのように見せていた。彼の唯一の後悔は、ヨーロッパ中のユダヤ人の殺害を組織化できなかったことである。エルサレムでの彼のパフォーマンスは、彼が軽蔑する官僚の真似をして、自分の命を守るために行われた。元ナチスがその犯罪の責任を問われることがいかに少ないかを考えると、これは全くもっともな目標であった。
また、彼の思考は、道具的合理性の巧みな利用だけにとどまらなかった。さらに問題なのは、彼が実際に道徳について考えていたという事実である。裁判では、彼はカント派であると主張して世間に衝撃を与えたが、アルゼンチンで書かれた文章は、彼がカントの教義の核心である普遍主義への傾倒を十分に理解し、それを拒否していたことを明らかにしている。ある文章が疑問を投げかけている。「道徳はどうなっているのか?そして、その答えを提示している。」キリスト教的道徳、倫理的価値観の道徳、戦争道徳、闘争(Kampf)道徳など、いくつもの道徳がある。そして、「キリスト教的道徳、倫理的価値観の道徳、戦争道徳、闘争(カンプ)道徳など、いくつもの道徳があるが、どれにすべきだろうか」3と答え、万人に主張する普遍的道徳があるかもしれないという考えは、後に説明するように、偽善であり、不条理だと考えている。実際、彼は、国際主義的なプロジェクトである哲学そのものに疑念を抱いている。
アイヒマンとその仲間たちにとって、真の思考とは人種的思考である。アイヒマンは、すべての民族が世界征服のための闘争に従事していると考えた。これは自然の法則であり、自己保存のための衝動は他のいかなる力、特に「いわゆる道徳的衝動」よりも強いと信じた。国家も軍隊も持たないユダヤ人は、自分たちの持っている武器、つまり知的な武器で戦った。旧約聖書の予言的メッセージに始まり、フリーメーソンによって推進されたフランス革命を経て、ユダヤ人カール・マルクスのボルシェビキのメッセージで最も危険なものに至るまで、彼らは国際主義の「偽りで欺く」教義を世に送り出したのである。アイヒマンは、「敵の武器を理解せよ、それはユダヤ文学と哲学全般を読むことである。ソクラテスがアテネの死刑を受け入れたという事実は、普遍主義者でさえ、道徳は国家権力に屈しなければならないことを知っていることを示している」「ソクラテスの知恵は、国家の法に屈する」とアイヒマンは書いている。このことは、もちろん、自然や権力の必然的な法則に屈服せざるを得ない人文主義の弱点を示すことを意味している4。彼は一瞬たりとも普遍主義的な立場を真剣に受け止めてはいない。カントは十分にドイツ的な思想家ではない、とアルゼンチンでしばしば繰り返したが、アイヒマンはその名誉をニーチェにも与えた。
アイヒマンがまじめな思想家であったことも、哲学をまじめに学んでいたことも、これらの発見からわかることはない。アイヒマンは「哲学は国際的なものだ」と考えていたのだろうから。スタングネスは、アイヒマンと書物との関係を、まるで泥棒が家に押し入って、取れるものは何でもさっさと取ってしまうようなものだと、巧みな表現で表現している。しかし、アルゼンチンの論文によれば、アイヒマンは、自分が誇りに思う世界観を構築するために、さまざまな哲学的テキストを手に取り、利用していた5。この主張のごった煮は、真に独立した思考とは到底言えない。徳とは、友人を助け、敵を傷つけることだろうか、あるいは、ある集団が共通の利益のために行動していると主張することによって、他の集団に対する権力を維持しようとする偽善的なレトリックの塊だろうかのどちらかである。プラトンの読者なら、『共和国』第1巻でソクラテスが普遍的な徳の概念を擁護するために提示した2つの立場が、この2つであることを認識するだろう。また、ミシェル・フーコーは、権力に関する分析がソクラテスの相手よりもはるかに豊かであったが、正義と権力の同一性を主張したため、普遍的正義の概念を否定した6。
アイヒマンの哲学的考察は粗雑で表面的なものかもしれないが、この種の粗雑で表面的な見方は今も私たちに残っており、その下品な単純さの割にはアイヒマンの哲学的考察は首尾一貫している。選択肢は2つだけだ。地球上のすべての人間に有効な普遍的な道徳的カテゴリーを信じるか、信じないか。その非常に単純な決断から、非常に多くの結果が導かれる。アルゼンチンのアイヒマンは、カントがどちら側だろうかをよく知っていた。ナチスの哲学者たちは、フロイトやハイネの著作を燃やしたように、ドイツの宝物を簡単に燃やしたくはなかったので、普遍主義を強調するユダヤ人カントと呼ばれるものと、義務や規則を守ることについて引用され、ドイツの美徳として正式に賞賛されるカントの部分とを慎重に区別して読んでいたかもしれない。このように、エルサレムのアイヒマンは、自分をカント派と呼ぶことで、敵(彼は、敵がすべてカント派であると仮定していたが、それは彼の条件からすれば妥当な仮定である)に気に入られ、少なくとも敵を混乱させて自分を許してもらうことを望んだのであった。原文のコピーがなかったら、信じがたいことである。アイヒマンの弁護士は、法廷での最終陳述でカント派の定式や言及を使うのをやめさせなければならなかった。
スタングネスを読んだ後では、アーレントと同じように、アイヒマンが「単に、口語的に言えば、自分のしていることに気づかなかった」7と言うことはできなくなった。彼自身の言葉を借りれば、彼自身、そして彼が選んだ彼の周りのすべての人が深く、明確に、意識的に取り組んでいた悪質な反ユダヤ、反共産主義のプログラムに従って歴史を形成したいという願望に駆られていたのである。世界が知る限り最も劣悪なイデオロギーの一つに対する彼の誇り高く揺るぎない献身に加え、アイヒマンには彼をよく知る人々をも欺く能力があり、「犯罪の首謀者」という言葉がぴったりである。多くのナチスと違って、彼が入手した盗品で自分自身を豊かにすることがなかったという事実は、ある人々にとっては緩和された証拠となるかもしれないが、多くの人々にとっては、イメージを暗くするだけであろう。彼自身の言葉を借りれば、普通の犯罪の誘惑とは無縁の理想主義者である男は、より人間的な欠点のある人間よりも恐ろしい悪に見えるかもしれない。『現代思想の中の悪』が主張するように、ホロコーストは、許容できるものから最低のものまで、さまざまな意図を持った多くの人々によって実行されたとすれば、アイヒマンのそれは最悪のものに属するだろう。
アーレントが入手できなかった歴史的証拠によって、「自分の出世のために並外れた勤勉さを除けば、(アイヒマンには)まったく動機がなかった」という彼女の主張が覆されることになった。しかし、悪の行為に悪意は必要ないという彼女の核心的な考えは損なわれていない。アイヒマンは、ドイツ人が今デスク犯と呼ぶ軽率な官僚を真似たが、彼らは真似されるために大勢いたのであり、彼らなしにはアイヒマンのような男の意図が実を結ぶことはほとんどないだろう。殺人的なイデオロギーと暴力への欲望が混じり合った毒に突き動かされる人々がいるが、その数は、最小限のトラブルで済まそうとする以外の意図なしに彼らを幇助する人々の数に比べれば、微々たるものである。この点は、他の犯罪を理解し、防止するために非常に重要であり、たとえアーレントが根拠とした例が間違ったものであったとしても、何度強調してもし過ぎることはないだろう。
この本の第三の側面として、私は今日、テロリズムについての議論を展開したいと思う。これは急いで書いたものである。私は編集者のイアン・マルコムに、何年もかけて書き上げた原稿の最終版を2001年10月1日までに提出することを、何にも邪魔されることなく約束していた。しかし、世界貿易センタービルとペンタゴンの同時多発テロによって、「悪」という言葉が脚光を浴び、私は窮地に立たされた。このまま出版に踏み切ってもいいのだろうか?イアンは賢明にも、他の編集上の提案と同様に、本を変えるのではなく、できることなら短い章を追加するようにと私に告げた。この本は、あの数週間、どこにいてもほとんどの人が抱いた感情の中で書かれたものだが、私はこの本の中のすべてを支持する。特に、ジョージ・W・ブッシュに同調して同時多発テロを悪と表現した左派の人々の多くは、道徳的・政治的な誤りであったと言える。他の種類の悪に責任がある人たちが、この概念を突然復活させたからと言って、他の人たちがそれを否定するようなことがあってはならない。そうすれば、私たちの言語の中で最も強力なものである道徳的概念が、それを使うのに最も不向きな人々の手に委ねられることになる、と私は主張した。悪は、他の多くの重要な概念と同様、本質を持つようなものではなく、悪のすべての事例を網羅する必要十分条件を求めて理解しようとしても無駄なのである。より形而上学的でない言葉で言えば、ある種の残虐行為に「悪」という言葉を使ったからといって、別のものに使うことができなくなるわけではない。私たちが悪と理解するものは時代とともに変化していた。地震、拷問、奴隷制度について考えてみよう。これは、この言葉が独り歩きしていると言っているのではなく、悪とひどいものを区別する唯一の方法は、特殊性を注意深く観察することなのである。
私は、次に書いた本『Moral Clarity』の第11章で、その特殊性を見ることにした。大人の理想主義者のためのガイド』(邦題『道徳の明晰さ』)の第11章で、その特殊性を探ることにした。(このタイトル自体、道徳的な言葉をひどく乱用した人たちから道徳的な言葉を奪い返そうという試みだった)。私がこの本を書いているとき、ブッシュ政権は批判されるに十分な時期だった。偽りの口実で始められ、拷問を伴ったイラク攻撃は、それまで何もなかったところにテロリストの基地を作る上で中心的な役割を果たした。拷問がいかに恐ろしいものだろうか、そしていかに無用なものだろうかは、この原稿を書いている間にも明らかにされ続けている。しかし、私は、ブッシュの「ラッキーなことに、私は3連勝した」という発言のような、それほど劇的でない、あるいは直接的に致命的な悪の形態にも興味があった。9月中旬、マンハッタンの廃墟がまだ煙を上げていた頃、ブッシュが初めてこの言葉を口にする前、この言葉を知っていたのは競馬ファンだけだったかもしれない。3連単とは、3頭の馬に賭けて、その賞金をすべて手にする幸運のことである。三連単とは、3頭の馬に賭けて賞金を全部もらうというもので、「大当たり」という意味である。2002年2月から6月にかけて、ブッシュが主に共和党の聴衆を前に行った13回のスピーチのうちの1回を紹介しよう。
不況-疑問の余地はない。選挙運動をしていたとき、私は、赤字支出はしないのかと言ったことを覚えている。そして私は、戦争や不況、あるいは国家的な緊急事態が発生した場合のみ、そうすると答えた。まさか、そうなるとは(笑と拍手)。それで、一時的に予算が赤字になったわけですが、それは戦争中であり、経済が回復しており、国家的緊急事態が発生したからだ。まさか三拍子揃うとは夢にも思わなかった。(笑)8
もしこの演説が、他の12の演説と同様に、ホワイトハウスの報道官室によって記録されていなければ、敵対する批評家たちによって捏造されたものだと疑うかもしれない-それは、ポール・クルーグマンがニューヨークタイムズで最初に報告したときになされた告発だ。アメリカの大統領が、戦争に行くための口実にしたテロの犠牲者について、資金集めのイベントでジョークを飛ばすなんて、実に信じがたい話だ。イラク戦争は誤った理想主義によって引き起こされたという神話にまだ説得されている人は、これらのスピーチを調べてみるとよいだろう。テロリストからもたらされた利益についての繰り返されるジョークは、ほとんど目に見える痕跡を残さなかったが、他人の死や損失を通じて得た機会についてのブッシュのほくそ笑みは、道徳的な言説における一瞬間であった。アメリカ大統領が冗談で生と死を安っぽく表現するとき、道徳的な言葉は粗雑さとキッチュさの間で迷子になるように思われる。
オバマ政権は、前政権が残した残骸に外交政策を制約されながらも、拷問を廃止し、グアンタナモを閉鎖しようと繰り返し試みたが、米国50州と106カ国が残りの捕虜の受け入れを拒否したため、阻止されただけであった。しかし、戦争とその犯罪の責任者は依然として逃亡しているだけでなく、要求されている。あらゆる証拠が揃っているにもかかわらず、尊敬されるメディアはブッシュ政権が嘘をついて戦争を始めたことをいまだに定期的に否定している。オバマの提案のうち最も議論の余地のないものにさえ共和党が前例のないほど反対したことを考えれば、戦争犯罪裁判や真実和解委員会さえも政治的選択肢ではなかったことは明らかである。
西ドイツがナチスの過去を検証するプロセスを開始するのに20年以上かかった。(共産主義の東ドイツは終戦後すぐに多数のナチスを裁き、判決を下すことができたが、戦後のドイツの両半身の違いの理由を探ることは、この文章の範囲を超えている)9。おそらくアメリカの犯罪の清算はブッシュとチェイニー、ライスとラムズフェルドが去った後に行われるであろう。一方、ISISの卑劣なビデオで私たちを驚かせる原理主義的暴力の原因は、彼らだけとは言い難いが、その火種となっているのは確かだ。「グアンタナモ」と叫ぶオレンジ色のジャンプスーツがなくても、その関連性はわかるだろう。
「道徳的明瞭さ」の中で私はこう書いた。
最初の写真が世に出た直後、(ラムズフェルドは)「アブグレイブで起きたことは正しくない」と宣言した。「しかし、ビデオカメラの前で誰かの首を切り落とすのとはわけが違う。」と宣言した。その通りだ。同じことではない。しかし、悪には本質があると考えるならばこそ、ラムズフェルドが私たちに求めた結論、すなわち、これらの行為の一つは悪であり、もう一つは単に悪すぎるという結論を導き出すことができる。違いはたくさんある。一方の悪は目に見えるが、もう一方はまだ見えない。一方は冷酷な個人の意志の産物であり、他方は個人の責任逃れを容易にする大きな複雑なシステムによって生み出された悪である。一方は死を明確な目標とし、他方は不運な副産物としている。一方はスクリーンの中で涙を流す、恐怖に震える青白い肉の塊に人を落とし、もう一方は顔のない裸の肉体に人を落とす。両者に共通するのは、あまりに憎むべき手法を用い、右往左往する敵を生み出そうとする姿勢である。しかし、最大の違いはこの点だろう。加害者の一方が他方よりはるかに強力であるため、その影響が長く続く可能性が高いのだ。アブグレイブは世界の悪夢を確認させ、アメリカ、西洋全般、そして将来、独裁者から人権を守ろうとする言葉を、どんなに誠実に語ろうとする人に対する憎悪と疑念を生み出した。議論のために、アブグレイブで囚人を拷問した米軍兵士の意図が、人質を斬首したグループの意図より優れていたとしよう。もし、その意図が結果的に悪い方向に向かえば、何の意味もないだろう10。
当時、「イシス」とは古代エジプトの女神のことであり、疎外された若者たちが比較的快適な西側を離れ、シリアの砂漠で戦うなどとは誰も想像していなかった。私は、自分自身の恐怖が杞憂であってほしいと、これほどまでに深く願ったことはない。今日、原理主義的なテロリズムの新たな悪質な波の中にあるヨーロッパからこの文章を書いている私は、それを許そうとは思わないが、私たち自身の政策がその拡大に寄与していることを理解しない限り、テロリズムを根絶することはできないだろう。
本書の第四の側面は、今日では異なる様相を呈しているだろう。この本を書いたとき、私はリスボン地震が歴史的な意味を持つとは思ってもみなかった。それは、近代化の出発点であり、悪についての見方を見直すためのものであったが、方向性を示すものでは到底なかった。私は、自然悪と道徳悪の区別は自然なものではなく、私たちができる悪を理解し、制御するための方法であると主張した。しかし、過去10年間に目撃された災害を前にすると、この区別はますます不自然になり、維持することも不可能に見えてくる。ほとんどの災害はリスボン地震よりも致命的であるだけでなく、グローバルメディアのおかげで、より存在感のあるものになっている。
もし悲劇的でなければ、宗教原理主義者たちが天からのメッセージを解読しようと競い合っている姿は滑稽でさえある。1755年当時の正教会の司祭のように、彼らは天変地異を神の言葉として捉えていたのである。特に2004年の津波に対する反応は印象的だった。イスラム教の伝道師たちは、タイの海岸から半裸の観光客を一掃するために送られた罰だと考えたが、仏教徒たちは、異常な量の肉が消費されるクリスマスの翌日に津波が発生したことをすぐに指摘したのである。キリスト教のウェブサイト「raptureready.com」は、聖ヨハネの予言に対応する災害の兆候をニュースで検索しているが、津波は終末が近いことを示すもう一つのサインであるとしている。このような反応は、冷静な読者には滑稽に映るかもしれないが、意味のない苦しみより、何でも耐えることができる、という深いニーズを指している。悲劇を神のメッセージとして解釈することは、悲劇を意味あるものにするための最短の道なのだ。
ワシントンポスト紙によると、調査したアメリカ人の4分の1がハリケーン・カトリーナは「神の意図的な行動」であったと確信している。ハリケーン・カトリーナを罰とみなす人々は、ニューオーリンズが昔から罪や賭博、悪事で知られていたことを指摘し、「最終的に神の裁きを受けるような行為」であるとした。半数は、嵐は罰ではなく、警告であり、神の最後の審判で流される前に罪を悔い改めるよう、残された人々に思い起こさせるものだと考えた。14%は、ハリケーンは信仰の試練であり、疑いや絶望を経て、主の意志がどうであれ、主を肯定するように導くものだと考え、残りの人は、大災害は人間には理解できない神の方法の一つだと考えている。
より魅力的だったのは、災害に対する政治的反応で、嵐そのものよりも、嵐に対するまともな人間の反応の欠如に焦点を当てたものであった。1755年、勇敢なポンバル侯爵は、飢饉を防ぐために穀物の貯蔵を徴発し、ペストを防ぐために死体の処理を組織し、略奪を防ぐために民兵を集め、そのすべてを効率的に行ったので、リスボンは週刊誌を一度も欠かさずに発行することができた。250年後、ニューオリンズで機能していたのはニュースだけだった。多くの人が何日も食べ物も水もなく、略奪と暴力の脅威に直面し、何百人もの警官がただ町を去り、死体が何週間も通りに浮遊していた。災害の規模はリスボン地震より大きかったが、それに対処するための資源も大きかった。このような危機への対応の違いは、時間の経過とともに不公正さを増してきた社会の違いを示している。現代のポルトガルはヨーロッパの一部であり、アメリカ人が夢見る社会民主主義の成果を享受している。現代のアメリカでは、貧しい人々が病気や災害に対して脆弱であるために、より多く、より早く死ぬことを保証する社会関係のシステムを何十年も無視してきたことが、一瞬、家に戻ったような気がした。18世紀のポルトガルが現在のアメリカよりも有能で包括的な社会構造を享受していたことは認めがたいが、大多数のアメリカ人にとって、貧困は政府が干渉すべきでない自然悪であることに変わりはないのである。19世紀の英国の聖職者が、アイルランドの飢饉の被害者を救済することは神の意思に背くことだと主張したのと何が違うのだろうか。
自然災害の多発は、世界の終わりが近いことを危惧させるが、それは救世主の到来ではなく、環境上の終末の日が近いからだ。数年前、当時10代だった私の子供の一人が、極地の氷冠の縮小とオゾンホールの拡大について正確な知識を持ち、さらにそれらが政治的行動を無駄にしていると確信して、私を驚かせたことがあった。私は、政治的変化に対して希望を持つべき理由を指摘した。私の世代は、公民権運動や女性運動によって、40年前にはまだ不十分とはいえ、想像もできなかったような変化が人々の生活にもたらされるのを目の当たりにしてきた。彼女の世代は、なぜ環境保護活動に取り組んで同じような成功を収めることができないのだろう?「ママ、私たちには40年もないわよ」と彼女は憤慨した。
深刻な気候変動に関する科学はすべて、彼女が正しいことを示唆している。最近の災害は、リスボン地震に見られるような自然悪と道徳悪の区別がもはや明確ではなく、その重要性さえも低下していることを示している。自然を改変する人間の力の大きさによって、何が人間で何が自然かという線引きがますます難しくなっているのだ。また、意図せずとも悪事を働かせることができることを知るにつけ、破壊や苦しみが意図的なものかどうかという問題はますます無意味になっている。
嵐を呼び起こす力は、かつては魔法や人間の空想の域を出ないものであった。しかし、人口増加、技術力、そして無限の生産を人間の幸福の鍵とみなす政治体制が相まって、以前の時代には夢想することしかできなかった力が生み出されているのだ。北極を溶かす?ハリケーンの発生?どのような境界線が残っているのだろうか。
「自然の怒り」という表現は、自然が反撃していることを示唆しており、環境保護主義者のレトリックの中には、不穏なほどアニミズム的なものもある。私はポスト・リスボン時代の産物として、自然が行動するのではなく、私たちが行動するのだと考えている。しかし、自然は確実に反応している。そして、どんな贅沢なレトリックよりもはるかに危険なのは、私たちが知っている地球を守るために必要な変化を政府や産業界が起こそうとしないことである。気候変動は、自然悪と道徳的悪の違いはもはや重要ではなく、重要なのは、私たちの無謀な自然利用が引き起こす自然災害に対して道徳的責任を負うことであることを示唆している。自然の大災害と人間の悪を区別することは、自然の破滅をもたらす自然の力を呼び起こす力を人間が持っている世界では、ますます意味をなさなくなる。意図的にせよ、これまで以上に使用が規制されていない核兵器によってせよ、軽率にせよ、最近ストームが穏やかな警告に思えるほどの環境災害が迫っている。人間の無頓着さが破壊を引き起こし、世界の最も貧しい人々を翻弄するとき、それは単なる悲劇ではなく、邪悪なものである。そして、そのような事態が発生するためには、最も平凡な意図以外には何も必要ないのである。近年の出来事がそのことに気づかせてくれるなら、リスボン地震の後に起こったのと同じくらい重要な理解の変化を引き起こすかもしれない。
本書の最後の変更点は、より大きな範囲であり、その波及効果についてはまだ検討中である。私は当時、「第二次世界大戦後の20年余りの間、私たちが二度と立ち直れないような形で限界を超えたという確信が、アウシュビッツよりもヒロシマという言葉によって捉えられた」11 (EMT、251頁)とも書き、アウシュビッツが現代の悪についての思考方法を終わらせた出来事である必要はない、リスボンが必ずしもそれを開始した出来事である必要もない、とも書いた。私の目的は、技術的な大量殺人を絶対的な尺度で測ることが可能だろうかのように、悪のヒエラルキーを確立することではなかった。むしろ、18世紀から20世紀にかけての、悪に対する私たちの認識に反映されている、近代(西洋)意識の変化を追跡しようとしたのである。そして、核戦争の脅威が後退したと思われる1970年代初頭以降、ヨーロッパやアメリカの人々の心には、広島や長崎よりもアウシュビッツの方が確実に大きく印象づけられている。
私は、広島・長崎の原爆投下70周年記念誌への寄稿を依頼されるまで、原爆投下直後の広島の意識が、なぜアウシュビッツの意識に完全に覆い隠されてしまったのかを問うことはなかった。私はその雑誌も編集者も知らなかったが、これまでアウシュビッツに注がれてきた批評的思考のほんの一部を原爆投下に充てようという要請に、道徳的に応えなければならないと思ったのである。(しかし残念なことに、『現代思想における悪』の中で述べたように、哲学科の内部では批判的考察はほとんど行われない。しかし、歴史家、社会学者、文学者、ジャーナリストは、図書館がいっぱいになるほどのナチスの犯罪についての考察を発表している)。私はこのテーマについて、2週間以内にエッセイにできるような考えを1つか2つ持っていたが、考察を始める前に、原爆投下の背景について少し実証的な調査をすることにした。
2カ月後、そして多くの本を読んだ後、私は自分が学んだことに衝撃を受けた。その瞬間まで、私はアメリカ人であれヨーロッパ人であれ、ほとんどの先生や友人が信じていることを信じていたのだ。広島の50周年を記念して書かれた短いエッセイの中で、ジョン・ロールズが要約したものを紹介しよう。
原爆は戦争の終結を早めるために投下された。トルーマンや他のほとんどの同盟国の指導者たちは、原爆投下がそうなると考えていたことは明らかである。もう一つの理由は、原爆投下によって人命が救われるからだ。ここでいう人命とは、アメリカ兵のことである。日本人の命は、軍人であれ民間人であれ、それほど重要視されなかったと思われる。ここでは、最小限の時間と最も多くの人命を救うという計算が相互に支え合っていたのである12。
それでも、ロールズはこう結論づけた。
広島も日本の都市への原爆投下も、政治家の義務として、危機の免除がない限り、政治指導者が避けるべき大きな害悪であった。(同上)。
ロールズの結論は、彼の経歴に照らしてみると、より感動的である。太平洋戦争の兵士として、彼は日本への侵攻によって失われたかもしれない命の一人であった。太平洋戦争の兵士であった彼は、日本への侵攻によって失われたかもしれない命の一つであったのだから。グンター・アンデルスのような作家は、原爆投下の結果が、失われた日本人の命をはるかに超えていることを強調している。アーレントがアウシュビッツについて書いたように、不可能が真実になったのであり、それは元に戻すことのできない可能性である。核兵器による地球の完全破壊が選択肢になると、私たちはその残虐性にほとんど気づかないほど、当たり前の事実としてそれを受け入れることになるのだ。原爆投下を命じた指導者たちは、それでも善意で行動したのだろうか。意図的であればなおさらである。
しかし、もしトルーマンや他の同盟国の指導者たちが、ロールズや私、そして最近のほとんどすべての観察者たちが信じていたように、戦争を終結させ人命を救うために原爆が必要だとは考えていなかったとしたらどうだろう。
彼らは公文書館を探し回り、容易に入手できない文書や日記を調べたが、原爆投下が侵略回避や戦争終結のためではなかったという事実は、1945年には広く知られており、ジョン・フォスター・ダレスとアルバート・アインシュタインの間と同じくらい深い政治的境界線を越えていたのである。トルーマンが依頼し、ポール・ニッツェやジョン・ケネス・ガルブレイスといった責任者が率いた1945年の調査は、次のような結論を出している。
すべての事実を詳細に調査し、関係する生存する日本人指導者の証言に裏付けられた結果、1945年12月31日以前に、そして1945年11月1日以前に、原爆が投下されていなくても、ロシアが参戦していなくても、侵略が計画・想定されていなくても、日本は確実に降伏していただろう…との見解が示されたのである。広島と長崎の原爆は、日本を敗北させたわけではないし、戦争を終結させた敵国の指導者の証言によれば、無条件降伏を受け入れるように日本を説得したわけでもないのである。14
調査以前にも、広島からわずか数週間後に、トルーマン自身が、原爆は戦争に勝つために必要なかったと公言している15。
広く受け入れられている反対意見は、慎重かつ意図的に作られたものである。陰謀論は、当然ながら疑いの目で見られる。しかし、この場合、歴史家は、原爆に対する現代の意識がどのように作られたかを正確に明らかにする詳細な情報を提供している。それは、核兵器使用についてトルーマンに助言するために設けられた暫定委員会のメンバーであるハーバード大学のジェームズ・コナント学長が、1947年9月に出した手紙から始まった。広島・長崎への原爆投下は、アメリカ国民の大多数が支持していた。しかし、マンハッタン計画に携わった科学者の多くが疑問を呈し始めていた。ジョン・ハーシーが原爆投下の後遺症を綴った「ニューヨーカー」の広島レポートは、より大きな衝撃を与えていた。「このようなセンチメンタリズムは、次の世代に大きな影響を与えるに違いない」とコナンは書いている。教職に就くような人、特に学校の教師は、この種の議論に大きな影響を受けるだろう」と書いている16。
彼は、1940年から 1945年まで陸軍長官を務めていたヘンリー・スティムソンに宛てて書いていた。引退したばかりで広く尊敬を集めていたスチムソンは、コナンが考えていた任務には理想的な人物であり、彼は説得されて、私たちのほとんどが当然と考える伝説を生み出す記事を書いた。スティムソン長官は、この数字が誤りであることを誰よりも知っていた。彼は、アイゼンハワー将軍、ルメイ将軍、そして当時の統合参謀本部議長であったリーヒー提督などの高位軍事顧問とともに、核攻撃反対を主張した高官たちの一人であった。しかし、新国務長官となった保守的な南カロライナ人のジェームズ・バーンズ氏が、トルーマン氏に原爆投下を説得し、却下された。何がスチムソン氏を説得し、虚偽と知りながら、そして私信によると後に後悔するような記述をさせたのか、私たちはおそらく知る由もないだろう。しかし、1947年のハーパーズ紙のエッセイは、どんな作家もうらやむような結果をもたらした。
今も続いている。先に述べたように、この神話を解体し、歴史的な記録を正すことに専念した優れた本が数多く存在する。その中でも、リフトン&ミッチェル著の『アメリカの中のヒロシマ』は、業界紙として出版されたほどである。ここでいう「大衆」とは、筆者も含め、読書家で善意の批評的知識人の多くを指す。読み書きのできる人なら、第二次世界大戦のヨーロッパ戦域で起こった出来事について、大まかではあるがおおむね正確に把握しているだろう。中等教育や、人気のある映画、テレビ、ラジオ番組が途切れることなく流れているので、歴史家でなくともアウシュビッツについての基本事実を知ることはできる。実際、アウシュビッツに関する情報を避けようとすれば、過去30年間を隠遁生活で過ごす必要があるだろう。これとは対照的に、太平洋戦争や広島・長崎への原爆投下に関する資料の多さは、簡単に見過ごすことができる。情報は、主に書籍や資料の中にあり、映画やその他のメディアにはほとんどないが、探さなければならない。別の言い方をすれば、スミソニアン博物館がヒロシマに関する企画展を開催できないでいる一方で、なぜワシントンモールにホロコースト専門の博物館があるのだろうか17。
反ユダヤ主義の雄牛の角をとって、最も一般的な疑惑に対処してみよう。ユダヤ人ロビーは確かに存在する。正確にはAIPACと呼ばれ、ユダヤ人が特にナチスの手によって犠牲になったことを強調することによって自らの政策の責任を回避しようとする右派のイスラエル政府を支援しようとするものである。しかし、広島からアウシュビッツへと民衆の意識が動いたことに責任はない。戦後何十年もの間、アウシュビッツの生存者は恥とされ、嫌悪感さえ持たれていた。18 新しく建国されたユダヤ国家は、犠牲者ではなく英雄を求めていたのだ。確かに、ユダヤ人は日本人が経験したことのない完全な被害者であると主張することは簡単である。対照的に、ドイツではナチスに対して小さいながらも明確な抵抗が存在し、マレーネ・ディートリッヒやハンナ・アーレントは、ナチス時代を通じて別のドイツへの献身を維持した、自発的・非自発的な何千人もの移民のうちの二人に過ぎなかった。それに匹敵するような日本人が存在しなかったという事実は、日本人が被害者であると主張することを受け入れ難くしている。
日本人とユダヤ人の被害者意識の違いは、広島とアウシュビッツに向けられた注目度の違いを示す一つの手がかりとなる。ユダヤ人犠牲者の相続人が被害者性を強調するのに有利な媒介的立場にあるという事実ではなく、彼らの被害者性が想像しうる限り明白であったという事実が、これほど多くの人々を注目させたのだ20。最近の歴史において、これほど単純な劇的特性を持つ出来事は他にないかもしれない。この物語の悪役が、『シンドラーのリスト』のようなハリウッドの優れた作品よりも複雑な人間であったとしても、彼らの犯罪は脚本家が考えうる限りの悪であり、被害者は自分たちが受けた運命に対する罪悪感をまったく感じないのである。さらに良いことに、ナチスは戦争に負け、600万人のユダヤ人が殺されたが、国民全体は生き残り、繁栄した。悪は罰せられ、無垢は報われたのだ。このような物語は、単にドラマチックなだけではなく、広く宗教的な意味でも必要なのだ。悪人が苦しみ、善人が救われるのであれば、世界全体が意味を持つ。
アウシュビッツの物語が神学に対する根深い欲求に応えるものであるにせよ、政治的欲求に応えるものであることは明らかである。道徳的な曖昧さを排除した犯罪に焦点を当てることで、他のどんな例にも及ばない絶対的な悪の姿が浮かび上がってくる。普通の人々が箱車に押し込められ、次にガス室に入れられるというイメージが繰り返されると、真の悪が何だろうかわかったような気になり、他のすべてが単に不幸に見えるだけになってしまうのである。悪の単純なモデルに焦点を当てれば当てるほど、より複雑な悪を見分ける練習ができなくなる。そして、広島と長崎への原爆投下から悲惨なイラク侵略に至るまで、この50年間、米国の外交政策を支配してきたのは、より複雑な悪の形態であった。広島に関する事実の抑圧は、私たちがどう認識しているかよりも、私たちの道徳的認識に大きな影響を及ぼしている。リフトンとミッチェルは、アメリカ人はヒロシマについて、漠然とした、実感のない、半ば強制的な知識を持っていると書いている。
政治家やあらゆる種類の役人、政府、そして私たちを統治するほぼすべての人々に対する不信感が高まっているが、近年私たちの公的生活に顕著に見られるこの怒りに満ちた冷笑主義が、ヒロシマとポスト・ヒロシマの核の虚偽と隠蔽の結果であるのか、自問しなければならないだろう21。
私は今、ヒロシマの抑圧とアウシュビッツへの注目によって、私たちの道徳的視野が歪められたと考えている。極度の近視の人々のように、私たちは大きな太いものしか認識できず、他のすべては曖昧で薄暗いままである。私はこれが偶然だとは思わないが、ユダヤ人の利益を代表すると主張する人々の仕業だとも思わない。むしろ、これほど明白な悪のイメージを広めることによって、米国の利益がもたらされる。アウシュビッツの炎に照らされると、イラン、グアテマラ、コンゴ、チリなど、原爆投下後の数十年間に米国の政策によって行われた悪の形は、視界から消えそうになるくらい淡く控えめなものに見える。精神分析的な言い方をすれば、アウシュビッツに焦点を当てることは、ヒロシマについて知りたくないことの置き換えの一形態である。
ここで述べた議論は、前述のエッセイでより詳細に述べられており、私は今後の作業でこれらの考えをさらに広げていくつもりです22。
おそらくナチの最悪の遺産は、死のキャンプの影に他のすべてを置き去りにしたことだろう。アウシュビッツはあまりにも極端だったので、その隣にいると、あまりにも多くのものが穏健に見えてしまうのだ。しかし、アウシュビッツの特異性に注目することは、他のどんなことに注目するよりも危険である。悪はあまりに多くの形で現れるため、閉じ込めることはできない。(同上, xv)
しかし、私自身が広島の背景について無知であり、公式見解を信じようとしていることは、既成概念を受け入れることがいかに容易だろうか、そして、概念の歴史が道を踏み外さないためには、いかに現実の歴史に通じていなければならないかを示している。
『現代思想の中の悪』は、現代の悪についての議論を喚起し、それに対して私はせいぜい部分的な答えを出すに過ぎないが、その本来の目的はもっと限定的なものであった。20 世紀の学生が幸運にも出会うことができた最高の哲学者たちの薫陶を受けながら、私は、自分が学んだものとは異なる哲学史の叙述を求めていたのである。午後のひとときであれ、生涯の仕事であれ、多くの人が哲学に寄せる期待と、プロの哲学者の実際の実践との間にあるギャップに苛立ちを覚えるようになった私は、このギャップが常に存在していたのではないかと考え、哲学の歴史に目を向けた。詭弁やスコラ哲学はどの時代にも存在したが、私が発見したのは、私が期待していたよりもさらに豊かなものだった。近代哲学の偉人たちは、外界の存在や他の心の存在を証明することに夢中にはなっていなかった。外見と現実の違いに対する彼らの関心は、世界が外見と異なることが判明するかもしれないという懐疑的な心配によってではなく、むしろ正反対であった。ライプニッツ、ルソー、カント、ヘーゲル、マルクスなど、さまざまな哲学者が、悪の多様な外観を説明することも救済することもできないという不安を抱いて、主要な著作を執筆したのである。バイエルやヒュームのような懐疑的な反対者は、ビリヤードの玉や普通の道徳的な問題に対する懐疑ではなく、ひどく欠陥があるように見える宇宙的構造を擁護したり正当化したりしようとする試みに対して悩んでいたのである。
私自身、その後の読書や考察を通じて、このような哲学史の読み方を確認し、さらに困惑している。20 世紀の哲学者たちは、なぜこのようにウェルトフレムド的な方法で先人を読もうとしたのか(ドイツ語にはしばしばあり得ないほど長い構文があるが、英語には世界からの疎外という意味のこの表現に対応するものはない)。なぜ、深遠で差し迫った問題に対する哲学の取り組みを無視し、カントが学徒にしか関心を持たないと知っていた問題に焦点を当てるのだろうか。なぜ、人を惹きつけてやまない分野を、生気を失い、ついには退屈な分野にしてしまうのだろうか。特に、バートランド・ラッセルのように、標準的な物語を作った哲学者の多くは、自らウェルトフレームドであったとは言い難いのだろうから、その答えを見つけるのは難しいだろう。また、慈愛の原則を過度に利用することで、哲学が克服したと考えられている宗教的な関心事に悪の問題を結びつけてしまうことも、その答えにはなり得ない。悪の問題は宗教的な問題ではなく、宗教はむしろ、悪の問題に対する一種の対応策なのである。
答えを見つけるのは難しいが、警告で締めくくるのは簡単である。多くの場所で多くの人々が哲学的な考察に飢えている。私たちは「セオリー」、あるいは「フィロソフィー」と呼ばれるファッションラベルを笑ったり、流行のポストモダン賢人たちの売上高を嘲笑したりすることがあるかもしれない。しかし、これらは、批判的な頭脳が退位したときに、より毛深い頭脳によって満たされるであろうニーズを指し示している。デジタル時代の到来により、多くの新しい問いが生まれたが、人々は依然としてカントを動かした問いと格闘しており、プロの哲学者がそれを無視するならば、彼らはその答えを別の場所に求めるだろう。本書が哲学を故郷と呼び続けることができますように。
