Contents
Difference – is it hated or desired? Reflections on the totalitarian state of mind
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32170738/
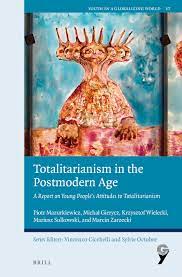
要旨
政治的見解が二極化し、ナショナリズムが高まっている時代に、精神分析の専門家が貢献することは極めて重要である。著者は、乳幼児期の発達と社会的・政治的行動との間に関連性を見出している。精神分析的、ユング的、関係論的な考え方が探求されている。フロイトと彼の「小さな違い」の理論から始まり、親密さと分離の間の二分法が調査される。筆者は、差異は人間のアイデンティティと人間の発達の中心にあると主張し、なぜ我々がそれを受け入れようとするのかを探っている。全体主義的な政治システムは、違いを排除するものとして説明されている。ある患者が、共生的で未分化な状態から、対象との関係や個性化に向けて奮闘している事例を紹介している。
キーワード:文化複合体、差異、アイデンティティ、個性化、政治的舞台、分離、影、社会的背景、共生、全体主義的精神
はじめに
近年、精神分析の専門家の間では、差異と多様性が注目されている。これは、ポストモダンの考え方やより包括的な態度に影響された社会の変化と関係している。精神分析の専門家の間では、これまで軽視され、十分に理解されていなかった患者の問題を考えるために、主に人種、性的、文化的な違いについての調査が行われてきた。
私の目的はそれとは少し違う。私は、人間の条件の一部である違いの本質を探っている。私が興味を持っているのは、人間がどのようにして別々のアイデンティティーを持った異なる個人として成長していくのかということである。私は、差異の望ましいあり方と、それに対抗するもの、つまり、差異と類似性、距離と親密性の間の二項対立を探究する。議論していく。
- 発達的な観点から見た違いの起源
- 乳幼児期の発達と社会的・政治的生活との関連性
- 愛と憎しみの起源、そして敵の必要性
- 差異への攻撃としての全体主義者の心理
私の理論的枠組みは多様である。私の目的は、精神分析、ユング、関係性といったさまざまな理論を統合し、それらがどのように相互に補完し合うかを示すことである。精神分析のコミュニティでは、このような考え方や働き方を取り入れることへの関心が高まっている。私の考えでは、これは貴重で必要なことであり、古いものと新しいものの間のリンクを提供し、現在の議論と新しい開発を促進するものである。私は、共通点を見つけ、違いを尊重するという精神でこの文章を書いている。政治的、社会的、文化的な見解が二極化している現在の状況では、精神分析の専門家が、二極化とは無縁の健全な対話に基づいて、その貢献を続けていくことが不可欠である。このことが、この論文自体に反映されていることを願っている。すなわち、違いに触発された対話である。さらなる発展に向けた新たな創造的な出発を生み出すためには、対話から生じるかもしれない緊張感が保持されなければならない。
差異に関する精神分析理論は、その概念を包括的に理解するものではない。しかし、差異や多様性は、フロイトの仕事以来、議論されてきた。差異のないアイデンティティはありえないので、差異とアイデンティティは常に結びついている。以前書いた文章(Czubinska 2017)で、私はアイデンティティの概念を詳しく調べた。哲学の分野では、差異に関する批判的な言説が行われてきたが(Laruelle 1986参照)こうした探求は、人間の経験と主観性に基づいた精神分析的な見解とは相容れない。
私は、人間の精神の発達と独立したアイデンティティの形成に関連した差異についての精神分析的な理解に従うとともに、なぜ我々が差異を受け入れることに問題があるのかについて光を当ててみたいと思う。
初期の自我の発達と敵の必要性
フロイトは「些細な違いの自己愛」という言葉を使い、「各個人は『個人的な孤立のタブー』によって他人から隔てられており、…他の点では似ている人々の些細な違いこそが、彼らの間に奇妙さや敵意の感情を形成する基礎となる」と説明した(Fordham 1976, p. 199)。彼は後にこの考えに戻り、1930年には国際的な場における自己愛の役割について語っている。このことについては、後ほど触れたいと思う。
現代の精神分析家であるカール・フィリオは、この考え方をさらに発展させ、「違いは、無意識に圧倒される同質性の感情から我々を守るために作られる」と提案した。我々は、心理的な健康の基本である分離性を守るために、違いを必要としているのである。Figlio氏は、「我々が違いを嫌うという考えがあまりにも深く浸透しているため、我々が嫌うのは同じであるという仮説を考えるのは難しいかもしれない」と書いている(2012,p.8)。彼は、自己愛状態のパラドックスを、その幻想的な側面を指摘することで説明している。自我と対象が同一であるという幻想は、外部の対象に侵される不安から自我を守るために作られる。これは、自我の独立したアイデンティティを脅かすことになる。発達の初期段階では、この困難に対処するために投射が行われる。フィリオはフロイトに倣って、同一性の恐怖、すなわち自我のナルシシズムから自我を守るために、投射によって差異が作り出されると考えている。
同一性と差異の問題に関する様々な理論的立場を簡単に説明する。その中には、現代の関係論や愛着論も含まれる。
フロイトの発達理論は、胎児が母親との至福の結合を経験すると考えられている子宮にまでさかのぼる。共生は通常、この発達段階と関連しており、フロイトは、外界が自我の一部として経験される「一次的自己愛」と表現している。
フロイトの見解を包括的に修正したブラスとブラットは、人間が分離の名のもとに共生的な結合状態を離れようとする必要性と、同時に人生の過程で他の人間に執着し続ける必要性との間のパラドックスを指摘している。彼らは、マーラーの分離-独立の概念と人間のくっつきたいという欲求の橋渡しをし、共生は他者との関係性の不可欠な要素であり、アイデンティティの確立に不可欠であると主張している(1996, p. 712)。
近年、英訳されたアルゼンチンの精神分析医ホセ・ブレガー(1967/2013)の研究は、共生と分離の問題に重要な貢献をしている。ブレガーは、フロイトの「完全な孤立から個人が徐々に抜け出す」という仮説に疑問を投げかけている。その代わりに、「原始的な未分化」という言葉を人間形成の出発点として用い、外界の役割と重要性を強調している。この状態には、対象者の環境も含まれる(2013,p.4)。彼にとって、人間はもともと社会的な存在であり、さまざまな関係を通じてさまざまな段階の変容を遂げていく。この点で、彼は、幼児の観察に基づいて証拠に基づく発達のモデルを提供する関係的、対人的な思想家に近いものがある。例えば、Beatrice Beebe and Frank Lachmann (2013)、The Boston Change Process Study Group (BCPSG 2007)、Peter Fonagy er al)。 (2002)、Daniel Stern (1985)、Ed Tronick (2007)、Allan Schore (1994, 2003)などの研究は、人間の発達に関する新しい理解に重要な貢献をしている。これらのアプローチはそれぞれ異なっているが、その中心となるのは、主要な対象物に対する愛着の役割である。
ダニエル・スターンは、関係性の観点から執筆しており、乳児は主観的な自己意識を持って生活に入ると考え、一次共生の概念を否定している。これは、マイケル・フォーダムの見解(1976年、p.11ff.)と一致している。Jacoby(1994, p.116)は、より仲介的な立場を提案しており、主観的な経験は共生の状態で起こるため、融合と混乱の状態が個人の初期の人生に特徴的であると主張している。ユングはこのような状態を「無意識のアイデンティティ」あるいは「参加の神秘性」と呼んだ(Jung 1, paras.821 and 856)。しかし、いずれの立場も、母との最初の融合を否定するものではない。そこでは、2つの実体の間の境界は伝染的である。重要なのは、乳児と母親との間の同調の質であると思われる。
ギリシャ系フランス人の哲学者であり、精神分析医でもあるコルネリオ・カストリアディスは、母性的な部分である乳房の不在は、乳児にとって意味の不在を意味するとしている。その不在は、その喪失を容易に管理できないため、苦悩と憎悪を引き起こす。喪失感や苦悩という悪い経験を投影できる外部の対象が必要なのである。このようにして、敵が作られるのだと彼は示唆している。カストリアディスは、フロイトが1930年に書いた言葉を引用している。
1930:
スペイン人とポルトガル人、北ドイツ人と南ドイツ人、イギリス人とスコットランド人などのように、領土が隣接し、他の方法でも関係している共同体こそが、常に反目し合い、嘲笑し合っているのである。私はこの現象を「些細な違いのナルシシズム」と名づけた。
(フロイト1930年、p.114)。
フロイトが観察したことは、今日の国際舞台でも明らかである。このことは、精神の社会的性質を強調するものであり、関係分析家とは対照的に、古典的な精神分析の作家たちがあまり探求していないテーマである。歴史的に見ても、個人と社会のつながりは認められてきた。メラニー・クラインは「人格の理解は社会生活の理解の基礎である」と述べている(1959年、p.247)。ウィニコットは、「社会心理学や集団心理学の手がかりは、個人の心理学である」(1965年、p.146)と提案した。集団分析家のファラッド・ダラルは、「個人心理の手がかりは集団の性質にある」(1998年、p.158)と言って、これらの見解を覆すことを提案している。どちらの立場も、個人と集団を結びつけるという点では有効である。それぞれの視点は、集団の中で個人に何が起こっているのか、また集団が個人にどのような影響を与えているのかについての理解を深めるための視点となるだろう。
現代のユング派分析家であるブライアン・フェルドマン(2004)は、Fordhamの幼児期の観察研究に基づいた知見を提供し、それを組織のダイナミックさに結びつけている。乳児は生まれたときに母親から分離していると主張するフォーダム(1985)とは対照的に、フェルドマンは、乳児と母親の関係は流動的であり、一緒になったり離れたりする間にさまざまな段階があることを示唆している。これは、母親との融合を分離の前の初期段階と見なす分析者たちの見解に反するものである。フェルドマンの観察は、組織の中で個人が取る傾向のある異なるポジションを説明するという点で興味深い。フェルドマンは、乳幼児の発達における関係性の側面と、大規模なグループ内の力学との間に橋をかけているのである。このようにして、彼は組織行動における文化的差異を説明しているのである(2004,p.256)。我々が個人としてだけでなく、夫婦、家族、大集団、社会といった社会的な文脈の中でどのように機能しているのかを理解するためには、学際的なアプローチが有効である。
トーマス・シンガーは、『世界で何が起きているのか、集団心理で何が起きているのかを理解するためには、歴史、経済、社会学、人類学、宗教学の基本的な問題に関心を持つ必要がある』と書いている(2016,p.5)。彼とキンブルズやヘンダーソンなどの同僚たちは、大きな集団や社会の中や間の違いを説明するために、文化複合体の理論を用いている。この新しいポスト・ユンギアン理論では、個人のコンプレックスとグループのコンプレックスの間にリンクが張られている。差異は対立の中心にあり、緊張を生み出す。この緊張は、理解され、調整されない限り、潜在的に破壊的なものである。エド・トロニック(2007)は、シンクロニティー(同一性)を達成するために修復する必要のある、乳児と母親の間のミスマッチ(相違点)について語っている。幼児と母親のモデルは、大人の関係においても同じように機能する。差異を許容する能力は、人間関係の必然的な要素であるミスマッチや断絶を修復してつながりを維持するという、長期にわたる成功体験に依存する。
関係論や愛着論は、初期の自我の発達と分離・差異化のプロセスを探る膨大な研究を提供している。例えば、Beebe and Lachmann (2013) の研究では、赤ちゃんと養育者の間の一瞬一瞬の緊密な相互作用について述べており、それぞれの当事者が相互に影響し合っていることを明らかにしている。これらの相互作用は、乳児の内部作業モデルを作成し、そこから個人の基礎的な行動パターンが生まれる。
この論文の中心的な目的は、初期の乳幼児の発達を大集団の力学と社会的/政治的行動に結びつけることである。そこで、破壊的かつ創造的な力としての「敵」の重要性に立ち返ることにする。Rosemary Gordon Montagnon (2005)は、「Do be my enemy for friendship’s sake」という論文の中で、敵は我々が自分自身や自分の個性を失うのを防ぐものだと仮定している。したがって、自分を差別化して前進するためには、敵が必要なのである。彼女は次のように提案している。
敵は多くの場合、人と違うこと、人と違う外見、人と違う言葉で話すこと、人と違う行動、人と違う服を着ること、人と違う美学や宗教的・政治的規範を守ることによって、敵として認識され、マークされる。つまり、怒りや憤り、軽蔑を表現することができ、多かれ少なかれ、罪の意識を持たずに暴力を振るうことができると信じている相手がここにいるのである。
(Gordon Montagnon 2005, p. 28)
ゴードン・モンタノンは、政治的行動にも言及し、個人のアイデンティティを社会的アイデンティティと結びつけている。英雄の原型を例に挙げ、競争や達成しようとする決意を、内なる敵である弱さや受動性に対する攻撃のポジティブな側面と捉えている。
我々は同じであることを恐れているので、違いを投影する敵が必要である。同一性は、差別化されていない自己愛的な機能状態に戻してしまうため、個性的で独立したアイデンティティと自己意識を脅かする。
個人とカップルの関係
カップルの関係は、異性のカップルでも単性のカップルでも、憎しみを引き起こす同質性の無意識の幻影の間の葛藤を最もよく表している。ここは、二極化が起こりやすい領域である。アニムスとアニマ(Jung 1951, paras.296-340)という対立する原型は、カップルの間に葛藤を生み、多くの苦しみの源となる。人間が合併に憧れ、相手との一体感を感じるのは、恋に落ちるときの特徴である。その状態のパラドックスの1つは、自分の境界線を失い、それゆえに独立した人間としてのアイデンティティを失う恐れがあることである。
フロイトの小異説によれば、このジレンマの解決策は、カップルの中に小さな違いを作り出したり、誇張したりすることで、十分な分離感を確保することにある。同じであることへの恐怖が強すぎる場合、安全性を確保するために異なる文化や民族のパートナーを選ぶ人もいるだろう。最初は魅力的で快適に見えても、後になって憎しみや困難の原因となる。肌の色や文化的背景よりもはるかに深い問題を、違いのせいにしてしまうのである。恋人は完璧なミラーリングが行われなくなったことに失望するが、同時に自分の自律性が保たれていることに無意識のうちに安堵する。そのため、些細な違いは、消滅への最も原始的な恐怖を回避するという非常に重要な機能のために作られることが多いのである。ガバードは次のように提案している。
理想化された他者との融合は、愛の中で求められるが、同時に恐怖でもある。同一性へのあこがれと差異への失望は、エディプス前とエディプス期の両方の経験に発達上の先例があり、これらはすべて、分離性と自律性を維持するためのこの根本的な懸念と一致している。
(Gabbard 1993, p. 238)
ジェームス・フィッシャーはこれを「一体感と分離感の間の揺らぎの緊張に耐えられる対象関係の状態」と表現している(1999年、p.220)。
男性も女性も、愛の対象の中に自分の鏡像を見出すというファンタジーを持って恋愛関係に入る。この幻想は持続しない。愛する対象のわずかな違いであっても、恋人にとっては自己愛的な傷として経験されることがある。ボウルビーが説明した内的ワーキングモデルは、意識の外にある幼少期のパターンや経験を暗黙のうちに記憶している。親密な関係になると、我々は特にこれらのモデルに頼る傾向があり、以前に学んだ特定の反応を期待する。それが期待はずれであれば、衝突や断絶が起こる。もし、その断絶を修復する能力がほとんどなければ(前出のトロニック参照)愛着の連続性は失われ、双方にとって深刻な結果をもたらす。
ジーン・ノックスは、「愛の恐怖:人間関係における自己の否定」という論文の中で、愛の能力の発達について論じている。彼女は、このプロセスを分離-分離のプロセスと結びつけ、このプロセスが成熟したレベルに達しない限り、愛は恐れられ、避けられてしまうと説明している(2007,p.553)。
大集団の力学と全体主義的な心の状態
個人の精神と同様に、集団や社会も防衛システムを作ることで不安定さに対処する。全体主義はそのようなシステムの極端な形態である。
精神分析の理論によれば、全体主義的な精神状態とは、本質的に偏執狂的なシゾイド型の組織である(Klein 1959)。全体主義の精神状態は、精神分析理論によれば、本質的に偏執狂的なシゾイド組織であり(Klein 1959)ある集団が他の集団よりも劣っていると認識され、それを否定しなければならないという極端な空想と理想化に支配されている。全体主義体制の例としては、ナチズムとスターリン主義がある。私がこの2つの例を選んだのは、両者について比較的よく知っていることと、前世紀のヨーロッパの歴史に根本的な影響を与え、現在も与え続けているからである。私は、ナチスによって壊滅的な打撃を受けたポーランドで生まれ育ち、戦後のスターリン主義の現実を経験している。どちらの政権も、やり方は違っても、同じように不寛容で抑圧的であった。
スターリン主義では、階級闘争が重視され、ブルジョアや貴族の価値観を社会から根絶やしにするというファンタジーがあった。この空想は、これらの価値観に触れることで利益を得られるかもしれない人を排除することにまで及んだ。告発された人々は裁判にかけられ、あらかじめ用意された証拠に基づいて自白させられた。これらの裁判には演劇的な要素が含まれていた。なぜなら、両者とも偽物をやっており、それを知っていたからである。このような行為は、恐怖と政権の存続に対する恐怖が動機となっていた。アーマンド・イアヌッチ監督の最近の映画『Death of Stalin』(2017)は、これを完璧に描いている。監督はブラックコメディを通じて狂気を示し、本質的には多くの世代にとって悲劇的な結果をもたらすファンタジーが現実に演じられたことを特徴づけている。同様に、ナチス政権は、純化のイデオロギーとアーリア人以外の人種の排除に基づいており、その結果、さまざまな民族的背景や国籍を持つ何百万人もの人々、特にユダヤ人が大量に殺害された。
全体主義を最もよく表しているのは、ドイツ生まれのアメリカ人哲学者・政治理論家であるハンナ・アーレントである。彼女の主著である『全体主義の起源』(1951)は、全体主義の指導者や構造物の心や態度を知る上で豊富な資料となっている。彼女は精神力学的な考え方に共感し、心が空想に支配され、それが行動に移されることをよく理解していた。彼女は、ナチスとスターリンの両方のメンタリティを描写し、その違いと共通点を明らかにしている。どちらのイデオロギーも、先に述べたように、他の視点を排除することを基本としている。アーレントは、ヒトラーとスターリンの特徴を説明する際に、彼らの心が非合理的であること、彼らの行動が空想に基づいていること、そして、どちらのイデオロギーにおいても、権力を行使する手段としての恐怖の役割を強調するなど、似たような言葉を使っている。
マイケル・ラスティンは、「全体主義」とその他の権威主義的な政府の形態を区別している。彼は「その動機と組織において、集合的な無意識のファンタジーが果たすダイナミックな役割」を指摘している(2016,p.23)。全体主義システムを特徴づけると思われるのは、特に破壊的な性質を持つ、共有された無意識の心の状態である。大きな集団や社会は、極端な社会的混乱の状態にあるときに、こうした状態に陥りやすい。このような状態は、無意識のうちに、消滅の空想と高度な不安に支配されている。
フロイト(1921)の集団心理に関する研究では、無秩序な集団におけるリーダーの影響に注目している。全体主義のリーダーの場合、破壊的でカリスマ性のあるリーダーを見出すことができる。このリーダーは、他の集団を切り捨てることに加担するように周囲を説得する能力を持っている。このことは、ヒトラーが権力を握り、危機的状況の中で社会にアピールすることに成功したことからもわかる。彼は、敵を殲滅することで安定と繁栄をもたらすことができると信者に信じ込ませたのである。
全体主義的な精神状態は、安定性を確保するためには差異を攻撃しなければならないことを示す例である。安定したシステムは健全なシステムを意味しない。政治学者が分析した全体主義体制は、完璧な社会的・政治的国家を作るというイデオロギーに基づいてた。これを実行するためには、独裁体制を敷かなければならなかった。経済や生活のあらゆる面を監督、管理しなければならなかった。現状を維持するためには、対話や反対意見を排除しなければならなかった。集団やシステムが不安定であればあるほど、現状維持のために攻撃性を発揮しなければならない。ユングの対極の枠組みによると、精神の中には2つの対立する力からなるダイナミックなシステムがある。エネルギーの流れはそのダイナミックさに依存しており、創造性や新たな発展につながる。同じことが、健全性とバランスを維持するために同じダイナミックさを必要とする社会的・政治的システムにも適用できる。全体主義的なシステムでは、反対意見は排除されなければならず、潜在的な創造力は、押し付けられたイデオロギーを守り、支持することに転用される。
喪に服すことができないことと、その社会的、政治的な意味合い
自己愛的なグループや社会は、喪に服すことが困難であり、そのために破壊的でない機能の方法を開発することができない。その代わりに、古い幻想を維持することで変化に対して躁的な防衛が行われている。
ギリシャ・キプロスの精神科医、分析家、平和活動家であるVamik Volkan(1986)は、喪に服すことに関する集団的プロセスと個人的プロセスは同じではないと述べている。政治的、軍事的なストレスの下では、喪に服すプロセスは行われないかもしれない。理想化された対象物や領土が失われたために、人や国が怒りで喪に服すことができない場合があるのである。喪に服すことができないという概念は、国際紛争を理解するのに役立つと同時に、理想化された対象物を失っても悲しむことができない理由を説明しているという。ポロックは、「嘆くことができるということは、変化することができるということだ。嘆くことができないこと、変化を否定することは、個人や組織に大きなリスクをもたらす」(1961年 p.29)と説明している。
喪に服すことができなければ、損失の心理的影響は次の世代に持ち越され、痛みを克服するために復讐を強要するようになるかもしれない。これは、北アイルランドのカトリックとプロテスタントの対立や、イスラエルとパレスチナの対立など、世代間の対立に見られる。
ヨーロッパの分断
第二次世界大戦後、ポーランド、チェコスロバキア、ハンガリーなどソビエト連邦に近い地域は、スターリンの全体主義体制の下に置かれた。鉄のカーテンは、思想や情報の流れを止め、差異を抑えるために作られた。旅行は許されず、資本主義の西側に対するプロパガンダが盛んに行われた。西側でもプロパガンダは同様に行われた。東欧は立ち入り禁止区域であり、文化的に劣り、後進的であり、知る価値もないと考えられてた。訪問は非常に制限されていた。それらの国には、何か危険で暗いものがあるという幻想があった。これは、ナチズムと戦争によってすでに荒廃していたヨーロッパのこの地域にとっては悲劇であった。この体制下では発展が望めないため、国は非常に苦しんでった。
なぜヨーロッパが二層構造になっているのかを理解するには、戦後に起こったことをもっとよく知る必要があるかもしれない。また、EUの意味と重要性、そしてEU内のナショナリズム的傾向を理解することもできる。我々は、Brexitについて行われた議論から、帰属と分離に関する緊張を無視できないことを学んだ。それが演技につながり、悲劇的な結果を招くこともあるのである。
私の考えでは、ヨーロッパやその他の地域で生じているナショナリズムの傾向は、脅威にさらされている個人のアイデンティティを守るための手段として理解する必要がある。乗っ取られたり、同化されたり、取り込まれたりすることへの恐怖は、アイデンティティが失われ、自律的な存在でなくなるという最も原始的な幻想である。EUの中でヨーロッパのルールに最も異議を唱えている国が、共産主義の下で最も苦しんだ国であることは驚くことではない。これらの国の国民心理には、自分たちの統合性や分離性を脅かすような、新たな侵略や飲み込みに対する恐怖がある。例えば、これらの国で難民受け入れに反対するのは、自分たち固有のアイデンティティを失い、差異に侵されることへの恐怖からくる反応である。
差異は敵として認識され、その中に過去に属していた幻影や恐怖を容易に投影することができる。アウトサイダーである外国人は、既存のコミュニティを消滅から守るという機能を果たしている。これが最も深く、最も恐ろしい恐怖であるように思われる。しかし、ここにはパラドックスがある。共産主義の全体主義体制から逃れ、新たな民主的変化を期待して欧州連合に加盟した国々は、今、新しい傘下組織に反発している。この組織は、それらの国々の個別の歴史や国民のアイデンティティを認めていないように見えるため、抑圧的であると認識されている。新しい敵は、過去の出来事で傷ついたこれらの国の特徴を守るために作られた。
ヴォルカンによれば、「敵と自分との間の心理的なギャップを強めるために、(些細な違いを)作り出す」(1986年、187ページ)。敵の存在は、自分が属する集団の中でのアイデンティティや、自己意識を支えるために必要であると強調している。ヴォルカンにとって、社会的な場と政治的な場の間に心理的なギャップが必要なのは、つながりを保ちつつ、類似性に脅かされないための方法なのである。敵に夢中になることで、安全なリンクを作ることができるのである。些細な違いを作り出すことは、特に隣人のような自分に似た人々の間では重要なことのようである。例えば、ステレオタイプ化は、未分化に対する安全性を目的とした境界線を作る。
この分割と投影のシステムは、安定したシステムを作り出す。自己愛的な幻想が現実となり、争いや憎しみの原因となる。宗教や民族の対立の例は数え切れないほどある。最近のビルマでの民族浄化や、西欧諸国を脅かすイスラムのテロリスト集団などは、その一例である。全体主義的な在り方や関わり方では、Ronald Britton (1998)やその他の人たち(Bolas 1987,Ogden 1994, 2004,Gerson 2004,Benjamin 2004など)が述べている、いわゆる「第三の立場」が欠けている。ブリットンは、観察する自我が存在せず、二者択一の対立が活性化している状況を考える。一次的なナルシシズムの一体感が、投影や投影的な同一化によって分裂し、敵意と分裂した白黒の経験の世界を作り出す。サードポジションは、思考、創造、反省のための空間として理解されている。
ジェシカ・ベンジャミン(2004)は、「モラル・サードまたはサード・イン・ワン」という言葉を使い、個人が2つの相反するものを識別しながらも、同時に中立で両方につながっている能力を意味している。これは、ユングの対立概念と、その間の緊張を保つことで生まれる創造性を反映している。ベンヤミンの「第三性」に関する考え方は、クライニアンの視点とは異なり、関係分析家に特徴的な、より民主的で階層的でないアプローチを提案している。Gerson(2004)は、これを「関係的第三」と呼んでいる。
上述したフロイト理論やクライニアン理論に存在する主語と目的語の分化は、対立、相違、混乱を伴う可能性のある無意識のダイアドに注意を払う関係分析家によってさらに発展する。Ogdenの分析的第三の概念は、二者間の関係性の質に同意している点で他の著者と一致している。彼は、間主観性が分析的第三者として存在し、二者間のユニークな弁証法の産物であると観察している。この概念は、社会的、政治的な分野にも適用できるものだと思う。
全体主義者の精神では、そして全体主義体制の下では、反省や検討の余地がないため、思考の余地がない。代わりに、憎しみを伴う空想が演じられ、現実を支配する。恐怖の役割は、第三の立場を抑圧し、排除することである。差異と偏向は、反省、対話、妥協を伴うような三角形の空間を作り出すことによって媒介することはできない。対立する2つの立場のためのスペースはなく、したがって他のものが入る余地もない。ユングは、影に支配され、何が外部で何が内部なのか、何が空想に属し、何が現実に属するのかという感覚がないと言う。これは狂気の一形態と言えるだろう。
集団的な影の活性化と支配の問題は、ユングが「現代の出来事に関するエッセイ」(1931/1970)の中で述べている。彼の視点によれば、集団的プロセスは個人的プロセスと同じように、個人や集団の中に抑圧された要素が戻ってくることで発生するという。この問題をさらに分析すると、サム・キンブルズはバイオンの「ベータ要素」を喚起して次のように述べている。
このような心の前の状態では、すべてが強固になり、感情的・象徴的な空間が失われ
そして、イメージ、感覚、知覚、行動を融合させた生の感情状態が、耐え難い不安を解消するという唯一の目的を持った行動の可能性に集約されるのである。この領域では、我々はユングの言う精神スペクトルの赤外端に身を置いていることになり、そこでは境界線や人間が侵害され、破壊される。
(Kimbles 2014, p.56)
相談室での体験
ここからはコンサルティングルームに目を向けて、これらの問題のいくつかが患者との臨床的な状況でどのように現れたかを説明していく。この論文を考えているときに「アリス」が頭に浮かんだのは、彼女の障害の性質と、分離や違いに対する困難さのためである。これは非常に複雑で豊かなケースであるが、この論文の目的のために、長期間にわたって行われた作業のほとんどを要約する。この資料の使用については、患者から同意を得ている。
願わくば、彼女の内的現実や転移の本質を失うことなく、彼女の身元を守るために、個人的な詳細は変更されている。私が彼女について書く可能性について話し合ったとき、彼女は情報開示について何の不安も感じていなかった。これは、彼女が両親から人間性を奪われ、両親の延長のように扱われてきたことと関係があるのではないかと後に理解した。
私がアリスに会ったのは、彼女が20代の頃であった。彼女は自分の出自を説明するのが苦手であった。彼女はモロッコで生まれたが、彼女が幼い頃に両親がモロッコを離れたため、生まれた国への愛着はなかった。両親は若くして政治活動家となり、どこにも定住できなかった。彼女の父親はアイルランドからイギリスに移民してきた人で、南アフリカで人権擁護運動をしているときに妻と出会ったのである。父親は全体主義者で、政治活動のために家庭生活を犠牲にする利己的な男と言われていた。アリスは一人っ子で、両親が自分の要求を受け入れてくれない、理解してくれないと感じてた。
彼女の父親は、両親を早くに亡くした後、親戚から性的虐待を受けていたのである。父親は両親を早くに亡くした後、親戚から性的虐待を受けてた。それに加えて、父親がアリスを別の人間として認識していなかったことが、世代間のトラウマの原因となってた。彼女の母親は彼女を守ることができないようだった。父親は教育機関を信用していないので、彼女は学校に行くことを禁じられていた。自宅で家庭教師をすることも試みられたが、定期的ではなかった。アリスはグループに属した経験がなく、仲間がいたこともなかった。
アリスが14歳のとき、一家はアイルランドに移住し、そこでハンガリー人のボーイフレンドと出会った。ボーイフレンドも彼女と同じように困難な家庭環境から逃れてきた。彼は東欧からの新しい移民で、私の患者と同じように、新しいアイデンティティを求めてた。ロンドンに来たとき、2人は10代であった。アリスは初めて学校に通うことになった。当然のことながら、彼女の基礎教育には大きな隔たりがあった。彼女は看護師になることを選んだが、これは大きな妥協だった。夫婦の間には薬物やアルコールの乱用があった。夫婦の関係はセックスレスで、融合と外界への恐怖に基づいていた。私のイメージでは、森の中で迷子になったヘンゼルとグレーテルのような夫婦であった。彼女は仕事を転々とし、形式的な組織に収まることができなかった。うつ病で自尊心を失った彼女は、助けを求めに来たのである。
転移のダイナミズム
仕事の質は非常に高く、彼女のニーズは圧倒的であった。彼女は肥満であったが、ワークのかなり後半になるまで、自分の摂食問題を探る準備ができていなかった。彼女の母親が摂食障害に苦しみ、様々なダイエットをしていたことが明らかになり、それが娘への食事の与え方に影響を与えてた。アリスは従順であったり、非常に厳しい態度であったりした。完全なミラーリングの必要性が最も高く、私はそれを提供しなければならないと無意識に思ってた。私は「食べさせる」必要があったが、食べたいもの、消化しやすいもの、甘い味のするものに限った。これは、彼女が自分自身のためにも提供する食べ物であった。私が手を差し伸べようとしても、コントロールを失うことを恐れて私を信頼することができず、却下されることが多かった。同時に、これは大いに望まれたことでもあった。
ワークの最初の段階では、内面と外面、空想と現実の間の混乱が特徴的であった。彼女が自分の過去を話している間、私は彼女の躁的な興奮を感じた。彼女の感情は、私が聞いていた虐待の話の内容にそぐわないものであったが、それは私に平然と語られたものであった。私の仕事は、長い間、主に社内で行われてた。つまり、彼女の投影を封じ込め、耐えなければならなかったのである。共感を得ることは難しく、しかもその話は悲しく、心をかき乱すものであった。
やがて私は、彼女のコンプライアンスの下で動いている全体主義的な精神状態に気づくようになった。彼女はあまりにも助けを求めていたので、意見の相違を避けることができなかった。外見上、彼女は私が自分を理解していないこと、私には彼女を助ける能力がないことを主張していた。
彼女は強い政治的意見を持っており、それを対立を生み出す手段として使っていた。彼女は家庭での状況を私と再現する傾向があり、主に父親が彼女を支配し、しばしば彼女を貶めてた。幼少期の経験は、彼女の意識の中にはなく、解離していた。幼少期の記憶や母親との経験はなかった。Bion(1962)は、不在の対象が「現在の迫害者」として知覚されるという仮説を立てている。私はそのような対象として認識された。
我々のやり取りから、患者は自分の内面世界に侵入してくる可能性のある私から自分を守っていることがわかった。私は彼女のファンタジーの中で、彼女の支配欲求を脅かす対象として機能していた。私が共感した気持ちを解釈で表現しようとすると、彼女はまるで他の人のことを話しているかのように、それを否定しがちであった。彼女の身体は切り離され、無視され、過剰な消費によって酷使されていた。私の理解では、彼女は自分がされたことを自分の体にしている、つまり分離の境界線を尊重していないのである。
これを許容するのは非常に困難であった。おそらく、Bion(2005,p.64)が警告しているように、ある種の理解に、おそらく早急に到達しようとしていたからである。Bion (2005, p.64) が警告しているように、理解する前に我慢することが必要だと彼は言っている。この中断された知識は、アリスと一緒にいるための私の長い闘いの一部であった。
オリナーは解離を生存防衛と表現し、「解離は対処メカニズムであり、精神の生存を確保するために主観を圧倒的な経験から分離することを目的としている」(2012, p. 7)と述べている。これは、心に大きな傷を負った患者を担当する人にはおなじみのことである。私の患者にとって最も目に見えて明らかな解離は、身体と心の解離であった。生存のための防衛であったものが、問題となったのである。防衛システムが障壁となって、患者が自分自身や外の世界と関わるのを妨げてしまうと、精神に負担がかかる。
アリスが「大きい」ことについて言及するまでには、何年もかかった。彼女は、私が彼女を批判する可能性を先取りし、それを期待して、ある種の勝利感を持ってこの話をした。私は、否定されなければならない隠された恥を知り、それを勝利に変えた。
我々の言葉によるコミュニケーションには中断があり、彼女が私に飲み込まれないようにするために、しばしば痛みを伴う衝突が生じた。彼女のジレンマは、一方では近くにいたい、融合したいという欲求があり、他方では別々の存在として認められたいというものであった。彼女は、自分の感情をコントロールしやすい場所に仕事を移すために、知的な防衛手段を用いる傾向があった。私は様々な種類の講義を受けてたが、挑戦する余地はなかった。彼女にとっては、部屋の中で2つの心がお互いに影響しあっていることを受け入れるのは難しいことであった。どちらかが正しく、どちらかが間違っていなければならず、それによって致命的な結果がもたらされるのではないかという思いがあった。どちらが生き残るかはわからなかった。彼女の挑発行為は試されていて、私への攻撃は近づくにつれて激しくなっていきた。これに対処し、彼女のもろさを尊重するのは大変なことであった。非常に原始的なレベルで、彼女は生と死の間で葛藤し、私にしがみつきながらも、同時に信頼できずに私を遠ざけてた。これは、彼女の両親が一貫して彼女に接することができなかったため、愛着パターンが乱れていたことを反映している。
徐々に彼女の摂食障害に対する理解が深まり、彼女が自分の体を自分とは別の物として使っていることがわかってきた。身体は、彼女の精神の望まれない、表現されない側面を保管する場所となったのである。このような作業をしている間、私は自分の胃が特に活発に物質を処理していることに気づいた。私は胃を通して作業する傾向があるので、これは全く珍しいことではないが、アリスの場合は代謝しなければならない極度の感情があった。毎回、セッション後には空腹感があったが、何を食べていいのかわからず、胸が締め付けられるような不快感があった。患者と一つの胃を共有するイメージがあった。考え事をするスペースはなく、胃の中だけでなく、2人には狭すぎると感じる部屋の中にも緊張感が漂ってた。
ロンバルディはこう言う。これらの古風なレベルには、無関心さと具体性が特徴の非・前記号的な領域に近づくことが含まれる」(2017,p.35)。ホセ・ブレガーは別の重要な洞察を提供している:「患者の設定は、母親の身体との最も原始的な融合であり、精神分析家の設定は、元の共生を再確立するために役立つものでなければならないが、それを変えるためにのみ役立つものであると言うことができる」(1967/2013, p.240)。
ユング(1946)は、主語と目的語の混乱から生じる創造的な可能性を常に認識しており、それは不可避であると考えていた。彼の参加型ミスティークの理解と使い方は、ブレガーが言うところの、主観と客観の境界が不安定で、個人の成長が始まる前パラノイド-シゾイドのコミュニケーション状態に近い。このテーマは、Geraldine Godsil(2018)の最近の論文でさらに掘り下げられており、患者と分析者の共生的なつながりの残滓を象徴的なレベルで語っている。
アリスが心理療法士を選んだことについて、まるでスターリン後の異なる国での私の過去の経験を無意識に知っていたことが、彼女にとって重要であったのではないかと思い始めた。転移の中で、私は、彼女が挑戦しなければならない父親であると同時に、彼女が愛着を持ち、愛している父親でもあるように感じた。全体主義体制の中で育った経験を持つ私は、家族やグループに属するために個人的な経験を否定しなければならない、この種の忠誠心についてよく知ってた。
一緒に仕事をしている途中で、私は人生の様々な変化を経験し、しばらくの間、ロンドン以外の場所に住むことになった。そのため、アリスは通勤するか、私に会わないかのどちらかにならざるを得なかった。仕事を続けなければならないことはお互いにわかっていたので、決断は難しくなかった。数ヶ月後、私はロンドンに新しいコンサルティングルームを開設することができたので、我々は半分ずつ会うことができるようになった。
同時に、アリスは安定した仕事に就くことができ、パートナーと一緒に住宅ローンを組むことができるようになった。これはブレイクスルーことだと思った。彼女はいつも所有権をうらやましく攻撃し、自分の家にいる私を見て静かに憤慨していた。その嫉妬心は、彼女の分析の中でも強力かつ隠れた形で作用しており、私の解釈を受け入れて感謝の気持ちを表すことを妨げてた。それ以来、何かが変わり、我々は似てきて、おそらく「対等」になったのである。私の理解では、彼女は当時、違いが耐えられなかったので、私と同じであることを切望していたのである。
この段階でアリスは、それまで分析作業にほとんど参加していなかった母親のことを自由に話せるようになった。しかし、彼女がいない間も、彼女はとても存在感があった。彼女に対する怒りは殺人的であり、言葉では表現できないものだと感じた。彼女は殺されたのだ。
やがて彼女は、善と悪の間の混乱を理解し、同じ対象に愛と憎しみを感じることができるようになった。この混乱は、母親の未処理の投影に侵され、それを同化できなかったことに起因するのではないかと思った。ここでもバイオンの未代謝ベータ元素の理論が思い浮かぶ。彼は、不浸透性の物体にさらされた子供は、未処理の投影が「名もなき恐怖」という形で戻ってくるという。フロイトは『ヒステリーの研究』の中で、「精神的なトラウマ、より正確にはトラウマの記憶は、異物のように作用し、侵入した後も長い間、まだ働いているエージェントと見なされ続けなければならないと……推定しなければならない」(1893-95, p.6)と述べている。
何が悪いことで何が良いことなのか、アリスが混乱しているのは、自分の中に留まっている、自分の一部でありながら自分の一部ではない異物を取り除こうとしているからだと理解できる。逆転移に取り組む中で、私は時に行き詰まりを感じ、監督によるサポートを必要とした。自分の内なる分析者にアクセスすることが難しく、まるで自分も心身ともに侵されているような感覚に陥った。自分の中の分析的な「第三の立場」が、しばらくの間使えなかった。未分化な心の状態から対象世界への旅は、発展的な達成である。分析家は、患者の回復の一部である耐え難い心の状態と混乱に耐えなければならない。
アリスは何年も分析過程にあり、彼女の外面的な生活が改善されただけでなく、内面的な殺人的傾向が減少したという証拠がある。彼女は今、私を専制的な全体主義の父親としてではなく、自分が何者であるかを発見させてくれる、より温和な人物として見ることができるようになった。彼女は自己嫌悪に苦しみ、自分の体を攻撃し続けているが、いつ、何のためにそんなことをするのか、より自覚的になっている。私との最終的な別れに向けて、彼女はこの問題にもっと向き合わなければならないと感じている。両親との別れで多くの悲しみを経験したが、私との別れは、まだ考えられないほどの痛みと喪失感をもたらすだろう。
まとめ
この患者は、自分のルーツや出身国、所属する場所がなく、自分の違いやアイデンティティに悩んでった。彼女の家庭での混沌とした愛着は、貧弱な自己イメージと低い自尊心をもたらした。分析的プロセスによって、彼女はより安全な愛着の失われた経験のいくつかにアクセスし、最終的な分離の可能性に直面することができた。
私は、初期の共生関係と、身体と心の分裂を説明し、それが身体的転移を生み出した。摂食障害は、彼女が生きていることと分離していることを維持するための防衛システムとして作られたが、この解決は満足できるものではなかった。同様に、彼女の精神の中にある全体主義的な構造は、挑戦しなければならない別の防御システムとなった。
私との分析的プロセスは、より安全な愛着の可能性を提供し、最終的には「第三の立場」を経験できる過渡的な空間を提供した。我々はともに移民で、生まれた国には住んでいなかった。私は、患者の転居や、帰属意識と差異との葛藤を理解することで、新たな機会を得ることができた。我々は同じ社会文化的現実を共有しており、それが我々を結びつけた。このことは、彼女が新しい精神的な場所にたどり着き、そこで自分の独立したアイデンティティと自己意識を発見できる可能性を生み出したのである。
おわりに
この論文で私は、違いに関連する現象と、それに対する人間の困難さを理解しようと努めてきた。私が興味を持ったのは、無意識の内的心理的プロセスを社会的・政治的行動に応用することであり、幼少期と大規模な集団の力学との間に関連性を持たせることであった。
世界中でナショナリズム的傾向が高まっているのは、グローバリゼーションに対する反応であり、特定のイディオムや歴史を持つ国の個々のアイデンティティが消滅しているのかもしれない。このプロセスを止めることはできないが、異なる方法で管理することは可能である。敵を必要とすることは人間の条件の一部であり、なぜ敵が存在するのか、また敵が破壊ではなく発展にどのように貢献できるのかを知ることは興味深いことである。差異は、分裂を生み出す上で極めて重要だ。分裂がなければ、議論や対話の機会はない。分裂がなければ、議論や対話の機会はない。 分裂や反対意見は、行わなければならない議論のために必要である。分裂がなければ、議論や対話の機会は得られない。
