Democracy Incorporated
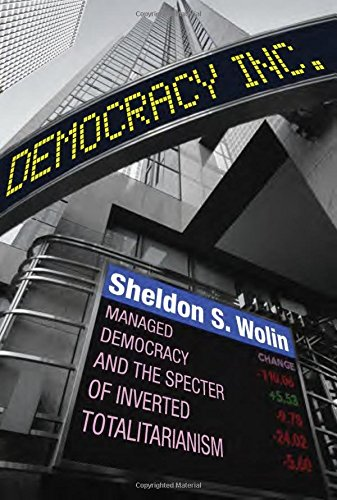
マネージド・デモクラシーと逆全体主義の亡霊
シェルドン・S. ウォーリン
カール・ショースクとエリザベス・ショースクへ
目次
- ペーパーバック版への序文
- 序文
- 謝辞
- はじめに
- 第1章 神話を創る
- 第2章 全体主義の逆転 恒久的な世界戦争という想像力の始まり
- 第3章 全体主義の逆転、民主主義の倒錯
- 第4章 新しい恐怖の世界
- 第5章 超大国のユートピア理論 公式版
- 第6章 変容のダイナミズム
- 第7章 アルカイックのダイナミズム
- 第8章 超大国の政治 マネージド・デモクラシー
- 第9章 民主主義に反対する知的エリート
- 第10章 超大国と帝国の時代における国内政治
- 第11章 逆全体主義 前例と先例
- 第12章 デモティック・モーメント
- 第13章 民主主義の展望 後方への展望
- ノート
- 索引
序文 変化への猶予
『Democracy Incorporated』は、アメリカ政治におけるある種の傾向を説明し、それが「逆全体主義」という独自の政治システムを強化するために役立っていると論じている。本書の要約を試みるよりも、むしろ、私の論点を無効化し、あるいは弱体化させるとも言える現代の政治的展開について考察してみたい。2008年にアフリカ系アメリカ人が大統領に当選するという前代未聞の事態が発生したことと、オバマ政権がブッシュ政権の行き過ぎた行為を速やかに是正するだろうという期待が広く共有されたことを指しているのだが、こうした期待の多くは、私が「民主主義の組み込み」の論文を支持する証拠として用いてきたものである。
オバマは、大統領選挙のテーマとして「変革」を掲げ、アップルパイのようなアメリカ的な思想を選択した。アメリカ人は、建国以来、自分たちを未来派とみなし、変化とその偽造品である新しさに対して、受容的で中毒的でさえあることが注目されてきた。一般に、変化とは事実上進歩と同義であり、ほとんどの国民の生活における着実な物質的向上や、子供たちのより良い未来が約束されていると考えられていた。したがって、変化は、ジャクソン民主主義に代表されるような、集団や階級間の力関係が大きく変化するような根本的な変化というよりも、機会の拡大と同定される傾向がある。根本的な変化のもう一つの例は、奴隷制の廃止である。しかし、第14条と第15条の修正条項の政治的約束は、間違いなく 2008年の大統領選挙まで実現されなかったのである。
アメリカの歴史の多くを通じて、政府は、根本的な変化を積極的に推進してきた。南北戦争の修正条項は、奴隷制度に関連した過去の過ちを取り消すことを目的としていた。ニューディール政策は、一般市民、特に貧困層の生活を著しく改善し、自由市場資本主義から、政府の重要なイニシアチブと経済への「干渉」が顕著な混合経済への方向転換を示すものであった。
このように、変化には二つの異なる概念があり、それぞれが政府の積極的な介入を伴うものである。ひとつは、緩和的変化、あるいは戦術的変化と呼ぶことができるものである。それは、力関係を大幅に修正することなく、状況や状態を是正しようとするものである(たとえば、「中産階級のための減税」)。もうひとつは、パラダイム・チェンジまたは戦略的チェンジで、新しいプログラムを導入するだけでなく、基本的な力関係を再構築するもので、改革し、権限を与え、新しい方向性を打ち出すものである(たとえば、単一支払い医療制度)。Democracy Incorporatedは、国家権力と企業権力の合体によって表されるパラダイム変化を表現している。
時には、パラダイム変化は、定着した、または長年の現状に対する攻撃の形をとる-例えば、前世のプランテーション所有者の力を減らすこと。また、緩和的な変化は、限定的な範囲で現状を回復するために、以前のパラダイム変化を元に戻そうとすることがある。例えば 2001年9月11日以降に始まった、政府による盗聴、モニタリング、適正手続きの否定といった抑圧的なパラダイムシフトは、適正手続きと修正第一条の権利をより尊重した以前の慣行を回復することによって、取り消されるかもしれない。
逆説的だが、オバマの勝利は、拘束者に対する拷問などブッシュ-チェイニー政権が導入した変化のいくつかを取り消す、ある種の現状維持への憧れ、反動であることが判明するかもしれない。もしそうなら 2008年の選挙で約束された変化は、パラダイムというより緩和的なもので、大きく異なる方向を選ぶというより、むしろ回復や修正を目指すものであるかもしれない。
20世紀半ば、冷戦とその国内外での反共聖戦に始まり、レーガンの反革命で強化された、変化に対する国民の執着は、経済や技術の強力な推進力を保持しながら、新しい自意識的保守主義に結びついた。それは、遠い「丘の上の都市」に向かって後ろ向きであることを公言する変化という、ユニークなダイナミズムであった。それは、過去を取り戻すという意味での逆進性ではない。むしろ、「新保守主義」は、「リベラリズム」に対する「文化戦争」の戦略として、理想化された神話的な過去に訴えたのである。政治的、宗教的、文化的な要素を組み合わせて、建国の父、「オリジナル」憲法、聖書、「家族の価値」、「伝統的結婚」の神聖さ、戦闘的愛国心に訴えるイデオロギーとしたのである(America, Love It or Leave It, and a militant patriotism. (その経済思想もまた、賢明な利己主義と「小さな政府」によって調和と繁栄がもたらされた「自由経済」という、想像上の過去に目を向けていた。
しかし、保守政治は単なるノスタルジーにとどまるものではなかった。非平等主義を意図的に推進することで、それは範例となる資格を得たのである。不変のものへの賛美は、平等主義的な社会プログラムによってもたらされた変化を可能な限り覆す、あるいは修正するという基本目標のためのイデオロギー的な隠れ蓑となった。多数を力づけるのに役立ったプログラムを縮小・廃止することで、非正規主義は国家権力と企業権力が一体となった構造を強化したのである。ジョージ・W・ブッシュ政権は、リベラルな社会プログラムと「寛容のリベラル文化」に対する攻撃を継続し、さらに強化したが、反共産主義が最初に生み出した力学に再び焦点を合わせる新しいパラダイムを代用したのであった。それは、帝国覇権の積極的な追求という、レーガン保守派の地方志向とは異なる強調を外に向かって押し進めるものであった。この新しいパラダイムは、これまでのナショナル・アイデンティティにはほとんど見られなかったユニークな特徴を示している。それは、テロリズムという、時間的、空間的、あるいは単一の固定された形態といった明白な限界を持たない敵を想定することによって、その支配の範囲を規定するものであった。このように、新しいパラダイムは、「共和国」や「民主主義」の影に隠れて、ナショナル・アイデンティティを再定義する記念碑的な変化を導入したのである。それまで大陸の下半分を示す名前であった「アメリカ合衆国」は、今や世界帝国を意味するようになった。
帝国はパラダイム的な変化であったが、その名を口にする勇気のない愛のように、大統領の役割が国家から帝国へと進化しているにもかかわらず 2008年の選挙戦ではそれが抑圧されたのである。その代わりに注目されたのが、アフリカ系アメリカ人の候補者が国の最高権力者の座を争い、勝利するという前代未聞の光景であった。この選挙が象徴する変化の程度と種類を評価する前に、その変化はどのような背景のもとに起こったのかを問う必要がある。20世紀を通じて、白人アメリカ人はアフリカ系アメリカ人のパフォーマー、つまり音楽家、俳優、女優、作家を受け入れ、崇拝してきたと言えるかもしれない。2008年の選挙後、環境保護団体、医療擁護団体、州知事、反戦団体、そして必然的に企業ロビイストなど、既存のあらゆる団体が次期政権に自らのアジェンダを押し付けるようになった。しかし、アフリカ系アメリカ人の支持団体は、あまり目立たなかった。自分たちの仲間」の選出は、力を与えるのではなく、抑制するという皮肉な結果を招いたのだろうか。
2008年8月以前は、国民が経済危機の到来を認識し始めた(あるいは認識させられた)とき、「変革」は主にイラクとアフガニスタンにおける米軍の作戦の終了と、社会経済的変化(医療保険改革、環境保護など)と政治改革(憲法保護の回復、拷問の禁止、行政権力の拡張概念の放棄など)の両方を約束するものであった。しかし、バグダッドにある巨大なアメリカ大使館建設の中止は語られず、オバマは2009年夏にイラクから大部分の軍隊を撤退させるというブッシュのスケジュールを守る一方、アフガニスタンへの軍事コミットメントを倍加し、タリバンをパキスタンまで追い詰めると約束しただけで、つまり、帝国の約束から切り離す話はなかったのである。
選挙直後から、オバマの言う変革とは極めて現実的なものであることが次第に明らかになった。具体的な変化の種類とその範囲と深さは、ブッシュ=チェイニーの政策に対する国民の反応の強さによって決まるのではなく、状況や政治的な計算によって決まるだろう。
つまり、パラダイムというよりは、緩和という意味合いが強いのである。その前提は、比較的少数の政治家、つまりエリートが存在し、その中から重要な人選を行うべきだというものであった。財務、経済政策、外交、規制政策、医療などの担当者に選ばれたのは、熟練した決定者であることが証明された。ダッシュルらの妥協的な内閣指名の失敗以前に、オバマの当初の内閣はクリントン派が中心であり、経済状況の深刻さが広く認識される前に選ばれていたことがうかがえる。つまり、経済がある程度軌道に乗り、イラク情勢が安定することを前提とした判断であった。このことは、オバマが大統領に就任する前から、民主党の指導者たちとともに、ブッシュ政権の最後の数週間に提案されたイニシアティブをほぼ踏襲していた事実が物語っている。その主なものは、難解でほとんど規制されていない業務が危機の主な原因である大手銀行や信用機関を6000億ドルで救済することであった。同時に、オバマ政権は、金融界で経験を積んだベテランを評議会に配置することを急いだ。巨額の資金と大胆な資金供与を除けば、ワシントンとウォール街の長年にわたる癒着の永続化以上に不変なものはないだろう。
社会の構成員が満足していると思われる繁栄期にはパラダイム・チェンジは起こりにくく、物事が非常にうまくいっていないときには、社会は大きな、それもパラダイム・チェンジを受け入れる傾向がある、と推測できるかもしれない。しかし 2008 年 11 月 4 日から 2009 年 1 月 20 日までの期間が短くなると、壮大な変革の約束は、経済の基本を変えるのではなく、経済を救済するための提案に取って代わられるようになった。経済がますます下降し始めると、変革の概念は縮小され、悪化する経済情勢に立ち向かうという新たな優先課題に従属させられなければならないのは必然であると、広く報じられるようになった。このように、変化が政策や行政の意思決定の優先順位と要件に屈するにつれて、変化の範囲 は「縮小」され、訳がわからなくなったのである。支持者たちも、オバマは少なくともブッシュよりはましだろう、変化とまではいかなくても、一息つけるだろう、と自らを慰めながら変化しはじめた。
複雑さとの遭遇によって政治的に冷静になったオバマは、ニュアンスを取り入れ、政治運動の美辞麗句を、「政策」と「意思決定」の慎重で内部的な言説に切り替えた。政策とは一般に、特定の目的や結果を達成するための一連のルールや行動指針を策定する試みと定義される。また、実質的な変化への取り組みが試される啓示の瞬間とも言えるかもしれない。オバマ政権の初期の決定から判断すると、イラクの明白な安定化と経済不況によってもたらされた二つのパラダイムチャンスは、「救済」あるいはできるだけ早く経済の現状を回復することと、アフガニスタン・パキスタン地域における帝国軍のプレゼンスを高めることを優先し、浪費された。危機は継続を求め、離脱を求めなかった。
失敗したのは銀行だけでなく、政治的、経済的想像力も同様であった。リベラル派の専門家やシンクタンクの職員は、絶望の中で、FDRのニューディールとその恐慌への対応にインスピレーションを見出そうと、「歴史的」な道を歩むことにしたのだ。FDRが当時の大銀行家(彼は彼らを「経済的王党派」と呼んだ)ほど袂を分かった相手はいなかったことを見落としていることに加え、FDRの行動の要点は、彼が前任者の真似をしようとせず、自分のプログラムのために以前の前例を求めなかったことである、ということは、既成概念論者には思いもよらなかったようである。その代わりに、彼は革新すること、より正確に言えば、パラダイムの変化を試みることを選んだのである。1930年代には「ニューディール実験」という言葉がよく使われ、通常のビジネスから脱却し、新しい、まだ試されていないアイデアを試すことを示唆していたにもかかわらず、ニューディールを語るとき、「実験」という概念をほとんど使わないのは、現代の深い保守性を示しているといえる。また、FDRがプログラム的な行動を要求する民衆運動によって下から圧力を受けていたことも見落とされていた。ヒューイ・ロングの「富の分配」、全市民の所得保証を求めるタウンゼント・プランなどである。
FDRとニューディールが変化の機会を利用したとすれば、オバマとその政権は変化の限界を自動的に引き受けることになったのである。このことは、20世紀における真に深遠な変化、すなわち政治的、経済的、文化的に企業の力が支配的になったことが、同様に深遠な変化、すなわち市民の効果的な管理を生み出さなかったか、という問題を提起している。明らかに、企業の支配と管理された有権者というこの2つの進展は、ある種の政治的硬直性を示唆している。このことは、現在の苦境の最も顕著な側面である、経済の正統性というテーマのバリエーション以外の選択肢の不在に反映されている。銀行の国有化が提案されたとき、それは「社会主義」に等しいと非難され、すぐに嵐を引き起こした。オバマ政権はパニックに陥り、直ちにそのような計画はないと宣言し、より想像力に富んだ救済策を自ら否定することになった。
この反応は、現在の正統派から逸脱した知的な提案が少ないという、もう一つの大きな逆行する変化を示している。それは、知的・思想的影響力が学界からシンクタンクに移行し、その大半が保守的で企業スポンサーに依存しているという、静かだがパラダイム的な変化の反映である。シンクタンクは、新しいパラダイムに挑戦する「非現実的な夢想家」や正統派の挑戦者である異端児を収容し育ててきたが、政策立案者に影響を与えることを目的としているため、その視野は現実性の要求によって制限され、企業スポンサーの利害によって、緩和的変化を提案することに制限される。
オバマ次期大統領は就任直前、広範囲に及ぶ社会・経済改革のための公約の一部を縮小する必要がある理由を、「後ろを向くのではなく、前を向かなければならない 」と言って説明しようとした。事実上、それは昔で、今は今である。しかし、オバマの発言は、二つの点で誤解を招くものであった。第一に、新政権が導入しようとしている解決策のシステム的な意義について、率直さに欠けるものであった。金融機関を復興の手段とすることは、国家と企業の同盟関係を強化することだ。銀行や金融機関の役員に政府代表が就任することの意義は、事実上、この提携とパラダイムシフトを正統化することであった。このようなパラダイムシフトは、ゼネラルモーターズ(GM)の救済に顕著に表れている。救済の条件は、強力な労働組合である全米自動車労組の共闘と無力化を伴うものだった。救済措置の条件として、政府、つまり「納税者」はGMに500億ドルを貸し付けた。クライスラーの55%の株を買わされた組合は、今度は年金基金を取り崩してGMの17.5%の株を購入しなければならなくなった。さらに組合は、賃金の凍結とストライキの禁止を約束した。その見返りとして、組合はGMの取締役会の代表権を得たが、その株式には議決権が与えられないという但し書きがあった。また、労働組合は、組合員の数千人の雇用を失うことを受け入れることに同意した。この「合意」のもとで、組合は事実上、法人化され、自らの屈辱の当事者となり、GM自体の将来が極めて疑わしいことから、すべてを失う可能性に直面することになったのである。
オバマの後ろ向きな姿勢は、大統領選挙で公約した政策を放棄したこと以上に深い意味がある。オバマは大統領就任当初から、議会共和党に「手を差し伸べる」ことで、変革を超党派で行うことを明言していた。この戦略の決定的な帰結は、ブッシュ政権関係者の弾劾されうる行動、とりわけ「署名文」を含む大統領権限の極端な拡大、拷問の実施、適正手続きの否定、そして何よりもイラク戦争を正当化するために用いられた嘘について国民を啓蒙しようとする真剣な試みを抑圧することであった。サンタヤーナの有名な言葉、「過去を忘れた者はそれを繰り返す運命にある」が、これほどまでに的を得ていることはない。ブッシュ政権がクリントン大統領の弾劾に至ったことと比較すれば、オバマ政権の視野の狭さがよくわかる。オバマが自伝で書いた「希望の大胆さ」は、確かに自らの当選という事実によって果たされたが、その大胆さは、国家に果てしない戦争、破産、不況、高い失業率をもたらした権力体制に挑戦しているようには見えないのである。この後のページで説明するような体制への流れが、多くの変化をもたらしているのである。
2009年7月
序文
誤解を避けるために、本書で取り上げたアプローチについて強調しておきたい。ヒトラー・ドイツへの言及は、海外に侵攻し、公式の教義として先制攻撃を正当化し、国内ではあらゆる反対勢力を弾圧する権力システムのベンチマークを読者に思い起こさせるために導入された。これらのベンチマークは、立憲民主主義の基本原則に反する、わが国の権力システムの傾向を明らかにするために導入された。こうした傾向は、支配、拡大、優越、至上主義に執着するという意味で、全体化であると私は考えている。
ムッソリーニやスターリンの体制は、全体主義がさまざまな形態をとることが可能であることを示している。たとえば、イタリアのファシズムは、反ユダヤ主義を公式に採用したのは政権の後半になってからであり、それも主としてドイツからの圧力に応じたものであった。スターリンは、大衆識字と医療を推進し、女性に専門的・技術的職業に就くことを奨励し、(短期間ではあるが)少数民族文化を振興するという「進歩的」政策を導入した。重要なのは、これらの「成果」が、その恐怖がまだ完全に理解されていない犯罪を補うということではない。むしろ、全体主義には局所的なバリエーションがある。もっとも、20世紀のバージョンに飽き足らず、今や全体主義者となる者は、20世紀以前のものをはるかにしのぐ支配、威嚇、大衆操作の技術を手に入れることができる。
ナチスとファシスト政権は、国家権力を獲得し、再構成し、独占するだけでなく、経済を支配することを目的とした革命的な運動によって動かされた。国家と経済を支配することで、革命家は社会を再構築し、動員するために必要な力を手に入れた。これに対して、逆全体主義は、国家を中心とした現象にすぎない。主に、企業権力の政治的成熟と市民の政治的非動員化を意味する。
古典的な全体主義が、社会を先入観に基づく全体像に押し込もうとする意図を公然と誇ったのとは異なり、逆全体主義は、イデオロギーとして明示的に概念化されたり、公共政策として対象化されたりすることはない。典型的には、権力者や市民によって推進され、彼らはしばしば自分たちの行動や不作為のより深い結果に気づいていないように見える。そこにはある種の無頓着さがあり、先入観なしに結果のパターンがどの程度まで形成されるかを真剣に受け止めることができない2。
この根深い不注意の根本的な理由は、よく知られているように、アメリカ人の変化に対する熱意と、それと同様に、天然資源に恵まれた広大な大陸を自由に使えるというアメリカ人の幸運が関係しており、搾取を誘発しているのである。アメリカ社会の歴史が絶え間ない変化の歴史であったことはよく知られているが、今日の変化のスピードが速くなっていることがもたらすものは、それほど明白ではない。変化は、既存の信念、慣習、期待を置き換える働きをする。歴史を通じて社会は変化を経験してきたが、イノベーションの促進が公共政策の主要な焦点となったのは、過去4世紀ほどのことだ。今日、高度に組織化された技術革新の追求とそれが奨励する文化のおかげで、変化はかつてないほど急速に、より包括的に、より歓迎されるようになっている。我々は、同時代性の勝利と、その共犯者である忘却または集団的健忘を経験しているのである。少し違う言い方をすれば、近世には変化が伝統を追いやったが、今日では変化が変化を引き継いでいる。
絶え間ない変化がもたらす効果は、統合を弱体化させることだ。例えば、南北戦争から1世紀以上経っても奴隷制の影響が残っていること、女性が選挙権を得てから1世紀近く経ってもその平等性が争われていること、公立学校が実現してから2世紀近く経った今、教育の民営化が進んでいることなどを考えてみるといい。変化の問題を理解するために、17世紀後半から18世紀の啓蒙主義の時代にかけて、政治家や知識人の間で、有史以来初めて、人間が自分の未来を意図的に形作ることが可能であるという確信が広がっていたことを思い出してほしい。科学と発明の進歩のおかげで、変化を「進歩」としてとらえることが可能になったのである。進歩とは、建設的な変化であり、世の中に新しいものをもたらし、すべての人に利益をもたらすものであった。進歩の擁護者たちは、変化により既存の信念、慣習、利益が消滅したり破壊されたりするかもしれないが、これらの大部分は消えて当然であると信じていた。
この近世の進歩の概念における重要な要素は、変化は、その決定に対して責任を負うことができる人々による政治的決定の問題である、ということであった。変化についてのこの理解は、19世紀後半に起こった経済力の集中の出現によって、かなり圧倒された。変化は、搾取と日和見主義から切り離せない私的事業となり、それによって、資本主義の力学の主要な、いや、主要な要素を構成するようになった。日和見主義とは、搾取できるものを絶え間なく探し求めることであり、やがてそれは、宗教、政治、人間の幸福に至るまで、事実上あらゆるものを意味するようになった。そして、やがて、宗教から政治、人間の幸福に至るまで、ほとんどあらゆるものがタブー視されるようになり、やがて変化は、利益を最大化するための計画的な戦略の対象となったのである。
今日、変化はかつてないほど急速で、より包括的なものになっていると、しばしば指摘される。この後のページで、私は、アメリカの民主主義は決して真に統合されたものではないことを指摘したい。その重要な要素の中には、実現されていないものや脆弱なものが残っており、また、反民主的な目的のために利用されているものもある。政治制度は、通常、社会が変化を秩序づけようとするための手段として説明されてきた。政治制度は、公権力の行使と制限、および役職者の説明責任を規定するための比較的不変の構造として、憲法の理想に例示されるように、それ自体が安定的に推移することが前提であった。
しかし、今日、ある政治的変化は革命的であり、ある政治的変化は反革命的である。あるものは国家の新しい方向性を示し、アメリカの権力を国内的にも(市民のモニタリング)国外的にも(海外に700ある基地)以前の政権が想像したこともないほど拡大する新しい手法を導入するものである。また、中流階級や貧困層の救済を目的とした社会政策の転換という意味で、反革命的な変化もある。
現代政治の実際の方向性は、政治指導者、マスメディア、シンクタンクの神託が主張するものとは正反対の、民主主義の世界的な模範となる政治体制に向かっていることを読者にどのように説得するのだろうか。本書をファンタジーと呼ぶ人もいるが、政治における大金の役割、マスメディアの信頼性、投票結果の信頼性など、「国家の向かうべき方向」に対して、広く市民が不安を募らせていることは確かであろう。2006年の中間選挙は、国民の多くが誤った戦争の早期解決を望んでいることを明確に示していた。一般市民が「自分の国が分からなくなった」と訴えるのを耳にすることが多くなった。先制攻撃、拷問の横行、国内スパイ、企業や政府の上層部の腐敗に関する果てしない報道は、この国の政治に何か深い問題があることを意味している。
この後の章では、起きている変化とその方向性を理解するための焦点を定めてみたいと思う。しかし、まず、民主主義が完全に実現されたわけではないにしても、少なくとも印象的な数の民主主義が存在したと仮定し、さらに、何らかの根本的な変化が起きていると仮定すると、「民主主義は何が原因で非民主的あるいは反民主的な制度に変わるのか」「民主主義はどのような制度に変わりそうなのか」という幅広い問いを提起することができるだろう。
何世紀にもわたって、政治家たちは、本格的な民主主義が覆されると、いやむしろ覆されたときには、専制政治に取って代わられると主張してきた。その主張は、民主主義は大きな自由を認めるがゆえに、本質的に無秩序になりやすく、富裕層が独裁者や暴君を支持するようになる可能性が高い、必要ならば冷酷に秩序を押し付けることができる人物である、というものであった。しかし、これこそわれわれの調査が扱う問題である。もし民主主義がその大衆文化においては自由(「何でもあり」)になりがちでありながら、政治においては恐怖に陥り、「テロリストを根絶する」と約束しながら、努力は終わりの見えない「戦争」であると主張する指導者に疑いの余地を与える用意があるとしたらどうだろうか。そのとき、民主主義は従順になり、手に負えなくなるというより私物化され、市民と政治的決定者との力関係を変えることになるかもしれない?
用語について一言。「スーパーパワー 」とは、力の外への投射を意味する。それは不確定で、束縛に苛立ち、境界を気にせず、自らの意思を時と場所を選ばず押し通す能力を開発しようとするものである。憲法上の権力のアンチテーゼである。「逆全体主義」は、権力を内側に投影する。ナチス・ドイツ、ファシスト・イタリア、スターリン・ロシアに代表される「古典的全体主義」からの派生ではない。これらの政権は、国家権力を奪取し、再構築し、独占することを目的とした革命的な運動によって動かされた。国家は権力の中心であり、社会を動員し再構築するために必要な力を提供するものと考えられていた。教会、大学、企業組織、報道・言論機関、文化機関などは、政府に買収されるか、無力化されるか、弾圧された。
これに対して、逆全体主義は、国家の権威と資源を利用しつつ、福音主義宗教など他の形態の権力と結合することによって、そして最も注目すべきは、伝統的な政府と現代の企業法人に代表される「民間」ガバナンスのシステムとの共生を促すことによってそのダイナミックさを獲得している。その結果、独自のアイデンティティを保持する対等なパートナーによる共同決定システムではなく、むしろ企業権力の政治的成熟を象徴するシステムが生まれたのである。
資本主義が最初に知的構築物として表現されたとき、主に18世紀後半に、それは、絶対王政とは異なり、一個人や政府機関が指示することができない、あるいは指示すべきシステム、分散型権力の完成形として歓迎された。また、「市場」が自由に活動できるように、分散した権力は放っておくのが一番というシステム(レッセフェール、レッセパッセール)として描かれた。市場は、自然発生的な経済活動を調整し、交換価値を設定し、需要と供給を調整するための構造を提供するものであった。アダム・スミスの有名な言葉にあるように、市場は、たとえ参加者が利己的な動機で動いていたとしても、見えない手によって参加者をつなぎ、彼らの努力を全員の共通の利益になるように導くものである。
スミスの主張の基本は、個人は小さな規模で合理的な意思決定を行うことができても、社会全体を合理的に理解し、その活動を指揮する力を持つ者はいない、ということであった。しかし、その100年後、企業の出現と急速な発展により、経済活動の規模は大きく変化した。無数のアクターに権力が分散し、市場は誰にも支配されないと思われていた経済が、価格、賃金、原材料の供給、市場への参入などを決定する(あるいは強く影響する)信託、独占、持ち株会社、カルテルなどの権力の集中形態に急速に取って代わられたのである。アダム・スミスはチャールズ・ダーウィンに、自由市場は適者生存に結びついたのである。企業の出現は、これまでにはなかった規模と数の私的権力の存在を示し、市民団体とは無縁の私的権力の集中を意味した。
企業が政治と経済を支配しているにもかかわらず、政治的、経済的に断固とした反対運動が起こり、企業の権力と影響力を抑制することを要求した。大企業は大きな政府を要求していると主張された。大きな政府、あるいは小さな政府でさえも、ある程度の無関心さを持たなければ、結果として企業権力と政府が共に利己主義という同じ生地から作られるという、両者にとって最悪の事態になる可能性があると考えられたが、しばしば忘れ去られていた。しかし、19世紀末から20世紀初頭にかけてのポピュリストや進歩主義者、労働組合員や小農民は、さらに一歩進んで、民主的な政府は無関心であると同時に「利害関係者」であるべきだと主張した。政府は、共通善と、人数が主な力の源泉である普通の人々の利益の双方に奉仕すべきである。彼らは、おそらく素朴に、民主主義では国民が主権者であり、政府は定義上、国民の味方であると主張した。主権者である国民は、資本主義経済が生み出す不平等を是正するために、政府の権力と資源を利用する十分な権利があったのである。
この信念は、ニューディール政策によって裏付けられ、確固たるものになった。さまざまな規制機関がつくられ、社会保障制度や最低賃金法が制定され、組合は団体交渉権とともに正当化され、公共事業や自然保護などの政府プログラムによって大量失業を減らすためのさまざまな試みが行われた。第二次世界大戦が勃発すると、ニューディールは、強制的な動員、経済全体の政府管理、成人男性人口の大部分の徴兵制によって取って代わられた。この戦争は、実質的に、この国で社会民主主義の暫定的な始まりを確立するための最初の大規模な努力の終わりを意味した。この社会民主主義は、多くの人々に恩恵を与える社会計画と、活発な選挙民主主義と政治的に無力な人々を代表する個人や組織による活発な政治活動とが結びついたものであった。
戦争は、政治的・社会的民主主義の勢いを止めると同時に、企業と国家の間のますますオープンな同居の規模を拡大させた。このパートナーシップは、冷戦時代(1947-93)にますます緊密化した。企業の経済力は、国家が依拠する権力の基盤となり、国家自身の野心も、巨大企業の野心と同様に、より拡大し、よりグローバルになり、時にはより好戦的なものになった。国家と企業はともに、科学技術に代表されるパワーの主要なスポンサーであり調整役となった。政治的、道徳的、知的、経済的な境界線に挑戦するだけでなく、その本質として、これらの境界線に絶えず挑戦し、地球そのものの限界にさえ挑戦するのである。これらの力はまた、政治的受動性を受け入れながら、変化と私的快楽を歓迎するよう消費者に教える文化を作り出し、広める手段でもある。その結果、(18世紀的な意味での)共和制というよりは帝国的で、民主主義的でもない、新しい「集団的アイデンティティ」が構築された。この新しいアイデンティティには、国民としてのわれわれは何者か、われわれは何を支持し何を支持するのか、われわれはどの程度まで共通の問題に関与するのか、国民のエネルギーと富を費やし、国の運命が国民の支配から急速に離れていく中で一部の国民に殺害と犠牲を求めることを正当化する民主主義の原則とは何か、という問題が含まれている。
しかし、我々の社会のある種の傾向は、自治、法の支配、平等主義、思慮深い公開討論から遠ざかり、私が「管理民主主義」と呼ぶ、逆全体主義のスマイリーフェイスのような方向へ向かっていると確信している。
今のところ、スーパーパワーは後退しており、逆全体主義は完全に実現された現実というよりも、一連の強い傾向として存在している。これらの傾向の方向性は、我々自身に問いかけるものであり、民主主義のみが「我々」を用いることを正当化する。
i
レニ・リーフェンシュタールがヒトラーに捧げた有名な(あるいは悪名高い)プロパガンダである『意志の勝利』は、1934年のニュルンベルクでのナチ党の集会を記念したものである。この作品は、ドラマチックで啓示的な瞬間から始まる。カメラはどんよりとした雲に覆われた空に向けられている。すると、突然雲が切れ、小さな飛行機が滑空してくる。飛行機は急降下して着陸し、制服を着た指導者が現れ、賞賛する群衆と党員たちの敬礼の前を凱旋して歩く。映画が終わりに近づくと、カメラは制服姿のナチが列をなして延々と続くパレードに釘付けになり、肩と肩を並べて、ゆらめく松明の中で雁字搦めになる。その光景は、今日でも、鉄の決意、征服のために構えた権力、断固とした権力、無心、神話に包まれた権力という印象を残している。
2003年5月1日、またしても緊密に仕組まれた「ドキュメンタリー」で、テレビ視聴者はアメリカ版の厳しい決意とそれを体現するリーダーを目にすることになる。空から軍用機が舞い降り、空母に着艦する。カメラははるか海上の軍艦のような錯覚を起こさせ、国土にとらわれない、世界のどこにでも通用する力を象徴している。リーダーは、平凡で民主的な役職者としてではなく、反民主的な象徴的権威を持つ者として登場する。飛行用ヘルメットを小脇に抱え、軍用パイロットの装備を身にまとい、毅然とした態度で歩を進める。頭上には “Mission Accomplished “の横断幕が掲げられている。あらかじめ用意された軍服の群れに敬礼する。その直後、彼は威勢よく民間の服装で現れたが、反民間の権威のオーラは捨てなかった。彼は空母エイブラハム・リンカーンの飛行甲板から魔術のように語り、周りは軍人で固められている。彼は、リーダーシップと服従の聖餐式を表現する儀式の輪の中に一人で立っている。それを合図に歓声と拍手が起こる。彼は、より高い力の祝福を呼び起こす。彼もまた、意志の勝利を約束したのである。
米国は
- 人間の尊厳のための願望を支持する。
- 世界的なテロリズムに打ち勝つために同盟関係を強化する。
- 地域紛争を和らげる。
- 敵が大量破壊兵器でわれわれと同盟国を脅かすのを阻止する。
- 世界経済成長の新時代を切り開く
- 社会を開放し、民主主義のインフラを構築することにより、開発の輪を広げる。
- 米国の国家安全保障機構を変革する。
権力に包まれた神話?権力への意志か?
2. どちらの光景も、神話創造という近代的な様式の顕著な例である。これらは、視覚メディアの自己意識的な構築物である。映画とテレビには、ある意味で専制的であるという共通の性質がある。映画やテレビは、修飾や曖昧さ、対話をもたらす可能性のあるもの、創作の全体的な力、印象の全体性を弱めたり複雑にしたりする可能性のあるものを遮断し排除することができるのである。
不思議なことだが、こうしたメディアの効果は、宗教的な実践とかみ合う。多くのキリスト教の宗教では、信者は儀式に参加し、映画やテレビを見る人は提示されたスペクタクルに参加する。どちらの場合も、民主的な市民がするはずの、決定に積極的に関与し、権力の行使を共有するような参加はしていない。彼らは、儀式の主が定めた儀式に参加する者として参加している。ニュルンベルクやエイブラハム・リンカーン号に集まった人々は、指導者と権力を共有していたわけではない。彼らは、不思議な力によって、その力によって選ばれた形とタイミングで恩恵を受けたのである。
このような栄光、「アメリカの世紀」、スーパーパワーの夢の根底にある形而上学は、ある政権高官が記者に「現実」の見方を帰属させ、それを政権のそれと対比させたときに明らかになった。記者や解説者は「我々(つまり政権)は現実主義コミュニティと呼んでいるが、それは、見分けられる現実を慎重に研究すれば、解決策が生まれると信じている。それはもう世界の常識ではありえない。我々は今、帝国であり、自分たちで現実を創り出しているのである。そして、あなたがその現実を研究している間にも、我々はまた行動を起こし、別の新しい現実を創り出す。我々は歴史の役者であり、あなた方は、我々のすることをただ研究することになるのだ」3。
真の政治とは本質的に「意志」の問題であり、権力の使い方をマスターし、現実を再構築するためにそれを展開しようとする決意であるという全体主義の信条を、これ以上忠実に代表するものはないだろう。この言葉は、リーフェンシュタールの『意志の勝利』の碑文にふさわしいものだが、アメリカの民主主義の碑文になりうるだろうか。
第1章 神話を創る
i
ロバート・S・ミューラー3世[FBI長官]とパウエル国務長官が聖書を朗読した。ミューラー氏のテーマは、「善対悪」。
「私たちは血肉と闘っているのではなく、支配者と闘い、権力者と闘い、現在の闇を支配する宇宙的な力と闘い、天の場所にいる悪の霊的な力と闘っている」
と、エペソ6:12-18を読み上げた。
続いて登場したパウエル氏は、神への信頼について触れた。
「だから、明日のことを思い煩ってはならない。明日は自分のことで精一杯なのだから」
と、パウエル氏はマタイ6:25-34を朗読した。
世界貿易センタービルディングを標的に選んだことで、テロリストたちは、21世紀の世界の特徴として、自由市場とそれに密接に関連する米国やその他の国の政治体制である民主主義の優位性を逆説的に演出してしまったのだ。
-マイケル・マンデルバウム2
1933年のドイツ連邦議会(ライヒスターク)の焼き討ちが、独裁による議会政治の破壊を予感させる象徴的な出来事だったとすれば 2001年9月11日の世界貿易センタービルの破壊とペンタゴンへの攻撃は、アメリカの政治史における啓示の瞬間であった。
選ばれた標的は何を象徴していたのだろうか。ライヒスターク火災とは異なり、今回の攻撃は、立憲民主主義の建築物とそれが象徴する権力システムを狙ったものではない。議会議事堂もホワイトハウスも攻撃されなかったし3 、民主主義の象徴である自由の女神、リンカーン記念館、独立記念館も攻撃されなかった。その代わりに、財力と軍事力の象徴である建物が実質的に同時に攻撃されたのである。米国がテロとの戦いを宣言すると、当然ながら、9.11の標的が象徴するグローバル化するパワーの実体を海外に投影することに注目が集まった。しかし、9.11の衝撃は、建築の象徴が無視された国内の権力システムに対する脅威を加速させるという点でも、同様に重要であることが証明されたのではないだろうか。
ii
9.11をきっかけに、テレビ、ラジオ、新聞などのメディアは一斉に行動し、一線を画し、その線引きと役割が何であるかを直感的に理解した4。その後の展開は、近代メディアの最大の成果であり、「新しい世界」とすぐに暗に表現されたものへの貢献だったかもしれない。ツインタワーの破壊を鮮やかに表現したメディアは、揺るぎない、疑いのない解釈を伴って、アメリカの脆弱性のイメージを固定化するという教訓的な目的を果たすと同時に、文化支配の可能性をも試したのである。
ある識者が好意的に書いているように、「この国に蔓延する恐怖は、過去10年間の自己満足の多くを洗い流す浄化剤として機能した」のである。子羊の血で洗われた。…..。実際、自堕落な生活を続けられる人は続け、そうでない人は息子や娘をアフガニスタンやイラクに送り込むことになる。
9月11日は聖なる日とされ、国民は犠牲者を悼むために召集された。その2年後に「ホワイトハウス高官」は、大統領が採用した2つの異なる悲嘆の儀式を説明した。「昨年は物理的にも比喩的にも傷口が開いたままだった。昨年は肉体的にも比喩的にも傷口が開いた状態だったが、今年は癒しという意味だ。
このようにして、9月11日は、国の政治的体面を管理し、その構成員の生活を秩序立てるための主要な基準点である原初的な出来事とされたのである。十字架につけられたものから救済されるものへ-国家。
しかし、それは「聖なる政治」なのか、それとも完全に政治なのか。8 キリスト教的でない強硬な政治を得意とする、著しくギムレーな目をした政権が、臆面もない企業文化を敬虔なマントで覆い、つまずくことなく、どのようにして可能だったのだろうか。確かに、その信心深そうな様子は、時折ジョークになることもあった。しかし、その冗談は、まるで、その冗談を言う人たち自身が、何か崇高な力を馬鹿にすることに不安を感じているかのように、途切れ途切れになってしまうのである。アメリカ人の圧倒的多数が「神を信じる」と宣言しているのだから、不遜な表現には歯止めがかかるだろう。
報道された象徴的なシステムを「自然発生的なもの」として特徴づけようとするならば、政権からの圧力があったことは間違いないが、テレビはほとんど自ら徴兵していたことを念頭におかなければならない。新聞は、アンディ・ウォーホルが予言した「15分間の名声」の不気味版として、消防士や警察の英雄的行為や自己犠牲の物語、そして犠牲者の略歴を次々と掲載した9。つまり、この日付は、仇となることを誓った人々の権力を正当化するだけでなく、神聖化するために、祀られ、準備されたのである10。
言論、メディア、宗教の自由が保証され、奇抜さが賞賛される社会で、なぜ結果は一蓮托生だったのだろうか。選択の自由を謳歌する社会が、より公然と強制的なシステムのそれに匹敵するような不気味な一致を生み出すのはなぜだろうか。アダム・スミスの自由市場の「隠れた手」のようなプロセスなのだろうか。中央の指揮機関に促されることなく、それぞれが自己の利益を追求する個人の非協調な行動が、それでも全体として皆にとって良い効果を生み出すのだろうか。
スミスのモデルは、すべての行為者が合理的な自己利益によって同じように動機づけられていると仮定しているが、9月11日の余波、その生産と再生産は、行為者の不調和、動機の多様性、それにもかかわらず一つの反応しか許されない壮大な瞬間を永続させるために結合されたことで注目すべきものである。9月11日は、現代社会では稀な現象、すなわち、矛盾、政治の曖昧さ、政治イデオロギーや識者の主張と反論を解消する、明確な真実となったのである。批評家たちは、予防戦争を正当なものとして擁護する懺悔者に変身し、最高責任者の意向で中断できるほど柔軟な憲法を称えるようになった。9.11の真実は、この国の国民を自由にしたというだけでなく、帝国とグローバリゼーションという広大な権力に関わることを抑制し、「なぜ世界の他の国々は我々を憎むのか」と悲しげに問いかけることができる無垢な存在にしたのだ。
このような一致を説明し、促進するものは何だろうか。その昔、アイデアの自由な流通を自由市場での競争にたとえるのが一般的だった。最高のアイデアは、優れた製品と同様に、劣った競争相手に打ち勝つだろう。しかし、メディア・コングロマリットが管理する高度に構造化されたアイデアの市場では、売り手が支配し、買い手は同じメディアが「主流」だと宣告したものに順応している。アイデアの自由な流通は、管理された循環性に取って代わられた。自称憲法修正第1条の番人たちは、釈明と合理的な批判を奨励する。常軌を逸した」と思われたくない批評家は、共同支配を内面化することによって買い手を獲得する。批評の慣習を受け入れることは、「家」の声によって作られ、強制される文脈を受け入れることを意味する。その結果、本質的に単色なメディアになってしまう。社内のコメンテーターは問題とそのパラメータを特定し、異論を唱える者たちがそこから逃れようと必死にもがく箱を作る。文脈を変えようと主張する批評家は、無関係、過激派、「左翼」として排除され、あるいは完全に無視される。より洗練された構造では、論説ページや編集者への手紙を取り入れることができる。理論的には、誰でも自由に記事や手紙を投稿することができるが、新聞社はその目的に合ったものを選び、その基準についての説明はほとんどない。批評家は「点数稼ぎ」をするよう奨励され、損傷し合うが、そのワクチンはガス抜き以上のものにはならない。
責任あるメディアの責任には、「左派」と「右派」を正反対のものとして、また道徳的・政治的に同等なものとして扱うイデオロギーの「バランス」を維持することが含まれる。ニューヨーク・タイムズ紙は長年にわたり、その責任を忠実に果たしてきた。1992年、アパルトヘイトの影響に苦しむ南アフリカ共和国についての記事を取り上げた。記者は、「植民地支配を終わらせる」ための戦争を支持する黒人の若者たちにインタビューした。その気持ちは、タイムズ紙の記者に「冷戦時代のタイムスリップ」に巻き込まれたような感覚を与えた。そして、「人民の軍隊」を求めるアフリカーナのネオナチ一味の描写を挿入して、反植民地主義者たちのバランスをとるように仕向けた。彼の結論は “この2つのグループには多くの共通点がある 」と。その共通点の一つは、それぞれの集団の人数が少ないことだと彼は発見した。黒人との「2時間の会話」の後、彼は結論を出した。この会話は、「モスクワからモガディシュまで信用されなくなったイデオロギー的語彙の再教育」であった12。
iii
最新の計算では、9月11日に3,000人以上の罪のない人々が、明らかな挑発や正当化なしに殺害された。物的損害、ニューヨーク市と一般経済への影響は甚大であった。これらの事実は、身近でありながら理解しがたいものであり、また、厳しい残忍な即時性を持っていた。量的にも、現実と同じように「リアル」であった。それ以来、あの日の現実は、さまざまな形で再現され、実用化されてきた。それは、それなりに、あの日の出来事と同じくらい驚くべきものであった。
国家は直ちに、性質も数も場所もほとんど不明な敵に対して宣戦布告された。それにもかかわらず、「敵国人」は検挙され、憲法上疑わしい条件の下で拘束された。国民は定期的に警戒態勢に入った。政府の権限は拡大、強化され、同時に社会福祉は大幅に縮小された。経済の低迷、社会階層間の格差の拡大、国家債務の膨張の中で、政権は独自の「クラスアクション」を推進することによって対応した。富裕層への偏向が強まる一方で、貧富の差は大きく、自分たちの無力さを訴える術もなく、政治的に無関心であり続けた。アメリカの力を条約や同盟国との協力の束縛から解放するために、挑発的な外交政策が採用された。「ある時点で、ある政権高官は、「アフガニスタンへの侵攻を望まなかった多くのヨーロッパ人が、腹に蝶を抱えたまま、(イラク侵攻の)計画に乗るか降りるかの二者択一を迫られていることに気づくだろう」と警告した(13)。先制攻撃の概念は、イラクに対して受け入れられ、実行に移された。
このような権力の拡大がもたらした一般的な効果は、すべてが実物よりも大きく、奇妙で、世界の運命を左右するような争いに明け暮れる巨大な権力に満ちた新しい世界を生み出した。9.11の現実は、世界を争う二つの大国の対決をドラマチックに描き、厳しい試練と驚異的な出来事の後に、創造主の祝福を受けた力が悪の力に勝利すると予言する神話に包まれるようになった。
9月11日の神話は、そのテーマが主にキリスト教的であった。この日は、磔刑の聖なる日、殉教の聖なる日として、政治的に転用され、複数の機能を果たすようになった。政治神学の基礎として、好戦的な共和国の神秘的な体を囲む交わりとして、政治的背信に対する警告として、国家の指導者を神聖化し、正当性が疑わしい強力な役職者から救済の道具に変えると同時に、信者に戦時中の戦闘性を煽り、無批判の忠誠と支援を求め、結束の秘跡と「世界から悪を排除する」という聖戦の参加者として呼び寄せるのであった。 「14 聖なるアメリカ帝国?
iv
神話は、(古代ギリシャの)本来の姿では、問題を明確に定式化することなく、答えを提供していた。ギリシャの)悲劇が神話の伝統を引き継ぐとき、神話はそれを使って、解決策のない問題を提起する。
-ジャン=ピエール・ヴェルナン15
神が存在することに賭けることの利得と損失を天秤にかけよう。この二つの可能性を見積もってみよう。得をすればすべてを得ることができ、損をすれば何も失うことはありません。それならば、躊躇することなく、神が存在することに賭けるのだ。
-ブレーズ・パスカル16
神がアメリカを祝福し続けますように。
-ジョージ・W・ブッシュ大統領
9月11日の余波で、アメリカ国民は神話の領域、つまりこの世のものではない新しい異次元の存在へと駆り立てられた。神話は物語を語る。この場合、光の軍勢が廃墟から立ち上がり、闇の勢力と戦い、打ち勝つという物語である。神話は功績を物語るものであって、議論や実証を示すものではない。神話は世界をわかりやすくするのではなく、ドラマチックにするだけである。その説明の過程で、神話の英雄たちの行動は、いかに血なまぐさいものであろうと、破壊的なものであろうと、正当な理由を獲得するのである。彼らは特権階級となり、他者には道徳的に否定される行動をとる権利が与えられる。イラクの民間人の犠牲者を集計する必要はない。
神話には、さまざまな大きさや形がある。我々の関心は、特定の種である宇宙神話と、宇宙神話が世俗的な神話と組み合わされたときに生じるユニークな順列にある。宇宙神話は、叙事詩的な願望を持つ劇形式と定義することができる。その主題は、単純な争いではなく、不倶戴天の諸勢力間の必然的な、必要でさえある対決であり、それぞれが最終的にその力は超自然的な資源に基づくと主張している。彼らの能力は通常の政治の規模をはるかに超えている。通常、一方の勢力は自らを世界の防衛者であるとし、他方は混沌を好む倒錯的な戦略によって世界を支配しようとしていると表現する。それぞれの勢力は、ライバルとは異なる形の力を有しているが、自分たちの力だけが神聖な源から引き出されたものであり、それゆえ自分たちだけが祝福され、敵は極悪非道であると主張するのである。各党の主張は相互に排他的で反証が不可能なだけでなく、各党は反対(=疑い)に不寛容で、自由で真に民主的な政治に不信感を抱いているのである。
2007年1月の一般教書演説で 2006年の中間選挙で明確な敗北を喫し、自らのイラク政策が大衆から否定されたブッシュ大統領は、今度はその最も地に足の着いた民主的プロセスを否定し、イラクの兵力レベルを2万人以上増加させるよう要求して、それに応えたのである。決定者は反抗的に、単なる選挙を超越し、その正当化の役割を無視し、利害関係の神話的表現に代えることを決めたのである。もしアメリカ軍が「バグダッドの安全が確保される前に退却」するならば、混沌が世界を脅かすことになるだろうと彼は警告した。
[イラク政府はあらゆる方面の過激派に蹂躙されることになるだろう。イランに支援されたシーア派過激派と、アルカイダや旧政権の支持者に支援されたスンニ派過激派との壮絶な戦いが予想される。暴力が国中に波及し、やがて地域全体が紛争に巻き込まれる可能性がある。
アメリカにとっては悪夢のようなシナリオである。敵にとっては、これが目的である。カオスはこの闘いにおける彼らの最大の味方である。イラクの混乱から、新たな安全な場所、新たな人材、新たな資源、そしてアメリカに害をなすというさらに大きな決意を持って、強化された敵が現れるだろう。
大統領は次に、逆全体主義の構造への貢献を示し、その過程で、「自由な社会」の主要な要素がすべて整っている場合でも、自由な選挙、自由なメディア、機能する議会、権利章典が、増長する行政官によって無視されることがあることを明らかにした。そして、「カオスとの戦いには終わりがない」ことを強調した。「テロとの戦いは世代を超えた戦いであり、あなた方(=議会)と私が任務を他人に譲り渡した後も続く」と宣言した。そして、大多数のアメリカ人と議会に試練を与え、陸軍と海兵隊を5年間で9万2000人増員する許可を議会に求めると宣言し、さらに、「ボランティアの市民予備力」の創設に協力するよう議会に迫ったのは、同様に重要なことだ。この部隊は、事実上、私設軍隊として機能することになる。彼は、「アメリカが必要とするときに、海外での任務に従事する重要な技能を持つ民間人」の部隊を想定していたのである17 。
v
20 世紀初頭、偉大な社会・政治理論家であるマックス・ウェーバーは、科学的合理主義と懐疑主義の 勝利によってもたらされた「世界の幻滅」について、感情的に書いている。科学的合理主義や懐疑主義の勝利によってもたらされた「世界の幻滅」を、彼はこう表現している。ウェーバーは信憑性の持続力を過小評価していただけでなく、近代科学の偉大な勝利が技術的な達成の基盤となり、神話を追放するどころか、知らず知らずのうちに神話を刺激することになるとは予見できなかったのである。
神話はまた、科学技術文化とは一見不釣り合いな、もう一つの源からも養われている。例えば、現代の広告によって絶えず創造され、再創造される想像の世界は、現代のメディアという包囲された文化によって事実上逃れられないものとなっている。同様に重要なことは、現代の広告が生み出す文化は、一見、宗教的、特に福音主義の教えに対するアンチテーゼとして、断固として世俗的、物質主義的に見えるが、実際にはそのダイナミズムを強化していることだ。ほとんどすべての製品が、あなたの人生を変えることを約束している。より美しく、より清潔に、よりセクシーに、より成功するようになる。いわば、生まれ変わるということだ。メッセージには未来についての約束が含まれており、常に楽観的で、大げさで、奇跡を期待させるものである。広告主のバーチャルリアリティと伝道者の「良い知らせ」は互いに補完し合い、天下一品である。日常を超越しようとする熱意と底なしの楽観主義が、超大国の傲慢さを煽る。それぞれが他と共謀しているのである。伝道者は「最後の日」を待ち望み、企業経営者は世界の希少な資源を計画的に枯渇させる。
バーチャルリアリティは非現実的なものであり、普通の世界、ありふれた匂いや景色、誕生、成長、衰退、死、再生といった制限されたリズムを超越したものである。広告、テクノロジー、資本主義の正統性、そして宗教的信仰から選ばれた人々であるアメリカ人にとって、バーチャルリアリティの最大の勝利は戦争であり、未体験の偉大な現実である。南北戦争以来、アメリカ人は遠く離れた場所で戦争をしてきた。キューバ、フィリピン、フランス、そして第二次世界大戦ではほとんどすべての大陸で、さらに韓国、ベトナム、中東でも戦争をしてきた。戦争はアクションゲームであり、リビングルームでプレイされ、あるいはスクリーン上のスペクタクルであるが、いずれにせよ実際に体験することはない。仕事、レクリエーション、プロスポーツ、家族旅行など、日常生活は途切れることなく続いている。9.11以降、テロはもうひとつの仮想現実となり、再現されたイメージを通してのみ体験され、その破壊力(=驚異)は、時折、公開される不幸なテロリストや捕虜となったジャーナリストのスペクタクルを通して吸収されるようになった。これとは対照的に、死んだ兵士の棺は一般に公開されないというのが、公式の方針である。
vi
近代の科学的合理主義と、深く懐疑的なポストモダンの狭間で、真実や事実が単に「別の話」であり、皮肉が勇気の証となる時代にあって、神話は一筋縄ではいかず、皮肉が当たり前の世代に「簡単に売れる」ものでもない。現実が大衆的な神話に変換されるためには、ある種の条件を満たすか、あるいは作り出す必要があった。そうして初めて、神話は9月11日以降の世界に対する大衆の理解と支配エリートの自己正当化レトリックの両方を決定づける要素となりうるのだ。その影響を受けやすい大衆とは、特にリベラル派によって、世俗主義が絶えず過大評価され、その信憑性が過小評価されている人々のことだ。仮想現実や驚異がシミュレートされるずっと以前から、それを信じていた人たちが大勢いたのである。さらに、神話が登場するのは、予言的な、あるいは技術以前の世界ではなく、科学革命や技術の驚異(クローン、月面着陸)に慣らされ、同時に信心深い、そうした観客のために、神話は身近でありながら不気味でもある力の驚異を描かなければならないのである。それは、より高度な文明の武器で武装した宇宙人、つまり「上の世界」ではなく、その逆で、原始的で悪魔的な、目に見えない「下の世界」の住人が、(巧妙なマネーロンダリングによって)現代のテクノロジーを購入し操作することができるようになる、というものだ。権力に蝕まれた世界は、自らの神話的王者を漫画のキャラクターにちなんで「スーパーパワー」と名付け、世界の支配権をめぐってテロリズムを繰り広げるだろう。その争いをきれいに表現する前に、権力を神話化する前に、新しい世界、神話的であると同時に信じられる、しかし必ずしも信じられるとは限らない新鮮な文脈が必要なのである。
曖昧さと頑固な事実があふれる世界で、神話が意思決定者を支配し始めると、その結果、行為者と現実との間に断絶が生じる。彼らは、闇の勢力が大量破壊兵器と核戦力を保有していること、自国は建国の父と憲法制定を鼓舞した神によって優遇されていること、大きく頑なな不平等が存在する階級構造は存在しないことを自分たちに信じ込ませているのである。しかし、少数の人々は、「最後の日」を生きる世界の前兆を、悲観的ではあるが喜びに満ちて見ている。
このような断絶は、どのような政治が最もよく現実を回復し、意思決定者に現実を考慮するよう促すことができるのかという問題を提起する。エリート層と選民層の組み合わせによって支配される政治なのか、それとも、「現実」にも、現実を自分たちの言葉で作り変える力を確信している人々にも、より密接に結びついた政治なのか。むしろ、現実がより頑固で、毎日従事しなければならない人生の事実である人々を巻き込んで代表する政治なのか。
