Contents
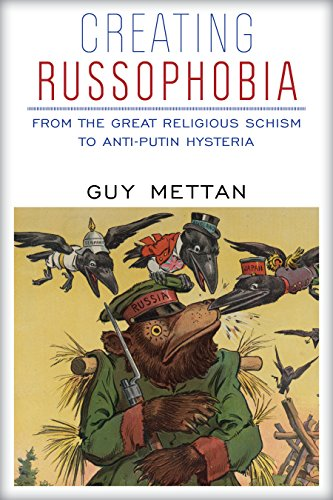
Creating Russophobia: From the Great Religious Schism to Anti-Putin Hysteria
目次
- まえがき:ロシア恐怖症か、それともロシア狂いか?/ 11
- サラエボに学ぶ / 13
- ロシアの擁護者、ソルジェニーツィンを捨てる / 15
- エリツィンの略奪 / 16
- 歴史的偏見の壁を破る/17
- 第一部 偏見の力
- 第1章 ロシアを理解する/23
- 同じでもなく、他でもない/26
- フランスとドイツは許し、ロシアは許さない/29
- プーチン=ヴァーステア?Verboten! / 30
- ロシアびいきをナビゲートする/31
- 「ロシアは好きだがプーチンは嫌い」/32
- ロシアびいきは心の状態/33
- 議会はロシアに対抗する/35
- 自虐的なロシア人?/ 36
- 第2章 パブロフ的なロシア恐怖症の反射/39
- ユーバーリンゲン墜落事故(2002)/41
- ベスラン人質事件(2004)/44
- プーチンに反対する115人の大西洋主義者/50
- ベスランで本当に起きたこと/53
- 第二次オセチア戦争(2008)/58
- ソチオリンピック(2014)/64
- 第3章 ウクライナをめぐるメディアの目くらまし/72
- 反ロシアのヴァルゲート/74
- ビクトリア・ヌーランドに質問はない/76
- 1991年の国民投票を再確認したクリミア人/80
- マレーシア航空機MH17/81
- NATOの拡張に関する別の見解/82
- ワントラックメディアの思考/86
- 答えのない質問/88
- 価値ある批評的他者という耐え難い概念/97
- 第1章 ロシアを理解する/23
- 第二部 ロシア恐怖症の短い歴史
- 第4章 シャルルマーニュ以来の宗教戦争/100
- 光の都ビザンティウムはローマを破滅させた/104
- 8世紀のソフトパワーとしての宗教/106
- ローマではなくコンスタンティノープルが優勢だった/107
- シャルルマーニュが作り出したフィリオルク論争/109
- 教皇庁と帝国、二つの剣の理論/111 コンスタンチンの不正な寄進と
- 教皇庁の至高性をめぐる戦い/113
- 西洋人は三位一体を再評価する/115
- 民主的な東方人と絶対主義的な西方人 / 116
- 二つの迂回十字軍:1204年と2003年 / 118
- 西洋で作られた分裂 / 120
- シーザロペリーの発明とビザンティニズム/121
- ロシア正教に対するヨーロッパの十字軍/122
- シーザロとローマ・ゲルマン皇帝/124
- ゴシック様式の教会がヨーロッパを二分する / 127
- 千年来の争いは今もなお激しさを増している/131
- ビザンティウムとロシアに対する歴史的恩義 / 132
- 西洋の歴史学には嘘が蔓延している/135
- 第5章 フランスのロシア恐怖症と東方専制君主の神話/137
- ピョートル大帝の偽造された遺言と拡張主義の神話/139
- 最初の旅行者がロシアの野蛮さの観念を打ち出す/142
- 同意する臣民を持つ専制政治は存在しうるか?/ 145
- 専制君主制の再認識 / 148
- 古代人と近代人の争いから進歩の概念へ / 149
- ロシア啓蒙的専制君主制の信奉者としてのライプニッツとヴォルテール / 151
- モンテスキューとロシアのカウンターパワーの不在 / 153
- フランスの決まり文句と日本の客観性 / 155
- 第一次自由主義論と東洋の専制君主制/157
- トクヴィルとロシア恐怖症の聖書
- クスティーヌへ / 159
- 社会主義の台頭とロシア・コミューン/162
- 個人の自由対ロシア・コミューン/165
- 最後の総合。修正可能なロシアと救済可能な後進性 / 166
- 文化的勾配の理論/171
- 第6章 イギリスのロシア恐怖症–帝国への執着/176
- 1815年以降、突然ロシアが脅威となる/178
- イギリスのロシア恐怖症の進化/181
- ギリシャ独立とポーランド反乱/184
- イギリスの報道機関が世論を煽る/186
- サーカス人の武装化/188
- グレート・ゲームとアジア争奪戦 / 189
- クリミア戦争のきっかけとなったオリエント問題 /
- 192 大英帝国の脆弱性 / 193
- 帝国主義的でロシア恐怖症的な小説『ドラキュラ』/196
- 「象は鯨と戦わない」/199
- 第7章 ドイツの露西亜主義–レーベンスラウムから歴史的健忘症へ/205
- ロマン主義的なドイツ性のビジョン/207
- ヘーゲルとプロイセン国家/209
- 地理と歴史に根ざすゲルマン性/211
- コスモポリタンなロシア。避けるべきモデル/213
- 学校の教科書によるロシア恐怖症の教化/214
- フリードリヒ・マイネッケと「スラヴ人の獣性」/216
- オストフォルシュングの実施/219
- レーベンスラウムとレイシズム/221
- 1966: ドイツの学校教科書に変化なし/222
- ナチズム=共産主義/224
- 共産主義者の犯罪をロシアだけに押し付ける / 227
- ナチスを倒したのは誰か?/ 228
- 記憶市場に溺れる / 231
- 歴史と歴史学の巧みな欺瞞/233
- ミュンヘン独ソ条約/235
- 2014.東洋のリーベンスラウム/237
- 第8章 アメリカのロシア恐怖症–その独裁性
- 自由/241
- 海洋国家としてのアメリカ/244
- 世界を支配するためにハートランド(ロシア)を支配する/245
- ソ連ロシアの軍事基地による封じ込め/248
- イデオロギー的封じ込め/249
- 1975年のヘルシンキ合意 / 251
- 自由対全体主義・左翼/253
- さよなら反共産主義。おかえりなさい。ロシア恐怖症 / 254
- ブレジンスキー ロシアの拡張主義をリサイクルし、ロシアを解体する/256
- ナイ:ソフトパワーと「スマート」な反ロシア枢軸/260
- 権力に奉仕する映画、シンクタンク、NGO/262
- 反ロシア・ロビー/265
- ここに再び行く。専制君主と拡張主義/268
- ロシアを貶めるためにオリガルヒを擁護する/273
- 第4章 シャルルマーニュ以来の宗教戦争/100
- 第三部 認知操作
- 第9章 意味論と反ロシア・ニュースピーク/277
- 言葉の選択と意味上の歪み/280
- ソースの選択/284
- フレーミングと事実の歪曲/289
- 「我々」と「彼ら」の二項対立/296
- 対談の戦略/304
- ソフトパワーの新しいアバター:羊飼い論/306
- 第10章 凶暴な熊の神話/310
- 語りの抜け穴をふさぐ/312
- プーチンを悪者にする/313
- アメリカの歴史学がロシア嫌いを定着させるミーム / 322
- 地理の重さ / 329
- ヨーロッパ統合を加速させるためにロシアに対抗する/332
- 第9章 意味論と反ロシア・ニュースピーク/277
- おわりに 共存、多極化、そして平和/334
- 参考文献 / 343
- 巻末資料 / 348
- インデックス / 382
序文 ロシア恐怖症それともロシアの狂気?
「今日の啓蒙的な西側社会(法律を制定している社会)は、実際にはほとんど寛容ではなく、特に争われたときには、従来の考え方の硬い鋳型の中に完全に鋳込まれてしまう。確かに、矛盾した人たちと戦うには、鉄槌を振るうのではなく、中傷と、それを押しとどめるための財力を使う。それでは、聡明な(アメリカの)新聞で、偏見と扇情的な主張の痕跡を突き破ろうと試みるのだ。
全国民の読者!
-アレクサンドル・ソルジェニーツィン1
本書は、長い仕事と個人的な経験の成果であると同時に 2014年のウクライナ危機の帰結でもある。
かつて権威があったが今は廃刊となったリベラル紙、ジュルナル・ド・ジュネーブでジャーナリストとしてインターンを始めた最初の週から、私は西側メディアや西側政治家が気に入らない国や政治体制に判断を下すときに適用する二重基準の意味を学んだ。1980年の春、ジュネーブで世界反共産主義者同盟の会議が開かれ、私はデスクに腰を下ろした。その週末は晴天が予想され、ペン習字の人たちは誰も取材に行こうとはしなかった。そこで、私が派遣された。
そこに集まったのは、地球上の独裁者、虐殺者たちのとんでもない一団であった。ピノチェトの使者、アルゼンチンの将軍、韓国、台湾、その他アジアの独裁国家の代表者たちである。その眉毛は、B級映画のように黒眼鏡で隠され、私服のままで落ち着きがなく、捨てられたばかりのケピスの跡が残っているように見えた。私は新聞に戻り、自分が見たこと、言われたことを忠実にまとめた。もちろん、日曜日なのでモニタリングの目はない。
ところが、月曜の朝は大騒ぎである。編集長室に呼び出され、厳重注意を受けた。この新聞の大株主の1人が連盟のスイス代表であることを知らなかった私が悪いのだが、差別は厳禁である。独裁者というのは、みんな同じではない。親欧米の将軍のように良いものもあれば、ロシアや東欧のように悪いものもある。あなたは、「反対者を投獄し、政治犯を拷問する独裁者たち 」ではなく、「共産主義の感染から守る自由世界の擁護者たち 」と言ったのだ。この教訓は決して忘れることはないだろう。
それから数年後の1985年11月19日、ジュネーブでレーガン-ゴルバチョフ第1回首脳会談が行われた。ベトナム戦争、赤軍のアフガニスタン侵入、ユーロミサイル危機、そして1983年3月のレーガンによる戦略防衛構想の開始以来、初めて東西の指導者が顔を合わせることになったのである。また、クレムリンが初めて、魅力的な配偶者に挟まれた若手の指導者を登場させ、急速にタブロイド紙の表紙を飾り、その幻想的な栄光にあっという間に陥落してしまったのである。その日は私の29歳の誕生日で、大きな希望と同時に、その会議が私の中に育んだ矛盾の感覚を今でも鮮明に覚えている。2つのブロックが衝突し、その中でより硬いものが明白なものではなかった。
ロシアはより柔軟で、不本意ながらも名誉ある和平を達成するために譲歩し、自分の教義を適応させる傾向があったが、アメリカはそうではなかった。彼にとっては、条約は条約だったのだ。
西洋人にとって協定は暫定的なステップに過ぎず、西洋の法学者が誇る法の支配は言葉の誤用であることを彼は理解していなかった。静的で不変の本質を持たないので不変の規則ではなく、利益、ロビー活動、はかない知的パンデミックの指示により、曲がりくねった、予測できない方法で進化し続けるので不動の、まっすぐな法でもないのである。アングロサクソンの精神に従えば、法は原則の問題ではなく、法学の進化なのである。
このように、西洋にとって法は、今日は有効だが明日は時代遅れになるプロセスである。戦争や新しい領土を非軍事的に征服するための便利な手段であり、それ自体が目的であることはほとんどない。むしろ、「私のものはすべて私のもの、あなたのものはすべて交渉可能 」という言葉に従って機能しているのである。ゴルバチョフはこの教訓を学ばず、1991年、NATOが東ヨーロッパに進出しないことを口約束する代わりに、ソ連軍を東ヨーロッパから撤退させ、同じ過ちを繰り返した。数年後、東欧諸国はすべてNATOの手に落ちた。NATOは、北大西洋から何千キロも離れたグルジアやアフガニスタンにさえ介入していたのである。私はこれらのことから、諺にもあるように、善意が良い政策になることはない、と結論づけた。教訓その2。
サラエボから学ぶ
ベルリンの壁が崩壊して4年後の1993年9月、『トリビューン・ド・ジュネーブ』の編集長だった私は、ボスニアのオスロボジェンエ新聞がセルビア人に脅かされ、その独立を支援しに来た国際ジャーナリストの一団とサラエボにいた。当時は、アメリカやEUが、既存の国境を壊すために民族の自決権を引き合いに出し、ユーゴスラビアのさまざまな民族に相談もせずに分離独立を勧めていた時代である。国境不可侵はまだ欧米では通用せず、それどころか、チェチェンからマケドニアまで、それまで同じ屋根の下で暮らしていた国家連合を解体して中欧の地図を作り直すことが正当とされた。しかし、それはウクライナやクリミアで起きた事件によって、西側の法学者が国際法をまったく逆の方向に解釈し直さざるを得なくなる前の話である。
そこで、パリのパンデミックに敏感な一握りの知識人と、フランスやヨーロッパの新聞社の権威あるコラムニストが、セルビアの野蛮人に干渉する権利と、それに立ち向かう義務を雄弁に語っていたのである。彼らの予言は、2年後のスレブレニツァで的中することになる。しかし、1993年当時、セルビア人はまだ、良くも悪くもない、他ならぬ民族主義の闘士に過ぎず、虐殺を防ぐためには、公平な解決に向けて国際的にしっかり関与することが遅くはなかった。
ヘルメットと防弾チョッキを着用して、爆撃で半壊し、蛮行への抵抗の象徴、ジャーナリズムの独立の中心、多文化主義の旗手となっていた新聞社本社に向かった。我々は記者たちと、イスラム教徒のボスニア人将校の手引きで、わずかに残ったセルビア人とクロアチア人の編集部員に会った。予想通り、我々が聞きたいと思うようなことを話してくれたので、皆、表向きは大喜びだった。1970年の「イスラム宣言」以来、ボスニアでイスラム主義を激しく推進しているイゼトベゴビッチ大統領のプロパガンダのために、我々が登録されたことなど、誰も思いもよらなかったのだ。
私はこの茶番劇に嫌気がさして、イタリア行きのアンフォルメ便に乗ることにした。かつて独立と多文化主義を体現していたサラエボを代表する日刊紙は、戯画と化し、当時はまだイスラム主義とは呼ばれていなかったボスニアのプロパガンダの利益を促進するためだけに存在するようになった。我々ジャーナリストはといえば、軽蔑された自由を守るという口実のもと、他の2陣営に対する1陣営の箔付けに過ぎなかった。神秘化を糾弾し、すべての当事者の声に偏りなく耳を傾けるべきなのに、我々は戦争兵器に変身してしまったのである。我々は、真実が明らかになるためには、まず個々の真実が表明されなければならないこと、そしてメディアは道徳的な姿勢を常に疑わなければならないことを忘れていた。なぜなら、ほとんどの場合、それは暴露されたくない利害関係を覆い隠してしまうからだ。教訓その3。
4つ目の体験は、もっと個人的なものである。1994年、ソビエト連邦崩壊後の最悪の時期に、我々は偶然にも小さなロシア人の女の子を養子に迎えた。スズダリで生まれたオクサナは、モスクワから180キロ離れたウラジーミルの孤児院にいた。12月のある日、吹雪の中、我々は彼女を迎えに行った。この出来事が、後にエリツィン政権の政令で私にロシア国籍が与えられるきっかけとなった。このことは、当然のことながら、私のロシア観を大きく変えることになった。共産主義後の単なる物珍しさから、この国がぐっと身近になったのだ。そして、ロシアをよく語るには、他の国と同様、憎む必要はなく、少しでも共感することが理解につながるという結論に至った。教訓その4。
こうして、ユーゴスラビア紛争やロシアの出来事について、仲間のジャーナリストたちが発表するレポートやコメントを、私はより批判的な目で観察するようになった。そして、西側のメディアの多くが、偏見を持ち、決まり文句を並べ、組織的に反ロシアに偏っていることに、めまいを覚えるようになった。旅をすればするほど、議論をすればするほど、読めば読むほど、西ヨーロッパとロシアの間の無理解と無知のギャップが明らかになった。
ロシアの擁護者、ソルジェニーツィンを捨てる
だからこそ、1990年代、私は西側諸国のソルジェニーツィンに対する扱いにショックを受けたのだ。何十年もの間、我々はこの偉大な作家を反ソビエト反体制の聖火として出版し、称え、賞賛してきたのである。ソルジェニーツィンが母国である共産主義ロシアを批判している限り、我々は空に向かって賞賛していたのだ。しかし、彼が移住してきた途端、反共産主義の会議に出席するよりも、バーモントの隠れ家で孤立して仕事をすることを好んだことに気づき、西側のメディアや学者たちはこの偉大な作家から距離を置き始めたのである。
偶像はもはや自分たちが築き上げたイメージにそぐわず、学問やジャーナリズムのキャリアプランの妨げになりつつあったのだ。そして、ソルジェニーツィンが米国を離れてロシアに戻り、オークションで売られている屈辱的で意気消沈した祖国を守り、ロシアの利益を否定して資本主義の谷間でもっと楽しもうとするロシアの「西欧人」や多元的リベラルに対して声を上げると、彼自身は何ら変わっていないのに、時代遅れで老年作家として注目され、共産党全体主義と同じ勢いで市場全体主義の欠点も非難しているようになったのだ。
彼は、ブーイングを浴びせられ、軽蔑され、その選択のために彼の名前は泥の中に引きずり込まれた、しばしば彼の最初の戦いを賞賛した人々によって。しかし、ソルジェニーツィンは、あらゆる困難にもかかわらず、また、彼を思いとどまらせようとする最も強力な権力者にもかかわらず、ロシアという唯一無二の大義を守り抜いた。彼は、自分を歓迎し、永遠に感謝しなければならないと感じていた西側に対してペンを向けたことが許されなかった。今日の反体制者、真実が必要とするところの反体制者、それが彼のモットーであった。このことは、記憶されるに値する。
エリツィンの略奪
やがて、私は別の疑念を抱くようになった。エリツィン時代の初め、1993年にロシアの装甲車が合法的なロシア議会を銃撃する光景を見て、西側のマスコミは拍手喝采を送った。偉大な物理学者が家賃を払えなくなり、研究所を捨ててマクドナルドでハンバーガーを売らなければならなくなっても、彼らは何の落胆も表さない。西側の専門家たちは、チェチェンでロシア人に戦争を仕掛け、ロシアの劇場や学校で罪のない人々を虐殺したイスラムのテロリストたちを、ニューヨークのツインタワーや東洋の西側の利益に対する同様のテロ行為を忌み嫌っていたにもかかわらず、言い訳を始めた。また、ロシアのオリガルヒが自国の富を略奪するやいなや、それを民主主義と貿易の自由の名の下に外国の競争相手に売り渡し、イギリスのサッカークラブや大統領への切符、ウクライナの首相の座(ユリア・チモシェンコ氏のように)を手に入れることを良しとするメディアも、そのことを賞賛している。
ロシアと西側諸国は、こうした軽率な判断や風刺画のようなニュースよりも、もっと良いものを得る資格がある。だから 2014年初頭、ウクライナのマイダン広場事件がクーデターに発展し、ついには内戦に発展したとき、私は黙って、再び、西側メディアを支配した反ロシア・ヒステリーの新しい爆発を反応せずに見ていることは不可能になってしまった。ロシアメディアの「プロパガンダ」疑惑によって攻撃を正当化する検察ジャーナリズムの吐き気を催す説明には、答えがないままではいられなかったのである。
歴史的偏見の壁を破る
そこで私は、この偏見の壁を打ち破りたい、せめて少しでも低くしたいと思い、本書の執筆に取り組み、欧米人が何世紀にもわたって、より正確にはカール大帝がビザンチウムから離脱して以来、ロシアに対して蓄積してきた歪んだイメージや偏った認識の長く、複雑だが魅力的な歴史に踏み込んでいったのである。
今日のロシア恐怖症の異常なまでの広がり、すなわち西側諸国の首相官邸や報道機関を掌握しているかのような「ロシア狂気」は、必然的なものではなく、意識的な選択の反映なのである。ロシアを憎む必要はない、と読者に納得してもらうことだ。
本書が決して反西欧的な感情から出発したものではないことを、ここで明記しておくことにしよう。ロシアを憎む原動力を明らかにすることは、フランス革命以来、欧米が推進してきた民主主義、自由、人権といった価値を捨てることを意味しないし、プーチン大統領のロシアにうっとりすることを意味するものでもない。西側の最も疑わしい姿勢を批判することは、ロシアの非を免罪することではない。
反米・反欧のパンフレットは、メディアが好む二元論を逆さまに再現するもので、善良だが迫害されるロシアと悪辣な欧米を対立させるものでしかないのだ。問題は、西側とロシアの関係を真実で複雑なものに戻すことであり、それによって、この25年間、輸入された民主主義ではなく、自ら選んだ民主主義を築き、民営化によって荒廃した経済を再建し、外から押し付けられたのではないクリーンな未来を築くために努力してきた数千万のロシア人たちに対して正しい行動をとることなのである。
最後に、本書が時にメディアに対して非常に批判的であるとしても、ジャーナリズムをドック入りさせることはない。世界中の編集局には、良い仕事をしようと努力するジャーナリストが大勢いる。しかし、ロビー団体や経済界、政治家の圧力から自分たちをもはや守ってくれない編集長に直面したとき、彼らは自らのもろさを痛感するのである。現在、ジャーナリストは職を失うという恐怖で麻痺している。政治的に正しいと思われていること、そして、周囲の偏見や有力な圧力団体の甘い誘いに応じてトピックの角度を変えるという中央デスクの要求に抵抗するだけの力があるとは、もはや思っていないのである。時間と自主性がないため、彼らは習慣の力に屈し、主流に溶け込むという心地よい感覚に陥る。ちょうど、正しいことだけでは自殺行為であり、大勢で間違っていることは生命保険である政治家たちと同じだ。
本書が、歴史から受け継いだ偏見の重さを示すことによって、この潜在的な戦争、つまり西洋を内側から蝕む千年来の排斥に歯止めをかけ、自らの大部分を切断することに貢献できれば、その目的は達成されたことになる。西側諸国は、自らを鏡に映したとき、米国から欧州連合まで、あるいはドゴール将軍の公式に従ってウラル山脈まで広がっているのではなく、ヨーロッパを通って太平洋まで、あるいはジョージ・H・W・ブッシュの言うようにバンクーバーからウラジオストクまで広がっていることをようやく理解するはずである。
私はこの本を3部構成にした。第一部は、欧米におけるロシア人への偏見の強さを、一連の例を通して示す。第1章では、ロシア人嫌いの現象を定義することに努め、次の章では、最近のニュースの中から、ユーバーリンゲン空中衝突事件、ベスラン人質事件、オセチア紛争、ソチオリンピックなどの出来事におけるロシア人嫌いの進展について詳しく説明する。第3章では、ウクライナ危機をめぐって、メディアが事実の報道をあきらめ、公式見解にそぐわない質問をしたり、見解を述べたりしたことが紹介されている。
第2部では、ロシア嫌悪の根底にある歴史的、宗教的、イデオロギー的、地政学的な起源を、5つの異なる形態のロシア恐怖症を通じて紹介する。シャルルマーニュがローマ帝国の後継者の座をビザンティウムと争って以来、13世紀にわたってヨーロッパ各国におけるロシア恐怖症の系譜をたどるのである。シャルルマーニュとローマ教皇庁による宗教的・帝国的対立から、フランス、イギリス、ドイツ、そしてアメリカのロシア恐怖症の発生まで、西洋は1000年にわたりロシアに対して多かれ少なかれ激しい敵対関係を持ってきた(後者もまた、公平に見てきたのだ!)。
第三部「認知操作」では、メディアや外交界における反ロシア的言説の構築、そして「悪者」の捏造と悪者化(現在、その役割はプーチンに与えられている)が、現代のロシア恐怖症の仕組みとして描かれている。言説と捏造はともに、凶暴な大統領によって鉄の棒で支配される獰猛なロシアの熊という神話の枠組みの中で特徴づけられている。これらすべての要素を総合的に読み解き、最近の出来事、特にウクライナ危機に照らして、純粋無垢なヨーロッパを食い尽くすことを夢見る悪いロシアという物語を押し付けるために、西側のソフトパワーのあらゆる資源が動員されてきたことを示す。
結論は、ロシアの他者性についてのこの否定的な言説が、決して達成されることのない西洋のアイデンティティの一部であることを示すものである。危機的状況にあり、分裂しているヨーロッパは、統一を達成するためにロシアの敵を必要としている。有名な白雪姫の童話にあるように、西欧は、自分たちの優位性を再確認するために鏡を問い続ける悪い継母のようなものである。しかし、ロシアの鏡は抵抗しており、西洋が世界で最も美しいわけではないこと、そして、非常に遠く離れた東洋に、少なくとも同じくらい美しい国があることを、常に示すことができる。こうして、ヨーロッパとロシア、そしてその逆を結ぶ両義的な関係を、パロディーのように皮肉と合成で表現するビジョンが徐々に形作られていくのである。
私はこの問題がタブーであり、ヨーロッパの大学ではほとんど研究されていないことをよく承知している。本書で引用されている著者の中には、研究費を打ち切られ、研究を中断せざるを得なかったという人も実際にいる。私はこの仕事を、権威ある大学の歴史学の教授が主導する学術的な研究としてではなく、ジャーナリスティックな方法でアプローチしている。新しい仮説を検証し、新しい思考法を開くことが目的であり、学術的な論文を書くことが目的ではない。
そのため、研究者からは、細部にわたって疑問を投げかけられ、「ごった煮」「総花的なアプローチ」と容赦ない批判を受ける危険性もある。また、プーチンがうるさい暴君であり、ロシアが拡張主義の帝国であることをあらゆる手段で証明しようとし、「ロシアの挑発とプロパガンダ “に反応するふりをするイデオローグとも対峙しなければならないだろう。
しかし、私は、私がロシア恐怖症の人たちを非難するようなこと、つまり、テーゼを確認する事実や意見を選択し、それを無効にしうるものを捨てたり無視したりすることを避けることによって、これらの反論に答えたと信じている。よく読めば、そのような反論が杞憂であることがわかるだろう。ロシア恐怖症の批判は、ロシアの効果的な行動や実際の行動と切り離されていることが非常に多く、それは欧米の集合的な潜在意識の中に非常に深く定着していることを証明している。ロシア恐怖症の長い歴史は、実はこの仮説を裏付けている。ロシア社会と権力の根源的な反西欧・反米志向に西欧が反応しただけだというロシア恐怖症の最も微妙なテーゼを解体するために、過去を掘り下げる必要があったのである。
そのうえで、西側諸国における同様の出来事によって生じた批判や反応と、選ばれたそれぞれの出来事を比較した。また、メディアとロシア恐怖症の専門家が体系的に破棄してきた、西側の公平な専門家による分析も紹介した。そして最後に、ウクライナのように実際の説明責任の立証がまだ困難な場合、ロシアに対しては常に厄介な質問がなされるが、西側諸国が関与している可能性がある場合には避けられることを簡単に紹介した。これらのことから、同じ行動をめぐって、ロシアは組織的に誹謗中傷され、西側諸国は免責されることがわかる。つまり、これはまさに西洋が始め、育てた情報戦の一形態であり、我々は1000年以上にわたって目撃してきたのだ。(少なくとも二人の戦士がいない戦争はないのだ)。
実際、ロシア恐怖症は、フランスのイギリス恐怖症やドイツ恐怖症とは逆に、もちろん違いはあるが、反ユダヤ主義やイスラム恐怖症に似ている現象である。反セミティズムやイスラム恐怖症のように、特定の歴史的な出来事と結びついた一過性の現象ではなく、まず見る者の頭の中に存在し、被害者の主張する行動や特徴には存在しないのである。反ユダヤ主義のように、ロシア恐怖症は、特定の疑似事実を、ロシアの場合は野蛮、専制主義、拡張主義という本質的で一面的な価値に転化し、汚名を着せ、排斥することを正当化するものである。
ロシア恐怖症はまた、宗教的な基盤を持っており、時間的な制約もない。それは何世紀にもわたって広がり続け、偶然の状況が許す限り、際限なく姿を現してくる。ロシア恐怖症は、何世紀にもわたって、偶然が許す限り、何度も繰り返し現れる。そして、時には完全に消え去り、思いがけない共感や賞賛に取って代わられることもある。そして、新たな事件、誤解された意図、無粋な宣言、新しい都市伝説、あるいは国境紛争などのおかげで、再び燃え上がるのである。つまり、反ユダヤ主義、反イスラム主義、反米主義のように、ロシア恐怖症は地政学的な要素を含んでいることは否定できない。
多面的、異文化的、変幻自在、多民族的、超歴史的、しかし、ロシア恐怖症は常にカトリックまたはプロテスタントの北半球に関連している。アジア、アフリカ、南米の人々は、決してロシア人を嫌ってはいない。中国や日本にはロシアとの国境問題があり、それをめぐって戦争になったこともあるが、彼らはロシア恐怖症ではないし、この種の言説を言い出したこともない。
一方、ロシアと国境を接し、宣戦布告をしたこともなく、二度の世界大戦で同盟を結んだアメリカは、現代史にないロシア国家恐怖症に陥っている。我々はまた、西洋文明全体の将来を擾乱する緊張のゴルディアスの結び目を切るために、発展させ、精緻化し、さらに進めていく必要のあるこの現象を探求したいと思った。
この仕事の遂行に協力してくれたすべての人々に感謝することは不可能である。しかし、このテーマを非常に大切にして、ノートや資料を提供してくれた最初の出版社セルジュ・ド・パーレンと、この道を共に歩んでくれた著者の方々には、感謝の意を表さなければならない。特に、西洋の「反ロシア主義」研究のパイオニアたちについて考えているのだが、彼らがほとんどアメリカ人かイギリス人であることは偶然ではない。アングロサクソンがロシア恐怖症を洗練された効率的な高みに押し上げたとすれば、彼らはまた、非常に厳格な学術的著作の中で、譲歩することなくそれを分析し非難してきたのである。彼らに敬意を表さねばならない。
このように、ロシア恐怖症のさまざまな形態について魅力的な研究論文を発表したアルゼンチンのエゼキエル・アダモフスキー、ジョン・ハウズ・グリーソン、トロイ・パドック、アンドレイ・ツィガンコフ、マーシャル・ポー、スティーブン・コーエン、フェリチタス・マギルクリスト、レイモンド・タラス、アイヴァー・ノイマン、ポール・サンダースには未払い金が発生している4。ル・モンド・ディプロマティークも、ジャック・サピールのいつも情報豊富なブログや、ヴィンヤード・セイカーの反権威的なウェブサイトと同様に、非常に有益であった。
最後に、この本を、その職業に固有の困難にもかかわらず、良心の要求と状況の許す限り仕事を続けるすべてのジャーナリスト仲間に捧げる。2015年に殺害された110人のジャーナリスト5と、シャルリー・エブド襲撃事件の17人の犠牲者の記憶が、表現の自由に対する脅威は常に外敵から来るのではなく、自分自身の最も濁った深みからも押し寄せてくることを我々に悟らせてくれるように。
