Contents
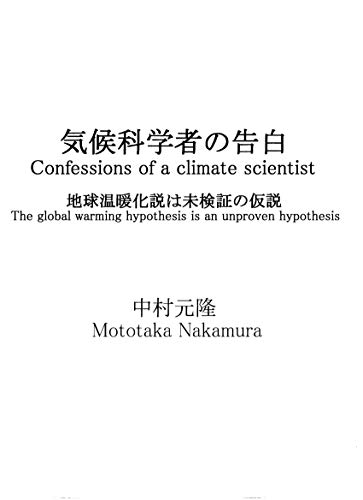
目次
- 「氷河期到来」から 「危機的温暖化 」 へ
- 1980年以前の「地球表面平均気温変化」は信用できない
- 気候予測モデル は 深刻な 欠陥 だらけ
- なぜ 地球温暖化 説 が 一般 市民 に 押し付けられているのか ?
- 気候 研究 にまつわる エピソード
- その 1 日本気候研究 界の恥晒し
- その 2 眞鍋博士のブッチャケ発言
- その 3 気候モデルはチューニングして使う物
- その 4 温暖化 懐疑論 は 叩か れる
- その 5 NHK 出演 の 舞台裏
- 結びの言葉
- 備忘録 : 大気海洋研究界 の 釣りバカ 達
中村元隆
Mototaka Nakamura
前書き
高校時代に気候変動に興味を持ち始め、気候専門の科学者になった。マサチューセッツ工科大での大学院生時代から、職業科学者としては引退した2014年3月までの二十数年間、自分の好きな様に研究に打ち込み、趣味を職業として楽しく生活する事ができた。
マサチューセッツ工科大での大学院生時代には、巨額な授業料を免除してもらった上に、毎月15万円ほどの返済無用の奨学金まで頂き、長期間に渡って直接的・間接的にアメリカと日本の納税者の方々には大変お世話になった。それに対する感謝の意を表す目的もあって、第一線で気候研究を続けた専門家の視点から、いかに「二酸化炭素増加による危機的地球温暖化」が科学的根拠に欠ける馬鹿騒ぎかという事実を、世の中に広く発信しておきたいと思ってきた。
本書の題は「気候科学者の告白」としてあるが、私自身は大学院生時代から「現存の気候シミュレーションモデルで中長期的気候変動予測などできるわけが無い」。と主張していたので、実は全く「告白」ではない。2014年1月には、NHK全国放送のニュース番組に生出演して、それをハッキリと言う機会もあった。単に、題名に「告白」とあった方が、センセーショナルな感じがして、より多くの読者の興味を引くのではないか、と思っただけである。
*
この手記の超短縮版は、2017年12月に、月刊「正論」に掲載されたのだが、やはり、「正論」記事には掲載されなかった詳細等も世に出しておきたいと思ってきた。残念ながら、この手記は、一冊の本として印刷出版するには短過ぎ、雑誌の記事としては長過ぎる、というのが実情で、かと言って、印刷出版するだけの為に、あれこれ書き足して長くするのも嫌なので、最も簡単な方法で出版する事にした。
これを読んで、少しでも多くの国民が、嘘を嘘で上塗りするのが普通となってしまった政府やマスコミ、大企業による洗脳から目を覚ましていただけると幸いに思う。また、既に目を覚ましている読者には、日本語ではほとんど語られる事の無い温暖化説の問題点について、理解を深めていただければ幸いに思う。
ついでに、一般の方々に、分野を問わず、金で飼われた「職業科学者」の主張は、とりあえず疑ってかかるべきだという現実も広く認識していただけると幸いに思う。本文中で少し詳しく後述するが、政府や大学が導入してきた研究資金提供システムの所為で、昔は基本的に信用できた大学教員らによる研究結果まで、近年では、とりあえず疑いの目で見なければならなくなってしまった。誠に残念な現実である。
*
本文を読まれる前に、一応、私の略歴を記しておく。便利な時代になったもので、私の略歴内容は、ほぼ全てインターネットで確認できる。[2019年9月追記:この本を翻訳ソフトで英語に換えて読んだ人達から英語版を買いて欲しいとの要望があったので、重要な部分だけを英語で書き加えた。
私は翻訳という作業が嫌いなので、日本語版の内容を元にしたものではなく、頭を英語モードに戻して思いつくままに書いたので、日本語版とはかなり違う記述をしている部分もある。勿論、要点は同じなのだが、説明が分かり易い場合もあり得るので、英語が得意な方には、英語版の部分も読んでみられる事をお薦めしたい。
略歴
山口県出身の大気・海洋・気候専門の科学者。1989年12月に米国ノースキャロライナ州立大学、物理数学科学学部、海洋地球大気科学科を卒業して学士号を取得。同年度全校卒業生中で最高位、首席で卒業。1990年9月にマサチューセッツ工科大学、地球大気惑星科学部の博士課程に入学し、同校から返済無用の奨学金と授業料免除の援助を受けて1995年2月に理学博士号を取得。
学生時代は大気科学全般と物理海洋科学を学びながら気候力学(大気・海洋力学、大気・海洋による熱と物質輸送、雲プロセス、放射プロセス、氷プロセス)に関する研究を行い、1995年から2014年までは、マサチューセッツ工科大学、ジョージア工科大学、ゴダードスペースフライトセンター(NASA)、ジェットプロパルションラボラトリー(NASA)、デューク大学、海洋研究開発機構で、異常気象や気候変動に関する研究を行った。
理論的研究、数値モデル構築・改良、数値モデル実験・検証、数物理的理論に基づいたデータ解析、と幅広く、同時に深い研究アプローチを得意とする。また、研究活動だけでなく、文部科学省でのレクチャー付きの記者会見、新聞や雑誌の取材対応、NHKのニュース番組への出演等を通じて、気候変動や異常気象に関する社会啓蒙活動も行った。
「氷河期到来」から「危機的温暖化」へ
1960年代~1970年代に騒がれた「氷河期到来説」は、1980年代になって、いつの間にか「大気中二酸化炭素増加による地球温暖化説」に取って代わられた。その後、僅か20年程で、あたかも二酸化炭素増加による地球温暖化は紛れもない事実であるかの様な論調が欧米と日本のメディア、政治経済界、一般市民、そして残念ながら気候研究業界や他の関連研究業界においても主流となってしまった。
今や、ジャーナリストや政治家や芸能人までもが、気候システムを理解したかの様な気になってしまっている様子が見える。驚異的な洗脳成功度と言える。[2019年2月追記:この数ヶ月間で、どういう訳かアメリカの一般マスコミが、NASAの太陽研究関連の科学者達が発する近未来の地球寒冷化を控え目ながら報道し始めた。
同じNASAでも気候シミュレーションに関わる研究者達の多くは相変わらず温暖化の危険を語っているが、以前は無視されていた太陽研究の科学者達の知見が一般市民の耳に届けられ始めたという事は、1970年代から1980年代にかけて起こった「氷河期到来の危機」から「地球の危機的温暖化」への一般市民洗脳転換の逆が今後10年間ほどで起こるのかもしれない。
単にアメリカ支配階層内部の勢力争いを反映しているだけかもしれないが、2030年代には誰もが「氷河期到来」で大騒ぎをして、今は「地球の危機的温暖化」で騒いでいる気候研究者達が「氷河期到来の危機」を旗に掲げて税金を無駄遣いしているという事態になれば実に滑稽であろう。
一般マスコミは単に飼い慣らされたオウムの集団であり、自らの思考を発信する事はできないので、そうなったら一斉に声を揃えて「氷河期到来の危機」を騒ぎ立てている事であろう。一般マスコミの「飼い慣らされたオウム」状態は、ありとあらゆる分野の報道に見られる。
例えば、最近、素晴らしい能力を持った18歳の女子競泳選手が非常に気の毒な事に白血病と診断され、マスコミが大騒ぎしていたが、国民の強い関心と憂慮を利用して、医療業界と製薬業界が営利目的で推進する治療を宣伝する様な報道ばかりで、放射線等の白血病の原因に関する科学的知見や、強い電磁場に長時間晒される仕事をする人達の発症率が顕著に高い、という重要な事実等には全く触れていない。
気の毒な白血病の患者、被害者が将来減る可能性に貢献しようという姿勢は皆無である。また、20年ほど前までは10万人に一人の発生率が統計事実であった脳腫瘍が近年は若年層で頻発していて(おそらく意図的に)新たな統計は計算されていないという事実、携帯電話やWiFi等に使われるパルス状の電磁波が脳血液関門を弱めると同時に遺伝子を破壊するという科学的事実等も、完全に無視されている。
しかも、近年の科学研究で、そういった電磁波による細胞レベルでの人体へのダメージが細胞外壁にあるカルシウムイオン流入ゲートを刺激する事で引き起こされるというメカニズムまで解明されてきたにもかかわらず、である。殆どの健康な人には深刻な問題とはならない麻疹が数百人に発症した程度で大騒ぎしてワクチン接種の宣伝は大々的にするくせに、毎年国内だけで何万人もの人達が電磁波・電磁場による深刻な健康被害を受けている可能性が高いのに日本の一般マスコミはダンマリである。
欧米では十数年前に脳腫瘍と携帯電話使用の因果関係が民事法上では認知され始めて巨額な賠償判決が出始めたので、法的責任回避の目的で十数年前から欧米で販売される携帯電話の使用説明書には小さな字で「使用の際には体から約1.5cm離すように」という旨の注意書きが加えられるようになった。
どういうわけか、日本では同様の注意書きは加えられていないようだ。携帯電話や通信事業業界、医療業界や製薬業界からの膨大な広告収入を考えると、単なる宣伝屋である民営マスコミが大事なお得意様に不都合な事実を報道しないのは理にかなっているが、税金や受信料で運営しているNHKまでもが宣伝屋と同レベルのオウム状態を呈しているのはちょっといただけない。
*
実のところ、私自身も気候変動に興味を持ち始めた1980年代初頭から1988年頃までは、地球温暖化説を基本的に受け入れていた。それが理由で気候研究分野への進学を選んだと言っても過言ではない。疑い始めたのは、大気科学と海洋科学の大学院レベルの勉強を始めた1989年頃である。
その疑念は、その後、大学院生、職業科学者として研究を続ける間も強くなり続けた。つまり、気候システムの科学的理解が進めば進むほど、大気中の二酸化炭素増加が危機的な地球温暖化を引き起こすという仮説に対する疑念が強くなったというわけである。
強調しておくが、私が疑念を持っているのは、「二酸化炭素の倍増、倍々増が、危機的な温暖化を引き起こす」。という仮説に対してである。大気中の二酸化炭素が赤外線吸収によって大気下層部に若干の温暖化効果を持つというのは事実であり、疑いの余地が無い。
産業革命前の大気中二酸化炭素濃度からの2倍増による直接的温暖化効果は地球表面平均気温の約0.5℃上昇であるというのが、優秀な気候科学者間で認識されている数値である。では、3倍になれば1.0℃の上昇効果があるかというと、そうではない。
二酸化炭素が増えれば増える程、その増加量に対する温暖化効果の増加は少なくなる。つまり、同じ量の二酸化炭素を大気に加えても、二酸化炭素が元々どれだけ大気中にあったか、によって温暖化効果が違うという事である。
さらに、気候システムは、現時点での人類の理解力をはるかに超える複雑な非線形プロセスと相互作用を無数に有しており、現実の気候システムに「何となく似ている様に見える」程度の気候シミュレーションモデルによる検証では、二酸化炭素増加の温暖化効果が実際の気候温暖化に繋がるかどうかは不明である。
*
ちなみに、「線形」とは、簡単に言うと、原因となる要因が増大すれば、その効果も同様に増大する、という安直な関係の事である。例えば、「y=2x, 負の無限大<x<正の無限大」などの安直な数式で表す事ができる関係は線形である。
従って、「非線形」とは、そういう安直ではない関係を指す。自然界の多くのプロセスや現象は現実には非線形であり、それらを線形理論で理解・表現できる範囲は非常に限られている。それにもかかわらず、科学研究で用いられる統計分析・解析手法は殆どが線形理論に基づいており、そういった手法で得られた知識は現実像の一部に限定される。
*
以下に、気候科学者としての最後の仕事として、何故私が危機的温暖化説に懐疑的なのかを、なるべく簡単に説明する。断っておくが、私はあくまでも懐疑的なのであって、否定的なのではない。私は、現在の人類には、その極めて難しい疑問に対する明確な答を出す能力は言うまでも無く、ある程度の信頼度を持った推測をする能力と情報さえ無い、と言っているだけである。
本来、科学者とは、完璧に立証されていない説や理論に対しては、仮にそれが自らの主張であったとしても、いくばくかの懐疑的な見方を保つべきである。その意味で、二酸化炭素増加による地球の危機的温暖化を信仰する人達に真の科学者は居ないと言える。
*
ややこしい科学の話には興味が無い読者には、次を飛ばして「なぜ地球温暖化説が一般市民に押し付けられているのか?」と「気候研究にまつわるエピソード」を読んでいただきたい。釣りが好きな読者には、オマケの「備忘録」も是非読んでいただきたい。
1980年以前の「地球表面平均気温変化」は信用できない
まず、地球温暖化を議論する際に、あたかも「確実にわかっている事実」かの様に受け入れられている「地球の平均表面気温の過去百数十年の変遷」が、実は1980年以前は全く信用できないという現実を指摘しておこう。一般大衆は勿論、ある程度の科学知識を持った人達や気候研究関連者の多くまでもが、産業革命以来の地球表面の平均気温が上昇したのは確認済みの事実だと信じ込んでいるが、実は、それを裏付ける確固たるデータは存在しない。
*
人工衛星によるほぼ全地球の観測が始まった1980年以前は、表面付近の気温がある程度の精度で頻繁に観測されていたのは陸地のほんの一部である。まして、それが19世紀に遡って信頼できるデータが存在する地域となると、せいぜい北アメリカと西ヨーロッパくらいのものである。
これが全陸地のどの程度なのかを頭に入れていただくには、普通の地図ではなく、地球儀を見ていただきたい。普通の地図は、中緯度域と高緯度域が実際よりもはるかに大きく見えるタイプで、物理的考察には不向きである。おまけに、地上観測が継続されてきた地点においても、その気温計測手法と観測地点環境に変化が起こってきた。例えば、観測地点周辺の都市化である。
日本の地方の小都市周辺ですら、過去50年間に広大な土地表面が田畑や草地・雑木林等からアスファルトやコンクリートに変わってしまった。これがもたらす地域的な温暖化効果は非常に大きい。また、エアコンの普及が進んだ所為で、夏の住宅地や商業地周辺の気温も上がっている。
(これがピンと来ない人達は、夏の昼間にエアコンが屋外に出している暖気をたっぷり浴びて、その地域にエアコンが何台位あるのかを推定してみるとよい)。気温の定点観測が長期間続けられてきた場所には、こういう地域環境変化の影響を強く受けている場所が少なくない。
さらに、地球表面の約75%を占める海洋表面の平均気温の精度は非常に疑わしい。1980年以前の海洋上の気温・水温観測は極めて少なく、主に貿易関連の航路周辺に集中していたし、観測地点、観測時間、観測手法にもばらつきがあった。
気候データセットとして使われてきた海洋上気温や海表面水温データは、生の観測値に様々な人為的調整が施されたものである。過去100年間の平均表面気温の変遷をある程度の精度で語れる地域は、現実的には地球表面のせいぜい5パーセント程度であろう。
勿論、一つの観測点が代表し得る面積をどんどん拡大していけば、極論としては、「一箇所で観測してきた気温変遷が地球全体の気温変遷を代表し得る」。という主張に繋がるわけであるが、それは地球の気候が大気と海洋の流れに非常に強い影響を受けているという現実を無視するもので、全く馬鹿げているのは言うまでもない。
一地点の観測データが、どれだけの周囲面積の中長期的気温変遷を正確に代表し得るかは、その地点が中大規模な大気と海洋の流れ、そして氷にどの様な影響を受けるかによって決まるので、安直に「一地点につき1,000,000平方キロメートル」などとは決められない。
(この本を翻訳ソフトで他言語に換えて読んだ方々には、日本語でのニュアンスが伝わっていないので、「一地点につき10000平方キロメートル」という記述を変更した。実際には、もし仮に地球全体に10000平方キロメートルに一つずつ観測点があって、一貫性を保って過去100年間に渡って観測されたデータがあれば、その期間の地球表面平均気温の変化をかなりの精度で語れると思う。
勿論、現実にはその様な観測網は無かったし、1980年からの人工衛星による観測も、初期の観測密度はかなり粗かった)。地点によって代表し得る面積が違う。気候変動を語る上で事実であるかの様に用いられてきた「産業革命以来の地球表面平均気温の上昇」を事実として受け入れるという事は、地球全表面の平均気温が、地球上の偏った極一部の地域の平均気温上昇と同じだけ上昇した、という考えを受け入れる事である。
言い換えれば、地球全体の表面気温変化は、上記の限定的地域の気温変化に正確に代表される、という考え方である。これがいかに馬鹿げた考えかというのは、長期間の気温観測が行われてきた地域だけを見ても、気温が上昇した地域もあれば下降した地域もあるという現実を直視すれば単純明解である。
*
実は、人工衛星による大気下層部の温度データも完璧とは言えないのだが、偏りがほぼ無いという点と観測領域の広さから、地上・海上観測データと比べると、地球全体の平均気温変遷を語るにおいては、はるかに優れている。人工衛星を用いた地球表面ほぼ全ての観測データによると、1980年以降、陸地上においても海洋上においても、表面気温が上昇した地域もあれば、下降した地域もある。
1980年以前にしっかりとした気温観測が存在した地域の気温変遷を見ても、気温が上昇した地域もあれば下降した地域もある。全地球表面の平均気温変化は、そうした地域的平均気温変化の誤差程度の大きさである。つまり、1980年以前の100年間に地球表面のどの位の面積においてどの様な気温変化があったか、が、ある程度の精度で分からなければ、産業革命以来の地球表面平均気温の変遷をある程度の精度で語るのは不可能であるというのが現実である。
1980年以前の至極限られた地域の気温観測に基づいて地球全体の中長期的平均気温変化を正確に推定できる、という考えは、中長期的な大気と海洋の熱力学的・力学的変動が気温に与える影響が、19世紀以降の二酸化炭素増加が気温に与える影響よりも圧倒的に小さいという考えであり、呆れるほど浅はかとしか言いようが無い。
*
この問題については、過去にいくつかの研究論文中で検証研究結果が報告されているが(例えば、Journal of Climateに掲載されたKarl et al 1995)、意味の有る検証は全くなされておらず、実際は大いなる不確実性が残ったままである。
Karl et al. (1995)は、上記の様に非常に限られた実際の気温データセットと、解像度が粗い欠陥だらけの大気・海洋結合の気候シミュレーションモデルによる実験で得られた全地球表面付近気温を統計解析し、過去の気温観測の地理的偏りは長期間の地球表面平均気温の変遷の計算に大きな影響を持たない、と結論づけている。
しかしながら、彼ら自身が論文中で認めている様に、現実には大きな不確実性が残されている。特に、彼らが当時全く認識していなかった、気候シミュレーションモデルによる気温変動や気温の地域的ばらつきの著しい過小評価という問題は、彼らの結論を全く無意味にしていると言える。
こういった大きな不確実性が存在するにもかかわらず、「産業革命以来の地球表面平均気温の上昇」が、あたかも確固たる科学検証で確認済みの事実であるかの様な扱いを受けている。おまけに近年は、過去の気温データに新たな「調整」処理が施され、地球平均気温上昇がずっと続いていると見える様にデータ改竄が堂々と行われる様になってしまった。
こうなっては、もう「地球表面平均気温変遷のデータ」は、科学的に意味の無い大衆向けプロパガンダ道具以外の何物でもない。マスコミが大衆向けに、やたらと「温暖化で地球上の氷が減っている」。と、氷が減っている地域の報道をして、氷が増えている地域は無視しているのと似ている。
*
[2019年12月追記:最近やたらとCOP25に絡めて「海面上昇で砂浜が小さくなった」等の報道を目にするが、全く馬鹿げている。まず、「数十年間で海面が数cm上昇」などというのは、実はそう簡単には計測できないし、人類とは無関係に長期的変動の一部としても起こり得る。
仮に、実際に僅かな海面上昇が起こっているとしても、その程度でマスコミが宣伝している様な砂浜侵食や陸地消失が起こるわけがない。あのような海岸侵食は海流変化が主要因である可能性が高い。砂浜の傾斜や消失した陸地の高度等を調べて、それらが海面上昇で起こるにはどれだけの上昇が必要か、は簡単にチェックできるはずだが、そんな事は全くやっていないのであろう。
考えてさえいないかもしれない。現実には、風、潮汐、気圧変動等に伴って100cm~1000cmスケールの非常に大きい短期的海面変動が常時起こっているし、地域的な陸地沈下や上昇、中・大規模な海流の変化(極端ではあるが、例えば、鳴門海峡の渦を思い浮かべて、それが通過する際に一地点での海面高度がどう変化するか、また、渦が一箇所に止まりながら流れが弱くなれば渦の端と中心部の海面高度がどう変化するか、を想像していただければ、数十km~数千kmスケールの構造を持つ海流がゆっくり変動するのに伴って発生する地域的な中長期的海面変動があるという事をおわかりいただけると思う)等の要因で、様々なスケールでの海面高度の変化が起こり得る。
そういった強いシグナルの中から、ノイズレベルの長期的に起こる僅かな平均的海面上昇を正確に抽出するには、非常に高度な人工衛星観測が必要で、現在の技術はともかく、30~40年前の人工衛星観測がその様に高いレベルにあったのか、大いに疑問が残る。
海岸浸食の原因が温暖化に伴う海面上昇であれば、少なくとも近隣半径数千km以上の広範囲に同様な状況が多く発生しているはずだが、マスコミはそれをチェックしようともしないし、長周期で起こる海流の変動や地盤沈下等の、よくある要因を完全に無視して、あたかも確実に温暖化が原因であるかの様に扱って、今後は一層悪化すると言ってやたらと危機感を煽ろうとしているのが見え見えだ。私は一般マスコミを「飼い慣らされたオウムの集団」と評してきたが、彼らはこの件でもそれを裏切らないオウムぶりを発揮している。
気候予測モデルは深刻な欠陥だらけ
世界気候研究界の主流派と政府やマスコミが、あたかも事実であるかの様に叫んでいる「今後、大気中二酸化炭素が増え続ければ地球表面に危機的レベルの温暖化が起こる」。という主張は、気候シミュレーションモデルを使った実験結果に基づいている。
一般大衆は、そういった予測が素晴らしい気候予測システムを使って計算されたものであると勘違いしている様子であるが、実際は、気候シミュレーションモデルは単なるコンピュータープログラムであり、もしそのプログラムの内部と、それが表現しようとしている実際の物理・化学プロセスを理解すれば、気候予測などには到底使えない代物である事を誰もが認識するであろう。
多少の差はあるものの、基本的に、気候予測に使われるシミュレーションモデルは、現実の大気に何となく似た大気を創り出すプログラムと、現実の海洋とは似ても似つかない海洋を創り出すプログラムと、極度に大雑把な雪・氷を創り出すプログラムが組み合わされたコンピュータープログラムの集合体である。
潜在的に非常に重要な役割を持つ植物と海中のプランクトン、そして大気中・海中の化学プロセスは表現されていないと言ってよい程度のレベルである。私は異常気象や中長期的な気候変動に特に興味があったので、大気と海洋の力学と熱力学、そして大気と海洋による熱と物質の運搬の勉強と研究に特に力を入れた。
その関連で、雲、水蒸気、そして降水にかかわる物理過程もかなり勉強した。(大気化学と海洋化学は一応大学院レベルの勉強をしたが、かじった程度で、専門家と対等に議論できるレベルではない)。そして、私自身は気候シミュレーションモデルを学術研究に使っていたという事情もあって、気候シミュレーションモデル内部における様々な物理プロセスの表現方法を熟知する事となった。
単に熟知しただけではなく、旧来の表現方法を改善した(少なくとも、より現実的な物理的理論に基づいた手法を導入した)事さえある。その結果、気候シミュレーションモデルは、限定的な学術研究には有用であるものの、予測や過去の気候変動要因検証等に使われる物としては致命的欠陥が幾つもある事を明確に認識した。
*
まず誰でも解る最大の問題は、気候シミュレーションモデル全てが、地球に到来する太陽エネルギーを不変として扱っている点である。現実には、太陽エネルギーは変動し、ほんの僅かな変動ですら地球に大きな影響を与える。しかしながら、人類には太陽エネルギーの変動をある程度の精度で予測する能力は全く無い。
それどころか、近年になるまで、地球に届く太陽エネルギーを正確に計測する事さえできなかった。したがって、全ての気候シミュレーションモデルは、地球に外部から届くエネルギーが不変であるとする致命的欠陥を持っている。太陽エネルギーが不変であるという仮定に基づいて気候予測をして、その結果に自信を示すモデル利用者達は、どうやら人類が出現する以前に大きな気候変動が頻繁に(ここで言う「頻繁」は、人間の時間スケールにおいてではなく、地球の時間スケールにおいて、である)。
起こっていたという無数の証拠を全く知らないか、信じていないようである。仮に、太陽エネルギーは不変であると仮定して、人類が排出する二酸化炭素が気候に与える影響だけを検証するのが「気候予測」の目的だとしても、現存の気候シミュレーションモデルは深刻な欠陥だらけで、二酸化炭素増加のみによる気候変化の予測や評価にすら使い物にならない。
私が熟知していない、浮遊微粒子や地海表面の熱と水収支に関わる化学・生物分野の欠陥を含めると、致命的な欠陥は際限無くあると思われるが、私が熟知している分野だけでもいくつもある。以下に、私が熟知する主な欠陥について簡単に説明しておく。
*
懐疑派科学者達の間でも意外と知られていないが、気候システムにおいて非常に重要な役割を果たしている海洋の流れとそれに関わるプロセスが、気候シミュレーションモデル内では除去されているか著しく歪められているかしており、モデル中の海洋の振る舞いが全く信用できないという事実がある。
海洋が気候の形成と変動・変化にどれだけ大きな役割を果たしているかを語り始めると切りが無いが、至極簡単に書いておこう。まず、海洋は大気と比べると全く比較にならない程の巨大な熱の倉庫であるという事実がある。海流は大気流と比べるとはるかに弱いが、膨大な量の熱を運び、大まかに言うと、地球上の比較的温度が低い地域で熱を放出して、そういった地域の気温を比較的高めに保つのに重要な貢献をしている。
海流は主に大気によって励起されているが、その大気流は海洋によって励起されている部分が大きく、実際には二者間には複雑な相互作用が存在し、海流は大気流と共に地球の気候の形成、変動、変化に極めて重要な役割を果たしている。当然、海流による熱と塩の運搬・拡散がある程度正確に表現されていない気候シミュレーションモデルでは意味のある気候予測はできない。
*
この極めて深刻な問題については、私が2000年頃から発表した6編の学術論文に詳しく記述してある。実は、この問題に気付いたのは、1995年にマサチューセッツ工科大のJohn Marshall教授と共に海洋モデルを改善しようとあれこれ試みていた時である。
後に私は、その問題点を確認する為にNASAのジェットプロパルションラボラトリーへ移動した。今では、この欠陥を指摘しているのは私だけではない。近年になって、主に流体力学理論に通じた海洋科学者達の間で、この深刻な問題の認識が広がり始めており、それに触れる論文も少しずつ増えている。
かなり複雑で専門的な内容なので大雑把に説明しよう。気候予測に使われる海洋モデルは、海洋中の熱、塩、運動量等の運搬・拡散に最も重要な役割を果たす数kmから数百kmスケールの流れを全く計算できない。そこで、その計算できない流れによる熱、塩、運動量等の運搬・拡散を、モデルが形式上は計算できる、より大きいスケールの水温、塩分、流れの構造等に基づいて推定するという方法を用いている。
問題はその推定方法で、約半分の場合において、実際にあるべき運搬・拡散の逆方向を推定してしまう、とんでもないナンチャッテ推定法なのである。(ここで私が言う「逆方向」というのは、厳密に言うと、モデルが計算できる大規模な海洋の状態に対しての事で、モデルが推定する小・中規模流による運搬・拡散は常に大規模な海洋の状態を「緩く、弱く」する様にしか働かないのに対し、現実にはおよそ半分の場合において「きつく、強く」する方向に働いている。
つまり、小・中規模流が大規模な海洋が持つエネルギーを使って強くなる場合には大規模な海洋の状態を「緩く、弱く」する方向に働くが、小・中規模流が弱くなる場合には大規模な海洋の状態を「きつく、強く」する方向に働く、という事である。
この表現も厳密には正確ではないが、これに関して正確・厳密に語るには非常に複雑で専門的な説明が必要になり、一般読者は勿論、普通レベルの気候研究者にとっても非常に難解な内容となるので、厳密・正確な理解を希望される方には、私の論文リストにある6、7、8、9、11、12と、それらに引用されてある論文を読んでいただきたい)。
方向だけではない。気候モデル内の海洋では、運搬・拡散の強さも極度に歪められている。その結果、気候モデル内では、本当の海洋自体の中で起こる小規模な流れと中・大規模な流れの相互作用が完全に除去されるだけでなく、本来は海洋自体が持つ数十年~数百年超周期の変動も除去されるか著しく歪められるかしている。
実際に、私は高解像度の海洋シミュレーションモデルが創り出す、より現実に近い仮想海洋の振舞いを様々な観点から解析して、気候シミュレーションに使われるナンチャッテ海洋モデルとは似ても似つかぬ振る舞いをする事を科学的に実証した。
*
この深刻な欠陥が引き起こす問題は海洋モデル内にとどまらない。大きく歪められた海洋モデルの振る舞いに応答する大気モデルの振る舞いも当然大きく歪められている。現実には、大気と海洋は相互に作用しあって非常に複雑な気候変動を励起しているので、それらの相互作用が除去された、あるいは著しく歪められた気候モデルによる中長期気候変動は予測目的には無意味となってしまっている。
特に、中長期的気候変動において海洋が最も重要な役割を担っている北大西洋周辺から北極へかけてと、南極大陸周辺に関しては、気候シミュレーションモデルの振る舞いが全く信用できない。中高緯度域では、雪・氷と地球の太陽光線反射率の間に、変動を増幅する相互作用があり、モデルの欠陥が増幅される傾向も強い。
当然、その様に地球全体の気候に非常に強い影響を持つ中高緯度域のプロセスの表現が全く信用できない気候モデルは、中長期気候予測には全く使い物にならない。実際、気候シミュレーションモデルが創り出す二酸化炭素増加による危機的温暖化の大きな要因の一つが、この雪・氷と太陽光線反射率の変動増幅作用であるのは広く知られている。
この問題を認めてしまうと都合が悪くなってしまう気候シミュレーションモデル利用者達は、仮にこの深刻な欠陥を知っても無視し続けてきた。何故なら、この問題を解決するには、気候予測モデル内の海洋モデルの解像度を大幅に上げる必要があり、その為には飛躍的なコンピューター性能向上が必要になるからだ。
ヨーロッパ訪問中にいろいろと世話になったので名前は伏せておくが、ヨーロッパの気候シミュレーションモデル開発の中心的人物の一人と突っ込んだ議論をした際にこの話を持ち出したところ、彼は「その問題は知っている。しかし、今のスーパーコンピューターではどうしようもない」。と言っていた。
*
また、中高緯度大気の海水温度場に対する応答も、気候シミュレーションモデル内では著しく歪められており、モデル中の大気の振る舞いも全く信用できない。数年前までは、「海洋が原因となる大規模な大気変動はエルニーニョ関連の熱帯・亜熱帯域変動が主で、中高緯度の海洋変動は大気に大きな影響を与えない」。というのが気候研究界の主流派の考えであった。その理由は、「様々な気候シミュレーションモデルを用いた多くの実験で、中高緯度の海洋変動に対して大気が応答するという明確な結果を得られない」。というものであった。
それを理由に気候変動研究主流派は、これまで使われてきた気候予測モデルが熱帯・亜熱帯域の海洋と大気のプロセスを比較的上手く再現するのであるから、モデルは気候予測に必要十分な大気・海洋プロセス再現能力を持っていると主張してきた。
この短絡思考に基づく主張に対して、1995年頃から私はずっと異議を唱えてきた。何故なら、実験に使われた全てのモデルは中高緯度の重要な大気・海洋プロセスを再現するには解像度が低過ぎ、さらに、実験結果解析はありふれた線形理論統計手法に基づいていたからである。
実際、通常の気候シミュレーションに使われる大気モデルの解像度よりも数倍解像度が高い大気シミュレーションモデル(AFESと呼ばれる大気モデル)の実験結果を解析する機会があったが、やはり通常の大気モデルと比べると遥かに人為的な平滑化が少なく、現実の大気が持つ複雑な非線形性が強い事を確認できた。
その後、他の大気モデルを使った実験で、当たり前であるが、解像度を上げれば、大気モデルが黒潮海流等に伴う海水温の細かい構造にも応答するという事実も検証した。その様な高解像度の大気モデルと高解像度海洋モデルがお互いに作用し合う高解像度気候シミュレーションモデルは、これまで使われてきた気候モデルとは全く別時限レベルの複雑な振舞いを見せるのは間違いない。
近年になって、気候シミュレーションモデルで中高緯度の大規模大気・海洋プロセスをある程度の精度で擬態するには、モデル内の緯度・経度のメッシュが大気で約0.2度以下、海洋では約0.1度以下の細かさが必要であるとわかってきた。これに対して実験や予測に使われてきた気候モデルの解像度は、緯度・経度のメッシュが1度~3度で、中高緯度の大気・海洋プロセスをある程度の精度で擬態するには明らかに不十分である。
実際、気候予測モデルの大気と海洋は、現実を再現するにはほど遠く、モデル中の様々なパラメーター値を調節する事でモデル気候の平均像はかろうじて現実にある程度似た数値を出してはいるものの、平均からの変動に関しては歪曲が著しい。モデル大気内では、中高緯度域の変動は大きく過小評価されているし、モデル海洋にいたっては、中高緯度域における現実的な変動は一切再現されていない程の劣悪な性能である。
気候モデル内の大気と海洋が現実と比べて著しく小さな変動しか起こさないのは、極度な解像度不足が主な原因であると考えられる。この欠陥が中長期気候変動予測を無意味にしてしまうのは、前述の中高緯度域における雪・氷と太陽光線反射率の間にある変動増幅相互作用と、海洋の熱塩大循環の振る舞いを大きく歪めるのが主な理由である。
*
過去の観測に基づくデータ解析では、中高緯度域における中大規模な大気と海洋の相互作用の検知は限定的であった。しかし、それはデータ不足と解析手法の問題が原因である。中高緯度域における大気と海洋の振る舞いは非線形である場合が多いのが現実であり、大気の海水面温度に対する応答も、多くの要因が複雑に絡み合った非線形である。
線形理論に基づいた統計手法では、その様なシグナルを抽出するのは困難であり、よほど解析手法を上手く工夫しなければ、意味のあるシグナルを見出す事は期待できない。実際、私自身もそのシグナルを抽出するのに散々苦労した後に、やっと地海表面観測データを強く反映したデータセットを、中高緯度の海洋と大気の力学的リンクとなるパラメーターに基づいて解析する事で、少なくとも北大西洋、北太平洋、グリーンランド海、そしてアガラス海の四つの中高緯度海域において、海水温度が中・大規模な大気の変動を引き起こす事があるという事実を確認した。
そして、それらは極域向きの熱や水蒸気の運搬にも大きな影響を与え得るので、雪・氷と太陽光線反射率の相互作用と海洋熱塩大循環を通じて長期的な気候変動・変化をも引き起こし得る。したがって、この様な重要な大気の振る舞いを再現できない気候シミュレーションモデルは、中長期的気候予測には全く使い物にならない。
おまけに、私が発見した中高緯度の大気と海洋の関係は、線形統計手法を使って検知された物であるから、全体像のほんの一部であろうと考えられる。もし膨大で精度の高い中高緯度域の大気・海洋のデータがあり、それをニューラルネットワーク等の非線形統計手法で解析すれば、もっと多くの複雑な関係が中高緯度域の大気と海洋の間で見出されるであろう。
*
気候研究者の殆どは、上記の問題を全く知らない。それどころか、私がこういう話を持ち出しても、意味が理解できない程レベルが低い研究者が多いのが残念な現実である。さらに、より現実的な気候モデルは、その振る舞いが非常に複雑になるので実験結果の理解が難しくなるし、これまで使われてきた気候モデルの様に、いくつかのパラメーター値を適当に調整して、利用者にとって望ましい実験結果を得る事が難しくなる。この様な理由で、現実の気候システムの理解度が低い多くの気候研究者にとって、高解像度の気候モデルを予測に使うというのは絶対に考えたくない事であろう。
*
最後に、懐疑派科学者達の間ではよく知られている雲と水蒸気に関する欠陥について書いておこう。私の博士論文研究のアドバイザーの1人であったRichard Lindzen教授や、授業と研究でお世話になったKerry Emanuel教授が、早くから気候モデル内の雲・水蒸気・降水等の表現手法に重大な問題があるという意見を表明しておられた事もあって、大学院生時代から気になっていた。
地球の大気において、水蒸気は二酸化炭素よりはるかに大きな温暖化効果を持つ最も重要な温暖化ガスである。気候シミュレーションモデルが予測する「二酸化炭素増加による危機的地球温暖化」の大きな原因は、実は二酸化炭素増加自体ではなく、モデルが予測する水蒸気と雲の変化にある。
したがって、気候シミュレーションモデル内の水蒸気と雲の計算精度は、中長期気候変動予測を語るにおいて非常に重要なのだ。全ての気候シミュレーションモデルは、水蒸気が絡む物理・化学プロセスのほぼ全てを物理方程式に基づいて計算する事ができない。そこで、それらのプロセスを多くの簡略化仮定に基づいて、極度に大雑把なナンチャッテ手法で表現している。
*
用いられている簡略化仮定には疑問視されるべきものが多いが、中でも気候予測に関して重大な意味を持つ簡略化仮定の一つが、「相対湿度の上下方向の基本分布は変わらない」。というものである。その仮定に基づいて、基本的な相対湿度の上下方向分布パターンは利用者にとって都合が良い様に設定されている。
相対湿度とは、普通にテレビの天気予報等で「湿度」と呼ばれているもので、空気が含み得る水蒸気の最大値に対して、実際にどの程度含まれているか、という意味を持っている。雨が降っている時などは、相対湿度はほぼ100%であり、逆に好天時の日中の砂漠では、相対湿度は10%以下である場合が多い。
そして、非常に重要な点は、気温が高ければ高いほど、含み得る水蒸気の量は多いという性質である。例えば、標高ゼロメートルの場所で気温が20℃であれば、空気は最大で1立方メートル当たり約12グラムしか含む事ができないが、21℃であれば、最大で1立方メートル当たり約13グラムの水蒸気を含む事ができる。
したがって、気候モデル内で、仮に相対湿度を固定すると、二酸化炭素増加による微弱な気温上昇に伴って大気中の水蒸気量が増え、水蒸気増加による温暖化効果増幅によって一層気温が上がる。そして、その気温上昇がさらに水蒸気量増加を招く、という、温暖化増幅の相互作用が発生するのである。
気候シミュレーションモデルが創り出す「二酸化炭素倍増による地球の危機的温暖化」は、この人為的な水蒸気量増加による温暖化効果によるところが大きい。では、この人為的な温暖化効果の元となる「相対湿度の上下方向分布は殆ど変わらない」。という仮定は科学的に強固な根拠によって正当化されるのか、と言うと、全くそうではない。
特に、現実の大気と気候モデル大気の瞬時の水蒸気分布を比較すると、似ても似つかない状態が頻繁に発生している。後でもう少し詳しく書くが、気候モデル利用者らが通常使う現実の大気と気候モデルが創り出す大気の比較方法は、一ヶ月平均や年平均であり、そういった比較で現実の大気中水蒸気分布と気候モデル創造の大気中水蒸気分布が何となく似ている事に基づいて気候モデルの性能を過信しがちである。
現実とモデル創造の水蒸気分布を比較する際に、水蒸気分布がもたらす熱放射・吸収も非常に重要で、そのためには瞬時の水蒸気分布から水蒸気のみの熱放射・吸収貢献分を算出して、その一ヶ月平均や年平均を計算しなければならない。
水蒸気量と熱放射・吸収の関係は非線形なので、平均からのバラツキが皆無でない限り、水蒸気の平均値からは熱放射・吸収の平均値は計算できないのだ。私の知る限り、気候予測において、その様な意味のある水蒸気分布とそれに伴う熱放射・吸収の精度チェックは行われていない。
*
この様な深刻な問題を知っていた私は、博士号取得後に、大気中で最強・最重要の温暖化ガスである水蒸気および雲と放射の関係を、Lindzen教授やNASAのMing-Dah Chou博士とArthur Hou博士と共に研究し、ほぼ全ての気候シミュレーションモデル内の水蒸気と雲の扱いが如何に非物理的かつ不正確であるかという事実も認識した。
水蒸気・雲・降水を物理的理論に基づいて気候モデル内で表現する現存唯一の手法も、その開発者であるEmanuel教授から学んだが、その手法でさえ様々な物理パラメーターを観測や理論に基づいた(そして、残念ながら、モデル利用上の便宜性にも基づく場合がある)推定値で固定せざるを得なく、雲や水蒸気の振る舞いを正確に表現するには程遠い。
2003年頃に、AFES という大気シミュレーションモデルの雲・水蒸気と降水再現能力を改善しようとして、Emanuel教授の手法に使われる物理パラメーターの一つ(確か降水効率だったと記憶している)を物理理論に基づいて水平気流の上下方向変化に依存させ、地球シミュレーターセンター研究員であった榎本剛氏にモデル改造とテストをしていただいたが、期待した様な大きな効果は得られなかった。かなりガッカリしたのを今でも覚えている。
*
大気モデル中の水蒸気は、大気モデル中で何がどう起こる様に仮定されるか、に大きく依存するだけでなく、大気と地面・海面の境界で何がどう起こる様に仮定されているか、にも強く依存する。私自身、大学生時代は大気と地面・海面との境界層の専門家教授達に囲まれて大気汚染研究もしていたので、大気中水蒸気の重要な供給源が気候シミュレーションモデル内で余りに雑な扱いを受けていたのを知って驚いたものだ。
特に、地面から大気への水蒸気供給は、地面がどれだけ水分を含んでいるか、だけではなく、地面にどの様な植物がどの程度の高さ、密度で生えているか、にも大きく依存するので非常に厄介なのだ。大気中においても、水蒸気量、雲の質と分布は、大気中を浮遊する微細粒子のタイプと数に大きく依存する。
気候シミュレーションモデル内での浮遊微細粒子の扱いも、仕方無いとは言え、あまりに雑である。(予測が難しい浮遊微粒子は、その色、大きさ、数、高度に依存する太陽光反射や赤外線吸収等の効果も持つので、気候シミュレーションにとっては非常に厄介な存在である)。とにかく、諸々の理由で、大気モデル内で水蒸気・雲・降水をある程度の精度で再現するのは、至難の業なのである。ましてや、それらの将来の変動を予測するなどは不可能と言っても過言ではなかろう。
*
水蒸気は、二酸化炭素とは比較にならない程効果的かつ重要な温暖化ガスで、その温暖化効果をある程度の精度で計算するには、水蒸気分布の正確な計算が必須である。しかも、水蒸気は大気の熱反射・放射・吸収に非常に重要かつ複雑な役割を演じる雲の生成源である。
二酸化炭素と大きく違い、水蒸気は大気中での時間的、空間的変動が非常に大きく、その分布は陸地表面や海面にも、大規模な大気と海洋の流れにも強く依存するので、気候予測における大きな不確実性要因になる。この問題の根本は、予測に使われる気候モデル全てが、「気候モデルで表現できる規模の大気の動きは、基本的に水平方向の動きが主で上下方向の動きは一回り以上小さい。
上下方向に不安定な大気は瞬時に上下に混ざり、不安定を解消してしまう」。という仮定に基づいている点にある。現実には、気流の上下方向と水平方向の速度は同程度である場合があり、その様な状況において強い降雨を伴う雲が発生する。しかしながら、気候予測に使われるシミュレーションモデルでは、その様な状況に物理方程式に基づく対応はできない。
これが理由で、気候モデル内では、計算できない雲や降水を発生させる大気の上下方向の動きは、モデルが計算できる大規模な大気の状態から推定される。そして、モデルが計算できる大規模な大気の流れによる水蒸気運搬と、モデルが計算できないので簡単な方法で推定される水蒸気運搬に基づいて、水蒸気・雲・降水の分布が推定される。
モデルが計算できない水蒸気運搬、雲形成、降水は、Emanuel教授が開発された手法を除いて、全てが物理理論に基づいていない上に観測データによる強固な裏づけも持たない、モデル利用上の便宜を最優先したナンチャッテ手法で推定される。
*
上下方向だけではない。気候モデルによる水平方向の水蒸気分布計算にも大きな問題がある。大規模な気流による水蒸気運搬はモデルが計算する水平流によって計算されるのだが、モデルが計算できない小規模な気流による水平方向の運搬は、一般的に「diffusion」と呼ばれる、人為的で便宜目的のナンチャッテ手法で計算される。
この計算の建前は「計算できない小規模気流による拡散を計算する」。というものであるが、現実には、シミュレーションモデルが異常数値を出して止まってしまわないように使われる人為的平滑化が主目的である。気温や運動エネルギー等の分布計算等にも使われ、それらには特に大きな問題は無い。
しかし、水蒸気の場合、温暖化効果計算の上で、この平滑化が大きな問題となる。気候モデルが計算する水蒸気分布の時間変化を瞬時の値で検証すると、実は、この人為的平滑化による効果が大規模流による運搬による効果と比べ、温暖化効果では大差無い場合が多いのだ。
(この人為的平滑化は上下方向にも強く働いている)。さらに、水蒸気観測データと比較すると、気候モデルが創り出す水蒸気の分布は、近隣で大きな値の差が発生しない様に「滑らか」にされている。これは、数値が高い箇所から低い箇所へ水蒸気が「浸み出す」というナンチャッテ手法を用いて行われる。
水蒸気の僅かな変化による温暖化効果も、元々水蒸気がどれだけあるかによって大きく左右される。元々多ければ多い程、僅かな量の変化による温暖化効果が小さい。逆に、元々少なければ少ない程、僅かな増加がより大きい温暖化効果を持つ。したがって、本来水蒸気が非常に少ない領域に人為的平滑化によって水蒸気が「浸み込む」と、その非科学的・人為的平滑化自体によって、「浸み出して減った」領域と「浸み込んできて増えた」領域の合計で、水蒸気量は同じでも、無視できない温暖化効果が発生してしまうわけだ。
*
気候シミュレーションモデルを予測に利用する人達は、モデルの性能を評価・宣伝するに当たって、モデルが計算する大気の状態の平均と、その平均からの標準的ブレを見る場合が多い。つまり、平均的1月、2月、3月、・・・というのを、30年間程度のシミュレーションから月毎に計算し、月毎に、それらの平均値から標準的にどの程度上下にぶれるのかを計算し、平均像とそれからのブレを実際の観測データ等と比較する。
一ヶ月平均の値は、気候シミュレーションモデルが一日に何回か計算する特定の瞬間の値を全て使うか、場合によっては、一日2~4回程度の瞬間値を使って計算される。当然、一ヶ月の平均値は、モデルが計算する瞬時の値とは大きく異なる場合が多い。
モデルが計算する風や気圧等を観測値と比較する場合は、その様に月平均と標準的ブレに着目すれば、それなりに意義のあるモデル性能の検討ができる。ところが、水蒸気と雲に関しては、そう単純ではない。その理由は、上にも書いたが、水蒸気と雲による熱反射・放射・吸収が、単純な線形ではないからだ。
つまり、一ヶ月平均の水蒸気分布を使って計算された熱の放射・吸収が、瞬間的水蒸気分布を使って計算された熱放射・吸収の一ヶ月平均とは必ずしも一致しないという事である。むしろ、明確に異なる場合が多いと言った方がよい。したがって、月平均値を基準にモデルを調整して、何となく観測と似た水蒸気・雲分布をモデルが創り出しても、それによる温暖化効果分布は似ても似つかない場合がある。
しかも、仮にモデルが計算する水蒸気量の誤差が非常に小さくとも、実際の水蒸気量が少ない場合は、水蒸気量誤差が伴う放射・吸収誤差は無視できない値になる。そして、現実に、気候モデルによる瞬間的水蒸気と雲の計算は、非常に精度が悪く、したがって、それらによる熱の反射・放射・吸収の計算精度はもっと悪い。
さらに厄介なのは、水蒸気・雲の観測データ自体の持つ誤差が5%以上あり、その誤差による温暖化効果が二酸化炭素倍増の効果に匹敵する大きさで、もし仮にモデルが観測データに100%合致する様に調整したとしても、モデルの変動に対する振る舞いが歪んでいる可能性が残ってしまう。
現在の水蒸気・雲分布とそれに伴う温暖化効果の計算精度が悪いのに、将来の変化・変動を正確に計算できると考えるのは、妄想としか言いようが無い。それにもかかわらず、「将来の温暖化と水蒸気増加」が、あたかも確実に起こる事かの様に語られ、それを前提にして異常気象や災害など、様々な予測が行われている。
深刻な洪水や旱魃等を伴う異常気象は、少なくとも中高緯度域においては、ゆっくりと動く偏西風の大きな蛇行に伴って起こる場合がほとんどで、その様な蛇行を引き起こす力学的・熱力学的要因が将来どう変わるかなどは、それらを再現する事さえ困難な気候シミュレーションモデルで予測できるわけがない。
*
上記の他にも、他分野の専門家達との議論等から、浮遊微粒子予測、地表面予測、海洋微生物・化学予測等もある程度の精度で気候シミュレーションモデルに組み込まなければ信頼できる気候予測はできないとも認識した。勿論、最初に書いた様に、無視できない程度の変動を示してきた太陽エネルギーも予測できないと気候予測などできるはずがない。
気候シミュレーションモデルを過信する研究者達は、全てのモデルが予測実験で同様な結果を出す事を理由にシミュレーションモデルの欠陥を軽視する主張をしがちであるが、これはナンセンスで、全てのモデルが同様な重大欠陥を持っているので同様で無意味な実験結果を出す、とも言える事を認識すべきである。
さらに、「気候シミュレーションモデルは、気候変化の傾向は正確に予測できる」。などと愚かな事をのたまう研究者も多い様だが、実際の気候システムが内包する相互作用等の重要な非線形プロセスの多くが欠如している、或いは全く正確に表現できていないモデルで変化傾向を正確に予測できるわけが無いという単純な事実を分かっていないという事が、彼らの極度な勉強不足・思考不足を示唆している。
勿論、その様な気候モデルで過去の二酸化炭素排出と気候変動の関係を正しく評価できるわけも無い。様々なパラメーター値をいじくり回してモデルをチューニングしても、過去数十年間に起こった重要な地域的気候変化等はほとんど再現できないというお粗末な代物なのだ。
そもそも、気候シミュレーションモデルは紙と鉛筆だけでは研究が難しいプロセスを研究する為の学術用道具であり、予測目的の物ではない。この事を改めて認識すべきである。気候シミュレーションモデルの中身と、それが内包する多くの欠陥・問題を認識する事なく様々な研究に使っている研究者達が世界中で非常に多くなっており、そういった研究結果に基づいて様々な政策が立てられる可能性も考えると、これが持つ問題は、単に税金の無駄遣いにとどまらないと懸念する。
また、環境保護活動家やその傾向を持つジャーナリスト、そして、気候科学専門ではない科学者達の多くが、こういった気候シミュレーションモデルの欠陥について「細かな技術的問題であって、温暖化説に疑問を投げかけるような物ではない」。という様な主張をするのは、私利私欲か、個人的感情か、知能不足か、勉強不足に基づいており、なんら科学的根拠は無いという事実を指摘しておく。
なぜ地球温暖化説が一般市民に押し付けられているのか?
さて、上記の様な重大な疑問点があるにもかかわらず、世界の気候研究者達の過半数、そして日本の気候研究者のほとんどが「二酸化炭素増加による危機的地球温暖化」を受け入れているのが現実である。
日本国内外で、温暖化説推進派の研究者達は、懐疑派科学者に論理と事実では勝てないから、潤沢な温暖化関連の研究費をバックに数で圧倒して懐疑派科学者を黙らせようとしてきた。それだけではない。懐疑派科学者に対して、政府やマスコミから様々な圧力がかけられてきた。
この傾向は、アメリカで特に強い様に感じた。過去のヨーロッパにおいて、「地球は平である」。という大間違いが科学的真実として押し付けられ、「地球は球体である」と主張していた科学者は抑圧されていたのと似ている。なぜであろう?いくつかの理由が考えられる。
*
まず、温暖化推進派の研究者達は単に頭が悪い、という可能性がある。だが、きちんと気候関連の物理プロセスを基本から学んで論文を考えながら読み、その上で上述の問題点を理解できないほど頭が悪いとなると、余程頭が悪いとしか言いようがないので、この可能性は低い。
むしろ、勉強不足であるという可能性の方が高いであろう。実際、温暖化研究を専門とする研究者達には、呆れるほど大気・海洋科学の理解度が低い人達が多い。「科学者」ではなく「プログラマー・データ可視化スペシャリスト」という人達で、気候シミュレーションモデル内の方程式と変数や定数の意味を学んで、それで現実の気候システムを理解できた、と大いに勘違いしている人達である。
気候研究に必要な科学の勉強がまだまだ不十分なまま研究職に就いてしまい、プログラミングとデータ可視化の仕事が忙しく、問題認識に繋がる様なレベルの高い科学の勉強をする時間が無い、というケースである。私の知る限り、大半の気候研究者は気候システムを水平方向(東西南北)、或いは東西方向に平均して、上下方向のみ、或いは南北方向のみに変化があるという様に極度に単純化されたシステムとして考え、大気流と海流が気候の形成、変動・変化に果たしている役割をほぼ無視しているのが現実である。
私自身の経験から、地球規模の流体力学が正しく考慮された気候力学は放射と化学反応だけに単純化されたナンチャッテ気候力学とは桁違いの複雑さである事は間違いなく、流体力学の理解度が低いまま(実は、流体力学を全く知らない気候研究者も多い)気候研究をする研究者達が温暖化説を信じ込んでいるのは何となく理解できる。
また、元々気候研究には無縁だった人達が、地球温暖化研究分野の研究資金増加に目を付け、付け刃程度の知識で気候変動研究に参入してくるというケースも多く見た。「環境科学」と呼ばれる分野で気候変動研究に関わっている人達が、その一例である。
そういった人達は、現実の気候システムに対する理解度が低いので、学術論文を読む際も、自分の信仰に近い内容の論文を選び、論文の内容を検証する目的で読むのではなく、論文中の主張を受け入れる目的で読む傾向が見られる。ほとんどの気候観測データセットが、実は限られた生の観測データを利用して人為的に作成された物で、作成段階で発生する様々な問題を含む可能性があるという事実さえ知らない人達も多い。
また、気候シミュレーションモデルは深刻な欠陥だらけだという現実を全く認識していないので、モデルが算出する結果を、科学的に意味がある物だと信じ込んでいる。実際、温暖化説を信じ込んでいる研究者達には、気候システムの理解が非常に浅い人達が多い。
気候システム内の物理・化学プロセスの理論的理解度が低いが故に、気候モデルが創り出す温暖化を宗教的に信じている様子が窺える。私自身、気候システム全体のほんの一部しか理解できていないが、自分の理解の限界を認識している分、彼らよりはマシであろう。
*
三つ目の可能性は性質が悪い。研究者が温暖化説の問題点を知りながら、自らの利益の為に問題を無視・軽視しているという可能性である。これには、この20年ほどで急速に大幅増加した気候関連の職業研究者と、日本政府が導入した大学教員や若手研究者達への研究費提供システムのあり方が強く関連している。
日本政府による気候研究費提供は、大きく分けて、研究機関という組織に対する資金提供と、大学や研究機関に所属する研究者個人や研究グループに対する資金提供という二つの形で行われる。当然、どちらの形を取るにせよ、政府の方針が強く反映される。
日本の気候関連研究費の大部分は地球温暖化が前提となっており、「本当に温暖化するのか?」や「現存の気候シミュレーションモデルで意味のある予測はできるのか?」などの、重要かつ有意義な疑問を追及する様な研究には研究費は提供されていないし、気候システムを構成する個々のプロセスを追及する様な研究も軽視されている。
研究機関に対する資金提供は、言うまでもなく、政府の方針がそのまま反映される。また、個人や研究グループに対する資金提供においては、資金提供是非の決定過程において、同じ分野の研究者達による研究プロジェクトの匿名審査が行われる。
即ち、研究機関の組織的研究活動には政府の方針が直接明確に反映され、研究者個人の研究活動には政府の方針に加えて同業者多数派の意向が反映されるわけである。この為、大学を含めて、研究組織内では政府方針を推進するのに都合が良い人事が行われ、独自の研究費が欲しい研究者は、なるべく同業者と仲良くする必要に迫られる。
この様な仕組みの気候研究業界で生き残り、昇進するためには、潤沢な資金提供に繋がり易い政府方針を積極的に推進する立場を明確にするのが最善であるのは明白であり、大規模な炭素税(露骨に「炭素税」とは呼ばれず、聞こえが良い「環境税」等の詐欺まがいの名前が付けられている)導入を推進する政府方針を正当化する為の「研究」を推進するのが研究者の経済的利益や社会的地位向上に繋がるのである。
実は、この様な研究資金提供システムはアメリカのシステムを真似たもので、アメリカにおける研究費提供を利用した科学研究活動の誘導は、日本におけるそれよりも露骨で強い。ちなみに、気候研究分野では稀であるが、他分野では、企業からの研究資金提供が活発で、そういった分野においては企業営利最優先の研究結果誘導や縛りが非常に強いのは言うまでもない。悲しい現実であるが、現代の科学研究の大半は、資金提供者の経済的目的や政治的目的を達成するための道具と化してしまっている。
*
四つ目の可能性は、「和」と「恩・義理」であろう。日本人は特に和を尊ぶので、「村」と呼んだ方がより適切な日本の小さな気候研究業界(主に日本気象学会と日本海洋学会)内の和を乱さない様に、二酸化炭素増加による地球温暖化説に露骨に疑問を呈する様な意見は言わない研究者も少なからず居ると思われる。
言い換えれば、孤立してでも言うべき事を言う気骨を持った研究者が居ない、という事である。実際、日本の研究者を見て、周囲に迎合して波風を立てない様に努める大人しい人達が多いと強く感じた。また、「あの先生にはお世話になったので、あの人の立場に反する様な意見は言えない」。といった、恩や義理が理由で異論を唱えない場合も大いにあり得る。実際、私と二人だけになった際に、温暖化説や気候予測に対する疑問を口にした日本人研究者は何人か居た。
アメリカやヨーロッパの優秀な科学者には、多勢の温暖化説に対して明確に疑問を表明する気骨を持った人達が多く居るのに対し、日本の気候研究者で温暖化説に疑問を持つ人達は、温暖化研究に直接関わらない事によって、声に出さずに意見を表明しているのかもしれない。
小さな日本の気候研究村で研究活動を続けるには、それはやむを得ないのかもしれない。村八分にされると行き詰まるのは気候研究者も同じなのだ。私はこの事情を認識していたので、決して共同研究者らに地球温暖化説の話を持ちかけなかった。
*
五つ目は、「恩・義理」の逆で、自分の部下や取り巻きの生活を守る「責任感」かもしれない。これは、研究組織内で階級がトップレベルの人達に考えられる可能性である。具体的には、元東京大学教授で、現在も日本の気候研究村の重鎮として活躍しておられる松野太郎博士について考えられる可能性である。
松野氏は他の温暖化説推進研究者とは違い、優れた科学者である。氏は、公には地球温暖化説を受け入れて、懐疑論は一切口にしない。しかしながら、私が松野氏と交わした会話を思い返すと、氏は、私が指摘している気候モデルの欠陥を認識しておられると思う。
他の温暖化研究者とは違い、松野氏の理論的理解力・洞察力は高く、自らの専門分野ではないものの、私が氏に直接説明した海洋モデルの深刻な問題点を理解されたし、通常の気候モデルでは表現できない中高緯度の海洋と大気の複雑な関係がこれまでの気候予測に非常に大きな問題を投げかけている事も、私が氏に自分の論文の別刷りを手渡しで差し上げた際に簡単に説明した事もあり、実は認識しておられるのではないかと思う。
また、気候モデル内の水蒸気と雲の非現実的な表現手法が、実は気候予測に大きな不確実性をもたらしている事実も十分認識しておられるのではないかと思う。近年、いわゆる「雲解像気候モデル」というのが松野氏や彼の取り巻きによって宣伝されているが、雲の生成・消滅プロセスを物理的に表現しているわけではなく、現実は全く「雲解像」ではない。
ただ単に、「個々の雲群の大きさを解像できる程度の解像度がありますよ」。というだけである。雲の生成・消滅は、通常のモデル同様にナンチャッテ表現法で行われているので、モデルの本質とそれが内包する問題は一般的な気候モデルのそれらと全く同じである。
取り巻きのボンクラさん達はともかく、松野氏は、それを認識しておられるはずだ。しかし、彼は立場上、仮に思っていたとしても、気候モデルが予測に使える代物ではない、などとは口が裂けても言えないであろう。そういう事情を理解していたし、松野氏はただの一度も私の科学的知見・意見を批判される事は無かったので、私は一度も松野氏を直接責める様な発言はしなかった。
大いに物議を醸したグリーンランド海水温と気候変動に関する論文の別刷りを手渡しして簡単に要点を説明した際も、真剣に耳を傾けられた後に私の意見に賛同されたし、「こういうソロの論文は好きですね」。とも言っておられた。多数の研究者達の生活が気候変動予測に依存しているのが現実であり、将来の日本の気候関連の教育発展にも気候変動予測研究が多大に貢献するのは間違いない。
現代社会において、教育と科学の進展に豊富な資金が必要なのは、逃れようの無い現実である。「中長期的気候変動予測など不可能である」という事実を認めてしまうと研究資金が激減してしまうのは必然であり、日本の気候研究村の重鎮である松野氏が、気候モデルによる気候変動予測の正当性を否定する様な発言をする事は決してできないであろう。
氏が政府の政策によってその様な立場に立たされてしまったのだとしたら、それは日本の気候科学にとって不幸な事である。良くも悪しくも、「二酸化炭素増加による危機的地球温暖化」というバカ騒ぎのおかげで、貧乏だった弱小気候研究業界に急に潤沢な研究資金が流れ込み、研究組織が肥大化してしまったわけで、組織の生き残りの為に、気候研究業界全体で「二酸化炭素増加による危機的地球温暖化」という旗を掲げ続けなければならないという状況に置かれてしまっているのではないだろうか。
*
では、何故国連主導でこの様なバカ騒ぎが続くのであろうか?その理由は、私には憶測する事しかできないが、世界銀行とIMFが温暖化対策を推進してきた事実、彼らが世界規模での炭素税導入を推進しようとしてきた事実、世界銀行とIMFの運用で欧米の大手銀行とその友人達が膨大な権益を享受してきた事実、大手民間金融機関が二酸化炭素の排出権導入を利用した金融取引を計画してきた事実、こういった事実を考慮すると、欧米金融業界主導での、金融業界と国連関係団体の利権増大を狙った世界規模の炭素税徴収が主目的ではないだろうか。
実際に、2012年か2013年のビルダバーグ・グループ年次会合の席で、世界銀行の代表が世界規模の炭素税徴収を一手に引き受けたいと発言したと、アメリカ最大の独立系メディア Infowars.comが会合出席者の話を引用報道していた。
(国際金融の頂点に君臨する国際決済銀行は、何を推進するにしてもコソコソとやる傾向が強いが、温暖化対策推進に関しても静かである)。世界銀行元首席弁護士で、世界銀行とそれを取り巻く腐敗を内部告発されたKaren Hudes氏らが指摘してこられた様に、国連も、実態は欧米の金融業界主導である事実を考慮すると、世界規模での炭素税徴収が主目的であろうという憶測は、当たらずとも遠からずではないかと思う。少なくとも、環境改善が主目的ではないのは確かだ。
*
確か2011年頃であったと思うが、当時、マサチューセッツ工科大教授として、人工光合成に基づく安価で高効率の家庭用発電・蓄電システムを開発しておられたDaniel Nocera教授が、「発展途上国を皮切りに、約1年半後に実用システムをインドの大企業タタを通じて販売し始める。一般家庭の電力需要はこれで全て対応できる」。とインタビューで語っておられた。ところが、どういう訳か、その話は完全に立ち消えてしまった。
私自身、その発電・蓄電システムが欲しかったので、Nocera教授に何度か直接メールや電話で、その発電・蓄電システムの販売について問い合わせたのだが、回答を得られなかった。Nocera教授ほどの人物が、できそうにもない事をできるとは公言しないであろう。何らかの理由で事情が変わったのだとしか思えない。
当時オバマ政権は、表向きは二酸化炭素排出削減を非常に熱心に推進していたが、当時国務長官であったJohn Kerry氏がNocera教授設立の会社を公式に訪れていたにもかかわらず、Nocera教授の一般家庭向け発電・蓄電システムは未だに実用化されていない。
それどころか、その話自体が完全に消滅してしまった。世界中の一般家庭全てが光合成に基づく安価な自家発電・蓄電システムを持てば、どれだけ大気汚染悪化と二酸化炭素排出増を抑えられる事か。もちろん、それでは世界中の石油・石炭業界と電力業界と送電関連業界は大損をするし、主要国の金融業界は儲けにならないし、世界中の政府の税収も大幅に減ってしまう。
だから、いくら環境に良くても実用化される訳が無い。どういう形で潰されたのかは知る由も無いが、様々な飴と鞭が使用されたのではないかと憶測する。世界のエネルギー供給事情を大きく変える可能性がある、あの天才Nikola Tesla博士が理論を論文に残された超高効率のクォンタムエネルギー発生装置も、いくつかの小さな独立グループが製作を試みているだけで、どの国の政府も電力会社も実用化研究の対象としていないのも同じ理由であろう。
高価で効率が悪いパネル型太陽光発電システム程度は、既存のエネルギー関連産業から深刻な敵とは見なされていないという事であろうか。少なくとも、主要国政府が地球温暖化対策だとのたまう一連のバカ騒ぎは、偽善行為以外の何物でもない。
*
また、世界規模で炭素税を導入する事で、世界政府樹立に一歩近づける、という考えも根底にあると指摘する欧米の政治・経済・社会分析家も多い。例えば、第一期ブッシュ政権で閣僚メンバーであったが、後にアメリカ政府・経済界の腐敗と違法行為を指摘してアメリカ政府・経済界から弾圧を受けてきたCatherine Austin Fitts氏らが指摘している。
つまり、「地球温暖化は地球全体の問題=>地球規模での対応(炭素課税)が必要=>地球規模の政府が必要」という売りである。地球規模で二酸化炭素排出に課税する為には、地球上の大部分において、主に二酸化炭素を発生するエネルギー源が使われる必要がある。
個々の家庭に二酸化炭素を排出しない方法でエネルギー自立されては都合が悪いのだ。仮に世界政府が樹立されるとなると、国連がその中心的行政機関となり、国際決済銀行、世界銀行、そしてIMFがその中央銀行的役割を担う事になり、それらの関係者達が受ける経済的・政治的恩恵は想像を絶する規模になろう。
国連が二酸化炭素排出削減には熱心だが、安価で高効率で小規模運営が簡単な代替エネルギーシステムの開発と普及にはリップサービス程度の活動しかしていないのは、この辺りに理由があるのかもしれない。国連の本質について大いに勘違いしているお人好しな人達が多いので改めて書いておくが、国連は初めから第二次世界大戦戦勝国支配階層の利益になる様に世界運営する目的で設計された組織であり、リップサービス・広報活動を消去して活動実態を深く冷静に観察すると、その本質は全く変わっていないというのがよくわかる。
[2018年12月追記:2018年11月に、アメリカ支配階層のインサイダー中のインサイダーであるJames Rickards氏著の「The road to ruin」を購入して読んだところ、86ページから89ページにかけて、国連主導で、SDR(IMFが発行するSpecial Drawing Rights)を新国際基軸通貨として導入し、世界規模での課税、世界規模でのインフラ整備、世界共通通貨の発行を推進する為の足場構築目的で「気候変化」が口実として利用されているとの旨が明記してあった。
つまり、何の裏付けも無い米ドルを好きなだけ発行して世界中で物やサービスを買える特権を、アメリカ支配階層の一部からIMFの背後で恩恵を受けているグループに移行させようという動きである。
SDRも所詮は何の裏付けも無い主要国通貨をパッケージにしただけの通貨であるから、アメリカ連邦準備銀行や日銀やヨーロッパ中央銀行等の民間銀行が好きなだけ通貨を発行して様々な有形・無形資産を買えるという詐欺まがいの国際金融システムが本質的に変わるわけではないが、基軸通貨発行特権が移行するというのは、特権グループ内の力のバランスの大きな変化を伴うのは間違いないので、そう簡単には実現しないかもしれない。
この本は2016年11月に出版されたのだが、それまで何年間も氏の公開インタビューや公開記事を全てチェックしていたので、氏の本は読んでいなかった。すぐに買って読めばよかったと少々後悔している。Rickards氏はアメリカ支配階層の一員でありながら、一般市民に支配階層レベルの情報をある程度提供してこられた人物で、国際政治経済に興味がある読者は、氏が過去10年以上に渡って主に独立系メディアによるインタビュー等で発信してこられた情報を精査される事をお薦めする。
氏はアメリカ政府やアメリカ軍との職務関係からアメリカの国家機密レベルの政治経済情報を多く知っておられるので、発言に相当の自主検閲を課しておられるが、それでもじっくりと聞く価値がある。上述のFitts氏は現役インサイダーではないが、1990年代後半までは支配階層のエリートで、アメリカの政治経済情報収集と分析にかけてはトップレベルであり、しかも暗殺されかけた経験があるにもかかわらず弾圧を恐れずに自主検閲無しで情報と分析を発信しておられるので、氏のインタビューやSolari Reportもじっくり精査する価値が非常に高い。
特に、ジャーナリストのGreg Hunter氏によるFitts氏のインタビューと、「The Saker」という呼び名で活動しているロシア人軍事分析家とFitts氏の対話は質が高い。他にも、例えばPaul Craig Roberts氏、David Stockman氏、Nomi Prins氏らの元アメリカ支配階層のエリートが重要な情報・分析を発信してこられたが、一般的な日本人の耳には全く入っていないと思える。
こういう人達が発信してきた情報や分析を精査すると、日本のマスコミが発信してきた「国際政治経済専門家」による欧米の政治経済解説が、呆れる程レベルが低く、表に見える動きの根幹には触れていないプロパガンダであるという現実がよくわかる。
この10年間ほどで明らかに見えてきた米ドル中心の世界金融・経済システムの崩壊と新システムへの移行が急激に加速して、世界中の社会・経済が不安定化している現在、上記の様な人達が発信する情報は世界政治経済には無関心な人達も耳を傾けた方がよいであろう。
「気候変動・変化」が科学主導の研究トピックではなく、無国籍政治経済界と超国家組織主導の世界規模政策推進道具の一つになってしまっているので、「地球温暖化問題」を理解するには、国際政治経済を理解する必要があると思う。ちなみに、面白いのは、ここ十数年ほどで、欧米政治経済界のエリート達が使う言葉が「global warming(地球温暖化)」から「climate change(気候変化)」に変わった点で、「地球温暖化」が微妙になり始めたので、温暖化でも寒冷化でも使える「気候変化」に乗り換えたものと思われる。
彼らは気候科学に関してはド素人だが、気候は人類が出現するずっと前から変化し続けてきたし今後も変化し続けるであろうという正しい認識に基づいて、「地球温暖化」から「気候変化」へとスローガンをすり替えたのであろう。馬鹿の一つ覚えの様に「地球温暖化」を叫び続けているボンクラ温暖化説推進研究者達よりも現実をよくわかっているのかもしれない。
おそらく、温暖化説推進研究者達は、もし今後隠しおおせない程地球が寒冷化した場合には、「地球温暖化によって高緯度域の氷が溶けて海洋の熱塩循環流が弱まった結果として寒冷化したのだ」。などと言って誤魔化すつもりであろう。 熱塩循環流と大気の相互作用に関するトップクラスの専門家として書いておくが、熱塩循環流自体が持つ熱運搬と高緯度域の氷の間のフィードバックだけでも、中高緯度域の気温・海水温の中長期的上下振動を励起する事ができる。
実際には、少なくとも、それに大規模な大気による熱と水蒸気の運搬と風によるフィードバックが絡むので、熱塩循環流と高緯度域の気温の間には、ボンクラ温暖化説推進研究者達が想像するよりもはるかに複雑な関係があり、それらが様々な周期の気温変動を起こし得る。
前述の様に、現行の気候シミュレーションモデルにはこれらの物理プロセスは欠如しているか、著しく歪められた形で表現されている。勿論、大気中二酸化炭素増加による温暖化が原因で熱塩循環流が弱まる可能性はあるが、現行の気候シミュレーションモデルにはそれを検証する能力は無い。
地球規模の政府を樹立する事で無益で非人道的な戦争が減るのなら、それは大いに歓迎できるが、それを推進する為に世界中の市民を嘘で騙すのはいかがなものかと思う。本気で二酸化炭素排出を減らしたければ、世界中の市民から正当な根拠を欠く炭素税を盗るのではなく、逆に、二酸化炭素を排出しないエネルギー源を生産したり使用したりする事で得る利益や消費には今後永遠に一切課税しない、とすれば建設的であるのに、盗る事ばかり主張している。
所詮、地球温暖化説は、生産的活動を一切しないくせに経済的・社会的に大きな利益を享受したい連中に利用されているだけであろう。ほとんどの気候研究者は、それを推進する為に研究費で飼われているプロパガンダ隊員であるのが残念な現実である。
*
ちなみに、私は、石油や石炭の消費を減らすのは、実際に科学的検証確認済みの、人体健康や生活環境に悪影響を与える大気・水・食糧汚染を軽減する意味で良い事だと思う。さらに、新たな化石エネルギー資源の生成率が使用率を上回っていない限り、化石エネルギー資源に量的限界があるのは明白であるのだから、化石エネルギー資源依存を減らして他のエネルギー資源へ徐々に移行するべきなのは誰にでもわかる事だ。
また、化石エネルギー資源は多くの国家間、地域間の紛争や戦争の一要因となってきたのは明白で、世界規模で化石エネルギー資源依存を軽減する事で、そういった紛争や戦争が起こる可能性も減らす事ができるであろう。それを推進するのは結構だが、嘘をついて、減らしたい物に税金をかけて一般市民から盗もうとする、そのやり方が問題だと言っているのである。「詐欺はやめろ!」と言っているのである。
本気で二酸化炭素排出を削減したければ、合法化された詐欺・強盗の炭素税徴収ではなく、二酸化炭素を排出しないエネルギー資源に関わる全ての経済活動を永遠に非課税にする、とするのが最も効率が高く、しかも道徳的である。「危機的温暖化」を信じ込んで二酸化炭素排出削減を推進している活動家達は、そういった高効率で道徳的な政策を政府や国連等に要求するべきである。それならば私も大いに支持しよう。
*
[2019年12月追記:この半年ほどで、第二次世界大戦以降続いてきた米ドル中心の世界金融・経済システムから新システムへの移行の動きが急激に加速してきた。その兆候は様々な形で現われている。例えば、複数の米ドル圏外の多国間決済システム導入、米ドル以外での中東(サウジアラビアを含むのが重大な点)石油の売買、中国人民元をブロックチェイン化して金現物で裏付ける方向への動き、3月末のBasel III施行とその後の諸外国中央銀行や政府による保有資産の米ドルから他通貨や金への変換、等が挙げられる。
こういった動きに加え、9月16日に発生したアメリカのOvernight Repo市場での金利の危機的異常事態で見え始めた米ドル金融市場の深刻な問題と、それに対応して終わりが見えないまま拡大し続けているアメリカ連邦準備銀行による「一時的」緊急資金注入(12月13日には、年末の需要増大で金融市場が崩壊するのを防ぐ為に、12月31日~1月2日期の最低5000億ドルの資金注入準備を前もって発表した)が、新金融システムへの移行の動きが激化している事を如実に物語っている。
殆どのアメリカ国民は、偶然かどうかは不明だが、この緊急事態が発生した直後頃から急展開を始めた大統領弾劾劇場というエンターテインメントを提供されて、金融市場で起こっているこの異常事態には全く関心を持っていない様子だ。
日本での関心もほぼゼロの様で、耳には入っている人達も「対岸のボヤ」程度にしか考えていないのであろう。自分達の社会経済システムに大きな変動の兆候が見られるのに、何とものん気なものだ。ただ、新システムの中心はまだ決まっていない様子で、私の様な一般人に分かる範囲内では、国連・IMF・世界銀行主導で推進するSDRを基軸通貨とする体制と、中国・ロシア等の物資・資源生産国が推進する複数通貨プラス金現物決済の体制がある様だ。
それに抵抗しているのが米ドル基軸体制を少しでも延命させたいグループなのだが、最近の国際決済銀行、IMF、世界銀行、そしてその関係者達、さらにロシア政府や中国政府や他の複数の国の政府関係者達の公式な発表やコメント、非公式なコメント等を総合すると、米ドル基軸体制崩壊が誰の目にも見え始めるのは、そう遠くない将来なのではないかと思う。
ここ数年間の国際経済の動きの根底には、いかに手持ちの米ドルやドル建て資産をこっそりと有効活用するか、という駆け引きがある様だ。とは言え、国によって事情はかなり違うので、複雑怪奇に見える。
ロシアはかなり露骨に一気に放出してしまったが、中国の様に米ドル建て資産を大量保有する国が一気に放出すれば価値が暴落して自らが大損するのは明らかなので、なるべく放出が表面には見えにくくアメリカ経済と共倒れにならない形で活用するのが最も賢明なのは言うまでもない。
公式の米国債保有額は減らさないで実質的保有額をゼロにする方法はいくつもある。当然、対米貿易黒字は減らしたいだろう。日本の場合、ほとんどの日本国民は日本円で持っていると信じ込んでいる預貯金、年金、保険掛け金等の資産のかなりの部分が、実際には様々な形で米ドル資産(基本的に誰かのドル建て借金)・金融商品(基本的に誰かのドル建てギャンブル賭け金)に投資されており、新国際金融システムがどの様な体制になろうと、かなりの損失被害を受けるのではないかと危惧している。
かと言って、1年ほど前に「Federal Accounting Standards Advisory Board Standard 56」によって正式・公式に不透明状態が合法となってしまったアメリカ政府の会計では、米ドルを頼り続ける事もできない。
あれでアメリカ政府は自らの会計と米ドルの不透明性を世界に向けて公に発信してしまった。およそ一般的に言える事だが、目立つ所では派手な大喧嘩をしている人達が、誰も見ていない時には一致協力して何かを粛々と進めている場合は、それに注意を払った方がよい。
日本国民にはあまりできる事はないかもしれないが、これを読まれた方は、できる範囲で情報を集めて精査し、自分の状況に応じて自分の納得できる対応を取られる事をお薦めしたい。また、この様な状況では、「気候変化」を言い訳にして国連・IMF・世界銀行がSDR中心の新システムを推進するために、一層「一致団結して危機的温暖化に対応する必要があるから炭素税を払いなさい」。といった洗脳活動を強化してくるであろうから、それにも用心されたい。
世界中の「中央銀行」というフランチャイズ民間銀行に集積され続けている政府や企業発行の資産が、ほぼ意図的に引き起こされているとしか思えない金融危機を利用してIMF発行のSDRで「救済」されてしまうと、何の生産的活動もしない寄生虫もどきのIMFに国(国民)や企業の資産を差し押さえる権利を渡してしまう事になる。
日本の場合、日銀は国債の半分近く、上場優良企業株総発行額の約5%、かなりの額の企業債権を買い集めているので、気をつけないと日本国民・政府の力が届かないIMFとその後ろで恩恵を受けているグループに膨大な有形・無形資産を差し押さえられてしまう可能性が出て来る。
近年の例ではギリシャやウクライナを深く調べてみると、何故IMFが「International Mafia Federation」と揶揄されるかがよくわかるだろう。資産差し押さえの代わりに炭素税を徴収するという形も十分に考えられる。
おそらく、国連が推進するAgenda 2030は、それを意識した内容である。実際、最近は純真で知識不足がちで感情だけで行動しがちな若者達を洗脳・扇動して大々的にマスコミに報道させ、大衆洗脳活動を強化している。
また、単に定期的に学校をサボって温暖化問題に抗議の座り込みをしてきただけの一人の少女が常軌を逸した特別扱いを受けて洗脳活動推進に利用されているが、彼女の両親と取り巻きを調べると芸能人だらけで、女優への登竜門の最初の仕事をこなしているだけではないか、という疑念を感じざるをえない。
彼女の容姿・立ち居振る舞い・話し方は驚異的な程に人々の同情を買うのに効果的で、「普通の17歳の少女」がここまで完成されたパフォーマンスを観衆の注目の中で演じ続けるという設定には強い違和感を覚える。いずれにせよ、世界規模で金融・経済の大変動がある中ではカモにされがちなのが日本国民なので、くれぐれも用心していただきたい。
ちなみに、私は多くの情報源を元に様々な情報・分析を入手して、それらを様々な角度から比較・分析する事で自分なりの解釈に達している。参考までに、私が利用する主な情報源をリストしておくので、活用していただければ幸いに思う。
dailyreckoning.com, fort-russ.com, globalresearch.ca, golden-jackass.com, ITM Trading Report, Money GPS, rt.com, thesaker.is, wolfstreet.com, zerohedge.com, Martin Armstrong, Danielle DiMartino-Booth, Catherine Austin Fitts/Solari Report, Bill Holter, Rob Kirby, Alasdair Macleod, Gregory Mannarino, Nomi Prins, James Rickards, Paul Craig Roberts, David Stockman, John Williams/Shadow Government Statistics]
*
[2020年1月6日追記:気候問題とは無関係なのだが、日本国民にとっても非常に憂慮すべき事態が急展開し始めている可能性が高いので、参考にしていただければと思って以下を記しておく。日本でも大きく報道されているアメリカ軍によるイラン要人の殺害には、日本では殆ど正確に報道されていない複雑な背景があるのだが、それはともかく、アメリカ政府による意図的な対イラン緊張の激化は、12月下旬に行われた史上初のオマーン海・インド洋におけるイラン海軍・ロシア海軍・中国海軍の合同演習と、ほぼ同時に公式発表されたロシアのマッハ27(時速3万6千キロメートル程度)の核弾頭搭載可能な航路可変型超長距離巡航ミサイル部隊の実戦配備の直後に起こった。
イラン国民の英雄として広く敬われてきたイラン軍エリート部隊の要人を、アメリカ政府が公式に緊張緩和会談を持ちかけてイラクへ誘い出した上で狙って殺害したのは、状況を熟知する人達には想定範囲を超える過激なエスカレート行為と受け止められており、アメリカ政府の言葉とは裏腹に、イランに対して「今すぐもっと過激な攻撃をしてくれよ!」と言わんばかりの動きだ。
アメリカ政府はイラン軍エリート部隊をテロリスト集団と指定しているので、国内外で囮捜査を活用する延長で、この要人を単なるテロリストとしておびき出して殺しただけ、という立場の様だが、騙し討ちされたと受け取るイラン政府・国民は勿論、その意図を知らずに誘い出しに協力させられたイラク政府をも激怒させている。
2019年中には、ロシア政府はイランとの関係を「重要なパートナー」や「同盟」という言葉を使って表現し始めていた。これが何を潜在的に意味するのかは説明するまでもない。これとは別に、この十年間ほどはNATOがロシアを露骨に軍事包囲する姿勢を強めて、近年はロシア西部の国境付近で大規模な軍事演習も行ってきた。
つい最近も、核兵器搭載可能な爆撃機でロシアのカリングラードを爆撃する演習を行ったばかりで、今春にはソビエト連邦崩壊後最大規模のNATO軍事演習がロシアとの国境付近で行われる予定だ。単にNATOの存在意義を保つ為にやっているだけという見方もできるが、当然、仮想標的とされている側には嬉しくない。
ロシアは脅威に対抗する措置を取らざるを得なくなる。アメリカは、結局、ロシアに20分以内に一方的に本土を完全破壊する能力保持を発表され、核ミサイル搭載潜水艦だけがアメリカの抑止力となってしまった。
ロシアの露骨な脱米ドルの動きには、米ドルを使った経済攻撃に晒されてきた他に、こういった軍事事情も背景にある。更に、11月にはプーチン大統領が国際会議で「米ドルは近々崩壊する」と公式に発言していた事実がある。「近々」がどの程度先を指しているのかは微妙ながら、この重大発言で世界中に激震が走ったのだが、日本では完全に無視されていた。その後12月中旬には、ロシア軍制服組トップが「NATOはロシアに対して大規模な戦争をしかける準備をしている」と会見で発表し、直後にはロシア政府もその見解に同意する旨を発表した。
これを受けて、その数日後にアメリカ軍制服組トップが急遽スイスに飛んでロシア軍トップと緊張緩和の公式会談を行ったのだが、どの程度緩和されたのかは公表されていない。今の状況は冷戦時代のキューバ危機以上に危険だという現実を指摘するアメリカやロシアの分析家も居るのだが、冷戦時代と違って、一般マスコミはそういった危険を無視するか、軽視した扱いをするかで、不可解としか言いようがない無関心ぶりを見せている。
こういったロシア・中国・イランへの挑発とは別に、アメリカ国内では2008年以降、巧みな国民分断が行われてきた。その分断された国民が、進行中の大統領弾劾劇場で一触即発の状態に達している。最近の調査では、アメリカ国民の70%前後が、アメリカは内戦勃発の危機に直面していると感じている。
つまり、アメリカ国民は外からの脅威と内側の脅威に晒されている。この状況下で加速・進行中なのが12月に追記した金融・経済危機なのだが、米ドルが基軸通貨特権を失うと、その痛みを最も強く感じるのは当然アメリカ国民である。
この5年以上にわたって、実際にはアメリカの消費者物価上昇率は毎年10%前後で、一般市民は生活がどんどん苦しくなってきたのだが、基軸通貨特権を失うと、年率20%を超える物価上昇が起こっても不思議ではなく、それがもたらす社会の不安定化は想像を絶する。
おまけに、ここ数年間で大企業や州政府が運営する年金システムが破綻し始めており、連邦政府が運営する社会保障制度に払い込まれてきた掛け金が違法に流用されてきた可能性まで指摘され始めている。心配されていた2019年末の米ドル金融市場崩壊は、12月に追記した史上最大の「一時的」資金注入で回避したが、問題の根本は全く改善されておらず、むしろ悪化し続けている。
「絆創膏対応」で崩壊を防ぎ続ける事はできないであろう。崩壊を防ぐ為に連邦準備銀行が正式な半永久的大規模量的金融緩和を発動するしかないであろう、という見解を表明する金融専門家が増えている。
つまり、「日本化」するという事だ。問題は、日本円と違い、米ドルは世界の基軸通貨であるという点で、基軸通貨であり続けるには、米ドルの日本円化は許されない。したがって、半永久的量的金融緩和を発動した時点で、米ドルの基軸通貨体制は終焉宣言となる。そして、それがアメリカ社会・経済破綻に繋がるのは時間の問題だ。
このまま大事件無しで経済的に破綻した状態になると、露骨な腐敗が横行する政府や特権階層に対するアメリカ国民の怒りは爆発して、極端なばら撒き福祉政策でも社会安定を保つのが難しくなる可能性が高い。
中国政府が最も恐れるのは中国人民だというのはよく言われる事だが、実は、アメリカ政府・特権階層がアメリカ市民を恐れる度合いはもっと強い。中国人民は基本的に非武装だが、アメリカ国民はかなりの割合で武装しているし、いざとなればアッという間に武装市民は増えるであろう。
実際に、この十年間ほどで、連邦政府や州政府の横暴に反発してアメリカ国内各地で小規模なボランティア地域民兵軍が組織されてきた。つい最近もバージニア州で新たなボランティア民兵軍を結成する動きが、地域によっては自治体行政参加の形で始まっている。
加えて、アメリカ軍がアメリカ国民に対して武力攻撃をするというのは考えにくい。そうなると、この10年間で急激に軍隊化が進んだ警察をもってしても、怒り狂ったアメリカ国民を押さえ込むのは容易ではないだろう。こういったアメリカの内情を理解すれば、何故このタイミングでアメリカ国民間の分断・対立激化と、ロシアとイランへの挑発激化が起こっているのかが見えてくる。
つまり、「想定外の外からの攻撃」や「過激化した市民同士の争い」が原因で社会・経済が崩壊してしまった、というストーリーをお膳立てしているという可能性である。アメリカ政府の負債は、近未来の社会保障等を含めると200兆ドルを超えるという試算が多く、その殆どはアメリカ国民に対する負債なのだが、「戦争」や「内戦」と、「それらに引き起こされた経済崩壊」で国民の多くが死んでしまうと、そういった負債に対して不履行宣言するのにとても都合が良いというわけだ。
支配する側の論理としては、一旦国を「破産」させて「有効活用できる資産・資源」だけを保持して残りは処分する、というのが最善の選択肢なのだと考えると、膨大な天然資源が温存されてきたアメリカの国有地を格安価格で入手して、それを少数精鋭の人的資源とロボット・AIだけで活用する、という事ができれば支配する側にとっては理想的なのであろうという想像がつく。
最近の統計では、約20%のアメリカ国民が連邦政府から何らかの生活補助を受けており、支配する側からは、そういった人達や年金生活者は「不良資産」としか見られていないであろう。おまけに、全体的な教育レベルの低下が著しいアメリカでは、次世代社会に生産的な貢献をできる若い人口が非常に少ないとも見られている。
支配する側にとっては、そういった若い人達も将来の「不良資産」と見なされているのではないだろうか。支配する側としては、そういう「不良資産」の怒りの矛先が自分達に向かう事無く、互いに潰しあってくれれば理想的なのではないだろうか。
今のアメリカ社会は、私が住んでいた1980年代~1990年代とは全く別物になってしまった感がある。勿論、まだまだ素晴らしい面はいろいろとあるのだが、残念ながら、今後の全体的な衰退が逆転する兆しは全く見られない。米ドル基軸体制の崩壊は、その一つの現われであろう。
米ドル崩壊がゆっくりと進行してくれれば、日本国民も徐々に展開する困難な状況に対応できるであろうが、もしアメリカ経済が「想定外の外からの攻撃」で崩壊すると、急にクレジットフローと物流が止まってしまい、日本でも外への依存が強い地域・活動は危機的状況に陥る可能性がある。
実は、米ドル金融市場崩壊はアメリカ本土への攻撃無しでも十分起こり得るので油断は禁物である。金融市場内には一般的に「ディリヴァティヴ」と呼ばれる金融商品(基本的にギャンブル)が複雑に絡み合って存在しており、重要な物資価格、利率、為替レート、経済指標等のどれか一つでも想定範囲外の大きな変動を急激に起こすと、それが引き金となって連鎖的に巨額な損失に繋がり、遂には金融市場全体を麻痺させてしまう仕組みになっている。
したがって、例えば、中東で大規模な戦闘が起こって米軍空母艦隊が全滅させられてしまうなどの「想定外の展開」が起こると、金価格が暴騰、米ドル暴落、金ディリヴァティヴ市場と米ドル為替ディリヴァティヴ市場崩壊、そして金融市場全体の崩壊、クレジットフローと物流の停止、という展開が予想される。
「急な想定外の展開」は相互依存のカジノ化した「近代」金融市場にとっては非常に危険なのだ。ロシアもイランもこの脆弱性は理解しているので、今回の挑発激化に対しても、近年両国が見せてきた効果的な「asymmetric response(目には目を、ではなく、目を潰されたら相手の食料入手ルートを断つ、という様な対応)」でアメリカに報復する可能性もある。
中国の助けを借りれば、米ドル金融市場の弱っている部分を突いて金融・経済面で大打撃を与えるのは簡単だろう。当然、足跡を巧妙に隠したサイバー攻撃もありえるだろう。しかしながら、そういった可能性をアメリカ政府が逆手に取って自作自演のサイバー攻撃を金融システムに仕掛けて崩壊させ、いずれ起こるのは時間の問題である経済・金融崩壊の責任を全てイランに押し付けてしまうのではないかと疑っているアメリカ人達も居る。
と言うのも、昨日、Federal Depository という連邦準備銀行関係のウェブサイトがハックされ、イランのハッカーがイラン要人暗殺に対する報復を宣言する内容がデカデカと表示されたのだが、それに使われたトランプ大統領の絵が何となく滑稽でわざとらしく、とても本気で怒り狂って復習を誓っているグループに作られたとは思えない様子であったのだ。
そもそも、ロシア・中国が主導する多極構造世界秩序推進グループは、できるだけスムースに紛争や戦争無しで、参加国全てに公平な代替システムを構築したいと主張してきたし、その様に動いてもきたので、なるべく急激な危機は避けようとするはずだ。まあ、こういう事態になると、狸と狐の騙しあいの様なもので、表に見える動きの裏で一体何が本当に起こったのかは永遠にわからないであろう。
アメリカ支配階層内部でも、様々なグループ、個人が各自の利益を追求して動いているそうなので、この先も周りは振り回され続けるであろう。とにかく、今後の展開の詳細にかかわらず、米ドル基軸体制がどんどん弱くなっていくのは不可避であろう。
日本では、自立度が高い地方の田舎などであれば事態はそう深刻にはならないであろうが、都市圏や観光依存が強い地方などは深刻な危機に見舞われる可能性がある。無能な連中が多い日本政府だが、おそらく外務省や財務省あたりはこういった現実を認識しているのではないだろうか。それでも国民には何も言わない(言えない)のが擬似独立国家の政府の立場であろう。周囲に吹き込まれた事を喋るだけが仕事の日本の政治家達は、こういう事情は全く知らないであろう。
日本国民にできる事は限られているが、少なくとも、大震災や洪水等の災害時に中期的に対応できる程度の備えはしておかれた方が賢明であろう。各自がそういった備えをしておけば、大規模な核ミサイルの撃ち合いにならない限り、何とか困難な期間を乗り越えられるのではないかと思う。
これを読まれた方は、この追記部分だけでも広く発信していただきたい。常に現実に何が起こっているかを知りたい方は、12月追記分に記した海外の情報源を元に様々な情報を頻繁にチェックして、自分で比較・分析する事をお薦めする。私は元々推理小説等が好きなので、ここ数年は世界で何が起こっているのかを調べ、本当はどうなっているのかを推理するのが面白くてたまらない。
しかも、どんなに面白い推理小説の何百倍も複雑で面白いし、本物の緊迫感があり、実用的でもある。気候科学に興味が無くなってきたのには、こういう理由もある。ただし、2014年から大規模核戦争の瀬戸際に近づいた事が何度かあったので、心臓が弱い人達にはあまりお薦めできない。あまりゴチャゴチャ考えたくない人達や心配性な人達には、できるだけの備えをした後は日々の生活を楽しむ事をお薦めする。
*
[2020年8月追記:もう追記はしないつもりだったが、黙って見過ごせないプロパガンダを耳にしたので指摘しておこう。この8月の暑さにはウンザリしている人達が多い日本だが、つい先日、日本の研究チームがシミュレーションモデルを用いて、この8月の様な極端な猛暑が起こっている原因は間違いなく地球温暖化である、という結果を発表したと耳にした。
調べてみると、NHKの「シブ5時」という番組で実験を簡単に説明して、猛暑の原因が温暖化であると科学的に証明された、などと言っていたらしい。そんなに簡単に意味のある検証実験などできるわけがないと思って詳細を調べようとしたのだが、やっと見つけたのは「JCCテレビすべて」というサイトの8月25日放送分記録に書かれていた内容紹介であった。
その記述は「気象研究所などの研究グループが・・・」で始まり、シミュレーションモデルで温暖化が進んだ場合と温暖化が起こらなかった場合の実験結果を出して比較し、過去68年間の様に温暖化が進んだ場合は20%の確率で2018年7月以上の猛暑が起こり、温暖化が起こらなかった場合にはほぼ0%の確率だったと報告しているとの事であった。
そこには「温暖化なしの場合というのは、海水温のデータなどを温暖化が始まる前、産業革命前に固定して、シミュレーションを繰り返し行った」。と書いてあった。この研究の詳細を調べようとしたのだが、研究チームのメンバーさえ分からない。
プロパガンダ報道が多いNHKだが、全く存在しない研究報告を捏造報道する様な性悪ではないので、出たばかりの最新研究結果で、まだ論文やレポートの形になっていないものなのだろうと思う。詳細を検証できないので結果がデタラメだとは断定できないのだが、「JCCテレビすべて」にあった記述から判断すると、主張は非常に弱いであろう。
まず、猛暑(冷夏)という、日本の夏の極端な異常は北半球規模や地球規模の全体的な温暖化(寒冷化)ではなく、偏西風の通り道の異常に伴って起きるというのが現実である。そうなると、彼らの研究では、産業革命以前には偏西風の大規模な蛇行が日本の西側(例えば今年の様に中国南東部で)で大きく南よりになって日本付近に異常に多い熱帯の空気を運ばせた夏は皆無だった、という事になる。
私の意見では、その主張は非常に弱い。そういった偏西風の大規模蛇行につながる「ブロッキング」と呼ばれる現象は、通常の気候シミュレーションで使われる解像度ではまともに再現できない。ある程度の精度で頻度・強さを再現するには緯度経度共に0.2度くらいのメッシュが必要である。
これは、発生メカニズムに極小スケールの流体プロセスが重要な役割を果たしているからである。もし仮にそういった高解像度でシミュレーションを行っていたとしても、もう一つの深刻な問題がある可能性が高い。「温暖化なしの場合」に用いられた海面水温設定である。
報道記述が正しければ、産業革命前の海水温に固定していたわけで、おそらく、産業革命以前の海面水温の月別気候値を元に年間365日の日々刻々の水温を設定して、それを68年間のシミュレーション中毎年繰り返して使ったのであろう。そもそも、そんな昔の海水温データなどほとんど無いので、それ以外に考えられない。
それに対して、温暖化が起こった場合は、シミュレーション研究を好む人達の習性から推測して、おそらく存在する中で最も現実に近いと見なされている海面水温データセットを使ったのではないかと思う。残念ながら、1980年以前の海水温度データは、北大西洋以外は非常に少なく、ほとんどの海域ではポツポツとある観測データを元にして「製品データ」という人工データが作成される。
それでも、一応ある程度の観測データを使用している分、毎年の海水温変動が反映されており、何十年分ものデータセットを平均・平滑化した気候値海水温度場よりも、はるかに複雑な構造をしており、気候値からの偏差を見ると、かなり極端な温かさ、冷たさを示す年がある。
そういった毎年の海水温が気候値からの変動を持っている場合、それを使った大気シミュレーションは、当然ながら気候値海水温を使って行われたシミュレーションと比べて偏西風の蛇行等に伴う大きな異常をより頻繁に発生させる傾向が強い。この傾向は、シミュレーションモデルの解像度が高い程顕著になる。
したがって、報道された研究が私が推測している様な海水温設定で行われていた場合(他にはあまり考えられない)、海面水温が大気流に与える影響の面において公平な比較が全くできないという深刻な問題がある。更にもう一つの大きな潜在的問題は、本書内で簡単に解説した、シミュレーションモデル内で過大評価されがちな水蒸気と気温のフィードバックである。
「温暖化した場合」の実験では、おそらく大気中二酸化炭素濃度を次第に増加させたのであろうと考えられるが、それ自体は問題無いものの、それが引き起こす若干の温暖化が、モデル内での水蒸気増加・温室効果増大の過大評価を引き起こして、猛暑発生頻度の過大評価につながっている可能性も考えられる。
もしかすると、そういった水蒸気量過大評価の問題を避けるために、二酸化炭素増加を設定する代替としてモデル大気の温度が観測データから余り乖離しない様に調整しながらシミュレーションモデルを動かしたのかもしれないが、そのあたりは実験の詳細が報告されてみないとわからない。
また、日本付近で猛暑を起こし易い力学的要因は、実は日本のやや西側で傾圧性(南北の気温勾配に比例する)が強まる場合に強化される。つまり、何らかの理由で例年よりも中国の北部が冷たく、南部が暖かくなると、それによって局所的に偏西風が強化されて蛇行を強制し、東側の日本上空では偏西風蛇行によって南から熱帯由来の空気が運び込まれ易くなるという状況を作り出す、という事だ。
いずれにせよ、本当に科学的に有意義な形で「温暖化あり」と「温暖化なし」の場合の猛暑発生頻度の公平な比較をシミュレーションモデル実験で行うというのは、現在の研究資源では非常に難しいであろう。取材したNHKスタッフが研究結果を単純化・誇大解釈したという可能性もあるが、そのあたりも研究報告の詳細を待って判断したい。
仕方無いと言えば仕方無いが、マスコミ、特にテレビ番組は、科学研究結果を報道する際に極端に単純化する傾向が強いので、テレビ番組で複雑な科学研究結果が報道された場合には、厳密には正確でない可能性を念頭に置いた方が良い。
もしかすると、新型コロナウイルスの大問題で温暖化研究関連の研究費が減らされてしまう可能性を心配して、まだ詰めの甘い研究結果を誇張して身近な自然災害と結びつけ、自分達の研究費が減らされる事を防ごうとしているだけかもしれない。研究組織上層部や学会上層部からの圧力が来れば、そういった歪曲に中堅や若手の研究者達が抵抗するのは難しいであろう。
*
新型コロナと言えば、それに関して発信しておきたい事がたくさんあるので、ついでに書いておこう。ご存知の通り、この1月に追記した直後頃からアッと言う間に世界中に蔓延した新型コロナウイルスは殆どの国や地域で大混乱を引き起こしている。あの追記直後から、私も様々な情報源から出て来る報告・分析をずっと追っているが、正直言ってわからない事だらけだ。
中国、イラン、イタリアで起こっていた事と他の国で起こっていた事を比べると、どう考えても「一種類の新型ウイルスが武漢で自然発生して他国に広がった」という単純なストーリーがいかに馬鹿げたものかはすぐにわかる。
世界中に情報網を持っているグループらから断片的に情報が発信されてきたが、少なくとも二種類の微妙に異なるウイルスがばら撒かれ、ウイルス以外の様々な「道具」が引き金や重石として使われて、同じはずのウイルスが国や地域や民族・人種によって大きく異なる影響を与えるという、非常に複雑で難解な状況を作り出したというのが現実に近いのだろうと考えている。
意図的に放出されたという証拠は無いが、漏れたのだとすると、奇跡的に良いタイミングで漏れたとしか言いようがない。2003年からアメリカ支配階層の一部とバイオテックベンチャー企業が、特定の遺伝子を攻撃する細菌兵器を作って政治的テコに利用するべき、という主張を大っぴらにしていたので、高度な遺伝子操作技術が世界中に普及してしまった今となっては、アメリカに限らず、ある程度の資金力を持った組織なら簡単に厄介な細菌を作り出して利用する事ができるはずだ。
核兵器や化学兵器と違い、厄介な生物兵器を作るのは簡単らしい。まあ、私にとっては「こう来たか。とりあえず最悪の展開は避けられたかも」。という感じで、今年1月追記部分を読まれた方達もおそらく同じ様な反応をしておられるのではないかと思う。
このウイルス問題は、ちゃんと目を開けて頭を使って詳しく調べている人達には本質が見えていると思うが、おそらく第三次世界大戦の代替イベントであろう。まだ新たな世界秩序が確立されるまでに紆余曲折がありそうなので、「代替」で終わってくれるのか、「序章」となるのかは不明だが、とりあえず、大陸間を核ミサイルがバンバン飛び交ったりする状態になる様子ではないので、マシであろう。
まだ何種類かの厄介な新型ウイルスが放出されるかもしれないが、地球上が放射能まみれになるよりはずっとマシだと思っている。欧米支配階層が使ってきた言葉を借りると、「hard kill」ではなく「soft kill」が使われているのだから、冷静に実態を観察・分析して対処方法を考え適宜実践すれば、大混乱期を無事乗り切れるのではないかと考えている。
演出された自然淘汰で除去されてしまわない様に、個々が注意深く行動するべき時期が到来してしまっただけだと思う。欧米の本物インサイダー経済・金融分析家の数名が語っていたが、偶然かどうかは不明だが、このウイルス騒ぎの御陰で、世界経済・社会は、喩えて言うなら、家の土台、柱、外壁が突如同時崩壊する直前という危険極まりない危機的状況から、家の中の装飾・装備品から徐々に壊れ始めるという、比較的対応し易い状況になっている。
もしウイルス問題が起こっていなければ、戦争か金利危機で突如金融・通貨システムが崩壊し、世界中が現状とは比べ物にならない大混乱に陥ってしまうところだったそうだ。今の流れからは、まず実体経済を麻痺させて援助しながら縮小し、そこから波及するという形で問題の根源に近いバブルマネーゲームを危機に陥れ、それを救済するという形で元々破綻し始めていた通貨システムを破壊する、という展開が予想される。
こういう崩壊順序であれば、とりあえず始めの内は通貨発行というパラシュートで困窮者を援助しながら着地させる事ができ、問題の本当の根源、通貨システムとマネーゲームは責めを負わないで済むという、「全てはウイルスのせいですよ」で済ます事ができるという筋書きだ。
おそらく、超大雑把に言うと、「目に見えない敵との戦いで世界中の政府は異次元財政出動=>市民・政府の要請に基づく各国中央銀行による異次元通貨発行・無制限資産購入=>債務返済で異次元増税 and/or 資産差し押さえ and/orハイパーインフレで全ての通貨資産は無価値に=>中央銀行システムによる完全支配下で新たな世界秩序・経済システム導入」と、こんな感じを狙っているんだろうと考えている。
国民に借金を押し付けて無駄遣いをし、自分達の利権を拡大してきた多くの国の政府にとっては、「ウイルスが起こすハイパーインフレ」は自分達の無能・腐敗ぶりを隠す絶好の言い訳でもある。得体の知れない危機を演出し、皆に懇願されてタダで全てを買って世界を支配してしまおうとは、なんとも狡賢い連中だ。
ただ、国際決済銀行主導で中央銀行システム全体がこの動きに積極的に参加している様子ではないので、連邦準備銀行主導で中央銀行システムの一部が暴走しているというのが実情かもしれない。十分厄介な状況ではあるが、無能・腐敗だらけの日本政府・製薬・医療関連の「専門家」という連中が言う事に惑わされないで、自ら情報を収集・精査して、対応策を考えられるとよいだろう。
一番気の毒なのは真面目に患者を助けようと懸命に働いている医療現場の人達で、製薬業界から巨額な原稿料・講演料・コンサルタント料・研究費を貰って潤っている「偉い先生達」の腐敗・無能の犠牲者となっている。2010年頃には日本の製薬業界から日本の医療関係者に原稿料・講演料・顧問料等の名目で支払われた金額は年間約100億円であったのが、2015年には年間約350億円まで増えていた。
去年や今年は500億円を軽く越えるのではないだろうか。原稿料や講演料なら、厚生労働省直轄機関の「偉い先生達」でも合法的に報酬を受けられるであろう。こういった製薬業界の支出は総額だけが報告され、その詳細は公開されていない。詳細の公開を義務化する法律が提案されるたびに、医療関係団体から猛烈な反対が起こって潰されてきた。
個人情報保護の観点から理解できないでもないが、そういった関係は、私の見方では「買収」以外の何物でもない。勿論、政党と政治家は、与党、野党に関係なく、製薬業界からたっぷり合法献金を貰っている。合法ではあるが、私はそれを「買収」と見る。
一般市民はどう見るのだろうか。大学や大学付属病院の「偉い先生達」は、そういった原稿書き、講演、顧問相談等に加え、研究費提供という形で製薬業界や政府から資金が提供されている。「持ちつ持たれつ」と言ってしまえばそれまでだが、私の目には不健全極まりない関係としか見えない。
一般マスコミはあくまでも思考能力を持たない宣伝屋だから、相変わらずお得意様に好都合なプロパガンダと戯言を撒き散らしているのは仕方無いだろう。彼らにとっては、それが商売である。市民全てが、一般マスコミは報道機関ではなく宣伝・洗脳媒体だと正しく認識する必要がある。
よく「中国や北朝鮮のメディアは国のプロパガンダ発信ばかりしているから信用できない」などと聞くが、日本や欧米の一般メディアは別の意味で全く信用できないという現実を全くわかっていない人達が多いのに呆れてしまう。では独立系メディアは大半が信用できるのかというと、全くそんな事はない。
大半の独立系メディアが発信するのも、やはりプロパガンダと脳機能麻痺用毒が殆どだ。それに、多くの独立系メディアは実際には大企業資本の情報操作戦略の一環として運営されている場合が多いそうだ。結局、国家によるメディア統制と大企業集団によるメディア統制は、結果としては大差無いというのが現実だ。
日本では、兵器産業が強大になる事が許されていない分、まだ諸外国より若干マシであろう。NHKは、建前上は宣伝・洗脳媒体ではないはずなのだが、実態は民営メディアとほぼ同じという残念な現実だ。とどのつまりは、メディアを盲目的に頼るのではなく、個々が頭を鍛えて情報収集・分析・発信に努めなければ、個人の生活も社会も国家も潰れてしまうという事であろう。
ちなみに、私は今回のウイルス騒動でウイルスや免疫システムについて多く学ばなければならなくなってしまったが、非常に奥が深く複雑で、論文を読んでも理解できない部分が多かった。1月頃から何百時間を新型コロナウイルス関連の情報精査に費やしたかわからないほどだが、それでも、ウイルス学や免疫学は表面を撫でた程度なので、この新型コロナウイルスに関して断定的な事は書けない。
ただ、人間が科学研究やワクチン開発の過程で、多くの動物由来ウイルスを人間に感染する性質を持つ様に加速進化させたのは間違いないと確信するに至った。そういった活動には多くの国の科学者や研究開発者が関わっており、情報だけでなく、様々なウイルスや細胞サンプル等も共有されているそうだ。
今回の新型コロナウイルスに関しても、複数の国の政府や関係者達が共同で隠蔽活動を行っているのも頷ける。政府や「専門家」が発する戯言ではなく、より実態に近い情報を得たい方達には、2020年12月追記分に記した情報源の他に、アメリカの激ヤバ研究所でエボラウイルスに人間に感染する能力を与える等の仕事をされた世界でもトップクラスの分子生物科学者Judy Mikovits博士が、Paul Cottrell博士とPeter Breggin医師とJoseph Mecola医師によるインタビューで語った内容を精査してみる事をお薦めする。
分かり易い順番は、Breggin医師によるもの、Mercola医師によるもの、そしてCottrell博士によるもの、だろう。最も勉強になるのはCottrell博士によるインタビュー内容だが、多くの専門用語とそれらの背景にある事実、技術、仮説等のレベルが高くて、あのインタビュー関連だけでも何十時間も勉強したのだが、まだ全てを理解するにはほど遠い。
Mikovits博士から学んだ事で目から鱗だったのは、特定のウイルスが特定の病気を起こすとは限らず、新たなウイルスや他の免疫刺激要因で、既に人体内に存在したウイルスが覚醒されて病気を発症する場合があるという点であった。例えば、現在蔓延している新型コロナウイルスは単に人体の免疫バランスを崩す要因で、実際の非常に複雑で深刻な症状を引き起こしているのは様々な予防接種を介して前もって体内に感染していた様々な人体感染可能型動物由来レトロウイルスではないか、と推測しておられる。
つまり、様々な予防接種を受けるのはロシアンルーレットで引き金を引いている様なもので、当たると動物由来のレトロウイルスが体内の細胞を遺伝子レベルで徐々に変異・増殖させ始め、ある程度の時間が経過した後に何かのきっかけで急に重い病気を発症したり、様々な癌やauto-immune diseases(自分の免疫システムが自分の体を攻撃して炎症等を起こす病気)等の慢性病をジワジワと引き起こしたりする事に繋がる、というわけだ。
製造方法にもよるだろうが、同種の予防接種でもどの瓶に動物由来ウイルスが混入しているかは分からないので、まさにロシアンルーレットの様な物だと思う。予防接種に様々な動物由来の人体感染可能型ウイルスが混入するのは、ワクチン製造に様々な動物細胞が使われるのが原因だとのことだ。
そういった細胞の製造過程や様々な実験過程をMikovits博士自身の経験を基に説明しておられたが、様々なウイルスと切り刻んだ様々な動物の肉片や内臓等を、ウイルス除去能力が無く人間細胞と似た「Viro E-6」と呼ばれる猿の腎臓細胞と共に巨大な容器にグチャグチャに混ぜて保温してみるなど、素人の私が聞いても「それはヤバイでしょ・・・」という感じで、性質が予測できない様々な新型ウイルスがあれこれ出来てしまうのは当然だという認識に至った。
実際、そういう懸念が理由で、2012年にアメリカ国内では意図的に動物由来のウイルスに人体感染能力を与える「Gain Of Functions(機能獲得)」研究は禁止されたのだが、笑えないのは、そういった研究をアメリカのウイルス研究者達はアメリカ政府の研究費で法的制限が無い中国・武漢の生物研究所へ移動・継続させたという現実。
それを推進・認可した人物の一人が、最近は一般人の間でも有名になってしまったアメリカ政府の新型コロナ対策でトップ専門家として表に出ているAnthony Fauci博士である。2012年以降、彼の推しで、約4億円ずつ、二度にわたって武漢の生物研究所に資金提供して動物由来のコロナウイルスに人間細胞に感染する能力を与える研究を進めさせた事実が記録に残っている。
最近これが明るみに出て、トランプ政権がその研究プログラム支援を停止させたそうだが、二十数年間もそんな事を無制限でやっていれば、どんな厄介なウイルスを創り出しているか見当もつかない。技術が進んだ今では、遺伝子編集で新たなウイルスを「美しく」創作するのも簡単らしい。
今の新型コロナウイルスも、日本のナンチャッテ専門家達が語っているよりはるかに厄介な感染レセプターの多さと、安直な症状には出ない幾つもの内臓や脳・神経細胞や免疫細胞へのダメージが確認されており、欧米の本物専門家達の多くが、自然発生ではまず有り得ない進化形態であると指摘している。
アメリカ政府資金で運営されているカザフスタンの研究所でも、同様なGOF研究活動が行われてきたそうだ。ジョージアの研究所でも危険な生物研究をさせていると、ロシア政府や中国政府が批判していた。ウイルス研究者らの引き出しには一体何十種類の危険な新型ウイルスが保管されているのか見当もつかない。
そういったウイルス研究開発には、アメリカと中国の研究者だけでなく、他の多くの国の研究者も様々な形で関わっており、自分達の研究分野が危険だという理由で廃止されるのを恐れてか、世界中の同分野の研究者達が一致団結して「この新型コロナウイルスは自然発生したものだ」と言い張っているのもよくわかる。
また、そういうGOF研究を長年推進してきたFauci博士は2017年1月にジョージタウン大学で行った講演で、「今後2~3年以内に、全く予期しない驚く様な新たな感染症が発生するのは間違い無い」。などと言い切っていた。その時の様子はちゃんと録画・配布されていて、ノストラダムスもビックリの彼の驚異的な予知能力が証明されているのは疑いの余地が無い(勿論、皮肉である)。
当時は誰もその発言に特に注意を払わなかったようだが、今春になって多くのアメリカ国民の間で物議を醸していた。ちなみに、Fauci博士はBill Gatesと長年の交友関係を持っており、Gates財団とGates財団が資金提供している団体は、中国政府など比較にならないほど圧倒的に多い資金をWHOに拠出している。
Gates個人とGates財団が積極的に製薬企業に投資してきたこともよく知られた事実だ。Gates財団を筆頭とする民間資金はWHO予算の約80%を占めているのだから、WHOが欧米製薬業界の出先機関だと言われるのも当然だろう。
これを製薬業界からの「慈善的貢献」と見るか、製薬業界による「買収」と見るかは、立場によって意見の分かれるところではあろう。そうそう、Peak ProsperityチャンネルのChris Martenson博士が2月頃から頻繁に発信し続けているCOVID-19情報まとめレポートも徹底的に精査されるとよい。
Martenson博士はアメリカ南部のエリート校Duke大学出身の超真面目な科学者で、彼のレポートを精査すると、公平で偏りが無く、データの質や解析方法、解釈に徹底的に拘る正統派科学者だというのがよく分かる。ああいう妥協無しの性格では職業科学者として成功しなかったのは無理も無い。
確か1月に始まった彼のレポートを時系列に沿って精査すると、4月頃からHydroxychloroquine, Ivermectin, Azythromycin, Doxycycline, 亜鉛、Tocilizumab, Anakinra等を用いた安価で安全で効果的な予防法・治療法が世界中で多く広く報告されていたのに、膨大な研究費や補助金が提供される上に大きな販売利益が期待できる新薬・ワクチンの開発に熱心な日本の「専門家」達は無視し続けてきたというのもよくわかるだろう。
2011年に様々な予防接種に動物由来のレトロウイルスが混入している可能性を公に指摘しようとしたMikovits博士が、何の根拠も無しに犯罪者に仕立て上げられて命の危険も感じるほどの恐ろしい目に会ったという体験談も参考にされると、WHOも含め、世界中で医療業界やマスコミや政府から撒き散らされてきた医療情報の醜い実体が見えてくるのではないかと思う。
日本では、元々マスクを着用する習慣があったからか、国内感染拡大時期がスギ・ヒノキ花粉飛散の時期と重なった事もあって、多くの外国と比べると感染者数も死者数も圧倒的に少ない。にもかかわらず、政府・マスコミは国民の恐怖を煽りまくる様な情報発信をして、社会・経済を必要以上に麻痺させてしまっている。
多くの外国では、直近3~5年間の月毎の死者数をグラフにして発表して新型コロナウイルスの死者数への貢献度を示してきたが、日本ではデータがあるはずなのに報道されていない。ザックリ言うと、日本では過去数年間は毎月10万人超が死亡している計算で、3月から5月の三ヶ月間では、例年通りなら30万人以上が様々な原因で死亡する。
今年の場合、どうなのであろう?新型コロナが原因の死亡者数は、それの1%にも満たない数字で、実際に総合的に見た場合、例年であれば風邪やインフルエンザをこじらせて死亡する人達の数の一部が、今年は新型コロナによる死者数となっているのではないだろうか?
多くの外国では、そういった月毎の死亡者数のグラフを見ると、今年は明らかに新型コロナの影響で死者数が大きく増えているのが一目瞭然なのだが、もし日本で同様のグラフを作ると、グラフに手を加えないと肉眼では差が見えない程度になる。もしかすると、日本国民はウイルスを恐れて普通の年よりも健康に気を使って極力健全な生活をした結果、今年の3月以降の総死亡者数は去年や一昨年よりも少ないかもしれない。
そういうグラフを政府やマスコミが大々的に報道すると、国民はどういう反応をするであろう?「これならワクチンや薬無しでも何とかなるじゃないか?」という声が上がるのは必然で、製薬業界と関係者達にとってはあまり嬉しくない話になるであろう。
先進国の日本で、発展途上国の多くでさえ発表されている月毎の総死者数がグラフで報道されていないのは、こういう事情があるのではないかと疑っている。こうしてみると、気候研究界はまだまだカワイイもんだなぁとつくづく思う。
断っておくが、私は新型コロナウイルスを軽視する様に薦めているわけではない。このウイルスは、軽症や無症状の感染者にも数ヶ月間以上継続する様々な内臓や神経細胞の異常をもたらす場合がある事が確認されているので、決して軽視はしない方が良さそうだ。私はこのウイルスを恐れてはいないが、警戒はしている。
ちなみに、Mikovits博士はグーグル、ユーチューブ、フェイスブック、ツイッターに徹底的に検閲・削除・攻撃されているので、無編集のオリジナルのインタビュー動画を見つけるのに少々苦労するのを覚悟された方がよいであろう。
普通に検索すると、彼女を攻撃する内容のサイトや動画が圧倒的に多く出て来る。彼女が発信している情報が、強大な経済力・政治力を持つグループにとっていかに危険かを如実に示している。彼女と協力者達が生きているのが少々不思議だが、おそらく米軍やFBIの中に居る真面目な人達の強力なサポートを受けているのではないだろうか。
彼女が新型コロナウイルスに対する予防薬として推奨しているType 1 InterferonやSuraminといった既存薬の認知度が非常に低いのも、製薬業界主導の経済的・政治的圧力が理由であろう。このウイルス騒動をきっかけにあれこれ調べまくって知った事を一々書いていると一冊の本になってしまうのでこれで終わりにするが、興味がある人は上記を参考にして深く広く掘り返していくと、この先何年間も退屈しないで済むだろう。
それが自分と家族を守ることにもなるのではないかと思う。そうそう、2017/2018年シーズンのインフルワクチンを接種した米軍兵士は接種しなかった米軍兵士よりも4割近く高い割合で新型コロナウイルスに感染したという論文が発表されているので、Mikovits博士はインフルワクチンを避けろと警告を発しておられた。
製造方法にもよるだろうが、リスクはありそうなので、インフルワクチンを接種する前に製造方法等を自分で調べてみる事をお薦めする。Mikovits博士は、導入されつつある5G電磁波が毛細血管を損傷する効果と血液中の鉄分を分離させる効果が報告されていると指摘して、それらが新型コロナウイルスに人体に悪影響を与え易くしているとも語っておられる。
今後、5Gが人体に与える影響に関する研究報告が出て来るだろうが、通信に使われる電磁波が人体に悪影響を与えてきた現実を完全に無視し続けてきた日本の医療業界とマスコミから、こういった話が出る事は有り得ないので、自分で頻繁に最新情報を精査して自己防衛するしかない。
これまで使われてきた3Gや4Gと比べて、5Gは一味も二味も違う危険な性質を持っていると警告する専門家が多く、しかも、それが人工衛星から地上に向けて照射されるとなると、リスク軽減がこれまでより一段と難しくなりそうだ。
既に昨秋からSpaceXらが5G用人工衛星をポンポン射上げているので、この冬までには相当量の5G電磁波が地上に向けて照射される事になるのだろう。
軍事目的で利用されなければよいのだが、ルールなどあって無い様なものだから、覚悟しておいた方がよさそうだ。電磁波と言えば、ワクチンに混入している様々な動物由来レトロウイルスには白血病の原因となる種があるとMikovits博士は指摘しておられたので、強い電磁場・電磁波に長時間晒される人達に白血病発症確率が高いのは、電磁場・電磁波で人体細胞遺伝子に入り込んでいるそういったレトロウイルスが活性化されるのが理由なのかもしれないとも考え始めている。
私が知らないだけで、専門家の間では、そういった方向の研究もあるのかもしれない。一般的な人間の遺伝子には、大昔からの進化の過程で様々な動物由来のウイルス遺伝子等が入り込んでいるそうなので、電磁場・電磁波で覚醒するのはそういった昔から人体遺伝子の一部になっている物なのかもしれない。
とにかく、人体細胞・免疫システムと様々なウイルス・レトロウイルスを含む可能性がある動物細胞で作られるワクチンの関係は、私が考えていたよりはるかに複雑で、癌やauto-immune diseases等の中長期的な副作用もきちんと検証しなければ、解決しようとしている問題よりも一層厄介な問題の種を植えつけてしまう事になりかねないという事であろう。
日本でも医療システムが上へ行けば行くほど腐っているので、入手した有意義な情報を懇意な医療従事者と共有して、医療現場の協力を得る形で自分を守るという選択肢もあるだろう。
例えば、今の新型コロナウイルスならば、感染前や感染直後なら、安価でありふれたHydroxychloroquineと亜鉛とIvermectinとAzythromycinとDoxycyclineの様々な組み合わせが非常に有効だという臨床報告が無数に出回っているので、それらをまとめた報告書に基づいて、適当な理由をつけて必要量処方してもらうという事ができれば、「草の根」レベルで有効な新型コロナ対応ができるというものだ。
製薬業界が弱い国では、そういった治療法が5月頃から推進されてきた。例えばインドなどは、感染リスクが高い警察官に無償でHydroxychloroquineを政府が予防薬として提供してきた。そもそも類似薬のChloroquineは、今の新型コロナウイルス(SARS Cov-2)の前身であるSARSに有効であるという報告を2005年にアメリカ政府が公式発表していた。
今回の騒動に便乗した大儲けの障害になりかねないHydroxychloroquineは、即席の露骨なインチキ研究論文で叩きまくられて潰されてしまったが、そもそもマラリア予防・治療、リューマチ治療等で1940年代から広く安全に使われてきた薬なのであるから、露骨な嘘はすぐにばれてしまっている。
嘘がばれても報道されないのは、製薬業界に政治家も専門家もマスコミも買収されている日本の様な国だけだ。現場の医師の理解さえあれば、「東南アジアのジャングルへ行く準備」とかの名目でHydroxychloroquineをあっさり処方してもらえそうな気がするし、様々な症状に処方されてきたIvermectinも、何か理由をつけて処方してくれそうな気もする。
偉そうな顔をしてテレビに出てきてあれこれ言ったり、政府主催のナンチャッテ専門家会議に参加している様な腐った連中は無視して、現場で命懸けで治療にあたっている医療従事者達と協力する方が良いであろう。私自身、春から二度にわたって若干の独自性を見せる関西テレビにHydroxychloroquineやIvermectin等、既存の効果的な予防薬セットについて報道するように提案してみたが完全に無視されたし、6月には気骨があって有能そうな京大のウイルス専門科学者にMikovits博士が発信しておられる情報に関連したいくつかの質問を送ってみたのだが完全に無視されている。
やはり「長い物に巻かれろ」や「出る釘は打たれる」が骨の髄まで浸み込んでいるのだろうか。(ただし、その京大科学者は本務に加えてマスコミと行政機関への対応で激忙らしいので、私のメールに気付いていないか、対応する暇が無いという可能性も十分にある)。
幸い、最近になってとうとう日本では「信用できる先進国」とみなされているオーストラリア医療界の大御所の一人、Thomas Borody教授が、過去に世界中から多数報告されてきた臨床研究結果も合わせて、「Ivermectin Triple Therapy(Ivermectin+Doxycycline+亜鉛)」と呼ばれる予防と初期治療で100%の治癒率が報告されている治療法を、オーストラリアの医師全てに公式に推進する事を発表し、オーストラリア政府もこれを推している。
英国帝国の一部ではあるが、自国には強大な製薬業界が無いオーストラリアならではの事情があるのだろう。腰が引けがちな日本の医療従事者も、オーストラリアの有名な教授と政府が公式に推進していると聞けば、少しは勇気を出すかもしれない。
ちなみに、この治療法がオーストラリアだけでなく多くの外国で広く報道されたにもかかわらず、それから十日以上経った今も日本のマスコミもナンチャッテ専門家達も完全に無視している。この想像以上の腐敗ぶり、無能ぶりには、さすがの私も呆れ果ててしまった。
言うまでも無いが、金と票を集める事以外は頭に無い、頭も魂も空っぽの無能で腰抜けな日本の政治家達は、安全かつ効果的な既存の予防方法があるにもかかわらず、効果も安全性も疑わしい海外製ワクチンを購入・配布して、その副作用被害に対する補償を製薬会社ではなく日本国民に押し付ける(国が賠償金を支払う)法律を成立させようと動いている。
しかも、それを大々的に、あたかも国民にとって良い事であるかの様な宣伝をしている。けしからんでは済まない話だ。1~3月に中国で数え切れないほどの人達が急に倒れて死亡するという恐ろしい状況が発生していたという情報が多くの一般人から検閲をかいくぐる形で発信されていたそうだが、その状況を調査した専門家達は、かなりの数の中国国民が2003年以降にSARSワクチンを接種していた事を指摘して、Antibody-Dependent Enhancementや別のプロセスで発生したcytokine stormによって、既存のSARS抗体が新たに入ってきたSARS Cov-2に過剰反応した事で突然死が多発したのではないか、と推測していた。
中長期的な安全性検証無しで導入されようとしている新型コロナワクチンは、下手をすると将来日本でも同様な惨状を作り出してしまうかもしれない。そうなれば人災である。責任者は何度介錯無しで腹を切っても許されないレベルの重大犯罪だ。
幸い、まだ日本製ワクチンができていないからか、日本の宣伝屋達は今のところ新型コロナワクチンに対して若干の慎重論も報道している。しかしながら、今後感染者数が増えたり、国連や宗主国エリート達からの圧力が強まると対ワクチン慎重論が消滅してしまう可能性も十分あるので、要警戒であろう。
日本政府・政治家の無能・腰抜けぶりは、効果がほとんど確認されていない上に深刻な副作用が本国アメリカにおいてさえ報告されているRemdesivirが、異常な特別扱いで日本国内初のCovid-19治療薬に承認されてしまった経過を見れば一目瞭然である。
無能・腰抜けの代表格の一人は、これから起こる事の大筋を聞かされたか、本能的に危険を察したか、今日、突然、仮病を使って「一抜けた」をしてしまった様だ。情けない話だ。戦後最悪期の首相になるという貧乏くじを引かされるのが誰になろうと、全く期待はできない。
また、Mikovits博士が内部告発しておられる様に、多くのワクチンに様々な動物由来のレトロウイルスが混入しているならば、どの予防接種を受けるのもロシアンルーレットで引き金を引くのと同様な行為だという現実も認識された方が良いだろう。
日本で流通している様々なワクチンから動物由来レトロウイルスに感染する確率がどの程度なのかは見当もつかないが、一般普及型ワクチンで健康な人間細胞だけを元に作られた物があるとは聞いた事が無いので、リスクはゼロではなかろう。これを読まれた方は、この追記部分をどんどん拡散していただきたい。
ただし、新型コロナウイルスの実態に関する情報をツイッターやフェイスブックで発信してアカウントを閉鎖されたアメリカ人やアメリカの独立系報道機関がかなりあるので、一応そういう検閲の標的になる可能性を念頭に置いて対応していただく方がよろしいかとも思う。
例えば、「Mikovits博士」を「エムアイケーオーブイアイティーエスはくし」などと書いたりする事で、検閲ソフトのチェックをかわす事ができるかもしれない。もぐら叩きゲーム感覚で楽しんでもらうのもよいかもしれない。この先、新たな世界秩序が確立されるまでに何種類もの新型ウイルスが出て来る可能性も念頭に置いて、楽しみながら中長期的情報戦を戦い抜く気構えを持たれる事をお薦めする。
同様に大きな世界秩序変化を伴った第二次世界大戦に巻き込まれた世代と比べると、自分は本当に恵まれているとつくづく感じている。
*
[2020年10月追記:インフルワクチンの話を頻繁に聞く様になったので、Covid-19との関連をもう少し調べてみたが、実際には安直な関連性は証明されていないとわかったので訂正追記しておく。その前に、8月追記分を読み返して、猛暑や厳冬等の異常気象を起こす偏西風蛇行について少々書き足しておきたいと思ったので、それから始める。
同じ様な強い偏西風蛇行が繰り返し起こる場合、基本的には大規模な大気流を励起する要因が東西方向に不均一であるというのが原因で、チベット高原やロッキー山脈等の大規模山岳地形を除くと、「傾圧性」と呼ばれる大気下層部の水平方向気温勾配の非均一性による。
大雑把に言うと、中高緯度域では大気最下層部の気温勾配は南北方向に強く、海との相互作用も効いて北半球では黒潮・親潮続流とメキシコ湾流の大陸付近で顕著に強い。そして、それらの海流の下流(東側)へ行けば行くほど傾圧性が弱くなっている。
そういった要因で傾圧性に東西方向の大きな差がある場合、偏西風は傾圧性が強い地域で加速されると同時に低気圧・高気圧擾乱を励起し、傾圧性が弱く偏西風加速が弱い地域上空では擾乱の東進が滞って偏西風の北向き蛇行、或いは南北に割れる蛇行を引き起こす傾向がある。
こういった海流に伴う強い傾圧性は、季節変動を除くと極端に強くなったり弱くなったりする事は稀なのだが、陸地と海洋の表面温度差に伴う傾圧性や、大陸上の異常気象に伴う傾圧性は非常に強い異常状態を起こす場合がある。これは、海洋水面温度と比べて陸地表面温度が大きく変動しやすい事を反映している。
例えば、晩春から夏にかけて日射量が多い時期に大陸北部で雲や降雨が多い状態が続くと大陸上での傾圧性が通常より顕著に強くなり得るし、大陸上全てで雲や降雨が多い状態が続くと大陸と海洋の温度差による傾圧性が通常よりかなり強くなり得る。
すると、その様に傾圧性が強まった地域の東側で同様な傾圧性強化が起こっていない場合、その付近で偏西風の大きな蛇行が繰り返し起こる可能性が高まり、北向き蛇行の西側では冷夏・多雨が、東側では猛暑・少雨が起こりやすくなる。これは、偏西風が北向きに蛇行する地域で局所的に低気圧・高気圧の大気擾乱が発達し易くなる事を反映している。
データを解析していないので確実な事は言えないが、去年2019年秋頃から継続してユーラシア大陸東部から日本をまたいで北太平洋西部にかけて、まさにこの状態が起こっている様に見える。形圧性が強い地帯が南北にも延びていると(普通の地図をイメージして言うなら、下から上へ、或いは左下から右上方向へ延びている)、偏西風を北向きに加速させる傾向が強くなると同時に、西側から流れてくる低気圧・高気圧の擾乱と1万kmスケールの偏西風蛇行が相互作用を起こし、これも偏西風の大きな蛇行を繰り返し起こす一大要因となる。
偏西風の異常状態が繰り返されると、海洋との相互作用によって、偏西風の異常状態を維持・強化する傾向に働く。大陸と海洋の境界付近というのは、まさにこの様な複雑な要因が重なって存在する地域なのだ。そして、非常に厄介なことに、偏西風の強い蛇行が繰り返し起こるかどうか、どこで蛇行するか、は、北半球中高緯度域全体の傾圧性分布にも強く依存するので、一地域の状況だけに着目して偏西風の異常な振る舞いを理解するのは不可能である。
中高緯度域の傾圧性が全体的に弱く偏西風が弱い夏には、一地域の傾圧性異常が偏西風に与える影響が比較的分かり易くなるが、それでも限定的である。例えば、もし仮にユーラシア大陸東半分の中高緯度域が寒冷化していて、北太平洋海面水温に異常が無いとしたら、偏西風が強い冬には偏西風の北向き蛇行が日本の東側で繰り返し起こって、偏西風が弱い夏には日本の西側で繰り返し起こる、という状況を作り出すことも十分あり得る。
もし仮にユーラシア大陸全体の中高緯度域が寒冷化していて、北太平洋水温に異常が無いとしたら、日本上空に到達する偏西風は強化され、大陸東半分だけが寒冷化した場合と比べ、北向き蛇行の位置が大きく東側にずれてしまうとも想定される。
ただし、偏西風がチベット高原にどの様に影響を受けるかによっても偏西風がどの様に振る舞うかが変わってくる。さらに付け加えるなら、蛇行が起こるかどうか、蛇行がどこで起こるか、は、北大西洋上の状況にも、北太平洋の状況にも影響を受ける。
例えば、前述の例で記した日本付近での偏西風の北向き蛇行は、ユーラシア大陸上の異常ではなく、北太平洋中部広域で海面水温の南北勾配が著しく弱くなる傾圧性異常でも起こり得る。そして、それが引き金となって日射量が多い晩春から夏にかけてユーラシア大陸上に冷夏・多雨をもたらす結果にもなり得る。
こういった多種複雑な要因が寄与して発生する現象を、シミュレーションモデルを使ってある程度の精度で再現・予測するには、仮に海洋水温を設定する実験で検証するにしても、高い解像度に加え、陸地表面の温度変動をある程度の精度で表現できる性能が必要になる。
私が知る限り、そういった性能を持つ大気シミュレーションモデルは存在しない。陸地上の熱収支、水収支、そして日射量に関わるプロセスは、現存の大気シミュレーションモデル内では極度に単純化されたナンチャッテ表現法で行われており、それらが重要な役割を持つ現象の予測や、異常気象等の現象に二酸化炭素増加が寄与しているかどうかの検証等には全く使い物にならない。
大気科学、海洋科学、地球流体力学の理解度が非常に低いが故にやたらと「シミュレーションモデル」という単純なコンピュータープログラムを多用してあれこれ試して「研究成果」というゴミ(次章中に記してある眞鍋博士の言葉を引用)を論文として数多く発表する気候研究者が主流派となってしまっているので、科学的根拠は皆無か非常に弱い実験結果が「科学的事実」として巷に溢れているのを念頭に置いておかれる方がよい。
8月追記分で触れた「最近の日本の猛暑は、間違いなく二酸化炭素増加による地球温暖化が原因」という研究結果が基づいていたのは、知人から貰った情報によると、おそらく「Imada et al., 2019: The July 2018 high temperature event in Japan could not have happened without human-induced global warming. SOLA Vol. 15A, 8-12」という論文で発表された研究結果であろうと判明した。
比較的短い論文なので、実験に使われた「温暖化が起こらなかった場合」の海面水温設定の記述が曖昧で、具体的にどの様な温度場を使ったのかが明確ではない。意図的に曖昧にしてあるのか、重要だと認識していないから曖昧なのかは不明だが、あれでは意味のある比較実験が全くできていない可能性が残る。
したがって、あれも典型的なゴミ結果である可能性がある。大きな問題なのは、全ての研究分野で言える事なのだが、どんなゴミ結果でも論文として発表してさえしまえば、「科学的に検証された事実」として主張されてしまうという点である。専門家によって査読された論文として発表されるという事自体は大事なのだが、「査読する専門家」が著者と利権を共有している場合は全く「査読」の意味が無くなってしまう。
警察と泥棒が利益を分かち合っていたらどうなるか、想像してみられるとよい。ちなみに、もし太陽光線が次第に弱まってきていたり、北大西洋熱塩循環流が弱まってきていたりしてユーラシア大陸が次第に冷えてきているとすると、ユーラシア大陸東端部から北太平洋西端部にかけて偏西風を北向きに蛇行させる要因が強まり、蛇行の南向き部分と北向き部分がどこにかかるかによって極端な異常気象が続く可能性も十分ある。
つまり、北半球寒冷化の兆候でユーラシア大陸が冷えると、大陸東側では冷夏が続き、そのすぐ東の日本に猛暑が続く可能性も十分にあるという事だ。大陸寒冷化が進行して夏の偏西風が強くなると、同じ原理で発生する北向き蛇行が東へずれて、大陸東側だけでなく日本も冷夏が続く様になる可能性もある。
また、偏西風が強まる冬季には、同じ要因が日本に繰り返し厳冬をもたらす可能性も十分にある。この一見矛盾した大陸上の気温変化傾向と北太平洋西端付近の気温変化傾向は、陸地表面が簡単に冷えるのに対して海洋表面、特に黒潮に強く影響を受ける海域はなかなか冷えないのが理由である。
ましてや、偏西風の北向き蛇行が日本付近で繰り返し起こると、大規模な大気・海洋相互作用によって、大陸上は寒冷化しているのに、その東側の海洋は温暖化するという、一見不可思議な状態も発生し得る。一地域の猛暑や冷夏、暖冬や厳冬などは、あくまでも短期的かつ地域的現象であり、地球規模は言うまでもなく、半球規模の変化・変動とさえ傾向は一致しないのが普通と認識しておくべきである。
そういった異常状態が繰り返し起これば地域的気候変化と言えるが、それも半球規模や地球規模の気候変化とは傾向が一致する必然性は全く無い。現象を引き起こすメカニズムを理解することなく「シミュレーションモデル」という扱いが簡単で利用者が望む結果を出し易いオモチャに頼る研究者達は、研究費獲得目的のプロパガンダを撒き散らす前に、以上の様な複雑な物理メカニズムの現実を認識する必要がある(わかっていてインチキをやっているのかもしれない)。
これは気候研究だけでなく、ウイルス感染者数予測等、他の分野の研究においても同じである。今回の新型コロナ騒ぎで耳にしたウイルス感染者数シミュレーションモデルのあまりのテキトーさには唖然としてしまった。
本当に、「え!こんな数値モデルで予測???マジ???」であった。まあ、あの分野は比較的新しい様なのでシミュレーションの幼稚園児達がやっている事と思えば許せる気もするが、あんな「定量化」が出す情報を基に社会・経済・人命を大きく左右する国の政策を決めるのは余りにも馬鹿げている。
重要なフィードバックに特に強い影響を持つのが「人間の心理」という、数式表現が極めて難しい要因なので、現実的な数値化に苦労するのは理解できるが、「一般大衆は馬鹿で無知だから何を言っても大丈夫だろう」とでも考えて「予測」を発表しているのであろうか・・・ あの連中がやっている「シミュレーション予測」と比べると、最もイーカゲンな気候シミュレーション予測さえマトモに見えてしまう。
*
さて、回り道が長くなってしまったが、インフルワクチンに話を戻そう。まず、上記8月追記分で書いた2017/2018年シーズンのインフルワクチンを接種した米軍兵士は接種しなかった米軍兵士よりも4割近く高い割合で新型コロナウイルスに感染したという論文が発表されているという話は、正確には論文で報告されている検証対象はコロナウイルス全般で、私の解釈が間違っていた。
Mikovits博士は、私や他の多くの欧米人と同様に、会話中では新型コロナウイルスに言及する際に単に「Corona」や「Corona virus」と簡略化することが多く、正式名称である「SARS Cov-2」や「Novel Corona virus」と呼んで他のコロナウイルスと区別されない傾向が強いので、私が勘違いしていた。ちなみに、Covid-19は病名であり、ウイルス名ではない。
現在、世界中で「一般人社会において認識されている事実」では、人間に感染するコロナウイルスは風邪の要因となる4種、SARS第1号、MERS、そして今の「新型コロナウイルス」SARS第2号の7種があるということになっている。おそらく、世界中に点在する生物研究所には何十種類もの人間感染能力を持つ新型コロナウイルスが存在するであろうし、そういったウイルスに常日頃関わっている人達は特に症状を起こす事無く感染している可能性も十分にあるが、ここではそれはとりあえず無視しよう。
そうすると、その論文でのデータ解析が行われた当時は、まだSARS第2号は建前上では一般社会では識別されていなかったので、上述の論文で報告されていたコロナウイルスは建前上ではSARS第2号以外の6種という事になる。Martensen博士が、インフルワクチン接種率が高い国ほどCovid-19による死亡率が顕著に高いという統計解析結果を報告する論文を紹介していたが、彼も指摘する通り、データポイントの多くが大きく異なる他要因を含んでいる上に、データポイントのばらつきが非常に大きいので、私の目にはその主張はほぼ無意味に見える。
ただ、Mikovits博士は、SARS第2号はインフルワクチン等を経由して人体に入りおとなしくしていたのが、強い電磁波等の外的要因で人体免疫バランスが崩れた事で活性化して増殖し、そこから対人感染が広まったと考えておられる様で、2017/2018年にアメリカで使われたインフルワクチンがその導入経路の一つだとも考えておられるようだ。
つまり、人体内に静かに存在していた間は悪者扱いされなかったのが、増殖し始めた事で、増殖を伴う場合がある様々な症状の原因という悪者扱いされ始めた、という解釈である。8月追記分中で書いたが、Mikovits博士は、前もって人体中で増殖していた様々な動物由来のレトロウイルスが「Covid-19、新型コロナウウイルス感染症」の本当の原因だとも推測しておられる。
言い換えると、「新型コロナウイルス感染症」と呼ばれる症状と「新型コロナウイルスの増加」の相関関係を、他の「無視されている、或いは存在しないことになっているレトロウイルス増加」を調べないまま、「新型コロナウイルスが新型コロナウイルス感染症を起こしている」という因果関係とすり替えている、という解釈である。
つまり、動物由来のレトロウイルスが引き起こす症状をSARS第2号に責任転嫁している、という解釈だ。最近、Covid-19の深刻な症状の主要因の一つはBradykinin Stormという現象によるという仮説が大きく注目されており、私もそれを勉強してみたのだが(勿論、ほんの少ししか理解できていない)、もし本当に5Gの強い電磁波が毛細血管を損傷させる効果と血液中の鉄分を分離する効果を持っているならば(以前にも書いたが、3Gや4G等に使われてきた電磁波でも遺伝子を損傷する効果は科学的に確認・報告されている)、ウイルスとは無関係に、5G電磁波がBradykinin Storm発生要因となって「深刻な新型コロナ症状」を引き起こすという可能性は十分あるという素人解釈に達している。
(Bradykinin Stormの詳細を知りたい読者は、論文を読む前に、まずはMobeen Syed医師の解説動画を視聴してみる事をお薦めする)。それに伴って、元々体内に静かに存在したSARS第2号が活性化・増殖すると、「新型コロナウイルスによって重篤状態に陥った」というストーリーになってしまう可能性もあるというわけだ。
したがって、もしそういったメカニズムが現実に起こっているなら、「2019年からずっと山中で隔離された生活をしていたのに、知らない間に人工衛星から照射された強い電磁波を浴びて、新型コロナ感染症を発症してしまった」。というケースも考えられる。
最近、「ちゃんと予防対策をしていたし、誰とも濃厚接触が無かったのに、なぜか新型コロナに感染してしまった」。というケースがポツポツと起こっているのは、大都市圏で拡大されつつある5Gネットワークの強い電磁波によって、既に体内に存在した新型コロナウイルスが覚醒されたというのが実態なのかもしれない。
ただ、Mikovits博士の推測が正しければ、仮に新型コロナウイルスが覚醒しても、実際に深刻な症状を引き起こす様々な動物由来のレトロウイルスが体内で増殖していなければ、ちょっとした風邪の症状程度で済んでしまう場合が多いのだろう。
また、Mikovits博士は、PCR検査がRNAウイルスの破片を何十億倍にも増殖させる課程で被験サンプル遺伝子情報に多くの変異が発生するので、それが普通の風邪コロナウイルスの破片やペット動物が持つ様々な非人体感染型コロナウイルスの破片からSARS第2号陽性という誤った結果を出し得るので、SARS第2号感染検査にはウイルスその物の抽出という正統手法を使うべきだとも指摘しておられる。
意図的に感染者数を増やすのが目的か、それとも世界中で繰り返し行われるPCRテストから得られる膨大な特許使用料収入が目的か、その両方か、理由は明確ではないが、世界中で繰り返し行われているPCRテストは不適切だと主張しておられる。
さらに、SARS第2号のPCR検査で一体何を検知させられているのかが不明瞭で、SARS第2号の遺伝子羅列とされている様々な羅列情報の何の検出を以って陽性としているのか、それがCovid-19という病気の本当の原因なのか、その辺りが全く明確にされていないとの事だ。
こういった専門レベルの高い話になると私にはよくわからないので彼女の話や論文を正しく解釈していない可能性も十分あるので、興味がある人達には自分で納得がいくまで深く掘り下げてみられる事をお薦めしたい。高度な分子生物科学の話に多大な時間を費やしたくない読者には、新型コロナ騒ぎに関連するカネの動きを詳しく調べてみる事をお薦めする。
とにかく、人為的に操作可能な電磁波、新型コロナウイルス、風邪のコロナウイルス、動物由来のレトロウイルス、不確実なウイルス検査、これらの要因が想像を絶する複雑怪奇な状況を作り出し得るのは何となくわかって頂けるのではないかと思う。
人工衛星から地上へ向けて局地的に強い電磁波を照射する事が簡単にできる現代では、人為的に活性化されたウイルスが、最初の発症者から市中感染が広まって不可解極まりない状況になる、という可能性も十分想定できる。電磁波照射によってウイルスとは無関係の体調不良人口増加を地域的に発生させる事が可能となると、なおさらである。
症状は恐ろしいが状況把握が簡単なエボラウイルス感染やSARS感染よりも、「ほとんどの人には心配無いが、重症化する可能性もあり、どうなってるのかわけがわからん」というCovid-19の様な感染症の方が社会不安醸成・大衆操作には利用価値が高いであろう。
強くなり続けている環境中の電磁場・電磁波の特性とそれが人体に与える悪影響、そして、それらの悪影響を軽減する方法については、私もこれから真剣に勉強しようと考えている。さて、インフルワクチンに話を戻そう。まず、最近、インフルに関して世界中で誰の目にも明確になっている事実がある。
新型コロナ感染予防対策がインフル感染予防に驚異的な効果を発揮しており、国や地域によってばらつきはあるが、新型コロナ感染予防対策でインフル感染をほぼ100%予防できている。今年のインフル患者数は例年の100分の1から1000分の1という驚異的な少なさで、この状況下において、アルミ塩やチメロサール(約半分は有機水銀)やホルムアルデヒドやPolysorbate80等のトンデモ有害物質が含まれている(ちゃんと表示されている)物が多いインフルワクチンを接種する理由は、個人的には全く思いつかない。
そういった有害物質は極微量で、食べ物や飲み物に混ざった状態で口から入るのなら全く心配しないが、直接血液中・筋肉中に注入するのは真っ平ゴメンだ。さらに、インフルワクチンを接種した人達の75%前後はインフルにかからない事を挙げて「70~80%の予防効果がある」とよく言われるが、実は、インフルワクチンを接種しない人達の75%前後もインフルにかからないというのが現実だ。
では、製薬業界の金儲け以外に、インフルワクチン接種の意味は?また、「インフルワクチンはインフルにかかった際に重症化を防ぐ効果がある」という主張を頻繁に聞くので、徹底的にその根拠を探してみたのだが、理論的根拠だけで、その主張を裏付けるデータは全く存在しないという事実が判明した。
毎度の事とは言え、本当に呆れてしまった。データ無視で、複雑な現象の一部だけに関する理論を元に誇大主張をする単純思考の輩はどの分野にも多い。金儲けが絡むと特にその傾向が強い様だ。道理で真面目な医者は、「重症化を抑えると言われています」。という控え目な言い方をするわけだ。もちろん、8月追記分に記した様に、一般普及型ワクチンのどれにも動物由来のレトロウイルスが混入している可能性があるので、統計的に言うなら、接種者にとっては、「インフルワクチン接種は百害あって一利無し」と言えよう。
ワクチンついでに新型コロナワクチンについてもちょっと書いておこう。春頃に、新型コロナワクチンに、新しいタイプのmRNAワクチン、RNAワクチン、DNAワクチン等の、接種者の遺伝子を変えてウイルス感染予防をしようという話を多く聞いた。
その時は、そういったタイプのワクチンには有害な添加物等が使われない上に自分の体が遺伝子レベルで免疫を作り出すので安全なのかとも思ったが、その後学んだ多くの事実から、仮に短期的に副作用が見られなくとも、数年~十年という期間を考えると、遺伝子・細胞変異によって癌やauto-immune diseases等の非常に厄介な病気を引き起こす可能性が高いのではないかという疑問を持つようになった。
そういうリスク不明の商品は、まずは開発者・推進者・製造会社・大株主とその家族達に使ってもらって、最低でも10年間の接種後観察で安全性と予防効果が検証されない限り、絶対に拒否しようと決めている。考えてみれば、短期的には安全で中長期的には原因不明の厄介な慢性病等を起こすワクチンを売る事ができれば、「多くの健康な人にワクチンを売って将来の病気の種を撒いておき、病気発症後にその症状を軽減・解消する商品を売る」という、製薬業界・医療業界にとっては理想的なビジネスモデルになるのであろう。
長期的に安定した利益を上げる事だけを重視するなら、天才的な経営戦略である。非常に高いレベルで様々な情報を収集・分析してこられたCatherine Austin Fitts氏は、様々なワクチンの大規模接種促進は、単なる金儲けなどではなく、もっと深くスケールが大きい目標達成へ向けての手段の一つであろうと疑っておられる。
私自身も、調べれば調べるほど、単なる金儲け以上の意図が背景にあるのではないかという疑念が強くなっている。例えば、欧米支配階層の一部にEugenicists(劣勢遺伝子を持つ個体は淘汰して、優秀な遺伝子を持つ個体だけが繁栄する社会を人類にも適用するべきだと考える人達)と呼ばれる人達が存在するのはよく知られているが、そういう人達にとっても有用な道具の一つとなるのかもしれない。
彼らの基準による「優秀な遺伝子」を残しながら緩やかに地球人口を減少させるには、エネルギー生産・消費を強制的に減らすという選択肢もあるし、経済崩壊を起こすという選択肢もあるし、複雑怪奇な感染病蔓延を演出するという選択肢もあるし、原因不明の慢性病を次々導入するという選択肢もあるし、食糧生産を妨害するという選択肢もあろう。
もしかすると、「新型ウイルス蔓延」という非常に効果的な大衆操作方法を優先使用すると決めて、今のところあまり進捗が見られない「炭素税導入によるエネルギー消費減少」という選択肢を破棄してくるかもしれない。(もしそうなると、危機的地球温暖化プロパガンダの声が次第に弱まっていくであろう。
今後数年間、その視点にも着目して政府やマスコミの様子を見てみると面白いだろう)。一般大衆を牛や羊などの家畜と同列にして考えると、AI.・ロボットが進化すれば家畜の多くは不要になるという考え方になるのであろう。私の目には、この十数年間の欧米や日本の様子は、多くの家畜が様々な方法で行き先不明な貨物列車に乗るように誘導されている様に映ってきたが、今回のウイルス騒動で、それがよりハッキリと見えてきた気がする。
自然界の原理として「種の保存・繁栄には、劣勢遺伝子淘汰は必要だ」という主張に一理はあるが、特定の集団による独善的な淘汰対象選定には様々な道徳的問題があるというのが私の意見だ。ちなみに、私自身は一般的な感染予防対策の他に、インフル撃退・不特定新型ウイルス撃退目的で、良質な動物性・植物性脂肪が大目の健康的な食事、適度な運動、良質な睡眠、強い電磁波・電磁場の回避、ビタミンD3確保の日光浴、ビタミンC補給、Quercetin+亜鉛補給、を実践している。
それらの詳細や科学的根拠に興味がある読者には、Joseph Mercola医師が過去20数年間にわたってmercola.comを通じて発信してこられた様々な情報を元に、広く深く調べてみる事をお薦めする。一つ強調しておきたいが、優秀で純粋な意図を持つ科学者・医学者の主張も、なるべく鵜呑みにしないで、自分で頭を使って考えてみる事が重要だ。
例えば、私はMikovits博士の人間性を信用して、トップレベルの科学者に対する敬意を持って彼女の話を聞いているが、絶対に主張・推測を鵜呑みにはしない。どんなに優れた人間も完璧ではないからだ。彼女は免疫システム弱体化と酸素吸入量減少という正当な懸念からマスク着用に強く反対しておられるが、データと論理に基づいた私の意見は「飛散させる、或いは吸収するウイルスの数を減らして免疫システム勝利の確率を高める意味で効果的」というChris Martenson博士の意見とほぼ同じで、状況に応じて適宜着用している。ただし、密閉性が高いN95等のマスクは酸素不足を生じる心配があるので使わない。「健康状態を良好に保って少数のウイルスを吸入し、免疫システムを高いレベルに保つ」というのが私の狙うところだ。
私の主張・推測も、他の科学者・医学者の主張・推測も、まずは「本当か?」と疑って聞いていただきたい。言うまでもないが、主張・推測等で利益を得そうな連中(日本のマスコミに登場する「専門家」は基本的に皆そういう連中であろう)が言う事は、基本的に嘘・プロパガンダだと考えた方が無難であろう。
気候科学の話からずいぶんと離れて政治・経済からウイルス問題まであちこちに首を突っ込んで書いてきたが、諸々の要因が重なって、今月以降は本当の大混乱期が数年間は続く可能性が高いと考えているので、ウイルスや健康に限らず、現在と将来の生活に影響を持つ全ての重要な分野について個々が正確な情報・理論武装することを強くお薦めする。「自然淘汰」の対象になってしまうリスク軽減に簡単かつ効果的であろう。
アメリカでは既に日本とは比較にならない程の大混乱状態に陥っており、11月3日以降は更に悪化する様にいろいろと手をつくした演出が続けられていると見える。幸い、日本では武器武装はほぼ必要無いであろうから、諸外国居住の一般市民よりもかなり恵まれていると思う。
最後に、この追記部分も他の部分も、メールで拡散するなり、テキストとしてブログに掲載するなり、PDFファイルにしてブログ等からダウンロードできるようにするなり、どんな形を使って拡散していただいても構わないので、自由にしていただければ幸いである。
気候研究にまつわるエピソード
最後に、私の研究生活体験から、気候研究の実態が垣間見えるものをいくつか紹介する。
その1 日本気候研究界の恥晒し
まずは、最も強く印象に残っている、元国立環境研究所理事長、東京大学名誉教授の住明正のマサチューセッツ工科大における驚愕レベルの恥晒しプレゼンテーションについて書いておこう。確か、1992年か1993年だったと思う。
当時、私が大学院生として所属していたマサチューセッツ工科大の地球大気惑星科学部の主催で、アメリカとヨーロッパの主だった気候シミュレーションモデルを開発・運用している大学や研究所の代表らを招いて、それらのモデルの特徴、長所、短所を発表してもらい、マサチューセッツ工科大がそれらのモデルを導入すべきか、或いは独自に気候モデルを開発すべきか、を検討する材料にしよう、という集会があった。
学部内での関心は非常に高く、18階建ての学部専用ビルの9階にあったセミナー室は、教員、研究者、学生で埋まっていた。その集会に唯一アジアから参加していたのは、東京大学の気候研究センターで、住明正という教授が代表を務めていた。その時まで、住の名前を聞いた事はなかったし、その時まで、日本に気候研究グループがある事さえ知らなかった。
*
当日、他グループの代表達は、それぞれのモデルの特徴、長点、欠点等を、様々な資料を見せながら説明していた。そして、東大代表の住の番になり、あの男は何も持たないで部屋の前に出て行った。そこから約10分間にわたり、あの男は前代未聞のプレゼンテーションを敢行した。
まず、奴は発表者用の演台に立つのではなく、その横に発表者が資料や飲み物を置く目的で設置されていたテーブル席に座り込んだ。そして、目を閉じて斜め下を向いて、しかめっ面で黙っていた。それだけでも十分異様であったが、それからが凄まじかった。
しばらく押し黙っていた住は、やっと口を開いたかと思うと、「As Professor Lindzen said, >?<+*{{|{]:^=/`@|¥…….(リンゼン教授が仰ったように、ムニャムニャムニャ・・・・・)」と、上述の私の恩師の一人であるLindzen教授を拝み奉る様に、「リンゼン教授が仰った様に」をハッキリと言った他は、聞き取り不可能かつ意味不明の事を小声で言ったのである。
しかも、それを、しばらくの沈黙をはさんで最後まで延々と繰り返したのであるから、もう、それは想像を絶する異常な醜態であった。結局、奴は最初から最後までずっとテーブル席に座って目を閉じて、Lindzen教授を拝み奉るお経をムニャムニャと唱えただけであった。
この前代未聞の醜態を目の当たりにした参加者達は唖然としていた。当然である。はるか日本からわざわざ東大を代表してやって来た教授が、Lindzen教授に媚びへつらっただけで、意味のある事は一言も発する事無く自分の持ち時間を潰してしまったのである。
*
私は過去に何百というプレゼンテーションを見てきたが、あの様な異常な醜態を見たのは、後にも先にもあの時だけであった。あれは「プレゼンテーション」と呼べる代物ではなかった。しかしながら、奴自身はそれを醜態だとは思っていなかった様である。
何故なら、奴はその醜態を晒した後の休憩時間中に、セミナー室後方の休憩場で飲み物を持ってウロウロして、私が日本人だと知ると、「何年生?何の研究やってるの?」と、偉そうにタメ口で話しかけてきたからである。その神経にも本当に驚いた。
マトモな神経をしていれば、あれだけの醜態を晒した後は、トイレにでも籠って人目を避けるものであろうが、奴は平気だった様だ。私は、最低のカスにタメ口で話しかけられたので大いにムカついたし、それよりも、あんなカスと知り合いだと他の参加者に勘違いされるのが絶対に嫌だったので、ろくに口もきかずにさっさと奴から離れた。
後年に何人もの日本人気候研究者にこのエピソードを話し聞かせたが、彼らの多くが「あぁ、あの人ならやりそうだな」。と、何でも無い事であるかの様に言っていたのにはもっと驚いた。あの様な醜態を多くの参加者の面前で晒すのが「日本の常識」の範疇であるとは思いたくないのだが・・・
*
ちなみに、住が拝み奉ったLindzen教授は超一流の大気科学者で、1980年代から、二酸化炭素増加による危機的温暖化説に対して懐疑的な意見を発し続けてきた。気候シミュレーションモデルの欠陥を指摘し始めたのも彼である。そして、Lindzen教授は歯に絹を着せぬ発言で有名でもあったので、多くの大気・気候学者に恐れられていた。
住は、Lindzen教授に突っ込まれるのが怖かったのであろう。加えて、Lindzen教授の信者を装う事で、他の研究所の科学者達からの辛口コメントを避ける事もできると思ったのではないか。それで、奴は「リンゼン教授が仰った様に」だけをハッキリ言い、他は全てムニャムニャで誤魔化したのではないかと思う。
私はあれを見て、日本の気候研究界はカスと無能の集団であろう、と確信し、絶対に日本の気候研究界とは関わりたくないと思った。おそらく、そこに居た科学者達の多くもそう思ったのではないだろうか。東大の代表教授があんな無能なカスでは、残りはもっとダメなのであろう、と思うのが自然である。実際、後で住の科学研究業績を見てみたが、何一つ光る物が無かった。それどころか、奴の論文を見た限り、奴の気候システムの理解度はかなり低いという印象を強く受けた。
*
あの集会の後、折に触れてマサチューセッツ工科大の教授や研究者や学生の間で、住の醜態が侮蔑の笑い話のネタになったのは言うまでもない。もしかすると日本の科学研究界ではあの様な醜態は醜態と見なされないのかもしれないが、アメリカの科学研究界、特にマサチューセッツ工科大学では、教授だろうが、若手研究者だろうが、学生だろうが、自らの意見を筋立てて堂々と主張し、いかなる相手にもベストを尽くして論戦するのが敬意に値する科学者の姿であると考えられている。
私自身も、可能な限り自らの意見を主張して論戦していた。例えば、大気科学での恩師の一人、Lindzen教授とは、海洋熱塩循環流が気候に及ぼし得る影響については、完全に意見が対立していた。一度その点でLindzen教授と議論になったが、完全に平行線を辿ったので、その後はお互いの意見を尊重して議論になる事は無かった。
同様に、他の教授、研究者、学生とも頻繁に議論を交わしていた。勿論、私だけではない。他の学生や若手研究者も、特に優秀な者は、頻繁に他の科学者と議論を交わしていた。その様に切磋琢磨する事が科学者のあるべき姿とされていたマサチューセッツ工科大における住の「リンゼン教授が仰った様に」経の読経は、最大級の侮蔑に値する醜態であったのだ。その様な最低の無能なカスが日本における温暖化研究の表向きリーダー役を果たしてきたという事実が、日本の気候研究村の実態を物語っていると言えよう。
*
その会議での日本人研究者の尊厳にとって唯一の救いだったのは、カリフォルニア大学ロサンゼルス校を代表して参加しておられた荒川昭夫教授が会場にどっしりと構えておられ、彼の代役で木本昌秀氏が同校の気候シミュレーションモデルについて淡々と普通に説明をされた事であった。
現在の木本氏は東大教授で、一見胡散臭そうな「初老のおっさん」と化してしまわれたが、当時の彼は初々しい若者で、駆け出し研究者ながら、住とは対照的に普通なプレゼンテーションをされた木本氏のおかげで、日本人研究者の面目総崩れという状況にはならずに済んだ。
私は、「自分は一人の人間であって、たまたま日本人である」という認識で、自分が日本人の一人であるという意識を殆ど持たない。それでも、外国に居て、身近で他の日本人が醜態を晒すとイライラしてしまうし、逆に、日本人が素晴らしい事をすれば、なんとなく嬉しく思うのである。
*
その会議には、プリンストン大学・GFDLを代表して、以下に書く眞鍋淑郎教授の代わりにIsaac Held教授が来ておられたのが少々残念であった。私の一番の釣り仲間であり最大の恩師でもあるAlan Plumb教授の友人であったHeld教授とは、気軽に議論したり共同研究したりする関係であったので、彼が来られたのが嫌だったというわけではなく、ただ気候研究業界の日本人代表と言っても過言ではない眞鍋氏の、パワー全開のエネルギッシュなプレゼンテーションを見たかっただけである。
(確か1992年に眞鍋氏の熱演をマサチューセッツ工科大で聞いた事があった。全身を使ったジェスチャーを混ぜながら、早口でカタカナ英語をまくし立てて聴衆を圧倒するという、凄いパフォーマンスであった。カタカナ英語も、使い方によっては効果的だという実証であった)。
ちなみに、私はこの約十年後に、地球シミュレーターというスーパーコンピューターに釣られて海洋研究開発機構で研究する事になったのであるが、実際には、日本の気候研究村にも至極少数ながら優秀な研究者は居るという事を知った。
その2 眞鍋博士のブッチャケ発言
次は、気候シミュレーションの開祖とも言える、プリンストン大学教授・GFDL上席研究員、眞鍋淑郎博士との面白い話を紹介しよう。私が眞鍋氏に初めてお会いしたのは、確か1992年に、氏がマサチューセッツ工科大を訪れて講演された時であったと思う。
上述のEmanuel教授に、「眞鍋さんを他の大学院生数名と共にレストランへ連れて行って夕食会を催してくれないか?」と頼まれて、他の大学院生2名を誘って眞鍋氏をボストンのレストランへお連れした。眞鍋氏はとても話好きで饒舌で、次から次へと様々な話題を持ち出して私達を楽しませてくださった。
その中で、特に印象に残っているのは、氏の「Garbage in, garbage out.(ゴミを突っ込んでゴミを出す)」という発言である。気候シミュレーションモデルを使った学術研究について、4人であれこれ議論していた際に、氏が驚くほど率直に、「気候シミュレーションモデルを使った研究は、ゴミを突っ込んでゴミを出す様なものだ。しかしながら、もしかするとその内の5%くらいは科学的に意義があるのではないか、と希望的に考えている」。という旨の発言をされたのだ。私達大学院生3名は、それを聞いて「うんうん、同意。何と正直な方だ」。という感じで感嘆した。気候シミュレーションの開祖として、殆どの研究業績を気候シミュレーションモデルで上げてこられた眞鍋氏の口から、まさかその様な辛口で現実的な言葉を聞くとは私達は思っていなかったので、正直なところ3人とも良い意味で非常に驚いたのだ。
氏は、自らの研究に信念と情熱を持っておられたが、同時に、冷静に自らの研究成果を客観的に評価しておられたと言える。それこそが科学者のあるべき姿ではなかろうか。ちなみに、氏はその際に、「I believe (私は信じる)と言えば、完全に私が間違っていると証明されない限り、何でも主張できるからいいんだよ!宗教と同じさ!」と、少々茶目っ気を混ぜて語っておられた。
*
私自身は、自らの研究業績全てが100年以上後にも正当性を失う事が無い様に、確固たる内容にしようと常に努めていたが、100%正しい研究成果を出し続けるというのは、実は至難の業なのである。実際、私は一度だけ訂正論文を発表した事がある。
あの時は、幸い計算修正後も結論は殆ど変わらなかったので良かったが、再計算結果を確認するまで少々冷汗をかいた。上述のLindzen教授の様な超一流科学者でさえ、いくつかポカをやっておられる。酷いのになると、理論を裏付ける為の数式の負号間違いに気付かずに論文を発表し、それを論敵に学術誌上で指摘された、というのがあるほどだ。
ましてや気候シミュレーションモデルを使うと、モデルが内包する様々な簡略化仮定や便宜上の設定が、研究成果を全く無意味な物にしてしまう場合が多い。眞鍋氏は、その厳しい現実を認識しておられたし、それを若手研究者に明け透けに語ってくださった。
なかなかできる事ではない。その2年後に、私は氏の気候シミュレーションモデルの欠陥を強く批判する論文を発表し、プリンストン大学を訪れて氏と1時間以上激しく議論するなどしたが、常に氏を真摯な科学者と評価して好感を失う事はなかった。
その3 気候モデルはチューニングして使う物
次は、私が又聞きした話なので、事実かどうかは不明である。が、話してくれた人物の人柄から判断して、十分信用できる話である。私がNASAのジェットプロパルションラボラトリーで研究していた頃、大学院を出たばかりの真面目な台湾人女性が同じオフィスに居た期間があった。彼女とは、様々な会話を交わしていたが、ある日、気候温暖化説の話になった際、よくありそうな話を聞かされた。
当時彼女には、イリノイ大学でMichael Schlesinger教授という気候学者の下で博士号を取得すべく励んでいた、台湾出身の友人が居た。(私はこのSchlesinger教授を直接は知らないが、恩師の一人であるPeter Stoneマサチューセッツ工科大教授が、とある論文に関する公開論争で的外れな主張を続けていたSchlesinger教授を「あの男は愚か者だ」。
とこき下ろしていたのを聞いた事がある)。その友人は、Schlesinger教授の指導で、自らの博士論文テーマとして、IPCCレポートのネタにする気候温暖化に関する研究をしていた。その一環として、気候シミュレーションモデルを使って、二酸化炭素倍増シナリオの実験をしていたそうである。
その友人が悩んで彼女に打ち明けたそうであるが、Schlesinger教授の指導で、教授が望む地球平均気温上昇値が出るまで、シミュレーションモデル内の様々なパラメーター値を変更して実験をやり直しさせられたとの事であった。その彼女の友人は、「こんなのは科学ではないのではないか?」という疑問を抱いて、悩んでいたそうである。
*
実際、気候シミュレーションモデルには多くのパラメーターがあり、それらの値は科学的根拠に基づいて決められるのではなく、モデル利用者の都合で決められる場合がほとんどである。つまり、シミュレーションモデルの振る舞いを「チューニング」する目的で値が決められる。
気候モデルがコンピュータープログラムで表現できない多くの物理・化学プロセスを、ナンチャッテ表現法を使って表している以上、これは仕方がないのである。私自身も様々なパラメーター値を使って気候モデルをチューニングしていた。本来、気候シミュレーションモデルは、そういったモデルの限界を認識した上で、その限界の範囲内で科学的に意義のある研究に使われるべく開発された学術研究用の道具であり、気候変動予測に使われるべき物ではないのだ。
任意に選べるパラメーター値を変更する事で結果がコロコロ変わる様なモデルで、意味のある予測ができるわけがない、という単純な事実を、その真面目な大学院生はよく分かっていたようだ。だからこそ、望む結果が出るまでモデルをチューニングし続けよ、という指導教官の指令に深刻に悩んだのであろう。
その4 温暖化懐疑論は叩かれる
次に、地球温暖化説に懐疑論を唱えると政治的圧力がかかる、という私自身の体験を紹介しよう。温暖化説に懐疑論を唱えて様々な圧力を受けるのは、私の恩師達を含め、他の真面目な科学者らも体験している事なので、全く驚く事ではないのだが、あまり一般市民の耳には入らないのかもしれない。
私が受けた圧力は、私が聞いた他の科学者達の体験と比べると圧力の内に入らない様な些細なものだが、一応参考の為に書いておく。確か、2013年の10月頃であった。産経新聞の長辻象平氏の取材を受けた私は、氏に「今後35年間程、北半球は若干の寒冷化を経験するであろう」。という旨の話をした。
そして氏は、そのインタビュー内容を主旨とした記事を産経新聞紙に掲載された。その記事が出た直後であった。突然、環境省の役人(名前は忘れてしまった)から私に直接電話があり、言葉自体は役人らしく丁寧であったものの、露骨に圧力をかけようとするかの様にインギンで高圧的な調子で「産経新聞の記事に書かれてあった内容は間違いないんでしょうか」。と言ってきた。
通常、空気を読んでも無視する事が多い私だが、この時は実はぶち切れた。本当は怒鳴りたかったが、おそらく会話が録音されているであろうと考え、あくまでも言葉使いは丁寧に、それでも怒りが相手に明確に伝わる調子で、「何が間違いだと思うんですか?え?あの記事のどこが間違いだと思うのかと訊いているんですよ。私が読んだ限り、あの記事は私の話の内容をほぼ正確に反映していますがね」。等の言葉で始め、いかに地球温暖化のバカ騒ぎに科学的根拠が乏しいか、欧米では優秀な科学者達が大声で懐疑論を唱えている、その根拠が弱い仮説を基に政府がバカ騒ぎしてトンデモ税を導入しようと検討しているなど非常にけしからん、等をクドクドとその役人に向かって言い続けた。
その男は、私の勢いに戸惑った様子で、弱気になって長い間大人しく聞いていたが、とうとう最後には、「私どもは専門家ではございませんので、専門家のまとめた意見を基にして政策を立てております。一般的にその分野の権威であると認められているIPCCの報告書を真実であると受け止めて政策を立てております」。といった旨の逃げ口上を言って電話を切ってしまった。
*
私に圧力をかけるどころか、逆に叱責されてしまったその男は、どうせその後で海洋研究開発機構の役員レベルに苦情を言うのだろうと思ったので、もっとあれこれ言ってやりたかったが、確かに、その役人が言う通り、奴らは科学的思考ができない連中で、そうなると、国連や日本政府のお墨付きであるIPCCレポートの内容を鵜呑みにするしかないのであろう、と納得し、それ以上突っ込むのを止めた。
そうなのである。結局、職業科学者集団が、自らの利権を守る為に結束すると、専門知識を持たない政策立案組織を操作するのは簡単なのである。そして、確固たる理論・実験・検証ではなく多数決で「科学的真偽」を決める民主主義的科学研究システムを利用して、研究業界の継続的発展を図るのに都合が良い「科学的事実」を捏造する事もあり得るのだ。
*
ちなみに、その半年後に海洋研究開発機構との5年契約が終わる予定になっていたが、後に私が所属していた研究プログラムのディレクターから「理由は明らかにされなかったが、中村さんの契約更新はダメだ、と研究担当理事から言われた」。という話があった。
環境省が海洋研究開発機構に直接苦情を言ったのかもしれない。周囲に迎合して徒党を組むのが大嫌いな私は、常にそういう結末をある程度覚悟していたので、特に驚きはしなかった。気候科学の主流が詐欺まがいの馬鹿げた茶番を演じてきたのを見て辟易していたので丁度良かったかもしれない。
そう言えば、日本の温暖化説推進派の研究者は、誰一人として、私の懐疑論に直接苦情を言ってきたり、論戦を挑んできたりはしなかった。完全に避けられていた感じがある。おそらく、私の経歴と性格から判断して、私と論戦をするとグチャグチャに叩き潰されてしまうとわかっていたのだろう。
私も、温暖化研究に携わっている人達が必ずしも好き好んでそういう研究をやっているわけではない可能性を認識していたし、問題点を指摘しても全く理解できない様な人達に時間とエネルギーを無駄に使うのも嫌だったので、自分から好戦的に論戦を持ちかける事はしなかった。
*
私が北半球寒冷化で取材を受けたりした原因は、2013年に発表した、グリーンランド海の水温変動とそれに伴う北半球の気候変動に関する論文であったのだが、これについても面白い話がある。この論文は、気候学術誌としては、国際的に最も質的評価が高いと言われてきた Journal of Climate に、三名の匿名科学者による査読を経て掲載された。
原稿についての彼らの評価コメントを読む限り、三名共に有能な科学者であったと思う。この論文掲載に当たり、文部科学省でレクチャー付きの記者会見をやったのだが、その直後に朝日新聞が、私の北半球寒冷化説を記事にして、それを Voice of Russia が様々な言語で世界中に報道したものだから、話が一人歩きし始めてしまった。
遂には、海外の様々なネット情報サイトで、私が氷河期到来を主張している事になってしまっていた。これには驚いた。「北半球の若干の寒冷化」が、どういうわけか、「氷河期到来」に歪曲されてしまったのだ。おそらく、これはよくある手で、私の信用を失墜させるために、あたかも私が氷河期到来などと極端に大袈裟な事を主張しているかの様に書いたものであろう。
*
こういう騒動も関係してか、この論文は、その頃Journal of Climate に掲載された数百の論文の内、直近一年間で Journal of Climate のサイトからダウンロードされた回数が最も多い論文十編のランキングに、通算一年間以上居座り続けた。
10位~8位にランクされていた事が多かったが、二ヶ月間連続で6位にまで浮上していた時もあった。通常、一つの論文があれだけ読まれれば、良いと認められるかダメだとケチをつけられるか、いずれにせよ、かなりの引用回数を期待できるものである。
ところが、非常に面白い事に、3年間にわたって、あの論文は他の研究者達に完全に無視されていた。ケチをつけてくる研究者さえ居ないのである。完全に黙殺であった。最近になって、やっと他研究者の論文で引用されたと思ったら、なんと、ロシア語の論文であった。
その後、そのロシア語の論文の英訳版も出たらしいが、実質的には他研究者に引用されたのは、その一回だけである。実に面白い。おそらく、あの論文はダメ出ししようにもできない内容なので、温暖化説信者達は仕方なく無視しているのであろう。「叩けないなら知らんぷり」というところか。
*
あの論文中で指摘したグリーンランド海周辺の水温に対する非常に重要な大気の反応は、既存の解像度が粗い気候シミュレーションモデルでは全く再現できない。(あの海域で起こる重要な大気現象を考慮すると、解像度を上げるだけではなく、大気の上下運動を診断値として割り出す現行の気候モデルから、上下運動も水平方向の運動と同様に計算できるモデルに変更する必要があろう。
さらに、あの海域の海流は水平方向10km以下のスケールの大気運動に伴う風に強く影響されるという事実がわかっているので、大気と海洋の相互作用もある程度正確に再現するには、飛躍的な解像度向上も必要になると想定される)。つまり、あの論文を認めてしまうと、中長期的気候変動に重要な役割を果たす大気の振る舞いを再現できない気候モデルで気候予測をやってきたという事を認めなくてはならなくなる。
彼らにとって非常に都合が悪いのだ。だから無視しているのではないかと思う。論文がダウンロードされても読まれていないという可能性もあるが、ここまで極端に無視されているのは、やはり何らかの理由があると思う。欠陥だらけの気候シミュレーションモデルを使って科学的意義皆無の論文が無数に発表され、仲の良い同業者同志で引用しあって互恵的に引用回数を増やしている連中がとても多いが、自分達に都合が悪い論文は寄ってたかってケチをつけるか、皆で無視するか、なのである。
これも今の気候研究業界の悲しい現実である。私が気候シミュレーションに使われる海洋モデルの致命的欠陥を指摘した複数の論文も、流体力学理論系の科学者以外は完全に無視している。致命的欠陥がある事は知っていても、対応不可能なので無視しているのである。
しかし、温暖化信者ではない気候研究者達があの論文を無視しているのは少々不思議である。温暖化懐疑派の科学者には、どちらかと言うと理論派が多いのが理由の一つかもしれないが、変に話題になった論文だから関わりたくないのか、つまらない内容だと思われているのか・・・ 全くつまらなくないと思うのだが・・・ う~ん、である。
その 5 NHK出演の舞台裏
最後に、2014年1月8日に私がNHKのニュース番組、NEWSWEBに生出演した際の舞台裏について少々書いておこう。あの出演は、ほんの十分間程ではあったが、過去に数え切れないほど行った講演や音楽生演奏のどれよりも、強いやり甲斐を感じた。
実は、あの出演の1~2週間前に、確か、エジプト辺りで珍しく雪が降った際に、北半球寒冷化に関して電話取材をNEWSWEBスタッフから受けた。その取材に対して、「一度や二度異常な寒気が温帯域や亜熱帯域に南下してきたからと言って、それを北半球寒冷化と直接関連付けるのは間違いである」。
という旨の対応をした。加えて、スタッフから地球温暖化説や、今後の中長期的な気候の変動について質問を受けたが、それに対しては、いつも通り、「温暖化説は未検証の仮説であり科学的根拠は乏しく、人類は気候の中長期的変動をある程度の精度で予測する能力など持ち合わせていない」。
という内容の発言をした。そして、「過去の周期的な変動から、北大西洋周辺を中心に、北半球は今後30~40年間少し寒くなるであろう」。という知見を伝えた。その上で、「温暖化説があたかも検証済みの様な扱いを受けて国際規模で政策に反映され始めているのは、世界規模の炭素税徴収が真の目的ではないか」。という憶測も提供した。
*
あれだけズケズケと放送タブー気味な事を本音で話せば、まずNHKが出演を依頼してくる事は無いであろう、と思っていた。ところが、驚いた事に、1月上旬に北米に大寒波が南下した際に、確か寒波の翌日の午後になって突然NEWSWEBから電話取材を受け、その数時間後、17時過ぎて正式な生出演の依頼を受けた。
生出演なら、自分の発言を編集される心配は無いので、即受諾した。収録であれば、発言を編集されて、自分が言おうとした意味の逆を言った様に放送される可能性が十分あるので出演は拒否するが、生放送であれば、自分の言いたい事をそのまま視聴者に伝える事ができる。
しかも、NEWSWEBスタッフは、私の言いたい事を事前に知っている。「それならば、国民に気候科学の現実をそのまま語ってやろう」。という気持ちで依頼を受けた。ところが、実際に打ち合わせが始まってみると、主なネタの北米大寒波と北半球寒冷化について簡単に語るだけでも時間が足らないほどで、温暖化説の真相について語る余裕など全く無いというのがわかった。しかしながら、本物の気候専門科学者が中期的な北半球寒冷化を語る事で、間接的に温暖化騒ぎに一石を投じる事になるであろうから、それはそれでよしとした。
*
さて、電話とメールを使って、放送で使う図の作成や打ち合わせをしたのだが、一般視聴者向けに解り易い物を作らなければならないので、かなり手間取ってしまった。そして、確か20時を過ぎて、やっと実際に渋谷のNHKへ出向く事になり、雨の中を慌てて電車を乗り継いで渋谷に着いた。
NHKの入り口ロビーで海洋研究開発機構の広報課課長と合流し、NEWSWEBスタッフから出演に関してザックリと説明を受けた。その際、広報課課長は「地球温暖化については触れない様にお願いいたします」。とNEWSWEBスタッフに釘を刺していた。
私は「ああ、そういう事か」。と思ったが、まあ、間接的に温暖化のバカ騒ぎに水をかける事にはなるので納得した。その後、私だけが司会進行役の橋本奈穂子アナウンサーと濱野智史氏に会って、放送で使う大まかな流れを確認し、あとは質問・応答という形で放送内容に関連した様々な話をした。
その時の説明で、放送は視聴者からリアルタイムで届く質問やコメントを橋本さんが適宜拾って、それを放送に反映していくという、インターアクティヴな物である事を知った。つまり、大まかな流れは決まっているが、詳細はインプロヴァイズするという事であった。
それを知った私は本当にウキウキした。私は高校時代にジャズにはまり、数年間の休止期間が何度かあったものの、2003年まではずっとジャズ演奏を続けていたからだ。一度は職業科学者を辞めて音楽演奏家に転身しようと、約2年間、主に音楽演奏で生計を立てていた時期もあった。
ジャズ演奏によくある形は、大まかな流れを決めて、詳細はインプロヴァイズするという物であり、NEWSWEBの放送形式と似ているのだ。こうなると、私にとっては、NEWSWEB生出演というのが、少なくとも数万人、もしかすると何十万人もの視聴者を観客席に迎えたジャズの生演奏かの様に思えてきた。
*
その後、控え室でしばらく待機したが、意外に早く出番がやってきた。言いたい事は山ほどあったが、橋本さんを始め、NEWSWEBスタッフに迷惑はかけられないので、ある程度抑え目に行こうと考えた。私のセグメントは、予定通り北米寒波の話題で始まり、自然な流れで北半球寒冷化に関する話になった。
(後で録画DVDを頂いて見たが、寒冷化の解説自体はイマイチだった。残念)。「こんなもんで終わりかな」と思い始めたところ、橋本さんが、「長期的には地球の気候はどうなるのか?」という質問を投げかけてきた。
これは、実は、橋本さんが私との打ち合わせ中にも持ち出された質問で、私は当然、橋本さんに打ち合わせ中に差し上げた「そんなのはわかりっこない。予測モデルは深刻な欠陥だらけだ」。という旨の回答を、モデル批判のトーンをやや抑え気味にして簡単に繰り返した。これは本当に素晴らしい質問だった。これによって、「温暖化には触れない」という「口かせ」を外さないまま、温暖化説の暴走に若干の冷水を浴びせる事ができたのだ。
実際、私の知る限り、その疑問は、思考能力を失っていない一般市民の間には根強い。橋本さん自身も、その疑問を持っておられた様子だった。橋本さんは、あの質問を何気なく私に振ってこられた様子であったが、実は、相当勇気を出して振ってこられたのではないかと思う。
本物の気候専門家があの事実を言うのは、今の日本では限り無く放送タブーに近いであろう。私は、橋本さんに大変感謝している。あの橋本さんの質問は、当時のNEWSWEBディレクターの意向も反映されていたのかもしれない。マスコミ関係者にも一般市民にも、思考能力を失っていない人達は居るのである。
私に事実を広く発信する機会をくださった、当時のNEWSWEBディレクターさん達のジャーナリスト魂にも大変感謝している。私にとって、あの出演は橋本さんと濱野さんというパートナーにサポートされた人生最高のジャムセッションであった。
*
ちなみに、この出演を視ておられた海洋研究開発機構の当時の理事長、平朝彦博士は、大変好感を持たれた様子で、直後に、「今回の北米寒波について、海洋研究開発機構のホームページに載せるコラムを書いて欲しい」。と要請してこられた。
嬉しく思った私は、かなり力を入れてコラムを日本語と英語で書いたのであるが、そのコラム中で、「今回の寒波は温暖化が原因の一部であると主張する向きも少数ながらあるが、それはナンセンスである」。とも書き、その理由も書き添えた。(この時に書いたコラムは、この改訂版を書いている2019年2月時点でも海洋研究開発機構のサイトに掲載されており、「中村元隆 JAMSTEC 北米 寒波」で検索すると出て来る)。平氏は、実は国際的にも評価が高い優秀な固体地球科学者であるという話を、日本内外の流体力学系の科学者数名から聞いた事がある。
理論に強く、頭が切れる科学者の多くは、実は温暖化説の暴走に辟易しているのではないか、と常々思ってきた。平氏がコラム記事を書いて欲しいと要請してこられたのは、そういう気持ちの現われだったのではないだろうか。
日本国民は殆ど聞かされていないようであるが、理論に強い海外の大気・海洋科学者で、温暖化説に対して私と同様な意見を持つ人達は多い。私が直接知っている優秀な大気・海洋科学者はほぼ全て、温暖化説に懐疑的な意見を持っていた。日本にも、高い思考能力を持つ大気・海洋科学者は少数ながら存在する。日本の大気・海洋研究界で、懐疑論が全く表に聞こえて来ないのは、やはり文化の違いが根底にあるのかもしれない。
*
そう言えば、私を高く評価して日本の研究界へ引き込んでくださった東京大学の山形俊男教授は、当時、周囲に私を紹介する際に、やたらと私の事を「さすらいのガンマン」と呼んでおられた。
当時は、何故、氏が私を「さすらいのガンマン」と呼んでおられたのか、考えもしなかったが、私がどの著名・有力な科学者の傘下にも入らず、気の向くままに研究所から研究所へと渡り歩き、ハードコア科学に拘って気候シミュレーションモデルの欠陥に関係する論文を何編も発表していた事が理由だったのかもしれない。
山形氏は温暖化説の暴走を批判された事はないが、理論にも非常に強い、世界でもトップクラスの優秀な海洋科学者であるので、気候モデルの実態を知っておられるはずだ。実際、氏は相当の野心家であるにもかかわらず、自らが指揮したり深く関わったりする研究では、温暖化研究から遠く距離を保っておられた。
私はそれに少なからず好感を持っていた。本当は、彼は日本における地球温暖化説の暴走にブレーキをかけたかったのかもしれない。もしかすると、彼は私をヒットマンとして日本の気候研究界に迎え入れたのであろうか?面白い可能性である。
結びの言葉
さて、この手記の超短縮版が2017年12月25日に、月刊誌「正論」に出版され、そのしばらく後に、週刊プレイボーイの記事にも私のインタビュー内容が反映された短い記事が掲載されたのであるが、現時点(英語記述を加えた改訂版を書いている2019年10月)でも、日本気候研究村からの反応は全く無い。
雑誌記事と違い、この電子書籍は長期間に渡って簡単に入手可能になる。もしも、この手記が多くの国民に読まれて話題になると、日本の温暖化研究村と温暖化説推進の政府組織はどういう反応をするであろうか?斬り合いに喩えると、この手記は、連中に深手の傷を与える一太刀となるかもしれないが、致命傷にはならないであろう。
国連や国際金融機関をバックにした洗脳活動は想像以上に強力である。始めに書いておいた通り、私としては、これを科学者としての最後の仕事とするつもりなので(科学者としての義務を果たしたいが、他にもやりたい事があるので、もう面倒くさくなってきた)、彼らは静かに傷が癒えるのを待つ可能性が高いであろう。
私としては、連中が反撃してくる方が生活に刺激ができて面白いが、連中は政治的立ち回りの面では非常に賢いので、下手に反撃して私から更なる攻撃を受けて傷を増やすよりは、この手記を無視して、ひたすら静かに傷が癒えるのを待つという選択肢を取るのではないかと思う。
結局、この手記は、私がずっと感じてきた科学者としての義務感を満足させるだけに終わってしまう可能性も大いにあるのではないかとも思う。が、仮に自己満足であっても、やはり私が書かなければ日本語でこういう情報が発信される事は無いであろうと考えると、書かないよりはマシであろう。
これを読んだ方々には、できるだけ、地球温暖化説に疑問を持ち続け、政府、マスコミ、そして、気候研究組織・気候研究者に疑問をぶつけ続けて頂きたいと思う。[2019年12月追記:9月に部分的に英語で書き加えたところ、アメリカ、カナダ、オーストラリアを中心に、9月と10月に英語圏諸国とヨーロッパの一部で自分でもギョッとする程大きな反響があり、ネット上の記事だけでなく、ウォールストリートジャーナルや地方新聞のコラム等でも取り上げられたと聞いた。
気候問題には無関心のアメリカの古い友人達から数年ぶりに突然メールが入って、「凄く話題になっていたよ。ほとんどは好意的な反響みたい」。と聞かされて本当に驚いた。アマゾンからのレポートによると、本書の読者のほとんどは海外の人達で、せっかく日本国民に読んでもらおうと書いたのに、と、少々複雑な気持ちだ。
海外の一般市民やメディアからあれだけの反応があれば、屁理屈をこねるのが上手い欧米の研究者達から何らかの反論・口撃があるかと思ったのだが、今のところ入って来たのは個人的なサポートのメールだけで、少々拍子抜けしている。考えてみれば、北米の気候研究者達の方が日本の研究者達よりも私の事をよく知っているだろうから、迂闊に口撃する事は避けるのは自然かもしれない。
しかしながら、こうなると不気味なのは本当に権力を持った連中の動きで、これ以上海外で反響が続く様なら、私の信用を失墜させようという動きが出て来るのではないかと大いに警戒している。私の様な小物でも、少なくとも数百兆円規模の金と権力が絡んだ計画遂行に障害になるなら除去しようとするであろう。
ハッカーを使って、私の知らない間に携帯やパソコンに児童ポルノ等を埋め込んだり、或いは、怪しげな海外の銀行口座から私の銀行口座に多額な送金をして資金洗浄の証拠を捏造したり、とういのは実に簡単な事だ。そういった手法が気候科学者に適用された例は聞いた事が無いが、外国で他の分野の人達の社会的抹殺手段として使われたという話は耳にしている。
日本の一般市民には、私の懸念が大袈裟だと思われる方が多いだろうが、実は、当初私がこの手記をアマゾンで売り出すという話を聞いたアメリカの某大手銀行の中堅管理職であった友人が、私の身の安全を心配してくれた。
その時、その友人には「日本語で出すだけだから大丈夫」と言っておいたが、英語でこれだけ広まってしまうと、リスクを軽視する事はできない。
残念ながら、私達はそういう世の中に住んでいるのだ。露骨な口封じの殺人や変死がちょくちょく起こるアメリカでは当たり前の現実なのだが、比較的平和な日本に住んできた人達には、こういう話がピンと来ないかもしれない。
気候が専門でなければ英語でどれだけ「温暖化詐欺」と騒いでも無視してもらえるだろうが、私の様に気候科学の理論、データ、モデルに精通していると、無視してはもらえない可能性がある。取り越し苦労だと良いのだが、私には後ろ盾になる強力なサポートグループが無いので、こうやって前もってここに書いておく事で、少しでも予防線になればと思ってこれを追記している。
*
最後に、私の大学院教育と自由な科学研究活動の資金を直接的・間接的に拠出していただいた、アメリカと日本の納税者の方々に対して感謝の意を表したい。
備忘録:大気海洋研究界の釣りバカ達
マサチューセッツ工科大での大学院生活は、最初の二年間こそ授業と研究で無茶苦茶大変だったが、二年目の春に、無事、博士号資格試験を通過した後の3年間は研究、釣り、音楽を好きに楽しめた幸せな期間であった。それと言うのも、指導教官であったAlan Plumb教授が、私と同じくフライフィッシングが大好きだったからだ。
毎年、半数程度が落とされて学部から追放される恐ろしい博士号資格試験の所為でストレスを溜め込んでいた私が、資格試験通過後、ニューハンプシャーの渓流に入り浸り始めたのを他の生徒から聞いたPlumb教授が、ある日、私に「フライフィッシングに行ってるんだって?どこ辺りに行くんだい?」という感じで話しかけてきた。
(ここからは普通にAlanと呼ぼう)。実はAlanも私と同じ位フライフィッシングが大好きだったのだ。この時からAlanと私は「指導教官と生徒」ではなく、「釣りバカコンビ」となってしまった。Alanの自由時間が多い夏季の二人の典型的な会話は、「明日は天気が良さそうだね」。
「行く?」「何時?」「3時は?」「OK」という様なパターンであった。二人で一緒に行く事もあれば、別々に行く事もあった。独りで釣行した後は、地図を見せながら情報交換するのが常となった。その結果、私達は顔が合えば釣りの話ばかりして、科学の話は滅多にしなくなってしまった。
お互いに、科学の話よりも釣りの話の方がずっと楽しいのであるから、これは仕方なかった。私達が交わした会話の99%以上が釣りに関するものであったと自信を持って断言できる。二人の間に、何となく科学の話をしたくないという雰囲気ができあがってしまったのだ。
その所為で、指導教官であったAlanとの共著論文は1994年に掲載された一遍だけになってしまったが、おかげで、私は堂々と5月~10月は平均で週3日程度はニューハンプシャーやヴァーモントの渓流や湖で釣りまくっていた。(「そんなのでよく博士号を4年半で取得できたな」と思われるかもしれないが、マサチューセッツ以北の11月~4月は、釣りなど頭に思い浮かばないほど寒いので、毎日研究と音楽に没頭していたのだ)。
1996年の夏に、一ヶ月間だけJohn Marshall教授との研究を進める為にジョージア工科大からマサチューセッツ工科大に戻った際も、初日にニューハンプシャーの釣り仲間から、「アトランティックサーモンの群れを見つけたからすぐに来い!」という連絡を受け、昼頃にJohnと軽く打ち合わせをした直後に私はニューハンプシャーへ向かい、3時間後にはニューハンプシャーの美しい川辺に立ち、生まれて初めてのアトランティックサーモンを数匹釣り上げて舞い上がっていた。
そうそう、1996年には釣り仲間の一人が「Moto’s Minnow」と名づけてくれた独創的なオリジナルのフライを創って大爆釣を繰り返し、彼の勧めでOrvisという大手のフライフィッシング用品会社に、最新ロッド一本と交換でそのデザインの幾つかを提供した事もあった。そのフライは「Moto’s Minnow」の名前で1998年にOrvisが売り出したのだが大ヒットとなり、最初の年は約1万本売れて、その後も安定して売れ行きが好調だそうだ。
*
遊びまくっていても研究活動をビシバシやる、という評判が定着していたおかげで、私は釣りに行き放題であった。Alanも本当はそうしたかったのであろうが、彼は講義、学生指導、小学生の子供二人の世話で大変忙しく、気の向くままに釣りに行く私が羨ましかった様だった。ただ、その後、私は彼の凄さを知る事となった。が、その話は後回しにして、先に他の釣り仲間達とのエピソードを書いておこう。
*
どういう訳か、当時、マサチューセッツ工科大の地球大気惑星科学部と合同プログラムを持っていたウッズホール研究所には、フライフィッシング狂が数名集っていた。その一人、研究でお世話になったLarry Pratt博士は、一流の理論派海洋物理学者で、確か当時は上席研究員であったが、自他共に認める海のフライフィッシング狂であり、一度、彼のボートに乗せてもらってスマガツオ2匹とストライプトバス1匹を釣った事がある。
それが私の初めての海のフライフィッシングであった。彼の巧みなボート操作と、的確な釣り方指導のおかげで、普通はそう簡単には釣れないスマガツオを半日で2匹も釣る事ができた。彼はアメリカ人には珍しく自分の車は持っていなかったが(奥さんは持っていた)、その代わりに立派なボートを持っていた。
彼は地元ケイプコッド周辺のストライプトバス釣りが熱い5月~6月は、絶対に出張しないという話であった。そうそう、彼から、クリスマス島のラグーンだか周辺だかの海流を計測する研究計画を立てて予算をつけてもらってクリスマス島へ観測船で行き、行ったらボーンフィッシュがうじゃうじゃ居たので釣りまくって腕が痛くなった、という話も聞いた記憶がある。
ちなみに、クリスマス島はボーンフィッシュのフライフィッシングで世界的に有名な島であるが、釣りガイドと釣りロッジは多いものの、釣具店は無く、道具のレンタルも無い。ボーンフィッシュに効果的なフライは、スマガツオやストライプトバスに効くフライとは全く違うのだが、Larryはたまたまそういうフライを沢山持ち合わせていたようだ。
*
同級生だったが、海洋物理専門だったので2年目の夏からウッズホール研究所に滞在して研究を進めていた、Joeという友人が居た。彼は生粋のアメリカ人であるが、今ではノルウェーの大学で教授として活躍している。彼もとんでもない釣りバカであった。
確か1995年の夏だったと思う。Lindzen教授のおかげで、その年の「Conference on waves and stability (波動と安定性に関する学会)」は、モンタナ州のビッグスカイというスキーリゾート地で行われた。
鱒のフライフィッシングのメッカと言っても過言ではない地域だ。非常に不便な場所なので、殆どの参加者には不評だったが、当然、私は参加した。Joeも大いに張り切って参加した。その時、私はコロラド州ボルダーにある研究所を先に訪れてからモンタナに飛んだ事もあって、自前の釣り道具は持参しなかったが、Joeは当然の様に自前の道具を持参していた。
私は、前もってレンタカーを空港でピックアップする予約をしておいたので、同学部のJoeとIgorとMikeの三名と待ち合わせ、空港から1時間ほどのビッグスカイへと向かった。ちなみに、空港がある町の名前が日本人にとってはなかなか面白い。
ボウズマンという、冗談の様な名前だった。ここでJoeはちょっとした失態をやらかした。ボウズマン空港のレンタカー駐車場の金網に、持参した釣竿を立てかけて置き忘れてしまったのだ。ただ、これに気付いたのはホテルに着いてからだった。
*
さて、ビッグスカイへの車中では、ずっと横を流れていたギャラティン川という、アメリカのフライフィッシャー達の憧れの川を眺めながら、釣りの話や学校の話で盛り上がったが、Joeは、同学部のノルウェー人大学院生の奥さんが臨月で、いつ第一子が生まれても不思議ではない状態であったので、ホテルに到着次第、奥さんに電話してホテルの名前と連絡先を知らせなければいけない、と言っていた。
(当時は携帯電話などという便利な物は普及していなかった)。ところが、ホテルに到着すると、Joeは釣竿を空港に置き忘れてしまった事に気付き、大慌てになってしまった。すぐにホテルから空港に電話して探してもらったが、見つからない。
そして、レンタカー駐車場かもしれない、と気付いてレンタカー事務所に電話し、駐車場を探してもらったところ、無事に見つかった。翌朝早く、釣りに行く前に回収に行くので保管しておいてもらう事になり、これにて一件落着であった。この時には既に辺りが薄暗くなっていたので、モンタナの牛肉やバイソンの肉やエルクの肉を料理して出すレストランへ出向いて4人で夕食を楽しんだ。
「Roadkill Cafe」という面白い名前のレストランだった。(「Roadkill」とは、交通事故で死んで、路上にころがっている動物の死体の事)。この間も、翌日の釣りの予定や珍しい肉料理等、話がいろいろと盛り上がり、Joeは異国の地で独り研究に励んでいた臨月の奥さんの事を完璧に忘れていた。
アメリカの医療システムでは、出産に際しては産気づいてから病院へ向かい、出産が終われば一泊か二泊の後はすぐに退院させられる。家族が近くに居ないと、臨月の妊婦はかなり心細いのだ。本来なら、あの状況でJoeはモンタナでの学会には行くべきではなかったんじゃないかと思うのだが・・・
*
翌日、日曜日の早朝、私、Joe、そして急遽釣りに参加する事にしたIgorの三名は、何故か全館停電してしまったホテルの部屋で目覚め、「このホテルはどうなってんだ?大丈夫かよ」。みたいな事をブツブツ言いながら釣りの支度をして、私の運転でボウズマン空港へと向かった。
車中は当然、釣りの話で大いに盛り上がっていた。途中、地元のドーナツ店で朝食を買って、それを頬張りながら空港へ行き、Joeの竿を回収してから、今度はギャラティン川近くのフライフィッシング用品店へ一時間ほど運転して行き、私とIgorはレンタルの釣具を調達した。
それから私達は、2時間ほど運転して有名なマジソン川へ行き、雨が降ったり止んだりする中を数時間釣り歩いた。川は雪解け水のせいで水量が多くて釣りにくい状態で、私は50cmを軽く超える虹鱒を2回掛けたのだが、近くに寄せた際にフライが魚の口から外れて逃げられてしまった。
それでも、やっとの事で35cmほどのブラウントラウトを釣り上げる事ができた。JoeとIgorは大苦戦で、全く当たりが無かった。午後を過ぎて雪解け水が増え、一層釣りにくい状況になってしまったので、近くのマジソン湖に移動して、そこで夕方まで釣る事にした。
が、全く反応が無い。夕方近くなったので、腹も減った事だから、どこかで夕食を食べてホテルへ戻ろうという話になった。そして三人で車に乗り込み、湖の横を通っていると、湖面に、鱒が捕食してできる様な波紋ができているのがいくつか見えた。
車を停めて湖面を凝視して、「もうちょっと釣って行こうか」とも話したが、まだ一週間のチャンスがあるから、その日は終わりにしよう、という意見の一致を見た。そして、再度車に乗り込み、しばらく走らせた時であった。Joeが突然、とんでもない事をやらかしたかの様な声で「Oh my God…」と言ったのだ。
見ると、顔が青ざめている感じであった。私が、「どうした?」と訊くと、Joeは呆然とした様子で「シシリアに電話するのを忘れた」。と言ったのだ。「今朝電話したのかと思ったぞ」。と私が言うと、Joeは「完全に忘れていた」。と言った。何という男だろう。奥さんや家族を大事にする傾向が強いアメリカ人のJoeが、「釣りバカ日誌」のハマちゃんでさえやらかしそうにない事をやらかしてしまったのだ。まったく、とんでもない男である。
*
さあ、それからが大変であった。既に午後6時は軽く過ぎていたと思う。つまり、Joeの奥さんが居るマサチューセッツでは午後8時を過ぎていた。ホテルまで1時間半はかかる。ホテルへ向かいながら公衆電話を探そうという事になり、鹿やエルクを警戒しながら、一応建前では制限速度が時速55マイル(約90km)の一般道路を、時速80マイル~90マイル(約130km~145km)で走った。
日産のサニーだったが、なかなか調子が良かった。ところが、ただでさえド田舎のモンタナでも、あの辺りは特に住人が少ない地域で、たまにポツンと民家がある程度で、公衆電話などなかなか見つからない。やっと一つ見つけて車を停めたが、なんと壊れていた。また、かなり車を走らせて、やっと二つ目を見つけて車を停めた。が、なんと、それも壊れていた。
*
「なんちゅー所だ、ここは。信じられん」。みたいな事を三人で言いながら、どんどん車を走らせたが、三つ目が一向に見つからない。そして、道路が長い直線の下り坂になっている箇所に差し掛かった時、坂の最下部辺りの道路脇に何やら青っぽい車が停まっているのが見えた。
まさか、数分に一度車が通るか通らないか、という程交通量が少ない場所で警察がスピードチェックをしているとは思わなかったが、一応警戒してスピードを落として近づいたところ、なんと、それは本当にパトカーであった。案の定、私達が通過すると、すぐに青いランプを点滅させながら追っかけて来た。
私は、「あーあ、5ドルか」。と思いながら車を道路脇に停めた。(当時のモンタナでは、スピード違反で捕まると、現場で警官に5ドル払って「はい、さようなら」という、嘘の様な本当の法律が使われていた)。私達の車にやって来た警官は、「君は83マイル(約135km)で走っていた。
30マイル近くオーバーだ」。と言って、私に運転免許証と車の登録証を提出する様に指示してきた。そして、私の運転免許証をパトカーに持ち帰って何やら書いている様子だった。やがて戻って来た警官は、私に封筒型の違反切符を渡し、「期限内にこれを払え。
クレジットカードも使える。夕方は動物が出て来るから、もうちょっとゆっくり走れよ」。と言って引き上げて行ったのだ。その切符を見て私達は驚いた。モンタナ州警察ではなく、イエローストーン国立公園の公園警備隊発行となっており、罰金額は85ドルだったのだ。
後で地元の人達に聞いたところ、確かにその区間だけ、イエローストーン公園の端を通っており、歳入増加を狙う公園警備隊が頻繁にスピードチェックをしているとの事であった。地元の人達は知っているので気をつけるが、よそ者は大抵捕まるらしい。
つまり観光客狙いのスピードチェックという事だ。道理でクレジットカードで罰金を支払える様になっていたわけだ。その件でかなりテンションが下がってしまったが、それでも、早く公衆電話を見つけないといけないので、私は適度なスピードで運転を再開した。
*
あと30分程度でホテルに着くという時に、やっと営業中のリゾートロッジを見つけて駐車場に入ると、駐車場脇に公衆電話があるのが見えた。三つ目にして、やっと正常に機能している公衆電話であった。Joeは恐る恐る自宅に電話をかけ、私とIgorは数メートル離れて様子を窺っていた。
奥さんは既に出産で入院していた可能性もあったのだが、幸い、すぐに電話に出た様子で、Joeは必死になって謝り、前日ホテルに着いた時は遅くなっていて(微妙・・・)、釣竿を空港に置き忘れてパニックになって(本当)、その日は朝起きたらホテル内が停電していてパニックになって(微妙・・・)、空港まで竿を取りに行くので時間がかかって(言い訳になってないような・・・)、釣りに行ったら釣り場近辺に使える公衆電話が全く無くて(釣りが終わるまで忘れていた・・・)、等の理由を挙げて奥さんの理解を求めていた。
私とIgorは声を殺してずっと爆笑していた。今でもあの時のJoeの様子が脳裏に焼きついていて、思い出す度に笑いが止まらなくなる。電話が終わって、Joeに奥さんの反応を訊いてみると、奥さんは「Oh Joe! Oh Joe!」と泣きそうな声で繰り返していたそうだ。
かわいそうに。まあ、しかし、今でもJoeは奥さんと子供二人に恵まれて仲良く暮らしているそうなので、あの件以降はとんでもない事はやらかしていないのだろう。無事、重要案件を片付けた私達は、そのロッジのレストランで美味しい野生動物肉料理を食べた。85ドルのスピード違反切符に同情してくれたJoeとIgorは、私の夕食代を払ってくれた。
*
さて、このモンタナでの学会に絡んで、もっといろいろと面白い出来事があったのだが、その内の一つだけ書いておこう。その週の火曜日、学会二日目の夜であった。夕食後、会場となっていたホテルのバーに顔を出したところ、馴染みの顔が大勢集っており、Joeを含むその内の数人が、「明日は主に大気科学分野の発表だから釣りに行こう」。
(彼らは海洋科学専門)、という計画を話し合っていた。当然、私も誘われた。が、翌日の午前の第一セッションに私自身の発表予定があり、さらに、一日中、私の研究に深く関連する発表がいくつかポツポツと予定されていたので、彼らの誘いを断った。
しかし、彼らはしつこく、「お前の発表は朝一なんだからいいじゃないか。行こうぜ。よし、Moto(私は仲間内ではそう呼ばれていた)は明日俺達と一緒に釣りに行く!」という感じで誘ってきた。が、それでも私は「いや、俺は明日こそは絶対に一日中ここに居る。
釣りには行かない。お前ら行ってくれば?」という感じで断り続けた。と言うのも、前日、月曜日は、午後からちょっとした用事があって車で一時間半ほどのリヴィングストンという町へ出かけたのだが、夕方からの降雪を伴う嵐で、学会会場に戻ったのは火曜日の午後だったからだ。
夜も遅くなり、私はそろそろ明朝の発表の準備をしなければ、と席を立ったのだが、その時、Joeら数名が、「よし、賭けをしよう。明日、Motoが発表後に俺達と釣りに行く、っていう方に賭ける。どうだ?」などと、フトドキな事を言い出した。
ほぼ全員が、私が釣りに行く方に賭けていた様な気がする。そしてJoeが、「お前の発表を聞きに行くから、そのすぐ後に釣りに行こうな。明日はファイヤーホール川を釣る予定だぞ。今いいらしいぞ!」などと言っていたので、私は再度「い~や、明日は絶対釣りには行かん。じゃあ明日、会場でな」。と応えて自分の部屋へ引き上げた。
*
翌朝、第一セッションで発表予定の私は最前列に座り、自分の番を待っていた。確か発表は3番目くらいではなかったかと思う。そして自分の番になり、演台に立った私は、襟元にマイクを付け、広い会場を見渡した。すると、数百人の聴衆の後方にJoe達の姿を発見した。
遠かったのでハッキリとは見えなかったが、何やらニヤニヤしている様子だった。私はいつもの様に淡々と発表を始めた。そして、こう言ったのだ。「今日は発表時間が12分程度で限られていますので、結果の詳細を話す事はできません。大事な部分だけに焦点を当てて話します。
もし詳細を知りたければ、発表の後で質問に来てもいいですよ、・・・今日は釣りに行かないので」。これを聞いた聴衆の多くが爆笑していた。私としては「今日は釣りに行かないので」はフトドキな賭けをしていたJoe達へ向けた意思表示のつもりだったのであるが、どういう訳かジョークだと思われたらしく、事情を知らないはずの他の聴衆の多くも爆笑していた。
研究仲間であったイギリス人の若手海洋学者(確かDavidという名前だったと思う)などは、息も苦しそうに腹を抱えて笑っていた。私はそれを無視して平然と発表を始め、ビシバシとポイントを押さえて話し、時間内にピッタリ終わらせて、いくつかの質問にも的確に対応した。
そして、次の発表者にマイクを渡しながらJoe達を見ると、彼らは私の方を見てニコニコしながら手を振って会場から出て行ってしまった。外は小雪が舞っている状態で、かなり寒かったので、あまり羨ましいとは思わなかったのを覚えている。
その後の休憩時間中には、知らない人を含め、何人にも話しかけられた。中には、研究内容の詳細について質問してきた人も居た。皆、好意的であった。その内の一人などは、「ジョークで笑わせて皆の目を覚まさせておいてから素晴らしいプレゼンテーションをするなんて、やるね!」という感じのコメントをくれた。
ジョークじゃなかったのだが・・・ 初日から真面目に発表の一つ一つを採点して、1から10までの数字で発表の良し悪しを発表予定表に書き込んでいたDavidが採点表を見せてくれたが、私の発表には数字ではなく「!」という評価が書かれていた。
その夜、バーに集った馴染みの顔ぶれが、この話で盛り上がったのは言うまでもない。期せずして、この学会での私のプレゼンテーションは、私の釣りバカぶりを北米の大気海洋研究界に広く知らしめる事となり、その後一年以上にわたって面白話のネタにされてしまった。まあ、私にとって悪影響は無かった様なので、良しとしよう。ちなみに、小雪の舞う寒い中を釣りに出かけたおバカさん達は、意外にも、そこそこの釣果を上げて意気揚々と帰って来たと記憶している。
*
さて、最後にAlanの話で締めくくろう。最後にふさわしい話である。Alanは、あのマサチューセッツ工科大が、「是非とも来て欲しい!」と懇願して教授に迎えた程の超一流の流体力学系大気科学者である。しかも、彼は素朴な人柄で、真面目で、人当たりも良く、良き父親でもあった。
同じ超一流でも、傍若無人な振る舞いが目立ったLindzen教授とは対照的であった。Alanは、当時、フルタイムで働いていた奥さんと二人の小学生と一緒に、大学から車で1時間ほど北の、ニューハンプシャーとの州境近くに暮らしていた。
奥さんよりAlanの方が仕事時間の自由度が高かったので、彼は頻繁に自宅で仕事をして、子供達の監督をしていた。それでも、週に2~3回は大学にやって来て、講義をしたり、学生や若手研究者達の指導をし、また、ちょくちょく他の研究所や大学に出張で出かけたり、と多忙な生活をしていた。それだけ忙しい中を、彼はなんとか時間をやりくりして、時々釣りに出かけていた。特に6月~8月は講義が無いので、Alanもちょくちょく釣りに行っていた。
*
確か1995年であった。9月に入ってAlanは次第に忙しくなり、10月になると、釣りに行く時間など全く無い程の忙しさであった。私はと言うと、ニューハンプシャーの多くの渓流や池が10月15日で釣りシーズン終了であったので、9月~10月はラストスパートで頻繁に釣りに出かけていた。
その年は、夏に、Alanが地元の知る人ぞ知るホールポンドというブルックトラウトという美しい鱒がうじゃうじゃ居る小さめの湖を見つけてきて、二人で何度かAlanのカヌーを持ち込んで釣った事がある。私一人の時は、ウェイダーと呼ばれる胸の辺りまでの長さの長靴を履いて、湖に立ち込んで釣っていた。
9月もなかなかの釣れ具合であったが、10月に入ってから一層良くなった。紅葉で有名なホワイトマウンテンズの奥にあるホールポンドは9月中旬から黄色、赤、紫等の鮮やかな色がつき始め、10月にはピークとなる。それもあって、この年は10月に入ると、私は三日と空けずにホールポンドに通った。
そして、私という悪い奴は、釣行後は毎回の様に大学へ行って、その前年頃から大学内のコンピューター間で使え始めた電子メールで、釣果報告をAlanへ送ったのだった。自宅で仕事をする事が多いAlanは、自宅のパソコンを大学のコンピューターに繋いでもらっていたので、自宅でも私の報告を読む事ができた。
おまけに、一度か二度は、Alanを学部のコンピューター室で見かけたので、いかにホールポンドでよく釣れているか、どういうフライに反応が良いか、絶対にシーズン終了までに一度は行くべきか、等を熱く語って聞かせたのだった。Alanは溜息をつきながら、「あ~行きたい。
でも火曜と木曜は講義をしなければいけないし、嫁さんが忙しくて、なかなか自分が丸一日家を空けられないし、他にもやらなくてはならん事が山積しているし。全く行けそうにない。う~ん、困った」。などと言って、寂しそうな悔しそうな顔をしていた。
そんなAlanに釣果報告を送り続けた私は、本当に悪い奴だったのだ。ところが、10月15日が近づいたある夜、私が学部のコンピューター室で仕事をしていると、突然「ピーン」と音がして、電子メールが届いたという知らせが来た。「何だ?」と思ってメールを開けてみると、Alanからだった。
短いメールだったが、「今日ホールポンドへ行った。釣れたよ!良かった!」という様な内容で、嬉しそうな様子を察し取れた。私は思わずニコニコしてしまい、「それは良かった!」と返信した。が、何かちょっと腑に落ちない感じがした。ちなみに、私は勿論ホールポンドのシーズン最終日は、朝から夕暮れまでホールポンドで釣りまくったのであった。
*
それから数日後、私が学部のコピー機室で何やらやっていると、AlanやLindzen教授ら数名の共通秘書、Tracyがコピーする書類を持ってやってきて、私を見かけて話しかけてきた。「Alanは本当に釣りが好きなのね」。私は「そうなんだよ。
でも彼は凄く忙しくてそんなに行けないから気の毒なんだ」。と応えた。すると、彼女はこう続けた。「先日ね、彼が朝電話してきて、今日は釣りに行くから講義はキャンセルだって学生達に伝えてくれって言ってきたのよ」。私は思わず彼女の方に向き直って「なに?!本当?!」と訊いてしまった。
彼女は「本当よ。だから私、教室へ行って「講義はキャンセル」っていう張り紙をしたんだから」。と続けた。私はそこでハタと気が付いた。そうだ、Alanから釣行報告が来た日は、彼は講義があったはずだったのだ。それで、何か変だと思ったのであった。
いや~、まいった、まいった。講義が重視されるマサチューセッツ工科大で、おおっぴらに「釣りに行くから講義はキャンセル」とは・・・ しかも、秘書に言っただけではなかった。Alanは彼の授業を受けていた学生や若手研究者にも言っていたのだ。
後で他の学生や若手研究者数名から、Alanが彼らに「ゴメン、あの時は釣りに行ったんだよ」。という様な話をしたと聞かされた。確かNatalieという学生だったと思うが、私に向かってニヤニヤ笑いながら「Alanは講義をキャンセルして釣りに行っちゃったのよ。
あなたはAlanに悪影響よ」。と言っていた。そうそう、Richardというイギリス人学生は、講義キャンセル当日はどうしても出席できなかったので、翌日Alanのオフィスへ行って欠席を詫び、講義ノートをコピーさせて欲しいと頼んだそうだが、Alanに「ああ、気にしないで。
昨日は釣りに行って授業はキャンセルしたから。また来週」。と言われて「はあ、そうですか」。と呆気に取られてしまったと言っていた。私はこの時ばかりは「うわ、負けた・・・」と思った。1992年に「釣りバカコンビ」になってから、私とAlanは、何となく釣りバカぶりを競っていた感があったが、自由気ままな立場を利用して常に優位に立っていた私も、この時は本当にグウの音も出ない程の完敗であった。
また凄いのは、そのドタキャン「被害」に逢った学生や若手研究者が皆、Alanの行動を一切責めていなかったという点だ。いや、責めるどころか、私が話を聞いた数名はニコニコしながら、「いやぁ、彼がやっと釣りに行けて良かったよ」。という様な事を言っていた。
Alanの人徳があってこそ、であろう。あぁ、あの頃が懐かしい。楽しい日々であった。それから約10年後、ハワイ大に滞在中であった私はAlanをハワイ大に招待して再会を果たし、一緒にオアフのボーンフィッシュを釣る事もできた。そのAlanも、去年は70歳になり、スッパリ引退された様だ。彼の残りの人生が、楽しい釣りで満たされる事を祈るばかりだ。
初版発行:2018年7月
第一改訂版発行:2018年10月
第二改訂版発行:2018年12月
第三改訂版発行:2019年2月
第四改訂版発行:2019年7月
第五改訂版発行:2019年9月
第六改訂版発行:2019年10月
© Mototaka Nakamura 2018, 2019
