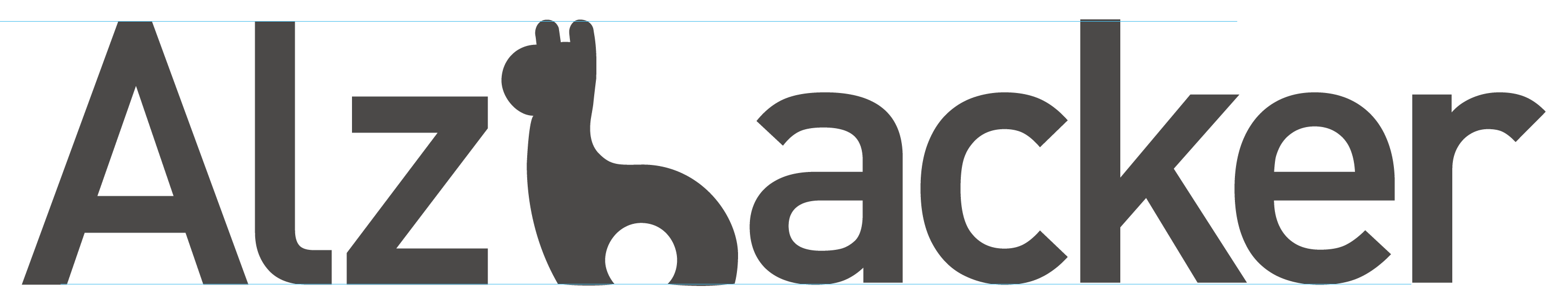Contents
運動してもらうことの難しさ
一番の難関は、病気の症状のひとつである無気力状態のある認知症患者に、どうやって運動してもらうか、、につきる。
さらに難しくしているのは、アルハカの母はもともと運動があまり好きではない、その上病気の影響で、物事始めることが億劫になっている。
※運動嫌いがゆえに認知症発症のリスクを高めたとも言えるので、そこには必然性があるかもしれない。
その母にどうやっって
脳の回復に効果があるとされる強度の運動をしてもらうか、ということ。
※ここで言う効果のある運動とは、一回30分 週4日 手が汗ばむ程度の有酸素運動、又は高負荷の筋トレ
一緒に散歩という打開案 → ベスト案
一年後にこう思うでしょう。
今日スタートすれば良かったと。
我が家では、おそらくここは多くの家族の境遇と一緒だと思うのだが、運動が大事だという情報は、すでにあちこちで目にしていて、「そうはいってもなあ、方法が思いつかないし」と、いった感じで、診断されてから最初の数年間は実行に移せずにいた。
よくある運動への言い訳
「時間ができたら、やろう」
「ちゃんとした運動でないと、効果があまりないだろう」
「長いこと運動をしてなかったから、今更してもダメだろう」
「持病があるので、運動をすればかえって悪くなると思う」
「いかにも運動していますっていうのが恥ずかしい」
「運動の効果があるのは、健康な人にだけだと思う。」
「楽な運動がいい、運動で汗はかいたりしない。」
「運動は健康になる1つの方法であって、他にいろいろやってるから大丈夫だと思う」
「運動するとつかれるし、めんどくさいし、」
「週に1,2回すれば十分だろう。」
以上の台詞に、ひとつでも該当するものがあれば、運動のリスクは避けられない。
結局のところ、アルハカ家も、当時、
「ちょっと物忘れするくらいで、そこまで困っているわけではないし」
「重要なんだろうけど、手間暇がかかるし」
「どうしていいかわからないし、本人がやる気にならないとなあ」
と無意識に理由を並べていたのだと思う。
つまり本当の意味では、重要さというものを分かっていなくて、
「社会通念のレベルで運動は大事」というふうにしか、思っていなかったのだと思う。
だが、数々の運動による認知機能の改善効果、研究成果を知って、生理学的なレベルで運動の重要性、他のあまたある改善策とはレベルが大きく違うということがわかってくると、これはもう無視できないぞ自覚するようになってきた。
おすすめ書籍

家族で話し合った結果、最終的には妹が出勤時に母を一緒に連れて出て、何駅かを飛ばして早足徒歩通勤という形で、散歩運動をしてくれることなった。
この散歩運動が、結果的にではあるが、認知症改善方法として大正解だった。
散歩を始めてから

黙って歩き、アルツハイマーを終わらせなさい。
そして、苦し紛れの案ではあったものの、案外、運動習慣のない人が運動を始めるために必要なコツみたいなものが詰まっていたことにも、後から気がついた。
まず妹に感謝なのだが、母と妹の仲が良かったため、喜んで出てくれるようになった。
また幸い、今はまだ知り慣れた道であれば、母がまだ道を迷わずに帰ることができるため、妹が会社に着いたら後は一人で帰ってくる。
有酸素運動には至っていないが、歩く距離は散歩だけで平均的に一日一万歩は超えるようになった。
散歩を始めてからの母の改善はめざましく、この頃は、同じセリフを延々と繰り返していた母が、5,6回くらい繰り返した後に「さっきも言ったかもしれないけど」とか、明確に短期記憶が回復していると感じられた。
これだけあれやこれや改善策を講じた中で、「どれが一番効果を感じた?」と家族に聞くと、迷わず「散歩だ」と断言するほどだ。
また母が「歩き始めてから、いろんなことがわかりだした」と、どきっとするようなつぶやきがあったりと、見失っていた自分の人格を、取り戻しているようにさえも思えてきた。
うおー、こんなに劇的に変わるならもっと早くやっとけば良かったー
、、それから数年が経過、
散歩もずっと継続し人格も保たれているものの、短期記憶だけは再び悪化してきたように思う。何か方策を打たねば、、いや実はいくつか打っているのだが結果が出るのはまだ先の話しだ。
とはいえ、母があの時運動(散歩)を初めていなければ、(それだけではダメだが)今の状態を維持していたとはとても信じられない。
それだけは運動を未だ躊躇しているみんなにも理解してほしい。
運動してもらうための5つのコツ
母は、散歩に関しては今は完全に習慣化しており、妹が通勤する時に何も言わなくても、雨の日でも一緒に散歩していってくれる。
運動してもらうために、おもに自分の体験から得た小さなトリック、コツなどを、書いてみたい。
1 最初の二ヶ月は、ストレスが大きくかかる運動をしない。
どれほど崇高な目標があったとしても、
極端な努力をしてしまうと、続かなくなります。ダライ・ラマ
世の中の散歩やウォーキング指南は、みんな健康効果だとか、歩行の技術ばかりにフォーカスしてしまっていて、前提の問題を見過ごしているアルハカは思っている。
大原則1 運動が続かなければ、どんな技術論も研究も意味がない。
すでに知っている人も多いと思いけど、認知症になって記憶力が失われて出来事の記憶は失われるけど、感情的な記憶(潜在記憶)は残っていると言われている。
なので、運動中、感覚的に楽しいと思わせることが非常に重要。
「運動しなきゃダメだ」っていう思いは、実は逆効果。そう思えば思うほど運動そのものが楽しくないものだと、潜在意識に植え付けられるからだ。
これが、家族や周囲から言われるとなおさらのことだ。
(「じゃあ、どうすればいいんだ!」という声が聞こえてくる、、後で書いていきます。)
これは一般の人が、重い腰を上げて運動を始めようとする時にも言えるのだが、特に認知症患者にはタブーだと思う。
心理学の世界で、一つの行為が習慣化するためには二ヶ月が必要と言われている。
そのため、運動をはじめて最初の二ヶ月が勝負
勝負といってもやるぞ!という気合を入れる勝負ではなく、むしろ気合を入れないというか、だましだまし自然体で始める。
とにかく、最初の二ヶ月は、運動が楽しいと思い込ませることだけに全力をつくす。
運動の強度だとか、歩行距離だとか、有酸素運動のスピードだとか、「楽しさ」と関係のないことは一切考えない。
だから、むしろ30分とか運動しないほうがいい。
思い切って5分だけと決めてしまう。
その代わり5分間ウォーキングを、最初の2ヶ月間の間は、週に3回以上を確保する。
5分だけだと、普通は、ちょっと物足りな感があるはず、このちょっと物足りない感が実はとても大事なのだ。
例えば30分歩いて、歩ききった感を味わうと一見それがいいようにも感じるのだが、それはその時だけであって、無意識的には次の散歩欲求には繋がりにくくなったりする。
大原則その2 やる気というのは資源である。
コツはね、はりきらないことですよ。 タモリ
制御資源枯渇理論というものがあり、個人がある期間内に自己をコントロールできる量は限られているとする理論が存在する。
例えばチョコレートを食べることを我慢するよう求められた被験者では、そうしなかった被験者よりも、他で与えられたチャレンジ(パズルの完成)を諦めるのが早かった。
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9599441
もし散歩の後、「歩き切った、まんぞくー」と感じたのなら、それは「やる気の資源を使い切ったぞー」という意味でもあるのだ。
このことはもっと強調されるべきだと思っている。
もちろん、次の日になればやる気の資源は補充されるのだが、まだ運動が身について段階では、その補充がちょこっとしかなされない。
だから最初の二ヶ月は、5分歩いて、もっと歩きたいなと思ったとしても、それ以上歩いてはだめ。
散歩の最後に、「いやあ、今日はがっつり歩いたなあ」と思ったら、その散歩は失敗だったと思うぐらいがいい。
※ただし、ちょっと物足りないなと思う歩行距離や時間の範囲内であるなら、5分以上伸ばしてもOK。
※言い換えれば、二ヶ月を過ぎて、やる気資源が次の日には回復できるような身体が出来上がっていれば、歩ききっても全然OK
ここで、毎日嫌だけど頑張らなければとか思いながら運動をすると、その記憶が定着してしまって運動を始める前よりも、運動に対してネガティブな感情が作られてしまう。
疲労感がひどい時に、無理して運動してしんどいまま終わると、つらかった記憶が焼き付いてしまうため、ますますしたくない、という感情が植え付けられてしまう。そういう時はむしろ運動はしてはいけない。
かといって、したい時にだけするとなると、今度はずっと運動をしないまま終わってしまう。
このバランスをはかるのが難しいのだけど、
ポイントは、
「運動する前は乗り気ではなかったけど、初めてみたらそれなりに楽しい」
というぐらいの感覚。運動前がそれぐらいの疲労感や嫌々さであればOK。
だから、運動中もだけど運動が終わってからの疲労感を見極める。運動後にベタッとベッドに寝込むようであれば運動前の疲労感が元々大きすぎたか、運動がオーバーワークになっているかなので運動量を減らす。
これは、本人が自覚的に言う顕在記憶の言葉を信用してもダメ。
運動が終わっても、それなりに活動的であることが見て取れるくらいが理想だと思う。
2 普段、日常的に行っている行動と重ねてみる。

アルハカ家では以前に書いたとおり、妹が出勤時に一緒に母と散歩にでるという打開案だったのだが、これが結果的に非常に良かった。
結局、
「人が運動を負担に感じるピークは、スタート直後」
と言っても過言ではない。
これは言い換えると、
「運動をスタートした瞬間、運動の半分は達成」
ということでもある。
散歩に限らず、何かを始める時、人はおうおうにして努力量を当割して考えてしまうのだが、習慣化すると運動そのものの気持ちよさが生まれてくるので、一定期間をすぎれば、継続はそれほど難しいことではなくなってくる。
繰り返すようだが、
努力資源の7割は最初の二ヶ月の継続だけに注ぎ込むべき。
二ヶ月続けて、それでやめると考えて始めてしまってもいいと思う。
アルハカ家では、通勤という必ずしなければならない行為に付随させたため、ずっと続けることができるようになったとも言える。
家の中で行うのなら、テレビを見ながらルームランナーを歩くとか、足踏み昇降機を使いながらパソコンを使うとかも選択肢としてはあるかもしれない。
ただ、これは
でも書いたけど、空間認知活動としての刺激にはつながらない。
3 家族と始める、会話しながら運動をする。
人と一緒に運動すると、より多くのドーパミンが放出されることが研究でわかっている。つまりより楽しく運動ができて、扁桃体も刺激されるため、それが記憶にも定着しやすくなる。
これも、母と妹が一緒に散歩にでることで、歩きながら会話をしたりもできるため、散歩の楽しさにつながりやすくなったといえる。
また、これは人にもよるが、母は「妹を無事見送る」という自分の役割として捉えている節もあり、(あながち嘘でもない)このことも、「人の役に立つという感情」がうまく下支えしてくれたように思う。
その人が何を望むのか、無意識の欲求を読み解いた上で、継続につなげていくということはとても大切だと思う。
4 運動30分前に、PQQ、カフェイン錠剤、その他サプリの摂取、小さなテクニックを掛け合わせる。
アルツハイマー病の改善に有効であるサプリメントの中には、運動の効果を上げてくれるサプリメントも多かったりする。
カフェインやPQQもそのひとつで、運動とは関係なく摂取するのであれば、それならそれを運動前に摂取して、やる気につなげられれば一挙両得である。
こういう小さい小道具を馬鹿にしてはいけない。
脳の内部では、「やる気がある」「ない」というような単純なしくみではなく、楽しいという感情と、嫌だやりたくないという感情が激しくぶつかりあって、その結果ちょっとの差で、意識的には「ちょっと楽しくないな」という感情が生まれたりする。
しかし、ちょっとであっても、それが積もり積もると、結局楽しくないという大きな感情になってしまい、最終的には挫折につながったりもする。
この潜在的な思考経路は意識には登ってこないため、「楽しくないから止めたんだ」とは自分では気が付きにくい。
これは自分や母を実験台に(汗)何度も繰り返しているのでわかるが、運動前の活動を促進するカフェインやPQQなどが欠けた状態で運動を繰り返すと、異なる理由を持ち出して運動拒否を示すようになる。
自分自身もまあ今日はパスしとうこうかと思った後で、よく考えるとバレットプルーフコーヒーを飲んでいなかったな、と気がついたりすることもある。
このちょっとの差を埋めるのが、サプリだけではなく、コーヒーを摂るだとか、お気に入りの場所を持つとか、小さなテクニックの積み重ねだったりする。
5 音楽を聞きながら運動
会話ができているなら、あまり必要ないかもしれないけど、お気に入りの音楽を用意して聞いてもらうというのは、これも、小さなテクだがとても効果的。
ポイントは3つ
・音楽にこだわらない。音楽も可能な限り多種多様なものを揃える。
・選曲は一曲一曲シビアに行う。
・本体でMP3再生ができるタイプのコードレスヘッドフォンを使う。
まとめ
繰り返すけど「やる気」は資源!
単純に「やる気」で行動を起こそうとするのは「やる気」の資源消費、最初は良くても後が続かない。
「やる気」はお金と一緒で、使えば失くなるので、やる気が貯まる体質ができていない時は長続きしない!
大事なのは「やる気」持とうとする意思ではなく、環境の創意工夫によって「やる気マネー」を増やしていくこと!
「やる気マネー」が失われないように、環境の小さな工夫を積み重ねる!
運動を続けていく方法を文献ベースで調べてみた記事はこちら